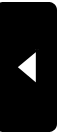2024年05月21日
「小休止その4、肥前は遠い国…」
こんばんは。“本編”で主要な登場人物が世を去る話を書くと、しばらく脱力感に見舞われる…ということが多いです。
次の下書きも間に合ってませんので、例によって小休止します。
あまり感想を書いていない、2024年大河ドラマ『光る君へ』ですが、結構、楽しみに観ています。
やけに仲の良い紫式部(まひろ)と清少納言とか…来週にはついに、枕草子の『春はあけぼの…』が出そうだとか、見どころはたくさんあります。

――ところで、私の心に響いたセリフがありました。
たぶん、一般的な視聴者はあまり気にしない内容で、それは、まひろ(紫式部)〔演:吉高由里子〕の友人・さわ〔演:野村麻純〕の言葉。
父が肥前守(佐賀・長崎の国司)に任じられて、九州赴任についていくことになった事を告げる場面。たしか第18回の後半。
「肥前は遠い国…」と、まひろに語り、「もう、会えないかもしれない~」と、かなり騒いでいました。

――ですが、その次の回(19)だったと思いますが…
その肥前国に行ったはずの、さわから手紙が来て、「婿を取りました!」と、いきなりのメッセージ。
「…そがんね、よか男の居ったとね!?」と言いたくなったのは、佐賀の人ぐらいでしょうか。
当時の肥前の国府は、佐賀市の大和町あたりかな…と考えます。国司の任期は4年と言いますが、その場所で人生の決断にかかったようです。
――公式HPでは、この、さわという女性について
「愛情に飢えた、一風変わった娘、まひろを慕い親しくなる」とあります。
まひろの父・藤原為時〔演:岸谷五朗〕が看病をしていた女性が、以前の結婚で産んだ娘で、残された家での立場が弱い…という描写だった思います。
さわがまひろと一緒に石山寺に旅をした時、すっかりひねくれてしまった話も、記憶に新しいです。
「そうね、佐賀に行ってから幸せになったとね~」と温かい目線で、一連のエピソードを受けとめた私。

――「そうだ、私の探している答えも、きっと佐賀にある」
さわという女性の物語への登場はこれで完了のようですが、感情の振れ幅の大きい、少し気になる脇役でした。
ひょっとすると、この「肥前は遠い国…」という物語の中での言葉。私が、次に選択する行動に影響したかもしれません。そのお話は、また次回に。
次の下書きも間に合ってませんので、例によって小休止します。
あまり感想を書いていない、2024年大河ドラマ『光る君へ』ですが、結構、楽しみに観ています。
やけに仲の良い紫式部(まひろ)と清少納言とか…来週にはついに、枕草子の『春はあけぼの…』が出そうだとか、見どころはたくさんあります。
――ところで、私の心に響いたセリフがありました。
たぶん、一般的な視聴者はあまり気にしない内容で、それは、まひろ(紫式部)〔演:吉高由里子〕の友人・さわ〔演:野村麻純〕の言葉。
父が肥前守(佐賀・長崎の国司)に任じられて、九州赴任についていくことになった事を告げる場面。たしか第18回の後半。
「肥前は遠い国…」と、まひろに語り、「もう、会えないかもしれない~」と、かなり騒いでいました。
――ですが、その次の回(19)だったと思いますが…
その肥前国に行ったはずの、さわから手紙が来て、「婿を取りました!」と、いきなりのメッセージ。
「…そがんね、よか男の居ったとね!?」と言いたくなったのは、佐賀の人ぐらいでしょうか。
当時の肥前の国府は、佐賀市の大和町あたりかな…と考えます。国司の任期は4年と言いますが、その場所で人生の決断にかかったようです。
――公式HPでは、この、さわという女性について
「愛情に飢えた、一風変わった娘、まひろを慕い親しくなる」とあります。
まひろの父・藤原為時〔演:岸谷五朗〕が看病をしていた女性が、以前の結婚で産んだ娘で、残された家での立場が弱い…という描写だった思います。
さわがまひろと一緒に石山寺に旅をした時、すっかりひねくれてしまった話も、記憶に新しいです。
「そうね、佐賀に行ってから幸せになったとね~」と温かい目線で、一連のエピソードを受けとめた私。
――「そうだ、私の探している答えも、きっと佐賀にある」
さわという女性の物語への登場はこれで完了のようですが、感情の振れ幅の大きい、少し気になる脇役でした。
ひょっとすると、この「肥前は遠い国…」という物語の中での言葉。私が、次に選択する行動に影響したかもしれません。そのお話は、また次回に。
2024年02月04日
「新章は始められるのか」
こんにちは。およそ10日ばかり更新を止めてしまいました。
「人は色々な事を同時に考えると、短期記憶が飛んでしまう」と聞いたことがあります。平たく言えば「忙しいと、つい先ほどの事を忘れる」という意味でしょう。
本日の記事は、このところ疲れ気味な私が「再生とは何か?」を考えるためのつぶやきです。
――「最近、時々物忘れが…」と感じ始めている、私。
あまり“老化”とは認めたくないので、こう考えました。「これは、複数の案件を同時並行で処理した結果、短期記憶が飛んでしまったのだ」と。
なお、これは私の現状分析に基づく判断なので、本当に物忘れが気になる方は、ぜひとも病院を受診してください。
それはさておき、新年に入ってから何かと忙しく、全く“本編”の下書きも進んでいない状況があります。

――「母なる佐賀の海よ、私に力を!」
そんなふうに叫んだわけでもないのですが、私の手元には、以前入手していた“佐賀海苔”がありました。
「母なる佐賀の海!」とは言いましたが、当然ながら、私の母が有明海というわけではありません。
そういう設定だと、私は干潟で生まれた“潟〔ガタ〕太郎”みたいな存在になるので、鬼退治でもできれば良いのですが、そんな昔話、聞いたことも無いです。
有明海が「佐賀の者にそれだけの恵みを与える大きな存在」という喩えです。
――前置きが長くなりましたが、数枚の佐賀海苔をパリパリとかじります。
「おお、みるみるうちに気力の戻ってくるとよ!」
…と、そこまで劇的に回復するわけでもないのですが、これが結構美味しくて、また数枚を取り出します。

――「これは、良かごた!」
さすがは“海苔の中の海苔”とでも言うべき、佐賀海苔。私だけの効能かもしれませんが、力が回復してきた印象があります。
ここで、私は“幕末佐賀藩の大河ドラマ”を追い求めるあまり、抑えてきた事があるのではないか?と思い至ります。
「特定の商品や企業のことを強調してはいけない、NHKなんで!」とばかり、無自覚のうち、己に制限をかけてきたように感じたのです。
そもそも、私は「テレビでは民放より、NHKを見ている事が多い」だけの、ただの“一(いち)視聴者”に過ぎません。
――「もっと、佐賀の品物への愛も語ろう!」
私のこの気付き。密かに“第20話”へとつながっていく予定です。
「人は色々な事を同時に考えると、短期記憶が飛んでしまう」と聞いたことがあります。平たく言えば「忙しいと、つい先ほどの事を忘れる」という意味でしょう。
本日の記事は、このところ疲れ気味な私が「再生とは何か?」を考えるためのつぶやきです。
――「最近、時々物忘れが…」と感じ始めている、私。
あまり“老化”とは認めたくないので、こう考えました。「これは、複数の案件を同時並行で処理した結果、短期記憶が飛んでしまったのだ」と。
なお、これは私の現状分析に基づく判断なので、本当に物忘れが気になる方は、ぜひとも病院を受診してください。
それはさておき、新年に入ってから何かと忙しく、全く“本編”の下書きも進んでいない状況があります。
――「母なる佐賀の海よ、私に力を!」
そんなふうに叫んだわけでもないのですが、私の手元には、以前入手していた“佐賀海苔”がありました。
「母なる佐賀の海!」とは言いましたが、当然ながら、私の母が有明海というわけではありません。
そういう設定だと、私は干潟で生まれた“潟〔ガタ〕太郎”みたいな存在になるので、鬼退治でもできれば良いのですが、そんな昔話、聞いたことも無いです。
有明海が「佐賀の者にそれだけの恵みを与える大きな存在」という喩えです。
――前置きが長くなりましたが、数枚の佐賀海苔をパリパリとかじります。
「おお、みるみるうちに気力の戻ってくるとよ!」
…と、そこまで劇的に回復するわけでもないのですが、これが結構美味しくて、また数枚を取り出します。
――「これは、良かごた!」
さすがは“海苔の中の海苔”とでも言うべき、佐賀海苔。私だけの効能かもしれませんが、力が回復してきた印象があります。
ここで、私は“幕末佐賀藩の大河ドラマ”を追い求めるあまり、抑えてきた事があるのではないか?と思い至ります。
「特定の商品や企業のことを強調してはいけない、NHKなんで!」とばかり、無自覚のうち、己に制限をかけてきたように感じたのです。
そもそも、私は「テレビでは民放より、NHKを見ている事が多い」だけの、ただの“一(いち)視聴者”に過ぎません。
――「もっと、佐賀の品物への愛も語ろう!」
私のこの気付き。密かに“第20話”へとつながっていく予定です。
2024年01月15日
「幕末娘の“推し活”」
こんばんは。
最近、好きな芸能人等を「推し」という表現で語るのをよく聞きます。年末年始のテレビ番組やネット配信、貴方の“推し”は元気な姿を見せたでしょうか。
ちなみに「“推し”がいるから、日常でも頑張れる!」と好きなアイドル等の応援に励むことを「推し活」というそうです。
ところで、幕末の黎明期だった文化・文政年間(1804年~1830年)。
当時は佐賀藩の諫早領だった、現在の佐賀県太良町あたりに、幕末の村娘たちのアイドルだったという、伝説の美少年がいました。

――題材は、佐賀県の民謡・『岳(たけ)の新太郎さん』
佐賀県内の若い方でも、この民謡の存在は知っているが、古い歌だと思っている人が多いのではないでしょうか。
幾度か語っていますが、角度を変えてまた書きます。「けっこう現代っぽい感覚の歌なんです…」という視点で、今回は、この民謡そのものを説明してみます。
民謡といえば、希望の見えない、辛い日々の労働などを歌い込んだ「日本版“ブルース”」のような曲も多いと思います。
まだまだ江戸時代だった幕末黎明期を題材とした、この佐賀県民謡。

現在の形になったのは、後年かもしれませんが、当時の佐賀県の女子たちが、陽気な“ラブソング”とともに生きていたことを感じさせるのです。
しかも“ラブソング”とはいっても、彼女たちの妄想のような歌で、それも現代的な感じがします。
――「アイドルを、“出待ち”するファンの歌」みたいなものでしょうか。
でも、まずは時代背景を考えます。当ブログを熱心にお読みいただいている方ならば、この話題にもそこそこ関心を持っていただけるはず…
1804年 ロシアのレザノフが長崎に来航 幕府に通商を迫る
→佐賀藩は、千人体制で長崎港の警備を固める

1808年 イギリスのフェートン号が長崎港に侵入
→佐賀藩は、出費を嫌がって長崎に警備隊をおいておらず厳重処罰される
1814年 のちの第10代佐賀藩主・鍋島直正 江戸の藩邸で誕生する
1825年 幕府が異国船打払令を出す
→佐賀藩は、その前年に長崎警備を熊本藩に押しつけようとして失敗
“名君”の就任前なので、佐賀藩は財政難に苦しみ、迷走している時期です。出費が嵩む長崎警備をどうにかしたい…という辺りに、時代が出ています。

年表から20年くらい後には、次の殿様・鍋島直正が「佐賀藩の独力でも長崎を守ってみせる!」と、すごい責任感で港の入口を要塞化するのですが…
幕府から異国船打払令が出た時期には、日本の表玄関である、長崎の警備から手を引いて(熊本に押しつけて)、パスしようとしています。
――こんな激動の時代に「アイドルの出待ちソング」とは。
ここでも、「やはり佐賀は最先端だった…」と言えるのかもしれません。
多良岳の山頂にある金泉寺、ここが寺侍だった“岳の新太郎さん”の勤務地。修験道の霊峰と聞く多良岳。
厳しい修行の場である、その寺も当時は女人禁制でした。
かくして、幕末のハンサム侍である“岳の新太郎さん”の姿を見たい女子たちは、自分たちからその姿を見に行くことはできません。

――月に幾度だけ用務のために、山から下りてくる“岳の新太郎さん”
イメージとして示されるのは、涼しげな顔立ちに、どこか神々しい美少年。下山のときは、会いたくても会えないアイドルの“ご尊顔”を拝むチャンス。
アイドルが登場した時、歓声とともに「尊(とうと)い~!」とペンライトを振る、現代の女子の姿が重なるようです。
彼女たちの感情は、ザンザザンザ…という擬音で表されます。これは、乙女の気持ちの高鳴りを、近隣に多くあった水車の音に喩えたものと聞きました。

――稀(まれ)に見られる、その“アイドル”の姿は…
「色者(イロシャ)の粋者(スイシャ)」と表現されています。
年若くして、女人禁制の寺に勤める、寺侍の“岳の新太郎さん”。山に籠もっているときには、おそらく女性と関わる機会は無いはず。
それが触れてはいけない禁断の香りを漂わせるのか、ただのモテ男とは違う、清廉さと神秘性を醸し出しています。
普段、見ることができないからこそ、その姿をはっきり見たい…

――彼女たちの妄想は、さらに強くなり…
“岳の新太郎さん”が来る時には、千の灯籠で周囲を照らし、帰ろうとする時には道に水をかけてでも、歩みを遅らせる…
少しでも長く“アイドル”の姿を見ていたいという、気持ちの表現なのでしょう。
「岳の新太郎さんの、来らすとよ~」とキャッキャする、当時の佐賀女子たちのざわめきが目に浮かぶようです。
その歌詞は「竿じゃ届かぬ、高木の熟柿」と続き、その存在が“高嶺の花”であったことが表現されています。
――おそらくは、その思いは思いのままで…
歌詞には続きがあるそうで、「傘を忘れた、山茶花の茶屋」に「空が曇れば思い出す…」と、何だか叙情的で、歳月を経た回想のような印象を感じます。

ちなみに、「山茶花(さざんか)茶屋」で調べると、県境を越えた長崎県諫早市に、その跡地の情報が出てきました。実は、近代へと続く道『多良海道』…。
そこは、また語るとして、時は流れ“アイドル”に熱狂した、若き日々の後にも、きっと、彼女たちの人生は続いていきます。
私の解釈は中途半端なので、その正確さはともかく、あらためて歌詞を追うと、とても現代的な民謡という感想を得ました。
――先ほどの“歴史年表”から3年ほど後、
1828年には、子年の大風(シーボルト台風)が発生。現在の太良町内では、灯台が倒れるほどの威力の風が吹き、大きな被害が出たことが伝わります。

私は感情移入しやすいので、“岳の新太郎さん”に熱狂した彼女たちは、無事だったのだろうか…ということも考えます。
財政難の折、台風でさらに大きな被害を受けた佐賀藩。こうして、迷走のうちに文政年間が終わっていきます。
そして、天保元年(1830年)には数え年で17歳。若き藩主となった鍋島直正が佐賀を率いることになり、新しい時代が進んでいきます。
――“本編”の第20話「長崎方控」では、
この佐賀県民謡の要素を、少し取り込んでいこうかと考えています。
「もっと、佐賀を語っていこう」というのは、今年のテーマでもあるので、どんな表現になるか…期待できそうな方は、気長にお待ちいただければ幸いです。
○過去の関連記事
(岳の新太郎さん)「主に太良町民の皆様を対象にしたつぶやき」
(多良海道の紹介)「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕
(本編での多良海道)第16話「攘夷沸騰」⑭(多良海道の往還)
最近、好きな芸能人等を「推し」という表現で語るのをよく聞きます。年末年始のテレビ番組やネット配信、貴方の“推し”は元気な姿を見せたでしょうか。
ちなみに「“推し”がいるから、日常でも頑張れる!」と好きなアイドル等の応援に励むことを「推し活」というそうです。
ところで、幕末の黎明期だった文化・文政年間(1804年~1830年)。
当時は佐賀藩の諫早領だった、現在の佐賀県太良町あたりに、幕末の村娘たちのアイドルだったという、伝説の美少年がいました。
――題材は、佐賀県の民謡・『岳(たけ)の新太郎さん』
佐賀県内の若い方でも、この民謡の存在は知っているが、古い歌だと思っている人が多いのではないでしょうか。
幾度か語っていますが、角度を変えてまた書きます。「けっこう現代っぽい感覚の歌なんです…」という視点で、今回は、この民謡そのものを説明してみます。
民謡といえば、希望の見えない、辛い日々の労働などを歌い込んだ「日本版“ブルース”」のような曲も多いと思います。
まだまだ江戸時代だった幕末黎明期を題材とした、この佐賀県民謡。
現在の形になったのは、後年かもしれませんが、当時の佐賀県の女子たちが、陽気な“ラブソング”とともに生きていたことを感じさせるのです。
しかも“ラブソング”とはいっても、彼女たちの妄想のような歌で、それも現代的な感じがします。
――「アイドルを、“出待ち”するファンの歌」みたいなものでしょうか。
でも、まずは時代背景を考えます。当ブログを熱心にお読みいただいている方ならば、この話題にもそこそこ関心を持っていただけるはず…
1804年 ロシアのレザノフが長崎に来航 幕府に通商を迫る
→佐賀藩は、千人体制で長崎港の警備を固める

1808年 イギリスのフェートン号が長崎港に侵入
→佐賀藩は、出費を嫌がって長崎に警備隊をおいておらず厳重処罰される
1814年 のちの第10代佐賀藩主・鍋島直正 江戸の藩邸で誕生する
1825年 幕府が異国船打払令を出す
→佐賀藩は、その前年に長崎警備を熊本藩に押しつけようとして失敗
“名君”の就任前なので、佐賀藩は財政難に苦しみ、迷走している時期です。出費が嵩む長崎警備をどうにかしたい…という辺りに、時代が出ています。
年表から20年くらい後には、次の殿様・鍋島直正が「佐賀藩の独力でも長崎を守ってみせる!」と、すごい責任感で港の入口を要塞化するのですが…
幕府から異国船打払令が出た時期には、日本の表玄関である、長崎の警備から手を引いて(熊本に押しつけて)、パスしようとしています。
――こんな激動の時代に「アイドルの出待ちソング」とは。
ここでも、「やはり佐賀は最先端だった…」と言えるのかもしれません。
多良岳の山頂にある金泉寺、ここが寺侍だった“岳の新太郎さん”の勤務地。修験道の霊峰と聞く多良岳。
厳しい修行の場である、その寺も当時は女人禁制でした。
かくして、幕末のハンサム侍である“岳の新太郎さん”の姿を見たい女子たちは、自分たちからその姿を見に行くことはできません。
――月に幾度だけ用務のために、山から下りてくる“岳の新太郎さん”
イメージとして示されるのは、涼しげな顔立ちに、どこか神々しい美少年。下山のときは、会いたくても会えないアイドルの“ご尊顔”を拝むチャンス。
アイドルが登場した時、歓声とともに「尊(とうと)い~!」とペンライトを振る、現代の女子の姿が重なるようです。
彼女たちの感情は、ザンザザンザ…という擬音で表されます。これは、乙女の気持ちの高鳴りを、近隣に多くあった水車の音に喩えたものと聞きました。
――稀(まれ)に見られる、その“アイドル”の姿は…
「色者(イロシャ)の粋者(スイシャ)」と表現されています。
年若くして、女人禁制の寺に勤める、寺侍の“岳の新太郎さん”。山に籠もっているときには、おそらく女性と関わる機会は無いはず。
それが触れてはいけない禁断の香りを漂わせるのか、ただのモテ男とは違う、清廉さと神秘性を醸し出しています。
普段、見ることができないからこそ、その姿をはっきり見たい…
――彼女たちの妄想は、さらに強くなり…
“岳の新太郎さん”が来る時には、千の灯籠で周囲を照らし、帰ろうとする時には道に水をかけてでも、歩みを遅らせる…
少しでも長く“アイドル”の姿を見ていたいという、気持ちの表現なのでしょう。
「岳の新太郎さんの、来らすとよ~」とキャッキャする、当時の佐賀女子たちのざわめきが目に浮かぶようです。
その歌詞は「竿じゃ届かぬ、高木の熟柿」と続き、その存在が“高嶺の花”であったことが表現されています。
――おそらくは、その思いは思いのままで…
歌詞には続きがあるそうで、「傘を忘れた、山茶花の茶屋」に「空が曇れば思い出す…」と、何だか叙情的で、歳月を経た回想のような印象を感じます。
ちなみに、「山茶花(さざんか)茶屋」で調べると、県境を越えた長崎県諫早市に、その跡地の情報が出てきました。実は、近代へと続く道『多良海道』…。
そこは、また語るとして、時は流れ“アイドル”に熱狂した、若き日々の後にも、きっと、彼女たちの人生は続いていきます。
私の解釈は中途半端なので、その正確さはともかく、あらためて歌詞を追うと、とても現代的な民謡という感想を得ました。
――先ほどの“歴史年表”から3年ほど後、
1828年には、子年の大風(シーボルト台風)が発生。現在の太良町内では、灯台が倒れるほどの威力の風が吹き、大きな被害が出たことが伝わります。
私は感情移入しやすいので、“岳の新太郎さん”に熱狂した彼女たちは、無事だったのだろうか…ということも考えます。
財政難の折、台風でさらに大きな被害を受けた佐賀藩。こうして、迷走のうちに文政年間が終わっていきます。
そして、天保元年(1830年)には数え年で17歳。若き藩主となった鍋島直正が佐賀を率いることになり、新しい時代が進んでいきます。
――“本編”の第20話「長崎方控」では、
この佐賀県民謡の要素を、少し取り込んでいこうかと考えています。
「もっと、佐賀を語っていこう」というのは、今年のテーマでもあるので、どんな表現になるか…期待できそうな方は、気長にお待ちいただければ幸いです。
○過去の関連記事
(岳の新太郎さん)
(多良海道の紹介)
(本編での多良海道)
2023年09月06日
「夏の終わりに…」
こんばんは。まだ秋風までは感じられないものの、さすがの猛暑もようやく陰りを見せ始めたと思います。
灼熱の日々が続くと、“夏の終わり”などと情緒的な言葉も出て来ないのですが、ふと、それらしき寂しさを感じる知らせを聞きました。
今夏は、まったく筆が進みませんでした。気持ちが乗ってくるまで、しばらくは、思い付くことを綴ってみます。
――夏が去りゆく時に、思い出す言葉がある。
数十年前のドラマだったと思う。ある女性が、海辺で昔なじみの男性に向かってこんな事を言う。
「私、1年の中で、夏の終わりが一番嫌い。」
聞けば、最もさびしさを感じる季節だからだという。
もう8月は過ぎた設定だろうか。白波がよせる砂浜には、賑わった夏の気配も残ってはいない。戯れに波打ち際で、水面を蹴るような振りをする女性。
もう若いとは言い切れなくなった、微妙な年頃の2人だけが、夏の終わりの海を望んでたたずむ、しずかな風景だ。

――なお、セリフは曖昧な記憶で、綴っている。
ドラマについては多くは語らない。たぶんコメディ調の作品だったと思うが、この場面が、やけに強く印象に残っている。
ここで私が語りたいのは、暑かった夏の終わりに、秋風の吹き始める時期は、「ふと、寂しさを感じる」季節だったはずということだ。
いまや、暑過ぎて感傷に浸れない…ということは横に置いておく。
――では、私は何が寂しいのかを語る。
ある日、ネットで『佐賀新聞』の記事を見た時に、今夏の8月下旬で1つの時代の終わりを感じさせる記事があった。
その記事の見出しはこうだった。
「佐賀玉屋レストラン街、43年の歴史に幕…」とあった。タイトルは「たくさんの思い出、ごちそうさまでした」と続く。

寂しい…なんて適切な見出しを付けるのだ、さすがは『佐賀新聞』。やはり新聞の顔である題字が、副島種臣先生の書なのは、ダテではない。
そして、この出来事の原因は“コロナ禍”が経営を圧迫したのか、レストランの運営会社が、飲食事業部を廃止するためであるという。
――「何だ!この異様な寂寥感は…」
私は愕然とした。以前、佐賀駅構内の積文館書店が閉店する一報を聞いたときにも、似た感覚を味わった記憶がある。
近年、随分と佐賀県に帰還しづらくなっていたから、結局、知らぬ間になくなっていた感覚に近い。
おそらく数えるほどしか行ったことのない「佐賀玉屋レストラン街」の閉鎖がここまで堪(こた)えるとは…

※2019年撮影
――昭和の百貨店にあったレストラン街の…
“王道”のような雰囲気を持つ印象だった。それだけに近年は苦戦する様子は察していたのだ。
だが、「しぶとく残ってくれるのではないか」と期待していたところもあった。
佐賀の中心街を眼下に眺めながら、スパゲッティを食んでいた感覚も、もはや遠くにある。
ただ、なにげに心地が良かったと記憶している。きっと、そこが“特別な場所”だったからだ。
これから、佐賀に帰還して玉屋を訪れても、もう南館7階にあの場所はない…この感情の根元はそこにあるらしい。

――私という人間も、ずいぶんと“欲張り”なのか。
最近では、大物ミュージシャンの記念コンサートもこなせる『SAGAアリーナ』の開業に大喜び。駅内商業施設『サガハツ』が出来たことも快く思っていた。
その一方で、佐賀に帰ったら、あって当然と思っていた施設がなくなると、強い落ち込みを感じるのだ。
「古き良きものが残って、新しい風も吹き込む」
佐賀には、そうあってほしいと思うが、おそらく、わがままな願望なのだろう。
私に何ができるわけでもない。佐賀県から遠くにいる分、情報だけが届いて、余計に、もどかしいところがある。
異常に暑かった、この夏も過ぎ去っていく。今回はいまの、この気持ちだけを記しておきたい。
灼熱の日々が続くと、“夏の終わり”などと情緒的な言葉も出て来ないのですが、ふと、それらしき寂しさを感じる知らせを聞きました。
今夏は、まったく筆が進みませんでした。気持ちが乗ってくるまで、しばらくは、思い付くことを綴ってみます。
――夏が去りゆく時に、思い出す言葉がある。
数十年前のドラマだったと思う。ある女性が、海辺で昔なじみの男性に向かってこんな事を言う。
「私、1年の中で、夏の終わりが一番嫌い。」
聞けば、最もさびしさを感じる季節だからだという。
もう8月は過ぎた設定だろうか。白波がよせる砂浜には、賑わった夏の気配も残ってはいない。戯れに波打ち際で、水面を蹴るような振りをする女性。
もう若いとは言い切れなくなった、微妙な年頃の2人だけが、夏の終わりの海を望んでたたずむ、しずかな風景だ。
――なお、セリフは曖昧な記憶で、綴っている。
ドラマについては多くは語らない。たぶんコメディ調の作品だったと思うが、この場面が、やけに強く印象に残っている。
ここで私が語りたいのは、暑かった夏の終わりに、秋風の吹き始める時期は、「ふと、寂しさを感じる」季節だったはずということだ。
いまや、暑過ぎて感傷に浸れない…ということは横に置いておく。
――では、私は何が寂しいのかを語る。
ある日、ネットで『佐賀新聞』の記事を見た時に、今夏の8月下旬で1つの時代の終わりを感じさせる記事があった。
その記事の見出しはこうだった。
「佐賀玉屋レストラン街、43年の歴史に幕…」とあった。タイトルは「たくさんの思い出、ごちそうさまでした」と続く。
寂しい…なんて適切な見出しを付けるのだ、さすがは『佐賀新聞』。やはり新聞の顔である題字が、副島種臣先生の書なのは、ダテではない。
そして、この出来事の原因は“コロナ禍”が経営を圧迫したのか、レストランの運営会社が、飲食事業部を廃止するためであるという。
――「何だ!この異様な寂寥感は…」
私は愕然とした。以前、佐賀駅構内の積文館書店が閉店する一報を聞いたときにも、似た感覚を味わった記憶がある。
近年、随分と佐賀県に帰還しづらくなっていたから、結局、知らぬ間になくなっていた感覚に近い。
おそらく数えるほどしか行ったことのない「佐賀玉屋レストラン街」の閉鎖がここまで堪(こた)えるとは…
※2019年撮影
――昭和の百貨店にあったレストラン街の…
“王道”のような雰囲気を持つ印象だった。それだけに近年は苦戦する様子は察していたのだ。
だが、「しぶとく残ってくれるのではないか」と期待していたところもあった。
佐賀の中心街を眼下に眺めながら、スパゲッティを食んでいた感覚も、もはや遠くにある。
ただ、なにげに心地が良かったと記憶している。きっと、そこが“特別な場所”だったからだ。
これから、佐賀に帰還して玉屋を訪れても、もう南館7階にあの場所はない…この感情の根元はそこにあるらしい。
――私という人間も、ずいぶんと“欲張り”なのか。
最近では、大物ミュージシャンの記念コンサートもこなせる『SAGAアリーナ』の開業に大喜び。駅内商業施設『サガハツ』が出来たことも快く思っていた。
その一方で、佐賀に帰ったら、あって当然と思っていた施設がなくなると、強い落ち込みを感じるのだ。
「古き良きものが残って、新しい風も吹き込む」
佐賀には、そうあってほしいと思うが、おそらく、わがままな願望なのだろう。
私に何ができるわけでもない。佐賀県から遠くにいる分、情報だけが届いて、余計に、もどかしいところがある。
異常に暑かった、この夏も過ぎ去っていく。今回はいまの、この気持ちだけを記しておきたい。
タグ :佐賀
2023年03月02日
「出られるが入れない、SAGA」
こんばんは。
最近、佐賀の話が出るたびに、よく耳にするキーワードが、幾つかあります。その1つが「佐賀は、出られるけど入れない」です。
ご存知の方も多いと思いますが、元ネタは昨年12月の漫才コンクール『M-1グランプリ』で“さや香”というコンビが披露した「免許返納」を題材にした漫才。
その終盤では「免許返納でタクシー料金を割り引く」という“佐賀県”の存在が、カギとなっていました。佐賀以外では、難しい構成ではないかとも感じます。
おそらくは会場でも、全国のお茶の間でも、「佐賀はでれるけど入られへん」というフレーズで、爆笑の渦が巻き起こったと思われます。

――ネットニュース等でも話題となった、この漫才。
佐賀県が直近の「都道府県魅力度ランキング」で、47位となってしまった事と並んで、よく使われるネタです。
このように佐賀県出身者である私にとっては“道具”が次々と手元に集まって、もはや故郷・佐賀を紹介する材料には事欠きません。
そして以前に比して、近隣の商業施設では、佐賀県産の商品が陳列棚で、次々と良いポジションを確保。
〔参照(前半):「オールド・イマリ・ロマンス」〕
民放テレビ局の全国放送でも、佐賀の番組が連発されるなど、実のところ、「佐賀の勢い」を生活の端々で感じているところです。
〔参照:「もしかしてだけど、言いたい事がある」〕
――しかし、先ほどの漫才のセリフは結構、響きました。
「佐賀は出れるけど入られへん!」
これは県外(特に九州の外まで)出てしまった人、そして、年齢が高い人ほど、染み入る言葉ではないかと思います。
「故郷は遠くにありて…」とか言いますが、他地域に「生活基盤ができており、もはや簡単には動けない」という方も多いでしょう。
今春にも「佐賀を愛するものの、あえて大都市圏に向かう」若者が、県内から数多く旅立っていくことと思います。
心のどこかで「佐賀への帰り道」は意識してほしいと考えますし、また佐賀県も「出てからも入れる場所」であってほしいと、切に思います。

――長い前置きでしたが、本題です。
「幕末!出られるが入れない、佐賀藩」
いや、基本的には出る事も難しかったのですが、本編・第18話のおさらいも兼ねて、2人の脱藩者のその後を追います。
○ケース1:佐賀藩士・江藤新平
文久二年(1862年)六月に佐賀を脱藩し、京都での情報収集にあたります。
この脱藩の目的は、佐賀の大殿(前藩主)・鍋島直正に、幕末動乱の中心地・京の都の情勢を伝えること。
本編でも、夜更けまで報告書をまとめて寝不足の江藤の姿を描いています。
〔参照(中盤):第18話「京都見聞」⑱(秋風の吹く頃に)〕
――結果から言えば、江藤が頑張って書いた報告書は、
身分の差を超えて、しっかり鍋島直正に届きました。直正公は報告書を一読して、江藤新平の才能に気付きます。
そして、江藤の父・助右衛門に長男・新平を連れ戻すよう命じたそうです。
⇒〔ケース1:結論〕飛び抜けた才能があれば、佐賀から出ても呼び戻される。

○ケース2:小城の大庄屋・古賀利渉
安政五年(1858年)に佐賀、詳しく言えば小城支藩から抜け出した人物。
本編でも登場していますが、「祇園太郎」と名乗って幕末の京都などで活動した、尊王攘夷の志士です。
脱藩の動機や活動にも不明な点が多く、小城では立派な大庄屋だったものの、尊攘思想に感化されて脱藩したと言われます。
江藤新平が脱藩した時点では、長崎に居た可能性もありますが、本編では京都の“案内役”として登場しました。
〔参照:第18話「京都見聞」⑦(ちょっと、待たんね!)〕
幕末の京都では“佐賀の志士”がほぼ活動しておらず、江藤の脱藩にも何か「祇園太郎」が関わったのでは…という推測からの筋書きです。
――なお、祇園太郎(古賀利渉)の行き着いた先ですが、
幕末のうちに、地元・小城に戻ってきています。
佐賀藩の重臣で様々な記録を残している、鍋島夏雲によると、この祇園太郎は「三百諸侯の情報を送ってくる」と評されたそうです。
各地の志士たちと関わって、持ち帰った全国の情報は、佐賀藩にとって価値のある内容でした。
⇒〔ケース2:結論〕地元のために役立つと、佐賀から出ても帰って来られる。

――この「幕末、佐賀藩から出ても入れた」条件を見ると…
意外や、幕末でも現代でも、基本はあまり変わらないようにも思います。
先ほどの漫才では「人間が普通に生きてたら、佐賀に行くタイミングはない!」という旨の強烈なセリフもありました。
私の曲解では「漫然と日々を生きるようでは、“佐賀への道”は開かないぞ!」という警句に聞こえてきます。
「佐賀は出られるばってん、入れんとよ…」
忙しく歳月が過ぎれば、遙かに遠くに感じる佐賀。普通以上の生き方をすれば、たどり着くことが出来るのか。とりあえず私も、頑張ってみます。
最近、佐賀の話が出るたびに、よく耳にするキーワードが、幾つかあります。その1つが「佐賀は、出られるけど入れない」です。
ご存知の方も多いと思いますが、元ネタは昨年12月の漫才コンクール『M-1グランプリ』で“さや香”というコンビが披露した「免許返納」を題材にした漫才。
その終盤では「免許返納でタクシー料金を割り引く」という“佐賀県”の存在が、カギとなっていました。佐賀以外では、難しい構成ではないかとも感じます。
おそらくは会場でも、全国のお茶の間でも、「佐賀はでれるけど入られへん」というフレーズで、爆笑の渦が巻き起こったと思われます。
――ネットニュース等でも話題となった、この漫才。
佐賀県が直近の「都道府県魅力度ランキング」で、47位となってしまった事と並んで、よく使われるネタです。
このように佐賀県出身者である私にとっては“道具”が次々と手元に集まって、もはや故郷・佐賀を紹介する材料には事欠きません。
そして以前に比して、近隣の商業施設では、佐賀県産の商品が陳列棚で、次々と良いポジションを確保。
〔参照(前半):
民放テレビ局の全国放送でも、佐賀の番組が連発されるなど、実のところ、「佐賀の勢い」を生活の端々で感じているところです。
〔参照:
――しかし、先ほどの漫才のセリフは結構、響きました。
「佐賀は出れるけど入られへん!」
これは県外(特に九州の外まで)出てしまった人、そして、年齢が高い人ほど、染み入る言葉ではないかと思います。
「故郷は遠くにありて…」とか言いますが、他地域に「生活基盤ができており、もはや簡単には動けない」という方も多いでしょう。
今春にも「佐賀を愛するものの、あえて大都市圏に向かう」若者が、県内から数多く旅立っていくことと思います。
心のどこかで「佐賀への帰り道」は意識してほしいと考えますし、また佐賀県も「出てからも入れる場所」であってほしいと、切に思います。
――長い前置きでしたが、本題です。
「幕末!出られるが入れない、佐賀藩」
いや、基本的には出る事も難しかったのですが、本編・第18話のおさらいも兼ねて、2人の脱藩者のその後を追います。
○ケース1:佐賀藩士・江藤新平
文久二年(1862年)六月に佐賀を脱藩し、京都での情報収集にあたります。
この脱藩の目的は、佐賀の大殿(前藩主)・鍋島直正に、幕末動乱の中心地・京の都の情勢を伝えること。
本編でも、夜更けまで報告書をまとめて寝不足の江藤の姿を描いています。
〔参照(中盤):
――結果から言えば、江藤が頑張って書いた報告書は、
身分の差を超えて、しっかり鍋島直正に届きました。直正公は報告書を一読して、江藤新平の才能に気付きます。
そして、江藤の父・助右衛門に長男・新平を連れ戻すよう命じたそうです。
⇒〔ケース1:結論〕飛び抜けた才能があれば、佐賀から出ても呼び戻される。
○ケース2:小城の大庄屋・古賀利渉
安政五年(1858年)に佐賀、詳しく言えば小城支藩から抜け出した人物。
本編でも登場していますが、「祇園太郎」と名乗って幕末の京都などで活動した、尊王攘夷の志士です。
脱藩の動機や活動にも不明な点が多く、小城では立派な大庄屋だったものの、尊攘思想に感化されて脱藩したと言われます。
江藤新平が脱藩した時点では、長崎に居た可能性もありますが、本編では京都の“案内役”として登場しました。
〔参照:
幕末の京都では“佐賀の志士”がほぼ活動しておらず、江藤の脱藩にも何か「祇園太郎」が関わったのでは…という推測からの筋書きです。
――なお、祇園太郎(古賀利渉)の行き着いた先ですが、
幕末のうちに、地元・小城に戻ってきています。
佐賀藩の重臣で様々な記録を残している、鍋島夏雲によると、この祇園太郎は「三百諸侯の情報を送ってくる」と評されたそうです。
各地の志士たちと関わって、持ち帰った全国の情報は、佐賀藩にとって価値のある内容でした。
⇒〔ケース2:結論〕地元のために役立つと、佐賀から出ても帰って来られる。
――この「幕末、佐賀藩から出ても入れた」条件を見ると…
意外や、幕末でも現代でも、基本はあまり変わらないようにも思います。
先ほどの漫才では「人間が普通に生きてたら、佐賀に行くタイミングはない!」という旨の強烈なセリフもありました。
私の曲解では「漫然と日々を生きるようでは、“佐賀への道”は開かないぞ!」という警句に聞こえてきます。
「佐賀は出られるばってん、入れんとよ…」
忙しく歳月が過ぎれば、遙かに遠くに感じる佐賀。普通以上の生き方をすれば、たどり着くことが出来るのか。とりあえず私も、頑張ってみます。
2023年02月10日
「オールド・イマリ・ロマンス」
こんばんは。
“本編”の合間にお送りする、私の日記的な投稿です。最近なんとなく気になるのが、NHK土曜ドラマ『探偵ロマンス』。
若き日、まだ才能を開花させていない推理作家・江戸川乱歩が主人公。ある老齢の名探偵の助手となって、「わからない、だから知りたい」と奮闘する話。
タイトルにある「ロマンス」という言葉は、語源では、恋愛だけを対象としたものではなく、空想(伝奇)小説の意にも取れるようです。
…というわけで、今日は“紅茶”と対話する不思議話です。
――慌ただしく流れる日々に、出会ったものがある。
ある日の昼下がりに「珍しい客を見かけた」と、私はそんな一報を受けていた。
夜になって仕事を終え、人混みの中で長い帰路を戻った私。椅子に腰掛けて、そいつが現れるのを待った。
「よう、兄さん。久しぶりだな。」
「貴方は“ウレシノ”じゃないか。なぜ、こんなところに。」

――事前に聞いてはいたが、私は、やはり目を見張った。
このような都会の片隅に、佐賀に居るはずの“嬉野紅茶”が来ているなんて。
「なんだい、疲れが顔に出てるぞ。」
「そこそこ、頑張っているからな。最近じゃ、朝が辛くて仕方ない。」
ほのかな茶葉の香り。一見渋い感じだが、眠たい朝でも飲みやすい爽やかな紅茶だ。ウレシノからの語りかけに、私はこのように返した。
――私が、その“嬉野紅茶”と出会ったのは、
昨年の初夏。およそ2年半ぶりに、佐賀への帰還を果たした時だった。
一口、その紅茶を飲んだ時、私はこう思った。「紅茶は嬉野(ウレシノ)と、それ以外に分類されるのか!」と。そのぐらいの衝撃だったのだ。
〔参照:連続ブログ小説「聖地の剣」(9)“醒覚”の紅茶〕
ウレシノと名乗る紅茶は、軽い笑みを浮かべ…いや、茶葉を浮かべたかのように続ける。
「兄さん、そう言ってくれるのは“嬉しいの”だがな。」
「…どういうことだ。」
どうやら私が怪訝(けげん)に思っているのは、表情に出ているようだ。
「まぁ、佐賀の紅茶は、俺(ウレシノ)だけじゃない…ってことだ。」

――私は困惑した。佐賀で“和紅茶”と言えば、嬉野だろう。
疑いなく、そう思っていたのだが、他にもあるのか。佐賀の和紅茶が。
「あいつだ。“イマリ”だよ。まだ、会ったことは無いかもしれんな。」
「ちょっと待て。“伊万里紅茶”だって…!?聞いたことがないぞ。」
「そこが、兄さんの調べの浅いところさ。まぁ幕末の佐賀を語るんなら、もう少し頑張るんだな。」
私には、どうも詰めが甘いところがある。ウレシノは、その甘さを指摘した。
ところで、嬉野紅茶は和菓子の甘さを引き立てるらしい。この辺りに“お茶”として揺るがない信念のようなものを感じるのだ。
――日本茶のブランドとして知られる、嬉野茶だが、
幕末期には紅茶の姿で、世界で活躍した。当時、開国したばかりの日本にとっては、主要な輸出品の1つでもあった。
〔参照(後半):第14話「遣米使節」②(オランダ商館の午後)〕
「イマリと言えば、陶磁器ではないのか…?」
「お察しのとおりですが、伊万里には幾つもの顔があるとご理解ください。」

「…いつの間に!」
いきなり隣に現れた、その紅茶は“イマリ”と名乗った。私にとっては、未知なる存在の伊万里紅茶だ。
そのブランド名から、どことなく紳士然とした印象を受けるが、自然栽培の力強さを持つという。
伊万里の紅茶には毎日でも飲める、普段使いの良さがあるようだ。高級感があるのか、親しみやすいのか…ますます、わからない。
――陶磁器について、私は充分な知識が得られていない。
しかし、いずれはパリ万博(1867年)やウィーン万博(1873年)の話を書くつもりがある。そこまでに、ある程度は知りたい。
江戸期を通じて、陶磁器の積出港だった伊万里から長崎を経て、海外に出たのは“古伊万里”だったと理解する。
主に欧州では「オールド・イマリ」と呼ばれたのだろう。何だか浪漫(ロマン)を感じる響きなのである。
“伊万里”は有田焼をはじめ、周辺地域から集まる“肥前磁器”の総称らしい。長崎県の波佐見焼などは「普段使い」を追求しているとも聞く。

むしろ伊万里で生産したのは、将軍や大名への献上(贈答)品に使う国内向け高級磁器で、“鍋島”の名を冠する伊万里焼。
「たしかに、伊万里の顔は1つではない…か。」
秘窯の里かと思えば、伝統の港湾都市でもある。プロフィールにも、二面性があって、どことなくミステリアスに感じる街なのだ。
「…さて、飲んでみれば、あなたにもわかるかもしれませんよ。」
“本編”の合間にお送りする、私の日記的な投稿です。最近なんとなく気になるのが、NHK土曜ドラマ『探偵ロマンス』。
若き日、まだ才能を開花させていない推理作家・江戸川乱歩が主人公。ある老齢の名探偵の助手となって、「わからない、だから知りたい」と奮闘する話。
タイトルにある「ロマンス」という言葉は、語源では、恋愛だけを対象としたものではなく、空想(伝奇)小説の意にも取れるようです。
…というわけで、今日は“紅茶”と対話する不思議話です。
――慌ただしく流れる日々に、出会ったものがある。
ある日の昼下がりに「珍しい客を見かけた」と、私はそんな一報を受けていた。
夜になって仕事を終え、人混みの中で長い帰路を戻った私。椅子に腰掛けて、そいつが現れるのを待った。
「よう、兄さん。久しぶりだな。」
「貴方は“ウレシノ”じゃないか。なぜ、こんなところに。」
――事前に聞いてはいたが、私は、やはり目を見張った。
このような都会の片隅に、佐賀に居るはずの“嬉野紅茶”が来ているなんて。
「なんだい、疲れが顔に出てるぞ。」
「そこそこ、頑張っているからな。最近じゃ、朝が辛くて仕方ない。」
ほのかな茶葉の香り。一見渋い感じだが、眠たい朝でも飲みやすい爽やかな紅茶だ。ウレシノからの語りかけに、私はこのように返した。
――私が、その“嬉野紅茶”と出会ったのは、
昨年の初夏。およそ2年半ぶりに、佐賀への帰還を果たした時だった。
一口、その紅茶を飲んだ時、私はこう思った。「紅茶は嬉野(ウレシノ)と、それ以外に分類されるのか!」と。そのぐらいの衝撃だったのだ。
〔参照:
ウレシノと名乗る紅茶は、軽い笑みを浮かべ…いや、茶葉を浮かべたかのように続ける。
「兄さん、そう言ってくれるのは“嬉しいの”だがな。」
「…どういうことだ。」
どうやら私が怪訝(けげん)に思っているのは、表情に出ているようだ。
「まぁ、佐賀の紅茶は、俺(ウレシノ)だけじゃない…ってことだ。」
――私は困惑した。佐賀で“和紅茶”と言えば、嬉野だろう。
疑いなく、そう思っていたのだが、他にもあるのか。佐賀の和紅茶が。
「あいつだ。“イマリ”だよ。まだ、会ったことは無いかもしれんな。」
「ちょっと待て。“伊万里紅茶”だって…!?聞いたことがないぞ。」
「そこが、兄さんの調べの浅いところさ。まぁ幕末の佐賀を語るんなら、もう少し頑張るんだな。」
私には、どうも詰めが甘いところがある。ウレシノは、その甘さを指摘した。
ところで、嬉野紅茶は和菓子の甘さを引き立てるらしい。この辺りに“お茶”として揺るがない信念のようなものを感じるのだ。
――日本茶のブランドとして知られる、嬉野茶だが、
幕末期には紅茶の姿で、世界で活躍した。当時、開国したばかりの日本にとっては、主要な輸出品の1つでもあった。
〔参照(後半):
「イマリと言えば、陶磁器ではないのか…?」
「お察しのとおりですが、伊万里には幾つもの顔があるとご理解ください。」
「…いつの間に!」
いきなり隣に現れた、その紅茶は“イマリ”と名乗った。私にとっては、未知なる存在の伊万里紅茶だ。
そのブランド名から、どことなく紳士然とした印象を受けるが、自然栽培の力強さを持つという。
伊万里の紅茶には毎日でも飲める、普段使いの良さがあるようだ。高級感があるのか、親しみやすいのか…ますます、わからない。
――陶磁器について、私は充分な知識が得られていない。
しかし、いずれはパリ万博(1867年)やウィーン万博(1873年)の話を書くつもりがある。そこまでに、ある程度は知りたい。
江戸期を通じて、陶磁器の積出港だった伊万里から長崎を経て、海外に出たのは“古伊万里”だったと理解する。
主に欧州では「オールド・イマリ」と呼ばれたのだろう。何だか浪漫(ロマン)を感じる響きなのである。
“伊万里”は有田焼をはじめ、周辺地域から集まる“肥前磁器”の総称らしい。長崎県の波佐見焼などは「普段使い」を追求しているとも聞く。
むしろ伊万里で生産したのは、将軍や大名への献上(贈答)品に使う国内向け高級磁器で、“鍋島”の名を冠する伊万里焼。
「たしかに、伊万里の顔は1つではない…か。」
秘窯の里かと思えば、伝統の港湾都市でもある。プロフィールにも、二面性があって、どことなくミステリアスに感じる街なのだ。
「…さて、飲んでみれば、あなたにもわかるかもしれませんよ。」
2023年01月13日
「もしかしてだけど、言いたい事がある」
こんばんは。
新年早々に、佐賀県内に住む叔父上からの連絡があり、民放のテレビ番組をチェックしてみたところ、意外な情報に行き当たりました。
今回、“本編”への導入も兼ねますが、少し意表を突いた話なので、柔らかくお読みいただければ幸いです。
――今週始めから、フジテレビ系列で、
全国ネットの『ぽかぽか』という、昼の新番組がスタートしています。
平日昼のバラエティーであれば、ふだん私が目にする事はないのですが、この『ぽかぽか』という番組の情報は、叔父上からの連絡で抑えていました。
「佐賀のローカル番組が、全国ネットで見られるとよ。」という一言。同番組を制作しているサガテレビで、全国放送の告知があったそうです。
「少しでも佐賀が映れば、良かったとしよう」ぐらいの気持ちで録画をしました。

――「もしかしてだけど~♪」
この番組(『ぽかぽか』)内の企画にあったのは、地域のローカル番組を全国ネットで流すという試みです。
もちろん昼の新番組だから、視聴率は「喉から手が出るほどに」欲しいはずで、「必勝を期している」に違いありません。
そんな勝負の1週目に選択したのが、サガテレビ『どぶろっくの一物』という、佐賀の番組だったようです。
こうして1月9日(月)から5日間にわたり、正味30分程度は、佐賀ローカルの番組が全国ネットで流れることに。
以降、佐賀県内で同番組を見ている方には、違和感があるかもしれませんが、そもそも郷里から離れている私には初見なので、その感覚でご覧ください。
――ギターによる軽妙なメロディーから繰り出されるのは…
佐賀県(基山町)出身、お笑い芸人・どぶろっくの2人が得手とする“下ネタ”の数々が披露されます。
これが佐賀県内でロケをする随所で上手い具合に歌唱されます。“街ブラ”の中で、美味な食事に出会えば「ウマイチモツ」という決めゼリフもある様子。

昭和期のテレビは自由そのものな感じでしたが、ある意味で現在のテレビでは、“禁じ手”となりうる部分への挑戦なのかもしれません。
これを、現代の日本に蔓延する息苦しさに抗い、閉塞感を打ち破る試みだと考えれば、また見え方も変わるのでしょう。
あるいは、やっぱり“下ネタ”に聞こえるとしても、許容範囲は人それぞれ…と考え、話を次に進めます。
――幕末期、とても熱かった“佐賀”。
細かく言えば“どぶろっく”さんの出身地・基山町は、私がメインテーマとする、佐賀藩内ではなく、対馬藩の田代領にあたるはずです。
“本編”・第16話「攘夷沸騰」でも、現在では佐賀県にあたる地域の対馬藩士たちの活躍を少し描いています。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑳(基山の誇り、田代の想い)〕
当時、この地域にも、幕末期の熱い風が強く吹いていたことは言うまでもなく、しかも、佐賀県内の話なので、表現したい気持ちがあります。
しかし幕末の話が、サガテレビ『どぶろっくの一物』が全国で紹介されることと、どう関係するかといえば…

――「言いたい事がある~♪」
実のところ、この“どぶろっく”の2人(森慎太郎さん・江口直人さん)には、既に「幕末期の大河ドラマ」への出演歴があるそうです。
2015年大河ドラマ『花燃ゆ』に出演。しかも“端役”ではなく、歴史の教科書でも扱いの大きい重要人物のキャストになっています。
なんと、その配役は一橋慶喜〔演:森慎太郎〕と島津久光〔演:江口直人〕。
もともと、役者志望だった方々とは聞きますが、幕末期において、江戸幕府の最後の将軍と、政局を大きく動かした薩摩藩の国父(藩主の父)。
さすがに予想外の配役だったようで、当時のざわめきが、今でもインターネット上に残っていました。
――私も、この配役を知らなかったので、驚きました。
私は、たぶん放送回を見ていないと思われますが、これを利用して“本編”の時代背景として、補足します。
江藤新平が佐賀を脱藩し、京都で活動していた、文久二年(1862年)夏。
同年春に京都で藩内の勤王派の勢力を一掃した、薩摩の国父・島津久光は薩摩藩兵を率いて、意気揚々と江戸へと向かったそうです。
〔参照:第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕
これは以前に、薩摩藩が将軍候補として推した、一橋慶喜らを幕政の中枢に据えて、薩摩の影響力を強めるための行動だったと言われています。

――但し、2015年大河『花燃ゆ』は、長州藩を軸に展開した話。
江戸幕府最後の将軍となる一橋慶喜や薩摩藩の島津久光の登場は少なめと思いますが、“どぶろっく”の2人が演じたと思うと不思議な感覚があります。
話が二転三転しましたが、民放の全国ネットで、佐賀のローカル番組が放送されているのは、痛快事ではありました。
ちなみに同番組での“一物”(いちもつ)とは、一番の物(ナンバーワン)・唯一の物(オンリーワン)を指すのだとか。
知っている人には、すでに魅力がある佐賀県だと思いますので、新年早々に認知度も少し上がって良いのかも…と感じました。
新年早々に、佐賀県内に住む叔父上からの連絡があり、民放のテレビ番組をチェックしてみたところ、意外な情報に行き当たりました。
今回、“本編”への導入も兼ねますが、少し意表を突いた話なので、柔らかくお読みいただければ幸いです。
――今週始めから、フジテレビ系列で、
全国ネットの『ぽかぽか』という、昼の新番組がスタートしています。
平日昼のバラエティーであれば、ふだん私が目にする事はないのですが、この『ぽかぽか』という番組の情報は、叔父上からの連絡で抑えていました。
「佐賀のローカル番組が、全国ネットで見られるとよ。」という一言。同番組を制作しているサガテレビで、全国放送の告知があったそうです。
「少しでも佐賀が映れば、良かったとしよう」ぐらいの気持ちで録画をしました。
――「もしかしてだけど~♪」
この番組(『ぽかぽか』)内の企画にあったのは、地域のローカル番組を全国ネットで流すという試みです。
もちろん昼の新番組だから、視聴率は「喉から手が出るほどに」欲しいはずで、「必勝を期している」に違いありません。
そんな勝負の1週目に選択したのが、サガテレビ『どぶろっくの一物』という、佐賀の番組だったようです。
こうして1月9日(月)から5日間にわたり、正味30分程度は、佐賀ローカルの番組が全国ネットで流れることに。
以降、佐賀県内で同番組を見ている方には、違和感があるかもしれませんが、そもそも郷里から離れている私には初見なので、その感覚でご覧ください。
――ギターによる軽妙なメロディーから繰り出されるのは…
佐賀県(基山町)出身、お笑い芸人・どぶろっくの2人が得手とする“下ネタ”の数々が披露されます。
これが佐賀県内でロケをする随所で上手い具合に歌唱されます。“街ブラ”の中で、美味な食事に出会えば「ウマイチモツ」という決めゼリフもある様子。
昭和期のテレビは自由そのものな感じでしたが、ある意味で現在のテレビでは、“禁じ手”となりうる部分への挑戦なのかもしれません。
これを、現代の日本に蔓延する息苦しさに抗い、閉塞感を打ち破る試みだと考えれば、また見え方も変わるのでしょう。
あるいは、やっぱり“下ネタ”に聞こえるとしても、許容範囲は人それぞれ…と考え、話を次に進めます。
――幕末期、とても熱かった“佐賀”。
細かく言えば“どぶろっく”さんの出身地・基山町は、私がメインテーマとする、佐賀藩内ではなく、対馬藩の田代領にあたるはずです。
“本編”・第16話「攘夷沸騰」でも、現在では佐賀県にあたる地域の対馬藩士たちの活躍を少し描いています。
〔参照:
当時、この地域にも、幕末期の熱い風が強く吹いていたことは言うまでもなく、しかも、佐賀県内の話なので、表現したい気持ちがあります。
しかし幕末の話が、サガテレビ『どぶろっくの一物』が全国で紹介されることと、どう関係するかといえば…
――「言いたい事がある~♪」
実のところ、この“どぶろっく”の2人(森慎太郎さん・江口直人さん)には、既に「幕末期の大河ドラマ」への出演歴があるそうです。
2015年大河ドラマ『花燃ゆ』に出演。しかも“端役”ではなく、歴史の教科書でも扱いの大きい重要人物のキャストになっています。
なんと、その配役は一橋慶喜〔演:森慎太郎〕と島津久光〔演:江口直人〕。
もともと、役者志望だった方々とは聞きますが、幕末期において、江戸幕府の最後の将軍と、政局を大きく動かした薩摩藩の国父(藩主の父)。
さすがに予想外の配役だったようで、当時のざわめきが、今でもインターネット上に残っていました。
――私も、この配役を知らなかったので、驚きました。
私は、たぶん放送回を見ていないと思われますが、これを利用して“本編”の時代背景として、補足します。
江藤新平が佐賀を脱藩し、京都で活動していた、文久二年(1862年)夏。
同年春に京都で藩内の勤王派の勢力を一掃した、薩摩の国父・島津久光は薩摩藩兵を率いて、意気揚々と江戸へと向かったそうです。
〔参照:
これは以前に、薩摩藩が将軍候補として推した、一橋慶喜らを幕政の中枢に据えて、薩摩の影響力を強めるための行動だったと言われています。
――但し、2015年大河『花燃ゆ』は、長州藩を軸に展開した話。
江戸幕府最後の将軍となる一橋慶喜や薩摩藩の島津久光の登場は少なめと思いますが、“どぶろっく”の2人が演じたと思うと不思議な感覚があります。
話が二転三転しましたが、民放の全国ネットで、佐賀のローカル番組が放送されているのは、痛快事ではありました。
ちなみに同番組での“一物”(いちもつ)とは、一番の物(ナンバーワン)・唯一の物(オンリーワン)を指すのだとか。
知っている人には、すでに魅力がある佐賀県だと思いますので、新年早々に認知度も少し上がって良いのかも…と感じました。
2023年01月02日
「夢と冒険の、SAGA」
こんばんは。
「一年の計は、元旦にあり」と言いますので、佐賀についても考えます。昨年、長くコロナ禍に隔てられ3年振り、わずかな時間でも佐賀に“帰藩”できました。
ここで「佐賀で調べ物も要るし、ライトファンタジーも見たい」と思い「やるぞ!」と意気込むも、仕事等が忙しく、動ける気配は無いまま年は暮れました。
最近は、いつも超高速で“帰藩”しては、戻らねばなりません。本当は、武雄で、嬉野で、古湯で…ゆっくり、佐賀の温泉につかりたい。
本日は気持ちだけでも「冒険はいつだって想いのままに」と、つぶやきます。

――“都会”と呼ばれる場所の片隅で、小競り合いを繰り返す日々。
その間にも、どんどんどんと…佐賀は変化しており、逆に置いていかれている感じがあります。
建設中だった「SAGAアリーナ」も今年5月から始動するらしく、松任谷由実やB’zなど“伝説級”大物アーティストも、続々と佐賀で公演予定だとか。
ディズニー・オン・アイスの公演も予定にあり、「伝説も、夢の世界も、佐賀に来る」時代の到来なのかもしれません。
――皆様は、地元メディアの情報から…
意識せずとも耳に入るかもしれませんが、私は先ほどの情報をインターネット上の記事でたまたま見かけたところです。
「これは、佐賀が“都会化”してきている…?」
大都市圏の優位点の一角と言える「参加したいイベントに行きやすい」要素。これからの佐賀は、こういうポイントを抑える戦略なのか…と感じるところも。

※嬉野温泉
――佐賀県の、デザインマンホールの話をよく聞きます。
以前から『ゾンビランドサガ』のマンホールが佐賀県内20市町に設置される件は注目しています。
〔参照(中盤):連続ブログ小説「聖地の剣」(21)下も向いて歩こう、SAGA〕
他にゲームを題材としたマンホールもあるらしい…とは知っていました。
SAGAアリーナ周辺には、その『ロマンシング サガ』のデザインマンホールが配置されたと聞きます。
――「ロマンシング佐賀?」
実は、私も名称しか知らなかったのですが、テレビゲームのシリーズとして、熱烈なファンも多いという『ロマンシング サガ』。
人生の諸先輩の皆様に説明を試みると、西洋的な剣と魔法の世界の物語が多い、ロールプレイング(RPG)と呼ばれる分野のゲームの1種のようです。
ゲームをする人は、主人公のキャラクターを操作し、敵と戦っていく中で、剣や魔法の腕を磨き、装備を整えて成長して、目的の達成のために進みます。
――しばらく前に「ロマンシング サガ2」を特集した番組があり、
やっぱり「サガ」という響きが気になって見てみたのですが、内容としては全く「佐賀」ではありませんでした。
しかし、千年もの時間の経過を、複数の主人公でつないで、閃き(ひらめき)で歴史を作っていく…そんなゲームと聞くと、浪漫のあるシナリオだと感じます。
このシリーズの“サガ”(物語)という響きを、佐賀県側も気になっていたようで、ゲーム製作会社(スクエア・エニックス)とコラボレーションに至ったようです。
異例と思われる自治体とゲームとの共同企画、現時点で8年間も続いているらしく、2022年は乗り物、2021年は温泉(風呂)がテーマだった様子。
〇参考(佐賀県庁)※外部リンク
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387373/index.html (2022乗り物)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384463/index.html (2021佐賀の温泉)

※古湯温泉
――そして、過去(2018年)には「“七賢人”コラボ」という企画も。
過去にCMで耳にした記憶があり、「たぶん、間に合わせの企画だろう…」と、失礼ながら甘く見ていました。
遅まきながら参照すると、佐賀の名君・鍋島直正が、初代司法卿・江藤新平が、政党内閣で初の総理大臣・大隈重信が…
中世の西洋騎士風に、剣と魔法の世界観の雰囲気をまとう“イケメン”キャラクターとして、異様な存在感を見せています。
〇参考(スクウェア・エニックス)※外部リンク
https://romasaga.jp/2018/
※コメントはページ上部、キャラクターはページ下部に表示
――このゲームを作った人のコメントを見て、もっと驚きました。
河津秋敏さんという方。ゲーム業界に疎く、私は存じ上げなかったのですが、とても有名な人で、作品のファンの方からは”神”とまで称されるようです。
以下、コメントより引用します。
①佐賀藩による禁中警護が実現していたら、幕末はどう変わっただろうか。
②江藤と大久保が手を携えていたら、日本はどんな近代化を果たしえたのか。
③大隈が伊藤との権力闘争に敗れなければ、帝国憲法はどんな姿になっていたか。
――以上のような記載を見かけて、私はゾクッとしたわけです。
なぜなら…私の書く“本編”も、鍋島直正・江藤新平・大隈重信が3部作をつないでいくイメージで進めています。
そして、コメントにあった3項目(①~③)のポイントが、各人物に関わる重大な局面と、ズバリ対応していたからです。

※武雄温泉
――さらに、追い打ちのコメントがありました。
「このような夢想は賢人達に笑われることでしょう。夢を描くな、夢を成せと。」
たしかに佐賀の賢人には理想を語るだけでなく、実現する力がありました。
歴史研究者と違った意味で、説得力のあるコメントだったので、第一線で活躍されているクリエイターの才能は凄いものだな…という感想を持ちました。
本当に能力のある方が動けば、相当に良い物語が作れるはずですが、今は私なりの「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を淡々と進めていきたいと思います。
ちなみに①のポイントに対応したお話は、第19話「閑叟上洛」で、鍋島直正が「佐賀藩を率いて京都を警護する」と、朝廷に申し出る場面で描きたいです。
「一年の計は、元旦にあり」と言いますので、佐賀についても考えます。昨年、長くコロナ禍に隔てられ3年振り、わずかな時間でも佐賀に“帰藩”できました。
ここで「佐賀で調べ物も要るし、ライトファンタジーも見たい」と思い「やるぞ!」と意気込むも、仕事等が忙しく、動ける気配は無いまま年は暮れました。
最近は、いつも超高速で“帰藩”しては、戻らねばなりません。本当は、武雄で、嬉野で、古湯で…ゆっくり、佐賀の温泉につかりたい。
本日は気持ちだけでも「冒険はいつだって想いのままに」と、つぶやきます。
――“都会”と呼ばれる場所の片隅で、小競り合いを繰り返す日々。
その間にも、どんどんどんと…佐賀は変化しており、逆に置いていかれている感じがあります。
建設中だった「SAGAアリーナ」も今年5月から始動するらしく、松任谷由実やB’zなど“伝説級”大物アーティストも、続々と佐賀で公演予定だとか。
ディズニー・オン・アイスの公演も予定にあり、「伝説も、夢の世界も、佐賀に来る」時代の到来なのかもしれません。
――皆様は、地元メディアの情報から…
意識せずとも耳に入るかもしれませんが、私は先ほどの情報をインターネット上の記事でたまたま見かけたところです。
「これは、佐賀が“都会化”してきている…?」
大都市圏の優位点の一角と言える「参加したいイベントに行きやすい」要素。これからの佐賀は、こういうポイントを抑える戦略なのか…と感じるところも。
※嬉野温泉
――佐賀県の、デザインマンホールの話をよく聞きます。
以前から『ゾンビランドサガ』のマンホールが佐賀県内20市町に設置される件は注目しています。
〔参照(中盤):
他にゲームを題材としたマンホールもあるらしい…とは知っていました。
SAGAアリーナ周辺には、その『ロマンシング サガ』のデザインマンホールが配置されたと聞きます。
――「ロマンシング佐賀?」
実は、私も名称しか知らなかったのですが、テレビゲームのシリーズとして、熱烈なファンも多いという『ロマンシング サガ』。
人生の諸先輩の皆様に説明を試みると、西洋的な剣と魔法の世界の物語が多い、ロールプレイング(RPG)と呼ばれる分野のゲームの1種のようです。
ゲームをする人は、主人公のキャラクターを操作し、敵と戦っていく中で、剣や魔法の腕を磨き、装備を整えて成長して、目的の達成のために進みます。
――しばらく前に「ロマンシング サガ2」を特集した番組があり、
やっぱり「サガ」という響きが気になって見てみたのですが、内容としては全く「佐賀」ではありませんでした。
しかし、千年もの時間の経過を、複数の主人公でつないで、閃き(ひらめき)で歴史を作っていく…そんなゲームと聞くと、浪漫のあるシナリオだと感じます。
このシリーズの“サガ”(物語)という響きを、佐賀県側も気になっていたようで、ゲーム製作会社(スクエア・エニックス)とコラボレーションに至ったようです。
異例と思われる自治体とゲームとの共同企画、現時点で8年間も続いているらしく、2022年は乗り物、2021年は温泉(風呂)がテーマだった様子。
〇参考(佐賀県庁)※外部リンク
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387373/index.html (2022乗り物)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384463/index.html (2021佐賀の温泉)
※古湯温泉
――そして、過去(2018年)には「“七賢人”コラボ」という企画も。
過去にCMで耳にした記憶があり、「たぶん、間に合わせの企画だろう…」と、失礼ながら甘く見ていました。
遅まきながら参照すると、佐賀の名君・鍋島直正が、初代司法卿・江藤新平が、政党内閣で初の総理大臣・大隈重信が…
中世の西洋騎士風に、剣と魔法の世界観の雰囲気をまとう“イケメン”キャラクターとして、異様な存在感を見せています。
〇参考(スクウェア・エニックス)※外部リンク
https://romasaga.jp/2018/
※コメントはページ上部、キャラクターはページ下部に表示
――このゲームを作った人のコメントを見て、もっと驚きました。
河津秋敏さんという方。ゲーム業界に疎く、私は存じ上げなかったのですが、とても有名な人で、作品のファンの方からは”神”とまで称されるようです。
以下、コメントより引用します。
①佐賀藩による禁中警護が実現していたら、幕末はどう変わっただろうか。
②江藤と大久保が手を携えていたら、日本はどんな近代化を果たしえたのか。
③大隈が伊藤との権力闘争に敗れなければ、帝国憲法はどんな姿になっていたか。
――以上のような記載を見かけて、私はゾクッとしたわけです。
なぜなら…私の書く“本編”も、鍋島直正・江藤新平・大隈重信が3部作をつないでいくイメージで進めています。
そして、コメントにあった3項目(①~③)のポイントが、各人物に関わる重大な局面と、ズバリ対応していたからです。
※武雄温泉
――さらに、追い打ちのコメントがありました。
「このような夢想は賢人達に笑われることでしょう。夢を描くな、夢を成せと。」
たしかに佐賀の賢人には理想を語るだけでなく、実現する力がありました。
歴史研究者と違った意味で、説得力のあるコメントだったので、第一線で活躍されているクリエイターの才能は凄いものだな…という感想を持ちました。
本当に能力のある方が動けば、相当に良い物語が作れるはずですが、今は私なりの「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を淡々と進めていきたいと思います。
ちなみに①のポイントに対応したお話は、第19話「閑叟上洛」で、鍋島直正が「佐賀藩を率いて京都を警護する」と、朝廷に申し出る場面で描きたいです。
2022年10月10日
「都道府県魅力度ランキングへの私見」
こんばんは。
先日、テレビ欄を見て、例年行われている『都道府県魅力度ランキング』が、今年も実施されたことに気付きました。
〔参照・昨年度(前半):「魅力度と“第三の男”(前編)」」
ご存じの方も多いと思いますが、佐賀県は“最下位”47位と発表されました。この結果を受けて、インターネット上で様々なコメントが飛び交ったようです。
以降、テレビやネット上の情報を参照した個人的な感想です。また前提となる情報も不正確な可能性があります。いろいろな角度から考えてみました。
――このランキング自体は、2009年に始まったらしいのですが、
2022年の現在まで、最下位は北関東3県(茨城・栃木・群馬)のいずれかが取っていたと聞きます。
なお、隣接する埼玉県についても下位にある事が多かったようです。
このたび北関東3県による寡占の伝統を打ち破り、初めて最下位の47位を”奪取”したのが、九州地方の佐賀県。
「伝統を革新する佐賀」の姿が、こういった形で登場するのは、意外でした。

※バルーンミュージアム佐賀で撮影
――前年の最下位だった、茨城県の一部には“動揺”の声も。
「最下位の過ごし方」など逆説的なアピールで冊子も作成して、茨城の魅力の発信に努めていると聞くので、戦略の見直しが要るのでしょう。
…今回は、46位・47位で競っている佐賀県に“逆転”されたからです。
また、“最下位の称号”には利用価値もあるらしく「47位を奪われた!」という反応までありますが、素直に喜んでいる茨城県民の方が多いとは思います。
なお発表時のテレビ番組では、ラストの「最下位争い」を最も盛り上げる構成とするのが、恒例のようです。
――ランキング全体としては、前年度からあまり変わらず、
もはや“上位争い”では、視聴者の興味を保つのは難しいという判断なのか、1~5位の発表は「いつもの顔ぶれ」で、あっさりと中盤で終了。
以前、調査項目を軽く調べたことがあり、「認知度」やメディアや伝聞等での「情報接触度」、実際の「訪問経験」等の項目が並ぶのを見かけました。
「…順位が固定化する作りなのか」と感じましたが、「魅力度」の項目に限ったランキングという話もあり、調査対象の抽出・集計方法等の詳細は不知です。
おそらくは、「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」「所属の県がはっきりわかる観光名所がある」ことも、上位へのカギなのではと見ています。

※涼しげな“風鈴”でも知られる、伊万里
――大都市圏や、観光産業が主軸の“県”が圧倒的に有利。
そして、各地方の中間にある県は、他地域の方には位置すら知られていない可能性が高まり、さらに不利になる傾向を感じます。
そのため、「面積が大きい」「各地方の端にある」県には、地理的に目立つというアドバンテージ(優位性)があるという推測です。
例えると、全国の小学生が、日本の地理を勉強する時に覚えてもらいにくい県は、上位にはなりづらいという感覚でしょうか。
たぶん各都道府県の努力では逆転が難しいランキングの構成で、埼玉県や北関東3県が下位なのは、このような理由の積み重ねなのかもしれません。
――この仮説で、「佐賀県は有利なのか」を検討してみます。
「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」
→九州以外の者(もん)にはたぶん…わからんたい。
「所属の県がはっきりわかる観光名所」
→たしかに佐賀は、バルーン飛ばすとき以外は、観光名所ではなかたいね。ばってん、唐津も、伊万里も有田も、吉野ヶ里遺跡も、嬉野温泉も佐賀県とよ。
「面積が大きい」
→そがん、大きか県ではなかよ。限られた土地でも、農業は健闘しとるばい。
「各地方の端にある」
→福岡県と長崎県(双方とも上位ランク)の間やけん、目立たんもんね~。
…以上、主観的な仮説での分析ですが、佐賀県には不利な要素が多く、このランキングの傾向では、上位に浮上する可能性は低いと考えています。

※有田陶器市は佐賀県内でも、全国的な知名度の高い大イベント。
――ほかにも、結構影響がありそうなのが、
「佐賀県出身の芸能人が少ない」
→両隣の福岡県・長崎県では、芸能人が知名度に与える効果は侮れません。
私は、「佐賀県民の気質は、あまり芸能人に向かない」と考えています。佐賀の駅では、飾り気がなく、透明感のある学生たちが通るのを見かけます。
贔屓(ひいき)目かもしれませんが、佐賀に美しさで芸能人に劣らない“原石”はあるのでしょう。でもオーラを発すべきところは、たぶん芸能じゃない。
そして「佐賀の美は、ひたむきに生きる、その日常の中にこそある」というのが、私の持論です。
「あのクスノキのように、そのまま真っ直ぐに伸びていってほしい!」と何だか、こういう気持ちになるのですね。
――個人的な結論として、
「この魅力度ランキングで、上位を目指すのは、ひとまずあきらめましょう。」という提案をしたいと思います。もっと、勝ちを取りに行くべき指標があるはず。
だいたい埼玉県のような、「“さいたま”が主役」の映画まで大ヒットし、異様な存在感を発揮している“強者”ですら45位なのです。
また、大都市圏の中でも、製造業が強みの愛知県は、他の大都市圏(東京都・神奈川県、京都府・大阪府・兵庫県、福岡県)に比べて、順位が低いのです。

※吉野ヶ里遺跡。意外と、時代を先導する傾向の佐賀。それは弥生時代から…
――地元での住みやすさや、産業構造の手堅さは、
知名度寄りの調査では伸びない要素かもしれません。やはり観光・サービス業への重点ランキングと見ました。
佐賀の主要産業といえば、伝統的には農業、窯業、製薬業など。最近ではIT産業の裏方でも活躍していますが、やはり堅実な印象。
真面目に働き、口も堅いので信用度は高いと思いますが、やっぱり地味です。少しでも目立つから「47位を堅守する」のが得策…という意見も見かけます。
――でも、佐賀県の“順位”にかかわらず、
日本全国からも、「佐賀県の位置」ぐらいは知られたいですが、幅広い知名度より、本当に佐賀を好きな人(関係人口)を増やす方が大事な気がします。
個人的には10人が1度だけ来るよりも、1人が10回訪れて深いファンになるのが、佐賀の観光スタイルには合っていると思うからです。
『ゾンビランドサガ』などのアニメ作品の影響で、佐賀を“聖地”と語る人がいるのは、かなり良い事例だと考えます。

※佐賀県でも屈指の“映える“場所、鹿島の祐徳稲荷神社。朱塗りがまばゆい。
――私のイメージでは、日本近代化のドラマの“聖地”である佐賀。
明治初期、佐賀藩士の大木喬任・江藤新平は「東西両都論」をとなえ、東京に首都を移すことを主導しました。
これは、同じく佐賀藩士の大隈重信が、鉄道を敷設する計画ともつながり、「東京-京都間」の”両都”をスムーズに往来する事を見据えた案でした。
以降も、佐賀県は技術者等で活躍する優秀な人材を、首都・東京を中心として、各地へと送り続けてきたはずです。
一般的な知名度は遅れを取っても、まず佐賀と縁のある人から、その魅力に気付いてもらって、全国から佐賀を想う方々が増えてほしいと考えています。
先日、テレビ欄を見て、例年行われている『都道府県魅力度ランキング』が、今年も実施されたことに気付きました。
〔参照・昨年度(前半):
ご存じの方も多いと思いますが、佐賀県は“最下位”47位と発表されました。この結果を受けて、インターネット上で様々なコメントが飛び交ったようです。
以降、テレビやネット上の情報を参照した個人的な感想です。また前提となる情報も不正確な可能性があります。いろいろな角度から考えてみました。
――このランキング自体は、2009年に始まったらしいのですが、
2022年の現在まで、最下位は北関東3県(茨城・栃木・群馬)のいずれかが取っていたと聞きます。
なお、隣接する埼玉県についても下位にある事が多かったようです。
このたび北関東3県による寡占の伝統を打ち破り、初めて最下位の47位を”奪取”したのが、九州地方の佐賀県。
「伝統を革新する佐賀」の姿が、こういった形で登場するのは、意外でした。
※バルーンミュージアム佐賀で撮影
――前年の最下位だった、茨城県の一部には“動揺”の声も。
「最下位の過ごし方」など逆説的なアピールで冊子も作成して、茨城の魅力の発信に努めていると聞くので、戦略の見直しが要るのでしょう。
…今回は、46位・47位で競っている佐賀県に“逆転”されたからです。
また、“最下位の称号”には利用価値もあるらしく「47位を奪われた!」という反応までありますが、素直に喜んでいる茨城県民の方が多いとは思います。
なお発表時のテレビ番組では、ラストの「最下位争い」を最も盛り上げる構成とするのが、恒例のようです。
――ランキング全体としては、前年度からあまり変わらず、
もはや“上位争い”では、視聴者の興味を保つのは難しいという判断なのか、1~5位の発表は「いつもの顔ぶれ」で、あっさりと中盤で終了。
以前、調査項目を軽く調べたことがあり、「認知度」やメディアや伝聞等での「情報接触度」、実際の「訪問経験」等の項目が並ぶのを見かけました。
「…順位が固定化する作りなのか」と感じましたが、「魅力度」の項目に限ったランキングという話もあり、調査対象の抽出・集計方法等の詳細は不知です。
おそらくは、「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」「所属の県がはっきりわかる観光名所がある」ことも、上位へのカギなのではと見ています。
※涼しげな“風鈴”でも知られる、伊万里
――大都市圏や、観光産業が主軸の“県”が圧倒的に有利。
そして、各地方の中間にある県は、他地域の方には位置すら知られていない可能性が高まり、さらに不利になる傾向を感じます。
そのため、「面積が大きい」「各地方の端にある」県には、地理的に目立つというアドバンテージ(優位性)があるという推測です。
例えると、全国の小学生が、日本の地理を勉強する時に覚えてもらいにくい県は、上位にはなりづらいという感覚でしょうか。
たぶん各都道府県の努力では逆転が難しいランキングの構成で、埼玉県や北関東3県が下位なのは、このような理由の積み重ねなのかもしれません。
――この仮説で、「佐賀県は有利なのか」を検討してみます。
「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」
→九州以外の者(もん)にはたぶん…わからんたい。
「所属の県がはっきりわかる観光名所」
→たしかに佐賀は、バルーン飛ばすとき以外は、観光名所ではなかたいね。ばってん、唐津も、伊万里も有田も、吉野ヶ里遺跡も、嬉野温泉も佐賀県とよ。
「面積が大きい」
→そがん、大きか県ではなかよ。限られた土地でも、農業は健闘しとるばい。
「各地方の端にある」
→福岡県と長崎県(双方とも上位ランク)の間やけん、目立たんもんね~。
…以上、主観的な仮説での分析ですが、佐賀県には不利な要素が多く、このランキングの傾向では、上位に浮上する可能性は低いと考えています。
※有田陶器市は佐賀県内でも、全国的な知名度の高い大イベント。
――ほかにも、結構影響がありそうなのが、
「佐賀県出身の芸能人が少ない」
→両隣の福岡県・長崎県では、芸能人が知名度に与える効果は侮れません。
私は、「佐賀県民の気質は、あまり芸能人に向かない」と考えています。佐賀の駅では、飾り気がなく、透明感のある学生たちが通るのを見かけます。
贔屓(ひいき)目かもしれませんが、佐賀に美しさで芸能人に劣らない“原石”はあるのでしょう。でもオーラを発すべきところは、たぶん芸能じゃない。
そして「佐賀の美は、ひたむきに生きる、その日常の中にこそある」というのが、私の持論です。
「あのクスノキのように、そのまま真っ直ぐに伸びていってほしい!」と何だか、こういう気持ちになるのですね。
――個人的な結論として、
「この魅力度ランキングで、上位を目指すのは、ひとまずあきらめましょう。」という提案をしたいと思います。もっと、勝ちを取りに行くべき指標があるはず。
だいたい埼玉県のような、「“さいたま”が主役」の映画まで大ヒットし、異様な存在感を発揮している“強者”ですら45位なのです。
また、大都市圏の中でも、製造業が強みの愛知県は、他の大都市圏(東京都・神奈川県、京都府・大阪府・兵庫県、福岡県)に比べて、順位が低いのです。
※吉野ヶ里遺跡。意外と、時代を先導する傾向の佐賀。それは弥生時代から…
――地元での住みやすさや、産業構造の手堅さは、
知名度寄りの調査では伸びない要素かもしれません。やはり観光・サービス業への重点ランキングと見ました。
佐賀の主要産業といえば、伝統的には農業、窯業、製薬業など。最近ではIT産業の裏方でも活躍していますが、やはり堅実な印象。
真面目に働き、口も堅いので信用度は高いと思いますが、やっぱり地味です。少しでも目立つから「47位を堅守する」のが得策…という意見も見かけます。
――でも、佐賀県の“順位”にかかわらず、
日本全国からも、「佐賀県の位置」ぐらいは知られたいですが、幅広い知名度より、本当に佐賀を好きな人(関係人口)を増やす方が大事な気がします。
個人的には10人が1度だけ来るよりも、1人が10回訪れて深いファンになるのが、佐賀の観光スタイルには合っていると思うからです。
『ゾンビランドサガ』などのアニメ作品の影響で、佐賀を“聖地”と語る人がいるのは、かなり良い事例だと考えます。
※佐賀県でも屈指の“映える“場所、鹿島の祐徳稲荷神社。朱塗りがまばゆい。
――私のイメージでは、日本近代化のドラマの“聖地”である佐賀。
明治初期、佐賀藩士の大木喬任・江藤新平は「東西両都論」をとなえ、東京に首都を移すことを主導しました。
これは、同じく佐賀藩士の大隈重信が、鉄道を敷設する計画ともつながり、「東京-京都間」の”両都”をスムーズに往来する事を見据えた案でした。
以降も、佐賀県は技術者等で活躍する優秀な人材を、首都・東京を中心として、各地へと送り続けてきたはずです。
一般的な知名度は遅れを取っても、まず佐賀と縁のある人から、その魅力に気付いてもらって、全国から佐賀を想う方々が増えてほしいと考えています。
2022年09月23日
「幕末浪漫 西九州新幹線」
こんばんは。
本日、2022年9月23日。この日の到来はずっと気になっていました。
――様々な想いが交錯する、西九州新幹線の開業。
全国に報じられたニュースに映るのは、華やかな開業のセレモニー。期待感にあふれています。
一方で「並行在来線」となる地域があることも、語られていました。
〔参照:「さよなら…ではなく、ありがとう。」〕
こちらの行く先の議論については、佐賀と長崎に現住する方々にお任せするほかなさそうです。

――では、いま私が為すべき事は何か。
やはり西九州地域の幕末期にどれだけのドラマがあったかを、語り続けることか…と考えるところです。
1年と少し前に、新幹線の開業を先取りした企画を書いた事があります。
〔参照:「西九州にほえろ!」〕
――これを「西九州新幹線、五つの駅の物語」として再掲します。
①武雄温泉駅:日本の近代化を牽引した佐賀藩を、先導した人物がいた。
〔参照:「多くの仕事を成し遂げた者」〔武雄温泉駅〕〕
②嬉野温泉駅:英国船を調査した佐賀の侍に“忍者”の役回りがあった。
〔参照:「佐賀の忍者、幕末を走る!」〔嬉野温泉駅〕〕
③新大村駅:倒幕の志士として活躍した大村藩士に、凄腕の剣客がいた。
〔参照:「鞍馬天狗は、長崎の人?」〔新大村駅〕〕
④諫早駅:実は佐賀藩内だった諫早領、日本の最前線で異国と対峙した。
〔参照:「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕〕
⑤長崎駅:江戸期、日本で唯一の“西洋”である長崎は夢の舞台だった。
〔参照:「夢の舞台は、隣の県」〔長崎駅〕〕

――それぞれ、深掘りしたいポイントはありますが、
開業の初日に、あまり細かく語るのも野暮のように思います。
ただ、単なる観光地として見るのは、私の感覚としては勿体(もったい)ない…と言わざるを得ません。
まずは、西九州新幹線の無事の開業を祝したい。“新幹線かもめ”にも、早く乗って見たいという気持ちもあります。
とくに久しぶりに“鉄道駅”が帰ってきた、嬉野の皆様。おめでとうございます。
本日、2022年9月23日。この日の到来はずっと気になっていました。
――様々な想いが交錯する、西九州新幹線の開業。
全国に報じられたニュースに映るのは、華やかな開業のセレモニー。期待感にあふれています。
一方で「並行在来線」となる地域があることも、語られていました。
〔参照:
こちらの行く先の議論については、佐賀と長崎に現住する方々にお任せするほかなさそうです。
――では、いま私が為すべき事は何か。
やはり西九州地域の幕末期にどれだけのドラマがあったかを、語り続けることか…と考えるところです。
1年と少し前に、新幹線の開業を先取りした企画を書いた事があります。
〔参照:
――これを「西九州新幹線、五つの駅の物語」として再掲します。
①武雄温泉駅:日本の近代化を牽引した佐賀藩を、先導した人物がいた。
〔参照:
②嬉野温泉駅:英国船を調査した佐賀の侍に“忍者”の役回りがあった。
〔参照:
③新大村駅:倒幕の志士として活躍した大村藩士に、凄腕の剣客がいた。
〔参照:
④諫早駅:実は佐賀藩内だった諫早領、日本の最前線で異国と対峙した。
〔参照:
⑤長崎駅:江戸期、日本で唯一の“西洋”である長崎は夢の舞台だった。
〔参照:
――それぞれ、深掘りしたいポイントはありますが、
開業の初日に、あまり細かく語るのも野暮のように思います。
ただ、単なる観光地として見るのは、私の感覚としては勿体(もったい)ない…と言わざるを得ません。
まずは、西九州新幹線の無事の開業を祝したい。“新幹線かもめ”にも、早く乗って見たいという気持ちもあります。
とくに久しぶりに“鉄道駅”が帰ってきた、嬉野の皆様。おめでとうございます。
2022年09月20日
「さよなら…ではなく、ありがとう。」
こんばんは。
台風14号は、南九州を中心に猛威をふるった様子が報じられていました。
年々、このような「前例の無い」風水害が多くなっている印象はありますが、可能な範囲で備えるほかない…のかもしれません。
長崎・佐賀の西九州エリアは、何とか大きい被害を免れたようで、どうにか次のイベントに進めるようです。
――「9月23日 西九州新幹線の開業」
佐賀県の西部地域にとっては、分岐点となる出来事でしょうか。武雄市・嬉野市にとっては、待望の開業で周辺の期待も大きいはず。
鹿島市・太良町にとっては、長崎本線がメインルートから外れてしまう感覚が強いかもしれません。
並行在来線としての当該区間を管理するのは、一般社団法人「佐賀長崎鉄道管理センター」と聞きます。
鹿島市に事務所を構える…と他地域にいる私は、最近ようやく知りました。

――「何だか、寂しいなぁ。」
“特急かもめ”は、もう長崎本線を走らないので、そう想うのも当然と思います。
そして9月22日には肥前鹿島駅で、特急かもめに感謝を伝える“卒業式”のようなイベントがあるようです。
22時~23時頃の遅い時間帯ではあるものの、ホームを“かもめ”への感謝で埋め尽くす試みがなされるそうです。
「さよなら」ではなく「ありがとう」。進学や就職、悲喜こもごもの人生を乗せて走ってきた“かもめ”の旅立ちに贈る言葉。

――この展開、泣けてきます。
しかし“佐賀の者”として、ただ感傷に立ち尽くすわけにはいかない…ということなのか。
翌日には「ようこそ かささぎ」という合い言葉とともに、早朝6時台には“特急かささぎ”の出発式。8時台には、その“かささぎ”の出迎えがあるそうです。
その9月23日の肥前鹿島駅は、太良町・鹿島市・白石町・江北町の近隣1市3町で終日イベントがある様子。
https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/26631.html ※外部サイト(鹿島市)
――その『魅力発信フェス@肥前鹿島駅』でも
江北町は、町制70周年記念のテーマソングを舞台で、披露する様子です。
楽曲制作を担当したバンドは“くるり”さんで、曲名は「宝探し」。
個人的には、NHK『ファミリーヒストリー』の主題歌「Remember me(リメンバー・ミー)」などでも耳なじみがある歌手です。

――どんな楽曲か、気になったので…
江北町70周年記念サイトをあたってみると、トップの動画で視聴できました。
https://kouhoku70th.jp/ ※外部サイト(江北町70周年 記念特設サイト)
「宝探しに~夢中になった~♪」というメロディーに乗せてプロモーションビデオ(PV)風に動画が流れます。
もともと音楽を探していたのですが、江北町の学校の先生の目線から、淡々と映し出される“物語”に見入ってしまいました。
――「さよなら…」ではなく、「ありがとう。」
毎年のように、卒業生を見送り続けてきたのだろう、中年の教師。
“コロナ禍”で日常が失われても、いつもの年のように生徒に過ごしてほしいと、奮闘する様子がうかがえます。
そして、ラスト近くで、この先生は「肥前山口駅」の“卒業”に出会う事に。

――分岐点として親しまれてきた、この駅名も、
9月22日で卒業となります。新しく「江北駅」としての“物語”が続くようです。
「せんせい。」
駅のホームで声をかけられた教師は、すっかり成長して、2人の子どもを連れた、かつての卒業生に声をかけられます。
たぶん、卒業生から笑顔で声をかけられるのは、“教師冥利“に尽きる瞬間なのでしょう。

――「宝探し」とは、よく言ったもので、
いろいろ考えさせられました。江北町は、良いテーマソングを得たようですね。
私自身が、今行っている事も“宝探し”だと考えています。ほぼリモートの活動ですが、きっと佐賀には、私が見つけるべき“何か”があると。
長崎本線にも88年の歴史があるそうで、これから見つかる“宝”もあるんじゃないかと思います。そのうちに、現地での“発掘”にも向かいたいです。
〔最近の関連記事〕
「そこに“かもめ”は、飛ばずとも…」(太良町)
「“かささぎ”が舞う、干潟の街に」(鹿島市)
「主に江北町民の皆様を対象にしたつぶやき」(江北町)
連続ブログ小説「聖地の剣」(14)泥をすすって花の咲く(白石町)※特産品関連
台風14号は、南九州を中心に猛威をふるった様子が報じられていました。
年々、このような「前例の無い」風水害が多くなっている印象はありますが、可能な範囲で備えるほかない…のかもしれません。
長崎・佐賀の西九州エリアは、何とか大きい被害を免れたようで、どうにか次のイベントに進めるようです。
――「9月23日 西九州新幹線の開業」
佐賀県の西部地域にとっては、分岐点となる出来事でしょうか。武雄市・嬉野市にとっては、待望の開業で周辺の期待も大きいはず。
鹿島市・太良町にとっては、長崎本線がメインルートから外れてしまう感覚が強いかもしれません。
並行在来線としての当該区間を管理するのは、一般社団法人「佐賀長崎鉄道管理センター」と聞きます。
鹿島市に事務所を構える…と他地域にいる私は、最近ようやく知りました。
――「何だか、寂しいなぁ。」
“特急かもめ”は、もう長崎本線を走らないので、そう想うのも当然と思います。
そして9月22日には肥前鹿島駅で、特急かもめに感謝を伝える“卒業式”のようなイベントがあるようです。
22時~23時頃の遅い時間帯ではあるものの、ホームを“かもめ”への感謝で埋め尽くす試みがなされるそうです。
「さよなら」ではなく「ありがとう」。進学や就職、悲喜こもごもの人生を乗せて走ってきた“かもめ”の旅立ちに贈る言葉。
――この展開、泣けてきます。
しかし“佐賀の者”として、ただ感傷に立ち尽くすわけにはいかない…ということなのか。
翌日には「ようこそ かささぎ」という合い言葉とともに、早朝6時台には“特急かささぎ”の出発式。8時台には、その“かささぎ”の出迎えがあるそうです。
その9月23日の肥前鹿島駅は、太良町・鹿島市・白石町・江北町の近隣1市3町で終日イベントがある様子。
https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/26631.html ※外部サイト(鹿島市)
――その『魅力発信フェス@肥前鹿島駅』でも
江北町は、町制70周年記念のテーマソングを舞台で、披露する様子です。
楽曲制作を担当したバンドは“くるり”さんで、曲名は「宝探し」。
個人的には、NHK『ファミリーヒストリー』の主題歌「Remember me(リメンバー・ミー)」などでも耳なじみがある歌手です。
――どんな楽曲か、気になったので…
江北町70周年記念サイトをあたってみると、トップの動画で視聴できました。
https://kouhoku70th.jp/ ※外部サイト(江北町70周年 記念特設サイト)
「宝探しに~夢中になった~♪」というメロディーに乗せてプロモーションビデオ(PV)風に動画が流れます。
もともと音楽を探していたのですが、江北町の学校の先生の目線から、淡々と映し出される“物語”に見入ってしまいました。
――「さよなら…」ではなく、「ありがとう。」
毎年のように、卒業生を見送り続けてきたのだろう、中年の教師。
“コロナ禍”で日常が失われても、いつもの年のように生徒に過ごしてほしいと、奮闘する様子がうかがえます。
そして、ラスト近くで、この先生は「肥前山口駅」の“卒業”に出会う事に。
――分岐点として親しまれてきた、この駅名も、
9月22日で卒業となります。新しく「江北駅」としての“物語”が続くようです。
「せんせい。」
駅のホームで声をかけられた教師は、すっかり成長して、2人の子どもを連れた、かつての卒業生に声をかけられます。
たぶん、卒業生から笑顔で声をかけられるのは、“教師冥利“に尽きる瞬間なのでしょう。
――「宝探し」とは、よく言ったもので、
いろいろ考えさせられました。江北町は、良いテーマソングを得たようですね。
私自身が、今行っている事も“宝探し”だと考えています。ほぼリモートの活動ですが、きっと佐賀には、私が見つけるべき“何か”があると。
長崎本線にも88年の歴史があるそうで、これから見つかる“宝”もあるんじゃないかと思います。そのうちに、現地での“発掘”にも向かいたいです。
〔最近の関連記事〕
2022年08月14日
「有工に見た、“終わらない物語”」
こんにちは。
夏の全国高校野球・甲子園大会に、佐賀県代表で出場した有田工業高校。
同校キャプテンが、試合前に「9年前に1勝している先輩たちを超えたい」と、語っている姿も放送されていました。
昨日の試合では勝ち進むことはできませんでしたが、こうして過去から現在、未来の後輩へと“物語”は受け継がれていくのだな…と感じた場面です。

――春のセンバツ甲子園大会に続いて、遠かった1勝。
実は、個人的にどうしても抜けられない都合が入ってしまい、私は春に続いて、リアルタイムでの応援をしそこないました。
〔参照:「有工の“明るさ”が…」〕
有田工が1点を先制をした時に、家を出る時間となり、出先で逆転された事を知り、また同点に追いついたことも把握します。
どうやら、また点差を付けられたらしい…と認識してから帰宅すると、相手校(島根県・浜田高校)監督の勝利インタビューが放送中…という状況でした。
――録画で振り返るにも、
今回は、大体の試合経過を知っており、盛り上がりに欠けるところがあります。そこで、周辺情報を見ていると「おや…?」と思うことがありました。
有田工関連のニュースや記事が、インターネット上に出始めたからです。
アメリカ・メジャーリーグのサイトにまで、有田工の話題が掲載されたと報じる記事も見かけます。
――その内容は、“打席の変更”について。
有田工業には左右両打席に立てる「スイッチヒッター」がおり、春のセンバツ甲子園でも打席変更の場面を見たように記憶します。
また、夏の地方予選である佐賀大会でも、その話題は出ていたと思います。
ただ夏の甲子園の本大会で、これだけ打席のスイッチ(切り換え)を実行する選手が現れたことに、結構なインパクト(衝撃)があったようなのです。

――これは、“賛否両論”の手法ではあるようで、
相手ピッチャーの投球数を増やしたり、拍子を狂わせる効果を期待するところがあり、「高校生らしくない」という意見もあるようです。
また、技術的には左右双方の打席に練習時間を割くことになり、高いレベルで使いこなすのが難しいという論評も見かけました。
ところが、意外に「今後につながる、面白い試みではないか」という立ち位置での反応が多かったように思います。
――たしかに、1球ごとに、
早足に打席を変更し、そそくさと動き回る姿を見ると「必死な感じ」という印象を受けたのは私だけではないはず。
これも、チームが主導して組織的に連発する作戦ならば、あまり良いイメージでは語られないでしょう。
ただ、個人のアイデアをチームがつぶさずに許容するのは、逆に「懐が深い」感じがしました。
――「創意工夫することをやめず、実践してみる。」
もともと有田工は、明治期に窯業の技術者養成機関として設立された学校が前身と聞いており、創意も、実践も…同校には伝統なのでしょうか。
「個人レベルの貪欲さ、それを受容できる組織…」大きく言えば、現在の日本に不足している要素なのかもしれません。

――かつて、幕末期の佐賀では。
佐賀藩は幕府からの誘いを受け、海外への出展に乗り出しました。1867年(慶応三年)フランス・パリの万国博覧会です。
もともと、海外貿易での販路開拓には熱心な佐賀藩でしたが、有田焼などの陶磁器を主力商品として500箱を超える出品を行ったと聞きます。
これは同時に出展した、幕府と薩摩藩を合わせた数より多いそうで、政治闘争よりも真面目に商売をしようとする佐賀藩…という印象です。
伝統的な皿など実用品中心の品揃えで臨みますが、ヨーロッパで注目はされるものの5分の1程度の商品しかさばけず、販売は成功に至りませんでした。
こうして現地パリに渡った、佐賀の関係者は売れ残り品の処分に奔走することになったそうです。

――そして明治時代となった、日本。
今度は新政府の主導により、1873年(明治六年)オーストリア・ウィーン万国博覧会に臨みました。
この時は、佐賀の出身者が中心メンバーとなり、パリ万博の経験者・佐野常民が現地責任者(副総裁)として派遣されます。
なお、組織トップの総裁は大隈重信ですが、現地入りはしなかったはずです。
ここでパリ万博の反省を活かし、伝統を活かしつつも、日本を強く印象づけるデザインに洗練した、巨大な花びんなどの有田焼が投入されます。
柔軟な発想で対応したことで商業的に成功するだけでなく、ヨーロッパの美術にもインパクトを残す…など、見事に“リベンジ”を果たしたようです。
〔参照:「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(後編)」〕
――夏の高校野球。佐賀県代表が勝ち進めなかったのは悔しいですが…
テレビの解説でも高校生らしいと評された堅実な野球。あわせて夏の甲子園での“打席の変更”を実行して話題となるなど、インパクトも残してくれました。
スイッチヒッターからは、左右の打席を変更する事で“視点”が変わり、冷静に状況が見られるという話もあるようです。
手堅い中にも、創意工夫があって活き活きとした選手たち。有田工には良いものを見させてもらったな…と思います。
夏の全国高校野球・甲子園大会に、佐賀県代表で出場した有田工業高校。
同校キャプテンが、試合前に「9年前に1勝している先輩たちを超えたい」と、語っている姿も放送されていました。
昨日の試合では勝ち進むことはできませんでしたが、こうして過去から現在、未来の後輩へと“物語”は受け継がれていくのだな…と感じた場面です。
――春のセンバツ甲子園大会に続いて、遠かった1勝。
実は、個人的にどうしても抜けられない都合が入ってしまい、私は春に続いて、リアルタイムでの応援をしそこないました。
〔参照:
有田工が1点を先制をした時に、家を出る時間となり、出先で逆転された事を知り、また同点に追いついたことも把握します。
どうやら、また点差を付けられたらしい…と認識してから帰宅すると、相手校(島根県・浜田高校)監督の勝利インタビューが放送中…という状況でした。
――録画で振り返るにも、
今回は、大体の試合経過を知っており、盛り上がりに欠けるところがあります。そこで、周辺情報を見ていると「おや…?」と思うことがありました。
有田工関連のニュースや記事が、インターネット上に出始めたからです。
アメリカ・メジャーリーグのサイトにまで、有田工の話題が掲載されたと報じる記事も見かけます。
――その内容は、“打席の変更”について。
有田工業には左右両打席に立てる「スイッチヒッター」がおり、春のセンバツ甲子園でも打席変更の場面を見たように記憶します。
また、夏の地方予選である佐賀大会でも、その話題は出ていたと思います。
ただ夏の甲子園の本大会で、これだけ打席のスイッチ(切り換え)を実行する選手が現れたことに、結構なインパクト(衝撃)があったようなのです。
――これは、“賛否両論”の手法ではあるようで、
相手ピッチャーの投球数を増やしたり、拍子を狂わせる効果を期待するところがあり、「高校生らしくない」という意見もあるようです。
また、技術的には左右双方の打席に練習時間を割くことになり、高いレベルで使いこなすのが難しいという論評も見かけました。
ところが、意外に「今後につながる、面白い試みではないか」という立ち位置での反応が多かったように思います。
――たしかに、1球ごとに、
早足に打席を変更し、そそくさと動き回る姿を見ると「必死な感じ」という印象を受けたのは私だけではないはず。
これも、チームが主導して組織的に連発する作戦ならば、あまり良いイメージでは語られないでしょう。
ただ、個人のアイデアをチームがつぶさずに許容するのは、逆に「懐が深い」感じがしました。
――「創意工夫することをやめず、実践してみる。」
もともと有田工は、明治期に窯業の技術者養成機関として設立された学校が前身と聞いており、創意も、実践も…同校には伝統なのでしょうか。
「個人レベルの貪欲さ、それを受容できる組織…」大きく言えば、現在の日本に不足している要素なのかもしれません。
――かつて、幕末期の佐賀では。
佐賀藩は幕府からの誘いを受け、海外への出展に乗り出しました。1867年(慶応三年)フランス・パリの万国博覧会です。
もともと、海外貿易での販路開拓には熱心な佐賀藩でしたが、有田焼などの陶磁器を主力商品として500箱を超える出品を行ったと聞きます。
これは同時に出展した、幕府と薩摩藩を合わせた数より多いそうで、政治闘争よりも真面目に商売をしようとする佐賀藩…という印象です。
伝統的な皿など実用品中心の品揃えで臨みますが、ヨーロッパで注目はされるものの5分の1程度の商品しかさばけず、販売は成功に至りませんでした。
こうして現地パリに渡った、佐賀の関係者は売れ残り品の処分に奔走することになったそうです。
――そして明治時代となった、日本。
今度は新政府の主導により、1873年(明治六年)オーストリア・ウィーン万国博覧会に臨みました。
この時は、佐賀の出身者が中心メンバーとなり、パリ万博の経験者・佐野常民が現地責任者(副総裁)として派遣されます。
なお、組織トップの総裁は大隈重信ですが、現地入りはしなかったはずです。
ここでパリ万博の反省を活かし、伝統を活かしつつも、日本を強く印象づけるデザインに洗練した、巨大な花びんなどの有田焼が投入されます。
柔軟な発想で対応したことで商業的に成功するだけでなく、ヨーロッパの美術にもインパクトを残す…など、見事に“リベンジ”を果たしたようです。
〔参照:
――夏の高校野球。佐賀県代表が勝ち進めなかったのは悔しいですが…
テレビの解説でも高校生らしいと評された堅実な野球。あわせて夏の甲子園での“打席の変更”を実行して話題となるなど、インパクトも残してくれました。
スイッチヒッターからは、左右の打席を変更する事で“視点”が変わり、冷静に状況が見られるという話もあるようです。
手堅い中にも、創意工夫があって活き活きとした選手たち。有田工には良いものを見させてもらったな…と思います。
2022年08月11日
「有田の夏と、青春の形…」
こんばんは。本日は有田町をテーマにつぶやきます。
「青春の真っ只中の人は書くことができないので、その時代を終えた人が書くのが“青春小説”…」どこかで、そんな意味合いの言葉を聞いた気がします。
私はといえば、青春の終わりから、幾多の歳月を隔て、遅まきながら気付いた佐賀の歴史の価値に夢を追いかけている。
…これを見苦しいと思うか、ある意味で清々しいと考えるかは、受け手の皆様によるのかなと思います。
――2022年夏、有田の若者に注目してみます。
あさっての13日(土曜)の第1試合に、夏の高校野球の夢の舞台・甲子園に、登場する予定の有田工業高校。
今春のセンバツ高校野球にも有田工は出場しており、その時にも相当な盛り上がりがあったと記憶します。
〔参照:「球春に唸〔うな〕れ!」〕
「何だか、キャラが立っている…」という表現になるのか、バッテリーを中心に個性を感じる選手が多いのですね。
〔参照:「有工の“明るさ”が…」〕

――再登場、期待して待ってました。
佐賀大会の決勝戦は、男子新体操でも名を知られる、神埼清明高校。昨夏は有田工業に勝ったとも聞きますし、それだけ激闘だったと聞いています。
神埼清明の活躍も見たかった気はしますが、佐賀県から2校の出場を見たいと言っては、欲張り…というものなのでしょう。
こうして今夏は、春に続いて甲子園への切符を掴んだ有田工業高校。
コロナ禍の影響は続き、入場行進はプラカードの先導だけという高校も結構あり、有田工も同じ状況でしたが、無事に試合ができそうで良かったです。
――各地の強豪と呼ばれる、高校と違って、
ベンチ入りする選手たちは地元・有田町と近隣の武雄市・伊万里市ぐらいの地域から集まっているようですね。
〔参照:「武雄よ、共〔とも〕に…」〕
佐賀県の陶磁器産地と重なるところもありそうですが、セラミックの学科もあると聞く、有田工業らしい地域性を感じます。
――「あの有田陶器市で知られる、佐賀県西部の町」
私もそうですが、たぶん全国の佐賀県出身者が応援しています。テレビ放送での地元紹介のVTRとか、すごく楽しみにしています。
私の個人的な経験から語ると、有田町は佐賀県の中では“全国受け”が良いブランド力のある場所という印象です。
〔参照:「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(前編)」〕
「佐賀県の有田。」工業の名を冠するも、地域の特性からデザインにも強い。こんなイメージも全国的に刷り込んでほしい…という期待もあります。

――“全国”の晴れ舞台に立つ選手たち。その一方で、
地元・有田町では、“もう1つの甲子園”のイメージで、開催されている行事があると知りました。
すでに第17回目の開催だそうですが、その名も『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』。試合の会場は有田の街中で、商店での展示の技術を競うようです。
やきもののまち・有田で営業する店舗を舞台として、「品物が伝えたいこと」をいかに魅せるか…とか、相当に実践的な感じです。
――福岡・佐賀・長崎の高校生が、アートな感性を競う。
スポーツでの活躍が多くの人に注目されて、地域の盛り上がりや全国からの知名度を上げる即効性があるものならば…
こうしたイベントの開催は、地道に参加者の技量を高め、持続的に地域産業のブランド力を高めるもの…というイメージでしょうか。
投票そのものは終了しているようですが、8月28日までの約1か月間は14店舗で展示は続くらしく、ご興味のある方には一見の価値があるかもしれません。

――「若いって、いいなぁ。」
ちなみに幕末の青春時代から明治を経て老人になるまでずっと、大隈重信と友達だった、久米邦武も設立に関わったという“香蘭社”前の会場。
当地の陶磁器が、世界に羽ばたいた象徴的な場所で『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』の開会は宣言されたようです。
…こちらは、明日12日(金曜)がプレゼンテーション・表彰式のようですね。
参照:https://aritahappynews.sagafan.jp/c23382.html(有田観光協会)※外部サイト
――私が有田町まで足を運ぶことは容易ではなく、
結局、テレビを通じてですが、高校野球での有田工業の勇姿だけでも、見つめていきたいと考えるところです。
まだ、来た道を振り返るには若すぎる高校生たち。学業でも部活でもひたすらに前を向いて、突き進んでほしいと思います。
「青春の真っ只中の人は書くことができないので、その時代を終えた人が書くのが“青春小説”…」どこかで、そんな意味合いの言葉を聞いた気がします。
私はといえば、青春の終わりから、幾多の歳月を隔て、遅まきながら気付いた佐賀の歴史の価値に夢を追いかけている。
…これを見苦しいと思うか、ある意味で清々しいと考えるかは、受け手の皆様によるのかなと思います。
――2022年夏、有田の若者に注目してみます。
あさっての13日(土曜)の第1試合に、夏の高校野球の夢の舞台・甲子園に、登場する予定の有田工業高校。
今春のセンバツ高校野球にも有田工は出場しており、その時にも相当な盛り上がりがあったと記憶します。
〔参照:
「何だか、キャラが立っている…」という表現になるのか、バッテリーを中心に個性を感じる選手が多いのですね。
〔参照:
――再登場、期待して待ってました。
佐賀大会の決勝戦は、男子新体操でも名を知られる、神埼清明高校。昨夏は有田工業に勝ったとも聞きますし、それだけ激闘だったと聞いています。
神埼清明の活躍も見たかった気はしますが、佐賀県から2校の出場を見たいと言っては、欲張り…というものなのでしょう。
こうして今夏は、春に続いて甲子園への切符を掴んだ有田工業高校。
コロナ禍の影響は続き、入場行進はプラカードの先導だけという高校も結構あり、有田工も同じ状況でしたが、無事に試合ができそうで良かったです。
――各地の強豪と呼ばれる、高校と違って、
ベンチ入りする選手たちは地元・有田町と近隣の武雄市・伊万里市ぐらいの地域から集まっているようですね。
〔参照:
佐賀県の陶磁器産地と重なるところもありそうですが、セラミックの学科もあると聞く、有田工業らしい地域性を感じます。
――「あの有田陶器市で知られる、佐賀県西部の町」
私もそうですが、たぶん全国の佐賀県出身者が応援しています。テレビ放送での地元紹介のVTRとか、すごく楽しみにしています。
私の個人的な経験から語ると、有田町は佐賀県の中では“全国受け”が良いブランド力のある場所という印象です。
〔参照:
「佐賀県の有田。」工業の名を冠するも、地域の特性からデザインにも強い。こんなイメージも全国的に刷り込んでほしい…という期待もあります。
――“全国”の晴れ舞台に立つ選手たち。その一方で、
地元・有田町では、“もう1つの甲子園”のイメージで、開催されている行事があると知りました。
すでに第17回目の開催だそうですが、その名も『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』。試合の会場は有田の街中で、商店での展示の技術を競うようです。
やきもののまち・有田で営業する店舗を舞台として、「品物が伝えたいこと」をいかに魅せるか…とか、相当に実践的な感じです。
――福岡・佐賀・長崎の高校生が、アートな感性を競う。
スポーツでの活躍が多くの人に注目されて、地域の盛り上がりや全国からの知名度を上げる即効性があるものならば…
こうしたイベントの開催は、地道に参加者の技量を高め、持続的に地域産業のブランド力を高めるもの…というイメージでしょうか。
投票そのものは終了しているようですが、8月28日までの約1か月間は14店舗で展示は続くらしく、ご興味のある方には一見の価値があるかもしれません。
――「若いって、いいなぁ。」
ちなみに幕末の青春時代から明治を経て老人になるまでずっと、大隈重信と友達だった、久米邦武も設立に関わったという“香蘭社”前の会場。
当地の陶磁器が、世界に羽ばたいた象徴的な場所で『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』の開会は宣言されたようです。
…こちらは、明日12日(金曜)がプレゼンテーション・表彰式のようですね。
参照:https://aritahappynews.sagafan.jp/c23382.html(有田観光協会)※外部サイト
――私が有田町まで足を運ぶことは容易ではなく、
結局、テレビを通じてですが、高校野球での有田工業の勇姿だけでも、見つめていきたいと考えるところです。
まだ、来た道を振り返るには若すぎる高校生たち。学業でも部活でもひたすらに前を向いて、突き進んでほしいと思います。
2022年07月14日
「序章・“忘れ物”を取りに行く話」
こんばんは。
またしても、新型コロナ感染症の急拡大。佐賀県の感染者も千人を超えてしまった事に、いささか驚きました。
私が「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をテーマとする、当ブログを始めてから、概ね2年半を過ぎたところですが、大半の期間でこの話題がついて回っています。
――やはり、物事にはタイミングがあるようで、
「早めに“決断”しておいて良かった…」
ここ数年、幾度となく目にしたテレビからの感染拡大の報道。
わりと真面目に大都市圏からの帰省の自粛を行ってしまう私。この状況になるたび、故郷の佐賀に帰れないという展開が繰り返されました。
――今回のいわゆる“第7波”の到来の少し前。
私は「好機は、今だ!」とばかりに、佐賀への緊急“帰藩”を行っていました。
最近では仕事も忙しく、気力・体力ともに足りていない感じですが、あまり長いこと“忘れ物”を置いておくのも気にかかっていました。
以下、いつもの感じで書きます。

――私の“忘れ物”とは…
2018年(平成30年)当時に、実際の会場に足を運んだ方には「なんと慎ましい…」と思われるかもしれない。
それは『肥前さが幕末維新博覧会』の置き土産である“メモリアル展示”なのである。
私が何を“置き忘れた”かと言えば、博覧会のドキュメンタリー映像は見たことがあるが、2018年当時に会場で上映された内容をまだ見ていないのだ。
〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(33)涙のメモリアル〕
――佐賀に“還る”べき時、それは今。
私は、多少の無茶を覚悟した。2019年(令和元年)に佐賀に帰っていた時でも、さほど時間の余裕はなかった。
もはや、今度は“旅行”という水準での時間すらも取れない。多額の交通費を使って、何と勿体ないことを…という気持ちも浮かぶ。
「否(いな)!この2年半の想いを持って、佐賀に帰っておく事に意義がある!」
――あゝ、佐賀の偉大な“先輩”たちに比べて、何と小さい決意であろう。
ただ、その一歩はコロナ禍で郷里と隔てられた私にとって大きい意味を持つ。
まずは「佐賀への道」を再び開く。それは体力を消耗し、気力に欠けた今の私には、必ずしも容易な事ではなかったのである。

…と、このような調子で、次回以降は、しばらく連続ブログ小説『聖地の剣』を綴る予定です。
調べ物に負担が少なく、写真素材も揃っているため、まとまった時間の取れない現況でも書きやすい“旅日記”を選択しました。
「佐賀を“聖地”として、語っていく展開」になると思います。お時間とご興味のある方は、ご覧いただければ幸いです。
またしても、新型コロナ感染症の急拡大。佐賀県の感染者も千人を超えてしまった事に、いささか驚きました。
私が「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をテーマとする、当ブログを始めてから、概ね2年半を過ぎたところですが、大半の期間でこの話題がついて回っています。
――やはり、物事にはタイミングがあるようで、
「早めに“決断”しておいて良かった…」
ここ数年、幾度となく目にしたテレビからの感染拡大の報道。
わりと真面目に大都市圏からの帰省の自粛を行ってしまう私。この状況になるたび、故郷の佐賀に帰れないという展開が繰り返されました。
――今回のいわゆる“第7波”の到来の少し前。
私は「好機は、今だ!」とばかりに、佐賀への緊急“帰藩”を行っていました。
最近では仕事も忙しく、気力・体力ともに足りていない感じですが、あまり長いこと“忘れ物”を置いておくのも気にかかっていました。
以下、いつもの感じで書きます。
――私の“忘れ物”とは…
2018年(平成30年)当時に、実際の会場に足を運んだ方には「なんと慎ましい…」と思われるかもしれない。
それは『肥前さが幕末維新博覧会』の置き土産である“メモリアル展示”なのである。
私が何を“置き忘れた”かと言えば、博覧会のドキュメンタリー映像は見たことがあるが、2018年当時に会場で上映された内容をまだ見ていないのだ。
〔参照:
――佐賀に“還る”べき時、それは今。
私は、多少の無茶を覚悟した。2019年(令和元年)に佐賀に帰っていた時でも、さほど時間の余裕はなかった。
もはや、今度は“旅行”という水準での時間すらも取れない。多額の交通費を使って、何と勿体ないことを…という気持ちも浮かぶ。
「否(いな)!この2年半の想いを持って、佐賀に帰っておく事に意義がある!」
――あゝ、佐賀の偉大な“先輩”たちに比べて、何と小さい決意であろう。
ただ、その一歩はコロナ禍で郷里と隔てられた私にとって大きい意味を持つ。
まずは「佐賀への道」を再び開く。それは体力を消耗し、気力に欠けた今の私には、必ずしも容易な事ではなかったのである。
…と、このような調子で、次回以降は、しばらく連続ブログ小説『聖地の剣』を綴る予定です。
調べ物に負担が少なく、写真素材も揃っているため、まとまった時間の取れない現況でも書きやすい“旅日記”を選択しました。
「佐賀を“聖地”として、語っていく展開」になると思います。お時間とご興味のある方は、ご覧いただければ幸いです。
2022年07月04日
「“かささぎ”が舞う、干潟の街に」
こんばんは。
西九州新幹線の開業を9月に控え、佐賀の熱い夏は進んでいくようですね。
一方、この秋からのダイヤ改正など多方面に影響が及ぶところもあり、諸手を挙げては喜べない地域の方々も多いはず…と、つい最近、思い至りました。
長崎本線の特急『かもめ』は廃止となり、途中の肥前鹿島駅までは、代わりに特急『かささぎ』が走ると聞きます。
書き進めるペースは遅くなっても、「佐賀の大河ドラマ」を考えてやまない私。干潟〔ガタ〕のイベントで知られる街・鹿島にも色々と連想することがあります。

――“物語の中心”で描かれないところにも、物語はある。
2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の時代設定は、幕末・明治期でしたが、桂小五郎・勝海舟・坂本龍馬などの配役は無かったはず。
主人公・渋沢栄一を丁寧に描こうとすれば、どうしても、登場人物の“選択”を迫られることになったのかもしれません。
…という話から、西九州新幹線の開業においては“主役”でなくとも、これからの物語として語るべき、佐賀県内の街も特集してみます。
今回のテーマは鹿島市。大隈重信が、ずっと心に引っ掛かっていたであろう「鹿島に行った女性(ひと)」についてです。
――現在の“本編”で描くのは、1862年(文久二年)頃。
第18話では江藤新平が佐賀を脱藩し、京都で活動した同年夏の話を展開します。この周辺の時期には、大隈八太郎(重信)の物語も動いていました。
佐賀の大殿・鍋島直正への蘭学の進講や、開国の影響で、より西洋の風が吹き込む長崎での活動です。
このように“本編”で書きたい内容が同時期に多数あるのは、構成上の贅沢な悩みです。

――この頃、若き大隈八太郎にも“縁談”が。
お相手は、江副美登という女性。大隈重信はその妻との間に、熊子という娘を授かります。
長女・大隈熊子は、のち明治期には、“秘書”のような役回りで大隈重信を、影ながら支えたようです。
大隈の側近だった政治家・犬養毅は「もし(熊子が)男であったなら、父・重信より偉くなっただろう」と評したそうで、その有能さがうかがえます。
人格も素晴らしいと評判だった大隈の娘・熊子。父・重信の気性からすれば、これは母・美登ゆずりだったのかもしれません。
――しかし、『青天を衝け』で登場した、大隈重信の妻は、
大隈綾子という、幕臣(旗本)の家柄の女性。大隈にとっては再婚相手です。
〔参照:「新キャストを考える⑤」(奥様も出演します)〕
大倉孝二さんの熱演で、物語後半の軸として存在感を見せた大隈重信。妻・綾子役の朝倉あきさんも好演でした。
幕臣として近代化に活躍した小栗上野介(忠順)の従妹にあたり、皆が洋装に流れてドレスを着る中、和装を選ぶなど、芯の強いところも見られました。
〔参照:「新キャストを考える①」(“明治の父”の1人)〕

なお、最初の妻だった美登は、明治に入っても大隈重信の妻として“東京”に行くことはなく、佐賀に留まりました。
そして、佐賀の鹿島支藩の武士と再婚し、新たな家族を築いて、鹿島の地で生きたようです。
――日本では、ほぼ有明海の周辺に生息する、かささぎ(かちがらす)。
大隈重信は、最初の結婚について多くを語らなかったと聞きます。
ただ、他の明治維新の志士たちがこういった場合に、なし崩し的に複数の“妻”を持つのに比べて、女性側の意思が強く感じられるのです。
当時、新国家の中枢で、洋学を修めた真価を発揮し始めた、大隈。
最初の妻・美登は、東京で活躍する大隈を見て、身を引いたと言いますが、「私は生きるべき場所で、生きていたい」という感覚があったかもしれません。
――この展開を、今後の“本編”でどう描くか。
生涯を通じて母の愛に見守られ、佐賀では最初の妻のもと自由闊達に動き回り、東京で2人目の妻に背中を押され、娘の気配りに支えられて走り続けた。
…これが大隈八太郎(重信)、という物語構成も可能に思います。
日常は忙しく廻り、鹿島で干潟を眺めて、ゆったり考えを巡らせたいと願望も浮かびます。最近は思い付いても、まとめる余裕がない…そんな日々です。
西九州新幹線の開業を9月に控え、佐賀の熱い夏は進んでいくようですね。
一方、この秋からのダイヤ改正など多方面に影響が及ぶところもあり、諸手を挙げては喜べない地域の方々も多いはず…と、つい最近、思い至りました。
長崎本線の特急『かもめ』は廃止となり、途中の肥前鹿島駅までは、代わりに特急『かささぎ』が走ると聞きます。
書き進めるペースは遅くなっても、「佐賀の大河ドラマ」を考えてやまない私。干潟〔ガタ〕のイベントで知られる街・鹿島にも色々と連想することがあります。
――“物語の中心”で描かれないところにも、物語はある。
2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の時代設定は、幕末・明治期でしたが、桂小五郎・勝海舟・坂本龍馬などの配役は無かったはず。
主人公・渋沢栄一を丁寧に描こうとすれば、どうしても、登場人物の“選択”を迫られることになったのかもしれません。
…という話から、西九州新幹線の開業においては“主役”でなくとも、これからの物語として語るべき、佐賀県内の街も特集してみます。
今回のテーマは鹿島市。大隈重信が、ずっと心に引っ掛かっていたであろう「鹿島に行った女性(ひと)」についてです。
――現在の“本編”で描くのは、1862年(文久二年)頃。
第18話では江藤新平が佐賀を脱藩し、京都で活動した同年夏の話を展開します。この周辺の時期には、大隈八太郎(重信)の物語も動いていました。
佐賀の大殿・鍋島直正への蘭学の進講や、開国の影響で、より西洋の風が吹き込む長崎での活動です。
このように“本編”で書きたい内容が同時期に多数あるのは、構成上の贅沢な悩みです。
――この頃、若き大隈八太郎にも“縁談”が。
お相手は、江副美登という女性。大隈重信はその妻との間に、熊子という娘を授かります。
長女・大隈熊子は、のち明治期には、“秘書”のような役回りで大隈重信を、影ながら支えたようです。
大隈の側近だった政治家・犬養毅は「もし(熊子が)男であったなら、父・重信より偉くなっただろう」と評したそうで、その有能さがうかがえます。
人格も素晴らしいと評判だった大隈の娘・熊子。父・重信の気性からすれば、これは母・美登ゆずりだったのかもしれません。
――しかし、『青天を衝け』で登場した、大隈重信の妻は、
大隈綾子という、幕臣(旗本)の家柄の女性。大隈にとっては再婚相手です。
〔参照:
大倉孝二さんの熱演で、物語後半の軸として存在感を見せた大隈重信。妻・綾子役の朝倉あきさんも好演でした。
幕臣として近代化に活躍した小栗上野介(忠順)の従妹にあたり、皆が洋装に流れてドレスを着る中、和装を選ぶなど、芯の強いところも見られました。
〔参照:
なお、最初の妻だった美登は、明治に入っても大隈重信の妻として“東京”に行くことはなく、佐賀に留まりました。
そして、佐賀の鹿島支藩の武士と再婚し、新たな家族を築いて、鹿島の地で生きたようです。
――日本では、ほぼ有明海の周辺に生息する、かささぎ(かちがらす)。
大隈重信は、最初の結婚について多くを語らなかったと聞きます。
ただ、他の明治維新の志士たちがこういった場合に、なし崩し的に複数の“妻”を持つのに比べて、女性側の意思が強く感じられるのです。
当時、新国家の中枢で、洋学を修めた真価を発揮し始めた、大隈。
最初の妻・美登は、東京で活躍する大隈を見て、身を引いたと言いますが、「私は生きるべき場所で、生きていたい」という感覚があったかもしれません。
――この展開を、今後の“本編”でどう描くか。
生涯を通じて母の愛に見守られ、佐賀では最初の妻のもと自由闊達に動き回り、東京で2人目の妻に背中を押され、娘の気配りに支えられて走り続けた。
…これが大隈八太郎(重信)、という物語構成も可能に思います。
日常は忙しく廻り、鹿島で干潟を眺めて、ゆったり考えを巡らせたいと願望も浮かびます。最近は思い付いても、まとめる余裕がない…そんな日々です。
2022年06月29日
「そこに“かもめ”は、飛ばずとも…」
こんばんは。
私がブログを始めてから2年半ばかり、それは新型コロナの拡大への警戒期と、ほぼ重なっていました。
なかなか佐賀に帰ることはかなわず、当初の計画のように現地で情報収集を行って、物語を進める目算は大きく外れてしまったのです。
そして、県内のメディアによる報道も、自然には入って来ない私は、感覚的に気付かないことがあります。
――西九州新幹線も、9月の開業が間近となってきた。
私は、佐賀を走る特急に『かささぎ』という愛称が付くと聞き、意気揚々とした。『かちがらす』だと思えば、さらに佐賀らしさが増す。
しかし、その周辺情報を知った時。いや、冷静に考えればわかる事なのだが、その特急の新設は“救済策”だったことを、遅まきながら理解した。
これは「ボーッと生きてきた」帰結なのか。“佐賀の大河ドラマ”を志向する身として、まさに「チコちゃんに叱られ」ても仕方のない展開である。

――なんと、気付いていなかったのだ。
長崎本線を走る、特急『かもめ』が廃止となる重大事に。大都市圏にいる私は、お気楽なことに『かささぎ』が追加されると“足し算”で考えていたのだ。
その次にあった情報が、さらに私を打ち据える。
「肥前浜~諫早間は、“非電化”区間になる…」
鹿島市までは電車が走るが、太良町からは汽車になることを意味するようだ。
これは厳しい。浮かれている場合では無い…と何やらムズムズとするが、この局面で私にできることは皆無である。
――この頃に見かけた『町報たら 2022年6月号』
「いきなり何を言い出すのか?」という方が大半だろう。もし、これが即座に理解できる方がいれば、佐賀県の太良町民。もしくは、縁のある方に相違ない。
ちなみに、私は『さがファンブログ』から参照した。こういうところは便利な世となっている。大事なのは、その中身である。
そのページの標題は『さが未来発見塾』。主催は佐賀新聞社とある。
https://static.saga-ebooks.jp/actibook_data/t_tara_2022_06_2022006130000/HTML5/pc.html#/page/3(『町報たら』の掲載箇所※外部リンク)
――参加者は、太良町の中学3年生。
“塾生”として、その企画に参加したのは11名。言うなれば太良町の“明日”のために、7つのプランを建言していた。
多少、私が書きやすいように言葉を加除しながら記す。

その1.海中鳥居に「新たらふく館」(道の駅)を
その2.「6時間観光プラン」で滞在時間増
以下は、3.「太良ミカンアイス」を夏の名物に、4.家族向けに海のレジャーを充実、5.SNSでの魅力発信の強化、6.道の駅連携で「車での観光」を促進、7.兼業・副業で働く場所を増やす…というように続く。
なお、県内の各地域で同様の企画は開催されるが、今回は、非電化の憂き目にあう、太良町の“反撃”の物語を見守りたい。
――そして、私の目がとまったのは、“その2”だ。
「6時間…観光プランだと…!?」
県内・近隣県からの行楽や、遠距離の観光客の旅プランの一部に…ということなのだろうか。
この一文は、私に発想の転換を促すことになる。私は、佐賀に“帰藩”するためには、まとまった日程が要ると思い込んでいたのだ。
「そうだ、佐賀に行こう。」
まだ太良町には足を運べずとも、この“6時間観光”という象徴的なキーワードは、私にも勇気を与えたのである。
――太良町の中学生が考えた“6時間”には…
実はもっと深い意図があった。有明海の干満の差は6メートルもあって、日本一という。その満ち引きの時間に合わせ、観光プランを立てるらしい。
名所・海中鳥居の前に拠点となる施設を築き、万全の体勢で待ち受ける策のようだ。「月の引力が見える町」という、“異名”も映える戦術と感じさせる。
――「望みを捨てぬ者だけに、道は開けるのです。」
ふと思い出すのは、2016年大河ドラマ『真田丸』で、主人公・真田信繁(幸村)〔演:堺雅人〕が発したセリフである。
若者が考えた太良町の7つの策が、功を奏することを期待したい。

特急は肥前鹿島駅で止まろうとも、肥前浜駅以降はディーゼル車が走ろうと、これからも『多良海道』の物語は、諫早を経て、長崎まで続くに違いない。
“映える”使い方かはさておき、私もブログでは太良町の写真を多用している。応援になるかはともかく、その辺りも近いうちに紹介したいと考えている。
私がブログを始めてから2年半ばかり、それは新型コロナの拡大への警戒期と、ほぼ重なっていました。
なかなか佐賀に帰ることはかなわず、当初の計画のように現地で情報収集を行って、物語を進める目算は大きく外れてしまったのです。
そして、県内のメディアによる報道も、自然には入って来ない私は、感覚的に気付かないことがあります。
――西九州新幹線も、9月の開業が間近となってきた。
私は、佐賀を走る特急に『かささぎ』という愛称が付くと聞き、意気揚々とした。『かちがらす』だと思えば、さらに佐賀らしさが増す。
しかし、その周辺情報を知った時。いや、冷静に考えればわかる事なのだが、その特急の新設は“救済策”だったことを、遅まきながら理解した。
これは「ボーッと生きてきた」帰結なのか。“佐賀の大河ドラマ”を志向する身として、まさに「チコちゃんに叱られ」ても仕方のない展開である。
――なんと、気付いていなかったのだ。
長崎本線を走る、特急『かもめ』が廃止となる重大事に。大都市圏にいる私は、お気楽なことに『かささぎ』が追加されると“足し算”で考えていたのだ。
その次にあった情報が、さらに私を打ち据える。
「肥前浜~諫早間は、“非電化”区間になる…」
鹿島市までは電車が走るが、太良町からは汽車になることを意味するようだ。
これは厳しい。浮かれている場合では無い…と何やらムズムズとするが、この局面で私にできることは皆無である。
――この頃に見かけた『町報たら 2022年6月号』
「いきなり何を言い出すのか?」という方が大半だろう。もし、これが即座に理解できる方がいれば、佐賀県の太良町民。もしくは、縁のある方に相違ない。
ちなみに、私は『さがファンブログ』から参照した。こういうところは便利な世となっている。大事なのは、その中身である。
そのページの標題は『さが未来発見塾』。主催は佐賀新聞社とある。
https://static.saga-ebooks.jp/actibook_data/t_tara_2022_06_2022006130000/HTML5/pc.html#/page/3(『町報たら』の掲載箇所※外部リンク)
――参加者は、太良町の中学3年生。
“塾生”として、その企画に参加したのは11名。言うなれば太良町の“明日”のために、7つのプランを建言していた。
多少、私が書きやすいように言葉を加除しながら記す。
その1.海中鳥居に「新たらふく館」(道の駅)を
その2.「6時間観光プラン」で滞在時間増
以下は、3.「太良ミカンアイス」を夏の名物に、4.家族向けに海のレジャーを充実、5.SNSでの魅力発信の強化、6.道の駅連携で「車での観光」を促進、7.兼業・副業で働く場所を増やす…というように続く。
なお、県内の各地域で同様の企画は開催されるが、今回は、非電化の憂き目にあう、太良町の“反撃”の物語を見守りたい。
――そして、私の目がとまったのは、“その2”だ。
「6時間…観光プランだと…!?」
県内・近隣県からの行楽や、遠距離の観光客の旅プランの一部に…ということなのだろうか。
この一文は、私に発想の転換を促すことになる。私は、佐賀に“帰藩”するためには、まとまった日程が要ると思い込んでいたのだ。
「そうだ、佐賀に行こう。」
まだ太良町には足を運べずとも、この“6時間観光”という象徴的なキーワードは、私にも勇気を与えたのである。
――太良町の中学生が考えた“6時間”には…
実はもっと深い意図があった。有明海の干満の差は6メートルもあって、日本一という。その満ち引きの時間に合わせ、観光プランを立てるらしい。
名所・海中鳥居の前に拠点となる施設を築き、万全の体勢で待ち受ける策のようだ。「月の引力が見える町」という、“異名”も映える戦術と感じさせる。
――「望みを捨てぬ者だけに、道は開けるのです。」
ふと思い出すのは、2016年大河ドラマ『真田丸』で、主人公・真田信繁(幸村)〔演:堺雅人〕が発したセリフである。
若者が考えた太良町の7つの策が、功を奏することを期待したい。
特急は肥前鹿島駅で止まろうとも、肥前浜駅以降はディーゼル車が走ろうと、これからも『多良海道』の物語は、諫早を経て、長崎まで続くに違いない。
“映える”使い方かはさておき、私もブログでは太良町の写真を多用している。応援になるかはともかく、その辺りも近いうちに紹介したいと考えている。
2022年06月19日
「記事500件目への到達」
こんにちは。
幕末佐賀藩の大河ドラマをイメージして書いています“本編”の現在位置は、第18話「京都見聞」の中盤です。
そして、例によって書き溜めた原稿のストックが切れましたので、また小休止を入れたいと思います。
――前回で、通算での記事投稿数が500件になりました。
ちょうど本編で描いたのは、佐賀を脱藩した江藤新平が、京都にある長州藩の屋敷に乗り込んだ場面。
〔参照:第18話「京都見聞」⑫(江藤、“長州”と出会う)〕

この展開が、のちに明治初頭で新政府に、佐賀藩が加わって“薩長土肥”の一角に入ることにつながっていきます。
場面の描写は想像によるところですが、ここが後の明治への転換期にかなり大きい意味を持ってくるので、区切りとしては良かったのではと思います。
――実際に書いてみて、体感していることがあります。
昨年(2021年)の夏。佐賀の視点から幕末の動乱期を描こうと、本編を再開し、第2部を始めてから1年あまり。
〔参照:「第2部を、どう描くか?」〕
ひたすら幕末黎明期の“佐賀による近代化”を綴る感じだった第1部と違い、相当に書きづらい第2部。
〔参照(中盤):「佐賀の物語を描け!」(独自色③)〕
直接的には佐賀藩の話ではない、幕府や他の雄藩の動向など…抑えるべきポイントは増える一方なのです。
――この辺りが、佐賀の「大河ドラマ」への道が険しい理由の一つかも。
例えば司馬遼太郎さんの『歳月』などの作品を読むと書きやすくなりそうですが、私の力量では“名作”に引っ張られた話になってしまう…と思っています。
まずは、なるべく佐賀に特化したオリジナルの試作品を作りたい想いがあり、これが“本編”を書くうえで四苦八苦する理由です。
〔参照:「長崎街道をゆく」〕

私が調べている情報にも、司馬先生の影響を受けた記述が含まれる可能性はありますが、当面、作品自体は読まないようにしています。
今のところ、他にも各作家の先生が著わした“佐賀の歴史ドラマ”の傑作も、一通り書き終えてから読むつもりです。
後で「こう書けば良かったか…」という気分にひたるのも、楽しみにしています。
――私の周辺にも、何やら険しさを増す…日々の仕事。
たしかに私の書く記事の“燃料”にもなっている、仕事のストレスですが、最近は「燃料の過積載」の傾向があり、こうなると厳しいところ。
ブログ開始当初から比べれば、記事の投稿頻度も相当に落ちており、現在は3~4日に1記事がやっとのペースになっています。
新型コロナ禍は一時より落ち着いているのに、佐賀へと“帰藩”できない要因でもあります。どこかで隙を見つけ、再び「佐賀への道」は開きたいです。
――というわけで、第18話「京都見聞」の後半の…
再開の時期は、話の構成や下書きが、ある程度整ってからになりそうです。
長州藩と接点を持つことになった江藤は、ある有力な公家と出会い、幕末の動乱が深まっていく京都の情勢を探ることに…というあらすじの予定。
しばらくは佐賀への「望郷の想い」を時折綴っていきたいと考えていますので、こちらもよろしくお願いします。
幕末佐賀藩の大河ドラマをイメージして書いています“本編”の現在位置は、第18話「京都見聞」の中盤です。
そして、例によって書き溜めた原稿のストックが切れましたので、また小休止を入れたいと思います。
――前回で、通算での記事投稿数が500件になりました。
ちょうど本編で描いたのは、佐賀を脱藩した江藤新平が、京都にある長州藩の屋敷に乗り込んだ場面。
〔参照:

この展開が、のちに明治初頭で新政府に、佐賀藩が加わって“薩長土肥”の一角に入ることにつながっていきます。
場面の描写は想像によるところですが、ここが後の明治への転換期にかなり大きい意味を持ってくるので、区切りとしては良かったのではと思います。
――実際に書いてみて、体感していることがあります。
昨年(2021年)の夏。佐賀の視点から幕末の動乱期を描こうと、本編を再開し、第2部を始めてから1年あまり。
〔参照:
ひたすら幕末黎明期の“佐賀による近代化”を綴る感じだった第1部と違い、相当に書きづらい第2部。
〔参照(中盤):
直接的には佐賀藩の話ではない、幕府や他の雄藩の動向など…抑えるべきポイントは増える一方なのです。
――この辺りが、佐賀の「大河ドラマ」への道が険しい理由の一つかも。
例えば司馬遼太郎さんの『歳月』などの作品を読むと書きやすくなりそうですが、私の力量では“名作”に引っ張られた話になってしまう…と思っています。
まずは、なるべく佐賀に特化したオリジナルの試作品を作りたい想いがあり、これが“本編”を書くうえで四苦八苦する理由です。
〔参照:
私が調べている情報にも、司馬先生の影響を受けた記述が含まれる可能性はありますが、当面、作品自体は読まないようにしています。
今のところ、他にも各作家の先生が著わした“佐賀の歴史ドラマ”の傑作も、一通り書き終えてから読むつもりです。
後で「こう書けば良かったか…」という気分にひたるのも、楽しみにしています。
――私の周辺にも、何やら険しさを増す…日々の仕事。
たしかに私の書く記事の“燃料”にもなっている、仕事のストレスですが、最近は「燃料の過積載」の傾向があり、こうなると厳しいところ。
ブログ開始当初から比べれば、記事の投稿頻度も相当に落ちており、現在は3~4日に1記事がやっとのペースになっています。
新型コロナ禍は一時より落ち着いているのに、佐賀へと“帰藩”できない要因でもあります。どこかで隙を見つけ、再び「佐賀への道」は開きたいです。
――というわけで、第18話「京都見聞」の後半の…
再開の時期は、話の構成や下書きが、ある程度整ってからになりそうです。
長州藩と接点を持つことになった江藤は、ある有力な公家と出会い、幕末の動乱が深まっていく京都の情勢を探ることに…というあらすじの予定。
しばらくは佐賀への「望郷の想い」を時折綴っていきたいと考えていますので、こちらもよろしくお願いします。
2022年05月22日
「小京都・小城の謎を追う…(第18話・場面解説①)」
こんばんは。
“本編”を作成していますが、また「重たい話」を織り込もうとしているので、なかなか進みません。
今回は「九州の小京都」をキーワードに、第18話の、今までとこれからの話の整理を試みます。
九州各地にも、京都のように伝統や文化を受け継ぐ雰囲気を持ちながら、それぞれの個性を持つ“小京都”が見られます。
――佐賀県では小城市と伊万里市が、よく“小京都”と呼ばれる街。
伊万里が“小京都”と呼ばれるのは京都の特色でもある“美術・工芸都市”の側面が強いからでしょう。
しかし、陶磁器(窯業)での“特殊な力”の蓄積がある港湾都市・伊万里は、“城下町”の風情が漂う街とは別に語った方が良いのかもしれません。
そんな理由なのかはわかりませんが、九州各県の“小京都”の並びで、佐賀県では小城市がその立場を担うのが一般的のようです。

※「小城 屋根のない博物館」。小城藩邸は城ではなく、“陣屋”の扱いなのですね。
そして、佐賀の支藩の1つである小城藩は、本編第2部の主人公・江藤新平と縁が深い場所。
以下は、本編の物語構成を前提としたお話が中心ですので、ご留意ください。
――小京都・小城から、幕末の京都へとつながる第18話。
江藤新平が京に発つ前、小城藩の代官所を尋ねた設定で描きました。
〔参照:第18話「京都見聞」④(湯呑みより茶が走る)〕
当時、富岡敬明は大野代官所で小城藩領・山内を管轄。この場所は、現在は佐賀市富士町のようですが、本記事に含めています。
“本編”で佐賀の藩境を超える時の手引き役は、義祭同盟の同志・古賀一平で描写しましたが、小城領の代官・富岡敬明が関与したとする説もあります。
〔参照(終盤):第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)〕

――また、江藤が京都に旅立つ前に、
富岡は小城から出て、京でも活動する人物が居るとを示唆(しさ)します。
〔参照(中盤):第18話「京都見聞」⑤(清水の滝、何処…)〕
1858年(安政五年)に脱藩し、播磨(兵庫)を拠点に、上方の京・大坂で活動したという謎の男・祇園太郎。
江藤にとっては、佐賀から脱藩した先輩(?)にあたる存在ですが、“変名”での活動が伝わります。
私は、この人物が“祇園太郎”と名乗った理由を「佐賀の色」を隠して、秘密裏に動きたかったから…と想像しました。
――江藤が京・伏見に着くなり、
ここで、わかりやすく、もう1人の脱藩者が現れます。この辺りの展開が安直なのは、私の創作能力の限界なのですが、楽しんでいただけていれば幸いです。
〔参照:第18話「京都見聞」⑥(もう1人の脱藩者)〕
“本編”では、この謎の男は「上方ことば」で話し始めます。あえて出身地・佐賀の影を隠す“祇園太郎”。地道な努力で情報収集にあたる姿と表現しました。
実際に、この「現地の言葉で、自然と周囲に溶け込む」アプローチを用いたかは定かではありません。
ここは“佐賀”の存在を前面に出す、江藤との対比で描こうと思います。

※この方が、第18話のカギとなる人物です。
――“祇園太郎”は長崎と京を行き来しますが、
1863年(文久三年)には長州藩・桂小五郎に推挙され“学習院”出仕という、公家とも関われる立ち位置にまでなったと言います。
その前年の1862年(文久二年)に江藤と会い、京で公家と接点を持つ差配をしたのも、長州(山口)の桂小五郎です。
このため、同郷の江藤と“祇園太郎”には何か関わりがある方が自然では…と考えて、話を構成しました。
――そして、この“祇園太郎”の正体。
小城支藩内の大庄屋だった、古賀利渉という人物と伝わっています。
実際は、上方から長崎へ移動した時期があり、江藤が脱藩したタイミングでは、京に居なかった可能性もあります。
また、尊王攘夷の志士でありつつも、佐賀本藩の指令を受けて動く“密偵”という見解もある様子。想像を膨らませる余地を持った“謎の人物”です。

――小城が“小京都”である理由の1つに。
「祇園川のホタル」による風情があるそうです。いまは5月下旬ですから、現地の小城ではホタル観賞のシーズンなのでしょうか。
祇園太郎(古賀利渉)は、1833年(天保四年)生まれと聞きました。江藤新平より1歳年上という同年代。
ここ数回の“本編”では、祇園太郎の“情報通”としての実力と、小城とともに「九州の小京都」である福岡県の秋月(朝倉市)にも触れる話を…考えます。
――今回の調べ物をした際に、
小城に存在するという、謎の“混ぜ麺”「マジェンバ」の存在を知りました。調べるほどに、気になる事が増えていく小城の“小京都ミステリー”。
いま、佐賀県に帰省しようものならば、時間はいくらあっても足らない…そんな気がしています。
“本編”を作成していますが、また「重たい話」を織り込もうとしているので、なかなか進みません。
今回は「九州の小京都」をキーワードに、第18話の、今までとこれからの話の整理を試みます。
九州各地にも、京都のように伝統や文化を受け継ぐ雰囲気を持ちながら、それぞれの個性を持つ“小京都”が見られます。
――佐賀県では小城市と伊万里市が、よく“小京都”と呼ばれる街。
伊万里が“小京都”と呼ばれるのは京都の特色でもある“美術・工芸都市”の側面が強いからでしょう。
しかし、陶磁器(窯業)での“特殊な力”の蓄積がある港湾都市・伊万里は、“城下町”の風情が漂う街とは別に語った方が良いのかもしれません。
そんな理由なのかはわかりませんが、九州各県の“小京都”の並びで、佐賀県では小城市がその立場を担うのが一般的のようです。
※「小城 屋根のない博物館」。小城藩邸は城ではなく、“陣屋”の扱いなのですね。
そして、佐賀の支藩の1つである小城藩は、本編第2部の主人公・江藤新平と縁が深い場所。
以下は、本編の物語構成を前提としたお話が中心ですので、ご留意ください。
――小京都・小城から、幕末の京都へとつながる第18話。
江藤新平が京に発つ前、小城藩の代官所を尋ねた設定で描きました。
〔参照:
当時、富岡敬明は大野代官所で小城藩領・山内を管轄。この場所は、現在は佐賀市富士町のようですが、本記事に含めています。
“本編”で佐賀の藩境を超える時の手引き役は、義祭同盟の同志・古賀一平で描写しましたが、小城領の代官・富岡敬明が関与したとする説もあります。
〔参照(終盤):
――また、江藤が京都に旅立つ前に、
富岡は小城から出て、京でも活動する人物が居るとを示唆(しさ)します。
〔参照(中盤):
1858年(安政五年)に脱藩し、播磨(兵庫)を拠点に、上方の京・大坂で活動したという謎の男・祇園太郎。
江藤にとっては、佐賀から脱藩した先輩(?)にあたる存在ですが、“変名”での活動が伝わります。
私は、この人物が“祇園太郎”と名乗った理由を「佐賀の色」を隠して、秘密裏に動きたかったから…と想像しました。
――江藤が京・伏見に着くなり、
ここで、わかりやすく、もう1人の脱藩者が現れます。この辺りの展開が安直なのは、私の創作能力の限界なのですが、楽しんでいただけていれば幸いです。
〔参照:
“本編”では、この謎の男は「上方ことば」で話し始めます。あえて出身地・佐賀の影を隠す“祇園太郎”。地道な努力で情報収集にあたる姿と表現しました。
実際に、この「現地の言葉で、自然と周囲に溶け込む」アプローチを用いたかは定かではありません。
ここは“佐賀”の存在を前面に出す、江藤との対比で描こうと思います。
※この方が、第18話のカギとなる人物です。
――“祇園太郎”は長崎と京を行き来しますが、
1863年(文久三年)には長州藩・桂小五郎に推挙され“学習院”出仕という、公家とも関われる立ち位置にまでなったと言います。
その前年の1862年(文久二年)に江藤と会い、京で公家と接点を持つ差配をしたのも、長州(山口)の桂小五郎です。
このため、同郷の江藤と“祇園太郎”には何か関わりがある方が自然では…と考えて、話を構成しました。
――そして、この“祇園太郎”の正体。
小城支藩内の大庄屋だった、古賀利渉という人物と伝わっています。
実際は、上方から長崎へ移動した時期があり、江藤が脱藩したタイミングでは、京に居なかった可能性もあります。
また、尊王攘夷の志士でありつつも、佐賀本藩の指令を受けて動く“密偵”という見解もある様子。想像を膨らませる余地を持った“謎の人物”です。
――小城が“小京都”である理由の1つに。
「祇園川のホタル」による風情があるそうです。いまは5月下旬ですから、現地の小城ではホタル観賞のシーズンなのでしょうか。
祇園太郎(古賀利渉)は、1833年(天保四年)生まれと聞きました。江藤新平より1歳年上という同年代。
ここ数回の“本編”では、祇園太郎の“情報通”としての実力と、小城とともに「九州の小京都」である福岡県の秋月(朝倉市)にも触れる話を…考えます。
――今回の調べ物をした際に、
小城に存在するという、謎の“混ぜ麺”「マジェンバ」の存在を知りました。調べるほどに、気になる事が増えていく小城の“小京都ミステリー”。
いま、佐賀県に帰省しようものならば、時間はいくらあっても足らない…そんな気がしています。
2022年05月17日
「佐賀でも、光る君へ…?」
こんばんは。
現在放送中の2022年『鎌倉殿の13人』、来年2023年は『どうする家康』、再来年2024年は『光る君へ』…。
何となくですが、前々回・前回と今回。これからの大河ドラマ3作品を意識したタイトルを続けています。
いま、2025年こそ『幕末佐賀藩の大河ドラマ』を目指して…ひとまず前回、「どうする、配役」で語りきれなかった、配役イメージの3人目を紹介します。
――“配役”の勝手なイメージ〔その③〕
武勇に優れるうえに思慮深く、見栄えも良い、坂東武者の“優等生”。
『鎌倉殿の13人』では、畠山重忠を演じる中川大志さん。重たい展開も多い物語で、“清涼剤”のような爽やかさが際立つ、イケメン武将です。
源平合戦の“一ノ谷の戦い”では崖から奇襲をかける際、馬を傷つけないよう担いで降りた…というエピソードでよく語られる畠山重忠。
――馬にも愛のある、心映えまで“キラキラ”とした武将…?
最近、ゲームやアニメで流行っているらしい“ウマ娘”からもモテてしまいそう。ちなみに、同ゲームの開発会社は、佐賀に大規模な拠点がありますね。
話を戻します。たしか『鎌倉殿』では、伝説の「馬を担いで崖を降りる」場面は再現されておらず、セリフでの表現と記憶します。
平家方の陣を望む高台。畠山重忠〔演:中川大志〕は、そこから馬を背負ってでも下りていくと、源義経〔演:菅田将暉〕に宣言します。
「末代までの語り草になりそうです。」
やっぱり“優等生”キャラの畠山重忠。坂東武者として、後の世でどのように名を残すか。そこまでしっかり考えています。

――この俳優さん、以前見たテレビ番組でもキラキラとしていました。
バラエティー番組での中川大志さんの姿に「この俳優さんは“持っている”な」と感じたことがあります。
他局(テレビ東京系)で『池の水ぜんぶ抜く』という企画を行う番組。佐賀城の南堀が作業対象のロケ地になっており、私は大喜びして見ていました。
出演者の1人で、イケメン俳優枠(?)でのメンバーが中川大志さんでした。
――堀の底で“掘り出し物”を探す、一行。
“鍋島焼”の出現などが期待されるも、今ひとつ振り切った成果の出ない中…
時間は経過し「フライト(飛行機)の時間もあり、そろそろ撤収か」という空気が流れたところ。「もう少し、頑張りたい」様子で、延長を希望する中川大志さん。
――佐賀城の南堀の水を抜くなど、普通には無い事。
堀の水を抜くのは400年ぶりとも言われ、もちろん泥まみれの堀の底。“持っている”その人は、拾い上げてきました。
タイムリミットの迫る頃、泥の中からその手に掴んだのは、本丸の建物にあったのだろう、鬼瓦の一部。何とも絵になる場面でした。

――“佐賀の大河ドラマ”が実現した時に…
この佐賀において「運命的に何かを掴んだ感じ」が、中川大志さんを“主役級”に推したいと考える理由の1つです。
かつて2016年の大河ドラマ『真田丸』では、豊臣秀吉〔演:小日向文世〕の子・豊臣秀頼役でした。
主人公・真田信繁(幸村)〔演:堺雅人〕は、大坂城に駆けつけ、徳川の大軍と“真田丸”で戦うことになります。
その時、総大将・豊臣秀頼〔演:中川大志〕にオーラがあり過ぎると評判で、「今年の“大坂の陣”は豊臣方が勝つかな?」と言い出す人も居たようです。
――できるなら、この人を演じてほしい〔その③〕
壮大な前振りでしたが、大隈八太郎(重信)役で見てみたい俳優さんです。
背丈が182センチほどと言われる、長身の大隈重信。とくに以下のような筋書きだと、コメディ要素もこなせる中川大志さんが適任に思えてきています。
母親べったりの甘えん坊だった大隈家の長男・八太郎くん。あふれんばかりの母の愛に育まれ、すくすくと成長します。
――ところが今度は、元気に育ちすぎて、
急にケンカに明け暮れる子になり、別の意味で母を悩ませます。しかし、頭の回転も速く、要領も良かった八太郎。賢い先輩たちの影響で志を立てます。
やがて“西洋”の学問に出会った、大隈八太郎。ついには殿様に講義をする身分になり、母の苦労も報われます。
〔参照(前半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕

―…と可愛いけど、手のかかる我が子を見守る、母の物語にもできます。
尊王の想いを強める八太郎は、幕末動乱への介入に慎重な大殿・鍋島直正の方針に反発を感じ始めます。
一方で、長崎での貿易や英学校の開設など、様々な課題に慌ただしく挑んでいくことに…と、長崎を舞台にした、青春活劇にもできそうです。
――2021年大河『青天を衝け』を思い起せば…
大隈重信役のキャスト・大倉孝二さんが、明治期の“新しい大隈像”を築いたと感じる好演でした。
「おいも、なん~も知らん」とか言うインパクトの強いセリフも印象的。
〔参照:「【速報】『青天を衝け』が、大隈祭(?)に…」〕
「佐賀は、日本一の洋学通ぞ」とかローカル的に嬉しいものや「開化のための費用は、やむを得んばい」とか、さすがと思う名セリフも多くて…
〔参照(前半):「その青天に“救い”は見えるか」〕
仮に中川大志さんが同様のセリフを語ったら、味わいは大倉さんとは異なるものの、すごく絵になりそうな感じがするのですが、どうでしょう。

――幕末期、長崎の“光る海”を見つめて…
現在の“本編”では、江藤新平の京都での活動を書いていますが、その頃から大隈重信はよく長崎に足を運んでいた様子。
「江藤さんが、京で公家(くげ)衆に会っているらしい…」という感じで、若き大隈も先輩の動向を気にしていたそうです。
『青天を衝け』では、視聴者の想像に任された幕末期、大隈重信の前日譚。大隈を軸とした“長崎編”も、ぜひ書いてみたい内容です。
――さて、ここ2回ほどは、
「こんな配役があると、面白いのでは」という、私の“空想”を記事にしました。正直、期待した2024年の大河に当たらなかったので、多少はショックでした。
「幕末佐賀藩の大河ドラマは、いつ実現するんだろうか…」という気持ちもあり、具体的な配役もイメージすることで、気合いを入れ直したところです。
なお、当ブログで、私が語る配役イメージは、その時々の思いつきです。実在の俳優さんの活動には、何ら関わりは無いので、念のため申し添えます。
現在放送中の2022年『鎌倉殿の13人』、来年2023年は『どうする家康』、再来年2024年は『光る君へ』…。
何となくですが、前々回・前回と今回。これからの大河ドラマ3作品を意識したタイトルを続けています。
いま、2025年こそ『幕末佐賀藩の大河ドラマ』を目指して…ひとまず前回、「どうする、配役」で語りきれなかった、配役イメージの3人目を紹介します。
――“配役”の勝手なイメージ〔その③〕
武勇に優れるうえに思慮深く、見栄えも良い、坂東武者の“優等生”。
『鎌倉殿の13人』では、畠山重忠を演じる中川大志さん。重たい展開も多い物語で、“清涼剤”のような爽やかさが際立つ、イケメン武将です。
源平合戦の“一ノ谷の戦い”では崖から奇襲をかける際、馬を傷つけないよう担いで降りた…というエピソードでよく語られる畠山重忠。
――馬にも愛のある、心映えまで“キラキラ”とした武将…?
最近、ゲームやアニメで流行っているらしい“ウマ娘”からもモテてしまいそう。ちなみに、同ゲームの開発会社は、佐賀に大規模な拠点がありますね。
話を戻します。たしか『鎌倉殿』では、伝説の「馬を担いで崖を降りる」場面は再現されておらず、セリフでの表現と記憶します。
平家方の陣を望む高台。畠山重忠〔演:中川大志〕は、そこから馬を背負ってでも下りていくと、源義経〔演:菅田将暉〕に宣言します。
「末代までの語り草になりそうです。」
やっぱり“優等生”キャラの畠山重忠。坂東武者として、後の世でどのように名を残すか。そこまでしっかり考えています。
――この俳優さん、以前見たテレビ番組でもキラキラとしていました。
バラエティー番組での中川大志さんの姿に「この俳優さんは“持っている”な」と感じたことがあります。
他局(テレビ東京系)で『池の水ぜんぶ抜く』という企画を行う番組。佐賀城の南堀が作業対象のロケ地になっており、私は大喜びして見ていました。
出演者の1人で、イケメン俳優枠(?)でのメンバーが中川大志さんでした。
――堀の底で“掘り出し物”を探す、一行。
“鍋島焼”の出現などが期待されるも、今ひとつ振り切った成果の出ない中…
時間は経過し「フライト(飛行機)の時間もあり、そろそろ撤収か」という空気が流れたところ。「もう少し、頑張りたい」様子で、延長を希望する中川大志さん。
――佐賀城の南堀の水を抜くなど、普通には無い事。
堀の水を抜くのは400年ぶりとも言われ、もちろん泥まみれの堀の底。“持っている”その人は、拾い上げてきました。
タイムリミットの迫る頃、泥の中からその手に掴んだのは、本丸の建物にあったのだろう、鬼瓦の一部。何とも絵になる場面でした。
――“佐賀の大河ドラマ”が実現した時に…
この佐賀において「運命的に何かを掴んだ感じ」が、中川大志さんを“主役級”に推したいと考える理由の1つです。
かつて2016年の大河ドラマ『真田丸』では、豊臣秀吉〔演:小日向文世〕の子・豊臣秀頼役でした。
主人公・真田信繁(幸村)〔演:堺雅人〕は、大坂城に駆けつけ、徳川の大軍と“真田丸”で戦うことになります。
その時、総大将・豊臣秀頼〔演:中川大志〕にオーラがあり過ぎると評判で、「今年の“大坂の陣”は豊臣方が勝つかな?」と言い出す人も居たようです。
――できるなら、この人を演じてほしい〔その③〕
壮大な前振りでしたが、大隈八太郎(重信)役で見てみたい俳優さんです。
背丈が182センチほどと言われる、長身の大隈重信。とくに以下のような筋書きだと、コメディ要素もこなせる中川大志さんが適任に思えてきています。
母親べったりの甘えん坊だった大隈家の長男・八太郎くん。あふれんばかりの母の愛に育まれ、すくすくと成長します。
――ところが今度は、元気に育ちすぎて、
急にケンカに明け暮れる子になり、別の意味で母を悩ませます。しかし、頭の回転も速く、要領も良かった八太郎。賢い先輩たちの影響で志を立てます。
やがて“西洋”の学問に出会った、大隈八太郎。ついには殿様に講義をする身分になり、母の苦労も報われます。
〔参照(前半):
―…と可愛いけど、手のかかる我が子を見守る、母の物語にもできます。
尊王の想いを強める八太郎は、幕末動乱への介入に慎重な大殿・鍋島直正の方針に反発を感じ始めます。
一方で、長崎での貿易や英学校の開設など、様々な課題に慌ただしく挑んでいくことに…と、長崎を舞台にした、青春活劇にもできそうです。
――2021年大河『青天を衝け』を思い起せば…
大隈重信役のキャスト・大倉孝二さんが、明治期の“新しい大隈像”を築いたと感じる好演でした。
「おいも、なん~も知らん」とか言うインパクトの強いセリフも印象的。
〔参照:
「佐賀は、日本一の洋学通ぞ」とかローカル的に嬉しいものや「開化のための費用は、やむを得んばい」とか、さすがと思う名セリフも多くて…
〔参照(前半):
仮に中川大志さんが同様のセリフを語ったら、味わいは大倉さんとは異なるものの、すごく絵になりそうな感じがするのですが、どうでしょう。
――幕末期、長崎の“光る海”を見つめて…
現在の“本編”では、江藤新平の京都での活動を書いていますが、その頃から大隈重信はよく長崎に足を運んでいた様子。
「江藤さんが、京で公家(くげ)衆に会っているらしい…」という感じで、若き大隈も先輩の動向を気にしていたそうです。
『青天を衝け』では、視聴者の想像に任された幕末期、大隈重信の前日譚。大隈を軸とした“長崎編”も、ぜひ書いてみたい内容です。
――さて、ここ2回ほどは、
「こんな配役があると、面白いのでは」という、私の“空想”を記事にしました。正直、期待した2024年の大河に当たらなかったので、多少はショックでした。
「幕末佐賀藩の大河ドラマは、いつ実現するんだろうか…」という気持ちもあり、具体的な配役もイメージすることで、気合いを入れ直したところです。
なお、当ブログで、私が語る配役イメージは、その時々の思いつきです。実在の俳優さんの活動には、何ら関わりは無いので、念のため申し添えます。
2022年05月14日
「どうする、“配役”」
こんばんは。
2024年の大河ドラマは、『光る君へ』に決まったと発表されました。
主人公は「源氏物語」の作者・紫式部〔演:吉高由里子〕。華やかな平安時代を舞台とした物語で、気になるのは「誰が、藤原道長を演じるのか?」。
ここが、注目のポイントになるのでは…と考えるところです。早くもネット上では、どの俳優さんが演じるか“予想合戦”が始まっている様子です。
――「やはり、“配役”は大事。」
いかに“幕末の佐賀藩”に大きな意義があったとしても、脚本がどう描かれて、どう演出されるかで伝わり方が異なります。
そして、登場人物を演じる俳優さんで、作品の“成否”が決するのでしょう。
以上でお察しのことかと思いますが、私は『幕末佐賀藩の大河ドラマ』を見ることを、全くあきらめていません。

――おそらくは、次の“大河”の発表も近づいている。
いま2024年大河の情報が出たのは、通例よりは遅めのはず。平安期を描く大河ドラマ『光る君へ』の放送開始までは、あと1年半程度なのです。
続く2025年の大河ドラマは、さほどの間を開けずに発表されると考えます。
よもや、ここで気を抜くようでは日本の夜明け前…のさらに前、幕末の黎明期から走っていた、佐賀の“先輩”たちに合わせる顔がありません。
…というわけで、より強く“佐賀の物語”をイメージするべく、今回は“配役”について考えてみます。
――今回のイメージは、放送中の『鎌倉殿の13人』と…
同じ三谷幸喜さんの脚本、2016年大河『真田丸』を参考にしています。
私が“本編”を描くときも、仮キャストの俳優さんをイメージしている時があります。これも、いわゆる“当て書き”なのかもしれません。
三谷さんの脚本では、その“当て書き”が徹底しているらしく、演じる俳優さんの特徴がハッキリと表われていると聞いたことがあります。
その手法を取ろうとしても、私は中途半端なので、時々の気分によって史実の人物そのままのイメージだったり、“仮キャスト”が代わる事もあります。
――今日は、そんな“仮キャスト”のお話です。
なお、私の配役イメージは個人的な思いつきの域を出ず、もちろん例示する、実在の俳優さんには何の関わりもありません。
できれば皆様も、ご自身で「佐賀の歴史上の人物を、誰に演じてほしいか」をイメージしてみてほしいのです。
きっと、その方が実現したときの楽しみが増えることでしょう。では私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」での個人的な配役イメージの例をご紹介します。
――“配役”の勝手なイメージ〔その①〕
冴え渡る知略、渋い声と佇(たたず)まいだけで、凄みを感じさせる策士。
『鎌倉殿』では、源頼朝〔演:大泉洋〕の懐刀とも言うべき知恵者・大江広元を演じる、栗原英雄さん。
『真田丸』では真田昌幸〔演:草刈正雄〕の弟で、信繁(幸村)〔演:堺雅人〕の叔父にあたる、真田信尹を好演。
そこでも“策士”として強い印象を残し、真田家のため様々な謀略を尽くします。まだ若かった甥っ子の信繁に「儂のようには成るな」と語る姿が渋すぎました。

――できるなら、この人を演じてほしい〔その①〕
個人的には、佐賀の名君・鍋島直正の師匠・古賀穀堂のキャストで見てみたい俳優さんです。
穀堂先生も、前回に引き続き“古賀さん”なのですが、幕末期に佐賀藩の改革の道筋を付けた…ある意味、日本の近代化の“道案内”をした方です。
名君の幼少期から素質を見抜き、その才能を鍛え上げ、鍋島直正が藩政の実権を握れるように策を講じた師匠です。
〔参照(終盤):第1話「長崎警護」⑦〕
「勉強しない藩士は処罰したいのう…」と考えがちな怖い一面もあります。この姿勢が日本一、勉強熱心と評された佐賀藩を作ったのかもしれません。
〔参照(前半):STEP1:名君の登場まで〕
――“配役”の勝手なイメージ〔その②〕
醍醐寺で修行を20年。“風を起こす業”も会得した…らしい法師。『鎌倉殿』では阿野全成を演じる、新納慎也さん。
源頼朝の異母弟、源義経〔演:菅田将暉〕の同母兄という立場。鎌倉で様々な儀式を行う、清々しく坊主頭の“醍醐禅師”として登場。
北条義時〔演:小栗旬〕の妹・実衣〔演:宮澤エマ〕とのコメディー色の強い夫婦は、同番組の“癒やし要素”と思う人も多いはず。

――できるなら、この人を演じてほしい〔その②〕
個人的には、佐賀藩が誇る“万能の研究主任”佐野常民役のイメージが近いです。もともと医者だった佐野が坊主頭だったから…というのは安直な理由。
〔参照(後半):第10話「蒸気機関」⑨(佐野、精錬方へ)〕
もう1つの理由は、よく感動して泣くエピソードで知られる佐野。この俳優さんは、涙の演技の印象が強いのです。
『真田丸』では豊臣秀吉〔演:小日向文世〕の甥、関白・豊臣秀次を演じました。天下の重責に苦しむ、豊臣秀次は出奔し、切腹へと追い込まれます。
――その時、“豊臣秀次”の涙がやたらに重く…
いち視聴者である私は、「この辺りから豊臣政権に暗雲が漂ってくるのか…」と、妙に納得したように記憶します。
なお、NHKの正月時代劇に『風雲児たち~蘭学革命篇~』という作品があり、これも“三谷脚本”だったのですが、新納慎也さんは杉田玄白役で出演。
作品のラストだと思いますが、新納さん演じる杉田玄白が、丸坊主の医者の姿で旧友と涙を流す場面があり、これが私には佐野常民のイメージでした。
――あと1人、語りたい方がいるのですが、
少し長くなってしまいそうなので、次回以降に。私の配役(キャスト)イメージは、個人的な“空想”であることをあらためてお伝えしておきます。
各々の得意分野も異なり、とても個性的な佐賀の“先輩”たち。新しい知識を得たり、場面や時期の設定でイメージする俳優さんも変わる事があります。
「この人物は、あの俳優さんに演じてほしい…」とか佐賀の街角でそんな会話が広がる日々を期待しています。
2024年の大河ドラマは、『光る君へ』に決まったと発表されました。
主人公は「源氏物語」の作者・紫式部〔演:吉高由里子〕。華やかな平安時代を舞台とした物語で、気になるのは「誰が、藤原道長を演じるのか?」。
ここが、注目のポイントになるのでは…と考えるところです。早くもネット上では、どの俳優さんが演じるか“予想合戦”が始まっている様子です。
――「やはり、“配役”は大事。」
いかに“幕末の佐賀藩”に大きな意義があったとしても、脚本がどう描かれて、どう演出されるかで伝わり方が異なります。
そして、登場人物を演じる俳優さんで、作品の“成否”が決するのでしょう。
以上でお察しのことかと思いますが、私は『幕末佐賀藩の大河ドラマ』を見ることを、全くあきらめていません。
――おそらくは、次の“大河”の発表も近づいている。
いま2024年大河の情報が出たのは、通例よりは遅めのはず。平安期を描く大河ドラマ『光る君へ』の放送開始までは、あと1年半程度なのです。
続く2025年の大河ドラマは、さほどの間を開けずに発表されると考えます。
よもや、ここで気を抜くようでは日本の夜明け前…のさらに前、幕末の黎明期から走っていた、佐賀の“先輩”たちに合わせる顔がありません。
…というわけで、より強く“佐賀の物語”をイメージするべく、今回は“配役”について考えてみます。
――今回のイメージは、放送中の『鎌倉殿の13人』と…
同じ三谷幸喜さんの脚本、2016年大河『真田丸』を参考にしています。
私が“本編”を描くときも、仮キャストの俳優さんをイメージしている時があります。これも、いわゆる“当て書き”なのかもしれません。
三谷さんの脚本では、その“当て書き”が徹底しているらしく、演じる俳優さんの特徴がハッキリと表われていると聞いたことがあります。
その手法を取ろうとしても、私は中途半端なので、時々の気分によって史実の人物そのままのイメージだったり、“仮キャスト”が代わる事もあります。
――今日は、そんな“仮キャスト”のお話です。
なお、私の配役イメージは個人的な思いつきの域を出ず、もちろん例示する、実在の俳優さんには何の関わりもありません。
できれば皆様も、ご自身で「佐賀の歴史上の人物を、誰に演じてほしいか」をイメージしてみてほしいのです。
きっと、その方が実現したときの楽しみが増えることでしょう。では私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」での個人的な配役イメージの例をご紹介します。
――“配役”の勝手なイメージ〔その①〕
冴え渡る知略、渋い声と佇(たたず)まいだけで、凄みを感じさせる策士。
『鎌倉殿』では、源頼朝〔演:大泉洋〕の懐刀とも言うべき知恵者・大江広元を演じる、栗原英雄さん。
『真田丸』では真田昌幸〔演:草刈正雄〕の弟で、信繁(幸村)〔演:堺雅人〕の叔父にあたる、真田信尹を好演。
そこでも“策士”として強い印象を残し、真田家のため様々な謀略を尽くします。まだ若かった甥っ子の信繁に「儂のようには成るな」と語る姿が渋すぎました。
――できるなら、この人を演じてほしい〔その①〕
個人的には、佐賀の名君・鍋島直正の師匠・古賀穀堂のキャストで見てみたい俳優さんです。
穀堂先生も、前回に引き続き“古賀さん”なのですが、幕末期に佐賀藩の改革の道筋を付けた…ある意味、日本の近代化の“道案内”をした方です。
名君の幼少期から素質を見抜き、その才能を鍛え上げ、鍋島直正が藩政の実権を握れるように策を講じた師匠です。
〔参照(終盤):
「勉強しない藩士は処罰したいのう…」と考えがちな怖い一面もあります。この姿勢が日本一、勉強熱心と評された佐賀藩を作ったのかもしれません。
〔参照(前半):
――“配役”の勝手なイメージ〔その②〕
醍醐寺で修行を20年。“風を起こす業”も会得した…らしい法師。『鎌倉殿』では阿野全成を演じる、新納慎也さん。
源頼朝の異母弟、源義経〔演:菅田将暉〕の同母兄という立場。鎌倉で様々な儀式を行う、清々しく坊主頭の“醍醐禅師”として登場。
北条義時〔演:小栗旬〕の妹・実衣〔演:宮澤エマ〕とのコメディー色の強い夫婦は、同番組の“癒やし要素”と思う人も多いはず。
――できるなら、この人を演じてほしい〔その②〕
個人的には、佐賀藩が誇る“万能の研究主任”佐野常民役のイメージが近いです。もともと医者だった佐野が坊主頭だったから…というのは安直な理由。
〔参照(後半):
もう1つの理由は、よく感動して泣くエピソードで知られる佐野。この俳優さんは、涙の演技の印象が強いのです。
『真田丸』では豊臣秀吉〔演:小日向文世〕の甥、関白・豊臣秀次を演じました。天下の重責に苦しむ、豊臣秀次は出奔し、切腹へと追い込まれます。
――その時、“豊臣秀次”の涙がやたらに重く…
いち視聴者である私は、「この辺りから豊臣政権に暗雲が漂ってくるのか…」と、妙に納得したように記憶します。
なお、NHKの正月時代劇に『風雲児たち~蘭学革命篇~』という作品があり、これも“三谷脚本”だったのですが、新納慎也さんは杉田玄白役で出演。
作品のラストだと思いますが、新納さん演じる杉田玄白が、丸坊主の医者の姿で旧友と涙を流す場面があり、これが私には佐野常民のイメージでした。
――あと1人、語りたい方がいるのですが、
少し長くなってしまいそうなので、次回以降に。私の配役(キャスト)イメージは、個人的な“空想”であることをあらためてお伝えしておきます。
各々の得意分野も異なり、とても個性的な佐賀の“先輩”たち。新しい知識を得たり、場面や時期の設定でイメージする俳優さんも変わる事があります。
「この人物は、あの俳優さんに演じてほしい…」とか佐賀の街角でそんな会話が広がる日々を期待しています。
2022年05月11日
「古賀殿が3人…!?」
こんばんは。
“本編”第18話に戻ろうとするのですが、個人的に気忙しい状況が続き、集中して書くことができません。
そんな中、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の脚本家・三谷幸喜さんの作る物語には、呆然とします。まさか源義経〔演:菅田将暉〕を、あのように描くとは…。
しかも“悲劇”が近づく予感とともに、何だか義経の好感度がアップする演出が、視聴者を振り回してきますし、私も、まんまと術中にハマっているようです。
やはり、著名なプロフェッショナルは違う。もし「佐賀を題材とした大河ドラマ」が実現すれば、傑作を創れる脚本家さんは居られるのだろうと思います。
――最大の問題は、その“実現”が不確かなこと。
2024年の大河ドラマの主役は、なんと紫式部〔演:吉高由里子〕に決まったそうです。(2022年5月11日発表。先ほど確認して、衝撃を受けています)

※紫式部と同時代の“ライバル”・和泉式部の像(嬉野市塩田町)。
〔参照:「醒覚の剣(歌枕)」〕
なかなか発表が無く「佐賀県内でも走行試験が始まった“西九州新幹線”開業のタイミングを待っているのか?」と都合の良い想像をしたのですが…
今回は期待していたので残念ですが、私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」への想いは、これからも綴っていきたいと思います。
共感できそうな皆様とは、一緒に盛り上がりたいと思うところです…とはいえ、私は2年半ほど帰省すらできず、なかなか“佐賀への道”は開かれません。
――そんな気分の中、本日は“道案内”をする人のお話です。
3年ほど前から「幕末の佐賀藩」を語る価値を、はっきりと認識したことで、すっかり故郷・佐賀への誇りを取り戻した私。
全国放送で、佐賀が映るテレビ番組や、あるいは話題になった、佐賀の広報動画なども確認することがあります。
――そこで何となく、気付いた傾向が。
全然、別の番組や動画を見ていたのですが、偶然なのか案内役の人の名字が「古賀さん」。
嬉野でも「古賀さん」が姿を見せ、佐賀市内でも「古賀さん」が説明を担当していました。
出典が不確かですが、佐賀県の古賀姓の方は1万人を超えるとか。数字が正しければ、県の人口が約80万人ですので、かなり高い割合だと思います。
――当初は、こう思っていました。
“本編”を書くうえで、佐賀の殿様の一門や親類、もしくは重臣が名乗る「鍋島」の名字が、同時に複数登場するのは、やむを得ない。
だが、他はややこしくなるので、なるべく同一の名字の人物が、“本編”で同時期に並行して登場するのは控えよう…と。
これを打破したのは、「佐賀のレポートでは、“古賀さん”が1度は登場しがち」という“佐賀県あるある”でした。

※嬉野市内・嬉野温泉
――もし、「佐賀の物語」を描くならば…
「古賀さんが登場しない話は、逆に“不完全”なのでは…」と思い直します。
まず、本編で最も自由に書いている人物の1人「①嬉野の忍者・古賀」。そのモデルは、佐賀の支藩である蓮池藩士・古賀源太夫です。
イギリス船の動向を探る忍者(下級武士)という設定は、実在の人物寄り。
――次第に、「西洋事情に通じる」だけでなく、
野良着を愛用する“佐賀ことば”が強めの中年…なぜか相棒がネコ。いろいろ属性が追加されていき、創作寄りの人物像になっています。
また、佐賀藩の“火術方”に関わったらしい…という不確実な情報から、想像をはたらかせて、“本編”中では、江藤新平に何らかの影響を与えています。
〔参照:第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)〕
忍者を「特殊な技術を用いて、調査の任務にあたり、情報を持ち帰る役割の下級武士」と定義すれば、佐賀にも結構、“忍者”は居たのかも知れません。
〔参照:「佐賀の忍者、幕末を走る!」〔嬉野温泉駅〕〕

※佐賀市内・長崎街道
――その一方で、史実寄りの登場をする“古賀さん”もいます。
佐賀の“秘密結社”義祭同盟の一員で、のち明治初期には、東京近郊に存在した“品川県”を任された実務家。
第17話では「②佐賀の志士・古賀一平」も登場しました。わりと常識人なのですが、こと“勤王”の話題になると、急に熱くなる人物として描きました。
〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕
明治期も、新政府のために尽くした内務官僚として語られることが多い印象。
キャラの強い“佐賀の七賢人”や師匠・枝吉神陽に比べ、なるべく普通の人っぽく書くようにしています。
当時、三瀬の番所を担当したことから、江藤新平の脱藩の手引きをした…という説は有力なようです。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)〕

※小城市内・羊羹の名店が並ぶ
――そして、京の都にも、“古賀さん”の姿が。
直近の“本編”で、京都(伏見)に到着したばかりの江藤新平の前に現れた、「③謎の男・祇園太郎」。
〔参照:第18話「京都見聞」⑥(もう1人の脱藩者)〕
こちらも幕末期に実在した佐賀出身者で、地元は小城です。播磨(兵庫)を拠点に、京・大坂でも活動した…とされる人物。
――但し、この前後には長崎に移っていた可能性も。
“祇園太郎”には、佐賀本藩に情勢を報告したとか、義祭同盟の活動にも関わったとか、色々な話が伝わります。
細かい足跡や活動目的には、やはり謎が多い人物。この“祇園太郎”も本名は、古賀さんです。
登場人物に古賀姓が増えてきて、なぜか全員が道を教える役回り…かえって「佐賀の物語」としては、リアルな感じがするのですが…どうでしょう。
“本編”第18話に戻ろうとするのですが、個人的に気忙しい状況が続き、集中して書くことができません。
そんな中、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の脚本家・三谷幸喜さんの作る物語には、呆然とします。まさか源義経〔演:菅田将暉〕を、あのように描くとは…。
しかも“悲劇”が近づく予感とともに、何だか義経の好感度がアップする演出が、視聴者を振り回してきますし、私も、まんまと術中にハマっているようです。
やはり、著名なプロフェッショナルは違う。もし「佐賀を題材とした大河ドラマ」が実現すれば、傑作を創れる脚本家さんは居られるのだろうと思います。
――最大の問題は、その“実現”が不確かなこと。
2024年の大河ドラマの主役は、なんと紫式部〔演:吉高由里子〕に決まったそうです。(2022年5月11日発表。先ほど確認して、衝撃を受けています)
※紫式部と同時代の“ライバル”・和泉式部の像(嬉野市塩田町)。
〔参照:
なかなか発表が無く「佐賀県内でも走行試験が始まった“西九州新幹線”開業のタイミングを待っているのか?」と都合の良い想像をしたのですが…
今回は期待していたので残念ですが、私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」への想いは、これからも綴っていきたいと思います。
共感できそうな皆様とは、一緒に盛り上がりたいと思うところです…とはいえ、私は2年半ほど帰省すらできず、なかなか“佐賀への道”は開かれません。
――そんな気分の中、本日は“道案内”をする人のお話です。
3年ほど前から「幕末の佐賀藩」を語る価値を、はっきりと認識したことで、すっかり故郷・佐賀への誇りを取り戻した私。
全国放送で、佐賀が映るテレビ番組や、あるいは話題になった、佐賀の広報動画なども確認することがあります。
――そこで何となく、気付いた傾向が。
全然、別の番組や動画を見ていたのですが、偶然なのか案内役の人の名字が「古賀さん」。
嬉野でも「古賀さん」が姿を見せ、佐賀市内でも「古賀さん」が説明を担当していました。
出典が不確かですが、佐賀県の古賀姓の方は1万人を超えるとか。数字が正しければ、県の人口が約80万人ですので、かなり高い割合だと思います。
――当初は、こう思っていました。
“本編”を書くうえで、佐賀の殿様の一門や親類、もしくは重臣が名乗る「鍋島」の名字が、同時に複数登場するのは、やむを得ない。
だが、他はややこしくなるので、なるべく同一の名字の人物が、“本編”で同時期に並行して登場するのは控えよう…と。
これを打破したのは、「佐賀のレポートでは、“古賀さん”が1度は登場しがち」という“佐賀県あるある”でした。
※嬉野市内・嬉野温泉
――もし、「佐賀の物語」を描くならば…
「古賀さんが登場しない話は、逆に“不完全”なのでは…」と思い直します。
まず、本編で最も自由に書いている人物の1人「①嬉野の忍者・古賀」。そのモデルは、佐賀の支藩である蓮池藩士・古賀源太夫です。
イギリス船の動向を探る忍者(下級武士)という設定は、実在の人物寄り。
――次第に、「西洋事情に通じる」だけでなく、
野良着を愛用する“佐賀ことば”が強めの中年…なぜか相棒がネコ。いろいろ属性が追加されていき、創作寄りの人物像になっています。
また、佐賀藩の“火術方”に関わったらしい…という不確実な情報から、想像をはたらかせて、“本編”中では、江藤新平に何らかの影響を与えています。
〔参照:
忍者を「特殊な技術を用いて、調査の任務にあたり、情報を持ち帰る役割の下級武士」と定義すれば、佐賀にも結構、“忍者”は居たのかも知れません。
〔参照:
※佐賀市内・長崎街道
――その一方で、史実寄りの登場をする“古賀さん”もいます。
佐賀の“秘密結社”義祭同盟の一員で、のち明治初期には、東京近郊に存在した“品川県”を任された実務家。
第17話では「②佐賀の志士・古賀一平」も登場しました。わりと常識人なのですが、こと“勤王”の話題になると、急に熱くなる人物として描きました。
〔参照:
明治期も、新政府のために尽くした内務官僚として語られることが多い印象。
キャラの強い“佐賀の七賢人”や師匠・枝吉神陽に比べ、なるべく普通の人っぽく書くようにしています。
当時、三瀬の番所を担当したことから、江藤新平の脱藩の手引きをした…という説は有力なようです。
〔参照(後半):
※小城市内・羊羹の名店が並ぶ
――そして、京の都にも、“古賀さん”の姿が。
直近の“本編”で、京都(伏見)に到着したばかりの江藤新平の前に現れた、「③謎の男・祇園太郎」。
〔参照:
こちらも幕末期に実在した佐賀出身者で、地元は小城です。播磨(兵庫)を拠点に、京・大坂でも活動した…とされる人物。
――但し、この前後には長崎に移っていた可能性も。
“祇園太郎”には、佐賀本藩に情勢を報告したとか、義祭同盟の活動にも関わったとか、色々な話が伝わります。
細かい足跡や活動目的には、やはり謎が多い人物。この“祇園太郎”も本名は、古賀さんです。
登場人物に古賀姓が増えてきて、なぜか全員が道を教える役回り…かえって「佐賀の物語」としては、リアルな感じがするのですが…どうでしょう。
2022年03月28日
「年度末に“○○ロス”を語る。」
こんばんは。
学生や社会人、高齢者まで…おそらくは、何だか気ぜわしい年度末。花盛りは一瞬で、すぐに散ってしまう桜の姿にも急かされる気がします。
わかりやすくは、進級、進学、就職、転職、転勤。退職された方とて、年度末と無縁ではありません。
日常的に関わってきた人たちが、上記の事情で去りゆくこともあるでしょう。
――そんな別れの季節でもある春。
卒業する学生にとって春と言えば、いつもの場所でいつもの仲間と会っていた、青春の日々からの旅立ちの時でもあります。
また、自身は動かないけども、当たり前にあったはずの環境が変わることも。それらを軽妙に(?)表現する言葉を、しばらく前から聞くようになりました。
テレビ番組の終了やドラマの登場人物の退場、異性に人気のある芸能人の結婚などで使われ出した印象です。
私が最初に聞き始めたのは、2013年の秋でした。

――その言葉とは、「○○ロス」。
テレビでの代表例は、舞台となった東北のみならず、全国的に大ブームを巻き起こした2013年連続テレビ小説「あまちゃん」。
未だ地方創生や関係人口の話題とも結びつき、その存在感は続く作品です。
連続テレビ小説(朝ドラ)は半期に1度は、物語が変わる定めではあるものの、この時の世間の反応はすごかった。
――半年のうちに、視聴者が感じてきた“仲間意識”。
「ああ…もう、あの“北三陸”の人たちに会えないんだ…」
皆がそう思ったか「あまロス」という言葉が飛び交っていたことを記憶します。
親しみを感じていたドラマや定番番組の終了。当たり前にあったものが見られなくなるのは寂しいものです。
――有名人の結婚パターンで言えば…
あえて長崎出身と強調しますが、福山雅治さんの結婚の報に落胆する女性が数多くいたことを思い出します。
これは「福山ロス」あるいは「ましゃ(雅治)ロス」と表現されていたようです。
芸能人の結婚パターンの場合は、仕事(家事)が手に付かない、あるいは会社を早退する人が続出する…という“症状”を伴うことが多いようです。
その都度、飛び交うのは「○○ロス」という言葉。

――物語での登場人物の退場パターンも。
直近の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で言えば、主人公・北条義時〔演:小栗旬〕の兄・宗時〔演:片岡愛之助〕。
歴史上では父・北条時政〔演:坂東彌十郎〕や弟・義時に比べて、あまり知られていない人物のはず。実は私も存じ上げなかった。
序盤からゴリゴリの武闘派として強い印象を残した北条宗時。同番組を代表する“暗殺者”・善児〔演:梶原善〕からの不意打ちによる衝撃的な最期でした。
結果として、視聴者には強烈な「北条宗時ロス」が生じたようです。
――北条宗時を演じた、片岡愛之助さんの“役作り”が…
人気アニメ『鬼滅の刃』で壮絶な最期を遂げ、後輩である主人公たちに大きい影響を残す“炎柱・煉獄杏寿郎”をイメージしていたと話題になりました。
たしかに主人公・北条義時が、坂東武士のための政権を関東に作り上げると“立志”するところに強い影響を与えるなど、納得の表現でした。
――これからが本題です。私は“ロス”の話で、何を語りたかったか。
多くの人々が共感する「あまロス」「福山ロス」などの社会現象にもなるロス。
「北条宗時ロス」など物語の中に、強い影響を残して作品を形成していくロス。
年度替わりにありがちな、職場の“柱”の転勤など。関係者にしか響かないものの、当事者には切実な「○○さんロス」。

――私は、ブログを書く中で“ロス”に遭遇しました。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”を書く中で、第17話に難所がありました。
わりと序盤から登場していた主要人物の最期を書かねばならなかったのです。この書き出しでわかる方は、もう私と同じ“作品”を視ているのかもしれません。
――幕末の佐賀藩士である、中野方蔵。
大木喬任・江藤新平の親友で、実現の10年くらい前に“大政奉還”をイメージできていたと考えられる人物。
計画どおりに江戸への留学を勝ち取るなど、佐賀の“義祭同盟”のメンバーの中でも要領の良い印象で、突出して行動力があったと思われます。
中野にとっては“次の時代”を見据えた動きで、他藩への人脈を築いていましたが、人とのつながりが豊富にあったことが“諸刃の剣”となりました。
〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑯(つながりは諸刃の剣)〕
――“坂下門外の変”に連座して捕縛され、獄中で落命する。
第17話「佐賀脱藩」で描いた、中野方蔵の最期を調べると、概ねこの一行での説明が一般的でした。
私の拙い能力で、何とか“物語化”を図りました。その最後に救いの要素がほしくて、佐賀での仲間たちとの日々と、故郷の空を想い起こす…という話に。
〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑱(青葉茂れる頃に)〕
――この顛末が、江藤新平が佐賀を脱藩した動機と言われます。
序盤から、とても描きやすかった中野方蔵。一番年下でしたが、親友2人より常に先を走っていた印象です。
厳然とした史実があるため、その最期を書きましたが、その後の脱力感が半端ではなかったです。これが、私が当ブログを続ける中で遭遇した“ロス”。
…言うなれば、「中野方蔵ロス」の一部始終でした。
一方で、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現した時には、全国の視聴者が、“ロス”を感じるほどに仕上げてほしい…というのが私の想いです。
学生や社会人、高齢者まで…おそらくは、何だか気ぜわしい年度末。花盛りは一瞬で、すぐに散ってしまう桜の姿にも急かされる気がします。
わかりやすくは、進級、進学、就職、転職、転勤。退職された方とて、年度末と無縁ではありません。
日常的に関わってきた人たちが、上記の事情で去りゆくこともあるでしょう。
――そんな別れの季節でもある春。
卒業する学生にとって春と言えば、いつもの場所でいつもの仲間と会っていた、青春の日々からの旅立ちの時でもあります。
また、自身は動かないけども、当たり前にあったはずの環境が変わることも。それらを軽妙に(?)表現する言葉を、しばらく前から聞くようになりました。
テレビ番組の終了やドラマの登場人物の退場、異性に人気のある芸能人の結婚などで使われ出した印象です。
私が最初に聞き始めたのは、2013年の秋でした。
――その言葉とは、「○○ロス」。
テレビでの代表例は、舞台となった東北のみならず、全国的に大ブームを巻き起こした2013年連続テレビ小説「あまちゃん」。
未だ地方創生や関係人口の話題とも結びつき、その存在感は続く作品です。
連続テレビ小説(朝ドラ)は半期に1度は、物語が変わる定めではあるものの、この時の世間の反応はすごかった。
――半年のうちに、視聴者が感じてきた“仲間意識”。
「ああ…もう、あの“北三陸”の人たちに会えないんだ…」
皆がそう思ったか「あまロス」という言葉が飛び交っていたことを記憶します。
親しみを感じていたドラマや定番番組の終了。当たり前にあったものが見られなくなるのは寂しいものです。
――有名人の結婚パターンで言えば…
あえて長崎出身と強調しますが、福山雅治さんの結婚の報に落胆する女性が数多くいたことを思い出します。
これは「福山ロス」あるいは「ましゃ(雅治)ロス」と表現されていたようです。
芸能人の結婚パターンの場合は、仕事(家事)が手に付かない、あるいは会社を早退する人が続出する…という“症状”を伴うことが多いようです。
その都度、飛び交うのは「○○ロス」という言葉。

――物語での登場人物の退場パターンも。
直近の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で言えば、主人公・北条義時〔演:小栗旬〕の兄・宗時〔演:片岡愛之助〕。
歴史上では父・北条時政〔演:坂東彌十郎〕や弟・義時に比べて、あまり知られていない人物のはず。実は私も存じ上げなかった。
序盤からゴリゴリの武闘派として強い印象を残した北条宗時。同番組を代表する“暗殺者”・善児〔演:梶原善〕からの不意打ちによる衝撃的な最期でした。
結果として、視聴者には強烈な「北条宗時ロス」が生じたようです。
――北条宗時を演じた、片岡愛之助さんの“役作り”が…
人気アニメ『鬼滅の刃』で壮絶な最期を遂げ、後輩である主人公たちに大きい影響を残す“炎柱・煉獄杏寿郎”をイメージしていたと話題になりました。
たしかに主人公・北条義時が、坂東武士のための政権を関東に作り上げると“立志”するところに強い影響を与えるなど、納得の表現でした。
――これからが本題です。私は“ロス”の話で、何を語りたかったか。
多くの人々が共感する「あまロス」「福山ロス」などの社会現象にもなるロス。
「北条宗時ロス」など物語の中に、強い影響を残して作品を形成していくロス。
年度替わりにありがちな、職場の“柱”の転勤など。関係者にしか響かないものの、当事者には切実な「○○さんロス」。
――私は、ブログを書く中で“ロス”に遭遇しました。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”を書く中で、第17話に難所がありました。
わりと序盤から登場していた主要人物の最期を書かねばならなかったのです。この書き出しでわかる方は、もう私と同じ“作品”を視ているのかもしれません。
――幕末の佐賀藩士である、中野方蔵。
大木喬任・江藤新平の親友で、実現の10年くらい前に“大政奉還”をイメージできていたと考えられる人物。
計画どおりに江戸への留学を勝ち取るなど、佐賀の“義祭同盟”のメンバーの中でも要領の良い印象で、突出して行動力があったと思われます。
中野にとっては“次の時代”を見据えた動きで、他藩への人脈を築いていましたが、人とのつながりが豊富にあったことが“諸刃の剣”となりました。
〔参照:
――“坂下門外の変”に連座して捕縛され、獄中で落命する。
第17話「佐賀脱藩」で描いた、中野方蔵の最期を調べると、概ねこの一行での説明が一般的でした。
私の拙い能力で、何とか“物語化”を図りました。その最後に救いの要素がほしくて、佐賀での仲間たちとの日々と、故郷の空を想い起こす…という話に。
〔参照:
――この顛末が、江藤新平が佐賀を脱藩した動機と言われます。
序盤から、とても描きやすかった中野方蔵。一番年下でしたが、親友2人より常に先を走っていた印象です。
厳然とした史実があるため、その最期を書きましたが、その後の脱力感が半端ではなかったです。これが、私が当ブログを続ける中で遭遇した“ロス”。
…言うなれば、「中野方蔵ロス」の一部始終でした。
一方で、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現した時には、全国の視聴者が、“ロス”を感じるほどに仕上げてほしい…というのが私の想いです。
2022年03月13日
「ロード・オブ・サガ ~三つの“佐賀”~(後編)」
こんばんは。
さて、前編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Road of Saga)」でした。「佐賀へと、つながる道」という感じでしょうか。
後編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Lord of Saga)」で、まとめてみます。
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語タイトル(The 13 Lords of the Shogun)は、概ね「鎌倉幕府の将軍を支える13人の領主たち」の意味と聞きます。
そして江戸時代の“藩主”や、藩内各地域の“領主”も、大まかには“Lord”の単語で訳すようなので…こんな事を考えてみました。
――当ブログを始めてから行き当たった課題。
それは「私が語るべき“佐賀”は、どこまでの範囲なのか…」という疑問。普通に考えれば「それは佐賀藩なのでは?」という答えになるのでしょう。
現在の「佐賀県」の江戸時代の姿について。幕府の直轄領(天領)を除けば、三つに大別されるという見方が一般的であると思います。
A.佐賀藩
B.唐津藩
C.対馬藩(田代領)
前編に続いて三択クイズっぽいですが、3つとも正解です。ちなみに佐賀藩内には、さらに三つの“支藩”(小城・蓮池・鹿島)があります。

――まずは「A.佐賀藩」。
佐賀藩の中に、三つの支藩があることはお伝えしましたが、他に各地域にも、ご領主(邑主)が居られます。
この辺りは、まだまだ私は勉強中で知識が浅いのですが、今後のために整理を試みます。私が参照した資料では概ね以下の内容でした。
・支藩(3家)…小城・蓮池・鹿島
・親類(4家)…白石・神代・久保田村田・村田
・親類同格(4家)…武雄・多久・諫早・須古
「親類」の神代家・久保田村田家、「親類同格」の多久・諫早家以外は、上記の名称後に“鍋島家”が付くようです。
また「親類」の“白石”は、みやき町周辺に領地のあった白石鍋島家。「親類同格」の“須古鍋島家”は、現在の白石町にありました。
――あわせて佐賀藩の上級家臣団11家。
では、この領主たちを「“佐賀殿”の11人(The 11 Lords of the Saga)」とでも語るべきか…(?)とか連想したりもします。
ちなみに「親類同格」の4家は、元は龍造寺氏の家柄で「龍造寺四家」という呼び方もするようです。
〔参照(中盤):「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕〕
幕末期には鍋島直正の藩政改革に助力し、明治初期には戊辰戦争で奮闘するなど、この龍造寺四家はそれぞれに存在感を示しました。
県内にお住まいの方は、身近な地域の“ご領主”さまを意識すると、親近感がアップして良いかも(!)…と思います。

――続いて「B.唐津藩」。
「A.佐賀藩」の話が複雑になり過ぎたので、ここからはシンプルに書きます。
現在のところ“本編”で「唐津藩」の登場人物は、幕末に老中格として難局に挑んだ小笠原長行にのみ焦点を絞っています。
江戸に行くなり、幕府の重職に就いた小笠原長行ですが、その見つめる先には、いつも若き第14代将軍・徳川家茂の姿があるような描き方にしています。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑤(若き“将軍”への視線)〕
博学で、温厚そうなイメージのある方ですが、幾つかのエピソードから「上様のためなら!」という心意気を感じるところがあります。
――明治初期に、旧幕府方として戦ったためか…?
藩主の名代(代理)として扱われている小笠原長行。唐津藩主に就いていたかについては、議論があるようです。
〔参照(後半):「もしも不遇を感じた時には…」〕
また、小笠原家は先代藩主の水野家より、唐津の領地を引き継いでから、わずか半世紀ほどで、江戸幕府が終わってしまいました。
江戸期を通じて佐賀藩主だった鍋島家とは事情が異なるので、唐津の皆様から小笠原家は、どの程度の親しみを持たれているか…気になるところです。
現在の佐賀県には、幕府に忠義を尽くそうとした“佐幕派”の唐津藩もあったことは意識しながら、“本編”を書いています。

――そして「C.対馬藩(田代領)」。
当初は「“本編”では描けないか…」と考えましたが、第16話に現在の佐賀県鳥栖市(東部)・基山町にあたる対馬藩・田代領の物語を入れてみました。
1861年(万延二年・文久元年)には、“対馬事件”が起きました。ロシア軍艦ポサドニック号が対馬に上陸し、島内の土地を占拠した事件です。
この事態を受け、第16話に登場した田代領の若者たちも、本藩がある対馬(現・長崎県)へと向かいます。
その頃、佐賀藩士たちも、蒸気船“電流丸”を運用して周辺海域の警戒にあたっていました。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕
――“佐賀”にいた対馬藩士の視点も取り入れた、第16話「攘夷沸騰」。
当時、佐賀藩は幕府から蒸気船“観光丸”を預かっており、船長は佐野常民。幕府の外国奉行・小栗忠順に同行して、対馬に上陸しています。
こういった佐賀藩のエピソードを、さらに深掘りする書き方もあったのかもしれませんが、あえて田代領の対馬藩士たちだけが登場する回を加えています。
個人的に「対馬藩(田代領)の三部作」と呼称するシリーズです。ちなみに対馬藩主・宗義和は、お名前のみが登場します。
〔参照①:第16話「攘夷沸騰」⑮(“薬の街”に吹く風)〕
〔参照②:第16話「攘夷沸騰」⑯(露西亜〔ロシア〕の牙)〕
〔参照③:第16話「攘夷沸騰」⑳(基山の誇り、田代の想い)〕
この後、対馬藩士たちは“攘夷派”として長州藩(山口)に接近していきます。

――幕末。三つの“佐賀”の物語。
私は行けなかった2018年の「肥前さが幕末・維新博覧会」。当時の冊子を入手し、佐賀市内だけでなく、唐津・鳥栖にサテライト館があったと知りました。
開国を進める幕府に忠義を尽くそうとする唐津藩。異国の脅威を打ち払おうと攘夷に目覚める対馬藩(田代領)。
そして、日本の近代化こそ問題の解決につながると信じ、早くから独自の路線を進んできた佐賀藩。三者それぞれの立場で繰り広げられた“佐賀”の幕末。
さすがに「佐賀だけで幕末が語れる」とまでは言いませんが、「佐賀の視点で幕末を語る」と新しい物語が見えてくる!のは確かだと思います。
さて、前編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Road of Saga)」でした。「佐賀へと、つながる道」という感じでしょうか。
後編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Lord of Saga)」で、まとめてみます。
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語タイトル(The 13 Lords of the Shogun)は、概ね「鎌倉幕府の将軍を支える13人の領主たち」の意味と聞きます。
そして江戸時代の“藩主”や、藩内各地域の“領主”も、大まかには“Lord”の単語で訳すようなので…こんな事を考えてみました。
――当ブログを始めてから行き当たった課題。
それは「私が語るべき“佐賀”は、どこまでの範囲なのか…」という疑問。普通に考えれば「それは佐賀藩なのでは?」という答えになるのでしょう。
現在の「佐賀県」の江戸時代の姿について。幕府の直轄領(天領)を除けば、三つに大別されるという見方が一般的であると思います。
A.佐賀藩
B.唐津藩
C.対馬藩(田代領)
前編に続いて三択クイズっぽいですが、3つとも正解です。ちなみに佐賀藩内には、さらに三つの“支藩”(小城・蓮池・鹿島)があります。
――まずは「A.佐賀藩」。
佐賀藩の中に、三つの支藩があることはお伝えしましたが、他に各地域にも、ご領主(邑主)が居られます。
この辺りは、まだまだ私は勉強中で知識が浅いのですが、今後のために整理を試みます。私が参照した資料では概ね以下の内容でした。
・支藩(3家)…小城・蓮池・鹿島
・親類(4家)…白石・神代・久保田村田・村田
・親類同格(4家)…武雄・多久・諫早・須古
「親類」の神代家・久保田村田家、「親類同格」の多久・諫早家以外は、上記の名称後に“鍋島家”が付くようです。
また「親類」の“白石”は、みやき町周辺に領地のあった白石鍋島家。「親類同格」の“須古鍋島家”は、現在の白石町にありました。
――あわせて佐賀藩の上級家臣団11家。
では、この領主たちを「“佐賀殿”の11人(The 11 Lords of the Saga)」とでも語るべきか…(?)とか連想したりもします。
ちなみに「親類同格」の4家は、元は龍造寺氏の家柄で「龍造寺四家」という呼び方もするようです。
〔参照(中盤):
幕末期には鍋島直正の藩政改革に助力し、明治初期には戊辰戦争で奮闘するなど、この龍造寺四家はそれぞれに存在感を示しました。
県内にお住まいの方は、身近な地域の“ご領主”さまを意識すると、親近感がアップして良いかも(!)…と思います。
――続いて「B.唐津藩」。
「A.佐賀藩」の話が複雑になり過ぎたので、ここからはシンプルに書きます。
現在のところ“本編”で「唐津藩」の登場人物は、幕末に老中格として難局に挑んだ小笠原長行にのみ焦点を絞っています。
江戸に行くなり、幕府の重職に就いた小笠原長行ですが、その見つめる先には、いつも若き第14代将軍・徳川家茂の姿があるような描き方にしています。
〔参照(後半):
博学で、温厚そうなイメージのある方ですが、幾つかのエピソードから「上様のためなら!」という心意気を感じるところがあります。
――明治初期に、旧幕府方として戦ったためか…?
藩主の名代(代理)として扱われている小笠原長行。唐津藩主に就いていたかについては、議論があるようです。
〔参照(後半):
また、小笠原家は先代藩主の水野家より、唐津の領地を引き継いでから、わずか半世紀ほどで、江戸幕府が終わってしまいました。
江戸期を通じて佐賀藩主だった鍋島家とは事情が異なるので、唐津の皆様から小笠原家は、どの程度の親しみを持たれているか…気になるところです。
現在の佐賀県には、幕府に忠義を尽くそうとした“佐幕派”の唐津藩もあったことは意識しながら、“本編”を書いています。
――そして「C.対馬藩(田代領)」。
当初は「“本編”では描けないか…」と考えましたが、第16話に現在の佐賀県鳥栖市(東部)・基山町にあたる対馬藩・田代領の物語を入れてみました。
1861年(万延二年・文久元年)には、“対馬事件”が起きました。ロシア軍艦ポサドニック号が対馬に上陸し、島内の土地を占拠した事件です。
この事態を受け、第16話に登場した田代領の若者たちも、本藩がある対馬(現・長崎県)へと向かいます。
その頃、佐賀藩士たちも、蒸気船“電流丸”を運用して周辺海域の警戒にあたっていました。
〔参照:
――“佐賀”にいた対馬藩士の視点も取り入れた、第16話「攘夷沸騰」。
当時、佐賀藩は幕府から蒸気船“観光丸”を預かっており、船長は佐野常民。幕府の外国奉行・小栗忠順に同行して、対馬に上陸しています。
こういった佐賀藩のエピソードを、さらに深掘りする書き方もあったのかもしれませんが、あえて田代領の対馬藩士たちだけが登場する回を加えています。
個人的に「対馬藩(田代領)の三部作」と呼称するシリーズです。ちなみに対馬藩主・宗義和は、お名前のみが登場します。
〔参照①:
〔参照②:
〔参照③:
この後、対馬藩士たちは“攘夷派”として長州藩(山口)に接近していきます。
――幕末。三つの“佐賀”の物語。
私は行けなかった2018年の「肥前さが幕末・維新博覧会」。当時の冊子を入手し、佐賀市内だけでなく、唐津・鳥栖にサテライト館があったと知りました。
開国を進める幕府に忠義を尽くそうとする唐津藩。異国の脅威を打ち払おうと攘夷に目覚める対馬藩(田代領)。
そして、日本の近代化こそ問題の解決につながると信じ、早くから独自の路線を進んできた佐賀藩。三者それぞれの立場で繰り広げられた“佐賀”の幕末。
さすがに「佐賀だけで幕末が語れる」とまでは言いませんが、「佐賀の視点で幕末を語る」と新しい物語が見えてくる!のは確かだと思います。
2022年03月09日
「ロード・オブ・サガ ~三つの“佐賀”~(前編)」
こんばんは。
一時、ブログが閲覧できなかっただけで仰々しくも「心新たに“佐賀”を語ろう」と決意した前回。
今回は、何やら洋画劇場っぽいタイトルですが、それほど壮大な話ではなく、佐賀ローカルの話を展開します。
でも、県内在住の皆様ならば、日常にある“冒険”の世界。「もっと、サガを探索しよう…」と前振りをしてみます。
――ふと、気付いた事があります。
それは「私にとって“佐賀”とは何処なのか…」という問題。とくに哲学的な物語が待っているわけではありません。
私は地名として“佐賀”と書く時に、おそらくは3種類の意味で使い分けます。
①佐賀県
②佐賀市
③佐賀藩
…「以上の3つのうち、正解はどれ?」という、三択クイズではありません。
気付いたのは最近ですが、無意識に“三つの佐賀”を記していたようです。

――まずは、「①佐賀県」。
写真は、有名な県境の橋から…おそらく私が単に“佐賀”と書けば「佐賀県」の意味で使っていることが最も多いと思います。
これは九州以外の他地域に住む、佐賀の出身者には、ある程度は共通する感覚なのではないか…と考えるところ。
いざ、関門海峡を渡ってしまうと、市町単位ではなく、都道府県単位で捉えて話をすることが多いと思うのですね。
九州の出身者同士とわかった時、例えば「長崎の出身」と聞けば、「私は佐賀なんですよ~」という流れです。

――続いて、「②佐賀市」。
これが最も、佐賀に住む皆様の感覚に近いかもしれませんね。県内の方が、「今日は“佐賀”に行ってきたとよ。」とか会話する時。
これは、佐賀市内と見て間違いない…あるいは、もっと狭く、佐賀市中心街を指している事もあるかもしれません。
当ブログは、県内に居住していない私が書いているので、このような場面では「佐賀」とは言わず、なるべく“佐賀市内”と表現することを心がけています。
なお、書籍などで「佐賀じゃなかよ、唐津ばい…」という表現を見かけることもあります。これは唐津市であって佐賀市ではないという意味なのか、それとも…
――そして、「③佐賀藩」。
佐賀藩のことをそのまま「佐賀」と語ってしまうのは“歴史好き”に限定されるでしょう。日常会話で使うと誤解が生じそうです。
ただ、当ブログは一応は“歴史系”のブログに分類されると思うので、“佐賀”という言葉がそのまま「佐賀藩」を指す記事も多いです。
「この時、佐賀の存在が…」とか書く時は、ほぼ佐賀藩を表現しています。
現在の佐賀市中心部に近い佐賀城周辺を語る時には、“佐賀城下”という表現を使っていることが多いはず。

――“佐賀”という、地名1つで語っても…
このように多面的な解釈が可能です。とくに「③佐賀藩」については、当ブログが最も熱く語りたいところです。
なお、先ほどの唐津市の「佐賀じゃなかばい」アピールは、歴史的経過が関係するところが大きいかと。
――ご存知のように、佐賀県北西部の唐津市周辺は
佐賀藩ではなく、唐津藩が統治していました。そして、佐賀県東部・基山町と鳥栖市(東部)には、対馬藩の田代領がありました。
以前は「…わかりづらい」とか思っていましたが、最近では「佐賀は、この複雑さが面白い」と感じるようになっています。詳しくは後編で語ろうと思います。

――よく佐賀県の地図を眺めながら…
私の手元には、叔父上から届いた地図があります。佐賀県の道路を示したものですが、ここに「…ロード(Road)・オブ・サガ」との英字表記が含まれます。
こうして加齢に伴う記憶力の低下、仕事で降り注ぐ情報による記憶の容量不足をものともせず、私の佐賀に関する知識は増える一方です。
――後編も「ロード・オブ・サガ」で語る予定ですが、
英単語は、「Road(道路)」から「Lord(領主、所有者)」へと変わります。
洋画「ロード・オブ・ザ・リング」、そして大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語副題(The 13 Lords of the Shogun)は、こちらのロード(Lord)のようですね。
前編は現代を中心に語りましたが、後編は幕末に話を寄せたいと思います。
一時、ブログが閲覧できなかっただけで仰々しくも「心新たに“佐賀”を語ろう」と決意した前回。
今回は、何やら洋画劇場っぽいタイトルですが、それほど壮大な話ではなく、佐賀ローカルの話を展開します。
でも、県内在住の皆様ならば、日常にある“冒険”の世界。「もっと、サガを探索しよう…」と前振りをしてみます。
――ふと、気付いた事があります。
それは「私にとって“佐賀”とは何処なのか…」という問題。とくに哲学的な物語が待っているわけではありません。
私は地名として“佐賀”と書く時に、おそらくは3種類の意味で使い分けます。
①佐賀県
②佐賀市
③佐賀藩
…「以上の3つのうち、正解はどれ?」という、三択クイズではありません。
気付いたのは最近ですが、無意識に“三つの佐賀”を記していたようです。
――まずは、「①佐賀県」。
写真は、有名な県境の橋から…おそらく私が単に“佐賀”と書けば「佐賀県」の意味で使っていることが最も多いと思います。
これは九州以外の他地域に住む、佐賀の出身者には、ある程度は共通する感覚なのではないか…と考えるところ。
いざ、関門海峡を渡ってしまうと、市町単位ではなく、都道府県単位で捉えて話をすることが多いと思うのですね。
九州の出身者同士とわかった時、例えば「長崎の出身」と聞けば、「私は佐賀なんですよ~」という流れです。
――続いて、「②佐賀市」。
これが最も、佐賀に住む皆様の感覚に近いかもしれませんね。県内の方が、「今日は“佐賀”に行ってきたとよ。」とか会話する時。
これは、佐賀市内と見て間違いない…あるいは、もっと狭く、佐賀市中心街を指している事もあるかもしれません。
当ブログは、県内に居住していない私が書いているので、このような場面では「佐賀」とは言わず、なるべく“佐賀市内”と表現することを心がけています。
なお、書籍などで「佐賀じゃなかよ、唐津ばい…」という表現を見かけることもあります。これは唐津市であって佐賀市ではないという意味なのか、それとも…
――そして、「③佐賀藩」。
佐賀藩のことをそのまま「佐賀」と語ってしまうのは“歴史好き”に限定されるでしょう。日常会話で使うと誤解が生じそうです。
ただ、当ブログは一応は“歴史系”のブログに分類されると思うので、“佐賀”という言葉がそのまま「佐賀藩」を指す記事も多いです。
「この時、佐賀の存在が…」とか書く時は、ほぼ佐賀藩を表現しています。
現在の佐賀市中心部に近い佐賀城周辺を語る時には、“佐賀城下”という表現を使っていることが多いはず。
――“佐賀”という、地名1つで語っても…
このように多面的な解釈が可能です。とくに「③佐賀藩」については、当ブログが最も熱く語りたいところです。
なお、先ほどの唐津市の「佐賀じゃなかばい」アピールは、歴史的経過が関係するところが大きいかと。
――ご存知のように、佐賀県北西部の唐津市周辺は
佐賀藩ではなく、唐津藩が統治していました。そして、佐賀県東部・基山町と鳥栖市(東部)には、対馬藩の田代領がありました。
以前は「…わかりづらい」とか思っていましたが、最近では「佐賀は、この複雑さが面白い」と感じるようになっています。詳しくは後編で語ろうと思います。
――よく佐賀県の地図を眺めながら…
私の手元には、叔父上から届いた地図があります。佐賀県の道路を示したものですが、ここに「…ロード(Road)・オブ・サガ」との英字表記が含まれます。
こうして加齢に伴う記憶力の低下、仕事で降り注ぐ情報による記憶の容量不足をものともせず、私の佐賀に関する知識は増える一方です。
――後編も「ロード・オブ・サガ」で語る予定ですが、
英単語は、「Road(道路)」から「Lord(領主、所有者)」へと変わります。
洋画「ロード・オブ・ザ・リング」、そして大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語副題(The 13 Lords of the Shogun)は、こちらのロード(Lord)のようですね。
前編は現代を中心に語りましたが、後編は幕末に話を寄せたいと思います。
2022年03月01日
「風の強い日はお嫌いですか?」
こんばんは。
前回、“みやき町”を語ると思いきや、隣県・福岡の久留米の事ばかり書いてしまいました。
タイトルで何かに気づく方は『ゾンビランドサガ』をご覧になったのでしょう。それはそうと、みやき町について書き足らないので「リベンジ(?)」を試みます。
佐賀の“音風景”の表現も試しますが、擬音語の表現は、人によるところがあります。表記した音は私の感覚です。

――チックタック、チックタック…
随分とデカい“秒針”のような音が響く。JR長崎本線の車窓からは、佐賀平野の景色が移ろう。各駅停車で県内を行く日の記憶である。
駅に停まる時には“ピンポーン、ピンポーン”と少し間延びしたような音がする。ちなみにホームで電車待ちをする時の“プルルルル…”には、毎度驚く。現在、私が住む街に比べて、警報音が相当大きいのだ。
ガラガラッ…とドアは空いた。開いた扉から涼しい空気が流れ込む。
――「もう少し佐賀の風でも、感じておくか…」
私の記憶が確かならば、中原(なかばる)駅にて電車は少し停まっていた。座席を立った私は、やや曇り空にミスト(霧)のような水蒸気を含む風に当たる。
そして数年後に日々、佐賀についての記事を書き続ける事になろうとは思いも寄らなかった。
肺に行き渡るように、目いっぱいの呼吸をしておいた。あとで知ったのだが、みやき町は、“風の名所”でもあるようだ。

――“名所”と知るよしもなかったが、「都会とは、風が違う…」とは感じた。
佐賀県内で暮らす叔父上が撮っていた写真。みやき町の“綾部八幡神社”である。地図で確認すると、その中原駅から見て北側だ。日本最古の気象台と称され、風の神様として有名という。
テレビでも見た記憶があるが、名物は“ぼたもち”と聞く。しかも、鎌倉期に源頼朝の奥州征伐で活躍し、凱旋した肥前国の武将・綾部氏を祝して…と八百年くらい前からの由緒があるそうだ。
なお知ったばかりの情報なので、詳しい解説はできない。とにかく“ぼたもち”は美味しいらしい。
――長崎本線の南側にも名所が。
みやき町のご領主で、文久年間(1861年~)頃には佐賀藩の主要な重役となっていた、鍋島直暠(なおてる)公。
“白石神社”のご祭神の一柱である。実は、私が書く“本編”第17話でも登場いただいている。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕
幕末期の佐賀藩で、勤王派の中心的な組織となった“義祭同盟”の式典にも初期から参加した方だとは幾度か書いた。しかし、セリフのある登場は初めてだったかもしれない。
〔参照(中盤):「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」〕

――佐賀七賢人では最年少の大隈八太郎(重信)。
みやき町のご領主(邑主)で、当時の佐賀藩中枢にいた重臣・鍋島直暠とは身分の差はあれど、世代が近い。主要登場人物では大木喬任(民平)と同年で、文久年間には30歳前後。大隈から見ると、6歳ほど年上。
複数の書籍で、長崎で活動した大隈に様々な許可を与えたと記されていた。“上司”的なポジションであったのだろうか。
この頃の大隈重信の行動は、語学研修や貿易業務や、あるいは鉱山探索のようなことまで、とにかく色々と関わっている。
――大隈が“上役”を利用したのか、“上役”が大隈を走らせたのか…
許可を与えた側の鍋島直暠の人物像まで、私の浅い調べでは届いていない。
これは想像の域を出ないのだが、半ば面白がって、いろいろと突っ走る大隈に“許可”も出していたのではないか。その時の経験が、のちの大隈重信を育てて、明治期の近代化の力になったのではないか。
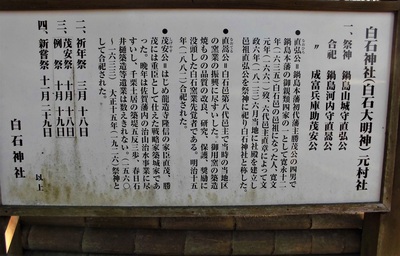
私の空想では、今と変わらぬ“みやき町”の風に吹かれ、地元名産の陶磁器・白石焼の発展に注力する、まだ若いご領主の姿が浮かぶ。
「大隈にでも、販路を拓かせてみるか…」とを、画策しているイメージなのだ。
――風の強い日は嫌いじゃない…
「いや強く吹いては困る日もあるのだが、行事ごとがあると大変なのだが…」という側面はある。
しかし、あの時。みやき町で触れたホームからの風は心地よかった。また風を感じに行きたい。
結構な年代になってから、佐賀県内を走り回ることになった叔父上からの写真で、私には“聖地”が増えていくのである。
前回、“みやき町”を語ると思いきや、隣県・福岡の久留米の事ばかり書いてしまいました。
タイトルで何かに気づく方は『ゾンビランドサガ』をご覧になったのでしょう。それはそうと、みやき町について書き足らないので「リベンジ(?)」を試みます。
佐賀の“音風景”の表現も試しますが、擬音語の表現は、人によるところがあります。表記した音は私の感覚です。
――チックタック、チックタック…
随分とデカい“秒針”のような音が響く。JR長崎本線の車窓からは、佐賀平野の景色が移ろう。各駅停車で県内を行く日の記憶である。
駅に停まる時には“ピンポーン、ピンポーン”と少し間延びしたような音がする。ちなみにホームで電車待ちをする時の“プルルルル…”には、毎度驚く。現在、私が住む街に比べて、警報音が相当大きいのだ。
ガラガラッ…とドアは空いた。開いた扉から涼しい空気が流れ込む。
――「もう少し佐賀の風でも、感じておくか…」
私の記憶が確かならば、中原(なかばる)駅にて電車は少し停まっていた。座席を立った私は、やや曇り空にミスト(霧)のような水蒸気を含む風に当たる。
そして数年後に日々、佐賀についての記事を書き続ける事になろうとは思いも寄らなかった。
肺に行き渡るように、目いっぱいの呼吸をしておいた。あとで知ったのだが、みやき町は、“風の名所”でもあるようだ。
――“名所”と知るよしもなかったが、「都会とは、風が違う…」とは感じた。
佐賀県内で暮らす叔父上が撮っていた写真。みやき町の“綾部八幡神社”である。地図で確認すると、その中原駅から見て北側だ。日本最古の気象台と称され、風の神様として有名という。
テレビでも見た記憶があるが、名物は“ぼたもち”と聞く。しかも、鎌倉期に源頼朝の奥州征伐で活躍し、凱旋した肥前国の武将・綾部氏を祝して…と八百年くらい前からの由緒があるそうだ。
なお知ったばかりの情報なので、詳しい解説はできない。とにかく“ぼたもち”は美味しいらしい。
――長崎本線の南側にも名所が。
みやき町のご領主で、文久年間(1861年~)頃には佐賀藩の主要な重役となっていた、鍋島直暠(なおてる)公。
“白石神社”のご祭神の一柱である。実は、私が書く“本編”第17話でも登場いただいている。
〔参照(後半):
幕末期の佐賀藩で、勤王派の中心的な組織となった“義祭同盟”の式典にも初期から参加した方だとは幾度か書いた。しかし、セリフのある登場は初めてだったかもしれない。
〔参照(中盤):
――佐賀七賢人では最年少の大隈八太郎(重信)。
みやき町のご領主(邑主)で、当時の佐賀藩中枢にいた重臣・鍋島直暠とは身分の差はあれど、世代が近い。主要登場人物では大木喬任(民平)と同年で、文久年間には30歳前後。大隈から見ると、6歳ほど年上。
複数の書籍で、長崎で活動した大隈に様々な許可を与えたと記されていた。“上司”的なポジションであったのだろうか。
この頃の大隈重信の行動は、語学研修や貿易業務や、あるいは鉱山探索のようなことまで、とにかく色々と関わっている。
――大隈が“上役”を利用したのか、“上役”が大隈を走らせたのか…
許可を与えた側の鍋島直暠の人物像まで、私の浅い調べでは届いていない。
これは想像の域を出ないのだが、半ば面白がって、いろいろと突っ走る大隈に“許可”も出していたのではないか。その時の経験が、のちの大隈重信を育てて、明治期の近代化の力になったのではないか。
私の空想では、今と変わらぬ“みやき町”の風に吹かれ、地元名産の陶磁器・白石焼の発展に注力する、まだ若いご領主の姿が浮かぶ。
「大隈にでも、販路を拓かせてみるか…」とを、画策しているイメージなのだ。
――風の強い日は嫌いじゃない…
「いや強く吹いては困る日もあるのだが、行事ごとがあると大変なのだが…」という側面はある。
しかし、あの時。みやき町で触れたホームからの風は心地よかった。また風を感じに行きたい。
結構な年代になってから、佐賀県内を走り回ることになった叔父上からの写真で、私には“聖地”が増えていくのである。
2022年02月25日
「みやき町から東に向かって先を読む。」
こんばんは。
第17話途中で投稿するつもりが、掲載を延期していた「振り返りシリーズ」3本のうちの後編。
〔参照(前編):「伊万里から西に向かって振り返る。」〕
〔参照(中編):「佐賀の空を起点として振り返る。」〕
佐賀県・みやき町から“振り返る”…話を入れる予定でしたが、どちらかと言えば、今後の展開を“先読み”する内容になりました。
記事にすべき原稿のストックも無い、今こそ“書きどき”です。これから、どう話を進めるか…?今回は、私の試行錯誤も見えるかと思います。

――「いざ、みやき町。」
数々の大舞台で見せた「一本背負い」の清冽な感動とともに、今後も語り継がれるであろう、伝説の柔道家・古賀稔彦さんを育んだのが、現在のみやき町。
古賀選手が、少年期に足腰を鍛えたという“千栗(ちりく)八幡宮”の石段。栄光へと続く道だった、この階段を昇りきった者だけに見える景色があります。
…今回語りたいのは、福岡県久留米市方面へと広がる風景です。
“みやき町”の視点から見る話なので、あまりみやき町自体については充分に語れませんが、九州北部に続くスケールの大きい(!)展開を試みます。
――地図を参照しますと、意外と久留米の市街地が近い。
2年以上も佐賀に帰れていない私。現地で千栗八幡宮からの写真を撮影できるはずもありません。ここで県内在住の叔父上を頼るのは、いつもの通りです。
気になっていた素材の調達に感謝するとともに「叔父上、この石段を昇るのは大丈夫だったのか…!?」と心配になるところも。
しかし、新型コロナ禍における都市生活の中で自粛を重ね、身体能力が低下の一途をたどる私と違って、叔父上は佐賀で日々に自然と親しんでいます。
電話した感じ、叔父上も平気そうなので、ひとまず「心配、ご無用!」と思っておくことにします。

――「いや、ここは久留米に向かった話に集中せねば。」
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で、久留米を語れば初代・“からくり儀右衛門”こと田中久重の名を語ることになるでしょう。
最近は“本編”での登場機会が少ないのですが、久留米のご出身の方です。佐賀の大河ドラマで描く時には、福岡県出身の俳優さんに…と思うところ。
技術者としての腕を活かし、京都で活躍。“蘭学”にも親しみ、そこで佐賀藩の佐野常民(栄寿)と出会ったそうです。
〔参照(後半):第7話「尊王義祭」⑨〕
――幕末期には、福岡の勤王志士に強い影響を与える人物が。
第17話で福岡の志士として久留米藩の真木和泉(保臣)の名も挙げました。みやき町との県境もほど近い、久留米“水天宮”の神官だったようです。
江藤新平が、佐賀を発つまでを書いた第17話の最終記事。現・福岡県にあたる地域の志士たちの存在に触れています。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)〕
文久元年(1861年)頃。現在の福岡県の北部(筑前)・南部(筑後)の志士たちは薩摩藩(鹿児島)とよく関わっています。
ところが文久二年四月。志士たちが活動する京都・伏見を舞台に、薩摩藩の凄惨な同士討ちとなる事件“寺田屋騒動”が起きました。
〔参照(中盤):「新キャストを考える④」(“絶望”を越えて行け)〕

――この事件が“福岡の志士たち”に暗い影を落とすことに。
江藤が佐賀を出たのは“騒動”の2か月ほど後。第18話で、この事件の余波をどう表現するかは検討中です。
事件の少し前には“義祭同盟”を率いる枝吉神陽との連携を求め、真木和泉は息子・主馬を佐賀に派遣していたようです。
本編で幾度か登場した福岡藩・平野国臣、お名前だけの紹介になった秋月藩・海賀宮門も、同時期に佐賀に来訪しています。
そして福岡の志士たちの意見に理解は示すものの、佐賀の志士たちの師匠・枝吉神陽は慎重でした。なぜか、動こうとしないのです。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕
――「もしや、神陽先生はこの展開を懸念した…?」と思う話が続きます。
先ほどの京都・伏見での事件により、連携した薩摩藩の“尊王攘夷”急進派は粛清され、巻き込まれた福岡の志士たちは、壊滅的な打撃を受けました。
秋月藩の海賀宮門という方の名は最近知りました。20代後半だったそうです。最後が悲劇的過ぎて志半ばに歴史の表舞台から去る無念を思わせます。
事件後、久留米藩の真木和泉は次第に長州藩(山口)に接近しますが、ここからも壮絶でした…
――あまり語られない印象の“福岡の幕末”。
お気付きの方も多いと思いますが、先ほどから薩摩(鹿児島)の存在が繰り返し出ており、“尊王攘夷”の活動には長州(山口)との関わりが見えます。
私が“本編”を書く速度から薩長が同盟を組むのは、相当先になりそうですが、「薩長同盟”の萌芽は“福岡”にあった」旨の見解もあり、考えさせられます。

――政局から出遅れた佐賀藩が、なぜ“薩長土肥”の一角となり得たか。
これも先の展開になりますが、大木喬任(民平)・江藤新平ら、佐賀の志士は久留米にも出向いています。
今までも佐賀藩における“近代化”の源泉が、「西洋(技術)への窓口」だった西の隣県・長崎にあったことは、よく語っています。
こうして技術的には“最先端”だったものの、明治維新に向けた“政治闘争”では目立った動きの見えづらい佐賀藩。
それを補う「国内(政局)への窓口」が、東の隣県・福岡での情報収集だったとすると…
――「佐賀が、佐賀であるために…(!)」。
やはり東に福岡・西に長崎が存在することが、必然だったのかもしれません。
佐賀の皆様には、福岡・長崎のいずれか、あるいは両県にご親戚が居られるという方々も多いでしょう。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば、九州北部を舞台として展開する、新しい幕末史の見え方も開かれるはず。
福岡県・長崎県の皆様にも共感できるところがあって、親戚の集まりで話題となる…ような「佐賀の物語」が作れればと思っています。
第17話途中で投稿するつもりが、掲載を延期していた「振り返りシリーズ」3本のうちの後編。
〔参照(前編):
〔参照(中編):
佐賀県・みやき町から“振り返る”…話を入れる予定でしたが、どちらかと言えば、今後の展開を“先読み”する内容になりました。
記事にすべき原稿のストックも無い、今こそ“書きどき”です。これから、どう話を進めるか…?今回は、私の試行錯誤も見えるかと思います。
――「いざ、みやき町。」
数々の大舞台で見せた「一本背負い」の清冽な感動とともに、今後も語り継がれるであろう、伝説の柔道家・古賀稔彦さんを育んだのが、現在のみやき町。
古賀選手が、少年期に足腰を鍛えたという“千栗(ちりく)八幡宮”の石段。栄光へと続く道だった、この階段を昇りきった者だけに見える景色があります。
…今回語りたいのは、福岡県久留米市方面へと広がる風景です。
“みやき町”の視点から見る話なので、あまりみやき町自体については充分に語れませんが、九州北部に続くスケールの大きい(!)展開を試みます。
――地図を参照しますと、意外と久留米の市街地が近い。
2年以上も佐賀に帰れていない私。現地で千栗八幡宮からの写真を撮影できるはずもありません。ここで県内在住の叔父上を頼るのは、いつもの通りです。
気になっていた素材の調達に感謝するとともに「叔父上、この石段を昇るのは大丈夫だったのか…!?」と心配になるところも。
しかし、新型コロナ禍における都市生活の中で自粛を重ね、身体能力が低下の一途をたどる私と違って、叔父上は佐賀で日々に自然と親しんでいます。
電話した感じ、叔父上も平気そうなので、ひとまず「心配、ご無用!」と思っておくことにします。
――「いや、ここは久留米に向かった話に集中せねば。」
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で、久留米を語れば初代・“からくり儀右衛門”こと田中久重の名を語ることになるでしょう。
最近は“本編”での登場機会が少ないのですが、久留米のご出身の方です。佐賀の大河ドラマで描く時には、福岡県出身の俳優さんに…と思うところ。
技術者としての腕を活かし、京都で活躍。“蘭学”にも親しみ、そこで佐賀藩の佐野常民(栄寿)と出会ったそうです。
〔参照(後半):
――幕末期には、福岡の勤王志士に強い影響を与える人物が。
第17話で福岡の志士として久留米藩の真木和泉(保臣)の名も挙げました。みやき町との県境もほど近い、久留米“水天宮”の神官だったようです。
江藤新平が、佐賀を発つまでを書いた第17話の最終記事。現・福岡県にあたる地域の志士たちの存在に触れています。
〔参照(中盤):
文久元年(1861年)頃。現在の福岡県の北部(筑前)・南部(筑後)の志士たちは薩摩藩(鹿児島)とよく関わっています。
ところが文久二年四月。志士たちが活動する京都・伏見を舞台に、薩摩藩の凄惨な同士討ちとなる事件“寺田屋騒動”が起きました。
〔参照(中盤):

――この事件が“福岡の志士たち”に暗い影を落とすことに。
江藤が佐賀を出たのは“騒動”の2か月ほど後。第18話で、この事件の余波をどう表現するかは検討中です。
事件の少し前には“義祭同盟”を率いる枝吉神陽との連携を求め、真木和泉は息子・主馬を佐賀に派遣していたようです。
本編で幾度か登場した福岡藩・平野国臣、お名前だけの紹介になった秋月藩・海賀宮門も、同時期に佐賀に来訪しています。
そして福岡の志士たちの意見に理解は示すものの、佐賀の志士たちの師匠・枝吉神陽は慎重でした。なぜか、動こうとしないのです。
〔参照(後半):
――「もしや、神陽先生はこの展開を懸念した…?」と思う話が続きます。
先ほどの京都・伏見での事件により、連携した薩摩藩の“尊王攘夷”急進派は粛清され、巻き込まれた福岡の志士たちは、壊滅的な打撃を受けました。
秋月藩の海賀宮門という方の名は最近知りました。20代後半だったそうです。最後が悲劇的過ぎて志半ばに歴史の表舞台から去る無念を思わせます。
事件後、久留米藩の真木和泉は次第に長州藩(山口)に接近しますが、ここからも壮絶でした…
――あまり語られない印象の“福岡の幕末”。
お気付きの方も多いと思いますが、先ほどから薩摩(鹿児島)の存在が繰り返し出ており、“尊王攘夷”の活動には長州(山口)との関わりが見えます。
私が“本編”を書く速度から薩長が同盟を組むのは、相当先になりそうですが、「薩長同盟”の萌芽は“福岡”にあった」旨の見解もあり、考えさせられます。
――政局から出遅れた佐賀藩が、なぜ“薩長土肥”の一角となり得たか。
これも先の展開になりますが、大木喬任(民平)・江藤新平ら、佐賀の志士は久留米にも出向いています。
今までも佐賀藩における“近代化”の源泉が、「西洋(技術)への窓口」だった西の隣県・長崎にあったことは、よく語っています。
こうして技術的には“最先端”だったものの、明治維新に向けた“政治闘争”では目立った動きの見えづらい佐賀藩。
それを補う「国内(政局)への窓口」が、東の隣県・福岡での情報収集だったとすると…
――「佐賀が、佐賀であるために…(!)」。
やはり東に福岡・西に長崎が存在することが、必然だったのかもしれません。
佐賀の皆様には、福岡・長崎のいずれか、あるいは両県にご親戚が居られるという方々も多いでしょう。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば、九州北部を舞台として展開する、新しい幕末史の見え方も開かれるはず。
福岡県・長崎県の皆様にも共感できるところがあって、親戚の集まりで話題となる…ような「佐賀の物語」が作れればと思っています。
2022年02月20日
「“聖地”へとつながる道」
こんにちは。
前回で、“本編”第17話「佐賀脱藩」の投稿を完了しました。お読みいただいた皆様、いかがだったでしょうか。
いまの私に書ける上限を目指したのが第17話でした。第18話「京都見聞」に向け、準備期間を取りたいので、しばらく“本編”以外の記事を投稿予定です。
このところ仕事の方にも色々とあって、想いを叩き込むように書いていた感覚も強くありました。
――そんな私への“応援歌”となっているのは…
現在放送中の2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』。平安末期~鎌倉初期の“大河”なので、当ブログの主題とは、少し時代設定が離れています。
佐賀との関わりも、江藤新平のルーツと言われる千葉氏の代表的な人物が登場する…ぐらいでしょうか。
今週末には、千葉常胤〔演:岡本信人〕の出番もありそうで、注目しています。
〔参照(終盤):「紅白から“源平”を考える。」〕

※写真は「佐賀駅前の10人(“佐賀の八賢人”と古賀穀堂先生、そして武雄領主・鍋島茂義公)」です。“鎌倉殿”っぽく見せようとしましたが、難しい…
――「でも、時代が“幕末”から外れ、興味は薄れたのでは?」
…と思う方もいるかもしれませんが、視聴者として次週を楽しみに見る気持ちは、昨年以上のものがあります。
主人公・北条義時〔演:小栗旬〕は、いろいろ我慢をしながら、調整に走り回るタイプの印象。個人的にキャラクター設定で共感できる度合いは高いのです。
それと北条時政〔演:坂東彌十郎〕が良い意味で胡散(うさん)臭く、策士なのかと思えば、敵側から煽られると、すぐ挑発に乗って突撃したり…面白いです。
時おり、源頼朝〔演:大泉洋〕を見捨てようとするのに、妙な説得力を感じます。
――現代の生活の中でも、日々、生じていく“小競り合い”。
『鎌倉殿の13人』の第1回のタイトルは「大いなる小競り合い」でした。様々な方の人生に響くような、上手い言い回しだな…と感じています。
私を顧みると、例年より低く感じる気温、めっきり抜けない疲労感、新型コロナへの警戒も要る通勤時間、たどり着く先は仕事場。
毎日のように“小競り合い”が繰り返される…暮らしとも言えるでしょう。最近、朝の通勤時に決まって、私の心に流れてくるメロディーがありました。
それは『鎌倉殿の13人』メインテーマの楽曲。今の私には「思い起こすだけで、わずかでも気力を上げてくれる」貴重な音楽なのです。
――今年の大河ドラマの“オープニング”。
イメージに残るのは、まるで西洋の叙事詩のような、登場人物が“塑像”として次々現れる感じのスタイリッシュな映像。
幕末期に比べ、現代から遙かに遠い時代。平安・鎌倉期の“大河”のテーマを作曲したのは、エバン・コールさん。
私は初めてお聞きしたお名前で、海外の方なのですね。異文化からの視点も取り込んで、現代との違和感を際立たせる狙いなのでしょうか。
それでいて勇壮な響きが見事に“和”を表現。アニメやゲームの作曲で活躍されている方と知って納得しました。
――そんなオープニング映像で、好きな場面が幾つか。
1つは「いざ」という文字が背景に浮かぶ演出。「いざ、鎌倉」が題材の演出と思いますが、人には困難に立ち向かう瞬間がある…という感覚で見ています。
もう1つは、鎌倉“鶴岡八幡宮”の大鳥居前と思われる道に、主人公が臨む姿のようなシーン。人には、各々に“聖地”がある…と見えてきます。
以上の解釈は、個人的感想です。一言でまとめると「オープニングから、勇気づけられる大河ドラマ」だと思っています。

――平安・鎌倉期の歴史に、あまり詳しくないので、
先の展開も大雑把にしかわかっておらず、いつも以上にワクワクします。
そして、私にも「いざ、聖地へ」と臨みたい場所があります。佐賀市民の方々には日常風景でしょうが、佐賀の“シンボルロード”である「中央大通り」です。
…そんな「佐賀への道」も、私からは遠い道のりとなって2年以上を隔てます。
今回はオープニングに特化したお話でした。もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」ならば、どんな映像・音楽で表現されるか…そんな事を考えるのも楽しみです。
「大河よ、共に…」という気持ちで、今年の『鎌倉殿の13人』も追っていきたいと思います。
前回で、“本編”第17話「佐賀脱藩」の投稿を完了しました。お読みいただいた皆様、いかがだったでしょうか。
いまの私に書ける上限を目指したのが第17話でした。第18話「京都見聞」に向け、準備期間を取りたいので、しばらく“本編”以外の記事を投稿予定です。
このところ仕事の方にも色々とあって、想いを叩き込むように書いていた感覚も強くありました。
――そんな私への“応援歌”となっているのは…
現在放送中の2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』。平安末期~鎌倉初期の“大河”なので、当ブログの主題とは、少し時代設定が離れています。
佐賀との関わりも、江藤新平のルーツと言われる千葉氏の代表的な人物が登場する…ぐらいでしょうか。
今週末には、千葉常胤〔演:岡本信人〕の出番もありそうで、注目しています。
〔参照(終盤):
※写真は「佐賀駅前の10人(“佐賀の八賢人”と古賀穀堂先生、そして武雄領主・鍋島茂義公)」です。“鎌倉殿”っぽく見せようとしましたが、難しい…
――「でも、時代が“幕末”から外れ、興味は薄れたのでは?」
…と思う方もいるかもしれませんが、視聴者として次週を楽しみに見る気持ちは、昨年以上のものがあります。
主人公・北条義時〔演:小栗旬〕は、いろいろ我慢をしながら、調整に走り回るタイプの印象。個人的にキャラクター設定で共感できる度合いは高いのです。
それと北条時政〔演:坂東彌十郎〕が良い意味で胡散(うさん)臭く、策士なのかと思えば、敵側から煽られると、すぐ挑発に乗って突撃したり…面白いです。
時おり、源頼朝〔演:大泉洋〕を見捨てようとするのに、妙な説得力を感じます。
――現代の生活の中でも、日々、生じていく“小競り合い”。
『鎌倉殿の13人』の第1回のタイトルは「大いなる小競り合い」でした。様々な方の人生に響くような、上手い言い回しだな…と感じています。
私を顧みると、例年より低く感じる気温、めっきり抜けない疲労感、新型コロナへの警戒も要る通勤時間、たどり着く先は仕事場。
毎日のように“小競り合い”が繰り返される…暮らしとも言えるでしょう。最近、朝の通勤時に決まって、私の心に流れてくるメロディーがありました。
それは『鎌倉殿の13人』メインテーマの楽曲。今の私には「思い起こすだけで、わずかでも気力を上げてくれる」貴重な音楽なのです。
――今年の大河ドラマの“オープニング”。
イメージに残るのは、まるで西洋の叙事詩のような、登場人物が“塑像”として次々現れる感じのスタイリッシュな映像。
幕末期に比べ、現代から遙かに遠い時代。平安・鎌倉期の“大河”のテーマを作曲したのは、エバン・コールさん。
私は初めてお聞きしたお名前で、海外の方なのですね。異文化からの視点も取り込んで、現代との違和感を際立たせる狙いなのでしょうか。
それでいて勇壮な響きが見事に“和”を表現。アニメやゲームの作曲で活躍されている方と知って納得しました。
――そんなオープニング映像で、好きな場面が幾つか。
1つは「いざ」という文字が背景に浮かぶ演出。「いざ、鎌倉」が題材の演出と思いますが、人には困難に立ち向かう瞬間がある…という感覚で見ています。
もう1つは、鎌倉“鶴岡八幡宮”の大鳥居前と思われる道に、主人公が臨む姿のようなシーン。人には、各々に“聖地”がある…と見えてきます。
以上の解釈は、個人的感想です。一言でまとめると「オープニングから、勇気づけられる大河ドラマ」だと思っています。
――平安・鎌倉期の歴史に、あまり詳しくないので、
先の展開も大雑把にしかわかっておらず、いつも以上にワクワクします。
そして、私にも「いざ、聖地へ」と臨みたい場所があります。佐賀市民の方々には日常風景でしょうが、佐賀の“シンボルロード”である「中央大通り」です。
…そんな「佐賀への道」も、私からは遠い道のりとなって2年以上を隔てます。
今回はオープニングに特化したお話でした。もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」ならば、どんな映像・音楽で表現されるか…そんな事を考えるのも楽しみです。
「大河よ、共に…」という気持ちで、今年の『鎌倉殿の13人』も追っていきたいと思います。
2022年01月22日
「佐賀の空を起点として振り返る。」
こんばんは。
遠方に住むため、私はニュースで状況を知りますが、佐賀でも新型コロナの感染者数が増えたり、地震での揺れがあったり…と心配事の多いところです。
最近、下を向きそうになるような話題も多いですが、『さがファンブログ』には、よく空の写真を載せておられる方々もいます。
「時に、空を見上げることも大事。」と教えられた私は、青天を仰ぎ見ることに。ただ、そのたび「ポキポキっ…」と音をたてる関節。加齢と疲労は感じます。
――さて、振り返りシリーズ第2回・中編です。
特に『佐賀空港』がキーワードというわけではなく、最近の“本編”では江戸(東京)との手紙のやり取りで展開する話が多いため、こういう表現にしました。
気持ちだけでも「佐賀の中心から空を見上げて、東京方面に向かう」ぐらいのイメージで語ります。
〔参照(直近の本編記事):第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)〕

――本シリーズは「制作裏話」でもあります。
私が「幕末期の佐賀の歴史」を顧みるようになって、まだ3年ほど。それゆえ、調べながら書いており、未知だった“史実”が次々わかってしまうことが。
書き手としては、「話を作り終えた後で、この展開になると辛い…」というのが、素直な感想です。
――“創作”を標榜するとはいえ、
「もし、佐賀の大河ドラマが実現すれば、こんな書き方もありうる!」という域を目指したい気持ちだけはあるので葛藤しながら、話の”着地点”を探ります。
実際の「大河ドラマ」では、史実を監修する先生が仕上がった原稿をチェックするのか、会議でシナリオの方向を決めてから書くのか…興味深いところです。
――ケース①「長崎街道の旅人」
佐賀城の南堀端をゆく、大木喬任(民平)と江藤新平。師匠・枝吉神陽宅の門前に見えるのは、会話している二人のさむらいの姿。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑧(福岡から来た“さぶらい”)〕
一人は佐賀藩士・古賀一平なので問題なし。しかし、うち一人は福岡脱藩の志士・平野国臣。ここが問題なのです。
ここで2年ちょっと前に佐賀市内、白山通りのアーケードの下で、撮影した写真をご覧ください。

――“長崎街道”の看板があります。
よく見ると江戸時代に「街道を行く旅人たちは、城内はもちろん武家地への立入りは原則禁止。街道以外の通行も制限」されたと説明が記載されています。
「こいは、いかんばいっ!」とばかりに、筋書きがマズい方向に行っている…と気付いた私。ここから軌道修正を試みます。
平野国臣は、隣県である福岡(藩)を代表する勤王の志士。私の書いた文章では“さがんもん”じゃない人が城下の奥深くに来ている展開になっています。
――“史実”と思われる情報から。
文久元年(1861年)秋、佐賀の義祭同盟のメンバーと福岡脱藩の平野国臣が出会って、意見交換をしたと幾つかの資料で見かけました。
行動力のある勤王の志士・平野国臣ですが、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』頃の時代(平安末期・鎌倉初期)のような装束を好んで着たと聞きます。
…その辺りからの発想で「福岡の“さぶらい”」という表現をしてみました。
地元・福岡に居る時ならともかく、佐賀に来た時まで“古風”な格好をしたかは不明です。問題は出入り禁止のはずの佐賀城下に“旅人”がいる状況。
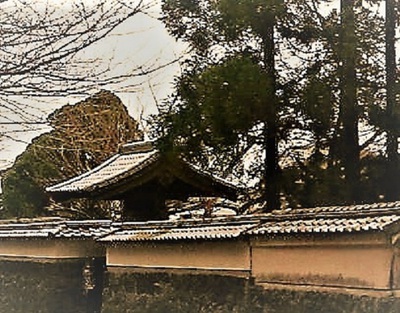
――江藤らの義祭同盟の仲間・古賀一平。
ひとしきり勤王の話に熱中した古賀ですが「ここに“お客人”が居ては危うい」と気づき、旅人・平野国臣を“長崎街道”沿いに戻して一件落着(?)。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕
大木と江藤、そして中野方蔵の三人を軸に描くことが多かったので、どうしても他の仲間が“常識人”としての役回りになりがちです。
古賀一平は、明治初期に東京(埼玉、神奈川)の一部にあった“品川県”を任された人物…ですが、古賀の担当地域が、そのまま“県”になったようです。
――ケース②「江藤新平の家族」
佐賀藩の下級役人として、のちの“働き者”の片鱗を見せる、江藤新平。
妻・千代子と結婚し、長男・熊太郎も誕生。武家屋敷街の一角に居を構える。そんな時期だったようです。
当時の江藤家に近い姿を想像し、穏やかな日々も描いてみました。但し「いずれ国に大事がある時には、立たねば」と気概を秘めた一家と表現しています。
〔参照(後半:第17話「佐賀脱藩」⑫(陽だまりの下で)〕
――この場面にも登場する、江藤新平の妻について。
私はある“創作物”での情報から、江藤のいとこだった千代子の年齢を設定し、筋書きを作成していました。
最近、ある資料を参照したところ当初の想定より、江藤千代子の年齢はかなり若かったようです。
しかし「溢れる才能には危ういところもある」のが江藤の人物像だとすれば、「奥様は年齢によらず“しっかり者”にならざるを得ないかな…」とも思います。ここは、とくに軌道修正せずに進めようと思います。

――江藤らに届く、親友・中野方蔵からの手紙。
佐賀の義祭同盟のメンバーは、大都会・江戸(東京)に出てから他藩の志士たちと活発に交流する中野の動きを知ります。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)〕
下級武士としては、江藤はおそらく順調に活躍している方です。佐賀藩からも「英語を学ばせたい」と期待されている印象。
暮らし向きも良くなっていますが「このままで良いのか…」との焦りは強くあったのではないかと想像します。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)〕
江藤新平の時代と前提は異なるものの、現代の若者にも「地元で暮らすか、都会に出るか」は大きい選択なのかもしれません。
――今後も思い切って“本編”を書きたいので、
今回はあえて、制作上の諸問題があることをご紹介しました。いまは、「誤りを恐れずに進む」つもりで書き続けたいと思います。
こうして「史実と創作の狭間で」もがき続けることで、きっと佐賀藩士に魅力的な人物が、数多くいたことが見えてくるはず。
…私は“佐賀の先輩たち”の、歴史ドラマにおける活躍の幅が広がることを切に願っています。
次回は「みやきから振り返る」企画の予定でしたが、一旦“本編”を再開します。みやき町のお話は「ここぞ」という時に繰り出すので、ご了承ください。
遠方に住むため、私はニュースで状況を知りますが、佐賀でも新型コロナの感染者数が増えたり、地震での揺れがあったり…と心配事の多いところです。
最近、下を向きそうになるような話題も多いですが、『さがファンブログ』には、よく空の写真を載せておられる方々もいます。
「時に、空を見上げることも大事。」と教えられた私は、青天を仰ぎ見ることに。ただ、そのたび「ポキポキっ…」と音をたてる関節。加齢と疲労は感じます。
――さて、振り返りシリーズ第2回・中編です。
特に『佐賀空港』がキーワードというわけではなく、最近の“本編”では江戸(東京)との手紙のやり取りで展開する話が多いため、こういう表現にしました。
気持ちだけでも「佐賀の中心から空を見上げて、東京方面に向かう」ぐらいのイメージで語ります。
〔参照(直近の本編記事):
――本シリーズは「制作裏話」でもあります。
私が「幕末期の佐賀の歴史」を顧みるようになって、まだ3年ほど。それゆえ、調べながら書いており、未知だった“史実”が次々わかってしまうことが。
書き手としては、「話を作り終えた後で、この展開になると辛い…」というのが、素直な感想です。
――“創作”を標榜するとはいえ、
「もし、佐賀の大河ドラマが実現すれば、こんな書き方もありうる!」という域を目指したい気持ちだけはあるので葛藤しながら、話の”着地点”を探ります。
実際の「大河ドラマ」では、史実を監修する先生が仕上がった原稿をチェックするのか、会議でシナリオの方向を決めてから書くのか…興味深いところです。
――ケース①「長崎街道の旅人」
佐賀城の南堀端をゆく、大木喬任(民平)と江藤新平。師匠・枝吉神陽宅の門前に見えるのは、会話している二人のさむらいの姿。
〔参照(中盤):
一人は佐賀藩士・古賀一平なので問題なし。しかし、うち一人は福岡脱藩の志士・平野国臣。ここが問題なのです。
ここで2年ちょっと前に佐賀市内、白山通りのアーケードの下で、撮影した写真をご覧ください。
――“長崎街道”の看板があります。
よく見ると江戸時代に「街道を行く旅人たちは、城内はもちろん武家地への立入りは原則禁止。街道以外の通行も制限」されたと説明が記載されています。
「こいは、いかんばいっ!」とばかりに、筋書きがマズい方向に行っている…と気付いた私。ここから軌道修正を試みます。
平野国臣は、隣県である福岡(藩)を代表する勤王の志士。私の書いた文章では“さがんもん”じゃない人が城下の奥深くに来ている展開になっています。
――“史実”と思われる情報から。
文久元年(1861年)秋、佐賀の義祭同盟のメンバーと福岡脱藩の平野国臣が出会って、意見交換をしたと幾つかの資料で見かけました。
行動力のある勤王の志士・平野国臣ですが、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』頃の時代(平安末期・鎌倉初期)のような装束を好んで着たと聞きます。
…その辺りからの発想で「福岡の“さぶらい”」という表現をしてみました。
地元・福岡に居る時ならともかく、佐賀に来た時まで“古風”な格好をしたかは不明です。問題は出入り禁止のはずの佐賀城下に“旅人”がいる状況。
――江藤らの義祭同盟の仲間・古賀一平。
ひとしきり勤王の話に熱中した古賀ですが「ここに“お客人”が居ては危うい」と気づき、旅人・平野国臣を“長崎街道”沿いに戻して一件落着(?)。
〔参照(中盤):
大木と江藤、そして中野方蔵の三人を軸に描くことが多かったので、どうしても他の仲間が“常識人”としての役回りになりがちです。
古賀一平は、明治初期に東京(埼玉、神奈川)の一部にあった“品川県”を任された人物…ですが、古賀の担当地域が、そのまま“県”になったようです。
――ケース②「江藤新平の家族」
佐賀藩の下級役人として、のちの“働き者”の片鱗を見せる、江藤新平。
妻・千代子と結婚し、長男・熊太郎も誕生。武家屋敷街の一角に居を構える。そんな時期だったようです。
当時の江藤家に近い姿を想像し、穏やかな日々も描いてみました。但し「いずれ国に大事がある時には、立たねば」と気概を秘めた一家と表現しています。
〔参照(後半:
――この場面にも登場する、江藤新平の妻について。
私はある“創作物”での情報から、江藤のいとこだった千代子の年齢を設定し、筋書きを作成していました。
最近、ある資料を参照したところ当初の想定より、江藤千代子の年齢はかなり若かったようです。
しかし「溢れる才能には危ういところもある」のが江藤の人物像だとすれば、「奥様は年齢によらず“しっかり者”にならざるを得ないかな…」とも思います。ここは、とくに軌道修正せずに進めようと思います。
――江藤らに届く、親友・中野方蔵からの手紙。
佐賀の義祭同盟のメンバーは、大都会・江戸(東京)に出てから他藩の志士たちと活発に交流する中野の動きを知ります。
〔参照(後半):
下級武士としては、江藤はおそらく順調に活躍している方です。佐賀藩からも「英語を学ばせたい」と期待されている印象。
暮らし向きも良くなっていますが「このままで良いのか…」との焦りは強くあったのではないかと想像します。
〔参照(後半):
江藤新平の時代と前提は異なるものの、現代の若者にも「地元で暮らすか、都会に出るか」は大きい選択なのかもしれません。
――今後も思い切って“本編”を書きたいので、
今回はあえて、制作上の諸問題があることをご紹介しました。いまは、「誤りを恐れずに進む」つもりで書き続けたいと思います。
こうして「史実と創作の狭間で」もがき続けることで、きっと佐賀藩士に魅力的な人物が、数多くいたことが見えてくるはず。
…私は“佐賀の先輩たち”の、歴史ドラマにおける活躍の幅が広がることを切に願っています。
次回は「みやきから振り返る」企画の予定でしたが、一旦“本編”を再開します。みやき町のお話は「ここぞ」という時に繰り出すので、ご了承ください。
2022年01月18日
「伊万里から西に向かって振り返る。」
こんばんは。
前回、ご案内した“本編”振り返りシリーズ第1回目です。
全3回のうち、本日が“前編”ということに。キーワードは『松浦鉄道』です。例によって、鉄道そのものの写真はございませんが、語ることはできます。
――登場する駅名は東から西へ。「伊万里」→「楠久」→「久原」の3か所。
なお、私は10年ほど前に松浦鉄道沿線を回る計画を立てましたが、その時は諸事情により断念しました。
それゆえ地元に住まう方から見れば、おかしな記述もあるかもしれませんが、思い切って書きます。構成の都合上、「伊万里」「久原」「楠久」の順番で…
――まず、1本目・「伊万里」について。
“本編”では、佐賀藩の産業政策を支える“柱”の1つ、陶磁器産業を語るため、賑わう積出港として舞台になることが多いです。
なお、伊万里の商人について、深く描くことは出来ていませんが、場面設定で用いることは時折あります。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑰(積出港の昼下がり)〕

――次に、2本目・「久原」について。
“本編”には、創作要素の強い話が含まれることがあります。例えば、第16話「攘夷沸騰」から、なぜか度々、伊万里湾を望む高台に現れる、江藤新平。
〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」⑩(英国船の行方)〕
これは、江藤が藩の貿易部門・代品方に移る前振り。また第18話「京都見聞」の展開の都合で考えた設定です。
史実寄りの情報では、江藤の剣術道場の先輩で、小城(支藩)の富岡敬明が、伊万里にいろいろと関わりがありそうです。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」②(小城の秘剣)〕
――佐賀の支藩・小城藩の飛び地だったという「久原」。
“本編”では少し先の時期になりますが、1864年頃に小城藩内の抗争で責任を取る形になった富岡は、囚われの身として当地にいたようです。
富岡敬明に恩のあった、江藤は「久原」まで足を運び、剣舞を踊って励ました…らしいのです。
「江藤には伊万里の土地勘があったのでは…」との推測はこの辺りからです。
明治に入ってから、江藤らの助力で赦免された富岡。新政府の地方官僚として“伊万里県”から仕事を始め、熊本県や山梨県での活躍が伝わります。
〔参照:「励まし方も、人による(第16話・場面解説①)」〕

――そして、3本目・「楠久」について。
佐賀藩海軍の拠点として描くことが多い、伊万里。鍋島直正の“相棒”のように描くこともある、オランダ生まれの蒸気船・電流丸。
〔参照(前半):第15話「江戸動乱」⑫(その船、電流丸)〕
なお時々、殿様に呼びかけられると、電流丸が「ボッ…!」とか応えるのは、私の趣味による脚色です。
文久元年(1861年)。対馬に上陸したロシア船への警戒のため、佐賀藩海軍は電流丸を派遣します。その寄港地として、記述を見つけたのが「楠久」です。
――幕末期。蒸気船が行き交った、伊万里の海。
当時の対馬藩主・宗義和から、電流丸乗組員たちへの労(ねぎら)いとして“酒のつまみ”が授与されたといいます。高級珍味だったのか…気になります。
他の資料では、伊万里の浅瀬の多い場所からは小舟で、水深のある「楠久」に物資を移してから、大船で動かす…という話もありました。
港での操船には、かつて伊万里近辺で活躍した“松浦党”の水軍技術が活きたとか。“元寇”を描いた2001年大河ドラマ『北条時宗』を想い出します。

――この“ポサドニック号”事件の時に、
もう1つの蒸気船・観光丸の艦長として対馬に上陸したのが、佐野常民。長崎に近い優位性。佐賀藩士は海軍技術に通じた人材が多いのが特徴的です。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕
幕府から佐賀が預かっていた、観光丸の方は「久原」に寄港したという話も。
外輪蒸気船・観光丸。2010年大河ドラマ『龍馬伝』でもロケに使われた“復元船”が存在し、長崎で運行されていますが、いまはシーズンオフのようです。
――“観光丸”は、勝海舟や坂本龍馬も関わった船なのですが…
私の視点だと、鍋島直正が「この船(のちの観光丸)は、幾らで買えるのか?」と質問して、オランダの関係者を慌てさせたとか…
〔参照:第11話「蝦夷探検」①(殿、蒸気船に乗る)〕
幕府から佐賀藩に預けられた時に佐野常民だけでなく、島義勇も艦長だったことがあるとか…佐賀に関するエピソードが満載の蒸気船です。
佐賀藩士たちが蒸気船を運用して、伊万里の港からも海を駆けていた姿を、想う人が増えると良いな…という気持ちで書きました。
前回、ご案内した“本編”振り返りシリーズ第1回目です。
全3回のうち、本日が“前編”ということに。キーワードは『松浦鉄道』です。例によって、鉄道そのものの写真はございませんが、語ることはできます。
――登場する駅名は東から西へ。「伊万里」→「楠久」→「久原」の3か所。
なお、私は10年ほど前に松浦鉄道沿線を回る計画を立てましたが、その時は諸事情により断念しました。
それゆえ地元に住まう方から見れば、おかしな記述もあるかもしれませんが、思い切って書きます。構成の都合上、「伊万里」「久原」「楠久」の順番で…
――まず、1本目・「伊万里」について。
“本編”では、佐賀藩の産業政策を支える“柱”の1つ、陶磁器産業を語るため、賑わう積出港として舞台になることが多いです。
なお、伊万里の商人について、深く描くことは出来ていませんが、場面設定で用いることは時折あります。
〔参照:
――次に、2本目・「久原」について。
“本編”には、創作要素の強い話が含まれることがあります。例えば、第16話「攘夷沸騰」から、なぜか度々、伊万里湾を望む高台に現れる、江藤新平。
〔参照(後半):
これは、江藤が藩の貿易部門・代品方に移る前振り。また第18話「京都見聞」の展開の都合で考えた設定です。
史実寄りの情報では、江藤の剣術道場の先輩で、小城(支藩)の富岡敬明が、伊万里にいろいろと関わりがありそうです。
〔参照:
――佐賀の支藩・小城藩の飛び地だったという「久原」。
“本編”では少し先の時期になりますが、1864年頃に小城藩内の抗争で責任を取る形になった富岡は、囚われの身として当地にいたようです。
富岡敬明に恩のあった、江藤は「久原」まで足を運び、剣舞を踊って励ました…らしいのです。
「江藤には伊万里の土地勘があったのでは…」との推測はこの辺りからです。
明治に入ってから、江藤らの助力で赦免された富岡。新政府の地方官僚として“伊万里県”から仕事を始め、熊本県や山梨県での活躍が伝わります。
〔参照:
――そして、3本目・「楠久」について。
佐賀藩海軍の拠点として描くことが多い、伊万里。鍋島直正の“相棒”のように描くこともある、オランダ生まれの蒸気船・電流丸。
〔参照(前半):
なお時々、殿様に呼びかけられると、電流丸が「ボッ…!」とか応えるのは、私の趣味による脚色です。
文久元年(1861年)。対馬に上陸したロシア船への警戒のため、佐賀藩海軍は電流丸を派遣します。その寄港地として、記述を見つけたのが「楠久」です。
――幕末期。蒸気船が行き交った、伊万里の海。
当時の対馬藩主・宗義和から、電流丸乗組員たちへの労(ねぎら)いとして“酒のつまみ”が授与されたといいます。高級珍味だったのか…気になります。
他の資料では、伊万里の浅瀬の多い場所からは小舟で、水深のある「楠久」に物資を移してから、大船で動かす…という話もありました。
港での操船には、かつて伊万里近辺で活躍した“松浦党”の水軍技術が活きたとか。“元寇”を描いた2001年大河ドラマ『北条時宗』を想い出します。
――この“ポサドニック号”事件の時に、
もう1つの蒸気船・観光丸の艦長として対馬に上陸したのが、佐野常民。長崎に近い優位性。佐賀藩士は海軍技術に通じた人材が多いのが特徴的です。
〔参照:
幕府から佐賀が預かっていた、観光丸の方は「久原」に寄港したという話も。
外輪蒸気船・観光丸。2010年大河ドラマ『龍馬伝』でもロケに使われた“復元船”が存在し、長崎で運行されていますが、いまはシーズンオフのようです。
――“観光丸”は、勝海舟や坂本龍馬も関わった船なのですが…
私の視点だと、鍋島直正が「この船(のちの観光丸)は、幾らで買えるのか?」と質問して、オランダの関係者を慌てさせたとか…
〔参照:
幕府から佐賀藩に預けられた時に佐野常民だけでなく、島義勇も艦長だったことがあるとか…佐賀に関するエピソードが満載の蒸気船です。
佐賀藩士たちが蒸気船を運用して、伊万里の港からも海を駆けていた姿を、想う人が増えると良いな…という気持ちで書きました。
2022年01月16日
「“本編”への集中。」
こんにちは。
NHK土曜ドラマ『わげもん』。第2回でますます幕末・長崎の描写が充実していますね。私には、画面の外に佐賀藩士たちの姿も見えるかのようです。
現在、“本編”第17話「佐賀脱藩」の後半を準備中です。なかなか重たい展開になっており、かなり気合を入れねば、書き進めることができません。
“本編”についてですが、年始ぐらいから当ブログをご覧になり始めた方もいるかもしれませんので、念のためご説明します。

――当ブログで“本編”とは…
「こんな“幕末佐賀藩の大河ドラマ”が見たい!」という、私のイメージを記事にしたものです。
開始前は「あらすじだけを書く」予定でしたが、実際書き始めると、どんどんと内容が細かくなっていきました。
たぶん本来の大河ドラマならば、「ナレーション」や「画面上の地図」で表現しそうなところまで、セリフを入れていることも多いです。
――いまや、書きたいところは書いています。
開始時から重要エピソードになると考えた、第17話「佐賀脱藩」。年末年始をまたいでしまったため、小休止していました。
その間に、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、長崎を描く土曜ドラマ『わげもん』の放送開始など、気になる情報も多くありました。
すでに“本編”の下書きは再開していますが、このところ個人的に忙しいのと、集中力が必要そうな展開なので、しばらくは年末までの話を振り返ります。

――振り返りは、3回で企画します。
前編は、佐賀県の西部。長崎県ともつながっていく、伊万里市に関する話を。
〔参照(前半):第16話「攘夷沸騰」⑰(積出港の昼下がり)〕
中編は、佐賀県の中央。佐賀城下での展開と、そこから見える江戸の話を。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)〕
後編は、佐賀県の東部。隣接する福岡県を意識しながら、みやき町の話を。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕
――ちなみに“解説”も含め、当ブログの記事は…
様々な情報を寄せ集め、想像を巡らせて書いています。参照資料の信頼性にも相当な差があり、特に“本編”は史実に着想を得た創作とご理解ください。
もう少し、しっかり調べた方が良さそうなのですが、時間にも制約がある中で、何とか“本編”を進めたい気持ちも強いです。
第1回(前編)は伊万里編を予定します。一度、松浦鉄道にも乗ってみたいのですが、「佐賀の遠か…」という状況は続いています。
NHK土曜ドラマ『わげもん』。第2回でますます幕末・長崎の描写が充実していますね。私には、画面の外に佐賀藩士たちの姿も見えるかのようです。
現在、“本編”第17話「佐賀脱藩」の後半を準備中です。なかなか重たい展開になっており、かなり気合を入れねば、書き進めることができません。
“本編”についてですが、年始ぐらいから当ブログをご覧になり始めた方もいるかもしれませんので、念のためご説明します。
――当ブログで“本編”とは…
「こんな“幕末佐賀藩の大河ドラマ”が見たい!」という、私のイメージを記事にしたものです。
開始前は「あらすじだけを書く」予定でしたが、実際書き始めると、どんどんと内容が細かくなっていきました。
たぶん本来の大河ドラマならば、「ナレーション」や「画面上の地図」で表現しそうなところまで、セリフを入れていることも多いです。
――いまや、書きたいところは書いています。
開始時から重要エピソードになると考えた、第17話「佐賀脱藩」。年末年始をまたいでしまったため、小休止していました。
その間に、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、長崎を描く土曜ドラマ『わげもん』の放送開始など、気になる情報も多くありました。
すでに“本編”の下書きは再開していますが、このところ個人的に忙しいのと、集中力が必要そうな展開なので、しばらくは年末までの話を振り返ります。
――振り返りは、3回で企画します。
前編は、佐賀県の西部。長崎県ともつながっていく、伊万里市に関する話を。
〔参照(前半):
中編は、佐賀県の中央。佐賀城下での展開と、そこから見える江戸の話を。
〔参照(後半):
後編は、佐賀県の東部。隣接する福岡県を意識しながら、みやき町の話を。
〔参照(後半):
――ちなみに“解説”も含め、当ブログの記事は…
様々な情報を寄せ集め、想像を巡らせて書いています。参照資料の信頼性にも相当な差があり、特に“本編”は史実に着想を得た創作とご理解ください。
もう少し、しっかり調べた方が良さそうなのですが、時間にも制約がある中で、何とか“本編”を進めたい気持ちも強いです。
第1回(前編)は伊万里編を予定します。一度、松浦鉄道にも乗ってみたいのですが、「佐賀の遠か…」という状況は続いています。