2024年03月05日
第20話「長崎方控」①(“よか男”の通らす道)
こんばんは。
本編・第20話を始めます。第一幕は佐賀県の民謡『岳の新太郎さん』から、着想したエピソードです。しばし“物語”に、お付き合いください。
舞台は現在の長崎県諫早市から佐賀県太良町へと続く“多良海道”で、長崎からの帰路の設定。時期のイメージは、文久二年(1862年)の秋。

佐賀藩から出ずに長崎と往復可能な「便利なルート」を行く若い男性が2人。ともに佐賀の侍ですが、ひときわ背丈もあるのが、大隈八太郎(重信)。
もう1人も、普通の武士とは一風変わった印象があります。山口範蔵(尚芳)という人物なのですが…
――多良岳から経ヶ岳への稜線が青く光って見える。
「あ~よか天気ばい。」
「そうですね。ナイス サニー ディ」
「何ね…?差(さ)に出(い)で…?」
大隈八太郎は、その言い回しに困惑した。この山口範蔵という男、時折、聞き取れない異国の言葉を発する。
「こいは、失礼。」
山口は「つい、英語が出てきた…」という顔をした。大隈は「実はわかっとるよ」という表情を返した。負けず嫌いである。
ガラン…、ガラン…と傍の小川では、水車が音をたてていた。この村は、収穫後の作業で忙しい時期かもしれない。

――どこからともなく、女性たちの歌声がする…
声の主は、若い村娘たちのようだ。
「たけの~しんたろさんの~♪」
大隈が、先に気付いた。
「…ほう、女子たちの元気のよかごたね。」
「はい、女性が元気なのは、良かことです。」
山口がフッと笑った。“西洋かぶれ”というか、何だか気取って見える。
村娘たちは、川向かいの小屋の横で作業をしているらしく、歩く2人の視界にもその姿が見えてきた。
――よく働くようだが、同時に歌も盛り上がってきている。
歌う娘によって、曲の調子も音程もまちまち。荷を運ぶ勢いでも付けるふうだ。芸事と見れば、お世辞にも上手とは言えないが、活発な可愛らしさはある。
「いろしゃのすいしゃで~♪きは、ざんざ~♪」
山口は、耳ざわりが良いな…ばかりにと娘たちの歌を聞き流すが、大隈は、そもそも何を歌っているのかが、気になる様子だ。
「娘たちは、何ば言いよっとね?」
「あぁ“色者の粋者で、気はザンザ”と歌いよるそうです。」

「道ば通りよる…“たけの しんたろう”って誰ね?」
「昔、ここを“よか男”が通って、娘たちの気持ちがざわつきよったですよ。」
この辺りの土地の事情にも、やけに詳しい山口。長崎との往来には、とくに慣れている様子だ。
――歌われている“岳の新太郎”は、文化・文政年間の美少年と伝わる。
佐賀藩で言えば鍋島直正が、数え17歳で藩主に就任した天保年間より、さらに前の年代が文化・文政の年間。
1830年(天保元年)より古いから、この時点からは「30年以上前の“よか男”への恋心の歌」ということになる。
次々と質問をぶつける大隈に対して、山口は淡々と説明を返す。
「そいぎ、随分と昔の話ということです。」
「その“新太郎”さんも生きておれば、今頃、相当なじいさんとよ。」
「寺侍だったと聞きますが、勤めは、金泉寺かと思いよるです。」
「本当に、ただの寺侍とね?」

修験道の聖地としても知られる、多良岳にあるという金泉寺。そこからは、有明海をゆく船の出入りも見通せるらしい。
そして、戦国期よりも古い時代から、修験道を行ずる山伏たちは、諸国の情報収集に長けていたという。
――山口も「おいにも、わからんとです」とさらりと返した。
当時の武雄領主・鍋島茂義に才能を見いだされた、山口範蔵。以前から長崎に学問の修行に出ており、はじめオランダ語を習得した。
今は長崎奉行所に設けられた伝習の教場で、イギリスの言葉という英語を学んでいる。
大隈とて、大殿・鍋島直正(閑叟)にオランダの法律などを講義することもあるが、英語には、ほとんど手を出せてはいない。
――歩くうちに村娘たちの声が、より近づいてきた。
「岳の~新太郎さんの~登らす道にゃ~♪」
興が乗ってきたのか、2番の歌唱に入る。ここで、川向かいの2人と村娘たちで目線が合った。
すかさず、山口は「ごきげんよう」と言うふうに会釈をした。動きが西洋かぶれで、幾分キザに見える。

まさに、“よか男”の歌に興じた女子たちは、山口の不思議な挨拶に面食らうも、ちょっと盛り上がっているようだ。
「にゃ~、山口。気取った男ばい。」
大隈は、後れを取った…と感じるのか、少し気にさわったふうですねている。
――のちに、山口尚芳(ますか)として知られる、山口範蔵。
明治期には、もともと大隈重信(八太郎)が発案していた西洋への使節に、行きがかり上、“大隈の代わり”として参加する立場となる。
10年ほど前のこの時点では、佐賀藩でさえ、オランダの蘭学からイギリスの英学へと関心が移りはじめたところだった。
英語の習得でも、時代の一歩先を進んでいたのが、武雄領出身の山口範蔵(尚芳)だった。
(続く)
◎参考記事
○佐賀県民謡「岳の新太郎さん」
・「幕末娘の“推し活”」
・「主に太良町民の皆様を対象にしたつぶやき」
○山口尚芳(やまぐちますか、山口範蔵)
・「魅力度と“第三の男”(前編)」
・「魅力度と“第三の男”(後編)」
本編・第20話を始めます。第一幕は佐賀県の民謡『岳の新太郎さん』から、着想したエピソードです。しばし“物語”に、お付き合いください。
舞台は現在の長崎県諫早市から佐賀県太良町へと続く“多良海道”で、長崎からの帰路の設定。時期のイメージは、文久二年(1862年)の秋。
佐賀藩から出ずに長崎と往復可能な「便利なルート」を行く若い男性が2人。ともに佐賀の侍ですが、ひときわ背丈もあるのが、大隈八太郎(重信)。
もう1人も、普通の武士とは一風変わった印象があります。山口範蔵(尚芳)という人物なのですが…
――多良岳から経ヶ岳への稜線が青く光って見える。
「あ~よか天気ばい。」
「そうですね。ナイス サニー ディ」
「何ね…?差(さ)に出(い)で…?」
大隈八太郎は、その言い回しに困惑した。この山口範蔵という男、時折、聞き取れない異国の言葉を発する。
「こいは、失礼。」
山口は「つい、英語が出てきた…」という顔をした。大隈は「実はわかっとるよ」という表情を返した。負けず嫌いである。
ガラン…、ガラン…と傍の小川では、水車が音をたてていた。この村は、収穫後の作業で忙しい時期かもしれない。
――どこからともなく、女性たちの歌声がする…
声の主は、若い村娘たちのようだ。
「たけの~しんたろさんの~♪」
大隈が、先に気付いた。
「…ほう、女子たちの元気のよかごたね。」
「はい、女性が元気なのは、良かことです。」
山口がフッと笑った。“西洋かぶれ”というか、何だか気取って見える。
村娘たちは、川向かいの小屋の横で作業をしているらしく、歩く2人の視界にもその姿が見えてきた。
――よく働くようだが、同時に歌も盛り上がってきている。
歌う娘によって、曲の調子も音程もまちまち。荷を運ぶ勢いでも付けるふうだ。芸事と見れば、お世辞にも上手とは言えないが、活発な可愛らしさはある。
「いろしゃのすいしゃで~♪きは、ざんざ~♪」
山口は、耳ざわりが良いな…ばかりにと娘たちの歌を聞き流すが、大隈は、そもそも何を歌っているのかが、気になる様子だ。
「娘たちは、何ば言いよっとね?」
「あぁ“色者の粋者で、気はザンザ”と歌いよるそうです。」
「道ば通りよる…“たけの しんたろう”って誰ね?」
「昔、ここを“よか男”が通って、娘たちの気持ちがざわつきよったですよ。」
この辺りの土地の事情にも、やけに詳しい山口。長崎との往来には、とくに慣れている様子だ。
――歌われている“岳の新太郎”は、文化・文政年間の美少年と伝わる。
佐賀藩で言えば鍋島直正が、数え17歳で藩主に就任した天保年間より、さらに前の年代が文化・文政の年間。
1830年(天保元年)より古いから、この時点からは「30年以上前の“よか男”への恋心の歌」ということになる。
次々と質問をぶつける大隈に対して、山口は淡々と説明を返す。
「そいぎ、随分と昔の話ということです。」
「その“新太郎”さんも生きておれば、今頃、相当なじいさんとよ。」
「寺侍だったと聞きますが、勤めは、金泉寺かと思いよるです。」
「本当に、ただの寺侍とね?」
修験道の聖地としても知られる、多良岳にあるという金泉寺。そこからは、有明海をゆく船の出入りも見通せるらしい。
そして、戦国期よりも古い時代から、修験道を行ずる山伏たちは、諸国の情報収集に長けていたという。
――山口も「おいにも、わからんとです」とさらりと返した。
当時の武雄領主・鍋島茂義に才能を見いだされた、山口範蔵。以前から長崎に学問の修行に出ており、はじめオランダ語を習得した。
今は長崎奉行所に設けられた伝習の教場で、イギリスの言葉という英語を学んでいる。
大隈とて、大殿・鍋島直正(閑叟)にオランダの法律などを講義することもあるが、英語には、ほとんど手を出せてはいない。
――歩くうちに村娘たちの声が、より近づいてきた。
「岳の~新太郎さんの~登らす道にゃ~♪」
興が乗ってきたのか、2番の歌唱に入る。ここで、川向かいの2人と村娘たちで目線が合った。
すかさず、山口は「ごきげんよう」と言うふうに会釈をした。動きが西洋かぶれで、幾分キザに見える。
まさに、“よか男”の歌に興じた女子たちは、山口の不思議な挨拶に面食らうも、ちょっと盛り上がっているようだ。
「にゃ~、山口。気取った男ばい。」
大隈は、後れを取った…と感じるのか、少し気にさわったふうですねている。
――のちに、山口尚芳(ますか)として知られる、山口範蔵。
明治期には、もともと大隈重信(八太郎)が発案していた西洋への使節に、行きがかり上、“大隈の代わり”として参加する立場となる。
10年ほど前のこの時点では、佐賀藩でさえ、オランダの蘭学からイギリスの英学へと関心が移りはじめたところだった。
英語の習得でも、時代の一歩先を進んでいたのが、武雄領出身の山口範蔵(尚芳)だった。
(続く)
◎参考記事
○佐賀県民謡「岳の新太郎さん」
・
・
○山口尚芳(やまぐちますか、山口範蔵)
・
・
2024年03月11日
第20話「長崎方控」②(聞きまちがいから出た本音)
こんばんは。
場面設定は、文久二年(1862年)秋。長崎から佐賀を通って、小倉へと続く、長崎街道の中で“多良海道”とも呼ばれた、現在では佐賀県南西部の区間。
この頃から、藩校の蘭学教師としてだけでなく、“秘密の仕事”を始めており、長崎出張から帰る大隈八太郎(重信)。

所用があって出身の武雄領に戻る、山口範蔵(尚芳)と連れだって歩く、水車の回る小径で、村娘たちの歌声が気になる様子です。
――山口の“西洋風”の会釈(えしゃく)が、女子に受けている。
村娘たちは「エレガント」という言葉を知りようもないが、長崎仕込みの、山口の立ち振る舞いに“優雅さ”が見えたのか。
そして、女子のおしゃべりは労働の日々の潤いでもあるようで、川向かいから「え~、なんね―」「よかじゃない?」と盛り上がる様子だ。
その山口の傍で、負けず嫌いの大隈から、ちょっとした“嫉妬の炎”がプスプスとくすぶる。

――大隈八太郎は、幼少期こそ甘えん坊だったが、
少年期には性格も変わり、よく喧嘩もした。青年の今も負けん気は強い。
「山口範蔵…何ね。気取った男ばい…」と、少し苛(いら)立っている。
「あぁ、大隈さん。そろそろ先に進まんば、陽も傾くですよ。」
一方で何だか、余裕を感じる山口である。長崎奉行所が仕切る英語の伝習を受けるとは、最先端の「選ばれた人材」と言ってもよい。
――今回は大隈も、「この武雄の“西洋かぶれ”…手強い」と見たか。
ここでは、山口に対抗するのを断念したようで、こう、つぶやいた。
「ふん。おいには、美登(みと)さんの居(お)っけん。良かもんね。」
大隈は柄にもなく「その他大勢の“女子ウケ”が良くなくても構わないのだ…」とばかり、ぶつぶつと言っている。
その大隈の言葉が耳に入ったか。今度は、山口が気にするふうを見せる。
「いま…水戸(みと)さんと、言いよったですか?」
――なお、大隈が口にした“美登(みと)さん”という名は、
江副美登という女性で、佐賀藩士の娘。大隈八太郎の婚約者ということだ。

「…あぁ、良かごた。何でもなかばい。」
大隈は、急に身を乗り出してきた、山口の質問を受け流そうとした。
「水戸(みと)…、“水戸”の気になるごたです。」
しかし、山口はしつこく尋ねてくる。その思考の中では、水戸藩(茨城)の話になっている。
「そがん、美登(みと)の気になるとね?たしかに、器量の良か女子とよ。」
「おなご…?何の話でしょうか。」
――この山口。気取って見えたが、根は真面目な男らしい。
「“水戸烈公”の亡きいま、水戸はどう動くか、気になっとです。」
1858年頃だから、当時から4年ばかり前。井伊直弼が大老の時期の“安政の大獄”で、水戸の徳川斉昭は政治の表舞台から退いた。
そのまま失意のもと、2年後に世を去った。
「尊王攘夷」という言葉は水戸から全国に伝わったから、“烈公”こと徳川斉昭の存在感は、かなり大きいものだったのだ。

「山口範蔵…そがん、水戸が気になるとね?」
「水戸には、勤王の志ばあると思いますけん。」
大隈にとっては、意外だった。英語の伝習とはいえ、幕府の長崎奉行所に関わる、山口から朝廷を意識した“勤王”という言葉が出るとは。
蘭学・英学など西洋の学問を知る2人なので、“攘夷”については異国の排斥を行いたいなら、まず列強に実力で追いつかねば…と冷めて見ている。
しかし“勤王(尊王)”の方は本来、日本を率いるのは幕府ではなく朝廷であるべきで、佐賀藩こそが先導を務めねばならぬ…という熱い気持ちがある。

――大隈八太郎は、急に、山口に親しみを覚えた。
「そうたい。佐賀は、もっと“勤王の志”を持たんばならん。」
最近では、大隈が藩内で胸を張って、こう語れる機会は少なくなっていた。
かつては、佐賀城下では“義祭同盟”がその場所だったが、主宰の枝吉神陽が数か月前に流行病で世を去ったので、今後どうなるかはわからない。
――それに肩書は、藩校の蘭学教師となっている大隈。
最近では、大隈が貿易や利殖で、“佐賀藩が儲ける話”を提案した場合は、案外と重役たちも、興味を持って聞いてくれる。
ところが、「藩を挙げて、勤王のはたらきを為すべし」とか言うと、幕府を重視する佐賀藩では、ほぼ無視されるか、露骨に止められるかだとわかってきた。
「ばってん、“徳川の世”も、そう長くは続くまいと思うております。」
山口は涼しい顔で語り出す。幕府の奉行所に出入りするはずなのだが…

「そいは、言わん方がよかじゃなかとね!?」
大隈が驚くほど過激な発言をした、武雄領の山口。
その言葉には、佐賀本藩で賢く立ち回ろうと考え、まずは財力を確保する作戦に出た、大隈が語らなくなった“本音”があった。
(続く)
◎参考記事
○水戸藩(茨城県)関連
・(冒頭部分)「魅力度と“第三の男”(前編)」
・(本編)第11話「蝦夷探検」③(“懐刀”の想い)
○安政の大獄
・「“安政の大獄”をどう描くか?」
・(本編)第15話「江戸動乱」⑭(“赤鬼”が背負うもの)
○枝吉神陽
・(本編)第19話「閑叟上洛」⑦(愛する者へ、最後の講義)
場面設定は、文久二年(1862年)秋。長崎から佐賀を通って、小倉へと続く、長崎街道の中で“多良海道”とも呼ばれた、現在では佐賀県南西部の区間。
この頃から、藩校の蘭学教師としてだけでなく、“秘密の仕事”を始めており、長崎出張から帰る大隈八太郎(重信)。
所用があって出身の武雄領に戻る、山口範蔵(尚芳)と連れだって歩く、水車の回る小径で、村娘たちの歌声が気になる様子です。
――山口の“西洋風”の会釈(えしゃく)が、女子に受けている。
村娘たちは「エレガント」という言葉を知りようもないが、長崎仕込みの、山口の立ち振る舞いに“優雅さ”が見えたのか。
そして、女子のおしゃべりは労働の日々の潤いでもあるようで、川向かいから「え~、なんね―」「よかじゃない?」と盛り上がる様子だ。
その山口の傍で、負けず嫌いの大隈から、ちょっとした“嫉妬の炎”がプスプスとくすぶる。
――大隈八太郎は、幼少期こそ甘えん坊だったが、
少年期には性格も変わり、よく喧嘩もした。青年の今も負けん気は強い。
「山口範蔵…何ね。気取った男ばい…」と、少し苛(いら)立っている。
「あぁ、大隈さん。そろそろ先に進まんば、陽も傾くですよ。」
一方で何だか、余裕を感じる山口である。長崎奉行所が仕切る英語の伝習を受けるとは、最先端の「選ばれた人材」と言ってもよい。
――今回は大隈も、「この武雄の“西洋かぶれ”…手強い」と見たか。
ここでは、山口に対抗するのを断念したようで、こう、つぶやいた。
「ふん。おいには、美登(みと)さんの居(お)っけん。良かもんね。」
大隈は柄にもなく「その他大勢の“女子ウケ”が良くなくても構わないのだ…」とばかり、ぶつぶつと言っている。
その大隈の言葉が耳に入ったか。今度は、山口が気にするふうを見せる。
「いま…水戸(みと)さんと、言いよったですか?」
――なお、大隈が口にした“美登(みと)さん”という名は、
江副美登という女性で、佐賀藩士の娘。大隈八太郎の婚約者ということだ。

「…あぁ、良かごた。何でもなかばい。」
大隈は、急に身を乗り出してきた、山口の質問を受け流そうとした。
「水戸(みと)…、“水戸”の気になるごたです。」
しかし、山口はしつこく尋ねてくる。その思考の中では、水戸藩(茨城)の話になっている。
「そがん、美登(みと)の気になるとね?たしかに、器量の良か女子とよ。」
「おなご…?何の話でしょうか。」
――この山口。気取って見えたが、根は真面目な男らしい。
「“水戸烈公”の亡きいま、水戸はどう動くか、気になっとです。」
1858年頃だから、当時から4年ばかり前。井伊直弼が大老の時期の“安政の大獄”で、水戸の徳川斉昭は政治の表舞台から退いた。
そのまま失意のもと、2年後に世を去った。
「尊王攘夷」という言葉は水戸から全国に伝わったから、“烈公”こと徳川斉昭の存在感は、かなり大きいものだったのだ。

「山口範蔵…そがん、水戸が気になるとね?」
「水戸には、勤王の志ばあると思いますけん。」
大隈にとっては、意外だった。英語の伝習とはいえ、幕府の長崎奉行所に関わる、山口から朝廷を意識した“勤王”という言葉が出るとは。
蘭学・英学など西洋の学問を知る2人なので、“攘夷”については異国の排斥を行いたいなら、まず列強に実力で追いつかねば…と冷めて見ている。
しかし“勤王(尊王)”の方は本来、日本を率いるのは幕府ではなく朝廷であるべきで、佐賀藩こそが先導を務めねばならぬ…という熱い気持ちがある。
――大隈八太郎は、急に、山口に親しみを覚えた。
「そうたい。佐賀は、もっと“勤王の志”を持たんばならん。」
最近では、大隈が藩内で胸を張って、こう語れる機会は少なくなっていた。
かつては、佐賀城下では“義祭同盟”がその場所だったが、主宰の枝吉神陽が数か月前に流行病で世を去ったので、今後どうなるかはわからない。
――それに肩書は、藩校の蘭学教師となっている大隈。
最近では、大隈が貿易や利殖で、“佐賀藩が儲ける話”を提案した場合は、案外と重役たちも、興味を持って聞いてくれる。
ところが、「藩を挙げて、勤王のはたらきを為すべし」とか言うと、幕府を重視する佐賀藩では、ほぼ無視されるか、露骨に止められるかだとわかってきた。
「ばってん、“徳川の世”も、そう長くは続くまいと思うております。」
山口は涼しい顔で語り出す。幕府の奉行所に出入りするはずなのだが…

「そいは、言わん方がよかじゃなかとね!?」
大隈が驚くほど過激な発言をした、武雄領の山口。
その言葉には、佐賀本藩で賢く立ち回ろうと考え、まずは財力を確保する作戦に出た、大隈が語らなくなった“本音”があった。
(続く)
◎参考記事
○水戸藩(茨城県)関連
・(冒頭部分)
・(本編)
○安政の大獄
・
・(本編)
○枝吉神陽
・(本編)
2024年03月17日
第20話「長崎方控」③(西洋風の“紳士”)
こんばんは。
2026年大河ドラマが『豊臣兄弟!』に決定…とか、『光る君へ』の感想とか…先週の『歴史探偵』とか…いろいろと語りたくはありますが、“本編”を続けます。
さて、ここ数話で登場している山口範蔵(尚芳)は、佐賀藩の武雄領出身。
のち明治期には、岩倉使節団の副使・山口尚芳(ますか)として、歴史番組にも、時々出てくる集合写真で、その姿を見かけます。
〔参考(終盤):「武雄よ、共〔とも〕に…」〕※集合写真が一部映り込んでいます。

山口尚芳は、少年期より当地・武雄の自治領主で、極端な“西洋かぶれ”だった、鍋島茂義にその才覚を見いだされたそうです。
15歳頃から蘭学の修業のため、長崎に派遣され、まずオランダ語を身につけ、次に英語の習得にもあたりました。では、ここから本編に戻ります。
――気取った“西洋かぶれ”と見えていた、山口範蔵(尚芳)だったが…
この多良海道を並んで歩くうち、だんだんと山口は、“勤王の志士”としての顔を見せ始めた。
「そがんですね…、事が動くまでは、語らん方がよか事もありますけん。」
「おお、そうたい。賢くやらんば。」
わりと無鉄砲な大隈八太郎(重信)だが、今回は、山口が「もはや、幕府(徳川政権)は長続きしない」と発言したのを、諭(さと)す感じになっている。

――大隈も、藩の上層部に“儲け話”の提案をはじめてから、
知らず“空気を読む”ことを覚えたか、“実利を取る”考え方になってしまったのかもしれない。
「…ばってん、山口さんの言いたかことは良くわかるとよ。」
大隈は、うんうんと大きくうなずきながら、こう続けた。
当時の佐賀藩は、幕府の海外使節団に藩士たちを同行させ、イギリスやアメリカで通用する、英語の重要性を意識した時期だ。
大隈もアメリカへの派遣から帰った、小出千之助から体験談を聞いて、今までのオランダ語にこだわるよりも、英語の習得が必要だと思うようになった。

ところが、一緒に勉強するはずの面々に蒸気船での出動命令が出たり、他にも貿易調査の任務が入ったり…と集中して、学習する機会を逃している。
この山口範蔵(尚芳)なら、開国により新たな貿易相手も増えた長崎にいて、西洋に詳しく、幕府の通訳たちに混ざって英語も学んでいる。
その経歴で“勤王の志”もあるという、すごく珍しくて値打ちのある存在だ。
――ここで、友達になっておけば、極めて“お得”である。
そして、大隈が学生の時からよく取る手段は、「賢い奴に勉強させれば、大体のことは聞けばわかる」だ。ぜひとも山口とは、ここで仲良くなっておこう。
とりあえず、高い志への感銘を伝えて、親しくなるのが良さそうだ。
「山口さんね、」と、大隈が話を切り出した。
「大隈さん!“勤王の同志”に、ここで出会うとは嬉しかことです。」
意外や今度も、山口の方が前のめりだ。右手を差し伸べて、こう続けた。
「もう、我らは同志ですけん。“シェイクハンド”を願うても、よかですか。」

山口が提案をする。この儀礼は大隈も知っていた。西洋人は両者が手を握ることで、敵意の無いことを示すのだと。
「よかごた!」
大隈が応じ、山口とグッと手を握り合う。秋の陽が2人の長い影を作りだした。
「なんね…??」
さっきまで川向かいで歌っていた村娘の1人が不思議そうに、その一部始終を見つめていた。がっちり手を握り合う、若い男2人の様子が気になるようだ。
――山口は、その村娘の方を向いて「バァイ!」と、掌を挙げた。
軽く微笑む山口、これも英米での別れの表現か。視線が合った娘は、何だか照れているが、つられて掌を挙げて返した。気が合うのかもしれない。
「…よく、女子に色目を使う奴ばい。」
大隈八太郎、この日はなんとなく、山口範蔵に振り回されっぱなしである。

「西洋では品格があり、女性にも優しか男をジェントルマンと呼びよるです。」
「“全取る”(ぜんとる)とは…、強欲のごた響きたい。」
大隈が、ちょっと投げやりな感じで言い放った。
「いえ、ジェントルマンです。“紳士”とでも言ったらよかですかね。」
山口が、真面目な顔で言い返した。
「よか。わかったばい。」
大隈は、山口の振る舞いを見て思い立った。何だか、西洋を知るふうで格好良いではないか。今度、長崎に行ったときに、ぜんぶ真似してみようかと。

わからなかったところは、藩校に戻った時に、アメリカから帰った小出千之助に聞いておけば、抜かりは無いだろう。
――そして、山口は、武雄に帰っている目的を語り始めた。
「武雄のご隠居さまに、ご機嫌うかがいに。」
「そがん、親しか間柄になるとね。」
武雄の前領主・鍋島茂義は、佐賀藩の大殿・鍋島直正の義兄にあたり“兄貴分”と言ってよい存在。藩の上層部の中でも、特に重要な人物だ。
「ご隠居さまのおかげで、今があるとです。」
山口は語学をはじめ、西洋を学ぶことができるのは、当時の領主・鍋島茂義の恩恵だと力説する。
こうして山口は、茂義公の期待どおり、立派な“西洋かぶれ”に育ったようだ。
「このところ、武雄からの“ご注文”が滞りおるので、気になりまして。」

――大隈は最近、長崎で商人とも関わり始めている。
たしかに以前より武雄からは、西洋の品物の注文が多くあったと聞く。長崎で取り寄せる舶来の品には、高く売れる物も多い。
武雄の鍋島茂義も、齢(よわい)六十を越えるが、老いたからといって海外への興味を無くす気性でもない。
こうして、山口範蔵(尚芳)は、自分の大切な“恩人”が心配になり、一時、武雄へと様子を見に戻ることにしたようだった。
(続く)
◎参考記事(文中記載の人物名について補足)
○小出千之助
幕府の遣米使節に随行して、アメリカを見聞し、佐賀藩の「英学の祖」とも呼ばれるそうです。
本編での関連記事
・第16話「攘夷沸騰」⑪(“英学”の風が吹く)
・第16話「攘夷沸騰」⑫(“錬金術”と闘う男)
・第16話「攘夷沸騰」⑬(あの者にも英学を)
・第16話「攘夷沸騰」⑭(多良海道の往還)
その他の関連記事
・「夜明けを目指して」
2026年大河ドラマが『豊臣兄弟!』に決定…とか、『光る君へ』の感想とか…先週の『歴史探偵』とか…いろいろと語りたくはありますが、“本編”を続けます。
さて、ここ数話で登場している山口範蔵(尚芳)は、佐賀藩の武雄領出身。
のち明治期には、岩倉使節団の副使・山口尚芳(ますか)として、歴史番組にも、時々出てくる集合写真で、その姿を見かけます。
〔参考(終盤):
山口尚芳は、少年期より当地・武雄の自治領主で、極端な“西洋かぶれ”だった、鍋島茂義にその才覚を見いだされたそうです。
15歳頃から蘭学の修業のため、長崎に派遣され、まずオランダ語を身につけ、次に英語の習得にもあたりました。では、ここから本編に戻ります。
――気取った“西洋かぶれ”と見えていた、山口範蔵(尚芳)だったが…
この多良海道を並んで歩くうち、だんだんと山口は、“勤王の志士”としての顔を見せ始めた。
「そがんですね…、事が動くまでは、語らん方がよか事もありますけん。」
「おお、そうたい。賢くやらんば。」
わりと無鉄砲な大隈八太郎(重信)だが、今回は、山口が「もはや、幕府(徳川政権)は長続きしない」と発言したのを、諭(さと)す感じになっている。
――大隈も、藩の上層部に“儲け話”の提案をはじめてから、
知らず“空気を読む”ことを覚えたか、“実利を取る”考え方になってしまったのかもしれない。
「…ばってん、山口さんの言いたかことは良くわかるとよ。」
大隈は、うんうんと大きくうなずきながら、こう続けた。
当時の佐賀藩は、幕府の海外使節団に藩士たちを同行させ、イギリスやアメリカで通用する、英語の重要性を意識した時期だ。
大隈もアメリカへの派遣から帰った、小出千之助から体験談を聞いて、今までのオランダ語にこだわるよりも、英語の習得が必要だと思うようになった。
ところが、一緒に勉強するはずの面々に蒸気船での出動命令が出たり、他にも貿易調査の任務が入ったり…と集中して、学習する機会を逃している。
この山口範蔵(尚芳)なら、開国により新たな貿易相手も増えた長崎にいて、西洋に詳しく、幕府の通訳たちに混ざって英語も学んでいる。
その経歴で“勤王の志”もあるという、すごく珍しくて値打ちのある存在だ。
――ここで、友達になっておけば、極めて“お得”である。
そして、大隈が学生の時からよく取る手段は、「賢い奴に勉強させれば、大体のことは聞けばわかる」だ。ぜひとも山口とは、ここで仲良くなっておこう。
とりあえず、高い志への感銘を伝えて、親しくなるのが良さそうだ。
「山口さんね、」と、大隈が話を切り出した。
「大隈さん!“勤王の同志”に、ここで出会うとは嬉しかことです。」
意外や今度も、山口の方が前のめりだ。右手を差し伸べて、こう続けた。
「もう、我らは同志ですけん。“シェイクハンド”を願うても、よかですか。」
山口が提案をする。この儀礼は大隈も知っていた。西洋人は両者が手を握ることで、敵意の無いことを示すのだと。
「よかごた!」
大隈が応じ、山口とグッと手を握り合う。秋の陽が2人の長い影を作りだした。
「なんね…??」
さっきまで川向かいで歌っていた村娘の1人が不思議そうに、その一部始終を見つめていた。がっちり手を握り合う、若い男2人の様子が気になるようだ。
――山口は、その村娘の方を向いて「バァイ!」と、掌を挙げた。
軽く微笑む山口、これも英米での別れの表現か。視線が合った娘は、何だか照れているが、つられて掌を挙げて返した。気が合うのかもしれない。
「…よく、女子に色目を使う奴ばい。」
大隈八太郎、この日はなんとなく、山口範蔵に振り回されっぱなしである。
「西洋では品格があり、女性にも優しか男をジェントルマンと呼びよるです。」
「“全取る”(ぜんとる)とは…、強欲のごた響きたい。」
大隈が、ちょっと投げやりな感じで言い放った。
「いえ、ジェントルマンです。“紳士”とでも言ったらよかですかね。」
山口が、真面目な顔で言い返した。
「よか。わかったばい。」
大隈は、山口の振る舞いを見て思い立った。何だか、西洋を知るふうで格好良いではないか。今度、長崎に行ったときに、ぜんぶ真似してみようかと。
わからなかったところは、藩校に戻った時に、アメリカから帰った小出千之助に聞いておけば、抜かりは無いだろう。
――そして、山口は、武雄に帰っている目的を語り始めた。
「武雄のご隠居さまに、ご機嫌うかがいに。」
「そがん、親しか間柄になるとね。」
武雄の前領主・鍋島茂義は、佐賀藩の大殿・鍋島直正の義兄にあたり“兄貴分”と言ってよい存在。藩の上層部の中でも、特に重要な人物だ。
「ご隠居さまのおかげで、今があるとです。」
山口は語学をはじめ、西洋を学ぶことができるのは、当時の領主・鍋島茂義の恩恵だと力説する。
こうして山口は、茂義公の期待どおり、立派な“西洋かぶれ”に育ったようだ。
「このところ、武雄からの“ご注文”が滞りおるので、気になりまして。」

――大隈は最近、長崎で商人とも関わり始めている。
たしかに以前より武雄からは、西洋の品物の注文が多くあったと聞く。長崎で取り寄せる舶来の品には、高く売れる物も多い。
武雄の鍋島茂義も、齢(よわい)六十を越えるが、老いたからといって海外への興味を無くす気性でもない。
こうして、山口範蔵(尚芳)は、自分の大切な“恩人”が心配になり、一時、武雄へと様子を見に戻ることにしたようだった。
(続く)
◎参考記事(文中記載の人物名について補足)
○小出千之助
幕府の遣米使節に随行して、アメリカを見聞し、佐賀藩の「英学の祖」とも呼ばれるそうです。
本編での関連記事
・
・
・
・
その他の関連記事
・
2024年03月24日
第20話「長崎方控」④(肥前浜の“酔客”)
こんばんは。
前回ですっかり意気投合した、大隈八太郎(重信)と山口範蔵(尚芳)。
大隈は西暦でいえば1838年生まれ、山口は1歳年下のようですから、この頃は2人とも、まだ20代前半の若者ということになります。

多良海道で村娘たちの歌声につられて、寄り道が過ぎたのか、肥前浜の宿場(現在の佐賀県鹿島市)近くで、日暮れを迎えてしまったようです。
――佐賀藩では、鹿島の支藩が治める一帯の宿場町…の近く。
「にゃ~、日の暮れおったばい。」
「いささか、話し込みが過ぎましたね。」
すっかり、秋の陽は水平線に潜っており、すでに月が姿を見せている。大隈と山口は暗くなった道中で、顔を見合わせる。

「大隈さん。私は、まだ話し足らんとです。」
「そいは、おいも同じばい。どうね、肥前浜の宿場でも少し飲まんね。」
「よかですね!大いに国事を論じましょう。」
「よか。今日は、愉快たい。」
――肥前浜の宿場。賑わう旅籠(はたご)の2階にて。
近隣の部屋から、わいわいと、酒を飲んでいる者たちの声が聞こえる。
「おお、美味か酒とよ!染みるばい。」
「この辺りのは、佐賀の酒でも上物ばい。味わって飲まんね!」
街道を行き交う人々の憩いとして、絶賛される地元の銘酒。米も水も豊かな、佐賀。皆、上機嫌で、当地の夜に酔いしれている様子だ。

――窓辺からは、秋の月が涼やかな姿を見せている。
「では、大隈さん。さっそく我らも、肥前浜の酒を少々いただきますか。」
「よかね~、山口さん。」
「…ですが、我らの話は、勤王の志高いもの。酔いも程よかところで。」
「…よかごた。」
この山口範蔵という男。気障(きざ)かと思えば、変に真面目なところがある。

――賑わう旅籠の中、山口の妙に慎重な態度。
大隈も、ひそひそ話を余儀なくされている。
「そいぎ、江藤さんは、京で公家とも関わっとったとよ。」
「そがんですか。その江藤さんという方は、国を抜けて京に!」
ところが、山口の方から、急に大きな声を出す。
「…“秘密の話”ば、しとるんじゃなかとね!」
大隈が、呆れて制止する。さすがに「佐賀からの脱藩」の話を大声で復唱されては、まずい。

「…失礼。この山口範蔵、いたく感銘を受けました。」
勤王の話をできるのは、大隈も喜んでいる。だが、西洋にかぶれているせいなのか。山口の反応は、わりと大げさなのだ。
山口は、あたかも“佐賀の風”のように、爽やかに言い放った。
「大隈さん。続けてくれんですか。」
――山口の真剣なまなざし。“勤王”を志すというのは本気らしい。
「よか。そん江藤さんが、佐賀に帰ってきてしまったとよ。」
「なしてですか!せっかく、京の貴き方々とも、お会いできっとのに!」
「そうたい。戻ってきたのは、よかばってん。命も危うか。」
「そんお人は、一度、国を抜けてますからね。」

当時、佐賀では“脱藩”は重罪であり、江藤の志が認められても、名誉だけは保っての切腹を命ぜられる可能性も残る。
「志ば持って、京で気張っとたのに、勿体(もったい)なか。」
大隈が残念がる。
「そがんです。江藤さん、なして戻ってきたとですか!」
江藤をよく知らないはずの山口までが、酔いに任せて残念がる。
――大隈は、勢いづけに肥前の美酒をあおった。
もう、山口の反応が目立つのを気にしていては疲れる。存分に語ろう。
「あーうまか酒ばい。山口さんね、おいも、そがん思うとよ。」
「…ですよね。大隈さん。」
このように、大隈と山口の話で「なぜ、佐賀に帰ってきた」と話題に挙がった江藤新平は、佐賀城下で謹慎中だ。
江藤は、自身の連れ戻しが実父にも命ぜられ、京の都に居続けるのも難しく、大殿・鍋島直正に情勢を伝えるためにと、命懸けで帰藩していた。

だが、大隈ましてや武雄領の山口には、そこまでの仔細(しさい)は伝わっていない。ここでは、諸処の酒場に見られる“外野”の噂話のようなものだ。
「大隈さん、いや、八太郎さんと呼んだらよかですか。」
「山口さん…、あーもう“範蔵”とか言ってもよかね。」
酒が回ってきたのか、意気投合から馴れ合いの段階に移ってきている。これは、楽しい夜だ。
――恐るべき、“佐賀の酒”の力と言うべきか。
「ようし、範蔵!よう聞かんね。今から取っておきの話をするばい!」
「八太郎さん!待ってました。」
しかし、この辺りが盛り上がりの頂だった。ここで、急に大隈が“ひそひそ話”に戻ると宣言する。
「…ばってん、こん話は小声に戻るばい。実は、大殿が…」
「佐賀の大殿が…?小声でよかです。大声は慎みます。」

志は高いものの、振る舞いは常識人の山口範蔵である。
もちろん大殿・鍋島直正の動向は、佐賀藩の機密事項。京の都に向かう予定を知っているのだが、大隈も顔を寄せての密談とするつもりのようだ。
(続く)
前回ですっかり意気投合した、大隈八太郎(重信)と山口範蔵(尚芳)。
大隈は西暦でいえば1838年生まれ、山口は1歳年下のようですから、この頃は2人とも、まだ20代前半の若者ということになります。
多良海道で村娘たちの歌声につられて、寄り道が過ぎたのか、肥前浜の宿場(現在の佐賀県鹿島市)近くで、日暮れを迎えてしまったようです。
――佐賀藩では、鹿島の支藩が治める一帯の宿場町…の近く。
「にゃ~、日の暮れおったばい。」
「いささか、話し込みが過ぎましたね。」
すっかり、秋の陽は水平線に潜っており、すでに月が姿を見せている。大隈と山口は暗くなった道中で、顔を見合わせる。
「大隈さん。私は、まだ話し足らんとです。」
「そいは、おいも同じばい。どうね、肥前浜の宿場でも少し飲まんね。」
「よかですね!大いに国事を論じましょう。」
「よか。今日は、愉快たい。」
――肥前浜の宿場。賑わう旅籠(はたご)の2階にて。
近隣の部屋から、わいわいと、酒を飲んでいる者たちの声が聞こえる。
「おお、美味か酒とよ!染みるばい。」
「この辺りのは、佐賀の酒でも上物ばい。味わって飲まんね!」
街道を行き交う人々の憩いとして、絶賛される地元の銘酒。米も水も豊かな、佐賀。皆、上機嫌で、当地の夜に酔いしれている様子だ。
――窓辺からは、秋の月が涼やかな姿を見せている。
「では、大隈さん。さっそく我らも、肥前浜の酒を少々いただきますか。」
「よかね~、山口さん。」
「…ですが、我らの話は、勤王の志高いもの。酔いも程よかところで。」
「…よかごた。」
この山口範蔵という男。気障(きざ)かと思えば、変に真面目なところがある。
――賑わう旅籠の中、山口の妙に慎重な態度。
大隈も、ひそひそ話を余儀なくされている。
「そいぎ、江藤さんは、京で公家とも関わっとったとよ。」
「そがんですか。その江藤さんという方は、国を抜けて京に!」
ところが、山口の方から、急に大きな声を出す。
「…“秘密の話”ば、しとるんじゃなかとね!」
大隈が、呆れて制止する。さすがに「佐賀からの脱藩」の話を大声で復唱されては、まずい。
「…失礼。この山口範蔵、いたく感銘を受けました。」
勤王の話をできるのは、大隈も喜んでいる。だが、西洋にかぶれているせいなのか。山口の反応は、わりと大げさなのだ。
山口は、あたかも“佐賀の風”のように、爽やかに言い放った。
「大隈さん。続けてくれんですか。」
――山口の真剣なまなざし。“勤王”を志すというのは本気らしい。
「よか。そん江藤さんが、佐賀に帰ってきてしまったとよ。」
「なしてですか!せっかく、京の貴き方々とも、お会いできっとのに!」
「そうたい。戻ってきたのは、よかばってん。命も危うか。」
「そんお人は、一度、国を抜けてますからね。」
当時、佐賀では“脱藩”は重罪であり、江藤の志が認められても、名誉だけは保っての切腹を命ぜられる可能性も残る。
「志ば持って、京で気張っとたのに、勿体(もったい)なか。」
大隈が残念がる。
「そがんです。江藤さん、なして戻ってきたとですか!」
江藤をよく知らないはずの山口までが、酔いに任せて残念がる。
――大隈は、勢いづけに肥前の美酒をあおった。
もう、山口の反応が目立つのを気にしていては疲れる。存分に語ろう。
「あーうまか酒ばい。山口さんね、おいも、そがん思うとよ。」
「…ですよね。大隈さん。」
このように、大隈と山口の話で「なぜ、佐賀に帰ってきた」と話題に挙がった江藤新平は、佐賀城下で謹慎中だ。
江藤は、自身の連れ戻しが実父にも命ぜられ、京の都に居続けるのも難しく、大殿・鍋島直正に情勢を伝えるためにと、命懸けで帰藩していた。
だが、大隈ましてや武雄領の山口には、そこまでの仔細(しさい)は伝わっていない。ここでは、諸処の酒場に見られる“外野”の噂話のようなものだ。
「大隈さん、いや、八太郎さんと呼んだらよかですか。」
「山口さん…、あーもう“範蔵”とか言ってもよかね。」
酒が回ってきたのか、意気投合から馴れ合いの段階に移ってきている。これは、楽しい夜だ。
――恐るべき、“佐賀の酒”の力と言うべきか。
「ようし、範蔵!よう聞かんね。今から取っておきの話をするばい!」
「八太郎さん!待ってました。」
しかし、この辺りが盛り上がりの頂だった。ここで、急に大隈が“ひそひそ話”に戻ると宣言する。
「…ばってん、こん話は小声に戻るばい。実は、大殿が…」
「佐賀の大殿が…?小声でよかです。大声は慎みます。」
志は高いものの、振る舞いは常識人の山口範蔵である。
もちろん大殿・鍋島直正の動向は、佐賀藩の機密事項。京の都に向かう予定を知っているのだが、大隈も顔を寄せての密談とするつもりのようだ。
(続く)
2024年04月22日
第20話「長崎方控」⑤(京の冬と、大殿の葛藤)
こんばんは。さて、結構長い“ひと呼吸”を置きましたが、“本編”に戻ります。
前回からの舞台、長崎街道の宿場町・肥前浜は、鹿島藩(佐賀藩の支藩)の経済を支えた町だと聞きます。
〔参照:第20話「長崎方控」④(肥前浜の“酔客”)〕
現在でも、佐賀の銘酒が造られる酒蔵の通りは、旅番組などにも向いた“映える”景色という印象。

すっかり気分良く酔いの回った大隈八太郎(重信)と山口範蔵(尚芳)ですが、大殿・鍋島直正(閑叟)の動向を語るに、少し真面目な顔になっています。
設定は文久二年(1862年)の晩秋から冬。現在の季節感と、ほぼ逆転してしまいました。今回は途中で秋の肥前浜宿から、冬の京都に場面転換します。
――ひそひそと話を切り出す、大隈。
だいぶ、山口と顔が近い。ほとんど、耳打ちをする様子である。
「範蔵さん…閑叟さまは、京に向かうとよ。」
「えっ、そがんですか!」
「ここは、宿場町たい。大声はいかんばい。」
大隈は、山口に念を押した。
そこまで、周囲の聞き耳が気になるのなら、話さなければいいのに…と思うが、よほど「言いたいことがある」らしい。
「心得ました。話ば続けてくれんですか。」
「そいぎ、言わせてもらうばい。」

――そして、大隈八太郎の“言いたいこと”は、こうだった。
「京の都に行くだけじゃなかと。閑叟さまは、“参内”ばなさるとよ。」
そう語る大隈は得意気だった。
「参内(さんだい)…?み…帝(みかど)に拝謁なさると?ふごっ…」
山口も小さく聞き返したが、大隈はあらかじめ口を押さえにかかっていた。
「そうたい。」
「八太郎さん…そがん、口ば押さえんでも、わかりますけん。」
山口はこう言うが、“帝”と言葉にしてしまうあたり、やはり冷静さを欠いている。それだけ、大きいお知らせなのだ。

時折、大隈は、蘭学の講義を命じられて、前藩主である鍋島直正(閑叟)の傍に寄る機会があるから、かなりの情報が得られる。
――大殿・鍋島直正(閑叟)は、西洋への興味の持ち方が深いから、
大隈にしたら、まだ準備していないところまで「続きを訳せ」とか言ってくるし、質問も鋭くて大変なのだが、それだけの値打ちがある蘭学講師の役回りだ。
「…ついに、佐賀が表舞台に立つ時ばい。」
大隈、気持ちが抑えられないのか、とりあえず立ち上がった。
「その時は、武雄のご隠居も、大殿とともに!」
ついで、山口も立ち上がった。
――山口にすれば自身を見い出してくれた、先の武雄領主・鍋島茂義。
大殿・鍋島直正の“兄貴分”でもあるし、佐賀が表舞台に出れば、きっと武雄の茂義公も並んで立つことだろう。そう思うだけで、山口には誇らしい。

2人の若者の心は、沸き立っていた。佐賀藩の力で、朝廷を中心とした秩序を先導して、日本の各地から英知を結集し、西洋に負けない国を作るのだと。
端から見れば、若い酔っぱらいの2人だが、その心は国事への奔走を決めた、まさに“志士”であった。
――同じく文久二年、師走(旧暦十二月)。冬の京都。
第19話の終盤に、時を戻す。佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)の一行は、京の市街地の北東にある、黒谷の真如堂を宿所としていた。
地元・佐賀で、熱くたぎる若者たちの視線が、その大殿に注がれる中、京への出立は、予定より遅く冬の手前となった。
そして、たしかに大隈や山口に期待されていたように、帝(孝明天皇)に拝謁する段取りも整っていた。

――しかし、若者たちの期待とは、ほど遠い状況がそこにはあった。
たしかに、鍋島直正(閑叟)の一行は佐賀を発ってから、北九州から蒸気船を使って大坂に入港し、すみやかに京都へと進んだ。
だが、実のところ、胃痛や痔疾に苦しみ、主に消化器系に多くの故障を抱えており、出立そのものも危うかったのだ。
〔参照(中盤):第19話「閑叟上洛」⑭(急ぐ理由と、動けぬ事情)〕

「肥後(熊本)の細川から、ご挨拶にとの申し入れが。」
鍋島直正への熱視線は、何も地元の若者だけではなく、各地の大名からも注がれていた。
「…うむ。閑叟さま、いかがいたしましょう。」
難しい顔をするのは、鍋島直正の幼少期からの側近・古川与一(松根)。
「肥後…、細川家とは、親しくしておきたいのだがな。」
京では、どうしても外せない行事がある。御所へ参内する日程が最優先だ。
――そこで体調を崩し、参内できないなどあってはならない。
温暖な佐賀平野に比べれば、京の冬には、しんしんとした底冷えを感じる。

取り次ぎ役が、今度は少々遠慮しながら言上した。
「…宇和島(愛媛)の伊達さまは、直々に面会をお望みのようで…」
「…うむ、大殿。いまは難しいでしょうな。」
――大殿・直正(閑叟)の状態をよく知る、古川が先に答えを出した。
「伊達どのとも、話をしておきたいのだがな…」
直正は、ぽつりと語ると、少し悔しそうな顔を見せた。宇和島の伊達宗城も、西洋の技術に関心を持つ殿様として評判がある。

もはや若き日は遠く、あちこち身体を損なって、思うようには動けない。もどかしくも、これが佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)の今の姿だった。
直正の体調不良は、その行動を予測しづらくした。その意図を深読みする者も多く、各地の大名から志士までに疑心を起こさせる事になる。
(続く)
○参考記事〔本編〕
・第19話「閑叟上洛」㉔(御所へと参じる日)
前回からの舞台、長崎街道の宿場町・肥前浜は、鹿島藩(佐賀藩の支藩)の経済を支えた町だと聞きます。
〔参照:
現在でも、佐賀の銘酒が造られる酒蔵の通りは、旅番組などにも向いた“映える”景色という印象。
すっかり気分良く酔いの回った大隈八太郎(重信)と山口範蔵(尚芳)ですが、大殿・鍋島直正(閑叟)の動向を語るに、少し真面目な顔になっています。
設定は文久二年(1862年)の晩秋から冬。現在の季節感と、ほぼ逆転してしまいました。今回は途中で秋の肥前浜宿から、冬の京都に場面転換します。
――ひそひそと話を切り出す、大隈。
だいぶ、山口と顔が近い。ほとんど、耳打ちをする様子である。
「範蔵さん…閑叟さまは、京に向かうとよ。」
「えっ、そがんですか!」
「ここは、宿場町たい。大声はいかんばい。」
大隈は、山口に念を押した。
そこまで、周囲の聞き耳が気になるのなら、話さなければいいのに…と思うが、よほど「言いたいことがある」らしい。
「心得ました。話ば続けてくれんですか。」
「そいぎ、言わせてもらうばい。」
――そして、大隈八太郎の“言いたいこと”は、こうだった。
「京の都に行くだけじゃなかと。閑叟さまは、“参内”ばなさるとよ。」
そう語る大隈は得意気だった。
「参内(さんだい)…?み…帝(みかど)に拝謁なさると?ふごっ…」
山口も小さく聞き返したが、大隈はあらかじめ口を押さえにかかっていた。
「そうたい。」
「八太郎さん…そがん、口ば押さえんでも、わかりますけん。」
山口はこう言うが、“帝”と言葉にしてしまうあたり、やはり冷静さを欠いている。それだけ、大きいお知らせなのだ。
時折、大隈は、蘭学の講義を命じられて、前藩主である鍋島直正(閑叟)の傍に寄る機会があるから、かなりの情報が得られる。
――大殿・鍋島直正(閑叟)は、西洋への興味の持ち方が深いから、
大隈にしたら、まだ準備していないところまで「続きを訳せ」とか言ってくるし、質問も鋭くて大変なのだが、それだけの値打ちがある蘭学講師の役回りだ。
「…ついに、佐賀が表舞台に立つ時ばい。」
大隈、気持ちが抑えられないのか、とりあえず立ち上がった。
「その時は、武雄のご隠居も、大殿とともに!」
ついで、山口も立ち上がった。
――山口にすれば自身を見い出してくれた、先の武雄領主・鍋島茂義。
大殿・鍋島直正の“兄貴分”でもあるし、佐賀が表舞台に出れば、きっと武雄の茂義公も並んで立つことだろう。そう思うだけで、山口には誇らしい。
2人の若者の心は、沸き立っていた。佐賀藩の力で、朝廷を中心とした秩序を先導して、日本の各地から英知を結集し、西洋に負けない国を作るのだと。
端から見れば、若い酔っぱらいの2人だが、その心は国事への奔走を決めた、まさに“志士”であった。
――同じく文久二年、師走(旧暦十二月)。冬の京都。
第19話の終盤に、時を戻す。佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)の一行は、京の市街地の北東にある、黒谷の真如堂を宿所としていた。
地元・佐賀で、熱くたぎる若者たちの視線が、その大殿に注がれる中、京への出立は、予定より遅く冬の手前となった。
そして、たしかに大隈や山口に期待されていたように、帝(孝明天皇)に拝謁する段取りも整っていた。
――しかし、若者たちの期待とは、ほど遠い状況がそこにはあった。
たしかに、鍋島直正(閑叟)の一行は佐賀を発ってから、北九州から蒸気船を使って大坂に入港し、すみやかに京都へと進んだ。
だが、実のところ、胃痛や痔疾に苦しみ、主に消化器系に多くの故障を抱えており、出立そのものも危うかったのだ。
〔参照(中盤):
「肥後(熊本)の細川から、ご挨拶にとの申し入れが。」
鍋島直正への熱視線は、何も地元の若者だけではなく、各地の大名からも注がれていた。
「…うむ。閑叟さま、いかがいたしましょう。」
難しい顔をするのは、鍋島直正の幼少期からの側近・古川与一(松根)。
「肥後…、細川家とは、親しくしておきたいのだがな。」
京では、どうしても外せない行事がある。御所へ参内する日程が最優先だ。
――そこで体調を崩し、参内できないなどあってはならない。
温暖な佐賀平野に比べれば、京の冬には、しんしんとした底冷えを感じる。
取り次ぎ役が、今度は少々遠慮しながら言上した。
「…宇和島(愛媛)の伊達さまは、直々に面会をお望みのようで…」
「…うむ、大殿。いまは難しいでしょうな。」
――大殿・直正(閑叟)の状態をよく知る、古川が先に答えを出した。
「伊達どのとも、話をしておきたいのだがな…」
直正は、ぽつりと語ると、少し悔しそうな顔を見せた。宇和島の伊達宗城も、西洋の技術に関心を持つ殿様として評判がある。

もはや若き日は遠く、あちこち身体を損なって、思うようには動けない。もどかしくも、これが佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)の今の姿だった。
直正の体調不良は、その行動を予測しづらくした。その意図を深読みする者も多く、各地の大名から志士までに疑心を起こさせる事になる。
(続く)
○参考記事〔本編〕
・
2024年04月29日
第20話「長崎方控」⑥(“理”の通った、帰藩者)
こんばんは。
文久二年(1862年)冬、十二月の設定です。佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)は京に着くなり、朝廷からの呼びかけに応じて御所に参じました。
この文久二年からの鍋島直正の東上、全体の行程から見ると、江戸への行き帰りの途中で、京都に立ち寄った形になっています。

そして、京に向かった直正(閑叟)の旅路を、皆が気にしている状況です。
しかし、今回の面々は、前回までの大隈八太郎(重信)や山口範蔵(尚芳)とは、少し違った感覚で、大殿の旅路を見つめています。
――佐賀城下。謹慎中となっている江藤新平の屋敷。
2人ほどの仲間うちが、家まで来ている様子だ。
「…謹慎とはいうが、のんびりしたもんだな。」
大木民平(喬任)が、言葉のとおり、あくびでも出そうに語った。
「そがんですね。我らが出入りしても、藩庁の見張りもおりませんし。」
もう1人、坂井辰之允という佐賀藩士も来ている。
「家からは出らんゆえ、特に咎(とが)められてもおらん。」
江藤が、言葉を返す。
さすがに外出は差し控えているようだが、重罪のはずの“脱藩者”の扱いとしては、かなり緩い。

――そして、江藤の処分は、いつ決まるのかもわからない。
大木が拍子抜けするほど、穏やかな日々が続いているのだ。
「ばってん、江藤。こいは、閑叟さまが戻るまでの事かもしれんぞ。」
「そうですよ。原田さまは、手ぐすね引いておられるごたです。」
佐賀藩の保守派で、執政格の実力者・原田小四郎が、通例どおり「脱藩者には、死罪」が相当と主張し続けている。
しかし、江藤の処分が決まる前に、大殿が京へと出立してしまったので、その結論は棚上げとなったようだ。
「原田さまの言いよる事も、先例からは理が通る。」
江藤が答えを返す。神経を尖らせた脱藩の前と違い、かなり落ち着いている。

「おい、江藤よ。お前が原田さまの味方をして、どがん(どう)する。」
ここで大木が、毒づいた。
自身の処刑を主張されているのに、藩の職務に忠実な保守派・原田小四郎について、江藤は意外と悪い印象を持っていないようだ。
――大木が、ふくれっ面をして言葉を継ぐ。
「それじゃ、俺が困るとぞ。中野に続いて、江藤まで失うわけにはいかん。」
大木と江藤が特に懇意にした、中野方蔵は“坂下門外の変”への関与を疑われ、落命している。
「それはそうだな…得心した。」
亡き友・中野の名を聞いて、ここは、江藤も真剣な表情に戻った。

――江藤とて、佐賀藩のために京に出て調べを行ったのだ。
たしかに脱藩はしたが、それだけの情報は持ち帰った。報告書は「京都見聞」としてまとめ、藩庁からの問合せにも、懇切丁寧に回答している。
「…鹿島の殿様は、味方をしてくれるかもしれんです。」
坂井が、何だか希望の見えそうなことを言った。
「鹿島の直彬公か。たしかに、学のある方と聞くぞ。」
大木は、その話を聞いて、少し表情をゆるめた。
佐賀の支藩の1つである鹿島藩主・鍋島直彬。勉強熱心な人物らしく、江藤の報告書のことを知ったのかもしれない。
もし江藤の助命を後押ししてくれれば、裁定の結果にも良い影響が出そうだ。

――だが、江藤は自身の助命より、気にする事がある様子。
「どがんした。お前の話をしとるんだが。さっきから、何ば考えよるか。」
大木は、少し不服そうだ。
江藤には服装からして、自分のことに頓着しないところがある。それが、時々危うさを感じさせるのだ。
次いで、坂井の方が問いかけた。
「江藤さん。京の都が気になるとですか。」
「然(しか)り。閑叟さまのことだ。道ば誤らぬか、憂慮しておる。」
「佐賀の大殿が…道ば、誤ると?」

「京で、“攘夷”を唱える者は、暴論の徒ばかりだった。」
江藤は脱藩から戻った際に、京の都で見聞きした、公家や諸藩の人物評を、大殿・直正に届くように書き送っている。
――欧米列強の実力を知る、佐賀藩だからこそ、
西洋の力量も知らず、考え無しに「攘夷だ!異国打払いだ!」と、叫ぶ者たちに巻き込まれてはまずい。彼らは異人とみれば斬りかかる勢いだ。
京に居た時に、江藤から朝廷への意見書を出したが、まず手順を考えることが大事で、「まず、幕府から外交権を取れ」と記した。
洋学と実務に長じた佐賀藩が関わる必要も、この辺りにある。江藤の策は、「順次、王政復古を行う」と続く。

ところが、いまの朝廷では、幕府に代わって政権を担う人材を求めるのに無理がある。江藤も、その才能を知る者たちから、随分と京に引き留められた。
――京では、大殿・鍋島直正が御所に参じることになるだろう。
江藤は、大隈たちとは違って、今回の上洛に成果を期待しないようだ。
「馬鹿な“巻き添え”ば食らうぐらいなら、参内のみで良いやもしれん。」
「いまの都では、何もわかっとらん者たちが力を持っとる…ということか。」
大木にも、実際に京都を見た江藤が、逆に慎重になった理由がわかってきた。
――簡単に“攘夷”というが、勢いだけでできることではない。
もし、本気で異国を退けるならば、列強に匹敵する国力が必要だ。
「京の都には、大殿をお導きできる者が、誰もおらんばい。」

万一、佐賀藩に直接、異国打払いの命令など出ては、長崎の台場で外国船を砲撃せねばならず、無益で危険な戦いに巻き込まれてしまう。
「此度は、おかしな事にならねば、それでよか。」
江藤は、脱藩前と随分と変わって、達観した感じとなってしまった。
「ばってん…江藤よ、そいでよかとか!」
金策に苦労して脱藩者・江藤を送り出した、大木としては、この状況には、いまいち不満が残るようだ。
(続く)
◎参考記事〔本編〕
○江藤たちの親友・中野方蔵の最期(第17話)
・第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)
・第17話「佐賀脱藩」⑱(青葉茂れる頃に)
○朝廷への意見書、佐賀藩への報告書(第18話)
・第18話「京都見聞」⑳(公卿の評判)
・第18話「京都見聞」⑯(“故郷”を守る者たち)
○江藤を京都に引き留めたかった人々(第19話)
・第19話「閑叟上洛」⑧(“逃げるが勝ち”とも申すのに)
・第19話「閑叟上洛」⑫(新しき御代〔みよ〕に)
文久二年(1862年)冬、十二月の設定です。佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)は京に着くなり、朝廷からの呼びかけに応じて御所に参じました。
この文久二年からの鍋島直正の東上、全体の行程から見ると、江戸への行き帰りの途中で、京都に立ち寄った形になっています。
そして、京に向かった直正(閑叟)の旅路を、皆が気にしている状況です。
しかし、今回の面々は、前回までの大隈八太郎(重信)や山口範蔵(尚芳)とは、少し違った感覚で、大殿の旅路を見つめています。
――佐賀城下。謹慎中となっている江藤新平の屋敷。
2人ほどの仲間うちが、家まで来ている様子だ。
「…謹慎とはいうが、のんびりしたもんだな。」
大木民平(喬任)が、言葉のとおり、あくびでも出そうに語った。
「そがんですね。我らが出入りしても、藩庁の見張りもおりませんし。」
もう1人、坂井辰之允という佐賀藩士も来ている。
「家からは出らんゆえ、特に咎(とが)められてもおらん。」
江藤が、言葉を返す。
さすがに外出は差し控えているようだが、重罪のはずの“脱藩者”の扱いとしては、かなり緩い。

――そして、江藤の処分は、いつ決まるのかもわからない。
大木が拍子抜けするほど、穏やかな日々が続いているのだ。
「ばってん、江藤。こいは、閑叟さまが戻るまでの事かもしれんぞ。」
「そうですよ。原田さまは、手ぐすね引いておられるごたです。」
佐賀藩の保守派で、執政格の実力者・原田小四郎が、通例どおり「脱藩者には、死罪」が相当と主張し続けている。
しかし、江藤の処分が決まる前に、大殿が京へと出立してしまったので、その結論は棚上げとなったようだ。
「原田さまの言いよる事も、先例からは理が通る。」
江藤が答えを返す。神経を尖らせた脱藩の前と違い、かなり落ち着いている。
「おい、江藤よ。お前が原田さまの味方をして、どがん(どう)する。」
ここで大木が、毒づいた。
自身の処刑を主張されているのに、藩の職務に忠実な保守派・原田小四郎について、江藤は意外と悪い印象を持っていないようだ。
――大木が、ふくれっ面をして言葉を継ぐ。
「それじゃ、俺が困るとぞ。中野に続いて、江藤まで失うわけにはいかん。」
大木と江藤が特に懇意にした、中野方蔵は“坂下門外の変”への関与を疑われ、落命している。
「それはそうだな…得心した。」
亡き友・中野の名を聞いて、ここは、江藤も真剣な表情に戻った。
――江藤とて、佐賀藩のために京に出て調べを行ったのだ。
たしかに脱藩はしたが、それだけの情報は持ち帰った。報告書は「京都見聞」としてまとめ、藩庁からの問合せにも、懇切丁寧に回答している。
「…鹿島の殿様は、味方をしてくれるかもしれんです。」
坂井が、何だか希望の見えそうなことを言った。
「鹿島の直彬公か。たしかに、学のある方と聞くぞ。」
大木は、その話を聞いて、少し表情をゆるめた。
佐賀の支藩の1つである鹿島藩主・鍋島直彬。勉強熱心な人物らしく、江藤の報告書のことを知ったのかもしれない。
もし江藤の助命を後押ししてくれれば、裁定の結果にも良い影響が出そうだ。

――だが、江藤は自身の助命より、気にする事がある様子。
「どがんした。お前の話をしとるんだが。さっきから、何ば考えよるか。」
大木は、少し不服そうだ。
江藤には服装からして、自分のことに頓着しないところがある。それが、時々危うさを感じさせるのだ。
次いで、坂井の方が問いかけた。
「江藤さん。京の都が気になるとですか。」
「然(しか)り。閑叟さまのことだ。道ば誤らぬか、憂慮しておる。」
「佐賀の大殿が…道ば、誤ると?」
「京で、“攘夷”を唱える者は、暴論の徒ばかりだった。」
江藤は脱藩から戻った際に、京の都で見聞きした、公家や諸藩の人物評を、大殿・直正に届くように書き送っている。
――欧米列強の実力を知る、佐賀藩だからこそ、
西洋の力量も知らず、考え無しに「攘夷だ!異国打払いだ!」と、叫ぶ者たちに巻き込まれてはまずい。彼らは異人とみれば斬りかかる勢いだ。
京に居た時に、江藤から朝廷への意見書を出したが、まず手順を考えることが大事で、「まず、幕府から外交権を取れ」と記した。
洋学と実務に長じた佐賀藩が関わる必要も、この辺りにある。江藤の策は、「順次、王政復古を行う」と続く。
ところが、いまの朝廷では、幕府に代わって政権を担う人材を求めるのに無理がある。江藤も、その才能を知る者たちから、随分と京に引き留められた。
――京では、大殿・鍋島直正が御所に参じることになるだろう。
江藤は、大隈たちとは違って、今回の上洛に成果を期待しないようだ。
「馬鹿な“巻き添え”ば食らうぐらいなら、参内のみで良いやもしれん。」
「いまの都では、何もわかっとらん者たちが力を持っとる…ということか。」
大木にも、実際に京都を見た江藤が、逆に慎重になった理由がわかってきた。
――簡単に“攘夷”というが、勢いだけでできることではない。
もし、本気で異国を退けるならば、列強に匹敵する国力が必要だ。
「京の都には、大殿をお導きできる者が、誰もおらんばい。」
万一、佐賀藩に直接、異国打払いの命令など出ては、長崎の台場で外国船を砲撃せねばならず、無益で危険な戦いに巻き込まれてしまう。
「此度は、おかしな事にならねば、それでよか。」
江藤は、脱藩前と随分と変わって、達観した感じとなってしまった。
「ばってん…江藤よ、そいでよかとか!」
金策に苦労して脱藩者・江藤を送り出した、大木としては、この状況には、いまいち不満が残るようだ。
(続く)
◎参考記事〔本編〕
○江藤たちの親友・中野方蔵の最期(第17話)
・
・
○朝廷への意見書、佐賀藩への報告書(第18話)
・
・
○江藤を京都に引き留めたかった人々(第19話)
・
・
2024年05月06日
第20話「長崎方控」⑦(海を渡る、鷹の夢)
こんばんは。“本編”を続けます。文久二年(1862年)からの鍋島直正(閑叟)の東上。当時の体調不良はかなりのもので、無理をおして旅をしたようです。
朝廷、幕府、諸大名…そして、地元の若者たちだけでなく、各地の志士からも注目をされる佐賀の前藩主・直正ですが、思うように動けてはいません。
旧暦の十二月には、どうにか参内して、時の天皇に挨拶を行ったものの、疲れが見える様子です。

その直正の心の支えであっただろう“兄貴分”・鍋島茂義は14歳ばかり年上、前の武雄領主でした。
幕末期、佐賀藩が「近代化のトップランナー」となれたのは、この鍋島茂義が先行して、西洋の文物を取り入れた影響が大きかったとも言われます。
――粉雪の舞う十二月、京の都・黒谷。
御所に参じて、孝明天皇に拝謁し、天杯を授けられる待遇を受けた、佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)。
〔参照:第19話「閑叟上洛」㉔(御所へと参じる日)〕
「閑叟さま、お疲れでしょう。少しお休みください。」
朝廷に招かれるなど稀(まれ)なことだ。側近・古川与一(松根)が労りの言葉をかける。
「おお、松根。すまんな。そのように、いたそう。」
体調も良くない直正だが、御所に出向くのはひと苦労の様子だ。
「座敷は、暖かくしておきましたゆえ。」
「それは、ありがたいのう…」
ほどなく、直正はうとうととして、いささか眠くなってきたようだ。

――歳月を経て、衰えた身体。もはや、自在とは言えぬ…
幼い頃は、その身から溢れんばかりの“元気”があり、その目から見えるものにも“力”があった。
ところで、鍋島直正の幼名は貞丸といった。有力大名・鍋島家の嫡男なので、江戸からは出られず、江戸育ちの“都会っ子”だった。
そして、“家庭教師”を務めていたのは、佐賀藩の儒学者・古賀穀堂。
「若君は利発じゃ。これは…学べば学ぶほど伸びられるぞっ!」と、古賀先生が喜んだ顔を見せるので、幼少の直正(貞丸)も、いっそう頑張った。
〔参照(後半):第1話「長崎警護」⑦〕

「…穀堂の期待にこたえるのも、楽ではないのう…」
現代で言えば、まだ小学校低学年か、幼い貞丸は、ぽつりとつぶやいた。
「若君、まだまだ“お若い”のにお疲れか。」
ちょっと、くだけた感じの物言いで、声をかけてきた少年がいた。
こちらも佐賀藩の重臣となるべく、見聞を広めることを期待されてか、江戸にもよく来ている、武雄領主の息子・十左衞門だった。
――幼い若君・貞丸の表情が、パッと明るくなった。
「十左(じゅうざ)ではないか!江戸に来ておったのか。」
「あぁ、おいは江戸より、長崎の方が良かけどもな。」
「なにゆえ、長崎が良いのか。」
「若はまだ幼いゆえ、わかるかのう。長崎には、海の向こうの物が来る。」
「阿蘭陀(オランダ)渡りの品かの。」
「…!若君、よぅ知っとるな。よか事ぞ。」
今度は、十左衞門少年が嬉しそうな表情を見せた。

この十左衞門が、のちに“蘭癖”と呼ばれ、佐賀藩が西洋の技術を取り入れることを先導する、武雄領主・鍋島茂義となる。
〔参照:第2話「算盤大名」②-2〕
――「あっ、」という感じで、貞丸が何かに気付いた。
「そうじゃ、十左。余(よ)に、鷹の絵を描いてほしい。」
「たか…?空を飛ぶ、鷹か。ご所望ならば、そのうち描くとしよう。」
十左衞門は西洋好きなだけではなく、絵画も学ぶなど、なかなか多才なのだ。
そんな、お願いをしながら、貞丸は、十左衞門をじっと見つめた。
「…いま描いてほしい、と言いよるか?」
貞丸は、「うん」と大きくうなずいた。
「んにゃ…、これから学問の時間なのだが。」
豪放でさばさばとした十左衞門だが、予定もあるので、少し面食らっている。だが、純真な子ども、しかも若君のお願いである。むげにはできない。

「よか。しばし待たれよ!」
十左衞門、鷹の絵を描くつもりのようだ。
――筆と硯(すずり)を手元にそろえて、
「よいか、刻が無いゆえ、此度は、即興になるぞ。」
ぐっと、紙を見つめる十左衞門。後年の茂義が、西洋の文物を見る時と同じ、前のめりな集中力がある。
「いざ、」
ザッと紙に筆を押さえつけた、十左衞門。さらさらと、鳥の輪郭を描き出す。
「おおっ…」
貞丸も食い入るように、墨を走らせる十左衞門の筆先を見つめる。

鳥の輪郭は、やがて鷹の姿を現した。風を切り、雲を背に舞っていく。
「…!」
その鷹を描き出しているはずの十左衞門。先ほどまで筆先を見ていたはずの、貞丸の視線の変化に気付く。
「上を見とらす…」
――若君・貞丸は大空を見上げていた。
「十左、見事じゃ。天晴(あっぱ)れな鷹の姿よ。」
紙と空に交互に視線を送りながら、十左衞門は唖然としていた。
「…これは、まるで絵から抜け出たごた…」
「鷹は、海も越えて飛ぶと聞くぞ。」
貞丸が満面の笑みを見せた。

「いずれは余も、行ってみたい。海の向こうへ。」
「若君、それはわしもだ。海ば渡ってみたい。」
十左衞門、若き茂義は思った。
「この若君なら大丈夫だ。行けるぞ、佐賀が日本を引っ張る日も必ず来る」と。
――そして、この若君、貞丸が殿様になる時まで、
まずは自分が頑張らねば…と強く感じた。
「十左、いかがしたのだ…?」
「若、また、鷹の絵は描きますぞ。」
「そうじゃな。楽しみにしておる。」
貞丸は、嬉しそうに答えを返した。
「そして、わしは今から勉学に、励んで参りますぞ。」
えらく気合いが入っている、十左衞門。
「若君も、励みなされ。」
「…励むぞ。がんばる。」
未来への希望を得たか、異様な迫力をまとった十左衞門(茂義)。貞丸(直正)には、その時の茂義の決意までは感じとれていなかった。
――だが、とても大きく見えた、茂義の背中を見送った。
「…おお、いかんいかん。すっかり寝入ってしまった。」
ここで、直正は夢から覚めた。かつて貞丸と呼ばれていた頃から、既に40年ばかりの歳月が流れている。
残念ながら、いまの直正(閑叟)に、往時の元気な若君の面影は乏しい。

…と、その時。粉雪に冷え込む廊下に、けたたましい足音がした。
「お休み中、失礼を。申し上げたき事が。」
「構わぬ。申せ。」
「…武雄のご隠居さまが、身罷(みまか)られました。」
その一報に接して、直正の心の中にあった“兄貴分”・茂義の背中が、ふっと見えなくなる。
大きな存在で隠れていた断崖が、急に眼前に現われたような感覚が生じた。
(続く)
朝廷、幕府、諸大名…そして、地元の若者たちだけでなく、各地の志士からも注目をされる佐賀の前藩主・直正ですが、思うように動けてはいません。
旧暦の十二月には、どうにか参内して、時の天皇に挨拶を行ったものの、疲れが見える様子です。
その直正の心の支えであっただろう“兄貴分”・鍋島茂義は14歳ばかり年上、前の武雄領主でした。
幕末期、佐賀藩が「近代化のトップランナー」となれたのは、この鍋島茂義が先行して、西洋の文物を取り入れた影響が大きかったとも言われます。
――粉雪の舞う十二月、京の都・黒谷。
御所に参じて、孝明天皇に拝謁し、天杯を授けられる待遇を受けた、佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)。
〔参照:
「閑叟さま、お疲れでしょう。少しお休みください。」
朝廷に招かれるなど稀(まれ)なことだ。側近・古川与一(松根)が労りの言葉をかける。
「おお、松根。すまんな。そのように、いたそう。」
体調も良くない直正だが、御所に出向くのはひと苦労の様子だ。
「座敷は、暖かくしておきましたゆえ。」
「それは、ありがたいのう…」
ほどなく、直正はうとうととして、いささか眠くなってきたようだ。

――歳月を経て、衰えた身体。もはや、自在とは言えぬ…
幼い頃は、その身から溢れんばかりの“元気”があり、その目から見えるものにも“力”があった。
ところで、鍋島直正の幼名は貞丸といった。有力大名・鍋島家の嫡男なので、江戸からは出られず、江戸育ちの“都会っ子”だった。
そして、“家庭教師”を務めていたのは、佐賀藩の儒学者・古賀穀堂。
「若君は利発じゃ。これは…学べば学ぶほど伸びられるぞっ!」と、古賀先生が喜んだ顔を見せるので、幼少の直正(貞丸)も、いっそう頑張った。
〔参照(後半):

「…穀堂の期待にこたえるのも、楽ではないのう…」
現代で言えば、まだ小学校低学年か、幼い貞丸は、ぽつりとつぶやいた。
「若君、まだまだ“お若い”のにお疲れか。」
ちょっと、くだけた感じの物言いで、声をかけてきた少年がいた。
こちらも佐賀藩の重臣となるべく、見聞を広めることを期待されてか、江戸にもよく来ている、武雄領主の息子・十左衞門だった。
――幼い若君・貞丸の表情が、パッと明るくなった。
「十左(じゅうざ)ではないか!江戸に来ておったのか。」
「あぁ、おいは江戸より、長崎の方が良かけどもな。」
「なにゆえ、長崎が良いのか。」
「若はまだ幼いゆえ、わかるかのう。長崎には、海の向こうの物が来る。」
「阿蘭陀(オランダ)渡りの品かの。」
「…!若君、よぅ知っとるな。よか事ぞ。」
今度は、十左衞門少年が嬉しそうな表情を見せた。
この十左衞門が、のちに“蘭癖”と呼ばれ、佐賀藩が西洋の技術を取り入れることを先導する、武雄領主・鍋島茂義となる。
〔参照:
――「あっ、」という感じで、貞丸が何かに気付いた。
「そうじゃ、十左。余(よ)に、鷹の絵を描いてほしい。」
「たか…?空を飛ぶ、鷹か。ご所望ならば、そのうち描くとしよう。」
十左衞門は西洋好きなだけではなく、絵画も学ぶなど、なかなか多才なのだ。
そんな、お願いをしながら、貞丸は、十左衞門をじっと見つめた。
「…いま描いてほしい、と言いよるか?」
貞丸は、「うん」と大きくうなずいた。
「んにゃ…、これから学問の時間なのだが。」
豪放でさばさばとした十左衞門だが、予定もあるので、少し面食らっている。だが、純真な子ども、しかも若君のお願いである。むげにはできない。

「よか。しばし待たれよ!」
十左衞門、鷹の絵を描くつもりのようだ。
――筆と硯(すずり)を手元にそろえて、
「よいか、刻が無いゆえ、此度は、即興になるぞ。」
ぐっと、紙を見つめる十左衞門。後年の茂義が、西洋の文物を見る時と同じ、前のめりな集中力がある。
「いざ、」
ザッと紙に筆を押さえつけた、十左衞門。さらさらと、鳥の輪郭を描き出す。
「おおっ…」
貞丸も食い入るように、墨を走らせる十左衞門の筆先を見つめる。
鳥の輪郭は、やがて鷹の姿を現した。風を切り、雲を背に舞っていく。
「…!」
その鷹を描き出しているはずの十左衞門。先ほどまで筆先を見ていたはずの、貞丸の視線の変化に気付く。
「上を見とらす…」
――若君・貞丸は大空を見上げていた。
「十左、見事じゃ。天晴(あっぱ)れな鷹の姿よ。」
紙と空に交互に視線を送りながら、十左衞門は唖然としていた。
「…これは、まるで絵から抜け出たごた…」
「鷹は、海も越えて飛ぶと聞くぞ。」
貞丸が満面の笑みを見せた。
「いずれは余も、行ってみたい。海の向こうへ。」
「若君、それはわしもだ。海ば渡ってみたい。」
十左衞門、若き茂義は思った。
「この若君なら大丈夫だ。行けるぞ、佐賀が日本を引っ張る日も必ず来る」と。
――そして、この若君、貞丸が殿様になる時まで、
まずは自分が頑張らねば…と強く感じた。
「十左、いかがしたのだ…?」
「若、また、鷹の絵は描きますぞ。」
「そうじゃな。楽しみにしておる。」
貞丸は、嬉しそうに答えを返した。
「そして、わしは今から勉学に、励んで参りますぞ。」
えらく気合いが入っている、十左衞門。
「若君も、励みなされ。」
「…励むぞ。がんばる。」
未来への希望を得たか、異様な迫力をまとった十左衞門(茂義)。貞丸(直正)には、その時の茂義の決意までは感じとれていなかった。
――だが、とても大きく見えた、茂義の背中を見送った。
「…おお、いかんいかん。すっかり寝入ってしまった。」
ここで、直正は夢から覚めた。かつて貞丸と呼ばれていた頃から、既に40年ばかりの歳月が流れている。
残念ながら、いまの直正(閑叟)に、往時の元気な若君の面影は乏しい。

…と、その時。粉雪に冷え込む廊下に、けたたましい足音がした。
「お休み中、失礼を。申し上げたき事が。」
「構わぬ。申せ。」
「…武雄のご隠居さまが、身罷(みまか)られました。」
その一報に接して、直正の心の中にあった“兄貴分”・茂義の背中が、ふっと見えなくなる。
大きな存在で隠れていた断崖が、急に眼前に現われたような感覚が生じた。
(続く)
2024年05月14日
第20話「長崎方控」⑧(長く生きた者よ)
こんばんは。
前回は大殿・鍋島直正(閑叟)の幼少期の場面を綴りました。直正の14歳年上の少年として登場した鍋島茂義は、佐賀藩の重役となる立場の武雄領主。
この武雄領も含めた自治領主は、かなりの権限があったので、茂義は幕末の佐賀で“西洋化”を先導する役回りを果たしました。
その頼れる“兄貴分”が逝去したのが、文久二年十一月(旧暦)と聞きます。これは、鍋島直正が京都に出向いていた時期と重なるようです。
この一報を、寒い冬の京都にいたはずの直正がいつ聞いたかは、今のところ不知なのですが、御所に参内した前後では無いか…と考えています。

――文久二年(1862年)の晩秋。佐賀藩の武雄領。
ザッザッザッ…、武雄領の侍が“行進”をする様子で、揃った足音がする。
「ハルト!(止まれ)」
ザッ!動いていた侍たちが、一斉に停止した様子だ。
チャカ、チャカチャカ…その場で、待機した者たちが、長い銃を扱う音が鳴る。
指揮を執る者は、幾つかの号令を発した後、大きくうなずいて一声を発した。
「ヒュール!(撃て)」
――パン、パパン、パン…!乾いた音が響いた。
ザザッ…、チャッ…
ひとしきり発砲した侍たちが、退避の動きを取り、控えていた侍が立ち上がる。
控えの侍たちも、すぐさま、肩に据えた銃を、パパパン…と撃ち始めた。
その場を仕切っていた指揮官、鍋島茂昌(しげはる)は、幾つかの確認を完了すると、「よか!」を大声を上げて、その場を締めた。
ここで行っているのは、軍事訓練のようだ。服装は侍のままだが、装備する銃は最新式、号令はオランダの影響を受けたようだ。

――しばらく後、武雄領の屋敷。
武雄の隠居(前領主)・鍋島茂義は、ひどく体調を崩しているが、この日は小康を得て、のんびりと過ごす様子だ。
老臣が先ほど見た、訓練の風景を茂義に報告している。
「そうか。“銃砲”の鍛錬に励んでおるか。」
「茂昌さまも、ご立派に成られました。」
少々、感慨深そうな老臣だが、茂義は「う~む」と苦い顔をしている。
「はて…、いかがなされましたか。」
「あやつは、“銃砲”にしか興味を持ちよらん。」
――鍋島茂義が、早々に武雄領主を引退したので…
茂昌は幼少期から領主の肩書きを引き継ぐが、実権は茂義にあった。佐賀藩へ欧米列強の技術を取り込むべく、茂義は自由に動ける身分が欲しかった。
「西洋の文明は、もっと深きものよ。」
茂義の世界への興味は、軍事だけでは無かったが、子・茂昌が学ぼうとする範囲は限られている。
「もっと、学んでほしいものだがな。」
「…茂昌さまも、励んでおられますよ。」
現在の武雄領主・鍋島茂昌は、戦に使えそうな西洋の技術にしか、ほとんど関心を持たない。だが、それも努力のうちだと、老臣がかばっている。
「はっはっ…お主は昔から優しか男だったからのう。」
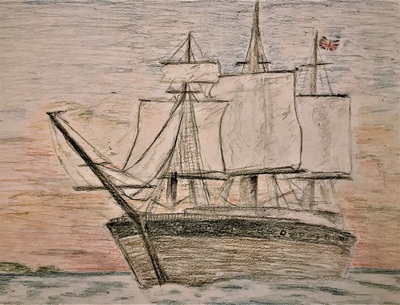
――かれこれ、六十余年の歳月を生きてきた。
幼き日に聞いた「英国の軍艦が長崎の港で暴れた」ことを。佐賀藩が幕府から咎められた、フェートン号事件の時、茂義はまだ子どもだった。
それから異国と戦うには、異国の力を知る必要があると思った。だが、調べれば調べるほどに“西洋”には惹かれていった。
実用的な理化学だけでなく、飲食物・嗜好品・絵画…何でも面白く感じた。
「そういえば、山口が、“小言”を申してきおった。」
「山口範蔵ですか?何ば言いよったのですか。」

武雄領から長崎に派遣し、英語も学ばせている、山口範蔵(尚芳)。先日に、何やら慌てて武雄に帰ってきた。
「異国に興味を持たなくなれば、儂(わし)は、儂でなくなるそうだ。」
「…なんと、無礼な。山口も随分なことを申しますな!」
老臣が怒ったが、茂義は「当たっておる」とばかりに、からからと笑った。
――この年、茂義は大好きな“西洋の文物”の注文を抑えていた。
茂義の“お買い物”が途切れていることが、山口を心配させたようだ。
「もはや、この世から去る者が、あまり買い物をしてもな。」
茂義が、そう語る目はどこか寂しそうだった。老臣には、かける言葉がない。
「儂は“長生き”をしたのだろうか。それだけ多くのことを為したか…」
「…しましたとも!武雄の働きあって、いまの佐賀の力はあるとです!」
老臣が若かった頃のように、声を張る。
「お主は、優しいからな…」
「いえ、たとえ、平山が見ておっても同じように申すはず。」
「おおっ、平山か。“平山山平”か。」
茂義が、少し愉快そうな顔をした。

――かつて、茂義が重用した“平山醇左衛門”という家来がいた。
長崎で西洋式の砲術を学んで、それを茂義に伝える仕事もしていた。平山の熱心な指導もあって、茂義は高島流砲術の免許皆伝を許された。
茂義も、平山が長崎から帰ってくるのを楽しみにするから、「平山、平山…」と言い過ぎて、“平山山平”と呼んでしまっていた事もある。
「いや、平山は…儂には言いたい事が山ほどあるに相違ない。」
「…そんな、平山も分かっておるはず。」
――かつて天保年間に、西洋の学問が厳しく取り締まられた時期がある。
幕府で権力を持っていた、鳥居耀蔵の執拗なまでの“蘭学”への敵意。オランダ渡りの蘭学が最も盛んだった、佐賀藩も目を付けられていた。
その時、平山醇左衛門は武雄領、そして佐賀藩が追及されないように、一人で“疑い”を背負い込み、切腹により命を落としたのだ。
ここで茂義は、後悔を口にした。
「儂は、蒸気船も作れておらん。まだまだ出来ることがあったはずじゃ。」
「…それは、佐賀の者がきっと成し遂げましょう。」
「そうやもしれぬな。」

――茂義は区切りを付けるように、ふーっと一息を付いた。
「これからも、“小言を申す者”は、大事にいたせ。」
「…はっ。」
短く応えながら、老臣は目に涙を浮かべていた。
「そろそろ儂は、平山から“小言”をもらってくるとするか。」
「…きっと、労(ねぎら)いの言葉もありましょう。」
「では、茂昌を頼んだぞ。山口範蔵にもよろしく伝えてくれ。」
幕末の黎明期より近代への扉を開いてきた、佐賀藩武雄領主・鍋島茂義は文久二年十一月二十七日に、この世を去ったと記される。
そして、茂義が購入した西洋の文物を書き留めた買い物帳『長崎方控』も、この年の記録で終わっている。
(続く)
◎参考記事〔本編〕
○鍋島茂義と家臣の場面(第2話)
・第2話「算盤大名」②-1
・第2話「算盤大名」②-2
○蘭学の弾圧(第3話)
・第3話「西洋砲術」④-1
○平山醇左衛門の最期(第3話)
・第3話「西洋砲術」④-2
・第3話「西洋砲術」⑤
○山口範蔵(尚芳)の心配(第20話)
・第20話「長崎方控」③(西洋風の“紳士”)
前回は大殿・鍋島直正(閑叟)の幼少期の場面を綴りました。直正の14歳年上の少年として登場した鍋島茂義は、佐賀藩の重役となる立場の武雄領主。
この武雄領も含めた自治領主は、かなりの権限があったので、茂義は幕末の佐賀で“西洋化”を先導する役回りを果たしました。
その頼れる“兄貴分”が逝去したのが、文久二年十一月(旧暦)と聞きます。これは、鍋島直正が京都に出向いていた時期と重なるようです。
この一報を、寒い冬の京都にいたはずの直正がいつ聞いたかは、今のところ不知なのですが、御所に参内した前後では無いか…と考えています。

――文久二年(1862年)の晩秋。佐賀藩の武雄領。
ザッザッザッ…、武雄領の侍が“行進”をする様子で、揃った足音がする。
「ハルト!(止まれ)」
ザッ!動いていた侍たちが、一斉に停止した様子だ。
チャカ、チャカチャカ…その場で、待機した者たちが、長い銃を扱う音が鳴る。
指揮を執る者は、幾つかの号令を発した後、大きくうなずいて一声を発した。
「ヒュール!(撃て)」
――パン、パパン、パン…!乾いた音が響いた。
ザザッ…、チャッ…
ひとしきり発砲した侍たちが、退避の動きを取り、控えていた侍が立ち上がる。
控えの侍たちも、すぐさま、肩に据えた銃を、パパパン…と撃ち始めた。
その場を仕切っていた指揮官、鍋島茂昌(しげはる)は、幾つかの確認を完了すると、「よか!」を大声を上げて、その場を締めた。
ここで行っているのは、軍事訓練のようだ。服装は侍のままだが、装備する銃は最新式、号令はオランダの影響を受けたようだ。

――しばらく後、武雄領の屋敷。
武雄の隠居(前領主)・鍋島茂義は、ひどく体調を崩しているが、この日は小康を得て、のんびりと過ごす様子だ。
老臣が先ほど見た、訓練の風景を茂義に報告している。
「そうか。“銃砲”の鍛錬に励んでおるか。」
「茂昌さまも、ご立派に成られました。」
少々、感慨深そうな老臣だが、茂義は「う~む」と苦い顔をしている。
「はて…、いかがなされましたか。」
「あやつは、“銃砲”にしか興味を持ちよらん。」
――鍋島茂義が、早々に武雄領主を引退したので…
茂昌は幼少期から領主の肩書きを引き継ぐが、実権は茂義にあった。佐賀藩へ欧米列強の技術を取り込むべく、茂義は自由に動ける身分が欲しかった。
「西洋の文明は、もっと深きものよ。」
茂義の世界への興味は、軍事だけでは無かったが、子・茂昌が学ぼうとする範囲は限られている。
「もっと、学んでほしいものだがな。」
「…茂昌さまも、励んでおられますよ。」
現在の武雄領主・鍋島茂昌は、戦に使えそうな西洋の技術にしか、ほとんど関心を持たない。だが、それも努力のうちだと、老臣がかばっている。
「はっはっ…お主は昔から優しか男だったからのう。」
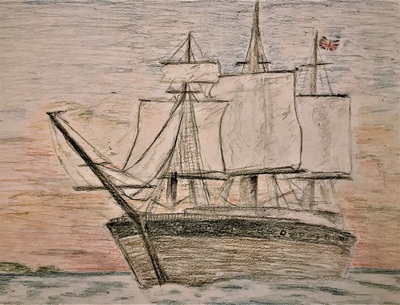
――かれこれ、六十余年の歳月を生きてきた。
幼き日に聞いた「英国の軍艦が長崎の港で暴れた」ことを。佐賀藩が幕府から咎められた、フェートン号事件の時、茂義はまだ子どもだった。
それから異国と戦うには、異国の力を知る必要があると思った。だが、調べれば調べるほどに“西洋”には惹かれていった。
実用的な理化学だけでなく、飲食物・嗜好品・絵画…何でも面白く感じた。
「そういえば、山口が、“小言”を申してきおった。」
「山口範蔵ですか?何ば言いよったのですか。」

武雄領から長崎に派遣し、英語も学ばせている、山口範蔵(尚芳)。先日に、何やら慌てて武雄に帰ってきた。
「異国に興味を持たなくなれば、儂(わし)は、儂でなくなるそうだ。」
「…なんと、無礼な。山口も随分なことを申しますな!」
老臣が怒ったが、茂義は「当たっておる」とばかりに、からからと笑った。
――この年、茂義は大好きな“西洋の文物”の注文を抑えていた。
茂義の“お買い物”が途切れていることが、山口を心配させたようだ。
「もはや、この世から去る者が、あまり買い物をしてもな。」
茂義が、そう語る目はどこか寂しそうだった。老臣には、かける言葉がない。
「儂は“長生き”をしたのだろうか。それだけ多くのことを為したか…」
「…しましたとも!武雄の働きあって、いまの佐賀の力はあるとです!」
老臣が若かった頃のように、声を張る。
「お主は、優しいからな…」
「いえ、たとえ、平山が見ておっても同じように申すはず。」
「おおっ、平山か。“平山山平”か。」
茂義が、少し愉快そうな顔をした。

――かつて、茂義が重用した“平山醇左衛門”という家来がいた。
長崎で西洋式の砲術を学んで、それを茂義に伝える仕事もしていた。平山の熱心な指導もあって、茂義は高島流砲術の免許皆伝を許された。
茂義も、平山が長崎から帰ってくるのを楽しみにするから、「平山、平山…」と言い過ぎて、“平山山平”と呼んでしまっていた事もある。
「いや、平山は…儂には言いたい事が山ほどあるに相違ない。」
「…そんな、平山も分かっておるはず。」
――かつて天保年間に、西洋の学問が厳しく取り締まられた時期がある。
幕府で権力を持っていた、鳥居耀蔵の執拗なまでの“蘭学”への敵意。オランダ渡りの蘭学が最も盛んだった、佐賀藩も目を付けられていた。
その時、平山醇左衛門は武雄領、そして佐賀藩が追及されないように、一人で“疑い”を背負い込み、切腹により命を落としたのだ。
ここで茂義は、後悔を口にした。
「儂は、蒸気船も作れておらん。まだまだ出来ることがあったはずじゃ。」
「…それは、佐賀の者がきっと成し遂げましょう。」
「そうやもしれぬな。」

――茂義は区切りを付けるように、ふーっと一息を付いた。
「これからも、“小言を申す者”は、大事にいたせ。」
「…はっ。」
短く応えながら、老臣は目に涙を浮かべていた。
「そろそろ儂は、平山から“小言”をもらってくるとするか。」
「…きっと、労(ねぎら)いの言葉もありましょう。」
「では、茂昌を頼んだぞ。山口範蔵にもよろしく伝えてくれ。」
幕末の黎明期より近代への扉を開いてきた、佐賀藩武雄領主・鍋島茂義は文久二年十一月二十七日に、この世を去ったと記される。
そして、茂義が購入した西洋の文物を書き留めた買い物帳『長崎方控』も、この年の記録で終わっている。
(続く)
◎参考記事〔本編〕
○鍋島茂義と家臣の場面(第2話)
・
・
○蘭学の弾圧(第3話)
・
○平山醇左衛門の最期(第3話)
・
・
○山口範蔵(尚芳)の心配(第20話)
・




