2020年05月31日
「岐路の剣」
こんばんは。
第10話「蒸気機関」いかがだったでしょうか。当ブログも開始から半年近くを経て、岐路に立っている感じがあります。
今回は、ある佐賀藩士(?)の日常を描く『望郷の剣』シリーズ第3弾です。
――歴史には、様々な分岐点と選択があるようです。
概ね年代順に幕末の歴史を追っているところですが、開国か攘夷かで、すっきり二分される話ではないようです。
例えば、第9話で存在感を見せた、老中・阿部正弘は“雄藩との連携”を目指し、後に登場する大老・井伊直弼は“幕府の主導権”を取り戻しにかかる…と同じ開国派でもかなりの違いがあります。
――現在の佐賀県にまつわる話題で言えば…
長崎新幹線の話合いに応じ、全線のスピード開業を目指すのか。
佐賀県は負担を強いられるだけで、素通りされると警戒するか。
…長崎~武雄温泉間の開業が決まっている以上、動かぬ間にも問題は拡大していくでしょう。ただ、佐賀に一定の力の蓄積が無ければ、後者の心配も否めないところです。
――そして佐賀で分岐点を語るのに相応しい場所を選んでみました。
「肥前山口」駅です。ここでも選択肢が示されます。

長崎に行くのか。
佐世保に向かうのか。
――おそらくは、人生もまた分岐と選択の繰り返し…
「長崎に行くのか、佐世保に向かうのか。それが問題だ…」
実際は佐世保の親戚に会いにいったので、考える余地は無かったのですが、分岐点ならではの「もう1つの道を選んだら…」という感覚は味わえました。
――また「本当に選択肢は2つなのか?」という疑問もあります。
例えば肥前山口駅でそのまま下車。
「江北町を散歩する」という選択を取ることも可能です。
これをブログの方針に例えるなら、日々、呼吸をするぐらいの気持ちで更新するといったところでしょうか。
――私は色々と思うところあり「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と、ひたすらに書き綴っています。
分類上は、一定の目的に向かって走っているタイプのブログになるでしょう。
しかしながら、「さがファンブログ」の諸先輩方には、人生の流れの中で、ごく自然に更新を続けている方も多く見かけます。
『望郷の剣』というシリーズタイトルにかぶせた言い方をすると、あたかも軽妙に剣を遣う“達人”と遭遇した気分になることも、しばしばです。
…力の入り過ぎというのも、また良くないのだな…と思います。
第10話「蒸気機関」いかがだったでしょうか。当ブログも開始から半年近くを経て、岐路に立っている感じがあります。
今回は、ある佐賀藩士(?)の日常を描く『望郷の剣』シリーズ第3弾です。
――歴史には、様々な分岐点と選択があるようです。
概ね年代順に幕末の歴史を追っているところですが、開国か攘夷かで、すっきり二分される話ではないようです。
例えば、第9話で存在感を見せた、老中・阿部正弘は“雄藩との連携”を目指し、後に登場する大老・井伊直弼は“幕府の主導権”を取り戻しにかかる…と同じ開国派でもかなりの違いがあります。
――現在の佐賀県にまつわる話題で言えば…
長崎新幹線の話合いに応じ、全線のスピード開業を目指すのか。
佐賀県は負担を強いられるだけで、素通りされると警戒するか。
…長崎~武雄温泉間の開業が決まっている以上、動かぬ間にも問題は拡大していくでしょう。ただ、佐賀に一定の力の蓄積が無ければ、後者の心配も否めないところです。
――そして佐賀で分岐点を語るのに相応しい場所を選んでみました。
「肥前山口」駅です。ここでも選択肢が示されます。

長崎に行くのか。
佐世保に向かうのか。
――おそらくは、人生もまた分岐と選択の繰り返し…
「長崎に行くのか、佐世保に向かうのか。それが問題だ…」
実際は佐世保の親戚に会いにいったので、考える余地は無かったのですが、分岐点ならではの「もう1つの道を選んだら…」という感覚は味わえました。
――また「本当に選択肢は2つなのか?」という疑問もあります。
例えば肥前山口駅でそのまま下車。
「江北町を散歩する」という選択を取ることも可能です。
これをブログの方針に例えるなら、日々、呼吸をするぐらいの気持ちで更新するといったところでしょうか。
――私は色々と思うところあり「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と、ひたすらに書き綴っています。
分類上は、一定の目的に向かって走っているタイプのブログになるでしょう。
しかしながら、「さがファンブログ」の諸先輩方には、人生の流れの中で、ごく自然に更新を続けている方も多く見かけます。
『望郷の剣』というシリーズタイトルにかぶせた言い方をすると、あたかも軽妙に剣を遣う“達人”と遭遇した気分になることも、しばしばです。
…力の入り過ぎというのも、また良くないのだな…と思います。
2020年05月30日
第10話「蒸気機関」⑩(佐賀の産業革命)
こんばんは。
佐賀藩の理化学研究所“精錬方”(せいれんかた)。
殿・鍋島直正の期待どおり、佐野栄寿(常民)がチームを機能させていきます。今回は、1854年の年明け、ロシアのプチャーチンが長崎を去った直後の話です。
――長崎でロシアとの交渉にあたっていた、幕府の勘定奉行・川路聖謨。
佐賀藩の製砲主任・本島藤太夫に申し入れを行う。
「ロシアとの談判の間、我々を守った“台場”を見せてはもらえぬか。」
「公儀(幕府)にお力添えをいただいた“台場”です。喜んでお見せいたしましょう。」
実際は、ほぼ佐賀藩の独力で作ったのだが、本島は幕府への気遣いも忘れない。
幕府からの借入も含め、台場の築造にかかった費用は、およそ十六万両と言われている。
――川路だけでなく、老中クラスの扱いの筒井も同席している。高位の幕府の役人に、佐賀藩の力を示す好機である。
長崎台場の佐賀藩士たちは、砲術の演習を見せることとなった。
「おおっ、これは見事な。」
築地反射炉で製造した150ポンド砲である。
「では、筒井さま!川路さま!ご高覧あれ!!」

本島は声を張る。佐賀藩の号令はオランダ語である。
「ヒュール!(撃て)」
――ドォン!…爆音とともに、砲弾が標的に飛ぶ。
ほぼ水平に飛んでいく軌道である。
異国船が暴れれば、横っ腹を狙う設計と言ってよい。
ドゴォーン!!
海上に設置した的を破砕する。大きい波しぶきが立つ。
1,500メートルは離れた遠距離の標的に、砲弾が次々に命中する。
大砲の性能もさることながら、佐賀藩の砲兵部隊はよく訓練されていた。
――砲弾は12発中10発の命中。筒井や川路をはじめ、幕府からの参観者が喝采する。
「長崎の守りは、もはや心配なし!」
「肥前佐賀、武威を示す!天晴(あっぱれ)なり!」
のちに川路らが江戸で行った報告により、佐賀藩は幕府から五万両の借金返済を免除される。
長崎台場の築造にかかった費用には遠く及ばないが、名声が高まるのは“武士の誉れ”と言ってよい。
――佐賀城。本島が殿・鍋島直正に報告を行う。

「そうか、本島よ。大儀であった。」
「ははっ!」
「ほう、これは何かのう。」
直正が、報告に添えられた短冊をペラっと捲る。
「殿にお見せするほどのものでは!」
本島、少し慌てる。
――短冊にはこのように綴られていた。
ますら雄が
打つや三五のたまのうらに
砕けぬものはあらじとぞ思ふ
「つい、和歌(うた)を詠んでしまいました。」
本島、その場の勢いで詠んだ一首に照れる。
「瓊浦(たまのうら)と、弾(たま)を掛けたか。お主の誇らしい心持ちがよく伝わるのう。」
直正は、本島の心意気を讃えた。
ちなみに、瓊浦(たまのうら)とは長崎のことである。
――さて、舞台は佐賀城下・多布施に移る。ここには幕府用の反射炉がある。川路の視察は続き、再び本島が案内をする。
「水車か!」
ガラン、ガラン…
多布施川に置かれた水車が廻っている。
「いずれは“蒸気仕掛け”で行いたいのですが、今のところは、“水車(みずぐるま)”にございます。」
この水車小屋は、鉄製大砲の砲身を繰り抜くための工房だった。

――動力源こそ“水力”ではあるが、作業そのものは自動で進む。オートメーション化である。そして、多布施には理化学研究所“精錬方”もある。
コンコン、カン!カン!
「中村さん!これで良いのですか!」
「おおっ、“二代目”はん!上々の出来です。」
科学者・中村奇輔が設計した部品を、二代目“儀右衛門”が手掛ける。
――そして、ドカン!と、作業小屋の近くで轟音がした。
「おい、また爆発しちゃっとるぞ!大丈夫か!」
翻訳に追われる石黒寛次が、突然の轟音に驚く。
「フフフ…石黒さん!何の問題もなか!予定どおりばい…」
「田中さん!ほんまに予定どおりやろな!」
「気にせんでよか。石黒さんは、翻訳ば続けんね!」
――田中久重の不敵な笑み。石黒、度重なる“ドカン!”が気になり、翻訳に集中できない。
「佐野~っ!すごく不安や~」
「心配なかですよ!騒々しかだけです。」
帰ってきた佐野栄寿(常民)。まとめ役となっていた。
「信じるで!ここに居ってもええねんな。」
石黒は、また“翻訳小屋”に引き籠り、洋書と格闘する。
――勘定奉行・川路。“精錬方”の様子が気になるようだ。
「本島どの。向こうも、えらく賑やかだな。」
「あれは“精錬方”にございます。熱心な者たちゆえ、少々騒がしいです。」
本島は、苦笑した。
この頃、日本の近代化を引っ張る“産業革命”は佐賀で進行していた。幕末の佐賀藩には、ヨーロッパの二流国並みの実力はあったと言われている。これは、その始まりの話である。
(第11話「蝦夷探検」に続く)
佐賀藩の理化学研究所“精錬方”(せいれんかた)。
殿・鍋島直正の期待どおり、佐野栄寿(常民)がチームを機能させていきます。今回は、1854年の年明け、ロシアのプチャーチンが長崎を去った直後の話です。
――長崎でロシアとの交渉にあたっていた、幕府の勘定奉行・川路聖謨。
佐賀藩の製砲主任・本島藤太夫に申し入れを行う。
「ロシアとの談判の間、我々を守った“台場”を見せてはもらえぬか。」
「公儀(幕府)にお力添えをいただいた“台場”です。喜んでお見せいたしましょう。」
実際は、ほぼ佐賀藩の独力で作ったのだが、本島は幕府への気遣いも忘れない。
幕府からの借入も含め、台場の築造にかかった費用は、およそ十六万両と言われている。
――川路だけでなく、老中クラスの扱いの筒井も同席している。高位の幕府の役人に、佐賀藩の力を示す好機である。
長崎台場の佐賀藩士たちは、砲術の演習を見せることとなった。
「おおっ、これは見事な。」
築地反射炉で製造した150ポンド砲である。
「では、筒井さま!川路さま!ご高覧あれ!!」

本島は声を張る。佐賀藩の号令はオランダ語である。
「ヒュール!(撃て)」
――ドォン!…爆音とともに、砲弾が標的に飛ぶ。
ほぼ水平に飛んでいく軌道である。
異国船が暴れれば、横っ腹を狙う設計と言ってよい。
ドゴォーン!!
海上に設置した的を破砕する。大きい波しぶきが立つ。
1,500メートルは離れた遠距離の標的に、砲弾が次々に命中する。
大砲の性能もさることながら、佐賀藩の砲兵部隊はよく訓練されていた。
――砲弾は12発中10発の命中。筒井や川路をはじめ、幕府からの参観者が喝采する。
「長崎の守りは、もはや心配なし!」
「肥前佐賀、武威を示す!天晴(あっぱれ)なり!」
のちに川路らが江戸で行った報告により、佐賀藩は幕府から五万両の借金返済を免除される。
長崎台場の築造にかかった費用には遠く及ばないが、名声が高まるのは“武士の誉れ”と言ってよい。
――佐賀城。本島が殿・鍋島直正に報告を行う。

「そうか、本島よ。大儀であった。」
「ははっ!」
「ほう、これは何かのう。」
直正が、報告に添えられた短冊をペラっと捲る。
「殿にお見せするほどのものでは!」
本島、少し慌てる。
――短冊にはこのように綴られていた。
ますら雄が
打つや三五のたまのうらに
砕けぬものはあらじとぞ思ふ
「つい、和歌(うた)を詠んでしまいました。」
本島、その場の勢いで詠んだ一首に照れる。
「瓊浦(たまのうら)と、弾(たま)を掛けたか。お主の誇らしい心持ちがよく伝わるのう。」
直正は、本島の心意気を讃えた。
ちなみに、瓊浦(たまのうら)とは長崎のことである。
――さて、舞台は佐賀城下・多布施に移る。ここには幕府用の反射炉がある。川路の視察は続き、再び本島が案内をする。
「水車か!」
ガラン、ガラン…
多布施川に置かれた水車が廻っている。
「いずれは“蒸気仕掛け”で行いたいのですが、今のところは、“水車(みずぐるま)”にございます。」
この水車小屋は、鉄製大砲の砲身を繰り抜くための工房だった。

――動力源こそ“水力”ではあるが、作業そのものは自動で進む。オートメーション化である。そして、多布施には理化学研究所“精錬方”もある。
コンコン、カン!カン!
「中村さん!これで良いのですか!」
「おおっ、“二代目”はん!上々の出来です。」
科学者・中村奇輔が設計した部品を、二代目“儀右衛門”が手掛ける。
――そして、ドカン!と、作業小屋の近くで轟音がした。
「おい、また爆発しちゃっとるぞ!大丈夫か!」
翻訳に追われる石黒寛次が、突然の轟音に驚く。
「フフフ…石黒さん!何の問題もなか!予定どおりばい…」
「田中さん!ほんまに予定どおりやろな!」
「気にせんでよか。石黒さんは、翻訳ば続けんね!」
――田中久重の不敵な笑み。石黒、度重なる“ドカン!”が気になり、翻訳に集中できない。
「佐野~っ!すごく不安や~」
「心配なかですよ!騒々しかだけです。」
帰ってきた佐野栄寿(常民)。まとめ役となっていた。
「信じるで!ここに居ってもええねんな。」
石黒は、また“翻訳小屋”に引き籠り、洋書と格闘する。
――勘定奉行・川路。“精錬方”の様子が気になるようだ。
「本島どの。向こうも、えらく賑やかだな。」
「あれは“精錬方”にございます。熱心な者たちゆえ、少々騒がしいです。」
本島は、苦笑した。
この頃、日本の近代化を引っ張る“産業革命”は佐賀で進行していた。幕末の佐賀藩には、ヨーロッパの二流国並みの実力はあったと言われている。これは、その始まりの話である。
(第11話「蝦夷探検」に続く)
2020年05月29日
第10話「蒸気機関」⑨(佐野、精錬方へ)
こんばんは。
前回は、殿・鍋島直正が、長崎の佐野栄寿(常民)の塾に、お忍びで足を運びました。
黒船来航の年。異国に戦を仕掛けさせないよう、技術開発を急ぐ直正は、佐野に帰藩の命令を出します。
――佐野は、殿・直正の意を受けて、長崎を離れようとしていた。
「渡辺さん、申し訳ない。佐賀に戻ることとなりました。」
佐野の塾には、大坂の適塾で同門だった渡辺卯三郎も滞在している。
渡辺は、あの緒方洪庵が子供を預けるほど、見込んでいた人物という。のちに故郷の加賀(石川)で地域医療の発展に貢献することになる。
「後は儂らで、どうにかするがや。」
「よろしく頼みます。」
「急な呼び戻しとは、佐野さんは期待されとるがや。頑張んまっし!」
「渡辺さん、ありがとう!」

――佐野、蘭学の仲間たちの気遣いに感激する。今話ではやたら涙目になる展開が多い。
物々しい警備が続く長崎を去り、ほどなく佐賀に戻ってきた佐野。
「“精錬方”はどがんなっとるかね…」
「佐野~っ!久しぶりやないか!」
“翻訳小屋”から、石黒寛次の声がする。
「佐野はん!お帰りやす!」
科学者・中村奇輔は一足早く、長崎から帰って研究を再開していた。
「おおっ、佐野どの!」
機械技術者・田中久重も顔を出す。
――皆、表情が明るい。佐野栄寿の帰藩を待ち望んでいた様子だ。
「そいぎ、長崎で見た“蒸気機関”やねんけどな。」
科学者・中村が、戻ったばかりの佐野に相談を持ち掛ける。
「中村さん…“そいぎ”って、佐賀の者みたか言葉ですね。」
佐野が、次第に“佐賀ことば”が混ざってきている中村に気付く。
「そがんことより、“蒸気罐”(ボイラー)の試作を早よ考えな!」
「…わかりました!すぐに皆で、話合いましょう!」
少なくとも中村は、佐賀に馴染んでいる様子だ。佐野は安堵した。
――そして、佐賀に帰ったばかりだが、佐野に休んでいる暇は無いようだ。
「フフフ…腕が鳴るばい!」
田中久重、目がキラリと光る。
「翻訳は任せろ。但し、なるべく関わりのありそうな洋書で頼む…」
石黒、研究の方向性の見えぬまま、手当たり次第に洋書の翻訳をしてきた。取りまとめ役になりそうな佐野への期待は大きい。

「ところで、佐野さま!」
ここで田中久重の養子、二代目“儀右衛門”が言葉を発する。
「おおっ!“二代目”さん、どがんしなさった。」
「佐野さまの頭なのですが…」
――長崎から帰ったばかりの佐野。やや髪型が不自然である。
「気づかれたばい。」
「えっ、まずかったですか…」
“二代目”は、佐野の反応を見て、少々引き気味である。
「こがんは、鬘(カツラ)ばい!」
佐野がカポッと小気味の良い音を立て、カツラを取る。
実は、まだ丸坊主のままだった。
「殿が…突然、お役目に就け!とおっしゃられるので。」
今回の帰藩にあたって、殿・鍋島直正は、佐野に栄寿左衛門(えいじゅざえもん)という、いかにも重みのある名前を授けた。
――今まで“医者モード”の丸坊主にしていた佐野。急に武士としての立ち位置が強化され、戸惑っている様子だ。
「髷(まげ)を結って、お役目に出ようにも、急に髪は伸びぬものでございますな。」
苦笑する佐野。
「ふふふ…ワシらの頭(かしら)は、鬘(カツラ)か…」
田中久重が含み笑いをする。
「田中さん!からかわんでくださいよ。」
「はっはっは…これは失敬!」
こうして佐野栄寿が戻ったことで、精錬方(せいれんかた)は、1つの“チーム”として機能するようになった。
“万能の研究主任”・佐野の活躍はこれからである。
(続く)
前回は、殿・鍋島直正が、長崎の佐野栄寿(常民)の塾に、お忍びで足を運びました。
黒船来航の年。異国に戦を仕掛けさせないよう、技術開発を急ぐ直正は、佐野に帰藩の命令を出します。
――佐野は、殿・直正の意を受けて、長崎を離れようとしていた。
「渡辺さん、申し訳ない。佐賀に戻ることとなりました。」
佐野の塾には、大坂の適塾で同門だった渡辺卯三郎も滞在している。
渡辺は、あの緒方洪庵が子供を預けるほど、見込んでいた人物という。のちに故郷の加賀(石川)で地域医療の発展に貢献することになる。
「後は儂らで、どうにかするがや。」
「よろしく頼みます。」
「急な呼び戻しとは、佐野さんは期待されとるがや。頑張んまっし!」
「渡辺さん、ありがとう!」
――佐野、蘭学の仲間たちの気遣いに感激する。今話ではやたら涙目になる展開が多い。
物々しい警備が続く長崎を去り、ほどなく佐賀に戻ってきた佐野。
「“精錬方”はどがんなっとるかね…」
「佐野~っ!久しぶりやないか!」
“翻訳小屋”から、石黒寛次の声がする。
「佐野はん!お帰りやす!」
科学者・中村奇輔は一足早く、長崎から帰って研究を再開していた。
「おおっ、佐野どの!」
機械技術者・田中久重も顔を出す。
――皆、表情が明るい。佐野栄寿の帰藩を待ち望んでいた様子だ。
「そいぎ、長崎で見た“蒸気機関”やねんけどな。」
科学者・中村が、戻ったばかりの佐野に相談を持ち掛ける。
「中村さん…“そいぎ”って、佐賀の者みたか言葉ですね。」
佐野が、次第に“佐賀ことば”が混ざってきている中村に気付く。
「そがんことより、“蒸気罐”(ボイラー)の試作を早よ考えな!」
「…わかりました!すぐに皆で、話合いましょう!」
少なくとも中村は、佐賀に馴染んでいる様子だ。佐野は安堵した。
――そして、佐賀に帰ったばかりだが、佐野に休んでいる暇は無いようだ。
「フフフ…腕が鳴るばい!」
田中久重、目がキラリと光る。
「翻訳は任せろ。但し、なるべく関わりのありそうな洋書で頼む…」
石黒、研究の方向性の見えぬまま、手当たり次第に洋書の翻訳をしてきた。取りまとめ役になりそうな佐野への期待は大きい。

「ところで、佐野さま!」
ここで田中久重の養子、二代目“儀右衛門”が言葉を発する。
「おおっ!“二代目”さん、どがんしなさった。」
「佐野さまの頭なのですが…」
――長崎から帰ったばかりの佐野。やや髪型が不自然である。
「気づかれたばい。」
「えっ、まずかったですか…」
“二代目”は、佐野の反応を見て、少々引き気味である。
「こがんは、鬘(カツラ)ばい!」
佐野がカポッと小気味の良い音を立て、カツラを取る。
実は、まだ丸坊主のままだった。
「殿が…突然、お役目に就け!とおっしゃられるので。」
今回の帰藩にあたって、殿・鍋島直正は、佐野に栄寿左衛門(えいじゅざえもん)という、いかにも重みのある名前を授けた。
――今まで“医者モード”の丸坊主にしていた佐野。急に武士としての立ち位置が強化され、戸惑っている様子だ。
「髷(まげ)を結って、お役目に出ようにも、急に髪は伸びぬものでございますな。」
苦笑する佐野。
「ふふふ…ワシらの頭(かしら)は、鬘(カツラ)か…」
田中久重が含み笑いをする。
「田中さん!からかわんでくださいよ。」
「はっはっは…これは失敬!」
こうして佐野栄寿が戻ったことで、精錬方(せいれんかた)は、1つの“チーム”として機能するようになった。
“万能の研究主任”・佐野の活躍はこれからである。
(続く)
2020年05月27日
第10話「蒸気機関」⑧
こんばんは。前回の続きです。
1853年。黒船来航の年に、佐野栄寿(常民)の運命も大きく動きます。
――年の暮れも押し迫った佐野の蘭学塾。
「うー、長崎も冬は寒かね~」
佐野は塾を休講にしていた。
本日は佐賀藩士で、大砲鋳造を担う本島藤太夫が来訪する約束である。
――すると深く編笠をかぶった武士が現れる。その周りには、数人の侍がいた。
いずれも佐賀城下で見たことのある顔ぶれだ。
「佐野どの!」
傍らにいた本島が、佐野に声を掛ける。
「ささっ狭い所ですが、どうぞ」
佐野はひとまず、一行を塾の中へと案内した。

――蘭学塾の玄関に進む“客人”。数人の侍は身辺警護の者らしい。
ここで編笠の武士が正体を明かす。
「佐野栄寿よ!突然、押しかけて済まぬの。」
「と…殿!お知らせいただければ、少しは支度を整えましたものを。」
佐野が、大急ぎでその場に控える。
――編笠の武士は、佐賀藩主・鍋島直正だった。
「良い、気遣いは無用じゃ!お主の“蘭学塾”を見ておきたくてな。」
直正は、佐賀藩が警備体制を敷く、ロシア船来航の情勢を見分するため、長崎に来ていた。
「余が来るとなれば、途端に仰々しくなっていかん。」
直正は軽く笑って“お忍び”で来た理由を語る。
――もともと佐野は城に蘭学の講義に出向くこともあった。殿と話をすることには慣れている。
「佐野よ!台場の者が、そなたの医術に救われたと聞くぞ。」
「はっ!全力を尽くしました。」
「お主の見事な働き、感じ入った!」
「もったいなきお言葉!」

殿・鍋島直正から活躍を絶賛される、佐野栄寿。
感激のあまり涙目で、これからの決意を語る。
「ますます医術に精進し、この塾を大きくしたいと存じます!」
「ならぬ!」
「ありがたき幸せ…えっ!?」
――佐野、状況がよく飲み込めない。殿・直正は自分の医術を認めてくれたはず。
直正は、豆鉄砲でもくらったような表情をする佐野に言葉を続ける。
「お主は、佐賀に戻るのだ。」
「はっ…恐れながら、私に粗相(そそう)がございましたでしょうか。」
佐野は、何が直正の機嫌を損ねたのかと訝(いぶか)しがった。
直正は、軽く笑みを浮かべる。
「心得違いをしておらぬか。余の機嫌は頗(すこぶ)る良いぞ。」
「では、何故でございますか。」
「お主の腕が要るゆえ、佐賀に戻れと申したのだ。」
「医者が、ご入用なのですか?」
「たしかにお主の医術は惜しいが、もし戦となれば、いかな名医とて全ての者を救うことはできまい。」
――黒船来航の年。海外事情に通じた直正だったが、さらに危機が眼前にあると認識していた。
「時が無いのだ。夷狄(いてき)に侮られぬよう、備えを進めねばならん。」

ここで直正が“夷狄”と呼ぶのは、無法な振舞いをする異国のことである。
「戦が…いえ、異国が迫ってきていると。」
――佐野は“戦”という言葉を飲み込んだ。西洋列強との技術力の差は見えている。そして「はっ!」と、直正の真意に気付いた
「お主が集めてきた者たちは、其々に優れておる。しかし束ねる者が居らねば、器は成せぬ。」
直正の期待に応え、佐野は科学者・中村奇輔や技術者・田中久重を連れてきたが、今のところ成果は出ていない。
「余に力を与えよ。お主は“精錬方”をまとめるのだ。」
「…殿の仰せとあらば!」
こうして佐野は新しい道に踏み出すことになった。
個性的な科学者・翻訳家・技術者の力をまとめて、結果を出すことが佐野の任務となったのである。
(続く)
1853年。黒船来航の年に、佐野栄寿(常民)の運命も大きく動きます。
――年の暮れも押し迫った佐野の蘭学塾。
「うー、長崎も冬は寒かね~」
佐野は塾を休講にしていた。
本日は佐賀藩士で、大砲鋳造を担う本島藤太夫が来訪する約束である。
――すると深く編笠をかぶった武士が現れる。その周りには、数人の侍がいた。
いずれも佐賀城下で見たことのある顔ぶれだ。
「佐野どの!」
傍らにいた本島が、佐野に声を掛ける。
「ささっ狭い所ですが、どうぞ」
佐野はひとまず、一行を塾の中へと案内した。

――蘭学塾の玄関に進む“客人”。数人の侍は身辺警護の者らしい。
ここで編笠の武士が正体を明かす。
「佐野栄寿よ!突然、押しかけて済まぬの。」
「と…殿!お知らせいただければ、少しは支度を整えましたものを。」
佐野が、大急ぎでその場に控える。
――編笠の武士は、佐賀藩主・鍋島直正だった。
「良い、気遣いは無用じゃ!お主の“蘭学塾”を見ておきたくてな。」
直正は、佐賀藩が警備体制を敷く、ロシア船来航の情勢を見分するため、長崎に来ていた。
「余が来るとなれば、途端に仰々しくなっていかん。」
直正は軽く笑って“お忍び”で来た理由を語る。
――もともと佐野は城に蘭学の講義に出向くこともあった。殿と話をすることには慣れている。
「佐野よ!台場の者が、そなたの医術に救われたと聞くぞ。」
「はっ!全力を尽くしました。」
「お主の見事な働き、感じ入った!」
「もったいなきお言葉!」

殿・鍋島直正から活躍を絶賛される、佐野栄寿。
感激のあまり涙目で、これからの決意を語る。
「ますます医術に精進し、この塾を大きくしたいと存じます!」
「ならぬ!」
「ありがたき幸せ…えっ!?」
――佐野、状況がよく飲み込めない。殿・直正は自分の医術を認めてくれたはず。
直正は、豆鉄砲でもくらったような表情をする佐野に言葉を続ける。
「お主は、佐賀に戻るのだ。」
「はっ…恐れながら、私に粗相(そそう)がございましたでしょうか。」
佐野は、何が直正の機嫌を損ねたのかと訝(いぶか)しがった。
直正は、軽く笑みを浮かべる。
「心得違いをしておらぬか。余の機嫌は頗(すこぶ)る良いぞ。」
「では、何故でございますか。」
「お主の腕が要るゆえ、佐賀に戻れと申したのだ。」
「医者が、ご入用なのですか?」
「たしかにお主の医術は惜しいが、もし戦となれば、いかな名医とて全ての者を救うことはできまい。」
――黒船来航の年。海外事情に通じた直正だったが、さらに危機が眼前にあると認識していた。
「時が無いのだ。夷狄(いてき)に侮られぬよう、備えを進めねばならん。」

ここで直正が“夷狄”と呼ぶのは、無法な振舞いをする異国のことである。
「戦が…いえ、異国が迫ってきていると。」
――佐野は“戦”という言葉を飲み込んだ。西洋列強との技術力の差は見えている。そして「はっ!」と、直正の真意に気付いた
「お主が集めてきた者たちは、其々に優れておる。しかし束ねる者が居らねば、器は成せぬ。」
直正の期待に応え、佐野は科学者・中村奇輔や技術者・田中久重を連れてきたが、今のところ成果は出ていない。
「余に力を与えよ。お主は“精錬方”をまとめるのだ。」
「…殿の仰せとあらば!」
こうして佐野は新しい道に踏み出すことになった。
個性的な科学者・翻訳家・技術者の力をまとめて、結果を出すことが佐野の任務となったのである。
(続く)
2020年05月25日
第10話「蒸気機関」⑦
こんばんは。
長崎に停泊中のロシア船に招かれ、蒸気機関車の模型を見ることができた中村奇輔。しかし、“蒸気機関”の構造は見通せないままでした。
――長崎。ひとまず佐野栄寿(常民)の蘭学塾に戻る、中村奇輔。
「おおっ、中村さん!“蒸気機関”は、どがんでしたか!」
「佐野はん…大見得を切って出てったのに、情けない!」
蘭学塾の玄関に入るやいなや、中村が悔しそうな表情を露(あら)わにする。
「ほんまやったら、仕組みがわかるまで…噛り付いてでも見続けたかった…」
見学を許されたとはいえ、ロシア艦隊の船上である。
中村は“物珍しい機関車に喜ぶ人”を装い、何とか構造を理解しようと努めた。

しかし、外国船の艦上であまりおかしな行動を取ることもできない。その場の勢いで「もっと機関車を見せて!」とリクエストできるのは、数回が限度だ。
――佐野栄寿、涙目で悔しがる中村にもらい泣きをする。
「悔しかね…、悔しかごたね…」
佐野、とても共感力が高い様子だ。
その時、中村が、自分たちの様子を見守る“第三者”の存在に気付く。
「まぁ、頑張んまっし!」
「…どなたか存じまへんが、ありがとうございます。」
――中村、まだ名前も知らない相手からも励まされた。
「渡辺さん!来てたんですか!」
佐野が声を掛ける。この“第三者”の名は、渡辺卯三郎という。
加賀(石川)の出身である。大坂の適塾で、佐野とは旧知の間柄だ。
この渡辺卯三郎も適塾で、塾頭(運営代表)を務めるほどの秀才である。佐野が蘭学塾を開いていると知り、遠く長崎まで足を運んでいた。

――そして、季節は秋から冬に移ろう。ロシア艦隊を巡る不足の事態に備え、佐賀藩の長崎警備は続いていた。
蘭学塾の門前で、佐賀藩士たちが騒がしい。
「伊東と申す!急ぎ佐野どのにお会いしたい!」
「はい、何かご用ですやろか。」
塾から出てきたのは、中村奇輔である。まだ長崎に滞在し、参考になりそうな洋書を探している。
「佐野どのは居られるか!この者を助けてほしいのだ!」
長崎台場の責任者・伊東次兵衛が、急患となった部下を担ぎこんできた。
高熱でうなされる佐賀藩士、永渕という名である。担架のような板で運ばれている。
「ううっ…」
「永渕、気を確かに持て!蘭方の先生が診てくれるぞ!」
伊東は苦しむ部下を励ます。
――偶然だが“伊東”という名の人物が、医者・佐野栄寿に救いを求めてきた。
江戸での師匠・伊東玄朴のことが、ふと頭をよぎる。
佐野には医術の教えを受け、病気から救ってもらった恩人を、裏切ってしまった過去がある。
「たしか“伊東さま”と、おっしゃいましたね。」
「いかにも。長崎の台場を受け持つ、伊東次兵衛と申す。」
佐野は、1つ深呼吸をして心の中でつぶやいた。
「玄朴先生…不肖の弟子、佐野栄寿。まだ“医の道”をあきらめてはおりません…」

――その時、佐野栄寿は、医者の顔に戻っていた。苦しむ患者に、佐野は声を掛けた。
「ううっ…う…」
「永渕さん…と言いましたね。もう大丈夫です。」
江戸の伊東玄朴に教えを受け、大坂の緒方洪庵の適塾で学び、紀州(和歌山)で華岡流の麻酔も研修した。佐野は、当時、最先端クラスの医術を修業していたのである。
「渡辺さん!手を貸してください!」
佐野は、適塾から来た旧友・渡辺卯三郎に手伝いを求めた。
「いま…支度しとるがや…」
言われる間でもなく、渡辺は準備を始めていた。
「助かります。」
気迫に満ちた、佐野の治療が始まった。
――治療の間、手出しのできない科学者・中村奇輔は、遠巻きに様子を眺める。
「佐野はん!格好よろしいなぁ。負けてられまへん!」
これから、中村は佐賀の“精錬方”に戻る。医師・佐野栄寿の活躍は、中村の研究への情熱を呼び起こしていた。
(続く)
長崎に停泊中のロシア船に招かれ、蒸気機関車の模型を見ることができた中村奇輔。しかし、“蒸気機関”の構造は見通せないままでした。
――長崎。ひとまず佐野栄寿(常民)の蘭学塾に戻る、中村奇輔。
「おおっ、中村さん!“蒸気機関”は、どがんでしたか!」
「佐野はん…大見得を切って出てったのに、情けない!」
蘭学塾の玄関に入るやいなや、中村が悔しそうな表情を露(あら)わにする。
「ほんまやったら、仕組みがわかるまで…噛り付いてでも見続けたかった…」
見学を許されたとはいえ、ロシア艦隊の船上である。
中村は“物珍しい機関車に喜ぶ人”を装い、何とか構造を理解しようと努めた。
しかし、外国船の艦上であまりおかしな行動を取ることもできない。その場の勢いで「もっと機関車を見せて!」とリクエストできるのは、数回が限度だ。
――佐野栄寿、涙目で悔しがる中村にもらい泣きをする。
「悔しかね…、悔しかごたね…」
佐野、とても共感力が高い様子だ。
その時、中村が、自分たちの様子を見守る“第三者”の存在に気付く。
「まぁ、頑張んまっし!」
「…どなたか存じまへんが、ありがとうございます。」
――中村、まだ名前も知らない相手からも励まされた。
「渡辺さん!来てたんですか!」
佐野が声を掛ける。この“第三者”の名は、渡辺卯三郎という。
加賀(石川)の出身である。大坂の適塾で、佐野とは旧知の間柄だ。
この渡辺卯三郎も適塾で、塾頭(運営代表)を務めるほどの秀才である。佐野が蘭学塾を開いていると知り、遠く長崎まで足を運んでいた。

――そして、季節は秋から冬に移ろう。ロシア艦隊を巡る不足の事態に備え、佐賀藩の長崎警備は続いていた。
蘭学塾の門前で、佐賀藩士たちが騒がしい。
「伊東と申す!急ぎ佐野どのにお会いしたい!」
「はい、何かご用ですやろか。」
塾から出てきたのは、中村奇輔である。まだ長崎に滞在し、参考になりそうな洋書を探している。
「佐野どのは居られるか!この者を助けてほしいのだ!」
長崎台場の責任者・伊東次兵衛が、急患となった部下を担ぎこんできた。
高熱でうなされる佐賀藩士、永渕という名である。担架のような板で運ばれている。
「ううっ…」
「永渕、気を確かに持て!蘭方の先生が診てくれるぞ!」
伊東は苦しむ部下を励ます。
――偶然だが“伊東”という名の人物が、医者・佐野栄寿に救いを求めてきた。
江戸での師匠・伊東玄朴のことが、ふと頭をよぎる。
佐野には医術の教えを受け、病気から救ってもらった恩人を、裏切ってしまった過去がある。
「たしか“伊東さま”と、おっしゃいましたね。」
「いかにも。長崎の台場を受け持つ、伊東次兵衛と申す。」
佐野は、1つ深呼吸をして心の中でつぶやいた。
「玄朴先生…不肖の弟子、佐野栄寿。まだ“医の道”をあきらめてはおりません…」

――その時、佐野栄寿は、医者の顔に戻っていた。苦しむ患者に、佐野は声を掛けた。
「ううっ…う…」
「永渕さん…と言いましたね。もう大丈夫です。」
江戸の伊東玄朴に教えを受け、大坂の緒方洪庵の適塾で学び、紀州(和歌山)で華岡流の麻酔も研修した。佐野は、当時、最先端クラスの医術を修業していたのである。
「渡辺さん!手を貸してください!」
佐野は、適塾から来た旧友・渡辺卯三郎に手伝いを求めた。
「いま…支度しとるがや…」
言われる間でもなく、渡辺は準備を始めていた。
「助かります。」
気迫に満ちた、佐野の治療が始まった。
――治療の間、手出しのできない科学者・中村奇輔は、遠巻きに様子を眺める。
「佐野はん!格好よろしいなぁ。負けてられまへん!」
これから、中村は佐賀の“精錬方”に戻る。医師・佐野栄寿の活躍は、中村の研究への情熱を呼び起こしていた。
(続く)
2020年05月23日
第10話「蒸気機関」⑥
こんばんは。
今回は、幕府の役人に同行し、佐賀藩士たちが長崎に停泊するロシア船に乗り込みます。
そして、佐野栄寿(常民)が京都からスカウトした科学者・中村奇輔が、実物の“蒸気機関”に出会います。
――まず幕府の役人がロシア船に乗り込み、製砲主任の本島藤太夫をはじめ、佐賀藩士たちが続く。
ロシア艦隊の士官たちが、幕府の役人と言葉を交わす。例によって、オランダ語の通訳を介した対話である。
「ようこそ、“パルラダ号”へ。」
「貴艦にお招きいただき、光栄である!」
この時点で、日露の交渉を担当した筒井政憲・川路聖謨は、まだ長崎に来ていない。公式な会談は、これから数か月後の話になる。
――本島藤太夫は、鍋島直正の側近で上級武士である。儀礼的なことにも気を遣わなくてはいけない。
「中村どの!私はまだ動けぬ。貴方は見聞を進めてくれ。」
本島の声を受けて、科学者・中村奇輔は甲板を見回した。
やはり“和船”とは安定感が違う。
「さすがは、西洋の艦船…といったところやな。大砲も積み放題か…」
――そして、中村の目はロシア艦隊の1隻、汽走艦“ボストーク号”を捉えた。
ロシア艦隊の4隻のうち、2隻は蒸気船である。
「蒸気船…しかも“外輪”が見当たらん!」
当時はペリーの黒船のように、船の側面に付いている水車のような“外輪”で進むのが一般的だった。
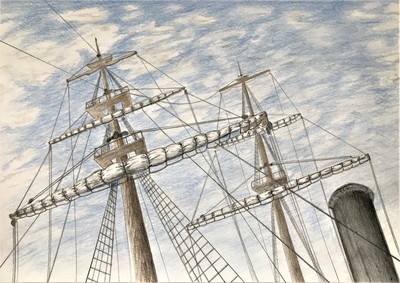
しかし中村が注目した“ボストーク号”は、最新鋭の推進装置“スクリュー”を備えていた。スクリューは水面下に隠れているので、中村には見えていない。
「仕掛けが見えんぞ!あの蒸気船は、どう進むんや…」
隣に並ぶ汽走艦を凝視して、思案を巡らせる中村。
「たしかに巨船では無いが、あの蒸気船は得体が知れんで…」
ロシア艦隊は、日本に来航する前にイギリスに寄っている。
イギリスの会社から購入した“ボストーク号”を艦隊に加えるためである。
――最新鋭のスクリュー推進型の蒸気船“ボストーク号”。大型の蒸気船に比べ、船足が早く、小回りも利く。
北九州の沿岸から、日本海の周辺海域まで、迅速な航行が可能である。ロシアには沿岸の地勢を調べて、今後の活動の足がかりとする意図もあった。
――船外を見遣る、中村の背後。やや艦上が賑やかとなった。
「中村どの!」
本島が呼びかけている。
「はい、本島さま!お呼びですか。」
中村が振り返り、船の縁から甲板の中央へと戻る。
「中村どの!貴方が見なければならぬものが来るぞ!」
「あれは“蒸気機関”…!?」
――ロシア艦隊の士官は、模型の機関車を持参していた。
熱湯を注ぎ、アルコールに点火することで、簡易な“蒸気機関”を形成している。
「見テテ、クダサイ!コレガ機関車デス!」
通訳が日本語で解説する前に、列席者に呼びかけたロシア人士官。
ネジ状のコックを捻ると、速やかに模型機関車は走り出した。

「中村どの!あれは如何なる仕組みなのだ!?」
佐賀藩の誇る“鋳立方の七人”のリーダー・本島も驚いている。
――中村奇輔が声を発した。「いま一度、お見せください!」と。
ロシア人士官が軽く手を挙げる。通訳する間でもなく、中村の要求を理解した様子だ。
ポッ!
軽く煙を発する。模型機関車。
すみやかに走り出し、軌道上をクルクルと旋回する。
「本島さま…あきまへん。わかりませんでした。」
淡々とした言葉とは、裏腹に中村の右拳は固く握られていた。
(続く)
今回は、幕府の役人に同行し、佐賀藩士たちが長崎に停泊するロシア船に乗り込みます。
そして、佐野栄寿(常民)が京都からスカウトした科学者・中村奇輔が、実物の“蒸気機関”に出会います。
――まず幕府の役人がロシア船に乗り込み、製砲主任の本島藤太夫をはじめ、佐賀藩士たちが続く。
ロシア艦隊の士官たちが、幕府の役人と言葉を交わす。例によって、オランダ語の通訳を介した対話である。
「ようこそ、“パルラダ号”へ。」
「貴艦にお招きいただき、光栄である!」
この時点で、日露の交渉を担当した筒井政憲・川路聖謨は、まだ長崎に来ていない。公式な会談は、これから数か月後の話になる。
――本島藤太夫は、鍋島直正の側近で上級武士である。儀礼的なことにも気を遣わなくてはいけない。
「中村どの!私はまだ動けぬ。貴方は見聞を進めてくれ。」
本島の声を受けて、科学者・中村奇輔は甲板を見回した。
やはり“和船”とは安定感が違う。
「さすがは、西洋の艦船…といったところやな。大砲も積み放題か…」
――そして、中村の目はロシア艦隊の1隻、汽走艦“ボストーク号”を捉えた。
ロシア艦隊の4隻のうち、2隻は蒸気船である。
「蒸気船…しかも“外輪”が見当たらん!」
当時はペリーの黒船のように、船の側面に付いている水車のような“外輪”で進むのが一般的だった。
しかし中村が注目した“ボストーク号”は、最新鋭の推進装置“スクリュー”を備えていた。スクリューは水面下に隠れているので、中村には見えていない。
「仕掛けが見えんぞ!あの蒸気船は、どう進むんや…」
隣に並ぶ汽走艦を凝視して、思案を巡らせる中村。
「たしかに巨船では無いが、あの蒸気船は得体が知れんで…」
ロシア艦隊は、日本に来航する前にイギリスに寄っている。
イギリスの会社から購入した“ボストーク号”を艦隊に加えるためである。
――最新鋭のスクリュー推進型の蒸気船“ボストーク号”。大型の蒸気船に比べ、船足が早く、小回りも利く。
北九州の沿岸から、日本海の周辺海域まで、迅速な航行が可能である。ロシアには沿岸の地勢を調べて、今後の活動の足がかりとする意図もあった。
――船外を見遣る、中村の背後。やや艦上が賑やかとなった。
「中村どの!」
本島が呼びかけている。
「はい、本島さま!お呼びですか。」
中村が振り返り、船の縁から甲板の中央へと戻る。
「中村どの!貴方が見なければならぬものが来るぞ!」
「あれは“蒸気機関”…!?」
――ロシア艦隊の士官は、模型の機関車を持参していた。
熱湯を注ぎ、アルコールに点火することで、簡易な“蒸気機関”を形成している。
「見テテ、クダサイ!コレガ機関車デス!」
通訳が日本語で解説する前に、列席者に呼びかけたロシア人士官。
ネジ状のコックを捻ると、速やかに模型機関車は走り出した。
「中村どの!あれは如何なる仕組みなのだ!?」
佐賀藩の誇る“鋳立方の七人”のリーダー・本島も驚いている。
――中村奇輔が声を発した。「いま一度、お見せください!」と。
ロシア人士官が軽く手を挙げる。通訳する間でもなく、中村の要求を理解した様子だ。
ポッ!
軽く煙を発する。模型機関車。
すみやかに走り出し、軌道上をクルクルと旋回する。
「本島さま…あきまへん。わかりませんでした。」
淡々とした言葉とは、裏腹に中村の右拳は固く握られていた。
(続く)
2020年05月21日
第10話「蒸気機関」⑤
こんばんは。
第10話「蒸気機関」は、第9話「和親条約」と時期がかなり重なっています。
黒船来航の2年前(1851年)から始まって、この時点ではアメリカのペリーが江戸湾から一旦、退去した後。ロシアのプチャーチンが長崎に来航している時期です。
――1853年秋。佐野栄寿(常民)に続いて、科学者・中村奇輔も長崎に行ってしまった。
取り残された感のある、翻訳家・石黒寛次。
今日も“精錬方”の小屋で「得体の知れない洋書」を翻訳している。
「何や…ようわからん本やな。舎密(せいみ)か…!?」
西洋の化学関係の書物のようだが、はっきりしない。
「おい、中村…!」
石黒の呼びかけた相手、中村は佐賀藩の仕事で長崎に出張中。この場にいない。
丹後田辺(舞鶴)の出身の石黒は、いまや故郷から遠く佐賀に就職している。
「はぁー!さすがに気が滅入るわ…暗い生活やなぁ~」
孤独な翻訳作業の疲れもあって、大きくため息をつく石黒。

――すると、俄(にわ)かに眼前がパッと明るくなった。
「なんや!」
石黒が驚く。突如、強力な灯りが差し出されたのである。
「はい!無尽灯(むじんとう)!」
ヌッと現れた声の主は、田中久重である。
「田中さんか!驚かさんといてや…」
「ふふふ…ワシ、儀右衛門(ぎえもん)。」
田中久重は、得意気な表情を浮かべていた。
「…お主、先ほど“暗い”と言ったであろう。」
「いや、言っちゃっとるけども!」
――「不便を感じている人の力になりたい!」が、田中久重の研究の原動力なのである。
「養父上(ちちうえ)!今の“儀右衛門”は、私ではないのですか!」
二代目・儀右衛門が困惑している。田中の養子で、金属加工のスペシャリストである。
「おう、すまんすまん。つい癖が出たばい。」
田中久重は、久留米(福岡)の出身。久しぶり九州に戻って元気いっぱいである。
「ワシら2人で、“からくり儀右衛門”と言うことでどうね!ハッハッハッ…」
「養父上!ややこしゅうこざいます!」
小競り合いをする田中父子。
ふと石黒が、西の空を見遣った。長崎の方角だ。
「儂もロシア船が!“蒸気機関”が見たいんや。」
――長崎での科学者・中村奇輔の任務とは、ロシア船の装備の視察である。

ロシアのプチャーチン艦隊は長崎に停泊している間、日本側と交流を試みた。
幕府や、佐賀藩の視察団を受け入れていたのである。
「中村どの!参りますぞ。」
迎えに来たのは、本島藤太夫。
大砲製造チーム「鋳立方(いたてがた)の七人」のリーダーという存在。蘭学つながりで、佐野とも面識がある。
「ほな、佐野はん!行って来ますで。この目ぇで“蒸気機関”の仕組みを明かしてきます!」
中村が、佐野栄寿(常民)の蘭学塾を出立する。
「中村さん!本当は私も行きたい!」
「まかせとき!佐野はんの分まで見て来ますわ!」
力強く決意を表明する、中村。
――2人がまず乗り込むのは、ロシア船「パルラダ号」。その艦上で待つものは…
本島藤太夫が、中村奇輔に伝える。
「私は“大砲”を見ます!貴方は“蒸気機関”を!」
中村が言葉を返す。
「望むところです!我々“精錬方”で、直ぐに追いついてみせます!」
(続く)
第10話「蒸気機関」は、第9話「和親条約」と時期がかなり重なっています。
黒船来航の2年前(1851年)から始まって、この時点ではアメリカのペリーが江戸湾から一旦、退去した後。ロシアのプチャーチンが長崎に来航している時期です。
――1853年秋。佐野栄寿(常民)に続いて、科学者・中村奇輔も長崎に行ってしまった。
取り残された感のある、翻訳家・石黒寛次。
今日も“精錬方”の小屋で「得体の知れない洋書」を翻訳している。
「何や…ようわからん本やな。舎密(せいみ)か…!?」
西洋の化学関係の書物のようだが、はっきりしない。
「おい、中村…!」
石黒の呼びかけた相手、中村は佐賀藩の仕事で長崎に出張中。この場にいない。
丹後田辺(舞鶴)の出身の石黒は、いまや故郷から遠く佐賀に就職している。
「はぁー!さすがに気が滅入るわ…暗い生活やなぁ~」
孤独な翻訳作業の疲れもあって、大きくため息をつく石黒。

――すると、俄(にわ)かに眼前がパッと明るくなった。
「なんや!」
石黒が驚く。突如、強力な灯りが差し出されたのである。
「はい!無尽灯(むじんとう)!」
ヌッと現れた声の主は、田中久重である。
「田中さんか!驚かさんといてや…」
「ふふふ…ワシ、儀右衛門(ぎえもん)。」
田中久重は、得意気な表情を浮かべていた。
「…お主、先ほど“暗い”と言ったであろう。」
「いや、言っちゃっとるけども!」
――「不便を感じている人の力になりたい!」が、田中久重の研究の原動力なのである。
「養父上(ちちうえ)!今の“儀右衛門”は、私ではないのですか!」
二代目・儀右衛門が困惑している。田中の養子で、金属加工のスペシャリストである。
「おう、すまんすまん。つい癖が出たばい。」
田中久重は、久留米(福岡)の出身。久しぶり九州に戻って元気いっぱいである。
「ワシら2人で、“からくり儀右衛門”と言うことでどうね!ハッハッハッ…」
「養父上!ややこしゅうこざいます!」
小競り合いをする田中父子。
ふと石黒が、西の空を見遣った。長崎の方角だ。
「儂もロシア船が!“蒸気機関”が見たいんや。」
――長崎での科学者・中村奇輔の任務とは、ロシア船の装備の視察である。

ロシアのプチャーチン艦隊は長崎に停泊している間、日本側と交流を試みた。
幕府や、佐賀藩の視察団を受け入れていたのである。
「中村どの!参りますぞ。」
迎えに来たのは、本島藤太夫。
大砲製造チーム「鋳立方(いたてがた)の七人」のリーダーという存在。蘭学つながりで、佐野とも面識がある。
「ほな、佐野はん!行って来ますで。この目ぇで“蒸気機関”の仕組みを明かしてきます!」
中村が、佐野栄寿(常民)の蘭学塾を出立する。
「中村さん!本当は私も行きたい!」
「まかせとき!佐野はんの分まで見て来ますわ!」
力強く決意を表明する、中村。
――2人がまず乗り込むのは、ロシア船「パルラダ号」。その艦上で待つものは…
本島藤太夫が、中村奇輔に伝える。
「私は“大砲”を見ます!貴方は“蒸気機関”を!」
中村が言葉を返す。
「望むところです!我々“精錬方”で、直ぐに追いついてみせます!」
(続く)
2020年05月19日
第10話「蒸気機関」④
こんばんは。
少々バテ気味ではありますが、いつもご覧いただいている皆様、ありがとうございます。
さて、日本の科学技術力が、相対的に低下したと言われる昨今です。
いまや学術研究にも見栄えのする成果が求められがちで、地道な研究が評価されない傾向もあるようです。
幕末の名君・鍋島直正は、基礎研究や試行錯誤を大事にしたトップと言ってよいでしょう。
佐賀で研究者・技術者たちが、文字通り命を賭けた技術開発は、のちに日本の近代化につながっていきます。
――1853年夏、長崎。佐野栄寿(常民)が立ち上げた、蘭学塾。
京都から“精錬方”に就職した、科学者・中村奇輔が尋ねてくる。
「佐野はん、お邪魔します。」
「やぁ、中村さん。“精錬方”は順調ですか?」
佐野が笑顔で出迎える。
長崎の塾では“蘭方医”も兼ねているので、再びキレイな丸坊主にしてみた。
「それがやな…」
中村の表情が少しひきつる。
「えっ、何かあったんですか!?」
佐野は、蘭学塾の運営に夢中で、最近の情勢に疎くなっていた。

――1か月ほど前、ペリー来航の衝撃が冷めやらぬ佐賀城内。
「殿!公儀(幕府)より石火矢(大砲)の御用を命ぜられました!」
重臣・鍋島夏雲(市佑)が報告する。日記など几帳面に記録を残すタイプの人である。
「これは名誉なことにござる。直ちに支度を!」
側近の1人・原田小四郎である。
殿・鍋島直正と、重臣たちが集まって話をしている。
――いわゆる保守派の家来たちも、幕府の命令で大砲を造ることに異論はない。むしろ幕府の評価は気になるので、積極的でさえある。
「殿!公儀(幕府)御用の製作所はいずこに設けましょう。」
「少し前に、安房とも話おうていたが“多布施”であろうな。」
“精錬方”と近い立地を考えていた直正。
「多布施でございますか。」
「これを機に“精錬方”を、石火矢(大砲)の御用にお取込みなさっては。」
勘定方に近しい重臣からの提案である。
――耳ざわりは良い表現だが、“精錬方”の吸収合併、もっと言えば“廃止”を提案している。
「厳しく申し上げれば、かの“精錬方”、今のところ何も産み出してはおりません。」
側近の原田も同調する。
「左様にござる。余所者(よそもの)が多く、まとまりに欠ける感もございます。」
さらに保守派の宿老が畳みかける。
これから幕府の発注に対応する“反射炉”をもう1つ造るのだ。たしかに資金繰りは難しい。
――公式な会議として設定した場ではないが、話の行きがかり上、殿・鍋島直正は孤立した。
藩のナンバー2・鍋島安房は他事でこの場におらず、頼れる“義兄上”・鍋島茂義も武雄に戻っている。

そして、蘭学に通じた“長崎御番”の主力たちは、ロシアのプチャーチン来航を受けて、出払っている。
直正、この場は1人で収拾を付けることにした。
「皆の者、よく聞け!」
「はっ!」
原田小四郎は頑固ではあるが、忠義者である。
殿が何か言葉を発すると見れば、しっかり傾聴する。
――他の重臣たちも一斉に、直正の発言に注目する。
「“精錬方”は…」
皆が固唾をのんで、直正を見つめる。多額の資金を使う“大事業”の行方は…
「余の…」
思い切り間を取り、溜めをつくる直正。
「…いかに」
重臣たちに緊張が走る。
――そして急激に間を詰め、直正が言い放った。
「道楽じゃ!口を挟むでない!」
「…はっ…」
呆気に取られる重臣たち。まさか“余の道楽”で一蹴されるとは…
「ははーっ!殿がそこまで仰せならば!」
原田小四郎、殿の決意が通じたのか…なぜか得心が言ったらしい。
こうして、直正は一瞬で場の空気を掴むことに成功した。
――何とか“精錬方”は存続の危機を乗り越えた。いわば殿の政策決定による“特別予算”のような扱いである。

中村奇輔は息を切らせながら、佐野栄寿に以上の事柄を一気に説明した。
「佐野…水もろうてもええか。」
中村、のどが渇いたらしい。
「…すぐ持ってきます。」
そして、佐野は蘭学塾の奥にある井戸まで、水を汲みにいったのである。
(続く)
少々バテ気味ではありますが、いつもご覧いただいている皆様、ありがとうございます。
さて、日本の科学技術力が、相対的に低下したと言われる昨今です。
いまや学術研究にも見栄えのする成果が求められがちで、地道な研究が評価されない傾向もあるようです。
幕末の名君・鍋島直正は、基礎研究や試行錯誤を大事にしたトップと言ってよいでしょう。
佐賀で研究者・技術者たちが、文字通り命を賭けた技術開発は、のちに日本の近代化につながっていきます。
――1853年夏、長崎。佐野栄寿(常民)が立ち上げた、蘭学塾。
京都から“精錬方”に就職した、科学者・中村奇輔が尋ねてくる。
「佐野はん、お邪魔します。」
「やぁ、中村さん。“精錬方”は順調ですか?」
佐野が笑顔で出迎える。
長崎の塾では“蘭方医”も兼ねているので、再びキレイな丸坊主にしてみた。
「それがやな…」
中村の表情が少しひきつる。
「えっ、何かあったんですか!?」
佐野は、蘭学塾の運営に夢中で、最近の情勢に疎くなっていた。

――1か月ほど前、ペリー来航の衝撃が冷めやらぬ佐賀城内。
「殿!公儀(幕府)より石火矢(大砲)の御用を命ぜられました!」
重臣・鍋島夏雲(市佑)が報告する。日記など几帳面に記録を残すタイプの人である。
「これは名誉なことにござる。直ちに支度を!」
側近の1人・原田小四郎である。
殿・鍋島直正と、重臣たちが集まって話をしている。
――いわゆる保守派の家来たちも、幕府の命令で大砲を造ることに異論はない。むしろ幕府の評価は気になるので、積極的でさえある。
「殿!公儀(幕府)御用の製作所はいずこに設けましょう。」
「少し前に、安房とも話おうていたが“多布施”であろうな。」
“精錬方”と近い立地を考えていた直正。
「多布施でございますか。」
「これを機に“精錬方”を、石火矢(大砲)の御用にお取込みなさっては。」
勘定方に近しい重臣からの提案である。
――耳ざわりは良い表現だが、“精錬方”の吸収合併、もっと言えば“廃止”を提案している。
「厳しく申し上げれば、かの“精錬方”、今のところ何も産み出してはおりません。」
側近の原田も同調する。
「左様にござる。余所者(よそもの)が多く、まとまりに欠ける感もございます。」
さらに保守派の宿老が畳みかける。
これから幕府の発注に対応する“反射炉”をもう1つ造るのだ。たしかに資金繰りは難しい。
――公式な会議として設定した場ではないが、話の行きがかり上、殿・鍋島直正は孤立した。
藩のナンバー2・鍋島安房は他事でこの場におらず、頼れる“義兄上”・鍋島茂義も武雄に戻っている。

そして、蘭学に通じた“長崎御番”の主力たちは、ロシアのプチャーチン来航を受けて、出払っている。
直正、この場は1人で収拾を付けることにした。
「皆の者、よく聞け!」
「はっ!」
原田小四郎は頑固ではあるが、忠義者である。
殿が何か言葉を発すると見れば、しっかり傾聴する。
――他の重臣たちも一斉に、直正の発言に注目する。
「“精錬方”は…」
皆が固唾をのんで、直正を見つめる。多額の資金を使う“大事業”の行方は…
「余の…」
思い切り間を取り、溜めをつくる直正。
「…いかに」
重臣たちに緊張が走る。
――そして急激に間を詰め、直正が言い放った。
「道楽じゃ!口を挟むでない!」
「…はっ…」
呆気に取られる重臣たち。まさか“余の道楽”で一蹴されるとは…
「ははーっ!殿がそこまで仰せならば!」
原田小四郎、殿の決意が通じたのか…なぜか得心が言ったらしい。
こうして、直正は一瞬で場の空気を掴むことに成功した。
――何とか“精錬方”は存続の危機を乗り越えた。いわば殿の政策決定による“特別予算”のような扱いである。

中村奇輔は息を切らせながら、佐野栄寿に以上の事柄を一気に説明した。
「佐野…水もろうてもええか。」
中村、のどが渇いたらしい。
「…すぐ持ってきます。」
そして、佐野は蘭学塾の奥にある井戸まで、水を汲みにいったのである。
(続く)
2020年05月17日
第10話「蒸気機関」③
おはようございます。
前回の続きです。技術開発にあわせて、少し佐賀藩の内情の表現を試みます。
――1852年。佐賀城下の“多布施”に位置する「精錬方」の施設。研究所、工場、居宅などが集まっている。
「田中さん!どがんですか、佐賀の住み心地は?」
佐野栄寿が田中久重に問う。
「いや、良くしてもらっておるぞ!」
機械技術者・田中にとって、衣食住と製作環境が揃う、この待遇は期待以上らしい。
――田中父子だけでなく、中村奇輔、石黒寛次も多布施に住居を与えられている。
「ここでの暮らしは良い!まぁ…ずっと蘭書を訳しているがな!」
石黒寛次は、翻訳に没頭している。
「そうだ、石黒さん!これもお願いします!」
実は彼らのスカウトを行った佐野自身は、なんと長崎で蘭学塾を立ち上げていた。
――今日は、自分がスカウトした4人の様子伺いと、石黒に翻訳してもらう書物を届けに来たのである。

「砲術…造船…、それと何だこりゃ!?まぁ…ええけどな。」
“得体の知れない洋書”の登場に、石黒も苦笑いである。
――そして科学者・中村奇輔が、佐野の姿を見つける。
「佐野はん!実は先だって…」
中村が何か言いたそうだ。
「実は、お殿様が幾度か来られてな…」
「あぁ、そうでしたか。」
佐野があっさりとした反応をする。重大事を話したつもりの中村は面食らった。
「佐野はん、驚かんのか!お殿様やで!」
「殿は、“弘道館”(藩校)にもよくお越しになりますので…佐賀ではよくあることです。」
殿・鍋島直正が勉強する者の近くに現れるのは、常のことだった。
――しかし、殿も大変なのであった。佐賀城の一角にて。
「殿っ!申し上げたき儀(ぎ)がござる!」
「原田か。いかがした。」
直正に声を掛けたのは、原田小四郎。
最近、めきめきと頭角を現している、直正の有力な側近の1人である。
「“精錬方”のことにござる!」
「…あぁ、そのことか。」
――いわゆる“重臣のお小言”である。あまり気が乗らない反応をする直正。
「海の物とも、山の物ともつかぬ余所者(よそもの)を、多額の費えで雇うとは!」
「いや…原田よ!あれは大事な者たちなのだ。」
「殿っ!お聞きくだされ!」
「…うむうむ。」
――佐賀藩は、支藩(鹿島など)や、鍋島家の親類などの領主が治める自治領(武雄など)に細かく分かれていた。
長崎警備などで財政負担の大きかった佐賀本藩は、長年の間、支藩である鹿島藩の吸収合併を計画していたのである。
そして、幕府も巻き込んだ騒ぎに発展したことがある。
直正も「腹を割って話そう」と調整に苦心し、何とか騒動は収束した。
「幾度も厳しきことを申し付けております、鹿島(支藩)の者たちの目もござるぞ。まずは、倹約ではござらぬか。」
原田小四郎、ストレートに“正論”をぶつけてくる。これもサムライの忠義の形である。

――原田小四郎は、親類(支藩や親類、その同格)に次ぐクラスの名家出身のエリートで、発言力も強い。
鍋島直正は、西洋の技術に熱心だが、ただの新しい物好きではない。
佐賀県人の気質に通ずるしれないが、マジメで秩序を重んじる保守的な性格でもある。
ゆえに直正の目指した価値は、秩序と革新の両立である。保守派の急先鋒・原田も、また直正の理想のために働いているのだ。
「原田、お主の言うこともわかるぞ!しかしだな…」
――そこに“武雄のご隠居”鍋島茂義が現れる。
「原田よ!」
ここで茂義の“乱入”により、風向きが変わる。
「おおっ、武雄の“義兄上(あにうえ)”」
直正、助け舟の登場にホッとした様子だ。
「彼の(かの)者たちは、儂が殿より命ぜられた“蒸気機関”の仕立てに欠かせぬ者どもじゃ!」
「儂の顔を立ててくれんか!」
もはや、お願いなのか、威圧なのかがわからない。久しぶりの“武雄のご隠居”の剛腕である。
「…かような仕儀なれば、しばし様子を見まする…」
原田、不承不承ではあるが引き下がった。
――原田小四郎が去り、ひと息つく直正と茂義。
「殿!…たいそう家来に気を遣うのだな。」
茂義が少し、皮肉を言う。
殿であるとはいえ、もともと直正は14歳年下の“弟分”でもある。とくに遠慮はない。
「原田とて、儂の意を受けて、励んでおるのだ。無下には扱えん。」
農村は富み、商いは活発、城下の治安も良い…当時の佐賀藩。その根本は、秩序を重んじ、それぞれの為すべき仕事に全力を傾けることだった。
鍋島直正は、実際に仕事にあたる部下をよく見ている。その分、悩みも増えるのである。
(続く)
前回の続きです。技術開発にあわせて、少し佐賀藩の内情の表現を試みます。
――1852年。佐賀城下の“多布施”に位置する「精錬方」の施設。研究所、工場、居宅などが集まっている。
「田中さん!どがんですか、佐賀の住み心地は?」
佐野栄寿が田中久重に問う。
「いや、良くしてもらっておるぞ!」
機械技術者・田中にとって、衣食住と製作環境が揃う、この待遇は期待以上らしい。
――田中父子だけでなく、中村奇輔、石黒寛次も多布施に住居を与えられている。
「ここでの暮らしは良い!まぁ…ずっと蘭書を訳しているがな!」
石黒寛次は、翻訳に没頭している。
「そうだ、石黒さん!これもお願いします!」
実は彼らのスカウトを行った佐野自身は、なんと長崎で蘭学塾を立ち上げていた。
――今日は、自分がスカウトした4人の様子伺いと、石黒に翻訳してもらう書物を届けに来たのである。
「砲術…造船…、それと何だこりゃ!?まぁ…ええけどな。」
“得体の知れない洋書”の登場に、石黒も苦笑いである。
――そして科学者・中村奇輔が、佐野の姿を見つける。
「佐野はん!実は先だって…」
中村が何か言いたそうだ。
「実は、お殿様が幾度か来られてな…」
「あぁ、そうでしたか。」
佐野があっさりとした反応をする。重大事を話したつもりの中村は面食らった。
「佐野はん、驚かんのか!お殿様やで!」
「殿は、“弘道館”(藩校)にもよくお越しになりますので…佐賀ではよくあることです。」
殿・鍋島直正が勉強する者の近くに現れるのは、常のことだった。
――しかし、殿も大変なのであった。佐賀城の一角にて。
「殿っ!申し上げたき儀(ぎ)がござる!」
「原田か。いかがした。」
直正に声を掛けたのは、原田小四郎。
最近、めきめきと頭角を現している、直正の有力な側近の1人である。
「“精錬方”のことにござる!」
「…あぁ、そのことか。」
――いわゆる“重臣のお小言”である。あまり気が乗らない反応をする直正。
「海の物とも、山の物ともつかぬ余所者(よそもの)を、多額の費えで雇うとは!」
「いや…原田よ!あれは大事な者たちなのだ。」
「殿っ!お聞きくだされ!」
「…うむうむ。」
――佐賀藩は、支藩(鹿島など)や、鍋島家の親類などの領主が治める自治領(武雄など)に細かく分かれていた。
長崎警備などで財政負担の大きかった佐賀本藩は、長年の間、支藩である鹿島藩の吸収合併を計画していたのである。
そして、幕府も巻き込んだ騒ぎに発展したことがある。
直正も「腹を割って話そう」と調整に苦心し、何とか騒動は収束した。
「幾度も厳しきことを申し付けております、鹿島(支藩)の者たちの目もござるぞ。まずは、倹約ではござらぬか。」
原田小四郎、ストレートに“正論”をぶつけてくる。これもサムライの忠義の形である。

――原田小四郎は、親類(支藩や親類、その同格)に次ぐクラスの名家出身のエリートで、発言力も強い。
鍋島直正は、西洋の技術に熱心だが、ただの新しい物好きではない。
佐賀県人の気質に通ずるしれないが、マジメで秩序を重んじる保守的な性格でもある。
ゆえに直正の目指した価値は、秩序と革新の両立である。保守派の急先鋒・原田も、また直正の理想のために働いているのだ。
「原田、お主の言うこともわかるぞ!しかしだな…」
――そこに“武雄のご隠居”鍋島茂義が現れる。
「原田よ!」
ここで茂義の“乱入”により、風向きが変わる。
「おおっ、武雄の“義兄上(あにうえ)”」
直正、助け舟の登場にホッとした様子だ。
「彼の(かの)者たちは、儂が殿より命ぜられた“蒸気機関”の仕立てに欠かせぬ者どもじゃ!」
「儂の顔を立ててくれんか!」
もはや、お願いなのか、威圧なのかがわからない。久しぶりの“武雄のご隠居”の剛腕である。
「…かような仕儀なれば、しばし様子を見まする…」
原田、不承不承ではあるが引き下がった。
――原田小四郎が去り、ひと息つく直正と茂義。
「殿!…たいそう家来に気を遣うのだな。」
茂義が少し、皮肉を言う。
殿であるとはいえ、もともと直正は14歳年下の“弟分”でもある。とくに遠慮はない。
「原田とて、儂の意を受けて、励んでおるのだ。無下には扱えん。」
農村は富み、商いは活発、城下の治安も良い…当時の佐賀藩。その根本は、秩序を重んじ、それぞれの為すべき仕事に全力を傾けることだった。
鍋島直正は、実際に仕事にあたる部下をよく見ている。その分、悩みも増えるのである。
(続く)
2020年05月15日
第10話「蒸気機関」②
こんばんは。
前回、佐賀に登場した関西出身の2人。
中村奇輔、石黒寛次は、京都の蘭学塾“時習堂”で、佐野栄寿(常民)と同門でした。
参考:第7話「尊王義祭」⑩、第8話「黒船来航」③
同時期の話に、50歳にして“時習堂”に入門した、からくり技師(機械技術者)も登場しています。
久留米出身の田中久重。通称“からくり儀右衛門”とも呼ばれる人物です。
――佐野栄寿が、スカウトした技術人材が次々と佐賀に到着する。
「田中どの!お久しゅうござる。」
「おおっ、佐野どのか!久しかのう!」
田中久重は、佐賀に近い久留米(福岡)の生まれである。
年相応の白髭を生やすが、その目は好奇心で活き活きとしている。
故郷の久留米ではないものの、九州に戻ってきた喜びも感じられる。
――上方(京・大坂)では、田中は“からくり儀右衛門”として、寺社の門前などで興業も行っていた。

田中久重の作った精妙な作品は人々を引き付けた。
「人形が弓を曳いたり、筆で文字を書くよ!」
「森羅万象を示し、万年を刻む時鐘(時計)だ!」
「尽きることなく、闇を照らす…無尽灯(むじんとう)だ!」
…このように芝居のような呼び込みまで行われ、既に上方では有名人だったのである。
――佐野の友達の1人、舞鶴出身の蘭学者・石黒寛次。田中久重に声をかける。
「おおっ!“儀右衛門”どの!久方ぶりやないですか。」
「はいっ!」
なぜか、田中久重に同行している男が返事をする。
「ん…何やろ!?」
違和感を感じる、石黒。
「“儀右衛門”どの!」
石黒は、もう1度呼び掛けてみた。
「はっ!何でしょう。」
また、田中久重に同行している男が反応する。
――「ハッハッハ…!」豪快に笑う、田中久重。
「ご紹介しよう!“二代目・からくり儀右衛門”。ワシの後継ぎだ。」
同行していた男は、田中久重の養子。
田中の精妙な作品には欠かせない、練達の金属加工技術者である。
「申し遅れました。田中の跡取りで“儀右衛門”でございます。」
「ほう、“二代目”やったんか。よろしくな。」
石黒が挨拶を返した。
――佐野栄寿。一度は別れた、京都での仲間たちの集結に感無量である。

「ウッ…ウッ!」
佐野栄寿。急に声を詰まらせる。
「佐野はん!どうしはりましたか?」
いつの間にか合流していた、科学者・中村奇輔が様子を伺う。
「皆さま…遠路はるばる…」
このタイミングで感激のあまり涙を流す、佐野。
佐野の呼びかけに応じてくれた仲間たち。しかも地元・佐賀に集まってくれた。涙もろい佐野が泣くには、充分な条件が揃った。
――佐野は、のちに「泣きの常民」とまで言われる。
「おい、おい…佐野、泣いとるで。」
蘭学者・石黒は、反応に困っている。
「佐野はん!次の仕切りを考えなあきまへんで。」
科学者・中村が、話の収拾に着手する。
「ヒック…そうでした…。」
佐野栄寿、ひと泣きして落ち着いた様子だ。
――佐賀藩は伝統的に、“余所者(よそもの)”の受入に厳しい。
長崎では、海外の技術習得に熱心な佐賀藩。
しかし、国内での他藩との交流には、極めて慎重だった。
幕府の海外への“鎖国”と併せて、佐賀の国内への“二重鎖国”と形容されるほどだ。
これには諸説あるようだが、陶磁器などの技術流出を警戒したためとも言われる。
中村が気づいた。
「そこで、あの“ご隠居”さまの、お力添えがある…」
すっかり落ち着いた佐野が答える。
「そがんです!何せ“ご隠居”さまは、人徳のあるお方ですので…」
――たとえ殿の意向があっても、佐賀藩内の保守派は、“余所者”の受入れには難色を示すだろう。
そのため“外部人材”を採用する準備は水面下で進んでいた。
武雄のご隠居・鍋島茂義が動く。
「“役者”が揃ったようだな。では、殿のご機嫌を伺ってくるとするか。」
「行ってらっしゃいませ。殿も、良い知らせをお待ちかねでしょう。」
今回の人材集めの調整役でもあった“蘭学じじい”が見送る。
――そして、殿・鍋島直正は、佐賀藩の理化学研究所「精錬方」を立ち上げる。この翌年(1852年)のことである。
(続く)
前回、佐賀に登場した関西出身の2人。
中村奇輔、石黒寛次は、京都の蘭学塾“時習堂”で、佐野栄寿(常民)と同門でした。
参考:
同時期の話に、50歳にして“時習堂”に入門した、からくり技師(機械技術者)も登場しています。
久留米出身の田中久重。通称“からくり儀右衛門”とも呼ばれる人物です。
――佐野栄寿が、スカウトした技術人材が次々と佐賀に到着する。
「田中どの!お久しゅうござる。」
「おおっ、佐野どのか!久しかのう!」
田中久重は、佐賀に近い久留米(福岡)の生まれである。
年相応の白髭を生やすが、その目は好奇心で活き活きとしている。
故郷の久留米ではないものの、九州に戻ってきた喜びも感じられる。
――上方(京・大坂)では、田中は“からくり儀右衛門”として、寺社の門前などで興業も行っていた。
田中久重の作った精妙な作品は人々を引き付けた。
「人形が弓を曳いたり、筆で文字を書くよ!」
「森羅万象を示し、万年を刻む時鐘(時計)だ!」
「尽きることなく、闇を照らす…無尽灯(むじんとう)だ!」
…このように芝居のような呼び込みまで行われ、既に上方では有名人だったのである。
――佐野の友達の1人、舞鶴出身の蘭学者・石黒寛次。田中久重に声をかける。
「おおっ!“儀右衛門”どの!久方ぶりやないですか。」
「はいっ!」
なぜか、田中久重に同行している男が返事をする。
「ん…何やろ!?」
違和感を感じる、石黒。
「“儀右衛門”どの!」
石黒は、もう1度呼び掛けてみた。
「はっ!何でしょう。」
また、田中久重に同行している男が反応する。
――「ハッハッハ…!」豪快に笑う、田中久重。
「ご紹介しよう!“二代目・からくり儀右衛門”。ワシの後継ぎだ。」
同行していた男は、田中久重の養子。
田中の精妙な作品には欠かせない、練達の金属加工技術者である。
「申し遅れました。田中の跡取りで“儀右衛門”でございます。」
「ほう、“二代目”やったんか。よろしくな。」
石黒が挨拶を返した。
――佐野栄寿。一度は別れた、京都での仲間たちの集結に感無量である。

「ウッ…ウッ!」
佐野栄寿。急に声を詰まらせる。
「佐野はん!どうしはりましたか?」
いつの間にか合流していた、科学者・中村奇輔が様子を伺う。
「皆さま…遠路はるばる…」
このタイミングで感激のあまり涙を流す、佐野。
佐野の呼びかけに応じてくれた仲間たち。しかも地元・佐賀に集まってくれた。涙もろい佐野が泣くには、充分な条件が揃った。
――佐野は、のちに「泣きの常民」とまで言われる。
「おい、おい…佐野、泣いとるで。」
蘭学者・石黒は、反応に困っている。
「佐野はん!次の仕切りを考えなあきまへんで。」
科学者・中村が、話の収拾に着手する。
「ヒック…そうでした…。」
佐野栄寿、ひと泣きして落ち着いた様子だ。
――佐賀藩は伝統的に、“余所者(よそもの)”の受入に厳しい。
長崎では、海外の技術習得に熱心な佐賀藩。
しかし、国内での他藩との交流には、極めて慎重だった。
幕府の海外への“鎖国”と併せて、佐賀の国内への“二重鎖国”と形容されるほどだ。
これには諸説あるようだが、陶磁器などの技術流出を警戒したためとも言われる。
中村が気づいた。
「そこで、あの“ご隠居”さまの、お力添えがある…」
すっかり落ち着いた佐野が答える。
「そがんです!何せ“ご隠居”さまは、人徳のあるお方ですので…」
――たとえ殿の意向があっても、佐賀藩内の保守派は、“余所者”の受入れには難色を示すだろう。
そのため“外部人材”を採用する準備は水面下で進んでいた。
武雄のご隠居・鍋島茂義が動く。
「“役者”が揃ったようだな。では、殿のご機嫌を伺ってくるとするか。」
「行ってらっしゃいませ。殿も、良い知らせをお待ちかねでしょう。」
今回の人材集めの調整役でもあった“蘭学じじい”が見送る。
――そして、殿・鍋島直正は、佐賀藩の理化学研究所「精錬方」を立ち上げる。この翌年(1852年)のことである。
(続く)





