2024年01月23日
「影の上司…?」
こんばんは。
“組織で働く”ということをするならば、切っても切れないものが「上司と部下」。
まず、現代の都会で細々と生きる、私の日常を書いてから、少しだけ幕末期の佐賀の話に入ります。
――ある夜の仕事終わり、職場の入るビルの階段にて。
「“SR”さん、お久しぶりです。」
振り返って話かけてきたのは、私が前にいた職場での部下だった。
私は、かなり彼の後方にいた。まさか、この距離で私の気配を察したのか。
「実は、この男。相当に腕が立つのではないか…」とか考えてみた。
これは、いかん。“佐賀の大河ドラマ”が、私の日常に入り込んでしまっている。早う、現代に戻らんばならんとよ。

――かろうじて現代に立ち戻り、元・上司として様子伺いをする。
「そういや、最近会ってなかったな。元気にしてる?」
私の問いかけに、彼は身体の調子はまずまずだと答えると、こう続けた。
「いま職場で、タチの悪い風邪が流行ってましてね。」
「そうか、今年もか。」
「だいぶ、咳き込んでる人もいますよ。」
以前は“コロナ禍”の影響もあったが、それなりに風邪をひく人もいた気がする。
「それは気を付けないと。」
彼の言葉に、なぜだか私は両拳を顎(あご)の前で構えた。いわゆる、ファイティングポーズというやつだ。
――何と戦おうとしているかと言えば、たぶんウイルスである。
そう、“奴ら”は姿が見えない。もし、懐(ふところ)に入られると、免疫力での勝負になるから厄介だ。
適度に距離をとって、基本の予防対策を怠らずに対処したい…、そんなメッセージが伝わるのか伝わらないのか。
「ところで、今日は寄るところがあってね。」
近場にちょっとした用事があって、ここで道を曲がる。「お疲れさまでした」と言葉をかわして、元・部下と私はここで別れた。

そして、所用が片付いてから、こう思った。
「…あれ、彼は何か言いたいことがあって、話かけてきたか。」
次に会う時には、一応、何か用があったのかは聞いておこう。
――私の日記は、ほどほどにして、少しずつ本題に近づいていく。
もう1年ぐらいも前のことで、昨年春、野球の“ワールドカップ”であるWBCが開催されていた時に、あちこちで、こんな会話があったかもしれない。
部下が「あ~あ、栗山監督みたいな上司がいたら、僕も伸びるんだろうな。」とつぶやく。
その一方で、上司は「俺も、大谷選手みたいな部下がいれば、苦労しねぇんだけどな。」と愚痴を言う。
こういう感じの部下と上司は、私から見ると“お似合い”だと思っている。
「意外と、うまく行ってるんじゃない?」と想像するところだ。
上司も部下も、なかなか選ぶことはできないようです。たとえ組織にいなくても、周囲の人間関係も…同じようなものかもしれません。
――さて、前置きが長くなりました。ここから少しが、いつもの“本題”です。
佐賀藩をテーマにすると…今までの幕末を舞台にした大河ドラマよりも、“組織人”の物語になりそうな気がしています。

大殿(前藩主)・鍋島直正がトップとして、佐賀藩という組織を率いたのですが、もちろん組織内には、さまざまな上司・部下もいたはずです。
チャレンジとして描きたいのが、機密の任務でのつながりがあったと思われる、佐賀藩の重役・鍋島河内(直暠)と大隈重信(八太郎)。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕
大隈は、主に長崎で商人と深くかかわるような活動をしていたのですが、その裏で資金を用意していた人物が…
今までの“本編”では、どうして大隈重信が、明治期の近代化の原動力となり得たかが、あまり描けておらず、第20話では意識していきたいと思います。
“組織で働く”ということをするならば、切っても切れないものが「上司と部下」。
まず、現代の都会で細々と生きる、私の日常を書いてから、少しだけ幕末期の佐賀の話に入ります。
――ある夜の仕事終わり、職場の入るビルの階段にて。
「“SR”さん、お久しぶりです。」
振り返って話かけてきたのは、私が前にいた職場での部下だった。
私は、かなり彼の後方にいた。まさか、この距離で私の気配を察したのか。
「実は、この男。相当に腕が立つのではないか…」とか考えてみた。
これは、いかん。“佐賀の大河ドラマ”が、私の日常に入り込んでしまっている。早う、現代に戻らんばならんとよ。
――かろうじて現代に立ち戻り、元・上司として様子伺いをする。
「そういや、最近会ってなかったな。元気にしてる?」
私の問いかけに、彼は身体の調子はまずまずだと答えると、こう続けた。
「いま職場で、タチの悪い風邪が流行ってましてね。」
「そうか、今年もか。」
「だいぶ、咳き込んでる人もいますよ。」
以前は“コロナ禍”の影響もあったが、それなりに風邪をひく人もいた気がする。
「それは気を付けないと。」
彼の言葉に、なぜだか私は両拳を顎(あご)の前で構えた。いわゆる、ファイティングポーズというやつだ。
――何と戦おうとしているかと言えば、たぶんウイルスである。
そう、“奴ら”は姿が見えない。もし、懐(ふところ)に入られると、免疫力での勝負になるから厄介だ。
適度に距離をとって、基本の予防対策を怠らずに対処したい…、そんなメッセージが伝わるのか伝わらないのか。
「ところで、今日は寄るところがあってね。」
近場にちょっとした用事があって、ここで道を曲がる。「お疲れさまでした」と言葉をかわして、元・部下と私はここで別れた。
そして、所用が片付いてから、こう思った。
「…あれ、彼は何か言いたいことがあって、話かけてきたか。」
次に会う時には、一応、何か用があったのかは聞いておこう。
――私の日記は、ほどほどにして、少しずつ本題に近づいていく。
もう1年ぐらいも前のことで、昨年春、野球の“ワールドカップ”であるWBCが開催されていた時に、あちこちで、こんな会話があったかもしれない。
部下が「あ~あ、栗山監督みたいな上司がいたら、僕も伸びるんだろうな。」とつぶやく。
その一方で、上司は「俺も、大谷選手みたいな部下がいれば、苦労しねぇんだけどな。」と愚痴を言う。
こういう感じの部下と上司は、私から見ると“お似合い”だと思っている。
「意外と、うまく行ってるんじゃない?」と想像するところだ。
上司も部下も、なかなか選ぶことはできないようです。たとえ組織にいなくても、周囲の人間関係も…同じようなものかもしれません。
――さて、前置きが長くなりました。ここから少しが、いつもの“本題”です。
佐賀藩をテーマにすると…今までの幕末を舞台にした大河ドラマよりも、“組織人”の物語になりそうな気がしています。
大殿(前藩主)・鍋島直正がトップとして、佐賀藩という組織を率いたのですが、もちろん組織内には、さまざまな上司・部下もいたはずです。
チャレンジとして描きたいのが、機密の任務でのつながりがあったと思われる、佐賀藩の重役・鍋島河内(直暠)と大隈重信(八太郎)。
〔参照(後半):
大隈は、主に長崎で商人と深くかかわるような活動をしていたのですが、その裏で資金を用意していた人物が…
今までの“本編”では、どうして大隈重信が、明治期の近代化の原動力となり得たかが、あまり描けておらず、第20話では意識していきたいと思います。
2024年01月15日
「幕末娘の“推し活”」
こんばんは。
最近、好きな芸能人等を「推し」という表現で語るのをよく聞きます。年末年始のテレビ番組やネット配信、貴方の“推し”は元気な姿を見せたでしょうか。
ちなみに「“推し”がいるから、日常でも頑張れる!」と好きなアイドル等の応援に励むことを「推し活」というそうです。
ところで、幕末の黎明期だった文化・文政年間(1804年~1830年)。
当時は佐賀藩の諫早領だった、現在の佐賀県太良町あたりに、幕末の村娘たちのアイドルだったという、伝説の美少年がいました。

――題材は、佐賀県の民謡・『岳(たけ)の新太郎さん』
佐賀県内の若い方でも、この民謡の存在は知っているが、古い歌だと思っている人が多いのではないでしょうか。
幾度か語っていますが、角度を変えてまた書きます。「けっこう現代っぽい感覚の歌なんです…」という視点で、今回は、この民謡そのものを説明してみます。
民謡といえば、希望の見えない、辛い日々の労働などを歌い込んだ「日本版“ブルース”」のような曲も多いと思います。
まだまだ江戸時代だった幕末黎明期を題材とした、この佐賀県民謡。

現在の形になったのは、後年かもしれませんが、当時の佐賀県の女子たちが、陽気な“ラブソング”とともに生きていたことを感じさせるのです。
しかも“ラブソング”とはいっても、彼女たちの妄想のような歌で、それも現代的な感じがします。
――「アイドルを、“出待ち”するファンの歌」みたいなものでしょうか。
でも、まずは時代背景を考えます。当ブログを熱心にお読みいただいている方ならば、この話題にもそこそこ関心を持っていただけるはず…
1804年 ロシアのレザノフが長崎に来航 幕府に通商を迫る
→佐賀藩は、千人体制で長崎港の警備を固める

1808年 イギリスのフェートン号が長崎港に侵入
→佐賀藩は、出費を嫌がって長崎に警備隊をおいておらず厳重処罰される
1814年 のちの第10代佐賀藩主・鍋島直正 江戸の藩邸で誕生する
1825年 幕府が異国船打払令を出す
→佐賀藩は、その前年に長崎警備を熊本藩に押しつけようとして失敗
“名君”の就任前なので、佐賀藩は財政難に苦しみ、迷走している時期です。出費が嵩む長崎警備をどうにかしたい…という辺りに、時代が出ています。

年表から20年くらい後には、次の殿様・鍋島直正が「佐賀藩の独力でも長崎を守ってみせる!」と、すごい責任感で港の入口を要塞化するのですが…
幕府から異国船打払令が出た時期には、日本の表玄関である、長崎の警備から手を引いて(熊本に押しつけて)、パスしようとしています。
――こんな激動の時代に「アイドルの出待ちソング」とは。
ここでも、「やはり佐賀は最先端だった…」と言えるのかもしれません。
多良岳の山頂にある金泉寺、ここが寺侍だった“岳の新太郎さん”の勤務地。修験道の霊峰と聞く多良岳。
厳しい修行の場である、その寺も当時は女人禁制でした。
かくして、幕末のハンサム侍である“岳の新太郎さん”の姿を見たい女子たちは、自分たちからその姿を見に行くことはできません。

――月に幾度だけ用務のために、山から下りてくる“岳の新太郎さん”
イメージとして示されるのは、涼しげな顔立ちに、どこか神々しい美少年。下山のときは、会いたくても会えないアイドルの“ご尊顔”を拝むチャンス。
アイドルが登場した時、歓声とともに「尊(とうと)い~!」とペンライトを振る、現代の女子の姿が重なるようです。
彼女たちの感情は、ザンザザンザ…という擬音で表されます。これは、乙女の気持ちの高鳴りを、近隣に多くあった水車の音に喩えたものと聞きました。

――稀(まれ)に見られる、その“アイドル”の姿は…
「色者(イロシャ)の粋者(スイシャ)」と表現されています。
年若くして、女人禁制の寺に勤める、寺侍の“岳の新太郎さん”。山に籠もっているときには、おそらく女性と関わる機会は無いはず。
それが触れてはいけない禁断の香りを漂わせるのか、ただのモテ男とは違う、清廉さと神秘性を醸し出しています。
普段、見ることができないからこそ、その姿をはっきり見たい…

――彼女たちの妄想は、さらに強くなり…
“岳の新太郎さん”が来る時には、千の灯籠で周囲を照らし、帰ろうとする時には道に水をかけてでも、歩みを遅らせる…
少しでも長く“アイドル”の姿を見ていたいという、気持ちの表現なのでしょう。
「岳の新太郎さんの、来らすとよ~」とキャッキャする、当時の佐賀女子たちのざわめきが目に浮かぶようです。
その歌詞は「竿じゃ届かぬ、高木の熟柿」と続き、その存在が“高嶺の花”であったことが表現されています。
――おそらくは、その思いは思いのままで…
歌詞には続きがあるそうで、「傘を忘れた、山茶花の茶屋」に「空が曇れば思い出す…」と、何だか叙情的で、歳月を経た回想のような印象を感じます。

ちなみに、「山茶花(さざんか)茶屋」で調べると、県境を越えた長崎県諫早市に、その跡地の情報が出てきました。実は、近代へと続く道『多良海道』…。
そこは、また語るとして、時は流れ“アイドル”に熱狂した、若き日々の後にも、きっと、彼女たちの人生は続いていきます。
私の解釈は中途半端なので、その正確さはともかく、あらためて歌詞を追うと、とても現代的な民謡という感想を得ました。
――先ほどの“歴史年表”から3年ほど後、
1828年には、子年の大風(シーボルト台風)が発生。現在の太良町内では、灯台が倒れるほどの威力の風が吹き、大きな被害が出たことが伝わります。

私は感情移入しやすいので、“岳の新太郎さん”に熱狂した彼女たちは、無事だったのだろうか…ということも考えます。
財政難の折、台風でさらに大きな被害を受けた佐賀藩。こうして、迷走のうちに文政年間が終わっていきます。
そして、天保元年(1830年)には数え年で17歳。若き藩主となった鍋島直正が佐賀を率いることになり、新しい時代が進んでいきます。
――“本編”の第20話「長崎方控」では、
この佐賀県民謡の要素を、少し取り込んでいこうかと考えています。
「もっと、佐賀を語っていこう」というのは、今年のテーマでもあるので、どんな表現になるか…期待できそうな方は、気長にお待ちいただければ幸いです。
○過去の関連記事
(岳の新太郎さん)「主に太良町民の皆様を対象にしたつぶやき」
(多良海道の紹介)「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕
(本編での多良海道)第16話「攘夷沸騰」⑭(多良海道の往還)
最近、好きな芸能人等を「推し」という表現で語るのをよく聞きます。年末年始のテレビ番組やネット配信、貴方の“推し”は元気な姿を見せたでしょうか。
ちなみに「“推し”がいるから、日常でも頑張れる!」と好きなアイドル等の応援に励むことを「推し活」というそうです。
ところで、幕末の黎明期だった文化・文政年間(1804年~1830年)。
当時は佐賀藩の諫早領だった、現在の佐賀県太良町あたりに、幕末の村娘たちのアイドルだったという、伝説の美少年がいました。
――題材は、佐賀県の民謡・『岳(たけ)の新太郎さん』
佐賀県内の若い方でも、この民謡の存在は知っているが、古い歌だと思っている人が多いのではないでしょうか。
幾度か語っていますが、角度を変えてまた書きます。「けっこう現代っぽい感覚の歌なんです…」という視点で、今回は、この民謡そのものを説明してみます。
民謡といえば、希望の見えない、辛い日々の労働などを歌い込んだ「日本版“ブルース”」のような曲も多いと思います。
まだまだ江戸時代だった幕末黎明期を題材とした、この佐賀県民謡。
現在の形になったのは、後年かもしれませんが、当時の佐賀県の女子たちが、陽気な“ラブソング”とともに生きていたことを感じさせるのです。
しかも“ラブソング”とはいっても、彼女たちの妄想のような歌で、それも現代的な感じがします。
――「アイドルを、“出待ち”するファンの歌」みたいなものでしょうか。
でも、まずは時代背景を考えます。当ブログを熱心にお読みいただいている方ならば、この話題にもそこそこ関心を持っていただけるはず…
1804年 ロシアのレザノフが長崎に来航 幕府に通商を迫る
→佐賀藩は、千人体制で長崎港の警備を固める

1808年 イギリスのフェートン号が長崎港に侵入
→佐賀藩は、出費を嫌がって長崎に警備隊をおいておらず厳重処罰される
1814年 のちの第10代佐賀藩主・鍋島直正 江戸の藩邸で誕生する
1825年 幕府が異国船打払令を出す
→佐賀藩は、その前年に長崎警備を熊本藩に押しつけようとして失敗
“名君”の就任前なので、佐賀藩は財政難に苦しみ、迷走している時期です。出費が嵩む長崎警備をどうにかしたい…という辺りに、時代が出ています。
年表から20年くらい後には、次の殿様・鍋島直正が「佐賀藩の独力でも長崎を守ってみせる!」と、すごい責任感で港の入口を要塞化するのですが…
幕府から異国船打払令が出た時期には、日本の表玄関である、長崎の警備から手を引いて(熊本に押しつけて)、パスしようとしています。
――こんな激動の時代に「アイドルの出待ちソング」とは。
ここでも、「やはり佐賀は最先端だった…」と言えるのかもしれません。
多良岳の山頂にある金泉寺、ここが寺侍だった“岳の新太郎さん”の勤務地。修験道の霊峰と聞く多良岳。
厳しい修行の場である、その寺も当時は女人禁制でした。
かくして、幕末のハンサム侍である“岳の新太郎さん”の姿を見たい女子たちは、自分たちからその姿を見に行くことはできません。
――月に幾度だけ用務のために、山から下りてくる“岳の新太郎さん”
イメージとして示されるのは、涼しげな顔立ちに、どこか神々しい美少年。下山のときは、会いたくても会えないアイドルの“ご尊顔”を拝むチャンス。
アイドルが登場した時、歓声とともに「尊(とうと)い~!」とペンライトを振る、現代の女子の姿が重なるようです。
彼女たちの感情は、ザンザザンザ…という擬音で表されます。これは、乙女の気持ちの高鳴りを、近隣に多くあった水車の音に喩えたものと聞きました。
――稀(まれ)に見られる、その“アイドル”の姿は…
「色者(イロシャ)の粋者(スイシャ)」と表現されています。
年若くして、女人禁制の寺に勤める、寺侍の“岳の新太郎さん”。山に籠もっているときには、おそらく女性と関わる機会は無いはず。
それが触れてはいけない禁断の香りを漂わせるのか、ただのモテ男とは違う、清廉さと神秘性を醸し出しています。
普段、見ることができないからこそ、その姿をはっきり見たい…
――彼女たちの妄想は、さらに強くなり…
“岳の新太郎さん”が来る時には、千の灯籠で周囲を照らし、帰ろうとする時には道に水をかけてでも、歩みを遅らせる…
少しでも長く“アイドル”の姿を見ていたいという、気持ちの表現なのでしょう。
「岳の新太郎さんの、来らすとよ~」とキャッキャする、当時の佐賀女子たちのざわめきが目に浮かぶようです。
その歌詞は「竿じゃ届かぬ、高木の熟柿」と続き、その存在が“高嶺の花”であったことが表現されています。
――おそらくは、その思いは思いのままで…
歌詞には続きがあるそうで、「傘を忘れた、山茶花の茶屋」に「空が曇れば思い出す…」と、何だか叙情的で、歳月を経た回想のような印象を感じます。
ちなみに、「山茶花(さざんか)茶屋」で調べると、県境を越えた長崎県諫早市に、その跡地の情報が出てきました。実は、近代へと続く道『多良海道』…。
そこは、また語るとして、時は流れ“アイドル”に熱狂した、若き日々の後にも、きっと、彼女たちの人生は続いていきます。
私の解釈は中途半端なので、その正確さはともかく、あらためて歌詞を追うと、とても現代的な民謡という感想を得ました。
――先ほどの“歴史年表”から3年ほど後、
1828年には、子年の大風(シーボルト台風)が発生。現在の太良町内では、灯台が倒れるほどの威力の風が吹き、大きな被害が出たことが伝わります。
私は感情移入しやすいので、“岳の新太郎さん”に熱狂した彼女たちは、無事だったのだろうか…ということも考えます。
財政難の折、台風でさらに大きな被害を受けた佐賀藩。こうして、迷走のうちに文政年間が終わっていきます。
そして、天保元年(1830年)には数え年で17歳。若き藩主となった鍋島直正が佐賀を率いることになり、新しい時代が進んでいきます。
――“本編”の第20話「長崎方控」では、
この佐賀県民謡の要素を、少し取り込んでいこうかと考えています。
「もっと、佐賀を語っていこう」というのは、今年のテーマでもあるので、どんな表現になるか…期待できそうな方は、気長にお待ちいただければ幸いです。
○過去の関連記事
(岳の新太郎さん)
(多良海道の紹介)
(本編での多良海道)
2024年01月10日
「顔で笑って、肚(はら)で泣く」
こんばんは。当面の間は、本編・第20話の下書きを進めたいと思いますので、時折、佐賀県や大河ドラマにかかわった雑談をします。
いつか「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と語り続けている私。
毎年の大河だけでなく、ドラマの配役を見ると、「この俳優さんが、あの佐賀の賢人を演じるとどうなるかな…」とシミュレーションをしてしまう事があります。
本日は、昨年に見たドラマを前振りとして語っていきます。そもそも番組を視聴していない方にはわかりづらく、うろ覚えの事柄もありますが、ご容赦ください。

――昨年の晩秋に、NHK(月-木曜の夜 22:45~)の…
「夜ドラ」の枠で、『ミワさんなりすます』というドラマが放送されていました。
筋書きは詳しく書きませんが、世界的に有名な俳優に強い憧れを持ち、映画が大好きだが、あまり生き方が上手くない女子の物語。
主人公・久保田ミワ役は、某携帯電話会社のCMでも見かける松本穂香さん。昭和期を描いたドラマでも見かけており、古風な雰囲気も出せる女優さんです。
〔参照(終盤):「“大河ドラマ” 誕生秘話を見て」〕

その映画大好き女子が、一生をかけて“推す”という憧れの俳優・八海崇役は、堤真一さんが演じました。
――この物語が結構、面白かったのです。
真面目だが要領が良くなくて、何かと損をしてきた主人公。偶然、その俳優宅の家政婦に“なりすます”機会を得て、生活が一変するという展開の話です。
主人公のミワさんは、うまく行かない現実には耐えつづけて、映画の世界だけが生きがいという設定。

彼女が画面の向こう側から見つめる、憧れの俳優を評した言葉があります。「顔で笑って、肚(はら)で泣く、そんな演技が俳優・八海崇の真骨頂だ…」と。
――そのセリフを耳にした視聴者の私は…
「たぶん、そういう存在感が要りますよね…」と、妙に得心します。
私は、佐賀の大河ドラマをイメージしたブログを書いていますので、いざドラマを見だすと、一般的なテレビ視聴とは別の要素も入ってきます。
寂しそうに笑うときの説得力とか、活字にすれば滑稽なセリフに、深い苦悩がこもっているとか…

佐賀の大殿・鍋島直正公を表現するにあたって、使いたいキーワードが、先ほどのドラマの「顔で笑って~」の台詞に凝縮していました。
――現時点での、個人的な意見ですが、
もし、佐賀の大殿・鍋島直正役を演じてほしい俳優さんをイメージすると、このドラマで“世界的俳優”を演じた、堤真一さんが一番近い、と考えています。
〔参照(終盤):「二つの感想」〕
明暗の二面性を上手く表現できそうで、“本編”のある場面で想定する「痔(じ)でござってな」という言葉も、この方なら、カッコ良く決めてくれる気がします。
一見して、ただの体調不良アピールですが、台詞に込められた想いで、全国の視聴者が涙する…そんな演技ができる俳優さんではないかと思うのです。

――ちなみに実際のテレビドラマで、鍋島直正役を演じた人と言えば、
今のところ、小日向文世さんのキャストで見た記憶があります。
これもNHKだったのですが、北海道150周年の記念ドラマとして放送された『永遠のニシパ』の終盤に少しだけ登場しました。
――明治初期に、蝦夷地に新しい名を付ける場面。
当時は大納言に任じられ、旧大名の中でも新政府中枢にいた鍋島直正公は、蝦夷地の開拓長官という立場で登場します。

ドラマでの鍋島直正も、松浦武四郎〔演:松本潤〕の考案した「北海道」という名を採用し、日本の一部であることを明確にする重要な役回りでした。
小日向さんは、一瞬の登場でも「ただ者ではない」ことが示される俳優さんなので、ドラマの進行上も効果的な配役だったと思います。
――幕末の日本で、最も“世界”が見えていた“殿様”。
直正公については、近代化を引っ張った「名君中の名君」という評価もしっかりありますが、同時に国内の政治闘争から距離をおいていたことも伝わります。
「諸外国の動向を見て、国内の衝突を回避する」という意図だったと考えますが、周囲は「佐賀はどう動くかわからない」と疑心暗鬼になっていたようです。
結果、幕末期に「大陰謀家」だとか「肥前の妖怪」とまで語られ、明治期には長生きしなかったので、風評のイメージが残ってしまったのは哀しいことです。
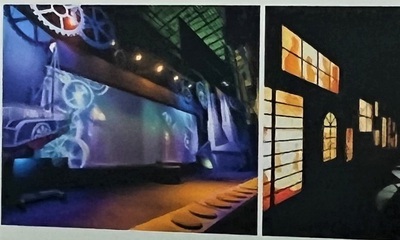
――本来なら、すでに数々のドラマに登場して、
様々な名優さんが演じていても不思議ではない、鍋島直正公。
きっと物語の質と量が、まだ足りていないのです。この辺りは、私も“本編”を書き進める中で、いろいろな可能性を探っていきたいです。
鍋島直正役のイメージについて、ネット上で見ると大泉洋さんが適役だとか、岸部一徳さんの雰囲気だとか、人それぞれの感覚があるようです。
佐賀の名君に誇りを感じる全ての人へ。貴方ならば、どんな俳優さんに演じてほしいでしょうか。
いつか「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と語り続けている私。
毎年の大河だけでなく、ドラマの配役を見ると、「この俳優さんが、あの佐賀の賢人を演じるとどうなるかな…」とシミュレーションをしてしまう事があります。
本日は、昨年に見たドラマを前振りとして語っていきます。そもそも番組を視聴していない方にはわかりづらく、うろ覚えの事柄もありますが、ご容赦ください。
――昨年の晩秋に、NHK(月-木曜の夜 22:45~)の…
「夜ドラ」の枠で、『ミワさんなりすます』というドラマが放送されていました。
筋書きは詳しく書きませんが、世界的に有名な俳優に強い憧れを持ち、映画が大好きだが、あまり生き方が上手くない女子の物語。
主人公・久保田ミワ役は、某携帯電話会社のCMでも見かける松本穂香さん。昭和期を描いたドラマでも見かけており、古風な雰囲気も出せる女優さんです。
〔参照(終盤):

その映画大好き女子が、一生をかけて“推す”という憧れの俳優・八海崇役は、堤真一さんが演じました。
――この物語が結構、面白かったのです。
真面目だが要領が良くなくて、何かと損をしてきた主人公。偶然、その俳優宅の家政婦に“なりすます”機会を得て、生活が一変するという展開の話です。
主人公のミワさんは、うまく行かない現実には耐えつづけて、映画の世界だけが生きがいという設定。
彼女が画面の向こう側から見つめる、憧れの俳優を評した言葉があります。「顔で笑って、肚(はら)で泣く、そんな演技が俳優・八海崇の真骨頂だ…」と。
――そのセリフを耳にした視聴者の私は…
「たぶん、そういう存在感が要りますよね…」と、妙に得心します。
私は、佐賀の大河ドラマをイメージしたブログを書いていますので、いざドラマを見だすと、一般的なテレビ視聴とは別の要素も入ってきます。
寂しそうに笑うときの説得力とか、活字にすれば滑稽なセリフに、深い苦悩がこもっているとか…
佐賀の大殿・鍋島直正公を表現するにあたって、使いたいキーワードが、先ほどのドラマの「顔で笑って~」の台詞に凝縮していました。
――現時点での、個人的な意見ですが、
もし、佐賀の大殿・鍋島直正役を演じてほしい俳優さんをイメージすると、このドラマで“世界的俳優”を演じた、堤真一さんが一番近い、と考えています。
〔参照(終盤):
明暗の二面性を上手く表現できそうで、“本編”のある場面で想定する「痔(じ)でござってな」という言葉も、この方なら、カッコ良く決めてくれる気がします。
一見して、ただの体調不良アピールですが、台詞に込められた想いで、全国の視聴者が涙する…そんな演技ができる俳優さんではないかと思うのです。
――ちなみに実際のテレビドラマで、鍋島直正役を演じた人と言えば、
今のところ、小日向文世さんのキャストで見た記憶があります。
これもNHKだったのですが、北海道150周年の記念ドラマとして放送された『永遠のニシパ』の終盤に少しだけ登場しました。
――明治初期に、蝦夷地に新しい名を付ける場面。
当時は大納言に任じられ、旧大名の中でも新政府中枢にいた鍋島直正公は、蝦夷地の開拓長官という立場で登場します。
ドラマでの鍋島直正も、松浦武四郎〔演:松本潤〕の考案した「北海道」という名を採用し、日本の一部であることを明確にする重要な役回りでした。
小日向さんは、一瞬の登場でも「ただ者ではない」ことが示される俳優さんなので、ドラマの進行上も効果的な配役だったと思います。
――幕末の日本で、最も“世界”が見えていた“殿様”。
直正公については、近代化を引っ張った「名君中の名君」という評価もしっかりありますが、同時に国内の政治闘争から距離をおいていたことも伝わります。
「諸外国の動向を見て、国内の衝突を回避する」という意図だったと考えますが、周囲は「佐賀はどう動くかわからない」と疑心暗鬼になっていたようです。
結果、幕末期に「大陰謀家」だとか「肥前の妖怪」とまで語られ、明治期には長生きしなかったので、風評のイメージが残ってしまったのは哀しいことです。
――本来なら、すでに数々のドラマに登場して、
様々な名優さんが演じていても不思議ではない、鍋島直正公。
きっと物語の質と量が、まだ足りていないのです。この辺りは、私も“本編”を書き進める中で、いろいろな可能性を探っていきたいです。
鍋島直正役のイメージについて、ネット上で見ると大泉洋さんが適役だとか、岸部一徳さんの雰囲気だとか、人それぞれの感覚があるようです。
佐賀の名君に誇りを感じる全ての人へ。貴方ならば、どんな俳優さんに演じてほしいでしょうか。
2024年01月07日
「“光る君へ”、直前に」
こんにちは。
年始に想定外のことがあり、言葉に詰まるところもあるのですが、深呼吸をして淡々と続けます。昨年末には、これからのブログの進め方を考えていました。
“本編”の第18話・第19話は構成上、京都を舞台とした話が多くなっており、次話(第20話)は、なるべく佐賀と長崎を場面設定に入れたいと思っています。
今年こそ、少し時間をとって佐賀県に滞在したい願望も書いていたところです。
――その前に、今年の大河ドラマ初回が気になる。
2024年大河ドラマ『光る君へ』。
予告を見る限りでは、動く美術館のような映像美。華やかな色彩との対比で、際立つ壮絶な権力闘争…というような印象を持ちました。

大河ドラマファンにありがち(?)な傾向かもしれませんが、その年の放送作品を見て、その時代に興味を持つ。
登場人物や出来事を調べたくなって、さらに知識が深くなる…という、ループ(循環)が私にもあります。
――平安時代については、細かい知識が乏しいです。
平安末期の京都ならば、2012年大河ドラマ『平清盛』〔主演:松山ケンイチ〕で描かれていたのが、記憶にあります。
その時は、武士の世の幕開けにいたる、混沌とした世情が砂煙の舞うリアルな映像で表現された印象です。
同作は画面の暗さが批判の対象にもなりましたが、闇に潜む底知れない何かを感じさせる…そんな余韻のある作品だったと感じています。

そして、昨年の『どうする家康』では、“軍師、あるいはイカサマ師(?)”という難役・本多正信を演じた、松山ケンイチさん。
私には、『平清盛』での蓄積がすごく活きていると感じられました。
――ひと言で“平安時代”と言っても…
藤原道長(平安中期)と、先ほどの平清盛(平安末期)とを誕生年で比べると、150年くらい開きがあるようです。
言ってしまえば、幕末の佐賀藩士と、現代の佐賀県民ぐらいの年代差。
まだ平安中期の話で、源平合戦はずっと後ですから、今作は光と影の対比で、華やかな部分を際立たせるのかなと予想します。
過去作で、詳細に描かれていない平安貴族の時代だけに「どんな筋書きになるのか、全く想像できない」のが面白いです。

――しかも、初回が子役なのも久しぶり(?)な感じ。
のちの紫式部(役名:まひろ)を吉高由里子さんが、藤原道長を柄本佑さんが演じることは、かなり前に発表されています。
主役のお2人は初回放送ではあまり出番が無さそうで、幼少期の物語のみが展開するのかもしれません。
私の浅い理解でいえば、紫式部は、藤原道長の娘が入内して中宮(皇后)になった時、教養を高めるために付いた先生。
平安中期の宮中は、教養のある女性を集めたサロンで、歌や日記などの文学で競うようなところが見えます。
紫式部も、また“家庭教師、あるいは軍師(?)”なのかもしれません。

――少々、力技ですが、佐賀県の話につなげます。
紫式部と関わりのあった、同時代の教養人に和泉式部がいます。
生没年不詳でミステリアスなのですが、知性と教養で宮中の女性たちが、鎬(しのぎ)を削った時代に、凄腕の歌人として知られた、和泉式部。
その生涯にかかる記録の少なさから、実は全国の各地に和泉式部ゆかりの地が存在しているようです。
佐賀県では、白石町で生誕し、幼少期は嬉野市で育った伝説が残っていて、同市の塩田町には“和泉式部公園”まで存在します。

――もし、大河ドラマで、“佐賀県出身説”が採用でもされたら…
もし、私に近い思考回路の人であれば、大喜びすると思います。
たぶん、和泉式部の登場はあっても出身地の描写は無いか、あっても畿内の周辺だと考えていますが、こんなサプライズがあったなら歓迎ですね。
ここは期待しすぎない程度に待ちましょう。
○関連記事(前半)「醒覚の剣(歌枕)」
年始に想定外のことがあり、言葉に詰まるところもあるのですが、深呼吸をして淡々と続けます。昨年末には、これからのブログの進め方を考えていました。
“本編”の第18話・第19話は構成上、京都を舞台とした話が多くなっており、次話(第20話)は、なるべく佐賀と長崎を場面設定に入れたいと思っています。
今年こそ、少し時間をとって佐賀県に滞在したい願望も書いていたところです。
――その前に、今年の大河ドラマ初回が気になる。
2024年大河ドラマ『光る君へ』。
予告を見る限りでは、動く美術館のような映像美。華やかな色彩との対比で、際立つ壮絶な権力闘争…というような印象を持ちました。
大河ドラマファンにありがち(?)な傾向かもしれませんが、その年の放送作品を見て、その時代に興味を持つ。
登場人物や出来事を調べたくなって、さらに知識が深くなる…という、ループ(循環)が私にもあります。
――平安時代については、細かい知識が乏しいです。
平安末期の京都ならば、2012年大河ドラマ『平清盛』〔主演:松山ケンイチ〕で描かれていたのが、記憶にあります。
その時は、武士の世の幕開けにいたる、混沌とした世情が砂煙の舞うリアルな映像で表現された印象です。
同作は画面の暗さが批判の対象にもなりましたが、闇に潜む底知れない何かを感じさせる…そんな余韻のある作品だったと感じています。
そして、昨年の『どうする家康』では、“軍師、あるいはイカサマ師(?)”という難役・本多正信を演じた、松山ケンイチさん。
私には、『平清盛』での蓄積がすごく活きていると感じられました。
――ひと言で“平安時代”と言っても…
藤原道長(平安中期)と、先ほどの平清盛(平安末期)とを誕生年で比べると、150年くらい開きがあるようです。
言ってしまえば、幕末の佐賀藩士と、現代の佐賀県民ぐらいの年代差。
まだ平安中期の話で、源平合戦はずっと後ですから、今作は光と影の対比で、華やかな部分を際立たせるのかなと予想します。
過去作で、詳細に描かれていない平安貴族の時代だけに「どんな筋書きになるのか、全く想像できない」のが面白いです。
――しかも、初回が子役なのも久しぶり(?)な感じ。
のちの紫式部(役名:まひろ)を吉高由里子さんが、藤原道長を柄本佑さんが演じることは、かなり前に発表されています。
主役のお2人は初回放送ではあまり出番が無さそうで、幼少期の物語のみが展開するのかもしれません。
私の浅い理解でいえば、紫式部は、藤原道長の娘が入内して中宮(皇后)になった時、教養を高めるために付いた先生。
平安中期の宮中は、教養のある女性を集めたサロンで、歌や日記などの文学で競うようなところが見えます。
紫式部も、また“家庭教師、あるいは軍師(?)”なのかもしれません。
――少々、力技ですが、佐賀県の話につなげます。
紫式部と関わりのあった、同時代の教養人に和泉式部がいます。
生没年不詳でミステリアスなのですが、知性と教養で宮中の女性たちが、鎬(しのぎ)を削った時代に、凄腕の歌人として知られた、和泉式部。
その生涯にかかる記録の少なさから、実は全国の各地に和泉式部ゆかりの地が存在しているようです。
佐賀県では、白石町で生誕し、幼少期は嬉野市で育った伝説が残っていて、同市の塩田町には“和泉式部公園”まで存在します。
――もし、大河ドラマで、“佐賀県出身説”が採用でもされたら…
もし、私に近い思考回路の人であれば、大喜びすると思います。
たぶん、和泉式部の登場はあっても出身地の描写は無いか、あっても畿内の周辺だと考えていますが、こんなサプライズがあったなら歓迎ですね。
ここは期待しすぎない程度に待ちましょう。
○関連記事(前半)
2024年01月05日
「涙が出た、正月」
こんばんは。
私のブログは、いつか「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい」という趣旨で書いているもの。
本日は少し、本筋から外れた話をします。私なりの気持ちの整理を付けるための文章です。
なお、私の感情の動きに基づいた、主観的な内容であり、正確性を伴わないことを申し添えます。
――1月1日の、16時過ぎ。
正月のお休みだった私は『さがファンブログ』でお読みいただいている皆様に、年始のご挨拶がわりの記事を整えていました。
そんな時、テレビから何とも耳を衝くようなアラーム音が響きます。
「また、地震か…」と思ったのですが、そこまでは事の重大性には気付いていませんでした。
――異変に気付いたのは、その後。
例によって、NHKの放送を付けていたのですが、聞こえてくる女性の声が、何とも野太く聞こえるのです。
始めに聞いた時は、その声がとても女子アナウンサーのものとは思えず、「防災を専門とする何者かの発声なのか!?」とさえ思いました。
よく訓練された声で「いますぐ逃げること!」と叫ぶ、彼女の姿は見えません。
――「津波の危険があるところから離れて!」
「すぐ逃げて!」と繰り返される言葉。「テレビを見ている場合ではない!」と、その場に留まっている人への一喝までありました。
もちろん現場にいたわけでもなく、「高台まで後ろを振り向かず進め!」とばかりの、画面から流れる声を聞き続ける私は、しばらく呆然としました。
まるで、軍隊の司令のように、声を張り続ける女性。さすがに、非常事態が起きていることは認識できるようになりました。
――そして、涙が出てきました。
「この人、いま戦っている…」
表現としては適切かわかりませんが、昔、映画の予告だけを見た記憶がある、“ジャンヌ・ダルク”の映像を思い出しました。
「フォロー・ミー!(私に続け)」と声を張るシーンが妙に印象に残ったのです。
たぶん、私の感情の混乱もあるのですが、テレビの向こう側で姿の見えない“英雄”が、画面の向こう側の人々を救おうと声を振り絞っている…
――そういう、感覚を持ちました。
すでに言及されている方も多いのですが、正月2日目の夕刻にも、気持ちを揺さぶられる事故がありました。
羽田空港で航空機が燃えている…という情報を見かけたのです。
「なんて、正月だ…」
映像を見て、唖然としました。空港の滑走路で旅客機が炎上しているのが、映し出されています。
「まさか…乗客、まだ降りてないのか!?」
気が気でなかったのですが、この心配は、ニュース速報で打ち消されました。
――その時点で、全ての乗客が降りていたと。
すでに旅客機の乗務員が、全員を機体から退避させていたそうです。衝突のアクシデントが起きてからの離脱で、機内全員が無事…
訓練では想定していた事態なのかもしれませんが、乗客一人ひとりが生身で存在し、意思を持って動く中でどう対応したのか。
これを実際にやってのけるとは…日本ではあまり聞かない表現ですが、すでに海外の報道では“英雄”的な仕事と賞賛されていると聞きます。
――旅客機のクルーにより、乗客の命は守られましたが…
そのあと、旅客機に衝突したのが、海上保安庁の飛行機であり、そもそも能登半島に救援物資を運ぶところだった…と知りました。
これを聞いたら、また涙が出てきました。おそらくは、緊急時の準備を整えて“少しでも早く”と出動したのでしょう。
そんな方々が、命を落としたと認識すると、いたたまれないものがあります。
――こんな、正月三が日は記憶にない…
自分の狭い人生の中で、年始が大変だった時期の記憶もありますが、ちょっとスケールの違いすぎる、涙の正月。
たしか3日目の夜にも、私はニュースを見て、目に溜まる涙を感じていました。
被災地となった町の、倒壊したビルの下。オレンジの隊服の複数名が確認できます。他地域から到着した救援隊のようです。
「…取り残された人を救おうとしているのか。」
――この場面で、余震が起きたらしく、
救援隊は、一時ビルの下から退避します。その姿を見ていたら、結局、3日続けて涙が出てきました。
倒壊したビルが崩れることも容易に想像できます。もう、完全に命懸けの仕事。
「すごい、すごすぎる…とても真似ができない。」
――正直、私が何をできるわけでもない。
おそらくは歳を重ねて涙もろくもなっています。でも、彼らのはたらきを賞賛したい。少なくとも、頑張っている人たちの足を引っ張るような生き方はするまい…、
できれば巡り巡ってでも良いので、どこかで何かの助けになるように、しっかり生きようと思う。この正月に感じたことでした。
私のブログは、いつか「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい」という趣旨で書いているもの。
本日は少し、本筋から外れた話をします。私なりの気持ちの整理を付けるための文章です。
なお、私の感情の動きに基づいた、主観的な内容であり、正確性を伴わないことを申し添えます。
――1月1日の、16時過ぎ。
正月のお休みだった私は『さがファンブログ』でお読みいただいている皆様に、年始のご挨拶がわりの記事を整えていました。
そんな時、テレビから何とも耳を衝くようなアラーム音が響きます。
「また、地震か…」と思ったのですが、そこまでは事の重大性には気付いていませんでした。
――異変に気付いたのは、その後。
例によって、NHKの放送を付けていたのですが、聞こえてくる女性の声が、何とも野太く聞こえるのです。
始めに聞いた時は、その声がとても女子アナウンサーのものとは思えず、「防災を専門とする何者かの発声なのか!?」とさえ思いました。
よく訓練された声で「いますぐ逃げること!」と叫ぶ、彼女の姿は見えません。
――「津波の危険があるところから離れて!」
「すぐ逃げて!」と繰り返される言葉。「テレビを見ている場合ではない!」と、その場に留まっている人への一喝までありました。
もちろん現場にいたわけでもなく、「高台まで後ろを振り向かず進め!」とばかりの、画面から流れる声を聞き続ける私は、しばらく呆然としました。
まるで、軍隊の司令のように、声を張り続ける女性。さすがに、非常事態が起きていることは認識できるようになりました。
――そして、涙が出てきました。
「この人、いま戦っている…」
表現としては適切かわかりませんが、昔、映画の予告だけを見た記憶がある、“ジャンヌ・ダルク”の映像を思い出しました。
「フォロー・ミー!(私に続け)」と声を張るシーンが妙に印象に残ったのです。
たぶん、私の感情の混乱もあるのですが、テレビの向こう側で姿の見えない“英雄”が、画面の向こう側の人々を救おうと声を振り絞っている…
――そういう、感覚を持ちました。
すでに言及されている方も多いのですが、正月2日目の夕刻にも、気持ちを揺さぶられる事故がありました。
羽田空港で航空機が燃えている…という情報を見かけたのです。
「なんて、正月だ…」
映像を見て、唖然としました。空港の滑走路で旅客機が炎上しているのが、映し出されています。
「まさか…乗客、まだ降りてないのか!?」
気が気でなかったのですが、この心配は、ニュース速報で打ち消されました。
――その時点で、全ての乗客が降りていたと。
すでに旅客機の乗務員が、全員を機体から退避させていたそうです。衝突のアクシデントが起きてからの離脱で、機内全員が無事…
訓練では想定していた事態なのかもしれませんが、乗客一人ひとりが生身で存在し、意思を持って動く中でどう対応したのか。
これを実際にやってのけるとは…日本ではあまり聞かない表現ですが、すでに海外の報道では“英雄”的な仕事と賞賛されていると聞きます。
――旅客機のクルーにより、乗客の命は守られましたが…
そのあと、旅客機に衝突したのが、海上保安庁の飛行機であり、そもそも能登半島に救援物資を運ぶところだった…と知りました。
これを聞いたら、また涙が出てきました。おそらくは、緊急時の準備を整えて“少しでも早く”と出動したのでしょう。
そんな方々が、命を落としたと認識すると、いたたまれないものがあります。
――こんな、正月三が日は記憶にない…
自分の狭い人生の中で、年始が大変だった時期の記憶もありますが、ちょっとスケールの違いすぎる、涙の正月。
たしか3日目の夜にも、私はニュースを見て、目に溜まる涙を感じていました。
被災地となった町の、倒壊したビルの下。オレンジの隊服の複数名が確認できます。他地域から到着した救援隊のようです。
「…取り残された人を救おうとしているのか。」
――この場面で、余震が起きたらしく、
救援隊は、一時ビルの下から退避します。その姿を見ていたら、結局、3日続けて涙が出てきました。
倒壊したビルが崩れることも容易に想像できます。もう、完全に命懸けの仕事。
「すごい、すごすぎる…とても真似ができない。」
――正直、私が何をできるわけでもない。
おそらくは歳を重ねて涙もろくもなっています。でも、彼らのはたらきを賞賛したい。少なくとも、頑張っている人たちの足を引っ張るような生き方はするまい…、
できれば巡り巡ってでも良いので、どこかで何かの助けになるように、しっかり生きようと思う。この正月に感じたことでした。
2024年01月01日
「遠路の剣Ⅲ(泥海)」
2024年(令和6年)の新春を迎えました。本年もよろしくお願いします。
ところで、元日から心配な地震のニュースもあり、正月気分は、すっかり抜けてしまいました。
ご挨拶のみでまとめるのも考えましたが、”一年の計”として書いた文章ですので、そのまま掲載します。

年越しで綴った、3回シリーズのまとめで、今年の目標も入っています。
師走に県内を出て、私の住む街の近くまで来た叔父上の旅。実は、私に「佐賀への想いを問う」ような“課題”を与えていました。
――昨年末。師走の旅から、県内へと帰った叔父上の様子をうかがった。
旅の最中に出会うと、叔父上は「最後の旅になるかもしれんとよ」と語った。歳を重ねてから旅に出ると、都度、そんな事を考えるものなのかもしれない。
ところが、いざ電話をしてみると、長旅だったにもかかわらず、意外と元気な声だった。旅の思い出と重ねてか、きれいな景色を思い返すようである。
「おいは、キラキラした海が好きとよ。」

――叔父上…なんだか、子どもみたいな事を言った。
女きょうだいの男の子なので、叔父上には、たまにそういうところがある。
「佐賀にも、有明の海があるじゃないですか。」
「…有明と言えば、泥とよ。あまり、キラキラとはしとらんばい。」
「まぁ、たしかにそうですが。」
有明海といえば、干潟。干潟といえば泥…これは否定しがたい。
「わりと濁っとるもんね~。太良町の方まで行ったら、澄んでるけども。」
――電話の後。かくして、私には“課題”があたえられた。
すっかり、叔父上は旅先で見た光る海に魅了されている。このままでは、佐賀の者としては心許(こころもと)ない。
いや、これは叔父上から私への、修業として与えられた試練なのか。
まばゆい海が見たければ、伊万里や玄海町、唐津方面に行けば良いように思うが、それでは“泥”という課題から逃げている気がする。

私とて、佐賀藩士(?)を名乗る者。新年早々だが、正面から“泥”をかぶっていく気迫で、向き合ってみようと思う。
――少し前、閉塞感のあった“コロナ禍”の時期…
主人公が理不尽な困難に立ち向かう姿もあって、大ヒットしたアニメがあった。その『鬼滅の刃』に着想を得て、泥を味方とした、佐賀の力を練っていきたい。
人は体内に空気を取り込まねば生きてはいけないが、普段、これを意識することは少ない。武芸やスポーツにおいても呼吸は、大事なものだと聞く。
同作品で、凄まじい力を生み出す技を“○○の呼吸”と名付けたのには、すごく説得力を感じる。
今回は「泥の呼吸」と称したまとめ方を使って、項目別に語ってみる。泥に限定して、佐賀県を語る修業を通じて、その魅力を見つめ直したい。

――では、泥の呼吸・壱の型 『覇王への米』から
もし他地域や県外の人に「佐賀って何もないもんね~」と言われた時、あなたならどう返すだろうか。
「そうとよ、なん~もなかばい。」これが大人の受け方。きっと、こう返せる人には心のゆとりがあるのだろう。しかし、私はそこまで悟れてはいない。
「佐賀県には、何もない」というのは、誤解だと私は思う。たとえ「泥の話」だけに限っても、きっとワクワクするほどの魅力を語ることができるはず…
まずは、優れた農業生産がある。なかなか生産量の1位を取れないが、様々な品目で好順位につけており、何より各品目の質が高い。

――NHK Eテレ(教育)で、「佐賀の米」を特集する番組を見かけた。
その中で、佐賀が練り上げてきた米の品質は、“覇王への道”を進んでいる…と喩えられていた。
同番組で佐賀の米を試食したゲストたちは、その味を大絶賛していたわけだが、ここに「泥の力」が作用していることが示されていた。
佐賀の泥の粘土質は、米作りの”理想郷”となる力をもたらすらしい。養分も豊富なため、小麦との二毛作で、強さと柔らかさを兼ね備える土壌になるようだ。
映像で出てきたのは白石町だったが、生産高2位の座を制しつつあるレンコンも、その豊かな泥の中から掘り出される。

――続いて、泥の呼吸・弐の型 『海苔の舞い』
舞台を有明海に移す。佐賀県が安定して1位の品目といえば、海苔の生産。
高級な贈答品となることも多いから、その品質も含めて、折り紙付きといってよい佐賀の特産品。
遠浅の海は濁って見えるところがあるが、計り知れない海の恵みをもたらし、海苔の養殖は、佐賀の風物詩として、全国放送のテレビでもよく映る。

――県南西部の太良町は、カキが有名であるが、
江戸前ずしのネタとして知られる、コハダ。太良町で獲れたものが関東の市場で、取扱量トップだと聞く。
土台となる米、ネタとなる海の幸、寿司には鮮やかに海苔で巻くものも多い。佐賀の特産品をイメージして、寿司を考えるだけで、美味しそうである。
この流れるような動きさえも、県北部の名物、呼子のイカの手を借りる間でもなく、県南部の有明海だけでカタがつく。
「何もない」とか言われるが、寿司に関しては、佐賀県では「探しているもの、全てがある」ようだ。

――最後に、泥の呼吸・参の型 『潟〔ガタ〕の咆哮』
佐賀県の魅力を語るなら、有田陶器市・吉野ヶ里遺跡・バルーンフェスタなどの名所や行事が外せない。
ただ泥…干潟に限ってなら、鹿島の『ガタリンピック』だ。よく見られる風景が、果てしなく続く干潟を這うように進む“潟〔ガタ〕スキー”。通称「ムツゴロウ」。
干潟の上に敷かれた板を、自転車(チャリ)で行く“潟〔ガタ〕チャリ”。
移動方法によらず、干潟を進む時間で勝負を付けるタイムトライアル競技・「25m自由ガタ」という種目もあるらしい。素晴らしいネーミングセンスだと感じる。
――そして、さらに精神を解放するもの。
時折、ニュース映像で見るほか、佐賀を舞台としたアニメ『ゾンビランドサガ』でもしっかりと描写された、“ガターザン”という競技があるようだ。
この言葉、「潟〔ガタ〕」と「ターザン」の複合語なのだろう。ターザンといえば、昔の映画で見た、ジャングルで育った野生児の物語。
成長し「ジャングルの王者」と呼ぶべき存在となったターザン。ロープを使って、木々の間を「ア~ア、アー!」と雄叫びを上げ、滑空する。

県内の若い世代には「フォレストアドベンチャー・吉野ヶ里のように森の中で宙を行く感じです」と言ったら説明になるだろうか。
――その勇姿を、干潟で再現した競技と思われる“ガターザン”。
選手はロープを掴んで、「ア~アァー!」とばかりに干潟に向けて飛ぶ。
「ムツゴロウ」や「ガタチャリ」は、一応は干潟を移動する手段に見えはするが、この競技は高く遠くへ跳んでも泥の中に落ちるのが、自然の理。
「必ず、泥に落ちる」。非常にいさぎよく、魂を解き放つ感じがする。
あたかも、多久やみやき町、大町町などで県内各地で大事に育てられている、二千年ハスのように「泥の中にこそ咲く花もあれ…」と語りたいところだ。

――私は、目が覚めたような心地になった。
「泥を題材とするだけで、佐賀県はここまで語れるのか!」と。
叔父上がキラキラした海にキャッキャッと喜んでいた反作用で、私は泥について、沈み込むようにズブズブと考えることになった。
これでもっと深く、佐賀を読み解くことができる。また叔父上には“修業”の成果を語っておかねば。
――この元旦には、叔父上からの年賀状が届いた。
そこには「法事ば予定しよるけん、こっちまで来んね。」という趣旨の“帰藩”を促す、添え書きがあった。
佐賀を語り続けてはいるものの、私は1年半ほど県内にすら入っていない。最近できた「SAGAアリーナ」も「サガハツ」すらも、実際には見ていない。
「今年こそ佐賀県へと帰って、現地で見聞きしたことで、さらに佐賀を語る」
昨年末の叔父上との再会は、私の新年の課題につながったのである。
ところで、元日から心配な地震のニュースもあり、正月気分は、すっかり抜けてしまいました。
ご挨拶のみでまとめるのも考えましたが、”一年の計”として書いた文章ですので、そのまま掲載します。
年越しで綴った、3回シリーズのまとめで、今年の目標も入っています。
師走に県内を出て、私の住む街の近くまで来た叔父上の旅。実は、私に「佐賀への想いを問う」ような“課題”を与えていました。
――昨年末。師走の旅から、県内へと帰った叔父上の様子をうかがった。
旅の最中に出会うと、叔父上は「最後の旅になるかもしれんとよ」と語った。歳を重ねてから旅に出ると、都度、そんな事を考えるものなのかもしれない。
ところが、いざ電話をしてみると、長旅だったにもかかわらず、意外と元気な声だった。旅の思い出と重ねてか、きれいな景色を思い返すようである。
「おいは、キラキラした海が好きとよ。」
――叔父上…なんだか、子どもみたいな事を言った。
女きょうだいの男の子なので、叔父上には、たまにそういうところがある。
「佐賀にも、有明の海があるじゃないですか。」
「…有明と言えば、泥とよ。あまり、キラキラとはしとらんばい。」
「まぁ、たしかにそうですが。」
有明海といえば、干潟。干潟といえば泥…これは否定しがたい。
「わりと濁っとるもんね~。太良町の方まで行ったら、澄んでるけども。」
――電話の後。かくして、私には“課題”があたえられた。
すっかり、叔父上は旅先で見た光る海に魅了されている。このままでは、佐賀の者としては心許(こころもと)ない。
いや、これは叔父上から私への、修業として与えられた試練なのか。
まばゆい海が見たければ、伊万里や玄海町、唐津方面に行けば良いように思うが、それでは“泥”という課題から逃げている気がする。
私とて、佐賀藩士(?)を名乗る者。新年早々だが、正面から“泥”をかぶっていく気迫で、向き合ってみようと思う。
――少し前、閉塞感のあった“コロナ禍”の時期…
主人公が理不尽な困難に立ち向かう姿もあって、大ヒットしたアニメがあった。その『鬼滅の刃』に着想を得て、泥を味方とした、佐賀の力を練っていきたい。
人は体内に空気を取り込まねば生きてはいけないが、普段、これを意識することは少ない。武芸やスポーツにおいても呼吸は、大事なものだと聞く。
同作品で、凄まじい力を生み出す技を“○○の呼吸”と名付けたのには、すごく説得力を感じる。
今回は「泥の呼吸」と称したまとめ方を使って、項目別に語ってみる。泥に限定して、佐賀県を語る修業を通じて、その魅力を見つめ直したい。
――では、泥の呼吸・壱の型 『覇王への米』から
もし他地域や県外の人に「佐賀って何もないもんね~」と言われた時、あなたならどう返すだろうか。
「そうとよ、なん~もなかばい。」これが大人の受け方。きっと、こう返せる人には心のゆとりがあるのだろう。しかし、私はそこまで悟れてはいない。
「佐賀県には、何もない」というのは、誤解だと私は思う。たとえ「泥の話」だけに限っても、きっとワクワクするほどの魅力を語ることができるはず…
まずは、優れた農業生産がある。なかなか生産量の1位を取れないが、様々な品目で好順位につけており、何より各品目の質が高い。
――NHK Eテレ(教育)で、「佐賀の米」を特集する番組を見かけた。
その中で、佐賀が練り上げてきた米の品質は、“覇王への道”を進んでいる…と喩えられていた。
同番組で佐賀の米を試食したゲストたちは、その味を大絶賛していたわけだが、ここに「泥の力」が作用していることが示されていた。
佐賀の泥の粘土質は、米作りの”理想郷”となる力をもたらすらしい。養分も豊富なため、小麦との二毛作で、強さと柔らかさを兼ね備える土壌になるようだ。
映像で出てきたのは白石町だったが、生産高2位の座を制しつつあるレンコンも、その豊かな泥の中から掘り出される。
――続いて、泥の呼吸・弐の型 『海苔の舞い』
舞台を有明海に移す。佐賀県が安定して1位の品目といえば、海苔の生産。
高級な贈答品となることも多いから、その品質も含めて、折り紙付きといってよい佐賀の特産品。
遠浅の海は濁って見えるところがあるが、計り知れない海の恵みをもたらし、海苔の養殖は、佐賀の風物詩として、全国放送のテレビでもよく映る。
――県南西部の太良町は、カキが有名であるが、
江戸前ずしのネタとして知られる、コハダ。太良町で獲れたものが関東の市場で、取扱量トップだと聞く。
土台となる米、ネタとなる海の幸、寿司には鮮やかに海苔で巻くものも多い。佐賀の特産品をイメージして、寿司を考えるだけで、美味しそうである。
この流れるような動きさえも、県北部の名物、呼子のイカの手を借りる間でもなく、県南部の有明海だけでカタがつく。
「何もない」とか言われるが、寿司に関しては、佐賀県では「探しているもの、全てがある」ようだ。
――最後に、泥の呼吸・参の型 『潟〔ガタ〕の咆哮』
佐賀県の魅力を語るなら、有田陶器市・吉野ヶ里遺跡・バルーンフェスタなどの名所や行事が外せない。
ただ泥…干潟に限ってなら、鹿島の『ガタリンピック』だ。よく見られる風景が、果てしなく続く干潟を這うように進む“潟〔ガタ〕スキー”。通称「ムツゴロウ」。
干潟の上に敷かれた板を、自転車(チャリ)で行く“潟〔ガタ〕チャリ”。
移動方法によらず、干潟を進む時間で勝負を付けるタイムトライアル競技・「25m自由ガタ」という種目もあるらしい。素晴らしいネーミングセンスだと感じる。
――そして、さらに精神を解放するもの。
時折、ニュース映像で見るほか、佐賀を舞台としたアニメ『ゾンビランドサガ』でもしっかりと描写された、“ガターザン”という競技があるようだ。
この言葉、「潟〔ガタ〕」と「ターザン」の複合語なのだろう。ターザンといえば、昔の映画で見た、ジャングルで育った野生児の物語。
成長し「ジャングルの王者」と呼ぶべき存在となったターザン。ロープを使って、木々の間を「ア~ア、アー!」と雄叫びを上げ、滑空する。
県内の若い世代には「フォレストアドベンチャー・吉野ヶ里のように森の中で宙を行く感じです」と言ったら説明になるだろうか。
――その勇姿を、干潟で再現した競技と思われる“ガターザン”。
選手はロープを掴んで、「ア~アァー!」とばかりに干潟に向けて飛ぶ。
「ムツゴロウ」や「ガタチャリ」は、一応は干潟を移動する手段に見えはするが、この競技は高く遠くへ跳んでも泥の中に落ちるのが、自然の理。
「必ず、泥に落ちる」。非常にいさぎよく、魂を解き放つ感じがする。
あたかも、多久やみやき町、大町町などで県内各地で大事に育てられている、二千年ハスのように「泥の中にこそ咲く花もあれ…」と語りたいところだ。
――私は、目が覚めたような心地になった。
「泥を題材とするだけで、佐賀県はここまで語れるのか!」と。
叔父上がキラキラした海にキャッキャッと喜んでいた反作用で、私は泥について、沈み込むようにズブズブと考えることになった。
これでもっと深く、佐賀を読み解くことができる。また叔父上には“修業”の成果を語っておかねば。
――この元旦には、叔父上からの年賀状が届いた。
そこには「法事ば予定しよるけん、こっちまで来んね。」という趣旨の“帰藩”を促す、添え書きがあった。
佐賀を語り続けてはいるものの、私は1年半ほど県内にすら入っていない。最近できた「SAGAアリーナ」も「サガハツ」すらも、実際には見ていない。
「今年こそ佐賀県へと帰って、現地で見聞きしたことで、さらに佐賀を語る」
昨年末の叔父上との再会は、私の新年の課題につながったのである。
タグ :佐賀




