2023年04月25日
第19話「閑叟上洛」⑨(想いが届けば、若返る…)
こんばんは。
文久二年(1862年)の夏から秋にかけての話を続けています。
旧暦のうえ閏(うるう)月などもあって複雑なため、季節感で表現していますが、江藤新平の行動履歴も、あまり明確でないようで、日付は深追いしません。
この年の八月には、朝廷から佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)あてに上洛を促す手紙が届いたそうです。
返事を送ったことで、鍋島直正が京都に向かう段取りは進みますが、佐賀藩は近代化に突き進む一方で、あまり政治工作に熱心ではありませんでした。
その結果、佐賀の志士が京の都で活動する機会はほとんどなく、幕末期には目立ちそこねて、明治の世でようやく実力の一端を見せることになります。

――佐賀城。本丸御殿。
50歳手前の大殿(前藩主)・鍋島直正に、報告を行っているのは、さらに10歳以上も年配の重臣・鍋島夏雲(市佑)。
〔参照(前半):第19話「閑叟上洛」④(誇りある、その仕事)〕
間違いなくご隠居の年代だが、藩庁に集まる、ありとあらゆる情報を記録する有能な“秘書官”でもある。鍋島夏雲は、今日も書面を携えて姿を見せている。
「知りうる限りで、これが最も詳しか、京の都の内情にございます。」
「長州(山口)は、薩摩(鹿児島)とは、また違った思惑で動いておるな。}
尊王攘夷派の公家を動かすべく、長州藩は京都で政治工作を進めていた。
朝廷の権威を背景に、幕府に対して外国を打ち払う“攘夷決行”を促すことで、先行する薩摩藩から優位を取ろうとしているのだ。

――この時期、薩摩藩は“公武合体策”を熱心に進めていた。
長州のようには“攘夷”を唱えない薩摩藩は、幕府の人事に介入し、将軍候補だった、一橋慶喜らを要職に付けて、幕政の主導権を握る戦略だった。
公武合体は朝廷と幕府を近づけるものだから、尊王攘夷を唱える“志士”は、その障壁となりかねない。
薩摩の国父(藩主の父)・島津久光は、京都の寺田屋で“勤王”の動きを見せた藩士たちを、薩摩の者の壮絶な“同士討ち”により粛清したという。
〔参照第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕

「寺田屋の一件も凄絶にございましたが、その後も…」
佐賀の老臣・鍋島夏雲は、いたって真面目に説明を続ける。
薩摩藩士だけでなく、その場に集まっていた、公家に仕える侍、各藩の浪士も、その事件に関わって、命を落とした様子が伝わる。
「…海に消えた者まで、居たようにございます。」
〔参照:第18話「京都見聞」⑨(その志は、海に消えても)〕
話を聞く、鍋島直正は殊更(ことさら)に渋い表情をしていた。
「真に国を憂う、志ある者も居たであろうに。」

西国の雄藩同士で、競い合うところはあったが、母方の従兄というつながりもあって、先代の薩摩藩主・島津斉彬は信頼できる人物だった。
〔参照(後半):第14話「遣米使節」⑪(名君たちの“約束”)〕
幕府中枢では、老中・阿部正弘は黒船来航を受けて国内の調整に腐心し、その後、大老に付いた井伊直弼も、全ての責任を背負うように決断をしていた。
――時代は進んで、皆、居なくなってしまった。
各々の立ち位置の違いはあったにせよ、直正は一抹の寂しさを感じていた。気苦労を重ねた、自身の体も相当傷んでおり、昔日の気力は、もはや無い。
少し感傷的になる直正に対して、夏雲は報告を淡々と進める。
「薩摩と長州が争うのみならず、諸国(各藩)が京に入らんとします。」

夏雲は、各藩が競って“勤王”につぎ込んでいる人員の数・金銭の量、それを受け取っている公家の人物評を説明し出した。
〔参照:第18話「京都見聞」⑮(京の覇権争い)〕
「…待て。夏雲よ。」
ここで直正は、何かに気付いた。
――佐賀藩は、京都の政局とは距離を置いてきた。
それにしては、朝廷や各藩に関わる、報告の内容が詳細に過ぎる。
京で起きた事件の顛末も、各藩の勢力争いの構図も、それに関わる人物の評価も、具体に動いた人数や金額まで記されている。
「どう調べた…もしや。」
「…お気付きになられましたか。」
年齢のこともあるが、多少は話疲れたか、夏雲がひと呼吸を置いた。

「それだけの事を、この夏の間に調べ上げたと申すか。あの男が。」
「ええ、江藤新平と申す者。ただ、一人にて。」
その問いに、夏雲が答える。しばしの沈黙がある。
あえて野放しにしていた、江藤が京で綴った報告書『京都見聞』は、直正まで届いたのだ。
〔参照:第19話「閑叟上洛」①(ある佐賀浪士への苦情)〕
――姿勢悪く、前屈みに座っていた、直正がスッと立ち上がる。
「連れ戻せ。」
「はっ。」
「捕らえるのではない。佐賀に呼び戻せ。」
「ははっ。」
このところ、胸痛にも悩まされていた、直正だったが、久々に声を張った。少し嬉しそうである。
「聞きたい事は、山ほどあるぞ。江藤は、身内の者に迎えに行かせよ。」

直正は、念を押した。
佐賀からの脱藩は重罪であるが、「罪人として扱ってはならない」という、大殿・直正の意思が込められた言葉だ。
藩のために、これだけ情報を集めたのだ。江藤が報告に込めた想いも直正には伝わっていた。
――「なれば!」と、老臣・鍋島夏雲も立ち上がった。
こちらも60歳超えであるが、何やら愉快そうに、こう言った。
「迎えには、江藤の父・助右衛門を遣わしましょう。」
直正は、少し心配そうな顔をした。江藤も30歳手前のはずだ。老齢の父親に、京での探索が務まるのか。
「…大丈夫なのか。」
ここは、夏雲に迷いがない。
「よかことです。老いてなお、成すべき事がある。幸いではなかですか。」
夏雲自身も年配者なので、説得力が違う。直正は、一言だけ告げた。
「…うむ、任せる。」
(続く)
文久二年(1862年)の夏から秋にかけての話を続けています。
旧暦のうえ閏(うるう)月などもあって複雑なため、季節感で表現していますが、江藤新平の行動履歴も、あまり明確でないようで、日付は深追いしません。
この年の八月には、朝廷から佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)あてに上洛を促す手紙が届いたそうです。
返事を送ったことで、鍋島直正が京都に向かう段取りは進みますが、佐賀藩は近代化に突き進む一方で、あまり政治工作に熱心ではありませんでした。
その結果、佐賀の志士が京の都で活動する機会はほとんどなく、幕末期には目立ちそこねて、明治の世でようやく実力の一端を見せることになります。
――佐賀城。本丸御殿。
50歳手前の大殿(前藩主)・鍋島直正に、報告を行っているのは、さらに10歳以上も年配の重臣・鍋島夏雲(市佑)。
〔参照(前半):
間違いなくご隠居の年代だが、藩庁に集まる、ありとあらゆる情報を記録する有能な“秘書官”でもある。鍋島夏雲は、今日も書面を携えて姿を見せている。
「知りうる限りで、これが最も詳しか、京の都の内情にございます。」
「長州(山口)は、薩摩(鹿児島)とは、また違った思惑で動いておるな。}
尊王攘夷派の公家を動かすべく、長州藩は京都で政治工作を進めていた。
朝廷の権威を背景に、幕府に対して外国を打ち払う“攘夷決行”を促すことで、先行する薩摩藩から優位を取ろうとしているのだ。

――この時期、薩摩藩は“公武合体策”を熱心に進めていた。
長州のようには“攘夷”を唱えない薩摩藩は、幕府の人事に介入し、将軍候補だった、一橋慶喜らを要職に付けて、幕政の主導権を握る戦略だった。
公武合体は朝廷と幕府を近づけるものだから、尊王攘夷を唱える“志士”は、その障壁となりかねない。
薩摩の国父(藩主の父)・島津久光は、京都の寺田屋で“勤王”の動きを見せた藩士たちを、薩摩の者の壮絶な“同士討ち”により粛清したという。
〔参照

「寺田屋の一件も凄絶にございましたが、その後も…」
佐賀の老臣・鍋島夏雲は、いたって真面目に説明を続ける。
薩摩藩士だけでなく、その場に集まっていた、公家に仕える侍、各藩の浪士も、その事件に関わって、命を落とした様子が伝わる。
「…海に消えた者まで、居たようにございます。」
〔参照:
話を聞く、鍋島直正は殊更(ことさら)に渋い表情をしていた。
「真に国を憂う、志ある者も居たであろうに。」
西国の雄藩同士で、競い合うところはあったが、母方の従兄というつながりもあって、先代の薩摩藩主・島津斉彬は信頼できる人物だった。
〔参照(後半):
幕府中枢では、老中・阿部正弘は黒船来航を受けて国内の調整に腐心し、その後、大老に付いた井伊直弼も、全ての責任を背負うように決断をしていた。
――時代は進んで、皆、居なくなってしまった。
各々の立ち位置の違いはあったにせよ、直正は一抹の寂しさを感じていた。気苦労を重ねた、自身の体も相当傷んでおり、昔日の気力は、もはや無い。
少し感傷的になる直正に対して、夏雲は報告を淡々と進める。
「薩摩と長州が争うのみならず、諸国(各藩)が京に入らんとします。」
夏雲は、各藩が競って“勤王”につぎ込んでいる人員の数・金銭の量、それを受け取っている公家の人物評を説明し出した。
〔参照:
「…待て。夏雲よ。」
ここで直正は、何かに気付いた。
――佐賀藩は、京都の政局とは距離を置いてきた。
それにしては、朝廷や各藩に関わる、報告の内容が詳細に過ぎる。
京で起きた事件の顛末も、各藩の勢力争いの構図も、それに関わる人物の評価も、具体に動いた人数や金額まで記されている。
「どう調べた…もしや。」
「…お気付きになられましたか。」
年齢のこともあるが、多少は話疲れたか、夏雲がひと呼吸を置いた。
「それだけの事を、この夏の間に調べ上げたと申すか。あの男が。」
「ええ、江藤新平と申す者。ただ、一人にて。」
その問いに、夏雲が答える。しばしの沈黙がある。
あえて野放しにしていた、江藤が京で綴った報告書『京都見聞』は、直正まで届いたのだ。
〔参照:
――姿勢悪く、前屈みに座っていた、直正がスッと立ち上がる。
「連れ戻せ。」
「はっ。」
「捕らえるのではない。佐賀に呼び戻せ。」
「ははっ。」
このところ、胸痛にも悩まされていた、直正だったが、久々に声を張った。少し嬉しそうである。
「聞きたい事は、山ほどあるぞ。江藤は、身内の者に迎えに行かせよ。」
直正は、念を押した。
佐賀からの脱藩は重罪であるが、「罪人として扱ってはならない」という、大殿・直正の意思が込められた言葉だ。
藩のために、これだけ情報を集めたのだ。江藤が報告に込めた想いも直正には伝わっていた。
――「なれば!」と、老臣・鍋島夏雲も立ち上がった。
こちらも60歳超えであるが、何やら愉快そうに、こう言った。
「迎えには、江藤の父・助右衛門を遣わしましょう。」
直正は、少し心配そうな顔をした。江藤も30歳手前のはずだ。老齢の父親に、京での探索が務まるのか。
「…大丈夫なのか。」
ここは、夏雲に迷いがない。
「よかことです。老いてなお、成すべき事がある。幸いではなかですか。」
夏雲自身も年配者なので、説得力が違う。直正は、一言だけ告げた。
「…うむ、任せる。」
(続く)
2023年04月17日
第19話「閑叟上洛」⑧(“逃げるが勝ち”とも申すのに)
こんばんは。
文久二年(1862年)初秋。佐賀の志士たちは、偉大な師匠・枝吉神陽を失いますが、それでも季節は巡り、時は流れていきます。
佐賀からの脱藩者・江藤新平がいる京の都にも秋風が吹いていました。幕府も、京都守護職を設置する等、政情の安定を図ろうとしていた年です。
そんな混沌とした状況の中、江藤は大殿・鍋島直正(閑叟)が京の都に来る前に、正確な情勢を伝える機会があると信じて、佐賀への帰藩を決断します。
――京の都。鴨川にほど近い、長州藩の屋敷。
「江藤くん、佐賀に戻るのは考え直さんか。」
説得を始めているのは、長州藩士・桂小五郎だ。

「諸侯が京に入るも、混乱は深まる一方にて、佐賀の“中将様”(鍋島直正)に、お出ましを頂きたいと存ずる。」
京に残らないかという誘いを断るためか、江藤は固く答えた。「朝廷への忠節」が前提の話なので、鍋島直正のことも“公家風”の呼び方になっている。
江藤は長州(山口)・土佐(高知)・筑前(福岡)・肥後(熊本)・仙台(宮城)などの諸藩が、一斉に京に入って収拾が付かなくなった状況を憂慮していた。
〔参照(終盤):第18話「京都見聞」⑮(京の覇権争い)〕
――その、まとめ役となりうるのは、佐賀藩しかない。
それが、江藤の確信するところだった。
「今が動くべき時節にて、この機を逸するべきではなか。」
もともと一直線な江藤だが、今日はさらにまっすぐな印象である。桂が半ば呆れながら、言葉を続ける。

「それは、わかっとるんじゃ。佐賀では国を抜けることは、重罪と聞くぞ。」
「佐賀を出た時から、それは覚悟のうえ。」
「むざむざと、命を捨てる事は無いと言うちょるんじゃ。」
「京の都で見聞したところを、いま伝えねば、佐賀は動かぬと存ずる。」
――桂の説得には、理由があった。
長州藩と近い有力公家・姉小路公知が江藤の事を気に入っており、このまま供回りに迎えたいという希望もあるようだ。
〔参照:第19話「閑叟上洛」②(入り組んだ、京の風向き)〕
これは江藤を紹介した立場の、長州藩としても悪い話ではない。江藤にとっても、勢いのある公家・姉小路に仕えれば、経済的な心配も無いはずだ。
〔参照:第18話「京都見聞」⑭(若き公家の星)〕

瞬時に、理の通った手順を組み立てる江藤の才覚は、桂から見ても、他に類を見ないものだった。
そして、洋学にも通じた佐賀藩が動けば、新しい世の姿に影響を与えるのは必定だ。ぜひとも江藤は仲間内に残して、佐賀と連携をとる切り札としたい。
――しかし、江藤は、京への残留を承知しない。
「桂さんには感謝をするが、佐賀には戻らんばならん。」
「まったく佐賀の者は、頑固じゃのう!」
少々、投げやりな一言を発したのちに、桂は念を押した。
「ええか、命は粗末にしちゃならん。逃げ回ってでも、夜明けを見るんじゃ。」
桂も考えてくれている。この言いようには、江藤もしっかりと目を見合わせた。
「では志を果たせずに、命を落とす見込みなれば、立ち戻るとしよう。」
――ここには江藤も応じたが、桂は合点がいかないようだ。
「何ゆえ、わざわざ危ない橋を渡るんじゃ…」
この江藤の話しぶりだと、「命がけで佐賀に戻る」のは、取り下げていない。

真面目で融通の利かない、それだけに地道にまっすぐに事を成す。機を見て、方向転換するのも早い長州とは、また異質な力が佐賀にはある。
ここは、江藤にしては珍しく沈黙のままだった。さらに桂が言葉を続ける。
「もしや…肥前侯が、それだけ尽くす値打ちのある、御仁じゃいうことか。」
――桂が、答えを見いだしたとみるや、
江藤はいつものように、はっきりと言葉を発した。
「その、ご高恩に報いるため。」
「それが話に聞く、佐賀の“葉隠”の忠義か。」
桂にも江藤の言わんとする事はわかる。実力者として知られる鍋島直正が京の政局に介入すれば、功を焦る各藩をまとめることができるかもしれない。

だが、そのために江藤が命を賭す動機が、もはや佐賀の“鍋島武士”ならではの「主君への忠義」ぐらいしか思い当たらないのだ。
「…お主も進んどるんか、古臭いんか、ようわからん男じゃのう。」
――脱藩者であるはずの、江藤には、
郷里・佐賀を捨てる気持ちなど、微塵(みじん)も感じられない様子だ。
そこには、佐賀藩の大殿(前藩主)・鍋島直正が、混迷を深める京の都に入って存在感を見せることへの期待があった。
京で自身の調べた事が、大殿の役に立つことで、きっと、この国は進むべき道を見いだす事ができる。
江藤にとっては、その道筋をつけることが朝廷に尽くす“勤王”のはたらきであり、それが己の役回りという自負心は、とても大きなものだった。
(続く)
文久二年(1862年)初秋。佐賀の志士たちは、偉大な師匠・枝吉神陽を失いますが、それでも季節は巡り、時は流れていきます。
佐賀からの脱藩者・江藤新平がいる京の都にも秋風が吹いていました。幕府も、京都守護職を設置する等、政情の安定を図ろうとしていた年です。
そんな混沌とした状況の中、江藤は大殿・鍋島直正(閑叟)が京の都に来る前に、正確な情勢を伝える機会があると信じて、佐賀への帰藩を決断します。
――京の都。鴨川にほど近い、長州藩の屋敷。
「江藤くん、佐賀に戻るのは考え直さんか。」
説得を始めているのは、長州藩士・桂小五郎だ。
「諸侯が京に入るも、混乱は深まる一方にて、佐賀の“中将様”(鍋島直正)に、お出ましを頂きたいと存ずる。」
京に残らないかという誘いを断るためか、江藤は固く答えた。「朝廷への忠節」が前提の話なので、鍋島直正のことも“公家風”の呼び方になっている。
江藤は長州(山口)・土佐(高知)・筑前(福岡)・肥後(熊本)・仙台(宮城)などの諸藩が、一斉に京に入って収拾が付かなくなった状況を憂慮していた。
〔参照(終盤):
――その、まとめ役となりうるのは、佐賀藩しかない。
それが、江藤の確信するところだった。
「今が動くべき時節にて、この機を逸するべきではなか。」
もともと一直線な江藤だが、今日はさらにまっすぐな印象である。桂が半ば呆れながら、言葉を続ける。
「それは、わかっとるんじゃ。佐賀では国を抜けることは、重罪と聞くぞ。」
「佐賀を出た時から、それは覚悟のうえ。」
「むざむざと、命を捨てる事は無いと言うちょるんじゃ。」
「京の都で見聞したところを、いま伝えねば、佐賀は動かぬと存ずる。」
――桂の説得には、理由があった。
長州藩と近い有力公家・姉小路公知が江藤の事を気に入っており、このまま供回りに迎えたいという希望もあるようだ。
〔参照:
これは江藤を紹介した立場の、長州藩としても悪い話ではない。江藤にとっても、勢いのある公家・姉小路に仕えれば、経済的な心配も無いはずだ。
〔参照:
瞬時に、理の通った手順を組み立てる江藤の才覚は、桂から見ても、他に類を見ないものだった。
そして、洋学にも通じた佐賀藩が動けば、新しい世の姿に影響を与えるのは必定だ。ぜひとも江藤は仲間内に残して、佐賀と連携をとる切り札としたい。
――しかし、江藤は、京への残留を承知しない。
「桂さんには感謝をするが、佐賀には戻らんばならん。」
「まったく佐賀の者は、頑固じゃのう!」
少々、投げやりな一言を発したのちに、桂は念を押した。
「ええか、命は粗末にしちゃならん。逃げ回ってでも、夜明けを見るんじゃ。」
桂も考えてくれている。この言いようには、江藤もしっかりと目を見合わせた。
「では志を果たせずに、命を落とす見込みなれば、立ち戻るとしよう。」
――ここには江藤も応じたが、桂は合点がいかないようだ。
「何ゆえ、わざわざ危ない橋を渡るんじゃ…」
この江藤の話しぶりだと、「命がけで佐賀に戻る」のは、取り下げていない。
真面目で融通の利かない、それだけに地道にまっすぐに事を成す。機を見て、方向転換するのも早い長州とは、また異質な力が佐賀にはある。
ここは、江藤にしては珍しく沈黙のままだった。さらに桂が言葉を続ける。
「もしや…肥前侯が、それだけ尽くす値打ちのある、御仁じゃいうことか。」
――桂が、答えを見いだしたとみるや、
江藤はいつものように、はっきりと言葉を発した。
「その、ご高恩に報いるため。」
「それが話に聞く、佐賀の“葉隠”の忠義か。」
桂にも江藤の言わんとする事はわかる。実力者として知られる鍋島直正が京の政局に介入すれば、功を焦る各藩をまとめることができるかもしれない。

だが、そのために江藤が命を賭す動機が、もはや佐賀の“鍋島武士”ならではの「主君への忠義」ぐらいしか思い当たらないのだ。
「…お主も進んどるんか、古臭いんか、ようわからん男じゃのう。」
――脱藩者であるはずの、江藤には、
郷里・佐賀を捨てる気持ちなど、微塵(みじん)も感じられない様子だ。
そこには、佐賀藩の大殿(前藩主)・鍋島直正が、混迷を深める京の都に入って存在感を見せることへの期待があった。
京で自身の調べた事が、大殿の役に立つことで、きっと、この国は進むべき道を見いだす事ができる。
江藤にとっては、その道筋をつけることが朝廷に尽くす“勤王”のはたらきであり、それが己の役回りという自負心は、とても大きなものだった。
(続く)
2023年04月10日
第19話「閑叟上洛」⑦(愛する者へ、最後の講義)
こんばんは。本編を続けます。文久二年(1862年)の八月。
弟子の1人・江藤新平が脱藩している最中に、佐賀の志士の師匠・枝吉神陽は世を去ったといいます。
やがて、枝吉神陽の門下生たちは、明治の新時代の礎を築き、近代国家の屋台骨を支える人材となります。
実弟の副島種臣や、京都で情勢を見聞する江藤新平、その資金を調達した大木喬任、この時期から長崎にもよく出入りし始めた大隈重信…も弟子です。

神陽先生の学問は思想を唱えるだけでなく、律令(法律)を深く学ばせたので、実務に応用が利いたようです。
また、神陽のもとには、海軍の中牟田倉之助や、電信の石丸安世など“理系人材”と言うべき、科学技術の運用などに長じた門下生も集っていました。
――文久二年の夏。
異国から来たという、疫病・”虎狼痢”(コレラ)の影響は、佐賀城下にも及ぶ。普段は若手の藩士を、学問で鍛えた枝吉神陽だが、この時は、自宅に居た。
「おしづよ、加減はいかがか。」
「旦那さま…面目ございません。」
病の床に伏せっているのは、枝吉神陽の妻・しづである。神陽が、妻の身辺の世話をしている様子だ。
――神陽は、快活に笑って見せた。
「いつもわしは、おしづに弟子どもの面倒を見てもらっているのだ。」
「それは、枝吉神陽の妻として、当然のこと。」

しづは、起き上がれはしないものの、キリッと言葉を返した。佐賀の志士たちの師匠として崇敬される、枝吉神陽である。妻にも、相応の誇りがあるようだ。
「たまには、わしの方も、そなたの世話をいたさねば罰が当たろう。」
「…では、甘えておきますね。」
神陽は献身的に看病にあたるが、それでも妻・しづの病状は悪化していた。
――もはや、病名の察しは付いている。
嘔吐と下痢が続き、体から水分が失われ衰弱する。“虎狼痢(コロリ)”と呼ばれる流行の疫病だ。
「もう、わたくしは駄目のようでございます。」
この病は伝染するらしい。手遅れかもしれないが、看病する神陽を遠ざけようとする妻・しづ。
「ほう駄目ならば、なおの事。最期まで、わしに看病をさせよ。」
「…“先生”がいなくなっては、皆が困ります。」
しづも、次第に弱っているが、はっきりと言葉を発する。
「ならば、言おう。夫にも代わりは、おらぬはずだ。」
他藩から来た者も、ひとたび会えば敬服してしまうような威厳があったという、枝吉神陽。いまは、妻のためだけに自らの意思を語る。

――神陽の言葉を、妻・しづはじっと聞いていた。
「それに“先生”なら、代わりは育っておるやもしれぬぞ。」
いつもの調子で、枝吉神陽は言葉を続けた。
「年長者なら、団右衛門(島義勇)もおる。」
弟子たちに向けるかわりに、妻に対して、最後の講義をするようでもあった。
「才がある者なら、江藤(新平)がおる。思慮深さなら大木(喬任)だろう。」
覇気に満ちあふれた弁舌。妻から見れば、いつもと変わらない夫・枝吉神陽の姿がそこにあった。
――そして神陽は「わしの志を受け継ぐに足る者は…」と付け加える。
「そうじゃな、何より我が弟・次郎(副島種臣)がおったわ。」
これでもう、大丈夫だと神陽は豪快に笑う。しづもそれに応じて微笑んだ。
やがて枝吉神陽の妻・しづは、夫に看取られて世を去った。
「やはり、おしづは良く出来た妻だ。最後までわしの面目を立てたようじゃ。」
――妻を看取ったのちに、神陽は盛大に嘔吐をする。
ひとたび事物を知れば、記憶から失うことは無いという枝吉神陽である。始めから、わかっていた。コレラは伝染病である。

その学識だけでなく、富士山を下駄で登ったなど、超人的な体力でも知られる神陽だが、どうやらこの病には勝てぬようだ。
「ふふ、あまりに早く後を追いかけると、おしづには、笑われるかのう…」
多くの佐賀の志士たちを鍛え育てた、枝吉神陽。妻を見送る手筈(てはず)も残された時間で整え、その2日後には、この世から旅立っていくこととなる。
(続く)
弟子の1人・江藤新平が脱藩している最中に、佐賀の志士の師匠・枝吉神陽は世を去ったといいます。
やがて、枝吉神陽の門下生たちは、明治の新時代の礎を築き、近代国家の屋台骨を支える人材となります。
実弟の副島種臣や、京都で情勢を見聞する江藤新平、その資金を調達した大木喬任、この時期から長崎にもよく出入りし始めた大隈重信…も弟子です。
神陽先生の学問は思想を唱えるだけでなく、律令(法律)を深く学ばせたので、実務に応用が利いたようです。
また、神陽のもとには、海軍の中牟田倉之助や、電信の石丸安世など“理系人材”と言うべき、科学技術の運用などに長じた門下生も集っていました。
――文久二年の夏。
異国から来たという、疫病・”虎狼痢”(コレラ)の影響は、佐賀城下にも及ぶ。普段は若手の藩士を、学問で鍛えた枝吉神陽だが、この時は、自宅に居た。
「おしづよ、加減はいかがか。」
「旦那さま…面目ございません。」
病の床に伏せっているのは、枝吉神陽の妻・しづである。神陽が、妻の身辺の世話をしている様子だ。
――神陽は、快活に笑って見せた。
「いつもわしは、おしづに弟子どもの面倒を見てもらっているのだ。」
「それは、枝吉神陽の妻として、当然のこと。」
しづは、起き上がれはしないものの、キリッと言葉を返した。佐賀の志士たちの師匠として崇敬される、枝吉神陽である。妻にも、相応の誇りがあるようだ。
「たまには、わしの方も、そなたの世話をいたさねば罰が当たろう。」
「…では、甘えておきますね。」
神陽は献身的に看病にあたるが、それでも妻・しづの病状は悪化していた。
――もはや、病名の察しは付いている。
嘔吐と下痢が続き、体から水分が失われ衰弱する。“虎狼痢(コロリ)”と呼ばれる流行の疫病だ。
「もう、わたくしは駄目のようでございます。」
この病は伝染するらしい。手遅れかもしれないが、看病する神陽を遠ざけようとする妻・しづ。
「ほう駄目ならば、なおの事。最期まで、わしに看病をさせよ。」
「…“先生”がいなくなっては、皆が困ります。」
しづも、次第に弱っているが、はっきりと言葉を発する。
「ならば、言おう。夫にも代わりは、おらぬはずだ。」
他藩から来た者も、ひとたび会えば敬服してしまうような威厳があったという、枝吉神陽。いまは、妻のためだけに自らの意思を語る。
――神陽の言葉を、妻・しづはじっと聞いていた。
「それに“先生”なら、代わりは育っておるやもしれぬぞ。」
いつもの調子で、枝吉神陽は言葉を続けた。
「年長者なら、団右衛門(島義勇)もおる。」
弟子たちに向けるかわりに、妻に対して、最後の講義をするようでもあった。
「才がある者なら、江藤(新平)がおる。思慮深さなら大木(喬任)だろう。」
覇気に満ちあふれた弁舌。妻から見れば、いつもと変わらない夫・枝吉神陽の姿がそこにあった。
――そして神陽は「わしの志を受け継ぐに足る者は…」と付け加える。
「そうじゃな、何より我が弟・次郎(副島種臣)がおったわ。」
これでもう、大丈夫だと神陽は豪快に笑う。しづもそれに応じて微笑んだ。
やがて枝吉神陽の妻・しづは、夫に看取られて世を去った。
「やはり、おしづは良く出来た妻だ。最後までわしの面目を立てたようじゃ。」
――妻を看取ったのちに、神陽は盛大に嘔吐をする。
ひとたび事物を知れば、記憶から失うことは無いという枝吉神陽である。始めから、わかっていた。コレラは伝染病である。
その学識だけでなく、富士山を下駄で登ったなど、超人的な体力でも知られる神陽だが、どうやらこの病には勝てぬようだ。
「ふふ、あまりに早く後を追いかけると、おしづには、笑われるかのう…」
多くの佐賀の志士たちを鍛え育てた、枝吉神陽。妻を見送る手筈(てはず)も残された時間で整え、その2日後には、この世から旅立っていくこととなる。
(続く)
2023年04月05日
第19話「閑叟上洛」⑥(兄の語る言葉は)
こんばんは。
第19話の序盤には、初秋の京都で江藤新平の話を進めましたが、ここ数回は少し時を遡り、夏が過ぎゆく頃の佐賀城下を舞台として展開しています。
文久二年(1862年)八月。佐賀の志士にとって大きい出来事がありました。
楠木正成・正行父子を崇敬し、尊王を志す者が集った“義祭同盟”。主宰者の枝吉神陽は、若き志士たちを導くリーダーであり、偉大な師匠でした。

この数年後、日本の新時代には、佐賀の志士たちは近代国家の基礎づくりに活躍しますが、中心にいたはずの枝吉神陽の姿は、そこに無かったのです。
――佐賀城下も、夏の終わりを迎えていた。
「副島先生は、居られんですか。」
ある男が秘密裡に、副島種臣のもとを訪ねていた。居宅からは返事がない。
前回も登場した、京から戻った“脱藩者”・祇園太郎である。所用があるとして、藩の重臣・鍋島夏雲の役宅から、そそくさと退出してきた。
出身は小城(支藩)だが、一度は勝手に佐賀を抜けた者。脱藩者と知れれば危うい立場のはずだが、水路の走る小径を抜けて、平然と城下を歩む。

普通ならば、もちろん佐賀城下に入っては来られない身の上だ。
ところが、この“祇園太郎”と名乗る男は、何か特別扱いの理由でもあるのか、「帰ってきたとよ~」とばかりに、時折、佐賀の街に現れる。
――もう一度、大声を出す“祇園太郎”。
「副島先生は、居られんね~」
どうしても話をしたい相手がいたとしても、脱藩者のわりに声が大きすぎる。
「そがんに…声を張らずとも、ここに居る。」
なぜか副島種臣は、薄暗い物影にたたずんでいた。
「…驚かさんでください、副島先生。そこで何をしよるですか。」
いざ話しかけられると驚く、祇園太郎。

まるで“密偵”のように情報は集めるが、“忍び”のような特殊な訓練は受けていないようで、庭先にいた副島の気配には、全く気付いていなかった。
「副島先生、このたびは…」
すると祇園太郎はお悔やみの言葉を述べ始めた。副島は黙って聞いており、その反応も生気に欠ける印象だ。
――副島種臣、もともとの名は、枝吉次郎。
幕末期、著名な国学者として各地で名を知られた、枝吉神陽は実兄である。
「お力落としの無きよう…」
祇園太郎は、そう言葉を続けるが、副島の表情があまりに暗いので、次第に心配になってきた。
「副島先生、失礼を承知で言いますばい。元気ば出さんね!」
いきなり、話しぶりが切り替わった。元は小城の大庄屋としても、才覚を見せた祇園太郎だ。なかなか面倒見の良いところがある。

「偉大な神陽先生の志ば、継ぐっとは副島先生しかおらんです。」
今度は、激励の気持ちを投げかける。常日頃、尊王攘夷派の志士と交流しているので、勢いが強めである。
そして、祇園太郎も上方(京周辺)に居たときは、無理に当地の言葉を真似ていたが、佐賀ことばに戻ると訛(なま)りが非常に強い。
――文久二年八月。枝吉神陽は、流行(はやり)病により世を去った。
言葉にすればこれだけだが、佐賀の志士たち、ましてや実弟の副島にとって、その衝撃は計り知れない。
「継げるものか。私が正しいのは、ただ兄上の言葉の写しを語る時だけだ。」
副島は、憔悴(しょうすい)していた。
「私は兄上とは違う。もはや、“先生”と呼ばれるほどの者でもない。」

近年、志を持って、事を起こしても失敗ばかりが続く。
〔参照:第15話「江戸動乱」⑩(いざゆけ!次郎)〕
それどころか、救いたかった仲間も助けられない。
〔参照(終盤):第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)〕
副島が感じていたのは、己の非力さ、無力さだった。
――「なんば、言いよっとね!」と、祇園太郎は言い放った。
「副島先生は、皆に慕われとるばい。おいは“先生”と呼び続けるけんね。」
安政五年(1858年)、当時、小城の大庄屋だった古賀利渉という人物は、“祇園太郎”と名乗って脱藩した。
同年に副島種臣は学究のために京に居り、公家たちと関わったが、この時も、佐賀藩兵の京への派遣を打診して、謹慎処分を受ける始末となっている。
「…もう、私には、期待をするな。」
常に進むべき道を示してくれる実兄・枝吉神陽という“羅針盤”を失い、途方に暮れる副島種臣。闇夜を歩むような日々が続く。

「おいは、これから長崎に行くけん。副島先生も近いうちにどうね?」
ここで祇園太郎の勧めた長崎行き、実は“新しい世”への入口となる場所だったが、そこに副島がたどり着くまでには、今しばらく時がかかるようである。
(続く)
第19話の序盤には、初秋の京都で江藤新平の話を進めましたが、ここ数回は少し時を遡り、夏が過ぎゆく頃の佐賀城下を舞台として展開しています。
文久二年(1862年)八月。佐賀の志士にとって大きい出来事がありました。
楠木正成・正行父子を崇敬し、尊王を志す者が集った“義祭同盟”。主宰者の枝吉神陽は、若き志士たちを導くリーダーであり、偉大な師匠でした。
この数年後、日本の新時代には、佐賀の志士たちは近代国家の基礎づくりに活躍しますが、中心にいたはずの枝吉神陽の姿は、そこに無かったのです。
――佐賀城下も、夏の終わりを迎えていた。
「副島先生は、居られんですか。」
ある男が秘密裡に、副島種臣のもとを訪ねていた。居宅からは返事がない。
前回も登場した、京から戻った“脱藩者”・祇園太郎である。所用があるとして、藩の重臣・鍋島夏雲の役宅から、そそくさと退出してきた。
出身は小城(支藩)だが、一度は勝手に佐賀を抜けた者。脱藩者と知れれば危うい立場のはずだが、水路の走る小径を抜けて、平然と城下を歩む。
普通ならば、もちろん佐賀城下に入っては来られない身の上だ。
ところが、この“祇園太郎”と名乗る男は、何か特別扱いの理由でもあるのか、「帰ってきたとよ~」とばかりに、時折、佐賀の街に現れる。
――もう一度、大声を出す“祇園太郎”。
「副島先生は、居られんね~」
どうしても話をしたい相手がいたとしても、脱藩者のわりに声が大きすぎる。
「そがんに…声を張らずとも、ここに居る。」
なぜか副島種臣は、薄暗い物影にたたずんでいた。
「…驚かさんでください、副島先生。そこで何をしよるですか。」
いざ話しかけられると驚く、祇園太郎。
まるで“密偵”のように情報は集めるが、“忍び”のような特殊な訓練は受けていないようで、庭先にいた副島の気配には、全く気付いていなかった。
「副島先生、このたびは…」
すると祇園太郎はお悔やみの言葉を述べ始めた。副島は黙って聞いており、その反応も生気に欠ける印象だ。
――副島種臣、もともとの名は、枝吉次郎。
幕末期、著名な国学者として各地で名を知られた、枝吉神陽は実兄である。
「お力落としの無きよう…」
祇園太郎は、そう言葉を続けるが、副島の表情があまりに暗いので、次第に心配になってきた。
「副島先生、失礼を承知で言いますばい。元気ば出さんね!」
いきなり、話しぶりが切り替わった。元は小城の大庄屋としても、才覚を見せた祇園太郎だ。なかなか面倒見の良いところがある。

「偉大な神陽先生の志ば、継ぐっとは副島先生しかおらんです。」
今度は、激励の気持ちを投げかける。常日頃、尊王攘夷派の志士と交流しているので、勢いが強めである。
そして、祇園太郎も上方(京周辺)に居たときは、無理に当地の言葉を真似ていたが、佐賀ことばに戻ると訛(なま)りが非常に強い。
――文久二年八月。枝吉神陽は、流行(はやり)病により世を去った。
言葉にすればこれだけだが、佐賀の志士たち、ましてや実弟の副島にとって、その衝撃は計り知れない。
「継げるものか。私が正しいのは、ただ兄上の言葉の写しを語る時だけだ。」
副島は、憔悴(しょうすい)していた。
「私は兄上とは違う。もはや、“先生”と呼ばれるほどの者でもない。」

近年、志を持って、事を起こしても失敗ばかりが続く。
〔参照:
それどころか、救いたかった仲間も助けられない。
〔参照(終盤):
副島が感じていたのは、己の非力さ、無力さだった。
――「なんば、言いよっとね!」と、祇園太郎は言い放った。
「副島先生は、皆に慕われとるばい。おいは“先生”と呼び続けるけんね。」
安政五年(1858年)、当時、小城の大庄屋だった古賀利渉という人物は、“祇園太郎”と名乗って脱藩した。
同年に副島種臣は学究のために京に居り、公家たちと関わったが、この時も、佐賀藩兵の京への派遣を打診して、謹慎処分を受ける始末となっている。
「…もう、私には、期待をするな。」
常に進むべき道を示してくれる実兄・枝吉神陽という“羅針盤”を失い、途方に暮れる副島種臣。闇夜を歩むような日々が続く。
「おいは、これから長崎に行くけん。副島先生も近いうちにどうね?」
ここで祇園太郎の勧めた長崎行き、実は“新しい世”への入口となる場所だったが、そこに副島がたどり着くまでには、今しばらく時がかかるようである。
(続く)
2023年04月01日
第19話「閑叟上洛」⑤(ある忍者の“人事異動”)
こんばんは。
文久二年(1862年)晩夏の佐賀城下。藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲に呼び出されたのは、“嬉野の忍者”・古賀。いつものように猫を連れています。
この頃、京の都を中心に存在感を強める尊王攘夷の志士。朝廷に働きかけ、すぐに異国を打ち払うよう、幕府に圧力をかけていました。
西洋列強の技術力に追いつこうと奮闘する佐賀藩にとって、この志士たちの考え方は短慮と見えるのですが、その影響は無視できなくなってきています。

――“祇園太郎”と名乗る、旅姿の男が現れた。
いきなり上方(京・大坂)の言葉で話し始めたことを詫びる、祇園太郎。
佐賀藩の重臣でも年配の鍋島夏雲(市佑)だが、いたわりの言葉を口にした。
「気にせんでよか。ここまでの道中は、大過なかったか。」
この辺りが年の功だけでなく、夏雲に情報が集まる理由なのかもしれない。
〔参照(後半):「主に上峰町民の方を対象にしたつぶやき」〕
「おいは、小城を抜けた者やけん、相変わらず国境はえすか(怖い)です。」
聞けば、この“祇園太郎”は、佐賀の小城支藩からの脱藩者だという。
〔参照:第18話「京都見聞」⑬(ある佐賀の峠にて)〕

――傍らに控え、二者の会話を聞く“嬉野の忍者”。
この祇園太郎だが、どうやら“忍び”では無さそうである。脱藩者の身の上で、よく佐賀に帰って来られたものだ。
夏雲が、言葉を続ける。
「時に“危ない橋”もあったであろうな。昨今の京の様子は、どうね。」
祇園太郎は尊王攘夷派とよく関わっている。鍋島夏雲も京の都で力を持ってきた各地からの志士たちの動きが気になる様子だ。
「江藤さんがあれこれ調べ回っとるけん、そちらが詳しかと思います。」
傍で話を聞く、嬉野の忍者・古賀。鍋島夏雲と“祇園太郎”の話に出てきた、江藤新平という青年を想い出した。
〔参照:第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)〕
「才のある男だと思ったが、どうやら佐賀を抜け、京でも頑張っておるらしい」と考えると、少し感慨もある。

――重臣・鍋島夏雲と、脱藩者・祇園太郎との問答は続く。
「まずは、概ねの話でよい。」
「京で勤王を志す者たちの間では…」
「ほうほう。」
「佐賀は、腹の底で何ば考えおるかわからぬ、と。」
「…。」
夏雲は黙って聞いていた。
「朝廷にも徳川にも良い顔をして、世間を欺(あざむ)きおる、と。」
「うむうむ。」
佐賀藩は朝廷も重んじるが、幕府にも協力的なので、勤王を唱える者には、そこが気に入らないのだろう。
「佐賀はどちらの味方かわからんゆえ、全く信用ならん、と言いよります。」
――温厚な中にも、ふと鋭さが見える鍋島夏雲。
無言で祇園太郎の報告を聞いており、すました表情をしているが、佐賀藩が「世間を欺いている」とまで言われると釈然としない。
「わしら佐賀は、日和見(ひよりみ)…と言われておるか。」
たしかに長崎警備の役回りを持つ佐賀藩は、どこより欧米各国からの見え方を気にするところがある。
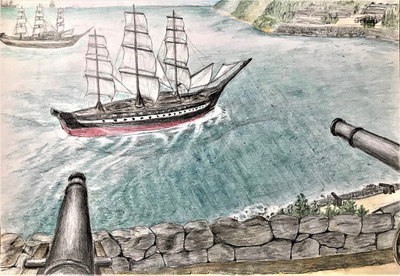
いまや欧米の列強国が通商などで入り込むなか、国内で内紛が起きれば危ういというのが、佐賀藩の立場であり、それが行動の慎重さにつながっている。
出来うる限り、朝廷と幕府の関係悪化は避けたい思惑もあるのだが、これが尊王攘夷派には「どっち付かず」と取られるようだ。
――ひと通りの報告を終えると、祇園太郎は退出した。
この“小城の密偵”のような男は、佐賀城下でも所用があるらしく、そそくさと去っていった。忙しいことに長崎に行った後に、京都に戻る予定もあるという。
「先ほどまでの話で、察しはついておるだろうか。」
ここで鍋島夏雲は、聞き役に徹していた“嬉野の忍者”に用件を伝え始めた。
「長崎も港を開いたゆえ、異国船は表から調べることもできよう。」
――夏雲の語りたいことはわかる。これも時代の流れだ。
この年に佐賀藩は、欧州や清国の上海にも調査団の人員を送った。
もはや通訳や商人からも情報は得られる。隠れて異国船に近づく危険な調査をあえて選択する必要も無さそうだ。
「これからは、長崎に来ておる浪士たちの動きを探ってほしい。」
夏雲の言うことには、密かに調べたいのは、長州(山口)や土佐(高知)など、各地の雄藩を動かしつつある、尊王攘夷派の実情だという。

「おい(私)も歳ば取りましたけん、あん男でよかじゃなかですか。」
「祇園太郎か。あれは良い調べをするが、考えが長州の者と近すぎる。」
佐賀藩にも情報をもたらすが、勤王の志で脱藩をしたという祇園太郎に全幅の信頼を置くわけにはいかないようだ。夏雲は、こう続けた。
「それに、お主は長崎での探索ならば、手慣れたものじゃなかね。」
たしかに開港後の長崎を見ると、西国の雄藩と欧米の商人の接触も増えつつある。今までの仕事の延長線上とも言えるが、古賀はあまり気乗りがしない。
――いわば“配置転換”の通告を受けた、嬉野の忍者・古賀。
祇園太郎の退出から、しばし後に鍋島夏雲の役宅を後にした。いつになく足取りの重い嬉野の忍者である。
異国船を調べる任務を始めた頃から、すっかり歳月も流れた。
「おいの気張ってきた仕事も、いまや時代遅れのやり方とね…」
そこに傍らの雉(きじ)猫が何かを伝える様子で、ニャーンと、ひと鳴きする。
「“おいも、まだ頑張るけん。もう、ひと踏ん張りせんね…”か。よかたい。」
気を取り直したか早足に歩き始めるや、古賀も猫もすっかり姿を消していた。
(続く)
文久二年(1862年)晩夏の佐賀城下。藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲に呼び出されたのは、“嬉野の忍者”・古賀。いつものように猫を連れています。
この頃、京の都を中心に存在感を強める尊王攘夷の志士。朝廷に働きかけ、すぐに異国を打ち払うよう、幕府に圧力をかけていました。
西洋列強の技術力に追いつこうと奮闘する佐賀藩にとって、この志士たちの考え方は短慮と見えるのですが、その影響は無視できなくなってきています。

――“祇園太郎”と名乗る、旅姿の男が現れた。
いきなり上方(京・大坂)の言葉で話し始めたことを詫びる、祇園太郎。
佐賀藩の重臣でも年配の鍋島夏雲(市佑)だが、いたわりの言葉を口にした。
「気にせんでよか。ここまでの道中は、大過なかったか。」
この辺りが年の功だけでなく、夏雲に情報が集まる理由なのかもしれない。
〔参照(後半):
「おいは、小城を抜けた者やけん、相変わらず国境はえすか(怖い)です。」
聞けば、この“祇園太郎”は、佐賀の小城支藩からの脱藩者だという。
〔参照:
――傍らに控え、二者の会話を聞く“嬉野の忍者”。
この祇園太郎だが、どうやら“忍び”では無さそうである。脱藩者の身の上で、よく佐賀に帰って来られたものだ。
夏雲が、言葉を続ける。
「時に“危ない橋”もあったであろうな。昨今の京の様子は、どうね。」
祇園太郎は尊王攘夷派とよく関わっている。鍋島夏雲も京の都で力を持ってきた各地からの志士たちの動きが気になる様子だ。
「江藤さんがあれこれ調べ回っとるけん、そちらが詳しかと思います。」
傍で話を聞く、嬉野の忍者・古賀。鍋島夏雲と“祇園太郎”の話に出てきた、江藤新平という青年を想い出した。
〔参照:
「才のある男だと思ったが、どうやら佐賀を抜け、京でも頑張っておるらしい」と考えると、少し感慨もある。
――重臣・鍋島夏雲と、脱藩者・祇園太郎との問答は続く。
「まずは、概ねの話でよい。」
「京で勤王を志す者たちの間では…」
「ほうほう。」
「佐賀は、腹の底で何ば考えおるかわからぬ、と。」
「…。」
夏雲は黙って聞いていた。
「朝廷にも徳川にも良い顔をして、世間を欺(あざむ)きおる、と。」
「うむうむ。」
佐賀藩は朝廷も重んじるが、幕府にも協力的なので、勤王を唱える者には、そこが気に入らないのだろう。
「佐賀はどちらの味方かわからんゆえ、全く信用ならん、と言いよります。」
――温厚な中にも、ふと鋭さが見える鍋島夏雲。
無言で祇園太郎の報告を聞いており、すました表情をしているが、佐賀藩が「世間を欺いている」とまで言われると釈然としない。
「わしら佐賀は、日和見(ひよりみ)…と言われておるか。」
たしかに長崎警備の役回りを持つ佐賀藩は、どこより欧米各国からの見え方を気にするところがある。
いまや欧米の列強国が通商などで入り込むなか、国内で内紛が起きれば危ういというのが、佐賀藩の立場であり、それが行動の慎重さにつながっている。
出来うる限り、朝廷と幕府の関係悪化は避けたい思惑もあるのだが、これが尊王攘夷派には「どっち付かず」と取られるようだ。
――ひと通りの報告を終えると、祇園太郎は退出した。
この“小城の密偵”のような男は、佐賀城下でも所用があるらしく、そそくさと去っていった。忙しいことに長崎に行った後に、京都に戻る予定もあるという。
「先ほどまでの話で、察しはついておるだろうか。」
ここで鍋島夏雲は、聞き役に徹していた“嬉野の忍者”に用件を伝え始めた。
「長崎も港を開いたゆえ、異国船は表から調べることもできよう。」
――夏雲の語りたいことはわかる。これも時代の流れだ。
この年に佐賀藩は、欧州や清国の上海にも調査団の人員を送った。
もはや通訳や商人からも情報は得られる。隠れて異国船に近づく危険な調査をあえて選択する必要も無さそうだ。
「これからは、長崎に来ておる浪士たちの動きを探ってほしい。」
夏雲の言うことには、密かに調べたいのは、長州(山口)や土佐(高知)など、各地の雄藩を動かしつつある、尊王攘夷派の実情だという。
「おい(私)も歳ば取りましたけん、あん男でよかじゃなかですか。」
「祇園太郎か。あれは良い調べをするが、考えが長州の者と近すぎる。」
佐賀藩にも情報をもたらすが、勤王の志で脱藩をしたという祇園太郎に全幅の信頼を置くわけにはいかないようだ。夏雲は、こう続けた。
「それに、お主は長崎での探索ならば、手慣れたものじゃなかね。」
たしかに開港後の長崎を見ると、西国の雄藩と欧米の商人の接触も増えつつある。今までの仕事の延長線上とも言えるが、古賀はあまり気乗りがしない。
――いわば“配置転換”の通告を受けた、嬉野の忍者・古賀。
祇園太郎の退出から、しばし後に鍋島夏雲の役宅を後にした。いつになく足取りの重い嬉野の忍者である。
異国船を調べる任務を始めた頃から、すっかり歳月も流れた。
「おいの気張ってきた仕事も、いまや時代遅れのやり方とね…」
そこに傍らの雉(きじ)猫が何かを伝える様子で、ニャーンと、ひと鳴きする。
「“おいも、まだ頑張るけん。もう、ひと踏ん張りせんね…”か。よかたい。」
気を取り直したか早足に歩き始めるや、古賀も猫もすっかり姿を消していた。
(続く)




