2020年04月23日
「望郷の剣」
こんばんは。第8話「黒船来航」はいかがだったでしょうか。
ちなみに今日は“本編”ではありません。
文章の練習として、かなりふざけていますので、あまり熱心にお読みいただかなくても…
新型コロナウイルスにより一時帰藩が叶わない、ある佐賀藩士(?)の物語です。
「ついに“ブラックモンブラン”も、最後の1本か…」
――私は数か月前、近所のスーパーの九州物産展で入手したアイスバーを見つめていた。
佐賀から遠い“脱藩の地”で「竹下製菓のアイス」を見つけた私。
“ブラックモンブラン”と“ミルクック”の豪奢な詰め合わせである。
私は躊躇なく品物を手に取り、人の少ないレジに向かった。
アイスバーの持ち帰りは時間との勝負である。
――それは、佐賀県小城市の工場で生産された品だった。
私が希少な価値を見出した、この品物。佐賀市内で購入することはたやすい。
現在では、ウェブショッピングで取り寄せることすら可能である。
…しかし、それでは風情が無さすぎる。
私は冷凍庫で大事に保管したアイスバーを1本ずつ消費していた。
――私は一時帰藩の際、このアイス界の至宝“ブラックモンブラン”を潤沢に揃える施設を見た。

佐賀バルーンミュージアムの1階にある「佐賀工房」のショップである。
しかも冷凍庫には“ストロベリー”や“抹茶”味のブラックモンブランまで備える様子だ。
私から見れば、“黄金郷”に等しい品揃えだった。
――しかし行程に余裕のなかった私は思った。「この場には、次の帰藩の際に立ち寄るべし」と。
しかし年が明け、新型コロナウイルスが猛威を奮う。
“疫病”の蔓延が高い壁となって、私と佐賀との間を隔てたのである。
――愕然と膝をつく私。しかし…
誰かの声が聞こえたような気がする。
「あきらめるな!まだ“ミルクック”が3本も残っているではないか!」
「その、お声はもしや…!」
私は、遠く西の空を見遣ったのである。
…以上です。着地点のよくわからない文章ににお付き合いいただいた方。ありがとうございます。
たぶん、私は皆様より感染リスクの高い地域におります。
そのため、残念ながら佐賀への帰藩を自粛しているところです。
皆様も充分にお気をつけて。
ちなみに今日は“本編”ではありません。
文章の練習として、かなりふざけていますので、あまり熱心にお読みいただかなくても…
新型コロナウイルスにより一時帰藩が叶わない、ある佐賀藩士(?)の物語です。
「ついに“ブラックモンブラン”も、最後の1本か…」
――私は数か月前、近所のスーパーの九州物産展で入手したアイスバーを見つめていた。
佐賀から遠い“脱藩の地”で「竹下製菓のアイス」を見つけた私。
“ブラックモンブラン”と“ミルクック”の豪奢な詰め合わせである。
私は躊躇なく品物を手に取り、人の少ないレジに向かった。
アイスバーの持ち帰りは時間との勝負である。
――それは、佐賀県小城市の工場で生産された品だった。
私が希少な価値を見出した、この品物。佐賀市内で購入することはたやすい。
現在では、ウェブショッピングで取り寄せることすら可能である。
…しかし、それでは風情が無さすぎる。
私は冷凍庫で大事に保管したアイスバーを1本ずつ消費していた。
――私は一時帰藩の際、このアイス界の至宝“ブラックモンブラン”を潤沢に揃える施設を見た。

佐賀バルーンミュージアムの1階にある「佐賀工房」のショップである。
しかも冷凍庫には“ストロベリー”や“抹茶”味のブラックモンブランまで備える様子だ。
私から見れば、“黄金郷”に等しい品揃えだった。
――しかし行程に余裕のなかった私は思った。「この場には、次の帰藩の際に立ち寄るべし」と。
しかし年が明け、新型コロナウイルスが猛威を奮う。
“疫病”の蔓延が高い壁となって、私と佐賀との間を隔てたのである。
――愕然と膝をつく私。しかし…
誰かの声が聞こえたような気がする。
「あきらめるな!まだ“ミルクック”が3本も残っているではないか!」
「その、お声はもしや…!」
私は、遠く西の空を見遣ったのである。
…以上です。着地点のよくわからない文章ににお付き合いいただいた方。ありがとうございます。
たぶん、私は皆様より感染リスクの高い地域におります。
そのため、残念ながら佐賀への帰藩を自粛しているところです。
皆様も充分にお気をつけて。
2020年05月09日
「望郷の剣2」
こんばんは。
お読みいただいている皆様、第9話「和親条約」いかがだったでしょうか。なるべく海外の情勢も折り込もうと試みました。
もともと”本編”は“史実に着想を得たフィクション”として構成しておりますが、「実は、こういう展開だったかもしれない…」という可能性を残したい願望もあります。
そのため、情報の取捨選択で、迷うことも多いです。
時々思うのですが、もう少し世界史も勉強しておけば良かった…いや、全般的にもっと勉強しておくべきでした。
…幕末の佐賀藩士たちの足跡を追うと、そう思わずにはいられません。
――さて本編はお休みで、息抜きの企画です。

ありふれた日常の風景を、むりに幕末っぽく描きます。
佐賀のプレゼンス(存在感)を高めるため、消費行動を通じて戦う、現代の佐賀藩士(?)のお話です。
――新型コロナの拡大により、緊張感の増した日々の買い物。私は近隣のスーバーに出向く。
私が外出の自粛に備え、迅速に棚より商品の選定を行っていた。そこで、目に留まった品がある。
“定番でない品”が陳列される棚。季節物や新商品などを扱う場所である。
その最上段に、佐賀銘菓「丸ぼうろ」が姿を見せた。
――この新型コロナ蔓延(はびこ)る、世の荒波を乗り越え、私の眼前に現れた“丸ぼうろ”。
遥々と佐賀からの道のりを超えてきたと思うと感慨もひとしおである。
「おぉ!“丸ぼうろ”ではないか。久しいのう!」
…と、声をかけるほどまでは、私の妄想はひどくはない。
しかし私は同時に、これを好機と判断した。
手持ちの買い物カゴに、おもむろに“丸ぼうろ”の大袋3つを追加したのである。
――「これはお買い得だ!ぜひ、買うべきだ!」私の躊躇のない背中は、そう語ったらしい。
私の行動に引っ張られるように、他のお客が“丸ぼうろ”を手に取った。そして、同じように買い物カゴに入れたのである。
私は想った。
「これでいい。佐賀の特産品に売れ残りなど、あってはならんのだ。」
このような妄想とともに、戦いの日々は続いていきます。
幕末佐賀藩の存在が、遍(あまね)く人々に知られ、この国が誇りを取り戻すその日まで…
以上です。
佐賀の菓子の甘さは絶妙です。
新型コロナの騒乱が終息したら、ぜひ佐賀で甘味も食べ歩きたいものです。
お読みいただいている皆様、第9話「和親条約」いかがだったでしょうか。なるべく海外の情勢も折り込もうと試みました。
もともと”本編”は“史実に着想を得たフィクション”として構成しておりますが、「実は、こういう展開だったかもしれない…」という可能性を残したい願望もあります。
そのため、情報の取捨選択で、迷うことも多いです。
時々思うのですが、もう少し世界史も勉強しておけば良かった…いや、全般的にもっと勉強しておくべきでした。
…幕末の佐賀藩士たちの足跡を追うと、そう思わずにはいられません。
――さて本編はお休みで、息抜きの企画です。
ありふれた日常の風景を、むりに幕末っぽく描きます。
佐賀のプレゼンス(存在感)を高めるため、消費行動を通じて戦う、現代の佐賀藩士(?)のお話です。
――新型コロナの拡大により、緊張感の増した日々の買い物。私は近隣のスーバーに出向く。
私が外出の自粛に備え、迅速に棚より商品の選定を行っていた。そこで、目に留まった品がある。
“定番でない品”が陳列される棚。季節物や新商品などを扱う場所である。
その最上段に、佐賀銘菓「丸ぼうろ」が姿を見せた。
――この新型コロナ蔓延(はびこ)る、世の荒波を乗り越え、私の眼前に現れた“丸ぼうろ”。
遥々と佐賀からの道のりを超えてきたと思うと感慨もひとしおである。
「おぉ!“丸ぼうろ”ではないか。久しいのう!」
…と、声をかけるほどまでは、私の妄想はひどくはない。
しかし私は同時に、これを好機と判断した。
手持ちの買い物カゴに、おもむろに“丸ぼうろ”の大袋3つを追加したのである。
――「これはお買い得だ!ぜひ、買うべきだ!」私の躊躇のない背中は、そう語ったらしい。
私の行動に引っ張られるように、他のお客が“丸ぼうろ”を手に取った。そして、同じように買い物カゴに入れたのである。
私は想った。
「これでいい。佐賀の特産品に売れ残りなど、あってはならんのだ。」
このような妄想とともに、戦いの日々は続いていきます。
幕末佐賀藩の存在が、遍(あまね)く人々に知られ、この国が誇りを取り戻すその日まで…
以上です。
佐賀の菓子の甘さは絶妙です。
新型コロナの騒乱が終息したら、ぜひ佐賀で甘味も食べ歩きたいものです。
2020年05月31日
「岐路の剣」
こんばんは。
第10話「蒸気機関」いかがだったでしょうか。当ブログも開始から半年近くを経て、岐路に立っている感じがあります。
今回は、ある佐賀藩士(?)の日常を描く『望郷の剣』シリーズ第3弾です。
――歴史には、様々な分岐点と選択があるようです。
概ね年代順に幕末の歴史を追っているところですが、開国か攘夷かで、すっきり二分される話ではないようです。
例えば、第9話で存在感を見せた、老中・阿部正弘は“雄藩との連携”を目指し、後に登場する大老・井伊直弼は“幕府の主導権”を取り戻しにかかる…と同じ開国派でもかなりの違いがあります。
――現在の佐賀県にまつわる話題で言えば…
長崎新幹線の話合いに応じ、全線のスピード開業を目指すのか。
佐賀県は負担を強いられるだけで、素通りされると警戒するか。
…長崎~武雄温泉間の開業が決まっている以上、動かぬ間にも問題は拡大していくでしょう。ただ、佐賀に一定の力の蓄積が無ければ、後者の心配も否めないところです。
――そして佐賀で分岐点を語るのに相応しい場所を選んでみました。
「肥前山口」駅です。ここでも選択肢が示されます。

長崎に行くのか。
佐世保に向かうのか。
――おそらくは、人生もまた分岐と選択の繰り返し…
「長崎に行くのか、佐世保に向かうのか。それが問題だ…」
実際は佐世保の親戚に会いにいったので、考える余地は無かったのですが、分岐点ならではの「もう1つの道を選んだら…」という感覚は味わえました。
――また「本当に選択肢は2つなのか?」という疑問もあります。
例えば肥前山口駅でそのまま下車。
「江北町を散歩する」という選択を取ることも可能です。
これをブログの方針に例えるなら、日々、呼吸をするぐらいの気持ちで更新するといったところでしょうか。
――私は色々と思うところあり「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と、ひたすらに書き綴っています。
分類上は、一定の目的に向かって走っているタイプのブログになるでしょう。
しかしながら、「さがファンブログ」の諸先輩方には、人生の流れの中で、ごく自然に更新を続けている方も多く見かけます。
『望郷の剣』というシリーズタイトルにかぶせた言い方をすると、あたかも軽妙に剣を遣う“達人”と遭遇した気分になることも、しばしばです。
…力の入り過ぎというのも、また良くないのだな…と思います。
第10話「蒸気機関」いかがだったでしょうか。当ブログも開始から半年近くを経て、岐路に立っている感じがあります。
今回は、ある佐賀藩士(?)の日常を描く『望郷の剣』シリーズ第3弾です。
――歴史には、様々な分岐点と選択があるようです。
概ね年代順に幕末の歴史を追っているところですが、開国か攘夷かで、すっきり二分される話ではないようです。
例えば、第9話で存在感を見せた、老中・阿部正弘は“雄藩との連携”を目指し、後に登場する大老・井伊直弼は“幕府の主導権”を取り戻しにかかる…と同じ開国派でもかなりの違いがあります。
――現在の佐賀県にまつわる話題で言えば…
長崎新幹線の話合いに応じ、全線のスピード開業を目指すのか。
佐賀県は負担を強いられるだけで、素通りされると警戒するか。
…長崎~武雄温泉間の開業が決まっている以上、動かぬ間にも問題は拡大していくでしょう。ただ、佐賀に一定の力の蓄積が無ければ、後者の心配も否めないところです。
――そして佐賀で分岐点を語るのに相応しい場所を選んでみました。
「肥前山口」駅です。ここでも選択肢が示されます。

長崎に行くのか。
佐世保に向かうのか。
――おそらくは、人生もまた分岐と選択の繰り返し…
「長崎に行くのか、佐世保に向かうのか。それが問題だ…」
実際は佐世保の親戚に会いにいったので、考える余地は無かったのですが、分岐点ならではの「もう1つの道を選んだら…」という感覚は味わえました。
――また「本当に選択肢は2つなのか?」という疑問もあります。
例えば肥前山口駅でそのまま下車。
「江北町を散歩する」という選択を取ることも可能です。
これをブログの方針に例えるなら、日々、呼吸をするぐらいの気持ちで更新するといったところでしょうか。
――私は色々と思うところあり「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と、ひたすらに書き綴っています。
分類上は、一定の目的に向かって走っているタイプのブログになるでしょう。
しかしながら、「さがファンブログ」の諸先輩方には、人生の流れの中で、ごく自然に更新を続けている方も多く見かけます。
『望郷の剣』というシリーズタイトルにかぶせた言い方をすると、あたかも軽妙に剣を遣う“達人”と遭遇した気分になることも、しばしばです。
…力の入り過ぎというのも、また良くないのだな…と思います。
2020年06月27日
「発心の剣」
こんにちは。
お読みいただいている皆様、第11話「蝦夷探検」はいかがだったでしょうか。
今年も大雨への心配が尽きないシーズンですね。あらためて自然の大きさを感じるのは、こういう時なのかもしれません。
――さて、本日は息抜きに投稿しております「望郷の剣」シリーズです。
帰るに帰れない郷里・佐賀を想いながら、現代の大都市圏で生きる…ある佐賀藩士(?)の物語。
同シリーズのエピソード・ゼロ(前日譚)にあたる“出会い”を描いてみます。たぶん2~3年前の出来事です。
――「今日の仕事も終わった。いや、終わらせた…」夜の帰路を急ぐ。電車には乗り遅れ、途中からの最終バスも逃した。
日中の強い日差しが、余韻を残している。
アスファルトで固められたような街に、乾いた砂ぼこりが舞う。
大都市圏であれば、人の数は居る。物は集まる。むろん情報やお金の流れもある。
但し、そこで暮らす人生が、“豊か”であるかは、別の問題だ。

――早く帰って眠りたい。私は時間をかけて歩くのをあきらめ、タクシーを選ぶことが増えていた。
広い道である。何台かのタクシーが直進し、通り過ぎていった。
運転手と目の合った1台が、手前まで寄ってくれる。
「こんばんは。」
簡単な挨拶を交わすと、私は目的地を告げた。
「この道を左に曲がってください。」
とりあえず、少しは早く帰れそうだ。私はホッと一息をついた。
――しばしの沈黙のあと、運転手が口を開く。ドライバーによって個性が出る“タクシー車内の雑談”である。
しかし、今日はいつもと勝手が違う。
急に、ぶしつけな質問が飛んできたのだ。
「兄さん、どこの人ね。」
私の疲れた頭はこう考えた。
「タクシーの呼び止め方が…当地の作法と違ったのか?」と。
おそらくは“出身地”に関する問いだ。まず、こう答えよう。
「生まれは、九州です。」
すると想定以上のトーン(声量)で、さらに質問が来る。
「九州のどこね!?」
――ここで「佐賀県です」と答えればよいのだが、私には躊躇があった。
それまでの私の人生で、佐賀出身と伝えたときの経験によるが、
「え、何県だって?」→「佐賀県です!」
「どこにあるんだ?」→「九州にあります!」
…という展開が多い。あまり芳しくない傾向がある。
この運転手さんの質問だと、その展開に陥る心配はない。
「…出身は、佐賀です。」
「そうね!やっぱり、そうね!佐賀のどこね!?」
――タクシーの運転手さんは、佐賀の出身者だった。そして故郷を離れてから、かなりの歳月が流れていると想像できた。
私に“さがんもん”の気配を感じ取り、積極的な質問に至ったようだ。
彼は「望郷の念」を強く持つ者であったらしい。私が佐賀の出身と知るや、嬉々としている。
「特急“かもめ”号のシートは、よかたい!」
…それが、佐賀の自慢になるのかは定かではない。しかし、喜んで語っている気持ちは良く伝わった。
――日中と違い、夜は空いた道である。目的地にはアッという間に辿り着いた。
私は、タクシーの運転手さんに料金を支払い、礼を述べる。
佐賀の話が、楽しかったと申し添えて。
…家まで少し歩く間に、色々なことを考えた。
私は、わずか二言を発しただけで“佐賀出身”と見抜かれている。
――当時の私に、“佐賀”を意識する機会は、ほとんど無かった。
だが、見る人が見れば、一瞬で“さがんもん”と判るという事実が突き付けられたのである。
これが、運転手さんの能力によるものなのか、よほど私が“佐賀”っぽい雰囲気を纏(まと)って生きているのか…これは、今のところ分からない。
ある年配のタクシードライバーの「望郷の想い」。おそらくは、私の現在の行動につながっているのである。
お読みいただいている皆様、第11話「蝦夷探検」はいかがだったでしょうか。
今年も大雨への心配が尽きないシーズンですね。あらためて自然の大きさを感じるのは、こういう時なのかもしれません。
――さて、本日は息抜きに投稿しております「望郷の剣」シリーズです。
帰るに帰れない郷里・佐賀を想いながら、現代の大都市圏で生きる…ある佐賀藩士(?)の物語。
同シリーズのエピソード・ゼロ(前日譚)にあたる“出会い”を描いてみます。たぶん2~3年前の出来事です。
――「今日の仕事も終わった。いや、終わらせた…」夜の帰路を急ぐ。電車には乗り遅れ、途中からの最終バスも逃した。
日中の強い日差しが、余韻を残している。
アスファルトで固められたような街に、乾いた砂ぼこりが舞う。
大都市圏であれば、人の数は居る。物は集まる。むろん情報やお金の流れもある。
但し、そこで暮らす人生が、“豊か”であるかは、別の問題だ。

――早く帰って眠りたい。私は時間をかけて歩くのをあきらめ、タクシーを選ぶことが増えていた。
広い道である。何台かのタクシーが直進し、通り過ぎていった。
運転手と目の合った1台が、手前まで寄ってくれる。
「こんばんは。」
簡単な挨拶を交わすと、私は目的地を告げた。
「この道を左に曲がってください。」
とりあえず、少しは早く帰れそうだ。私はホッと一息をついた。
――しばしの沈黙のあと、運転手が口を開く。ドライバーによって個性が出る“タクシー車内の雑談”である。
しかし、今日はいつもと勝手が違う。
急に、ぶしつけな質問が飛んできたのだ。
「兄さん、どこの人ね。」
私の疲れた頭はこう考えた。
「タクシーの呼び止め方が…当地の作法と違ったのか?」と。
おそらくは“出身地”に関する問いだ。まず、こう答えよう。
「生まれは、九州です。」
すると想定以上のトーン(声量)で、さらに質問が来る。
「九州のどこね!?」
――ここで「佐賀県です」と答えればよいのだが、私には躊躇があった。
それまでの私の人生で、佐賀出身と伝えたときの経験によるが、
「え、何県だって?」→「佐賀県です!」
「どこにあるんだ?」→「九州にあります!」
…という展開が多い。あまり芳しくない傾向がある。
この運転手さんの質問だと、その展開に陥る心配はない。
「…出身は、佐賀です。」
「そうね!やっぱり、そうね!佐賀のどこね!?」
――タクシーの運転手さんは、佐賀の出身者だった。そして故郷を離れてから、かなりの歳月が流れていると想像できた。
私に“さがんもん”の気配を感じ取り、積極的な質問に至ったようだ。
彼は「望郷の念」を強く持つ者であったらしい。私が佐賀の出身と知るや、嬉々としている。
「特急“かもめ”号のシートは、よかたい!」
…それが、佐賀の自慢になるのかは定かではない。しかし、喜んで語っている気持ちは良く伝わった。
――日中と違い、夜は空いた道である。目的地にはアッという間に辿り着いた。
私は、タクシーの運転手さんに料金を支払い、礼を述べる。
佐賀の話が、楽しかったと申し添えて。
…家まで少し歩く間に、色々なことを考えた。
私は、わずか二言を発しただけで“佐賀出身”と見抜かれている。
――当時の私に、“佐賀”を意識する機会は、ほとんど無かった。
だが、見る人が見れば、一瞬で“さがんもん”と判るという事実が突き付けられたのである。
これが、運転手さんの能力によるものなのか、よほど私が“佐賀”っぽい雰囲気を纏(まと)って生きているのか…これは、今のところ分からない。
ある年配のタクシードライバーの「望郷の想い」。おそらくは、私の現在の行動につながっているのである。
2020年08月01日
「望郷の剣3」
こんにちは。
お読みいただいた方、第12話「海軍伝習」いかがだったでしょうか。今年も8月になってしまいました。
本日は、ある佐賀藩士(?)の想いを描く「望郷の剣」シリーズです。
――私の個人的な事情だが、周辺環境の変化により、4月以降の活動は苦戦を強いられている。
「この展開は予期できなかった…」
ブログ開始時の想定に比べて、現在の私を取り巻く状況は厳しい。いまや2日に1度の投稿ペースを守るのに手一杯である。
「いかん…写真の素材も無い!」
また新型コロナの蔓延により、佐賀に帰藩して行うはずの事柄が実施できない。いまや情報の収集にも高いハードルが生じている。
――しかし、そのことは私の“望郷の念”をより強いものとしている。
いろいろ疑問符(?)が付くとはいえ、仮にも“佐賀藩士”を名乗るならば、この程度の困難に屈してはならない。
これまでの「望郷の剣」の続きになるが、帰藩が叶わずとも、動く手立てはある。まずは“消費行動”で、佐賀の価値を示すのである。
――こうして我が家の食卓には、嬉野茶、伊万里梨、白石産“玉ねぎ”が並ぶこととなった。
佐賀県の農産物は生産高でトップは取れなくても、ランキング高順位の品目が多い。良い位置に付けているのだ。もちろん品質は申し分ない。
これに小城の工場で製造される“ブラックモンブラン”、佐賀市内の製菓店の“丸ぼうろ”を加えれば、さらに彩りが増すことであろう。
――今年6月。新商業施設“コムボックス”がオープンし、佐賀駅前が少し賑わっていると聞く。
私が“帰藩”できた時期は、まだ工事中だったのが、ついに動き始めたのだ。

今まで「インバウンド」という言葉は、主に“観光用語”として使われてきた。外国人観光客による消費を指して使われている経過がある。
しかし「インバウンド」にはもう1つの意味があるらしい。“ビジネス用語”では、国内外を問わず「顧客から企業にアプローチしてくる動き」全般を指すという。
――例えば、有田焼で特定の窯元のファンが直接訪ねて来る…という動きは、もう1つの「インバウンド」であるようだ。
駅前の新商業施設には、観光・県産品案内の拠点“SAGA MADO”があり、特産品の展示ブースがあると聞く。いわば常設の見本市ができた。
これにより県内外の方と、佐賀の特産品との“出会い”の場が創り出されるはず…そんな展開に期待している。
佐賀県内の「この地域、この商品」のファンが増えれば、まず県内の生産者が潤う。苦境にある地元の飲食業や温泉などの観光業にも、安定した資金が回る好循環を作り出せないか…
――「私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマ」を追う中で、佐賀を主役にした“新しい消費行動”の実現を想うようになった。
もちろん、幕末期に佐賀藩が行った政策のイメージに感化されている。
まずは全国各地に散らばっている佐賀藩士(?)に呼び掛けを試みたい。
「佐賀産の品物を選択すべし!」と。
小さなところから、各々の“決起”を促すことも大事だと思うのである。
――以上です。最後にブログをお読みの皆様で、主に大都市圏に親族がいらっしゃる方へのつぶやきです。
たとえお盆の帰省は自粛しても、このような佐賀との繋がり方もあります。
新型コロナへの心配で、帰省を迷っている親族をお持ちの皆様には、ひとまず特産品を通じて“望郷の想い”を満たす方法もあるのではないかと思います。
…わずかでも佐賀の経済にプラスにはたらきますし、大都市圏に“佐賀への想い”を持つ同志(?)が増えれば、私も心強いです。
今は好機の到来を待つことにします。
お読みいただいた方、第12話「海軍伝習」いかがだったでしょうか。今年も8月になってしまいました。
本日は、ある佐賀藩士(?)の想いを描く「望郷の剣」シリーズです。
――私の個人的な事情だが、周辺環境の変化により、4月以降の活動は苦戦を強いられている。
「この展開は予期できなかった…」
ブログ開始時の想定に比べて、現在の私を取り巻く状況は厳しい。いまや2日に1度の投稿ペースを守るのに手一杯である。
「いかん…写真の素材も無い!」
また新型コロナの蔓延により、佐賀に帰藩して行うはずの事柄が実施できない。いまや情報の収集にも高いハードルが生じている。
――しかし、そのことは私の“望郷の念”をより強いものとしている。
いろいろ疑問符(?)が付くとはいえ、仮にも“佐賀藩士”を名乗るならば、この程度の困難に屈してはならない。
これまでの「望郷の剣」の続きになるが、帰藩が叶わずとも、動く手立てはある。まずは“消費行動”で、佐賀の価値を示すのである。
――こうして我が家の食卓には、嬉野茶、伊万里梨、白石産“玉ねぎ”が並ぶこととなった。
佐賀県の農産物は生産高でトップは取れなくても、ランキング高順位の品目が多い。良い位置に付けているのだ。もちろん品質は申し分ない。
これに小城の工場で製造される“ブラックモンブラン”、佐賀市内の製菓店の“丸ぼうろ”を加えれば、さらに彩りが増すことであろう。
――今年6月。新商業施設“コムボックス”がオープンし、佐賀駅前が少し賑わっていると聞く。
私が“帰藩”できた時期は、まだ工事中だったのが、ついに動き始めたのだ。
今まで「インバウンド」という言葉は、主に“観光用語”として使われてきた。外国人観光客による消費を指して使われている経過がある。
しかし「インバウンド」にはもう1つの意味があるらしい。“ビジネス用語”では、国内外を問わず「顧客から企業にアプローチしてくる動き」全般を指すという。
――例えば、有田焼で特定の窯元のファンが直接訪ねて来る…という動きは、もう1つの「インバウンド」であるようだ。
駅前の新商業施設には、観光・県産品案内の拠点“SAGA MADO”があり、特産品の展示ブースがあると聞く。いわば常設の見本市ができた。
これにより県内外の方と、佐賀の特産品との“出会い”の場が創り出されるはず…そんな展開に期待している。
佐賀県内の「この地域、この商品」のファンが増えれば、まず県内の生産者が潤う。苦境にある地元の飲食業や温泉などの観光業にも、安定した資金が回る好循環を作り出せないか…
――「私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマ」を追う中で、佐賀を主役にした“新しい消費行動”の実現を想うようになった。
もちろん、幕末期に佐賀藩が行った政策のイメージに感化されている。
まずは全国各地に散らばっている佐賀藩士(?)に呼び掛けを試みたい。
「佐賀産の品物を選択すべし!」と。
小さなところから、各々の“決起”を促すことも大事だと思うのである。
――以上です。最後にブログをお読みの皆様で、主に大都市圏に親族がいらっしゃる方へのつぶやきです。
たとえお盆の帰省は自粛しても、このような佐賀との繋がり方もあります。
新型コロナへの心配で、帰省を迷っている親族をお持ちの皆様には、ひとまず特産品を通じて“望郷の想い”を満たす方法もあるのではないかと思います。
…わずかでも佐賀の経済にプラスにはたらきますし、大都市圏に“佐賀への想い”を持つ同志(?)が増えれば、私も心強いです。
今は好機の到来を待つことにします。
2020年08月02日
「慈雨の剣」
こんばんは。
前回の投稿で、うっかり「写真素材が無い!」とつぶやいてしまったので、色々とお気遣いの言葉をいただきました。
「望郷の剣」というタイトルでの投稿もシリーズ化しています。今では少し距離が遠くても、新型コロナの影響で隔てられても、佐賀がとても近くに感じられます。これは皆様のおかげであると思います。
…というわけで、今日もある佐賀藩士(?)の想いを描く同シリーズの投稿です。
ちなみに“本編”の第13話は「通商条約」の予定ですが、話の構成を迷うところです。準備期間として、色々と投稿しながら考えていきたいと思います。
――さて、豪雨は困りますが、猛暑に見舞われ出すと、穏やかな雨を懐かしく想います。
思えば元号が“令和”になってから、まだ1年ちょっとしか経っていません。
今日は、いきなり“平成”ラストの一日に話が戻るのですが…この日、皆様は何か特別な過ごし方をなさっていたでしょうか。
以前「発心の剣」というタイトルで、私が“佐賀出身”であると、一瞬で見抜かれた話を投稿しました。今回は、私が佐賀藩士(?)として、活動し始める契機になった日のお話です。
――“平成”最後の日、早朝。佐賀市内には霧のような優しい雨が降っていた。
私が佐賀に帰ってきたのは、祖父の墓参りをするためだった。
ごく幼少の頃に祖父とは死別した。
それゆえ私は、はっきりと祖父の姿を覚えているわけではない。
しかし、受け継いだ…あるいは受け継いでしまったものは確かにあるらしい。
――しかし、先んじて墓参りの際は、滝のような雨に見舞われた。
「わざわざ孫が墓参りにきたので、感激の涙雨ではないか…」
…などと他愛のない会話をしながら、慌ただしい墓参となったのである。
こうして主たる用事が終わり、佐賀での滞在の最終日。
早朝に目が覚めてしまった。特に為すべきこともないので、まだ人通りもほとんどない県庁通りを歩いた。

――そのまま南下し、佐賀城公園に向かったのである。
雨はポツポツと降り続いていた。
ただ、お堀端を歩く。どの場所も丁寧に掃除が行き届いている様子だ。
このお城が、いかに周りの市民から愛されているかが伝わってくる。本丸歴史館が開くまでには、まだ随分と時間があった。
――涼しい雨を傘で受けながら、おそらくは贅沢な時間を過ごした。
「やはり、ここは私にとっては“特別な場所”なのだ…」
そう感じずにはいられなかった。
時計の針が進むのも忘れたかのような時間を過ごした。
あと15時間ほどが経てば“元号”も変わるのだ…それが、より一層の特別感を醸し出していた。
――ほどなく本丸歴史館が開く。
佐賀藩についての知識が得たくて、設置されているモニターの前に座る。
「幕末期、日本の近代化の先駆けとなった肥前佐賀藩…」
概ね、このような解説だっただろうか。
その前年の大河ドラマが「西郷どん」だったので、少なくとも“佐賀七賢人”のうち3人は登場した。その辺りの情報は、少し調べていた。
――しかし、モニターの音声は、予想外の人物の解説を始めた。
「財政、教育を担当した藩の請役(ナンバー2)で、須古領主の鍋島安房…」
私は完全に隙を突かれた。まったくノーマークだった人物の名が出てくる。

しかも財政再建と教育改革を成し遂げた、殿・鍋島直正の“右腕”のような補佐役とは…幕末の佐賀藩において、極めて重要なところである。
その衝撃はハッキリと覚えているが、その後、資料館内で何を調べたかの記憶は曖昧である。ただ「幕末佐賀藩の活躍は、もっと広く知られるべきだ!」という気持ちは確信に変わった。
――全国が“新しい時代へのカウントダウン”で浮き立っていた、その日。私は佐賀を発った。
こうして今度は佐賀出身者であるだけでなく、佐賀藩士(?)としての気付きを得てしまった私。大都市圏に戻っての活動が始まった。
まず“令和”に元号が変わった次の日から、本棚の奥にあった古い日本史の教科書を引っ張り出した。そして、おもむろに佐賀藩の年表と見比べたのである。
…クールダウンを意識してみましたが、やはり佐賀藩の話に言及すると多少は熱くなるようです…しばらくの間、忙しくなりそうなのですが、休み休みになっても、何とか続けていきたいと思います。
前回の投稿で、うっかり「写真素材が無い!」とつぶやいてしまったので、色々とお気遣いの言葉をいただきました。
「望郷の剣」というタイトルでの投稿もシリーズ化しています。今では少し距離が遠くても、新型コロナの影響で隔てられても、佐賀がとても近くに感じられます。これは皆様のおかげであると思います。
…というわけで、今日もある佐賀藩士(?)の想いを描く同シリーズの投稿です。
ちなみに“本編”の第13話は「通商条約」の予定ですが、話の構成を迷うところです。準備期間として、色々と投稿しながら考えていきたいと思います。
――さて、豪雨は困りますが、猛暑に見舞われ出すと、穏やかな雨を懐かしく想います。
思えば元号が“令和”になってから、まだ1年ちょっとしか経っていません。
今日は、いきなり“平成”ラストの一日に話が戻るのですが…この日、皆様は何か特別な過ごし方をなさっていたでしょうか。
以前「発心の剣」というタイトルで、私が“佐賀出身”であると、一瞬で見抜かれた話を投稿しました。今回は、私が佐賀藩士(?)として、活動し始める契機になった日のお話です。
――“平成”最後の日、早朝。佐賀市内には霧のような優しい雨が降っていた。
私が佐賀に帰ってきたのは、祖父の墓参りをするためだった。
ごく幼少の頃に祖父とは死別した。
それゆえ私は、はっきりと祖父の姿を覚えているわけではない。
しかし、受け継いだ…あるいは受け継いでしまったものは確かにあるらしい。
――しかし、先んじて墓参りの際は、滝のような雨に見舞われた。
「わざわざ孫が墓参りにきたので、感激の涙雨ではないか…」
…などと他愛のない会話をしながら、慌ただしい墓参となったのである。
こうして主たる用事が終わり、佐賀での滞在の最終日。
早朝に目が覚めてしまった。特に為すべきこともないので、まだ人通りもほとんどない県庁通りを歩いた。
――そのまま南下し、佐賀城公園に向かったのである。
雨はポツポツと降り続いていた。
ただ、お堀端を歩く。どの場所も丁寧に掃除が行き届いている様子だ。
このお城が、いかに周りの市民から愛されているかが伝わってくる。本丸歴史館が開くまでには、まだ随分と時間があった。
――涼しい雨を傘で受けながら、おそらくは贅沢な時間を過ごした。
「やはり、ここは私にとっては“特別な場所”なのだ…」
そう感じずにはいられなかった。
時計の針が進むのも忘れたかのような時間を過ごした。
あと15時間ほどが経てば“元号”も変わるのだ…それが、より一層の特別感を醸し出していた。
――ほどなく本丸歴史館が開く。
佐賀藩についての知識が得たくて、設置されているモニターの前に座る。
「幕末期、日本の近代化の先駆けとなった肥前佐賀藩…」
概ね、このような解説だっただろうか。
その前年の大河ドラマが「西郷どん」だったので、少なくとも“佐賀七賢人”のうち3人は登場した。その辺りの情報は、少し調べていた。
――しかし、モニターの音声は、予想外の人物の解説を始めた。
「財政、教育を担当した藩の請役(ナンバー2)で、須古領主の鍋島安房…」
私は完全に隙を突かれた。まったくノーマークだった人物の名が出てくる。
しかも財政再建と教育改革を成し遂げた、殿・鍋島直正の“右腕”のような補佐役とは…幕末の佐賀藩において、極めて重要なところである。
その衝撃はハッキリと覚えているが、その後、資料館内で何を調べたかの記憶は曖昧である。ただ「幕末佐賀藩の活躍は、もっと広く知られるべきだ!」という気持ちは確信に変わった。
――全国が“新しい時代へのカウントダウン”で浮き立っていた、その日。私は佐賀を発った。
こうして今度は佐賀出身者であるだけでなく、佐賀藩士(?)としての気付きを得てしまった私。大都市圏に戻っての活動が始まった。
まず“令和”に元号が変わった次の日から、本棚の奥にあった古い日本史の教科書を引っ張り出した。そして、おもむろに佐賀藩の年表と見比べたのである。
…クールダウンを意識してみましたが、やはり佐賀藩の話に言及すると多少は熱くなるようです…しばらくの間、忙しくなりそうなのですが、休み休みになっても、何とか続けていきたいと思います。
2020年08月29日
「異郷の剣」
こんばんは。
来週くらいまで第13話「通商条約」が続きそうなのですが、週末に入ったので、一息入れます。
なかなか故郷に帰ることが叶わない、ある佐賀藩士(?)のお話。これを「望郷の剣」シリーズと称しています。まったく歴史に関わらない、現代の小さな日常の話を“本編”のトーンのまま描きます。
今回は、同じ肥前国でありつつも、佐賀ではない…あえて“異郷”と表現した、長崎への複雑な想い(!)です。
――果たして、お1人でも覚えておられる方がいるだろうか。
私は「望郷の剣2」という投稿で、幾袋かの佐賀銘菓・“丸ぼうろ”を購入した。
〔参照:「望郷の剣2」〕
大袈裟に“脱藩”と形容しているが、私は容易に佐賀へと帰ることができない。そんな私に届けとばかり、眼前に“丸ぼうろ”が現れた話である。
先だって、その最後の1袋を完食した。
「しばしの別れだ。また相見(あいまみ)える、その日まで…」
――こうして、再び“丸ぼうろ”の無い日々を送る私。
断じて「ネットショッピングで買ったら?」などと指摘してはならない。
これは「望郷の剣」シリーズの“お約束”のようなものである。
そんな、ある日。
都市圏で活動を続ける私に、西国からの支援が届く。

――同じ“肥前国”ではあるが、その荷物の差出は長崎からだった。
長崎に住む親族が、送ってきた品。
それは、長崎の某有名カステラ会社の詰め合わせである。
「…これは期待して良いのでは。」
佐賀藩の貿易部門が、品物を検品を行うような心持ちで箱を開封した。
2箱に仕分けられた品の陣容は、以下である。
その1つは、餡をふっくらの生地で包む和風菓子“三笠山”
もう1つは、カステラを生地で巻いた洋風菓子“カステラ巻”
――長崎から来た菓子には“佐賀の品”をも超える要素がある。
それは、甘味の強さである。
「この菓子…“さがんもん”より、かなり甘い!」
昔から“砂糖”と言えば、長崎である。流石(さすが)はシュガーロードと称される“長崎街道”の起点。
“甘さ”で余所に後れをとることは、おそらくは長崎の誇りが許さない。
「これが、長崎にとっての“正義”…」
――砂糖が足らないことは「長崎の遠か…」と例えると聞く。
「佐賀を深く描くには、もっと広く長崎を知らねば…」
江戸時代、長崎は幕府直轄の港だった。また、現在の長崎県にあたる地域には、佐賀藩の領地もあった。
そして大村藩、平戸藩など…“西洋に近い”長崎にある各藩は、影日向に“幕末”に関わってきたのだ。
「長崎には、いずれ向き合わねばなるまい。」
こうして長崎の甘味は、私の決意を新たにするのだった。
来週くらいまで第13話「通商条約」が続きそうなのですが、週末に入ったので、一息入れます。
なかなか故郷に帰ることが叶わない、ある佐賀藩士(?)のお話。これを「望郷の剣」シリーズと称しています。まったく歴史に関わらない、現代の小さな日常の話を“本編”のトーンのまま描きます。
今回は、同じ肥前国でありつつも、佐賀ではない…あえて“異郷”と表現した、長崎への複雑な想い(!)です。
――果たして、お1人でも覚えておられる方がいるだろうか。
私は「望郷の剣2」という投稿で、幾袋かの佐賀銘菓・“丸ぼうろ”を購入した。
〔参照:
大袈裟に“脱藩”と形容しているが、私は容易に佐賀へと帰ることができない。そんな私に届けとばかり、眼前に“丸ぼうろ”が現れた話である。
先だって、その最後の1袋を完食した。
「しばしの別れだ。また相見(あいまみ)える、その日まで…」
――こうして、再び“丸ぼうろ”の無い日々を送る私。
断じて「ネットショッピングで買ったら?」などと指摘してはならない。
これは「望郷の剣」シリーズの“お約束”のようなものである。
そんな、ある日。
都市圏で活動を続ける私に、西国からの支援が届く。
――同じ“肥前国”ではあるが、その荷物の差出は長崎からだった。
長崎に住む親族が、送ってきた品。
それは、長崎の某有名カステラ会社の詰め合わせである。
「…これは期待して良いのでは。」
佐賀藩の貿易部門が、品物を検品を行うような心持ちで箱を開封した。
2箱に仕分けられた品の陣容は、以下である。
その1つは、餡をふっくらの生地で包む和風菓子“三笠山”
もう1つは、カステラを生地で巻いた洋風菓子“カステラ巻”
――長崎から来た菓子には“佐賀の品”をも超える要素がある。
それは、甘味の強さである。
「この菓子…“さがんもん”より、かなり甘い!」
昔から“砂糖”と言えば、長崎である。流石(さすが)はシュガーロードと称される“長崎街道”の起点。
“甘さ”で余所に後れをとることは、おそらくは長崎の誇りが許さない。
「これが、長崎にとっての“正義”…」
――砂糖が足らないことは「長崎の遠か…」と例えると聞く。
「佐賀を深く描くには、もっと広く長崎を知らねば…」
江戸時代、長崎は幕府直轄の港だった。また、現在の長崎県にあたる地域には、佐賀藩の領地もあった。
そして大村藩、平戸藩など…“西洋に近い”長崎にある各藩は、影日向に“幕末”に関わってきたのだ。
「長崎には、いずれ向き合わねばなるまい。」
こうして長崎の甘味は、私の決意を新たにするのだった。
2020年09月18日
「醒覚の剣」(秘窯)
こんばんは。
各話終了後に息抜きとして、お送りしています「望郷の剣」シリーズです。
現代の何気ない日常の風景を、なるべく幕末っぽく描きます。
――今回の舞台になるのは、佐賀県の伊万里。
大都市圏から容易に帰郷することができない…ある佐賀藩士(?)。たとえ一時の帰藩が叶っても、動ける時間は限られます。
現地取材は思うに任せず、まずは写真素材の調達が急務となりました。そして、叔父上に助太刀(すけだち)を頼む仕儀となったのです。
――“電話”が鳴る。いきなり雰囲気を壊すが、これは現代なので、やむを得ない。
日本の情報通信は、電信の石丸安世や、電話の石井忠亮らの努力で近代に進んだのだ。言うまでもなく、2人とも佐賀藩士である。
…ひとまず“電話”を取る。
「叔父上、いかがなさいました。」
「今、時間はよかね?」

――“幕末風”の設定が崩れ気味だが、叔父上は飄々としたものだ。
「いや~すごかよ!」
「何やら、良き物を目にしたのですか。」
叔父上は遥か西方の郷里・佐賀に居るが、その高揚ぶりは伝わってくる。これが、文明の利器“電話”の力である。
「叔父上、たしか…本日は、伊万里に。」
「そうたい。奥まで進んだことがなかったけん。にゃ~行ってみたら、すごかった。」
――叔父上は熱っぽく、伊万里の“深奥”について語る。
今までは“表面”しか見て来なかったことに気付いたのである。
「“青”がすごか!!」
「鍋島焼の青…、それも聞いたことがありますね。」
有名な鍋島青磁の自然な青色だが、本場・伊万里で見ると感動が違うようだ。

――伊万里は佐賀藩が誇る、至高の贈答品・鍋島焼が生産される場所。
“秘窯”と称されるのは技法が“門外不出の奥義”であることも示すのであろう。
歩を進めるごとに、眼前に現れる“非日常”の景色は、叔父上を魅了したらしい。
「2時間も歩いたとよ。」
…叔父上の言葉に想う。
「やはり佐賀の魅力は、求めねば知り得ないのだ…」と。
そして叔父上は、佐賀の“秘めた力”の1つを見つけたようだ。
――かつての佐賀藩士たちも、東北や蝦夷地(北海道)を歩き回った。
知らない土地を見て、新たな知識を得る。これは遠方に限ったことではない。
私の我儘(わがまま)は思わぬ方向に作用したのである。
「次の依頼があれば、待っとるばい。」
こうして叔父上は、醒覚(せいかく)を得たようだ。平たく言えば、目覚めたということである。
…これも1つの旅の始まりであるのかもしれない。
各話終了後に息抜きとして、お送りしています「望郷の剣」シリーズです。
現代の何気ない日常の風景を、なるべく幕末っぽく描きます。
――今回の舞台になるのは、佐賀県の伊万里。
大都市圏から容易に帰郷することができない…ある佐賀藩士(?)。たとえ一時の帰藩が叶っても、動ける時間は限られます。
現地取材は思うに任せず、まずは写真素材の調達が急務となりました。そして、叔父上に助太刀(すけだち)を頼む仕儀となったのです。
――“電話”が鳴る。いきなり雰囲気を壊すが、これは現代なので、やむを得ない。
日本の情報通信は、電信の石丸安世や、電話の石井忠亮らの努力で近代に進んだのだ。言うまでもなく、2人とも佐賀藩士である。
…ひとまず“電話”を取る。
「叔父上、いかがなさいました。」
「今、時間はよかね?」
――“幕末風”の設定が崩れ気味だが、叔父上は飄々としたものだ。
「いや~すごかよ!」
「何やら、良き物を目にしたのですか。」
叔父上は遥か西方の郷里・佐賀に居るが、その高揚ぶりは伝わってくる。これが、文明の利器“電話”の力である。
「叔父上、たしか…本日は、伊万里に。」
「そうたい。奥まで進んだことがなかったけん。にゃ~行ってみたら、すごかった。」
――叔父上は熱っぽく、伊万里の“深奥”について語る。
今までは“表面”しか見て来なかったことに気付いたのである。
「“青”がすごか!!」
「鍋島焼の青…、それも聞いたことがありますね。」
有名な鍋島青磁の自然な青色だが、本場・伊万里で見ると感動が違うようだ。
――伊万里は佐賀藩が誇る、至高の贈答品・鍋島焼が生産される場所。
“秘窯”と称されるのは技法が“門外不出の奥義”であることも示すのであろう。
歩を進めるごとに、眼前に現れる“非日常”の景色は、叔父上を魅了したらしい。
「2時間も歩いたとよ。」
…叔父上の言葉に想う。
「やはり佐賀の魅力は、求めねば知り得ないのだ…」と。
そして叔父上は、佐賀の“秘めた力”の1つを見つけたようだ。
――かつての佐賀藩士たちも、東北や蝦夷地(北海道)を歩き回った。
知らない土地を見て、新たな知識を得る。これは遠方に限ったことではない。
私の我儘(わがまま)は思わぬ方向に作用したのである。
「次の依頼があれば、待っとるばい。」
こうして叔父上は、醒覚(せいかく)を得たようだ。平たく言えば、目覚めたということである。
…これも1つの旅の始まりであるのかもしれない。
タグ :伊万里
2020年10月24日
「醒覚の剣」(満干)
こんばんは。
今週末は「秋の佐賀城公園イベント」が開催されていますね。
〔参照:「“さが維新まつり”について」〕
私も現地で「佐賀さいこう!」と唱和したいのですが、そこには高い壁が生じています。なかなか帰郷できない佐賀藩士(?)を描く「望郷の剣」シリーズです。
…念のためご説明します。“本編”から離れて、ありふれた現代の日常を幕末っぽく表現する“息抜き”の投稿です。
――今年、新型コロナの感染症の影響は、随所に現れる。
これは、私の都市圏での“生業”とも無関係ではなかった。
帰郷の自粛のみならず、増えた仕事が追い打ちとなった。遠い郷里・佐賀がますます遠ざかる日々。私が現地取材に出向くにも、困難な状況が続く。
そこで手を差し伸べたのが、叔父上である。
「写真?良かったら撮るよ。どうせヒマやけん。」
…実際は叔父上も、わりと忙しい。しかし、私はその言葉に甘えると決めた。

――そして、ある日。叔父上からの荷物が届いた。
私は「写真情報もその中に入れた」と聞いていた。叔父上は、先日の伊万里市の大川内山に続き、今度は鹿島市・太良町の有明海沿いを歩んだ。
〔参照:「醒覚の剣」(秘窯)〕
結構な労力である。もし、祖母が存命であれば、きっと「ご苦労さんだにゃあ」と評したであろう。荷物の中には、叔父上からの贈り物も詰められていた。
1つは“クレメンティン”まんじゅう。“クレメンティン”は希少な柑橘類で、太良町の特産として知られる。
――江戸期の長崎では、目的品の空きスペースに“脇荷”と呼ばれる品を積んで貿易したと聞く。
市場での“希少価値”がある原料。何やら長崎貿易のロマンを感じる響きだ。しかし、叔父上からの贈り物は、太良町の特産だけではなかった。
「これは“丸ぼうろ”ではないですか!しかも、相当に大きい…」
「随分、押し込んだけん。つぶれとらんね?」
「いえ、完全な姿の“丸ぼうろ”が見えます。」
「それは、良かったばい。」
電話口で礼を言う。叔父上は、私の“丸ぼうろ”への想いを覚えていたらしい。
〔参照:「望郷の剣2」〕

――有明海では、満ち引きで最大約6メートルの潮位の差が生じる。
日本一の“干満差”という説明が付くことが多い。
干満の差は、そこに住まう人々に海苔やコハダといった水産資源という恵みも、海水が陸地に逆流する災いも与えてきたことだろう。
――今日も有明の海は、潮の満ち引きを繰り返す。
きっと人生は良い時ばかりでも、悪い時ばかりでもない。
「与えられた状況をどう活かすかは、自分次第なのだ。」
有明沿海の人々は、ずっとそのように生きてきたに違いない。
「そして…凹んでも、また膨らめば良い。」
叔父上の送ってきた積荷に有明の風を想う。凹んでも膨らむ“丸ぼうろ”には、“不屈”の精神を見出すのであった。
今週末は「秋の佐賀城公園イベント」が開催されていますね。
〔参照:
私も現地で「佐賀さいこう!」と唱和したいのですが、そこには高い壁が生じています。なかなか帰郷できない佐賀藩士(?)を描く「望郷の剣」シリーズです。
…念のためご説明します。“本編”から離れて、ありふれた現代の日常を幕末っぽく表現する“息抜き”の投稿です。
――今年、新型コロナの感染症の影響は、随所に現れる。
これは、私の都市圏での“生業”とも無関係ではなかった。
帰郷の自粛のみならず、増えた仕事が追い打ちとなった。遠い郷里・佐賀がますます遠ざかる日々。私が現地取材に出向くにも、困難な状況が続く。
そこで手を差し伸べたのが、叔父上である。
「写真?良かったら撮るよ。どうせヒマやけん。」
…実際は叔父上も、わりと忙しい。しかし、私はその言葉に甘えると決めた。
――そして、ある日。叔父上からの荷物が届いた。
私は「写真情報もその中に入れた」と聞いていた。叔父上は、先日の伊万里市の大川内山に続き、今度は鹿島市・太良町の有明海沿いを歩んだ。
〔参照:
結構な労力である。もし、祖母が存命であれば、きっと「ご苦労さんだにゃあ」と評したであろう。荷物の中には、叔父上からの贈り物も詰められていた。
1つは“クレメンティン”まんじゅう。“クレメンティン”は希少な柑橘類で、太良町の特産として知られる。
――江戸期の長崎では、目的品の空きスペースに“脇荷”と呼ばれる品を積んで貿易したと聞く。
市場での“希少価値”がある原料。何やら長崎貿易のロマンを感じる響きだ。しかし、叔父上からの贈り物は、太良町の特産だけではなかった。
「これは“丸ぼうろ”ではないですか!しかも、相当に大きい…」
「随分、押し込んだけん。つぶれとらんね?」
「いえ、完全な姿の“丸ぼうろ”が見えます。」
「それは、良かったばい。」
電話口で礼を言う。叔父上は、私の“丸ぼうろ”への想いを覚えていたらしい。
〔参照:
――有明海では、満ち引きで最大約6メートルの潮位の差が生じる。
日本一の“干満差”という説明が付くことが多い。
干満の差は、そこに住まう人々に海苔やコハダといった水産資源という恵みも、海水が陸地に逆流する災いも与えてきたことだろう。
――今日も有明の海は、潮の満ち引きを繰り返す。
きっと人生は良い時ばかりでも、悪い時ばかりでもない。
「与えられた状況をどう活かすかは、自分次第なのだ。」
有明沿海の人々は、ずっとそのように生きてきたに違いない。
「そして…凹んでも、また膨らめば良い。」
叔父上の送ってきた積荷に有明の風を想う。凹んでも膨らむ“丸ぼうろ”には、“不屈”の精神を見出すのであった。
2020年11月20日
「醒覚の剣」(都風)
こんばんは。
概ね1年前。私は限られた時間で駆け回り、郷里・佐賀の取材に猛進しました。ある意味、奇跡的な時間でしたが、そう長くは続きませんでした。
いまや、簡単に佐賀に帰藩できる状況ではありません。
「しまった。あの場所には立ち寄るべきだった!」…と、後悔は、頭を巡ります。
――しかし、私には“切り札”があった。
私より“佐賀藩士”としての純度が高く、地元・佐賀に住む協力者
…平たく言えば、叔父上である。
「私には、小城に関する知識が、ほとんどありません。」
遠き故郷とつながる、電話口。
叔父上は、私のこの“つぶやき”を拾った。
「あ、小城ね。行っても良かよ。」
――そして、あっさりと依頼を聞き入れる。
小城の別名は「佐賀の小京都」とも聞く。
どの辺りが“京都”なのか、それにも興味があった。
「あぁ小城ね。行ってきたとよ。」
しばらく後、電話口の叔父上が語る。
こちらが知らぬ間に、すでに叔父上は小城まで足を運んでいた。

――「法事とかで、わりと忙しかったのでは?」という疑問はさておき…
この場合、ご厚意には甘えておくのが、私の流儀である。
「…して、叔父上。小城はいかがでしたか。」
「屋敷跡の庭園が良かよ。」
手入れが行き届いた庭とは…たしかに“小京都”の趣きだ。
「他には…やはり、小城羊羹(ようかん)ですか。」
「羊羹も買ったばってん、面白かものを見つけたよ。」
――私からの頼みではなく、叔父上の感覚で掴んだ物。
「何か、小城に“新名物”でもあったのですか?」
「珍しかお菓子があったよ。“シベリア”とか言いよっと。」
…“シベリア”。それは、聞き覚えのある名だった。
「そのお菓子。以前、大河ドラマに出てきました!」
大河ドラマ「いだてん」。陸上競技を描いた回に“シベリア”が登場する。女子体育教育の先駆者・二階堂トクヨ(演:寺島しのぶ)が教え子に勧めていた。

――この“シベリア”というお菓子。大正時代には各地に存在したという。
叔父上は無自覚のうちに、私のテーマに合った物を選んでいたのだ。
ふんわりとしたカステラで、ヒンヤリとした食感の羊羹を挟み込む。一説には、この羊羹がシベリアの永久凍土をイメージさせるらしい。
「上品な甘さやけん。食べやすかよ。」
こうして、叔父上も絶賛する“シベリア”が、私の手元にも届いた。
――そして昭和初期。子供が食べたいお菓子№1の座だったとも聞く。
私も丁寧に“シベリア”を開封し、一切れを口元に運ぶ。
「…これは、何と優雅な味わいか!」
軽やかに溶けゆくカステラの風味と、溶け残る小城羊羹の余韻。
この儚(はかな)さと、それでいて強い本物の存在感。
私に小城の実力の一端が示される。佐賀の“小京都”と呼ばれるには、それだけ秘めた力があるのだろう。

――幕末期。小城にも京都と同じ“風”が吹いた。
日本中で湧き立つ“尊王攘夷”の思想。今は羊羹の聖地・小城にも広がった。
その地には佐賀藩の支藩の1つ、小城藩があった。幕末期、小城支藩の動きは、いろいろと不可解なのだ。
ある夜、忽然と姿を消して京都に現れた、小城の庄屋の話。
そして佐賀七賢人の1人・江藤新平も、この地と深く関わる。
「何とか小城を、本編に織り込まねば…」
名残り惜しく“シベリア”と別れのひとかけらを口にした私。決意を新たにした。
概ね1年前。私は限られた時間で駆け回り、郷里・佐賀の取材に猛進しました。ある意味、奇跡的な時間でしたが、そう長くは続きませんでした。
いまや、簡単に佐賀に帰藩できる状況ではありません。
「しまった。あの場所には立ち寄るべきだった!」…と、後悔は、頭を巡ります。
――しかし、私には“切り札”があった。
私より“佐賀藩士”としての純度が高く、地元・佐賀に住む協力者
…平たく言えば、叔父上である。
「私には、小城に関する知識が、ほとんどありません。」
遠き故郷とつながる、電話口。
叔父上は、私のこの“つぶやき”を拾った。
「あ、小城ね。行っても良かよ。」
――そして、あっさりと依頼を聞き入れる。
小城の別名は「佐賀の小京都」とも聞く。
どの辺りが“京都”なのか、それにも興味があった。
「あぁ小城ね。行ってきたとよ。」
しばらく後、電話口の叔父上が語る。
こちらが知らぬ間に、すでに叔父上は小城まで足を運んでいた。
――「法事とかで、わりと忙しかったのでは?」という疑問はさておき…
この場合、ご厚意には甘えておくのが、私の流儀である。
「…して、叔父上。小城はいかがでしたか。」
「屋敷跡の庭園が良かよ。」
手入れが行き届いた庭とは…たしかに“小京都”の趣きだ。
「他には…やはり、小城羊羹(ようかん)ですか。」
「羊羹も買ったばってん、面白かものを見つけたよ。」
――私からの頼みではなく、叔父上の感覚で掴んだ物。
「何か、小城に“新名物”でもあったのですか?」
「珍しかお菓子があったよ。“シベリア”とか言いよっと。」
…“シベリア”。それは、聞き覚えのある名だった。
「そのお菓子。以前、大河ドラマに出てきました!」
大河ドラマ「いだてん」。陸上競技を描いた回に“シベリア”が登場する。女子体育教育の先駆者・二階堂トクヨ(演:寺島しのぶ)が教え子に勧めていた。
――この“シベリア”というお菓子。大正時代には各地に存在したという。
叔父上は無自覚のうちに、私のテーマに合った物を選んでいたのだ。
ふんわりとしたカステラで、ヒンヤリとした食感の羊羹を挟み込む。一説には、この羊羹がシベリアの永久凍土をイメージさせるらしい。
「上品な甘さやけん。食べやすかよ。」
こうして、叔父上も絶賛する“シベリア”が、私の手元にも届いた。
――そして昭和初期。子供が食べたいお菓子№1の座だったとも聞く。
私も丁寧に“シベリア”を開封し、一切れを口元に運ぶ。
「…これは、何と優雅な味わいか!」
軽やかに溶けゆくカステラの風味と、溶け残る小城羊羹の余韻。
この儚(はかな)さと、それでいて強い本物の存在感。
私に小城の実力の一端が示される。佐賀の“小京都”と呼ばれるには、それだけ秘めた力があるのだろう。
――幕末期。小城にも京都と同じ“風”が吹いた。
日本中で湧き立つ“尊王攘夷”の思想。今は羊羹の聖地・小城にも広がった。
その地には佐賀藩の支藩の1つ、小城藩があった。幕末期、小城支藩の動きは、いろいろと不可解なのだ。
ある夜、忽然と姿を消して京都に現れた、小城の庄屋の話。
そして佐賀七賢人の1人・江藤新平も、この地と深く関わる。
「何とか小城を、本編に織り込まねば…」
名残り惜しく“シベリア”と別れのひとかけらを口にした私。決意を新たにした。
2021年01月13日
「醒覚の剣」(古城)
こんばんは。
昨夜、江藤新平が特集された“知恵泉”をご覧になった方。感想はいかがだったでしょうか。
…おそらくクールダウンが必要なので、別企画で投稿します。昨夜の番組を見て、いろいろと熱くなっている私の頭を過ぎったのは、叔父上の言葉でした。
――私が、佐賀の歴史を追い始めてから…
全国ネットで、佐賀の良さが語られる機会が少ないことを実感する。
今回も歴史の話だが、私がいつも熱くなっている幕末の話ではない。この年末には、戦国武将の“総選挙”というテレビ番組があった。
そこで出演タレントが“トップ10”に入る武将の予想をするコーナーがあった。
――“龍造寺隆信”。この名を挙げた方がいた。
爆笑問題の田中裕二さんだ。龍造寺の家来だったご先祖がいるという。
“龍造寺”は言うまでもなく、佐賀の戦国大名である。のちの佐賀の殿様・鍋島家の主君だったことも幾度か語っている。
須古城(白石町)を拠点に、九州北部をほぼ制圧した時期があったはずだ。

――「おおっ!何やら佐賀が目立った!」
テレビでのやり取りに、私は目を見開く。しかし次の瞬間に変転が起きる。
「龍造寺…?無い、無い…!」
よく耳にする声だ。時代劇の名優・高橋英樹さんである。
――「高橋氏!それは、わかっている!わかっているのだ…」
ランキングの上位は「大河ドラマ」常連の有名武将で占められるだろう。たしかに“龍造寺隆信”が登場した「大河ドラマ」は…無いのかもしれない。
でも、あえて、わがままを言いたい。
もし、高橋氏が「龍造寺も、途中までは良かったんですけどね~」とか言ってくれたら「さすがは歴史通!」と感激したことだろう。
この話をバッサリ切る方向に“桃太郎侍”の腕前は発揮しないでほしかった…
――私は、この顛末(てんまつ)を叔父上に語った。
ここ1年帰れなかった遠い郷里への電話。
叔父上の反応は、こうだった。
「あぁ龍造寺隆信、名前が出とったね。」
「…それにしても扱われ方があんまりです!」
私は、まだ釈然としていない。
「まずは名前だけでも、出られて良しとせんば!」
――まいど飄々(ひょうひょう)とした、叔父上。
その口調は、きわめて明るかった。
「…まったく、叔父上には敵(かな)いませぬな。」
“柳の枝に雪折れなし”という言葉がある。最近、降雪のあった佐賀。
叔父上の言葉には、まったく力みがなかった。
私は、まるで力まかせに木剣を振るように語っていたのか。
それが、見事に空振りしたような感覚を味わったのである。
昨夜、江藤新平が特集された“知恵泉”をご覧になった方。感想はいかがだったでしょうか。
…おそらくクールダウンが必要なので、別企画で投稿します。昨夜の番組を見て、いろいろと熱くなっている私の頭を過ぎったのは、叔父上の言葉でした。
――私が、佐賀の歴史を追い始めてから…
全国ネットで、佐賀の良さが語られる機会が少ないことを実感する。
今回も歴史の話だが、私がいつも熱くなっている幕末の話ではない。この年末には、戦国武将の“総選挙”というテレビ番組があった。
そこで出演タレントが“トップ10”に入る武将の予想をするコーナーがあった。
――“龍造寺隆信”。この名を挙げた方がいた。
爆笑問題の田中裕二さんだ。龍造寺の家来だったご先祖がいるという。
“龍造寺”は言うまでもなく、佐賀の戦国大名である。のちの佐賀の殿様・鍋島家の主君だったことも幾度か語っている。
須古城(白石町)を拠点に、九州北部をほぼ制圧した時期があったはずだ。
――「おおっ!何やら佐賀が目立った!」
テレビでのやり取りに、私は目を見開く。しかし次の瞬間に変転が起きる。
「龍造寺…?無い、無い…!」
よく耳にする声だ。時代劇の名優・高橋英樹さんである。
――「高橋氏!それは、わかっている!わかっているのだ…」
ランキングの上位は「大河ドラマ」常連の有名武将で占められるだろう。たしかに“龍造寺隆信”が登場した「大河ドラマ」は…無いのかもしれない。
でも、あえて、わがままを言いたい。
もし、高橋氏が「龍造寺も、途中までは良かったんですけどね~」とか言ってくれたら「さすがは歴史通!」と感激したことだろう。
この話をバッサリ切る方向に“桃太郎侍”の腕前は発揮しないでほしかった…
――私は、この顛末(てんまつ)を叔父上に語った。
ここ1年帰れなかった遠い郷里への電話。
叔父上の反応は、こうだった。
「あぁ龍造寺隆信、名前が出とったね。」
「…それにしても扱われ方があんまりです!」
私は、まだ釈然としていない。
「まずは名前だけでも、出られて良しとせんば!」
――まいど飄々(ひょうひょう)とした、叔父上。
その口調は、きわめて明るかった。
「…まったく、叔父上には敵(かな)いませぬな。」
“柳の枝に雪折れなし”という言葉がある。最近、降雪のあった佐賀。
叔父上の言葉には、まったく力みがなかった。
私は、まるで力まかせに木剣を振るように語っていたのか。
それが、見事に空振りしたような感覚を味わったのである。
2021年01月24日
「醒覚の剣」(聖廟)
こんにちは。
最近では県内の各市町でも新型コロナの感染者数が日々報じられています。それなりに遠くから、郷里を見ている私。
自分の周辺地域では、淡々と数値が増え続け、感覚が麻痺(まひ)しがち。一方で、佐賀での感染状況には敏感です。
――最近、叔父上との電話で。
「佐賀の写真が必要なら、また動くとよ。」
“現地取材の要望には、即応する”と言う。
叔父上からのありがたい申し出である。
…ある、ありますとも!佐賀で確保したい素材は。
――しかし、私はこう返事をする。
「佐賀でも感染が広がっている様子。まず、叔父上の身の安全が第一です。」
…これも、偽らざる気持ちである。叔父上に何かあっては、元も子もない。
いまや大都市圏では“緊急事態宣言”が出ている。佐賀でも、油断は禁物だ。
「私には、今までに頂いた素材もあります。」
「そうね。じゃあ、またご要望があれば。」
――今ある材料で、何とかする…
これも、佐賀藩士らしくはないか。不利な状況を弾き返す実力を磨くのだ。
幕末期。技術情報が不足でも、鉄製大砲や蒸気機関を作り上げた。
明治期。たとえ官軍入りが遅くても、新政府の中枢で活躍できる。
…この底力を持つのが、佐賀だと理解している。

――昨年。私は大都市圏からの移動を自粛した。
当時、佐賀では新型コロナの感染情報を聞く事は少なかった。帰れない私に対して、叔父上は比較的自由に動けたのである。
私が依頼した中で、叔父上が初期に着手したのが、多久への取材だった。
多久市は「佐賀県のほぼ中央にあり、福岡にも長崎にも1時間で行ける」…と、密かに良い位置にある。
――ある夏の日。“多久”に降り立った、叔父上。
若くはない甥が「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と動き始めた。普通の叔父さんなら「ムダだから止めておけ!」と諭しても、手伝おうとはするまい。
しかし叔父上は、“多久聖廟”の前でカメラを構え、“聖人”や“領主”の石像を見つければ、写真を撮ることにも余念がない。
「にゃ~、天気がいま一つやったばい!」
むしろ使える絵を撮ろうと、いろいろ画策するのである。
――聖学が華開き、文教の風薫る郷・多久。
叔父上の現地入りから、およそ半年。多久で撮影した写真は、あたかもタイムカプセルのように「聖学の華、文教の風」を、現在の私に届けた。
“論語”の郷として、特徴を持つ多久市。全国ネットのテレビでも「多久の若者は、誰でも論語を暗唱している!」と“珍百景”扱いで見かけることがある。
今回、“多久”について考えた私は、本質はもっと深い所にあると感じる。“骨太の学び”をした者は、いざという時の“冷静さ”に勝る…そんな気がするのだ。
最近では県内の各市町でも新型コロナの感染者数が日々報じられています。それなりに遠くから、郷里を見ている私。
自分の周辺地域では、淡々と数値が増え続け、感覚が麻痺(まひ)しがち。一方で、佐賀での感染状況には敏感です。
――最近、叔父上との電話で。
「佐賀の写真が必要なら、また動くとよ。」
“現地取材の要望には、即応する”と言う。
叔父上からのありがたい申し出である。
…ある、ありますとも!佐賀で確保したい素材は。
――しかし、私はこう返事をする。
「佐賀でも感染が広がっている様子。まず、叔父上の身の安全が第一です。」
…これも、偽らざる気持ちである。叔父上に何かあっては、元も子もない。
いまや大都市圏では“緊急事態宣言”が出ている。佐賀でも、油断は禁物だ。
「私には、今までに頂いた素材もあります。」
「そうね。じゃあ、またご要望があれば。」
――今ある材料で、何とかする…
これも、佐賀藩士らしくはないか。不利な状況を弾き返す実力を磨くのだ。
幕末期。技術情報が不足でも、鉄製大砲や蒸気機関を作り上げた。
明治期。たとえ官軍入りが遅くても、新政府の中枢で活躍できる。
…この底力を持つのが、佐賀だと理解している。
――昨年。私は大都市圏からの移動を自粛した。
当時、佐賀では新型コロナの感染情報を聞く事は少なかった。帰れない私に対して、叔父上は比較的自由に動けたのである。
私が依頼した中で、叔父上が初期に着手したのが、多久への取材だった。
多久市は「佐賀県のほぼ中央にあり、福岡にも長崎にも1時間で行ける」…と、密かに良い位置にある。
――ある夏の日。“多久”に降り立った、叔父上。
若くはない甥が「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と動き始めた。普通の叔父さんなら「ムダだから止めておけ!」と諭しても、手伝おうとはするまい。
しかし叔父上は、“多久聖廟”の前でカメラを構え、“聖人”や“領主”の石像を見つければ、写真を撮ることにも余念がない。
「にゃ~、天気がいま一つやったばい!」
むしろ使える絵を撮ろうと、いろいろ画策するのである。
――聖学が華開き、文教の風薫る郷・多久。
叔父上の現地入りから、およそ半年。多久で撮影した写真は、あたかもタイムカプセルのように「聖学の華、文教の風」を、現在の私に届けた。
“論語”の郷として、特徴を持つ多久市。全国ネットのテレビでも「多久の若者は、誰でも論語を暗唱している!」と“珍百景”扱いで見かけることがある。
今回、“多久”について考えた私は、本質はもっと深い所にあると感じる。“骨太の学び”をした者は、いざという時の“冷静さ”に勝る…そんな気がするのだ。
2021年02月01日
「望郷の剣4」
こんばんは。
現在、放送中の大河ドラマ「麒麟がくる」も、来週で最終回。
“コロナ禍”での撮影中断など様々な困難があった様子。当初の予定通りには描けなかった?…と見えたところもありました。
もう少し続けてほしかった“麒麟”ですが、最後まで見届けたいと思います。
――次の大河ドラマ「青天を衝け」の番宣(紹介)も放送されています。
まず、渋沢栄一(吉沢亮)が幕臣となり、一橋慶喜(草彅剛)に仕える展開を描く様子。一橋慶喜の実家・水戸藩(茨城)の人物は多数出演するようですね。
「全国都道府県魅力度ランキング」で、2020年に最下位を脱出した茨城県。
一時は「どうせ最下位(47位)…」と自虐的な路線を歩んだ事もあると聞きます。
いまや自身の魅力を見つめ直した茨城県。偶然か必然か、今年の「大河ドラマ」では、強い印象を残しそうです。
〔参照:「あと40日…」〕
――ちなみに同ランキングでは、佐賀は45位。
今のところ「青天を衝け」では、佐賀藩士の出演情報を得ていません。
郷里から離れた場所で「佐賀の大河ドラマ」を想うに至り…最近では、「佐賀の扱われ方」がさらに気になります。今日は、そんな私の日常を描きます。

――商品棚に苦戦をする、佐賀の特産品あれば…
ある日、“丸ぼうろ”をスーバーの特売品を扱う棚で見つけた。値段がいつもより安い。これは“廉価版”のようだ。
そして、佐賀でよく見かける個包装の品ではない。しかも肩書が「佐賀銘菓」ではなく「九州銘菓」となっている。
――製造は、佐賀市内のメーカーと確認。
高額な特産品には手が届かないが、お菓子ぐらいならば存分に手が出せる。
ここで、いつもの言葉を心で唱える。
「佐賀の特産品に売れ残りなどあってはならんのだ!」
…「“本編”と違って、えらくスケールが小さいな」という批判は甘受する。
――しかし、私にはある疑念が残った。
「このメーカーの“腕前”。この程度では無いはず…」
別の店で、同メーカーの“丸ぼうろ”を買い求めた事がある。
とても美味だったため、名残り惜しく1つずつ消費をしていたのを想い出す。
〔参照:「望郷の剣2」〕
「もしや、佐賀から“本気の一品”を送り出せない理由でもあるのか。」
――全国的に「佐賀ブランド」が浸透しているとは言い難い。
“九州”の名のもと、己(佐賀)を潜めて生きる。これも“葉隠”の精神なのか。
「いやいや…、あまり潜んでいると存在感が無くなってしまうぞ!」
まさに声の大きい者が優位な時代。“さがんもん”は声量が大きいとの説もあるが、厚かましさには欠ける印象だ。

――あまり“奥ゆかしい”のは、得策とは言えない。
…かと言って、自慢やハッタリを振りかざすのでは、佐賀の美点を損なう。
「では、どう存在を示すべきか…」
佐賀の人は「腹の底が見えない」と評されるという。それも“慎ましさ”ゆえか。
ならば、幕末期の佐賀のように秘めた実力が、周囲に認知されれば良い。
おそらく必要なのは、ブランドを再構築する地道な努力なのだろう。佐賀県内にも奮闘する人たちがいる。微力ながら私なりの方法で、加勢を試みる。
――そして「大河ドラマ」の空想以外で、私にできる事は…
スーバーの棚から“九州銘菓・丸ぼうろ”が、日々、地道に売れていく。暗躍するのは、私である。もともと好物のうえ日持ちもする。買い貯めても問題は無い。
やはり消費者は、売れている商品に惹かれるようだ。この“誘引”が功を奏したかは定かではない…が、“呼び水”にはなったか。棚の商品は売れてきた。
廉価版であっても、やはり佐賀の“丸ぼうろ”。紅茶にも、牛乳にも合う。たとえ、佐賀の肩書は背負っていない時でも、“丸ぼうろ”は売れ筋で無ければならぬ。
――私が振り回す、「望郷の剣」。
今は、まだ微風のような威力だ。
帰るに帰れない郷里・佐賀にとって、何の力にもなってはいない。
企業ごとに戦略はあるのだろう。しかし、堂々と佐賀ブランドを掲げる事が、勝利への道であってほしい。
まずは消費行動を持って大都市圏でも、佐賀の実力を示す。あまりにも地味な、その道のりも長く険しい…
現在、放送中の大河ドラマ「麒麟がくる」も、来週で最終回。
“コロナ禍”での撮影中断など様々な困難があった様子。当初の予定通りには描けなかった?…と見えたところもありました。
もう少し続けてほしかった“麒麟”ですが、最後まで見届けたいと思います。
――次の大河ドラマ「青天を衝け」の番宣(紹介)も放送されています。
まず、渋沢栄一(吉沢亮)が幕臣となり、一橋慶喜(草彅剛)に仕える展開を描く様子。一橋慶喜の実家・水戸藩(茨城)の人物は多数出演するようですね。
「全国都道府県魅力度ランキング」で、2020年に最下位を脱出した茨城県。
一時は「どうせ最下位(47位)…」と自虐的な路線を歩んだ事もあると聞きます。
いまや自身の魅力を見つめ直した茨城県。偶然か必然か、今年の「大河ドラマ」では、強い印象を残しそうです。
〔参照:
――ちなみに同ランキングでは、佐賀は45位。
今のところ「青天を衝け」では、佐賀藩士の出演情報を得ていません。
郷里から離れた場所で「佐賀の大河ドラマ」を想うに至り…最近では、「佐賀の扱われ方」がさらに気になります。今日は、そんな私の日常を描きます。
――商品棚に苦戦をする、佐賀の特産品あれば…
ある日、“丸ぼうろ”をスーバーの特売品を扱う棚で見つけた。値段がいつもより安い。これは“廉価版”のようだ。
そして、佐賀でよく見かける個包装の品ではない。しかも肩書が「佐賀銘菓」ではなく「九州銘菓」となっている。
――製造は、佐賀市内のメーカーと確認。
高額な特産品には手が届かないが、お菓子ぐらいならば存分に手が出せる。
ここで、いつもの言葉を心で唱える。
「佐賀の特産品に売れ残りなどあってはならんのだ!」
…「“本編”と違って、えらくスケールが小さいな」という批判は甘受する。
――しかし、私にはある疑念が残った。
「このメーカーの“腕前”。この程度では無いはず…」
別の店で、同メーカーの“丸ぼうろ”を買い求めた事がある。
とても美味だったため、名残り惜しく1つずつ消費をしていたのを想い出す。
〔参照:
「もしや、佐賀から“本気の一品”を送り出せない理由でもあるのか。」
――全国的に「佐賀ブランド」が浸透しているとは言い難い。
“九州”の名のもと、己(佐賀)を潜めて生きる。これも“葉隠”の精神なのか。
「いやいや…、あまり潜んでいると存在感が無くなってしまうぞ!」
まさに声の大きい者が優位な時代。“さがんもん”は声量が大きいとの説もあるが、厚かましさには欠ける印象だ。
――あまり“奥ゆかしい”のは、得策とは言えない。
…かと言って、自慢やハッタリを振りかざすのでは、佐賀の美点を損なう。
「では、どう存在を示すべきか…」
佐賀の人は「腹の底が見えない」と評されるという。それも“慎ましさ”ゆえか。
ならば、幕末期の佐賀のように秘めた実力が、周囲に認知されれば良い。
おそらく必要なのは、ブランドを再構築する地道な努力なのだろう。佐賀県内にも奮闘する人たちがいる。微力ながら私なりの方法で、加勢を試みる。
――そして「大河ドラマ」の空想以外で、私にできる事は…
スーバーの棚から“九州銘菓・丸ぼうろ”が、日々、地道に売れていく。暗躍するのは、私である。もともと好物のうえ日持ちもする。買い貯めても問題は無い。
やはり消費者は、売れている商品に惹かれるようだ。この“誘引”が功を奏したかは定かではない…が、“呼び水”にはなったか。棚の商品は売れてきた。
廉価版であっても、やはり佐賀の“丸ぼうろ”。紅茶にも、牛乳にも合う。たとえ、佐賀の肩書は背負っていない時でも、“丸ぼうろ”は売れ筋で無ければならぬ。
――私が振り回す、「望郷の剣」。
今は、まだ微風のような威力だ。
帰るに帰れない郷里・佐賀にとって、何の力にもなってはいない。
企業ごとに戦略はあるのだろう。しかし、堂々と佐賀ブランドを掲げる事が、勝利への道であってほしい。
まずは消費行動を持って大都市圏でも、佐賀の実力を示す。あまりにも地味な、その道のりも長く険しい…
2021年03月08日
「回想の剣」
こんばんは。
最近わりと忙しく、何かと余裕がありません。
「数年前なら、もう少しは動けたのに…」と思うことも増えてきました。
ふと、若き日のことを想い出したので、唐突に語ります。
なお、文末までには佐賀藩の話に持っていきますので、“心配ご無用!”です。
――たしか、私が17歳ぐらいのとき…
遠い昔の話。なぜ急に思い出したのかは、わからない。何の文化行事だったか「演劇鑑賞」をした記憶がある。
観劇を終えると別のクラスだが、時折、話をする同級生が来た。
「おう“SR”じゃないか。さっきの演劇はどうだった?」
意図の読めない質問。私はこう答えた。
「…高校生が観るには、少し子供っぽい内容だったかな。」
――同級生の反応は、意外なものだった。
「…いや、かなり良かったぞ。」
“ほう、好意的な反応だったか。” 私はそう思って、次の言葉を待った。
「若さの持つ、他に代えがたい価値を見事に表現している。」
ロシアだったか…外国の文豪の名まで出したうえで、演劇の内容を讃える。
――「若さの持つ価値…?」そのときの、私の心の声。
私の中で「お前は、一体いくつ(何歳)なんだ?」という疑念が巡った。
それから少し月日は進む。高望みをした私は、受験に失敗した。顧みたくもない時間を経て、私は次の学校へと進んだ。
そこには、先ほどの同級生もいた。私と似たような時間軸で動いていたようだ。
「また、同じ学校になったようだな…」
ある日、この友人が読んだ小説に「書評」をしているのを見る機会があった。
“江藤新平”を題材とした物語。日本の近代司法制度を作った人物とある。

――歴史上の顛末(てんまつ)は、教科書で知っている。
当時、それ以上の興味は湧かなかった。
「佐賀の出身で、明治政府に反乱を起こして負けた人だ…」と。
そのときの私に、友の言に耳を傾ける器量があれば、どうなったであろうか。
…そこで、運命は大なる変化の時を迎えたのかもしれないんである。
(わかる人だけで良いので、大隈重信の演説調だと思ってください。)
岐路に立つ時、過去の選択への後悔もある。未来の選択は、まだ変えられる。きっと、そのために歴史を学んでいる…
――以上のように…、いま私も岐路に立っています。
まず、この春からの展開が全く読めません。しばらくは“本編”の続きを練りつつ、「省エネモード」で投稿を続けようと考えています。
“本編”をあと2話ぐらい進めてから年度末に至りたかったのですが、第15話「江戸動乱」も、かなり重い内容だったので、厳しかったです。
そして、「どこで第1部と第2部が切り替わるか…」も迷っているところですが、「第2部の主役は、ぜひ江藤新平に設定したい!」という思いです。
――ラストは、告知をします。
3月9日(火)午後10時~“NHK Eテレ”「先人たちの底力 知恵泉」再放送。江藤新平の特集ですので、ご覧になっていない方はいかがでしょうか。
…なお、私は視聴後に少々落ち着かず「江藤新平にはフィクションの物語でも、もっと活躍してほしい!」と暴走しています。
〔参照(中盤):「帰らんば、あの世界へ。」〕
最近わりと忙しく、何かと余裕がありません。
「数年前なら、もう少しは動けたのに…」と思うことも増えてきました。
ふと、若き日のことを想い出したので、唐突に語ります。
なお、文末までには佐賀藩の話に持っていきますので、“心配ご無用!”です。
――たしか、私が17歳ぐらいのとき…
遠い昔の話。なぜ急に思い出したのかは、わからない。何の文化行事だったか「演劇鑑賞」をした記憶がある。
観劇を終えると別のクラスだが、時折、話をする同級生が来た。
「おう“SR”じゃないか。さっきの演劇はどうだった?」
意図の読めない質問。私はこう答えた。
「…高校生が観るには、少し子供っぽい内容だったかな。」
――同級生の反応は、意外なものだった。
「…いや、かなり良かったぞ。」
“ほう、好意的な反応だったか。” 私はそう思って、次の言葉を待った。
「若さの持つ、他に代えがたい価値を見事に表現している。」
ロシアだったか…外国の文豪の名まで出したうえで、演劇の内容を讃える。
――「若さの持つ価値…?」そのときの、私の心の声。
私の中で「お前は、一体いくつ(何歳)なんだ?」という疑念が巡った。
それから少し月日は進む。高望みをした私は、受験に失敗した。顧みたくもない時間を経て、私は次の学校へと進んだ。
そこには、先ほどの同級生もいた。私と似たような時間軸で動いていたようだ。
「また、同じ学校になったようだな…」
ある日、この友人が読んだ小説に「書評」をしているのを見る機会があった。
“江藤新平”を題材とした物語。日本の近代司法制度を作った人物とある。
――歴史上の顛末(てんまつ)は、教科書で知っている。
当時、それ以上の興味は湧かなかった。
「佐賀の出身で、明治政府に反乱を起こして負けた人だ…」と。
そのときの私に、友の言に耳を傾ける器量があれば、どうなったであろうか。
…そこで、運命は大なる変化の時を迎えたのかもしれないんである。
(わかる人だけで良いので、大隈重信の演説調だと思ってください。)
岐路に立つ時、過去の選択への後悔もある。未来の選択は、まだ変えられる。きっと、そのために歴史を学んでいる…
――以上のように…、いま私も岐路に立っています。
まず、この春からの展開が全く読めません。しばらくは“本編”の続きを練りつつ、「省エネモード」で投稿を続けようと考えています。
“本編”をあと2話ぐらい進めてから年度末に至りたかったのですが、第15話「江戸動乱」も、かなり重い内容だったので、厳しかったです。
そして、「どこで第1部と第2部が切り替わるか…」も迷っているところですが、「第2部の主役は、ぜひ江藤新平に設定したい!」という思いです。
――ラストは、告知をします。
3月9日(火)午後10時~“NHK Eテレ”「先人たちの底力 知恵泉」再放送。江藤新平の特集ですので、ご覧になっていない方はいかがでしょうか。
…なお、私は視聴後に少々落ち着かず「江藤新平にはフィクションの物語でも、もっと活躍してほしい!」と暴走しています。
〔参照(中盤):
2021年04月17日
「望郷の剣5」
こんばんは。
全国各地で新型コロナの変異株が広がりつつあるようです。私としては、佐賀に“危険”を持ち込むことは何としても避けたく、帰省の自粛を続けています。
実際、ブログの開設以来、一度も“帰藩”できていません。手を変え、品を変えて綴る「望郷の想い」。そんな私にも、佐賀からの“援軍”は来るようです。
最近、“本編”を書けていませんが、ありふれた日常を幕末っぽく(?)描きます。
――ついに、潮目が変わったのか…
私は幕末・明治期に、日本の近代化を先導した佐賀の活躍を追っている。
もう少し若いうちから価値に気づきたかったが、今からでも遅くは無いと信じる。最近、ほんの少しだが「佐賀の扱い」が変わってきたと感じる出来事があった。

――ある大都市圏の、某スーパーで催された“九州物産展”。
今までの流れで言えば…
「“九州の名産”なのに、佐賀の品物だけが無かよ!」とか。
チラシの地図を見ても…
「にゃ~、佐賀んところに色も塗られてなかばい!」とか。
以上のように、様々な悲嘆が私に降りかかっていた。
――しかし、今回は違う。
佐賀牛を先陣に、柑橘が、アスパラが、豆腐が…集結する。本来、当たり前だがチラシの地図、福岡と長崎の間。北部九州の中心に「佐賀」の表示がある。
…ようやく、佐賀県の存在が浮上してきたのだ。
概ね状況を把握した私は、スーパーまで出向くこととした。
――「これは、“会い”に行かねばならぬ」と。
私が、佐賀の物産を応援しているのか。逆に、孤独な戦いを続ける私が、佐賀の品物に激励されているのか。答えは、その両方かもしれない。
「おおっ!“丸ぼうろ”ではないか!?」
陣中には、四百年の伝統を誇る佐賀銘菓も集う。この銘柄を見るのは久しい。
この品はパッケージから、堂々と“佐賀”の存在を示している。
〔参照(後半):「望郷の剣2」〕
以前に同じ店で、佐賀の名を伏せ“九州銘菓”の名のもとに忍ぶ“丸ぼうろ”を見かけたことがあった。それは、どうやら本気を出す前の偵察だったようだ。
〔参照(後半):「望郷の剣4」〕

――さらに“新顔”とも出会った。
佐賀県産大豆(フクユタカ)を100%と潤沢に使用し、武雄市で作られた豆腐。原料の生産地も含めて、生粋の“さがんもん”と言ってよいだろう。
武雄といえば、幕末の佐賀藩でも“精鋭部隊”として知られた強者。
「…よく来てくれた。何とも頼もしい。」
もはや豆腐とも対話している感じになっているが、大目に見てほしい。そのくらい感動しているのだ。
――少しずつだが、着実に「佐賀の時代」は近づいている…
偶然なのかもしれない。明らかに以前とは違う“佐賀の扱い”。そして、佐賀の名を背負う品々は、順調な売れ行きを見せていた。
「これも、“変化の兆し”と見てもよいのか…」
先の見えない世の中。“希望”は細い糸のように頼りないかもしれない。しかし、私は本来あるべき姿への潮流を感じずにはいられなかった。
全国各地で新型コロナの変異株が広がりつつあるようです。私としては、佐賀に“危険”を持ち込むことは何としても避けたく、帰省の自粛を続けています。
実際、ブログの開設以来、一度も“帰藩”できていません。手を変え、品を変えて綴る「望郷の想い」。そんな私にも、佐賀からの“援軍”は来るようです。
最近、“本編”を書けていませんが、ありふれた日常を幕末っぽく(?)描きます。
――ついに、潮目が変わったのか…
私は幕末・明治期に、日本の近代化を先導した佐賀の活躍を追っている。
もう少し若いうちから価値に気づきたかったが、今からでも遅くは無いと信じる。最近、ほんの少しだが「佐賀の扱い」が変わってきたと感じる出来事があった。
――ある大都市圏の、某スーパーで催された“九州物産展”。
今までの流れで言えば…
「“九州の名産”なのに、佐賀の品物だけが無かよ!」とか。
チラシの地図を見ても…
「にゃ~、佐賀んところに色も塗られてなかばい!」とか。
以上のように、様々な悲嘆が私に降りかかっていた。
――しかし、今回は違う。
佐賀牛を先陣に、柑橘が、アスパラが、豆腐が…集結する。本来、当たり前だがチラシの地図、福岡と長崎の間。北部九州の中心に「佐賀」の表示がある。
…ようやく、佐賀県の存在が浮上してきたのだ。
概ね状況を把握した私は、スーパーまで出向くこととした。
――「これは、“会い”に行かねばならぬ」と。
私が、佐賀の物産を応援しているのか。逆に、孤独な戦いを続ける私が、佐賀の品物に激励されているのか。答えは、その両方かもしれない。
「おおっ!“丸ぼうろ”ではないか!?」
陣中には、四百年の伝統を誇る佐賀銘菓も集う。この銘柄を見るのは久しい。
この品はパッケージから、堂々と“佐賀”の存在を示している。
〔参照(後半):
以前に同じ店で、佐賀の名を伏せ“九州銘菓”の名のもとに忍ぶ“丸ぼうろ”を見かけたことがあった。それは、どうやら本気を出す前の偵察だったようだ。
〔参照(後半):
――さらに“新顔”とも出会った。
佐賀県産大豆(フクユタカ)を100%と潤沢に使用し、武雄市で作られた豆腐。原料の生産地も含めて、生粋の“さがんもん”と言ってよいだろう。
武雄といえば、幕末の佐賀藩でも“精鋭部隊”として知られた強者。
「…よく来てくれた。何とも頼もしい。」
もはや豆腐とも対話している感じになっているが、大目に見てほしい。そのくらい感動しているのだ。
――少しずつだが、着実に「佐賀の時代」は近づいている…
偶然なのかもしれない。明らかに以前とは違う“佐賀の扱い”。そして、佐賀の名を背負う品々は、順調な売れ行きを見せていた。
「これも、“変化の兆し”と見てもよいのか…」
先の見えない世の中。“希望”は細い糸のように頼りないかもしれない。しかし、私は本来あるべき姿への潮流を感じずにはいられなかった。
タグ :佐賀
2021年06月19日
「終活の剣」
こんばんは。
最近は、アニメ『ゾンビランドサガ』と大河ドラマ『青天を衝け』の感想ばかり。
一応は“佐賀”と“大河ドラマ”の話を綴ってはいるのですが、目的地と言うべき「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージが全く進んでいません。
その理由は最近わりと仕事が忙しく、そこそこ精神的にもキツい状況にあります。
――私の心を支えるのは、遠き郷里・佐賀の存在。
いわゆる“都会”に住む私がなぜこう考えるに至ったのか。もちろん佐賀が私の故郷であるためなのですが、ある人生の“転機”に思ったことに起因します。
当時は、今以上に仕事ばかりの日々でした。私はそれほど仕事が好きでもなければ、働き者でもありません。本音を言えば、のんびり過ごしたいのです。
――それを許さないのも、また人生。
佐賀が誇る“偉大な先輩”たちには、足元も見えないくらい遠く及ばず、私には大した力は無いようです。
しかし窮地を切り抜けるためには、全力を出す必要があります。身体を傷めても、それなりの無理をして、さらに身体が弱化する…と厳しい循環が続きました。
こんなことを考える時もありました。「このまま自分が倒れて、骨となった場合は、どこに埋めてもらえるかな…」と。

――その時、ふと思った故郷の存在。
朧(おぼろ)げに思い出す佐賀の景色。青々とした麦が揺れて、吹き抜けた風の形までが見えるよう。
「ここ(都会)よりも、向こう(佐賀)に骨は埋めてもらいたいかもな…」
そんな日々の中、トボトボと歩く夜道。ある出会いがありました。
わずかな言葉を発しただけで、私を佐賀の出身と見抜いた、タクシーの運転手は「望郷の念」を持ち続ける“さがんもん”でした。
〔参照:「発心の剣」〕
――「私もいずれ…、佐賀に行きたい。」
ある年に思いもよらぬ好機が訪れ、私は佐賀へと旅立ちます。佐賀城の本丸歴史館で、それまで無関心だった“佐賀の先輩”の偉大さに感激しました。
〔参照(後半):「慈雨の剣」〕
こうして調べを進めるうち、次々に“衝撃の事実”を知っていきます。私の気持ちは“佐賀藩士(?)”に還り、佐賀に出向くことは“帰藩”となりました。

――時間を捻り出し、取材のために佐賀に帰る秋。
「見えない世界遺産」三重津海軍所跡にて、案内役の方と話をした時。私は先の想いを吐露することになります。
〔参照(後半):連続ブログ小説「旅立の剣」(7)時を超える“双眼鏡”〕
貴重な現地取材。一言でも聞き漏らすまいと案内役の方の説明に“全集中”を試みます。出身は佐賀だと語った私に、案内役の方が尋ねました。
「あなたは佐賀に戻って来られないのですか?」
「そう簡単には戻れませんね。あるいは骨になったら還ってきたいものですが…」
「…!?」
――私も、歳は取りましたが…
“終活”には、まだ早い年代と思われます。しかも貫禄に欠ける私は実年齢より若く見えてしまうようです。
…ここで私は「しまった、案内役の方が反応に困る言葉を発した」と気づきます。
とりあえず“問題発言”はさておいて、「佐賀の大河ドラマ」への想いを語り始めました。しかし、先の発言には私の本音も含まれています。
――「いつの日か、佐賀へ還る。」
古の聖人たちも“最期の旅”と言うのでしょうか。亡くなる前に郷里に向かって歩み出す話をよく聞きます。おそらく、それは私のような凡人も持つ想い。
きっと、そう思うだけでも救われているのでしょう。人はもちろん、あるいは動物にだって、安息の“終(つい)の棲家”を求める心はあるように感じられます。
でも、生きているうちに成し得ることがあるはず。故郷のために“一花”咲かせてみたい…そんな気持ちが私を動かしています。
最近は、アニメ『ゾンビランドサガ』と大河ドラマ『青天を衝け』の感想ばかり。
一応は“佐賀”と“大河ドラマ”の話を綴ってはいるのですが、目的地と言うべき「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージが全く進んでいません。
その理由は最近わりと仕事が忙しく、そこそこ精神的にもキツい状況にあります。
――私の心を支えるのは、遠き郷里・佐賀の存在。
いわゆる“都会”に住む私がなぜこう考えるに至ったのか。もちろん佐賀が私の故郷であるためなのですが、ある人生の“転機”に思ったことに起因します。
当時は、今以上に仕事ばかりの日々でした。私はそれほど仕事が好きでもなければ、働き者でもありません。本音を言えば、のんびり過ごしたいのです。
――それを許さないのも、また人生。
佐賀が誇る“偉大な先輩”たちには、足元も見えないくらい遠く及ばず、私には大した力は無いようです。
しかし窮地を切り抜けるためには、全力を出す必要があります。身体を傷めても、それなりの無理をして、さらに身体が弱化する…と厳しい循環が続きました。
こんなことを考える時もありました。「このまま自分が倒れて、骨となった場合は、どこに埋めてもらえるかな…」と。
――その時、ふと思った故郷の存在。
朧(おぼろ)げに思い出す佐賀の景色。青々とした麦が揺れて、吹き抜けた風の形までが見えるよう。
「ここ(都会)よりも、向こう(佐賀)に骨は埋めてもらいたいかもな…」
そんな日々の中、トボトボと歩く夜道。ある出会いがありました。
わずかな言葉を発しただけで、私を佐賀の出身と見抜いた、タクシーの運転手は「望郷の念」を持ち続ける“さがんもん”でした。
〔参照:
――「私もいずれ…、佐賀に行きたい。」
ある年に思いもよらぬ好機が訪れ、私は佐賀へと旅立ちます。佐賀城の本丸歴史館で、それまで無関心だった“佐賀の先輩”の偉大さに感激しました。
〔参照(後半):
こうして調べを進めるうち、次々に“衝撃の事実”を知っていきます。私の気持ちは“佐賀藩士(?)”に還り、佐賀に出向くことは“帰藩”となりました。
――時間を捻り出し、取材のために佐賀に帰る秋。
「見えない世界遺産」三重津海軍所跡にて、案内役の方と話をした時。私は先の想いを吐露することになります。
〔参照(後半):
貴重な現地取材。一言でも聞き漏らすまいと案内役の方の説明に“全集中”を試みます。出身は佐賀だと語った私に、案内役の方が尋ねました。
「あなたは佐賀に戻って来られないのですか?」
「そう簡単には戻れませんね。あるいは骨になったら還ってきたいものですが…」
「…!?」
――私も、歳は取りましたが…
“終活”には、まだ早い年代と思われます。しかも貫禄に欠ける私は実年齢より若く見えてしまうようです。
…ここで私は「しまった、案内役の方が反応に困る言葉を発した」と気づきます。
とりあえず“問題発言”はさておいて、「佐賀の大河ドラマ」への想いを語り始めました。しかし、先の発言には私の本音も含まれています。
――「いつの日か、佐賀へ還る。」
古の聖人たちも“最期の旅”と言うのでしょうか。亡くなる前に郷里に向かって歩み出す話をよく聞きます。おそらく、それは私のような凡人も持つ想い。
きっと、そう思うだけでも救われているのでしょう。人はもちろん、あるいは動物にだって、安息の“終(つい)の棲家”を求める心はあるように感じられます。
でも、生きているうちに成し得ることがあるはず。故郷のために“一花”咲かせてみたい…そんな気持ちが私を動かしています。
2021年07月08日
「道標の剣」
こんばんは。
さすがに7月。気温も湿度も高く、マスクの着用で体感温度も上がりますね。
本日記事の私のようになった時には少し頭を冷やして水分を取り、木陰や室内で涼んでみると良いかもしれません。
…そんな夏。私の日常の話。ほぼ“幻覚”なのかもしれませんが、一握りの真実を感じていただければと思います。
――故郷・佐賀に帰れないまま、2回目の夏が来た。
いま私の住む街より、きっと佐賀は暑いことだろう…
その朝も失せた気力のまま通勤をする。そして、少しお腹をさすった。
「また、随分と痩せてしまったな…」
――近くに大きい神社が見える。
1つ、ため息をつく私。マスク越しの深呼吸では、夏の季節感は入って来ない。
「お主…、気を確かに持て。」
なぜだか社殿の方から、そう言われている気配を感じる。
「もしや、殿!?」
いや…そんなはずは無い。眼前に見えるのは「佐嘉(さが)神社」ではないぞ。幻覚にしても距離感があり過ぎる。

――お構いなしに、殿の気配は続く。
「この地とて“佐賀”とはつながっておる…」
私は、疲れているのか。もちろん、この神社のご祭神は鍋島直正公ではない。
「海沿いに行けばつながっている…と言えなくも無いのでございますが。」
「お主には、語るまでもないと思うが、佐賀はこちらの方角じゃ。決して見失うでないぞ。」
「御意(ぎょい)!」
…殿様への返答と言えば、やはりこの言葉であろう。
――この日は、朝からかなりの暑さ。
朦朧(もうろう)とする中で、佐賀藩士(?)として受け答えをする私。きっと心の声に留まっている。周囲の人たちには聞こえないはず。
…そして地図上に線でも引いたかのように、佐賀の方角を再確認した私。
わずかであるが、それまでより身体が軽く感じる。神社の前で見た“幻覚”には、回復の効果があったのかもしれない。
――そして、日中も…
年を経るごとに、より高くなる“仕事の壁”。昔は思っていた。「ある程度の歳月を重ねれば、きっと楽になるのだ」と…それは思い過ごしだったようだ。
そうも言ってられない、とにかく現状の打開を試みねば。
「大隈先生っ…私に力をお貸しください!」
もはや“出たとこ”勝負。ここで私が想い出す、佐賀の賢人は大隈重信侯だ。

――『青天を衝け』でも見かけた…
イギリス公使・パークス。「7日以内に、帝から条約の勅許(チョッキョ)を取って来い」と開港の実施を迫る姿が印象的だった、超おっかない外交官である。
大隈重信は明治初頭の外交の舞台で、そのパークスと真っ向から論戦。一歩も引かず、その要求を突っぱねたという。
誰もが恐れるイギリス公使と外交の折衝をすることは、当時なら刀で斬り合う以上に度胸が必要だったかもしれない。
…私もいろいろ苦しい気持ちの中、その勇姿を想って拳を握る。
――佐賀の“先輩”への憧れを、いま力に変える。
著しく能力の差はあっても、立ち向かうべき仕事の重さは全然違っても。
こんな日々を過ごす中、私が思い至った事がある。
「…想いを持ち続けるなら、万難を排して“佐賀に還る”べきなのかもしれない。」
私が「佐賀を見失わないために成すべきこと」とは何か。そろそろ、私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」“本編”第2部を綴っていかねば…と思うのである。
さすがに7月。気温も湿度も高く、マスクの着用で体感温度も上がりますね。
本日記事の私のようになった時には少し頭を冷やして水分を取り、木陰や室内で涼んでみると良いかもしれません。
…そんな夏。私の日常の話。ほぼ“幻覚”なのかもしれませんが、一握りの真実を感じていただければと思います。
――故郷・佐賀に帰れないまま、2回目の夏が来た。
いま私の住む街より、きっと佐賀は暑いことだろう…
その朝も失せた気力のまま通勤をする。そして、少しお腹をさすった。
「また、随分と痩せてしまったな…」
――近くに大きい神社が見える。
1つ、ため息をつく私。マスク越しの深呼吸では、夏の季節感は入って来ない。
「お主…、気を確かに持て。」
なぜだか社殿の方から、そう言われている気配を感じる。
「もしや、殿!?」
いや…そんなはずは無い。眼前に見えるのは「佐嘉(さが)神社」ではないぞ。幻覚にしても距離感があり過ぎる。
――お構いなしに、殿の気配は続く。
「この地とて“佐賀”とはつながっておる…」
私は、疲れているのか。もちろん、この神社のご祭神は鍋島直正公ではない。
「海沿いに行けばつながっている…と言えなくも無いのでございますが。」
「お主には、語るまでもないと思うが、佐賀はこちらの方角じゃ。決して見失うでないぞ。」
「御意(ぎょい)!」
…殿様への返答と言えば、やはりこの言葉であろう。
――この日は、朝からかなりの暑さ。
朦朧(もうろう)とする中で、佐賀藩士(?)として受け答えをする私。きっと心の声に留まっている。周囲の人たちには聞こえないはず。
…そして地図上に線でも引いたかのように、佐賀の方角を再確認した私。
わずかであるが、それまでより身体が軽く感じる。神社の前で見た“幻覚”には、回復の効果があったのかもしれない。
――そして、日中も…
年を経るごとに、より高くなる“仕事の壁”。昔は思っていた。「ある程度の歳月を重ねれば、きっと楽になるのだ」と…それは思い過ごしだったようだ。
そうも言ってられない、とにかく現状の打開を試みねば。
「大隈先生っ…私に力をお貸しください!」
もはや“出たとこ”勝負。ここで私が想い出す、佐賀の賢人は大隈重信侯だ。
――『青天を衝け』でも見かけた…
イギリス公使・パークス。「7日以内に、帝から条約の勅許(チョッキョ)を取って来い」と開港の実施を迫る姿が印象的だった、超おっかない外交官である。
大隈重信は明治初頭の外交の舞台で、そのパークスと真っ向から論戦。一歩も引かず、その要求を突っぱねたという。
誰もが恐れるイギリス公使と外交の折衝をすることは、当時なら刀で斬り合う以上に度胸が必要だったかもしれない。
…私もいろいろ苦しい気持ちの中、その勇姿を想って拳を握る。
――佐賀の“先輩”への憧れを、いま力に変える。
著しく能力の差はあっても、立ち向かうべき仕事の重さは全然違っても。
こんな日々を過ごす中、私が思い至った事がある。
「…想いを持ち続けるなら、万難を排して“佐賀に還る”べきなのかもしれない。」
私が「佐賀を見失わないために成すべきこと」とは何か。そろそろ、私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」“本編”第2部を綴っていかねば…と思うのである。
2021年07月31日
「暑中の剣」
こんにちは。
ふと気づけば「暑中お見舞い申し上げます」と、ご挨拶すべき時期。熱戦が続くオリンピックですが、流れる情報量が多過ぎて、追いつかないところもあります。
昨夜、ひと息ついた時に“ある競技”で活躍する“剣士の一団”が私の目に飛び込んできました。
…というわけで、本日は“本編”を小休止し、競技の趣旨から、かなり飛躍のある内容に空想を飛ばす、私の「オリンピック噺(ばなし)」です。
――暑い…、そして忙しい。
しかも、全国的に新型コロナの感染まで拡大してきた。オリンピックが盛り上がる一方で、感染症への不安があり、バランスが取れていない。
…いろいろと葛藤のある夏。また佐賀への“帰藩”は遠くなりそうだ。
なぜ、そんなタイミングで“第2部”を続けるのか。それはきっと「佐賀藩士(?)を名乗る者ならば、何かを頑張らねばならぬ…」という想いからだ。
――テレビを付ければ、オリンピック。
まさに「人並み外れた努力と才能をもって、己の目指すところで頑張る人たち」の集う場と言えるだろう。
一方で、多種多様な競技が放送されると、見慣れない風景も多い。カシャカシャと金属の触れ合う音色。ピッ…という電子音とともに点灯する鮮やかな蛍光色。
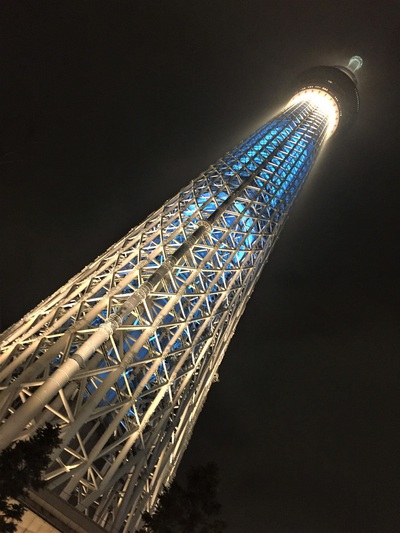
――「おぉ、西洋の剣術か!」
なんとなく幕末風に語ったが、競技の名は“フェンシング”である。昨夜は「エペ」という種目で、日本人選手たちの活躍が報じられていた。
軽いフットワークで前後に動き、相手の隙をつくって、すかさず刺突する展開が見える。フェンシングの中でも自由度が高く、全身が有効面となる種目らしい。
ピッ…、ピッ…と小気味よく点数が重なっていく様は、ゲームでも見るかのよう。
――よく見ると、団体戦である様子。
ルールは調べていないが一定の時間で、次の選手に交代する仕組みのようだ。わずかな時間で見ても、攻守のスタイルに選手の個性を感じる。
…競技を見ながら、私は本編・第2部で描いている“剣士の一団”を想った。
「桜田門外の変」の直後、江戸(現・東京)にいる殿様・鍋島直正公を護衛するために急ぎ派遣された佐賀の剣士たち。
一団には、30人ばかりが居たという。私の粗い調べだと、彼らの個性までは掴むことができない。ただ各人各様に、剣の流儀や得意技もあっただろうと思う。
――江戸時代は比較的、平穏な時期が続いたが…
かなり物騒になっていた幕末期。武士だけではなく、農民や町人も剣の鍛錬に励んだことは「大河ドラマ」でもよく題材となる。
幕府の要人や外国人にも、剣術を用いた襲撃事件が相次いだ。逆に“志士”を取り締まる側も、有無を言わせず斬りかかる時勢だった。
――しかし、そう言った“凶刃”が光る場面に…
武術の鍛錬に励んだ佐賀藩士の姿を見かけることは、ほぼ無いようだ。
「積極的に戦わない佐賀藩」なので、ドラマで表現しづらいのも理解はできる。
「幕末の佐賀は、日和見(ひよりみ)をした」と貶(けな)されたように、否定的な見え方も入ってくるのかもしれない。

――「腕が立つのに、刀を抜かない侍」。
技術を向上し、鍛錬を重ねて強くなれば“争わず”に済む。もっと進めば“周囲を争わせず”に済む。私は幕末期に佐賀藩が求めた“理想”をこう形容したい。
一説には“幕末最強”との評価もある佐賀藩。目指していた理想、挫折、そして救済。そこまでを物語で表現したいのだが、時間も才能も足りそうにない。
「それゆえ、私も努力で補うほかないな…」
激闘のすえ金メダルを獲得し、歓喜に湧く“フェンシング”の日本チーム。肩を抱き合う“剣士たち”の姿を見ながら、私はそんなことを考えていた。
ふと気づけば「暑中お見舞い申し上げます」と、ご挨拶すべき時期。熱戦が続くオリンピックですが、流れる情報量が多過ぎて、追いつかないところもあります。
昨夜、ひと息ついた時に“ある競技”で活躍する“剣士の一団”が私の目に飛び込んできました。
…というわけで、本日は“本編”を小休止し、競技の趣旨から、かなり飛躍のある内容に空想を飛ばす、私の「オリンピック噺(ばなし)」です。
――暑い…、そして忙しい。
しかも、全国的に新型コロナの感染まで拡大してきた。オリンピックが盛り上がる一方で、感染症への不安があり、バランスが取れていない。
…いろいろと葛藤のある夏。また佐賀への“帰藩”は遠くなりそうだ。
なぜ、そんなタイミングで“第2部”を続けるのか。それはきっと「佐賀藩士(?)を名乗る者ならば、何かを頑張らねばならぬ…」という想いからだ。
――テレビを付ければ、オリンピック。
まさに「人並み外れた努力と才能をもって、己の目指すところで頑張る人たち」の集う場と言えるだろう。
一方で、多種多様な競技が放送されると、見慣れない風景も多い。カシャカシャと金属の触れ合う音色。ピッ…という電子音とともに点灯する鮮やかな蛍光色。
――「おぉ、西洋の剣術か!」
なんとなく幕末風に語ったが、競技の名は“フェンシング”である。昨夜は「エペ」という種目で、日本人選手たちの活躍が報じられていた。
軽いフットワークで前後に動き、相手の隙をつくって、すかさず刺突する展開が見える。フェンシングの中でも自由度が高く、全身が有効面となる種目らしい。
ピッ…、ピッ…と小気味よく点数が重なっていく様は、ゲームでも見るかのよう。
――よく見ると、団体戦である様子。
ルールは調べていないが一定の時間で、次の選手に交代する仕組みのようだ。わずかな時間で見ても、攻守のスタイルに選手の個性を感じる。
…競技を見ながら、私は本編・第2部で描いている“剣士の一団”を想った。
「桜田門外の変」の直後、江戸(現・東京)にいる殿様・鍋島直正公を護衛するために急ぎ派遣された佐賀の剣士たち。
一団には、30人ばかりが居たという。私の粗い調べだと、彼らの個性までは掴むことができない。ただ各人各様に、剣の流儀や得意技もあっただろうと思う。
――江戸時代は比較的、平穏な時期が続いたが…
かなり物騒になっていた幕末期。武士だけではなく、農民や町人も剣の鍛錬に励んだことは「大河ドラマ」でもよく題材となる。
幕府の要人や外国人にも、剣術を用いた襲撃事件が相次いだ。逆に“志士”を取り締まる側も、有無を言わせず斬りかかる時勢だった。
――しかし、そう言った“凶刃”が光る場面に…
武術の鍛錬に励んだ佐賀藩士の姿を見かけることは、ほぼ無いようだ。
「積極的に戦わない佐賀藩」なので、ドラマで表現しづらいのも理解はできる。
「幕末の佐賀は、日和見(ひよりみ)をした」と貶(けな)されたように、否定的な見え方も入ってくるのかもしれない。
――「腕が立つのに、刀を抜かない侍」。
技術を向上し、鍛錬を重ねて強くなれば“争わず”に済む。もっと進めば“周囲を争わせず”に済む。私は幕末期に佐賀藩が求めた“理想”をこう形容したい。
一説には“幕末最強”との評価もある佐賀藩。目指していた理想、挫折、そして救済。そこまでを物語で表現したいのだが、時間も才能も足りそうにない。
「それゆえ、私も努力で補うほかないな…」
激闘のすえ金メダルを獲得し、歓喜に湧く“フェンシング”の日本チーム。肩を抱き合う“剣士たち”の姿を見ながら、私はそんなことを考えていた。
2021年08月07日
「醒覚の剣」(回航)
こんばんは。
開催自体に賛否両論あったところですが、やはりオリンピックは気になる話題。終盤を迎えて、無意識のうちにテレビを付ける回数も増えたように思います。
一方で、全国的に新型コロナの感染急拡大は続きます。そんな折、私は郷里・佐賀に住む叔父上に、“ある連絡”を入れていました。
――ある暑い日に、電話をする。
「叔父上、お時間はよろしいか。」
「うん、よかよ。暑かね~」
『さがファンブログ』の記事を通じ、“佐賀の暑さ”はこちらに伝わってくる。その日の天気にも拠ると思うが、たぶん私の周囲よりも佐賀は相当に暑いと見る。
――佐賀への“帰藩”の自粛は継続中である。
そんな環境でもブログを書き続けるため、叔父上には色々と頼み事をしている。
「佐賀でも“新型コロナ”が油断ならない様子ですね。」
「そうたいね。」
以前は「県内各地域の感染者数など」を日常的に把握する便利な“情報源”があったが、今はあえて調べねば状況がわからない。
「当面、お願いした件の実行は、控えてください。」
まずは安全策。感染が抑え込めたタイミングで動いても、とくに問題は無い。

――「心配なかよ。」
そういう感じで叔父上は、言葉を続けた。
「まぁ暑すぎて動けんから、どのみち今は出られんばい…」
…それにワクチンの接種もあるようで、しばらくは用心しておくと聞いた。
「こちらには、まだ、(ワクチンが)“回って”きませんがね。」
「にゃ、回っとらんね。」
――このやり取り。
叔父上には、私の“仕事”が回っていないと伝わったようだ。
「…いや、確かに仕事も回っていませんが、こちらにはワクチンも来ません。」
「そうね。ちょっとずつでも回さんば。」
もはや仕事でも、ワクチンでも、とにかく少しずつでも回ればよい…というのが、叔父上の受けとめ方だ。

――幕末期。日本の沿海で“蒸気船”を運用する佐賀藩。
西の外海に開けた“天草”(熊本)の軍港計画は幻に終わったので、主な拠点は有明海の“三重津海軍所”となる。
佐賀藩内の港として、蒸気船の回航時には“伊万里”の地名もよく見かけるが、陶磁器の積出港は、大規模な運用には向かなかった…と推測する。
本当は現地で確認したい事が山ほどある。佐賀から遠い、私の不利な点だ。
――瀬戸内海などで、佐賀藩は蒸気船をよく回航した。
殿・鍋島直正は参勤交代でも蒸気船を使用。幕府からは“観光丸”を預かり、佐野常民が運用。江戸から退避した時も兵庫からは蒸気船だったようだ。
〔参照①:第15話「江戸動乱」⑬(海に駆ける)〕
〔参照②(後半):第16話「攘夷沸騰」④(その船を、取りに行け)〕
〔参照③(終盤):第16話「攘夷沸騰」⑥(積年の胃痛にて…)〕
隠居後に直正公は、大坂城で将軍・徳川慶喜に会う際にも蒸気船で乗り込むはず。殿の「御座船」で、まるで“相棒”のような蒸気船“電流丸”が活躍する。
〔参照:「主に伊万里市民の方を対象にしたつぶやき」〕

――それも、佐賀には“力の蓄積”があったから。
長崎での海軍伝習に佐賀藩が派遣した人数は48名と言われる。“本編”で描く時期には、佐野常民を中心に“三重津海軍所”を整備中のはずだ。
“蒸気船”を動かす人材の訓練だけでなく、外国に頼らずに、自力で船の修繕もしてしまうのが佐賀藩。
ここでは、佐野常民の作った“プロジェクトチーム”の田中久重・中村奇輔らの影響が見える。“海に駆ける力”も、努力の積み重ねなのである。
――いかに、幕末期の佐賀藩とて。
最初から自在に“蒸気船”を運用できたわけではない。例えるならオリンピックに出ているアスリートとて、才能とともに、影日向での努力で結果が出ているはず。
佐賀藩士(?)を名乗りながら、地道な努力を厭(いと)うのは理屈に合わない。私も、可能なところから回していくほか無さそうだ。
いま、一気に事態を打開することは難しい。しかし千里の“回航”も、おそらくは“船出”の一歩から。私は、叔父上の言葉を受け取った。
「少しずつでも回さんば…ですね。」
開催自体に賛否両論あったところですが、やはりオリンピックは気になる話題。終盤を迎えて、無意識のうちにテレビを付ける回数も増えたように思います。
一方で、全国的に新型コロナの感染急拡大は続きます。そんな折、私は郷里・佐賀に住む叔父上に、“ある連絡”を入れていました。
――ある暑い日に、電話をする。
「叔父上、お時間はよろしいか。」
「うん、よかよ。暑かね~」
『さがファンブログ』の記事を通じ、“佐賀の暑さ”はこちらに伝わってくる。その日の天気にも拠ると思うが、たぶん私の周囲よりも佐賀は相当に暑いと見る。
――佐賀への“帰藩”の自粛は継続中である。
そんな環境でもブログを書き続けるため、叔父上には色々と頼み事をしている。
「佐賀でも“新型コロナ”が油断ならない様子ですね。」
「そうたいね。」
以前は「県内各地域の感染者数など」を日常的に把握する便利な“情報源”があったが、今はあえて調べねば状況がわからない。
「当面、お願いした件の実行は、控えてください。」
まずは安全策。感染が抑え込めたタイミングで動いても、とくに問題は無い。
――「心配なかよ。」
そういう感じで叔父上は、言葉を続けた。
「まぁ暑すぎて動けんから、どのみち今は出られんばい…」
…それにワクチンの接種もあるようで、しばらくは用心しておくと聞いた。
「こちらには、まだ、(ワクチンが)“回って”きませんがね。」
「にゃ、回っとらんね。」
――このやり取り。
叔父上には、私の“仕事”が回っていないと伝わったようだ。
「…いや、確かに仕事も回っていませんが、こちらにはワクチンも来ません。」
「そうね。ちょっとずつでも回さんば。」
もはや仕事でも、ワクチンでも、とにかく少しずつでも回ればよい…というのが、叔父上の受けとめ方だ。
――幕末期。日本の沿海で“蒸気船”を運用する佐賀藩。
西の外海に開けた“天草”(熊本)の軍港計画は幻に終わったので、主な拠点は有明海の“三重津海軍所”となる。
佐賀藩内の港として、蒸気船の回航時には“伊万里”の地名もよく見かけるが、陶磁器の積出港は、大規模な運用には向かなかった…と推測する。
本当は現地で確認したい事が山ほどある。佐賀から遠い、私の不利な点だ。
――瀬戸内海などで、佐賀藩は蒸気船をよく回航した。
殿・鍋島直正は参勤交代でも蒸気船を使用。幕府からは“観光丸”を預かり、佐野常民が運用。江戸から退避した時も兵庫からは蒸気船だったようだ。
〔参照①:
〔参照②(後半):
〔参照③(終盤):
隠居後に直正公は、大坂城で将軍・徳川慶喜に会う際にも蒸気船で乗り込むはず。殿の「御座船」で、まるで“相棒”のような蒸気船“電流丸”が活躍する。
〔参照:
――それも、佐賀には“力の蓄積”があったから。
長崎での海軍伝習に佐賀藩が派遣した人数は48名と言われる。“本編”で描く時期には、佐野常民を中心に“三重津海軍所”を整備中のはずだ。
“蒸気船”を動かす人材の訓練だけでなく、外国に頼らずに、自力で船の修繕もしてしまうのが佐賀藩。
ここでは、佐野常民の作った“プロジェクトチーム”の田中久重・中村奇輔らの影響が見える。“海に駆ける力”も、努力の積み重ねなのである。
――いかに、幕末期の佐賀藩とて。
最初から自在に“蒸気船”を運用できたわけではない。例えるならオリンピックに出ているアスリートとて、才能とともに、影日向での努力で結果が出ているはず。
佐賀藩士(?)を名乗りながら、地道な努力を厭(いと)うのは理屈に合わない。私も、可能なところから回していくほか無さそうだ。
いま、一気に事態を打開することは難しい。しかし千里の“回航”も、おそらくは“船出”の一歩から。私は、叔父上の言葉を受け取った。
「少しずつでも回さんば…ですね。」
2021年10月23日
「醒覚の剣」(時鐘)
こんばんは。
今週末は佐賀城公園が“秋祭り”の様子で佐賀の中心街も盛況かと察します。観光資源が豊富な、唐津周辺にも各地から人が集まっているかもしれません。
少し日常が取り戻せる気配。一方、なかなか佐賀に帰れない現況の私。もはや、1年半にわたる叔父上への依頼。それは佐賀県内の各地域の写真撮影です。
なお、“本編”を更新する速度は著しく落ちていますが、書きたいことも多いのは相変わらずです。
――時期は、少し前に遡る。
私は、“本編”第16話「攘夷沸騰」を海を軸とする構成で計画していた。最近、仕事が忙しい等…個人的事情もあるが、描き方も難しい年代に入ったと感じる。
「叔父上、また海の写真が要りようなのです。」
「あ~、近いうちに唐津まで行くけん、そこで撮ったらよかね。」
私は、2年近く佐賀に戻れていないが、もし帰っても動けるのは限られた時間。ブログを続ければ、県内に住む叔父上の力を借りるのは必然だったようだ。

――たぶん叔父上も、人生が始まって以来…
現在が最も多く“佐賀の写真”を撮っていることだろう。私にとって“写真”とは、一瞬の時間を切り取り、空間を枠内に収めるもの…という感覚だ。
かなり年をとってから、急に“佐賀藩士”に覚醒した甥っ子のわがままに応えて、叔父上は一定の集中力を駆使して、佐賀の風景に向き合うこととなった。
――“本編”で様々な場面を設定して考える。
この作業も写真と共通するところがあるのかもしれない。しかし、私には対象になる150年ぐらい前の“佐賀の先輩”たちの動向を、正確につかむ力は無い。
研究を進める方々の資料で知る“史実”に近いと思われる内容が頼りで、願望を言えば、佐賀県立図書館辺りに、しばらく通い詰めて調べ物を進めたいほどだ。
――時間(一瞬)の積み重ねが、歴史なのだろうか。
現在の佐賀県内には、江戸期の佐賀藩だけでなく、唐津藩や対馬藩(田代領)もある。写真の“鐘楼”は、叔父上が唐津藩の情報として選んでくれたものだ。
徳川に近しい譜代大名が統治した唐津藩。初代藩主の寺沢氏から“幕領”の時代を経て、5家(大久保、松平、土井、水野、小笠原)の変遷があったそうだ。

※4代目の大名・土井氏の時代の“鐘楼”を復元したそうです。
――5代目の大名・水野氏は…
“天保の改革”で知られる水野忠邦までで唐津を去る。“長崎見廻役”の負担が、幕閣での出世の妨げになると考えたとか、早々に国替えを希望したと聞く。
〔参照:「主に唐津市民の方を対象にしたつぶやき」〕
6代目の大名・小笠原氏が唐津藩主だったのは、激動の時代・幕末の半世紀。江戸時代を長きに渡り、鍋島家が治めた佐賀藩とは、また違った物語を感じる。
――その“鐘楼”では、決まった時刻になると…
正装した唐津藩士の人形が現れて、時の太鼓をドンドンと鳴らしてから櫓の中に戻るという。唐津を治める大名ごとに、時の告げ方にも変遷があったようだ。
「佐賀県には…私の見てみたい景色が、山のようにある。」
私自身、佐賀の歴史の重みに気づくまで、その“価値”を顧みて来なかった。
県内に住む叔父上の視点から、写真の枠内に収める佐賀の風景。写し取った一瞬が“時を告げる太鼓”のように、いまの私にはとても良く響いている。
今週末は佐賀城公園が“秋祭り”の様子で佐賀の中心街も盛況かと察します。観光資源が豊富な、唐津周辺にも各地から人が集まっているかもしれません。
少し日常が取り戻せる気配。一方、なかなか佐賀に帰れない現況の私。もはや、1年半にわたる叔父上への依頼。それは佐賀県内の各地域の写真撮影です。
なお、“本編”を更新する速度は著しく落ちていますが、書きたいことも多いのは相変わらずです。
――時期は、少し前に遡る。
私は、“本編”第16話「攘夷沸騰」を海を軸とする構成で計画していた。最近、仕事が忙しい等…個人的事情もあるが、描き方も難しい年代に入ったと感じる。
「叔父上、また海の写真が要りようなのです。」
「あ~、近いうちに唐津まで行くけん、そこで撮ったらよかね。」
私は、2年近く佐賀に戻れていないが、もし帰っても動けるのは限られた時間。ブログを続ければ、県内に住む叔父上の力を借りるのは必然だったようだ。
――たぶん叔父上も、人生が始まって以来…
現在が最も多く“佐賀の写真”を撮っていることだろう。私にとって“写真”とは、一瞬の時間を切り取り、空間を枠内に収めるもの…という感覚だ。
かなり年をとってから、急に“佐賀藩士”に覚醒した甥っ子のわがままに応えて、叔父上は一定の集中力を駆使して、佐賀の風景に向き合うこととなった。
――“本編”で様々な場面を設定して考える。
この作業も写真と共通するところがあるのかもしれない。しかし、私には対象になる150年ぐらい前の“佐賀の先輩”たちの動向を、正確につかむ力は無い。
研究を進める方々の資料で知る“史実”に近いと思われる内容が頼りで、願望を言えば、佐賀県立図書館辺りに、しばらく通い詰めて調べ物を進めたいほどだ。
――時間(一瞬)の積み重ねが、歴史なのだろうか。
現在の佐賀県内には、江戸期の佐賀藩だけでなく、唐津藩や対馬藩(田代領)もある。写真の“鐘楼”は、叔父上が唐津藩の情報として選んでくれたものだ。
徳川に近しい譜代大名が統治した唐津藩。初代藩主の寺沢氏から“幕領”の時代を経て、5家(大久保、松平、土井、水野、小笠原)の変遷があったそうだ。
※4代目の大名・土井氏の時代の“鐘楼”を復元したそうです。
――5代目の大名・水野氏は…
“天保の改革”で知られる水野忠邦までで唐津を去る。“長崎見廻役”の負担が、幕閣での出世の妨げになると考えたとか、早々に国替えを希望したと聞く。
〔参照:
6代目の大名・小笠原氏が唐津藩主だったのは、激動の時代・幕末の半世紀。江戸時代を長きに渡り、鍋島家が治めた佐賀藩とは、また違った物語を感じる。
――その“鐘楼”では、決まった時刻になると…
正装した唐津藩士の人形が現れて、時の太鼓をドンドンと鳴らしてから櫓の中に戻るという。唐津を治める大名ごとに、時の告げ方にも変遷があったようだ。
「佐賀県には…私の見てみたい景色が、山のようにある。」
私自身、佐賀の歴史の重みに気づくまで、その“価値”を顧みて来なかった。
県内に住む叔父上の視点から、写真の枠内に収める佐賀の風景。写し取った一瞬が“時を告げる太鼓”のように、いまの私にはとても良く響いている。
2022年01月03日
「醒覚の剣(歌枕)」
こんばんは。
私のブログでは、ここ2年間ほど佐賀に帰れないと語るわりに、佐賀の写真をよく掲載します。この“妙技”を可能にしているのが、地元に住む叔父上です。
…叔父上に次々と舞い込むのは、もう若くはない甥っ子からの依頼の数々。
今回はちょっと“新春ミステリー”風の書き出しで正月らしさを意識しましたが、嬉野~唐津へとつながる…まるで“2時間ドラマ”のような長文になりました。
――時に、私の想像の“斜め上”を行く叔父上。
「嬉野に寄るときに“和泉式部”が居たから、撮ってきたとよ。」
「…!和泉式部…、なぜ佐賀に?」
平安時代の歌人の名であることはわかる。しかし、一応は歴史好きのはずの私だが、その辺りの知識は乏しい。
「…平安期か…」
私は、思考を巡らした。こういう時の叔父上は、極めて無邪気である。奇をてらったところが無い分、動きが読めない。

――これを「幕末佐賀藩の大河ドラマ」がテーマのブログで、どう使う…?
「まず地図ば、見んね?」
私の住む地から、遠く隔たった佐賀。電話口から叔父上の声がする。そうだ、考えるだけでは駄目だ。現地に足を運べずとも、できる事があると言うことか。
「和泉式部像の所在は、嬉野市・塩田の辺りですね…。」
「そうたい、塩田の近くばい。」
嬉野市・塩田。そういえば“本編”でも描いたことがある。有明海の干満の差を利用し、江戸期に水運で栄えたという。

――隆盛(りゅうせい)を誇った“川の港”。
十二単(じゅうにひとえ)姿の女性像は、叔父上が私に出した公案(課題)であるのか。電話を切ったあと、さらに思索を重ねる。
「もしや京都と、佐賀にある塩田の港がつながっていた…ということか!」
少し調べると、実は全国各地に“和泉式部”の伝承はあるようだ。幾人もの、和泉式部の影。
――著名な平安の歌人だった和泉式部は、
生没年も不詳というが、恋多き女性だったと伝わるようだ。かの『源氏物語』の作者・紫式部は彼女の華やかさに妬みを感じていた…と聞いた事がある。
和泉式部像の周辺情報によると、佐賀出身説は、おそらくは御仏のご加護により、現在の白石町に生まれた才女が、ここ嬉野市・塩田の夫妻に育てられ、都に上ったそうだ。

――この歌碑は“千年”も前の、出来事の手がかりなのか。
古の時代にも、佐賀と京都の間にあったかもしれない、点と点を結ぶ“動線”。
百五十年ばかりしか離れていない、幕末でもわからぬ事だらけなのだ。さすがに、千年となれば厳しい。
「…この事案は、管轄外だ。私には追えない。」
しかし、幾つかの点には、思い当たるところがある。
1つ、当地・塩田が何らかの形で、京の都と交流があったと思われる事。
1つ、高名な女流歌人が輩出される素地がある、文化水準が推測できる事。
――現在、『さがファンブログ』でも閲覧できる…
“市報うれしの”にも、短歌を掲載するコーナーを見つけた。この流れだと、何の不思議もない。きっと心が動いた時には、歌を詠むのだ。では、
念願の 鉄路来たれる 嬉野に
茶の沸く 湯も湧く また街もわく
私に短歌の心得は無い…そして“字余り”だが、祝福の気持ちは込めた。嬉野に鉄道の新駅が来る。西九州新幹線の開業年には、いろいろと期待もある。

――さて平安期に、京の歌人たちは…
実際に足を運べずとも、遙か東北の地にさえ想いを馳せ、歌を詠んだという。
こうして名所化された場所を“歌枕”と呼び、江戸時代の俳人・松尾芭蕉などは、それら“聖地”を巡っていたと聞く。
いわば“強く想う力”が重なって、本物の“聖地”を創り出した事例もあるということか。強く想うことだけならば、微力ながらも、私の得手とするところである。
――想い出すのは、昨年の大河ドラマ『青天を衝け』での、
江戸幕府14代将軍・徳川家茂〔演:磯村勇斗〕と和宮〔演:深川麻衣〕の場面。美男美女で優雅であり、個人的に“源氏物語”っぽく見えてしまった。
但し、この“ご夫婦”、恋多き男女とは真逆。まるで、二昔くらい前の少女マンガでしか見られないような、一途な純愛物語と言ってよさそうだ。
――そして妻・和宮が、夫・家茂への気持ちを詠んだ和歌には、
涙を誘うような想いが伝わる一首がある。『青天を衝け』でも一瞬、この内容の場面が登場したが、ここでは詳細を差し控える。
妻だけでなく、幕臣たちからも慕われた“上様”だったのか。京都で苦境にあった将軍・徳川家茂を救おうとした人物もいた。
こちらも現在の佐賀県にある、唐津藩の小笠原長行。将軍・家茂を苦しめる攘夷派を一掃すべく、軍勢を率い、京都へ乗り込もうとした史実があるようだ。

――こうして、私の新春一本目の調査(?)は完了した。
「…叔父上。あの写真。どうにか、幕末の佐賀とつながりました。」
この記事が、調査報告だ。実際のところ叔父上は「あんまり無理ばせんと。」とよく言ってくれる。たぶん今回も、そうだろう。
佐賀県全体に通じる“物語”を描こうとする試み…“本編”を描く道のりは、今年も険しそうだ。
私のブログでは、ここ2年間ほど佐賀に帰れないと語るわりに、佐賀の写真をよく掲載します。この“妙技”を可能にしているのが、地元に住む叔父上です。
…叔父上に次々と舞い込むのは、もう若くはない甥っ子からの依頼の数々。
今回はちょっと“新春ミステリー”風の書き出しで正月らしさを意識しましたが、嬉野~唐津へとつながる…まるで“2時間ドラマ”のような長文になりました。
――時に、私の想像の“斜め上”を行く叔父上。
「嬉野に寄るときに“和泉式部”が居たから、撮ってきたとよ。」
「…!和泉式部…、なぜ佐賀に?」
平安時代の歌人の名であることはわかる。しかし、一応は歴史好きのはずの私だが、その辺りの知識は乏しい。
「…平安期か…」
私は、思考を巡らした。こういう時の叔父上は、極めて無邪気である。奇をてらったところが無い分、動きが読めない。
――これを「幕末佐賀藩の大河ドラマ」がテーマのブログで、どう使う…?
「まず地図ば、見んね?」
私の住む地から、遠く隔たった佐賀。電話口から叔父上の声がする。そうだ、考えるだけでは駄目だ。現地に足を運べずとも、できる事があると言うことか。
「和泉式部像の所在は、嬉野市・塩田の辺りですね…。」
「そうたい、塩田の近くばい。」
嬉野市・塩田。そういえば“本編”でも描いたことがある。有明海の干満の差を利用し、江戸期に水運で栄えたという。
――隆盛(りゅうせい)を誇った“川の港”。
十二単(じゅうにひとえ)姿の女性像は、叔父上が私に出した公案(課題)であるのか。電話を切ったあと、さらに思索を重ねる。
「もしや京都と、佐賀にある塩田の港がつながっていた…ということか!」
少し調べると、実は全国各地に“和泉式部”の伝承はあるようだ。幾人もの、和泉式部の影。
――著名な平安の歌人だった和泉式部は、
生没年も不詳というが、恋多き女性だったと伝わるようだ。かの『源氏物語』の作者・紫式部は彼女の華やかさに妬みを感じていた…と聞いた事がある。
和泉式部像の周辺情報によると、佐賀出身説は、おそらくは御仏のご加護により、現在の白石町に生まれた才女が、ここ嬉野市・塩田の夫妻に育てられ、都に上ったそうだ。
――この歌碑は“千年”も前の、出来事の手がかりなのか。
古の時代にも、佐賀と京都の間にあったかもしれない、点と点を結ぶ“動線”。
百五十年ばかりしか離れていない、幕末でもわからぬ事だらけなのだ。さすがに、千年となれば厳しい。
「…この事案は、管轄外だ。私には追えない。」
しかし、幾つかの点には、思い当たるところがある。
1つ、当地・塩田が何らかの形で、京の都と交流があったと思われる事。
1つ、高名な女流歌人が輩出される素地がある、文化水準が推測できる事。
――現在、『さがファンブログ』でも閲覧できる…
“市報うれしの”にも、短歌を掲載するコーナーを見つけた。この流れだと、何の不思議もない。きっと心が動いた時には、歌を詠むのだ。では、
念願の 鉄路来たれる 嬉野に
茶の沸く 湯も湧く また街もわく
私に短歌の心得は無い…そして“字余り”だが、祝福の気持ちは込めた。嬉野に鉄道の新駅が来る。西九州新幹線の開業年には、いろいろと期待もある。
――さて平安期に、京の歌人たちは…
実際に足を運べずとも、遙か東北の地にさえ想いを馳せ、歌を詠んだという。
こうして名所化された場所を“歌枕”と呼び、江戸時代の俳人・松尾芭蕉などは、それら“聖地”を巡っていたと聞く。
いわば“強く想う力”が重なって、本物の“聖地”を創り出した事例もあるということか。強く想うことだけならば、微力ながらも、私の得手とするところである。
――想い出すのは、昨年の大河ドラマ『青天を衝け』での、
江戸幕府14代将軍・徳川家茂〔演:磯村勇斗〕と和宮〔演:深川麻衣〕の場面。美男美女で優雅であり、個人的に“源氏物語”っぽく見えてしまった。
但し、この“ご夫婦”、恋多き男女とは真逆。まるで、二昔くらい前の少女マンガでしか見られないような、一途な純愛物語と言ってよさそうだ。
――そして妻・和宮が、夫・家茂への気持ちを詠んだ和歌には、
涙を誘うような想いが伝わる一首がある。『青天を衝け』でも一瞬、この内容の場面が登場したが、ここでは詳細を差し控える。
妻だけでなく、幕臣たちからも慕われた“上様”だったのか。京都で苦境にあった将軍・徳川家茂を救おうとした人物もいた。
こちらも現在の佐賀県にある、唐津藩の小笠原長行。将軍・家茂を苦しめる攘夷派を一掃すべく、軍勢を率い、京都へ乗り込もうとした史実があるようだ。
――こうして、私の新春一本目の調査(?)は完了した。
「…叔父上。あの写真。どうにか、幕末の佐賀とつながりました。」
この記事が、調査報告だ。実際のところ叔父上は「あんまり無理ばせんと。」とよく言ってくれる。たぶん今回も、そうだろう。
佐賀県全体に通じる“物語”を描こうとする試み…“本編”を描く道のりは、今年も険しそうだ。
2022年03月05日
「再会の剣」
こんにちは。
2日ばかり、『さがファンブログ』が閲覧できず、色々と想う事がありました。
私は遠方に住んでいますが、このブログで“佐賀の日常”は身近にあります。復旧まで、郷里から切り離された感覚になったのは、結構辛いところでした。
なお、『さがファンブログ』のトップページから参照したところ、愛知県や静岡県などの一部地域ブログでも類似の現象は見られたようです。
時おり書いています「望郷の剣」シリーズ。私の一風変わった郷里への想いを綴ります。ここから、ブログを再開していきたいと思います。
――「暗闇でしか 見えぬものがある。」
連続テレビ小説(朝ドラ)『カムカムエヴリバディ』をご覧の方なら、聞き慣れたフレーズだろう。私はごく最近、見始めた新参者だ。
〔参照:「急に“朝ドラ”にハマる。」〕
今月3日の朝。いつものように『さがファンブログ』を確認しようとした私の目前に、突如として“暗闇”は現れた。
…いや、厳密に言えば、画面が遷移せず“暗闇”のままだった。
「何か異変があったのか…。」
たまに、そういう事もあるのだろう。電車を乗り継いでの通勤の途上でもあり、さほど気にもしていなかった。

※2019「サガ・ライトファンタジー」開催期間中に撮影
――その日。午前の仕事は波乱含みの展開。ひとまずお昼を取る。
「さて、ブログは見られるだろうか…。」
何か佐賀とつながる事で、少しでも気力を回復したかったが、やはり私の端末からは閲覧ができなかった。
まだ、暗闇は続く。その日の夜も、状況は変わらなかった。習慣になっていたものが、見られないのは気になるものだ。
その原因と、復旧の目途はもちろんだが、様々な事が気になってくる。毎日、投稿する“さがファンブロガー”の方々も似たような状態にあるのだろうか。
――本来ならば、見られたはずの…
今日は、佐賀の“街ネタ”があったのだろうか、県内で東や西にいるネコたちは元気にやっているだろうか…
家族のエピソードや、丁寧な手仕事、良い風景が撮れれば記事を作成する方々も、私と同じ状況なら、定めし…モヤモヤとしていることだろう。
私の記事を見てくれたはずの人も“空振り”になったか…も少し気になった。
――「私は佐賀に居ない。2年以上、帰れてもいない…」
「…にも関わらず、もう私はここまで佐賀とつながっていたのか!」というのは、一種の驚きだった。
自覚はしていなかった。これは“暗闇”に入ってみて、はじめて見えたことだ。
私の気持ちは、あたかも「何かの密命による探索中に、本藩との連絡が途切れた佐賀藩士(?)」のようだった。

――「暗闇でしか 聴こえぬ歌がある。」
言うなれば、私は耳を澄ませた。周辺状況を探り始めたのである。情報は少なかったが、概ね何が起きていたのかはわかった。
しかし、とりあえずは復旧を待つことしかできない。佐賀を語りたい私にとって、他のブログサービスでは得がたい価値がここにはあるからだ。
ここで、連続テレビ小説(朝ドラ)のセリフを、もう1つ振り返る。現在の主人公・大月ひなた〔演:川栄李奈〕の、幼少期〔演:新津ちせ(子役)〕が発した一言。
――「わたし… 侍になりたいです!」
幼い女の子が目をキラキラさせて語る。3人目の主人公・ひなたはラジオの英語講座が続かない子と描かれたと思う。この頃はしっかり視聴していない…
そんな幼少期のひなたは、テレビ時代劇の大スター“モモケン”こと、二代目・桃山剣之介〔演:尾上菊之助〕と対面して、この言葉を発した。
その“回想”場面が、たしかブログが見られなくなる直前の放送回で出た。この時、モモケンからひなた(子役)への返答がある。
――「志を失わなければ、きっとなれますよ。」
この言葉が、視聴する私の胸には妙に染みていた。この朝ドラでは、侍は「こうと決めたことはやり遂げる、意志の強い者」として語られるようだ。
ブログが復旧するまでの間、佐賀とつながれない時を経て、私も考えさせられた。月並みな結論だが、これは「初心を忘れるな」ということなのかもしれない。
――ちなみに、本日のタイトルを“再会”としたのは、
私が記事を投稿できるだけでなく、また、皆様のブログも見られるようになったからです。いつものような“佐賀の日常”を楽しみにしております。
2日ばかり、『さがファンブログ』が閲覧できず、色々と想う事がありました。
私は遠方に住んでいますが、このブログで“佐賀の日常”は身近にあります。復旧まで、郷里から切り離された感覚になったのは、結構辛いところでした。
なお、『さがファンブログ』のトップページから参照したところ、愛知県や静岡県などの一部地域ブログでも類似の現象は見られたようです。
時おり書いています「望郷の剣」シリーズ。私の一風変わった郷里への想いを綴ります。ここから、ブログを再開していきたいと思います。
――「暗闇でしか 見えぬものがある。」
連続テレビ小説(朝ドラ)『カムカムエヴリバディ』をご覧の方なら、聞き慣れたフレーズだろう。私はごく最近、見始めた新参者だ。
〔参照:
今月3日の朝。いつものように『さがファンブログ』を確認しようとした私の目前に、突如として“暗闇”は現れた。
…いや、厳密に言えば、画面が遷移せず“暗闇”のままだった。
「何か異変があったのか…。」
たまに、そういう事もあるのだろう。電車を乗り継いでの通勤の途上でもあり、さほど気にもしていなかった。
※2019「サガ・ライトファンタジー」開催期間中に撮影
――その日。午前の仕事は波乱含みの展開。ひとまずお昼を取る。
「さて、ブログは見られるだろうか…。」
何か佐賀とつながる事で、少しでも気力を回復したかったが、やはり私の端末からは閲覧ができなかった。
まだ、暗闇は続く。その日の夜も、状況は変わらなかった。習慣になっていたものが、見られないのは気になるものだ。
その原因と、復旧の目途はもちろんだが、様々な事が気になってくる。毎日、投稿する“さがファンブロガー”の方々も似たような状態にあるのだろうか。
――本来ならば、見られたはずの…
今日は、佐賀の“街ネタ”があったのだろうか、県内で東や西にいるネコたちは元気にやっているだろうか…
家族のエピソードや、丁寧な手仕事、良い風景が撮れれば記事を作成する方々も、私と同じ状況なら、定めし…モヤモヤとしていることだろう。
私の記事を見てくれたはずの人も“空振り”になったか…も少し気になった。
――「私は佐賀に居ない。2年以上、帰れてもいない…」
「…にも関わらず、もう私はここまで佐賀とつながっていたのか!」というのは、一種の驚きだった。
自覚はしていなかった。これは“暗闇”に入ってみて、はじめて見えたことだ。
私の気持ちは、あたかも「何かの密命による探索中に、本藩との連絡が途切れた佐賀藩士(?)」のようだった。
――「暗闇でしか 聴こえぬ歌がある。」
言うなれば、私は耳を澄ませた。周辺状況を探り始めたのである。情報は少なかったが、概ね何が起きていたのかはわかった。
しかし、とりあえずは復旧を待つことしかできない。佐賀を語りたい私にとって、他のブログサービスでは得がたい価値がここにはあるからだ。
ここで、連続テレビ小説(朝ドラ)のセリフを、もう1つ振り返る。現在の主人公・大月ひなた〔演:川栄李奈〕の、幼少期〔演:新津ちせ(子役)〕が発した一言。
――「わたし… 侍になりたいです!」
幼い女の子が目をキラキラさせて語る。3人目の主人公・ひなたはラジオの英語講座が続かない子と描かれたと思う。この頃はしっかり視聴していない…
そんな幼少期のひなたは、テレビ時代劇の大スター“モモケン”こと、二代目・桃山剣之介〔演:尾上菊之助〕と対面して、この言葉を発した。
その“回想”場面が、たしかブログが見られなくなる直前の放送回で出た。この時、モモケンからひなた(子役)への返答がある。
――「志を失わなければ、きっとなれますよ。」
この言葉が、視聴する私の胸には妙に染みていた。この朝ドラでは、侍は「こうと決めたことはやり遂げる、意志の強い者」として語られるようだ。
ブログが復旧するまでの間、佐賀とつながれない時を経て、私も考えさせられた。月並みな結論だが、これは「初心を忘れるな」ということなのかもしれない。
――ちなみに、本日のタイトルを“再会”としたのは、
私が記事を投稿できるだけでなく、また、皆様のブログも見られるようになったからです。いつものような“佐賀の日常”を楽しみにしております。
タグ :佐賀
2022年06月24日
「醒覚の剣(蛙歌)」
こんばんは。
私は“大河ドラマ”を意識してブログを進めているため、テレビなどのメディアで「佐賀が、どのように伝えられるか」に、かなり注目している方だと思います。
佐賀出身の芸能人を多く見るわけではありませんが、最近では「佐賀への愛」を臆せずに語る傾向も出てきた…と感じるところです。
コメントの類型(パターン)は幾つかありますが、まず「食べ物が美味しい」は、よく聞きます。納得の答えです。
――そして「疲れた人には、佐賀はお勧めできる…」と。
ここからは、ありふれた日常をどことなく、幕末っぽく語るシリーズです。最近、やや疲れ気味の私に、佐賀から届いた“音”がありました。

「そろそろ、落ち着いて来たとよ。」
私の電話は佐賀県へとつながっている。声の主は、叔父上である。
猛威をふるった新型コロナの影響も弱まり、大都市圏から佐賀に帰省できた人も多いだろう。そろそろ郷里との往来も可能のはずだ。
――私がブログを始めてから、記事は通算500本を超えた。
その期間は概ね2年半になる。主に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを書き連ねてきたのだが、実はこの間、一度も佐賀に帰れてはいない。
「…今度は別の理由で、なかなか帰れそうにありません。」
いろいろとタイミングに不都合がある。動ける可能性のある時には“緊急事態宣言”にぶつかり、“警戒”が緩んでいる時には、仕事等が忙しい。
――そんな経過もあり、叔父上は私に代わって…
写真素材の確保を引き受けてくれており、県内各地を探索中の状況にある。
「ちょっと地図を見てくるばい、」
電話を携えて、叔父上は車に置いた地図を取るのか、屋外へと出た様子だ。
「ゲコゲコ…ケロケロ、グワッグワッ…」
叔父上の移動中。不意に電話へと語りかけてきたのは、佐賀に住む蛙たち。まさに『かえるの合唱』が、遠方にいる私の耳にまで届く…
――「叔父上、こちらにも“かえるの歌”が聞こえる…」
「あ~、いつもの事やけん。気にもせんかったよ。」
佐賀の六月である、四方の水田から響き渡るは“蛙の歌声”。地元に居れば、いちいち心が動く事ではないだろう。
しかし、もはや四周が“コンクリートジャングル”と言ってしまってよい、無機質な暮らしぶりの私には響くものがある。

都市圏域でも少し移動すれば、さすがに蛙ぐらいは豊富に居るはずなのだが、何やら“佐賀の蛙”は、私に直接、語りかけてくる感じがした。
――「早う、帰って来んね。」
実際のところ、ケロケロ、クワックワッ…と、恵みの雨の予感に喜んでいるだけかもしれない。但し蛙たちとて、豪雨は願い下げだろう、ほどよく降ってほしい。
そんな蛙の歌に耳を澄ませる。私には「たまには、顔ぐらい出さんね。」という、メッセージにも感じられるのだ。
佐賀のカエルには「そがんこと、言っとらんばい。」と異論があるかもしれないが、私はそう受け取った。
――「月並みだが、何とか近々に“かえる”としよう。」
安直だが、私はそう考えた。“佐賀の蛙歌”は、乾いた心に染み入って、潤いをもたらしたのである。
「まさか…カエルで、そんなに喜ぶとは思わんかったよ。」
叔父上が苦笑するのは電話口にもわかる様子だが、それはそれで良かった。
こうして、幕末の佐賀藩を追い求めるだけでなく、いまの佐賀県もどうにか語りたい…また、そんな想いに至るのだった。
私は“大河ドラマ”を意識してブログを進めているため、テレビなどのメディアで「佐賀が、どのように伝えられるか」に、かなり注目している方だと思います。
佐賀出身の芸能人を多く見るわけではありませんが、最近では「佐賀への愛」を臆せずに語る傾向も出てきた…と感じるところです。
コメントの類型(パターン)は幾つかありますが、まず「食べ物が美味しい」は、よく聞きます。納得の答えです。
――そして「疲れた人には、佐賀はお勧めできる…」と。
ここからは、ありふれた日常をどことなく、幕末っぽく語るシリーズです。最近、やや疲れ気味の私に、佐賀から届いた“音”がありました。
「そろそろ、落ち着いて来たとよ。」
私の電話は佐賀県へとつながっている。声の主は、叔父上である。
猛威をふるった新型コロナの影響も弱まり、大都市圏から佐賀に帰省できた人も多いだろう。そろそろ郷里との往来も可能のはずだ。
――私がブログを始めてから、記事は通算500本を超えた。
その期間は概ね2年半になる。主に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを書き連ねてきたのだが、実はこの間、一度も佐賀に帰れてはいない。
「…今度は別の理由で、なかなか帰れそうにありません。」
いろいろとタイミングに不都合がある。動ける可能性のある時には“緊急事態宣言”にぶつかり、“警戒”が緩んでいる時には、仕事等が忙しい。
――そんな経過もあり、叔父上は私に代わって…
写真素材の確保を引き受けてくれており、県内各地を探索中の状況にある。
「ちょっと地図を見てくるばい、」
電話を携えて、叔父上は車に置いた地図を取るのか、屋外へと出た様子だ。
「ゲコゲコ…ケロケロ、グワッグワッ…」
叔父上の移動中。不意に電話へと語りかけてきたのは、佐賀に住む蛙たち。まさに『かえるの合唱』が、遠方にいる私の耳にまで届く…
――「叔父上、こちらにも“かえるの歌”が聞こえる…」
「あ~、いつもの事やけん。気にもせんかったよ。」
佐賀の六月である、四方の水田から響き渡るは“蛙の歌声”。地元に居れば、いちいち心が動く事ではないだろう。
しかし、もはや四周が“コンクリートジャングル”と言ってしまってよい、無機質な暮らしぶりの私には響くものがある。
都市圏域でも少し移動すれば、さすがに蛙ぐらいは豊富に居るはずなのだが、何やら“佐賀の蛙”は、私に直接、語りかけてくる感じがした。
――「早う、帰って来んね。」
実際のところ、ケロケロ、クワックワッ…と、恵みの雨の予感に喜んでいるだけかもしれない。但し蛙たちとて、豪雨は願い下げだろう、ほどよく降ってほしい。
そんな蛙の歌に耳を澄ませる。私には「たまには、顔ぐらい出さんね。」という、メッセージにも感じられるのだ。
佐賀のカエルには「そがんこと、言っとらんばい。」と異論があるかもしれないが、私はそう受け取った。
――「月並みだが、何とか近々に“かえる”としよう。」
安直だが、私はそう考えた。“佐賀の蛙歌”は、乾いた心に染み入って、潤いをもたらしたのである。
「まさか…カエルで、そんなに喜ぶとは思わんかったよ。」
叔父上が苦笑するのは電話口にもわかる様子だが、それはそれで良かった。
こうして、幕末の佐賀藩を追い求めるだけでなく、いまの佐賀県もどうにか語りたい…また、そんな想いに至るのだった。
タグ :佐賀
2022年08月29日
「望郷の剣6」
こんばんは。
今夏の前に実行した佐賀への“帰藩”の記録を続けていますが、合間に別の話も入れています。
最近ではなかなか、まとまった時間が取れない事もあり、“本編”はお休み中。旅日記と雑談ばかりを綴っている…というのが、現況です。
ひとまず一度は佐賀に帰れたものの、また新型コロナの第七波、積み重なる仕事での苦悩、降り注ぐ内外の雑事…
これは、言うなれば“四方の敵”と向き合う中で見る幻覚なのか。本日も、私の「望郷の叫び」をお聞きください。

――「いろいろ、片付かない…!」
今日も都会の片隅で、私なりの“戦い”は続いている。
私とて、次々と手を繰り出すが、一刀のもとにスッキリ解決することは少ない。時に押し込んで、時には引いての苦闘が続く。
こういう時にはNHK大河ドラマではなく、今やほとんど放映される枠の無い、民放のテレビ時代劇を想い出す。
よく『○○の剣』というタイトルの投稿をする私。さぞや、“腕が立つ”人物かと思っている方が、もし居るならば先に言っておきたい。
――「私に、大した腕前は無い!」
何も、声を大にして言うことでもないのだが、“痛快娯楽時代劇”の主人公のような立ち回りは到底できない。
逆に共感できるのは、よく各種時代劇の1回限りのゲストに出てくる「一応、剣の心得はある様子だが、それほど強くない侍」だ。
そういった人物がラストまで生き残れるかどうかは、その時代劇の物語の系統によるのだろう。
――そんな侍は、大体、一人か二人の敵にも苦戦する。
どうにか剣を抜き、相手の斬り込みは受け止めるが、刀を弾いて押し返すので、精一杯という感じだろうか。
戦乱が少なく、穏やかな時期が長かった江戸時代。武士にとって、刀は武器というより“身分証明”のようなものだったと聞いた事がある。

――現代風に言えば、“IDカード”だろうか。
こう考えると、普通の会社員のようだ。そして幕末の動乱期にも、佐賀藩士がどこかでチャンバラをしていた話はほとんど聞かない。
もちろん腕の立つ剣士は居たようなので、ここは、たぶん佐賀の殿様の統制力だ。うっかり家来が暴発しないよう抑えていたのだろう。
――そして私が書く『○○の剣』も、武勇伝とは、ほど遠い。
…というわけで、先の喩(たと)えによると、私の運命の分かれ道は、ヒーローが来るまで粘れるかどうかである。
一方で、日々の仕事は思うに任せない。膠着状態のまま、その日は切り上げとなり、帰路に着いた。
このところ熱帯夜が続く。水田からの涼風も期待できない、四周がコンクリートジャングルの街。都会的な暑さでボーッとした私は、コンビニに退避した。
――「どがんしたとね?えろう、へばっとる様子ばい。」
ある棚から、一陣の涼風が吹いた気がした。佐賀ことば風のセリフだが、誰か助っ人でも来たのか。
私は、この感覚のもとを見つけた。
「…モンブラン!?ブラックモンブランでは…!?なぜ、ここに?」
そこには、佐賀県の小城を拠点に、九州氷菓の代表格として名を轟かせる、アイスバー“ブラックモンブラン”の姿があった。

――以前は、九州にしか登場しなかったはずの“ブラックモンブラン”。
私は目を疑った。いつの間にか、この店で定番商品の座についている様子だ。
「ブラックモンブラン。ここまで来てくれて嬉しい。ただ、私には持ち帰るすべが無い…。」
「おいは、何度でも現れるけん。気にせんで、よか。」
「そうなのか、そういう事になったのか?」
私はまだ、状況が飲み込めていない。これからは、お子様からお年寄りにまで愛される九州の“ヒーロー“が、私の傍に居てくれるというのか。
――「心が折れそうになったら、いつでも、おいを訪ねるとよかばい。」
「ありがとう、モンブラン~。ブラックモンブラン~!」
ああ、雪山に声が響くようなこの感覚。涼しい…。とりあえず、保冷バックさえ持ってきたら普通に買えそうだ。
アルプスの最高峰(モンブラン)を見て、その雪山にチョコをかけたら、さぞ美味しいだろうという、壮大な着想から誕生したと聞く“ブラックモンブラン”。
各地で販路開拓を進めるとは聞いていたが、私の近くにも来ていたとは。
――佐賀銘菓である羊羹の“聖地”・小城から来たアイスバー。
何やら、後ろに“ブラックモンブラン”が控えていると思うだけで、少しは心強く思ってしまう私である。

…以上、当ブログをいつもご覧の皆様には「また、始まったか」という、おなじみの展開をお送りしました。
ちなみに本記事は『ブラックモンブラン』の製造元である、竹下製菓さまとは何ら関係がありません。
その商品に思い入れの強い、1人の佐賀出身者の戯れ言と、お聞き流しいただければと思います。
今夏の前に実行した佐賀への“帰藩”の記録を続けていますが、合間に別の話も入れています。
最近ではなかなか、まとまった時間が取れない事もあり、“本編”はお休み中。旅日記と雑談ばかりを綴っている…というのが、現況です。
ひとまず一度は佐賀に帰れたものの、また新型コロナの第七波、積み重なる仕事での苦悩、降り注ぐ内外の雑事…
これは、言うなれば“四方の敵”と向き合う中で見る幻覚なのか。本日も、私の「望郷の叫び」をお聞きください。
――「いろいろ、片付かない…!」
今日も都会の片隅で、私なりの“戦い”は続いている。
私とて、次々と手を繰り出すが、一刀のもとにスッキリ解決することは少ない。時に押し込んで、時には引いての苦闘が続く。
こういう時にはNHK大河ドラマではなく、今やほとんど放映される枠の無い、民放のテレビ時代劇を想い出す。
よく『○○の剣』というタイトルの投稿をする私。さぞや、“腕が立つ”人物かと思っている方が、もし居るならば先に言っておきたい。
――「私に、大した腕前は無い!」
何も、声を大にして言うことでもないのだが、“痛快娯楽時代劇”の主人公のような立ち回りは到底できない。
逆に共感できるのは、よく各種時代劇の1回限りのゲストに出てくる「一応、剣の心得はある様子だが、それほど強くない侍」だ。
そういった人物がラストまで生き残れるかどうかは、その時代劇の物語の系統によるのだろう。
――そんな侍は、大体、一人か二人の敵にも苦戦する。
どうにか剣を抜き、相手の斬り込みは受け止めるが、刀を弾いて押し返すので、精一杯という感じだろうか。
戦乱が少なく、穏やかな時期が長かった江戸時代。武士にとって、刀は武器というより“身分証明”のようなものだったと聞いた事がある。
――現代風に言えば、“IDカード”だろうか。
こう考えると、普通の会社員のようだ。そして幕末の動乱期にも、佐賀藩士がどこかでチャンバラをしていた話はほとんど聞かない。
もちろん腕の立つ剣士は居たようなので、ここは、たぶん佐賀の殿様の統制力だ。うっかり家来が暴発しないよう抑えていたのだろう。
――そして私が書く『○○の剣』も、武勇伝とは、ほど遠い。
…というわけで、先の喩(たと)えによると、私の運命の分かれ道は、ヒーローが来るまで粘れるかどうかである。
一方で、日々の仕事は思うに任せない。膠着状態のまま、その日は切り上げとなり、帰路に着いた。
このところ熱帯夜が続く。水田からの涼風も期待できない、四周がコンクリートジャングルの街。都会的な暑さでボーッとした私は、コンビニに退避した。
――「どがんしたとね?えろう、へばっとる様子ばい。」
ある棚から、一陣の涼風が吹いた気がした。佐賀ことば風のセリフだが、誰か助っ人でも来たのか。
私は、この感覚のもとを見つけた。
「…モンブラン!?ブラックモンブランでは…!?なぜ、ここに?」
そこには、佐賀県の小城を拠点に、九州氷菓の代表格として名を轟かせる、アイスバー“ブラックモンブラン”の姿があった。
――以前は、九州にしか登場しなかったはずの“ブラックモンブラン”。
私は目を疑った。いつの間にか、この店で定番商品の座についている様子だ。
「ブラックモンブラン。ここまで来てくれて嬉しい。ただ、私には持ち帰るすべが無い…。」
「おいは、何度でも現れるけん。気にせんで、よか。」
「そうなのか、そういう事になったのか?」
私はまだ、状況が飲み込めていない。これからは、お子様からお年寄りにまで愛される九州の“ヒーロー“が、私の傍に居てくれるというのか。
――「心が折れそうになったら、いつでも、おいを訪ねるとよかばい。」
「ありがとう、モンブラン~。ブラックモンブラン~!」
ああ、雪山に声が響くようなこの感覚。涼しい…。とりあえず、保冷バックさえ持ってきたら普通に買えそうだ。
アルプスの最高峰(モンブラン)を見て、その雪山にチョコをかけたら、さぞ美味しいだろうという、壮大な着想から誕生したと聞く“ブラックモンブラン”。
各地で販路開拓を進めるとは聞いていたが、私の近くにも来ていたとは。
――佐賀銘菓である羊羹の“聖地”・小城から来たアイスバー。
何やら、後ろに“ブラックモンブラン”が控えていると思うだけで、少しは心強く思ってしまう私である。
…以上、当ブログをいつもご覧の皆様には「また、始まったか」という、おなじみの展開をお送りしました。
ちなみに本記事は『ブラックモンブラン』の製造元である、竹下製菓さまとは何ら関係がありません。
その商品に思い入れの強い、1人の佐賀出身者の戯れ言と、お聞き流しいただければと思います。
2023年12月23日
「遠路の剣(雑踏)」
こんばんは。
今年も残り、あと1週間ほどになりました。
執筆者として、この1年を振り返ると「書きたい事が浮かんできてもまとめる力に欠けた」という印象です。この状態は今も変わっていません。
今年も、たびたび“帰藩”を叫ぶも、なかなか佐賀県に近づくこともできない私。逆に、つい最近、県内に住む叔父上が、こちらを訪ねてきたことがありました。

当ブログでは時折、『○○の剣』という大層なタイトルの記事を投稿しますが、もともとは、私の文章の練習から始まったシリーズです。
〔参照:「望郷の剣」〕
そのため、“本編”っぽい台詞回しもありますが、内容は長い日記みたいなものなので、気楽にお読みいただければ幸いです。
――ある、晩秋の日。叔父上から電話が入った。
「あぁ、叔父上。息災ですか。」
「元気とよ。それはよかけん、今度、そっちの近くまで行くことになったとよ。」
今年も、佐賀に行くためのまとまった時間は取れなかった。仕事や雑務に追われても、若ければ気力と体力で補うが、どちらも決定的に不足している。
「…え、叔父上が、こちらに来るのですか。」
私も歳を取ってきているのだから、叔父上が若いまま…ということはない。相応の年齢とそれなりの持病もある。

叔父上も、また「枯れても走ることを命と呼べ」という心持ちなのか。
――聞けば、旅行社のツアーで近くまで来るのだという、
しばらく、新型コロナ禍の影響で動けていなかった反動もあるのか、叔父上の動きも最近では活発である。
少し前、「青春って密なので」という言葉を聞いたが、年寄りの場合も、自在に動ける残り年数は限られる。その時間は、意外と“密”であり、貴重なのだ。
「近くに寄るけん、時間があったら、会えんかにゃ。」
「…ほう、私が佐賀県まで行かずとも、こちらで会えるという事ですか。」

当ブログで使う県内と周辺の写真は叔父上が撮ったものも多い。電話や郵便でのやり取りはよく行っているが、直接、会えてはいなかった。
――実際には、4年ほど対面していない。
私の住む街の近隣まで来るのなら、再会の好機と見てよいだろう。
「週末なら、会いに行けるくらいの時間はあります。」
「よかたい。そいじゃ、よろしく頼むとよ。」
叔父上からの頼まれ事もあり、週末に私はターミナル駅まで出向くこととした。
――そして、師走に入ってからの、ある週末に。
私はターミナル駅まで来ていた。四方八方からキャリーケースの車輪の音をガラガラと響かせながら、大勢の人が不規則に動いている。
概ね、待ち合わせ場所は決めていたものの、この人の数だ。あぁ大都市圏。もはや、人が人の影で見えなくなっている。
何やら、どこまでも、佐賀が遠く霞むような心地がした…

「さて叔父上は、到着しているのか…」
一瞬、ボーッとして、意識が佐賀駅近くまで飛んでいたが、気を取り直した私。
ここは、大都会の雑踏の中である。
この際、電話をかけて連絡をとる事にする。携帯電話のない、昔の待ち合わせならば、なかなか会うことができない状況だろう。
「待ち合わせでのすれ違い」それはそれで、ドラマ性がある響きだが、たぶん現代人には、そんな余裕はない。
――私は、携帯を手にして発信をしながらも、周囲を見回した。
ガチャッ。電話が通話状態となる。
「おじうえ~、どちらですか~」
「あ、もう着いてるとよ。」
ひょっとすると、今居るフロア(階数)が違うのか。私は、四周の人波を避けながら、叔父上を探した。

ごったがえす人々の動きは、まるで水の粒が集まって、大河の渦となるが如くに、ガヤガヤと流れに流れている。
文字・映像・音声…と情報量が多すぎるターミナル駅。私とて、日々の通勤で鍛えてはいるが、朝のラッシュ時よりも、人の流れが読みづらい。
…待ち人を探すには、かなり騒々しく、手強い環境である。
――このような都市圏の状況を表すのに、
“過剰負荷環境”という言葉があり、人間の脳の処理能力が、情報の多さに追いつかない事を示すらしい。
「田舎の人に比べて、都会の人は冷たく感じる」と言われる理由は、都会の人が、今より情報を増やさないよう防御するからだ…と
たしかNHKの番組『チコちゃんに叱られる』では、そんな説明だった。もはや、「ボーッと生きる」は贅沢なのだ…そんな気分も感じる、せわしない年末だ。

――話を戻す。私は通話を続けたままで、叔父上を探した。
「あ、叔父上…見っけ。」
私の視界には、4年前と全然、変わらない叔父上の姿が入る。どうやら、まだ移動しながら話していたらしい。
「おじうえ~、そこに居ましたか!」
「そがんね。で、“SR”くんは、どこに居っとね?」
叔父上からは、私を見つけられていない様子だ。電話でつながりながら、ご本人まで近づく、これは昭和や平成初期には無かった、待ち合わせの景色だ。
――私は歩みを進めながら、軽く手を振った。
「ここです。叔父上!」
「…ん、どこね?」
「目の前にいます。“ぶんぶんぶん”と、手を振りよるです!」
今度は携帯を耳にあてている、叔父上の目線を遮るように、手を振った。
「あ、そこに居ったね。前より痩せとったし、マスクで気付かんかったばい。」
…どうやら、私の方は叔父上と会っていなかった、この4年で、幾分、変わってしまったらしい。
(この話は…気が向いたら、続きを書きます)
今年も残り、あと1週間ほどになりました。
執筆者として、この1年を振り返ると「書きたい事が浮かんできてもまとめる力に欠けた」という印象です。この状態は今も変わっていません。
今年も、たびたび“帰藩”を叫ぶも、なかなか佐賀県に近づくこともできない私。逆に、つい最近、県内に住む叔父上が、こちらを訪ねてきたことがありました。

当ブログでは時折、『○○の剣』という大層なタイトルの記事を投稿しますが、もともとは、私の文章の練習から始まったシリーズです。
〔参照:
そのため、“本編”っぽい台詞回しもありますが、内容は長い日記みたいなものなので、気楽にお読みいただければ幸いです。
――ある、晩秋の日。叔父上から電話が入った。
「あぁ、叔父上。息災ですか。」
「元気とよ。それはよかけん、今度、そっちの近くまで行くことになったとよ。」
今年も、佐賀に行くためのまとまった時間は取れなかった。仕事や雑務に追われても、若ければ気力と体力で補うが、どちらも決定的に不足している。
「…え、叔父上が、こちらに来るのですか。」
私も歳を取ってきているのだから、叔父上が若いまま…ということはない。相応の年齢とそれなりの持病もある。
叔父上も、また「枯れても走ることを命と呼べ」という心持ちなのか。
――聞けば、旅行社のツアーで近くまで来るのだという、
しばらく、新型コロナ禍の影響で動けていなかった反動もあるのか、叔父上の動きも最近では活発である。
少し前、「青春って密なので」という言葉を聞いたが、年寄りの場合も、自在に動ける残り年数は限られる。その時間は、意外と“密”であり、貴重なのだ。
「近くに寄るけん、時間があったら、会えんかにゃ。」
「…ほう、私が佐賀県まで行かずとも、こちらで会えるという事ですか。」
当ブログで使う県内と周辺の写真は叔父上が撮ったものも多い。電話や郵便でのやり取りはよく行っているが、直接、会えてはいなかった。
――実際には、4年ほど対面していない。
私の住む街の近隣まで来るのなら、再会の好機と見てよいだろう。
「週末なら、会いに行けるくらいの時間はあります。」
「よかたい。そいじゃ、よろしく頼むとよ。」
叔父上からの頼まれ事もあり、週末に私はターミナル駅まで出向くこととした。
――そして、師走に入ってからの、ある週末に。
私はターミナル駅まで来ていた。四方八方からキャリーケースの車輪の音をガラガラと響かせながら、大勢の人が不規則に動いている。
概ね、待ち合わせ場所は決めていたものの、この人の数だ。あぁ大都市圏。もはや、人が人の影で見えなくなっている。
何やら、どこまでも、佐賀が遠く霞むような心地がした…
「さて叔父上は、到着しているのか…」
一瞬、ボーッとして、意識が佐賀駅近くまで飛んでいたが、気を取り直した私。
ここは、大都会の雑踏の中である。
この際、電話をかけて連絡をとる事にする。携帯電話のない、昔の待ち合わせならば、なかなか会うことができない状況だろう。
「待ち合わせでのすれ違い」それはそれで、ドラマ性がある響きだが、たぶん現代人には、そんな余裕はない。
――私は、携帯を手にして発信をしながらも、周囲を見回した。
ガチャッ。電話が通話状態となる。
「おじうえ~、どちらですか~」
「あ、もう着いてるとよ。」
ひょっとすると、今居るフロア(階数)が違うのか。私は、四周の人波を避けながら、叔父上を探した。

ごったがえす人々の動きは、まるで水の粒が集まって、大河の渦となるが如くに、ガヤガヤと流れに流れている。
文字・映像・音声…と情報量が多すぎるターミナル駅。私とて、日々の通勤で鍛えてはいるが、朝のラッシュ時よりも、人の流れが読みづらい。
…待ち人を探すには、かなり騒々しく、手強い環境である。
――このような都市圏の状況を表すのに、
“過剰負荷環境”という言葉があり、人間の脳の処理能力が、情報の多さに追いつかない事を示すらしい。
「田舎の人に比べて、都会の人は冷たく感じる」と言われる理由は、都会の人が、今より情報を増やさないよう防御するからだ…と
たしかNHKの番組『チコちゃんに叱られる』では、そんな説明だった。もはや、「ボーッと生きる」は贅沢なのだ…そんな気分も感じる、せわしない年末だ。

――話を戻す。私は通話を続けたままで、叔父上を探した。
「あ、叔父上…見っけ。」
私の視界には、4年前と全然、変わらない叔父上の姿が入る。どうやら、まだ移動しながら話していたらしい。
「おじうえ~、そこに居ましたか!」
「そがんね。で、“SR”くんは、どこに居っとね?」
叔父上からは、私を見つけられていない様子だ。電話でつながりながら、ご本人まで近づく、これは昭和や平成初期には無かった、待ち合わせの景色だ。
――私は歩みを進めながら、軽く手を振った。
「ここです。叔父上!」
「…ん、どこね?」
「目の前にいます。“ぶんぶんぶん”と、手を振りよるです!」
今度は携帯を耳にあてている、叔父上の目線を遮るように、手を振った。
「あ、そこに居ったね。前より痩せとったし、マスクで気付かんかったばい。」
…どうやら、私の方は叔父上と会っていなかった、この4年で、幾分、変わってしまったらしい。
(この話は…気が向いたら、続きを書きます)
タグ :佐賀
2023年12月29日
「遠路の剣Ⅱ(金波)」
こんばんは。
すでに年の瀬ですが、気にせず続けます。当ブログでは佐賀県に行くことを“帰藩”として語ることが多いですが、私は今年も帰れませんでした。
ところで、江戸期に佐賀藩ではなかった、佐賀県内の唐津(唐津藩)や、基山(対馬藩田代領)に行くことがあったなら、それは“帰藩”に数えて良いのか?
…という課題は、実際に行くことができてから考えます。

そして、私が佐賀に行く代わり…でもないのですが、叔父上がこちらに来た時の話を、長い日記のように綴るシリーズ、2回目も書くことにしました。
――叔父上と会ったのは、その旅の終盤。
次の予定も入っているらしく、なかなか慌ただしいスケジュールになっている。
ゆっくり話が出来たのは、移動中の電車内。ここで私は、大都市圏で習得してきた技能を使った。あらゆる予測をたてて、混雑する電車を避けたのだ。

結果、その車内が、一番落ち着いて話ができた。
向かい合った座席。叔父上が私の顔を見て、ふいに言葉を発する。
「“SR”くん。自分だけが、仕事をしよると思うてはならんばい。」
――その時、私は言葉の意味を、うまく拾えなかった。
かつて叔父上が、仕事で相当に苦労していた事は知っている。
たしかに皆、忙しく働いているわけだから疲れているのは、私だけではない。「もうちょっと、頑張ろうよ」という励ましなのかとも考えた。
そういえば、私が崇敬する“佐賀の大先輩”たちは、働き者ぞろいだ。

今年は「憧れるのをやめましょう」という言葉も流行った。だが、私には“大先輩”の背中を追えるほどの能力は無いので、憧れを持つぐらいにしておく。
――話を戻す。乗車した路線は、海に沿って進むようだ。
流れゆく空を眺める、叔父上。会話の内容はさておき、車窓から見えるのは、師走の好天である。光る海も見えてきた。
普段は「無理ば、せんごと…」と気遣ってくれることが多いので、先ほどの言葉も、単なる叱咤激励とは考えにくい。
ただ、今は「よかとね~」という雰囲気で海辺を見つめるものだから、それ以上は私からも、仕事の話をするのは差し控えた。
――まもなく、電車は目的地へと到着する。
「次の駅で、降ります。」
「そうね、思うたより早かったとね。」
次の予定は、郊外に出た海沿いの町にあると聞いていた。私は、その案内役のような役回りをしている。
あわせて、1時間ばかりは走ったか。電車は降車駅のホームへと入線した。

――私も来たことがない、海沿いの町。
下車してからも離れた海が見える。陽光をはじいて、波が金色に彩られる。
「にゃ~、あいつ。良かところに住んどるばい…」
意外だったが、叔父上は、この町に旧知の友がいるのだという。
もとは九州で作った友達のはずが、いろいろな場所に居るものだと感心する。
――友人との待ち合わせまでには、まだ時間があるという。
見た感じ、夏が似合いそうな海辺の町。だが、季節は師走。そこまで、寒くはなくとも12月である。
「珈琲でも、飲みますか。」
「よかごたよ。」
ある店のテラスで、サクサクと美味いがボロボロと崩れるパイをかじりながら、珈琲を飲む。
「身体の疲れは寝たらよかけど、気ば遣こうたら、ざっといかんばい。」
やはり、叔父上の言葉は心配の気持ちの表れだったらしい。今の私からは、疲労感という名の“波動”でも出ているのか…と驚く。
――ゆっくりと珈琲を飲み終えると…
いつの間にか、向こう側の道路に一台の車が止まっている。
「…んにゃ、あいつ、もう来とるばい。」
「あの車ですか。」
「そのうち来ると思うとったけんが、意外と早かったとね。」
この辺り、叔父上は、県内と同じ感覚でゆっつらと構えていたらしい。

その叔父上も、地元では佐賀の者のたしなみなのか、土いじりをする。
優れた注意力は、空を舞い果実を狙いに来る鳥や、地を這って野菜を奪いに来る小動物に向けられるから、旅先の都市圏ではのんびりしてしまっている。
――さて、ここで豪快にして、陽気な感じの年配の方が現れた。
「お前は、もう、来とったんかい。」
「予定よりちょっと、早う着いたとよ。」
叔父上は、その年配の男性に親しげに言葉を返す。これは、学生時代の友人と感動の再会の場面であろうか。
「それにしても、海の近くで、よかところに住んどるとね~。」
「ここに住んどるわけじゃないぞ。車に乗らんと、家には着かん。」
海沿いの景色を讃える叔父上。「家はもっと先だ!」と言葉を返す旧知の友。

「…んにゃ、こがん、きれいか海が見られるだけでよかごた。」
「おう、そんなにいいか?」
冬でも光る海は絵画的というか、詩的というか、上手く形容できないが美しい。
――叔父上があまりにも、自宅の近所を褒めまくるので、
旧知の友人さんも、やはり悪い気はしないらしい。この辺で、後ろに立っていた私の存在に気付いたようだ。
「ところで、一緒にいるのは誰ね?紹介ば、せんね。」
「あぁ、この辺りに住んどる甥っ子ばい。ここまで付いてきてもらったとよ。」
私は案内だけのつもりで行動していたが、期せず叔父上の学生時代の姿を見たような気がした。
長い歳月を経たはずだが、それを“解凍”するように、元の時間に戻っていく。景色だけでなく、この海辺の町で良いものを見た…と、私はそう思った。
(…おそらく、あと1回ぐらいは続きます)
すでに年の瀬ですが、気にせず続けます。当ブログでは佐賀県に行くことを“帰藩”として語ることが多いですが、私は今年も帰れませんでした。
ところで、江戸期に佐賀藩ではなかった、佐賀県内の唐津(唐津藩)や、基山(対馬藩田代領)に行くことがあったなら、それは“帰藩”に数えて良いのか?
…という課題は、実際に行くことができてから考えます。
そして、私が佐賀に行く代わり…でもないのですが、叔父上がこちらに来た時の話を、長い日記のように綴るシリーズ、2回目も書くことにしました。
――叔父上と会ったのは、その旅の終盤。
次の予定も入っているらしく、なかなか慌ただしいスケジュールになっている。
ゆっくり話が出来たのは、移動中の電車内。ここで私は、大都市圏で習得してきた技能を使った。あらゆる予測をたてて、混雑する電車を避けたのだ。
結果、その車内が、一番落ち着いて話ができた。
向かい合った座席。叔父上が私の顔を見て、ふいに言葉を発する。
「“SR”くん。自分だけが、仕事をしよると思うてはならんばい。」
――その時、私は言葉の意味を、うまく拾えなかった。
かつて叔父上が、仕事で相当に苦労していた事は知っている。
たしかに皆、忙しく働いているわけだから疲れているのは、私だけではない。「もうちょっと、頑張ろうよ」という励ましなのかとも考えた。
そういえば、私が崇敬する“佐賀の大先輩”たちは、働き者ぞろいだ。
今年は「憧れるのをやめましょう」という言葉も流行った。だが、私には“大先輩”の背中を追えるほどの能力は無いので、憧れを持つぐらいにしておく。
――話を戻す。乗車した路線は、海に沿って進むようだ。
流れゆく空を眺める、叔父上。会話の内容はさておき、車窓から見えるのは、師走の好天である。光る海も見えてきた。
普段は「無理ば、せんごと…」と気遣ってくれることが多いので、先ほどの言葉も、単なる叱咤激励とは考えにくい。
ただ、今は「よかとね~」という雰囲気で海辺を見つめるものだから、それ以上は私からも、仕事の話をするのは差し控えた。
――まもなく、電車は目的地へと到着する。
「次の駅で、降ります。」
「そうね、思うたより早かったとね。」
次の予定は、郊外に出た海沿いの町にあると聞いていた。私は、その案内役のような役回りをしている。
あわせて、1時間ばかりは走ったか。電車は降車駅のホームへと入線した。
――私も来たことがない、海沿いの町。
下車してからも離れた海が見える。陽光をはじいて、波が金色に彩られる。
「にゃ~、あいつ。良かところに住んどるばい…」
意外だったが、叔父上は、この町に旧知の友がいるのだという。
もとは九州で作った友達のはずが、いろいろな場所に居るものだと感心する。
――友人との待ち合わせまでには、まだ時間があるという。
見た感じ、夏が似合いそうな海辺の町。だが、季節は師走。そこまで、寒くはなくとも12月である。
「珈琲でも、飲みますか。」
「よかごたよ。」
ある店のテラスで、サクサクと美味いがボロボロと崩れるパイをかじりながら、珈琲を飲む。
「身体の疲れは寝たらよかけど、気ば遣こうたら、ざっといかんばい。」
やはり、叔父上の言葉は心配の気持ちの表れだったらしい。今の私からは、疲労感という名の“波動”でも出ているのか…と驚く。
――ゆっくりと珈琲を飲み終えると…
いつの間にか、向こう側の道路に一台の車が止まっている。
「…んにゃ、あいつ、もう来とるばい。」
「あの車ですか。」
「そのうち来ると思うとったけんが、意外と早かったとね。」
この辺り、叔父上は、県内と同じ感覚でゆっつらと構えていたらしい。
その叔父上も、地元では佐賀の者のたしなみなのか、土いじりをする。
優れた注意力は、空を舞い果実を狙いに来る鳥や、地を這って野菜を奪いに来る小動物に向けられるから、旅先の都市圏ではのんびりしてしまっている。
――さて、ここで豪快にして、陽気な感じの年配の方が現れた。
「お前は、もう、来とったんかい。」
「予定よりちょっと、早う着いたとよ。」
叔父上は、その年配の男性に親しげに言葉を返す。これは、学生時代の友人と感動の再会の場面であろうか。
「それにしても、海の近くで、よかところに住んどるとね~。」
「ここに住んどるわけじゃないぞ。車に乗らんと、家には着かん。」
海沿いの景色を讃える叔父上。「家はもっと先だ!」と言葉を返す旧知の友。
「…んにゃ、こがん、きれいか海が見られるだけでよかごた。」
「おう、そんなにいいか?」
冬でも光る海は絵画的というか、詩的というか、上手く形容できないが美しい。
――叔父上があまりにも、自宅の近所を褒めまくるので、
旧知の友人さんも、やはり悪い気はしないらしい。この辺で、後ろに立っていた私の存在に気付いたようだ。
「ところで、一緒にいるのは誰ね?紹介ば、せんね。」
「あぁ、この辺りに住んどる甥っ子ばい。ここまで付いてきてもらったとよ。」
私は案内だけのつもりで行動していたが、期せず叔父上の学生時代の姿を見たような気がした。
長い歳月を経たはずだが、それを“解凍”するように、元の時間に戻っていく。景色だけでなく、この海辺の町で良いものを見た…と、私はそう思った。
(…おそらく、あと1回ぐらいは続きます)
タグ :佐賀
2024年01月01日
「遠路の剣Ⅲ(泥海)」
2024年(令和6年)の新春を迎えました。本年もよろしくお願いします。
ところで、元日から心配な地震のニュースもあり、正月気分は、すっかり抜けてしまいました。
ご挨拶のみでまとめるのも考えましたが、”一年の計”として書いた文章ですので、そのまま掲載します。

年越しで綴った、3回シリーズのまとめで、今年の目標も入っています。
師走に県内を出て、私の住む街の近くまで来た叔父上の旅。実は、私に「佐賀への想いを問う」ような“課題”を与えていました。
――昨年末。師走の旅から、県内へと帰った叔父上の様子をうかがった。
旅の最中に出会うと、叔父上は「最後の旅になるかもしれんとよ」と語った。歳を重ねてから旅に出ると、都度、そんな事を考えるものなのかもしれない。
ところが、いざ電話をしてみると、長旅だったにもかかわらず、意外と元気な声だった。旅の思い出と重ねてか、きれいな景色を思い返すようである。
「おいは、キラキラした海が好きとよ。」

――叔父上…なんだか、子どもみたいな事を言った。
女きょうだいの男の子なので、叔父上には、たまにそういうところがある。
「佐賀にも、有明の海があるじゃないですか。」
「…有明と言えば、泥とよ。あまり、キラキラとはしとらんばい。」
「まぁ、たしかにそうですが。」
有明海といえば、干潟。干潟といえば泥…これは否定しがたい。
「わりと濁っとるもんね~。太良町の方まで行ったら、澄んでるけども。」
――電話の後。かくして、私には“課題”があたえられた。
すっかり、叔父上は旅先で見た光る海に魅了されている。このままでは、佐賀の者としては心許(こころもと)ない。
いや、これは叔父上から私への、修業として与えられた試練なのか。
まばゆい海が見たければ、伊万里や玄海町、唐津方面に行けば良いように思うが、それでは“泥”という課題から逃げている気がする。

私とて、佐賀藩士(?)を名乗る者。新年早々だが、正面から“泥”をかぶっていく気迫で、向き合ってみようと思う。
――少し前、閉塞感のあった“コロナ禍”の時期…
主人公が理不尽な困難に立ち向かう姿もあって、大ヒットしたアニメがあった。その『鬼滅の刃』に着想を得て、泥を味方とした、佐賀の力を練っていきたい。
人は体内に空気を取り込まねば生きてはいけないが、普段、これを意識することは少ない。武芸やスポーツにおいても呼吸は、大事なものだと聞く。
同作品で、凄まじい力を生み出す技を“○○の呼吸”と名付けたのには、すごく説得力を感じる。
今回は「泥の呼吸」と称したまとめ方を使って、項目別に語ってみる。泥に限定して、佐賀県を語る修業を通じて、その魅力を見つめ直したい。

――では、泥の呼吸・壱の型 『覇王への米』から
もし他地域や県外の人に「佐賀って何もないもんね~」と言われた時、あなたならどう返すだろうか。
「そうとよ、なん~もなかばい。」これが大人の受け方。きっと、こう返せる人には心のゆとりがあるのだろう。しかし、私はそこまで悟れてはいない。
「佐賀県には、何もない」というのは、誤解だと私は思う。たとえ「泥の話」だけに限っても、きっとワクワクするほどの魅力を語ることができるはず…
まずは、優れた農業生産がある。なかなか生産量の1位を取れないが、様々な品目で好順位につけており、何より各品目の質が高い。

――NHK Eテレ(教育)で、「佐賀の米」を特集する番組を見かけた。
その中で、佐賀が練り上げてきた米の品質は、“覇王への道”を進んでいる…と喩えられていた。
同番組で佐賀の米を試食したゲストたちは、その味を大絶賛していたわけだが、ここに「泥の力」が作用していることが示されていた。
佐賀の泥の粘土質は、米作りの”理想郷”となる力をもたらすらしい。養分も豊富なため、小麦との二毛作で、強さと柔らかさを兼ね備える土壌になるようだ。
映像で出てきたのは白石町だったが、生産高2位の座を制しつつあるレンコンも、その豊かな泥の中から掘り出される。

――続いて、泥の呼吸・弐の型 『海苔の舞い』
舞台を有明海に移す。佐賀県が安定して1位の品目といえば、海苔の生産。
高級な贈答品となることも多いから、その品質も含めて、折り紙付きといってよい佐賀の特産品。
遠浅の海は濁って見えるところがあるが、計り知れない海の恵みをもたらし、海苔の養殖は、佐賀の風物詩として、全国放送のテレビでもよく映る。

――県南西部の太良町は、カキが有名であるが、
江戸前ずしのネタとして知られる、コハダ。太良町で獲れたものが関東の市場で、取扱量トップだと聞く。
土台となる米、ネタとなる海の幸、寿司には鮮やかに海苔で巻くものも多い。佐賀の特産品をイメージして、寿司を考えるだけで、美味しそうである。
この流れるような動きさえも、県北部の名物、呼子のイカの手を借りる間でもなく、県南部の有明海だけでカタがつく。
「何もない」とか言われるが、寿司に関しては、佐賀県では「探しているもの、全てがある」ようだ。

――最後に、泥の呼吸・参の型 『潟〔ガタ〕の咆哮』
佐賀県の魅力を語るなら、有田陶器市・吉野ヶ里遺跡・バルーンフェスタなどの名所や行事が外せない。
ただ泥…干潟に限ってなら、鹿島の『ガタリンピック』だ。よく見られる風景が、果てしなく続く干潟を這うように進む“潟〔ガタ〕スキー”。通称「ムツゴロウ」。
干潟の上に敷かれた板を、自転車(チャリ)で行く“潟〔ガタ〕チャリ”。
移動方法によらず、干潟を進む時間で勝負を付けるタイムトライアル競技・「25m自由ガタ」という種目もあるらしい。素晴らしいネーミングセンスだと感じる。
――そして、さらに精神を解放するもの。
時折、ニュース映像で見るほか、佐賀を舞台としたアニメ『ゾンビランドサガ』でもしっかりと描写された、“ガターザン”という競技があるようだ。
この言葉、「潟〔ガタ〕」と「ターザン」の複合語なのだろう。ターザンといえば、昔の映画で見た、ジャングルで育った野生児の物語。
成長し「ジャングルの王者」と呼ぶべき存在となったターザン。ロープを使って、木々の間を「ア~ア、アー!」と雄叫びを上げ、滑空する。

県内の若い世代には「フォレストアドベンチャー・吉野ヶ里のように森の中で宙を行く感じです」と言ったら説明になるだろうか。
――その勇姿を、干潟で再現した競技と思われる“ガターザン”。
選手はロープを掴んで、「ア~アァー!」とばかりに干潟に向けて飛ぶ。
「ムツゴロウ」や「ガタチャリ」は、一応は干潟を移動する手段に見えはするが、この競技は高く遠くへ跳んでも泥の中に落ちるのが、自然の理。
「必ず、泥に落ちる」。非常にいさぎよく、魂を解き放つ感じがする。
あたかも、多久やみやき町、大町町などで県内各地で大事に育てられている、二千年ハスのように「泥の中にこそ咲く花もあれ…」と語りたいところだ。

――私は、目が覚めたような心地になった。
「泥を題材とするだけで、佐賀県はここまで語れるのか!」と。
叔父上がキラキラした海にキャッキャッと喜んでいた反作用で、私は泥について、沈み込むようにズブズブと考えることになった。
これでもっと深く、佐賀を読み解くことができる。また叔父上には“修業”の成果を語っておかねば。
――この元旦には、叔父上からの年賀状が届いた。
そこには「法事ば予定しよるけん、こっちまで来んね。」という趣旨の“帰藩”を促す、添え書きがあった。
佐賀を語り続けてはいるものの、私は1年半ほど県内にすら入っていない。最近できた「SAGAアリーナ」も「サガハツ」すらも、実際には見ていない。
「今年こそ佐賀県へと帰って、現地で見聞きしたことで、さらに佐賀を語る」
昨年末の叔父上との再会は、私の新年の課題につながったのである。
ところで、元日から心配な地震のニュースもあり、正月気分は、すっかり抜けてしまいました。
ご挨拶のみでまとめるのも考えましたが、”一年の計”として書いた文章ですので、そのまま掲載します。
年越しで綴った、3回シリーズのまとめで、今年の目標も入っています。
師走に県内を出て、私の住む街の近くまで来た叔父上の旅。実は、私に「佐賀への想いを問う」ような“課題”を与えていました。
――昨年末。師走の旅から、県内へと帰った叔父上の様子をうかがった。
旅の最中に出会うと、叔父上は「最後の旅になるかもしれんとよ」と語った。歳を重ねてから旅に出ると、都度、そんな事を考えるものなのかもしれない。
ところが、いざ電話をしてみると、長旅だったにもかかわらず、意外と元気な声だった。旅の思い出と重ねてか、きれいな景色を思い返すようである。
「おいは、キラキラした海が好きとよ。」
――叔父上…なんだか、子どもみたいな事を言った。
女きょうだいの男の子なので、叔父上には、たまにそういうところがある。
「佐賀にも、有明の海があるじゃないですか。」
「…有明と言えば、泥とよ。あまり、キラキラとはしとらんばい。」
「まぁ、たしかにそうですが。」
有明海といえば、干潟。干潟といえば泥…これは否定しがたい。
「わりと濁っとるもんね~。太良町の方まで行ったら、澄んでるけども。」
――電話の後。かくして、私には“課題”があたえられた。
すっかり、叔父上は旅先で見た光る海に魅了されている。このままでは、佐賀の者としては心許(こころもと)ない。
いや、これは叔父上から私への、修業として与えられた試練なのか。
まばゆい海が見たければ、伊万里や玄海町、唐津方面に行けば良いように思うが、それでは“泥”という課題から逃げている気がする。
私とて、佐賀藩士(?)を名乗る者。新年早々だが、正面から“泥”をかぶっていく気迫で、向き合ってみようと思う。
――少し前、閉塞感のあった“コロナ禍”の時期…
主人公が理不尽な困難に立ち向かう姿もあって、大ヒットしたアニメがあった。その『鬼滅の刃』に着想を得て、泥を味方とした、佐賀の力を練っていきたい。
人は体内に空気を取り込まねば生きてはいけないが、普段、これを意識することは少ない。武芸やスポーツにおいても呼吸は、大事なものだと聞く。
同作品で、凄まじい力を生み出す技を“○○の呼吸”と名付けたのには、すごく説得力を感じる。
今回は「泥の呼吸」と称したまとめ方を使って、項目別に語ってみる。泥に限定して、佐賀県を語る修業を通じて、その魅力を見つめ直したい。
――では、泥の呼吸・壱の型 『覇王への米』から
もし他地域や県外の人に「佐賀って何もないもんね~」と言われた時、あなたならどう返すだろうか。
「そうとよ、なん~もなかばい。」これが大人の受け方。きっと、こう返せる人には心のゆとりがあるのだろう。しかし、私はそこまで悟れてはいない。
「佐賀県には、何もない」というのは、誤解だと私は思う。たとえ「泥の話」だけに限っても、きっとワクワクするほどの魅力を語ることができるはず…
まずは、優れた農業生産がある。なかなか生産量の1位を取れないが、様々な品目で好順位につけており、何より各品目の質が高い。
――NHK Eテレ(教育)で、「佐賀の米」を特集する番組を見かけた。
その中で、佐賀が練り上げてきた米の品質は、“覇王への道”を進んでいる…と喩えられていた。
同番組で佐賀の米を試食したゲストたちは、その味を大絶賛していたわけだが、ここに「泥の力」が作用していることが示されていた。
佐賀の泥の粘土質は、米作りの”理想郷”となる力をもたらすらしい。養分も豊富なため、小麦との二毛作で、強さと柔らかさを兼ね備える土壌になるようだ。
映像で出てきたのは白石町だったが、生産高2位の座を制しつつあるレンコンも、その豊かな泥の中から掘り出される。
――続いて、泥の呼吸・弐の型 『海苔の舞い』
舞台を有明海に移す。佐賀県が安定して1位の品目といえば、海苔の生産。
高級な贈答品となることも多いから、その品質も含めて、折り紙付きといってよい佐賀の特産品。
遠浅の海は濁って見えるところがあるが、計り知れない海の恵みをもたらし、海苔の養殖は、佐賀の風物詩として、全国放送のテレビでもよく映る。
――県南西部の太良町は、カキが有名であるが、
江戸前ずしのネタとして知られる、コハダ。太良町で獲れたものが関東の市場で、取扱量トップだと聞く。
土台となる米、ネタとなる海の幸、寿司には鮮やかに海苔で巻くものも多い。佐賀の特産品をイメージして、寿司を考えるだけで、美味しそうである。
この流れるような動きさえも、県北部の名物、呼子のイカの手を借りる間でもなく、県南部の有明海だけでカタがつく。
「何もない」とか言われるが、寿司に関しては、佐賀県では「探しているもの、全てがある」ようだ。
――最後に、泥の呼吸・参の型 『潟〔ガタ〕の咆哮』
佐賀県の魅力を語るなら、有田陶器市・吉野ヶ里遺跡・バルーンフェスタなどの名所や行事が外せない。
ただ泥…干潟に限ってなら、鹿島の『ガタリンピック』だ。よく見られる風景が、果てしなく続く干潟を這うように進む“潟〔ガタ〕スキー”。通称「ムツゴロウ」。
干潟の上に敷かれた板を、自転車(チャリ)で行く“潟〔ガタ〕チャリ”。
移動方法によらず、干潟を進む時間で勝負を付けるタイムトライアル競技・「25m自由ガタ」という種目もあるらしい。素晴らしいネーミングセンスだと感じる。
――そして、さらに精神を解放するもの。
時折、ニュース映像で見るほか、佐賀を舞台としたアニメ『ゾンビランドサガ』でもしっかりと描写された、“ガターザン”という競技があるようだ。
この言葉、「潟〔ガタ〕」と「ターザン」の複合語なのだろう。ターザンといえば、昔の映画で見た、ジャングルで育った野生児の物語。
成長し「ジャングルの王者」と呼ぶべき存在となったターザン。ロープを使って、木々の間を「ア~ア、アー!」と雄叫びを上げ、滑空する。
県内の若い世代には「フォレストアドベンチャー・吉野ヶ里のように森の中で宙を行く感じです」と言ったら説明になるだろうか。
――その勇姿を、干潟で再現した競技と思われる“ガターザン”。
選手はロープを掴んで、「ア~アァー!」とばかりに干潟に向けて飛ぶ。
「ムツゴロウ」や「ガタチャリ」は、一応は干潟を移動する手段に見えはするが、この競技は高く遠くへ跳んでも泥の中に落ちるのが、自然の理。
「必ず、泥に落ちる」。非常にいさぎよく、魂を解き放つ感じがする。
あたかも、多久やみやき町、大町町などで県内各地で大事に育てられている、二千年ハスのように「泥の中にこそ咲く花もあれ…」と語りたいところだ。
――私は、目が覚めたような心地になった。
「泥を題材とするだけで、佐賀県はここまで語れるのか!」と。
叔父上がキラキラした海にキャッキャッと喜んでいた反作用で、私は泥について、沈み込むようにズブズブと考えることになった。
これでもっと深く、佐賀を読み解くことができる。また叔父上には“修業”の成果を語っておかねば。
――この元旦には、叔父上からの年賀状が届いた。
そこには「法事ば予定しよるけん、こっちまで来んね。」という趣旨の“帰藩”を促す、添え書きがあった。
佐賀を語り続けてはいるものの、私は1年半ほど県内にすら入っていない。最近できた「SAGAアリーナ」も「サガハツ」すらも、実際には見ていない。
「今年こそ佐賀県へと帰って、現地で見聞きしたことで、さらに佐賀を語る」
昨年末の叔父上との再会は、私の新年の課題につながったのである。
タグ :佐賀




