2020年09月24日
第14話「遣米使節」①(諭吉よ、何処へ行く)
こんばんは。
今回の投稿より、第14話です。
幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。
毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。
――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。
訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。
今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。
小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。
「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」
殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。
本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。
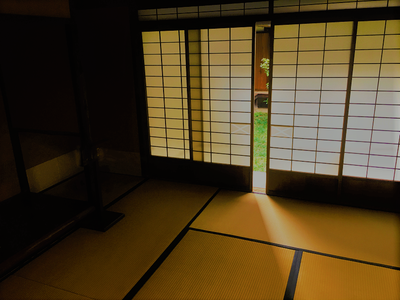
――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。
砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。
また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。
「どのように、賢か書生ですか?」
「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」
いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。
〔参照:第12話「海軍伝習」②(長崎の雨)〕
――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。
山本家の者が、玄関を掃き清めていた。
「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」
本島が口を開く。
「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」
家の者が返答する。
「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」
――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。
福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。
“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。
長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。
〔参照:第3話「西洋砲術」③-2〕
――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。
こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。
福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。
「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。
「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」
福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。
“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。
緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。
「そうか、お手を煩わせた。」
本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。
――本島は、何やら残念そうな表情をしている。
「既に長崎を去っていたか…」
本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。
「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」
小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。
「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」
側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。
その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。
(続く)
今回の投稿より、第14話です。
幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。
毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。
――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。
訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。
今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。
小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。
「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」
殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。
本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。
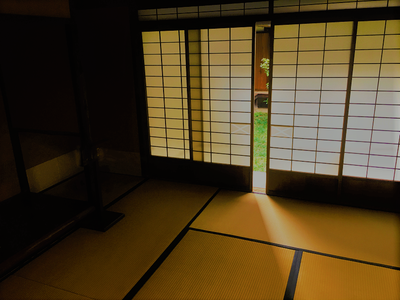
――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。
砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。
また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。
「どのように、賢か書生ですか?」
「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」
いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。
〔参照:
――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。
山本家の者が、玄関を掃き清めていた。
「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」
本島が口を開く。
「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」
家の者が返答する。
「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」
――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。
福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。
“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。
長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。
〔参照:
――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。
こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。
福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。
「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。
「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」
福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。
“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。
緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。
「そうか、お手を煩わせた。」
本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。
――本島は、何やら残念そうな表情をしている。
「既に長崎を去っていたか…」
本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。
「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」
小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。
「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」
側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。
その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。
(続く)
2020年09月26日
第14話「遣米使節」②(オランダ商館の午後)
こんばんは。
江戸時代“鎖国”が続いた時期も、日本と交流のあったオランダ。
商業上の思惑はあったとしても、日本に西洋との関わり方を助言し、近代海軍の育成にも協力を惜しみません。幕末期にも“親切”なオランダでした。
なお、各話をテーマ別に構成していますので、第12話「海軍伝習」の終盤と時期が重なっています。今回は、以下の投稿の少し後のお話です。
〔参照(後半):第12話「海軍伝習」⑧(いざ、長崎へ)〕
――1856年、長崎の出島。オランダ商館の午後。
「君タチはヨイ訓練がデキテル!私が退任シテモ、一層に励メ!」
強い語気で激励をする。長崎海軍伝習所の教官・ライケンである。
「モトシマ!若い者に負ケルナ!」
「カツ!船酔イは、気迫で乗リ切レ!」
「はい!ライケン教官!!」
佐賀藩士で、殿・鍋島直正の側近でもある、本島藤太夫が応答する。
「おう、合点(がってん)で!いや…、はい!ライケン教官!」
幕臣・勝麟太郎(海舟)。はじめに江戸ことばが出たが、要領よく声を揃えた。

――出島・オランダ商館の奥の方から、この館の主が姿を見せる。
「ハッハッハ…訓練の景色が見えるようです。」
オランダ商館長・クルチウスである。
「そしてライケンさん。ここは“海軍伝習所”ではありませんよ。」
「おお、商館長…これは癖だ。もはや治らん!」
――本島や勝がオランダ語に慣れても、やはりオランダ人同士の会話は段違いにスムーズである。
商館長・クルチウスには、さすがの教官・ライケンも一目おいている様子だ。
「長崎を去るそうだね。せっかくの機会だ。生徒たちも一緒にティータイムでもいかがか。」
昼下がりの紅茶を提案してきた商館長。海軍伝習所の教官・ライケンは、第一期の伝習終了後に、新任の教官と交代する予定だ。
〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑩-1(負けんばい!・前編)〕
――こうして商館の応接部屋に、紅茶の良い香りが漂う。
「いや…オランダのお茶も、乙(おつ)なもんですな。」
勝麟太郎が一口すすって、西洋茶の感想を述べる。
「わがオランダの紅茶を褒めてくれているだが、茶葉はウレシノだよ。」
商館長・クルチウスは、茶葉の生産地を述べた。
「耳慣れねぇ土地ですね。どこの島なんです?」
勝は、怪訝な顔をした。東南アジアのオランダ領には思い当たる地名が無い。

――佐賀藩士・本島が、商館長・クルチウスに確認する。
「佐賀の嬉野…にござりますか。」
「エエ、佐賀の茶葉デス。但し、紅茶は“発酵茶”で製法が違イマスガ。」
「我がオランダの者も、ここ長崎のオオウラサンと取引をしている。」
商館長が語った“オオウラさん”とは、長崎の商人・大浦慶である。
数年前、オランダ人に嬉野茶のサンプルを持たせて、いまやイギリスなどから大量の注文が出ている。
大浦慶は、当時まだ20代後半の女性で、凄腕の商人だった。
――“国際都市”長崎で海軍伝習を受ける、40代の本島藤太夫。
「オランダを通じ、もはや諸国とも“通商”が始まっておるに等しいか…」
このところ、西洋諸国が続々と「和親条約」を締結した。続いて“通商”の交渉も行われているらしい。
本島は、殿・鍋島直正の予測通り。あるいは、想定以上の速度で時代が進んでいくのを感じていた。
(続く)
江戸時代“鎖国”が続いた時期も、日本と交流のあったオランダ。
商業上の思惑はあったとしても、日本に西洋との関わり方を助言し、近代海軍の育成にも協力を惜しみません。幕末期にも“親切”なオランダでした。
なお、各話をテーマ別に構成していますので、第12話「海軍伝習」の終盤と時期が重なっています。今回は、以下の投稿の少し後のお話です。
〔参照(後半):
――1856年、長崎の出島。オランダ商館の午後。
「君タチはヨイ訓練がデキテル!私が退任シテモ、一層に励メ!」
強い語気で激励をする。長崎海軍伝習所の教官・ライケンである。
「モトシマ!若い者に負ケルナ!」
「カツ!船酔イは、気迫で乗リ切レ!」
「はい!ライケン教官!!」
佐賀藩士で、殿・鍋島直正の側近でもある、本島藤太夫が応答する。
「おう、合点(がってん)で!いや…、はい!ライケン教官!」
幕臣・勝麟太郎(海舟)。はじめに江戸ことばが出たが、要領よく声を揃えた。

――出島・オランダ商館の奥の方から、この館の主が姿を見せる。
「ハッハッハ…訓練の景色が見えるようです。」
オランダ商館長・クルチウスである。
「そしてライケンさん。ここは“海軍伝習所”ではありませんよ。」
「おお、商館長…これは癖だ。もはや治らん!」
――本島や勝がオランダ語に慣れても、やはりオランダ人同士の会話は段違いにスムーズである。
商館長・クルチウスには、さすがの教官・ライケンも一目おいている様子だ。
「長崎を去るそうだね。せっかくの機会だ。生徒たちも一緒にティータイムでもいかがか。」
昼下がりの紅茶を提案してきた商館長。海軍伝習所の教官・ライケンは、第一期の伝習終了後に、新任の教官と交代する予定だ。
〔参照(前半):
――こうして商館の応接部屋に、紅茶の良い香りが漂う。
「いや…オランダのお茶も、乙(おつ)なもんですな。」
勝麟太郎が一口すすって、西洋茶の感想を述べる。
「わがオランダの紅茶を褒めてくれているだが、茶葉はウレシノだよ。」
商館長・クルチウスは、茶葉の生産地を述べた。
「耳慣れねぇ土地ですね。どこの島なんです?」
勝は、怪訝な顔をした。東南アジアのオランダ領には思い当たる地名が無い。
――佐賀藩士・本島が、商館長・クルチウスに確認する。
「佐賀の嬉野…にござりますか。」
「エエ、佐賀の茶葉デス。但し、紅茶は“発酵茶”で製法が違イマスガ。」
「我がオランダの者も、ここ長崎のオオウラサンと取引をしている。」
商館長が語った“オオウラさん”とは、長崎の商人・大浦慶である。
数年前、オランダ人に嬉野茶のサンプルを持たせて、いまやイギリスなどから大量の注文が出ている。
大浦慶は、当時まだ20代後半の女性で、凄腕の商人だった。
――“国際都市”長崎で海軍伝習を受ける、40代の本島藤太夫。
「オランダを通じ、もはや諸国とも“通商”が始まっておるに等しいか…」
このところ、西洋諸国が続々と「和親条約」を締結した。続いて“通商”の交渉も行われているらしい。
本島は、殿・鍋島直正の予測通り。あるいは、想定以上の速度で時代が進んでいくのを感じていた。
(続く)
2020年09月28日
第14話「遣米使節」③(嬉野から来た忍び)
こんばんは。
佐賀藩には「蓮池藩」という“支藩”があります。藩の領地は、県内各地に分散しますが、現在の嬉野市あたりに大きい所領があります。
佐賀は本藩だけでなく、支藩や自治領なども長崎警備に携わりました。幕末期の脅威であった欧米列強も、佐賀藩の情報収集の対象になっています。
――1856年、長崎。イギリスの軍船が停泊中である。
下田・箱館(函館)が開港した当時でも、海外への表玄関は依然として国際都市・長崎であった。
長崎の街が賑わう宵のうち、穏やかな風景である。しかし、イギリス人にとっては不慣れな土地であるため、船外でも油断のない警備が続いていた。
「フー イズ ゼア!!」
じわじわと語気を強めた、1人の若いイギリス水兵。何かの気配を察したか、突如として前方に銃口を向ける。
「ニ゛ャーン!?」
“そこにいるのは誰だ!”と問われ、驚いて飛び上がる。尻尾の短いネコ。
――水兵の威嚇に、毛を逆立て硬直したネコ。次の瞬間には逃げ去った。
「ハッハッハ…ジャスト ア キャット…」
他のイギリス水兵たちが、失笑する。
「勇敢な兵士くん!!大した敵襲だったな…」
そんな目線が注がれていた。
「チッ…」
きまりが悪そうな若い水兵。軽く舌打ちをする。

――ベテランの水兵たちが、“心配性”の新人をからかっている間…
音も無く、その傍らを人影がすり抜けていた。
佐賀藩の支藩の1つである、蓮池藩士の古賀という人物である。
「さすがはエゲレス(イギリス)…立派な拵(こしら)えばい。」
夜闇に紛れて、英国船の大砲装備、兵員の数などを見聞して回る。
調査に先んじて、船外の警備は把握していた。
…古賀は、佐賀・蓮池藩が放った“忍者”である。
――1854年の日米和親条約以降、次々に西洋諸国が条約締結に動く。
日英和親条約が締結されてから、長崎にはイギリス船も入港した。
佐賀藩の悲劇でもあった、イギリス船“フェートン号”の長崎港への侵入事件。半世紀近くが経過し、海外との関わり方は激変していたのである。
「静かなもんたい。今のところ、暴れる気配は無かね…」
――ひと通りの調査を終えた、佐賀の蓮池藩士・古賀。
「ご苦労さんやったね。」
イギリス船から離れた蓮池藩士・古賀。先ほどのネコを撫でて、小魚を与える。
「ニャーン…」
尻尾の短いネコが、満足気にひと鳴きする。その間に古賀は夜闇に消えた。
佐賀藩は長崎を通じた探索に有利で、当時、異国からの情報には格段の強みを持っていたのである。
(続く)
佐賀藩には「蓮池藩」という“支藩”があります。藩の領地は、県内各地に分散しますが、現在の嬉野市あたりに大きい所領があります。
佐賀は本藩だけでなく、支藩や自治領なども長崎警備に携わりました。幕末期の脅威であった欧米列強も、佐賀藩の情報収集の対象になっています。
――1856年、長崎。イギリスの軍船が停泊中である。
下田・箱館(函館)が開港した当時でも、海外への表玄関は依然として国際都市・長崎であった。
長崎の街が賑わう宵のうち、穏やかな風景である。しかし、イギリス人にとっては不慣れな土地であるため、船外でも油断のない警備が続いていた。
「フー イズ ゼア!!」
じわじわと語気を強めた、1人の若いイギリス水兵。何かの気配を察したか、突如として前方に銃口を向ける。
「ニ゛ャーン!?」
“そこにいるのは誰だ!”と問われ、驚いて飛び上がる。尻尾の短いネコ。
――水兵の威嚇に、毛を逆立て硬直したネコ。次の瞬間には逃げ去った。
「ハッハッハ…ジャスト ア キャット…」
他のイギリス水兵たちが、失笑する。
「勇敢な兵士くん!!大した敵襲だったな…」
そんな目線が注がれていた。
「チッ…」
きまりが悪そうな若い水兵。軽く舌打ちをする。
――ベテランの水兵たちが、“心配性”の新人をからかっている間…
音も無く、その傍らを人影がすり抜けていた。
佐賀藩の支藩の1つである、蓮池藩士の古賀という人物である。
「さすがはエゲレス(イギリス)…立派な拵(こしら)えばい。」
夜闇に紛れて、英国船の大砲装備、兵員の数などを見聞して回る。
調査に先んじて、船外の警備は把握していた。
…古賀は、佐賀・蓮池藩が放った“忍者”である。
――1854年の日米和親条約以降、次々に西洋諸国が条約締結に動く。
日英和親条約が締結されてから、長崎にはイギリス船も入港した。
佐賀藩の悲劇でもあった、イギリス船“フェートン号”の長崎港への侵入事件。半世紀近くが経過し、海外との関わり方は激変していたのである。
「静かなもんたい。今のところ、暴れる気配は無かね…」
――ひと通りの調査を終えた、佐賀の蓮池藩士・古賀。
「ご苦労さんやったね。」
イギリス船から離れた蓮池藩士・古賀。先ほどのネコを撫でて、小魚を与える。
「ニャーン…」
尻尾の短いネコが、満足気にひと鳴きする。その間に古賀は夜闇に消えた。
佐賀藩は長崎を通じた探索に有利で、当時、異国からの情報には格段の強みを持っていたのである。
(続く)
2020年09月30日
第14話「遣米使節」④(長崎街道の往来)
こんばんは。
前回は、佐賀・蓮池支藩の“忍者”・古賀が登場しました。長崎でイギリス船の動きを探る…など、情報収集の任務をこなし、今回は佐賀への帰路です。
一方で、佐賀と長崎を行ったり来たりの人もいます。殿・鍋島直正から“海軍”の創設を指示された、佐野栄寿(常民)です。
――長崎街道・塩田宿の茶店。
小倉から長崎までをつなぐ長崎街道。蓮池藩士・古賀は、街道を急ぐ人通りを眺めていた。
「皆、忙しかごたね…」
茶店の表に置かれた、広いちゃぶ台といった感じの席に腰掛ける。
「団子を一ついただこうか。」
背中合わせに座った武士も、一服する様子だ。

――この武士も蓮池藩の者である。古賀に連絡があるらしい。
「美味い団子であったぞ。」
武士は、古賀とは言葉を交わさず、勘定を済ませると早々に立ち去った。
桟敷に置かれた紙切れを、古賀が拾う。
「報告は届いたが、直に説明せよ。“蓮池の館”に向かえ。」という指示書である。
「人づかいの荒かごた…」
古賀が、少し不平を口にする。
蓮池支藩の居館は、現在の佐賀市内にある。
塩田宿は、現在の嬉野市であるから、移動もひと仕事になるのだ。
――そして蓮池藩士・古賀は“忍者”にあるまじき行動を取る。
「団子ば、もう一本もらえんね。」
節制を常とする“忍者”が、団子のお代わりを要求した。
そこに長い尻尾のネコが寄って来た。
古賀は団子を一つかみ、ネコの眼前でクルクルと回す。
「ほれほれ…」
「ニャーン!」
“癒し”を求めたのか、寄ってきたネコと戯れる蓮池藩士・古賀。やけにハッキリした鳴き声で、反応を返すネコ。
――すると今度は、隣に客が座った。年の頃は30代半ばの武士。
「可愛かネコですね。」
「…あぁ、儂はよく懐かれるのでな。」
“忍者”は寡黙で、人を寄せ付けない…というイメージでよく語られる。しかし、忍者が情報を集めるには“人あたり”の良さが必須だったとの説もある。
「塩田の津も、なかなかに賑わっとるばい。」
――初対面の相手にも遠慮なく話しかける、佐野栄寿(常民)である。
「…まぁ、じきに潮が引くからな。荷揚げも忙しかろう。」
お代わりの団子を口にしながら、古賀がつぶやく。
塩田津は“川の港”。
有明海の満潮時に、積荷を満載した船が塩田川を遡って入ってくる。
――天草(熊本)から“陶石”を積んだ船が、川岸に付ける。
「伊万里への積荷ですかね。」
「…詳しか事は、わからんばい。」
蓮池藩士・古賀は、やや警戒心を持った。
佐野栄寿(常民)の好奇心が強すぎるのである。
おそらくは長崎に向かう、佐賀本藩の武士だろうとは察していた。
しかし、佐賀藩士を装った外部からの密偵かも知れない。

――“忍者”である古賀としては、用心に越したことはない。
「…では、儂はこれにて。」
蓮池藩士・古賀は席を立った。
「そうたい!“潮の満ち引き”を使えば良かね!」
佐野は、何かを思いついたのか、にわかに大声を出した。
「…何に“満ち引き”ば使うとね?」
かえって無視すると不自然。古賀が佐野に尋ねた。
「これで、大船ば“修理”できっとです!」
佐野は、知り合ったばかりの古賀に向けて、満面の笑みを見せた。
(続く)
前回は、佐賀・蓮池支藩の“忍者”・古賀が登場しました。長崎でイギリス船の動きを探る…など、情報収集の任務をこなし、今回は佐賀への帰路です。
一方で、佐賀と長崎を行ったり来たりの人もいます。殿・鍋島直正から“海軍”の創設を指示された、佐野栄寿(常民)です。
――長崎街道・塩田宿の茶店。
小倉から長崎までをつなぐ長崎街道。蓮池藩士・古賀は、街道を急ぐ人通りを眺めていた。
「皆、忙しかごたね…」
茶店の表に置かれた、広いちゃぶ台といった感じの席に腰掛ける。
「団子を一ついただこうか。」
背中合わせに座った武士も、一服する様子だ。
――この武士も蓮池藩の者である。古賀に連絡があるらしい。
「美味い団子であったぞ。」
武士は、古賀とは言葉を交わさず、勘定を済ませると早々に立ち去った。
桟敷に置かれた紙切れを、古賀が拾う。
「報告は届いたが、直に説明せよ。“蓮池の館”に向かえ。」という指示書である。
「人づかいの荒かごた…」
古賀が、少し不平を口にする。
蓮池支藩の居館は、現在の佐賀市内にある。
塩田宿は、現在の嬉野市であるから、移動もひと仕事になるのだ。
――そして蓮池藩士・古賀は“忍者”にあるまじき行動を取る。
「団子ば、もう一本もらえんね。」
節制を常とする“忍者”が、団子のお代わりを要求した。
そこに長い尻尾のネコが寄って来た。
古賀は団子を一つかみ、ネコの眼前でクルクルと回す。
「ほれほれ…」
「ニャーン!」
“癒し”を求めたのか、寄ってきたネコと戯れる蓮池藩士・古賀。やけにハッキリした鳴き声で、反応を返すネコ。
――すると今度は、隣に客が座った。年の頃は30代半ばの武士。
「可愛かネコですね。」
「…あぁ、儂はよく懐かれるのでな。」
“忍者”は寡黙で、人を寄せ付けない…というイメージでよく語られる。しかし、忍者が情報を集めるには“人あたり”の良さが必須だったとの説もある。
「塩田の津も、なかなかに賑わっとるばい。」
――初対面の相手にも遠慮なく話しかける、佐野栄寿(常民)である。
「…まぁ、じきに潮が引くからな。荷揚げも忙しかろう。」
お代わりの団子を口にしながら、古賀がつぶやく。
塩田津は“川の港”。
有明海の満潮時に、積荷を満載した船が塩田川を遡って入ってくる。
――天草(熊本)から“陶石”を積んだ船が、川岸に付ける。
「伊万里への積荷ですかね。」
「…詳しか事は、わからんばい。」
蓮池藩士・古賀は、やや警戒心を持った。
佐野栄寿(常民)の好奇心が強すぎるのである。
おそらくは長崎に向かう、佐賀本藩の武士だろうとは察していた。
しかし、佐賀藩士を装った外部からの密偵かも知れない。
――“忍者”である古賀としては、用心に越したことはない。
「…では、儂はこれにて。」
蓮池藩士・古賀は席を立った。
「そうたい!“潮の満ち引き”を使えば良かね!」
佐野は、何かを思いついたのか、にわかに大声を出した。
「…何に“満ち引き”ば使うとね?」
かえって無視すると不自然。古賀が佐野に尋ねた。
「これで、大船ば“修理”できっとです!」
佐野は、知り合ったばかりの古賀に向けて、満面の笑みを見せた。
(続く)
2020年10月02日
第14話「遣米使節」⑤(火術方への“就活”)
こんばんは。
“嬉野の忍者”が長崎~佐賀を行く投稿の3回目です。今回、蓮池藩士・古賀が出会うのは…のちに幕末佐賀藩のヒーローとなるあの人です。
――佐賀城の南東、蓮池支藩の御館。
「エゲレス(イギリス)船の見聞、滞りなく。」
「さすがは古賀じゃ。随分と黒船まで近付いたようだな。」
「ははっ。」
「良き調べであるから、蓮池のみで留めず、本家にもお伝えせよ。」
蓮池藩士・古賀の“殿様”は、蓮池藩主・鍋島直與(なおとも)という。やはり“蘭癖”(西洋かぶれ)大名として知られる。
――本藩の殿・鍋島直正だけでなく、支藩も自治領も、藩主(領主)が、やたらと西洋に詳しいのが佐賀藩の特徴である。
「はっ。」
「“火術方”に夏雲どのが居られるから、この文(ふみ)とともに一走りせよ。」
「承りました。」
信用のある“嬉野の忍者”古賀。今度は機密情報を一手に集める、殿・直正の書記官・鍋島夏雲のもとに向かう。

――蓮池藩士・古賀が、佐賀城下の“火術方”(大砲など火器を扱う部門)に走る。
「やっぱり、人づかいの荒かごたぁ…」
いくら“忍者”と言えども、愚痴は出る。しかし、その足取りは軽妙である。
微かに香る有明の潮風を切りながら、古賀はスイスイと進んでいく。その歩みは人目が無い裏道では、さらに加速した。
――ほどなく佐賀本藩の“火術方”の門前に到着した、古賀。
「ニー、ニー」
塀のたもとで、仔猫が鳴く。
「おお、可愛かばい。母ちゃんはどこね?」
仔猫に話しかける、蓮池藩士・古賀。
――そこで、ネコに話しかける“忍者”に歩み寄る影があった。
「お尋ね申す!“火術方”のお役人でござるか。」
鋭く通る声。
いきなりの大音声に、仔猫がビリビリと震える。へっぴり腰でピタリと止まったあと、一目散に母ネコの元に逃げ去った。

――蓮池藩士・古賀は緩やかに背を丸めた。死角には小刀を隠し持つ。
古賀は背を向けたまま、青年に言葉をかける。
「…よく通るお声で、ございますな。」
「相済まぬ。よく人を驚かせてしまうのだ。」
この青年、江藤新平である。人だけでなくネコも驚かせている。
古賀はひとまず安堵した。江藤を佐賀藩士と認識したのである。
「儂は“火術方”の者では無かばってん…所用がございましてな。」
――学費の不足で、“蘭学寮”を退学した江藤新平。
身なりは粗末なままだが、ボサボサしていた髪は整えた。
いわば佐賀藩で役目を得るための“就職活動中”である。
「失礼した。少々、気負いが過ぎたようだ。」
「いや…お若いの、頑張らんね。」
先ほどまでの警戒心は解け「なかなか面白そうな青年ではないか」と、古賀はそう感じたのである。
(続く)
“嬉野の忍者”が長崎~佐賀を行く投稿の3回目です。今回、蓮池藩士・古賀が出会うのは…のちに幕末佐賀藩のヒーローとなるあの人です。
――佐賀城の南東、蓮池支藩の御館。
「エゲレス(イギリス)船の見聞、滞りなく。」
「さすがは古賀じゃ。随分と黒船まで近付いたようだな。」
「ははっ。」
「良き調べであるから、蓮池のみで留めず、本家にもお伝えせよ。」
蓮池藩士・古賀の“殿様”は、蓮池藩主・鍋島直與(なおとも)という。やはり“蘭癖”(西洋かぶれ)大名として知られる。
――本藩の殿・鍋島直正だけでなく、支藩も自治領も、藩主(領主)が、やたらと西洋に詳しいのが佐賀藩の特徴である。
「はっ。」
「“火術方”に夏雲どのが居られるから、この文(ふみ)とともに一走りせよ。」
「承りました。」
信用のある“嬉野の忍者”古賀。今度は機密情報を一手に集める、殿・直正の書記官・鍋島夏雲のもとに向かう。
――蓮池藩士・古賀が、佐賀城下の“火術方”(大砲など火器を扱う部門)に走る。
「やっぱり、人づかいの荒かごたぁ…」
いくら“忍者”と言えども、愚痴は出る。しかし、その足取りは軽妙である。
微かに香る有明の潮風を切りながら、古賀はスイスイと進んでいく。その歩みは人目が無い裏道では、さらに加速した。
――ほどなく佐賀本藩の“火術方”の門前に到着した、古賀。
「ニー、ニー」
塀のたもとで、仔猫が鳴く。
「おお、可愛かばい。母ちゃんはどこね?」
仔猫に話しかける、蓮池藩士・古賀。
――そこで、ネコに話しかける“忍者”に歩み寄る影があった。
「お尋ね申す!“火術方”のお役人でござるか。」
鋭く通る声。
いきなりの大音声に、仔猫がビリビリと震える。へっぴり腰でピタリと止まったあと、一目散に母ネコの元に逃げ去った。

――蓮池藩士・古賀は緩やかに背を丸めた。死角には小刀を隠し持つ。
古賀は背を向けたまま、青年に言葉をかける。
「…よく通るお声で、ございますな。」
「相済まぬ。よく人を驚かせてしまうのだ。」
この青年、江藤新平である。人だけでなくネコも驚かせている。
古賀はひとまず安堵した。江藤を佐賀藩士と認識したのである。
「儂は“火術方”の者では無かばってん…所用がございましてな。」
――学費の不足で、“蘭学寮”を退学した江藤新平。
身なりは粗末なままだが、ボサボサしていた髪は整えた。
いわば佐賀藩で役目を得るための“就職活動中”である。
「失礼した。少々、気負いが過ぎたようだ。」
「いや…お若いの、頑張らんね。」
先ほどまでの警戒心は解け「なかなか面白そうな青年ではないか」と、古賀はそう感じたのである。
(続く)
2020年10月06日
第14話「遣米使節」⑥(月が綺麗ですね)
こんばんは。
“本編”を再開します。
かつて明治の文豪・夏目漱石は英語の「アイラブユー」を「我、君を愛す」と訳した学生に、ある指摘をしたと言われます。

「日本人は、あまり直接的な表現を使わない。“月が綺麗ですね”とでも訳しておくと良い」と…。今回の投稿は、そんな話も頭の片隅においてご覧ください。
――佐賀城下の夕暮れ。江藤家の門前。
就職活動とでも言うべきか、“火術方”への挨拶に出向いた江藤新平。
気合いが入り過ぎて、たまたま門前に居た蓮池藩士に、いつも以上に通った声で話しかけて驚かれた。
しかし、江藤の学力は、佐賀藩の“火術方”(大砲など火器を取扱う部門)でも知られており、挨拶そのものは、順調な展開となった。
「只今、戻りました。」
出迎える江藤家の面々、母・浅子が様子を伺う。
「いかがでしたか。」
「概ね、良かろうと存じます。」
――話をこの日の朝方に戻す。“火術方”への挨拶の出発前。
「これより“火術方”に出向きます。」
江藤が、母・浅子に出立を告げた、その時。
「お待ちください!」
小走りに玄関に来たのは、従姉(いとこ)の江口千代子である。

――かなり息が弾んでいる、江口千代子。
「そのように急ぎ足で、いかがしたのです。」
江藤が、駆け込んできた千代子に尋ねる。
その手には、鬢(びん)付け油が握られていた。
「…これをお使いに。」
「いささか高価なものと見受けるが。」
――江藤新平、得心のいかない表情で千代子を見つめる。
「日頃の…、倹約の賜物にございます。」
まだ、息の乱れがある千代子。随分、走った様子だ。
「新平。千代子さんのご厚意です。有難く使うのです。」
江藤の母・浅子が、確信を持った声で述べる。
――“いつもボサボサ”江藤の髪だが、千代子の“鬢付け油”で整った。
学問以外は、質素倹約。とにかく身なりを気にしない江藤新平。
なんとか髪だけは格好がついて“火術方”での挨拶となった。
何かと江藤家に来ることが多い従姉の千代子。新平の1歳年上である。この日の夕刻にも、江藤の母・浅子の手伝いに来ていた。
「千代子どの、朝方は忝(かたじけ)ない。」
江藤が、台所に居る千代子に礼を述べる。
「いえいえ、良き首尾だったご様子。何よりにございます。」
唯々、嬉しそうな千代子の表情である。

――そして宵闇に移り行く、佐賀城下の空。
「家まで、お送り致そう。」
江藤新平が、帰り支度をする千代子に声をかける。
庭先に出ると、大きい月が宵の空を照らし始めていた。
同じ瞬間に、夜空を見上げた2人。
「千代子どの!今宵は、綺麗な月だな。」
「ええ、とっても。」
――千代子は、きゅっと、小さく右拳を握った。
江藤の言葉を遠回しな“愛の告白”と受けとめたのである。
もともと、江藤家に入り浸っていた従姉の千代子。
江藤の両親も、いい加減、新平には、身を固めてほしい…と考えていた。
全く不都合のない結婚話は、トントンと進む。
聡明な妻・千代子は、溢れる才気を持った江藤新平にとって良き理解者となるのである。
(続く)
“本編”を再開します。
かつて明治の文豪・夏目漱石は英語の「アイラブユー」を「我、君を愛す」と訳した学生に、ある指摘をしたと言われます。
「日本人は、あまり直接的な表現を使わない。“月が綺麗ですね”とでも訳しておくと良い」と…。今回の投稿は、そんな話も頭の片隅においてご覧ください。
――佐賀城下の夕暮れ。江藤家の門前。
就職活動とでも言うべきか、“火術方”への挨拶に出向いた江藤新平。
気合いが入り過ぎて、たまたま門前に居た蓮池藩士に、いつも以上に通った声で話しかけて驚かれた。
しかし、江藤の学力は、佐賀藩の“火術方”(大砲など火器を取扱う部門)でも知られており、挨拶そのものは、順調な展開となった。
「只今、戻りました。」
出迎える江藤家の面々、母・浅子が様子を伺う。
「いかがでしたか。」
「概ね、良かろうと存じます。」
――話をこの日の朝方に戻す。“火術方”への挨拶の出発前。
「これより“火術方”に出向きます。」
江藤が、母・浅子に出立を告げた、その時。
「お待ちください!」
小走りに玄関に来たのは、従姉(いとこ)の江口千代子である。

――かなり息が弾んでいる、江口千代子。
「そのように急ぎ足で、いかがしたのです。」
江藤が、駆け込んできた千代子に尋ねる。
その手には、鬢(びん)付け油が握られていた。
「…これをお使いに。」
「いささか高価なものと見受けるが。」
――江藤新平、得心のいかない表情で千代子を見つめる。
「日頃の…、倹約の賜物にございます。」
まだ、息の乱れがある千代子。随分、走った様子だ。
「新平。千代子さんのご厚意です。有難く使うのです。」
江藤の母・浅子が、確信を持った声で述べる。
――“いつもボサボサ”江藤の髪だが、千代子の“鬢付け油”で整った。
学問以外は、質素倹約。とにかく身なりを気にしない江藤新平。
なんとか髪だけは格好がついて“火術方”での挨拶となった。
何かと江藤家に来ることが多い従姉の千代子。新平の1歳年上である。この日の夕刻にも、江藤の母・浅子の手伝いに来ていた。
「千代子どの、朝方は忝(かたじけ)ない。」
江藤が、台所に居る千代子に礼を述べる。
「いえいえ、良き首尾だったご様子。何よりにございます。」
唯々、嬉しそうな千代子の表情である。
――そして宵闇に移り行く、佐賀城下の空。
「家まで、お送り致そう。」
江藤新平が、帰り支度をする千代子に声をかける。
庭先に出ると、大きい月が宵の空を照らし始めていた。
同じ瞬間に、夜空を見上げた2人。
「千代子どの!今宵は、綺麗な月だな。」
「ええ、とっても。」
――千代子は、きゅっと、小さく右拳を握った。
江藤の言葉を遠回しな“愛の告白”と受けとめたのである。
もともと、江藤家に入り浸っていた従姉の千代子。
江藤の両親も、いい加減、新平には、身を固めてほしい…と考えていた。
全く不都合のない結婚話は、トントンと進む。
聡明な妻・千代子は、溢れる才気を持った江藤新平にとって良き理解者となるのである。
(続く)
2020年10月08日
第14話「遣米使節」⑦(前へ進む者たちへ)
こんばんは。
前回は、江藤新平の結婚を題材としたお話でした。新しい家族を形成した頃、他にも“ライフイベント”が目白押しとなってくる江藤。
江藤の就職予定先は、“火術方目付”という佐賀藩の役職です。下級役人ではありますが、ようやく安定した生活も見えてきたところです。
――佐賀城下。多布施にある理化学研究所“精錬方”。
試験用火薬の見聞に来た、江藤。向学心は相変わらずで、就職前の準備にも余念がない。
「おおっ!“蘭学寮”に居った書生さんやないか。」
“精錬方”の石黒寛次が、江藤の存在に気付く。
石黒は、佐野栄寿(常民)が、京都留学で知り合った友達の1人。技術書の翻訳が得意な“蘭学者”である。
「近々、“火術方”のお役目に就きます。」

――江藤が、いつものよく通る声で、言葉を返した。
「“蘭学寮”は辞めちゃったと聞いたで。勿体(もったい)ないと思うてたんや。」
翻訳家・石黒には、江藤の学力の高さは一目瞭然だったようだ。
かつて“蘭学寮”の学生だった江藤。佐賀藩が所蔵する、西洋の書物を片っ端から読んで見識を高めていた。
「お役目に付けそうで良かったなぁ。」
現代風に言えば“就職内定おめでとう”の意を表す、翻訳家・石黒。
――石黒は、小屋に籠ってオランダ語などの書物を訳す仕事が多い。
もともと石黒寛次は、日本海に面した港町・舞鶴(京都)辺りの出身である。佐野の推薦で、佐賀城下にある研究所“精錬方”に就職した。
…そのため言葉には関西の訛(なま)りがあるが、佐賀藩士である。
「旅支度でございますか。」
江藤が、石黒に問う。
「あぁ、長崎に行く。また海軍の伝習に加わるんでな。」
「オランダの者から直接、教えを受けられるのですね。」
「その通りや。佐野や中村(奇輔)は、もう長崎に居るけどな。」
――この頃“精錬方”のメンバーは、佐賀と長崎の往来で忙しい。
「ほんまは、あんたぐらい賢ければ、伝習を受ける値打ちがあるけどな。」
石黒は“本当は長崎に行きたい”江藤の気持ちを察した。
「…これからは為すべきお役目に励みます。」
江藤は、真面目な答えを返した。
「まぁ、いずれ芽が出ることもあるやろ。佐賀はそういう所のはずや。」
石黒には、江藤の才能が燻(くすぶ)っている…と見えた。

――石黒は“余所(よそ)者”であるが、佐賀藩では重用されている。
「学び続けておれば、佐賀なら幾らでも“好機”がある…いうことや。」
これは、江藤への“励まし”であった。
「まず殿様が余所とは違うからな。賢い連中が“野放し”で動ける。」
石黒が念頭に置くのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。
殿・鍋島直正から佐野は、無茶ぶりとも思えるほど様々な命令を受けている。すごく縛られているはずが、石黒には「佐野は“自由”だ」と見えるらしい。
――「自分の頭で考えることが許され、前に進んでいる」から“自由”である。“研究者”である石黒らしい理解の仕方だった。
石黒の励ましは嬉しい反面、江藤には、その立場が羨ましくもあった。下級役人の仕事には、“精錬方”の研究者のような“自由”は無いだろう。
江藤の父・助右衛門(胤光)も上役と衝突して、職を辞した時期があり、江藤も貧乏を甘受してきたのだ。
「いずれは、殿のお役に立たねばならぬ…」
“殿様が余所とは違う”。その言葉が江藤には、響いていた。
――いつになく熱弁を振るった、翻訳家・石黒。
「あ…、また置いて行かれてしもうた。」
いつの間にか、長崎に向かう者たちは出立していた。
(続く)
前回は、江藤新平の結婚を題材としたお話でした。新しい家族を形成した頃、他にも“ライフイベント”が目白押しとなってくる江藤。
江藤の就職予定先は、“火術方目付”という佐賀藩の役職です。下級役人ではありますが、ようやく安定した生活も見えてきたところです。
――佐賀城下。多布施にある理化学研究所“精錬方”。
試験用火薬の見聞に来た、江藤。向学心は相変わらずで、就職前の準備にも余念がない。
「おおっ!“蘭学寮”に居った書生さんやないか。」
“精錬方”の石黒寛次が、江藤の存在に気付く。
石黒は、佐野栄寿(常民)が、京都留学で知り合った友達の1人。技術書の翻訳が得意な“蘭学者”である。
「近々、“火術方”のお役目に就きます。」
――江藤が、いつものよく通る声で、言葉を返した。
「“蘭学寮”は辞めちゃったと聞いたで。勿体(もったい)ないと思うてたんや。」
翻訳家・石黒には、江藤の学力の高さは一目瞭然だったようだ。
かつて“蘭学寮”の学生だった江藤。佐賀藩が所蔵する、西洋の書物を片っ端から読んで見識を高めていた。
「お役目に付けそうで良かったなぁ。」
現代風に言えば“就職内定おめでとう”の意を表す、翻訳家・石黒。
――石黒は、小屋に籠ってオランダ語などの書物を訳す仕事が多い。
もともと石黒寛次は、日本海に面した港町・舞鶴(京都)辺りの出身である。佐野の推薦で、佐賀城下にある研究所“精錬方”に就職した。
…そのため言葉には関西の訛(なま)りがあるが、佐賀藩士である。
「旅支度でございますか。」
江藤が、石黒に問う。
「あぁ、長崎に行く。また海軍の伝習に加わるんでな。」
「オランダの者から直接、教えを受けられるのですね。」
「その通りや。佐野や中村(奇輔)は、もう長崎に居るけどな。」
――この頃“精錬方”のメンバーは、佐賀と長崎の往来で忙しい。
「ほんまは、あんたぐらい賢ければ、伝習を受ける値打ちがあるけどな。」
石黒は“本当は長崎に行きたい”江藤の気持ちを察した。
「…これからは為すべきお役目に励みます。」
江藤は、真面目な答えを返した。
「まぁ、いずれ芽が出ることもあるやろ。佐賀はそういう所のはずや。」
石黒には、江藤の才能が燻(くすぶ)っている…と見えた。
――石黒は“余所(よそ)者”であるが、佐賀藩では重用されている。
「学び続けておれば、佐賀なら幾らでも“好機”がある…いうことや。」
これは、江藤への“励まし”であった。
「まず殿様が余所とは違うからな。賢い連中が“野放し”で動ける。」
石黒が念頭に置くのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。
殿・鍋島直正から佐野は、無茶ぶりとも思えるほど様々な命令を受けている。すごく縛られているはずが、石黒には「佐野は“自由”だ」と見えるらしい。
――「自分の頭で考えることが許され、前に進んでいる」から“自由”である。“研究者”である石黒らしい理解の仕方だった。
石黒の励ましは嬉しい反面、江藤には、その立場が羨ましくもあった。下級役人の仕事には、“精錬方”の研究者のような“自由”は無いだろう。
江藤の父・助右衛門(胤光)も上役と衝突して、職を辞した時期があり、江藤も貧乏を甘受してきたのだ。
「いずれは、殿のお役に立たねばならぬ…」
“殿様が余所とは違う”。その言葉が江藤には、響いていた。
――いつになく熱弁を振るった、翻訳家・石黒。
「あ…、また置いて行かれてしもうた。」
いつの間にか、長崎に向かう者たちは出立していた。
(続く)
2020年10月12日
第14話「遣米使節」⑧(孤高のエンジニア)
こんばんは。
第14話「遣米使節」は、主に幕末期に海外に渡った人物のお話です。長い“鎖国”の時代を経て、彼らが得た西洋の知識は、のちに明治を開く力となります。
――佐賀城下。佐賀藩の理化学研究所である“精錬方”。
ここにも熱く語る青年がいる。名を秀島藤之助という。
「螺旋(らせん)の切り込みを入れた“試作砲”を、ぜひ見たい!」
二代目・儀右衛門(田中久重の養子)が短く返答する。
「いまは忙しい。義父(ちち)の考えた機工を、一刻も早く形に成すのだ!」
「いい加減、義父(ちち)放れしてはどうか。」
「何だって…!?」
明らかに険しい表情をする“二代目”。義父が出張中なのを良いことに、秀島が挑発をしてきた…と受け取った。
――“二代目”にとって、尊敬する初代・儀右衛門(田中久重)の設計は絶対である。
秀島に悪気は無かった。技術者として自身の考えで動けば良い…と言いたかったのだ。
「だから、時が無い!今は“蒸気仕掛け”を急いでおるのだ!」
二代目・儀右衛門が、余計につむじを曲げる。
「少し見聞したいだけだ。手を貸してくれ!」
秀島も、長崎に向かわねばならないが、何とか事前に知識を得たいようだ。

――長崎への出立が遅れていた、翻訳家・石黒寛次が2人の様子を伺う。
「そこに居るんは、秀島さんやないか。まだ残っていたんか。」
石黒が声をかけたが、秀島は“二代目”との議論に集中して気付かない。
「…これは、当分、終わらんな。」
石黒は、たまたま現れた江藤新平と雑談をしていただけだが、この“大論戦”に関係していると勘違いされて、長崎に出る一行から置いていかれたらしい。
「二代目!儂も長崎に向かうで!」
「石黒さん!お気をつけて!」
秀島と一緒に、長崎に行くべきかと考えたが、かなり熱が入っていて難しそうだ。まだ冷静な“二代目”に、声をかけると石黒は一人、長崎への旅路を急ぐ。
――佐賀藩の“精錬方”。いつもの最先端研究のパターンはこうだ。
まず、石黒が洋書を翻訳し、科学者・中村奇輔が理論を解明する。
主に製造を担当するのが、“からくり儀右衛門”父子である。田中久重(初代)が機械を設計し、養子の二代目・儀右衛門が精密部品を加工する。
このメンバー全員をスカウトしてきたのが佐野栄寿(常民)。研究プロジェクトを管理するリーダーである。
――対して、秀島藤之助は、佐賀藩の鉄製大砲の改良を担当する。
秀島とて、新進気鋭の技術者である。しかし、経験値では“精錬方”のメンバーには劣る。孤高の天才と言うべき秀島は、必死で技術情報を収集していた。
「あいつら、大丈夫かな…」
“二代目”儀右衛門と秀島藤之助の議論の行方は気になるが、石黒は、すでに長崎の海軍伝習に向かう集団から出遅れているのだ。

――牛津宿。“西の浪花”(大坂)とまで呼ばれる商人の町。
石黒は、長崎の海軍伝習に向かう“蘭学寮”の若手に追いついた。現代で言えば高校生くらいの男子たちである。ちょっと道草をして、団子など食っていた。
「あ…石黒さま。お取込み中とお見受けし、お声もかけず失礼を。」
石丸虎五郎(安世)。のちに英語の達人になって、日本に電信網を築く人物。
「…我らがご城下を出た時から計ると…かなりの早足でお着きですね。」
中牟田倉之助である。のちに海軍で活躍する。算術が得意だ。
――ほかの若手も反応する「おおっ、精錬方の石黒さまだ」と。
佐賀藩の先端研究を支える“翻訳家”に、どよめく“蘭学寮”の若手たち。
石黒も、賢い若手たちからの反応なので、まんざら悪い気はしない。
「いや…儂など、小屋に籠(こも)って、洋書と“にらめっこ”しとるだけやで。」
「まさか、石黒先生と道中、ご一緒できるとは!」
「色々とご教示ください!」
――何やら楽しい道中で、すっかり気分良く長崎に到着した、石黒。
「佐野!中村~っ!儂も長崎に来たで!」
石黒は長崎の宿舎に着くや、元気よく京都時代からの旧友2人を呼んだ。しかし、2人はすでに不在だった。
「また、どこかに行っちゃっとる…」
このとき、佐野栄寿(常民)と中村奇輔の2人は、石黒の予想だにしない場所に居たのである。
(続く)
第14話「遣米使節」は、主に幕末期に海外に渡った人物のお話です。長い“鎖国”の時代を経て、彼らが得た西洋の知識は、のちに明治を開く力となります。
――佐賀城下。佐賀藩の理化学研究所である“精錬方”。
ここにも熱く語る青年がいる。名を秀島藤之助という。
「螺旋(らせん)の切り込みを入れた“試作砲”を、ぜひ見たい!」
二代目・儀右衛門(田中久重の養子)が短く返答する。
「いまは忙しい。義父(ちち)の考えた機工を、一刻も早く形に成すのだ!」
「いい加減、義父(ちち)放れしてはどうか。」
「何だって…!?」
明らかに険しい表情をする“二代目”。義父が出張中なのを良いことに、秀島が挑発をしてきた…と受け取った。
――“二代目”にとって、尊敬する初代・儀右衛門(田中久重)の設計は絶対である。
秀島に悪気は無かった。技術者として自身の考えで動けば良い…と言いたかったのだ。
「だから、時が無い!今は“蒸気仕掛け”を急いでおるのだ!」
二代目・儀右衛門が、余計につむじを曲げる。
「少し見聞したいだけだ。手を貸してくれ!」
秀島も、長崎に向かわねばならないが、何とか事前に知識を得たいようだ。
――長崎への出立が遅れていた、翻訳家・石黒寛次が2人の様子を伺う。
「そこに居るんは、秀島さんやないか。まだ残っていたんか。」
石黒が声をかけたが、秀島は“二代目”との議論に集中して気付かない。
「…これは、当分、終わらんな。」
石黒は、たまたま現れた江藤新平と雑談をしていただけだが、この“大論戦”に関係していると勘違いされて、長崎に出る一行から置いていかれたらしい。
「二代目!儂も長崎に向かうで!」
「石黒さん!お気をつけて!」
秀島と一緒に、長崎に行くべきかと考えたが、かなり熱が入っていて難しそうだ。まだ冷静な“二代目”に、声をかけると石黒は一人、長崎への旅路を急ぐ。
――佐賀藩の“精錬方”。いつもの最先端研究のパターンはこうだ。
まず、石黒が洋書を翻訳し、科学者・中村奇輔が理論を解明する。
主に製造を担当するのが、“からくり儀右衛門”父子である。田中久重(初代)が機械を設計し、養子の二代目・儀右衛門が精密部品を加工する。
このメンバー全員をスカウトしてきたのが佐野栄寿(常民)。研究プロジェクトを管理するリーダーである。
――対して、秀島藤之助は、佐賀藩の鉄製大砲の改良を担当する。
秀島とて、新進気鋭の技術者である。しかし、経験値では“精錬方”のメンバーには劣る。孤高の天才と言うべき秀島は、必死で技術情報を収集していた。
「あいつら、大丈夫かな…」
“二代目”儀右衛門と秀島藤之助の議論の行方は気になるが、石黒は、すでに長崎の海軍伝習に向かう集団から出遅れているのだ。
――牛津宿。“西の浪花”(大坂)とまで呼ばれる商人の町。
石黒は、長崎の海軍伝習に向かう“蘭学寮”の若手に追いついた。現代で言えば高校生くらいの男子たちである。ちょっと道草をして、団子など食っていた。
「あ…石黒さま。お取込み中とお見受けし、お声もかけず失礼を。」
石丸虎五郎(安世)。のちに英語の達人になって、日本に電信網を築く人物。
「…我らがご城下を出た時から計ると…かなりの早足でお着きですね。」
中牟田倉之助である。のちに海軍で活躍する。算術が得意だ。
――ほかの若手も反応する「おおっ、精錬方の石黒さまだ」と。
佐賀藩の先端研究を支える“翻訳家”に、どよめく“蘭学寮”の若手たち。
石黒も、賢い若手たちからの反応なので、まんざら悪い気はしない。
「いや…儂など、小屋に籠(こも)って、洋書と“にらめっこ”しとるだけやで。」
「まさか、石黒先生と道中、ご一緒できるとは!」
「色々とご教示ください!」
――何やら楽しい道中で、すっかり気分良く長崎に到着した、石黒。
「佐野!中村~っ!儂も長崎に来たで!」
石黒は長崎の宿舎に着くや、元気よく京都時代からの旧友2人を呼んだ。しかし、2人はすでに不在だった。
「また、どこかに行っちゃっとる…」
このとき、佐野栄寿(常民)と中村奇輔の2人は、石黒の予想だにしない場所に居たのである。
(続く)
2020年10月14日
第14話「遣米使節」⑨(聞かれては困る話)
こんばんは。
前回の続きです。
長崎に着いて、佐野栄寿(常民)と中村奇輔に再会できると思った、翻訳家・石黒。しかし、宿舎に両名の姿は見当たりません。
少し時を遡って、佐野・中村の2名の足取りを追ってみます。
――長崎の夜。ある立派な屋敷の…屋根に佇(たたず)む者がいる。
見張りの役目にあたる、佐賀の蓮池藩士・古賀である。もはや“嬉野の忍者”といった方が通りが良いかもしれない。
そこに、屋根伝いに進む影があった。
「この辺りにも、ネズミさんが増えとるばい。」
影に近付いて声をかける、古賀。

――古賀の声に、他藩の忍びと思われる“ネズミ”が反応する。
「…なんじゃ、貴様。佐賀の“化け猫”か。」
「誰が“化け猫”やら言いよっとね!?」
バサッ!
古賀が言葉を返すや、“ネズミ”は右手から粉状の“目つぶし”を放った。
「…甘いんじゃ!」
――捨て台詞(ぜりふ)を吐く忍び。逃走の準備に入る。
しかし“目つぶし”を撒いた先には、すでに古賀の影は無い。
「昨今は“ネズミ”も、よう吠えよっとね…」
不意打ちを、低く丸くかわして“ネズミ”の背後に回っていたのである。
「…後ろに居たかっ!」
“ネズミ”と呼ばれた“忍び”の動きも速い。左手に持った短刀で背後を突く。
――古賀は、小刀を抜き付け、受け流す。
ギュルッ…
生々しい金属音がする。
バシッ!
…その瞬間、古賀の右足が伸び、“忍び”の腰を捉えた。
ガラン、ガラガラ…
勢い余ったところに、古賀に蹴りを加えられ、“忍び”の体勢は泳いだ。そのまま屋根から転げる。

――“忍び”は屋敷を見張る、佐賀藩“深堀領”の警備兵の間に落ちた。
「何奴(なにやつ)!屋根から降ってきたぞ。」
「…見るからに怪しかばい!」
ビシッ!ボコッ!
“深堀領”とは、長崎にある佐賀藩の領地(飛び地)。
長崎警備の第一線にあたる佐賀藩士たちは、怒らせると怖い。
――落ちた“忍び”は術を遣う間もなく、打ちのめされている様子だ。
地上の騒ぎを眺める“嬉野の忍者”古賀。
「明日は“我が身”かも知れんばい。えすか(怖い)ごたね…」
…忍びの定めを感じて、一言つぶやくと、また屋根の見張りに戻るのだった。
――この厳重な警備には理由があった。
殿・鍋島直正が、佐賀から長崎に来ていたのだ。辺りが騒々しいが、すぐ隣の屋敷では「聞かれては困る話」の最中である。
「此度(こたび)の航海では、薩摩に参るぞ!」
「殿…。“さつま”って、あの“薩摩”(鹿児島)ですか。」
「殿、念のためお伺いします。“観光丸”は公儀(幕府)からの預かり物です。」
「そうじゃ、良き船であるからのう。出航が楽しみであるな。」
――呆気に取られている2人、佐野栄寿(常民)と化学者・中村奇輔。
殿・直正は「幕府から借りた蒸気船“観光丸”で、薩摩に乗り入れる!」と告げたのである。2人が驚くのも無理はない。まだ“大名行列”の時代なのだ。
たしかに薩摩藩の島津斉彬は、殿・直正のいとこではあるが、他の大名の領国へ、直接、蒸気船で訪問するなど前代未聞の事だった。
佐野も「殿に海軍伝習で得た実力を見せよう!」と張り切っていた。しかし、訓練の成果を示すどころか、大変な船旅が始まろうとしていたのである。
(続く)
前回の続きです。
長崎に着いて、佐野栄寿(常民)と中村奇輔に再会できると思った、翻訳家・石黒。しかし、宿舎に両名の姿は見当たりません。
少し時を遡って、佐野・中村の2名の足取りを追ってみます。
――長崎の夜。ある立派な屋敷の…屋根に佇(たたず)む者がいる。
見張りの役目にあたる、佐賀の蓮池藩士・古賀である。もはや“嬉野の忍者”といった方が通りが良いかもしれない。
そこに、屋根伝いに進む影があった。
「この辺りにも、ネズミさんが増えとるばい。」
影に近付いて声をかける、古賀。
――古賀の声に、他藩の忍びと思われる“ネズミ”が反応する。
「…なんじゃ、貴様。佐賀の“化け猫”か。」
「誰が“化け猫”やら言いよっとね!?」
バサッ!
古賀が言葉を返すや、“ネズミ”は右手から粉状の“目つぶし”を放った。
「…甘いんじゃ!」
――捨て台詞(ぜりふ)を吐く忍び。逃走の準備に入る。
しかし“目つぶし”を撒いた先には、すでに古賀の影は無い。
「昨今は“ネズミ”も、よう吠えよっとね…」
不意打ちを、低く丸くかわして“ネズミ”の背後に回っていたのである。
「…後ろに居たかっ!」
“ネズミ”と呼ばれた“忍び”の動きも速い。左手に持った短刀で背後を突く。
――古賀は、小刀を抜き付け、受け流す。
ギュルッ…
生々しい金属音がする。
バシッ!
…その瞬間、古賀の右足が伸び、“忍び”の腰を捉えた。
ガラン、ガラガラ…
勢い余ったところに、古賀に蹴りを加えられ、“忍び”の体勢は泳いだ。そのまま屋根から転げる。

――“忍び”は屋敷を見張る、佐賀藩“深堀領”の警備兵の間に落ちた。
「何奴(なにやつ)!屋根から降ってきたぞ。」
「…見るからに怪しかばい!」
ビシッ!ボコッ!
“深堀領”とは、長崎にある佐賀藩の領地(飛び地)。
長崎警備の第一線にあたる佐賀藩士たちは、怒らせると怖い。
――落ちた“忍び”は術を遣う間もなく、打ちのめされている様子だ。
地上の騒ぎを眺める“嬉野の忍者”古賀。
「明日は“我が身”かも知れんばい。えすか(怖い)ごたね…」
…忍びの定めを感じて、一言つぶやくと、また屋根の見張りに戻るのだった。
――この厳重な警備には理由があった。
殿・鍋島直正が、佐賀から長崎に来ていたのだ。辺りが騒々しいが、すぐ隣の屋敷では「聞かれては困る話」の最中である。
「此度(こたび)の航海では、薩摩に参るぞ!」
「殿…。“さつま”って、あの“薩摩”(鹿児島)ですか。」
「殿、念のためお伺いします。“観光丸”は公儀(幕府)からの預かり物です。」
「そうじゃ、良き船であるからのう。出航が楽しみであるな。」
――呆気に取られている2人、佐野栄寿(常民)と化学者・中村奇輔。
殿・直正は「幕府から借りた蒸気船“観光丸”で、薩摩に乗り入れる!」と告げたのである。2人が驚くのも無理はない。まだ“大名行列”の時代なのだ。
たしかに薩摩藩の島津斉彬は、殿・直正のいとこではあるが、他の大名の領国へ、直接、蒸気船で訪問するなど前代未聞の事だった。
佐野も「殿に海軍伝習で得た実力を見せよう!」と張り切っていた。しかし、訓練の成果を示すどころか、大変な船旅が始まろうとしていたのである。
(続く)
2020年10月16日
第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)
こんばんは。
前回、殿・鍋島直正が、薩摩(鹿児島)に蒸気船で向かう計画を明かしました。当時の薩摩藩主・島津斉彬は、殿の母方のいとこにあたります。
この航海の目的は判然としておらず、時期にも諸説ありますが、「日米修好通商条約」締結の直前期で、何らかの相談があった…と推測されています。
――長崎。ある蒸気船の甲板。
佐賀藩が、幕府から訓練のため借りている“観光丸”である。
「ふーっ!」
大きく深呼吸をする、佐野栄寿(常民)。この航海の船長に重責がのしかかる。
「佐野はん。いや、船長。いよいよやな。」
化学・物理の双方に通じた、科学者・中村奇輔。出身地の“京言葉”が抜けない佐賀藩士である。
中村も、殿・直正の指示で、自作した“電信機”を手土産に薩摩に向かうのだ。
――このとき、佐賀の殿様も、密かに船に乗り込んだ。
肥前佐賀35万7千石の当主・鍋島直正。
佐賀と薩摩。外様の大藩同士での“密談”に向かうのである。そして、幕府には単なる訓練の航海で届け出ている。
「佐野。よろしく頼むぞ。」
「はっ!」
――秘密の航海には、危険が伴う。
その途上で事故でもあれば、佐賀藩が危機に瀕するのは明らかだった。
さすがの佐野も、緊張で手がブルブルとする。
「船出だ!帆を上げろ!」
「はい!!船長!」
海軍伝習の経験者が先導し、佐賀の水夫(船手方)たちも動く。
――この頃は蒸気船でも、燃料補給の問題もあり、よく帆走を使う。
“観光丸”は、ゆらりと風を受けて長崎を出港した。
港から離れると、殿・直正が甲板に現れた。殿様も、窮屈な生活である。ましてや、直正ほどの“実力”がある大名は、常に動向が注目されている。
「…海は良いのう。潮風が快い。」
「はっ、今日は良き日和(ひより)です。」
順調な船出に安堵した、佐野が応える。
「この海の向こう、この目で見てみたいものよ。」
いつになく、大きく伸びをする直正。遠く、海の彼方を見遣っていた。

――風が弱まり、凪(なぎ)となる。
「この時を待っておった!行け、佐野よ。」
殿・直正が弾んだ声をかける。
「汽走に切り換えるぞ!」
佐野が、海軍伝習を受けた士官たちに“蒸気機関”の起動を指示した。
ボッ…
煙突から、ゆらゆらと黒煙が立ち上がる。
ガランガラン…
船の両舷(げん)にある“外輪”が、水車のようにゆっくり回転を始める。
――わずか4年ばかり前。日本を驚愕させた“黒船”。
佐賀藩士たちは、いまや自在に蒸気船を操り、薩摩に向かっているのだ。
外輪は勢いよく水を掻き、“観光丸”は速度を増している。
「取り舵(左に旋回)だ。」
佐野が海図を見ながら、指示を出す。船は着実に南方へと進む。
「…いやぁ、やっぱり“蒸気機関”は、ええなぁ!」
作業からご機嫌で帰ってきた、中村奇輔。
――顔中が、炭で煤(すす)けているが笑顔である。
「中村よ。また、ずいぶん“蒸気仕掛け”と戯れたと見えるな。」
殿・直正が、中村にも声をかける。
「これは…お殿様。まぁ、仰せの通りです。」
恐縮しながらも、やはり楽しそうな中村。
「お主が、佐賀に来てくれて良かった。」
「はっ、勿体(もったい)なき、お言葉。私こそ果報者です。」
佐野からの誘いに応じて中村は、京都から佐賀に来た。蒸気機関を設計したり、電信機を作ったり…これが中村にとって、幸せな日々なのである。

――航海は順調に進む。薩摩の桜島(錦江湾)に寄せていく“観光丸”。
「殿…なにゆえ危険を顧みず、薩摩まで…」
佐野は船上で、ずっと聞きたかったことを、直正に尋ねた。
「薩摩さまに、差し出がましいことを申し上げるためじゃ。」
「…!?」
「狭い日本(ひのもと)で、“小競り合い”を為しても仕方ないとな。」
(続く)
前回、殿・鍋島直正が、薩摩(鹿児島)に蒸気船で向かう計画を明かしました。当時の薩摩藩主・島津斉彬は、殿の母方のいとこにあたります。
この航海の目的は判然としておらず、時期にも諸説ありますが、「日米修好通商条約」締結の直前期で、何らかの相談があった…と推測されています。
――長崎。ある蒸気船の甲板。
佐賀藩が、幕府から訓練のため借りている“観光丸”である。
「ふーっ!」
大きく深呼吸をする、佐野栄寿(常民)。この航海の船長に重責がのしかかる。
「佐野はん。いや、船長。いよいよやな。」
化学・物理の双方に通じた、科学者・中村奇輔。出身地の“京言葉”が抜けない佐賀藩士である。
中村も、殿・直正の指示で、自作した“電信機”を手土産に薩摩に向かうのだ。
――このとき、佐賀の殿様も、密かに船に乗り込んだ。
肥前佐賀35万7千石の当主・鍋島直正。
佐賀と薩摩。外様の大藩同士での“密談”に向かうのである。そして、幕府には単なる訓練の航海で届け出ている。
「佐野。よろしく頼むぞ。」
「はっ!」
――秘密の航海には、危険が伴う。
その途上で事故でもあれば、佐賀藩が危機に瀕するのは明らかだった。
さすがの佐野も、緊張で手がブルブルとする。
「船出だ!帆を上げろ!」
「はい!!船長!」
海軍伝習の経験者が先導し、佐賀の水夫(船手方)たちも動く。
――この頃は蒸気船でも、燃料補給の問題もあり、よく帆走を使う。
“観光丸”は、ゆらりと風を受けて長崎を出港した。
港から離れると、殿・直正が甲板に現れた。殿様も、窮屈な生活である。ましてや、直正ほどの“実力”がある大名は、常に動向が注目されている。
「…海は良いのう。潮風が快い。」
「はっ、今日は良き日和(ひより)です。」
順調な船出に安堵した、佐野が応える。
「この海の向こう、この目で見てみたいものよ。」
いつになく、大きく伸びをする直正。遠く、海の彼方を見遣っていた。

――風が弱まり、凪(なぎ)となる。
「この時を待っておった!行け、佐野よ。」
殿・直正が弾んだ声をかける。
「汽走に切り換えるぞ!」
佐野が、海軍伝習を受けた士官たちに“蒸気機関”の起動を指示した。
ボッ…
煙突から、ゆらゆらと黒煙が立ち上がる。
ガランガラン…
船の両舷(げん)にある“外輪”が、水車のようにゆっくり回転を始める。
――わずか4年ばかり前。日本を驚愕させた“黒船”。
佐賀藩士たちは、いまや自在に蒸気船を操り、薩摩に向かっているのだ。
外輪は勢いよく水を掻き、“観光丸”は速度を増している。
「取り舵(左に旋回)だ。」
佐野が海図を見ながら、指示を出す。船は着実に南方へと進む。
「…いやぁ、やっぱり“蒸気機関”は、ええなぁ!」
作業からご機嫌で帰ってきた、中村奇輔。
――顔中が、炭で煤(すす)けているが笑顔である。
「中村よ。また、ずいぶん“蒸気仕掛け”と戯れたと見えるな。」
殿・直正が、中村にも声をかける。
「これは…お殿様。まぁ、仰せの通りです。」
恐縮しながらも、やはり楽しそうな中村。
「お主が、佐賀に来てくれて良かった。」
「はっ、勿体(もったい)なき、お言葉。私こそ果報者です。」
佐野からの誘いに応じて中村は、京都から佐賀に来た。蒸気機関を設計したり、電信機を作ったり…これが中村にとって、幸せな日々なのである。
――航海は順調に進む。薩摩の桜島(錦江湾)に寄せていく“観光丸”。
「殿…なにゆえ危険を顧みず、薩摩まで…」
佐野は船上で、ずっと聞きたかったことを、直正に尋ねた。
「薩摩さまに、差し出がましいことを申し上げるためじゃ。」
「…!?」
「狭い日本(ひのもと)で、“小競り合い”を為しても仕方ないとな。」
(続く)
2020年10月20日
第14話「遣米使節」⑪(名君たちの“約束”)
こんばんは。
“本編”に戻ります。第14話「遣米使節」すでに11回目の投稿ですが、あと4回くらいは要りそうです。
「大河ドラマ」ならば1話分が45分で、オープニングとエンディング(紀行)を入れれば、実質40分ほど…この展開では、おそらく尺が足らないのですが、このまま描きたいので、続行します。〔前回参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕
――“トン・ツー・ツー・トン” 電信機で、信号を送る。
操作するのは佐賀藩士・中村奇輔。京都から来た“精錬方”の科学者である。
「中村さん、ゆくさ(ようこそ)おじゃった(お越しになった)。」
「こい(これ)は、おんし(お主)が?」
ザワザワとする薩摩藩士たち。
持参した電信機は、中村が作ったものである。
「西洋の物とて仕組みが明らかなら作れます。あとは“費用”の問題だけです。」
中村が、さらりと言ってのけた。
――場所は、薩摩(鹿児島)が力を注ぐ、近代化のための工場 “集成館”。
薩摩藩も研究開発に熱心である。中村の技術の価値も、すぐに理解される。
そんな薩摩の若者たちの標(しるべ)となる“光”が、薩摩藩主・島津斉彬。佐賀から蒸気船でやって来た、鍋島直正と、海沿いの庭園で歓談をする。
「さすがは、薩摩の”紅びいどろ”。鮮やかなものですな。」
殿・直正が、透き通った紅色のグラスを手に取り、見つめている。
「さすが佐賀の品、“隙の無い”仕上がりだな。」
一方、島津斉彬は、“肥前びいどろ”を見分していた。

――さて、この名君2人。会談の目的は“ガラス”の品評だけではない。
まず、口を開いたのは島津斉彬である。
「なにゆえ、一橋さまのご推挙に、お力添えくださらぬ?」
薩摩藩は、一橋慶喜を次期将軍に推す“一橋派”の急先鋒だった。佐賀の殿・直正はその活動から距離を置いている。
「それは、公儀(幕府)がお決めになること。外様の口出しは無用にござろう。」
蒸気船を乗り回しはするが、鍋島直正は秩序を重んじる“優等生”である。
「時勢は動くぞ。若年の上様(将軍)では、国の舵取りは難しいとは思わぬか。」
この頃、”一橋派”の理解者で、調整能力が抜群だった、老中・阿部正弘は既に逝去している。薩摩の殿・島津斉彬にも焦りがあった。
――佐賀と薩摩の殿様。話は並行線である。
達観したような表情の殿・直正。何か遠くを見通すような目である。
「…ほう、幼き頃と同じ顔をいたすのだな。」
島津斉彬と、年下の鍋島直正とは、母方のいとこで幼少期から交際がある。
「上様(将軍)のご推挙に口を出さば、相争うことにつながる。」
直正の心配事は、政治の主導権争いによる日本国内での“同士討ち”だった。
「その間に異国が割って入るのを、案じておられるか。」
「…ご明察。」
次期将軍の選定と、通商条約の締結は、この頃の二大争点だった。西洋文明の実力を知る名君2人は、異国の具体的な行動をイメージするのだ。

――手紙では、この“想い”までは通じない。
直正が危険を顧みず、薩摩への船旅を強行した理由でもあった。
ふふ…と笑う斉彬。
「相分かった。異国には付け入る隙を与えぬよう、肝に銘じておくとしよう。」
「約束ですぞ。くれぐれもお忘れ無きように。」
直正は子供のときのような、いたずらな笑みを見せた。
こうして“秘密の会談”を終えた、2人の名君。結論から言えば、この“約束”は果たされなかった。ほどなく、一方の当事者が世を去ったからである。
――蒸気船“観光丸”での帰路。
船長・佐野栄寿(常民)が、あらためて緊張している。
「佐賀に戻るまでが大事!帰り道こそ、気を引き締めねば!」
「佐野はん!気負い過ぎは、あきまへん(ダメですよ)。」
中村も少し気が抜けたのか、“京言葉”に戻っている。
「そうじゃ、佐野。伸び伸びとやればよい。」
殿・直正が船長に言葉をかける。しかし、佐野の緊張のもとは、その殿様を無事に送り届ける使命感からなのだ。
(続く)
“本編”に戻ります。第14話「遣米使節」すでに11回目の投稿ですが、あと4回くらいは要りそうです。
「大河ドラマ」ならば1話分が45分で、オープニングとエンディング(紀行)を入れれば、実質40分ほど…この展開では、おそらく尺が足らないのですが、このまま描きたいので、続行します。〔前回参照:
――“トン・ツー・ツー・トン” 電信機で、信号を送る。
操作するのは佐賀藩士・中村奇輔。京都から来た“精錬方”の科学者である。
「中村さん、ゆくさ(ようこそ)おじゃった(お越しになった)。」
「こい(これ)は、おんし(お主)が?」
ザワザワとする薩摩藩士たち。
持参した電信機は、中村が作ったものである。
「西洋の物とて仕組みが明らかなら作れます。あとは“費用”の問題だけです。」
中村が、さらりと言ってのけた。
――場所は、薩摩(鹿児島)が力を注ぐ、近代化のための工場 “集成館”。
薩摩藩も研究開発に熱心である。中村の技術の価値も、すぐに理解される。
そんな薩摩の若者たちの標(しるべ)となる“光”が、薩摩藩主・島津斉彬。佐賀から蒸気船でやって来た、鍋島直正と、海沿いの庭園で歓談をする。
「さすがは、薩摩の”紅びいどろ”。鮮やかなものですな。」
殿・直正が、透き通った紅色のグラスを手に取り、見つめている。
「さすが佐賀の品、“隙の無い”仕上がりだな。」
一方、島津斉彬は、“肥前びいどろ”を見分していた。
――さて、この名君2人。会談の目的は“ガラス”の品評だけではない。
まず、口を開いたのは島津斉彬である。
「なにゆえ、一橋さまのご推挙に、お力添えくださらぬ?」
薩摩藩は、一橋慶喜を次期将軍に推す“一橋派”の急先鋒だった。佐賀の殿・直正はその活動から距離を置いている。
「それは、公儀(幕府)がお決めになること。外様の口出しは無用にござろう。」
蒸気船を乗り回しはするが、鍋島直正は秩序を重んじる“優等生”である。
「時勢は動くぞ。若年の上様(将軍)では、国の舵取りは難しいとは思わぬか。」
この頃、”一橋派”の理解者で、調整能力が抜群だった、老中・阿部正弘は既に逝去している。薩摩の殿・島津斉彬にも焦りがあった。
――佐賀と薩摩の殿様。話は並行線である。
達観したような表情の殿・直正。何か遠くを見通すような目である。
「…ほう、幼き頃と同じ顔をいたすのだな。」
島津斉彬と、年下の鍋島直正とは、母方のいとこで幼少期から交際がある。
「上様(将軍)のご推挙に口を出さば、相争うことにつながる。」
直正の心配事は、政治の主導権争いによる日本国内での“同士討ち”だった。
「その間に異国が割って入るのを、案じておられるか。」
「…ご明察。」
次期将軍の選定と、通商条約の締結は、この頃の二大争点だった。西洋文明の実力を知る名君2人は、異国の具体的な行動をイメージするのだ。

――手紙では、この“想い”までは通じない。
直正が危険を顧みず、薩摩への船旅を強行した理由でもあった。
ふふ…と笑う斉彬。
「相分かった。異国には付け入る隙を与えぬよう、肝に銘じておくとしよう。」
「約束ですぞ。くれぐれもお忘れ無きように。」
直正は子供のときのような、いたずらな笑みを見せた。
こうして“秘密の会談”を終えた、2人の名君。結論から言えば、この“約束”は果たされなかった。ほどなく、一方の当事者が世を去ったからである。
――蒸気船“観光丸”での帰路。
船長・佐野栄寿(常民)が、あらためて緊張している。
「佐賀に戻るまでが大事!帰り道こそ、気を引き締めねば!」
「佐野はん!気負い過ぎは、あきまへん(ダメですよ)。」
中村も少し気が抜けたのか、“京言葉”に戻っている。
「そうじゃ、佐野。伸び伸びとやればよい。」
殿・直正が船長に言葉をかける。しかし、佐野の緊張のもとは、その殿様を無事に送り届ける使命感からなのだ。
(続く)
2020年10月22日
第14話「遣米使節」⑫(遠くまで…)
こんばんは。
今回の投稿は、長崎で“写真術”を身に付けた佐賀藩医が登場します。日本の“ジャーナリスト”の先駆けの1人、川崎道民です。
〔参照(終盤):第13話「通商条約」④(お大事になされませ!)〕
年代は少し進んで1859年頃の設定です。もちろん、殿・鍋島直正は無事に薩摩から帰還しています。
「通商条約の締結」「安政の大獄」と激動の時代は進み、豪腕とも評された、大老・井伊直弼が、幕府で奮闘していた時期のお話です。
〔参照(終盤):第13話「通商条約」⑬(豪腕、唸〔うな〕る)〕
――佐賀城内。北の堀端に面した“須古鍋島家”の屋敷。
“須古”は、現在の白石町にあった自治領。その領主・鍋島安房(茂真)は佐賀藩の請役(ナンバー2)を務める。
直正より1歳年上の異母兄は、30年近くも殿・直正を支え続けていた。
「川崎よ。立派になったな。」
「安房様から、学ぶ場をお授けいただいたのです。」
ひたすら感謝の意を述べている、坊主頭の青年。名を川崎道民という。利発そうな丸顔の若者である。

――川崎道民は、“須古領”の侍医(お付きの医者)に養子に入っていた。
鍋島安房は、才能ある川崎道民を領内に留めず、佐賀の藩医に推挙した。こうして川崎は、進んだ西洋の医術を学ぶことができた。
ふと、川崎が“良い事を思い付いた!”と、その表情を緩める。
「長崎にて、面白き業(わざ)を身に付けて参りました!」
「ほう…」
“興味がある”という反応の鍋島安房。この姿勢は変わらない。長年、寝る間も惜しんで、下級藩士たちの話も大切に聞き続けてきた。
昔日は、仕事場と藩校「弘道館」との往復に走り回ったが、今はその気力は感じられず、病身にも伺える。
――しかし探求心は、まだ失われていない様子だ。
「“写真”と呼ばれる業に、ございます。」
「人の姿を、ありのままに写すという業か。」
「左様(その通り)です。」
「もし、宜しければ…」
川崎は、“写真”撮影を提案した。
鍋島安房は、フッと寂しげな表情を浮かべる。
「今の私のありのままには、もはや値打ちは無い。」
――自分を引き立ててくれた、“ご領主”の言葉は芳(かんば)しくない。
川崎も、意気消沈の様子を見せる。
「…川崎よ。お主が写すべきものは、もっと遠くに、遥か向こうにあるのではないか。」
鍋島安房の目には、まだ確かな光が宿っている。その言葉に川崎は、ハッと胸を打たれた。
「…世を広く見聞し、必ずやご期待に応えてお見せします。」
川崎は、鍋島安房の言葉を受け止めた。
――元は、主従の関係だった、この2人。想いは引き継がれた。
ほどなく川崎道民は江戸に向かった。
そして、長年に渡って鍋島直正の補佐役を務めた、鍋島安房は“罷免”という形で表舞台を去っていく。

――1859年。江戸の佐賀藩邸。
川崎道民が、写真の道具を扱っている。この年に撮影されたものが、鍋島直正の肖像写真として最も有名な1枚として知られる。
「…川崎。もう動いても良いか?」
「殿…しばし、しばしのお待ちを!」
「“写真”も、なかなかに窮屈なものよ。」
「良き写りを得るためには、辛抱こそが肝要でござる!」
――殿・直正の“写真”撮影に奮闘する、川崎道民。
「ところで…川崎よ。メリケン(アメリカ)に行かぬか?」
「殿、しばし!動かずにお待ちを…え!?」
「海の向こうの異国、メリケンじゃ。」
「…殿。良き1枚が撮れたようです。」
殿・直正から、突然の海外渡航の提案。動揺する川崎道民だったが、さすがは佐賀の藩医。抜かりなく撮影は成し遂げた様子だ。
(続く)
今回の投稿は、長崎で“写真術”を身に付けた佐賀藩医が登場します。日本の“ジャーナリスト”の先駆けの1人、川崎道民です。
〔参照(終盤):
年代は少し進んで1859年頃の設定です。もちろん、殿・鍋島直正は無事に薩摩から帰還しています。
「通商条約の締結」「安政の大獄」と激動の時代は進み、豪腕とも評された、大老・井伊直弼が、幕府で奮闘していた時期のお話です。
〔参照(終盤):
――佐賀城内。北の堀端に面した“須古鍋島家”の屋敷。
“須古”は、現在の白石町にあった自治領。その領主・鍋島安房(茂真)は佐賀藩の請役(ナンバー2)を務める。
直正より1歳年上の異母兄は、30年近くも殿・直正を支え続けていた。
「川崎よ。立派になったな。」
「安房様から、学ぶ場をお授けいただいたのです。」
ひたすら感謝の意を述べている、坊主頭の青年。名を川崎道民という。利発そうな丸顔の若者である。

――川崎道民は、“須古領”の侍医(お付きの医者)に養子に入っていた。
鍋島安房は、才能ある川崎道民を領内に留めず、佐賀の藩医に推挙した。こうして川崎は、進んだ西洋の医術を学ぶことができた。
ふと、川崎が“良い事を思い付いた!”と、その表情を緩める。
「長崎にて、面白き業(わざ)を身に付けて参りました!」
「ほう…」
“興味がある”という反応の鍋島安房。この姿勢は変わらない。長年、寝る間も惜しんで、下級藩士たちの話も大切に聞き続けてきた。
昔日は、仕事場と藩校「弘道館」との往復に走り回ったが、今はその気力は感じられず、病身にも伺える。
――しかし探求心は、まだ失われていない様子だ。
「“写真”と呼ばれる業に、ございます。」
「人の姿を、ありのままに写すという業か。」
「左様(その通り)です。」
「もし、宜しければ…」
川崎は、“写真”撮影を提案した。
鍋島安房は、フッと寂しげな表情を浮かべる。
「今の私のありのままには、もはや値打ちは無い。」
――自分を引き立ててくれた、“ご領主”の言葉は芳(かんば)しくない。
川崎も、意気消沈の様子を見せる。
「…川崎よ。お主が写すべきものは、もっと遠くに、遥か向こうにあるのではないか。」
鍋島安房の目には、まだ確かな光が宿っている。その言葉に川崎は、ハッと胸を打たれた。
「…世を広く見聞し、必ずやご期待に応えてお見せします。」
川崎は、鍋島安房の言葉を受け止めた。
――元は、主従の関係だった、この2人。想いは引き継がれた。
ほどなく川崎道民は江戸に向かった。
そして、長年に渡って鍋島直正の補佐役を務めた、鍋島安房は“罷免”という形で表舞台を去っていく。

――1859年。江戸の佐賀藩邸。
川崎道民が、写真の道具を扱っている。この年に撮影されたものが、鍋島直正の肖像写真として最も有名な1枚として知られる。
「…川崎。もう動いても良いか?」
「殿…しばし、しばしのお待ちを!」
「“写真”も、なかなかに窮屈なものよ。」
「良き写りを得るためには、辛抱こそが肝要でござる!」
――殿・直正の“写真”撮影に奮闘する、川崎道民。
「ところで…川崎よ。メリケン(アメリカ)に行かぬか?」
「殿、しばし!動かずにお待ちを…え!?」
「海の向こうの異国、メリケンじゃ。」
「…殿。良き1枚が撮れたようです。」
殿・直正から、突然の海外渡航の提案。動揺する川崎道民だったが、さすがは佐賀の藩医。抜かりなく撮影は成し遂げた様子だ。
(続く)
2020年10月26日
第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)
こんばんは。
前回、鍋島直正の写真を撮影していた佐賀藩医・川崎道民。殿から出し抜けにアメリカ行きを提案される場面を描きました。
今回の投稿は、様々な場所で佐賀藩士たちの運命が動いていきます。日本における“英学の夜明け”という時期でしょうか。
――江戸。殿・直正から海外渡航の勧めを受けた、川崎道民。
「メリケン(アメリカ)に、ございますか!?」
「そうじゃ。医術や文物を見聞いたせ。お主なら“写真術”も遣える。」
この頃、幕府は“日米修好通商条約”の批准書を交換するため、アメリカに使節派遣を予定している。
日本の近代外交の扉は開いた。佐賀藩には、この機会に優秀な人物を海外に送り込み、西洋の事情を探ろうという意図があった。
「川崎は、腕の良い医者であるからな。同行すれば、皆も安心であろう。」
「皆…!?佐賀から、幾人もメリケンに行くのでございますか?」

――医者の髪型に、よくある坊主頭。川崎は、目を丸くして殿・直正に問う。
「無論じゃ。川崎よ、皆を頼むぞ。」
この使節団には、佐賀藩士8名が参加することになった。
川崎は、地元である“須古”の領主・鍋島安房の言葉を想い出した。恩義あるご領主からも「広く世を見聞せよ」と期待をされているのだ。
「この川崎、メリケンの進んだ技術を得られる限り、得て参ります。」
「…はっはっは。良い心意気じゃ。」
――川崎の反応は、直正の予想を上回るほど“前のめり”だった。
「仕度金は、百両でよいか。抜かりなく用意を致せ。」
「はっ!…百両も…!ありがたき幸せ!」
こうして、藩医・川崎道民のアメリカ行きが決まる。幕府の使節団が乗り込むアメリカ海軍の蒸気船に同乗することとなった。
船名を“ポーハタン号”という。アメリカのペリーが2度目の来日で乗船し、ハリスとの通商条約の調印場所になった、全長77メートル超の外輪蒸気船である。
――同じ頃、佐賀城下の“火術方”にて。
作業場で、オランダ語の技術書と睨み合う人物がいた。大砲の改良案を練る技術者・秀島藤之助。
〔参照:第14話「遣米使節」⑧(孤高のエンジニア)〕
「秀島さま!お城からのお呼びです!」
いきなり電流が走るような声が通った。
「…何だ!?いきなり大声で。お主はたしか…?」
耳を抑える秀島。よく通る声でツーンと来た様子である。

――声の主は“火術方”に下級役人として採用された、江藤新平。
「秀島さま!その図面は、新しい製砲の試みでござるか。」
江藤は蘭学を学んだので、ある程度、技術者たちの作業が理解できる。
「あぁ、そうだ。たしか江藤と言ったな。そこまで声を通さずとも聞こえている…」
寝る間も惜しみ研究をする、秀島。寝不足には江藤の地声は堪(こた)える。
「急ぎ、城へお向かいください!」
「…相分かった。」
――殿・直正が期待する、技術者・秀島藤之助もアメリカ行きが決定した。
使節を乗せる“ポーハタン号”を護衛するとの名目で、幕府も船を派遣する。
船名を“咸臨丸”という、秀島はそちらに乗船することとなった。
秀島の任務は、主に艦船や大砲などの調査である。
「メリケン(アメリカ)に行けば、進んだ技術をこの目で見られる…」
――そして、1860年1月。舞台は再び、江戸。
江戸湾の品川沖に停泊する2隻の蒸気船が並ぶ。
1隻は、アメリカ海軍の大型外輪蒸気船・“ポーハタン号”。
もう1隻は、幕府がオランダから購入した、スクリュー推進式蒸気船“咸臨丸”
――いよいよ、アメリカへの船出。港には乗船する使節団が集合した。
ここで佐賀の“蘭学寮”の英才が、幕府使節団の“同行者”に話しかけた。
「佐賀の小出千之助と申す。以後、お見知りおきを。」
「…豊前中津の出で、福沢と申します。」
福沢諭吉は、若くして“蘭学”の塾を構えるが、英語も一から学んでいる。
「やはり福沢どのだったか。思いのほか、早くお会いできたようだ。」
「…ご丁寧に恐れ入る。」
やや困惑する福沢。こんな疑念を持った。
「この小出という佐賀の者は、私に会うことを予期していたのか…?」
〔参照(終盤):第14話「遣米使節」①(諭吉よ、何処へ行く)〕

――蘭学寮の英才・小出千之助の任務は英語を修得し、殿・直正に代わり西洋を見聞すること。
福沢は「もはやオランダ語ではなく、英語を学ばねば!」と気付くのも早かった。開港後に発展した“横浜”でオランダ語が通じないショックを味わったのだ。
ほどなく小出千之助・川崎道民らは“ポーハタン号”。福沢諭吉・秀島藤之助らは“咸臨丸”へと分かれた。遠く海の向こうアメリカへ。太平洋への船出である。
(続く)
前回、鍋島直正の写真を撮影していた佐賀藩医・川崎道民。殿から出し抜けにアメリカ行きを提案される場面を描きました。
今回の投稿は、様々な場所で佐賀藩士たちの運命が動いていきます。日本における“英学の夜明け”という時期でしょうか。
――江戸。殿・直正から海外渡航の勧めを受けた、川崎道民。
「メリケン(アメリカ)に、ございますか!?」
「そうじゃ。医術や文物を見聞いたせ。お主なら“写真術”も遣える。」
この頃、幕府は“日米修好通商条約”の批准書を交換するため、アメリカに使節派遣を予定している。
日本の近代外交の扉は開いた。佐賀藩には、この機会に優秀な人物を海外に送り込み、西洋の事情を探ろうという意図があった。
「川崎は、腕の良い医者であるからな。同行すれば、皆も安心であろう。」
「皆…!?佐賀から、幾人もメリケンに行くのでございますか?」

――医者の髪型に、よくある坊主頭。川崎は、目を丸くして殿・直正に問う。
「無論じゃ。川崎よ、皆を頼むぞ。」
この使節団には、佐賀藩士8名が参加することになった。
川崎は、地元である“須古”の領主・鍋島安房の言葉を想い出した。恩義あるご領主からも「広く世を見聞せよ」と期待をされているのだ。
「この川崎、メリケンの進んだ技術を得られる限り、得て参ります。」
「…はっはっは。良い心意気じゃ。」
――川崎の反応は、直正の予想を上回るほど“前のめり”だった。
「仕度金は、百両でよいか。抜かりなく用意を致せ。」
「はっ!…百両も…!ありがたき幸せ!」
こうして、藩医・川崎道民のアメリカ行きが決まる。幕府の使節団が乗り込むアメリカ海軍の蒸気船に同乗することとなった。
船名を“ポーハタン号”という。アメリカのペリーが2度目の来日で乗船し、ハリスとの通商条約の調印場所になった、全長77メートル超の外輪蒸気船である。
――同じ頃、佐賀城下の“火術方”にて。
作業場で、オランダ語の技術書と睨み合う人物がいた。大砲の改良案を練る技術者・秀島藤之助。
〔参照:
「秀島さま!お城からのお呼びです!」
いきなり電流が走るような声が通った。
「…何だ!?いきなり大声で。お主はたしか…?」
耳を抑える秀島。よく通る声でツーンと来た様子である。
――声の主は“火術方”に下級役人として採用された、江藤新平。
「秀島さま!その図面は、新しい製砲の試みでござるか。」
江藤は蘭学を学んだので、ある程度、技術者たちの作業が理解できる。
「あぁ、そうだ。たしか江藤と言ったな。そこまで声を通さずとも聞こえている…」
寝る間も惜しみ研究をする、秀島。寝不足には江藤の地声は堪(こた)える。
「急ぎ、城へお向かいください!」
「…相分かった。」
――殿・直正が期待する、技術者・秀島藤之助もアメリカ行きが決定した。
使節を乗せる“ポーハタン号”を護衛するとの名目で、幕府も船を派遣する。
船名を“咸臨丸”という、秀島はそちらに乗船することとなった。
秀島の任務は、主に艦船や大砲などの調査である。
「メリケン(アメリカ)に行けば、進んだ技術をこの目で見られる…」
――そして、1860年1月。舞台は再び、江戸。
江戸湾の品川沖に停泊する2隻の蒸気船が並ぶ。
1隻は、アメリカ海軍の大型外輪蒸気船・“ポーハタン号”。
もう1隻は、幕府がオランダから購入した、スクリュー推進式蒸気船“咸臨丸”
――いよいよ、アメリカへの船出。港には乗船する使節団が集合した。
ここで佐賀の“蘭学寮”の英才が、幕府使節団の“同行者”に話しかけた。
「佐賀の小出千之助と申す。以後、お見知りおきを。」
「…豊前中津の出で、福沢と申します。」
福沢諭吉は、若くして“蘭学”の塾を構えるが、英語も一から学んでいる。
「やはり福沢どのだったか。思いのほか、早くお会いできたようだ。」
「…ご丁寧に恐れ入る。」
やや困惑する福沢。こんな疑念を持った。
「この小出という佐賀の者は、私に会うことを予期していたのか…?」
〔参照(終盤):

――蘭学寮の英才・小出千之助の任務は英語を修得し、殿・直正に代わり西洋を見聞すること。
福沢は「もはやオランダ語ではなく、英語を学ばねば!」と気付くのも早かった。開港後に発展した“横浜”でオランダ語が通じないショックを味わったのだ。
ほどなく小出千之助・川崎道民らは“ポーハタン号”。福沢諭吉・秀島藤之助らは“咸臨丸”へと分かれた。遠く海の向こうアメリカへ。太平洋への船出である。
(続く)
2020年10月28日
第14話「遣米使節」⑭(太平洋の嵐)
こんばんは。
前回、江戸・品川沖をアメリカに向けて出航した2隻の蒸気船。幕府の使節団を乗せた“ポーハタン号”と、同行する“咸臨丸”。
当時の航海技術では、太平洋を渡るには試練を伴います。佐賀藩士たちが同乗する、この2隻も困難に直面します。
――オランダより購入し、幕府が保有する“咸臨丸”の船上。
「佐賀の秀島と申す。福沢どのとお見受けする。」
佐賀藩士で、技術者・秀島藤之助である。
「…咸臨丸にも佐賀の方が居られましたか。」
福沢諭吉は長崎にいるとき、奉行所の関係者宅で書生をしていた。佐賀藩士とは関わる機会も多かった。
「お話中だったか、失礼した。そちらの方も、名をお伺いしたい。」
――秀島は、“賢い”と評判の福沢が、話している相手も気になった。
秀島は、極めて真面目だった。航海途上も情報収集に励む。
「マイネーム…中浜、万次郎と申します。」
万次郎と名乗るこの人物、やけに言葉がたどたどしい。
「中浜どのは土佐(高知)の出。漁に出て嵐に遭い、アメリカに渡ったそうだ。」
すかさず福沢が補足した。頭の回転が速い。
――“ジョン万次郎”として知られる、中浜万次郎。
海で遭難し、無人島で命をつないでいたところ、アメリカ船に救助された。当時、“鎖国”の影響もあって日本には帰れず、渡米の道を選んだ。
「ザッツ、ライト…いや、その通りです。」
万次郎は、アメリカで暮らしの間に“英語で考える頭”になっていた。
「メリケン(アメリカ)の言葉をご存じとは心強い。」
秀島藤之助、長崎の海軍伝習所でオランダ人から操船技術は学んだ。しかし、英語の習得はこれからだ。
そして“咸臨丸”での航海、秀島は船を動かす仕事には関われない。そこは幕府の“海軍士官”たちの領分なのだ。

――港を出た直後は、太平洋の航海は順調であったが…
「どうやら、ストーム(嵐)が来る…ようです。」
万次郎は、“咸臨丸”に同乗するアメリカ海軍のブルック大尉と話してきた。そこで「雲行きが怪しい」と聞いたらしい。
ほどなく上空は真っ暗となった。
ゴーォォ…
吠える風、うねる海。非情な大嵐である。
バキバキバキッ…
船体の様々な箇所が破損していく。
――甲板は斜め上に傾いたかと思えば、今度は、前方に下り坂を生じる。
乗組員たちは平衡感覚を失い、天地の分別もつかなくなった。
「勝さんは、まだ出て来ないのか…!」
「お体が優れぬらしいぞ。このような時に…!」
幕府の海軍士官たちは、混乱していた。1人…また1人と船酔いで倒れていく。
指揮を執るべき、勝麟太郎(海舟)は船室から出て来れなかった。
「おいらも、もう終(し)めぇか…」
絶望の言葉が口を付いて出る。勝海舟は強度の“船酔い”持ちだったと伝わる。陸(おか)でこそ活きる人物だったという。

――たとえ好天でも、日本人には経験の無い遠洋航海。
すでに“咸臨丸”の指揮命令は、機能していない。
そこで嵐の甲板に英語が響いた。
アメリカ海軍・ブルック大尉と水兵10人が同乗しているのだ。
「何と言っているのだ…」
佐賀藩士・秀島藤之助は、まだ充分に英語が理解できない。
「アメリカ海軍の魂を…お見せしよう!と言ってます…」
通訳をするジョン万次郎である。自身も船乗りの経験がある。ブルック大尉に協力するつもりのようだ。
――風が、吹きすさぶ荒天は数日続いたと言われる。
テキパキと活動するアメリカの水兵たちを見つめ、秀島は悔しさを嚙みしめる。
「もし佐賀の者が同船ならば、このように動けただろうか…」
長崎での海軍伝習の日々が浮かぶ。よく働く若手と、そのまとめ役がいた。
「中牟田…、石丸…、それに佐野(栄寿)さんが居れば…」
佐賀藩から派遣されている、秀島藤之助。勝手な動きをして、幕臣との軋轢(あつれき)を起こすわけにはいかなかった。
(続く)
前回、江戸・品川沖をアメリカに向けて出航した2隻の蒸気船。幕府の使節団を乗せた“ポーハタン号”と、同行する“咸臨丸”。
当時の航海技術では、太平洋を渡るには試練を伴います。佐賀藩士たちが同乗する、この2隻も困難に直面します。
――オランダより購入し、幕府が保有する“咸臨丸”の船上。
「佐賀の秀島と申す。福沢どのとお見受けする。」
佐賀藩士で、技術者・秀島藤之助である。
「…咸臨丸にも佐賀の方が居られましたか。」
福沢諭吉は長崎にいるとき、奉行所の関係者宅で書生をしていた。佐賀藩士とは関わる機会も多かった。
「お話中だったか、失礼した。そちらの方も、名をお伺いしたい。」
――秀島は、“賢い”と評判の福沢が、話している相手も気になった。
秀島は、極めて真面目だった。航海途上も情報収集に励む。
「マイネーム…中浜、万次郎と申します。」
万次郎と名乗るこの人物、やけに言葉がたどたどしい。
「中浜どのは土佐(高知)の出。漁に出て嵐に遭い、アメリカに渡ったそうだ。」
すかさず福沢が補足した。頭の回転が速い。
――“ジョン万次郎”として知られる、中浜万次郎。
海で遭難し、無人島で命をつないでいたところ、アメリカ船に救助された。当時、“鎖国”の影響もあって日本には帰れず、渡米の道を選んだ。
「ザッツ、ライト…いや、その通りです。」
万次郎は、アメリカで暮らしの間に“英語で考える頭”になっていた。
「メリケン(アメリカ)の言葉をご存じとは心強い。」
秀島藤之助、長崎の海軍伝習所でオランダ人から操船技術は学んだ。しかし、英語の習得はこれからだ。
そして“咸臨丸”での航海、秀島は船を動かす仕事には関われない。そこは幕府の“海軍士官”たちの領分なのだ。

――港を出た直後は、太平洋の航海は順調であったが…
「どうやら、ストーム(嵐)が来る…ようです。」
万次郎は、“咸臨丸”に同乗するアメリカ海軍のブルック大尉と話してきた。そこで「雲行きが怪しい」と聞いたらしい。
ほどなく上空は真っ暗となった。
ゴーォォ…
吠える風、うねる海。非情な大嵐である。
バキバキバキッ…
船体の様々な箇所が破損していく。
――甲板は斜め上に傾いたかと思えば、今度は、前方に下り坂を生じる。
乗組員たちは平衡感覚を失い、天地の分別もつかなくなった。
「勝さんは、まだ出て来ないのか…!」
「お体が優れぬらしいぞ。このような時に…!」
幕府の海軍士官たちは、混乱していた。1人…また1人と船酔いで倒れていく。
指揮を執るべき、勝麟太郎(海舟)は船室から出て来れなかった。
「おいらも、もう終(し)めぇか…」
絶望の言葉が口を付いて出る。勝海舟は強度の“船酔い”持ちだったと伝わる。陸(おか)でこそ活きる人物だったという。

――たとえ好天でも、日本人には経験の無い遠洋航海。
すでに“咸臨丸”の指揮命令は、機能していない。
そこで嵐の甲板に英語が響いた。
アメリカ海軍・ブルック大尉と水兵10人が同乗しているのだ。
「何と言っているのだ…」
佐賀藩士・秀島藤之助は、まだ充分に英語が理解できない。
「アメリカ海軍の魂を…お見せしよう!と言ってます…」
通訳をするジョン万次郎である。自身も船乗りの経験がある。ブルック大尉に協力するつもりのようだ。
――風が、吹きすさぶ荒天は数日続いたと言われる。
テキパキと活動するアメリカの水兵たちを見つめ、秀島は悔しさを嚙みしめる。
「もし佐賀の者が同船ならば、このように動けただろうか…」
長崎での海軍伝習の日々が浮かぶ。よく働く若手と、そのまとめ役がいた。
「中牟田…、石丸…、それに佐野(栄寿)さんが居れば…」
佐賀藩から派遣されている、秀島藤之助。勝手な動きをして、幕臣との軋轢(あつれき)を起こすわけにはいかなかった。
(続く)
2020年10月30日
第14話「遣米使節」⑮(水平線の向こうに)
こんばんは。
前回は、強い嵐に翻弄される“咸臨丸”の姿を描きました。
長く続いた第14話の投稿も、今回でラストです。
幕府の使節団が乗る“ポーハタン号”の佐賀藩士たちを描きます。“咸臨丸”と出航時点に少し差があるようですが、“ポーハタン号”も暴風雨に遭います。
――ゴーォォッ…、バキバキバキッ!
吠える風、破損する船体…
何日も続く大嵐に“ポーハタン号”も、“咸臨丸”と同じ惨状を見せる。
ドシャァァ-ン!
今度は、雷鳴が響いた。
「これは…、随分と厳しいようだ…」
蘭学寮の英才・小出千之助も、長崎での海軍伝習の経験者。操船技術の心得はあるが、アメリカ海軍の船では訓練された水兵の動きに感心するばかりだ。
―― ヘイ!ヘイッ!…己を鼓舞するような、水兵たちのかけ声が響く。
「嵐の海原を突っ切れ!」と、蒸気機関を全力で稼働させているのだ。
ガランガラン…
不規則に荒れる波しぶき、蒸気船の両舷で“外輪”は回り続ける。
「ゴー、アヘッド!(前へ進むんだ)」
「イエッサー!!(了解)」
ここでも“魂”を見せる、アメリカ海軍。
雨風に煽られ、足元も揺れる。そんな中でも小出は感服していた。
「これが…アメリカとの力の差か…もっと彼らの言葉を学ばねば。」

――どうにか、ハワイ諸島を望む海域まで来た“ポーハタン号”。
船の損傷箇所が多数ある。燃料も使い過ぎており、航海の継続は難しい。
「何とか、生きて陸(おか)にたどり着けるようですね。」
甲板に上がってきたのは、佐賀藩医・川崎道民である。
アメリカ水兵の会話を聴き取っていた、小出千之助が言葉を返す。
「おお、川崎どの。随分な嵐だったな。お加減はいかがですか。」
「私は医者ですよ。倒れるわけには参りませぬ。」
「失礼した。皆の具合はどうか。」
「“船酔い”で、気分が悪い者もいますが…陸に上がれば、心配無いでしょうな。」
――オアフ島の夕暮れ。浜辺から西に広がる水平線を見つめる。
「おおっ、夕陽が見事だな。“ビューテイホー・サンセッツ”と言うらしい。」
小出千之助は、地道に英語の習得を進めていた。
海上の嵐の恐怖から解き放たれ、皆が面白がって夕日に叫ぶ。
「ビューテイホー!!」
幾人かが声を揃えた。“ポーハタン号”に乗っていた佐賀藩士は、小出・川崎を含め7人の名が伝わる。
「佐賀の遠かごたぁ~!!」
急に1人が叫んだ。緊張が緩んだのか、まだ“行き道”なのに故郷に帰りたい。
「気ば、たしかに持たんね!」
「そうたい!この海は佐賀とつながっとるばい!」

――仲間たちが“よそ行き”の言葉ではなく“佐賀ことば”で励ます。
藩医の川崎道民は、その様子を眺めていた。そして「ふーっ」と深呼吸する。
殿には“皆を守る”と約束した。まずは医者である自分がしっかりせねばならぬ。
川崎は「大丈夫だ。海を渡り、使命を果たす。そして…皆で、必ず佐賀に帰る。」と自身に言い聞かせた。
――ほどなく川崎は、佐賀にいる家族に宛てて手紙を書いた。
太平洋の真ん中だが、次にホノルルに寄る“郵便船”で日本には届くはずだ。
「ご家族の皆様、息災(お元気)でしょうか。アメリカへの旅は、嵐の船出でした。途上の“オアフ島”にて船舶の修繕中です。出航も定かではありませぬ。」
「…しかし、佐賀の者たちは皆、気丈に振る舞っています。心強い限りです。」
――今度、嵐が来たら船は持ちこたえるのだろうか。
そして、アメリカには無事たどり着けるのか。
“気丈に振る舞っている”のは、川崎道民も同じだった。日本近代化のための“洋行”の先駆けは、命懸けの旅路でもあった。
(第15話「江戸動乱」に続く)
前回は、強い嵐に翻弄される“咸臨丸”の姿を描きました。
長く続いた第14話の投稿も、今回でラストです。
幕府の使節団が乗る“ポーハタン号”の佐賀藩士たちを描きます。“咸臨丸”と出航時点に少し差があるようですが、“ポーハタン号”も暴風雨に遭います。
――ゴーォォッ…、バキバキバキッ!
吠える風、破損する船体…
何日も続く大嵐に“ポーハタン号”も、“咸臨丸”と同じ惨状を見せる。
ドシャァァ-ン!
今度は、雷鳴が響いた。
「これは…、随分と厳しいようだ…」
蘭学寮の英才・小出千之助も、長崎での海軍伝習の経験者。操船技術の心得はあるが、アメリカ海軍の船では訓練された水兵の動きに感心するばかりだ。
―― ヘイ!ヘイッ!…己を鼓舞するような、水兵たちのかけ声が響く。
「嵐の海原を突っ切れ!」と、蒸気機関を全力で稼働させているのだ。
ガランガラン…
不規則に荒れる波しぶき、蒸気船の両舷で“外輪”は回り続ける。
「ゴー、アヘッド!(前へ進むんだ)」
「イエッサー!!(了解)」
ここでも“魂”を見せる、アメリカ海軍。
雨風に煽られ、足元も揺れる。そんな中でも小出は感服していた。
「これが…アメリカとの力の差か…もっと彼らの言葉を学ばねば。」

――どうにか、ハワイ諸島を望む海域まで来た“ポーハタン号”。
船の損傷箇所が多数ある。燃料も使い過ぎており、航海の継続は難しい。
「何とか、生きて陸(おか)にたどり着けるようですね。」
甲板に上がってきたのは、佐賀藩医・川崎道民である。
アメリカ水兵の会話を聴き取っていた、小出千之助が言葉を返す。
「おお、川崎どの。随分な嵐だったな。お加減はいかがですか。」
「私は医者ですよ。倒れるわけには参りませぬ。」
「失礼した。皆の具合はどうか。」
「“船酔い”で、気分が悪い者もいますが…陸に上がれば、心配無いでしょうな。」
――オアフ島の夕暮れ。浜辺から西に広がる水平線を見つめる。
「おおっ、夕陽が見事だな。“ビューテイホー・サンセッツ”と言うらしい。」
小出千之助は、地道に英語の習得を進めていた。
海上の嵐の恐怖から解き放たれ、皆が面白がって夕日に叫ぶ。
「ビューテイホー!!」
幾人かが声を揃えた。“ポーハタン号”に乗っていた佐賀藩士は、小出・川崎を含め7人の名が伝わる。
「佐賀の遠かごたぁ~!!」
急に1人が叫んだ。緊張が緩んだのか、まだ“行き道”なのに故郷に帰りたい。
「気ば、たしかに持たんね!」
「そうたい!この海は佐賀とつながっとるばい!」
――仲間たちが“よそ行き”の言葉ではなく“佐賀ことば”で励ます。
藩医の川崎道民は、その様子を眺めていた。そして「ふーっ」と深呼吸する。
殿には“皆を守る”と約束した。まずは医者である自分がしっかりせねばならぬ。
川崎は「大丈夫だ。海を渡り、使命を果たす。そして…皆で、必ず佐賀に帰る。」と自身に言い聞かせた。
――ほどなく川崎は、佐賀にいる家族に宛てて手紙を書いた。
太平洋の真ん中だが、次にホノルルに寄る“郵便船”で日本には届くはずだ。
「ご家族の皆様、息災(お元気)でしょうか。アメリカへの旅は、嵐の船出でした。途上の“オアフ島”にて船舶の修繕中です。出航も定かではありませぬ。」
「…しかし、佐賀の者たちは皆、気丈に振る舞っています。心強い限りです。」
――今度、嵐が来たら船は持ちこたえるのだろうか。
そして、アメリカには無事たどり着けるのか。
“気丈に振る舞っている”のは、川崎道民も同じだった。日本近代化のための“洋行”の先駆けは、命懸けの旅路でもあった。
(第15話「江戸動乱」に続く)




