2022年01月29日
第17話「佐賀脱藩」⑮(急転、江戸からの風)
こんにちは。
年が明けてからしばらく後、江戸から佐賀に届いた一通の手紙。大都会から届く中野方蔵の便りは、佐賀の同志たちの希望となっていたのですが…
少しばかり時間を遡って、舞台は文久二年(1862年)の年明け直後の江戸。現代では東京にあたる大都会。各地の出身者に“物語”があったことでしょう。
志士への追跡が強まる江戸で不急の外出を避けている中野方蔵。明治初期に東京への首都移転に活躍した大木喬任・江藤新平の親友の“物語”です。

――澄み切った正月の空気が漂う、江戸の街。
歳末を乗り切った長屋の町人たちの声が響く。
「おぅ、今年もよろしくな。」
「元気そうじゃねぇか、おっかねえ“掛取り”から逃げ切ったようだな。」
「おうよ、この通り清々しい新年だ。」
江戸期の商慣習で、歳末には売掛金の回収が集中する傾向があったようだ。いわば、年越しまで借金取りから逃げ切った男の武勇伝である。
「でもな、一時は逃げ切っても、後が怖えぞ…。」
「めでてぇ、正月から野暮(やぼ)な話は言いっこなしでぃ!」
――町人地に近い通りを行く、佐賀藩士・中野方蔵。
「年始まで、“掛取り”から逃げ切ったか…。」
少し風もある日だ。流れてくる、江戸の日常に耳を傾けながら小路を行く。
当時、勤王を唱える、諸藩の志士たちへの取り締まりは厳しくなる一方だ。
とくに皇女・和宮の降嫁に際して、挙兵のうえで“奪還”を図ったという儒学者・大橋訥庵の一派への追及は厳しい。
その大橋の私塾に出入りした中野も、幕府の捕り方に気をつけねばならない。
「無用な動きは、避けるに越した事はなかね…」

――『君子、危うきに近寄らず』と行きたい状況である。
佐賀の先輩・副島種臣とも相談し、しばらく中野は幕府の昌平坂学問所への出席を見送っていた。もちろん、市中の私塾にも出入りはしない。
〔参照(終盤):第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)〕
日用品の確保など所用を済ませ、急ぎ足で江戸での居宅に戻る。佐賀での住まいに比べれば、相当に狭いが単身で暮らすには問題はない。
郷里に置いてきた家族、離れている仲間たち。このように籠もった暮らし振りならば、もはや江戸に居続ける値打ちは無いのかもしれない。
中野は居宅に落ち着くと、佐賀から届いていた手紙に目を通した。
――「中野へ。この度“代品方”に転じることとなった。」
「へぇ、江藤くんは、いよいよ交易に関わるか。これは幸いだ。」
情報収集に熱心で“早耳”の中野。佐賀藩の貿易部門は、上方(京・大坂)への拠点強化に乗り出している。
「中野とともに“国事”に奔走するには、まだ時がかかりそうだ。」
「…承知。佐賀に戻るまでに、こちらもひと踏ん張りせんばね。」
これが都市生活の孤独か。江藤からの手紙に、中野は言葉を返してしまう。
――「近々、大木さんからも文(ふみ)を書き送る。」
江藤からの手紙は、大木からの通信の予告で結んでいた。この三人の関わり方は親友というより、もはや兄弟のようですらあった。
「…楽しみにしていますね。」
手紙を読み終えた、中野は軽く笑みを見せた。
一人の時間が戻る。学問所や私塾で志士たちと交流してきたが、取り締まりを警戒して、今は自粛をしている。
江戸での充実した日々を送ってきた中野にとっては、珍しく暇がある。
「そういえば、初風呂ぐらいは行っておくか。」

――江戸市中の湯屋(銭湯)に、出向いた中野。
そんな銭湯の脱衣所だ。また、活気のある江戸庶民の声が響いている。
「おう、今年は初顔合わせか。」
「あ~あ、新年もお前さんの、しけた面(つら)見ながら暮らすのかぁ…」
中野は都会にも馴染み、活きの良い江戸っ子の会話はむしろ耳に優しい。
「…もはや、こういった喧噪(けんそう)も落ち着くな。」
一言、つぶやいた中野。これからの佐賀のため、いや日本のためには諸藩との人脈を築いておくべきで、時間も足らない。
しかし、たまには町人の世間話に耳を傾ける、穏やかな時間も良いものだ。
――その時、にわかに出入り口が騒がしくなった。
その場に居合わせた町人たちが、さざめく。
「お役人だ…。」
「何の騒ぎでぃ…。」
物々しい幕府の捕り方が数人。ずかずかと銭湯に乗り込んできた。そして、あっという間に中野の周囲を取り巻いた。
「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」
人が集まり、狭い銭湯に逃げ場は無い。腰の刀も、先だって預けてしまった。
中野はスッと前を向いて、居並ぶ捕り方たちと目を合わせた。
(続く)
年が明けてからしばらく後、江戸から佐賀に届いた一通の手紙。大都会から届く中野方蔵の便りは、佐賀の同志たちの希望となっていたのですが…
少しばかり時間を遡って、舞台は文久二年(1862年)の年明け直後の江戸。現代では東京にあたる大都会。各地の出身者に“物語”があったことでしょう。
志士への追跡が強まる江戸で不急の外出を避けている中野方蔵。明治初期に東京への首都移転に活躍した大木喬任・江藤新平の親友の“物語”です。

――澄み切った正月の空気が漂う、江戸の街。
歳末を乗り切った長屋の町人たちの声が響く。
「おぅ、今年もよろしくな。」
「元気そうじゃねぇか、おっかねえ“掛取り”から逃げ切ったようだな。」
「おうよ、この通り清々しい新年だ。」
江戸期の商慣習で、歳末には売掛金の回収が集中する傾向があったようだ。いわば、年越しまで借金取りから逃げ切った男の武勇伝である。
「でもな、一時は逃げ切っても、後が怖えぞ…。」
「めでてぇ、正月から野暮(やぼ)な話は言いっこなしでぃ!」
――町人地に近い通りを行く、佐賀藩士・中野方蔵。
「年始まで、“掛取り”から逃げ切ったか…。」
少し風もある日だ。流れてくる、江戸の日常に耳を傾けながら小路を行く。
当時、勤王を唱える、諸藩の志士たちへの取り締まりは厳しくなる一方だ。
とくに皇女・和宮の降嫁に際して、挙兵のうえで“奪還”を図ったという儒学者・大橋訥庵の一派への追及は厳しい。
その大橋の私塾に出入りした中野も、幕府の捕り方に気をつけねばならない。
「無用な動きは、避けるに越した事はなかね…」
――『君子、危うきに近寄らず』と行きたい状況である。
佐賀の先輩・副島種臣とも相談し、しばらく中野は幕府の昌平坂学問所への出席を見送っていた。もちろん、市中の私塾にも出入りはしない。
〔参照(終盤):
日用品の確保など所用を済ませ、急ぎ足で江戸での居宅に戻る。佐賀での住まいに比べれば、相当に狭いが単身で暮らすには問題はない。
郷里に置いてきた家族、離れている仲間たち。このように籠もった暮らし振りならば、もはや江戸に居続ける値打ちは無いのかもしれない。
中野は居宅に落ち着くと、佐賀から届いていた手紙に目を通した。
――「中野へ。この度“代品方”に転じることとなった。」
「へぇ、江藤くんは、いよいよ交易に関わるか。これは幸いだ。」
情報収集に熱心で“早耳”の中野。佐賀藩の貿易部門は、上方(京・大坂)への拠点強化に乗り出している。
「中野とともに“国事”に奔走するには、まだ時がかかりそうだ。」
「…承知。佐賀に戻るまでに、こちらもひと踏ん張りせんばね。」
これが都市生活の孤独か。江藤からの手紙に、中野は言葉を返してしまう。
――「近々、大木さんからも文(ふみ)を書き送る。」
江藤からの手紙は、大木からの通信の予告で結んでいた。この三人の関わり方は親友というより、もはや兄弟のようですらあった。
「…楽しみにしていますね。」
手紙を読み終えた、中野は軽く笑みを見せた。
一人の時間が戻る。学問所や私塾で志士たちと交流してきたが、取り締まりを警戒して、今は自粛をしている。
江戸での充実した日々を送ってきた中野にとっては、珍しく暇がある。
「そういえば、初風呂ぐらいは行っておくか。」
――江戸市中の湯屋(銭湯)に、出向いた中野。
そんな銭湯の脱衣所だ。また、活気のある江戸庶民の声が響いている。
「おう、今年は初顔合わせか。」
「あ~あ、新年もお前さんの、しけた面(つら)見ながら暮らすのかぁ…」
中野は都会にも馴染み、活きの良い江戸っ子の会話はむしろ耳に優しい。
「…もはや、こういった喧噪(けんそう)も落ち着くな。」
一言、つぶやいた中野。これからの佐賀のため、いや日本のためには諸藩との人脈を築いておくべきで、時間も足らない。
しかし、たまには町人の世間話に耳を傾ける、穏やかな時間も良いものだ。
――その時、にわかに出入り口が騒がしくなった。
その場に居合わせた町人たちが、さざめく。
「お役人だ…。」
「何の騒ぎでぃ…。」
物々しい幕府の捕り方が数人。ずかずかと銭湯に乗り込んできた。そして、あっという間に中野の周囲を取り巻いた。
「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」
人が集まり、狭い銭湯に逃げ場は無い。腰の刀も、先だって預けてしまった。
中野はスッと前を向いて、居並ぶ捕り方たちと目を合わせた。
(続く)
2022年01月25日
第17話「佐賀脱藩」⑭(拓〔ひら〕け、代品方)
こんばんは。
“本編”の再開は、旧暦・新暦の差はありつつも、時期をあわせてみました。
文久二年(1862年)の年明けから、二十日ほど後を想定したお話です。
世間の正月気分も抜けきったかと思われる頃。佐賀藩では、新年も激しく働く者たちがいました。
――佐賀城下。藩の貿易部門“代品方”の拠点。
「白蝋(はくろう)ば、着いたと。」
「早う、数えんね!」
荷車が入り、藩の役人たちの間に飛び交う声。
櫨(はぜ)の木から精製した蝋(ろう)が、詰め込まれた木箱が到着している。
「箱の中も改めんば、ならんばい。」
鍋島家の一門が治める、白石領(みやき町)周辺から発送された品である。

――急ぎ、検品と数量の確認を要するらしい。
「心得た。」
この部署では、新入りと思われる佐賀藩士・江藤新平が木箱に向かう。
「!」
次の瞬間、積み荷の状態が変動する。すさまじい気迫で箱に向き合う、江藤。テキパキと箱を仕分け、検品と帳面の記載をこなしていく。
「…あん(の)男。たしか…」
「上佐賀代官所から来た、江藤と申す者。なかなか働きますばい。」
――「帳面を付け申した。品も数も問題のなかです。」
よく通る声でビシッと言い切った、江藤。
「よか。こん(の)荷は、まず伊万里まで運ばんね。」
江藤の仕事ぶりに、上役も疑いを差し挟まない。
もっとも、佐賀藩の生産管理は相当に厳しい。蝋を生産する側の領民たちも、相当な努力を重ねていた。
「ゆけっ!」と、木箱を載せた荷車は西へと送り出された。佐賀藩の各地域で栽培されたハゼの木から作られる白蝋は、西洋各国も重視する品だった。

――各地に設置が進む、佐賀藩の交易拠点。
蒸気船など西洋式軍艦の購入を進める佐賀藩。支払いの一部を、白蝋に代表される、金銭以外の代わりの品(代品)で補ったという。
また、陶磁器の販路を求めて、上方の大坂にも拠点を設置。幕府の貿易船を利用して、清国の上海(シャンハイ)にも進出の計画があった。
「我らは、かなり急(せ)わしい。あのような“働き者”は好ましか。」
佐賀藩が注力し、急拡大していく貿易業務。格好を気にする様子もなく、一風変わった男でも、仕事が出来れば良い。代品方の上役は、満足気だった。
――夕刻。佐賀城下の武家屋敷通り。
「江藤、どうね。代品方のお役目は。」
「坂井さんか。久しい。本年も、よろしく頼む。」
「そうだったな。まだ、睦月(一月)だったか。」
通りで出会ったのは“義祭同盟”の一員・坂井辰之允。こちらも忙しそうだ。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)〕
その中で、昨年までの代官所務めから転じた、江藤の仕事も気にかけていた。この坂井は、面倒見の良い気性であるのかもしれない。

――江藤は忙しく働きつつも、思うところがあるようだ。
「“代品方”は、お家(鍋島家)に利を為す、お役目と心得る。」
「それは、よか。きっと、お主なら出世もできる。」
「坂井さん。このまま“お家”大事と励むのは、正しいことか。」
佐賀が豊かになり、雄藩として存在感を増すのは、江藤や坂井など義祭同盟の面々にとっても良い話だ。
しかし開国以来、物流などは混乱し、経済に諸外国の影響が強く出ている。打ち払おうとする側の攘夷活動も勢いづいていた。
――持ち前の才覚で、仕事が順調なはずの江藤。
しかし江藤が藩の仕事に励む中でも、諸藩の志士たちの活動は「国の形から変えねばならぬ」という尊王思想とも結びつき、時勢は大きく動いている。
きっと時流を読んでいる江藤だから、焦るのだ。坂井が言葉を返した。
「そこはお主らがいつも語りおる大親友・中野方蔵くんに任せれば、よか。」
「然り。中野は江戸にて、我らの進むべき道を切り開いている。」
他藩の志士と大都会・江戸で交流する、中野からの手紙。佐賀に留まる同志に希望を与えている。江藤と話す坂井とて、便りを心待ちにする一人なのだ。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」④(上方からの“花嫁”)〕

――「まぁ、中野が居るけん、そがん焦らずとも…」
坂井は「…怠らず、お役目に励めば、そのうち道も拓けるだろう」と続けた。
親身になり熱心に語る、坂井。その背後に人影があることに気付かない。
「大木さん、どうした。何があった。」
江藤が、坂井の後ろの人影に向かって言葉を発する。そこに突っ立っていたのは、大木喬任(民平)だった。
「おっと…声ぐらいは、かけんね…」
気配の無かった大木に驚いて振り向いた坂井は、言葉を途中で止めた。
――明らかに、大木の様子がおかしい。
「…文(ふみ)が来た。江戸にいる、中野からだ。」
大木の表情に、いつものような手紙が来た時の嬉しそうな感じは無い。
憤るか、悲しむか…何か感情を抑え込むように小刻みな震えが感じられる。
「もしや、中野の身に何かあったか。」
江藤が険しい表情を見せ、鋭く言葉を返した。
(続く)
“本編”の再開は、旧暦・新暦の差はありつつも、時期をあわせてみました。
文久二年(1862年)の年明けから、二十日ほど後を想定したお話です。
世間の正月気分も抜けきったかと思われる頃。佐賀藩では、新年も激しく働く者たちがいました。
――佐賀城下。藩の貿易部門“代品方”の拠点。
「白蝋(はくろう)ば、着いたと。」
「早う、数えんね!」
荷車が入り、藩の役人たちの間に飛び交う声。
櫨(はぜ)の木から精製した蝋(ろう)が、詰め込まれた木箱が到着している。
「箱の中も改めんば、ならんばい。」
鍋島家の一門が治める、白石領(みやき町)周辺から発送された品である。
――急ぎ、検品と数量の確認を要するらしい。
「心得た。」
この部署では、新入りと思われる佐賀藩士・江藤新平が木箱に向かう。
「!」
次の瞬間、積み荷の状態が変動する。すさまじい気迫で箱に向き合う、江藤。テキパキと箱を仕分け、検品と帳面の記載をこなしていく。
「…あん(の)男。たしか…」
「上佐賀代官所から来た、江藤と申す者。なかなか働きますばい。」
――「帳面を付け申した。品も数も問題のなかです。」
よく通る声でビシッと言い切った、江藤。
「よか。こん(の)荷は、まず伊万里まで運ばんね。」
江藤の仕事ぶりに、上役も疑いを差し挟まない。
もっとも、佐賀藩の生産管理は相当に厳しい。蝋を生産する側の領民たちも、相当な努力を重ねていた。
「ゆけっ!」と、木箱を載せた荷車は西へと送り出された。佐賀藩の各地域で栽培されたハゼの木から作られる白蝋は、西洋各国も重視する品だった。
――各地に設置が進む、佐賀藩の交易拠点。
蒸気船など西洋式軍艦の購入を進める佐賀藩。支払いの一部を、白蝋に代表される、金銭以外の代わりの品(代品)で補ったという。
また、陶磁器の販路を求めて、上方の大坂にも拠点を設置。幕府の貿易船を利用して、清国の上海(シャンハイ)にも進出の計画があった。
「我らは、かなり急(せ)わしい。あのような“働き者”は好ましか。」
佐賀藩が注力し、急拡大していく貿易業務。格好を気にする様子もなく、一風変わった男でも、仕事が出来れば良い。代品方の上役は、満足気だった。
――夕刻。佐賀城下の武家屋敷通り。
「江藤、どうね。代品方のお役目は。」
「坂井さんか。久しい。本年も、よろしく頼む。」
「そうだったな。まだ、睦月(一月)だったか。」
通りで出会ったのは“義祭同盟”の一員・坂井辰之允。こちらも忙しそうだ。
〔参照(後半):
その中で、昨年までの代官所務めから転じた、江藤の仕事も気にかけていた。この坂井は、面倒見の良い気性であるのかもしれない。
――江藤は忙しく働きつつも、思うところがあるようだ。
「“代品方”は、お家(鍋島家)に利を為す、お役目と心得る。」
「それは、よか。きっと、お主なら出世もできる。」
「坂井さん。このまま“お家”大事と励むのは、正しいことか。」
佐賀が豊かになり、雄藩として存在感を増すのは、江藤や坂井など義祭同盟の面々にとっても良い話だ。
しかし開国以来、物流などは混乱し、経済に諸外国の影響が強く出ている。打ち払おうとする側の攘夷活動も勢いづいていた。
――持ち前の才覚で、仕事が順調なはずの江藤。
しかし江藤が藩の仕事に励む中でも、諸藩の志士たちの活動は「国の形から変えねばならぬ」という尊王思想とも結びつき、時勢は大きく動いている。
きっと時流を読んでいる江藤だから、焦るのだ。坂井が言葉を返した。
「そこはお主らがいつも語りおる大親友・中野方蔵くんに任せれば、よか。」
「然り。中野は江戸にて、我らの進むべき道を切り開いている。」
他藩の志士と大都会・江戸で交流する、中野からの手紙。佐賀に留まる同志に希望を与えている。江藤と話す坂井とて、便りを心待ちにする一人なのだ。
〔参照(中盤):
――「まぁ、中野が居るけん、そがん焦らずとも…」
坂井は「…怠らず、お役目に励めば、そのうち道も拓けるだろう」と続けた。
親身になり熱心に語る、坂井。その背後に人影があることに気付かない。
「大木さん、どうした。何があった。」
江藤が、坂井の後ろの人影に向かって言葉を発する。そこに突っ立っていたのは、大木喬任(民平)だった。
「おっと…声ぐらいは、かけんね…」
気配の無かった大木に驚いて振り向いた坂井は、言葉を途中で止めた。
――明らかに、大木の様子がおかしい。
「…文(ふみ)が来た。江戸にいる、中野からだ。」
大木の表情に、いつものような手紙が来た時の嬉しそうな感じは無い。
憤るか、悲しむか…何か感情を抑え込むように小刻みな震えが感じられる。
「もしや、中野の身に何かあったか。」
江藤が険しい表情を見せ、鋭く言葉を返した。
(続く)
2022年01月22日
「佐賀の空を起点として振り返る。」
こんばんは。
遠方に住むため、私はニュースで状況を知りますが、佐賀でも新型コロナの感染者数が増えたり、地震での揺れがあったり…と心配事の多いところです。
最近、下を向きそうになるような話題も多いですが、『さがファンブログ』には、よく空の写真を載せておられる方々もいます。
「時に、空を見上げることも大事。」と教えられた私は、青天を仰ぎ見ることに。ただ、そのたび「ポキポキっ…」と音をたてる関節。加齢と疲労は感じます。
――さて、振り返りシリーズ第2回・中編です。
特に『佐賀空港』がキーワードというわけではなく、最近の“本編”では江戸(東京)との手紙のやり取りで展開する話が多いため、こういう表現にしました。
気持ちだけでも「佐賀の中心から空を見上げて、東京方面に向かう」ぐらいのイメージで語ります。
〔参照(直近の本編記事):第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)〕

――本シリーズは「制作裏話」でもあります。
私が「幕末期の佐賀の歴史」を顧みるようになって、まだ3年ほど。それゆえ、調べながら書いており、未知だった“史実”が次々わかってしまうことが。
書き手としては、「話を作り終えた後で、この展開になると辛い…」というのが、素直な感想です。
――“創作”を標榜するとはいえ、
「もし、佐賀の大河ドラマが実現すれば、こんな書き方もありうる!」という域を目指したい気持ちだけはあるので葛藤しながら、話の”着地点”を探ります。
実際の「大河ドラマ」では、史実を監修する先生が仕上がった原稿をチェックするのか、会議でシナリオの方向を決めてから書くのか…興味深いところです。
――ケース①「長崎街道の旅人」
佐賀城の南堀端をゆく、大木喬任(民平)と江藤新平。師匠・枝吉神陽宅の門前に見えるのは、会話している二人のさむらいの姿。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑧(福岡から来た“さぶらい”)〕
一人は佐賀藩士・古賀一平なので問題なし。しかし、うち一人は福岡脱藩の志士・平野国臣。ここが問題なのです。
ここで2年ちょっと前に佐賀市内、白山通りのアーケードの下で、撮影した写真をご覧ください。

――“長崎街道”の看板があります。
よく見ると江戸時代に「街道を行く旅人たちは、城内はもちろん武家地への立入りは原則禁止。街道以外の通行も制限」されたと説明が記載されています。
「こいは、いかんばいっ!」とばかりに、筋書きがマズい方向に行っている…と気付いた私。ここから軌道修正を試みます。
平野国臣は、隣県である福岡(藩)を代表する勤王の志士。私の書いた文章では“さがんもん”じゃない人が城下の奥深くに来ている展開になっています。
――“史実”と思われる情報から。
文久元年(1861年)秋、佐賀の義祭同盟のメンバーと福岡脱藩の平野国臣が出会って、意見交換をしたと幾つかの資料で見かけました。
行動力のある勤王の志士・平野国臣ですが、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』頃の時代(平安末期・鎌倉初期)のような装束を好んで着たと聞きます。
…その辺りからの発想で「福岡の“さぶらい”」という表現をしてみました。
地元・福岡に居る時ならともかく、佐賀に来た時まで“古風”な格好をしたかは不明です。問題は出入り禁止のはずの佐賀城下に“旅人”がいる状況。
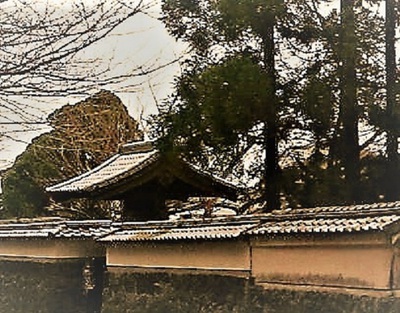
――江藤らの義祭同盟の仲間・古賀一平。
ひとしきり勤王の話に熱中した古賀ですが「ここに“お客人”が居ては危うい」と気づき、旅人・平野国臣を“長崎街道”沿いに戻して一件落着(?)。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕
大木と江藤、そして中野方蔵の三人を軸に描くことが多かったので、どうしても他の仲間が“常識人”としての役回りになりがちです。
古賀一平は、明治初期に東京(埼玉、神奈川)の一部にあった“品川県”を任された人物…ですが、古賀の担当地域が、そのまま“県”になったようです。
――ケース②「江藤新平の家族」
佐賀藩の下級役人として、のちの“働き者”の片鱗を見せる、江藤新平。
妻・千代子と結婚し、長男・熊太郎も誕生。武家屋敷街の一角に居を構える。そんな時期だったようです。
当時の江藤家に近い姿を想像し、穏やかな日々も描いてみました。但し「いずれ国に大事がある時には、立たねば」と気概を秘めた一家と表現しています。
〔参照(後半:第17話「佐賀脱藩」⑫(陽だまりの下で)〕
――この場面にも登場する、江藤新平の妻について。
私はある“創作物”での情報から、江藤のいとこだった千代子の年齢を設定し、筋書きを作成していました。
最近、ある資料を参照したところ当初の想定より、江藤千代子の年齢はかなり若かったようです。
しかし「溢れる才能には危ういところもある」のが江藤の人物像だとすれば、「奥様は年齢によらず“しっかり者”にならざるを得ないかな…」とも思います。ここは、とくに軌道修正せずに進めようと思います。

――江藤らに届く、親友・中野方蔵からの手紙。
佐賀の義祭同盟のメンバーは、大都会・江戸(東京)に出てから他藩の志士たちと活発に交流する中野の動きを知ります。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)〕
下級武士としては、江藤はおそらく順調に活躍している方です。佐賀藩からも「英語を学ばせたい」と期待されている印象。
暮らし向きも良くなっていますが「このままで良いのか…」との焦りは強くあったのではないかと想像します。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)〕
江藤新平の時代と前提は異なるものの、現代の若者にも「地元で暮らすか、都会に出るか」は大きい選択なのかもしれません。
――今後も思い切って“本編”を書きたいので、
今回はあえて、制作上の諸問題があることをご紹介しました。いまは、「誤りを恐れずに進む」つもりで書き続けたいと思います。
こうして「史実と創作の狭間で」もがき続けることで、きっと佐賀藩士に魅力的な人物が、数多くいたことが見えてくるはず。
…私は“佐賀の先輩たち”の、歴史ドラマにおける活躍の幅が広がることを切に願っています。
次回は「みやきから振り返る」企画の予定でしたが、一旦“本編”を再開します。みやき町のお話は「ここぞ」という時に繰り出すので、ご了承ください。
遠方に住むため、私はニュースで状況を知りますが、佐賀でも新型コロナの感染者数が増えたり、地震での揺れがあったり…と心配事の多いところです。
最近、下を向きそうになるような話題も多いですが、『さがファンブログ』には、よく空の写真を載せておられる方々もいます。
「時に、空を見上げることも大事。」と教えられた私は、青天を仰ぎ見ることに。ただ、そのたび「ポキポキっ…」と音をたてる関節。加齢と疲労は感じます。
――さて、振り返りシリーズ第2回・中編です。
特に『佐賀空港』がキーワードというわけではなく、最近の“本編”では江戸(東京)との手紙のやり取りで展開する話が多いため、こういう表現にしました。
気持ちだけでも「佐賀の中心から空を見上げて、東京方面に向かう」ぐらいのイメージで語ります。
〔参照(直近の本編記事):
――本シリーズは「制作裏話」でもあります。
私が「幕末期の佐賀の歴史」を顧みるようになって、まだ3年ほど。それゆえ、調べながら書いており、未知だった“史実”が次々わかってしまうことが。
書き手としては、「話を作り終えた後で、この展開になると辛い…」というのが、素直な感想です。
――“創作”を標榜するとはいえ、
「もし、佐賀の大河ドラマが実現すれば、こんな書き方もありうる!」という域を目指したい気持ちだけはあるので葛藤しながら、話の”着地点”を探ります。
実際の「大河ドラマ」では、史実を監修する先生が仕上がった原稿をチェックするのか、会議でシナリオの方向を決めてから書くのか…興味深いところです。
――ケース①「長崎街道の旅人」
佐賀城の南堀端をゆく、大木喬任(民平)と江藤新平。師匠・枝吉神陽宅の門前に見えるのは、会話している二人のさむらいの姿。
〔参照(中盤):
一人は佐賀藩士・古賀一平なので問題なし。しかし、うち一人は福岡脱藩の志士・平野国臣。ここが問題なのです。
ここで2年ちょっと前に佐賀市内、白山通りのアーケードの下で、撮影した写真をご覧ください。
――“長崎街道”の看板があります。
よく見ると江戸時代に「街道を行く旅人たちは、城内はもちろん武家地への立入りは原則禁止。街道以外の通行も制限」されたと説明が記載されています。
「こいは、いかんばいっ!」とばかりに、筋書きがマズい方向に行っている…と気付いた私。ここから軌道修正を試みます。
平野国臣は、隣県である福岡(藩)を代表する勤王の志士。私の書いた文章では“さがんもん”じゃない人が城下の奥深くに来ている展開になっています。
――“史実”と思われる情報から。
文久元年(1861年)秋、佐賀の義祭同盟のメンバーと福岡脱藩の平野国臣が出会って、意見交換をしたと幾つかの資料で見かけました。
行動力のある勤王の志士・平野国臣ですが、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』頃の時代(平安末期・鎌倉初期)のような装束を好んで着たと聞きます。
…その辺りからの発想で「福岡の“さぶらい”」という表現をしてみました。
地元・福岡に居る時ならともかく、佐賀に来た時まで“古風”な格好をしたかは不明です。問題は出入り禁止のはずの佐賀城下に“旅人”がいる状況。
――江藤らの義祭同盟の仲間・古賀一平。
ひとしきり勤王の話に熱中した古賀ですが「ここに“お客人”が居ては危うい」と気づき、旅人・平野国臣を“長崎街道”沿いに戻して一件落着(?)。
〔参照(中盤):
大木と江藤、そして中野方蔵の三人を軸に描くことが多かったので、どうしても他の仲間が“常識人”としての役回りになりがちです。
古賀一平は、明治初期に東京(埼玉、神奈川)の一部にあった“品川県”を任された人物…ですが、古賀の担当地域が、そのまま“県”になったようです。
――ケース②「江藤新平の家族」
佐賀藩の下級役人として、のちの“働き者”の片鱗を見せる、江藤新平。
妻・千代子と結婚し、長男・熊太郎も誕生。武家屋敷街の一角に居を構える。そんな時期だったようです。
当時の江藤家に近い姿を想像し、穏やかな日々も描いてみました。但し「いずれ国に大事がある時には、立たねば」と気概を秘めた一家と表現しています。
〔参照(後半:
――この場面にも登場する、江藤新平の妻について。
私はある“創作物”での情報から、江藤のいとこだった千代子の年齢を設定し、筋書きを作成していました。
最近、ある資料を参照したところ当初の想定より、江藤千代子の年齢はかなり若かったようです。
しかし「溢れる才能には危ういところもある」のが江藤の人物像だとすれば、「奥様は年齢によらず“しっかり者”にならざるを得ないかな…」とも思います。ここは、とくに軌道修正せずに進めようと思います。
――江藤らに届く、親友・中野方蔵からの手紙。
佐賀の義祭同盟のメンバーは、大都会・江戸(東京)に出てから他藩の志士たちと活発に交流する中野の動きを知ります。
〔参照(後半):
下級武士としては、江藤はおそらく順調に活躍している方です。佐賀藩からも「英語を学ばせたい」と期待されている印象。
暮らし向きも良くなっていますが「このままで良いのか…」との焦りは強くあったのではないかと想像します。
〔参照(後半):
江藤新平の時代と前提は異なるものの、現代の若者にも「地元で暮らすか、都会に出るか」は大きい選択なのかもしれません。
――今後も思い切って“本編”を書きたいので、
今回はあえて、制作上の諸問題があることをご紹介しました。いまは、「誤りを恐れずに進む」つもりで書き続けたいと思います。
こうして「史実と創作の狭間で」もがき続けることで、きっと佐賀藩士に魅力的な人物が、数多くいたことが見えてくるはず。
…私は“佐賀の先輩たち”の、歴史ドラマにおける活躍の幅が広がることを切に願っています。
次回は「みやきから振り返る」企画の予定でしたが、一旦“本編”を再開します。みやき町のお話は「ここぞ」という時に繰り出すので、ご了承ください。
2022年01月18日
「伊万里から西に向かって振り返る。」
こんばんは。
前回、ご案内した“本編”振り返りシリーズ第1回目です。
全3回のうち、本日が“前編”ということに。キーワードは『松浦鉄道』です。例によって、鉄道そのものの写真はございませんが、語ることはできます。
――登場する駅名は東から西へ。「伊万里」→「楠久」→「久原」の3か所。
なお、私は10年ほど前に松浦鉄道沿線を回る計画を立てましたが、その時は諸事情により断念しました。
それゆえ地元に住まう方から見れば、おかしな記述もあるかもしれませんが、思い切って書きます。構成の都合上、「伊万里」「久原」「楠久」の順番で…
――まず、1本目・「伊万里」について。
“本編”では、佐賀藩の産業政策を支える“柱”の1つ、陶磁器産業を語るため、賑わう積出港として舞台になることが多いです。
なお、伊万里の商人について、深く描くことは出来ていませんが、場面設定で用いることは時折あります。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑰(積出港の昼下がり)〕

――次に、2本目・「久原」について。
“本編”には、創作要素の強い話が含まれることがあります。例えば、第16話「攘夷沸騰」から、なぜか度々、伊万里湾を望む高台に現れる、江藤新平。
〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」⑩(英国船の行方)〕
これは、江藤が藩の貿易部門・代品方に移る前振り。また第18話「京都見聞」の展開の都合で考えた設定です。
史実寄りの情報では、江藤の剣術道場の先輩で、小城(支藩)の富岡敬明が、伊万里にいろいろと関わりがありそうです。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」②(小城の秘剣)〕
――佐賀の支藩・小城藩の飛び地だったという「久原」。
“本編”では少し先の時期になりますが、1864年頃に小城藩内の抗争で責任を取る形になった富岡は、囚われの身として当地にいたようです。
富岡敬明に恩のあった、江藤は「久原」まで足を運び、剣舞を踊って励ました…らしいのです。
「江藤には伊万里の土地勘があったのでは…」との推測はこの辺りからです。
明治に入ってから、江藤らの助力で赦免された富岡。新政府の地方官僚として“伊万里県”から仕事を始め、熊本県や山梨県での活躍が伝わります。
〔参照:「励まし方も、人による(第16話・場面解説①)」〕

――そして、3本目・「楠久」について。
佐賀藩海軍の拠点として描くことが多い、伊万里。鍋島直正の“相棒”のように描くこともある、オランダ生まれの蒸気船・電流丸。
〔参照(前半):第15話「江戸動乱」⑫(その船、電流丸)〕
なお時々、殿様に呼びかけられると、電流丸が「ボッ…!」とか応えるのは、私の趣味による脚色です。
文久元年(1861年)。対馬に上陸したロシア船への警戒のため、佐賀藩海軍は電流丸を派遣します。その寄港地として、記述を見つけたのが「楠久」です。
――幕末期。蒸気船が行き交った、伊万里の海。
当時の対馬藩主・宗義和から、電流丸乗組員たちへの労(ねぎら)いとして“酒のつまみ”が授与されたといいます。高級珍味だったのか…気になります。
他の資料では、伊万里の浅瀬の多い場所からは小舟で、水深のある「楠久」に物資を移してから、大船で動かす…という話もありました。
港での操船には、かつて伊万里近辺で活躍した“松浦党”の水軍技術が活きたとか。“元寇”を描いた2001年大河ドラマ『北条時宗』を想い出します。

――この“ポサドニック号”事件の時に、
もう1つの蒸気船・観光丸の艦長として対馬に上陸したのが、佐野常民。長崎に近い優位性。佐賀藩士は海軍技術に通じた人材が多いのが特徴的です。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕
幕府から佐賀が預かっていた、観光丸の方は「久原」に寄港したという話も。
外輪蒸気船・観光丸。2010年大河ドラマ『龍馬伝』でもロケに使われた“復元船”が存在し、長崎で運行されていますが、いまはシーズンオフのようです。
――“観光丸”は、勝海舟や坂本龍馬も関わった船なのですが…
私の視点だと、鍋島直正が「この船(のちの観光丸)は、幾らで買えるのか?」と質問して、オランダの関係者を慌てさせたとか…
〔参照:第11話「蝦夷探検」①(殿、蒸気船に乗る)〕
幕府から佐賀藩に預けられた時に佐野常民だけでなく、島義勇も艦長だったことがあるとか…佐賀に関するエピソードが満載の蒸気船です。
佐賀藩士たちが蒸気船を運用して、伊万里の港からも海を駆けていた姿を、想う人が増えると良いな…という気持ちで書きました。
前回、ご案内した“本編”振り返りシリーズ第1回目です。
全3回のうち、本日が“前編”ということに。キーワードは『松浦鉄道』です。例によって、鉄道そのものの写真はございませんが、語ることはできます。
――登場する駅名は東から西へ。「伊万里」→「楠久」→「久原」の3か所。
なお、私は10年ほど前に松浦鉄道沿線を回る計画を立てましたが、その時は諸事情により断念しました。
それゆえ地元に住まう方から見れば、おかしな記述もあるかもしれませんが、思い切って書きます。構成の都合上、「伊万里」「久原」「楠久」の順番で…
――まず、1本目・「伊万里」について。
“本編”では、佐賀藩の産業政策を支える“柱”の1つ、陶磁器産業を語るため、賑わう積出港として舞台になることが多いです。
なお、伊万里の商人について、深く描くことは出来ていませんが、場面設定で用いることは時折あります。
〔参照:
――次に、2本目・「久原」について。
“本編”には、創作要素の強い話が含まれることがあります。例えば、第16話「攘夷沸騰」から、なぜか度々、伊万里湾を望む高台に現れる、江藤新平。
〔参照(後半):
これは、江藤が藩の貿易部門・代品方に移る前振り。また第18話「京都見聞」の展開の都合で考えた設定です。
史実寄りの情報では、江藤の剣術道場の先輩で、小城(支藩)の富岡敬明が、伊万里にいろいろと関わりがありそうです。
〔参照:
――佐賀の支藩・小城藩の飛び地だったという「久原」。
“本編”では少し先の時期になりますが、1864年頃に小城藩内の抗争で責任を取る形になった富岡は、囚われの身として当地にいたようです。
富岡敬明に恩のあった、江藤は「久原」まで足を運び、剣舞を踊って励ました…らしいのです。
「江藤には伊万里の土地勘があったのでは…」との推測はこの辺りからです。
明治に入ってから、江藤らの助力で赦免された富岡。新政府の地方官僚として“伊万里県”から仕事を始め、熊本県や山梨県での活躍が伝わります。
〔参照:
――そして、3本目・「楠久」について。
佐賀藩海軍の拠点として描くことが多い、伊万里。鍋島直正の“相棒”のように描くこともある、オランダ生まれの蒸気船・電流丸。
〔参照(前半):
なお時々、殿様に呼びかけられると、電流丸が「ボッ…!」とか応えるのは、私の趣味による脚色です。
文久元年(1861年)。対馬に上陸したロシア船への警戒のため、佐賀藩海軍は電流丸を派遣します。その寄港地として、記述を見つけたのが「楠久」です。
――幕末期。蒸気船が行き交った、伊万里の海。
当時の対馬藩主・宗義和から、電流丸乗組員たちへの労(ねぎら)いとして“酒のつまみ”が授与されたといいます。高級珍味だったのか…気になります。
他の資料では、伊万里の浅瀬の多い場所からは小舟で、水深のある「楠久」に物資を移してから、大船で動かす…という話もありました。
港での操船には、かつて伊万里近辺で活躍した“松浦党”の水軍技術が活きたとか。“元寇”を描いた2001年大河ドラマ『北条時宗』を想い出します。
――この“ポサドニック号”事件の時に、
もう1つの蒸気船・観光丸の艦長として対馬に上陸したのが、佐野常民。長崎に近い優位性。佐賀藩士は海軍技術に通じた人材が多いのが特徴的です。
〔参照:
幕府から佐賀が預かっていた、観光丸の方は「久原」に寄港したという話も。
外輪蒸気船・観光丸。2010年大河ドラマ『龍馬伝』でもロケに使われた“復元船”が存在し、長崎で運行されていますが、いまはシーズンオフのようです。
――“観光丸”は、勝海舟や坂本龍馬も関わった船なのですが…
私の視点だと、鍋島直正が「この船(のちの観光丸)は、幾らで買えるのか?」と質問して、オランダの関係者を慌てさせたとか…
〔参照:
幕府から佐賀藩に預けられた時に佐野常民だけでなく、島義勇も艦長だったことがあるとか…佐賀に関するエピソードが満載の蒸気船です。
佐賀藩士たちが蒸気船を運用して、伊万里の港からも海を駆けていた姿を、想う人が増えると良いな…という気持ちで書きました。
2022年01月16日
「“本編”への集中。」
こんにちは。
NHK土曜ドラマ『わげもん』。第2回でますます幕末・長崎の描写が充実していますね。私には、画面の外に佐賀藩士たちの姿も見えるかのようです。
現在、“本編”第17話「佐賀脱藩」の後半を準備中です。なかなか重たい展開になっており、かなり気合を入れねば、書き進めることができません。
“本編”についてですが、年始ぐらいから当ブログをご覧になり始めた方もいるかもしれませんので、念のためご説明します。

――当ブログで“本編”とは…
「こんな“幕末佐賀藩の大河ドラマ”が見たい!」という、私のイメージを記事にしたものです。
開始前は「あらすじだけを書く」予定でしたが、実際書き始めると、どんどんと内容が細かくなっていきました。
たぶん本来の大河ドラマならば、「ナレーション」や「画面上の地図」で表現しそうなところまで、セリフを入れていることも多いです。
――いまや、書きたいところは書いています。
開始時から重要エピソードになると考えた、第17話「佐賀脱藩」。年末年始をまたいでしまったため、小休止していました。
その間に、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、長崎を描く土曜ドラマ『わげもん』の放送開始など、気になる情報も多くありました。
すでに“本編”の下書きは再開していますが、このところ個人的に忙しいのと、集中力が必要そうな展開なので、しばらくは年末までの話を振り返ります。

――振り返りは、3回で企画します。
前編は、佐賀県の西部。長崎県ともつながっていく、伊万里市に関する話を。
〔参照(前半):第16話「攘夷沸騰」⑰(積出港の昼下がり)〕
中編は、佐賀県の中央。佐賀城下での展開と、そこから見える江戸の話を。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)〕
後編は、佐賀県の東部。隣接する福岡県を意識しながら、みやき町の話を。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕
――ちなみに“解説”も含め、当ブログの記事は…
様々な情報を寄せ集め、想像を巡らせて書いています。参照資料の信頼性にも相当な差があり、特に“本編”は史実に着想を得た創作とご理解ください。
もう少し、しっかり調べた方が良さそうなのですが、時間にも制約がある中で、何とか“本編”を進めたい気持ちも強いです。
第1回(前編)は伊万里編を予定します。一度、松浦鉄道にも乗ってみたいのですが、「佐賀の遠か…」という状況は続いています。
NHK土曜ドラマ『わげもん』。第2回でますます幕末・長崎の描写が充実していますね。私には、画面の外に佐賀藩士たちの姿も見えるかのようです。
現在、“本編”第17話「佐賀脱藩」の後半を準備中です。なかなか重たい展開になっており、かなり気合を入れねば、書き進めることができません。
“本編”についてですが、年始ぐらいから当ブログをご覧になり始めた方もいるかもしれませんので、念のためご説明します。
――当ブログで“本編”とは…
「こんな“幕末佐賀藩の大河ドラマ”が見たい!」という、私のイメージを記事にしたものです。
開始前は「あらすじだけを書く」予定でしたが、実際書き始めると、どんどんと内容が細かくなっていきました。
たぶん本来の大河ドラマならば、「ナレーション」や「画面上の地図」で表現しそうなところまで、セリフを入れていることも多いです。
――いまや、書きたいところは書いています。
開始時から重要エピソードになると考えた、第17話「佐賀脱藩」。年末年始をまたいでしまったため、小休止していました。
その間に、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、長崎を描く土曜ドラマ『わげもん』の放送開始など、気になる情報も多くありました。
すでに“本編”の下書きは再開していますが、このところ個人的に忙しいのと、集中力が必要そうな展開なので、しばらくは年末までの話を振り返ります。
――振り返りは、3回で企画します。
前編は、佐賀県の西部。長崎県ともつながっていく、伊万里市に関する話を。
〔参照(前半):
中編は、佐賀県の中央。佐賀城下での展開と、そこから見える江戸の話を。
〔参照(後半):
後編は、佐賀県の東部。隣接する福岡県を意識しながら、みやき町の話を。
〔参照(後半):
――ちなみに“解説”も含め、当ブログの記事は…
様々な情報を寄せ集め、想像を巡らせて書いています。参照資料の信頼性にも相当な差があり、特に“本編”は史実に着想を得た創作とご理解ください。
もう少し、しっかり調べた方が良さそうなのですが、時間にも制約がある中で、何とか“本編”を進めたい気持ちも強いです。
第1回(前編)は伊万里編を予定します。一度、松浦鉄道にも乗ってみたいのですが、「佐賀の遠か…」という状況は続いています。
2022年01月11日
「願えば叶う街・長崎。」
こんばんは。
大河ドラマ『鎌倉殿の13人』とくに北条氏の登場人物のキャラが濃く、主人公・北条義時〔演:小栗旬〕だけが“常識人”に見える…印象でした。
源頼朝〔演:大泉洋〕の存在感も面白いですし、北条政子〔演:小池栄子〕の配役には期待以上の説得力を感じます。
――『青天を衝け』とはまた違った感じで。
やはりセリフが面白いですね…登場人物が覚えづらい方は“字幕”を付けながら見るとよいかもしれません。
始まって10分ほどは「…今年は地味かな?」と思いましたが、時間の経過とともに仕上がってきて、冒頭の「弓の追撃を避けながら、“姫“を乗せ、馬で駆ける」場面へとループ。
…まったく違う見え方をしました。
――たぶん“大河ドラマ”クラスの脚本家の方なら、
どなたが担当でも「幕末の佐賀藩が題材なら、面白く描けるんじゃないか…」と感じることはよくあります。
当ブログを長くご覧の方は、お気付きかもしれません。今、私は“本編”第17話の再開を準備中です。
実は次からかなり重い展開が待っており、書く方にも迷いがあるのです。今日は大河とは別のドラマの力を借りた“連想”で助走を付けます。

――お題は、NHK土曜ドラマ『わげもん』です。
漢字に起こすと“和解(わげ)者”でしょうか。副題は「~長崎通訳異聞~」ですね。「幕末の長崎を描いた時代劇」に、何かつぶやかずには居られません。
「通訳だった…父を探す」主役を永瀬廉さんが演じています。『紅白歌合戦』に『King&Prince』として出場。朝ドラ『おかえりモネ』でも注目されたと聞きます。
実は存じ上げない方でしたが、放送日の関連番組で「白飯が大好き」と繰り返しエピソードが出るところ好印象です。
「たらふく米を食べても、動けば痩せる…」という良いお手本かもしれません…
――ドラマでは耳慣れた“佐賀ことば”に近いセリフが飛び交う。
「よか」「急(せ)からしか」とか、やはり気になります。言葉だけ聞いていると、「もう“佐賀の大河ドラマ”が来たのか!?」という錯覚が…。
異国船の来航を示す“白帆注進”とか、一気に佐賀城下が慌ただしくなりそうなキーワードも出てきます。
“幕末佐賀藩の大河ドラマ”が実現した場合、この言葉が出るたび、城下に砂ぼこりが舞う大騒動になる…という描写を繰り返すと良いかなと思っています。

――ドラマの展開では、アメリカの軍艦が長崎港に来ています。
作品の舞台である1849年(嘉永二年)は、黒船来航として象徴的な“ペリー来航”の4年前という紹介。
…というわけで、その四年後の1853年(嘉永六年)に、ペリー提督は江戸方面に向かい、浦賀に来航しています。
〔参照:第8話「黒船来航」⑨〕
――ちなみに同年、長崎港へ来たのは、
ロシアのプチャーチン提督の方です。“本編”では、その時の佐賀藩の騒然とした様子も描いてみました。
〔参照(後半):第9話「和親条約」⑤〕
その時にも佐賀藩士たちは、長崎港の島々に築かれた台場に詰めて、年末の寒空の下で、大規模な警備体制を敷いています。
ドラマからまた離れていますが、この時に殿・鍋島直正公は、最前線の陣中見舞いに足を運んでいます。ここは「殿、お優しい…!」と感激しておきましょう。
〔参照(終盤):第9話「和親条約」⑨〕
――そんなわけで、『わげもん』を視聴ながらも…
1年交代とは聞きますが、長崎警備の当番として現地に居るのは「佐賀藩なのか、福岡藩なのか…どちらだ?」などと、いろいろ気になります。
こちらも、ドラマでは描かれませんが、その三年前ほどの出来事。1846年(弘化三年)にはフランス船が長崎に接近した事件がありました。
佐賀藩の諫早領(現在の長崎県諫早市・佐賀県太良町)などの警備部隊が、長崎港に急行し、進入を阻止している絵図が伝わります。
〔参照(終盤):「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕〕
――外国への対応に苦慮する、長崎奉行所。
『わげもん』の雰囲気から見ても、当時の長崎で外国船とはうっかり戦えないと強く感じられます。警備にあたる佐賀藩士たちにも相当な重圧があったはず。
一方で、ドラマでは「ここならできる、ここは長崎だろ!」というセリフが印象的。“願えば、夢の叶う街”…長崎の描写が光ってます。

――そう言えば、昨年の大河ドラマ『青天を衝け』でも、
大隈重信〔演:大倉孝二〕が「佐賀は日本一、西洋通ぞ!」と語っていました。
当時の長崎が、日本の表玄関として西洋との接点では“オンリーワン”の存在だったから、佐賀藩は近代化を牽引できたのは疑いの無いところ。
「きっと佐賀が“佐賀”であるために、長崎は“長崎”でなければならなかった」と、言葉に起こすと意味が伝わりづらいですが、たびたび想うのです。
――『わげもん』の物語は、
全体的にミステリー仕立てなのか。国際都市・長崎を舞台として、通訳(通詞)の活躍に焦点を絞ったつくりのようです。
年始から長崎の風を感じるドラマの登場。「やはり今年の長崎は一味違う…」と感じます。正月からの観光番組でも、長崎の特集が連発されています。
そんな期待感がある中、“新型コロナ”が危うい感じで、複雑な心境です。佐賀への帰藩はもちろん、長崎にも行きたい気持ちは強くなる一方…なのですが。
大河ドラマ『鎌倉殿の13人』とくに北条氏の登場人物のキャラが濃く、主人公・北条義時〔演:小栗旬〕だけが“常識人”に見える…印象でした。
源頼朝〔演:大泉洋〕の存在感も面白いですし、北条政子〔演:小池栄子〕の配役には期待以上の説得力を感じます。
――『青天を衝け』とはまた違った感じで。
やはりセリフが面白いですね…登場人物が覚えづらい方は“字幕”を付けながら見るとよいかもしれません。
始まって10分ほどは「…今年は地味かな?」と思いましたが、時間の経過とともに仕上がってきて、冒頭の「弓の追撃を避けながら、“姫“を乗せ、馬で駆ける」場面へとループ。
…まったく違う見え方をしました。
――たぶん“大河ドラマ”クラスの脚本家の方なら、
どなたが担当でも「幕末の佐賀藩が題材なら、面白く描けるんじゃないか…」と感じることはよくあります。
当ブログを長くご覧の方は、お気付きかもしれません。今、私は“本編”第17話の再開を準備中です。
実は次からかなり重い展開が待っており、書く方にも迷いがあるのです。今日は大河とは別のドラマの力を借りた“連想”で助走を付けます。
――お題は、NHK土曜ドラマ『わげもん』です。
漢字に起こすと“和解(わげ)者”でしょうか。副題は「~長崎通訳異聞~」ですね。「幕末の長崎を描いた時代劇」に、何かつぶやかずには居られません。
「通訳だった…父を探す」主役を永瀬廉さんが演じています。『紅白歌合戦』に『King&Prince』として出場。朝ドラ『おかえりモネ』でも注目されたと聞きます。
実は存じ上げない方でしたが、放送日の関連番組で「白飯が大好き」と繰り返しエピソードが出るところ好印象です。
「たらふく米を食べても、動けば痩せる…」という良いお手本かもしれません…
――ドラマでは耳慣れた“佐賀ことば”に近いセリフが飛び交う。
「よか」「急(せ)からしか」とか、やはり気になります。言葉だけ聞いていると、「もう“佐賀の大河ドラマ”が来たのか!?」という錯覚が…。
異国船の来航を示す“白帆注進”とか、一気に佐賀城下が慌ただしくなりそうなキーワードも出てきます。
“幕末佐賀藩の大河ドラマ”が実現した場合、この言葉が出るたび、城下に砂ぼこりが舞う大騒動になる…という描写を繰り返すと良いかなと思っています。
――ドラマの展開では、アメリカの軍艦が長崎港に来ています。
作品の舞台である1849年(嘉永二年)は、黒船来航として象徴的な“ペリー来航”の4年前という紹介。
…というわけで、その四年後の1853年(嘉永六年)に、ペリー提督は江戸方面に向かい、浦賀に来航しています。
〔参照:
――ちなみに同年、長崎港へ来たのは、
ロシアのプチャーチン提督の方です。“本編”では、その時の佐賀藩の騒然とした様子も描いてみました。
〔参照(後半):
その時にも佐賀藩士たちは、長崎港の島々に築かれた台場に詰めて、年末の寒空の下で、大規模な警備体制を敷いています。
ドラマからまた離れていますが、この時に殿・鍋島直正公は、最前線の陣中見舞いに足を運んでいます。ここは「殿、お優しい…!」と感激しておきましょう。
〔参照(終盤):
――そんなわけで、『わげもん』を視聴ながらも…
1年交代とは聞きますが、長崎警備の当番として現地に居るのは「佐賀藩なのか、福岡藩なのか…どちらだ?」などと、いろいろ気になります。
こちらも、ドラマでは描かれませんが、その三年前ほどの出来事。1846年(弘化三年)にはフランス船が長崎に接近した事件がありました。
佐賀藩の諫早領(現在の長崎県諫早市・佐賀県太良町)などの警備部隊が、長崎港に急行し、進入を阻止している絵図が伝わります。
〔参照(終盤):
――外国への対応に苦慮する、長崎奉行所。
『わげもん』の雰囲気から見ても、当時の長崎で外国船とはうっかり戦えないと強く感じられます。警備にあたる佐賀藩士たちにも相当な重圧があったはず。
一方で、ドラマでは「ここならできる、ここは長崎だろ!」というセリフが印象的。“願えば、夢の叶う街”…長崎の描写が光ってます。
――そう言えば、昨年の大河ドラマ『青天を衝け』でも、
大隈重信〔演:大倉孝二〕が「佐賀は日本一、西洋通ぞ!」と語っていました。
当時の長崎が、日本の表玄関として西洋との接点では“オンリーワン”の存在だったから、佐賀藩は近代化を牽引できたのは疑いの無いところ。
「きっと佐賀が“佐賀”であるために、長崎は“長崎”でなければならなかった」と、言葉に起こすと意味が伝わりづらいですが、たびたび想うのです。
――『わげもん』の物語は、
全体的にミステリー仕立てなのか。国際都市・長崎を舞台として、通訳(通詞)の活躍に焦点を絞ったつくりのようです。
年始から長崎の風を感じるドラマの登場。「やはり今年の長崎は一味違う…」と感じます。正月からの観光番組でも、長崎の特集が連発されています。
そんな期待感がある中、“新型コロナ”が危うい感じで、複雑な心境です。佐賀への帰藩はもちろん、長崎にも行きたい気持ちは強くなる一方…なのですが。
2022年01月09日
「紅白から“源平”を考える。」
こんばんは。
本日(日曜)の夜、今年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』がスタートしますね。
主人公は小栗旬さん演じる北条義時。最初は“若き東国武士”の一人として描くのかなと予想するところ。
序盤の軸は源氏の御曹子・源頼朝〔演:大泉洋〕と平家の“ゴッドファーザー”・平清盛〔演:松平健〕でしょうか。
今回は“平氏“について、考えてみたいと思いますが、ラストは佐賀に話が還ることに。まだ年明けから10日も経っていないのですが、年末を振り返ります。
――私の年末の定番は、『紅白歌合戦』から『ゆく年くる年』。
いたって平凡なのですが、個人的にはこれが一番落ち着くのです。
毎年『ゆく年くる年』が始まる瞬間。“紅白”フィナーレの喧噪からの、どこかの寺からの鐘の音「ゴ~ンッ…♪」を聞くと、年を越すのだなと実感します。
年末年始の時点では“新型コロナ”も落ち着いている印象だったので、東京・浅草の街の賑わいが映し出されました。中継には、凄い人出が見えました。

――その時点から、さらに遡ること3時間ほど前。
“紅白”の前半終了前に、2021年の大きい話題だった『東京オリンピック』に、存在したかもしれない“もう1つの開会式”のような演出がありました。
曲目は『マツケンサンバⅡ』の特別版のようです。その夢舞台の中心に居たのは“マツケン”こと松平健さん。いわずと知れた時代劇の大スター。
――陽気なリズムに乗り、金色の“マツケン”が躍る。
松平健さんの存在感を軸にカラフルな舞台が展開。まるで“幻の式典”。
「やはり“上様”。器の大きいことだ…」
『暴れん坊将軍』で徳川八代将軍・吉宗として、お見かけしていた松平健さん。
紅白前半をさすがの貫禄で締めくくり、後半への良い流れを作ったようです。『鎌倉殿の13人』で、その松平健さんが演じるのは“平清盛”。
司会の大泉洋さんは“源頼朝”ですので、源平そろい踏みに言及していましたが、ドラマでは2人の共演場面は無さそうな雰囲気でした。
――10年前。2012年の大河ドラマは『平清盛』。
この時の主人公・平清盛も“松ケン”でした。松山ケンイチさんが演じた清盛は砂ぼこりの中を駆け、瀬戸内海の船上で重い刀を振る“荒々しい若者”。
少し記憶は遠いのですが、とにかくワイルドで「武士の世をつくる!」と太陽の光に向かって、決意を固める感じの…魅力的な主役でした。
国際貿易が活発な神戸港も、平清盛が大工事を施した“大輪田泊”から発展。宋銭を利用した貨幣経済を促進する…早くから世界が見えた人という評価も。

――「あれっ!?佐賀ん話の無かよ…?」という方へ。お待たせしました。
佐賀の七賢人には“平氏”を称し、新しい朝廷(明治政府)に出仕した人物がいるようです。朝臣として“平 胤雄”と署名したという、江藤新平です。
平氏には幾つかの系統があり、“武家の棟梁”となりうる平氏は、桓武天皇のひ孫の代から、“平”姓となった家系だといいます。
清盛の出た伊勢平氏の“平家”とは別系統ですが、関東で鎌倉幕府の主力となった、御家人の側にも平氏の家系が多く、その1つが千葉氏。
――『鎌倉殿の13人』で注目したい登場人物が…
およそ900年前に現在の千葉県を地盤に活躍した東国武士、鎌倉幕府創立期を支えた千葉常胤(ちば つねたね)〔演:岡本信人〕。
生誕九百年を迎えた2018年にも、本拠だった千葉市で一族ゆかりの地が集う“千葉氏サミット”を開催。まさに“千葉のヒーロー”と言うべきか千葉常胤。
幾度か開催されたサミットの情報を見ると、参加リストに佐賀県の小城市も名を連ねていました。千葉の名は佐賀藩・鍋島家の家老クラスにも見られます。

――江藤家も、佐賀で活躍した千葉氏ゆかりの家系だそうです。
千葉市の情報を見ると、活躍した千葉氏の子孫として、江藤新平も紹介されていました。千葉氏では“胤”の字を、名に入れるのが通例だったようです。
江藤新平は“胤雄”。父・助右衛門は“胤光”という諱(いみな)だそうです。
諱(≒実名)が胤雄、字・あざな(≒通常使う名前)が新平という説明になるのかなと思います。“歴史好き“と言いつつ、今まで深く考えなかった部分です。
――暮らしは貧しくとも、平氏に連なる一族という誇り。
佐賀を脱藩した後、京都で身分の高い公家に会っても、江藤が動じなかった理由はここにありそうです。
…身なりは質素ながら、真っ直ぐに前を見据える、佐賀からの脱藩者。ただならぬ気迫を纏(まと)い、京の大路を行く…
佐賀藩の下級役人として生きる予定だった人物が、“佐賀のヒーロー”となる過程をどう描くか…私なりの答えは“本編”を書く中で探していこうと思います。
本日(日曜)の夜、今年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』がスタートしますね。
主人公は小栗旬さん演じる北条義時。最初は“若き東国武士”の一人として描くのかなと予想するところ。
序盤の軸は源氏の御曹子・源頼朝〔演:大泉洋〕と平家の“ゴッドファーザー”・平清盛〔演:松平健〕でしょうか。
今回は“平氏“について、考えてみたいと思いますが、ラストは佐賀に話が還ることに。まだ年明けから10日も経っていないのですが、年末を振り返ります。
――私の年末の定番は、『紅白歌合戦』から『ゆく年くる年』。
いたって平凡なのですが、個人的にはこれが一番落ち着くのです。
毎年『ゆく年くる年』が始まる瞬間。“紅白”フィナーレの喧噪からの、どこかの寺からの鐘の音「ゴ~ンッ…♪」を聞くと、年を越すのだなと実感します。
年末年始の時点では“新型コロナ”も落ち着いている印象だったので、東京・浅草の街の賑わいが映し出されました。中継には、凄い人出が見えました。
――その時点から、さらに遡ること3時間ほど前。
“紅白”の前半終了前に、2021年の大きい話題だった『東京オリンピック』に、存在したかもしれない“もう1つの開会式”のような演出がありました。
曲目は『マツケンサンバⅡ』の特別版のようです。その夢舞台の中心に居たのは“マツケン”こと松平健さん。いわずと知れた時代劇の大スター。
――陽気なリズムに乗り、金色の“マツケン”が躍る。
松平健さんの存在感を軸にカラフルな舞台が展開。まるで“幻の式典”。
「やはり“上様”。器の大きいことだ…」
『暴れん坊将軍』で徳川八代将軍・吉宗として、お見かけしていた松平健さん。
紅白前半をさすがの貫禄で締めくくり、後半への良い流れを作ったようです。『鎌倉殿の13人』で、その松平健さんが演じるのは“平清盛”。
司会の大泉洋さんは“源頼朝”ですので、源平そろい踏みに言及していましたが、ドラマでは2人の共演場面は無さそうな雰囲気でした。
――10年前。2012年の大河ドラマは『平清盛』。
この時の主人公・平清盛も“松ケン”でした。松山ケンイチさんが演じた清盛は砂ぼこりの中を駆け、瀬戸内海の船上で重い刀を振る“荒々しい若者”。
少し記憶は遠いのですが、とにかくワイルドで「武士の世をつくる!」と太陽の光に向かって、決意を固める感じの…魅力的な主役でした。
国際貿易が活発な神戸港も、平清盛が大工事を施した“大輪田泊”から発展。宋銭を利用した貨幣経済を促進する…早くから世界が見えた人という評価も。
――「あれっ!?佐賀ん話の無かよ…?」という方へ。お待たせしました。
佐賀の七賢人には“平氏”を称し、新しい朝廷(明治政府)に出仕した人物がいるようです。朝臣として“平 胤雄”と署名したという、江藤新平です。
平氏には幾つかの系統があり、“武家の棟梁”となりうる平氏は、桓武天皇のひ孫の代から、“平”姓となった家系だといいます。
清盛の出た伊勢平氏の“平家”とは別系統ですが、関東で鎌倉幕府の主力となった、御家人の側にも平氏の家系が多く、その1つが千葉氏。
――『鎌倉殿の13人』で注目したい登場人物が…
およそ900年前に現在の千葉県を地盤に活躍した東国武士、鎌倉幕府創立期を支えた千葉常胤(ちば つねたね)〔演:岡本信人〕。
生誕九百年を迎えた2018年にも、本拠だった千葉市で一族ゆかりの地が集う“千葉氏サミット”を開催。まさに“千葉のヒーロー”と言うべきか千葉常胤。
幾度か開催されたサミットの情報を見ると、参加リストに佐賀県の小城市も名を連ねていました。千葉の名は佐賀藩・鍋島家の家老クラスにも見られます。
――江藤家も、佐賀で活躍した千葉氏ゆかりの家系だそうです。
千葉市の情報を見ると、活躍した千葉氏の子孫として、江藤新平も紹介されていました。千葉氏では“胤”の字を、名に入れるのが通例だったようです。
江藤新平は“胤雄”。父・助右衛門は“胤光”という諱(いみな)だそうです。
諱(≒実名)が胤雄、字・あざな(≒通常使う名前)が新平という説明になるのかなと思います。“歴史好き“と言いつつ、今まで深く考えなかった部分です。
――暮らしは貧しくとも、平氏に連なる一族という誇り。
佐賀を脱藩した後、京都で身分の高い公家に会っても、江藤が動じなかった理由はここにありそうです。
…身なりは質素ながら、真っ直ぐに前を見据える、佐賀からの脱藩者。ただならぬ気迫を纏(まと)い、京の大路を行く…
佐賀藩の下級役人として生きる予定だった人物が、“佐賀のヒーロー”となる過程をどう描くか…私なりの答えは“本編”を書く中で探していこうと思います。
2022年01月06日
「“鎌倉”どうでしょう」
こんばんは。
年明け。仕事モードです。今回の記事は簡潔にと思いましたが、何を書いても話が佐賀に還ってしまう、私のブログ。どうしても長文になりがちです。
それはさておき、いよいよ今年(2022年)の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』が、スタートしますね。
まだ、放送してもいませんが、個人的に注目しているポイントを、前後2回ほどで記事にしようかと思います。

――前編は、“源氏”編。「とてもボヤきそうな、頼朝公」
今回の大河ドラマで、鎌倉幕府を開いた源頼朝公を演じる方。
北海道発のバラエティー番組『水曜どうでしょう』で有名となり、いまや全国区の人気者。昨年末には『紅白歌合戦』で司会を務めた、大泉洋さん。
2016年大河ドラマ『真田丸』で、主人公・真田信繁(幸村)〔演:堺雅人〕の兄・真田信幸(信之)役での実績があります。
――愚痴っぽくて、親しみやすい長男キャラでした。
「大博打(おおばくち)の始まりじゃあ!」とか「ではおのおの抜かりなく」など、数々の名ゼリフを発し、インパクト絶大の父・真田昌幸〔演:草刈正雄〕。
小回りの効く弟・真田信繁(幸村)と違って、他にも祖母のとり〔演:草笛光子〕など家族にも、ぶんぶん振り回される兄・真田信幸。
のち苦悩のすえ父弟と別れるお兄ちゃん。「私は決めた!」と敵だった徳川方につき、名も真田家の“幸”の字をはばかって“信之”と改め…。
板挟みの苦労人ぶりも、大泉さんの表情とともに記憶に残っています。

――そんな『真田丸』の舞台の1つが、佐賀にありました。
文禄・慶長の役での拠点となった、肥前名護屋城。「綺羅、星の如く」当地に集結する戦国武将たち。つかの間の“仮装大会“の準備に勤しみます。
「味良しの~瓜(うり)~ 召されそうらえ~♪」
未だに耳に残る、真田昌幸役・草刈正雄さんの歌声。(第26回「瓜売」より)
本筋とは別のところでも、忘れられない作品を見せる、脚本家・三谷幸喜さん。『鎌倉殿の13人』も三谷さんの脚本なので、注目せざるを得ないところです。
――肥前名護屋城址は、現在の佐賀県唐津市(鎮西町)に所在。
豊臣秀吉の朝鮮出兵のため、各地の武将が一堂に会した肥前名護屋の地。大名たちの陣屋を始め、多数の人々がひしめく“大都市”となりました。
『真田丸』では真田信繁(幸村)の目線で、豊臣秀吉〔演:小日向文世〕の晩年が描かれます。天下人として、栄華を誇った豊臣政権トップの“暴走”と老い。
その天下人の逝去とともに肥前名護屋は、歴史の表舞台から姿を消します。安土桃山時代に20万人が生活したと言われる“巨大都市”が存在したという歴史の一頁です。

――今年の『鎌倉殿の13人』に話を戻すと。
大泉洋さんは、かつて「いい国(1192年)作ろう、鎌倉幕府」でおなじみだった源頼朝を演じるという大役。
但し、現在では、鎌倉幕府は段階的に出来たので成立年は特定しないとか、成立年は“いい箱”(1185年)とする見解が優勢だという情報を見かけます。
歴史勉強中のお子様、お孫さんのいる方は、今の教科書をご覧になってみても良いかもしれません。
――地域ローカル番組から全国区に。
大活躍している今でも、北海道民の方々は大泉さんに対して、半分は心配の混ざった暖かい眼差しで見守っている…とよく聞きます。
また、北海道は“大河ドラマ”の中心地と離れていることが多いためか、「全国平均よりも大河ドラマの視聴率が低い」と聞いたことがあります。
その点、大泉さんが準主役で大きい存在感を残しそうな『鎌倉殿の13人』は大丈夫なのかもしれません。

――北海道が描ける「大河ドラマ」の“答え”なら、佐賀にもあります。
佐賀の七賢人の1人にして、“札幌”を創った人・島義勇。現在では200万人に届こうかという大都市の基礎を築いています。
当地では“判官さま”と呼ばれることが多いそうです。「五州第一の都(世界一の都市)」を作るという、まっすぐな想いを込めて計画したのが札幌の街。
――幕末期の佐賀藩を書くと、
北海道(蝦夷地)の状況も、しっかりと表現することができそうです。
近い未来に島義勇を演じる方は、できれば北海道(札幌周辺)の出身、表情が豊かで、印象に残る演技をする俳優さんが望ましいと考えるところ。
佐賀藩士の中でも独自の行動が多い印象なので、多忙なスケジュールの方でも、調整はききやすそうです。ラストはあえて一言でまとめます。
「…どうでしょう」と。
年明け。仕事モードです。今回の記事は簡潔にと思いましたが、何を書いても話が佐賀に還ってしまう、私のブログ。どうしても長文になりがちです。
それはさておき、いよいよ今年(2022年)の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』が、スタートしますね。
まだ、放送してもいませんが、個人的に注目しているポイントを、前後2回ほどで記事にしようかと思います。
――前編は、“源氏”編。「とてもボヤきそうな、頼朝公」
今回の大河ドラマで、鎌倉幕府を開いた源頼朝公を演じる方。
北海道発のバラエティー番組『水曜どうでしょう』で有名となり、いまや全国区の人気者。昨年末には『紅白歌合戦』で司会を務めた、大泉洋さん。
2016年大河ドラマ『真田丸』で、主人公・真田信繁(幸村)〔演:堺雅人〕の兄・真田信幸(信之)役での実績があります。
――愚痴っぽくて、親しみやすい長男キャラでした。
「大博打(おおばくち)の始まりじゃあ!」とか「ではおのおの抜かりなく」など、数々の名ゼリフを発し、インパクト絶大の父・真田昌幸〔演:草刈正雄〕。
小回りの効く弟・真田信繁(幸村)と違って、他にも祖母のとり〔演:草笛光子〕など家族にも、ぶんぶん振り回される兄・真田信幸。
のち苦悩のすえ父弟と別れるお兄ちゃん。「私は決めた!」と敵だった徳川方につき、名も真田家の“幸”の字をはばかって“信之”と改め…。
板挟みの苦労人ぶりも、大泉さんの表情とともに記憶に残っています。
――そんな『真田丸』の舞台の1つが、佐賀にありました。
文禄・慶長の役での拠点となった、肥前名護屋城。「綺羅、星の如く」当地に集結する戦国武将たち。つかの間の“仮装大会“の準備に勤しみます。
「味良しの~瓜(うり)~ 召されそうらえ~♪」
未だに耳に残る、真田昌幸役・草刈正雄さんの歌声。(第26回「瓜売」より)
本筋とは別のところでも、忘れられない作品を見せる、脚本家・三谷幸喜さん。『鎌倉殿の13人』も三谷さんの脚本なので、注目せざるを得ないところです。
――肥前名護屋城址は、現在の佐賀県唐津市(鎮西町)に所在。
豊臣秀吉の朝鮮出兵のため、各地の武将が一堂に会した肥前名護屋の地。大名たちの陣屋を始め、多数の人々がひしめく“大都市”となりました。
『真田丸』では真田信繁(幸村)の目線で、豊臣秀吉〔演:小日向文世〕の晩年が描かれます。天下人として、栄華を誇った豊臣政権トップの“暴走”と老い。
その天下人の逝去とともに肥前名護屋は、歴史の表舞台から姿を消します。安土桃山時代に20万人が生活したと言われる“巨大都市”が存在したという歴史の一頁です。
――今年の『鎌倉殿の13人』に話を戻すと。
大泉洋さんは、かつて「いい国(1192年)作ろう、鎌倉幕府」でおなじみだった源頼朝を演じるという大役。
但し、現在では、鎌倉幕府は段階的に出来たので成立年は特定しないとか、成立年は“いい箱”(1185年)とする見解が優勢だという情報を見かけます。
歴史勉強中のお子様、お孫さんのいる方は、今の教科書をご覧になってみても良いかもしれません。
――地域ローカル番組から全国区に。
大活躍している今でも、北海道民の方々は大泉さんに対して、半分は心配の混ざった暖かい眼差しで見守っている…とよく聞きます。
また、北海道は“大河ドラマ”の中心地と離れていることが多いためか、「全国平均よりも大河ドラマの視聴率が低い」と聞いたことがあります。
その点、大泉さんが準主役で大きい存在感を残しそうな『鎌倉殿の13人』は大丈夫なのかもしれません。
――北海道が描ける「大河ドラマ」の“答え”なら、佐賀にもあります。
佐賀の七賢人の1人にして、“札幌”を創った人・島義勇。現在では200万人に届こうかという大都市の基礎を築いています。
当地では“判官さま”と呼ばれることが多いそうです。「五州第一の都(世界一の都市)」を作るという、まっすぐな想いを込めて計画したのが札幌の街。
――幕末期の佐賀藩を書くと、
北海道(蝦夷地)の状況も、しっかりと表現することができそうです。
近い未来に島義勇を演じる方は、できれば北海道(札幌周辺)の出身、表情が豊かで、印象に残る演技をする俳優さんが望ましいと考えるところ。
佐賀藩士の中でも独自の行動が多い印象なので、多忙なスケジュールの方でも、調整はききやすそうです。ラストはあえて一言でまとめます。
「…どうでしょう」と。
2022年01月03日
「醒覚の剣(歌枕)」
こんばんは。
私のブログでは、ここ2年間ほど佐賀に帰れないと語るわりに、佐賀の写真をよく掲載します。この“妙技”を可能にしているのが、地元に住む叔父上です。
…叔父上に次々と舞い込むのは、もう若くはない甥っ子からの依頼の数々。
今回はちょっと“新春ミステリー”風の書き出しで正月らしさを意識しましたが、嬉野~唐津へとつながる…まるで“2時間ドラマ”のような長文になりました。
――時に、私の想像の“斜め上”を行く叔父上。
「嬉野に寄るときに“和泉式部”が居たから、撮ってきたとよ。」
「…!和泉式部…、なぜ佐賀に?」
平安時代の歌人の名であることはわかる。しかし、一応は歴史好きのはずの私だが、その辺りの知識は乏しい。
「…平安期か…」
私は、思考を巡らした。こういう時の叔父上は、極めて無邪気である。奇をてらったところが無い分、動きが読めない。

――これを「幕末佐賀藩の大河ドラマ」がテーマのブログで、どう使う…?
「まず地図ば、見んね?」
私の住む地から、遠く隔たった佐賀。電話口から叔父上の声がする。そうだ、考えるだけでは駄目だ。現地に足を運べずとも、できる事があると言うことか。
「和泉式部像の所在は、嬉野市・塩田の辺りですね…。」
「そうたい、塩田の近くばい。」
嬉野市・塩田。そういえば“本編”でも描いたことがある。有明海の干満の差を利用し、江戸期に水運で栄えたという。

――隆盛(りゅうせい)を誇った“川の港”。
十二単(じゅうにひとえ)姿の女性像は、叔父上が私に出した公案(課題)であるのか。電話を切ったあと、さらに思索を重ねる。
「もしや京都と、佐賀にある塩田の港がつながっていた…ということか!」
少し調べると、実は全国各地に“和泉式部”の伝承はあるようだ。幾人もの、和泉式部の影。
――著名な平安の歌人だった和泉式部は、
生没年も不詳というが、恋多き女性だったと伝わるようだ。かの『源氏物語』の作者・紫式部は彼女の華やかさに妬みを感じていた…と聞いた事がある。
和泉式部像の周辺情報によると、佐賀出身説は、おそらくは御仏のご加護により、現在の白石町に生まれた才女が、ここ嬉野市・塩田の夫妻に育てられ、都に上ったそうだ。

――この歌碑は“千年”も前の、出来事の手がかりなのか。
古の時代にも、佐賀と京都の間にあったかもしれない、点と点を結ぶ“動線”。
百五十年ばかりしか離れていない、幕末でもわからぬ事だらけなのだ。さすがに、千年となれば厳しい。
「…この事案は、管轄外だ。私には追えない。」
しかし、幾つかの点には、思い当たるところがある。
1つ、当地・塩田が何らかの形で、京の都と交流があったと思われる事。
1つ、高名な女流歌人が輩出される素地がある、文化水準が推測できる事。
――現在、『さがファンブログ』でも閲覧できる…
“市報うれしの”にも、短歌を掲載するコーナーを見つけた。この流れだと、何の不思議もない。きっと心が動いた時には、歌を詠むのだ。では、
念願の 鉄路来たれる 嬉野に
茶の沸く 湯も湧く また街もわく
私に短歌の心得は無い…そして“字余り”だが、祝福の気持ちは込めた。嬉野に鉄道の新駅が来る。西九州新幹線の開業年には、いろいろと期待もある。

――さて平安期に、京の歌人たちは…
実際に足を運べずとも、遙か東北の地にさえ想いを馳せ、歌を詠んだという。
こうして名所化された場所を“歌枕”と呼び、江戸時代の俳人・松尾芭蕉などは、それら“聖地”を巡っていたと聞く。
いわば“強く想う力”が重なって、本物の“聖地”を創り出した事例もあるということか。強く想うことだけならば、微力ながらも、私の得手とするところである。
――想い出すのは、昨年の大河ドラマ『青天を衝け』での、
江戸幕府14代将軍・徳川家茂〔演:磯村勇斗〕と和宮〔演:深川麻衣〕の場面。美男美女で優雅であり、個人的に“源氏物語”っぽく見えてしまった。
但し、この“ご夫婦”、恋多き男女とは真逆。まるで、二昔くらい前の少女マンガでしか見られないような、一途な純愛物語と言ってよさそうだ。
――そして妻・和宮が、夫・家茂への気持ちを詠んだ和歌には、
涙を誘うような想いが伝わる一首がある。『青天を衝け』でも一瞬、この内容の場面が登場したが、ここでは詳細を差し控える。
妻だけでなく、幕臣たちからも慕われた“上様”だったのか。京都で苦境にあった将軍・徳川家茂を救おうとした人物もいた。
こちらも現在の佐賀県にある、唐津藩の小笠原長行。将軍・家茂を苦しめる攘夷派を一掃すべく、軍勢を率い、京都へ乗り込もうとした史実があるようだ。

――こうして、私の新春一本目の調査(?)は完了した。
「…叔父上。あの写真。どうにか、幕末の佐賀とつながりました。」
この記事が、調査報告だ。実際のところ叔父上は「あんまり無理ばせんと。」とよく言ってくれる。たぶん今回も、そうだろう。
佐賀県全体に通じる“物語”を描こうとする試み…“本編”を描く道のりは、今年も険しそうだ。
私のブログでは、ここ2年間ほど佐賀に帰れないと語るわりに、佐賀の写真をよく掲載します。この“妙技”を可能にしているのが、地元に住む叔父上です。
…叔父上に次々と舞い込むのは、もう若くはない甥っ子からの依頼の数々。
今回はちょっと“新春ミステリー”風の書き出しで正月らしさを意識しましたが、嬉野~唐津へとつながる…まるで“2時間ドラマ”のような長文になりました。
――時に、私の想像の“斜め上”を行く叔父上。
「嬉野に寄るときに“和泉式部”が居たから、撮ってきたとよ。」
「…!和泉式部…、なぜ佐賀に?」
平安時代の歌人の名であることはわかる。しかし、一応は歴史好きのはずの私だが、その辺りの知識は乏しい。
「…平安期か…」
私は、思考を巡らした。こういう時の叔父上は、極めて無邪気である。奇をてらったところが無い分、動きが読めない。
――これを「幕末佐賀藩の大河ドラマ」がテーマのブログで、どう使う…?
「まず地図ば、見んね?」
私の住む地から、遠く隔たった佐賀。電話口から叔父上の声がする。そうだ、考えるだけでは駄目だ。現地に足を運べずとも、できる事があると言うことか。
「和泉式部像の所在は、嬉野市・塩田の辺りですね…。」
「そうたい、塩田の近くばい。」
嬉野市・塩田。そういえば“本編”でも描いたことがある。有明海の干満の差を利用し、江戸期に水運で栄えたという。
――隆盛(りゅうせい)を誇った“川の港”。
十二単(じゅうにひとえ)姿の女性像は、叔父上が私に出した公案(課題)であるのか。電話を切ったあと、さらに思索を重ねる。
「もしや京都と、佐賀にある塩田の港がつながっていた…ということか!」
少し調べると、実は全国各地に“和泉式部”の伝承はあるようだ。幾人もの、和泉式部の影。
――著名な平安の歌人だった和泉式部は、
生没年も不詳というが、恋多き女性だったと伝わるようだ。かの『源氏物語』の作者・紫式部は彼女の華やかさに妬みを感じていた…と聞いた事がある。
和泉式部像の周辺情報によると、佐賀出身説は、おそらくは御仏のご加護により、現在の白石町に生まれた才女が、ここ嬉野市・塩田の夫妻に育てられ、都に上ったそうだ。
――この歌碑は“千年”も前の、出来事の手がかりなのか。
古の時代にも、佐賀と京都の間にあったかもしれない、点と点を結ぶ“動線”。
百五十年ばかりしか離れていない、幕末でもわからぬ事だらけなのだ。さすがに、千年となれば厳しい。
「…この事案は、管轄外だ。私には追えない。」
しかし、幾つかの点には、思い当たるところがある。
1つ、当地・塩田が何らかの形で、京の都と交流があったと思われる事。
1つ、高名な女流歌人が輩出される素地がある、文化水準が推測できる事。
――現在、『さがファンブログ』でも閲覧できる…
“市報うれしの”にも、短歌を掲載するコーナーを見つけた。この流れだと、何の不思議もない。きっと心が動いた時には、歌を詠むのだ。では、
念願の 鉄路来たれる 嬉野に
茶の沸く 湯も湧く また街もわく
私に短歌の心得は無い…そして“字余り”だが、祝福の気持ちは込めた。嬉野に鉄道の新駅が来る。西九州新幹線の開業年には、いろいろと期待もある。
――さて平安期に、京の歌人たちは…
実際に足を運べずとも、遙か東北の地にさえ想いを馳せ、歌を詠んだという。
こうして名所化された場所を“歌枕”と呼び、江戸時代の俳人・松尾芭蕉などは、それら“聖地”を巡っていたと聞く。
いわば“強く想う力”が重なって、本物の“聖地”を創り出した事例もあるということか。強く想うことだけならば、微力ながらも、私の得手とするところである。
――想い出すのは、昨年の大河ドラマ『青天を衝け』での、
江戸幕府14代将軍・徳川家茂〔演:磯村勇斗〕と和宮〔演:深川麻衣〕の場面。美男美女で優雅であり、個人的に“源氏物語”っぽく見えてしまった。
但し、この“ご夫婦”、恋多き男女とは真逆。まるで、二昔くらい前の少女マンガでしか見られないような、一途な純愛物語と言ってよさそうだ。
――そして妻・和宮が、夫・家茂への気持ちを詠んだ和歌には、
涙を誘うような想いが伝わる一首がある。『青天を衝け』でも一瞬、この内容の場面が登場したが、ここでは詳細を差し控える。
妻だけでなく、幕臣たちからも慕われた“上様”だったのか。京都で苦境にあった将軍・徳川家茂を救おうとした人物もいた。
こちらも現在の佐賀県にある、唐津藩の小笠原長行。将軍・家茂を苦しめる攘夷派を一掃すべく、軍勢を率い、京都へ乗り込もうとした史実があるようだ。
――こうして、私の新春一本目の調査(?)は完了した。
「…叔父上。あの写真。どうにか、幕末の佐賀とつながりました。」
この記事が、調査報告だ。実際のところ叔父上は「あんまり無理ばせんと。」とよく言ってくれる。たぶん今回も、そうだろう。
佐賀県全体に通じる“物語”を描こうとする試み…“本編”を描く道のりは、今年も険しそうだ。
2022年01月01日
「昨年の我に、今年は勝つべし」
新年あけましておめでとうございます。
本年も、引き続きよろしくお願い申し上げます。
年の瀬の締めくくりは月並みに、NHK『紅白歌合戦』をずっと見ていました。
――心に響いた場面が…?
長崎市出身のさだまさしさんが、同じく長崎県の五島列島・福江島で生まれ育った、司会の川口春奈さんに呼びかけるところに反応する私。
「春奈ちゃん、早う長崎に帰って来んね~。」
いきなり長崎への帰還を促す、さださんのアピール。笑顔を見せる川口さん。
「この言葉…実は“長崎”が出身者を呼び戻そうとしている…?」
私は、今回も深読みしすぎなのかもしれない。だが全国に熱烈なファンを多数抱える、さだまさしさんの影響力は計り知れない。これが長崎の力か。

――序盤のVTRでも、故郷の島に帰省する川口さんの姿が。
一昨年の大河ドラマ『麒麟がくる』では、主人公・明智十兵衛光秀の幼なじみで、織田信長の正室・帰蝶役で急遽の登板。
コロナ禍で撮影も難航する中、凜々しい立ち姿を崩さず、大役を演じきったことが記憶に新しい。
大河ドラマの好演で名をあげ、紅白の司会も務めた、川口春奈さんは、すでに「故郷に錦を飾っている」といっても良いのかもしれません。
――そういえば、この方も長崎出身。
例年は年越しライブ会場からの中継が多い、福山雅治さんも今回は、紅白の舞台に来ていました。
「…来るべき新年に向けて、長崎は仕掛けているのか。」
何とはなしに西九州新幹線の開業を迎える、2022年に向けての長崎の勢いを感じる紅白でした。
ちなみに、新年からNHK総合・土曜9時からの枠で『わげもん』という幕末期・長崎の通訳者を描いたドラマがあるそうです。
江戸時代、西洋に唯一開かれていた日本の“表玄関”。国際都市・長崎を描かねば、佐賀藩の価値は語れません。これは良い傾向だと、期待しています。
〔参照:「西九州にほえろ!」〕

――ところで今回、紅白のテーマは“カラフル”でした。
「長崎の活躍はよかばってん、佐賀ん色の無かごたよ…」
冷静になって考えると、まぁ、そういう事ではあります。
これも県民性なのか、佐賀出身の“芸能人”は少ないと感じます。地道で堅実と語れば…それも佐賀の美点なので、ここは否定的に捉えていません。
やはり紅白で“佐賀の色”を出すならば、前回、語った『ゾンビランドサガ』の主人公グループ・フランシュシュに期待するのが近道かもしれません。
正攻法で映画版を大ヒットさせ、第3期のアニメ化も決定すれば、あるいは…。
――ちょっと見てみたい展開が、例えば…
コロナ禍の終息への期待も込めつつ、夏の甲子園等で佐賀代表となった高校の野球部に(吹奏楽部にも)期待することがあります。
『ゾンビランドサガ』の楽曲は、意外と“ブラスバンド”映えするのか、ネット上でも鳥栖や嬉野の楽団などが、演奏をしているのを見かけます。
“佐賀のテーマ”が鳴り響く中、不屈の“ゾンビィ旋風”を巻き起して、勝ち進む佐賀代表が話題となれば、棚ぼた的に紅白への勝機が見えるかと考えます。
…特に何の根拠もない話なので、“初夢”みたいなものとお考えください。

――そうだ、新年にあたって目標を語らねば…
このように年末年始で気が緩んでいる分、思考が散らかっております。
日常で「私は“佐賀藩士”だから我慢できるけど、もし“佐賀藩士”でなければ我慢できなかった!…(?)」と、心の中で叫ぶことも多い私。
〔参照:「私の失策とイルミネーションのご夫婦(前編)」〕
――うっかりすると、会議中にも、
「そいは、今やらんばならんです。」とか佐賀ことば寄りの発言が出る。内に秘めた佐賀の誇りは溢れ出ない程度に抑えながら、大都市圏で生きています。
有明海のように波穏やかに、小城の滝の清冽さをもって、みやき・吉野ヶ里の水路のごとく行き届く…柔軟でメリハリの効いた動きが、今年の目標です。
「言うは易く行うは難し…」ですが、これが出来れば少なくとも「“昨年の私”には勝ることができるはず」と考える、年始めの一日でした。
本年も、引き続きよろしくお願い申し上げます。
年の瀬の締めくくりは月並みに、NHK『紅白歌合戦』をずっと見ていました。
――心に響いた場面が…?
長崎市出身のさだまさしさんが、同じく長崎県の五島列島・福江島で生まれ育った、司会の川口春奈さんに呼びかけるところに反応する私。
「春奈ちゃん、早う長崎に帰って来んね~。」
いきなり長崎への帰還を促す、さださんのアピール。笑顔を見せる川口さん。
「この言葉…実は“長崎”が出身者を呼び戻そうとしている…?」
私は、今回も深読みしすぎなのかもしれない。だが全国に熱烈なファンを多数抱える、さだまさしさんの影響力は計り知れない。これが長崎の力か。
――序盤のVTRでも、故郷の島に帰省する川口さんの姿が。
一昨年の大河ドラマ『麒麟がくる』では、主人公・明智十兵衛光秀の幼なじみで、織田信長の正室・帰蝶役で急遽の登板。
コロナ禍で撮影も難航する中、凜々しい立ち姿を崩さず、大役を演じきったことが記憶に新しい。
大河ドラマの好演で名をあげ、紅白の司会も務めた、川口春奈さんは、すでに「故郷に錦を飾っている」といっても良いのかもしれません。
――そういえば、この方も長崎出身。
例年は年越しライブ会場からの中継が多い、福山雅治さんも今回は、紅白の舞台に来ていました。
「…来るべき新年に向けて、長崎は仕掛けているのか。」
何とはなしに西九州新幹線の開業を迎える、2022年に向けての長崎の勢いを感じる紅白でした。
ちなみに、新年からNHK総合・土曜9時からの枠で『わげもん』という幕末期・長崎の通訳者を描いたドラマがあるそうです。
江戸時代、西洋に唯一開かれていた日本の“表玄関”。国際都市・長崎を描かねば、佐賀藩の価値は語れません。これは良い傾向だと、期待しています。
〔参照:
――ところで今回、紅白のテーマは“カラフル”でした。
「長崎の活躍はよかばってん、佐賀ん色の無かごたよ…」
冷静になって考えると、まぁ、そういう事ではあります。
これも県民性なのか、佐賀出身の“芸能人”は少ないと感じます。地道で堅実と語れば…それも佐賀の美点なので、ここは否定的に捉えていません。
やはり紅白で“佐賀の色”を出すならば、前回、語った『ゾンビランドサガ』の主人公グループ・フランシュシュに期待するのが近道かもしれません。
正攻法で映画版を大ヒットさせ、第3期のアニメ化も決定すれば、あるいは…。
――ちょっと見てみたい展開が、例えば…
コロナ禍の終息への期待も込めつつ、夏の甲子園等で佐賀代表となった高校の野球部に(吹奏楽部にも)期待することがあります。
『ゾンビランドサガ』の楽曲は、意外と“ブラスバンド”映えするのか、ネット上でも鳥栖や嬉野の楽団などが、演奏をしているのを見かけます。
“佐賀のテーマ”が鳴り響く中、不屈の“ゾンビィ旋風”を巻き起して、勝ち進む佐賀代表が話題となれば、棚ぼた的に紅白への勝機が見えるかと考えます。
…特に何の根拠もない話なので、“初夢”みたいなものとお考えください。
――そうだ、新年にあたって目標を語らねば…
このように年末年始で気が緩んでいる分、思考が散らかっております。
日常で「私は“佐賀藩士”だから我慢できるけど、もし“佐賀藩士”でなければ我慢できなかった!…(?)」と、心の中で叫ぶことも多い私。
〔参照:
――うっかりすると、会議中にも、
「そいは、今やらんばならんです。」とか佐賀ことば寄りの発言が出る。内に秘めた佐賀の誇りは溢れ出ない程度に抑えながら、大都市圏で生きています。
有明海のように波穏やかに、小城の滝の清冽さをもって、みやき・吉野ヶ里の水路のごとく行き届く…柔軟でメリハリの効いた動きが、今年の目標です。
「言うは易く行うは難し…」ですが、これが出来れば少なくとも「“昨年の私”には勝ることができるはず」と考える、年始めの一日でした。




