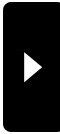2020年03月30日
第7話「尊王義祭」⑧
こんばんは。
藩校「弘道館」で教鞭をとる枝吉神陽。白熱する佐賀の教育現場を見に来た、幕末の有名人(になる人)が感銘を受けます。
――佐賀城本丸。殿・鍋島直正と、藩校の責任者・鍋島安房が会議中である。
安房から「義祭同盟」の状況について、報告を受ける直正。
「枝吉神陽、若い者たちを引き付ける力が、秀でておるな。」
直正もよく藩校を見ている。
「神陽の学問は、常に“いかに用いるか”を見据えておるようです。」
安房は、いわば“校長先生”であり、カリキュラムもある程度は把握している。

――凄まじい暗記力、そして知識を応用する力を持つ神陽。
「神陽…、“蘭学”も学んでくれんかのう。」
天才・枝吉神陽の能力を、佐賀の科学技術にも転用できないか考える直正。
「殿、それはさすがに難しいかと。」
安房がやや顔をしかめる。今のままの神陽がお気に入りのようだ。
後に、直正が待望する“万能の研究主任”の役割は、佐野常民が担う。この頃は、医術の修業のため各地を回っていた。佐賀にはいなかったのである。
――話を戻そう。神陽は“尊王”の志が高い国学者だが、知識は“考える材料”という柔軟さも持っていた。
神陽はとにかく学生たちに考えさせる。
「古典で語られる、聖人がなにゆえ“偉大”なのかを考えることだ!」
神陽は学ぶ目的を考えさせ、どう実践するかも考えさせた。
――こうして神陽のもとには“暗記”では物足らない“考える学生”が集まったのである。
「古の世に、我が身を置いたつもりで考えました。」
大木幡六(喬任)である。“思考実験(シミュレーション)”は、大木の得意とするところである。
「ほう…大木の考え方は面白いな。」
神陽が、独特の思考法を興味を持つ。
――続いて江藤新平である。
「この法典の趣旨は“民の安寧”ではございませぬか!」
江藤が古代中国の法典について、神陽からの質問を返す。
「いや、江藤よ。その答えには、お主の“想い”が入り過ぎておる。」
神陽は、書物の内容ではなく自身の理想を語ってしまっている、江藤の回答を否定した。
「先ほど、大木が語った前提を、もっと活かさねばならぬ。」
神陽の声は“鐘が鳴る”ように重厚に響いた。
「しかしながら、神陽先生!」
江藤も切り返していく。その声も“電流が走る”ような鋭さである。
――言うなれば神陽の“音響”と、江藤の“電撃”の競演。2人の間で「ゴォーン」と「ビリビリ」が繰り返される。

除夜の鐘も近い年の暮れになっていた。冬の底冷えする空気も熱するような、激しい師弟のやり取りを凝視している、他藩からの見学者がいた。
藩校の案内役が声をかける。
「吉田どの!“さがんもん”(佐賀の者)は声が大きいのだ。あまりお気になさるな。」
「いや…あの教師、“奇男子”だ!」
吉田という男、まだ20歳程度の若者である。教育者・神陽の傑出ぶりに打ち震えた。
――「“奇”という言葉を、またとない優れたもの」と扱うこの人物。
察しの良い方はお気づきかもしれない。長州藩士である。
九州諸国を回る長旅で、体調はボロボロだったようだが、佐賀の藩校を見学に来た。当時280人の寄宿生がいる「弘道館」。その活況を一目見ておきたかったようだ。
この藩校の見学者、7年後に長州(山口県)にある私塾“松下村塾”を引き継ぐことになる。長州藩の吉田寅次郎。後の吉田松陰である。
――その“吉田どの”は、すぐに友人に手紙を書き送った。
「佐賀の枝吉神陽。実は私も良く知らないのだが“奇男子”である。九州に行く機会があれば、必ず会っておくべきだ!」
(続く)
藩校「弘道館」で教鞭をとる枝吉神陽。白熱する佐賀の教育現場を見に来た、幕末の有名人(になる人)が感銘を受けます。
――佐賀城本丸。殿・鍋島直正と、藩校の責任者・鍋島安房が会議中である。
安房から「義祭同盟」の状況について、報告を受ける直正。
「枝吉神陽、若い者たちを引き付ける力が、秀でておるな。」
直正もよく藩校を見ている。
「神陽の学問は、常に“いかに用いるか”を見据えておるようです。」
安房は、いわば“校長先生”であり、カリキュラムもある程度は把握している。

――凄まじい暗記力、そして知識を応用する力を持つ神陽。
「神陽…、“蘭学”も学んでくれんかのう。」
天才・枝吉神陽の能力を、佐賀の科学技術にも転用できないか考える直正。
「殿、それはさすがに難しいかと。」
安房がやや顔をしかめる。今のままの神陽がお気に入りのようだ。
後に、直正が待望する“万能の研究主任”の役割は、佐野常民が担う。この頃は、医術の修業のため各地を回っていた。佐賀にはいなかったのである。
――話を戻そう。神陽は“尊王”の志が高い国学者だが、知識は“考える材料”という柔軟さも持っていた。
神陽はとにかく学生たちに考えさせる。
「古典で語られる、聖人がなにゆえ“偉大”なのかを考えることだ!」
神陽は学ぶ目的を考えさせ、どう実践するかも考えさせた。
――こうして神陽のもとには“暗記”では物足らない“考える学生”が集まったのである。
「古の世に、我が身を置いたつもりで考えました。」
大木幡六(喬任)である。“思考実験(シミュレーション)”は、大木の得意とするところである。
「ほう…大木の考え方は面白いな。」
神陽が、独特の思考法を興味を持つ。
――続いて江藤新平である。
「この法典の趣旨は“民の安寧”ではございませぬか!」
江藤が古代中国の法典について、神陽からの質問を返す。
「いや、江藤よ。その答えには、お主の“想い”が入り過ぎておる。」
神陽は、書物の内容ではなく自身の理想を語ってしまっている、江藤の回答を否定した。
「先ほど、大木が語った前提を、もっと活かさねばならぬ。」
神陽の声は“鐘が鳴る”ように重厚に響いた。
「しかしながら、神陽先生!」
江藤も切り返していく。その声も“電流が走る”ような鋭さである。
――言うなれば神陽の“音響”と、江藤の“電撃”の競演。2人の間で「ゴォーン」と「ビリビリ」が繰り返される。

除夜の鐘も近い年の暮れになっていた。冬の底冷えする空気も熱するような、激しい師弟のやり取りを凝視している、他藩からの見学者がいた。
藩校の案内役が声をかける。
「吉田どの!“さがんもん”(佐賀の者)は声が大きいのだ。あまりお気になさるな。」
「いや…あの教師、“奇男子”だ!」
吉田という男、まだ20歳程度の若者である。教育者・神陽の傑出ぶりに打ち震えた。
――「“奇”という言葉を、またとない優れたもの」と扱うこの人物。
察しの良い方はお気づきかもしれない。長州藩士である。
九州諸国を回る長旅で、体調はボロボロだったようだが、佐賀の藩校を見学に来た。当時280人の寄宿生がいる「弘道館」。その活況を一目見ておきたかったようだ。
この藩校の見学者、7年後に長州(山口県)にある私塾“松下村塾”を引き継ぐことになる。長州藩の吉田寅次郎。後の吉田松陰である。
――その“吉田どの”は、すぐに友人に手紙を書き送った。
「佐賀の枝吉神陽。実は私も良く知らないのだが“奇男子”である。九州に行く機会があれば、必ず会っておくべきだ!」
(続く)
2020年03月28日
第7話「尊王義祭」⑦
こんばんは。
“佐賀の七賢人”の中でも全国区の知名度を持つ2人、江藤新平と大隈重信(八太郎)。「私の見たい大河ドラマ」のイメージでは、こんな場面で出会います。「母の愛」が賢人たちを繋げ、新時代を築いた…というとオーバーでしょうか。
――例の3人組(大木喬任、江藤新平、中野方蔵)が大隈家に乗り込む当日。
「大木さん、いきなり突入して良いのか。」
中野が大木につられて、物騒な言い方をする。
「構わん、仔細は…わが母上から伝わっておるはずだ。」
重ねて言う。これは“殴り込み”ではない。
母方の親戚筋である大木が友達を連れて、大隈家を訪問するのだ。
「私も行ってよかですかね。」
江藤が、あらためて大木に確認する。
平家の傍流として、血筋には誇りを持つ江藤だが、現在の家格は低い。一方、大隈家は、三百石の上級武士と言ってよい家柄である。
「無論だ!」
大木は口下手である。
年少の八太郎くんと面識はあるが、話が弾んだ記憶はない。
しかし、大木にとって大隈家訪問は、母・シカの頼みである。
年長者として、八太郎くんの為になる話をすべきだ。
――大木の“切り札”は2枚。「社交的な中野」と「弁の立つ江藤」である。

「御免!」
大隈家の玄関。
大木が、武骨な挨拶をする。
「あら、幡六くんとお友達ね。いらっしゃい。」
大隈の母・三井子である。
「お初にお目にかかります。大木さんの後輩で、中野と申します。」
ここで、爽やかな中野方蔵の登場である。
“尊王”の話でヒートアップしない限りは、コミュニケーション能力は高い。
「同じく江藤と申す。以後、お見知りおきを!」
やはり身なりは粗末、髪はバサバサのいつもの江藤である。
「江藤くん!少々、声が鋭いぞ…」
中野が、江藤をヒジで小突き、小声で注意した。
――大隈三井子は“女丈夫”とも言われた元気な女性である。
「まぁまぁ玄関先で立っていないで、こちらにお入りなさい。」
三井子は、先輩たちの来訪を歓迎する。
父・信保を失い、気落ちする八太郎に何か良い話をしてやってほしいという想いもある。
「八太郎っ~!先輩方がお越しですよ。挨拶ばせんね~!」
――大隈八太郎(のちの大隈重信)13歳。
「先輩方、わざわざお越しいただき、ありがとうございます。」
いきなり3人も年長者が来訪したので、訝しがる八太郎。
「八太郎、久しいな。まず、お父上様にご挨拶をしよう。」
大木は親族らしく、亡くなった大隈の父・信保の仏前に手を合わせに行った。
――その後の展開について、大木の読みは概ね当たった。2枚の“切り札”のおかげで大木自身は、ほぼ話す必要がなかったのである。
中野方蔵が熱く語る。
「私は神陽先生が率いる“楠公”さまの祭典に是非加わりたい!」
大隈八太郎が呼応する。
「中野さん!この八太郎も幼き頃より“楠公”に憧れてまいりました!」
「八太郎くん!年少ながら分かっているな!」
ちなみに中野も14歳である。八太郎と1歳しか違わない。
その様子を見ていた江藤が、大木に注意を促す。
「また、中野が興奮して、机を割らんようにせんばならんです。」
――そこに大隈の母・三井子が菓子を持ってきた。

これには、江藤がすかさず反応した。
「こがん美味そうな物、いただいてもよかですか!」
三井子の持ってきた菓子は、砂糖の入った甘いものだった。
「ええ、どうぞ。召し上がってくださいな。」
実は大食家である江藤。
常にお腹が空いているのである。
「甘い…、“長崎”が眼前に広がるがごた…」
――佐賀を通る“長崎街道”には“シュガーロード”という異名がある。
この甘い“砂糖”こそ、幸せの味。
異国情緒あふれる長崎の味なのである。
大隈家の生活は、父・信保が亡くなり“役職給”が外れてからは厳しいものだったようだ。しかし、大隈三井子は、子・八太郎の友達に手料理や菓子を振る舞いとても大事にしたという。
こうして賢い先輩たちの話を聞くことで、大隈八太郎は成長していく。
(続く)
“佐賀の七賢人”の中でも全国区の知名度を持つ2人、江藤新平と大隈重信(八太郎)。「私の見たい大河ドラマ」のイメージでは、こんな場面で出会います。「母の愛」が賢人たちを繋げ、新時代を築いた…というとオーバーでしょうか。
――例の3人組(大木喬任、江藤新平、中野方蔵)が大隈家に乗り込む当日。
「大木さん、いきなり突入して良いのか。」
中野が大木につられて、物騒な言い方をする。
「構わん、仔細は…わが母上から伝わっておるはずだ。」
重ねて言う。これは“殴り込み”ではない。
母方の親戚筋である大木が友達を連れて、大隈家を訪問するのだ。
「私も行ってよかですかね。」
江藤が、あらためて大木に確認する。
平家の傍流として、血筋には誇りを持つ江藤だが、現在の家格は低い。一方、大隈家は、三百石の上級武士と言ってよい家柄である。
「無論だ!」
大木は口下手である。
年少の八太郎くんと面識はあるが、話が弾んだ記憶はない。
しかし、大木にとって大隈家訪問は、母・シカの頼みである。
年長者として、八太郎くんの為になる話をすべきだ。
――大木の“切り札”は2枚。「社交的な中野」と「弁の立つ江藤」である。

「御免!」
大隈家の玄関。
大木が、武骨な挨拶をする。
「あら、幡六くんとお友達ね。いらっしゃい。」
大隈の母・三井子である。
「お初にお目にかかります。大木さんの後輩で、中野と申します。」
ここで、爽やかな中野方蔵の登場である。
“尊王”の話でヒートアップしない限りは、コミュニケーション能力は高い。
「同じく江藤と申す。以後、お見知りおきを!」
やはり身なりは粗末、髪はバサバサのいつもの江藤である。
「江藤くん!少々、声が鋭いぞ…」
中野が、江藤をヒジで小突き、小声で注意した。
――大隈三井子は“女丈夫”とも言われた元気な女性である。
「まぁまぁ玄関先で立っていないで、こちらにお入りなさい。」
三井子は、先輩たちの来訪を歓迎する。
父・信保を失い、気落ちする八太郎に何か良い話をしてやってほしいという想いもある。
「八太郎っ~!先輩方がお越しですよ。挨拶ばせんね~!」
――大隈八太郎(のちの大隈重信)13歳。
「先輩方、わざわざお越しいただき、ありがとうございます。」
いきなり3人も年長者が来訪したので、訝しがる八太郎。
「八太郎、久しいな。まず、お父上様にご挨拶をしよう。」
大木は親族らしく、亡くなった大隈の父・信保の仏前に手を合わせに行った。
――その後の展開について、大木の読みは概ね当たった。2枚の“切り札”のおかげで大木自身は、ほぼ話す必要がなかったのである。
中野方蔵が熱く語る。
「私は神陽先生が率いる“楠公”さまの祭典に是非加わりたい!」
大隈八太郎が呼応する。
「中野さん!この八太郎も幼き頃より“楠公”に憧れてまいりました!」
「八太郎くん!年少ながら分かっているな!」
ちなみに中野も14歳である。八太郎と1歳しか違わない。
その様子を見ていた江藤が、大木に注意を促す。
「また、中野が興奮して、机を割らんようにせんばならんです。」
――そこに大隈の母・三井子が菓子を持ってきた。

これには、江藤がすかさず反応した。
「こがん美味そうな物、いただいてもよかですか!」
三井子の持ってきた菓子は、砂糖の入った甘いものだった。
「ええ、どうぞ。召し上がってくださいな。」
実は大食家である江藤。
常にお腹が空いているのである。
「甘い…、“長崎”が眼前に広がるがごた…」
――佐賀を通る“長崎街道”には“シュガーロード”という異名がある。
この甘い“砂糖”こそ、幸せの味。
異国情緒あふれる長崎の味なのである。
大隈家の生活は、父・信保が亡くなり“役職給”が外れてからは厳しいものだったようだ。しかし、大隈三井子は、子・八太郎の友達に手料理や菓子を振る舞いとても大事にしたという。
こうして賢い先輩たちの話を聞くことで、大隈八太郎は成長していく。
(続く)
2020年03月27日
第7話「尊王義祭」⑥
こんばんは。
第6話「鉄製大砲」と第7話「義祭同盟」は、ほぼ同時期の話を展開しています。双方とも、1850年を軸に、その前後のお話とお考えください。第7話は、今のところ、大木喬任(幡六)、江藤新平、中野方蔵の3人を中心に話を展開しています。
――「義祭同盟」が結成されてから、しばらく後。
中野方蔵が興奮気味に語る。
「江藤くん!聞いたか!先日の“楠公”の祭典を!」
江藤が言葉を返す。
「あぁ、聞いた。神陽先生が音頭を取っておられるとな。」
江藤と中野。ここでは、江藤の方が冷静である。
中野は、コミュニケーション能力が高い分、人の影響も受けやすい。
その点、江藤は“空気を読まない”のだ。
――いまいち江藤の反応が良くないが、語りたい中野は続ける。
「次の祭典には参加したい!しかし、それがしは若輩者!末席に加えてもらえるか…」

中野はまだ14歳そこそこだが、時おり古風な話し方をする。
それが教師や先輩に受け入れられやすいから、という理由もあるようだ。
「中野、そこまで焦らずとも良いのでは。」
江藤、何やら興味のある書物を見ているらしく、やや上の空である。
「尊王の志を立てるため、今、動きたいのだ!」
両手でドンと机を叩き、立ち上がる中野。
――ビキッ!!
使い古した机だったのか、中野の“打撃”でヒビが入った。
「あ~!!」
「中野。器物(きぶつ)を損壊(そんかい)せり…」
どうやら江藤が読んでいたのは、法律の書物であったようだ。
「さて、どう始末をつけようか。」
江藤は、貧乏なせいもあったが、全く格好を気にしないので、衣服ボロボロ、髪はバサバサ。でも“からたち小路”の女中たちの反応を見る限り、“よか男”ではあるらしい。
――そこに、2人よりちょっと年長者・大木が登場する。
「おう、事の顛末(てんまつ)は聞こえてるぞ。」
「机だが、俺が腰かけて割ってしまったことにしよう。」
無口な大木だが、言葉を続けた。
「大木さん!」
「代わりといっては何だが、相談がある。」
「やはり。そうなりますよね。」
中野は、この展開を読んでいた。
――佐賀藩の“砲術長”であった、大隈信保が亡くなったのは、この頃である。「義祭同盟」結成の翌月(1850年6月)だった。
大木の母であるシカは、大隈の母・三井子の親族であった。

大隈家の法事に出向く、大木シカ。
シカは、大隈三井子の手をしっかり握った。
そして、何か念を込めるように、三井子の目を見つめる。
「シカさん…、頑張れ!ってことね。」
大隈の母・三井子はシカの想いを理解した。
大木の父も早くに亡くなっているため、もう6年ほど大木は“母子家庭”で育っている。
大木が無口なのは、母・シカに似たのかは定かではない。
「…何かあったら、うちの子にも手伝わせるから。」
――大隈三井子、その瞬間、夫・信保が亡くなって曇っていた“教育ママ”の心を取り戻した。
「そういえば幡六くん、賢いらしいじゃない!うちの八太郎にも勉強を教えてもらえんね!?」
三井子、急に表情が明るくなる。
「幡六に言ってみる…。」
こうして大木シカは子の幡六(大木喬任)に、大隈家を訪ねるよう伝えたのだった。
――場面は、藩校「弘道館」の片隅の3人組(大木、江藤、中野)に戻る。
「…と、そういうわけだ。」
大木は、一部始終を語り終えた。
「一緒に来い…という理解でよろしいか。」
中野は瞬時に察した。
「えっ…私もですか!?」
江藤は察していなかった。
「決行は明後日、大隈の家に乗り込む。八太郎という子がおるので、皆で相手をしてやろう。」
大木の言い方は、何だか“殴り込み”に行くようで物騒だ。
何にせよ“佐賀の七賢人”がじわじわと繋がっていくのである。
(続く)
第6話「鉄製大砲」と第7話「義祭同盟」は、ほぼ同時期の話を展開しています。双方とも、1850年を軸に、その前後のお話とお考えください。第7話は、今のところ、大木喬任(幡六)、江藤新平、中野方蔵の3人を中心に話を展開しています。
――「義祭同盟」が結成されてから、しばらく後。
中野方蔵が興奮気味に語る。
「江藤くん!聞いたか!先日の“楠公”の祭典を!」
江藤が言葉を返す。
「あぁ、聞いた。神陽先生が音頭を取っておられるとな。」
江藤と中野。ここでは、江藤の方が冷静である。
中野は、コミュニケーション能力が高い分、人の影響も受けやすい。
その点、江藤は“空気を読まない”のだ。
――いまいち江藤の反応が良くないが、語りたい中野は続ける。
「次の祭典には参加したい!しかし、それがしは若輩者!末席に加えてもらえるか…」

中野はまだ14歳そこそこだが、時おり古風な話し方をする。
それが教師や先輩に受け入れられやすいから、という理由もあるようだ。
「中野、そこまで焦らずとも良いのでは。」
江藤、何やら興味のある書物を見ているらしく、やや上の空である。
「尊王の志を立てるため、今、動きたいのだ!」
両手でドンと机を叩き、立ち上がる中野。
――ビキッ!!
使い古した机だったのか、中野の“打撃”でヒビが入った。
「あ~!!」
「中野。器物(きぶつ)を損壊(そんかい)せり…」
どうやら江藤が読んでいたのは、法律の書物であったようだ。
「さて、どう始末をつけようか。」
江藤は、貧乏なせいもあったが、全く格好を気にしないので、衣服ボロボロ、髪はバサバサ。でも“からたち小路”の女中たちの反応を見る限り、“よか男”ではあるらしい。
――そこに、2人よりちょっと年長者・大木が登場する。
「おう、事の顛末(てんまつ)は聞こえてるぞ。」
「机だが、俺が腰かけて割ってしまったことにしよう。」
無口な大木だが、言葉を続けた。
「大木さん!」
「代わりといっては何だが、相談がある。」
「やはり。そうなりますよね。」
中野は、この展開を読んでいた。
――佐賀藩の“砲術長”であった、大隈信保が亡くなったのは、この頃である。「義祭同盟」結成の翌月(1850年6月)だった。
大木の母であるシカは、大隈の母・三井子の親族であった。

大隈家の法事に出向く、大木シカ。
シカは、大隈三井子の手をしっかり握った。
そして、何か念を込めるように、三井子の目を見つめる。
「シカさん…、頑張れ!ってことね。」
大隈の母・三井子はシカの想いを理解した。
大木の父も早くに亡くなっているため、もう6年ほど大木は“母子家庭”で育っている。
大木が無口なのは、母・シカに似たのかは定かではない。
「…何かあったら、うちの子にも手伝わせるから。」
――大隈三井子、その瞬間、夫・信保が亡くなって曇っていた“教育ママ”の心を取り戻した。
「そういえば幡六くん、賢いらしいじゃない!うちの八太郎にも勉強を教えてもらえんね!?」
三井子、急に表情が明るくなる。
「幡六に言ってみる…。」
こうして大木シカは子の幡六(大木喬任)に、大隈家を訪ねるよう伝えたのだった。
――場面は、藩校「弘道館」の片隅の3人組(大木、江藤、中野)に戻る。
「…と、そういうわけだ。」
大木は、一部始終を語り終えた。
「一緒に来い…という理解でよろしいか。」
中野は瞬時に察した。
「えっ…私もですか!?」
江藤は察していなかった。
「決行は明後日、大隈の家に乗り込む。八太郎という子がおるので、皆で相手をしてやろう。」
大木の言い方は、何だか“殴り込み”に行くようで物騒だ。
何にせよ“佐賀の七賢人”がじわじわと繋がっていくのである。
(続く)
2020年03月26日
第7話「尊王義祭」⑤
こんばんは。
前回の続きです。のちに鍋島安房を始め、藩の重役たちも参加していく「義祭同盟」ですが、スタートはわりと地味だったようです。
――五月。初夏の陽射しの中。
南北朝時代。南朝の後醍醐天皇に忠義を尽くした楠木正成。そのまっすぐな生き様を讃えるべく、集う者たち。
進行役は枝吉神陽。ただでさえ四方に広がっていく声を、さらに張る。
「皆様、本日のご参集、まことに忝(かたじけな)く存じます。」
そして、祭典の趣旨を語る神陽。
「我々も佐賀の先人を見習い“楠公”の“尊王”の志を大事に受け継ぎたいものであります。」
「義祭同盟」では、楠木正成と子・正行の父子を顕彰した。
楠木正成の没後も“小楠公”と呼ばれる子・正行は、父の遺志を継ぎ、南朝方で戦い続けた。正行もまた“楠公”の名に恥じない才を発揮したが、最後は河内国(大阪府)で“四條畷の戦い”に散った。
――「義祭同盟」最初の祭典は、滞りなく終了した。

その後は祭典に参加したメンバーで、様々な議論が交わされる。実は「義祭同盟」の活動は、祭典そのものではなく、後の“無礼講”が中心なのである。
結成に参加したのは38人と言われる。
島義勇や、枝吉次郎(後の副島種臣)も初期メンバーの1人だった。
――そんな枝吉次郎の横に、“団にょん”こと島義勇(団右衛門)が様子伺いに来る。
島が6歳年下の従兄弟、次郎に話しかける。
「すっかり立派になったな!」
「“団にょん”さん!お久しゅうございます。」
まだ藩校の学生・次郎(副島)が、今は佐賀藩の役人である“社会人”島義勇に挨拶する。
「藩校では“首班”として頑張っておると聞いたぞ!」
島が続ける。親戚の兄さんからの近況伺いと思ってほしい。
「後輩たちに、なかなか面白い者たちがおりますよ。」
藩校の“首班”とは、学生寮の“自治会長”と考えておこう。人望のある次郎のもとには、自然と校内の情報が集まってきた。
――面白い者たちとは、大木喬任・江藤新平・中野方蔵の3人組のことであった。
「とくに江藤と申す者。変わった物の見方をいたします。」
次郎(副島)は、中野方蔵の勧めで、江藤と話してみたようだ。
「どのように変わっとるんじゃ。」
島が、次郎の話に興味を持つ。
「何処で学んだのか、これからは“北方の開拓”であると語るのです。」
次郎は、少し不思議そうに言葉を発した。
「北方か…。たしかにそうじゃな!」
島は、遠く北の空を見遣った。
――同じ頃、藩校「弘道館」。例の3人が自習をしている。
「ぶぇっくしょい!」
江藤がくしゃみをする。バサバサの髪型なので、頭が揺れると髪も揺れる。
「どうした、江藤。夏風邪でも引いたか。」
大木が年長者らしい言葉をかける。
「誰かが江藤くんの噂でもしているのでしょう。」
江藤の評判をバラまいている、張本人・中野が事もなげに言った。
(続く)
※副島種臣が、副島家に養子に入るのは30歳を過ぎてからのようです。名字の“枝吉”で呼ぶと神陽先生と区別がしづらいので、幼少期からの名“次郎”を中心に使用しています。
前回の続きです。のちに鍋島安房を始め、藩の重役たちも参加していく「義祭同盟」ですが、スタートはわりと地味だったようです。
――五月。初夏の陽射しの中。
南北朝時代。南朝の後醍醐天皇に忠義を尽くした楠木正成。そのまっすぐな生き様を讃えるべく、集う者たち。
進行役は枝吉神陽。ただでさえ四方に広がっていく声を、さらに張る。
「皆様、本日のご参集、まことに忝(かたじけな)く存じます。」
そして、祭典の趣旨を語る神陽。
「我々も佐賀の先人を見習い“楠公”の“尊王”の志を大事に受け継ぎたいものであります。」
「義祭同盟」では、楠木正成と子・正行の父子を顕彰した。
楠木正成の没後も“小楠公”と呼ばれる子・正行は、父の遺志を継ぎ、南朝方で戦い続けた。正行もまた“楠公”の名に恥じない才を発揮したが、最後は河内国(大阪府)で“四條畷の戦い”に散った。
――「義祭同盟」最初の祭典は、滞りなく終了した。

その後は祭典に参加したメンバーで、様々な議論が交わされる。実は「義祭同盟」の活動は、祭典そのものではなく、後の“無礼講”が中心なのである。
結成に参加したのは38人と言われる。
島義勇や、枝吉次郎(後の副島種臣)も初期メンバーの1人だった。
――そんな枝吉次郎の横に、“団にょん”こと島義勇(団右衛門)が様子伺いに来る。
島が6歳年下の従兄弟、次郎に話しかける。
「すっかり立派になったな!」
「“団にょん”さん!お久しゅうございます。」
まだ藩校の学生・次郎(副島)が、今は佐賀藩の役人である“社会人”島義勇に挨拶する。
「藩校では“首班”として頑張っておると聞いたぞ!」
島が続ける。親戚の兄さんからの近況伺いと思ってほしい。
「後輩たちに、なかなか面白い者たちがおりますよ。」
藩校の“首班”とは、学生寮の“自治会長”と考えておこう。人望のある次郎のもとには、自然と校内の情報が集まってきた。
――面白い者たちとは、大木喬任・江藤新平・中野方蔵の3人組のことであった。
「とくに江藤と申す者。変わった物の見方をいたします。」
次郎(副島)は、中野方蔵の勧めで、江藤と話してみたようだ。
「どのように変わっとるんじゃ。」
島が、次郎の話に興味を持つ。
「何処で学んだのか、これからは“北方の開拓”であると語るのです。」
次郎は、少し不思議そうに言葉を発した。
「北方か…。たしかにそうじゃな!」
島は、遠く北の空を見遣った。
――同じ頃、藩校「弘道館」。例の3人が自習をしている。
「ぶぇっくしょい!」
江藤がくしゃみをする。バサバサの髪型なので、頭が揺れると髪も揺れる。
「どうした、江藤。夏風邪でも引いたか。」
大木が年長者らしい言葉をかける。
「誰かが江藤くんの噂でもしているのでしょう。」
江藤の評判をバラまいている、張本人・中野が事もなげに言った。
(続く)
※副島種臣が、副島家に養子に入るのは30歳を過ぎてからのようです。名字の“枝吉”で呼ぶと神陽先生と区別がしづらいので、幼少期からの名“次郎”を中心に使用しています。
2020年03月24日
第7話「尊王義祭」④
こんばんは。
佐賀の“県の木”はクスノキですね。南北朝時代に軍神と呼ばれた楠木正成。佐賀では古くから敬愛されていた武将だったようです。
前回で枝吉神陽が発見した木像は、江戸時代前期(1663年)に佐賀藩士・深江信渓が作らせたものです。
この“楠公さま”父子の木像が、幕末の佐賀を動かしていきます。
――藩校「弘道館」にて枝吉神陽が、鍋島安房に相談を持ち掛けている。
鍋島安房は佐賀藩の請役(藩政ナンバー2)であり、藩校の責任者でもあった。いわば“校長先生”に直談判をする“国学”の先生・枝吉神陽。
「私は、佐賀の先人から伝えられた“宝物”を見つけました。」
神陽の声は“鐘が鳴る”ようだと評される。聞く者を引き付ける、音色を持って重厚に響く声。
――鍋島安房も、神陽が語る「宝物」に興味を示す。
枝吉神陽は、藩校「弘道館」で、江戸での修業で磨きをかけた“国学”を教授している。とくに“賢い学生”には大人気であることを、安房は熟知していた。
「我らの先達の“宝”があるのか。」
安房はじっくり話を聴こうとする。
「安房様。実は“楠公さま”の像を見つけたのです。」
「おおっ!」
――南北朝時代の物語「太平記」で活躍する楠木正成。

神陽は見つけた木像について説明を続ける。
「“大楠公”と“小楠公”の『桜井の別れ』を表しております。」
「その像は、儂もぜひ見たい!そして“楠公”を祀るなら助力をいたすぞ。」
鍋島安房も、“楠木正成”ファンの様子である。
――なお、楠木正成が、子・正行に別れを告げる『桜井の別れ』は「太平記」の名場面である。
本編では大隈八太郎が、この場面を母から読み聞かせられて、母子2人で号泣している。
そして神陽は、木像の発見を機に「楠木正成父子を讃える集い」の開催を申し出た。
――こうして佐賀の尊王運動の中心「義祭同盟」は、実にあっさりと藩のナンバー2・鍋島安房の内諾を得た。
殿・鍋島直正が、“義祭同盟”について、安房から報告を受ける。
「安房よ。楠公を祀るのは構わんが、目を離さぬようにな。」
「ははっ、心得ました。」
直正は、言葉を続ける。
「そして、見込みのある者があれば、余に申し伝えよ」
「ははっ、抜かりなく。」
――早足で藩校「弘道館」に向かう鍋島安房。やや楽しくなってきたように見受けられる。
直正は、少々、心配そうにつぶやく。
「安房は、人が良いところがあるからのぅ。それに“楠公”びいきであるゆえ…」
――そこに“武雄のご隠居”、鍋島茂義が久しぶりに現れた。その巌のような存在感は衰えていない。

「殿、見込みがある者には、蘭学を学ばせる!とはお伝えいただいたか。」
茂義も50代となったが、相変わらずの“蘭癖”(西洋かぶれ)である。
「いかん、茂義どの!そこまでは言っておらぬぞ。」
「殿っ!そこが大事なところでござるぞ!」
この頃、鍋島茂義は蒸気機関の開発のため、目立たぬように人材集めを進めていた。
「相済まぬ。次は気を付ける!」
小さい頃から遊んでもらっていた“蘭学兄貴”には、なかなか頭が上がらない直正だった。
(続く)
佐賀の“県の木”はクスノキですね。南北朝時代に軍神と呼ばれた楠木正成。佐賀では古くから敬愛されていた武将だったようです。
前回で枝吉神陽が発見した木像は、江戸時代前期(1663年)に佐賀藩士・深江信渓が作らせたものです。
この“楠公さま”父子の木像が、幕末の佐賀を動かしていきます。
――藩校「弘道館」にて枝吉神陽が、鍋島安房に相談を持ち掛けている。
鍋島安房は佐賀藩の請役(藩政ナンバー2)であり、藩校の責任者でもあった。いわば“校長先生”に直談判をする“国学”の先生・枝吉神陽。
「私は、佐賀の先人から伝えられた“宝物”を見つけました。」
神陽の声は“鐘が鳴る”ようだと評される。聞く者を引き付ける、音色を持って重厚に響く声。
――鍋島安房も、神陽が語る「宝物」に興味を示す。
枝吉神陽は、藩校「弘道館」で、江戸での修業で磨きをかけた“国学”を教授している。とくに“賢い学生”には大人気であることを、安房は熟知していた。
「我らの先達の“宝”があるのか。」
安房はじっくり話を聴こうとする。
「安房様。実は“楠公さま”の像を見つけたのです。」
「おおっ!」
――南北朝時代の物語「太平記」で活躍する楠木正成。
神陽は見つけた木像について説明を続ける。
「“大楠公”と“小楠公”の『桜井の別れ』を表しております。」
「その像は、儂もぜひ見たい!そして“楠公”を祀るなら助力をいたすぞ。」
鍋島安房も、“楠木正成”ファンの様子である。
――なお、楠木正成が、子・正行に別れを告げる『桜井の別れ』は「太平記」の名場面である。
本編では大隈八太郎が、この場面を母から読み聞かせられて、母子2人で号泣している。
そして神陽は、木像の発見を機に「楠木正成父子を讃える集い」の開催を申し出た。
――こうして佐賀の尊王運動の中心「義祭同盟」は、実にあっさりと藩のナンバー2・鍋島安房の内諾を得た。
殿・鍋島直正が、“義祭同盟”について、安房から報告を受ける。
「安房よ。楠公を祀るのは構わんが、目を離さぬようにな。」
「ははっ、心得ました。」
直正は、言葉を続ける。
「そして、見込みのある者があれば、余に申し伝えよ」
「ははっ、抜かりなく。」
――早足で藩校「弘道館」に向かう鍋島安房。やや楽しくなってきたように見受けられる。
直正は、少々、心配そうにつぶやく。
「安房は、人が良いところがあるからのぅ。それに“楠公”びいきであるゆえ…」
――そこに“武雄のご隠居”、鍋島茂義が久しぶりに現れた。その巌のような存在感は衰えていない。

「殿、見込みがある者には、蘭学を学ばせる!とはお伝えいただいたか。」
茂義も50代となったが、相変わらずの“蘭癖”(西洋かぶれ)である。
「いかん、茂義どの!そこまでは言っておらぬぞ。」
「殿っ!そこが大事なところでござるぞ!」
この頃、鍋島茂義は蒸気機関の開発のため、目立たぬように人材集めを進めていた。
「相済まぬ。次は気を付ける!」
小さい頃から遊んでもらっていた“蘭学兄貴”には、なかなか頭が上がらない直正だった。
(続く)
2020年03月23日
第7話「尊王義祭」③
こんばんは。
江藤、大木に続いて、凄く久しぶりに、枝吉次郎(のちの副島種臣)が登場します。以前の登場では、カリスマのある兄・枝吉神陽と自身を比べて、迷っている姿を描きました。
当時の次郎は、なるべく優等生に見られるよう「周囲に受けの良い」学問をしていました。
そこで兄・神陽に一喝され、地道に勉強した結果、次郎は藩校で寮生を束ねる首班(リーダー)を務めています。
――枝吉次郎(副島種臣)は、藩校「弘道館」で人望を集める“良き先輩”である。
中野方蔵が次郎を見かけて、声をかける。
「枝吉(次郎)先輩、お話してもよろしいでしょうか。」
「おお、中野くんか。何か用かね。」
すっかり落ち着いた枝吉次郎。年齢は21歳である。
「それがし、面白き友を得ました。」
ここで中野は、最近知り合った江藤の話をした。
小城郡からの転入のため、江藤は「弘道館」の初等過程には通っていないのだ。
「そんなに面白いのか。」
「はい、とても奇抜で…優れた男です。」
年少ながらも行動力のある中野。次々に人を繋いでいく才能があった。
――その頃、藩校の片隅で江藤胤雄(新平)は考え事をしていた。

当人の頭の中は、超高速で回転をしている。こんな風に。
「日本の沿海で異国船が、不穏な動きをしているようだ。」
「だが、戦となれば敵わないだろう。尊王の志を果たそうにも、まず異国の業(技術)を取り入れねば…」
…が、傍目にはボーッとしているように見えた。
「おう、江藤。また考え事をしておったか。」
「大木さんにだけは、言われたくなかです。」
――大木幡六(喬任)が、すぐ横に来ていた。
大木もよく考え事をする。彼の場合は、もっと変わっている。
「俺が…古代中国、宋の国にいたとする。」
「そこで、高官の地位にいる俺は、政敵が罪人として引っ張られて来たところに出くわす。」
「しかし、その政敵が無実であることを、俺は知っているとする。」
「さぁ、どうする俺。真実を告げて政敵を救うか、あえて見過ごし邪魔者を排するのか!」
…大木の得意は“漢学”。ある意味、江藤よりぶっ飛んだ空想をしている。
“漢学”の歴史的背景を利用し、いわばデーターに基づくシミュレーションとして能力を磨くのが、大木流の鍛錬である。
――江藤、大木。“考え事”の2人組の前に、中野方蔵が現れる。
「大木さん、江藤くん、お揃いござるな。」
「おう、中野。来ていたのか。」
大木が応じる。大木は17歳、中野は14歳なのだが、あまり気にしている様子はない。
「先ほど、枝吉(次郎)先輩とお話しして参りました。」
中野が2人に話す。
「あの、神陽先生のご舎弟、次郎先輩か!」
江藤が反応する。
――枝吉次郎(副島種臣)も頑張っているのだが、いつも“神陽先生の弟”扱い。
兄貴がカリスマ過ぎると不憫である。
今は藩校「弘道館」でも教授を務める神陽。この日は佐賀城下の梅林庵という寺にいた。

「ご住職!これは、凄い宝物でござるぞ!」
枝吉神陽が、ただならぬ気配で言葉を発する。
神陽は、その木像を前に一礼し、少し後ろに下がって威儀を正す。そして、ビシッと背筋を正し、深々と座礼を行った。
「確かに古い物ではございますが…」
住職は、神陽の仰々しい態度を訝しがっている。
神陽が見つけた木像。
江戸時代初期に、ある佐賀藩士が作ったものである。
そこには、武将の父子の姿。
南北朝時代に、最後の戦いに向かう楠木正成と、子・正行の別れを描いた木像だった。
(続く)
江藤、大木に続いて、凄く久しぶりに、枝吉次郎(のちの副島種臣)が登場します。以前の登場では、カリスマのある兄・枝吉神陽と自身を比べて、迷っている姿を描きました。
当時の次郎は、なるべく優等生に見られるよう「周囲に受けの良い」学問をしていました。
そこで兄・神陽に一喝され、地道に勉強した結果、次郎は藩校で寮生を束ねる首班(リーダー)を務めています。
――枝吉次郎(副島種臣)は、藩校「弘道館」で人望を集める“良き先輩”である。
中野方蔵が次郎を見かけて、声をかける。
「枝吉(次郎)先輩、お話してもよろしいでしょうか。」
「おお、中野くんか。何か用かね。」
すっかり落ち着いた枝吉次郎。年齢は21歳である。
「それがし、面白き友を得ました。」
ここで中野は、最近知り合った江藤の話をした。
小城郡からの転入のため、江藤は「弘道館」の初等過程には通っていないのだ。
「そんなに面白いのか。」
「はい、とても奇抜で…優れた男です。」
年少ながらも行動力のある中野。次々に人を繋いでいく才能があった。
――その頃、藩校の片隅で江藤胤雄(新平)は考え事をしていた。

当人の頭の中は、超高速で回転をしている。こんな風に。
「日本の沿海で異国船が、不穏な動きをしているようだ。」
「だが、戦となれば敵わないだろう。尊王の志を果たそうにも、まず異国の業(技術)を取り入れねば…」
…が、傍目にはボーッとしているように見えた。
「おう、江藤。また考え事をしておったか。」
「大木さんにだけは、言われたくなかです。」
――大木幡六(喬任)が、すぐ横に来ていた。
大木もよく考え事をする。彼の場合は、もっと変わっている。
「俺が…古代中国、宋の国にいたとする。」
「そこで、高官の地位にいる俺は、政敵が罪人として引っ張られて来たところに出くわす。」
「しかし、その政敵が無実であることを、俺は知っているとする。」
「さぁ、どうする俺。真実を告げて政敵を救うか、あえて見過ごし邪魔者を排するのか!」
…大木の得意は“漢学”。ある意味、江藤よりぶっ飛んだ空想をしている。
“漢学”の歴史的背景を利用し、いわばデーターに基づくシミュレーションとして能力を磨くのが、大木流の鍛錬である。
――江藤、大木。“考え事”の2人組の前に、中野方蔵が現れる。
「大木さん、江藤くん、お揃いござるな。」
「おう、中野。来ていたのか。」
大木が応じる。大木は17歳、中野は14歳なのだが、あまり気にしている様子はない。
「先ほど、枝吉(次郎)先輩とお話しして参りました。」
中野が2人に話す。
「あの、神陽先生のご舎弟、次郎先輩か!」
江藤が反応する。
――枝吉次郎(副島種臣)も頑張っているのだが、いつも“神陽先生の弟”扱い。
兄貴がカリスマ過ぎると不憫である。
今は藩校「弘道館」でも教授を務める神陽。この日は佐賀城下の梅林庵という寺にいた。
「ご住職!これは、凄い宝物でござるぞ!」
枝吉神陽が、ただならぬ気配で言葉を発する。
神陽は、その木像を前に一礼し、少し後ろに下がって威儀を正す。そして、ビシッと背筋を正し、深々と座礼を行った。
「確かに古い物ではございますが…」
住職は、神陽の仰々しい態度を訝しがっている。
神陽が見つけた木像。
江戸時代初期に、ある佐賀藩士が作ったものである。
そこには、武将の父子の姿。
南北朝時代に、最後の戦いに向かう楠木正成と、子・正行の別れを描いた木像だった。
(続く)
2020年03月22日
第7話「尊王義祭」②
こんばんは。
前回、友人と剣術の稽古に励んでいた江藤新平(胤雄)ですが、今回も日常的なエピソードを描きます。
資料から着想を得ていますが、歴史上の事件に比べ、情報量が少ないです。「たぶん、こんな感じだったんじゃないか…」と想像力をはたらかせています。
――江藤たちの藩校「弘道館」での日々は続く。年の暮れが押し迫る頃。
「今日は、とりわけ冷えるな…」
江藤は、藩校で借り受けた本を持って佐賀城下を歩いていた。
いまは藩校での寄宿生活だが、年末は帰宅する。
いま、江藤の父・胤光は「貿易(かわりじな)方」という職務に就いている。但し、ほんの少し前までは、父が失職中だったので、江藤家の貧乏はまだ続いていた。
「帰ったら、母上の内職でも手伝うか…」
江藤の母・浅子は、祝い事に使う“水引”などを作って、子の学費の足しにしていた。
――こうして江藤の服装たるや、一目でわかる貧乏学生だった。
まもなく、江藤が、佐賀城下“からたち小路”に差し掛かろうとしている。
実は、この日には通るべきではない道だった。
「いや、参ったな…」
先に道を通った藩校の学生と思しき青年。戸惑っている様子だ。
何やら女性たちに担ぎ上げられたり、からかわれている。
昔の日本の地域社会には“ハレ(祭)”と“ケ(日常)”の日々の区別が強くあったとも言われる。この当日は、いわば“祭の日”。
当時の佐賀は、非常にわかりやすい“男性社会”である。
女性たちのフラストレーションの発散が認められた、例外的な“日と場所”があったようなのだ。今日は男子をからかい放題の無礼講…みたいな「謎の祭り」とでも考えてほしい。
――先ほどの藩校の学生は、そんな“祭の日”の罠にハマった1人である。

さて、江藤が同じ道(からたち小路)を行く。
リーダー格の女中が「また学生が来たから、一つからかってやろう」とばかりに動く。
「そこの書生さん!」
呼び止められた江藤。しばらく小城に住んでいたので、この辺りの風習にも疎く、状況は把握できていない。
「何用でござるか。」
江藤の声は、非常によく通る。声をかけた女中の方が、一瞬たじろぐ。しかも、内に秘めたエネルギーを感じさせる、まっすぐな目線。
女中さんは「あれっ、格好は粗末だけど、意外に“よか男”じゃないの」と、からかうのを躊躇した。
――こういう“空気を読む”のが、得意ではない江藤。
周囲の状況も不知のうえ、女性の感情の動きも読めていない。
江藤は「貧乏書生と侮られた」と判断した。
早々に退去することとし、歩みを進める。
その時、中国の古典思想である“孟子”の一節を、高唱し始めた。大声で読み上げる内容は、今のシチュエーションと何の関係もない。
「天の意志は、仁の心で行う、民の暮らしの安定である」という趣旨の言葉である。
江藤の声は、女中たちにビリビリと微細な電流を走らせるように響いた。
その後ろ姿を唖然と見つめながら、女中たちは口々に噂した。
「何だろう…あの子は?」
「不思議な子だったねぇ…」
――続いて“からたち小路”に、江藤の友人・中野方蔵が通りがかった。
中野も何気なく入り込んでしまったのだが、江藤とは対応が違った。
「あー、そんな行事があったか…」
まず、中野は“祭の日”のような、特別なシチュエーションであることを察した。
「ははは…、困った、困った~」
大きい声を出すのは江藤と同じだが、こちらは女中たちにからかわれてやることにした。中野も性格はマジメなのだが、少しユーモアがある。
中野が、担がれた状態から着地する。そして、ニコッと笑って言い放った。
「本年も、お勤めご苦労様です!では、お姉さま方も良いお年を!」
「感じのよか書生さんね。良いお年を!!」
女中たちも笑顔を返す。やたらコミュニケーション能力の高い中野。
この感じを“豪快な性格”と評する人もいるようだ。
そして、この友人・中野方蔵の存在が、江藤新平を次の舞台へと進めていく。
(続く)
前回、友人と剣術の稽古に励んでいた江藤新平(胤雄)ですが、今回も日常的なエピソードを描きます。
資料から着想を得ていますが、歴史上の事件に比べ、情報量が少ないです。「たぶん、こんな感じだったんじゃないか…」と想像力をはたらかせています。
――江藤たちの藩校「弘道館」での日々は続く。年の暮れが押し迫る頃。
「今日は、とりわけ冷えるな…」
江藤は、藩校で借り受けた本を持って佐賀城下を歩いていた。
いまは藩校での寄宿生活だが、年末は帰宅する。
いま、江藤の父・胤光は「貿易(かわりじな)方」という職務に就いている。但し、ほんの少し前までは、父が失職中だったので、江藤家の貧乏はまだ続いていた。
「帰ったら、母上の内職でも手伝うか…」
江藤の母・浅子は、祝い事に使う“水引”などを作って、子の学費の足しにしていた。
――こうして江藤の服装たるや、一目でわかる貧乏学生だった。
まもなく、江藤が、佐賀城下“からたち小路”に差し掛かろうとしている。
実は、この日には通るべきではない道だった。
「いや、参ったな…」
先に道を通った藩校の学生と思しき青年。戸惑っている様子だ。
何やら女性たちに担ぎ上げられたり、からかわれている。
昔の日本の地域社会には“ハレ(祭)”と“ケ(日常)”の日々の区別が強くあったとも言われる。この当日は、いわば“祭の日”。
当時の佐賀は、非常にわかりやすい“男性社会”である。
女性たちのフラストレーションの発散が認められた、例外的な“日と場所”があったようなのだ。今日は男子をからかい放題の無礼講…みたいな「謎の祭り」とでも考えてほしい。
――先ほどの藩校の学生は、そんな“祭の日”の罠にハマった1人である。

さて、江藤が同じ道(からたち小路)を行く。
リーダー格の女中が「また学生が来たから、一つからかってやろう」とばかりに動く。
「そこの書生さん!」
呼び止められた江藤。しばらく小城に住んでいたので、この辺りの風習にも疎く、状況は把握できていない。
「何用でござるか。」
江藤の声は、非常によく通る。声をかけた女中の方が、一瞬たじろぐ。しかも、内に秘めたエネルギーを感じさせる、まっすぐな目線。
女中さんは「あれっ、格好は粗末だけど、意外に“よか男”じゃないの」と、からかうのを躊躇した。
――こういう“空気を読む”のが、得意ではない江藤。
周囲の状況も不知のうえ、女性の感情の動きも読めていない。
江藤は「貧乏書生と侮られた」と判断した。
早々に退去することとし、歩みを進める。
その時、中国の古典思想である“孟子”の一節を、高唱し始めた。大声で読み上げる内容は、今のシチュエーションと何の関係もない。
「天の意志は、仁の心で行う、民の暮らしの安定である」という趣旨の言葉である。
江藤の声は、女中たちにビリビリと微細な電流を走らせるように響いた。
その後ろ姿を唖然と見つめながら、女中たちは口々に噂した。
「何だろう…あの子は?」
「不思議な子だったねぇ…」
――続いて“からたち小路”に、江藤の友人・中野方蔵が通りがかった。
中野も何気なく入り込んでしまったのだが、江藤とは対応が違った。
「あー、そんな行事があったか…」
まず、中野は“祭の日”のような、特別なシチュエーションであることを察した。
「ははは…、困った、困った~」
大きい声を出すのは江藤と同じだが、こちらは女中たちにからかわれてやることにした。中野も性格はマジメなのだが、少しユーモアがある。
中野が、担がれた状態から着地する。そして、ニコッと笑って言い放った。
「本年も、お勤めご苦労様です!では、お姉さま方も良いお年を!」
「感じのよか書生さんね。良いお年を!!」
女中たちも笑顔を返す。やたらコミュニケーション能力の高い中野。
この感じを“豪快な性格”と評する人もいるようだ。
そして、この友人・中野方蔵の存在が、江藤新平を次の舞台へと進めていく。
(続く)
2020年03月21日
第7話「尊王義祭」①
こんにちは。
今回から、第7話「尊王義祭」です。幕末の佐賀には「義祭同盟」という結社がありました。もとは「朝廷に忠義を尽くした楠木正成公を祀る」という集まりで、“尊王”についても活発な議論が行われました。
当時、最先端の国際都市・長崎に近い佐賀藩は、最初から西洋の学問を許容していて、“開明的”とも言える志士たちを輩出しています。
この頃の“佐賀の七賢人”の年齢構成ですが、過去の記事(「“主要な人物”をどう繋ぐか?」(関係性②))のラストに入れています。よろしければ、リンク先をご参考に。
――佐賀城・四十間堀の北詰、藩校「弘道館」にて。

大木幡六(喬任)が、2本の“竹刀”を持ってきた。
「“袋竹刀(ふくろじない)”借りてきたぞ。使え。」
大木はわりと無口なので、朴訥なしゃべり方をする。
「大木さん、助かる。」
江藤胤雄(新平)である。
弁舌の立つ江藤だが、寡黙な大木とは気が合うらしい。
2歳ほど大木が年上だが、一緒に行動することが増えてきた。
――“袋竹刀”は、割り竹を革袋で包んだ、剣術の稽古用具である。
当たれば、バシッと良い音がする。
もちろん体を打てば痛いが、竹刀よりはクッションが効いている。
江戸幕府の公式剣術でもある“柳生新陰流”で良く用いられる道具だ。
従来、佐賀藩では上級武士たちは、幕府公式の“新陰流”を学び、下級武士たちは“タイ捨流”など別の流派を学ぶことが多かったと聞く。
「では、早速始めましょう。大木さん!審判をお願いします。」
江藤の稽古相手だ。中野方蔵という少年が言葉を発する。
よく響く明るい声色に、人当たりの良い口調。コミュニケーション能力の高いタイプである。最近、江藤や大木と友達付き合いが始まった。
――この頃、佐賀藩は「文武課業法」という規則を導入すべく、準備を進めていた。
殿・鍋島直正は、常日頃から「余の家来はとにかく学ばねばならんのだ」と言う。
藩校のカリキュラムで一定の成績を修めなければ、藩の役職に付けない制度は、その言葉を実践する厳しいものだった。
佐賀藩士として、役職に付くには武術の修練にも励む必要があったのだ。
「中野、大丈夫か。江藤はかなり腕が立つぞ。」
大木は年長者として、稽古相手の中野を気にかけた。
「剣術に励むならば、強い方と稽古せねばならんとです。」
中野が応える。その答えに「真面目な奴だな…」と大木は思った。
――江藤と中野、そして大木の3人は剣術の自主練習をしているのだ。

藩校の空き地を使った野試合。足元は草むら、防具は無い。
「江藤くん、用意は良いですか!」
「いつでも良いぞ!」
江藤の返事を聞いた、大木が手短かに合図をする。
「では、始め!」
すぐに中野が仕掛ける。
「エエーィッ!」
――中野、普段の温厚な口ぶりからは、想像し難い気合を発する。
パァン!パン!…パァン!
中野の猛攻である。“袋竹刀”での打ち合い。
江藤は、正面からの打ち込みを二度、三度と打払う。
ザッ…ザザッ…
江藤が飛び下がって距離を取る。
古びた草履と、草の擦れる音がする。
「ィエエーィッ!」
「スキありっ!」
中野の打ち込みと同時に、江藤が懐に飛び込む。
――パァアアン!
両者の“袋竹刀”の打ち込みは重なった。
鍔迫り合いとなる。
…カタ・・・カタカタッ・・・
”袋竹刀”を通じた押し合いから、一瞬、距離が開いた。
「エエーィッ!」
ふたたび中野が打ち込もうとする瞬間、江藤も何か言葉を発した。
バシッ!!
斜め上方から、袈裟に打ちおろした江藤の剣先が当たる。
先ほどは、ご丁寧に「肩口を打つ!」と発声したらしい。
江藤が鋭く右に旋回したため、左面を狙っていた中野の剣は、ほぼ空を切ったようだ。
「勝負あり!江藤の勝ちだな。」
――大木は審判の役目を果たすと、こう続けた。
「そして、お主ら!もう少し静かに戦えんか…?」
いつの間にか、藩校の生徒たちが見物に集まっていた。試合中の掛け声が注目を集めてしまったようだ。
「とくに江藤!いつも戦う相手に話しかけておるな…」
「大木さん、これは癖なのだ。相済まぬ。」
論理的過ぎる江藤。掛け声までも、言語化されてしまうようだ。
(続く)
今回から、第7話「尊王義祭」です。幕末の佐賀には「義祭同盟」という結社がありました。もとは「朝廷に忠義を尽くした楠木正成公を祀る」という集まりで、“尊王”についても活発な議論が行われました。
当時、最先端の国際都市・長崎に近い佐賀藩は、最初から西洋の学問を許容していて、“開明的”とも言える志士たちを輩出しています。
この頃の“佐賀の七賢人”の年齢構成ですが、過去の記事(
――佐賀城・四十間堀の北詰、藩校「弘道館」にて。

大木幡六(喬任)が、2本の“竹刀”を持ってきた。
「“袋竹刀(ふくろじない)”借りてきたぞ。使え。」
大木はわりと無口なので、朴訥なしゃべり方をする。
「大木さん、助かる。」
江藤胤雄(新平)である。
弁舌の立つ江藤だが、寡黙な大木とは気が合うらしい。
2歳ほど大木が年上だが、一緒に行動することが増えてきた。
――“袋竹刀”は、割り竹を革袋で包んだ、剣術の稽古用具である。
当たれば、バシッと良い音がする。
もちろん体を打てば痛いが、竹刀よりはクッションが効いている。
江戸幕府の公式剣術でもある“柳生新陰流”で良く用いられる道具だ。
従来、佐賀藩では上級武士たちは、幕府公式の“新陰流”を学び、下級武士たちは“タイ捨流”など別の流派を学ぶことが多かったと聞く。
「では、早速始めましょう。大木さん!審判をお願いします。」
江藤の稽古相手だ。中野方蔵という少年が言葉を発する。
よく響く明るい声色に、人当たりの良い口調。コミュニケーション能力の高いタイプである。最近、江藤や大木と友達付き合いが始まった。
――この頃、佐賀藩は「文武課業法」という規則を導入すべく、準備を進めていた。
殿・鍋島直正は、常日頃から「余の家来はとにかく学ばねばならんのだ」と言う。
藩校のカリキュラムで一定の成績を修めなければ、藩の役職に付けない制度は、その言葉を実践する厳しいものだった。
佐賀藩士として、役職に付くには武術の修練にも励む必要があったのだ。
「中野、大丈夫か。江藤はかなり腕が立つぞ。」
大木は年長者として、稽古相手の中野を気にかけた。
「剣術に励むならば、強い方と稽古せねばならんとです。」
中野が応える。その答えに「真面目な奴だな…」と大木は思った。
――江藤と中野、そして大木の3人は剣術の自主練習をしているのだ。

藩校の空き地を使った野試合。足元は草むら、防具は無い。
「江藤くん、用意は良いですか!」
「いつでも良いぞ!」
江藤の返事を聞いた、大木が手短かに合図をする。
「では、始め!」
すぐに中野が仕掛ける。
「エエーィッ!」
――中野、普段の温厚な口ぶりからは、想像し難い気合を発する。
パァン!パン!…パァン!
中野の猛攻である。“袋竹刀”での打ち合い。
江藤は、正面からの打ち込みを二度、三度と打払う。
ザッ…ザザッ…
江藤が飛び下がって距離を取る。
古びた草履と、草の擦れる音がする。
「ィエエーィッ!」
「スキありっ!」
中野の打ち込みと同時に、江藤が懐に飛び込む。
――パァアアン!
両者の“袋竹刀”の打ち込みは重なった。
鍔迫り合いとなる。
…カタ・・・カタカタッ・・・
”袋竹刀”を通じた押し合いから、一瞬、距離が開いた。
「エエーィッ!」
ふたたび中野が打ち込もうとする瞬間、江藤も何か言葉を発した。
バシッ!!
斜め上方から、袈裟に打ちおろした江藤の剣先が当たる。
先ほどは、ご丁寧に「肩口を打つ!」と発声したらしい。
江藤が鋭く右に旋回したため、左面を狙っていた中野の剣は、ほぼ空を切ったようだ。
「勝負あり!江藤の勝ちだな。」
――大木は審判の役目を果たすと、こう続けた。
「そして、お主ら!もう少し静かに戦えんか…?」
いつの間にか、藩校の生徒たちが見物に集まっていた。試合中の掛け声が注目を集めてしまったようだ。
「とくに江藤!いつも戦う相手に話しかけておるな…」
「大木さん、これは癖なのだ。相済まぬ。」
論理的過ぎる江藤。掛け声までも、言語化されてしまうようだ。
(続く)
2020年03月20日
当ブログをお読みいただいている皆様へ
こんばんは。
「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」を書いております、SRです。
当ブログをお読みいただいている皆様、いつもありがとうございます。
今日は、本編から少し離れて、お話をしたいと思います。
第6話「鉄製大砲」いかがだったでしょうか。
当ブログでは、史実に着想を得た“フィクション”として物語を展開しています。
できれば年表どおりの展開に…と考えてきましたが、様々なエピソードが同時進行していますので、時折、数年くらい話が戻っていることがあります。
――それでも、なるべく年表どおりに描きたい理由があります。
例えば“本編”では、未だにペリーの黒船も来航していませんが、佐賀では鉄製大砲の鋳造が始まっています。
佐賀が近代化のトップランナーとして、日本を先導する立場だったことを強調したいのです。
なるべく史実に寄せたいのは、エピソードの年代と人物の設定。
どうしても想像力に偏るのは、人物の行動と関係性…という要素でしょうか。
――第6話を例にとると
大隈重信の父・信保が、“砲術長”の職務にあり、数字に強い人物であったことは、複数の資料より着想を得ました。
しかし、信保と「鋳立方の七人(御鋳立方七賢人)」が、どう関わったかは想像により描いています。
――そして、これから佐賀だけでなく、全国的にもファンが多い“江藤新平”が本格的に登場します。
当時、江藤新平の功績を抹消する意図だったと思われますが、現代まで続く卑劣な罠が仕掛けられています。
友人に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを書きたいと話すと、ドラマ化が「難しい理由」として一番に指摘された内容です。
私も調べを進める前に“ネット検索”により、大変なショックを受けたものです。
――とくに辛い画像に弱い方は“ネット検索”には注意してください。
逆にこれだけ酷い扱いを受けても、なお熱烈なファンが多くいる、江藤新平。
私の文章力で描けるかはさておき、よほど魅力的な人物と考えた方が良さそうです。
……私事ですが時折、ヘロヘロになって投稿しているときがあります。
今後とも暖かい目で見守っていただければ幸いです。
まだ、全47話中、第6話までしか書けていません。
さすがに“麒麟”の背中を追うのは、あきらめました。“青天を衝く”頃には完走できれば良いかなと思っています。
そのうちに「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」です。
「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」を書いております、SRです。
当ブログをお読みいただいている皆様、いつもありがとうございます。
今日は、本編から少し離れて、お話をしたいと思います。
第6話「鉄製大砲」いかがだったでしょうか。
当ブログでは、史実に着想を得た“フィクション”として物語を展開しています。
できれば年表どおりの展開に…と考えてきましたが、様々なエピソードが同時進行していますので、時折、数年くらい話が戻っていることがあります。
――それでも、なるべく年表どおりに描きたい理由があります。
例えば“本編”では、未だにペリーの黒船も来航していませんが、佐賀では鉄製大砲の鋳造が始まっています。
佐賀が近代化のトップランナーとして、日本を先導する立場だったことを強調したいのです。
なるべく史実に寄せたいのは、エピソードの年代と人物の設定。
どうしても想像力に偏るのは、人物の行動と関係性…という要素でしょうか。
――第6話を例にとると
大隈重信の父・信保が、“砲術長”の職務にあり、数字に強い人物であったことは、複数の資料より着想を得ました。
しかし、信保と「鋳立方の七人(御鋳立方七賢人)」が、どう関わったかは想像により描いています。
――そして、これから佐賀だけでなく、全国的にもファンが多い“江藤新平”が本格的に登場します。
当時、江藤新平の功績を抹消する意図だったと思われますが、現代まで続く卑劣な罠が仕掛けられています。
友人に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを書きたいと話すと、ドラマ化が「難しい理由」として一番に指摘された内容です。
私も調べを進める前に“ネット検索”により、大変なショックを受けたものです。
――とくに辛い画像に弱い方は“ネット検索”には注意してください。
逆にこれだけ酷い扱いを受けても、なお熱烈なファンが多くいる、江藤新平。
私の文章力で描けるかはさておき、よほど魅力的な人物と考えた方が良さそうです。
……私事ですが時折、ヘロヘロになって投稿しているときがあります。
今後とも暖かい目で見守っていただければ幸いです。
まだ、全47話中、第6話までしか書けていません。
さすがに“麒麟”の背中を追うのは、あきらめました。“青天を衝く”頃には完走できれば良いかなと思っています。
そのうちに「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」です。
2020年03月19日
第6話「鉄製大砲」⑩
こんばんは。
昨日の続きです。リーダーの本島藤太夫たち「鋳立方の七人」は苦闘を続けます。
――季節は巡り、春となっていた。鉄の溶解を進める。
鋳物師・谷口が率いる“鋳造チーム”が動く。
「皆!気を付けてかからんね!」
「おうっ!」
屈強な男たちが挑む“鋳立て”である。
ジュジュッ…ジューッ!!
改造した反射炉で銑鉄を溶かし、不純物を除く。グニャグニャとなった真っ赤な鉄。

それを鋳型により大砲の姿にしていく。
――そして、砲身を繰り抜くためには、水力が用いられた。
築地は佐賀城下の職人町の裏手にある。
近くの川を堰き止め、小規模なダムを構築して、水車を回した。
ガラン、ガラン…
即席のダムからの水力で“鉄の塊”の内側を削り続ける。
「杉谷さん、様子はどがんね?」
刀鍛冶・橋本が水車の近くまで様子を見に来た。
「良い具合です。馬場さんの計算は確かですから。」
翻訳担当の杉谷、七人の中で最も“西洋”に親しい人物である。
――桜の季節が去り、青葉が繁る頃。
ようやく試作の大砲一門が完成した。
さらに改良を重ね、砲術の部隊に試射を依頼する。
――固唾を呑んで見守る、「鋳立方の七人」
ドン!…ピキピキ、ビキッ!
異様な音を立てて、砲身は裂けた。
「ぎゃっ!」
安全を見越した配置にしていたはずが、ケガ人が出たのである。
――そして悲劇は続いた。
ドドーン…!
今度は、砲身が裂けたのではなく、爆発した。
とうとう砲術部隊に、殉職者が出てしまったのである。
「もう、お主らの造ったもんは、信じられんばい!」
砲術長が激怒している。この人物は、大隈信保の後任だった。
――どうしても砲身の強度は上がらず、大砲を試射に回せない。
本島は、技術書の編集担当で、サブリーダー格の田中を呼び寄せた。
「田中どの…話がある。」
その決意を聴いて、田中が諫める。
「本島さん!駄目だ!まだ、あきらめてはいかんぞ!」
リーダーとして、本島は製造の中止を進言すると決めた。
そして“切腹”により責任を取るつもりだった。
――佐賀城・本丸。本島は、殿・鍋島直正の面前にいた。

「殿、申し上げたき儀がございます!」
本島が声を張る。
「本島よ、かように大声を出さずとも聞こえておる。」
ゆっくりと本島の気負いを受け止める直正。
「大銃(大砲)の鋳立が成らず、申し訳ございません!」
やはり興奮気味に、殿に謝罪をする本島。
「つきましては…腹を切ってお詫びを…」
本島は“死”をもって償うと申し出た。
――鍋島直正、本島の言葉を受け止めると、背を向けて一呼吸おいた。
「死ぬことは許さん。生きて成し遂げよ。」
本島の気負った表情が崩れる。
「殿…しかし…」
直正は続けた。
「そなたらには、無茶を押し付けておる。すべて儂の責任だ。」
本島が涙を流した。
直正は少し表情を緩めて、本島に語りかける。
「重ねて申すぞ。命を絶つことは許さん!これは主命である。」
――このとき、1851年。日本が黒船来航の脅威に直面するまで、あと2年である。
(第7話「尊王義祭」に続く)
昨日の続きです。リーダーの本島藤太夫たち「鋳立方の七人」は苦闘を続けます。
――季節は巡り、春となっていた。鉄の溶解を進める。
鋳物師・谷口が率いる“鋳造チーム”が動く。
「皆!気を付けてかからんね!」
「おうっ!」
屈強な男たちが挑む“鋳立て”である。
ジュジュッ…ジューッ!!
改造した反射炉で銑鉄を溶かし、不純物を除く。グニャグニャとなった真っ赤な鉄。

それを鋳型により大砲の姿にしていく。
――そして、砲身を繰り抜くためには、水力が用いられた。
築地は佐賀城下の職人町の裏手にある。
近くの川を堰き止め、小規模なダムを構築して、水車を回した。
ガラン、ガラン…
即席のダムからの水力で“鉄の塊”の内側を削り続ける。
「杉谷さん、様子はどがんね?」
刀鍛冶・橋本が水車の近くまで様子を見に来た。
「良い具合です。馬場さんの計算は確かですから。」
翻訳担当の杉谷、七人の中で最も“西洋”に親しい人物である。
――桜の季節が去り、青葉が繁る頃。
ようやく試作の大砲一門が完成した。
さらに改良を重ね、砲術の部隊に試射を依頼する。
――固唾を呑んで見守る、「鋳立方の七人」
ドン!…ピキピキ、ビキッ!
異様な音を立てて、砲身は裂けた。
「ぎゃっ!」
安全を見越した配置にしていたはずが、ケガ人が出たのである。
――そして悲劇は続いた。
ドドーン…!
今度は、砲身が裂けたのではなく、爆発した。
とうとう砲術部隊に、殉職者が出てしまったのである。
「もう、お主らの造ったもんは、信じられんばい!」
砲術長が激怒している。この人物は、大隈信保の後任だった。
――どうしても砲身の強度は上がらず、大砲を試射に回せない。
本島は、技術書の編集担当で、サブリーダー格の田中を呼び寄せた。
「田中どの…話がある。」
その決意を聴いて、田中が諫める。
「本島さん!駄目だ!まだ、あきらめてはいかんぞ!」
リーダーとして、本島は製造の中止を進言すると決めた。
そして“切腹”により責任を取るつもりだった。
――佐賀城・本丸。本島は、殿・鍋島直正の面前にいた。

「殿、申し上げたき儀がございます!」
本島が声を張る。
「本島よ、かように大声を出さずとも聞こえておる。」
ゆっくりと本島の気負いを受け止める直正。
「大銃(大砲)の鋳立が成らず、申し訳ございません!」
やはり興奮気味に、殿に謝罪をする本島。
「つきましては…腹を切ってお詫びを…」
本島は“死”をもって償うと申し出た。
――鍋島直正、本島の言葉を受け止めると、背を向けて一呼吸おいた。
「死ぬことは許さん。生きて成し遂げよ。」
本島の気負った表情が崩れる。
「殿…しかし…」
直正は続けた。
「そなたらには、無茶を押し付けておる。すべて儂の責任だ。」
本島が涙を流した。
直正は少し表情を緩めて、本島に語りかける。
「重ねて申すぞ。命を絶つことは許さん!これは主命である。」
――このとき、1851年。日本が黒船来航の脅威に直面するまで、あと2年である。
(第7話「尊王義祭」に続く)