2021年12月31日
「紅白に想う、SAGA」
こんにちは。
年末年始のお休みに入り、何が楽しいかと言えば、時間を選ばずに、有田焼の急須で入れた嬉野茶を飲んで、丸ぼうろを食(は)むことができます。
一年を振り返ると、あのアニメに出会ったことを語らないわけにもいかず…
〔参照:「再起の剣」〕
年の瀬の忙しい中、また複雑な記事を書いてしまったので、共感できる方にお読みいただければ幸いです。
――2021(令和3)年。ようやく知るに至った“佐賀を救う力”の一端。
「気づいてなかったんか~い!」という激しい“ツッコミ”もあるかもしれません。
いや、佐賀から離れている私です。皆様と違って自然には情報が入りません。出遅れるのですよ。いろいろと。
『肥前さが幕末維新博覧会』が盛り上がっていた頃、2018年の佐賀をさらに熱くしたであろうアニメ『ゾンビランドサガ』。
…そのリアルタイムでの感動を知ることなく、周回遅れを3年ばかり。
2021年4月から放送された、同作品第2期(第2シリーズ)『ゾンビランドサガ リベンジ』。私に大きな感銘を与えました。

※嬉野温泉。作品のファンによる“マンホールのフタ”巡りでも、人気スポットと聞きます。
――いまも続く、異色のアイドルたちの活躍。
アニメから出でて、佐賀県内での“ご当地ナンバープレート”から“マンホールのフタ”にまで、作中のキャラクターが登場しているそうですね。
ここ2年間も佐賀に“帰藩”できておらず、残念ながら現物は見ておりません。
まずは“幕末佐賀藩の大河ドラマ”を志向する私ですので、当初は「さすがに、アイドル系のアニメまでは…」と引き気味でした。
第1期の再放送すら視聴していなかったのは、そのためです。
〔参照:「誰かが、誰かの“憧れの人”」〕
しかし、第2期で視聴した回を重ねるごとに、同作品への私の評価は急上昇。最後には“感涙もの”に分類したことは、幾度か語ってきました。
――これは“深読み”し過ぎかもしれませんが、
主人公のアイドルグループ“フランシュシュ”のメンバーは一度亡くなってから甦っています。
作中では“ゾンビィ”と呼称され、不思議な肉体をしていて、もし首が離れても、くっつければ元通りに動けるのです…
「…この作品。やはり本気で“佐賀を救おう”としている!?」
教科書、歴史番組、今ならインターネットの情報でも。佐賀出身者である私の心を痛めつける“あの事件”の辛すぎる結末。
そして歴史の過程でも、明治の一時期は県域が消滅するほど、佐賀県に与えられた痛烈なダメージ。
〔参照:「佐賀を取り戻す話」〕
――「よもや、ここを真っ向から書くとは…」
第2期(リベンジ)で明らかになってきた同作品の大枠。重要なエピソードがありました。まさかアイドル系アニメで、明治時代の話をまともに描いてくるとは。
主人公たちも、各々の時代で「もし生きていれば、佐賀に繁栄をもたらすはずだった少女たち」という設定なのが泣かせます。
このように“生死の境”が基準なら、アニメ限定の話になってしまうのですが…
「佐賀に残って(戻って)いれば、地域の発展につながったはずの人」が都会に出たまま還ってこない…という事は、現実にもあると思うのですね。

――「ところで、なぜ年内最終日にアニメの話をする?」
大晦日だから思うのです。近いうちに『ゾンビランドサガ』の主人公グループ・フランシュシュを紅白歌合戦で見ることはできないかと。
ここ一年でも、同アニメの声優さんたちは、千葉の幕張で大規模なライブを行い、NHKの歌番組にも出演を果たしています。
しかし、映画化が決定したとはいえ、一般的には同作品の盛り上がりのピークは過ぎているとの見方もあるようです。
「ここから、どう巻き返すか…」と年の瀬の最後まで、こんな事を考えています。
〔参照:「佐賀の“終わらない”物語…」〕
――今年は、特に“乱文”が多かった当ブログです。
そこそこ仕事も忙しく、幕末佐賀藩の大河ドラマをイメージした“本編”が進まなかった一年でした。
文章をまとめる時間の無い時は「佐賀への愛を叫ぶ(?)」企画も多かったので、読みづらい記事もあったと思います。
また年始にも語りそうですが「来年こそは“本編”を進めて、佐賀にも“帰藩”しよう!」という決意を新たにしているところです。
この一年もご覧いただいた皆様、ありがとうございます。良いお年をお迎えください。
年末年始のお休みに入り、何が楽しいかと言えば、時間を選ばずに、有田焼の急須で入れた嬉野茶を飲んで、丸ぼうろを食(は)むことができます。
一年を振り返ると、あのアニメに出会ったことを語らないわけにもいかず…
〔参照:
年の瀬の忙しい中、また複雑な記事を書いてしまったので、共感できる方にお読みいただければ幸いです。
――2021(令和3)年。ようやく知るに至った“佐賀を救う力”の一端。
「気づいてなかったんか~い!」という激しい“ツッコミ”もあるかもしれません。
いや、佐賀から離れている私です。皆様と違って自然には情報が入りません。出遅れるのですよ。いろいろと。
『肥前さが幕末維新博覧会』が盛り上がっていた頃、2018年の佐賀をさらに熱くしたであろうアニメ『ゾンビランドサガ』。
…そのリアルタイムでの感動を知ることなく、周回遅れを3年ばかり。
2021年4月から放送された、同作品第2期(第2シリーズ)『ゾンビランドサガ リベンジ』。私に大きな感銘を与えました。
※嬉野温泉。作品のファンによる“マンホールのフタ”巡りでも、人気スポットと聞きます。
――いまも続く、異色のアイドルたちの活躍。
アニメから出でて、佐賀県内での“ご当地ナンバープレート”から“マンホールのフタ”にまで、作中のキャラクターが登場しているそうですね。
ここ2年間も佐賀に“帰藩”できておらず、残念ながら現物は見ておりません。
まずは“幕末佐賀藩の大河ドラマ”を志向する私ですので、当初は「さすがに、アイドル系のアニメまでは…」と引き気味でした。
第1期の再放送すら視聴していなかったのは、そのためです。
〔参照:
しかし、第2期で視聴した回を重ねるごとに、同作品への私の評価は急上昇。最後には“感涙もの”に分類したことは、幾度か語ってきました。
――これは“深読み”し過ぎかもしれませんが、
主人公のアイドルグループ“フランシュシュ”のメンバーは一度亡くなってから甦っています。
作中では“ゾンビィ”と呼称され、不思議な肉体をしていて、もし首が離れても、くっつければ元通りに動けるのです…
「…この作品。やはり本気で“佐賀を救おう”としている!?」
教科書、歴史番組、今ならインターネットの情報でも。佐賀出身者である私の心を痛めつける“あの事件”の辛すぎる結末。
そして歴史の過程でも、明治の一時期は県域が消滅するほど、佐賀県に与えられた痛烈なダメージ。
〔参照:
――「よもや、ここを真っ向から書くとは…」
第2期(リベンジ)で明らかになってきた同作品の大枠。重要なエピソードがありました。まさかアイドル系アニメで、明治時代の話をまともに描いてくるとは。
主人公たちも、各々の時代で「もし生きていれば、佐賀に繁栄をもたらすはずだった少女たち」という設定なのが泣かせます。
このように“生死の境”が基準なら、アニメ限定の話になってしまうのですが…
「佐賀に残って(戻って)いれば、地域の発展につながったはずの人」が都会に出たまま還ってこない…という事は、現実にもあると思うのですね。

――「ところで、なぜ年内最終日にアニメの話をする?」
大晦日だから思うのです。近いうちに『ゾンビランドサガ』の主人公グループ・フランシュシュを紅白歌合戦で見ることはできないかと。
ここ一年でも、同アニメの声優さんたちは、千葉の幕張で大規模なライブを行い、NHKの歌番組にも出演を果たしています。
しかし、映画化が決定したとはいえ、一般的には同作品の盛り上がりのピークは過ぎているとの見方もあるようです。
「ここから、どう巻き返すか…」と年の瀬の最後まで、こんな事を考えています。
〔参照:
――今年は、特に“乱文”が多かった当ブログです。
そこそこ仕事も忙しく、幕末佐賀藩の大河ドラマをイメージした“本編”が進まなかった一年でした。
文章をまとめる時間の無い時は「佐賀への愛を叫ぶ(?)」企画も多かったので、読みづらい記事もあったと思います。
また年始にも語りそうですが「来年こそは“本編”を進めて、佐賀にも“帰藩”しよう!」という決意を新たにしているところです。
この一年もご覧いただいた皆様、ありがとうございます。良いお年をお迎えください。
2021年12月29日
「“銀天”ば衝け…?」
こんばんは。
大河ドラマ『青天を衝け』最終回まで見事な展開だと感じました。明治期以降は、大隈重信がしっかり描かれ、佐賀の存在感も見えていました。
しかし“佐賀の大河ドラマ”を志向する私。この描き方で満足することはなく…
「言いたいことは、それだけか。」
「否(いな)、まだ山ほどございまする!」
…という感じです。こうして、本記事は『青天を衝け』最終回の感想を、2年前に撮った佐賀の風景とともにお送りするという複雑な試みとなりました。
――放送開始から4分頃。東京養育院の場面。
ここでは養育院の運営に力を注ぐ渋沢栄一〔演:吉沢亮〕の来訪に喜び、子供たちが出迎えます。ポイントは、子供たちが口ずさむ歌。
「青葉茂れる~、桜井の~♪」
この歌は南北朝時代に活躍した武将・楠木正成を題材としたもの。古くから、佐賀藩には、天皇に忠義を尽くした楠木正成を崇敬する傾向がありました。
幕末期の佐賀から見ても、大きな意味のある歌なのです。

――佐賀市の、龍造寺八幡宮の境内にある社。
佐賀の志士たちが集った“義祭同盟”。楠木正成を勤王の象徴として崇めるだけでなく、秘密結社という側面もあったようです。
写真にある“楠神社”は、その象徴的な場所。若き日の大隈重信(八太郎)も“義祭同盟”のメンバーとなっていました。
『青天を衝け』では、大倉孝二さんの熱演で強い印象を残した大隈重信。
ちなみに、大隈八太郎という名は、この場所・龍造寺八幡宮に由来するそう。本記事では、大隈も通ったはずの道をたどります。

――同じく佐賀市の中心街にある、白山通り。
江戸時代には長崎街道の賑わいに加えて、龍造寺八幡宮の参道としても、栄えたといいます。
現在は、佐賀市内で唯一と聞くアーケード街。
「おいは己の力で立ちよるばい!“銀の天”に拳ば衝き上げるとよ。」
言うまでもなく『青天を衝け』のパロディーのつもりです。私も佐賀に帰藩したら、ひとまず“銀天”〔アーケード〕にでも拳を衝き上げてみようかと思います。
…きっと、その姿は「肩が痛いから伸びをする人」に見えるはずです。
それはさておき、このアーケード街で例年行われ、夏の風物詩ともなっている『さが銀天夜市』には50年もの歴史があるとか。
――ここで話を戻して、“50年もの歳月”と言えば…
『青天を衝け』最終回では、放送開始から11分頃。大隈邸の場面。
病床にある大隈重信〔演:大倉孝二〕を、渋沢栄一〔演:吉沢亮〕が見舞います。概ね80歳ぐらいの大隈老侯。
明治初期、大隈は30歳ぐらいですから、この2人はおよそ50年来の付き合いということに。
大隈は自宅の庭園で栽培しているメロン〔“早稲田”という品種〕を客人・渋沢に食べてほしいと考えます。
国際情勢を語りながらも「メロンばあるとよ、早う食べんね。」という感じの展開ですが、「~であるんである。」「~であ~る。」と、なぜか演説調の大隈老侯。
――その場面で私は、こう思いました。
「普通に“佐賀ことば”で話しておけば良いのに…」と。
しかし、次の瞬間に気づきました。初対面の渋沢栄一と出会って、明治新政府に引き込んだ時の大隈重信の演説を。
高い志と堂々たる弁舌で、渋沢の胸を“ぐるぐる”とさせた大隈。
「…これは50年経っても、出会った頃のままの自分を見せたかったのか」と。
談笑の中にも「元気さを見せようとする」大隈侯の意地を感じる場面でした。

――前回(第40回)の放送を思い起こせば、
「80歳に近い年寄りになって、まだ首相などやっておるのか」と詰め寄る渋沢。
「おいは一人、大正になっても維新の世の尻拭いばしているのである」と大声で返す、大隈。
大隈の強い語気の中に、寂しさと心細さを感じた一言でした。セリフで名が挙がるのは、長州の人たちでしたが、ここを深読みしました。
“佐賀の七賢人”の中で、最年少だった大隈重信。一緒に頑張ってきた、支えてくれる、あるいは安心して喧嘩のできる“佐賀の兄貴分”たちは、その時には、もうこの世にいないのです。
――明治期からの付き合いである渋沢には、
どことなく意地を張っているようにも見えた、大隈重信。私がどこか期待した、故郷・佐賀を懐かしむ大隈は描かれませんでした。
しかし、このように幾らでも深読みしたくなるほど、魅力的な大隈像が描かれた『青天を衝け』だったと思います。
なお最終回の再放送は、本日29日(水)の昼。午後1時5分~のようです。
近いうち“佐賀ことば”全開で突き進む、青年・大隈八太郎にも、大河ドラマで出会えることを楽しみにしています。
大河ドラマ『青天を衝け』最終回まで見事な展開だと感じました。明治期以降は、大隈重信がしっかり描かれ、佐賀の存在感も見えていました。
しかし“佐賀の大河ドラマ”を志向する私。この描き方で満足することはなく…
「言いたいことは、それだけか。」
「否(いな)、まだ山ほどございまする!」
…という感じです。こうして、本記事は『青天を衝け』最終回の感想を、2年前に撮った佐賀の風景とともにお送りするという複雑な試みとなりました。
――放送開始から4分頃。東京養育院の場面。
ここでは養育院の運営に力を注ぐ渋沢栄一〔演:吉沢亮〕の来訪に喜び、子供たちが出迎えます。ポイントは、子供たちが口ずさむ歌。
「青葉茂れる~、桜井の~♪」
この歌は南北朝時代に活躍した武将・楠木正成を題材としたもの。古くから、佐賀藩には、天皇に忠義を尽くした楠木正成を崇敬する傾向がありました。
幕末期の佐賀から見ても、大きな意味のある歌なのです。
――佐賀市の、龍造寺八幡宮の境内にある社。
佐賀の志士たちが集った“義祭同盟”。楠木正成を勤王の象徴として崇めるだけでなく、秘密結社という側面もあったようです。
写真にある“楠神社”は、その象徴的な場所。若き日の大隈重信(八太郎)も“義祭同盟”のメンバーとなっていました。
『青天を衝け』では、大倉孝二さんの熱演で強い印象を残した大隈重信。
ちなみに、大隈八太郎という名は、この場所・龍造寺八幡宮に由来するそう。本記事では、大隈も通ったはずの道をたどります。
――同じく佐賀市の中心街にある、白山通り。
江戸時代には長崎街道の賑わいに加えて、龍造寺八幡宮の参道としても、栄えたといいます。
現在は、佐賀市内で唯一と聞くアーケード街。
「おいは己の力で立ちよるばい!“銀の天”に拳ば衝き上げるとよ。」
言うまでもなく『青天を衝け』のパロディーのつもりです。私も佐賀に帰藩したら、ひとまず“銀天”〔アーケード〕にでも拳を衝き上げてみようかと思います。
…きっと、その姿は「肩が痛いから伸びをする人」に見えるはずです。
それはさておき、このアーケード街で例年行われ、夏の風物詩ともなっている『さが銀天夜市』には50年もの歴史があるとか。
――ここで話を戻して、“50年もの歳月”と言えば…
『青天を衝け』最終回では、放送開始から11分頃。大隈邸の場面。
病床にある大隈重信〔演:大倉孝二〕を、渋沢栄一〔演:吉沢亮〕が見舞います。概ね80歳ぐらいの大隈老侯。
明治初期、大隈は30歳ぐらいですから、この2人はおよそ50年来の付き合いということに。
大隈は自宅の庭園で栽培しているメロン〔“早稲田”という品種〕を客人・渋沢に食べてほしいと考えます。
国際情勢を語りながらも「メロンばあるとよ、早う食べんね。」という感じの展開ですが、「~であるんである。」「~であ~る。」と、なぜか演説調の大隈老侯。
――その場面で私は、こう思いました。
「普通に“佐賀ことば”で話しておけば良いのに…」と。
しかし、次の瞬間に気づきました。初対面の渋沢栄一と出会って、明治新政府に引き込んだ時の大隈重信の演説を。
高い志と堂々たる弁舌で、渋沢の胸を“ぐるぐる”とさせた大隈。
「…これは50年経っても、出会った頃のままの自分を見せたかったのか」と。
談笑の中にも「元気さを見せようとする」大隈侯の意地を感じる場面でした。
――前回(第40回)の放送を思い起こせば、
「80歳に近い年寄りになって、まだ首相などやっておるのか」と詰め寄る渋沢。
「おいは一人、大正になっても維新の世の尻拭いばしているのである」と大声で返す、大隈。
大隈の強い語気の中に、寂しさと心細さを感じた一言でした。セリフで名が挙がるのは、長州の人たちでしたが、ここを深読みしました。
“佐賀の七賢人”の中で、最年少だった大隈重信。一緒に頑張ってきた、支えてくれる、あるいは安心して喧嘩のできる“佐賀の兄貴分”たちは、その時には、もうこの世にいないのです。
――明治期からの付き合いである渋沢には、
どことなく意地を張っているようにも見えた、大隈重信。私がどこか期待した、故郷・佐賀を懐かしむ大隈は描かれませんでした。
しかし、このように幾らでも深読みしたくなるほど、魅力的な大隈像が描かれた『青天を衝け』だったと思います。
なお最終回の再放送は、本日29日(水)の昼。午後1時5分~のようです。
近いうち“佐賀ことば”全開で突き進む、青年・大隈八太郎にも、大河ドラマで出会えることを楽しみにしています。
2021年12月25日
第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)
こんばんは。
第17話は年内完結を目指しましたが、なかなか年末も忙しく、思惑どおりにはいきません。自由に動けないもどかしさ…を感じるところも多い1年でした。
今回の文久元年の師走(十二月)をイメージした話で、年内の“本編”はラストの予定です。なお、年末年始にも別企画での投稿ができればと考えています。
――江戸城内。書院にて。
幕閣から期待される、唐津藩・小笠原長行も、忙しく政務にあたる。生まれ故郷の唐津から、参勤交代で江戸に来たが、早くも能力の一端を見せている。
幕政の中心人物、老中・安藤信正と話をする。
「ご老中。先刻から上様のお姿が見当たりませぬが…。」
「小笠原どの。上様とて、時には羽を伸ばしたい時もござろうて。」
「何処に、いらっしゃるのですか。」
まだ少年の“上様”の行先を心配する小笠原長行。まるで“保護者”の目線。
「心配は無用。お庭に居られる。」

――ピッ…、ピピッ…。
籠〔かご〕に入った鳥を、優し気な眼差しで見つめる。幼い頃から、小動物を愛する子どもだった“上様”。第14代将軍・徳川家茂である。
「心が、安らぐのう…。」
「そちも、大空に羽ばたきたいか。」
「ピッ…、ピッピ。」
「昔の私なら、籠を開け放ち、そちを逃がしたであろうな。」
「ピッ…?」
寒さの増す師走だが、その日の江戸は、穏やかな陽光に包まれていた。
――多忙な政務の気晴らしか。
小鳥と語らう“上様”。
「しかしながら、そちを空に放たば、立ちどころに猛禽の餌食となろう…。」
「…ピッ!」
小鳥に物騒なことを語る上様。幼き日と違って様々な事も見えてくる。年頃は少年だが、武家の棟梁(とうりょう)・将軍だ。万事に責任を持たねばならない。
「許せ。私は、そちが傷つかぬよう、籠に留め置く。」
「ピピッ…」

――屋内から、その様子を窺(うかが)う女性たち。
「…あれが、公方(くぼう)様にあらしゃいます。」
傍にいた御付きの女性が、顔立ちに、あどけなさを残した少女にささやく。
「あの御方が…、公方さまやと?」
さすが気品のある顔立ち…といった印象。皇女・和宮である。話し方は“御所ことば”で柔らかいが、気難しい表情をした。
険しい中山道を来た京から江戸への旅路。望んでいた“京風”とは、ほど遠い江戸城内の暮らしでは、前将軍の正室・天璋院(篤姫)からの重圧も感じる。
――京を出て、和宮の表情は曇りがちだった。
江戸城には入ったが“婚礼”は年を越してからである。同年齢の“夫”の姿を、突然に見かけ、戸惑いが見られる。
「…公方さんは、よもや小鳥と話をされておるのか?」
「ええ、いかなお考えであらしゃいますやら。」
将軍(公方)・徳川家茂をどう理解したものか、考え込む京ことばの二人。
――眺める先には、将軍・家茂と籠の小鳥。
その周りをふんわりと陽だまりが包み込む。
「なんや武家らしゅうない、優しげな御方やな…。」
「それは、そうやもしれまへんなぁ。」
和宮の言葉に御付きの女性が相づちを打つ。武家らしく気詰まりな“夫”の姿を想像していた。拍子抜けしたか、固かった表情からは安堵の気配が見える。

――だが、この師走。江戸の市中は荒れていた。
「御用の者だ。神妙にいたせ!」
「おのれっ…無礼な幕吏(ばくり)どもめ。」
「手向かいいたすにおいては、容赦はせぬぞ!」
幕府の捕方が、尊王攘夷の志士たちが集まる私塾などを一斉に取り締まる。皇女・和宮の江戸への降嫁に際し、武装蜂起などを企てた嫌疑だった。
――江戸城下。佐賀藩の屋敷。
江戸詰めの藩士たちに、学問を教える役割だった副島種臣を、中野方蔵が訪ねていた。
「大橋先生の塾も、公儀(幕府)の取り締まりが入ったそうだな。」
「ええ、相当に物騒な有様(ありさま)となっておりましたゆえ。」
佐賀藩士・中野方蔵も、大橋訥庵の私塾にはよく立ち寄ったが、淡々と語る。塾に過激な浪士が関わっているのが危険と察知し、距離を取ったところだ。
「…中野も、あの塾に出入りしておったな。身辺に用心をすることだ。」
「当面は“昌平黌”(昌平坂学問所)への通いも控えます。」
「それが良かろう。」
――幕府公式の学問所でも、人脈を築いた中野。
尊王攘夷の志士が集まる私塾はもちろん危険だが、学問所も完全に幕府の領分。いま立ち寄るのは危うい。
「副島先生も、ご用心のほどを。」
「…うむ。」
副島種臣とて、勤王の思想家として名が知られる。穏やかでない年の瀬だ。佐賀藩上層部の“勤王”への動きは鈍い。副島にも、焦りはある。
「…然しながら、もはや軽挙はならぬのだ。」
中野には用心を念押しして、退出する後ろ姿を見送った。最近、謹慎が解けたばかりの副島である。ふと、溜め息をついた。
(続く)
〔参照記事〕
・第15話「江戸動乱」⑩(いざゆけ!次郎)
・第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)
・第16話「攘夷沸騰」⑨(玉石、相混じる)
第17話は年内完結を目指しましたが、なかなか年末も忙しく、思惑どおりにはいきません。自由に動けないもどかしさ…を感じるところも多い1年でした。
今回の文久元年の師走(十二月)をイメージした話で、年内の“本編”はラストの予定です。なお、年末年始にも別企画での投稿ができればと考えています。
――江戸城内。書院にて。
幕閣から期待される、唐津藩・小笠原長行も、忙しく政務にあたる。生まれ故郷の唐津から、参勤交代で江戸に来たが、早くも能力の一端を見せている。
幕政の中心人物、老中・安藤信正と話をする。
「ご老中。先刻から上様のお姿が見当たりませぬが…。」
「小笠原どの。上様とて、時には羽を伸ばしたい時もござろうて。」
「何処に、いらっしゃるのですか。」
まだ少年の“上様”の行先を心配する小笠原長行。まるで“保護者”の目線。
「心配は無用。お庭に居られる。」
――ピッ…、ピピッ…。
籠〔かご〕に入った鳥を、優し気な眼差しで見つめる。幼い頃から、小動物を愛する子どもだった“上様”。第14代将軍・徳川家茂である。
「心が、安らぐのう…。」
「そちも、大空に羽ばたきたいか。」
「ピッ…、ピッピ。」
「昔の私なら、籠を開け放ち、そちを逃がしたであろうな。」
「ピッ…?」
寒さの増す師走だが、その日の江戸は、穏やかな陽光に包まれていた。
――多忙な政務の気晴らしか。
小鳥と語らう“上様”。
「しかしながら、そちを空に放たば、立ちどころに猛禽の餌食となろう…。」
「…ピッ!」
小鳥に物騒なことを語る上様。幼き日と違って様々な事も見えてくる。年頃は少年だが、武家の棟梁(とうりょう)・将軍だ。万事に責任を持たねばならない。
「許せ。私は、そちが傷つかぬよう、籠に留め置く。」
「ピピッ…」
――屋内から、その様子を窺(うかが)う女性たち。
「…あれが、公方(くぼう)様にあらしゃいます。」
傍にいた御付きの女性が、顔立ちに、あどけなさを残した少女にささやく。
「あの御方が…、公方さまやと?」
さすが気品のある顔立ち…といった印象。皇女・和宮である。話し方は“御所ことば”で柔らかいが、気難しい表情をした。
険しい中山道を来た京から江戸への旅路。望んでいた“京風”とは、ほど遠い江戸城内の暮らしでは、前将軍の正室・天璋院(篤姫)からの重圧も感じる。
――京を出て、和宮の表情は曇りがちだった。
江戸城には入ったが“婚礼”は年を越してからである。同年齢の“夫”の姿を、突然に見かけ、戸惑いが見られる。
「…公方さんは、よもや小鳥と話をされておるのか?」
「ええ、いかなお考えであらしゃいますやら。」
将軍(公方)・徳川家茂をどう理解したものか、考え込む京ことばの二人。
――眺める先には、将軍・家茂と籠の小鳥。
その周りをふんわりと陽だまりが包み込む。
「なんや武家らしゅうない、優しげな御方やな…。」
「それは、そうやもしれまへんなぁ。」
和宮の言葉に御付きの女性が相づちを打つ。武家らしく気詰まりな“夫”の姿を想像していた。拍子抜けしたか、固かった表情からは安堵の気配が見える。
――だが、この師走。江戸の市中は荒れていた。
「御用の者だ。神妙にいたせ!」
「おのれっ…無礼な幕吏(ばくり)どもめ。」
「手向かいいたすにおいては、容赦はせぬぞ!」
幕府の捕方が、尊王攘夷の志士たちが集まる私塾などを一斉に取り締まる。皇女・和宮の江戸への降嫁に際し、武装蜂起などを企てた嫌疑だった。
――江戸城下。佐賀藩の屋敷。
江戸詰めの藩士たちに、学問を教える役割だった副島種臣を、中野方蔵が訪ねていた。
「大橋先生の塾も、公儀(幕府)の取り締まりが入ったそうだな。」
「ええ、相当に物騒な有様(ありさま)となっておりましたゆえ。」
佐賀藩士・中野方蔵も、大橋訥庵の私塾にはよく立ち寄ったが、淡々と語る。塾に過激な浪士が関わっているのが危険と察知し、距離を取ったところだ。
「…中野も、あの塾に出入りしておったな。身辺に用心をすることだ。」
「当面は“昌平黌”(昌平坂学問所)への通いも控えます。」
「それが良かろう。」
――幕府公式の学問所でも、人脈を築いた中野。
尊王攘夷の志士が集まる私塾はもちろん危険だが、学問所も完全に幕府の領分。いま立ち寄るのは危うい。
「副島先生も、ご用心のほどを。」
「…うむ。」
副島種臣とて、勤王の思想家として名が知られる。穏やかでない年の瀬だ。佐賀藩上層部の“勤王”への動きは鈍い。副島にも、焦りはある。
「…然しながら、もはや軽挙はならぬのだ。」
中野には用心を念押しして、退出する後ろ姿を見送った。最近、謹慎が解けたばかりの副島である。ふと、溜め息をついた。
(続く)
〔参照記事〕
・
・
・
2021年12月21日
第17話「佐賀脱藩」⑫(陽だまりの下で)
こんばんは。前回の続きです。
大都市・江戸での生活を続ける親友・中野方蔵に対して、佐賀から出る予定のない江藤新平。
この頃、江藤の家は、佐賀城下の武家屋敷街の一角。藩の役人として、それなりの住まいに移っていたそうです。
親しい大木喬任や中野方蔵に比べても家格が低く、長年、貧乏暮らしでしたが、脱却を果たした感がありました。
――ある冬の日。江藤家の屋敷。
幾分、寒さが和らぎ、陽だまりの心地がする日。
江藤は、長男・熊太郎を抱きかかえていた。
「よし、熊太郎。そろそろ漢詩を教えようか。」
「新平さま。まだ熊太郎は、赤子ですよ。」
「…しかし。千代子どの。」
「さすがに漢詩は、早うございますよ。」
「鉄は熱いうちに打てと申すが。」
「貴方さまのお子ですよ。ご心配なさらずとも、賢くなります。」

――江藤夫婦の長男・熊太郎は数え年で2つ(満1歳)になる。
「それと“千代子どの”はやめてくださいませ。よそよそしいです。」
「お主も“新平さま”と呼んでおるではないか。お互い様だ。」
…コホンと、江藤の父・助右衛門の咳払いが響く。
「昼日中から、仲の良さそうなことだな。」
「よし、熊太郎には、儂から“一節”聞かせてやろう。」
「赤子に“浄瑠璃”(じょうるり)も、早うございます。」
ここは、江藤の母・浅子から、父・助右衛門に鋭い指摘が入る。
――とりあえず熊太郎が、ぐずっている。
「…しかしだな、浅子。」
何だか納得していない助右衛門。
「はいはい~、熊太郎くん。“叔父上”でちゅよ。」
そこで、横にいた若い男が、熊太郎を受け取ると、あやしはじめた。
「おおっ、源作!赤子のあやし方がうまいな。」
「旦那さまと、新平が下手すぎるのでございます。」
…江藤の父と母、まったく違う角度からの反応である。
「ははっ、父上や兄者と比べれば上手かですよ。」
その若い男は、江藤の弟・源作。

――軽く、調子の良い反応をした。兄ほどの堅物では無いようだ。
「よし、源作。儂も、熊太郎をあやしてみせるぞ。」
何やら強い決意を見せる、江藤の父・助右衛門。
「やーらしか(可愛い)、熊太郎。“じーじー”でちゅよ。」
「…さすがの江藤助右衛門も、初孫には弱かね…。」
鋭い才覚を持っていたが、信念を曲げず、よく上役と激突したという江藤の父・助右衛門。もはや、ただの孫大好きのおじいちゃんになっている。
――キャッキャッと上機嫌な、熊太郎。
「源作。大したものだな。感心したぞ。」
「…兄上。そがん感じ入らずとも、よかです…。」
父・助右衛門がお役目を解かれたため、江藤の少年期はかなりの貧乏だったが、父も役人に復帰。江藤自身も佐賀藩の貿易部門への転属が決まる。
藩の産業に関わる有意義な仕事に就くこととなり、佐賀城下で、相応の屋敷にも入った。長男・熊太郎も、まずまず健やかに育っている。
――だが、江藤の妻・千代子には胸騒ぎがあった。
寒い冬の中、陽だまりに包まれたような一日。こんな幸せがずっと続いてほしい。しかし、いとこだった千代子にも、卓越した江藤の才能は見えていた。
この人は、いつかは“時代”に必要とされ“大事”に関わることになるのだろう。そして、いま談笑する江藤家の人々は、皆、その覚悟を秘めているのだと。
(続く)
大都市・江戸での生活を続ける親友・中野方蔵に対して、佐賀から出る予定のない江藤新平。
この頃、江藤の家は、佐賀城下の武家屋敷街の一角。藩の役人として、それなりの住まいに移っていたそうです。
親しい大木喬任や中野方蔵に比べても家格が低く、長年、貧乏暮らしでしたが、脱却を果たした感がありました。
――ある冬の日。江藤家の屋敷。
幾分、寒さが和らぎ、陽だまりの心地がする日。
江藤は、長男・熊太郎を抱きかかえていた。
「よし、熊太郎。そろそろ漢詩を教えようか。」
「新平さま。まだ熊太郎は、赤子ですよ。」
「…しかし。千代子どの。」
「さすがに漢詩は、早うございますよ。」
「鉄は熱いうちに打てと申すが。」
「貴方さまのお子ですよ。ご心配なさらずとも、賢くなります。」
――江藤夫婦の長男・熊太郎は数え年で2つ(満1歳)になる。
「それと“千代子どの”はやめてくださいませ。よそよそしいです。」
「お主も“新平さま”と呼んでおるではないか。お互い様だ。」
…コホンと、江藤の父・助右衛門の咳払いが響く。
「昼日中から、仲の良さそうなことだな。」
「よし、熊太郎には、儂から“一節”聞かせてやろう。」
「赤子に“浄瑠璃”(じょうるり)も、早うございます。」
ここは、江藤の母・浅子から、父・助右衛門に鋭い指摘が入る。
――とりあえず熊太郎が、ぐずっている。
「…しかしだな、浅子。」
何だか納得していない助右衛門。
「はいはい~、熊太郎くん。“叔父上”でちゅよ。」
そこで、横にいた若い男が、熊太郎を受け取ると、あやしはじめた。
「おおっ、源作!赤子のあやし方がうまいな。」
「旦那さまと、新平が下手すぎるのでございます。」
…江藤の父と母、まったく違う角度からの反応である。
「ははっ、父上や兄者と比べれば上手かですよ。」
その若い男は、江藤の弟・源作。
――軽く、調子の良い反応をした。兄ほどの堅物では無いようだ。
「よし、源作。儂も、熊太郎をあやしてみせるぞ。」
何やら強い決意を見せる、江藤の父・助右衛門。
「やーらしか(可愛い)、熊太郎。“じーじー”でちゅよ。」
「…さすがの江藤助右衛門も、初孫には弱かね…。」
鋭い才覚を持っていたが、信念を曲げず、よく上役と激突したという江藤の父・助右衛門。もはや、ただの孫大好きのおじいちゃんになっている。
――キャッキャッと上機嫌な、熊太郎。
「源作。大したものだな。感心したぞ。」
「…兄上。そがん感じ入らずとも、よかです…。」
父・助右衛門がお役目を解かれたため、江藤の少年期はかなりの貧乏だったが、父も役人に復帰。江藤自身も佐賀藩の貿易部門への転属が決まる。
藩の産業に関わる有意義な仕事に就くこととなり、佐賀城下で、相応の屋敷にも入った。長男・熊太郎も、まずまず健やかに育っている。
――だが、江藤の妻・千代子には胸騒ぎがあった。
寒い冬の中、陽だまりに包まれたような一日。こんな幸せがずっと続いてほしい。しかし、いとこだった千代子にも、卓越した江藤の才能は見えていた。
この人は、いつかは“時代”に必要とされ“大事”に関わることになるのだろう。そして、いま談笑する江藤家の人々は、皆、その覚悟を秘めているのだと。
(続く)
2021年12月18日
第17話「佐賀脱藩」⑪(“都会”の流儀)
こんばんは。前回の続きです。
鍋島直正の愛娘・貢姫の嫁ぎ先は、現在では埼玉県にあった川越藩でした。大名の正室として、江戸にいた貢姫。
夫で川越藩主だった松平直侯が亡くなったことで、のち江戸を離れ、川越へと移る定めとなります。
幕末期の江戸は、世界最大の人口規模を誇ったと言われる“百万”都市。様々な人々が集まり、悲喜こもごもに暮らす大都会でした。
――江戸。川越藩の屋敷。
薄暗い冬の日。夫の喪に服する貢姫。若くして“未亡人”となってしまった。
「父上…、貢は鍋島の娘として、何事もなし得ませんでした。」
同じく、まだ二十代前半だった夫を失い、途方に暮れる。夫婦の間には、まだ子はいなかった。愛娘の心には、頼れる父・鍋島直正の面影が浮かぶ。
父の心配どおり、真面目な鍋島家の長女は、自責の念に駆られていた。
――同じ頃、離れた娘の境遇を心配する父・直正。
「貢よ、己を責めるでないっ!松平さまのお立場も、厳しかったのだ…」
「殿、いかがなさいました…!?」
ふと、語り出した直正(閑叟)。“幼なじみ”の側近・古川与一(松根)が慌てる。
「…わが娘が、助けを呼ぶかと思えてな。つい、声に出たようだ。」
「殿!いや、ご隠居…閑叟さま…。姫が、心配にございますな。」

――先月から佐賀の殿様は、正式に隠居している。
「与一よ。もしや、儂の呼び方を迷うておるか?」
色々と困惑する古川を見て、気が逸れたのか。わずかに笑みを見せる、直正。
「まだ、落ち着かぬから、当面は“殿”と呼べばよい。」
「…心得ました。では、いずれ“ご老公”とお呼びいたしましょうか。」
「その呼び名は…、何やら収まりが良くない。」
人生、苦もあれば楽もある。「ここも、先憂後楽じゃ。」と、自らに言い聞かせる“佐賀のご老公”であった。
――さて、大都市・江戸の市中。儒学者・大橋訥庵の私塾にて。
「老中の所業、許しがたし!」
「おう、安藤を討つべし!」
大声を出す若者たちが集まって、荒々しく武術の訓練に励む。都合の悪いことに、老中・安藤信正に対し、公然と物騒なことを口にしている。
「…もはやこの塾には、立ち寄るべきではないのかもしれぬな。」
その場を、遠巻きに眺めていた、佐賀藩士・中野方蔵がつぶやく。大木喬任と江藤新平が、手紙を楽しみに待つ親友である。

――晩秋には、孝明天皇の妹・和宮が江戸に到着していた。
その“花嫁”の行列は3万人規模とも言われる壮麗なものだった。尊王攘夷派への警戒から、平坦な東海道を避けて、あえて険しい中山道を通ったという。
和宮は、御所風の生活を続けることを強く望む。暮らし方の調整が難航して、1か月ほどは城に入らなかったという。
――また、気勢を挙げる者がいる。
「和宮様を、城へお連れ奉る謀(はかりごと)を打ち砕かん!」
「そうじゃ、皇女さまを奪還せよ!」
いまにも、市中に出撃しそうな雰囲気だ。
「かかる“短慮”に巻き込まれては、大木さんや江藤くんに申し訳が立たぬ。」
諸藩の志士との交流は、佐賀に帰ったのち、他藩と連携して勤王に励み、これからの日本を導くためだ。中野は騒ぎに背を向け、その場を去った。
――すっかり“都会暮らし”に、馴染んでいた中野。
当時の過密都市は火災に弱く、風呂がある住まいを持つものは少ない。下級武士は、市中の銭湯にも出入りをしたという。
そこでは流行の芝居や商品の“広告”まで壁に掲示され、世の動きが見えた。小さい湯船から流れる温かい空気。威勢の良い江戸っ子たちの声が響く。

「京の都からの“花嫁”さまが、ついにお城に入るってよ。」
「…それだ。えれぇ、豪勢な行列だったようじゃねぇか。」
批判の対象にもなるが、わりと徳川将軍家は庶民から親しまれているようだ。
中野には、意外だった。「へぇ…江戸の町衆は、楽しげに語るものだな。」
過激な考えに凝り固まった志士よりも、時に、町人たちの方が闊達(かったつ)と見える時がある。中野は、朝廷のもとに民が集う“新しい世“を思った。
(続く)
鍋島直正の愛娘・貢姫の嫁ぎ先は、現在では埼玉県にあった川越藩でした。大名の正室として、江戸にいた貢姫。
夫で川越藩主だった松平直侯が亡くなったことで、のち江戸を離れ、川越へと移る定めとなります。
幕末期の江戸は、世界最大の人口規模を誇ったと言われる“百万”都市。様々な人々が集まり、悲喜こもごもに暮らす大都会でした。
――江戸。川越藩の屋敷。
薄暗い冬の日。夫の喪に服する貢姫。若くして“未亡人”となってしまった。
「父上…、貢は鍋島の娘として、何事もなし得ませんでした。」
同じく、まだ二十代前半だった夫を失い、途方に暮れる。夫婦の間には、まだ子はいなかった。愛娘の心には、頼れる父・鍋島直正の面影が浮かぶ。
父の心配どおり、真面目な鍋島家の長女は、自責の念に駆られていた。
――同じ頃、離れた娘の境遇を心配する父・直正。
「貢よ、己を責めるでないっ!松平さまのお立場も、厳しかったのだ…」
「殿、いかがなさいました…!?」
ふと、語り出した直正(閑叟)。“幼なじみ”の側近・古川与一(松根)が慌てる。
「…わが娘が、助けを呼ぶかと思えてな。つい、声に出たようだ。」
「殿!いや、ご隠居…閑叟さま…。姫が、心配にございますな。」
――先月から佐賀の殿様は、正式に隠居している。
「与一よ。もしや、儂の呼び方を迷うておるか?」
色々と困惑する古川を見て、気が逸れたのか。わずかに笑みを見せる、直正。
「まだ、落ち着かぬから、当面は“殿”と呼べばよい。」
「…心得ました。では、いずれ“ご老公”とお呼びいたしましょうか。」
「その呼び名は…、何やら収まりが良くない。」
人生、苦もあれば楽もある。「ここも、先憂後楽じゃ。」と、自らに言い聞かせる“佐賀のご老公”であった。
――さて、大都市・江戸の市中。儒学者・大橋訥庵の私塾にて。
「老中の所業、許しがたし!」
「おう、安藤を討つべし!」
大声を出す若者たちが集まって、荒々しく武術の訓練に励む。都合の悪いことに、老中・安藤信正に対し、公然と物騒なことを口にしている。
「…もはやこの塾には、立ち寄るべきではないのかもしれぬな。」
その場を、遠巻きに眺めていた、佐賀藩士・中野方蔵がつぶやく。大木喬任と江藤新平が、手紙を楽しみに待つ親友である。
――晩秋には、孝明天皇の妹・和宮が江戸に到着していた。
その“花嫁”の行列は3万人規模とも言われる壮麗なものだった。尊王攘夷派への警戒から、平坦な東海道を避けて、あえて険しい中山道を通ったという。
和宮は、御所風の生活を続けることを強く望む。暮らし方の調整が難航して、1か月ほどは城に入らなかったという。
――また、気勢を挙げる者がいる。
「和宮様を、城へお連れ奉る謀(はかりごと)を打ち砕かん!」
「そうじゃ、皇女さまを奪還せよ!」
いまにも、市中に出撃しそうな雰囲気だ。
「かかる“短慮”に巻き込まれては、大木さんや江藤くんに申し訳が立たぬ。」
諸藩の志士との交流は、佐賀に帰ったのち、他藩と連携して勤王に励み、これからの日本を導くためだ。中野は騒ぎに背を向け、その場を去った。
――すっかり“都会暮らし”に、馴染んでいた中野。
当時の過密都市は火災に弱く、風呂がある住まいを持つものは少ない。下級武士は、市中の銭湯にも出入りをしたという。
そこでは流行の芝居や商品の“広告”まで壁に掲示され、世の動きが見えた。小さい湯船から流れる温かい空気。威勢の良い江戸っ子たちの声が響く。
「京の都からの“花嫁”さまが、ついにお城に入るってよ。」
「…それだ。えれぇ、豪勢な行列だったようじゃねぇか。」
批判の対象にもなるが、わりと徳川将軍家は庶民から親しまれているようだ。
中野には、意外だった。「へぇ…江戸の町衆は、楽しげに語るものだな。」
過激な考えに凝り固まった志士よりも、時に、町人たちの方が闊達(かったつ)と見える時がある。中野は、朝廷のもとに民が集う“新しい世“を思った。
(続く)
2021年12月14日
第17話「佐賀脱藩」⑩(ご隠居の深き悩み)
こんばんは。前回の続きです。
1861年(文久元年)の晩秋。鍋島直正は佐賀藩主を退き、閑叟(かんそう)と正式に号します。
幕府を守ろうとする“佐幕”派にも、尊攘(尊王攘夷)派からも注目される佐賀の殿様。まだ、四十代での隠居です。
「何か思惑があるのか…?」と周囲には様々な憶測が。
ご隠居としてのんびりするかと言えば、政局をにらんで自由に活動できる身分を求めたという見解もあります。
しかし、当時の直正(閑叟)は体調面に不安を抱え、心配事も増えていました。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑦(父娘の心配事)〕
――「おいは、三瀬に戻らんば。」
福岡脱藩の志士・平野国臣が言うところの「佐賀の三平」の1人。古賀一平には、三瀬街道の番人という役目がある。
「神陽先生は、随分と慎重ではなかね。」
古賀は勤王志士の話に乗らない、師匠・枝吉神陽の動きを訝(いぶか)しがる。
「古賀さん。神陽先生の事だ。ご存念があるのだろう。」
江藤新平とて、平野の熱い想いには感銘を受けた。
「…殿のご隠居を待っておられるかだな。」
大木喬任(民平)は、師匠の思惑を推し量っていた。

――この年、鍋島直正は、着々と隠居の段取りを進めてきた。
「佐賀が一体で動かば、世に与える力は大きいだろうな。」
大木は、淡々と続けた。
「やぐらしか(面倒)な事だ…。」
真っ直ぐな気性の古賀。挙藩一致を待つだけなのが、釈然としないようだ。
「焦らずとも、江戸には中野が居るゆえ。」
諸藩の志士たちとの連携。江藤は、親友・中野方蔵の動きへの期待を語る。
――「そうか、また中野から文(ふみ)が来たら知らせんね。」
「承知した。」
大木が言葉を返す。三瀬の番所は、城下からかなり北にある。古賀は、名残り惜しそうに2人と別れた。
「ああは言ったが、古賀さんの心配ももっともだ。佐賀は時勢に遅れつつある。」
「そこはお主が述べたように、我らには中野がいる。殿様も、じき動くだろう。」
大木は、わりに悠然と構えているように見えた。
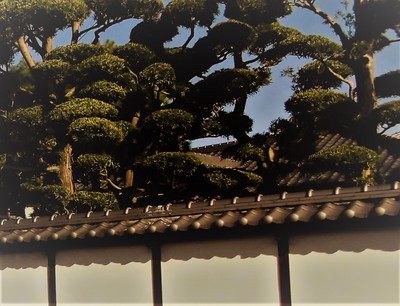
――しかし、隠居後まもなく、鍋島直正には悩みが生じた。
すっかり寒くなった冬のある日。川越藩(埼玉)の江戸屋敷からの急報を見るや、直正(閑叟)の様子がおかしい。
「…いかがなさいましたか。」
直正の世話係にして、幼なじみ・古川与一(松根)が顔色をうかがう。
「川越の…直侯どのが…」
「まさか、」
「…ご逝去なさった。」
川越藩主・松平直侯は、直正の娘・貢姫の夫だ。
――明らかに顔色の悪い、直正。
「…お気をたしかに。」
古川与一が、心配げに声をかける。
「貢(みつ)の胸中が察されてならぬ…。」
直正は、若くして夫を亡くした愛娘の心痛を思った。生真面目な長女のことだ。きっと思い悩んでいるに違いない。
病気療養中だった松平直侯。亡くなったのは、文久元年の十二月という。

――江戸の沿海警備の負担が重かった川越藩。
アメリカのペリーが来航した際、上陸した地点の警備担当だったという川越藩。松平直侯の藩主就任後には、品川の台場も受け持ちもあった。
くわえて他家からの養子では、さらに気を遣うところが多い。
「…定めし、心労があったことだろう。」
実父は、水戸烈公・徳川斉昭。実兄は英明の誉れ高い、一橋慶喜。貢姫の夫・松平直侯は、様々な重圧に耐え続けたのか。その短い生涯を閉じたのだった。
(続く)
1861年(文久元年)の晩秋。鍋島直正は佐賀藩主を退き、閑叟(かんそう)と正式に号します。
幕府を守ろうとする“佐幕”派にも、尊攘(尊王攘夷)派からも注目される佐賀の殿様。まだ、四十代での隠居です。
「何か思惑があるのか…?」と周囲には様々な憶測が。
ご隠居としてのんびりするかと言えば、政局をにらんで自由に活動できる身分を求めたという見解もあります。
しかし、当時の直正(閑叟)は体調面に不安を抱え、心配事も増えていました。
〔参照:
――「おいは、三瀬に戻らんば。」
福岡脱藩の志士・平野国臣が言うところの「佐賀の三平」の1人。古賀一平には、三瀬街道の番人という役目がある。
「神陽先生は、随分と慎重ではなかね。」
古賀は勤王志士の話に乗らない、師匠・枝吉神陽の動きを訝(いぶか)しがる。
「古賀さん。神陽先生の事だ。ご存念があるのだろう。」
江藤新平とて、平野の熱い想いには感銘を受けた。
「…殿のご隠居を待っておられるかだな。」
大木喬任(民平)は、師匠の思惑を推し量っていた。
――この年、鍋島直正は、着々と隠居の段取りを進めてきた。
「佐賀が一体で動かば、世に与える力は大きいだろうな。」
大木は、淡々と続けた。
「やぐらしか(面倒)な事だ…。」
真っ直ぐな気性の古賀。挙藩一致を待つだけなのが、釈然としないようだ。
「焦らずとも、江戸には中野が居るゆえ。」
諸藩の志士たちとの連携。江藤は、親友・中野方蔵の動きへの期待を語る。
――「そうか、また中野から文(ふみ)が来たら知らせんね。」
「承知した。」
大木が言葉を返す。三瀬の番所は、城下からかなり北にある。古賀は、名残り惜しそうに2人と別れた。
「ああは言ったが、古賀さんの心配ももっともだ。佐賀は時勢に遅れつつある。」
「そこはお主が述べたように、我らには中野がいる。殿様も、じき動くだろう。」
大木は、わりに悠然と構えているように見えた。
――しかし、隠居後まもなく、鍋島直正には悩みが生じた。
すっかり寒くなった冬のある日。川越藩(埼玉)の江戸屋敷からの急報を見るや、直正(閑叟)の様子がおかしい。
「…いかがなさいましたか。」
直正の世話係にして、幼なじみ・古川与一(松根)が顔色をうかがう。
「川越の…直侯どのが…」
「まさか、」
「…ご逝去なさった。」
川越藩主・松平直侯は、直正の娘・貢姫の夫だ。
――明らかに顔色の悪い、直正。
「…お気をたしかに。」
古川与一が、心配げに声をかける。
「貢(みつ)の胸中が察されてならぬ…。」
直正は、若くして夫を亡くした愛娘の心痛を思った。生真面目な長女のことだ。きっと思い悩んでいるに違いない。
病気療養中だった松平直侯。亡くなったのは、文久元年の十二月という。

――江戸の沿海警備の負担が重かった川越藩。
アメリカのペリーが来航した際、上陸した地点の警備担当だったという川越藩。松平直侯の藩主就任後には、品川の台場も受け持ちもあった。
くわえて他家からの養子では、さらに気を遣うところが多い。
「…定めし、心労があったことだろう。」
実父は、水戸烈公・徳川斉昭。実兄は英明の誉れ高い、一橋慶喜。貢姫の夫・松平直侯は、様々な重圧に耐え続けたのか。その短い生涯を閉じたのだった。
(続く)
2021年12月11日
第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)
こんばんは。2周年の記事では、たくさんの方にお読みいただき、コメントをくださった方も。ありがとうございました。
“本編”を再開します。前回、登場した福岡の志士・平野国臣。平安・鎌倉期を思わせる古風な武士の姿。髭を蓄え、時代物の装束に志を込めた“さぶらい”。
諸国でも“尊王活動家”として一目置かれた存在だったそうで、薩摩(鹿児島)にも出入りし、西郷吉之助(隆盛)と深く関わっています。
1861年(文久元年)秋。佐賀を訪ねた福岡脱藩・平野国臣には、枝吉神陽との連携を図る目的があったそうです。
――福岡の“さぶらい”・平野と問答を続ける江藤新平。
無言で見守る大木喬任(民平)は、こう考えた。
「おそらく江藤、この男が気に入ったな…」
江藤は開明派だが、一本気で筋の通った“古武士”には好意的だ。
大木も服装に無頓着で古風な格好を真似しようとは思わないが、平野が語る「我こそは朝廷の臣!」という考え方には共感できる。

――平野との話に盛り上がる江藤、それを見守る大木。
時が過ぎている。最初から居た古賀一平が冷静になって気づいた。
「ここでは、いかんばい!お客人を別のところにお連れせんば。」
上機嫌で話し続ける、平野は快活に答えた。
「何処に行こうが、一向に構わぬぞ。」
「佐賀には、窮屈な掟(おきて)がございましてな。」
古賀が、師匠・枝吉神陽との面会の場所を別に用意するようだ。
持ち前の行動力で突き進んだ福岡脱藩の平野だが、江戸期の佐賀では旅人への規制が強く、立ち寄れる場所は限られる。面倒ごとは避けたいところだ。
――よく“義祭同盟”の会合で集う社にて。
「筑前(福岡)の平野と申す。神陽先生にお会いできて光栄だ。」
「平野どのの、ご令名(れいめい)は聞き及んでいる。」
堂内に姿を見せた枝吉神陽。江藤らの師匠でもあるが、佐賀の藩政にも関わりがある。さらに貫禄が増した。
かつての天皇親政の時代。朝廷を中心とする世を理想とするのは、両者とも。もはや幕府には、朝廷から政治を任される価値はないという見解も一致する。

――「古式に則り、“あるべき姿”へと戻す。」
「然(しか)り…、得心できることばかりだ。」
勤王の想いが強い古賀一平が、師匠と平野国臣の議論に感じ入っている。
「神陽先生。佐賀が勤王のはたらきを為せば“回天”すら為せるはず。」
平野の想いとしては、佐賀藩が決起すれば時代は動く。藩上層部と志士たちの双方に影響力がある、枝吉神陽の賛同を求めていた。
もはや薩摩の名君・島津斉彬はいない。残る実力者として、佐賀の鍋島直正の動向にも、自然と注目が集まっている。
――ここで、珍しく大木が口を挟んだ。
枝吉神陽は時勢を語る平野に共感を示すが、倒幕への決起話には乗らない。
「平野先生にお伺いするが、やはり福岡の黒田さまは動かぬか。」
大木は話の展開を察してか、福岡藩の事も聞くようだ。
「黒田の殿には幾度でも言上するが、まず我が身で事を為すほかあるまい。」
福岡藩(黒田家)にも意見をした平野。風変わりな提案を強引な手段で行ったので、処罰の対象となった。
むしろ福岡藩は平野の過激な言動と志士との人脈が、幕府から咎(とが)められると警戒。平野は脱藩をして浪人となり、よく藩の捕方から追われている。

――その場は、意見の交換に終わった。
「平野どの、近いうちに時節が来よう。」
枝吉神陽が、福岡の“さぶらい”・平野に包み込むような一声をかける。
「…神陽先生は、よき門下生を育てておられるな。」
平野が、枝吉神陽との別れ際に語る。
「三人とも名に“平”の字を持つ者。佐賀に“三平”あり!と言うべきか。」
平野の語る“三平”の1人目は、勤王の話に熱く、手配りの良い古賀一平。
――次に、鋭く問答を仕掛けてくるが、強い才気を感じる江藤新平。
そして、何を思うか判然としないが、様々な思考を巡らせる大木民平(喬任)。
平野の言葉を受けて、神陽がうなずく。
「佐賀の“三平”か。平野どのの言葉なれば、さぞ喜ぶだろう。」
「我は、勤王の同志を集め、佐賀が動くのを待っておりますぞ。」
「いずれ、お会いしよう。」
双方が低い声で挨拶をかわすと、平野は長崎街道の旅路へと戻った。
明日は何処に行くものか。枝吉神陽は、福岡からの脱藩者の背中を見送る。
「平野どの。心持ちは解る…だが、あまり急(せ)いてはならぬぞ。」
(続く)
“本編”を再開します。前回、登場した福岡の志士・平野国臣。平安・鎌倉期を思わせる古風な武士の姿。髭を蓄え、時代物の装束に志を込めた“さぶらい”。
諸国でも“尊王活動家”として一目置かれた存在だったそうで、薩摩(鹿児島)にも出入りし、西郷吉之助(隆盛)と深く関わっています。
1861年(文久元年)秋。佐賀を訪ねた福岡脱藩・平野国臣には、枝吉神陽との連携を図る目的があったそうです。
――福岡の“さぶらい”・平野と問答を続ける江藤新平。
無言で見守る大木喬任(民平)は、こう考えた。
「おそらく江藤、この男が気に入ったな…」
江藤は開明派だが、一本気で筋の通った“古武士”には好意的だ。
大木も服装に無頓着で古風な格好を真似しようとは思わないが、平野が語る「我こそは朝廷の臣!」という考え方には共感できる。

――平野との話に盛り上がる江藤、それを見守る大木。
時が過ぎている。最初から居た古賀一平が冷静になって気づいた。
「ここでは、いかんばい!お客人を別のところにお連れせんば。」
上機嫌で話し続ける、平野は快活に答えた。
「何処に行こうが、一向に構わぬぞ。」
「佐賀には、窮屈な掟(おきて)がございましてな。」
古賀が、師匠・枝吉神陽との面会の場所を別に用意するようだ。
持ち前の行動力で突き進んだ福岡脱藩の平野だが、江戸期の佐賀では旅人への規制が強く、立ち寄れる場所は限られる。面倒ごとは避けたいところだ。
――よく“義祭同盟”の会合で集う社にて。
「筑前(福岡)の平野と申す。神陽先生にお会いできて光栄だ。」
「平野どのの、ご令名(れいめい)は聞き及んでいる。」
堂内に姿を見せた枝吉神陽。江藤らの師匠でもあるが、佐賀の藩政にも関わりがある。さらに貫禄が増した。
かつての天皇親政の時代。朝廷を中心とする世を理想とするのは、両者とも。もはや幕府には、朝廷から政治を任される価値はないという見解も一致する。
――「古式に則り、“あるべき姿”へと戻す。」
「然(しか)り…、得心できることばかりだ。」
勤王の想いが強い古賀一平が、師匠と平野国臣の議論に感じ入っている。
「神陽先生。佐賀が勤王のはたらきを為せば“回天”すら為せるはず。」
平野の想いとしては、佐賀藩が決起すれば時代は動く。藩上層部と志士たちの双方に影響力がある、枝吉神陽の賛同を求めていた。
もはや薩摩の名君・島津斉彬はいない。残る実力者として、佐賀の鍋島直正の動向にも、自然と注目が集まっている。
――ここで、珍しく大木が口を挟んだ。
枝吉神陽は時勢を語る平野に共感を示すが、倒幕への決起話には乗らない。
「平野先生にお伺いするが、やはり福岡の黒田さまは動かぬか。」
大木は話の展開を察してか、福岡藩の事も聞くようだ。
「黒田の殿には幾度でも言上するが、まず我が身で事を為すほかあるまい。」
福岡藩(黒田家)にも意見をした平野。風変わりな提案を強引な手段で行ったので、処罰の対象となった。
むしろ福岡藩は平野の過激な言動と志士との人脈が、幕府から咎(とが)められると警戒。平野は脱藩をして浪人となり、よく藩の捕方から追われている。
――その場は、意見の交換に終わった。
「平野どの、近いうちに時節が来よう。」
枝吉神陽が、福岡の“さぶらい”・平野に包み込むような一声をかける。
「…神陽先生は、よき門下生を育てておられるな。」
平野が、枝吉神陽との別れ際に語る。
「三人とも名に“平”の字を持つ者。佐賀に“三平”あり!と言うべきか。」
平野の語る“三平”の1人目は、勤王の話に熱く、手配りの良い古賀一平。
――次に、鋭く問答を仕掛けてくるが、強い才気を感じる江藤新平。
そして、何を思うか判然としないが、様々な思考を巡らせる大木民平(喬任)。
平野の言葉を受けて、神陽がうなずく。
「佐賀の“三平”か。平野どのの言葉なれば、さぞ喜ぶだろう。」
「我は、勤王の同志を集め、佐賀が動くのを待っておりますぞ。」
「いずれ、お会いしよう。」
双方が低い声で挨拶をかわすと、平野は長崎街道の旅路へと戻った。
明日は何処に行くものか。枝吉神陽は、福岡からの脱藩者の背中を見送る。
「平野どの。心持ちは解る…だが、あまり急(せ)いてはならぬぞ。」
(続く)
2021年12月08日
「どうにか、2周年。」
こんばんは。
本日は“本編”をひと休み。『さがファンブログ』を始めて2周年となりました。
今までの人生の中で、あまり故郷を深く顧みて来なかった私。もっと若いうちに、佐賀の持つ価値に気づいていれば…と考えることも度々あります。
最近、ご覧になり始めた皆様へ。“本編”の合間に時折、私の心の叫びが入るのが、当ブログでよくある展開で、息抜きと思ってご覧いただければ幸いです。
――「どうして、お前はもっと佐賀を叫んでこなかった!」と問われれば…
私がブログを始めて丸2年となりましたが、普段の生活で「佐賀出身です!」と声高に言うことはありません。
「佐賀が、こがんすごかところやと思わんかったばってん。しょうのなかばい。」という経過もありますが、誇りは内に秘めるものだと思っています。
「“薩長土肥”とか言うけれど、肥前の佐賀は何をしたのかにゃ?」
一応は、歴史好きに分類されるはずの、しかも、佐賀出身者である私ですら、以前はこの程度の認識でした。

――いまなら「日本の近代化に関わるところに大体、佐賀の影あり!」とか答えそうです。
今年の大河ドラマ『青天を衝け』、大隈重信〔演:大倉孝二〕が色々と、“佐賀”を語っていたのが印象的でした。
「佐賀は日本一“洋学通”ぞ!」とか「“開化”のための費用はやむを得んばい」とか「やはり佐賀藩の出身者…」と納得できる言い回しがたくさんありました。
…たぶんこの辺りが、幕末期の佐賀藩で推すべきポイントなのです。何とか広く知られてほしい“薩長土肥”の肥前。佐賀藩の持つ魅力。
――いまの佐賀の若者への期待。
「佐賀は、何もなか田舎だもんね~」という認識を改めて、早く気づいてほしい。ここは地元で熱心に活動する方々が居て、もう大丈夫なのかもしれません。
むしろ問題は、全国各地とくに大都市圏での佐賀の存在感の向上でしょうか。「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現しても“視聴率”という指標が存在します。
佐賀藩が目指した“近代化”の志、きっと“現代”にも通じる何かがある。是が非でも、広く知られねば。
ここは全国各地の佐賀関係者にしかできない…任務(?)なのかもしれません。
――現実では、なかなか佐賀に帰れない私。
日々遠くから叫んでいます。新型コロナの状況を見る限りでは、今が“帰藩”の好機なのですが、いささか仕事の状態が…。
ちなみに“本編”では、序盤から長崎の方は時々出ていますが、前回は福岡の志士も登場しました。
佐賀を中心として、九州北部に響く話を作っていきたい。本当は思う存分に、現地取材をして書きたい願望がありますが、ほぼ“夢”に近いような話です。

――全国に伝わることを目指すには、まず近隣から。
佐賀から発して、長崎・福岡。それから本州へ。「幕末佐賀藩の大河ドラマ」なら“札幌を創った人”(島義勇)も登場するでしょうから、北海道まで届くはず。
最近は、充分な時間も使えない日々が続きます。才能が足りないなら、想いの強さで何とかしたい…ということで、3年目もなるべく頑張ります。
3周年を迎えるまでには、一度は佐賀に“帰藩”したいものです。
本日は“本編”をひと休み。『さがファンブログ』を始めて2周年となりました。
今までの人生の中で、あまり故郷を深く顧みて来なかった私。もっと若いうちに、佐賀の持つ価値に気づいていれば…と考えることも度々あります。
最近、ご覧になり始めた皆様へ。“本編”の合間に時折、私の心の叫びが入るのが、当ブログでよくある展開で、息抜きと思ってご覧いただければ幸いです。
――「どうして、お前はもっと佐賀を叫んでこなかった!」と問われれば…
私がブログを始めて丸2年となりましたが、普段の生活で「佐賀出身です!」と声高に言うことはありません。
「佐賀が、こがんすごかところやと思わんかったばってん。しょうのなかばい。」という経過もありますが、誇りは内に秘めるものだと思っています。
「“薩長土肥”とか言うけれど、肥前の佐賀は何をしたのかにゃ?」
一応は、歴史好きに分類されるはずの、しかも、佐賀出身者である私ですら、以前はこの程度の認識でした。
――いまなら「日本の近代化に関わるところに大体、佐賀の影あり!」とか答えそうです。
今年の大河ドラマ『青天を衝け』、大隈重信〔演:大倉孝二〕が色々と、“佐賀”を語っていたのが印象的でした。
「佐賀は日本一“洋学通”ぞ!」とか「“開化”のための費用はやむを得んばい」とか「やはり佐賀藩の出身者…」と納得できる言い回しがたくさんありました。
…たぶんこの辺りが、幕末期の佐賀藩で推すべきポイントなのです。何とか広く知られてほしい“薩長土肥”の肥前。佐賀藩の持つ魅力。
――いまの佐賀の若者への期待。
「佐賀は、何もなか田舎だもんね~」という認識を改めて、早く気づいてほしい。ここは地元で熱心に活動する方々が居て、もう大丈夫なのかもしれません。
むしろ問題は、全国各地とくに大都市圏での佐賀の存在感の向上でしょうか。「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現しても“視聴率”という指標が存在します。
佐賀藩が目指した“近代化”の志、きっと“現代”にも通じる何かがある。是が非でも、広く知られねば。
ここは全国各地の佐賀関係者にしかできない…任務(?)なのかもしれません。
――現実では、なかなか佐賀に帰れない私。
日々遠くから叫んでいます。新型コロナの状況を見る限りでは、今が“帰藩”の好機なのですが、いささか仕事の状態が…。
ちなみに“本編”では、序盤から長崎の方は時々出ていますが、前回は福岡の志士も登場しました。
佐賀を中心として、九州北部に響く話を作っていきたい。本当は思う存分に、現地取材をして書きたい願望がありますが、ほぼ“夢”に近いような話です。
――全国に伝わることを目指すには、まず近隣から。
佐賀から発して、長崎・福岡。それから本州へ。「幕末佐賀藩の大河ドラマ」なら“札幌を創った人”(島義勇)も登場するでしょうから、北海道まで届くはず。
最近は、充分な時間も使えない日々が続きます。才能が足りないなら、想いの強さで何とかしたい…ということで、3年目もなるべく頑張ります。
3周年を迎えるまでには、一度は佐賀に“帰藩”したいものです。
2021年12月05日
第17話「佐賀脱藩」⑧(福岡から来た“さぶらい”)
こんにちは。
鍋島直正が佐賀藩主を退き「閑叟(かんそう)」と、正式に号した(名乗った)のは、1861年(文久元年)の晩秋と言われます。
その同じ年の秋。直正の“隠居”1か月ばかり前の10月頃、佐賀城下に、古い時代から来たような不思議な来訪者がありました。

――師匠・枝吉神陽の家に向かっている。
佐賀城の堀端を南に行くのは、大木喬任(民平)と江藤新平。この日も、江戸に出た親友・中野方蔵の話題をしている。
「次に、中野からの便りはいつ来ると思うか。」
「また催促が来るでしょう。中野は、よほど大木さんを引っ張り出したいらしい。」
大木の問いかけに、江藤が予測を述べる。
「ところで、江藤。“熊太郎”は、元気か?」
「ああ、健やかにしている。“赤子”も可愛いものだ。」
――「やはりお主のような者でも、“父親の顔”になるのか。」
少々ひねくれた言い方をする大木に、江藤が苦笑する。
「子を持てば、親になる。これも理に適(かな)った事。」
「…左様(さよう)か!」
江藤が幸せになるのは、大木とて嬉しいが、ぶっきらぼうな反応も大木らしい。
前年の11月頃に、江藤は妻・千代子との間に子を授かり、一児の父となった。その長男の名は熊太郎といって、もうじき1歳となる。

――遠目に見える屋敷の門前に、2つの人影がある。
うち1人は江藤らの仲間で、古賀一平。もう1人は、見かけぬ風体の人物だ。
「あん(の)一人は、佐賀の者では無かごたな…。」
「ええ、古賀さんに何事かを説くと見える。」
二人の反応には理由があった。古賀と向き合う謎の男の格好が奇妙なのだ。烏帽子(えぼし)を頭に乗せ、直垂(ひたたれ)を着る…という古風さである。
――その装束は、まるで“絵巻物”にでも出てきそうだ。
幕末からでも七百年ほど前になるが、朝廷で主に皇族を守る武士たちが居た。貴人に「候(さぶら)う」ので、後に武士たちは“さぶらい”と呼ばれたという。
それが“侍”の語源だというが、謎の男の服装には、その雰囲気がある。時代がかった“謎のさぶらい”と対話する古賀は、楽しげに盛り上がっている。
ここで古賀が、大木と江藤が来たことに気づいた。
「福岡から、珍しか客人ったい!」

――もともと福岡藩士だという、“さぶらい”。
二人と目線が合うと“さぶらい”は仰々しく一礼をした。時代を錯誤した服装で目立つだけでなく、何やら人を惹きつける魅力もある。
「筑前(福岡)より出た者で、平野国臣と申す!」
豪快に名乗った。“福岡脱藩”の志士というのが、現在の肩書きと見える。
「江藤と申す。平野さまに問う。その“装束”の意味するところは何か。」
まず名乗り返すものの、いきなり問答を始める江藤。
――向かい合う双方とも、声は大きい。
「我は、国のために動いておる。それを示す装束と心得ておる。」
福岡から来た勤王の志士・平野国臣。古めかしい服装に、信念がある様子だ。
「自分こそは、朝廷を守る武士」という真っ直ぐな想い。それが、朝廷を中心に世の中が回った“古い時代”を身に纏(まと)う理由らしい。
「貴殿の志、理解に至った。」
質素な身なりの江藤。平野と違って、服装で“志”を示したりはしない。しかし、その想いには得心したようだ。
(続く)
鍋島直正が佐賀藩主を退き「閑叟(かんそう)」と、正式に号した(名乗った)のは、1861年(文久元年)の晩秋と言われます。
その同じ年の秋。直正の“隠居”1か月ばかり前の10月頃、佐賀城下に、古い時代から来たような不思議な来訪者がありました。
――師匠・枝吉神陽の家に向かっている。
佐賀城の堀端を南に行くのは、大木喬任(民平)と江藤新平。この日も、江戸に出た親友・中野方蔵の話題をしている。
「次に、中野からの便りはいつ来ると思うか。」
「また催促が来るでしょう。中野は、よほど大木さんを引っ張り出したいらしい。」
大木の問いかけに、江藤が予測を述べる。
「ところで、江藤。“熊太郎”は、元気か?」
「ああ、健やかにしている。“赤子”も可愛いものだ。」
――「やはりお主のような者でも、“父親の顔”になるのか。」
少々ひねくれた言い方をする大木に、江藤が苦笑する。
「子を持てば、親になる。これも理に適(かな)った事。」
「…左様(さよう)か!」
江藤が幸せになるのは、大木とて嬉しいが、ぶっきらぼうな反応も大木らしい。
前年の11月頃に、江藤は妻・千代子との間に子を授かり、一児の父となった。その長男の名は熊太郎といって、もうじき1歳となる。
――遠目に見える屋敷の門前に、2つの人影がある。
うち1人は江藤らの仲間で、古賀一平。もう1人は、見かけぬ風体の人物だ。
「あん(の)一人は、佐賀の者では無かごたな…。」
「ええ、古賀さんに何事かを説くと見える。」
二人の反応には理由があった。古賀と向き合う謎の男の格好が奇妙なのだ。烏帽子(えぼし)を頭に乗せ、直垂(ひたたれ)を着る…という古風さである。
――その装束は、まるで“絵巻物”にでも出てきそうだ。
幕末からでも七百年ほど前になるが、朝廷で主に皇族を守る武士たちが居た。貴人に「候(さぶら)う」ので、後に武士たちは“さぶらい”と呼ばれたという。
それが“侍”の語源だというが、謎の男の服装には、その雰囲気がある。時代がかった“謎のさぶらい”と対話する古賀は、楽しげに盛り上がっている。
ここで古賀が、大木と江藤が来たことに気づいた。
「福岡から、珍しか客人ったい!」
――もともと福岡藩士だという、“さぶらい”。
二人と目線が合うと“さぶらい”は仰々しく一礼をした。時代を錯誤した服装で目立つだけでなく、何やら人を惹きつける魅力もある。
「筑前(福岡)より出た者で、平野国臣と申す!」
豪快に名乗った。“福岡脱藩”の志士というのが、現在の肩書きと見える。
「江藤と申す。平野さまに問う。その“装束”の意味するところは何か。」
まず名乗り返すものの、いきなり問答を始める江藤。
――向かい合う双方とも、声は大きい。
「我は、国のために動いておる。それを示す装束と心得ておる。」
福岡から来た勤王の志士・平野国臣。古めかしい服装に、信念がある様子だ。
「自分こそは、朝廷を守る武士」という真っ直ぐな想い。それが、朝廷を中心に世の中が回った“古い時代”を身に纏(まと)う理由らしい。
「貴殿の志、理解に至った。」
質素な身なりの江藤。平野と違って、服装で“志”を示したりはしない。しかし、その想いには得心したようだ。
(続く)
2021年12月01日
第17話「佐賀脱藩」⑦(蘭学教師・大隈)
こんばんは。
前回、母・三井子に感激の涙で見送られ、蘭学寮に着くなり、顔見知りの重役である鍋島河内から声をかけられたり、何かと忙しい大隈八太郎(重信)。
学問に熱心な佐賀の殿様・鍋島直正は、よく藩の学校を訪れ、もちろん洋学を研究する“蘭学寮”にも訪れたといいます。
大隈にとっては、オランダ語で学んだ西洋の知識を、殿に講義する晴れ舞台が、そこにありました。
――大隈の講義を聞く、殿・鍋島直正。
大隈は話が上手いうえ、準備も万端だ。殿の興味を引く話を続ける。
「こうしてオランダでは“憲法”が諸法度(はっと)の上に立つのであります…」
殿・直正は“うむ”とばかりにうなずいた。
「大隈よ。そなたの話、なかなかに面白い。」
「ありがたき、幸せ!」
よし、殿にもご満足いただける講義だっただろう。大隈はそう思った。

――しかし、佐賀の殿様の学習意欲が高い。
次の直正の発言から、大隈の想定を超えた事態が起きる。
「いや、興味深いぞ…!もう少し、聞きたいものだ。」
「…!」
小出千之助や石丸安世(虎五郎)といった“達人級”に比べ、語学力では一歩劣る大隈。準備できていない部分を、即興で読み解き、説明するのは困難だ。
「では、続きを訳せ。」
“生徒”から教師への言葉としては奇妙だが、これは殿様からの指示なのだ。
「…いや、“洋書”は訳せばよいというものではございませぬ。」
――ここは弁舌で“窮地”の脱出を図る、大隈八太郎。
「西洋の文物は、その背景まで知りてこそ。殿に講ずるならば、なおの事。」
大隈は、言葉を続ける。
「半端なる、お教えはいたしかねます。他日に、機会を賜りたく存じます。」
「…そこまで申すなら、日を改めよう。より一層、励むとよいぞ。」
本日はもっと勉強したかったが…、そんな表情の直正だった。
「はは―っ!」
そして、冷や汗をかく大隈だった。

――大隈が退出した後、城まで戻った直正。
「殿、お呼びにございますか。」
側近・古川松根(与一)が、殿様が居る書院に姿を見せる。
「やはり、ゆるりと学問をするのは良いものだな。」
「仰せになっていた…隠居の件に、ございますか。」
鍋島直正は、跡継ぎの直大(茂実)に、藩主の座を譲る段取りを進めていた。
「さすが与一だ。語らずともわかってくれるのだな。」
「長年の、お付き合いにて。」
古川が屈託なく言葉を返す。幼児期からずっと一緒の主従だ。ここから半年が過ぎた、晩秋に鍋島直正は佐賀藩主を退き、“隠居”をすることになる。
(続く)
前回、母・三井子に感激の涙で見送られ、蘭学寮に着くなり、顔見知りの重役である鍋島河内から声をかけられたり、何かと忙しい大隈八太郎(重信)。
学問に熱心な佐賀の殿様・鍋島直正は、よく藩の学校を訪れ、もちろん洋学を研究する“蘭学寮”にも訪れたといいます。
大隈にとっては、オランダ語で学んだ西洋の知識を、殿に講義する晴れ舞台が、そこにありました。
――大隈の講義を聞く、殿・鍋島直正。
大隈は話が上手いうえ、準備も万端だ。殿の興味を引く話を続ける。
「こうしてオランダでは“憲法”が諸法度(はっと)の上に立つのであります…」
殿・直正は“うむ”とばかりにうなずいた。
「大隈よ。そなたの話、なかなかに面白い。」
「ありがたき、幸せ!」
よし、殿にもご満足いただける講義だっただろう。大隈はそう思った。
――しかし、佐賀の殿様の学習意欲が高い。
次の直正の発言から、大隈の想定を超えた事態が起きる。
「いや、興味深いぞ…!もう少し、聞きたいものだ。」
「…!」
小出千之助や石丸安世(虎五郎)といった“達人級”に比べ、語学力では一歩劣る大隈。準備できていない部分を、即興で読み解き、説明するのは困難だ。
「では、続きを訳せ。」
“生徒”から教師への言葉としては奇妙だが、これは殿様からの指示なのだ。
「…いや、“洋書”は訳せばよいというものではございませぬ。」
――ここは弁舌で“窮地”の脱出を図る、大隈八太郎。
「西洋の文物は、その背景まで知りてこそ。殿に講ずるならば、なおの事。」
大隈は、言葉を続ける。
「半端なる、お教えはいたしかねます。他日に、機会を賜りたく存じます。」
「…そこまで申すなら、日を改めよう。より一層、励むとよいぞ。」
本日はもっと勉強したかったが…、そんな表情の直正だった。
「はは―っ!」
そして、冷や汗をかく大隈だった。
――大隈が退出した後、城まで戻った直正。
「殿、お呼びにございますか。」
側近・古川松根(与一)が、殿様が居る書院に姿を見せる。
「やはり、ゆるりと学問をするのは良いものだな。」
「仰せになっていた…隠居の件に、ございますか。」
鍋島直正は、跡継ぎの直大(茂実)に、藩主の座を譲る段取りを進めていた。
「さすが与一だ。語らずともわかってくれるのだな。」
「長年の、お付き合いにて。」
古川が屈託なく言葉を返す。幼児期からずっと一緒の主従だ。ここから半年が過ぎた、晩秋に鍋島直正は佐賀藩主を退き、“隠居”をすることになる。
(続く)




