2021年11月10日
第17話「佐賀脱藩」①(対馬事件の顛末)
こんばんは。
今まで「長崎」(第1話)と「江戸」(第15話)の地名はタイトルに付けていますが、第17話は初めて「佐賀」の名を冠する話で、大事なエピソードになる予定です。
まずは、第16話「攘夷沸騰」の続きからスタートです。少し説明的な言い方だと「ロシア軍艦(ポサドニック号)対馬占領事件」が、軸になった話でした。
佐賀藩が幕府から預かった蒸気船・観光丸で、外国奉行・小栗忠順に同行し、対馬に上陸した佐野常民(栄寿左衛門)。
事件中に、佐賀藩は複数の蒸気船で周辺海域の警戒にあたっていました。佐野も、拠点である佐賀の三重津海軍所へと戻ってきます。

――1861年(文久元年)秋。
あまり芳しくない天気だ。佐賀平野には、低い曇り空が広がっている。佐賀海軍の基地である三重津から佐賀城へは、さほどの距離は無い。
働き者の佐野は一息入れずに城へと向かう。任務の完了を報告するためだ。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑲(強くなりたいものだ)〕
「佐野、ご苦労であったな。」
「はっ。勿体(もったい)なき、お言葉。」
――佐賀の殿様・鍋島直正が、佐野の労をねぎらう。
殿・直正は胃の具合が良くないらしく、少し痩せた様子。以前より老けて見える。まず、佐野は見た限りの現地の様子を説明した。
「当面の危難は去ったか。ほかに奉行の小栗どのは、何か申されておったか。」
声色はいつも通りの殿だ。その問いかけに、佐野はこう答える。
「公儀(幕府)役人は怠惰に時を過ごす者が多い…と嘆いておられました。」
小栗の言い方では「食っては出すだけ…」と言おうか、もっと、辛辣(しんらつ)だったが、佐野は、ほとほどに再現した。

――直正は、片手の扇子をひらひらとする。
とくに暑いという時節でもない。何か想う事がある様子だった。
開国で、さらに“国際化”の進む長崎港。“日本の表玄関”の警備という役割は、異国からの“矢面”にたっているようなものだ。
殿・直正は責務を重く受け止めて、諸外国の動きに神経を遣う。
――幕府からも、直正の影響力への期待がある。
一方、各地での攘夷運動と、諸外国との軋轢(あつれき)も気になる。いま、佐賀藩の東隣・対馬藩の田代領では、事件の余波で攘夷派が意気盛んだという。
〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」⑳(基山の誇り、田代の想い)〕
考える事の多い佐賀藩主・直正。やや不敵な笑みをたたえ、こうつぶやいた。
「余も、そろそろ少し楽をしたいと思うぞ。」
佐野はその言葉を、真っ正面から受け止めた。
「殿は、この国にとって大事な御方。そのように弱気な事を…」

真面目な佐野の返答。何が可笑しいのか、少し上機嫌な殿様。
「まぁ良い。此度(こたび)は英国が、対馬の件に手を貸したわけじゃが。」
「はっ、もしイギリスの介入が無くば…どうなったか。助かったと言うべきかと。」
――直正の表情が「実はな…」という感じに一瞬で変わる。
「その英国にも、対馬を乗っ取る野心があったそうじゃ。」
「イギリスも油断のならぬところが…、考え得ることにございます。」
対馬には英国公使オールコックが交渉に乗り込んだ。ロシアは外交問題となるのを恐れて退去した。しかしイギリスにも対馬に入り込む計画があったという。
佐野は、占領を狙ったロシアの国旗が翻る現場を見ている。イギリスの動きは、実際に目にしていないが、そちらにも野心があったと聞くと得心がいく。
列強がひしめく日本近海を守っていくのは容易ではない。佐野は、そんな話を聞くと、また肝が冷えた。
(続く)
今まで「長崎」(第1話)と「江戸」(第15話)の地名はタイトルに付けていますが、第17話は初めて「佐賀」の名を冠する話で、大事なエピソードになる予定です。
まずは、第16話「攘夷沸騰」の続きからスタートです。少し説明的な言い方だと「ロシア軍艦(ポサドニック号)対馬占領事件」が、軸になった話でした。
佐賀藩が幕府から預かった蒸気船・観光丸で、外国奉行・小栗忠順に同行し、対馬に上陸した佐野常民(栄寿左衛門)。
事件中に、佐賀藩は複数の蒸気船で周辺海域の警戒にあたっていました。佐野も、拠点である佐賀の三重津海軍所へと戻ってきます。
――1861年(文久元年)秋。
あまり芳しくない天気だ。佐賀平野には、低い曇り空が広がっている。佐賀海軍の基地である三重津から佐賀城へは、さほどの距離は無い。
働き者の佐野は一息入れずに城へと向かう。任務の完了を報告するためだ。
〔参照:
「佐野、ご苦労であったな。」
「はっ。勿体(もったい)なき、お言葉。」
――佐賀の殿様・鍋島直正が、佐野の労をねぎらう。
殿・直正は胃の具合が良くないらしく、少し痩せた様子。以前より老けて見える。まず、佐野は見た限りの現地の様子を説明した。
「当面の危難は去ったか。ほかに奉行の小栗どのは、何か申されておったか。」
声色はいつも通りの殿だ。その問いかけに、佐野はこう答える。
「公儀(幕府)役人は怠惰に時を過ごす者が多い…と嘆いておられました。」
小栗の言い方では「食っては出すだけ…」と言おうか、もっと、辛辣(しんらつ)だったが、佐野は、ほとほどに再現した。
――直正は、片手の扇子をひらひらとする。
とくに暑いという時節でもない。何か想う事がある様子だった。
開国で、さらに“国際化”の進む長崎港。“日本の表玄関”の警備という役割は、異国からの“矢面”にたっているようなものだ。
殿・直正は責務を重く受け止めて、諸外国の動きに神経を遣う。
――幕府からも、直正の影響力への期待がある。
一方、各地での攘夷運動と、諸外国との軋轢(あつれき)も気になる。いま、佐賀藩の東隣・対馬藩の田代領では、事件の余波で攘夷派が意気盛んだという。
〔参照(後半):
考える事の多い佐賀藩主・直正。やや不敵な笑みをたたえ、こうつぶやいた。
「余も、そろそろ少し楽をしたいと思うぞ。」
佐野はその言葉を、真っ正面から受け止めた。
「殿は、この国にとって大事な御方。そのように弱気な事を…」
真面目な佐野の返答。何が可笑しいのか、少し上機嫌な殿様。
「まぁ良い。此度(こたび)は英国が、対馬の件に手を貸したわけじゃが。」
「はっ、もしイギリスの介入が無くば…どうなったか。助かったと言うべきかと。」
――直正の表情が「実はな…」という感じに一瞬で変わる。
「その英国にも、対馬を乗っ取る野心があったそうじゃ。」
「イギリスも油断のならぬところが…、考え得ることにございます。」
対馬には英国公使オールコックが交渉に乗り込んだ。ロシアは外交問題となるのを恐れて退去した。しかしイギリスにも対馬に入り込む計画があったという。
佐野は、占領を狙ったロシアの国旗が翻る現場を見ている。イギリスの動きは、実際に目にしていないが、そちらにも野心があったと聞くと得心がいく。
列強がひしめく日本近海を守っていくのは容易ではない。佐野は、そんな話を聞くと、また肝が冷えた。
(続く)
2021年11月13日
第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)
こんばんは。前回の続きです。
対外危機の当事者となったことで、佐賀藩の東隣にある田代領(現在の基山町と鳥栖市東部)を含め対馬藩は攘夷を唱える若者たちの動きが活発となります。
一方で、佐賀藩は警備の負担は大きくとも、長崎ではオランダとの交易に熱心だったので、外国全体の排斥を叫ぶような“攘夷”とは距離を置いていました。
1861年(文久元年)の冬~夏まで続いた対馬事件。その際、佐賀藩士が操る蒸気船が慌ただしく行き交った、伊万里の沿海も、平穏を取り戻しています。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕
――丘の上から、海を見つめる野良着の男性。
傍で跳びはねる雉(きじ)猫が、ニャーニャーと騒がしい。
その男、嬉野方面から伊万里まで陶磁器を運ぶ“人足”の風体をしているが、正体は、英国船の偵察を任務とする蓮池藩(※)の侍。※佐賀にある支藩の1つ
一言でいえば、蓮池藩領・嬉野から来た“忍者”であり、野良着は調査のための変装である。見た目は普通の中年で西洋の事情に通じる人物とはわからない。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑩(英国船の行方)〕

――「何ね。あんたは、また来たとね。」
そんな“嬉野の忍者”・古賀、高台に登ってきた若者と目を合わせる。佐賀藩の上佐賀代官所に務める下級武士・江藤新平である。
「きっと貴方が、ここで海を見ていると考えたゆえ、参った。」
江藤の真っ直ぐな視線、よく通る声は相変わらずだ。
…古賀の傍らでキジ猫は声に驚いたか、耳をピクッと動かし黒目を大きくする。
――すぐさま、本題を語り始めた江藤。
「対馬の一角をロシアが占有せる件、イギリスが介入したと聞く。」
「…こがん(このような)ところに来ても、何も見えんとよ。」
すでに“対馬事件”は、ひとまずの解決をみていた。イギリス軍艦が近海で圧力をかけたことにより、停泊したロシア船は対馬を退去したのである。
――この5年ほど前、1856(安政三)年。江藤は“図海策”を著す。
この意見書で、早々と開国の必要性を書いた江藤。「北方(蝦夷地)の開拓」でロシアに備え、「身分に関わらず人材を登用」し、「異国と通商すべし」と説いた。
単純な開国でもなく、目先の攘夷でもない。国力を付け、列強に対抗する想い。ただ、為すべき事はわかっても、江藤の身分からでは“届かない”のだ。
「急ぐのはわかるばってん…、今は力ば蓄えるべき時じゃなかね。」
古賀の語る横では、キジ猫が平らな木肌を見つけ、ガリガリと爪(つめ)を研ぐ。

――当時の江藤には、いくつかの打診があった。
1つは英語の修得。もう1つは貿易への従事だ。佐賀藩は人材の登用には熱心であり、江藤の才能は認められつつあった。
「“英語”に”通商”とは…また兄さんは、随分と見込まれとるばい。」
長崎港にも佐賀本藩にも姿を見せる“嬉野の忍者”・古賀。不思議な立ち位置の人物だ。「せっかくの藩の期待だ。ありがたく受け止めておけ…」と勧める。
しかし、江藤の返す言葉には、やや焦りが見えた。
「されど、安穏と日々を過ごすことは、時勢が許さぬと心得る。」
――親友・中野方蔵が伝える江戸の姿…
時代が動く気配がある。幕府や雄藩から注目される、佐賀の殿様・鍋島直正がどう動くかは、国の行方をも左右するはずだ。
江藤の意見書での想いも、佐賀藩では活かせる道もある。年配者らしく古賀が諭したように、普通の才の持ち主ならば、順風満帆の展開に喜ぶところだろう。
だが、非凡な才を持ったこの若者には運命の急転が待っていた。江藤が佐賀を発つことを決断するまで、この時、すでに残り1年を切っていたのである。
(続く)
対外危機の当事者となったことで、佐賀藩の東隣にある田代領(現在の基山町と鳥栖市東部)を含め対馬藩は攘夷を唱える若者たちの動きが活発となります。
一方で、佐賀藩は警備の負担は大きくとも、長崎ではオランダとの交易に熱心だったので、外国全体の排斥を叫ぶような“攘夷”とは距離を置いていました。
1861年(文久元年)の冬~夏まで続いた対馬事件。その際、佐賀藩士が操る蒸気船が慌ただしく行き交った、伊万里の沿海も、平穏を取り戻しています。
〔参照:
――丘の上から、海を見つめる野良着の男性。
傍で跳びはねる雉(きじ)猫が、ニャーニャーと騒がしい。
その男、嬉野方面から伊万里まで陶磁器を運ぶ“人足”の風体をしているが、正体は、英国船の偵察を任務とする蓮池藩(※)の侍。※佐賀にある支藩の1つ
一言でいえば、蓮池藩領・嬉野から来た“忍者”であり、野良着は調査のための変装である。見た目は普通の中年で西洋の事情に通じる人物とはわからない。
〔参照:
――「何ね。あんたは、また来たとね。」
そんな“嬉野の忍者”・古賀、高台に登ってきた若者と目を合わせる。佐賀藩の上佐賀代官所に務める下級武士・江藤新平である。
「きっと貴方が、ここで海を見ていると考えたゆえ、参った。」
江藤の真っ直ぐな視線、よく通る声は相変わらずだ。
…古賀の傍らでキジ猫は声に驚いたか、耳をピクッと動かし黒目を大きくする。
――すぐさま、本題を語り始めた江藤。
「対馬の一角をロシアが占有せる件、イギリスが介入したと聞く。」
「…こがん(このような)ところに来ても、何も見えんとよ。」
すでに“対馬事件”は、ひとまずの解決をみていた。イギリス軍艦が近海で圧力をかけたことにより、停泊したロシア船は対馬を退去したのである。
――この5年ほど前、1856(安政三)年。江藤は“図海策”を著す。
この意見書で、早々と開国の必要性を書いた江藤。「北方(蝦夷地)の開拓」でロシアに備え、「身分に関わらず人材を登用」し、「異国と通商すべし」と説いた。
単純な開国でもなく、目先の攘夷でもない。国力を付け、列強に対抗する想い。ただ、為すべき事はわかっても、江藤の身分からでは“届かない”のだ。
「急ぐのはわかるばってん…、今は力ば蓄えるべき時じゃなかね。」
古賀の語る横では、キジ猫が平らな木肌を見つけ、ガリガリと爪(つめ)を研ぐ。
――当時の江藤には、いくつかの打診があった。
1つは英語の修得。もう1つは貿易への従事だ。佐賀藩は人材の登用には熱心であり、江藤の才能は認められつつあった。
「“英語”に”通商”とは…また兄さんは、随分と見込まれとるばい。」
長崎港にも佐賀本藩にも姿を見せる“嬉野の忍者”・古賀。不思議な立ち位置の人物だ。「せっかくの藩の期待だ。ありがたく受け止めておけ…」と勧める。
しかし、江藤の返す言葉には、やや焦りが見えた。
「されど、安穏と日々を過ごすことは、時勢が許さぬと心得る。」
――親友・中野方蔵が伝える江戸の姿…
時代が動く気配がある。幕府や雄藩から注目される、佐賀の殿様・鍋島直正がどう動くかは、国の行方をも左右するはずだ。
江藤の意見書での想いも、佐賀藩では活かせる道もある。年配者らしく古賀が諭したように、普通の才の持ち主ならば、順風満帆の展開に喜ぶところだろう。
だが、非凡な才を持ったこの若者には運命の急転が待っていた。江藤が佐賀を発つことを決断するまで、この時、すでに残り1年を切っていたのである。
(続く)
2021年11月16日
第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)
こんばんは。前回の続きです。
1861年(文久元年)。徳川政権は、権威を回復する方法を模索していました。先年の“桜田門外の変”の後に、幕政の中枢を担ったのは、老中・安藤信正。
安藤を中心とした幕閣により“公武合体”が進められます。その象徴的な計画が、時の帝、孝明天皇の妹・和宮と第14代将軍・徳川家茂との“縁談”です。
江戸時代を通じて、幕府の法度(法令)により、朝廷は抑え込まれていましたが、幕末期には、その存在感を発揮していました。
――そんな国政の中枢から遠く離れて…肥前国・佐賀。
「江藤、お主に“良き知らせ”がある。心して聞くがよい。」
“上佐賀奉行所”の役人として働く江藤新平が上役に呼ばれる。表の働きぶりが認められたか、裏で江藤の才能を知る誰かが動いたのか…定かではない。
江藤は、次年に貿易部門・代品方へと移ることが決まる。あわせて、英語を研修するように藩からの指示もあった。

――佐賀城下の夕暮れ。よく集会に使う、お社にて。
「ようやく、江藤の運も開けてきた…と思ってよかな。」
2つばかり年上の大木喬任(民平)がニッと笑う。普段は、無口でぶっきらぼうなところもあるが、友達想いの“兄貴分”というところもある。
大木は漢学を主に勉強するが、江藤が西洋の語学と交易に関わるのは好機だと思っている様子がうかがえる。友の立身出世への道になると予想するからだ。
「本日は、我らが期待の中野君からの文(ふみ)も来ているぞ。」
酒も入っていないのに、やけに上機嫌な大木。もったいぶって江戸からの手紙を取り出した。あまり口が上手い方ではないが、いつになく楽しげに話す。
――2人にとって親友である、中野方蔵。いまは、江戸にいる。
いつも活き活きとした口調の中野らしく、手紙に記された文字からも、江戸での充実した日々が伝わるようだ。
「さて、大木兄さん、江藤くん…皆様、息災でしょうか。」
中野はいつも“志”を持って走っている。この手紙も、そんな弾んだ息づかいのまま書き記したのだろう。良い意味で、字が躍っている。

――その宵は、冴えた月夜となった佐賀城下。
大木・江藤の周りには、いつの間にか“義祭同盟”などで関わる友人も集まる。江戸にいる中野からの便りには、皆、興味を引かれるようだ。
「古賀に、坂井か…また、えらく集まってきたな。」
一同は、大木が引くぐらいに手紙に注目する。
ここでの“古賀”は、古賀一平という若手藩士。前回も登場した“嬉野の忍者”とは別人だ。もう1人は坂井辰之允という名だ。江藤とも親しい。
――何かと集まるのは、佐賀で“勤王”を目指す同志たち。
「わりと人数が多くなったな…江藤、読んでやってくれ。」
大木が、声の通る江藤に代読を託そうとする。
「たまには、大木さんが読み上げてみては。」
「江藤…、知っているだろう。俺はこういうのは、不得手だ。」
珍しく笑みを浮かべる江藤。それを、苦笑しながら返す大木。まるで少年のようだ。この2人がこのような表情を見せるのは珍しい。
――とにかく、親友・中野の活躍が嬉しいのだ。
「…昨今では“有為の者”たちと、時勢を語らいます。」
期待どおり、よく通る声で手紙の代読を始める、江藤。
この頃の中野は、江戸で“勤王”に熱心な学者や、他藩の志士たちとの交流を進めていた。
(続く)
1861年(文久元年)。徳川政権は、権威を回復する方法を模索していました。先年の“桜田門外の変”の後に、幕政の中枢を担ったのは、老中・安藤信正。
安藤を中心とした幕閣により“公武合体”が進められます。その象徴的な計画が、時の帝、孝明天皇の妹・和宮と第14代将軍・徳川家茂との“縁談”です。
江戸時代を通じて、幕府の法度(法令)により、朝廷は抑え込まれていましたが、幕末期には、その存在感を発揮していました。
――そんな国政の中枢から遠く離れて…肥前国・佐賀。
「江藤、お主に“良き知らせ”がある。心して聞くがよい。」
“上佐賀奉行所”の役人として働く江藤新平が上役に呼ばれる。表の働きぶりが認められたか、裏で江藤の才能を知る誰かが動いたのか…定かではない。
江藤は、次年に貿易部門・代品方へと移ることが決まる。あわせて、英語を研修するように藩からの指示もあった。
――佐賀城下の夕暮れ。よく集会に使う、お社にて。
「ようやく、江藤の運も開けてきた…と思ってよかな。」
2つばかり年上の大木喬任(民平)がニッと笑う。普段は、無口でぶっきらぼうなところもあるが、友達想いの“兄貴分”というところもある。
大木は漢学を主に勉強するが、江藤が西洋の語学と交易に関わるのは好機だと思っている様子がうかがえる。友の立身出世への道になると予想するからだ。
「本日は、我らが期待の中野君からの文(ふみ)も来ているぞ。」
酒も入っていないのに、やけに上機嫌な大木。もったいぶって江戸からの手紙を取り出した。あまり口が上手い方ではないが、いつになく楽しげに話す。
――2人にとって親友である、中野方蔵。いまは、江戸にいる。
いつも活き活きとした口調の中野らしく、手紙に記された文字からも、江戸での充実した日々が伝わるようだ。
「さて、大木兄さん、江藤くん…皆様、息災でしょうか。」
中野はいつも“志”を持って走っている。この手紙も、そんな弾んだ息づかいのまま書き記したのだろう。良い意味で、字が躍っている。
――その宵は、冴えた月夜となった佐賀城下。
大木・江藤の周りには、いつの間にか“義祭同盟”などで関わる友人も集まる。江戸にいる中野からの便りには、皆、興味を引かれるようだ。
「古賀に、坂井か…また、えらく集まってきたな。」
一同は、大木が引くぐらいに手紙に注目する。
ここでの“古賀”は、古賀一平という若手藩士。前回も登場した“嬉野の忍者”とは別人だ。もう1人は坂井辰之允という名だ。江藤とも親しい。
――何かと集まるのは、佐賀で“勤王”を目指す同志たち。
「わりと人数が多くなったな…江藤、読んでやってくれ。」
大木が、声の通る江藤に代読を託そうとする。
「たまには、大木さんが読み上げてみては。」
「江藤…、知っているだろう。俺はこういうのは、不得手だ。」
珍しく笑みを浮かべる江藤。それを、苦笑しながら返す大木。まるで少年のようだ。この2人がこのような表情を見せるのは珍しい。
――とにかく、親友・中野の活躍が嬉しいのだ。
「…昨今では“有為の者”たちと、時勢を語らいます。」
期待どおり、よく通る声で手紙の代読を始める、江藤。
この頃の中野は、江戸で“勤王”に熱心な学者や、他藩の志士たちとの交流を進めていた。
(続く)
2021年11月19日
第17話「佐賀脱藩」④(上方からの“花嫁”)
こんばんは。
佐賀城下の一角。月が冴える宵闇に、ある社(やしろ)に集まる若手藩士たち。
「一体、何の企てが…」と言いたいところですが、この時点では「都会に出た友達の手紙に盛り上がっているだけ」という状況です。
少し場面解説ですが、この手紙により、舞台は佐賀から江戸(東京)へと展開。登場人物も、佐賀藩から唐津藩(こちらも、現・佐賀県)へと一時的に移ります。
――江戸にいる、中野方蔵から来た手紙。
代読を続ける江藤新平の声が、月夜の杜(もり)に響く。
「公儀(幕府)には畏れ多くも、皇女さまを江戸にお連れ奉る動きあり…」
老中・安藤信正が計画する、孝明天皇の妹・和宮の江戸への降嫁。まだ若い、第14代将軍・徳川家茂の正室に“皇女”を迎え、朝廷の権威を取り入れる。
そして“公武合体”の名のもとに、幕府が朝廷と一体に動くことができれば、尊王攘夷派から、幕政が非難されにくくなる効果が期待できる。
――中野も、江戸で他藩の志士たちと一緒に憤る。
「これは、ご老中の謀(はかりごと)。姑息(こそく)な振舞いと存じます。」
傍らで、江藤の代読を聞いている仲間たちからも声が上がる。
「おおっ、そうたいっ!けしからんばい!」
「大橋先生、曰(いわ)く!」
少しの間、ざわざわとしたが、再び江藤が手紙を読み始めると、皆がその声に集中する。“大橋”とは、著名な江戸の学者だという。

――その儒学者・大橋訥庵は、この件に怒り心頭。
中野も、大橋が主宰する江戸市中の塾に出入りがあった。そこには「老中の陰謀を打ち砕け」とばかりに、過激な事を口走る“志士”も集まる様子だ。
「そうたい!」
佐賀の志士たちもいちいち合いの手を入れたくなる、熱い“勤王“の話が続く。
「長州の久坂くんなどは、こう語る!」
江藤の代読に、中野が交流している長州藩士の名が登場した。
――長州(山口)の俊才・久坂玄瑞。
吉田松陰の妹・文(ふみ)の夫で、松陰の主宰する塾で最も優秀とされた1人。
1859(安政六)年。“安政の大獄”で捕らえられた、久坂の師匠・吉田松陰は、役人の調べに対して「老中の暗殺を計画していた」と、あえて申し出たらしい。
この自白をしたことで、師は“刑場の露”と消えたが、その教えは数年のうちに、弟子・久坂の手腕により“伝説”を帯びたものとなっていく。
――中野の手紙には、才能ある志士たちが次々と現れる。
「すごか者(もん)が居るな。やはり江戸に、出らんばならんか。」
江藤らの友人・古賀一平が腕組みをしながら、発言をする。
「いや、さすがは中野…と言うべきでは無かね?」
集った仲間の一人・坂井辰之允は、江戸で他藩との人脈を築いていく中野方蔵の行動力に感心している。

――同じ時期に、幕府の中枢・江戸城内では
老中・安藤信正は、志士たちが憤慨する“皇女・和宮の降嫁”の支度に忙しい。前代未聞の大行列が、京から江戸への道を練り歩き、新しい時代を示すのだ。
「皇女さまを江戸にお迎えすること。いまや公儀(幕府)の命運がかかっておる。」
和宮の京からの降嫁には、巨額の費用を計上する。幕府と朝廷が一体と示すための“一大行事”は着々と進んでいた。
――幕政の建て直しに励む、老中・安藤信正。
大老・井伊直弼の亡き後、政権の運営は不安定であり、外国人への襲撃など物騒な事件が相次ぐ。豪腕と呼ばれた井伊大老とは違う、調整型の安藤老中。
苦闘する老中・安藤。これから幕閣の1人となる者がその背中を見つめていた。
唐津藩の若殿(藩主名代)で、名を小笠原長行という。参勤交代により、江戸に来たばかり。小笠原もまた、幕府で期待される“開明派”だった。
(続く)
佐賀城下の一角。月が冴える宵闇に、ある社(やしろ)に集まる若手藩士たち。
「一体、何の企てが…」と言いたいところですが、この時点では「都会に出た友達の手紙に盛り上がっているだけ」という状況です。
少し場面解説ですが、この手紙により、舞台は佐賀から江戸(東京)へと展開。登場人物も、佐賀藩から唐津藩(こちらも、現・佐賀県)へと一時的に移ります。
――江戸にいる、中野方蔵から来た手紙。
代読を続ける江藤新平の声が、月夜の杜(もり)に響く。
「公儀(幕府)には畏れ多くも、皇女さまを江戸にお連れ奉る動きあり…」
老中・安藤信正が計画する、孝明天皇の妹・和宮の江戸への降嫁。まだ若い、第14代将軍・徳川家茂の正室に“皇女”を迎え、朝廷の権威を取り入れる。
そして“公武合体”の名のもとに、幕府が朝廷と一体に動くことができれば、尊王攘夷派から、幕政が非難されにくくなる効果が期待できる。
――中野も、江戸で他藩の志士たちと一緒に憤る。
「これは、ご老中の謀(はかりごと)。姑息(こそく)な振舞いと存じます。」
傍らで、江藤の代読を聞いている仲間たちからも声が上がる。
「おおっ、そうたいっ!けしからんばい!」
「大橋先生、曰(いわ)く!」
少しの間、ざわざわとしたが、再び江藤が手紙を読み始めると、皆がその声に集中する。“大橋”とは、著名な江戸の学者だという。
――その儒学者・大橋訥庵は、この件に怒り心頭。
中野も、大橋が主宰する江戸市中の塾に出入りがあった。そこには「老中の陰謀を打ち砕け」とばかりに、過激な事を口走る“志士”も集まる様子だ。
「そうたい!」
佐賀の志士たちもいちいち合いの手を入れたくなる、熱い“勤王“の話が続く。
「長州の久坂くんなどは、こう語る!」
江藤の代読に、中野が交流している長州藩士の名が登場した。
――長州(山口)の俊才・久坂玄瑞。
吉田松陰の妹・文(ふみ)の夫で、松陰の主宰する塾で最も優秀とされた1人。
1859(安政六)年。“安政の大獄”で捕らえられた、久坂の師匠・吉田松陰は、役人の調べに対して「老中の暗殺を計画していた」と、あえて申し出たらしい。
この自白をしたことで、師は“刑場の露”と消えたが、その教えは数年のうちに、弟子・久坂の手腕により“伝説”を帯びたものとなっていく。
――中野の手紙には、才能ある志士たちが次々と現れる。
「すごか者(もん)が居るな。やはり江戸に、出らんばならんか。」
江藤らの友人・古賀一平が腕組みをしながら、発言をする。
「いや、さすがは中野…と言うべきでは無かね?」
集った仲間の一人・坂井辰之允は、江戸で他藩との人脈を築いていく中野方蔵の行動力に感心している。

――同じ時期に、幕府の中枢・江戸城内では
老中・安藤信正は、志士たちが憤慨する“皇女・和宮の降嫁”の支度に忙しい。前代未聞の大行列が、京から江戸への道を練り歩き、新しい時代を示すのだ。
「皇女さまを江戸にお迎えすること。いまや公儀(幕府)の命運がかかっておる。」
和宮の京からの降嫁には、巨額の費用を計上する。幕府と朝廷が一体と示すための“一大行事”は着々と進んでいた。
――幕政の建て直しに励む、老中・安藤信正。
大老・井伊直弼の亡き後、政権の運営は不安定であり、外国人への襲撃など物騒な事件が相次ぐ。豪腕と呼ばれた井伊大老とは違う、調整型の安藤老中。
苦闘する老中・安藤。これから幕閣の1人となる者がその背中を見つめていた。
唐津藩の若殿(藩主名代)で、名を小笠原長行という。参勤交代により、江戸に来たばかり。小笠原もまた、幕府で期待される“開明派”だった。
(続く)
2021年11月22日
第17話「佐賀脱藩」⑤(若き“将軍”への視線)
こんばんは。
突然、佐賀城下から江戸城内へと場面が転換した前回。
その“展開”を支える方が、唐津藩から来た小笠原長行。藩主の名代となってから3年ほどは、地元・唐津で藩政の改革を試みました。
この頃は30代後半です。1861年(万延二年・文久元年)4月から、参勤交代で江戸に来たと言います。
現在では、唐津藩も佐賀県内にあります。県内全域にわたる“佐賀の物語”を描くことを目指して、その視点も取り入れます。
〔参照(終盤):「主に唐津市民の方を対象にしたつぶやき」〕
――「小笠原どのか。励んでおるようじゃな。」
老中・安藤信正より声がかかる。江戸に来るや、幕府の中枢へ引き寄せられる唐津藩の小笠原長行(ながみち)。
小笠原は長崎出身の砲術家・高島秋帆にも学び、“海防”について幕府に意見を送れば、水戸の烈公・徳川斉昭をも唸(うな)らせたという見識の持ち主。
そのうえ、幕府の信頼厚い名家が配置される、唐津藩。それに外国の技術にも通じる開明派の人材となれば、期待されるのが当然だった。

――「ははっ、ありがたきお言葉。」
少し痩せた体躯だが、頭脳明晰な印象が漂う唐津の藩主名代・小笠原長行。
「本日は、上様がお成りだ。心されよ。」
激務の最中にも、いろいろと気を配る老中・安藤信正が、江戸に来たばかりの小笠原に一声をかける。
最近では“尊王攘夷”の志士が、むやみに外国人を襲撃するので、国政を主導する安藤の悩みは深い。
前年(旧暦で万延元年)の年の瀬にも、薩摩藩士がアメリカの通訳ヒュースケンを襲撃し、外交問題となった。
――ロシア船による“対馬事件”も、ようやく決着したところ。
現状は外国への対処で手一杯だ。まず国内の混乱要因である“尊攘志士”は抑えねばならない。
幕府にとって、朝廷の権威を借りる「公武合体策」は、暴れる志士たちを鎮めるための、わかりやすい“近道”だった。
「心得ました。上様のご尊顔を拝せるとは、恐悦にござります。」
小笠原長行は、気を引き締めた。国元・唐津の藩政が中途になったのが心残りだが、小笠原は幕府の重職に就く予定だ。
どれほど困難な状況が待ち受けるかは、老中・安藤の表情にうかがえる。そこには強い苦悩が見えた。
――ほどなく、江戸城内の書院にて。
「上様のお成りである!」そう告げる声が届く。
第14代将軍・徳川家茂が、その姿を見せた。まだ10代後半の若者。幕府の中で、信頼できそうな少数の者と話がしたい…という用向きだ。
井伊直弼をはじめとする“南紀派”が将軍候補として擁立したとき、幼年ながら紀州藩主(和歌山)で、徳川慶福と名乗った。いまは徳川家茂に改名している。

この少年が将軍と決まるまでには、一橋慶喜を候補に推す水戸・薩摩・福井などの“一橋派”との激しい対立があった。
幕府の官僚たちを率いた井伊大老の豪腕をもって決着が付いたのだが、双方に悲劇が生じている。
――こうして第14代将軍に就いた、徳川家茂。
「小笠原か。唐津から、よくぞ参った。そなたの智恵を頼りとするぞ。」
その声には、立場の重さを自覚し「将軍にふさわしくありたい」という意気込みが感じられる。この爽やかで、凜々しい少年が“上様”だ。
そんな若き将軍の姿を見るや、小笠原長行は嬉しくなった。
「ははっ!勿体(もったい)なき、お言葉。この身に余れど、励みといたします!」
――甘い物が好きで、小動物を愛する…
心優しい子供だったという徳川家茂。幼児期から紀州藩主だったが、実のところ、ずっと江戸の紀州藩邸に居た“都会っ子”である。
責任感の強い少年は、立派な将軍として振る舞おうと務めた。その想いが伝わるのか、「この上様をお守りしたい!」と、頑張る幕臣たちがいた。
唐津から来た小笠原長行も、その一人となっていく。
(続く)
〔関連記事(徳川家茂):「将軍継嗣問題をどう描くか?(後編)」〕
〔関連記事(小笠原長行):「もしも不遇を感じた時には…」〕
突然、佐賀城下から江戸城内へと場面が転換した前回。
その“展開”を支える方が、唐津藩から来た小笠原長行。藩主の名代となってから3年ほどは、地元・唐津で藩政の改革を試みました。
この頃は30代後半です。1861年(万延二年・文久元年)4月から、参勤交代で江戸に来たと言います。
現在では、唐津藩も佐賀県内にあります。県内全域にわたる“佐賀の物語”を描くことを目指して、その視点も取り入れます。
〔参照(終盤):
――「小笠原どのか。励んでおるようじゃな。」
老中・安藤信正より声がかかる。江戸に来るや、幕府の中枢へ引き寄せられる唐津藩の小笠原長行(ながみち)。
小笠原は長崎出身の砲術家・高島秋帆にも学び、“海防”について幕府に意見を送れば、水戸の烈公・徳川斉昭をも唸(うな)らせたという見識の持ち主。
そのうえ、幕府の信頼厚い名家が配置される、唐津藩。それに外国の技術にも通じる開明派の人材となれば、期待されるのが当然だった。
――「ははっ、ありがたきお言葉。」
少し痩せた体躯だが、頭脳明晰な印象が漂う唐津の藩主名代・小笠原長行。
「本日は、上様がお成りだ。心されよ。」
激務の最中にも、いろいろと気を配る老中・安藤信正が、江戸に来たばかりの小笠原に一声をかける。
最近では“尊王攘夷”の志士が、むやみに外国人を襲撃するので、国政を主導する安藤の悩みは深い。
前年(旧暦で万延元年)の年の瀬にも、薩摩藩士がアメリカの通訳ヒュースケンを襲撃し、外交問題となった。
――ロシア船による“対馬事件”も、ようやく決着したところ。
現状は外国への対処で手一杯だ。まず国内の混乱要因である“尊攘志士”は抑えねばならない。
幕府にとって、朝廷の権威を借りる「公武合体策」は、暴れる志士たちを鎮めるための、わかりやすい“近道”だった。
「心得ました。上様のご尊顔を拝せるとは、恐悦にござります。」
小笠原長行は、気を引き締めた。国元・唐津の藩政が中途になったのが心残りだが、小笠原は幕府の重職に就く予定だ。
どれほど困難な状況が待ち受けるかは、老中・安藤の表情にうかがえる。そこには強い苦悩が見えた。
――ほどなく、江戸城内の書院にて。
「上様のお成りである!」そう告げる声が届く。
第14代将軍・徳川家茂が、その姿を見せた。まだ10代後半の若者。幕府の中で、信頼できそうな少数の者と話がしたい…という用向きだ。
井伊直弼をはじめとする“南紀派”が将軍候補として擁立したとき、幼年ながら紀州藩主(和歌山)で、徳川慶福と名乗った。いまは徳川家茂に改名している。
この少年が将軍と決まるまでには、一橋慶喜を候補に推す水戸・薩摩・福井などの“一橋派”との激しい対立があった。
幕府の官僚たちを率いた井伊大老の豪腕をもって決着が付いたのだが、双方に悲劇が生じている。
――こうして第14代将軍に就いた、徳川家茂。
「小笠原か。唐津から、よくぞ参った。そなたの智恵を頼りとするぞ。」
その声には、立場の重さを自覚し「将軍にふさわしくありたい」という意気込みが感じられる。この爽やかで、凜々しい少年が“上様”だ。
そんな若き将軍の姿を見るや、小笠原長行は嬉しくなった。
「ははっ!勿体(もったい)なき、お言葉。この身に余れど、励みといたします!」
――甘い物が好きで、小動物を愛する…
心優しい子供だったという徳川家茂。幼児期から紀州藩主だったが、実のところ、ずっと江戸の紀州藩邸に居た“都会っ子”である。
責任感の強い少年は、立派な将軍として振る舞おうと務めた。その想いが伝わるのか、「この上様をお守りしたい!」と、頑張る幕臣たちがいた。
唐津から来た小笠原長行も、その一人となっていく。
(続く)
〔関連記事(徳川家茂):
〔関連記事(小笠原長行):
2021年11月28日
第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)
こんばんは。
前回、“本編”に第14代将軍・徳川家茂が登場しました。1人の心優しい少年が、将軍となって苦境にある幕府を背負うことになった…そんな印象です。
唐津藩主の名代(代理)・小笠原長行の視点で、江戸の状況に少し触れましたが、ここから佐賀藩の話に戻ります。
時期は少し前後して、1861年(文久元年)の春頃の設定となる話です。
――蘭学(オランダ語)を修業し…
長崎では、英語も学び始めた大隈八太郎(重信)。あてにした賢い先輩や仲間たちが、海外に出て行ったり、蒸気船で出動したり…と慌ただしい。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑭(多良海道の往還)〕

要領よく勉強したい大隈八太郎には逆境もあったが、これまでの地道な学習は実を結んだようで、ついに佐賀藩主・鍋島直正に講義を行う機会を得る。
――佐賀城下。大隈家。
「がんばって、八太郎。」
玄関先では、大隈の母・三井子が、正装した八太郎に激励の言葉をかける。
「これも、母上の教えの賜物(たまもの)です。」
本日は、大隈八太郎の“晴れ舞台”と言ってよいようだ。当人も少し気取って、母への感謝を述べたりする。
「行っておいで。しっかり、おやりなさい!」
「では、大隈信保が一子(いっし)、大隈八太郎。殿の御前へと参じます!」
――大隈の母・三井子は満面の笑みである。
我が子の発した言葉は、まるで“武将”の名乗りだ。それだけ誇らしいのか、やはり気取っているのか。いずれにせよ、八太郎の強い意気込みが感じられる。
「空の向こうのあなた…この三井子は、立派に成し遂げましたよ!」
拳をキュッと握る大隈三井子。
長男・八太郎が、まだ10歳ばかりだった頃。佐賀藩の砲術長として忙しく働いていた夫・信保は急逝した。
〔参照:第6話「鉄製大砲」⑨〕
――とくに理数に強く、賢い侍だったという大隈信保。
その頃は、まだ子どもだった八太郎も“蘭学”を修め、殿・鍋島直正へ進講するまでに成長した。何やら「憲法」とかいうオランダの法度(はっと)を説くらしい。
とにかく名誉には違いない。三井子は、亡き夫・信保と喜びを分かち合っているのか。八太郎の出発を見送ると、遙か西の空に向かって涙している。

――佐賀城下の洋学研究所・“蘭学寮”。
大隈は、“ある人物“とすれ違う。
「久しいな、大隈。殿に学問を講ずるとは、随分な出世ではないか。」
「これは“河内さま”。ご無沙汰をしており、恐れ入りまする。」
蘭学寮の廊下で、大隈に声をかけたのは、身なりの良い若い侍。“河内さま”と呼ばれたが、一目でわかる藩の重役という風格がある。
まだ“若様”といった雰囲気の侍。鍋島河内(直暠)という名だ。現在の佐賀県みやき町に領地を持つ、“白石鍋島家”の当主だ。
――佐賀で、勤王の志士が集った“義祭同盟”。
枝吉神陽が主宰した結社。大隈の先輩たちが多く参加し、島義勇・副島種臣・大木喬任・江藤新平・中野方蔵…と、才能がある人材が集まっている。
公式行事としては「“勤王”を貫いた英雄・楠木正成を讃える」式典を開催し、そこには藩の重役の参加もあった。

その代表的人物が当時の藩政ナンバー2の鍋島安房だが、他にも“ご領主”の家柄の者がいた。式典に初期から参加していた、鍋島河内だ。
〔参照(序盤):第12話「海軍伝習」④(義祭同盟の青春)〕
「本日は、殿の御前にて“オランダ憲法”を講ずる由にございます。」
身分の差はあっても、まだ歳は近い。大隈は、鍋島河内と顔見知りなのだ。
――その、みやき町近辺の“ご領主”が、一言を添える。
「それは良き事だ。大隈も随分と励んだのだな…、ところで、後ほど話がある。」
鍋島河内には、何か“企て”がある様子だ。
幕末期、白石鍋島家の領内では、外国との交易で値打ちを示すハゼ蝋(ろう)の生産が盛んで、陶磁器“白石焼”の製造も伸びていた。
のちに大隈八太郎は、長崎を拠点として、貿易から鉱山探索まで色々な活動を行ったという。それらの動きには、鍋島河内が大きく関わることになる。
(続く)
前回、“本編”に第14代将軍・徳川家茂が登場しました。1人の心優しい少年が、将軍となって苦境にある幕府を背負うことになった…そんな印象です。
唐津藩主の名代(代理)・小笠原長行の視点で、江戸の状況に少し触れましたが、ここから佐賀藩の話に戻ります。
時期は少し前後して、1861年(文久元年)の春頃の設定となる話です。
――蘭学(オランダ語)を修業し…
長崎では、英語も学び始めた大隈八太郎(重信)。あてにした賢い先輩や仲間たちが、海外に出て行ったり、蒸気船で出動したり…と慌ただしい。
〔参照:
要領よく勉強したい大隈八太郎には逆境もあったが、これまでの地道な学習は実を結んだようで、ついに佐賀藩主・鍋島直正に講義を行う機会を得る。
――佐賀城下。大隈家。
「がんばって、八太郎。」
玄関先では、大隈の母・三井子が、正装した八太郎に激励の言葉をかける。
「これも、母上の教えの賜物(たまもの)です。」
本日は、大隈八太郎の“晴れ舞台”と言ってよいようだ。当人も少し気取って、母への感謝を述べたりする。
「行っておいで。しっかり、おやりなさい!」
「では、大隈信保が一子(いっし)、大隈八太郎。殿の御前へと参じます!」
――大隈の母・三井子は満面の笑みである。
我が子の発した言葉は、まるで“武将”の名乗りだ。それだけ誇らしいのか、やはり気取っているのか。いずれにせよ、八太郎の強い意気込みが感じられる。
「空の向こうのあなた…この三井子は、立派に成し遂げましたよ!」
拳をキュッと握る大隈三井子。
長男・八太郎が、まだ10歳ばかりだった頃。佐賀藩の砲術長として忙しく働いていた夫・信保は急逝した。
〔参照:
――とくに理数に強く、賢い侍だったという大隈信保。
その頃は、まだ子どもだった八太郎も“蘭学”を修め、殿・鍋島直正へ進講するまでに成長した。何やら「憲法」とかいうオランダの法度(はっと)を説くらしい。
とにかく名誉には違いない。三井子は、亡き夫・信保と喜びを分かち合っているのか。八太郎の出発を見送ると、遙か西の空に向かって涙している。
――佐賀城下の洋学研究所・“蘭学寮”。
大隈は、“ある人物“とすれ違う。
「久しいな、大隈。殿に学問を講ずるとは、随分な出世ではないか。」
「これは“河内さま”。ご無沙汰をしており、恐れ入りまする。」
蘭学寮の廊下で、大隈に声をかけたのは、身なりの良い若い侍。“河内さま”と呼ばれたが、一目でわかる藩の重役という風格がある。
まだ“若様”といった雰囲気の侍。鍋島河内(直暠)という名だ。現在の佐賀県みやき町に領地を持つ、“白石鍋島家”の当主だ。
――佐賀で、勤王の志士が集った“義祭同盟”。
枝吉神陽が主宰した結社。大隈の先輩たちが多く参加し、島義勇・副島種臣・大木喬任・江藤新平・中野方蔵…と、才能がある人材が集まっている。
公式行事としては「“勤王”を貫いた英雄・楠木正成を讃える」式典を開催し、そこには藩の重役の参加もあった。
その代表的人物が当時の藩政ナンバー2の鍋島安房だが、他にも“ご領主”の家柄の者がいた。式典に初期から参加していた、鍋島河内だ。
〔参照(序盤):
「本日は、殿の御前にて“オランダ憲法”を講ずる由にございます。」
身分の差はあっても、まだ歳は近い。大隈は、鍋島河内と顔見知りなのだ。
――その、みやき町近辺の“ご領主”が、一言を添える。
「それは良き事だ。大隈も随分と励んだのだな…、ところで、後ほど話がある。」
鍋島河内には、何か“企て”がある様子だ。
幕末期、白石鍋島家の領内では、外国との交易で値打ちを示すハゼ蝋(ろう)の生産が盛んで、陶磁器“白石焼”の製造も伸びていた。
のちに大隈八太郎は、長崎を拠点として、貿易から鉱山探索まで色々な活動を行ったという。それらの動きには、鍋島河内が大きく関わることになる。
(続く)
2021年12月01日
第17話「佐賀脱藩」⑦(蘭学教師・大隈)
こんばんは。
前回、母・三井子に感激の涙で見送られ、蘭学寮に着くなり、顔見知りの重役である鍋島河内から声をかけられたり、何かと忙しい大隈八太郎(重信)。
学問に熱心な佐賀の殿様・鍋島直正は、よく藩の学校を訪れ、もちろん洋学を研究する“蘭学寮”にも訪れたといいます。
大隈にとっては、オランダ語で学んだ西洋の知識を、殿に講義する晴れ舞台が、そこにありました。
――大隈の講義を聞く、殿・鍋島直正。
大隈は話が上手いうえ、準備も万端だ。殿の興味を引く話を続ける。
「こうしてオランダでは“憲法”が諸法度(はっと)の上に立つのであります…」
殿・直正は“うむ”とばかりにうなずいた。
「大隈よ。そなたの話、なかなかに面白い。」
「ありがたき、幸せ!」
よし、殿にもご満足いただける講義だっただろう。大隈はそう思った。

――しかし、佐賀の殿様の学習意欲が高い。
次の直正の発言から、大隈の想定を超えた事態が起きる。
「いや、興味深いぞ…!もう少し、聞きたいものだ。」
「…!」
小出千之助や石丸安世(虎五郎)といった“達人級”に比べ、語学力では一歩劣る大隈。準備できていない部分を、即興で読み解き、説明するのは困難だ。
「では、続きを訳せ。」
“生徒”から教師への言葉としては奇妙だが、これは殿様からの指示なのだ。
「…いや、“洋書”は訳せばよいというものではございませぬ。」
――ここは弁舌で“窮地”の脱出を図る、大隈八太郎。
「西洋の文物は、その背景まで知りてこそ。殿に講ずるならば、なおの事。」
大隈は、言葉を続ける。
「半端なる、お教えはいたしかねます。他日に、機会を賜りたく存じます。」
「…そこまで申すなら、日を改めよう。より一層、励むとよいぞ。」
本日はもっと勉強したかったが…、そんな表情の直正だった。
「はは―っ!」
そして、冷や汗をかく大隈だった。

――大隈が退出した後、城まで戻った直正。
「殿、お呼びにございますか。」
側近・古川松根(与一)が、殿様が居る書院に姿を見せる。
「やはり、ゆるりと学問をするのは良いものだな。」
「仰せになっていた…隠居の件に、ございますか。」
鍋島直正は、跡継ぎの直大(茂実)に、藩主の座を譲る段取りを進めていた。
「さすが与一だ。語らずともわかってくれるのだな。」
「長年の、お付き合いにて。」
古川が屈託なく言葉を返す。幼児期からずっと一緒の主従だ。ここから半年が過ぎた、晩秋に鍋島直正は佐賀藩主を退き、“隠居”をすることになる。
(続く)
前回、母・三井子に感激の涙で見送られ、蘭学寮に着くなり、顔見知りの重役である鍋島河内から声をかけられたり、何かと忙しい大隈八太郎(重信)。
学問に熱心な佐賀の殿様・鍋島直正は、よく藩の学校を訪れ、もちろん洋学を研究する“蘭学寮”にも訪れたといいます。
大隈にとっては、オランダ語で学んだ西洋の知識を、殿に講義する晴れ舞台が、そこにありました。
――大隈の講義を聞く、殿・鍋島直正。
大隈は話が上手いうえ、準備も万端だ。殿の興味を引く話を続ける。
「こうしてオランダでは“憲法”が諸法度(はっと)の上に立つのであります…」
殿・直正は“うむ”とばかりにうなずいた。
「大隈よ。そなたの話、なかなかに面白い。」
「ありがたき、幸せ!」
よし、殿にもご満足いただける講義だっただろう。大隈はそう思った。
――しかし、佐賀の殿様の学習意欲が高い。
次の直正の発言から、大隈の想定を超えた事態が起きる。
「いや、興味深いぞ…!もう少し、聞きたいものだ。」
「…!」
小出千之助や石丸安世(虎五郎)といった“達人級”に比べ、語学力では一歩劣る大隈。準備できていない部分を、即興で読み解き、説明するのは困難だ。
「では、続きを訳せ。」
“生徒”から教師への言葉としては奇妙だが、これは殿様からの指示なのだ。
「…いや、“洋書”は訳せばよいというものではございませぬ。」
――ここは弁舌で“窮地”の脱出を図る、大隈八太郎。
「西洋の文物は、その背景まで知りてこそ。殿に講ずるならば、なおの事。」
大隈は、言葉を続ける。
「半端なる、お教えはいたしかねます。他日に、機会を賜りたく存じます。」
「…そこまで申すなら、日を改めよう。より一層、励むとよいぞ。」
本日はもっと勉強したかったが…、そんな表情の直正だった。
「はは―っ!」
そして、冷や汗をかく大隈だった。
――大隈が退出した後、城まで戻った直正。
「殿、お呼びにございますか。」
側近・古川松根(与一)が、殿様が居る書院に姿を見せる。
「やはり、ゆるりと学問をするのは良いものだな。」
「仰せになっていた…隠居の件に、ございますか。」
鍋島直正は、跡継ぎの直大(茂実)に、藩主の座を譲る段取りを進めていた。
「さすが与一だ。語らずともわかってくれるのだな。」
「長年の、お付き合いにて。」
古川が屈託なく言葉を返す。幼児期からずっと一緒の主従だ。ここから半年が過ぎた、晩秋に鍋島直正は佐賀藩主を退き、“隠居”をすることになる。
(続く)
2021年12月05日
第17話「佐賀脱藩」⑧(福岡から来た“さぶらい”)
こんにちは。
鍋島直正が佐賀藩主を退き「閑叟(かんそう)」と、正式に号した(名乗った)のは、1861年(文久元年)の晩秋と言われます。
その同じ年の秋。直正の“隠居”1か月ばかり前の10月頃、佐賀城下に、古い時代から来たような不思議な来訪者がありました。

――師匠・枝吉神陽の家に向かっている。
佐賀城の堀端を南に行くのは、大木喬任(民平)と江藤新平。この日も、江戸に出た親友・中野方蔵の話題をしている。
「次に、中野からの便りはいつ来ると思うか。」
「また催促が来るでしょう。中野は、よほど大木さんを引っ張り出したいらしい。」
大木の問いかけに、江藤が予測を述べる。
「ところで、江藤。“熊太郎”は、元気か?」
「ああ、健やかにしている。“赤子”も可愛いものだ。」
――「やはりお主のような者でも、“父親の顔”になるのか。」
少々ひねくれた言い方をする大木に、江藤が苦笑する。
「子を持てば、親になる。これも理に適(かな)った事。」
「…左様(さよう)か!」
江藤が幸せになるのは、大木とて嬉しいが、ぶっきらぼうな反応も大木らしい。
前年の11月頃に、江藤は妻・千代子との間に子を授かり、一児の父となった。その長男の名は熊太郎といって、もうじき1歳となる。

――遠目に見える屋敷の門前に、2つの人影がある。
うち1人は江藤らの仲間で、古賀一平。もう1人は、見かけぬ風体の人物だ。
「あん(の)一人は、佐賀の者では無かごたな…。」
「ええ、古賀さんに何事かを説くと見える。」
二人の反応には理由があった。古賀と向き合う謎の男の格好が奇妙なのだ。烏帽子(えぼし)を頭に乗せ、直垂(ひたたれ)を着る…という古風さである。
――その装束は、まるで“絵巻物”にでも出てきそうだ。
幕末からでも七百年ほど前になるが、朝廷で主に皇族を守る武士たちが居た。貴人に「候(さぶら)う」ので、後に武士たちは“さぶらい”と呼ばれたという。
それが“侍”の語源だというが、謎の男の服装には、その雰囲気がある。時代がかった“謎のさぶらい”と対話する古賀は、楽しげに盛り上がっている。
ここで古賀が、大木と江藤が来たことに気づいた。
「福岡から、珍しか客人ったい!」

――もともと福岡藩士だという、“さぶらい”。
二人と目線が合うと“さぶらい”は仰々しく一礼をした。時代を錯誤した服装で目立つだけでなく、何やら人を惹きつける魅力もある。
「筑前(福岡)より出た者で、平野国臣と申す!」
豪快に名乗った。“福岡脱藩”の志士というのが、現在の肩書きと見える。
「江藤と申す。平野さまに問う。その“装束”の意味するところは何か。」
まず名乗り返すものの、いきなり問答を始める江藤。
――向かい合う双方とも、声は大きい。
「我は、国のために動いておる。それを示す装束と心得ておる。」
福岡から来た勤王の志士・平野国臣。古めかしい服装に、信念がある様子だ。
「自分こそは、朝廷を守る武士」という真っ直ぐな想い。それが、朝廷を中心に世の中が回った“古い時代”を身に纏(まと)う理由らしい。
「貴殿の志、理解に至った。」
質素な身なりの江藤。平野と違って、服装で“志”を示したりはしない。しかし、その想いには得心したようだ。
(続く)
鍋島直正が佐賀藩主を退き「閑叟(かんそう)」と、正式に号した(名乗った)のは、1861年(文久元年)の晩秋と言われます。
その同じ年の秋。直正の“隠居”1か月ばかり前の10月頃、佐賀城下に、古い時代から来たような不思議な来訪者がありました。
――師匠・枝吉神陽の家に向かっている。
佐賀城の堀端を南に行くのは、大木喬任(民平)と江藤新平。この日も、江戸に出た親友・中野方蔵の話題をしている。
「次に、中野からの便りはいつ来ると思うか。」
「また催促が来るでしょう。中野は、よほど大木さんを引っ張り出したいらしい。」
大木の問いかけに、江藤が予測を述べる。
「ところで、江藤。“熊太郎”は、元気か?」
「ああ、健やかにしている。“赤子”も可愛いものだ。」
――「やはりお主のような者でも、“父親の顔”になるのか。」
少々ひねくれた言い方をする大木に、江藤が苦笑する。
「子を持てば、親になる。これも理に適(かな)った事。」
「…左様(さよう)か!」
江藤が幸せになるのは、大木とて嬉しいが、ぶっきらぼうな反応も大木らしい。
前年の11月頃に、江藤は妻・千代子との間に子を授かり、一児の父となった。その長男の名は熊太郎といって、もうじき1歳となる。
――遠目に見える屋敷の門前に、2つの人影がある。
うち1人は江藤らの仲間で、古賀一平。もう1人は、見かけぬ風体の人物だ。
「あん(の)一人は、佐賀の者では無かごたな…。」
「ええ、古賀さんに何事かを説くと見える。」
二人の反応には理由があった。古賀と向き合う謎の男の格好が奇妙なのだ。烏帽子(えぼし)を頭に乗せ、直垂(ひたたれ)を着る…という古風さである。
――その装束は、まるで“絵巻物”にでも出てきそうだ。
幕末からでも七百年ほど前になるが、朝廷で主に皇族を守る武士たちが居た。貴人に「候(さぶら)う」ので、後に武士たちは“さぶらい”と呼ばれたという。
それが“侍”の語源だというが、謎の男の服装には、その雰囲気がある。時代がかった“謎のさぶらい”と対話する古賀は、楽しげに盛り上がっている。
ここで古賀が、大木と江藤が来たことに気づいた。
「福岡から、珍しか客人ったい!」
――もともと福岡藩士だという、“さぶらい”。
二人と目線が合うと“さぶらい”は仰々しく一礼をした。時代を錯誤した服装で目立つだけでなく、何やら人を惹きつける魅力もある。
「筑前(福岡)より出た者で、平野国臣と申す!」
豪快に名乗った。“福岡脱藩”の志士というのが、現在の肩書きと見える。
「江藤と申す。平野さまに問う。その“装束”の意味するところは何か。」
まず名乗り返すものの、いきなり問答を始める江藤。
――向かい合う双方とも、声は大きい。
「我は、国のために動いておる。それを示す装束と心得ておる。」
福岡から来た勤王の志士・平野国臣。古めかしい服装に、信念がある様子だ。
「自分こそは、朝廷を守る武士」という真っ直ぐな想い。それが、朝廷を中心に世の中が回った“古い時代”を身に纏(まと)う理由らしい。
「貴殿の志、理解に至った。」
質素な身なりの江藤。平野と違って、服装で“志”を示したりはしない。しかし、その想いには得心したようだ。
(続く)
2021年12月11日
第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)
こんばんは。2周年の記事では、たくさんの方にお読みいただき、コメントをくださった方も。ありがとうございました。
“本編”を再開します。前回、登場した福岡の志士・平野国臣。平安・鎌倉期を思わせる古風な武士の姿。髭を蓄え、時代物の装束に志を込めた“さぶらい”。
諸国でも“尊王活動家”として一目置かれた存在だったそうで、薩摩(鹿児島)にも出入りし、西郷吉之助(隆盛)と深く関わっています。
1861年(文久元年)秋。佐賀を訪ねた福岡脱藩・平野国臣には、枝吉神陽との連携を図る目的があったそうです。
――福岡の“さぶらい”・平野と問答を続ける江藤新平。
無言で見守る大木喬任(民平)は、こう考えた。
「おそらく江藤、この男が気に入ったな…」
江藤は開明派だが、一本気で筋の通った“古武士”には好意的だ。
大木も服装に無頓着で古風な格好を真似しようとは思わないが、平野が語る「我こそは朝廷の臣!」という考え方には共感できる。

――平野との話に盛り上がる江藤、それを見守る大木。
時が過ぎている。最初から居た古賀一平が冷静になって気づいた。
「ここでは、いかんばい!お客人を別のところにお連れせんば。」
上機嫌で話し続ける、平野は快活に答えた。
「何処に行こうが、一向に構わぬぞ。」
「佐賀には、窮屈な掟(おきて)がございましてな。」
古賀が、師匠・枝吉神陽との面会の場所を別に用意するようだ。
持ち前の行動力で突き進んだ福岡脱藩の平野だが、江戸期の佐賀では旅人への規制が強く、立ち寄れる場所は限られる。面倒ごとは避けたいところだ。
――よく“義祭同盟”の会合で集う社にて。
「筑前(福岡)の平野と申す。神陽先生にお会いできて光栄だ。」
「平野どのの、ご令名(れいめい)は聞き及んでいる。」
堂内に姿を見せた枝吉神陽。江藤らの師匠でもあるが、佐賀の藩政にも関わりがある。さらに貫禄が増した。
かつての天皇親政の時代。朝廷を中心とする世を理想とするのは、両者とも。もはや幕府には、朝廷から政治を任される価値はないという見解も一致する。

――「古式に則り、“あるべき姿”へと戻す。」
「然(しか)り…、得心できることばかりだ。」
勤王の想いが強い古賀一平が、師匠と平野国臣の議論に感じ入っている。
「神陽先生。佐賀が勤王のはたらきを為せば“回天”すら為せるはず。」
平野の想いとしては、佐賀藩が決起すれば時代は動く。藩上層部と志士たちの双方に影響力がある、枝吉神陽の賛同を求めていた。
もはや薩摩の名君・島津斉彬はいない。残る実力者として、佐賀の鍋島直正の動向にも、自然と注目が集まっている。
――ここで、珍しく大木が口を挟んだ。
枝吉神陽は時勢を語る平野に共感を示すが、倒幕への決起話には乗らない。
「平野先生にお伺いするが、やはり福岡の黒田さまは動かぬか。」
大木は話の展開を察してか、福岡藩の事も聞くようだ。
「黒田の殿には幾度でも言上するが、まず我が身で事を為すほかあるまい。」
福岡藩(黒田家)にも意見をした平野。風変わりな提案を強引な手段で行ったので、処罰の対象となった。
むしろ福岡藩は平野の過激な言動と志士との人脈が、幕府から咎(とが)められると警戒。平野は脱藩をして浪人となり、よく藩の捕方から追われている。

――その場は、意見の交換に終わった。
「平野どの、近いうちに時節が来よう。」
枝吉神陽が、福岡の“さぶらい”・平野に包み込むような一声をかける。
「…神陽先生は、よき門下生を育てておられるな。」
平野が、枝吉神陽との別れ際に語る。
「三人とも名に“平”の字を持つ者。佐賀に“三平”あり!と言うべきか。」
平野の語る“三平”の1人目は、勤王の話に熱く、手配りの良い古賀一平。
――次に、鋭く問答を仕掛けてくるが、強い才気を感じる江藤新平。
そして、何を思うか判然としないが、様々な思考を巡らせる大木民平(喬任)。
平野の言葉を受けて、神陽がうなずく。
「佐賀の“三平”か。平野どのの言葉なれば、さぞ喜ぶだろう。」
「我は、勤王の同志を集め、佐賀が動くのを待っておりますぞ。」
「いずれ、お会いしよう。」
双方が低い声で挨拶をかわすと、平野は長崎街道の旅路へと戻った。
明日は何処に行くものか。枝吉神陽は、福岡からの脱藩者の背中を見送る。
「平野どの。心持ちは解る…だが、あまり急(せ)いてはならぬぞ。」
(続く)
“本編”を再開します。前回、登場した福岡の志士・平野国臣。平安・鎌倉期を思わせる古風な武士の姿。髭を蓄え、時代物の装束に志を込めた“さぶらい”。
諸国でも“尊王活動家”として一目置かれた存在だったそうで、薩摩(鹿児島)にも出入りし、西郷吉之助(隆盛)と深く関わっています。
1861年(文久元年)秋。佐賀を訪ねた福岡脱藩・平野国臣には、枝吉神陽との連携を図る目的があったそうです。
――福岡の“さぶらい”・平野と問答を続ける江藤新平。
無言で見守る大木喬任(民平)は、こう考えた。
「おそらく江藤、この男が気に入ったな…」
江藤は開明派だが、一本気で筋の通った“古武士”には好意的だ。
大木も服装に無頓着で古風な格好を真似しようとは思わないが、平野が語る「我こそは朝廷の臣!」という考え方には共感できる。

――平野との話に盛り上がる江藤、それを見守る大木。
時が過ぎている。最初から居た古賀一平が冷静になって気づいた。
「ここでは、いかんばい!お客人を別のところにお連れせんば。」
上機嫌で話し続ける、平野は快活に答えた。
「何処に行こうが、一向に構わぬぞ。」
「佐賀には、窮屈な掟(おきて)がございましてな。」
古賀が、師匠・枝吉神陽との面会の場所を別に用意するようだ。
持ち前の行動力で突き進んだ福岡脱藩の平野だが、江戸期の佐賀では旅人への規制が強く、立ち寄れる場所は限られる。面倒ごとは避けたいところだ。
――よく“義祭同盟”の会合で集う社にて。
「筑前(福岡)の平野と申す。神陽先生にお会いできて光栄だ。」
「平野どのの、ご令名(れいめい)は聞き及んでいる。」
堂内に姿を見せた枝吉神陽。江藤らの師匠でもあるが、佐賀の藩政にも関わりがある。さらに貫禄が増した。
かつての天皇親政の時代。朝廷を中心とする世を理想とするのは、両者とも。もはや幕府には、朝廷から政治を任される価値はないという見解も一致する。
――「古式に則り、“あるべき姿”へと戻す。」
「然(しか)り…、得心できることばかりだ。」
勤王の想いが強い古賀一平が、師匠と平野国臣の議論に感じ入っている。
「神陽先生。佐賀が勤王のはたらきを為せば“回天”すら為せるはず。」
平野の想いとしては、佐賀藩が決起すれば時代は動く。藩上層部と志士たちの双方に影響力がある、枝吉神陽の賛同を求めていた。
もはや薩摩の名君・島津斉彬はいない。残る実力者として、佐賀の鍋島直正の動向にも、自然と注目が集まっている。
――ここで、珍しく大木が口を挟んだ。
枝吉神陽は時勢を語る平野に共感を示すが、倒幕への決起話には乗らない。
「平野先生にお伺いするが、やはり福岡の黒田さまは動かぬか。」
大木は話の展開を察してか、福岡藩の事も聞くようだ。
「黒田の殿には幾度でも言上するが、まず我が身で事を為すほかあるまい。」
福岡藩(黒田家)にも意見をした平野。風変わりな提案を強引な手段で行ったので、処罰の対象となった。
むしろ福岡藩は平野の過激な言動と志士との人脈が、幕府から咎(とが)められると警戒。平野は脱藩をして浪人となり、よく藩の捕方から追われている。
――その場は、意見の交換に終わった。
「平野どの、近いうちに時節が来よう。」
枝吉神陽が、福岡の“さぶらい”・平野に包み込むような一声をかける。
「…神陽先生は、よき門下生を育てておられるな。」
平野が、枝吉神陽との別れ際に語る。
「三人とも名に“平”の字を持つ者。佐賀に“三平”あり!と言うべきか。」
平野の語る“三平”の1人目は、勤王の話に熱く、手配りの良い古賀一平。
――次に、鋭く問答を仕掛けてくるが、強い才気を感じる江藤新平。
そして、何を思うか判然としないが、様々な思考を巡らせる大木民平(喬任)。
平野の言葉を受けて、神陽がうなずく。
「佐賀の“三平”か。平野どのの言葉なれば、さぞ喜ぶだろう。」
「我は、勤王の同志を集め、佐賀が動くのを待っておりますぞ。」
「いずれ、お会いしよう。」
双方が低い声で挨拶をかわすと、平野は長崎街道の旅路へと戻った。
明日は何処に行くものか。枝吉神陽は、福岡からの脱藩者の背中を見送る。
「平野どの。心持ちは解る…だが、あまり急(せ)いてはならぬぞ。」
(続く)
2021年12月14日
第17話「佐賀脱藩」⑩(ご隠居の深き悩み)
こんばんは。前回の続きです。
1861年(文久元年)の晩秋。鍋島直正は佐賀藩主を退き、閑叟(かんそう)と正式に号します。
幕府を守ろうとする“佐幕”派にも、尊攘(尊王攘夷)派からも注目される佐賀の殿様。まだ、四十代での隠居です。
「何か思惑があるのか…?」と周囲には様々な憶測が。
ご隠居としてのんびりするかと言えば、政局をにらんで自由に活動できる身分を求めたという見解もあります。
しかし、当時の直正(閑叟)は体調面に不安を抱え、心配事も増えていました。
〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑦(父娘の心配事)〕
――「おいは、三瀬に戻らんば。」
福岡脱藩の志士・平野国臣が言うところの「佐賀の三平」の1人。古賀一平には、三瀬街道の番人という役目がある。
「神陽先生は、随分と慎重ではなかね。」
古賀は勤王志士の話に乗らない、師匠・枝吉神陽の動きを訝(いぶか)しがる。
「古賀さん。神陽先生の事だ。ご存念があるのだろう。」
江藤新平とて、平野の熱い想いには感銘を受けた。
「…殿のご隠居を待っておられるかだな。」
大木喬任(民平)は、師匠の思惑を推し量っていた。

――この年、鍋島直正は、着々と隠居の段取りを進めてきた。
「佐賀が一体で動かば、世に与える力は大きいだろうな。」
大木は、淡々と続けた。
「やぐらしか(面倒)な事だ…。」
真っ直ぐな気性の古賀。挙藩一致を待つだけなのが、釈然としないようだ。
「焦らずとも、江戸には中野が居るゆえ。」
諸藩の志士たちとの連携。江藤は、親友・中野方蔵の動きへの期待を語る。
――「そうか、また中野から文(ふみ)が来たら知らせんね。」
「承知した。」
大木が言葉を返す。三瀬の番所は、城下からかなり北にある。古賀は、名残り惜しそうに2人と別れた。
「ああは言ったが、古賀さんの心配ももっともだ。佐賀は時勢に遅れつつある。」
「そこはお主が述べたように、我らには中野がいる。殿様も、じき動くだろう。」
大木は、わりに悠然と構えているように見えた。
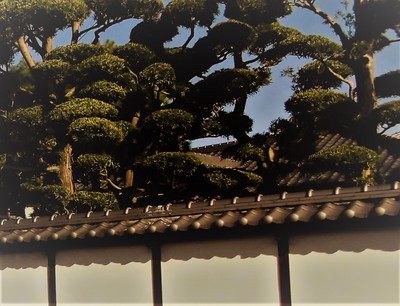
――しかし、隠居後まもなく、鍋島直正には悩みが生じた。
すっかり寒くなった冬のある日。川越藩(埼玉)の江戸屋敷からの急報を見るや、直正(閑叟)の様子がおかしい。
「…いかがなさいましたか。」
直正の世話係にして、幼なじみ・古川与一(松根)が顔色をうかがう。
「川越の…直侯どのが…」
「まさか、」
「…ご逝去なさった。」
川越藩主・松平直侯は、直正の娘・貢姫の夫だ。
――明らかに顔色の悪い、直正。
「…お気をたしかに。」
古川与一が、心配げに声をかける。
「貢(みつ)の胸中が察されてならぬ…。」
直正は、若くして夫を亡くした愛娘の心痛を思った。生真面目な長女のことだ。きっと思い悩んでいるに違いない。
病気療養中だった松平直侯。亡くなったのは、文久元年の十二月という。

――江戸の沿海警備の負担が重かった川越藩。
アメリカのペリーが来航した際、上陸した地点の警備担当だったという川越藩。松平直侯の藩主就任後には、品川の台場も受け持ちもあった。
くわえて他家からの養子では、さらに気を遣うところが多い。
「…定めし、心労があったことだろう。」
実父は、水戸烈公・徳川斉昭。実兄は英明の誉れ高い、一橋慶喜。貢姫の夫・松平直侯は、様々な重圧に耐え続けたのか。その短い生涯を閉じたのだった。
(続く)
1861年(文久元年)の晩秋。鍋島直正は佐賀藩主を退き、閑叟(かんそう)と正式に号します。
幕府を守ろうとする“佐幕”派にも、尊攘(尊王攘夷)派からも注目される佐賀の殿様。まだ、四十代での隠居です。
「何か思惑があるのか…?」と周囲には様々な憶測が。
ご隠居としてのんびりするかと言えば、政局をにらんで自由に活動できる身分を求めたという見解もあります。
しかし、当時の直正(閑叟)は体調面に不安を抱え、心配事も増えていました。
〔参照:
――「おいは、三瀬に戻らんば。」
福岡脱藩の志士・平野国臣が言うところの「佐賀の三平」の1人。古賀一平には、三瀬街道の番人という役目がある。
「神陽先生は、随分と慎重ではなかね。」
古賀は勤王志士の話に乗らない、師匠・枝吉神陽の動きを訝(いぶか)しがる。
「古賀さん。神陽先生の事だ。ご存念があるのだろう。」
江藤新平とて、平野の熱い想いには感銘を受けた。
「…殿のご隠居を待っておられるかだな。」
大木喬任(民平)は、師匠の思惑を推し量っていた。
――この年、鍋島直正は、着々と隠居の段取りを進めてきた。
「佐賀が一体で動かば、世に与える力は大きいだろうな。」
大木は、淡々と続けた。
「やぐらしか(面倒)な事だ…。」
真っ直ぐな気性の古賀。挙藩一致を待つだけなのが、釈然としないようだ。
「焦らずとも、江戸には中野が居るゆえ。」
諸藩の志士たちとの連携。江藤は、親友・中野方蔵の動きへの期待を語る。
――「そうか、また中野から文(ふみ)が来たら知らせんね。」
「承知した。」
大木が言葉を返す。三瀬の番所は、城下からかなり北にある。古賀は、名残り惜しそうに2人と別れた。
「ああは言ったが、古賀さんの心配ももっともだ。佐賀は時勢に遅れつつある。」
「そこはお主が述べたように、我らには中野がいる。殿様も、じき動くだろう。」
大木は、わりに悠然と構えているように見えた。
――しかし、隠居後まもなく、鍋島直正には悩みが生じた。
すっかり寒くなった冬のある日。川越藩(埼玉)の江戸屋敷からの急報を見るや、直正(閑叟)の様子がおかしい。
「…いかがなさいましたか。」
直正の世話係にして、幼なじみ・古川与一(松根)が顔色をうかがう。
「川越の…直侯どのが…」
「まさか、」
「…ご逝去なさった。」
川越藩主・松平直侯は、直正の娘・貢姫の夫だ。
――明らかに顔色の悪い、直正。
「…お気をたしかに。」
古川与一が、心配げに声をかける。
「貢(みつ)の胸中が察されてならぬ…。」
直正は、若くして夫を亡くした愛娘の心痛を思った。生真面目な長女のことだ。きっと思い悩んでいるに違いない。
病気療養中だった松平直侯。亡くなったのは、文久元年の十二月という。

――江戸の沿海警備の負担が重かった川越藩。
アメリカのペリーが来航した際、上陸した地点の警備担当だったという川越藩。松平直侯の藩主就任後には、品川の台場も受け持ちもあった。
くわえて他家からの養子では、さらに気を遣うところが多い。
「…定めし、心労があったことだろう。」
実父は、水戸烈公・徳川斉昭。実兄は英明の誉れ高い、一橋慶喜。貢姫の夫・松平直侯は、様々な重圧に耐え続けたのか。その短い生涯を閉じたのだった。
(続く)
2021年12月18日
第17話「佐賀脱藩」⑪(“都会”の流儀)
こんばんは。前回の続きです。
鍋島直正の愛娘・貢姫の嫁ぎ先は、現在では埼玉県にあった川越藩でした。大名の正室として、江戸にいた貢姫。
夫で川越藩主だった松平直侯が亡くなったことで、のち江戸を離れ、川越へと移る定めとなります。
幕末期の江戸は、世界最大の人口規模を誇ったと言われる“百万”都市。様々な人々が集まり、悲喜こもごもに暮らす大都会でした。
――江戸。川越藩の屋敷。
薄暗い冬の日。夫の喪に服する貢姫。若くして“未亡人”となってしまった。
「父上…、貢は鍋島の娘として、何事もなし得ませんでした。」
同じく、まだ二十代前半だった夫を失い、途方に暮れる。夫婦の間には、まだ子はいなかった。愛娘の心には、頼れる父・鍋島直正の面影が浮かぶ。
父の心配どおり、真面目な鍋島家の長女は、自責の念に駆られていた。
――同じ頃、離れた娘の境遇を心配する父・直正。
「貢よ、己を責めるでないっ!松平さまのお立場も、厳しかったのだ…」
「殿、いかがなさいました…!?」
ふと、語り出した直正(閑叟)。“幼なじみ”の側近・古川与一(松根)が慌てる。
「…わが娘が、助けを呼ぶかと思えてな。つい、声に出たようだ。」
「殿!いや、ご隠居…閑叟さま…。姫が、心配にございますな。」

――先月から佐賀の殿様は、正式に隠居している。
「与一よ。もしや、儂の呼び方を迷うておるか?」
色々と困惑する古川を見て、気が逸れたのか。わずかに笑みを見せる、直正。
「まだ、落ち着かぬから、当面は“殿”と呼べばよい。」
「…心得ました。では、いずれ“ご老公”とお呼びいたしましょうか。」
「その呼び名は…、何やら収まりが良くない。」
人生、苦もあれば楽もある。「ここも、先憂後楽じゃ。」と、自らに言い聞かせる“佐賀のご老公”であった。
――さて、大都市・江戸の市中。儒学者・大橋訥庵の私塾にて。
「老中の所業、許しがたし!」
「おう、安藤を討つべし!」
大声を出す若者たちが集まって、荒々しく武術の訓練に励む。都合の悪いことに、老中・安藤信正に対し、公然と物騒なことを口にしている。
「…もはやこの塾には、立ち寄るべきではないのかもしれぬな。」
その場を、遠巻きに眺めていた、佐賀藩士・中野方蔵がつぶやく。大木喬任と江藤新平が、手紙を楽しみに待つ親友である。

――晩秋には、孝明天皇の妹・和宮が江戸に到着していた。
その“花嫁”の行列は3万人規模とも言われる壮麗なものだった。尊王攘夷派への警戒から、平坦な東海道を避けて、あえて険しい中山道を通ったという。
和宮は、御所風の生活を続けることを強く望む。暮らし方の調整が難航して、1か月ほどは城に入らなかったという。
――また、気勢を挙げる者がいる。
「和宮様を、城へお連れ奉る謀(はかりごと)を打ち砕かん!」
「そうじゃ、皇女さまを奪還せよ!」
いまにも、市中に出撃しそうな雰囲気だ。
「かかる“短慮”に巻き込まれては、大木さんや江藤くんに申し訳が立たぬ。」
諸藩の志士との交流は、佐賀に帰ったのち、他藩と連携して勤王に励み、これからの日本を導くためだ。中野は騒ぎに背を向け、その場を去った。
――すっかり“都会暮らし”に、馴染んでいた中野。
当時の過密都市は火災に弱く、風呂がある住まいを持つものは少ない。下級武士は、市中の銭湯にも出入りをしたという。
そこでは流行の芝居や商品の“広告”まで壁に掲示され、世の動きが見えた。小さい湯船から流れる温かい空気。威勢の良い江戸っ子たちの声が響く。

「京の都からの“花嫁”さまが、ついにお城に入るってよ。」
「…それだ。えれぇ、豪勢な行列だったようじゃねぇか。」
批判の対象にもなるが、わりと徳川将軍家は庶民から親しまれているようだ。
中野には、意外だった。「へぇ…江戸の町衆は、楽しげに語るものだな。」
過激な考えに凝り固まった志士よりも、時に、町人たちの方が闊達(かったつ)と見える時がある。中野は、朝廷のもとに民が集う“新しい世“を思った。
(続く)
鍋島直正の愛娘・貢姫の嫁ぎ先は、現在では埼玉県にあった川越藩でした。大名の正室として、江戸にいた貢姫。
夫で川越藩主だった松平直侯が亡くなったことで、のち江戸を離れ、川越へと移る定めとなります。
幕末期の江戸は、世界最大の人口規模を誇ったと言われる“百万”都市。様々な人々が集まり、悲喜こもごもに暮らす大都会でした。
――江戸。川越藩の屋敷。
薄暗い冬の日。夫の喪に服する貢姫。若くして“未亡人”となってしまった。
「父上…、貢は鍋島の娘として、何事もなし得ませんでした。」
同じく、まだ二十代前半だった夫を失い、途方に暮れる。夫婦の間には、まだ子はいなかった。愛娘の心には、頼れる父・鍋島直正の面影が浮かぶ。
父の心配どおり、真面目な鍋島家の長女は、自責の念に駆られていた。
――同じ頃、離れた娘の境遇を心配する父・直正。
「貢よ、己を責めるでないっ!松平さまのお立場も、厳しかったのだ…」
「殿、いかがなさいました…!?」
ふと、語り出した直正(閑叟)。“幼なじみ”の側近・古川与一(松根)が慌てる。
「…わが娘が、助けを呼ぶかと思えてな。つい、声に出たようだ。」
「殿!いや、ご隠居…閑叟さま…。姫が、心配にございますな。」
――先月から佐賀の殿様は、正式に隠居している。
「与一よ。もしや、儂の呼び方を迷うておるか?」
色々と困惑する古川を見て、気が逸れたのか。わずかに笑みを見せる、直正。
「まだ、落ち着かぬから、当面は“殿”と呼べばよい。」
「…心得ました。では、いずれ“ご老公”とお呼びいたしましょうか。」
「その呼び名は…、何やら収まりが良くない。」
人生、苦もあれば楽もある。「ここも、先憂後楽じゃ。」と、自らに言い聞かせる“佐賀のご老公”であった。
――さて、大都市・江戸の市中。儒学者・大橋訥庵の私塾にて。
「老中の所業、許しがたし!」
「おう、安藤を討つべし!」
大声を出す若者たちが集まって、荒々しく武術の訓練に励む。都合の悪いことに、老中・安藤信正に対し、公然と物騒なことを口にしている。
「…もはやこの塾には、立ち寄るべきではないのかもしれぬな。」
その場を、遠巻きに眺めていた、佐賀藩士・中野方蔵がつぶやく。大木喬任と江藤新平が、手紙を楽しみに待つ親友である。
――晩秋には、孝明天皇の妹・和宮が江戸に到着していた。
その“花嫁”の行列は3万人規模とも言われる壮麗なものだった。尊王攘夷派への警戒から、平坦な東海道を避けて、あえて険しい中山道を通ったという。
和宮は、御所風の生活を続けることを強く望む。暮らし方の調整が難航して、1か月ほどは城に入らなかったという。
――また、気勢を挙げる者がいる。
「和宮様を、城へお連れ奉る謀(はかりごと)を打ち砕かん!」
「そうじゃ、皇女さまを奪還せよ!」
いまにも、市中に出撃しそうな雰囲気だ。
「かかる“短慮”に巻き込まれては、大木さんや江藤くんに申し訳が立たぬ。」
諸藩の志士との交流は、佐賀に帰ったのち、他藩と連携して勤王に励み、これからの日本を導くためだ。中野は騒ぎに背を向け、その場を去った。
――すっかり“都会暮らし”に、馴染んでいた中野。
当時の過密都市は火災に弱く、風呂がある住まいを持つものは少ない。下級武士は、市中の銭湯にも出入りをしたという。
そこでは流行の芝居や商品の“広告”まで壁に掲示され、世の動きが見えた。小さい湯船から流れる温かい空気。威勢の良い江戸っ子たちの声が響く。
「京の都からの“花嫁”さまが、ついにお城に入るってよ。」
「…それだ。えれぇ、豪勢な行列だったようじゃねぇか。」
批判の対象にもなるが、わりと徳川将軍家は庶民から親しまれているようだ。
中野には、意外だった。「へぇ…江戸の町衆は、楽しげに語るものだな。」
過激な考えに凝り固まった志士よりも、時に、町人たちの方が闊達(かったつ)と見える時がある。中野は、朝廷のもとに民が集う“新しい世“を思った。
(続く)
2021年12月21日
第17話「佐賀脱藩」⑫(陽だまりの下で)
こんばんは。前回の続きです。
大都市・江戸での生活を続ける親友・中野方蔵に対して、佐賀から出る予定のない江藤新平。
この頃、江藤の家は、佐賀城下の武家屋敷街の一角。藩の役人として、それなりの住まいに移っていたそうです。
親しい大木喬任や中野方蔵に比べても家格が低く、長年、貧乏暮らしでしたが、脱却を果たした感がありました。
――ある冬の日。江藤家の屋敷。
幾分、寒さが和らぎ、陽だまりの心地がする日。
江藤は、長男・熊太郎を抱きかかえていた。
「よし、熊太郎。そろそろ漢詩を教えようか。」
「新平さま。まだ熊太郎は、赤子ですよ。」
「…しかし。千代子どの。」
「さすがに漢詩は、早うございますよ。」
「鉄は熱いうちに打てと申すが。」
「貴方さまのお子ですよ。ご心配なさらずとも、賢くなります。」

――江藤夫婦の長男・熊太郎は数え年で2つ(満1歳)になる。
「それと“千代子どの”はやめてくださいませ。よそよそしいです。」
「お主も“新平さま”と呼んでおるではないか。お互い様だ。」
…コホンと、江藤の父・助右衛門の咳払いが響く。
「昼日中から、仲の良さそうなことだな。」
「よし、熊太郎には、儂から“一節”聞かせてやろう。」
「赤子に“浄瑠璃”(じょうるり)も、早うございます。」
ここは、江藤の母・浅子から、父・助右衛門に鋭い指摘が入る。
――とりあえず熊太郎が、ぐずっている。
「…しかしだな、浅子。」
何だか納得していない助右衛門。
「はいはい~、熊太郎くん。“叔父上”でちゅよ。」
そこで、横にいた若い男が、熊太郎を受け取ると、あやしはじめた。
「おおっ、源作!赤子のあやし方がうまいな。」
「旦那さまと、新平が下手すぎるのでございます。」
…江藤の父と母、まったく違う角度からの反応である。
「ははっ、父上や兄者と比べれば上手かですよ。」
その若い男は、江藤の弟・源作。

――軽く、調子の良い反応をした。兄ほどの堅物では無いようだ。
「よし、源作。儂も、熊太郎をあやしてみせるぞ。」
何やら強い決意を見せる、江藤の父・助右衛門。
「やーらしか(可愛い)、熊太郎。“じーじー”でちゅよ。」
「…さすがの江藤助右衛門も、初孫には弱かね…。」
鋭い才覚を持っていたが、信念を曲げず、よく上役と激突したという江藤の父・助右衛門。もはや、ただの孫大好きのおじいちゃんになっている。
――キャッキャッと上機嫌な、熊太郎。
「源作。大したものだな。感心したぞ。」
「…兄上。そがん感じ入らずとも、よかです…。」
父・助右衛門がお役目を解かれたため、江藤の少年期はかなりの貧乏だったが、父も役人に復帰。江藤自身も佐賀藩の貿易部門への転属が決まる。
藩の産業に関わる有意義な仕事に就くこととなり、佐賀城下で、相応の屋敷にも入った。長男・熊太郎も、まずまず健やかに育っている。
――だが、江藤の妻・千代子には胸騒ぎがあった。
寒い冬の中、陽だまりに包まれたような一日。こんな幸せがずっと続いてほしい。しかし、いとこだった千代子にも、卓越した江藤の才能は見えていた。
この人は、いつかは“時代”に必要とされ“大事”に関わることになるのだろう。そして、いま談笑する江藤家の人々は、皆、その覚悟を秘めているのだと。
(続く)
大都市・江戸での生活を続ける親友・中野方蔵に対して、佐賀から出る予定のない江藤新平。
この頃、江藤の家は、佐賀城下の武家屋敷街の一角。藩の役人として、それなりの住まいに移っていたそうです。
親しい大木喬任や中野方蔵に比べても家格が低く、長年、貧乏暮らしでしたが、脱却を果たした感がありました。
――ある冬の日。江藤家の屋敷。
幾分、寒さが和らぎ、陽だまりの心地がする日。
江藤は、長男・熊太郎を抱きかかえていた。
「よし、熊太郎。そろそろ漢詩を教えようか。」
「新平さま。まだ熊太郎は、赤子ですよ。」
「…しかし。千代子どの。」
「さすがに漢詩は、早うございますよ。」
「鉄は熱いうちに打てと申すが。」
「貴方さまのお子ですよ。ご心配なさらずとも、賢くなります。」
――江藤夫婦の長男・熊太郎は数え年で2つ(満1歳)になる。
「それと“千代子どの”はやめてくださいませ。よそよそしいです。」
「お主も“新平さま”と呼んでおるではないか。お互い様だ。」
…コホンと、江藤の父・助右衛門の咳払いが響く。
「昼日中から、仲の良さそうなことだな。」
「よし、熊太郎には、儂から“一節”聞かせてやろう。」
「赤子に“浄瑠璃”(じょうるり)も、早うございます。」
ここは、江藤の母・浅子から、父・助右衛門に鋭い指摘が入る。
――とりあえず熊太郎が、ぐずっている。
「…しかしだな、浅子。」
何だか納得していない助右衛門。
「はいはい~、熊太郎くん。“叔父上”でちゅよ。」
そこで、横にいた若い男が、熊太郎を受け取ると、あやしはじめた。
「おおっ、源作!赤子のあやし方がうまいな。」
「旦那さまと、新平が下手すぎるのでございます。」
…江藤の父と母、まったく違う角度からの反応である。
「ははっ、父上や兄者と比べれば上手かですよ。」
その若い男は、江藤の弟・源作。
――軽く、調子の良い反応をした。兄ほどの堅物では無いようだ。
「よし、源作。儂も、熊太郎をあやしてみせるぞ。」
何やら強い決意を見せる、江藤の父・助右衛門。
「やーらしか(可愛い)、熊太郎。“じーじー”でちゅよ。」
「…さすがの江藤助右衛門も、初孫には弱かね…。」
鋭い才覚を持っていたが、信念を曲げず、よく上役と激突したという江藤の父・助右衛門。もはや、ただの孫大好きのおじいちゃんになっている。
――キャッキャッと上機嫌な、熊太郎。
「源作。大したものだな。感心したぞ。」
「…兄上。そがん感じ入らずとも、よかです…。」
父・助右衛門がお役目を解かれたため、江藤の少年期はかなりの貧乏だったが、父も役人に復帰。江藤自身も佐賀藩の貿易部門への転属が決まる。
藩の産業に関わる有意義な仕事に就くこととなり、佐賀城下で、相応の屋敷にも入った。長男・熊太郎も、まずまず健やかに育っている。
――だが、江藤の妻・千代子には胸騒ぎがあった。
寒い冬の中、陽だまりに包まれたような一日。こんな幸せがずっと続いてほしい。しかし、いとこだった千代子にも、卓越した江藤の才能は見えていた。
この人は、いつかは“時代”に必要とされ“大事”に関わることになるのだろう。そして、いま談笑する江藤家の人々は、皆、その覚悟を秘めているのだと。
(続く)
2021年12月25日
第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)
こんばんは。
第17話は年内完結を目指しましたが、なかなか年末も忙しく、思惑どおりにはいきません。自由に動けないもどかしさ…を感じるところも多い1年でした。
今回の文久元年の師走(十二月)をイメージした話で、年内の“本編”はラストの予定です。なお、年末年始にも別企画での投稿ができればと考えています。
――江戸城内。書院にて。
幕閣から期待される、唐津藩・小笠原長行も、忙しく政務にあたる。生まれ故郷の唐津から、参勤交代で江戸に来たが、早くも能力の一端を見せている。
幕政の中心人物、老中・安藤信正と話をする。
「ご老中。先刻から上様のお姿が見当たりませぬが…。」
「小笠原どの。上様とて、時には羽を伸ばしたい時もござろうて。」
「何処に、いらっしゃるのですか。」
まだ少年の“上様”の行先を心配する小笠原長行。まるで“保護者”の目線。
「心配は無用。お庭に居られる。」

――ピッ…、ピピッ…。
籠〔かご〕に入った鳥を、優し気な眼差しで見つめる。幼い頃から、小動物を愛する子どもだった“上様”。第14代将軍・徳川家茂である。
「心が、安らぐのう…。」
「そちも、大空に羽ばたきたいか。」
「ピッ…、ピッピ。」
「昔の私なら、籠を開け放ち、そちを逃がしたであろうな。」
「ピッ…?」
寒さの増す師走だが、その日の江戸は、穏やかな陽光に包まれていた。
――多忙な政務の気晴らしか。
小鳥と語らう“上様”。
「しかしながら、そちを空に放たば、立ちどころに猛禽の餌食となろう…。」
「…ピッ!」
小鳥に物騒なことを語る上様。幼き日と違って様々な事も見えてくる。年頃は少年だが、武家の棟梁(とうりょう)・将軍だ。万事に責任を持たねばならない。
「許せ。私は、そちが傷つかぬよう、籠に留め置く。」
「ピピッ…」

――屋内から、その様子を窺(うかが)う女性たち。
「…あれが、公方(くぼう)様にあらしゃいます。」
傍にいた御付きの女性が、顔立ちに、あどけなさを残した少女にささやく。
「あの御方が…、公方さまやと?」
さすが気品のある顔立ち…といった印象。皇女・和宮である。話し方は“御所ことば”で柔らかいが、気難しい表情をした。
険しい中山道を来た京から江戸への旅路。望んでいた“京風”とは、ほど遠い江戸城内の暮らしでは、前将軍の正室・天璋院(篤姫)からの重圧も感じる。
――京を出て、和宮の表情は曇りがちだった。
江戸城には入ったが“婚礼”は年を越してからである。同年齢の“夫”の姿を、突然に見かけ、戸惑いが見られる。
「…公方さんは、よもや小鳥と話をされておるのか?」
「ええ、いかなお考えであらしゃいますやら。」
将軍(公方)・徳川家茂をどう理解したものか、考え込む京ことばの二人。
――眺める先には、将軍・家茂と籠の小鳥。
その周りをふんわりと陽だまりが包み込む。
「なんや武家らしゅうない、優しげな御方やな…。」
「それは、そうやもしれまへんなぁ。」
和宮の言葉に御付きの女性が相づちを打つ。武家らしく気詰まりな“夫”の姿を想像していた。拍子抜けしたか、固かった表情からは安堵の気配が見える。

――だが、この師走。江戸の市中は荒れていた。
「御用の者だ。神妙にいたせ!」
「おのれっ…無礼な幕吏(ばくり)どもめ。」
「手向かいいたすにおいては、容赦はせぬぞ!」
幕府の捕方が、尊王攘夷の志士たちが集まる私塾などを一斉に取り締まる。皇女・和宮の江戸への降嫁に際し、武装蜂起などを企てた嫌疑だった。
――江戸城下。佐賀藩の屋敷。
江戸詰めの藩士たちに、学問を教える役割だった副島種臣を、中野方蔵が訪ねていた。
「大橋先生の塾も、公儀(幕府)の取り締まりが入ったそうだな。」
「ええ、相当に物騒な有様(ありさま)となっておりましたゆえ。」
佐賀藩士・中野方蔵も、大橋訥庵の私塾にはよく立ち寄ったが、淡々と語る。塾に過激な浪士が関わっているのが危険と察知し、距離を取ったところだ。
「…中野も、あの塾に出入りしておったな。身辺に用心をすることだ。」
「当面は“昌平黌”(昌平坂学問所)への通いも控えます。」
「それが良かろう。」
――幕府公式の学問所でも、人脈を築いた中野。
尊王攘夷の志士が集まる私塾はもちろん危険だが、学問所も完全に幕府の領分。いま立ち寄るのは危うい。
「副島先生も、ご用心のほどを。」
「…うむ。」
副島種臣とて、勤王の思想家として名が知られる。穏やかでない年の瀬だ。佐賀藩上層部の“勤王”への動きは鈍い。副島にも、焦りはある。
「…然しながら、もはや軽挙はならぬのだ。」
中野には用心を念押しして、退出する後ろ姿を見送った。最近、謹慎が解けたばかりの副島である。ふと、溜め息をついた。
(続く)
〔参照記事〕
・第15話「江戸動乱」⑩(いざゆけ!次郎)
・第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)
・第16話「攘夷沸騰」⑨(玉石、相混じる)
第17話は年内完結を目指しましたが、なかなか年末も忙しく、思惑どおりにはいきません。自由に動けないもどかしさ…を感じるところも多い1年でした。
今回の文久元年の師走(十二月)をイメージした話で、年内の“本編”はラストの予定です。なお、年末年始にも別企画での投稿ができればと考えています。
――江戸城内。書院にて。
幕閣から期待される、唐津藩・小笠原長行も、忙しく政務にあたる。生まれ故郷の唐津から、参勤交代で江戸に来たが、早くも能力の一端を見せている。
幕政の中心人物、老中・安藤信正と話をする。
「ご老中。先刻から上様のお姿が見当たりませぬが…。」
「小笠原どの。上様とて、時には羽を伸ばしたい時もござろうて。」
「何処に、いらっしゃるのですか。」
まだ少年の“上様”の行先を心配する小笠原長行。まるで“保護者”の目線。
「心配は無用。お庭に居られる。」
――ピッ…、ピピッ…。
籠〔かご〕に入った鳥を、優し気な眼差しで見つめる。幼い頃から、小動物を愛する子どもだった“上様”。第14代将軍・徳川家茂である。
「心が、安らぐのう…。」
「そちも、大空に羽ばたきたいか。」
「ピッ…、ピッピ。」
「昔の私なら、籠を開け放ち、そちを逃がしたであろうな。」
「ピッ…?」
寒さの増す師走だが、その日の江戸は、穏やかな陽光に包まれていた。
――多忙な政務の気晴らしか。
小鳥と語らう“上様”。
「しかしながら、そちを空に放たば、立ちどころに猛禽の餌食となろう…。」
「…ピッ!」
小鳥に物騒なことを語る上様。幼き日と違って様々な事も見えてくる。年頃は少年だが、武家の棟梁(とうりょう)・将軍だ。万事に責任を持たねばならない。
「許せ。私は、そちが傷つかぬよう、籠に留め置く。」
「ピピッ…」
――屋内から、その様子を窺(うかが)う女性たち。
「…あれが、公方(くぼう)様にあらしゃいます。」
傍にいた御付きの女性が、顔立ちに、あどけなさを残した少女にささやく。
「あの御方が…、公方さまやと?」
さすが気品のある顔立ち…といった印象。皇女・和宮である。話し方は“御所ことば”で柔らかいが、気難しい表情をした。
険しい中山道を来た京から江戸への旅路。望んでいた“京風”とは、ほど遠い江戸城内の暮らしでは、前将軍の正室・天璋院(篤姫)からの重圧も感じる。
――京を出て、和宮の表情は曇りがちだった。
江戸城には入ったが“婚礼”は年を越してからである。同年齢の“夫”の姿を、突然に見かけ、戸惑いが見られる。
「…公方さんは、よもや小鳥と話をされておるのか?」
「ええ、いかなお考えであらしゃいますやら。」
将軍(公方)・徳川家茂をどう理解したものか、考え込む京ことばの二人。
――眺める先には、将軍・家茂と籠の小鳥。
その周りをふんわりと陽だまりが包み込む。
「なんや武家らしゅうない、優しげな御方やな…。」
「それは、そうやもしれまへんなぁ。」
和宮の言葉に御付きの女性が相づちを打つ。武家らしく気詰まりな“夫”の姿を想像していた。拍子抜けしたか、固かった表情からは安堵の気配が見える。
――だが、この師走。江戸の市中は荒れていた。
「御用の者だ。神妙にいたせ!」
「おのれっ…無礼な幕吏(ばくり)どもめ。」
「手向かいいたすにおいては、容赦はせぬぞ!」
幕府の捕方が、尊王攘夷の志士たちが集まる私塾などを一斉に取り締まる。皇女・和宮の江戸への降嫁に際し、武装蜂起などを企てた嫌疑だった。
――江戸城下。佐賀藩の屋敷。
江戸詰めの藩士たちに、学問を教える役割だった副島種臣を、中野方蔵が訪ねていた。
「大橋先生の塾も、公儀(幕府)の取り締まりが入ったそうだな。」
「ええ、相当に物騒な有様(ありさま)となっておりましたゆえ。」
佐賀藩士・中野方蔵も、大橋訥庵の私塾にはよく立ち寄ったが、淡々と語る。塾に過激な浪士が関わっているのが危険と察知し、距離を取ったところだ。
「…中野も、あの塾に出入りしておったな。身辺に用心をすることだ。」
「当面は“昌平黌”(昌平坂学問所)への通いも控えます。」
「それが良かろう。」
――幕府公式の学問所でも、人脈を築いた中野。
尊王攘夷の志士が集まる私塾はもちろん危険だが、学問所も完全に幕府の領分。いま立ち寄るのは危うい。
「副島先生も、ご用心のほどを。」
「…うむ。」
副島種臣とて、勤王の思想家として名が知られる。穏やかでない年の瀬だ。佐賀藩上層部の“勤王”への動きは鈍い。副島にも、焦りはある。
「…然しながら、もはや軽挙はならぬのだ。」
中野には用心を念押しして、退出する後ろ姿を見送った。最近、謹慎が解けたばかりの副島である。ふと、溜め息をついた。
(続く)
〔参照記事〕
・
・
・
2022年01月25日
第17話「佐賀脱藩」⑭(拓〔ひら〕け、代品方)
こんばんは。
“本編”の再開は、旧暦・新暦の差はありつつも、時期をあわせてみました。
文久二年(1862年)の年明けから、二十日ほど後を想定したお話です。
世間の正月気分も抜けきったかと思われる頃。佐賀藩では、新年も激しく働く者たちがいました。
――佐賀城下。藩の貿易部門“代品方”の拠点。
「白蝋(はくろう)ば、着いたと。」
「早う、数えんね!」
荷車が入り、藩の役人たちの間に飛び交う声。
櫨(はぜ)の木から精製した蝋(ろう)が、詰め込まれた木箱が到着している。
「箱の中も改めんば、ならんばい。」
鍋島家の一門が治める、白石領(みやき町)周辺から発送された品である。

――急ぎ、検品と数量の確認を要するらしい。
「心得た。」
この部署では、新入りと思われる佐賀藩士・江藤新平が木箱に向かう。
「!」
次の瞬間、積み荷の状態が変動する。すさまじい気迫で箱に向き合う、江藤。テキパキと箱を仕分け、検品と帳面の記載をこなしていく。
「…あん(の)男。たしか…」
「上佐賀代官所から来た、江藤と申す者。なかなか働きますばい。」
――「帳面を付け申した。品も数も問題のなかです。」
よく通る声でビシッと言い切った、江藤。
「よか。こん(の)荷は、まず伊万里まで運ばんね。」
江藤の仕事ぶりに、上役も疑いを差し挟まない。
もっとも、佐賀藩の生産管理は相当に厳しい。蝋を生産する側の領民たちも、相当な努力を重ねていた。
「ゆけっ!」と、木箱を載せた荷車は西へと送り出された。佐賀藩の各地域で栽培されたハゼの木から作られる白蝋は、西洋各国も重視する品だった。

――各地に設置が進む、佐賀藩の交易拠点。
蒸気船など西洋式軍艦の購入を進める佐賀藩。支払いの一部を、白蝋に代表される、金銭以外の代わりの品(代品)で補ったという。
また、陶磁器の販路を求めて、上方の大坂にも拠点を設置。幕府の貿易船を利用して、清国の上海(シャンハイ)にも進出の計画があった。
「我らは、かなり急(せ)わしい。あのような“働き者”は好ましか。」
佐賀藩が注力し、急拡大していく貿易業務。格好を気にする様子もなく、一風変わった男でも、仕事が出来れば良い。代品方の上役は、満足気だった。
――夕刻。佐賀城下の武家屋敷通り。
「江藤、どうね。代品方のお役目は。」
「坂井さんか。久しい。本年も、よろしく頼む。」
「そうだったな。まだ、睦月(一月)だったか。」
通りで出会ったのは“義祭同盟”の一員・坂井辰之允。こちらも忙しそうだ。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)〕
その中で、昨年までの代官所務めから転じた、江藤の仕事も気にかけていた。この坂井は、面倒見の良い気性であるのかもしれない。

――江藤は忙しく働きつつも、思うところがあるようだ。
「“代品方”は、お家(鍋島家)に利を為す、お役目と心得る。」
「それは、よか。きっと、お主なら出世もできる。」
「坂井さん。このまま“お家”大事と励むのは、正しいことか。」
佐賀が豊かになり、雄藩として存在感を増すのは、江藤や坂井など義祭同盟の面々にとっても良い話だ。
しかし開国以来、物流などは混乱し、経済に諸外国の影響が強く出ている。打ち払おうとする側の攘夷活動も勢いづいていた。
――持ち前の才覚で、仕事が順調なはずの江藤。
しかし江藤が藩の仕事に励む中でも、諸藩の志士たちの活動は「国の形から変えねばならぬ」という尊王思想とも結びつき、時勢は大きく動いている。
きっと時流を読んでいる江藤だから、焦るのだ。坂井が言葉を返した。
「そこはお主らがいつも語りおる大親友・中野方蔵くんに任せれば、よか。」
「然り。中野は江戸にて、我らの進むべき道を切り開いている。」
他藩の志士と大都会・江戸で交流する、中野からの手紙。佐賀に留まる同志に希望を与えている。江藤と話す坂井とて、便りを心待ちにする一人なのだ。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」④(上方からの“花嫁”)〕

――「まぁ、中野が居るけん、そがん焦らずとも…」
坂井は「…怠らず、お役目に励めば、そのうち道も拓けるだろう」と続けた。
親身になり熱心に語る、坂井。その背後に人影があることに気付かない。
「大木さん、どうした。何があった。」
江藤が、坂井の後ろの人影に向かって言葉を発する。そこに突っ立っていたのは、大木喬任(民平)だった。
「おっと…声ぐらいは、かけんね…」
気配の無かった大木に驚いて振り向いた坂井は、言葉を途中で止めた。
――明らかに、大木の様子がおかしい。
「…文(ふみ)が来た。江戸にいる、中野からだ。」
大木の表情に、いつものような手紙が来た時の嬉しそうな感じは無い。
憤るか、悲しむか…何か感情を抑え込むように小刻みな震えが感じられる。
「もしや、中野の身に何かあったか。」
江藤が険しい表情を見せ、鋭く言葉を返した。
(続く)
“本編”の再開は、旧暦・新暦の差はありつつも、時期をあわせてみました。
文久二年(1862年)の年明けから、二十日ほど後を想定したお話です。
世間の正月気分も抜けきったかと思われる頃。佐賀藩では、新年も激しく働く者たちがいました。
――佐賀城下。藩の貿易部門“代品方”の拠点。
「白蝋(はくろう)ば、着いたと。」
「早う、数えんね!」
荷車が入り、藩の役人たちの間に飛び交う声。
櫨(はぜ)の木から精製した蝋(ろう)が、詰め込まれた木箱が到着している。
「箱の中も改めんば、ならんばい。」
鍋島家の一門が治める、白石領(みやき町)周辺から発送された品である。
――急ぎ、検品と数量の確認を要するらしい。
「心得た。」
この部署では、新入りと思われる佐賀藩士・江藤新平が木箱に向かう。
「!」
次の瞬間、積み荷の状態が変動する。すさまじい気迫で箱に向き合う、江藤。テキパキと箱を仕分け、検品と帳面の記載をこなしていく。
「…あん(の)男。たしか…」
「上佐賀代官所から来た、江藤と申す者。なかなか働きますばい。」
――「帳面を付け申した。品も数も問題のなかです。」
よく通る声でビシッと言い切った、江藤。
「よか。こん(の)荷は、まず伊万里まで運ばんね。」
江藤の仕事ぶりに、上役も疑いを差し挟まない。
もっとも、佐賀藩の生産管理は相当に厳しい。蝋を生産する側の領民たちも、相当な努力を重ねていた。
「ゆけっ!」と、木箱を載せた荷車は西へと送り出された。佐賀藩の各地域で栽培されたハゼの木から作られる白蝋は、西洋各国も重視する品だった。
――各地に設置が進む、佐賀藩の交易拠点。
蒸気船など西洋式軍艦の購入を進める佐賀藩。支払いの一部を、白蝋に代表される、金銭以外の代わりの品(代品)で補ったという。
また、陶磁器の販路を求めて、上方の大坂にも拠点を設置。幕府の貿易船を利用して、清国の上海(シャンハイ)にも進出の計画があった。
「我らは、かなり急(せ)わしい。あのような“働き者”は好ましか。」
佐賀藩が注力し、急拡大していく貿易業務。格好を気にする様子もなく、一風変わった男でも、仕事が出来れば良い。代品方の上役は、満足気だった。
――夕刻。佐賀城下の武家屋敷通り。
「江藤、どうね。代品方のお役目は。」
「坂井さんか。久しい。本年も、よろしく頼む。」
「そうだったな。まだ、睦月(一月)だったか。」
通りで出会ったのは“義祭同盟”の一員・坂井辰之允。こちらも忙しそうだ。
〔参照(後半):
その中で、昨年までの代官所務めから転じた、江藤の仕事も気にかけていた。この坂井は、面倒見の良い気性であるのかもしれない。
――江藤は忙しく働きつつも、思うところがあるようだ。
「“代品方”は、お家(鍋島家)に利を為す、お役目と心得る。」
「それは、よか。きっと、お主なら出世もできる。」
「坂井さん。このまま“お家”大事と励むのは、正しいことか。」
佐賀が豊かになり、雄藩として存在感を増すのは、江藤や坂井など義祭同盟の面々にとっても良い話だ。
しかし開国以来、物流などは混乱し、経済に諸外国の影響が強く出ている。打ち払おうとする側の攘夷活動も勢いづいていた。
――持ち前の才覚で、仕事が順調なはずの江藤。
しかし江藤が藩の仕事に励む中でも、諸藩の志士たちの活動は「国の形から変えねばならぬ」という尊王思想とも結びつき、時勢は大きく動いている。
きっと時流を読んでいる江藤だから、焦るのだ。坂井が言葉を返した。
「そこはお主らがいつも語りおる大親友・中野方蔵くんに任せれば、よか。」
「然り。中野は江戸にて、我らの進むべき道を切り開いている。」
他藩の志士と大都会・江戸で交流する、中野からの手紙。佐賀に留まる同志に希望を与えている。江藤と話す坂井とて、便りを心待ちにする一人なのだ。
〔参照(中盤):
――「まぁ、中野が居るけん、そがん焦らずとも…」
坂井は「…怠らず、お役目に励めば、そのうち道も拓けるだろう」と続けた。
親身になり熱心に語る、坂井。その背後に人影があることに気付かない。
「大木さん、どうした。何があった。」
江藤が、坂井の後ろの人影に向かって言葉を発する。そこに突っ立っていたのは、大木喬任(民平)だった。
「おっと…声ぐらいは、かけんね…」
気配の無かった大木に驚いて振り向いた坂井は、言葉を途中で止めた。
――明らかに、大木の様子がおかしい。
「…文(ふみ)が来た。江戸にいる、中野からだ。」
大木の表情に、いつものような手紙が来た時の嬉しそうな感じは無い。
憤るか、悲しむか…何か感情を抑え込むように小刻みな震えが感じられる。
「もしや、中野の身に何かあったか。」
江藤が険しい表情を見せ、鋭く言葉を返した。
(続く)
2022年01月29日
第17話「佐賀脱藩」⑮(急転、江戸からの風)
こんにちは。
年が明けてからしばらく後、江戸から佐賀に届いた一通の手紙。大都会から届く中野方蔵の便りは、佐賀の同志たちの希望となっていたのですが…
少しばかり時間を遡って、舞台は文久二年(1862年)の年明け直後の江戸。現代では東京にあたる大都会。各地の出身者に“物語”があったことでしょう。
志士への追跡が強まる江戸で不急の外出を避けている中野方蔵。明治初期に東京への首都移転に活躍した大木喬任・江藤新平の親友の“物語”です。

――澄み切った正月の空気が漂う、江戸の街。
歳末を乗り切った長屋の町人たちの声が響く。
「おぅ、今年もよろしくな。」
「元気そうじゃねぇか、おっかねえ“掛取り”から逃げ切ったようだな。」
「おうよ、この通り清々しい新年だ。」
江戸期の商慣習で、歳末には売掛金の回収が集中する傾向があったようだ。いわば、年越しまで借金取りから逃げ切った男の武勇伝である。
「でもな、一時は逃げ切っても、後が怖えぞ…。」
「めでてぇ、正月から野暮(やぼ)な話は言いっこなしでぃ!」
――町人地に近い通りを行く、佐賀藩士・中野方蔵。
「年始まで、“掛取り”から逃げ切ったか…。」
少し風もある日だ。流れてくる、江戸の日常に耳を傾けながら小路を行く。
当時、勤王を唱える、諸藩の志士たちへの取り締まりは厳しくなる一方だ。
とくに皇女・和宮の降嫁に際して、挙兵のうえで“奪還”を図ったという儒学者・大橋訥庵の一派への追及は厳しい。
その大橋の私塾に出入りした中野も、幕府の捕り方に気をつけねばならない。
「無用な動きは、避けるに越した事はなかね…」

――『君子、危うきに近寄らず』と行きたい状況である。
佐賀の先輩・副島種臣とも相談し、しばらく中野は幕府の昌平坂学問所への出席を見送っていた。もちろん、市中の私塾にも出入りはしない。
〔参照(終盤):第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)〕
日用品の確保など所用を済ませ、急ぎ足で江戸での居宅に戻る。佐賀での住まいに比べれば、相当に狭いが単身で暮らすには問題はない。
郷里に置いてきた家族、離れている仲間たち。このように籠もった暮らし振りならば、もはや江戸に居続ける値打ちは無いのかもしれない。
中野は居宅に落ち着くと、佐賀から届いていた手紙に目を通した。
――「中野へ。この度“代品方”に転じることとなった。」
「へぇ、江藤くんは、いよいよ交易に関わるか。これは幸いだ。」
情報収集に熱心で“早耳”の中野。佐賀藩の貿易部門は、上方(京・大坂)への拠点強化に乗り出している。
「中野とともに“国事”に奔走するには、まだ時がかかりそうだ。」
「…承知。佐賀に戻るまでに、こちらもひと踏ん張りせんばね。」
これが都市生活の孤独か。江藤からの手紙に、中野は言葉を返してしまう。
――「近々、大木さんからも文(ふみ)を書き送る。」
江藤からの手紙は、大木からの通信の予告で結んでいた。この三人の関わり方は親友というより、もはや兄弟のようですらあった。
「…楽しみにしていますね。」
手紙を読み終えた、中野は軽く笑みを見せた。
一人の時間が戻る。学問所や私塾で志士たちと交流してきたが、取り締まりを警戒して、今は自粛をしている。
江戸での充実した日々を送ってきた中野にとっては、珍しく暇がある。
「そういえば、初風呂ぐらいは行っておくか。」

――江戸市中の湯屋(銭湯)に、出向いた中野。
そんな銭湯の脱衣所だ。また、活気のある江戸庶民の声が響いている。
「おう、今年は初顔合わせか。」
「あ~あ、新年もお前さんの、しけた面(つら)見ながら暮らすのかぁ…」
中野は都会にも馴染み、活きの良い江戸っ子の会話はむしろ耳に優しい。
「…もはや、こういった喧噪(けんそう)も落ち着くな。」
一言、つぶやいた中野。これからの佐賀のため、いや日本のためには諸藩との人脈を築いておくべきで、時間も足らない。
しかし、たまには町人の世間話に耳を傾ける、穏やかな時間も良いものだ。
――その時、にわかに出入り口が騒がしくなった。
その場に居合わせた町人たちが、さざめく。
「お役人だ…。」
「何の騒ぎでぃ…。」
物々しい幕府の捕り方が数人。ずかずかと銭湯に乗り込んできた。そして、あっという間に中野の周囲を取り巻いた。
「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」
人が集まり、狭い銭湯に逃げ場は無い。腰の刀も、先だって預けてしまった。
中野はスッと前を向いて、居並ぶ捕り方たちと目を合わせた。
(続く)
年が明けてからしばらく後、江戸から佐賀に届いた一通の手紙。大都会から届く中野方蔵の便りは、佐賀の同志たちの希望となっていたのですが…
少しばかり時間を遡って、舞台は文久二年(1862年)の年明け直後の江戸。現代では東京にあたる大都会。各地の出身者に“物語”があったことでしょう。
志士への追跡が強まる江戸で不急の外出を避けている中野方蔵。明治初期に東京への首都移転に活躍した大木喬任・江藤新平の親友の“物語”です。

――澄み切った正月の空気が漂う、江戸の街。
歳末を乗り切った長屋の町人たちの声が響く。
「おぅ、今年もよろしくな。」
「元気そうじゃねぇか、おっかねえ“掛取り”から逃げ切ったようだな。」
「おうよ、この通り清々しい新年だ。」
江戸期の商慣習で、歳末には売掛金の回収が集中する傾向があったようだ。いわば、年越しまで借金取りから逃げ切った男の武勇伝である。
「でもな、一時は逃げ切っても、後が怖えぞ…。」
「めでてぇ、正月から野暮(やぼ)な話は言いっこなしでぃ!」
――町人地に近い通りを行く、佐賀藩士・中野方蔵。
「年始まで、“掛取り”から逃げ切ったか…。」
少し風もある日だ。流れてくる、江戸の日常に耳を傾けながら小路を行く。
当時、勤王を唱える、諸藩の志士たちへの取り締まりは厳しくなる一方だ。
とくに皇女・和宮の降嫁に際して、挙兵のうえで“奪還”を図ったという儒学者・大橋訥庵の一派への追及は厳しい。
その大橋の私塾に出入りした中野も、幕府の捕り方に気をつけねばならない。
「無用な動きは、避けるに越した事はなかね…」
――『君子、危うきに近寄らず』と行きたい状況である。
佐賀の先輩・副島種臣とも相談し、しばらく中野は幕府の昌平坂学問所への出席を見送っていた。もちろん、市中の私塾にも出入りはしない。
〔参照(終盤):
日用品の確保など所用を済ませ、急ぎ足で江戸での居宅に戻る。佐賀での住まいに比べれば、相当に狭いが単身で暮らすには問題はない。
郷里に置いてきた家族、離れている仲間たち。このように籠もった暮らし振りならば、もはや江戸に居続ける値打ちは無いのかもしれない。
中野は居宅に落ち着くと、佐賀から届いていた手紙に目を通した。
――「中野へ。この度“代品方”に転じることとなった。」
「へぇ、江藤くんは、いよいよ交易に関わるか。これは幸いだ。」
情報収集に熱心で“早耳”の中野。佐賀藩の貿易部門は、上方(京・大坂)への拠点強化に乗り出している。
「中野とともに“国事”に奔走するには、まだ時がかかりそうだ。」
「…承知。佐賀に戻るまでに、こちらもひと踏ん張りせんばね。」
これが都市生活の孤独か。江藤からの手紙に、中野は言葉を返してしまう。
――「近々、大木さんからも文(ふみ)を書き送る。」
江藤からの手紙は、大木からの通信の予告で結んでいた。この三人の関わり方は親友というより、もはや兄弟のようですらあった。
「…楽しみにしていますね。」
手紙を読み終えた、中野は軽く笑みを見せた。
一人の時間が戻る。学問所や私塾で志士たちと交流してきたが、取り締まりを警戒して、今は自粛をしている。
江戸での充実した日々を送ってきた中野にとっては、珍しく暇がある。
「そういえば、初風呂ぐらいは行っておくか。」
――江戸市中の湯屋(銭湯)に、出向いた中野。
そんな銭湯の脱衣所だ。また、活気のある江戸庶民の声が響いている。
「おう、今年は初顔合わせか。」
「あ~あ、新年もお前さんの、しけた面(つら)見ながら暮らすのかぁ…」
中野は都会にも馴染み、活きの良い江戸っ子の会話はむしろ耳に優しい。
「…もはや、こういった喧噪(けんそう)も落ち着くな。」
一言、つぶやいた中野。これからの佐賀のため、いや日本のためには諸藩との人脈を築いておくべきで、時間も足らない。
しかし、たまには町人の世間話に耳を傾ける、穏やかな時間も良いものだ。
――その時、にわかに出入り口が騒がしくなった。
その場に居合わせた町人たちが、さざめく。
「お役人だ…。」
「何の騒ぎでぃ…。」
物々しい幕府の捕り方が数人。ずかずかと銭湯に乗り込んできた。そして、あっという間に中野の周囲を取り巻いた。
「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」
人が集まり、狭い銭湯に逃げ場は無い。腰の刀も、先だって預けてしまった。
中野はスッと前を向いて、居並ぶ捕り方たちと目を合わせた。
(続く)
2022年02月01日
第17話「佐賀脱藩」⑯(つながりは諸刃の剣)
こんばんは。
文久二年(1862年)。年明け早々の江戸市中。ある銭湯に来ていた、佐賀藩士・中野方蔵は逃げ道のない窮地にありました。
中野は、親友の二人。熟慮する大木喬任(民平)とも、理論派の江藤新平とも少し違ったタイプで、人との交流に長けている印象です。
佐賀から全国へ、今後の政局に向けた人脈をつくるため、中野は、留学先の幕府の学問所だけでなく、市中の私塾にも出入りしました。
この時期、皇女・和宮の江戸降嫁に際して、儒学者・大橋訥庵らに挙兵を企てた容疑がかかっており、関係者が次々と捕縛(ほばく)されています。
人付き合いの範囲が広い中野は、この大橋の塾にも出入りしていたのです。では、前回のラストの場面から、ご覧ください。

――銭湯の表口から幕府の捕り方が、中野方蔵を取り囲む。
「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」
捕り方のまとめ役が“御用改め”について、第一声を発した。
「はっ、佐賀の中野と申すは、それがしにござります。」
「神妙(しんみょう)にいたせ!」
「仰せのとおり、大橋の塾に出入りしたことがござります。」
「…そうか、認めるか。」
――充実した、他藩の志士との交友関係。
それが自身を危機にと追いやっているのだが、中野は泰然としている。
「何か大事でも、起き申したか。」
逆に捕り方に質問をする中野。
「…極めて、不埒(ふらち)な企てがあったと申しておこう。」
捕り方は言葉をにごした。江戸に入られた皇女・和宮“奪還”の計画があったなどど、口にできない。町人や下級武士も多い銭湯などで語れる事ではない。

――何やら、どちらが尋問しているかわからない。
先んじて、話をぐいぐいと進める中野。
「それは、けしからぬ事。そのような塾と見抜けず、恥じ入りまする。」
「中野とか申す者。その方にも疑いはかかっておるのだぞ。」
捕り方は、少し呆れたような物言いをした。
「それがしが存じおるような事柄は、包み隠さず申し上げます。」
「…それは、殊勝(しゅしょう)な心がけではないか。」
「かかるお疑いを持たれるとは、それがしの不徳の致すところ。」
「…では、お縄を頂戴(ちょうだい)しろ。」
――粛々と“仕事”は進むが、中野の勢いに押され気味の幕府の捕り方。
「やむを得ぬ事に、ございます。」
中野は、やけに、あっさり“捕まる”と答えた。
「…わかっておるではないか。」
捕り方が、拍子(ひょうし)抜けした表情を見せる。
中野方蔵については、意外に“豪傑肌”という評価もある。逃げても捕まるから得策ではないと考えたか、粛々(しゅくしゅく)と受け答えを進める。

――中野が来た銭湯は、一時騒然とした。
捕り方のまとめ役が、少し調子を崩して、こう言った。
「では、…引っ立てぇ~ぃ。」
「おいおい。あの兄ちゃん、連れて行かれちまったぜ…」
しばらく江戸っ子たちは、どよめいていたが、直に世間話へと戻っていった。
和宮の行列が江戸へと入った、文久元年の年末から翌・文久二年の年明けまで、このように志士の捕縛は相次いでいた。
黙っていなかったのは“尊王攘夷”思想の儒学者・大橋訥庵に連なる者たち。その中でも過激な残党だった。
――そして、中野が幕吏に捕らえられてから3日ほど後。
パァン!
江戸城・坂下門外に銃声が響く。弾丸は老中・安藤信正の乗る、駕籠(かご)に向けて放たれた。
「天子さまを唆(そそのか)し、皇女さまを江戸にお連れ奉った事、許せん。」
「奸物(かんぶつ)、安藤め。覚悟しろ!」
まず駕籠への銃声で合図を兼ねて、襲撃対象者の足を止めて斬りかかる。
この2年近く前にも水戸脱藩などの浪士たちが、大老・井伊直弼を襲撃した。その“桜田門外の変”を思わせるような手口だった。
(続く)
文久二年(1862年)。年明け早々の江戸市中。ある銭湯に来ていた、佐賀藩士・中野方蔵は逃げ道のない窮地にありました。
中野は、親友の二人。熟慮する大木喬任(民平)とも、理論派の江藤新平とも少し違ったタイプで、人との交流に長けている印象です。
佐賀から全国へ、今後の政局に向けた人脈をつくるため、中野は、留学先の幕府の学問所だけでなく、市中の私塾にも出入りしました。
この時期、皇女・和宮の江戸降嫁に際して、儒学者・大橋訥庵らに挙兵を企てた容疑がかかっており、関係者が次々と捕縛(ほばく)されています。
人付き合いの範囲が広い中野は、この大橋の塾にも出入りしていたのです。では、前回のラストの場面から、ご覧ください。
――銭湯の表口から幕府の捕り方が、中野方蔵を取り囲む。
「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」
捕り方のまとめ役が“御用改め”について、第一声を発した。
「はっ、佐賀の中野と申すは、それがしにござります。」
「神妙(しんみょう)にいたせ!」
「仰せのとおり、大橋の塾に出入りしたことがござります。」
「…そうか、認めるか。」
――充実した、他藩の志士との交友関係。
それが自身を危機にと追いやっているのだが、中野は泰然としている。
「何か大事でも、起き申したか。」
逆に捕り方に質問をする中野。
「…極めて、不埒(ふらち)な企てがあったと申しておこう。」
捕り方は言葉をにごした。江戸に入られた皇女・和宮“奪還”の計画があったなどど、口にできない。町人や下級武士も多い銭湯などで語れる事ではない。
――何やら、どちらが尋問しているかわからない。
先んじて、話をぐいぐいと進める中野。
「それは、けしからぬ事。そのような塾と見抜けず、恥じ入りまする。」
「中野とか申す者。その方にも疑いはかかっておるのだぞ。」
捕り方は、少し呆れたような物言いをした。
「それがしが存じおるような事柄は、包み隠さず申し上げます。」
「…それは、殊勝(しゅしょう)な心がけではないか。」
「かかるお疑いを持たれるとは、それがしの不徳の致すところ。」
「…では、お縄を頂戴(ちょうだい)しろ。」
――粛々と“仕事”は進むが、中野の勢いに押され気味の幕府の捕り方。
「やむを得ぬ事に、ございます。」
中野は、やけに、あっさり“捕まる”と答えた。
「…わかっておるではないか。」
捕り方が、拍子(ひょうし)抜けした表情を見せる。
中野方蔵については、意外に“豪傑肌”という評価もある。逃げても捕まるから得策ではないと考えたか、粛々(しゅくしゅく)と受け答えを進める。
――中野が来た銭湯は、一時騒然とした。
捕り方のまとめ役が、少し調子を崩して、こう言った。
「では、…引っ立てぇ~ぃ。」
「おいおい。あの兄ちゃん、連れて行かれちまったぜ…」
しばらく江戸っ子たちは、どよめいていたが、直に世間話へと戻っていった。
和宮の行列が江戸へと入った、文久元年の年末から翌・文久二年の年明けまで、このように志士の捕縛は相次いでいた。
黙っていなかったのは“尊王攘夷”思想の儒学者・大橋訥庵に連なる者たち。その中でも過激な残党だった。
――そして、中野が幕吏に捕らえられてから3日ほど後。
パァン!
江戸城・坂下門外に銃声が響く。弾丸は老中・安藤信正の乗る、駕籠(かご)に向けて放たれた。
「天子さまを唆(そそのか)し、皇女さまを江戸にお連れ奉った事、許せん。」
「奸物(かんぶつ)、安藤め。覚悟しろ!」
まず駕籠への銃声で合図を兼ねて、襲撃対象者の足を止めて斬りかかる。
この2年近く前にも水戸脱藩などの浪士たちが、大老・井伊直弼を襲撃した。その“桜田門外の変”を思わせるような手口だった。
(続く)
2022年02月05日
第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)
こんばんは。
前回の続きです。文久二年(1862年)の一月、江戸城門前で老中・安藤信正が襲撃された“坂下門外の変”の場面を描きました。
これは既に幕府に捕らえられていた佐賀藩士・中野方蔵の立場では、極めて都合の悪い展開だったはずです。
大木喬任・江藤新平らは、親友・中野方蔵を窮地から救おうと奔走することに。今回のお話は、江戸(東京)と佐賀の往復で展開します。
――老中襲撃事件の直後、江戸城内は騒然としていた。
「対馬守(安藤信正)さまは、ご無事なのだな!」
「手傷は負われておいでですが、お命には別状はござらぬ。」
「賊は、一人残らず、斬り捨て申した!」
「おのれ…不逞(ふてい)の浪士どもめ!」
“桜田門外の変”とは異なり、駕籠の中にいた老中・安藤信正には、襲撃者が放った銃弾が当たらなかった。
警備も厳重となっており、“坂下門外の変”では浪士たちの計画は失敗に終わったのである。
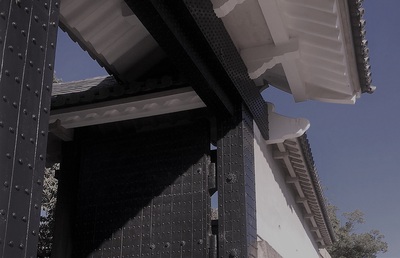
――この事件には、余波があった。
城内の書院にも幕閣たちが集まり、騒然としている。
「ご老中は、安藤さまは!いかがなさいましたか。」
「…小笠原どのか。ご無事ではあったのだがな。」
諸外国との難事にも対応した老中・安藤。唐津藩・小笠原長行ら、開国を進める幕府官僚の評判は悪くなかったが、負傷により療養、求心力が低下する。
「その場で打ち合わず、逃げ去るとは…。」
「武家の名折れよ…。」
どこからともなく、批判も湧いてくる。幕府内部にも、襲撃から身を守るべく退避した老中・安藤に、「そもそも“武士として”どうか」という声までが生じる。
老中を襲撃した浪士たちの狙いの一つ、幕府を揺さぶる効果は生じていた。
――冬の突き抜けた寒さが続く、江戸の牢獄。
「大木兄さん、江藤くん…それがし、少々調子づいていたのかもしれませぬ。」
弱々しく反省の言葉をつぶやく、中野方蔵。あるいは急ぎ過ぎていたのか、人付き合いを広げすぎたのかもしれない。
中野は、獄中からの手紙をしたためていた。
「…これも“身から出た錆”。恥じ入るばかりです。」
いつものように、佐賀の同志たちに熱気を伝える文面を書ける状況にはない。囚われの身では高らかに“国事”を語ることはできないのだ。
――佐賀。大木が右拳に握りしめているのは、中野からの手紙。
「…中野。」
「都合の悪か事に、安藤老中を襲った者たちは、大橋の塾の門弟らしい。」
江藤は淡々と語っているが、内心は大木と同じ想いだ。
「一時、中野が出入りした塾だな。」
その場に居合わせた坂井辰之允。以前の、中野からの手紙を思い起こす。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」④(上方からの“花嫁”)〕
ここで、江藤が一言を発する。
「獄につながれておるとはいえ、文(ふみ)が届くならば、途切れず続けよう。」

――江戸。次第に身体の弱っていく中野のもとに手紙が届いた。
差出人は、江藤だった。
「…どうした、中野。まるで、囚われの佳人(美人)のようではないか。」
「これもお主が軽率に人と関わったゆえ。お疑いが晴れるまで辛抱せよ。」
途中で役人が見る事を想定したか。堅物の江藤にしては、軽い文面である。
「中野は“八方美人”だったのか騒動に巻き込まれた」と見せたい意図か。
許される範囲で中野も筆を執った。親友二人には伝えておきたい事がある。
「江藤くん、大木兄さんにもお伝えください。この国に必要な学問の事です。」
――佐賀城内。大木は藩の重役に掛け合っていた。
「中野は藩校・弘道館でも規律を重んじた男。暴挙には関わりのなかです。」
「…騒動の首魁(しゅかい)・大橋の塾に出入りしたのだぞ。」
中野方蔵、藩校では“優等生”の振る舞いだった。佐賀藩の上層部にも受けが良いため、江戸に出られた経緯がある。
〔参照:第15話「江戸動乱」⑤(仮面の優等生)〕
――それが、いまや幕府から老中襲撃への関与を疑われている。
「まさか、中野があのような騒ぎに関わるとは…。」
佐賀藩保守派の筆頭格・原田小四郎をはじめ、重役たちに動揺も見られる。
「あやつは、学ぶ気持ちの強すぎ、人付き合いの良過ぎたとです。」
大木は、腹立ち気味に言い放った。
「中野は勉強熱心ゆえに、市中の私塾にも出入りした」という訴えだ。

――話は通らない。もどかしい思いのまま、その場から退出する大木。
「大木さん、いかがだったか。」
江藤が尋ねる。大木は無言で拳を握り、口惜しそうにしている。
「…まだだ。神陽先生も、副島さんもいる。諦(あきら)める道理は無い。」
大木は絞り出すように語った。
親友・中野を救う努力を打ち消すように、“坂下門外の変”が暗い影を落とす。大木や江藤が期待する面々に、幕府に気を遣う“保守派”の手が回っていた。
――再び、江戸。佐賀藩の屋敷でも訴えを続ける者がいた。
「あれは短慮に加わる者ではない。中野の釈放を掛け合っていただきたい。」
大木・江藤の先輩格である、副島種臣も上役への談判を繰り返している。
「副島よ、伝えねばならない事がある。」
「…先のお話を、お聞き届けくだされ。」
「佐賀のご隠居の傍に仕えよ。内密の役目ゆえ、他国との関わりも許さぬ。」
江戸で若手藩士の学問を指導する副島だが、佐賀に送還されることとなった。
前藩主・鍋島直正の側近に加えるためという名目も付き、自由に手紙を出す事も禁じられたのである。
(続く)
前回の続きです。文久二年(1862年)の一月、江戸城門前で老中・安藤信正が襲撃された“坂下門外の変”の場面を描きました。
これは既に幕府に捕らえられていた佐賀藩士・中野方蔵の立場では、極めて都合の悪い展開だったはずです。
大木喬任・江藤新平らは、親友・中野方蔵を窮地から救おうと奔走することに。今回のお話は、江戸(東京)と佐賀の往復で展開します。
――老中襲撃事件の直後、江戸城内は騒然としていた。
「対馬守(安藤信正)さまは、ご無事なのだな!」
「手傷は負われておいでですが、お命には別状はござらぬ。」
「賊は、一人残らず、斬り捨て申した!」
「おのれ…不逞(ふてい)の浪士どもめ!」
“桜田門外の変”とは異なり、駕籠の中にいた老中・安藤信正には、襲撃者が放った銃弾が当たらなかった。
警備も厳重となっており、“坂下門外の変”では浪士たちの計画は失敗に終わったのである。
――この事件には、余波があった。
城内の書院にも幕閣たちが集まり、騒然としている。
「ご老中は、安藤さまは!いかがなさいましたか。」
「…小笠原どのか。ご無事ではあったのだがな。」
諸外国との難事にも対応した老中・安藤。唐津藩・小笠原長行ら、開国を進める幕府官僚の評判は悪くなかったが、負傷により療養、求心力が低下する。
「その場で打ち合わず、逃げ去るとは…。」
「武家の名折れよ…。」
どこからともなく、批判も湧いてくる。幕府内部にも、襲撃から身を守るべく退避した老中・安藤に、「そもそも“武士として”どうか」という声までが生じる。
老中を襲撃した浪士たちの狙いの一つ、幕府を揺さぶる効果は生じていた。
――冬の突き抜けた寒さが続く、江戸の牢獄。
「大木兄さん、江藤くん…それがし、少々調子づいていたのかもしれませぬ。」
弱々しく反省の言葉をつぶやく、中野方蔵。あるいは急ぎ過ぎていたのか、人付き合いを広げすぎたのかもしれない。
中野は、獄中からの手紙をしたためていた。
「…これも“身から出た錆”。恥じ入るばかりです。」
いつものように、佐賀の同志たちに熱気を伝える文面を書ける状況にはない。囚われの身では高らかに“国事”を語ることはできないのだ。
――佐賀。大木が右拳に握りしめているのは、中野からの手紙。
「…中野。」
「都合の悪か事に、安藤老中を襲った者たちは、大橋の塾の門弟らしい。」
江藤は淡々と語っているが、内心は大木と同じ想いだ。
「一時、中野が出入りした塾だな。」
その場に居合わせた坂井辰之允。以前の、中野からの手紙を思い起こす。
〔参照(中盤):
ここで、江藤が一言を発する。
「獄につながれておるとはいえ、文(ふみ)が届くならば、途切れず続けよう。」
――江戸。次第に身体の弱っていく中野のもとに手紙が届いた。
差出人は、江藤だった。
「…どうした、中野。まるで、囚われの佳人(美人)のようではないか。」
「これもお主が軽率に人と関わったゆえ。お疑いが晴れるまで辛抱せよ。」
途中で役人が見る事を想定したか。堅物の江藤にしては、軽い文面である。
「中野は“八方美人”だったのか騒動に巻き込まれた」と見せたい意図か。
許される範囲で中野も筆を執った。親友二人には伝えておきたい事がある。
「江藤くん、大木兄さんにもお伝えください。この国に必要な学問の事です。」
――佐賀城内。大木は藩の重役に掛け合っていた。
「中野は藩校・弘道館でも規律を重んじた男。暴挙には関わりのなかです。」
「…騒動の首魁(しゅかい)・大橋の塾に出入りしたのだぞ。」
中野方蔵、藩校では“優等生”の振る舞いだった。佐賀藩の上層部にも受けが良いため、江戸に出られた経緯がある。
〔参照:
――それが、いまや幕府から老中襲撃への関与を疑われている。
「まさか、中野があのような騒ぎに関わるとは…。」
佐賀藩保守派の筆頭格・原田小四郎をはじめ、重役たちに動揺も見られる。
「あやつは、学ぶ気持ちの強すぎ、人付き合いの良過ぎたとです。」
大木は、腹立ち気味に言い放った。
「中野は勉強熱心ゆえに、市中の私塾にも出入りした」という訴えだ。
――話は通らない。もどかしい思いのまま、その場から退出する大木。
「大木さん、いかがだったか。」
江藤が尋ねる。大木は無言で拳を握り、口惜しそうにしている。
「…まだだ。神陽先生も、副島さんもいる。諦(あきら)める道理は無い。」
大木は絞り出すように語った。
親友・中野を救う努力を打ち消すように、“坂下門外の変”が暗い影を落とす。大木や江藤が期待する面々に、幕府に気を遣う“保守派”の手が回っていた。
――再び、江戸。佐賀藩の屋敷でも訴えを続ける者がいた。
「あれは短慮に加わる者ではない。中野の釈放を掛け合っていただきたい。」
大木・江藤の先輩格である、副島種臣も上役への談判を繰り返している。
「副島よ、伝えねばならない事がある。」
「…先のお話を、お聞き届けくだされ。」
「佐賀のご隠居の傍に仕えよ。内密の役目ゆえ、他国との関わりも許さぬ。」
江戸で若手藩士の学問を指導する副島だが、佐賀に送還されることとなった。
前藩主・鍋島直正の側近に加えるためという名目も付き、自由に手紙を出す事も禁じられたのである。
(続く)
2022年02月08日
第17話「佐賀脱藩」⑱(青葉茂れる頃に)
こんばんは。前回の続きです。ついに、この話を書かねばならなくなりました。
大木喬任(民平)・江藤新平の親友・中野方蔵。江戸の牢獄につながれたまま、釈放の見通しはたちません。
中野が捕縛された直後(3日ほど後と言われる)の“坂下門外の変”が暗い影を落としています。
佐賀藩内で一定の影響力を持つ、師匠・枝吉神陽や先輩・副島種臣も、幕府との軋轢(あつれき)を恐れた保守派の手回しか、打開は難しかったようです。
絶望的な状況の中で、中野は佐賀での青春の日々を回想していました。
――10年ばかり前。佐賀藩校・弘道館近く。
さすがに勉学に熱が入り過ぎた、議論疲れもした。ほどよい草むらを見つけ、ごろりと仰向けになる三人。
「青空だな…天下危急の折にも、のんびりしたもんだ。」
「天は動じず、雲は自在に変じるか。」
「大木兄さん、江藤くん。お二人とも、漢詩でも詠むのですか。」
「中野、何やら言い方にトゲのあるごたぞ。」
山のような書籍を読み疲れた、大木が少しごにゃごにゃと言う。

――「中野、お主の存念を聞こうか。」
あまり周囲の空気を読まない江藤だが、中野が何かを語りたがっているのは、わかるようだ。
「さすがは江藤くん、そう来なくては。」
中野が、勢いよく言葉を返す。
「雲を見てください。」
「…本日も、モクモクと威勢の良いことだ。“雲見酒”も良いかもな。」
本日、これからは用事も無い。酒好きの大木は、飲みたいらしい。
――その一方で、中野はまだ語りたいようだ。
「常日頃の“佐賀ん雲”だな。そこに中野は何を見る。」
江藤が問う。傍目(はため)には仰向けで、だらりとした書生3人。
「今、まさに変じようとしている“国の形”です。」
佐賀の青くて、近いような空。白い雲が風に乗り、形を変えていく。
「…そうか、お主が語りたいのは“国体”か。」
次第に、幕末の熱気を帯びてくる。ようやく大木も中野の話に乗ってきた。

――中野は、より熱く語る。
「雲はくっついて離れて、また形を変じる。」
「…たしかに“政”(まつりごと)の如しだな。」
「我らが“風”となり、雲を集めて行かねばなりません。」
朝廷が中心となり、民が等しくその下に集う国の形。その力になるという中野の決意表明だ。
「いつもの“佐賀ん雲”から、そこまで語るか。」
大木は感心したか、呆れたか。楽しそうではあるが、複雑な表情を見せる。
――サーッと、楠(くすのき)の枝葉に風がそよぐ。
「なれば、寄り集まった後の、仕組みづくりが入り用だな。」
江藤は、中野の話の続きを語った。
「そうです。その場には、江藤くんと大木兄さんが居れば間違いない。」
「…よし、わかった。中野が、我らを先導しろ。」
「はい!きっと、我ら三人で“国事”を動かす日が来るはずです。」
この3人の中では、一番年少の中野。元気よく、まとめの言葉を放った。
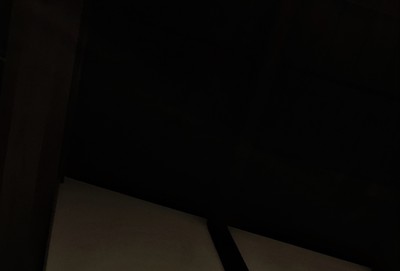
――江戸の牢獄。そんな青春の日々が遠い。
「…もう一度、佐賀の空が見たかね…。」
何やら胃の腑(ふ)が苦しい。仰向けとなった中野の眼前に見えるのは、ただ暗い牢の天井である。
すると、腹部全体にグッと激痛が走った。
「…これは、毒をもられている!?」
吐き戻そうにも、総身に痛みが回ったような感覚だ。意識は遠のいていく。
佐賀に残した家族が心配だ…、郷里の空に描いた志も果たせそうにない。
――文久二年の五月。
「大木兄さん、江藤くん。すまない…後を頼んだ。」
中野方蔵が世を去ったのは、初夏の青葉が茂れる頃。佐賀の“義祭同盟”の仲間たちが敬愛する“勤王の象徴”・楠木正成の命日だったという。
(続く)
大木喬任(民平)・江藤新平の親友・中野方蔵。江戸の牢獄につながれたまま、釈放の見通しはたちません。
中野が捕縛された直後(3日ほど後と言われる)の“坂下門外の変”が暗い影を落としています。
佐賀藩内で一定の影響力を持つ、師匠・枝吉神陽や先輩・副島種臣も、幕府との軋轢(あつれき)を恐れた保守派の手回しか、打開は難しかったようです。
絶望的な状況の中で、中野は佐賀での青春の日々を回想していました。
――10年ばかり前。佐賀藩校・弘道館近く。
さすがに勉学に熱が入り過ぎた、議論疲れもした。ほどよい草むらを見つけ、ごろりと仰向けになる三人。
「青空だな…天下危急の折にも、のんびりしたもんだ。」
「天は動じず、雲は自在に変じるか。」
「大木兄さん、江藤くん。お二人とも、漢詩でも詠むのですか。」
「中野、何やら言い方にトゲのあるごたぞ。」
山のような書籍を読み疲れた、大木が少しごにゃごにゃと言う。
――「中野、お主の存念を聞こうか。」
あまり周囲の空気を読まない江藤だが、中野が何かを語りたがっているのは、わかるようだ。
「さすがは江藤くん、そう来なくては。」
中野が、勢いよく言葉を返す。
「雲を見てください。」
「…本日も、モクモクと威勢の良いことだ。“雲見酒”も良いかもな。」
本日、これからは用事も無い。酒好きの大木は、飲みたいらしい。
――その一方で、中野はまだ語りたいようだ。
「常日頃の“佐賀ん雲”だな。そこに中野は何を見る。」
江藤が問う。傍目(はため)には仰向けで、だらりとした書生3人。
「今、まさに変じようとしている“国の形”です。」
佐賀の青くて、近いような空。白い雲が風に乗り、形を変えていく。
「…そうか、お主が語りたいのは“国体”か。」
次第に、幕末の熱気を帯びてくる。ようやく大木も中野の話に乗ってきた。
――中野は、より熱く語る。
「雲はくっついて離れて、また形を変じる。」
「…たしかに“政”(まつりごと)の如しだな。」
「我らが“風”となり、雲を集めて行かねばなりません。」
朝廷が中心となり、民が等しくその下に集う国の形。その力になるという中野の決意表明だ。
「いつもの“佐賀ん雲”から、そこまで語るか。」
大木は感心したか、呆れたか。楽しそうではあるが、複雑な表情を見せる。
――サーッと、楠(くすのき)の枝葉に風がそよぐ。
「なれば、寄り集まった後の、仕組みづくりが入り用だな。」
江藤は、中野の話の続きを語った。
「そうです。その場には、江藤くんと大木兄さんが居れば間違いない。」
「…よし、わかった。中野が、我らを先導しろ。」
「はい!きっと、我ら三人で“国事”を動かす日が来るはずです。」
この3人の中では、一番年少の中野。元気よく、まとめの言葉を放った。
――江戸の牢獄。そんな青春の日々が遠い。
「…もう一度、佐賀の空が見たかね…。」
何やら胃の腑(ふ)が苦しい。仰向けとなった中野の眼前に見えるのは、ただ暗い牢の天井である。
すると、腹部全体にグッと激痛が走った。
「…これは、毒をもられている!?」
吐き戻そうにも、総身に痛みが回ったような感覚だ。意識は遠のいていく。
佐賀に残した家族が心配だ…、郷里の空に描いた志も果たせそうにない。
――文久二年の五月。
「大木兄さん、江藤くん。すまない…後を頼んだ。」
中野方蔵が世を去ったのは、初夏の青葉が茂れる頃。佐賀の“義祭同盟”の仲間たちが敬愛する“勤王の象徴”・楠木正成の命日だったという。
(続く)
2022年02月12日
第17話「佐賀脱藩」⑲(残された2人)
こんばんは。前回の続きです。
文久二年(1862年)の五月。佐賀藩士・中野方蔵は、“坂下門外の変”への関与を疑われ、江戸の牢獄に入ったまま、その生涯を閉じました。
中野の親友だった大木喬任(民平)・江藤新平の二人は、しばらく後の六月に詳細を知ります。
“坂下門外の変”の負傷もあり、老中・安藤信正は辞職。幕政は揺らぎます。
その頃、薩摩藩(鹿児島)や長州藩(山口)は、朝廷の権威による力を得るべく京都で積極的に活動。雄藩は政局への影響力を競い始めていました。

――佐賀城下。大木の家。
「大木さん、邪魔をするぞ!」
きわめて険しい表情をした江藤新平。勢いよく大木家の土間へと至る。
「…ああ、江藤。ようやく来たか。」
大木喬任(民平)は、少し呆けたようにぼんやりとしている。
江戸から来た手紙はあるが、もはや差出人は親友・中野方蔵ではない。
「我ら二人は、また中野に置いて行かれてしまったようだ。」
――江藤の眼前に浮かぶ、今まで見たことのない大木の表情。
その目には、あふれんばかりの涙が不自然なほどに溜まっていた。
「正しく状況を伝えてほしい。中野はどうしたのか。」
江藤が鋭く問う。本心では、大木の答えを聞きたくはない。
「…旅立ったよ。俺たちを置いて、あの雲の向こうにな。」
ここでも、大木は気の抜けたように続けた。
「そげな感傷にひたっている場合か!」
「大木さん…、今日のところは、失礼する!」
続けざまにピリピリと響くような声を発する、江藤。入った時と同じ勢いで家の玄関を出ていった。

――しばらく後、佐賀城下の屋敷に帰った、江藤。
江藤の妻・千代子が心配する。夫・新平の様子が明らかに落ち着かない。
「昼過ぎより、小城に行って参る。留守を頼む。」
かろうじて行き先を告げるも、いつもと違い千代子とは目を合わせない新平。その心が、悲しみに満ちていることは語らずとも伝わってくる。
「はい。お気を付けて。」
夫の背中には何らかの決意が見て取れる。あるいは、将来に予感した大事が、すでに起きているのかもしれない。
千代子はキュッと拳を握る。夫に変事があろうと、江藤家と幼い長男・熊太郎は守り切る。そう覚悟を決めていた。
――数日後。再び佐賀城下・大木家。江藤が来ている。
「先日は、無礼をした。」
「…いや、俺も相当に腑抜け(ふぬけ)ていたようだ。」
「中野は、よか男だった。」
「そうだな。我ら三人で、最も美しい生き方をしていたのは中野だった。」
「なれば、佳人(美人)薄命と言うべきか。」
「この文(ふみ)が、中野からの最後の言葉だ。」

――そこには、今までの想いを込めた手紙を大事にしてほしいとあった。
「よく文(ふみ)が届くと思ったが、我ら二人への“形見”とする覚悟だったか。」
中野は手紙でも、政治や教育のあるべき姿を熱く語っていた。
自身が倒れても、その想いは残そうとしたか。いつも走っていた中野の面影は、今も大木と江藤、二人の中にある。
「…だが、“佐賀の雲”で描いた我らの夢も、暴風に散り散り…だな。」
一見、諦(あきら)めたように語る、大木。
――だが、弱々しい、その言葉に反して。
江藤の顔を覗き込む、大木の眼差しには光があった。
「さて、江藤くん。そろそろ“本題”を言わんね。」
大木が、少し中野の口調を真似(まね)て語る。柄(がら)にもないことをするので、似ていない。
「…やはり、大木さんには、わかるようだな。」
江藤が失笑をこらえて、言葉を返す。
――ついに江藤は、その決意を語った。
「中野が斃(たお)れた今、佐賀は時勢に遅れる一方だ。」
「それだけ、あいつの存在は大きかったということだ。」
「吾(われ)のほかに、中野の代わりに立つべき者は居らぬ。」
ついに江藤は佐賀を脱藩し、政局の中心となりつつある京都で行動する計画を大木に打ち明けた。
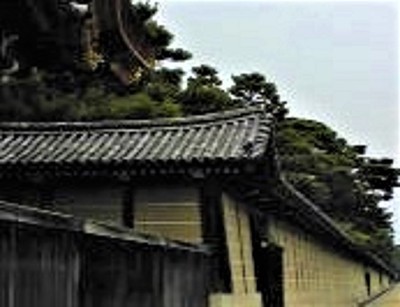
「江藤、一寸(ちょっと)待て。」
大木は、双手の動きとともに、わかりやすく次の言葉を遮(さえぎ)った。
「大木さん。たしかに“国”を抜けることは重罪だ。」
「…佐賀は出入りに厳しかぞ。他国とは、同じに考えん方がよか。」
――時に、“二重鎖国”とまで語られる肥前佐賀藩。
佐賀城下では旅人の滞在期間も縛り、通行も長崎街道に制限する。情報管理には、とりわけ厳しい。ましてや佐賀藩士の脱藩など論外で、重罰は必至だ。
「それも覚悟のうえ。それゆえ、大木さんには、先んじて伝えている。」
「だから、少し待て。」
「いや、今立たねばならん。」
江藤は、大木に鋭く言葉を返す。後に引くつもりはないらしい。
「…誰も止めてはおらん。ただ、これを持っていけ。」
大木が立ち上がり、背後にある戸棚に向かう。然(しか)る後に、江藤に向けて突き出したのはズシンと重みのある袋だった。
(続く)
文久二年(1862年)の五月。佐賀藩士・中野方蔵は、“坂下門外の変”への関与を疑われ、江戸の牢獄に入ったまま、その生涯を閉じました。
中野の親友だった大木喬任(民平)・江藤新平の二人は、しばらく後の六月に詳細を知ります。
“坂下門外の変”の負傷もあり、老中・安藤信正は辞職。幕政は揺らぎます。
その頃、薩摩藩(鹿児島)や長州藩(山口)は、朝廷の権威による力を得るべく京都で積極的に活動。雄藩は政局への影響力を競い始めていました。
――佐賀城下。大木の家。
「大木さん、邪魔をするぞ!」
きわめて険しい表情をした江藤新平。勢いよく大木家の土間へと至る。
「…ああ、江藤。ようやく来たか。」
大木喬任(民平)は、少し呆けたようにぼんやりとしている。
江戸から来た手紙はあるが、もはや差出人は親友・中野方蔵ではない。
「我ら二人は、また中野に置いて行かれてしまったようだ。」
――江藤の眼前に浮かぶ、今まで見たことのない大木の表情。
その目には、あふれんばかりの涙が不自然なほどに溜まっていた。
「正しく状況を伝えてほしい。中野はどうしたのか。」
江藤が鋭く問う。本心では、大木の答えを聞きたくはない。
「…旅立ったよ。俺たちを置いて、あの雲の向こうにな。」
ここでも、大木は気の抜けたように続けた。
「そげな感傷にひたっている場合か!」
「大木さん…、今日のところは、失礼する!」
続けざまにピリピリと響くような声を発する、江藤。入った時と同じ勢いで家の玄関を出ていった。
――しばらく後、佐賀城下の屋敷に帰った、江藤。
江藤の妻・千代子が心配する。夫・新平の様子が明らかに落ち着かない。
「昼過ぎより、小城に行って参る。留守を頼む。」
かろうじて行き先を告げるも、いつもと違い千代子とは目を合わせない新平。その心が、悲しみに満ちていることは語らずとも伝わってくる。
「はい。お気を付けて。」
夫の背中には何らかの決意が見て取れる。あるいは、将来に予感した大事が、すでに起きているのかもしれない。
千代子はキュッと拳を握る。夫に変事があろうと、江藤家と幼い長男・熊太郎は守り切る。そう覚悟を決めていた。
――数日後。再び佐賀城下・大木家。江藤が来ている。
「先日は、無礼をした。」
「…いや、俺も相当に腑抜け(ふぬけ)ていたようだ。」
「中野は、よか男だった。」
「そうだな。我ら三人で、最も美しい生き方をしていたのは中野だった。」
「なれば、佳人(美人)薄命と言うべきか。」
「この文(ふみ)が、中野からの最後の言葉だ。」
――そこには、今までの想いを込めた手紙を大事にしてほしいとあった。
「よく文(ふみ)が届くと思ったが、我ら二人への“形見”とする覚悟だったか。」
中野は手紙でも、政治や教育のあるべき姿を熱く語っていた。
自身が倒れても、その想いは残そうとしたか。いつも走っていた中野の面影は、今も大木と江藤、二人の中にある。
「…だが、“佐賀の雲”で描いた我らの夢も、暴風に散り散り…だな。」
一見、諦(あきら)めたように語る、大木。
――だが、弱々しい、その言葉に反して。
江藤の顔を覗き込む、大木の眼差しには光があった。
「さて、江藤くん。そろそろ“本題”を言わんね。」
大木が、少し中野の口調を真似(まね)て語る。柄(がら)にもないことをするので、似ていない。
「…やはり、大木さんには、わかるようだな。」
江藤が失笑をこらえて、言葉を返す。
――ついに江藤は、その決意を語った。
「中野が斃(たお)れた今、佐賀は時勢に遅れる一方だ。」
「それだけ、あいつの存在は大きかったということだ。」
「吾(われ)のほかに、中野の代わりに立つべき者は居らぬ。」
ついに江藤は佐賀を脱藩し、政局の中心となりつつある京都で行動する計画を大木に打ち明けた。
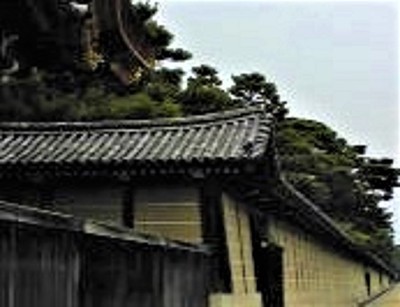
「江藤、一寸(ちょっと)待て。」
大木は、双手の動きとともに、わかりやすく次の言葉を遮(さえぎ)った。
「大木さん。たしかに“国”を抜けることは重罪だ。」
「…佐賀は出入りに厳しかぞ。他国とは、同じに考えん方がよか。」
――時に、“二重鎖国”とまで語られる肥前佐賀藩。
佐賀城下では旅人の滞在期間も縛り、通行も長崎街道に制限する。情報管理には、とりわけ厳しい。ましてや佐賀藩士の脱藩など論外で、重罰は必至だ。
「それも覚悟のうえ。それゆえ、大木さんには、先んじて伝えている。」
「だから、少し待て。」
「いや、今立たねばならん。」
江藤は、大木に鋭く言葉を返す。後に引くつもりはないらしい。
「…誰も止めてはおらん。ただ、これを持っていけ。」
大木が立ち上がり、背後にある戸棚に向かう。然(しか)る後に、江藤に向けて突き出したのはズシンと重みのある袋だった。
(続く)
2022年02月15日
第17話「佐賀脱藩」⑳(ご隠居が遣わす者)
こんばんは。前回の続きです。
現在のお話の前年、文久元年(1861年)に幕府に協力し、朝廷との橋渡しをする形で長州藩(山口)が、雄藩としての存在感を示します。
続く文久二年の春には、島津斉彬の異母弟で、薩摩藩を仕切る島津久光が動きます。京都に千人の兵を率いて上り、幕政改革への圧力をかけました。
先手を打たれたかと思えば打ち返し、加熱する薩長の競争。朝廷は“安全装置”とする思惑か、佐賀を含む他藩にも“勤王”を呼びかけたと言います。

こうして雄藩の政局への参画は強まります。カギとなるのは、京の都でした。
文久二年六月。江藤新平と大木喬任(民平)が向き合う佐賀城下の大木家。親友・中野方蔵の想いは、この2人に受け継がれています。
――明らかに金の入った袋を、江藤に突き出す大木。
「大木さん、これは何の真似(まね)だ。」
「…言わねばわからんか。こいは、餞別(せんべつ)たい。」
大木は、言葉を続ける。
「お前がどれだけ金子(きんす)を整えておるかは知らん。」
「ただ資金もなく、有為の動きができると思わんことだ。」
「その理はわかる。しかし、これだけの金を受け取る道理もない。」
――江藤の言葉に軽く笑みを浮かべる、大木。
「…俺は狡(ずる)いのだ。中野の想いをお前に押しつけようとしている。」
「では、大木さんも、ともに佐賀を出るか。」
江藤は発言の真意を測りかねた。大木も想いは同じで、ともに脱藩したいのではないか。
「いや、俺は行かぬ。」
大木は算段をしていた。二人で動けばそれだけ目立ち、出費は嵩(かさ)む。
中野が生きていた時には「早く、大木兄さんも江戸に来てください」とやたらに引っ張られたが、単独でも動けると期待されたのは、むしろ江藤だろう。
〔参照:第15話「江戸動乱」④(起きろ!兄さん!)〕

――ここは江藤を先に行かせねばならぬ。大木はそう考えた。
「…中野は、よう見えとったばい。放っておいても、江藤は動くとな。」
「承知した。金はありがたく“借り受ける”ことにする。」
大木の想いと、当座の資金が詰まった袋を受け取り、恭しく礼をする。京では他藩と関わるだけでなく、公家にも当たらねばならない。
資金が幾らでも要るのは、江藤もわかっていた。
「…して、佐賀を出てどうするつもりだ。」
「中野が居らぬ、江戸に出ても意義はなか。京で“形勢”を探る。」
――もともと同じ想いだった二人。本題に入る。
「江藤。京の都に行くとは…、古川さまと関わりがあるごたな。」
「然(しか)り。閑叟さまのもとを離れないはずの御仁が、佐賀を発った。」
六月の上旬には、佐賀の前藩主・鍋島直正の幼少期からの側近、古川与一(松根)が京都に派遣された。
古川は、直正の生活面の手配りをする人物。芸術にも造詣が深く、審美眼のある一級の文化人でもある。
直正(閑叟)は、「与一がいないと、何かと不便だ…」とか直ぐ言い出すそうだ。西洋風に言えば、古川は有能な執事である。
〔参照(中盤):第16話「攘夷沸騰」⑦(父娘の心配事)〕

――この主従が離れて行動するには、それなりの訳があるに違いない。
「古川さまは、京で公家衆に接触するはず。」
佐賀藩において文化的素養の高さで、古川の右に出る者は思い当たらない。この人選は、朝廷から佐賀へ内密の打診があったのかもしれない。
「近々に、閑叟さまは、京へと向かうのであろう。」
「なるほど。佐賀の動きに先駆けて、江藤が調べを行うのだな。」
隠居して自由の身となった、佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。その動向は、全国から注目される。
――ここからの佐賀の動きは、諸国にも影響するはずだ。
「…やがては、この国の行く末を決するに相違ない。」
江藤は確信を持ったように、言葉を結んだ。
亡き友・中野方蔵が志した、朝廷のもとに民が集う“国”を目指す。そこには、西洋の知識に通じた、佐賀藩の存在が不可欠なはずだ。
「佐賀が動くことが、中野が想った“国の形”につながるのか。」
「そこまで、閑叟さまをお連れする事、それは我が役目と心得ている。」
諸外国との力の差を考えない、無謀な攘夷論が渦巻く京の都。佐賀のご隠居・鍋島直正(閑叟)が、上洛した際に巻き込まれぬよう“道案内”が要る。
江藤の真意を聞くや、大木はニッと表情を緩めた。
(続く)
現在のお話の前年、文久元年(1861年)に幕府に協力し、朝廷との橋渡しをする形で長州藩(山口)が、雄藩としての存在感を示します。
続く文久二年の春には、島津斉彬の異母弟で、薩摩藩を仕切る島津久光が動きます。京都に千人の兵を率いて上り、幕政改革への圧力をかけました。
先手を打たれたかと思えば打ち返し、加熱する薩長の競争。朝廷は“安全装置”とする思惑か、佐賀を含む他藩にも“勤王”を呼びかけたと言います。

こうして雄藩の政局への参画は強まります。カギとなるのは、京の都でした。
文久二年六月。江藤新平と大木喬任(民平)が向き合う佐賀城下の大木家。親友・中野方蔵の想いは、この2人に受け継がれています。
――明らかに金の入った袋を、江藤に突き出す大木。
「大木さん、これは何の真似(まね)だ。」
「…言わねばわからんか。こいは、餞別(せんべつ)たい。」
大木は、言葉を続ける。
「お前がどれだけ金子(きんす)を整えておるかは知らん。」
「ただ資金もなく、有為の動きができると思わんことだ。」
「その理はわかる。しかし、これだけの金を受け取る道理もない。」
――江藤の言葉に軽く笑みを浮かべる、大木。
「…俺は狡(ずる)いのだ。中野の想いをお前に押しつけようとしている。」
「では、大木さんも、ともに佐賀を出るか。」
江藤は発言の真意を測りかねた。大木も想いは同じで、ともに脱藩したいのではないか。
「いや、俺は行かぬ。」
大木は算段をしていた。二人で動けばそれだけ目立ち、出費は嵩(かさ)む。
中野が生きていた時には「早く、大木兄さんも江戸に来てください」とやたらに引っ張られたが、単独でも動けると期待されたのは、むしろ江藤だろう。
〔参照:
――ここは江藤を先に行かせねばならぬ。大木はそう考えた。
「…中野は、よう見えとったばい。放っておいても、江藤は動くとな。」
「承知した。金はありがたく“借り受ける”ことにする。」
大木の想いと、当座の資金が詰まった袋を受け取り、恭しく礼をする。京では他藩と関わるだけでなく、公家にも当たらねばならない。
資金が幾らでも要るのは、江藤もわかっていた。
「…して、佐賀を出てどうするつもりだ。」
「中野が居らぬ、江戸に出ても意義はなか。京で“形勢”を探る。」
――もともと同じ想いだった二人。本題に入る。
「江藤。京の都に行くとは…、古川さまと関わりがあるごたな。」
「然(しか)り。閑叟さまのもとを離れないはずの御仁が、佐賀を発った。」
六月の上旬には、佐賀の前藩主・鍋島直正の幼少期からの側近、古川与一(松根)が京都に派遣された。
古川は、直正の生活面の手配りをする人物。芸術にも造詣が深く、審美眼のある一級の文化人でもある。
直正(閑叟)は、「与一がいないと、何かと不便だ…」とか直ぐ言い出すそうだ。西洋風に言えば、古川は有能な執事である。
〔参照(中盤):
――この主従が離れて行動するには、それなりの訳があるに違いない。
「古川さまは、京で公家衆に接触するはず。」
佐賀藩において文化的素養の高さで、古川の右に出る者は思い当たらない。この人選は、朝廷から佐賀へ内密の打診があったのかもしれない。
「近々に、閑叟さまは、京へと向かうのであろう。」
「なるほど。佐賀の動きに先駆けて、江藤が調べを行うのだな。」
隠居して自由の身となった、佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。その動向は、全国から注目される。
――ここからの佐賀の動きは、諸国にも影響するはずだ。
「…やがては、この国の行く末を決するに相違ない。」
江藤は確信を持ったように、言葉を結んだ。
亡き友・中野方蔵が志した、朝廷のもとに民が集う“国”を目指す。そこには、西洋の知識に通じた、佐賀藩の存在が不可欠なはずだ。
「佐賀が動くことが、中野が想った“国の形”につながるのか。」
「そこまで、閑叟さまをお連れする事、それは我が役目と心得ている。」
諸外国との力の差を考えない、無謀な攘夷論が渦巻く京の都。佐賀のご隠居・鍋島直正(閑叟)が、上洛した際に巻き込まれぬよう“道案内”が要る。
江藤の真意を聞くや、大木はニッと表情を緩めた。
(続く)
2022年02月17日
第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)
こんばんは。
思い入れの強かった“本編”第17話を今回の投稿で、ひとまず書き終えます。親友・中野方蔵が世を去ったことで、佐賀から出る決意を固めた江藤新平。
中野から「兄さん」とも慕われた大木喬任(民平)から資金を借り受け、旅立つ準備を進めます。江藤が佐賀を発ったのは文久二年(1862年)六月。
その前年あたりは、江藤らの師匠・枝吉神陽への面会を求めて、九州北部の各地から志士たちが佐賀に来訪した時期でした。
――“幕府寄り”と見られていた肥前佐賀藩。
朝廷に関わる諸藩の動向について情報が不足する。それを徹底して集めねばならない。江藤は大木に「京の都にて形勢を探る」と脱藩の目的を説明した。
「中野からの文(ふみ)に名があった者に、当たるつもりだ。」
「まずは長州の…、久坂という者か。」
長州(山口)の俊才・久坂玄瑞の名が出る。中野方蔵が送った、江戸からの手紙に度々登場した人物だ。
「久坂どのが、京に居るかはわからぬが、長州には当たらねばなるまい。」
根拠は無いが、次第に自信に満ちあふれた表情となる大木・江藤の二人。

――まるで、傍で親友・中野方蔵が笑っていた青春の日々のようだ。
「では、他国の“有為の者”たちとは、どうつなぎを取る。」
「佐賀を抜ければ、福岡を通る。それゆえ平野さまも尋ねてみるつもりだ。」
江藤は前年の秋、佐賀に来訪した福岡脱藩・平野国臣を話題にした。勤王家として知られた平野は、九州諸藩の志士たちの力を集めようとしていた。
二人は鎌倉期のような時代がかった装束で熱く語る“福岡のさぶらい”・平野を想い出し、少し愉快そうな表情を浮かべる。
〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕
そして平野は、福岡の支藩・秋月藩の海賀宮門、久留米の神官・真木和泉(保臣)などとつながる。
筑前・筑後の勤王志士たちは、いささか復古主義的な傾向はあるが、気概に満ちあふれており、京の都でも活動していた。
――彼らが是非とも賛同を得たかったのが、佐賀の枝吉神陽。
藩内では幕府寄りの保守派が有力だが、佐賀への期待の高さゆえに訪れる志士は後を絶たない。
「大木さん、後を頼んだ。」
もはや決意は語り尽くした。力強く立ち上がる、江藤。
「任せておけ。なか…」
江藤を見送る際、つい「中野にもよろしくな」と言葉を発しそうになった大木。
いや、いま確かに親友の気配を感じた。独りになって大木は言い直した。
「中野…、江藤を守ってやってくれ。頼むぞ。」

――江藤は大木家を出て、佐賀城下をゆく。
眼前に現れたのは“義祭同盟”を率いる師匠の枝吉神陽。風格のある立ち姿は変わらず、その大きい眼に見つめられると隠し事ができない感覚にもなる。
さすがの江藤も、脱藩の決意を固めたところ。しばし言葉に詰まった。向き合うだけで、気後れを感じる。
「神陽先生。」
佐賀を出る計画を語るべきか。いや、仔細(しさい)を語れば、藩内での立場もある師匠に迷惑をかける。
――通りを挟んで、江藤と正対する枝吉神陽。
神陽は、中野方蔵の師匠でもあったが、ここでその話を交わす事もなかった。しばらくの間があって、神陽は「うむ」とばかりに大きく頷(うなず)く。
厳しく学問を仕込んだ弟子・江藤新平の表情に覚悟を感じ取り、沈黙をもって応えるようだ。
かっと見開いた神陽のまなじりは「行け」と、江藤の進む方角へと向けられた。また、江藤も黙して一礼し、師匠の前を退出した。
――それから数週間が過ぎた。六月の下旬。三瀬の街道沿い。
夏の青葉さえ色を持たない、まだ夜も明けぬ刻。山中の小道には、強い草木の香りが漂う。さらに暗い脇道にガサガサ…っと木々を揺らす人影があった。
「そこに居る者は、誰か!」
矢でも射るかのように、ピーンと張り詰めた声が通る。
その人影は、ビリビリっと軽く震えたように見えた。
「…驚かすな。その声は江藤か…。おいだ。古賀だよ。」
「古賀さん。何ゆえ、こがん所に居るのか。」
「そいは、こちらが聞きたか事ばい。」

――三瀬の番所で役人を務める、古賀一平。
「…神陽先生は仔細(しさい)を教えてくれんばってん、肝を冷やしたばい。」
江藤の鋭い声に、よほど驚いたか。古賀の“佐賀ことば”が、いつもより強い。
「それに“隠密”行動のわりに、声の太かぞ…。まぁ、気を付けんね。」
古賀はゴニョゴニョと小声で続けたが、万一にも、人に聞かれては危うい内容と気付き、言葉を濁した。
そして江藤の目前では、こっそりと「あちらの山道に回れ。いま柵は無かぞ」と抜け道を指で示している。
「道案内たい…、正面から通られては、おいも都合の悪か。」
ここは、古賀はさらに声を抑えてつぶやいた。
――「気をつけて、家に帰らんね。」
はっきり口にしたのは、誰に聞かせるでもない、わざとらしい古賀一平の見送りの言葉。もちろん江藤の行く先は、佐賀城下へと戻る道ではない。
「心得た。」
そう答えた江藤。一旦は、佐賀の街に帰るかのように、古賀に背を向けた。実際はわずかに迂回するや、草木の茂る小道へと歩みを転ずる。

――このまま三瀬の山道を越えて、郷里・佐賀を後にするのだ。
佐賀では脱藩は厳罰の対象だ。無事に戻れるかも定かではない。“三瀬街道の番人”古賀一平が、密かに指し示す方向に歩みを進める江藤。
古賀は、江藤の後ろ姿を一目見ようとした。その時には、夜明け前の群青に紛れ、その影は見当たらなかった。
「あん男…、足取りの早かごた。」
わずかに色を見せ始めた緑の木々を撫でるように、一陣の風が吹いた。
(第18話「京都見聞」に続く)
思い入れの強かった“本編”第17話を今回の投稿で、ひとまず書き終えます。親友・中野方蔵が世を去ったことで、佐賀から出る決意を固めた江藤新平。
中野から「兄さん」とも慕われた大木喬任(民平)から資金を借り受け、旅立つ準備を進めます。江藤が佐賀を発ったのは文久二年(1862年)六月。
その前年あたりは、江藤らの師匠・枝吉神陽への面会を求めて、九州北部の各地から志士たちが佐賀に来訪した時期でした。
――“幕府寄り”と見られていた肥前佐賀藩。
朝廷に関わる諸藩の動向について情報が不足する。それを徹底して集めねばならない。江藤は大木に「京の都にて形勢を探る」と脱藩の目的を説明した。
「中野からの文(ふみ)に名があった者に、当たるつもりだ。」
「まずは長州の…、久坂という者か。」
長州(山口)の俊才・久坂玄瑞の名が出る。中野方蔵が送った、江戸からの手紙に度々登場した人物だ。
「久坂どのが、京に居るかはわからぬが、長州には当たらねばなるまい。」
根拠は無いが、次第に自信に満ちあふれた表情となる大木・江藤の二人。

――まるで、傍で親友・中野方蔵が笑っていた青春の日々のようだ。
「では、他国の“有為の者”たちとは、どうつなぎを取る。」
「佐賀を抜ければ、福岡を通る。それゆえ平野さまも尋ねてみるつもりだ。」
江藤は前年の秋、佐賀に来訪した福岡脱藩・平野国臣を話題にした。勤王家として知られた平野は、九州諸藩の志士たちの力を集めようとしていた。
二人は鎌倉期のような時代がかった装束で熱く語る“福岡のさぶらい”・平野を想い出し、少し愉快そうな表情を浮かべる。
〔参照:
そして平野は、福岡の支藩・秋月藩の海賀宮門、久留米の神官・真木和泉(保臣)などとつながる。
筑前・筑後の勤王志士たちは、いささか復古主義的な傾向はあるが、気概に満ちあふれており、京の都でも活動していた。
――彼らが是非とも賛同を得たかったのが、佐賀の枝吉神陽。
藩内では幕府寄りの保守派が有力だが、佐賀への期待の高さゆえに訪れる志士は後を絶たない。
「大木さん、後を頼んだ。」
もはや決意は語り尽くした。力強く立ち上がる、江藤。
「任せておけ。なか…」
江藤を見送る際、つい「中野にもよろしくな」と言葉を発しそうになった大木。
いや、いま確かに親友の気配を感じた。独りになって大木は言い直した。
「中野…、江藤を守ってやってくれ。頼むぞ。」

――江藤は大木家を出て、佐賀城下をゆく。
眼前に現れたのは“義祭同盟”を率いる師匠の枝吉神陽。風格のある立ち姿は変わらず、その大きい眼に見つめられると隠し事ができない感覚にもなる。
さすがの江藤も、脱藩の決意を固めたところ。しばし言葉に詰まった。向き合うだけで、気後れを感じる。
「神陽先生。」
佐賀を出る計画を語るべきか。いや、仔細(しさい)を語れば、藩内での立場もある師匠に迷惑をかける。
――通りを挟んで、江藤と正対する枝吉神陽。
神陽は、中野方蔵の師匠でもあったが、ここでその話を交わす事もなかった。しばらくの間があって、神陽は「うむ」とばかりに大きく頷(うなず)く。
厳しく学問を仕込んだ弟子・江藤新平の表情に覚悟を感じ取り、沈黙をもって応えるようだ。
かっと見開いた神陽のまなじりは「行け」と、江藤の進む方角へと向けられた。また、江藤も黙して一礼し、師匠の前を退出した。
――それから数週間が過ぎた。六月の下旬。三瀬の街道沿い。
夏の青葉さえ色を持たない、まだ夜も明けぬ刻。山中の小道には、強い草木の香りが漂う。さらに暗い脇道にガサガサ…っと木々を揺らす人影があった。
「そこに居る者は、誰か!」
矢でも射るかのように、ピーンと張り詰めた声が通る。
その人影は、ビリビリっと軽く震えたように見えた。
「…驚かすな。その声は江藤か…。おいだ。古賀だよ。」
「古賀さん。何ゆえ、こがん所に居るのか。」
「そいは、こちらが聞きたか事ばい。」
――三瀬の番所で役人を務める、古賀一平。
「…神陽先生は仔細(しさい)を教えてくれんばってん、肝を冷やしたばい。」
江藤の鋭い声に、よほど驚いたか。古賀の“佐賀ことば”が、いつもより強い。
「それに“隠密”行動のわりに、声の太かぞ…。まぁ、気を付けんね。」
古賀はゴニョゴニョと小声で続けたが、万一にも、人に聞かれては危うい内容と気付き、言葉を濁した。
そして江藤の目前では、こっそりと「あちらの山道に回れ。いま柵は無かぞ」と抜け道を指で示している。
「道案内たい…、正面から通られては、おいも都合の悪か。」
ここは、古賀はさらに声を抑えてつぶやいた。
――「気をつけて、家に帰らんね。」
はっきり口にしたのは、誰に聞かせるでもない、わざとらしい古賀一平の見送りの言葉。もちろん江藤の行く先は、佐賀城下へと戻る道ではない。
「心得た。」
そう答えた江藤。一旦は、佐賀の街に帰るかのように、古賀に背を向けた。実際はわずかに迂回するや、草木の茂る小道へと歩みを転ずる。
――このまま三瀬の山道を越えて、郷里・佐賀を後にするのだ。
佐賀では脱藩は厳罰の対象だ。無事に戻れるかも定かではない。“三瀬街道の番人”古賀一平が、密かに指し示す方向に歩みを進める江藤。
古賀は、江藤の後ろ姿を一目見ようとした。その時には、夜明け前の群青に紛れ、その影は見当たらなかった。
「あん男…、足取りの早かごた。」
わずかに色を見せ始めた緑の木々を撫でるように、一陣の風が吹いた。
(第18話「京都見聞」に続く)




