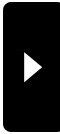2020年10月30日
第14話「遣米使節」⑮(水平線の向こうに)
こんばんは。
前回は、強い嵐に翻弄される“咸臨丸”の姿を描きました。
長く続いた第14話の投稿も、今回でラストです。
幕府の使節団が乗る“ポーハタン号”の佐賀藩士たちを描きます。“咸臨丸”と出航時点に少し差があるようですが、“ポーハタン号”も暴風雨に遭います。
――ゴーォォッ…、バキバキバキッ!
吠える風、破損する船体…
何日も続く大嵐に“ポーハタン号”も、“咸臨丸”と同じ惨状を見せる。
ドシャァァ-ン!
今度は、雷鳴が響いた。
「これは…、随分と厳しいようだ…」
蘭学寮の英才・小出千之助も、長崎での海軍伝習の経験者。操船技術の心得はあるが、アメリカ海軍の船では訓練された水兵の動きに感心するばかりだ。
―― ヘイ!ヘイッ!…己を鼓舞するような、水兵たちのかけ声が響く。
「嵐の海原を突っ切れ!」と、蒸気機関を全力で稼働させているのだ。
ガランガラン…
不規則に荒れる波しぶき、蒸気船の両舷で“外輪”は回り続ける。
「ゴー、アヘッド!(前へ進むんだ)」
「イエッサー!!(了解)」
ここでも“魂”を見せる、アメリカ海軍。
雨風に煽られ、足元も揺れる。そんな中でも小出は感服していた。
「これが…アメリカとの力の差か…もっと彼らの言葉を学ばねば。」

――どうにか、ハワイ諸島を望む海域まで来た“ポーハタン号”。
船の損傷箇所が多数ある。燃料も使い過ぎており、航海の継続は難しい。
「何とか、生きて陸(おか)にたどり着けるようですね。」
甲板に上がってきたのは、佐賀藩医・川崎道民である。
アメリカ水兵の会話を聴き取っていた、小出千之助が言葉を返す。
「おお、川崎どの。随分な嵐だったな。お加減はいかがですか。」
「私は医者ですよ。倒れるわけには参りませぬ。」
「失礼した。皆の具合はどうか。」
「“船酔い”で、気分が悪い者もいますが…陸に上がれば、心配無いでしょうな。」
――オアフ島の夕暮れ。浜辺から西に広がる水平線を見つめる。
「おおっ、夕陽が見事だな。“ビューテイホー・サンセッツ”と言うらしい。」
小出千之助は、地道に英語の習得を進めていた。
海上の嵐の恐怖から解き放たれ、皆が面白がって夕日に叫ぶ。
「ビューテイホー!!」
幾人かが声を揃えた。“ポーハタン号”に乗っていた佐賀藩士は、小出・川崎を含め7人の名が伝わる。
「佐賀の遠かごたぁ~!!」
急に1人が叫んだ。緊張が緩んだのか、まだ“行き道”なのに故郷に帰りたい。
「気ば、たしかに持たんね!」
「そうたい!この海は佐賀とつながっとるばい!」

――仲間たちが“よそ行き”の言葉ではなく“佐賀ことば”で励ます。
藩医の川崎道民は、その様子を眺めていた。そして「ふーっ」と深呼吸する。
殿には“皆を守る”と約束した。まずは医者である自分がしっかりせねばならぬ。
川崎は「大丈夫だ。海を渡り、使命を果たす。そして…皆で、必ず佐賀に帰る。」と自身に言い聞かせた。
――ほどなく川崎は、佐賀にいる家族に宛てて手紙を書いた。
太平洋の真ん中だが、次にホノルルに寄る“郵便船”で日本には届くはずだ。
「ご家族の皆様、息災(お元気)でしょうか。アメリカへの旅は、嵐の船出でした。途上の“オアフ島”にて船舶の修繕中です。出航も定かではありませぬ。」
「…しかし、佐賀の者たちは皆、気丈に振る舞っています。心強い限りです。」
――今度、嵐が来たら船は持ちこたえるのだろうか。
そして、アメリカには無事たどり着けるのか。
“気丈に振る舞っている”のは、川崎道民も同じだった。日本近代化のための“洋行”の先駆けは、命懸けの旅路でもあった。
(第15話「江戸動乱」に続く)
前回は、強い嵐に翻弄される“咸臨丸”の姿を描きました。
長く続いた第14話の投稿も、今回でラストです。
幕府の使節団が乗る“ポーハタン号”の佐賀藩士たちを描きます。“咸臨丸”と出航時点に少し差があるようですが、“ポーハタン号”も暴風雨に遭います。
――ゴーォォッ…、バキバキバキッ!
吠える風、破損する船体…
何日も続く大嵐に“ポーハタン号”も、“咸臨丸”と同じ惨状を見せる。
ドシャァァ-ン!
今度は、雷鳴が響いた。
「これは…、随分と厳しいようだ…」
蘭学寮の英才・小出千之助も、長崎での海軍伝習の経験者。操船技術の心得はあるが、アメリカ海軍の船では訓練された水兵の動きに感心するばかりだ。
―― ヘイ!ヘイッ!…己を鼓舞するような、水兵たちのかけ声が響く。
「嵐の海原を突っ切れ!」と、蒸気機関を全力で稼働させているのだ。
ガランガラン…
不規則に荒れる波しぶき、蒸気船の両舷で“外輪”は回り続ける。
「ゴー、アヘッド!(前へ進むんだ)」
「イエッサー!!(了解)」
ここでも“魂”を見せる、アメリカ海軍。
雨風に煽られ、足元も揺れる。そんな中でも小出は感服していた。
「これが…アメリカとの力の差か…もっと彼らの言葉を学ばねば。」

――どうにか、ハワイ諸島を望む海域まで来た“ポーハタン号”。
船の損傷箇所が多数ある。燃料も使い過ぎており、航海の継続は難しい。
「何とか、生きて陸(おか)にたどり着けるようですね。」
甲板に上がってきたのは、佐賀藩医・川崎道民である。
アメリカ水兵の会話を聴き取っていた、小出千之助が言葉を返す。
「おお、川崎どの。随分な嵐だったな。お加減はいかがですか。」
「私は医者ですよ。倒れるわけには参りませぬ。」
「失礼した。皆の具合はどうか。」
「“船酔い”で、気分が悪い者もいますが…陸に上がれば、心配無いでしょうな。」
――オアフ島の夕暮れ。浜辺から西に広がる水平線を見つめる。
「おおっ、夕陽が見事だな。“ビューテイホー・サンセッツ”と言うらしい。」
小出千之助は、地道に英語の習得を進めていた。
海上の嵐の恐怖から解き放たれ、皆が面白がって夕日に叫ぶ。
「ビューテイホー!!」
幾人かが声を揃えた。“ポーハタン号”に乗っていた佐賀藩士は、小出・川崎を含め7人の名が伝わる。
「佐賀の遠かごたぁ~!!」
急に1人が叫んだ。緊張が緩んだのか、まだ“行き道”なのに故郷に帰りたい。
「気ば、たしかに持たんね!」
「そうたい!この海は佐賀とつながっとるばい!」
――仲間たちが“よそ行き”の言葉ではなく“佐賀ことば”で励ます。
藩医の川崎道民は、その様子を眺めていた。そして「ふーっ」と深呼吸する。
殿には“皆を守る”と約束した。まずは医者である自分がしっかりせねばならぬ。
川崎は「大丈夫だ。海を渡り、使命を果たす。そして…皆で、必ず佐賀に帰る。」と自身に言い聞かせた。
――ほどなく川崎は、佐賀にいる家族に宛てて手紙を書いた。
太平洋の真ん中だが、次にホノルルに寄る“郵便船”で日本には届くはずだ。
「ご家族の皆様、息災(お元気)でしょうか。アメリカへの旅は、嵐の船出でした。途上の“オアフ島”にて船舶の修繕中です。出航も定かではありませぬ。」
「…しかし、佐賀の者たちは皆、気丈に振る舞っています。心強い限りです。」
――今度、嵐が来たら船は持ちこたえるのだろうか。
そして、アメリカには無事たどり着けるのか。
“気丈に振る舞っている”のは、川崎道民も同じだった。日本近代化のための“洋行”の先駆けは、命懸けの旅路でもあった。
(第15話「江戸動乱」に続く)
2020年10月28日
第14話「遣米使節」⑭(太平洋の嵐)
こんばんは。
前回、江戸・品川沖をアメリカに向けて出航した2隻の蒸気船。幕府の使節団を乗せた“ポーハタン号”と、同行する“咸臨丸”。
当時の航海技術では、太平洋を渡るには試練を伴います。佐賀藩士たちが同乗する、この2隻も困難に直面します。
――オランダより購入し、幕府が保有する“咸臨丸”の船上。
「佐賀の秀島と申す。福沢どのとお見受けする。」
佐賀藩士で、技術者・秀島藤之助である。
「…咸臨丸にも佐賀の方が居られましたか。」
福沢諭吉は長崎にいるとき、奉行所の関係者宅で書生をしていた。佐賀藩士とは関わる機会も多かった。
「お話中だったか、失礼した。そちらの方も、名をお伺いしたい。」
――秀島は、“賢い”と評判の福沢が、話している相手も気になった。
秀島は、極めて真面目だった。航海途上も情報収集に励む。
「マイネーム…中浜、万次郎と申します。」
万次郎と名乗るこの人物、やけに言葉がたどたどしい。
「中浜どのは土佐(高知)の出。漁に出て嵐に遭い、アメリカに渡ったそうだ。」
すかさず福沢が補足した。頭の回転が速い。
――“ジョン万次郎”として知られる、中浜万次郎。
海で遭難し、無人島で命をつないでいたところ、アメリカ船に救助された。当時、“鎖国”の影響もあって日本には帰れず、渡米の道を選んだ。
「ザッツ、ライト…いや、その通りです。」
万次郎は、アメリカで暮らしの間に“英語で考える頭”になっていた。
「メリケン(アメリカ)の言葉をご存じとは心強い。」
秀島藤之助、長崎の海軍伝習所でオランダ人から操船技術は学んだ。しかし、英語の習得はこれからだ。
そして“咸臨丸”での航海、秀島は船を動かす仕事には関われない。そこは幕府の“海軍士官”たちの領分なのだ。

――港を出た直後は、太平洋の航海は順調であったが…
「どうやら、ストーム(嵐)が来る…ようです。」
万次郎は、“咸臨丸”に同乗するアメリカ海軍のブルック大尉と話してきた。そこで「雲行きが怪しい」と聞いたらしい。
ほどなく上空は真っ暗となった。
ゴーォォ…
吠える風、うねる海。非情な大嵐である。
バキバキバキッ…
船体の様々な箇所が破損していく。
――甲板は斜め上に傾いたかと思えば、今度は、前方に下り坂を生じる。
乗組員たちは平衡感覚を失い、天地の分別もつかなくなった。
「勝さんは、まだ出て来ないのか…!」
「お体が優れぬらしいぞ。このような時に…!」
幕府の海軍士官たちは、混乱していた。1人…また1人と船酔いで倒れていく。
指揮を執るべき、勝麟太郎(海舟)は船室から出て来れなかった。
「おいらも、もう終(し)めぇか…」
絶望の言葉が口を付いて出る。勝海舟は強度の“船酔い”持ちだったと伝わる。陸(おか)でこそ活きる人物だったという。

――たとえ好天でも、日本人には経験の無い遠洋航海。
すでに“咸臨丸”の指揮命令は、機能していない。
そこで嵐の甲板に英語が響いた。
アメリカ海軍・ブルック大尉と水兵10人が同乗しているのだ。
「何と言っているのだ…」
佐賀藩士・秀島藤之助は、まだ充分に英語が理解できない。
「アメリカ海軍の魂を…お見せしよう!と言ってます…」
通訳をするジョン万次郎である。自身も船乗りの経験がある。ブルック大尉に協力するつもりのようだ。
――風が、吹きすさぶ荒天は数日続いたと言われる。
テキパキと活動するアメリカの水兵たちを見つめ、秀島は悔しさを嚙みしめる。
「もし佐賀の者が同船ならば、このように動けただろうか…」
長崎での海軍伝習の日々が浮かぶ。よく働く若手と、そのまとめ役がいた。
「中牟田…、石丸…、それに佐野(栄寿)さんが居れば…」
佐賀藩から派遣されている、秀島藤之助。勝手な動きをして、幕臣との軋轢(あつれき)を起こすわけにはいかなかった。
(続く)
前回、江戸・品川沖をアメリカに向けて出航した2隻の蒸気船。幕府の使節団を乗せた“ポーハタン号”と、同行する“咸臨丸”。
当時の航海技術では、太平洋を渡るには試練を伴います。佐賀藩士たちが同乗する、この2隻も困難に直面します。
――オランダより購入し、幕府が保有する“咸臨丸”の船上。
「佐賀の秀島と申す。福沢どのとお見受けする。」
佐賀藩士で、技術者・秀島藤之助である。
「…咸臨丸にも佐賀の方が居られましたか。」
福沢諭吉は長崎にいるとき、奉行所の関係者宅で書生をしていた。佐賀藩士とは関わる機会も多かった。
「お話中だったか、失礼した。そちらの方も、名をお伺いしたい。」
――秀島は、“賢い”と評判の福沢が、話している相手も気になった。
秀島は、極めて真面目だった。航海途上も情報収集に励む。
「マイネーム…中浜、万次郎と申します。」
万次郎と名乗るこの人物、やけに言葉がたどたどしい。
「中浜どのは土佐(高知)の出。漁に出て嵐に遭い、アメリカに渡ったそうだ。」
すかさず福沢が補足した。頭の回転が速い。
――“ジョン万次郎”として知られる、中浜万次郎。
海で遭難し、無人島で命をつないでいたところ、アメリカ船に救助された。当時、“鎖国”の影響もあって日本には帰れず、渡米の道を選んだ。
「ザッツ、ライト…いや、その通りです。」
万次郎は、アメリカで暮らしの間に“英語で考える頭”になっていた。
「メリケン(アメリカ)の言葉をご存じとは心強い。」
秀島藤之助、長崎の海軍伝習所でオランダ人から操船技術は学んだ。しかし、英語の習得はこれからだ。
そして“咸臨丸”での航海、秀島は船を動かす仕事には関われない。そこは幕府の“海軍士官”たちの領分なのだ。

――港を出た直後は、太平洋の航海は順調であったが…
「どうやら、ストーム(嵐)が来る…ようです。」
万次郎は、“咸臨丸”に同乗するアメリカ海軍のブルック大尉と話してきた。そこで「雲行きが怪しい」と聞いたらしい。
ほどなく上空は真っ暗となった。
ゴーォォ…
吠える風、うねる海。非情な大嵐である。
バキバキバキッ…
船体の様々な箇所が破損していく。
――甲板は斜め上に傾いたかと思えば、今度は、前方に下り坂を生じる。
乗組員たちは平衡感覚を失い、天地の分別もつかなくなった。
「勝さんは、まだ出て来ないのか…!」
「お体が優れぬらしいぞ。このような時に…!」
幕府の海軍士官たちは、混乱していた。1人…また1人と船酔いで倒れていく。
指揮を執るべき、勝麟太郎(海舟)は船室から出て来れなかった。
「おいらも、もう終(し)めぇか…」
絶望の言葉が口を付いて出る。勝海舟は強度の“船酔い”持ちだったと伝わる。陸(おか)でこそ活きる人物だったという。

――たとえ好天でも、日本人には経験の無い遠洋航海。
すでに“咸臨丸”の指揮命令は、機能していない。
そこで嵐の甲板に英語が響いた。
アメリカ海軍・ブルック大尉と水兵10人が同乗しているのだ。
「何と言っているのだ…」
佐賀藩士・秀島藤之助は、まだ充分に英語が理解できない。
「アメリカ海軍の魂を…お見せしよう!と言ってます…」
通訳をするジョン万次郎である。自身も船乗りの経験がある。ブルック大尉に協力するつもりのようだ。
――風が、吹きすさぶ荒天は数日続いたと言われる。
テキパキと活動するアメリカの水兵たちを見つめ、秀島は悔しさを嚙みしめる。
「もし佐賀の者が同船ならば、このように動けただろうか…」
長崎での海軍伝習の日々が浮かぶ。よく働く若手と、そのまとめ役がいた。
「中牟田…、石丸…、それに佐野(栄寿)さんが居れば…」
佐賀藩から派遣されている、秀島藤之助。勝手な動きをして、幕臣との軋轢(あつれき)を起こすわけにはいかなかった。
(続く)
2020年10月26日
第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)
こんばんは。
前回、鍋島直正の写真を撮影していた佐賀藩医・川崎道民。殿から出し抜けにアメリカ行きを提案される場面を描きました。
今回の投稿は、様々な場所で佐賀藩士たちの運命が動いていきます。日本における“英学の夜明け”という時期でしょうか。
――江戸。殿・直正から海外渡航の勧めを受けた、川崎道民。
「メリケン(アメリカ)に、ございますか!?」
「そうじゃ。医術や文物を見聞いたせ。お主なら“写真術”も遣える。」
この頃、幕府は“日米修好通商条約”の批准書を交換するため、アメリカに使節派遣を予定している。
日本の近代外交の扉は開いた。佐賀藩には、この機会に優秀な人物を海外に送り込み、西洋の事情を探ろうという意図があった。
「川崎は、腕の良い医者であるからな。同行すれば、皆も安心であろう。」
「皆…!?佐賀から、幾人もメリケンに行くのでございますか?」

――医者の髪型に、よくある坊主頭。川崎は、目を丸くして殿・直正に問う。
「無論じゃ。川崎よ、皆を頼むぞ。」
この使節団には、佐賀藩士8名が参加することになった。
川崎は、地元である“須古”の領主・鍋島安房の言葉を想い出した。恩義あるご領主からも「広く世を見聞せよ」と期待をされているのだ。
「この川崎、メリケンの進んだ技術を得られる限り、得て参ります。」
「…はっはっは。良い心意気じゃ。」
――川崎の反応は、直正の予想を上回るほど“前のめり”だった。
「仕度金は、百両でよいか。抜かりなく用意を致せ。」
「はっ!…百両も…!ありがたき幸せ!」
こうして、藩医・川崎道民のアメリカ行きが決まる。幕府の使節団が乗り込むアメリカ海軍の蒸気船に同乗することとなった。
船名を“ポーハタン号”という。アメリカのペリーが2度目の来日で乗船し、ハリスとの通商条約の調印場所になった、全長77メートル超の外輪蒸気船である。
――同じ頃、佐賀城下の“火術方”にて。
作業場で、オランダ語の技術書と睨み合う人物がいた。大砲の改良案を練る技術者・秀島藤之助。
〔参照:第14話「遣米使節」⑧(孤高のエンジニア)〕
「秀島さま!お城からのお呼びです!」
いきなり電流が走るような声が通った。
「…何だ!?いきなり大声で。お主はたしか…?」
耳を抑える秀島。よく通る声でツーンと来た様子である。

――声の主は“火術方”に下級役人として採用された、江藤新平。
「秀島さま!その図面は、新しい製砲の試みでござるか。」
江藤は蘭学を学んだので、ある程度、技術者たちの作業が理解できる。
「あぁ、そうだ。たしか江藤と言ったな。そこまで声を通さずとも聞こえている…」
寝る間も惜しみ研究をする、秀島。寝不足には江藤の地声は堪(こた)える。
「急ぎ、城へお向かいください!」
「…相分かった。」
――殿・直正が期待する、技術者・秀島藤之助もアメリカ行きが決定した。
使節を乗せる“ポーハタン号”を護衛するとの名目で、幕府も船を派遣する。
船名を“咸臨丸”という、秀島はそちらに乗船することとなった。
秀島の任務は、主に艦船や大砲などの調査である。
「メリケン(アメリカ)に行けば、進んだ技術をこの目で見られる…」
――そして、1860年1月。舞台は再び、江戸。
江戸湾の品川沖に停泊する2隻の蒸気船が並ぶ。
1隻は、アメリカ海軍の大型外輪蒸気船・“ポーハタン号”。
もう1隻は、幕府がオランダから購入した、スクリュー推進式蒸気船“咸臨丸”
――いよいよ、アメリカへの船出。港には乗船する使節団が集合した。
ここで佐賀の“蘭学寮”の英才が、幕府使節団の“同行者”に話しかけた。
「佐賀の小出千之助と申す。以後、お見知りおきを。」
「…豊前中津の出で、福沢と申します。」
福沢諭吉は、若くして“蘭学”の塾を構えるが、英語も一から学んでいる。
「やはり福沢どのだったか。思いのほか、早くお会いできたようだ。」
「…ご丁寧に恐れ入る。」
やや困惑する福沢。こんな疑念を持った。
「この小出という佐賀の者は、私に会うことを予期していたのか…?」
〔参照(終盤):第14話「遣米使節」①(諭吉よ、何処へ行く)〕

――蘭学寮の英才・小出千之助の任務は英語を修得し、殿・直正に代わり西洋を見聞すること。
福沢は「もはやオランダ語ではなく、英語を学ばねば!」と気付くのも早かった。開港後に発展した“横浜”でオランダ語が通じないショックを味わったのだ。
ほどなく小出千之助・川崎道民らは“ポーハタン号”。福沢諭吉・秀島藤之助らは“咸臨丸”へと分かれた。遠く海の向こうアメリカへ。太平洋への船出である。
(続く)
前回、鍋島直正の写真を撮影していた佐賀藩医・川崎道民。殿から出し抜けにアメリカ行きを提案される場面を描きました。
今回の投稿は、様々な場所で佐賀藩士たちの運命が動いていきます。日本における“英学の夜明け”という時期でしょうか。
――江戸。殿・直正から海外渡航の勧めを受けた、川崎道民。
「メリケン(アメリカ)に、ございますか!?」
「そうじゃ。医術や文物を見聞いたせ。お主なら“写真術”も遣える。」
この頃、幕府は“日米修好通商条約”の批准書を交換するため、アメリカに使節派遣を予定している。
日本の近代外交の扉は開いた。佐賀藩には、この機会に優秀な人物を海外に送り込み、西洋の事情を探ろうという意図があった。
「川崎は、腕の良い医者であるからな。同行すれば、皆も安心であろう。」
「皆…!?佐賀から、幾人もメリケンに行くのでございますか?」

――医者の髪型に、よくある坊主頭。川崎は、目を丸くして殿・直正に問う。
「無論じゃ。川崎よ、皆を頼むぞ。」
この使節団には、佐賀藩士8名が参加することになった。
川崎は、地元である“須古”の領主・鍋島安房の言葉を想い出した。恩義あるご領主からも「広く世を見聞せよ」と期待をされているのだ。
「この川崎、メリケンの進んだ技術を得られる限り、得て参ります。」
「…はっはっは。良い心意気じゃ。」
――川崎の反応は、直正の予想を上回るほど“前のめり”だった。
「仕度金は、百両でよいか。抜かりなく用意を致せ。」
「はっ!…百両も…!ありがたき幸せ!」
こうして、藩医・川崎道民のアメリカ行きが決まる。幕府の使節団が乗り込むアメリカ海軍の蒸気船に同乗することとなった。
船名を“ポーハタン号”という。アメリカのペリーが2度目の来日で乗船し、ハリスとの通商条約の調印場所になった、全長77メートル超の外輪蒸気船である。
――同じ頃、佐賀城下の“火術方”にて。
作業場で、オランダ語の技術書と睨み合う人物がいた。大砲の改良案を練る技術者・秀島藤之助。
〔参照:
「秀島さま!お城からのお呼びです!」
いきなり電流が走るような声が通った。
「…何だ!?いきなり大声で。お主はたしか…?」
耳を抑える秀島。よく通る声でツーンと来た様子である。
――声の主は“火術方”に下級役人として採用された、江藤新平。
「秀島さま!その図面は、新しい製砲の試みでござるか。」
江藤は蘭学を学んだので、ある程度、技術者たちの作業が理解できる。
「あぁ、そうだ。たしか江藤と言ったな。そこまで声を通さずとも聞こえている…」
寝る間も惜しみ研究をする、秀島。寝不足には江藤の地声は堪(こた)える。
「急ぎ、城へお向かいください!」
「…相分かった。」
――殿・直正が期待する、技術者・秀島藤之助もアメリカ行きが決定した。
使節を乗せる“ポーハタン号”を護衛するとの名目で、幕府も船を派遣する。
船名を“咸臨丸”という、秀島はそちらに乗船することとなった。
秀島の任務は、主に艦船や大砲などの調査である。
「メリケン(アメリカ)に行けば、進んだ技術をこの目で見られる…」
――そして、1860年1月。舞台は再び、江戸。
江戸湾の品川沖に停泊する2隻の蒸気船が並ぶ。
1隻は、アメリカ海軍の大型外輪蒸気船・“ポーハタン号”。
もう1隻は、幕府がオランダから購入した、スクリュー推進式蒸気船“咸臨丸”
――いよいよ、アメリカへの船出。港には乗船する使節団が集合した。
ここで佐賀の“蘭学寮”の英才が、幕府使節団の“同行者”に話しかけた。
「佐賀の小出千之助と申す。以後、お見知りおきを。」
「…豊前中津の出で、福沢と申します。」
福沢諭吉は、若くして“蘭学”の塾を構えるが、英語も一から学んでいる。
「やはり福沢どのだったか。思いのほか、早くお会いできたようだ。」
「…ご丁寧に恐れ入る。」
やや困惑する福沢。こんな疑念を持った。
「この小出という佐賀の者は、私に会うことを予期していたのか…?」
〔参照(終盤):

――蘭学寮の英才・小出千之助の任務は英語を修得し、殿・直正に代わり西洋を見聞すること。
福沢は「もはやオランダ語ではなく、英語を学ばねば!」と気付くのも早かった。開港後に発展した“横浜”でオランダ語が通じないショックを味わったのだ。
ほどなく小出千之助・川崎道民らは“ポーハタン号”。福沢諭吉・秀島藤之助らは“咸臨丸”へと分かれた。遠く海の向こうアメリカへ。太平洋への船出である。
(続く)
2020年10月24日
「醒覚の剣」(満干)
こんばんは。
今週末は「秋の佐賀城公園イベント」が開催されていますね。
〔参照:「“さが維新まつり”について」〕
私も現地で「佐賀さいこう!」と唱和したいのですが、そこには高い壁が生じています。なかなか帰郷できない佐賀藩士(?)を描く「望郷の剣」シリーズです。
…念のためご説明します。“本編”から離れて、ありふれた現代の日常を幕末っぽく表現する“息抜き”の投稿です。
――今年、新型コロナの感染症の影響は、随所に現れる。
これは、私の都市圏での“生業”とも無関係ではなかった。
帰郷の自粛のみならず、増えた仕事が追い打ちとなった。遠い郷里・佐賀がますます遠ざかる日々。私が現地取材に出向くにも、困難な状況が続く。
そこで手を差し伸べたのが、叔父上である。
「写真?良かったら撮るよ。どうせヒマやけん。」
…実際は叔父上も、わりと忙しい。しかし、私はその言葉に甘えると決めた。

――そして、ある日。叔父上からの荷物が届いた。
私は「写真情報もその中に入れた」と聞いていた。叔父上は、先日の伊万里市の大川内山に続き、今度は鹿島市・太良町の有明海沿いを歩んだ。
〔参照:「醒覚の剣」(秘窯)〕
結構な労力である。もし、祖母が存命であれば、きっと「ご苦労さんだにゃあ」と評したであろう。荷物の中には、叔父上からの贈り物も詰められていた。
1つは“クレメンティン”まんじゅう。“クレメンティン”は希少な柑橘類で、太良町の特産として知られる。
――江戸期の長崎では、目的品の空きスペースに“脇荷”と呼ばれる品を積んで貿易したと聞く。
市場での“希少価値”がある原料。何やら長崎貿易のロマンを感じる響きだ。しかし、叔父上からの贈り物は、太良町の特産だけではなかった。
「これは“丸ぼうろ”ではないですか!しかも、相当に大きい…」
「随分、押し込んだけん。つぶれとらんね?」
「いえ、完全な姿の“丸ぼうろ”が見えます。」
「それは、良かったばい。」
電話口で礼を言う。叔父上は、私の“丸ぼうろ”への想いを覚えていたらしい。
〔参照:「望郷の剣2」〕

――有明海では、満ち引きで最大約6メートルの潮位の差が生じる。
日本一の“干満差”という説明が付くことが多い。
干満の差は、そこに住まう人々に海苔やコハダといった水産資源という恵みも、海水が陸地に逆流する災いも与えてきたことだろう。
――今日も有明の海は、潮の満ち引きを繰り返す。
きっと人生は良い時ばかりでも、悪い時ばかりでもない。
「与えられた状況をどう活かすかは、自分次第なのだ。」
有明沿海の人々は、ずっとそのように生きてきたに違いない。
「そして…凹んでも、また膨らめば良い。」
叔父上の送ってきた積荷に有明の風を想う。凹んでも膨らむ“丸ぼうろ”には、“不屈”の精神を見出すのであった。
今週末は「秋の佐賀城公園イベント」が開催されていますね。
〔参照:
私も現地で「佐賀さいこう!」と唱和したいのですが、そこには高い壁が生じています。なかなか帰郷できない佐賀藩士(?)を描く「望郷の剣」シリーズです。
…念のためご説明します。“本編”から離れて、ありふれた現代の日常を幕末っぽく表現する“息抜き”の投稿です。
――今年、新型コロナの感染症の影響は、随所に現れる。
これは、私の都市圏での“生業”とも無関係ではなかった。
帰郷の自粛のみならず、増えた仕事が追い打ちとなった。遠い郷里・佐賀がますます遠ざかる日々。私が現地取材に出向くにも、困難な状況が続く。
そこで手を差し伸べたのが、叔父上である。
「写真?良かったら撮るよ。どうせヒマやけん。」
…実際は叔父上も、わりと忙しい。しかし、私はその言葉に甘えると決めた。
――そして、ある日。叔父上からの荷物が届いた。
私は「写真情報もその中に入れた」と聞いていた。叔父上は、先日の伊万里市の大川内山に続き、今度は鹿島市・太良町の有明海沿いを歩んだ。
〔参照:
結構な労力である。もし、祖母が存命であれば、きっと「ご苦労さんだにゃあ」と評したであろう。荷物の中には、叔父上からの贈り物も詰められていた。
1つは“クレメンティン”まんじゅう。“クレメンティン”は希少な柑橘類で、太良町の特産として知られる。
――江戸期の長崎では、目的品の空きスペースに“脇荷”と呼ばれる品を積んで貿易したと聞く。
市場での“希少価値”がある原料。何やら長崎貿易のロマンを感じる響きだ。しかし、叔父上からの贈り物は、太良町の特産だけではなかった。
「これは“丸ぼうろ”ではないですか!しかも、相当に大きい…」
「随分、押し込んだけん。つぶれとらんね?」
「いえ、完全な姿の“丸ぼうろ”が見えます。」
「それは、良かったばい。」
電話口で礼を言う。叔父上は、私の“丸ぼうろ”への想いを覚えていたらしい。
〔参照:
――有明海では、満ち引きで最大約6メートルの潮位の差が生じる。
日本一の“干満差”という説明が付くことが多い。
干満の差は、そこに住まう人々に海苔やコハダといった水産資源という恵みも、海水が陸地に逆流する災いも与えてきたことだろう。
――今日も有明の海は、潮の満ち引きを繰り返す。
きっと人生は良い時ばかりでも、悪い時ばかりでもない。
「与えられた状況をどう活かすかは、自分次第なのだ。」
有明沿海の人々は、ずっとそのように生きてきたに違いない。
「そして…凹んでも、また膨らめば良い。」
叔父上の送ってきた積荷に有明の風を想う。凹んでも膨らむ“丸ぼうろ”には、“不屈”の精神を見出すのであった。
2020年10月22日
第14話「遣米使節」⑫(遠くまで…)
こんばんは。
今回の投稿は、長崎で“写真術”を身に付けた佐賀藩医が登場します。日本の“ジャーナリスト”の先駆けの1人、川崎道民です。
〔参照(終盤):第13話「通商条約」④(お大事になされませ!)〕
年代は少し進んで1859年頃の設定です。もちろん、殿・鍋島直正は無事に薩摩から帰還しています。
「通商条約の締結」「安政の大獄」と激動の時代は進み、豪腕とも評された、大老・井伊直弼が、幕府で奮闘していた時期のお話です。
〔参照(終盤):第13話「通商条約」⑬(豪腕、唸〔うな〕る)〕
――佐賀城内。北の堀端に面した“須古鍋島家”の屋敷。
“須古”は、現在の白石町にあった自治領。その領主・鍋島安房(茂真)は佐賀藩の請役(ナンバー2)を務める。
直正より1歳年上の異母兄は、30年近くも殿・直正を支え続けていた。
「川崎よ。立派になったな。」
「安房様から、学ぶ場をお授けいただいたのです。」
ひたすら感謝の意を述べている、坊主頭の青年。名を川崎道民という。利発そうな丸顔の若者である。

――川崎道民は、“須古領”の侍医(お付きの医者)に養子に入っていた。
鍋島安房は、才能ある川崎道民を領内に留めず、佐賀の藩医に推挙した。こうして川崎は、進んだ西洋の医術を学ぶことができた。
ふと、川崎が“良い事を思い付いた!”と、その表情を緩める。
「長崎にて、面白き業(わざ)を身に付けて参りました!」
「ほう…」
“興味がある”という反応の鍋島安房。この姿勢は変わらない。長年、寝る間も惜しんで、下級藩士たちの話も大切に聞き続けてきた。
昔日は、仕事場と藩校「弘道館」との往復に走り回ったが、今はその気力は感じられず、病身にも伺える。
――しかし探求心は、まだ失われていない様子だ。
「“写真”と呼ばれる業に、ございます。」
「人の姿を、ありのままに写すという業か。」
「左様(その通り)です。」
「もし、宜しければ…」
川崎は、“写真”撮影を提案した。
鍋島安房は、フッと寂しげな表情を浮かべる。
「今の私のありのままには、もはや値打ちは無い。」
――自分を引き立ててくれた、“ご領主”の言葉は芳(かんば)しくない。
川崎も、意気消沈の様子を見せる。
「…川崎よ。お主が写すべきものは、もっと遠くに、遥か向こうにあるのではないか。」
鍋島安房の目には、まだ確かな光が宿っている。その言葉に川崎は、ハッと胸を打たれた。
「…世を広く見聞し、必ずやご期待に応えてお見せします。」
川崎は、鍋島安房の言葉を受け止めた。
――元は、主従の関係だった、この2人。想いは引き継がれた。
ほどなく川崎道民は江戸に向かった。
そして、長年に渡って鍋島直正の補佐役を務めた、鍋島安房は“罷免”という形で表舞台を去っていく。

――1859年。江戸の佐賀藩邸。
川崎道民が、写真の道具を扱っている。この年に撮影されたものが、鍋島直正の肖像写真として最も有名な1枚として知られる。
「…川崎。もう動いても良いか?」
「殿…しばし、しばしのお待ちを!」
「“写真”も、なかなかに窮屈なものよ。」
「良き写りを得るためには、辛抱こそが肝要でござる!」
――殿・直正の“写真”撮影に奮闘する、川崎道民。
「ところで…川崎よ。メリケン(アメリカ)に行かぬか?」
「殿、しばし!動かずにお待ちを…え!?」
「海の向こうの異国、メリケンじゃ。」
「…殿。良き1枚が撮れたようです。」
殿・直正から、突然の海外渡航の提案。動揺する川崎道民だったが、さすがは佐賀の藩医。抜かりなく撮影は成し遂げた様子だ。
(続く)
今回の投稿は、長崎で“写真術”を身に付けた佐賀藩医が登場します。日本の“ジャーナリスト”の先駆けの1人、川崎道民です。
〔参照(終盤):
年代は少し進んで1859年頃の設定です。もちろん、殿・鍋島直正は無事に薩摩から帰還しています。
「通商条約の締結」「安政の大獄」と激動の時代は進み、豪腕とも評された、大老・井伊直弼が、幕府で奮闘していた時期のお話です。
〔参照(終盤):
――佐賀城内。北の堀端に面した“須古鍋島家”の屋敷。
“須古”は、現在の白石町にあった自治領。その領主・鍋島安房(茂真)は佐賀藩の請役(ナンバー2)を務める。
直正より1歳年上の異母兄は、30年近くも殿・直正を支え続けていた。
「川崎よ。立派になったな。」
「安房様から、学ぶ場をお授けいただいたのです。」
ひたすら感謝の意を述べている、坊主頭の青年。名を川崎道民という。利発そうな丸顔の若者である。

――川崎道民は、“須古領”の侍医(お付きの医者)に養子に入っていた。
鍋島安房は、才能ある川崎道民を領内に留めず、佐賀の藩医に推挙した。こうして川崎は、進んだ西洋の医術を学ぶことができた。
ふと、川崎が“良い事を思い付いた!”と、その表情を緩める。
「長崎にて、面白き業(わざ)を身に付けて参りました!」
「ほう…」
“興味がある”という反応の鍋島安房。この姿勢は変わらない。長年、寝る間も惜しんで、下級藩士たちの話も大切に聞き続けてきた。
昔日は、仕事場と藩校「弘道館」との往復に走り回ったが、今はその気力は感じられず、病身にも伺える。
――しかし探求心は、まだ失われていない様子だ。
「“写真”と呼ばれる業に、ございます。」
「人の姿を、ありのままに写すという業か。」
「左様(その通り)です。」
「もし、宜しければ…」
川崎は、“写真”撮影を提案した。
鍋島安房は、フッと寂しげな表情を浮かべる。
「今の私のありのままには、もはや値打ちは無い。」
――自分を引き立ててくれた、“ご領主”の言葉は芳(かんば)しくない。
川崎も、意気消沈の様子を見せる。
「…川崎よ。お主が写すべきものは、もっと遠くに、遥か向こうにあるのではないか。」
鍋島安房の目には、まだ確かな光が宿っている。その言葉に川崎は、ハッと胸を打たれた。
「…世を広く見聞し、必ずやご期待に応えてお見せします。」
川崎は、鍋島安房の言葉を受け止めた。
――元は、主従の関係だった、この2人。想いは引き継がれた。
ほどなく川崎道民は江戸に向かった。
そして、長年に渡って鍋島直正の補佐役を務めた、鍋島安房は“罷免”という形で表舞台を去っていく。

――1859年。江戸の佐賀藩邸。
川崎道民が、写真の道具を扱っている。この年に撮影されたものが、鍋島直正の肖像写真として最も有名な1枚として知られる。
「…川崎。もう動いても良いか?」
「殿…しばし、しばしのお待ちを!」
「“写真”も、なかなかに窮屈なものよ。」
「良き写りを得るためには、辛抱こそが肝要でござる!」
――殿・直正の“写真”撮影に奮闘する、川崎道民。
「ところで…川崎よ。メリケン(アメリカ)に行かぬか?」
「殿、しばし!動かずにお待ちを…え!?」
「海の向こうの異国、メリケンじゃ。」
「…殿。良き1枚が撮れたようです。」
殿・直正から、突然の海外渡航の提案。動揺する川崎道民だったが、さすがは佐賀の藩医。抜かりなく撮影は成し遂げた様子だ。
(続く)
2020年10月20日
第14話「遣米使節」⑪(名君たちの“約束”)
こんばんは。
“本編”に戻ります。第14話「遣米使節」すでに11回目の投稿ですが、あと4回くらいは要りそうです。
「大河ドラマ」ならば1話分が45分で、オープニングとエンディング(紀行)を入れれば、実質40分ほど…この展開では、おそらく尺が足らないのですが、このまま描きたいので、続行します。〔前回参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕
――“トン・ツー・ツー・トン” 電信機で、信号を送る。
操作するのは佐賀藩士・中村奇輔。京都から来た“精錬方”の科学者である。
「中村さん、ゆくさ(ようこそ)おじゃった(お越しになった)。」
「こい(これ)は、おんし(お主)が?」
ザワザワとする薩摩藩士たち。
持参した電信機は、中村が作ったものである。
「西洋の物とて仕組みが明らかなら作れます。あとは“費用”の問題だけです。」
中村が、さらりと言ってのけた。
――場所は、薩摩(鹿児島)が力を注ぐ、近代化のための工場 “集成館”。
薩摩藩も研究開発に熱心である。中村の技術の価値も、すぐに理解される。
そんな薩摩の若者たちの標(しるべ)となる“光”が、薩摩藩主・島津斉彬。佐賀から蒸気船でやって来た、鍋島直正と、海沿いの庭園で歓談をする。
「さすがは、薩摩の”紅びいどろ”。鮮やかなものですな。」
殿・直正が、透き通った紅色のグラスを手に取り、見つめている。
「さすが佐賀の品、“隙の無い”仕上がりだな。」
一方、島津斉彬は、“肥前びいどろ”を見分していた。

――さて、この名君2人。会談の目的は“ガラス”の品評だけではない。
まず、口を開いたのは島津斉彬である。
「なにゆえ、一橋さまのご推挙に、お力添えくださらぬ?」
薩摩藩は、一橋慶喜を次期将軍に推す“一橋派”の急先鋒だった。佐賀の殿・直正はその活動から距離を置いている。
「それは、公儀(幕府)がお決めになること。外様の口出しは無用にござろう。」
蒸気船を乗り回しはするが、鍋島直正は秩序を重んじる“優等生”である。
「時勢は動くぞ。若年の上様(将軍)では、国の舵取りは難しいとは思わぬか。」
この頃、”一橋派”の理解者で、調整能力が抜群だった、老中・阿部正弘は既に逝去している。薩摩の殿・島津斉彬にも焦りがあった。
――佐賀と薩摩の殿様。話は並行線である。
達観したような表情の殿・直正。何か遠くを見通すような目である。
「…ほう、幼き頃と同じ顔をいたすのだな。」
島津斉彬と、年下の鍋島直正とは、母方のいとこで幼少期から交際がある。
「上様(将軍)のご推挙に口を出さば、相争うことにつながる。」
直正の心配事は、政治の主導権争いによる日本国内での“同士討ち”だった。
「その間に異国が割って入るのを、案じておられるか。」
「…ご明察。」
次期将軍の選定と、通商条約の締結は、この頃の二大争点だった。西洋文明の実力を知る名君2人は、異国の具体的な行動をイメージするのだ。

――手紙では、この“想い”までは通じない。
直正が危険を顧みず、薩摩への船旅を強行した理由でもあった。
ふふ…と笑う斉彬。
「相分かった。異国には付け入る隙を与えぬよう、肝に銘じておくとしよう。」
「約束ですぞ。くれぐれもお忘れ無きように。」
直正は子供のときのような、いたずらな笑みを見せた。
こうして“秘密の会談”を終えた、2人の名君。結論から言えば、この“約束”は果たされなかった。ほどなく、一方の当事者が世を去ったからである。
――蒸気船“観光丸”での帰路。
船長・佐野栄寿(常民)が、あらためて緊張している。
「佐賀に戻るまでが大事!帰り道こそ、気を引き締めねば!」
「佐野はん!気負い過ぎは、あきまへん(ダメですよ)。」
中村も少し気が抜けたのか、“京言葉”に戻っている。
「そうじゃ、佐野。伸び伸びとやればよい。」
殿・直正が船長に言葉をかける。しかし、佐野の緊張のもとは、その殿様を無事に送り届ける使命感からなのだ。
(続く)
“本編”に戻ります。第14話「遣米使節」すでに11回目の投稿ですが、あと4回くらいは要りそうです。
「大河ドラマ」ならば1話分が45分で、オープニングとエンディング(紀行)を入れれば、実質40分ほど…この展開では、おそらく尺が足らないのですが、このまま描きたいので、続行します。〔前回参照:
――“トン・ツー・ツー・トン” 電信機で、信号を送る。
操作するのは佐賀藩士・中村奇輔。京都から来た“精錬方”の科学者である。
「中村さん、ゆくさ(ようこそ)おじゃった(お越しになった)。」
「こい(これ)は、おんし(お主)が?」
ザワザワとする薩摩藩士たち。
持参した電信機は、中村が作ったものである。
「西洋の物とて仕組みが明らかなら作れます。あとは“費用”の問題だけです。」
中村が、さらりと言ってのけた。
――場所は、薩摩(鹿児島)が力を注ぐ、近代化のための工場 “集成館”。
薩摩藩も研究開発に熱心である。中村の技術の価値も、すぐに理解される。
そんな薩摩の若者たちの標(しるべ)となる“光”が、薩摩藩主・島津斉彬。佐賀から蒸気船でやって来た、鍋島直正と、海沿いの庭園で歓談をする。
「さすがは、薩摩の”紅びいどろ”。鮮やかなものですな。」
殿・直正が、透き通った紅色のグラスを手に取り、見つめている。
「さすが佐賀の品、“隙の無い”仕上がりだな。」
一方、島津斉彬は、“肥前びいどろ”を見分していた。
――さて、この名君2人。会談の目的は“ガラス”の品評だけではない。
まず、口を開いたのは島津斉彬である。
「なにゆえ、一橋さまのご推挙に、お力添えくださらぬ?」
薩摩藩は、一橋慶喜を次期将軍に推す“一橋派”の急先鋒だった。佐賀の殿・直正はその活動から距離を置いている。
「それは、公儀(幕府)がお決めになること。外様の口出しは無用にござろう。」
蒸気船を乗り回しはするが、鍋島直正は秩序を重んじる“優等生”である。
「時勢は動くぞ。若年の上様(将軍)では、国の舵取りは難しいとは思わぬか。」
この頃、”一橋派”の理解者で、調整能力が抜群だった、老中・阿部正弘は既に逝去している。薩摩の殿・島津斉彬にも焦りがあった。
――佐賀と薩摩の殿様。話は並行線である。
達観したような表情の殿・直正。何か遠くを見通すような目である。
「…ほう、幼き頃と同じ顔をいたすのだな。」
島津斉彬と、年下の鍋島直正とは、母方のいとこで幼少期から交際がある。
「上様(将軍)のご推挙に口を出さば、相争うことにつながる。」
直正の心配事は、政治の主導権争いによる日本国内での“同士討ち”だった。
「その間に異国が割って入るのを、案じておられるか。」
「…ご明察。」
次期将軍の選定と、通商条約の締結は、この頃の二大争点だった。西洋文明の実力を知る名君2人は、異国の具体的な行動をイメージするのだ。

――手紙では、この“想い”までは通じない。
直正が危険を顧みず、薩摩への船旅を強行した理由でもあった。
ふふ…と笑う斉彬。
「相分かった。異国には付け入る隙を与えぬよう、肝に銘じておくとしよう。」
「約束ですぞ。くれぐれもお忘れ無きように。」
直正は子供のときのような、いたずらな笑みを見せた。
こうして“秘密の会談”を終えた、2人の名君。結論から言えば、この“約束”は果たされなかった。ほどなく、一方の当事者が世を去ったからである。
――蒸気船“観光丸”での帰路。
船長・佐野栄寿(常民)が、あらためて緊張している。
「佐賀に戻るまでが大事!帰り道こそ、気を引き締めねば!」
「佐野はん!気負い過ぎは、あきまへん(ダメですよ)。」
中村も少し気が抜けたのか、“京言葉”に戻っている。
「そうじゃ、佐野。伸び伸びとやればよい。」
殿・直正が船長に言葉をかける。しかし、佐野の緊張のもとは、その殿様を無事に送り届ける使命感からなのだ。
(続く)
2020年10月18日
「主に太良町民の皆様を対象にしたつぶやき」
こんばんは。
今週末にも気分転換の投稿を作成しました。
とくに太良町ゆかりの方が、ご覧になっていれば幸いです。
現在、“本編”では、殿・鍋島直正が薩摩(鹿児島)に到着するところです。佐野常民(栄寿)が、蒸気船”観光丸”を船長として運用しています。
―― 人には、それぞれの標(しるべ)となる光がある。
いきなり何を言い出すか…という展開ですが、“本編”と太良町の幕末・明治に話をつなげるためです。
現在、江戸前ずしのネタとして有名な“コハダ”。最近、名が売れてきた高級な柑橘類・“クレメンティン”
…と、太良町には、海にも陸にも特産品があります。名所としては「海中鳥居」や「竹崎城址」にも触れたいところですが、それらは温存して別の話をします。
――まず、幕末(1804年~1829年)の文化・文政年間。
“本編”では、第1話「長崎警護」~第2話「算盤大名」で扱った年代。
1808年 フェートン号事件
1814年 鍋島直正、誕生
1825年 異国船打払令
1828年 シーボルト台風(子年の大風)
1830年 鍋島直正が佐賀藩主に就く
…佐賀藩としても、激動の時代でした。

――この時期、太良町に“村娘”たちの光となる人物がいたと伝わります。
佐賀には「岳の新太郎さん」という民謡があると知りました。
それが、この銅像の美少年を描いた歌です。
説明板を拡大すれば、その人となりが浮かび上がるはずです。多良岳の山頂近く、金泉寺の寺侍…とあります。
――なんと、彼が寺との山道を上り下りするだけで、
村娘たちの心は“ザンザ、ザンザ”と揺れ動いたと言われます。その心のざわめきは歌に残るほどだった…ということで、後世に伝わっています。
もはや単なる“イケメン”の域を超えて、「ご当地アイドル」としての存在感。
幕末史に名を残さずとも、こうやって銅像が建つこともある…
勤勉に働き、農業等の生産者として佐賀の躍進に貢献したであろう村娘たち。「新太郎さん」は彼女たちの潤いであり、光であったと言えるのかもしれません。
――さて、今度は明治に至る、船を導く光の話です。
遠浅である有明海。複雑な潮流と干満の差によって、海の難所だったそうです。そこで、船にとって大事な光のサインである、燈台を建てます。
太良町には江戸時代から燈台があり、近隣の寺が管理していたようです。当時のお寺には、そんな役割もあったのですね。
この燈台は幕末期に大風(台風)で破損し、何とか再建されたのは1869年(明治2年)でした。すでに、時代は明治へと移っていました。

――なんと、日本初 “十一面ガラス鏡式 洋風燈台”で設置されました。
太良町の“夜灯鼻燈台”の跡には、その石碑が建っています。
これも説明板によりますが、燈台を再建したのは、佐賀藩の自治領の1つ“諫早領”の家老の子孫・早田市右衛門という人物。
江戸時代に燈台を再建した早田番佐衛門の“五世”の孫と記されています。
「ご先祖の名に懸けて燈台を再建する!」という決意があったのでしょうか。
…個人的に、こういう展開のお話は好きです。
――この燈台再建の2年後。
明治政府で洋式燈台の普及のため、工部省の責任者(燈台頭)となった人物が…佐野常民(栄寿)。ここからは“本編”のPRになります。
第14話の設定年代は、まだ1855年~1860年頃です。同じ時代を様々な角度で見る構成なので、各話で年代の重なりは多いです。
幕末期、日本には“名君”という光もありました。
〔参照:第13話「通商条約」⑪(名君たちの“未来”)〕
…次回投稿の“伏線”となる話です。大きな存在だった“名君たち”の光と影。現代の感覚では描きにくいところですが、なるべく頑張って表現したいところです。
今週末にも気分転換の投稿を作成しました。
とくに太良町ゆかりの方が、ご覧になっていれば幸いです。
現在、“本編”では、殿・鍋島直正が薩摩(鹿児島)に到着するところです。佐野常民(栄寿)が、蒸気船”観光丸”を船長として運用しています。
―― 人には、それぞれの標(しるべ)となる光がある。
いきなり何を言い出すか…という展開ですが、“本編”と太良町の幕末・明治に話をつなげるためです。
現在、江戸前ずしのネタとして有名な“コハダ”。最近、名が売れてきた高級な柑橘類・“クレメンティン”
…と、太良町には、海にも陸にも特産品があります。名所としては「海中鳥居」や「竹崎城址」にも触れたいところですが、それらは温存して別の話をします。
――まず、幕末(1804年~1829年)の文化・文政年間。
“本編”では、第1話「長崎警護」~第2話「算盤大名」で扱った年代。
1808年 フェートン号事件
1814年 鍋島直正、誕生
1825年 異国船打払令
1828年 シーボルト台風(子年の大風)
1830年 鍋島直正が佐賀藩主に就く
…佐賀藩としても、激動の時代でした。
――この時期、太良町に“村娘”たちの光となる人物がいたと伝わります。
佐賀には「岳の新太郎さん」という民謡があると知りました。
それが、この銅像の美少年を描いた歌です。
説明板を拡大すれば、その人となりが浮かび上がるはずです。多良岳の山頂近く、金泉寺の寺侍…とあります。
――なんと、彼が寺との山道を上り下りするだけで、
村娘たちの心は“ザンザ、ザンザ”と揺れ動いたと言われます。その心のざわめきは歌に残るほどだった…ということで、後世に伝わっています。
もはや単なる“イケメン”の域を超えて、「ご当地アイドル」としての存在感。
幕末史に名を残さずとも、こうやって銅像が建つこともある…
勤勉に働き、農業等の生産者として佐賀の躍進に貢献したであろう村娘たち。「新太郎さん」は彼女たちの潤いであり、光であったと言えるのかもしれません。
――さて、今度は明治に至る、船を導く光の話です。
遠浅である有明海。複雑な潮流と干満の差によって、海の難所だったそうです。そこで、船にとって大事な光のサインである、燈台を建てます。
太良町には江戸時代から燈台があり、近隣の寺が管理していたようです。当時のお寺には、そんな役割もあったのですね。
この燈台は幕末期に大風(台風)で破損し、何とか再建されたのは1869年(明治2年)でした。すでに、時代は明治へと移っていました。
――なんと、日本初 “十一面ガラス鏡式 洋風燈台”で設置されました。
太良町の“夜灯鼻燈台”の跡には、その石碑が建っています。
これも説明板によりますが、燈台を再建したのは、佐賀藩の自治領の1つ“諫早領”の家老の子孫・早田市右衛門という人物。
江戸時代に燈台を再建した早田番佐衛門の“五世”の孫と記されています。
「ご先祖の名に懸けて燈台を再建する!」という決意があったのでしょうか。
…個人的に、こういう展開のお話は好きです。
――この燈台再建の2年後。
明治政府で洋式燈台の普及のため、工部省の責任者(燈台頭)となった人物が…佐野常民(栄寿)。ここからは“本編”のPRになります。
第14話の設定年代は、まだ1855年~1860年頃です。同じ時代を様々な角度で見る構成なので、各話で年代の重なりは多いです。
幕末期、日本には“名君”という光もありました。
〔参照:
…次回投稿の“伏線”となる話です。大きな存在だった“名君たち”の光と影。現代の感覚では描きにくいところですが、なるべく頑張って表現したいところです。
2020年10月16日
第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)
こんばんは。
前回、殿・鍋島直正が、薩摩(鹿児島)に蒸気船で向かう計画を明かしました。当時の薩摩藩主・島津斉彬は、殿の母方のいとこにあたります。
この航海の目的は判然としておらず、時期にも諸説ありますが、「日米修好通商条約」締結の直前期で、何らかの相談があった…と推測されています。
――長崎。ある蒸気船の甲板。
佐賀藩が、幕府から訓練のため借りている“観光丸”である。
「ふーっ!」
大きく深呼吸をする、佐野栄寿(常民)。この航海の船長に重責がのしかかる。
「佐野はん。いや、船長。いよいよやな。」
化学・物理の双方に通じた、科学者・中村奇輔。出身地の“京言葉”が抜けない佐賀藩士である。
中村も、殿・直正の指示で、自作した“電信機”を手土産に薩摩に向かうのだ。
――このとき、佐賀の殿様も、密かに船に乗り込んだ。
肥前佐賀35万7千石の当主・鍋島直正。
佐賀と薩摩。外様の大藩同士での“密談”に向かうのである。そして、幕府には単なる訓練の航海で届け出ている。
「佐野。よろしく頼むぞ。」
「はっ!」
――秘密の航海には、危険が伴う。
その途上で事故でもあれば、佐賀藩が危機に瀕するのは明らかだった。
さすがの佐野も、緊張で手がブルブルとする。
「船出だ!帆を上げろ!」
「はい!!船長!」
海軍伝習の経験者が先導し、佐賀の水夫(船手方)たちも動く。
――この頃は蒸気船でも、燃料補給の問題もあり、よく帆走を使う。
“観光丸”は、ゆらりと風を受けて長崎を出港した。
港から離れると、殿・直正が甲板に現れた。殿様も、窮屈な生活である。ましてや、直正ほどの“実力”がある大名は、常に動向が注目されている。
「…海は良いのう。潮風が快い。」
「はっ、今日は良き日和(ひより)です。」
順調な船出に安堵した、佐野が応える。
「この海の向こう、この目で見てみたいものよ。」
いつになく、大きく伸びをする直正。遠く、海の彼方を見遣っていた。

――風が弱まり、凪(なぎ)となる。
「この時を待っておった!行け、佐野よ。」
殿・直正が弾んだ声をかける。
「汽走に切り換えるぞ!」
佐野が、海軍伝習を受けた士官たちに“蒸気機関”の起動を指示した。
ボッ…
煙突から、ゆらゆらと黒煙が立ち上がる。
ガランガラン…
船の両舷(げん)にある“外輪”が、水車のようにゆっくり回転を始める。
――わずか4年ばかり前。日本を驚愕させた“黒船”。
佐賀藩士たちは、いまや自在に蒸気船を操り、薩摩に向かっているのだ。
外輪は勢いよく水を掻き、“観光丸”は速度を増している。
「取り舵(左に旋回)だ。」
佐野が海図を見ながら、指示を出す。船は着実に南方へと進む。
「…いやぁ、やっぱり“蒸気機関”は、ええなぁ!」
作業からご機嫌で帰ってきた、中村奇輔。
――顔中が、炭で煤(すす)けているが笑顔である。
「中村よ。また、ずいぶん“蒸気仕掛け”と戯れたと見えるな。」
殿・直正が、中村にも声をかける。
「これは…お殿様。まぁ、仰せの通りです。」
恐縮しながらも、やはり楽しそうな中村。
「お主が、佐賀に来てくれて良かった。」
「はっ、勿体(もったい)なき、お言葉。私こそ果報者です。」
佐野からの誘いに応じて中村は、京都から佐賀に来た。蒸気機関を設計したり、電信機を作ったり…これが中村にとって、幸せな日々なのである。

――航海は順調に進む。薩摩の桜島(錦江湾)に寄せていく“観光丸”。
「殿…なにゆえ危険を顧みず、薩摩まで…」
佐野は船上で、ずっと聞きたかったことを、直正に尋ねた。
「薩摩さまに、差し出がましいことを申し上げるためじゃ。」
「…!?」
「狭い日本(ひのもと)で、“小競り合い”を為しても仕方ないとな。」
(続く)
前回、殿・鍋島直正が、薩摩(鹿児島)に蒸気船で向かう計画を明かしました。当時の薩摩藩主・島津斉彬は、殿の母方のいとこにあたります。
この航海の目的は判然としておらず、時期にも諸説ありますが、「日米修好通商条約」締結の直前期で、何らかの相談があった…と推測されています。
――長崎。ある蒸気船の甲板。
佐賀藩が、幕府から訓練のため借りている“観光丸”である。
「ふーっ!」
大きく深呼吸をする、佐野栄寿(常民)。この航海の船長に重責がのしかかる。
「佐野はん。いや、船長。いよいよやな。」
化学・物理の双方に通じた、科学者・中村奇輔。出身地の“京言葉”が抜けない佐賀藩士である。
中村も、殿・直正の指示で、自作した“電信機”を手土産に薩摩に向かうのだ。
――このとき、佐賀の殿様も、密かに船に乗り込んだ。
肥前佐賀35万7千石の当主・鍋島直正。
佐賀と薩摩。外様の大藩同士での“密談”に向かうのである。そして、幕府には単なる訓練の航海で届け出ている。
「佐野。よろしく頼むぞ。」
「はっ!」
――秘密の航海には、危険が伴う。
その途上で事故でもあれば、佐賀藩が危機に瀕するのは明らかだった。
さすがの佐野も、緊張で手がブルブルとする。
「船出だ!帆を上げろ!」
「はい!!船長!」
海軍伝習の経験者が先導し、佐賀の水夫(船手方)たちも動く。
――この頃は蒸気船でも、燃料補給の問題もあり、よく帆走を使う。
“観光丸”は、ゆらりと風を受けて長崎を出港した。
港から離れると、殿・直正が甲板に現れた。殿様も、窮屈な生活である。ましてや、直正ほどの“実力”がある大名は、常に動向が注目されている。
「…海は良いのう。潮風が快い。」
「はっ、今日は良き日和(ひより)です。」
順調な船出に安堵した、佐野が応える。
「この海の向こう、この目で見てみたいものよ。」
いつになく、大きく伸びをする直正。遠く、海の彼方を見遣っていた。

――風が弱まり、凪(なぎ)となる。
「この時を待っておった!行け、佐野よ。」
殿・直正が弾んだ声をかける。
「汽走に切り換えるぞ!」
佐野が、海軍伝習を受けた士官たちに“蒸気機関”の起動を指示した。
ボッ…
煙突から、ゆらゆらと黒煙が立ち上がる。
ガランガラン…
船の両舷(げん)にある“外輪”が、水車のようにゆっくり回転を始める。
――わずか4年ばかり前。日本を驚愕させた“黒船”。
佐賀藩士たちは、いまや自在に蒸気船を操り、薩摩に向かっているのだ。
外輪は勢いよく水を掻き、“観光丸”は速度を増している。
「取り舵(左に旋回)だ。」
佐野が海図を見ながら、指示を出す。船は着実に南方へと進む。
「…いやぁ、やっぱり“蒸気機関”は、ええなぁ!」
作業からご機嫌で帰ってきた、中村奇輔。
――顔中が、炭で煤(すす)けているが笑顔である。
「中村よ。また、ずいぶん“蒸気仕掛け”と戯れたと見えるな。」
殿・直正が、中村にも声をかける。
「これは…お殿様。まぁ、仰せの通りです。」
恐縮しながらも、やはり楽しそうな中村。
「お主が、佐賀に来てくれて良かった。」
「はっ、勿体(もったい)なき、お言葉。私こそ果報者です。」
佐野からの誘いに応じて中村は、京都から佐賀に来た。蒸気機関を設計したり、電信機を作ったり…これが中村にとって、幸せな日々なのである。
――航海は順調に進む。薩摩の桜島(錦江湾)に寄せていく“観光丸”。
「殿…なにゆえ危険を顧みず、薩摩まで…」
佐野は船上で、ずっと聞きたかったことを、直正に尋ねた。
「薩摩さまに、差し出がましいことを申し上げるためじゃ。」
「…!?」
「狭い日本(ひのもと)で、“小競り合い”を為しても仕方ないとな。」
(続く)
2020年10月14日
第14話「遣米使節」⑨(聞かれては困る話)
こんばんは。
前回の続きです。
長崎に着いて、佐野栄寿(常民)と中村奇輔に再会できると思った、翻訳家・石黒。しかし、宿舎に両名の姿は見当たりません。
少し時を遡って、佐野・中村の2名の足取りを追ってみます。
――長崎の夜。ある立派な屋敷の…屋根に佇(たたず)む者がいる。
見張りの役目にあたる、佐賀の蓮池藩士・古賀である。もはや“嬉野の忍者”といった方が通りが良いかもしれない。
そこに、屋根伝いに進む影があった。
「この辺りにも、ネズミさんが増えとるばい。」
影に近付いて声をかける、古賀。

――古賀の声に、他藩の忍びと思われる“ネズミ”が反応する。
「…なんじゃ、貴様。佐賀の“化け猫”か。」
「誰が“化け猫”やら言いよっとね!?」
バサッ!
古賀が言葉を返すや、“ネズミ”は右手から粉状の“目つぶし”を放った。
「…甘いんじゃ!」
――捨て台詞(ぜりふ)を吐く忍び。逃走の準備に入る。
しかし“目つぶし”を撒いた先には、すでに古賀の影は無い。
「昨今は“ネズミ”も、よう吠えよっとね…」
不意打ちを、低く丸くかわして“ネズミ”の背後に回っていたのである。
「…後ろに居たかっ!」
“ネズミ”と呼ばれた“忍び”の動きも速い。左手に持った短刀で背後を突く。
――古賀は、小刀を抜き付け、受け流す。
ギュルッ…
生々しい金属音がする。
バシッ!
…その瞬間、古賀の右足が伸び、“忍び”の腰を捉えた。
ガラン、ガラガラ…
勢い余ったところに、古賀に蹴りを加えられ、“忍び”の体勢は泳いだ。そのまま屋根から転げる。

――“忍び”は屋敷を見張る、佐賀藩“深堀領”の警備兵の間に落ちた。
「何奴(なにやつ)!屋根から降ってきたぞ。」
「…見るからに怪しかばい!」
ビシッ!ボコッ!
“深堀領”とは、長崎にある佐賀藩の領地(飛び地)。
長崎警備の第一線にあたる佐賀藩士たちは、怒らせると怖い。
――落ちた“忍び”は術を遣う間もなく、打ちのめされている様子だ。
地上の騒ぎを眺める“嬉野の忍者”古賀。
「明日は“我が身”かも知れんばい。えすか(怖い)ごたね…」
…忍びの定めを感じて、一言つぶやくと、また屋根の見張りに戻るのだった。
――この厳重な警備には理由があった。
殿・鍋島直正が、佐賀から長崎に来ていたのだ。辺りが騒々しいが、すぐ隣の屋敷では「聞かれては困る話」の最中である。
「此度(こたび)の航海では、薩摩に参るぞ!」
「殿…。“さつま”って、あの“薩摩”(鹿児島)ですか。」
「殿、念のためお伺いします。“観光丸”は公儀(幕府)からの預かり物です。」
「そうじゃ、良き船であるからのう。出航が楽しみであるな。」
――呆気に取られている2人、佐野栄寿(常民)と化学者・中村奇輔。
殿・直正は「幕府から借りた蒸気船“観光丸”で、薩摩に乗り入れる!」と告げたのである。2人が驚くのも無理はない。まだ“大名行列”の時代なのだ。
たしかに薩摩藩の島津斉彬は、殿・直正のいとこではあるが、他の大名の領国へ、直接、蒸気船で訪問するなど前代未聞の事だった。
佐野も「殿に海軍伝習で得た実力を見せよう!」と張り切っていた。しかし、訓練の成果を示すどころか、大変な船旅が始まろうとしていたのである。
(続く)
前回の続きです。
長崎に着いて、佐野栄寿(常民)と中村奇輔に再会できると思った、翻訳家・石黒。しかし、宿舎に両名の姿は見当たりません。
少し時を遡って、佐野・中村の2名の足取りを追ってみます。
――長崎の夜。ある立派な屋敷の…屋根に佇(たたず)む者がいる。
見張りの役目にあたる、佐賀の蓮池藩士・古賀である。もはや“嬉野の忍者”といった方が通りが良いかもしれない。
そこに、屋根伝いに進む影があった。
「この辺りにも、ネズミさんが増えとるばい。」
影に近付いて声をかける、古賀。
――古賀の声に、他藩の忍びと思われる“ネズミ”が反応する。
「…なんじゃ、貴様。佐賀の“化け猫”か。」
「誰が“化け猫”やら言いよっとね!?」
バサッ!
古賀が言葉を返すや、“ネズミ”は右手から粉状の“目つぶし”を放った。
「…甘いんじゃ!」
――捨て台詞(ぜりふ)を吐く忍び。逃走の準備に入る。
しかし“目つぶし”を撒いた先には、すでに古賀の影は無い。
「昨今は“ネズミ”も、よう吠えよっとね…」
不意打ちを、低く丸くかわして“ネズミ”の背後に回っていたのである。
「…後ろに居たかっ!」
“ネズミ”と呼ばれた“忍び”の動きも速い。左手に持った短刀で背後を突く。
――古賀は、小刀を抜き付け、受け流す。
ギュルッ…
生々しい金属音がする。
バシッ!
…その瞬間、古賀の右足が伸び、“忍び”の腰を捉えた。
ガラン、ガラガラ…
勢い余ったところに、古賀に蹴りを加えられ、“忍び”の体勢は泳いだ。そのまま屋根から転げる。

――“忍び”は屋敷を見張る、佐賀藩“深堀領”の警備兵の間に落ちた。
「何奴(なにやつ)!屋根から降ってきたぞ。」
「…見るからに怪しかばい!」
ビシッ!ボコッ!
“深堀領”とは、長崎にある佐賀藩の領地(飛び地)。
長崎警備の第一線にあたる佐賀藩士たちは、怒らせると怖い。
――落ちた“忍び”は術を遣う間もなく、打ちのめされている様子だ。
地上の騒ぎを眺める“嬉野の忍者”古賀。
「明日は“我が身”かも知れんばい。えすか(怖い)ごたね…」
…忍びの定めを感じて、一言つぶやくと、また屋根の見張りに戻るのだった。
――この厳重な警備には理由があった。
殿・鍋島直正が、佐賀から長崎に来ていたのだ。辺りが騒々しいが、すぐ隣の屋敷では「聞かれては困る話」の最中である。
「此度(こたび)の航海では、薩摩に参るぞ!」
「殿…。“さつま”って、あの“薩摩”(鹿児島)ですか。」
「殿、念のためお伺いします。“観光丸”は公儀(幕府)からの預かり物です。」
「そうじゃ、良き船であるからのう。出航が楽しみであるな。」
――呆気に取られている2人、佐野栄寿(常民)と化学者・中村奇輔。
殿・直正は「幕府から借りた蒸気船“観光丸”で、薩摩に乗り入れる!」と告げたのである。2人が驚くのも無理はない。まだ“大名行列”の時代なのだ。
たしかに薩摩藩の島津斉彬は、殿・直正のいとこではあるが、他の大名の領国へ、直接、蒸気船で訪問するなど前代未聞の事だった。
佐野も「殿に海軍伝習で得た実力を見せよう!」と張り切っていた。しかし、訓練の成果を示すどころか、大変な船旅が始まろうとしていたのである。
(続く)
2020年10月12日
第14話「遣米使節」⑧(孤高のエンジニア)
こんばんは。
第14話「遣米使節」は、主に幕末期に海外に渡った人物のお話です。長い“鎖国”の時代を経て、彼らが得た西洋の知識は、のちに明治を開く力となります。
――佐賀城下。佐賀藩の理化学研究所である“精錬方”。
ここにも熱く語る青年がいる。名を秀島藤之助という。
「螺旋(らせん)の切り込みを入れた“試作砲”を、ぜひ見たい!」
二代目・儀右衛門(田中久重の養子)が短く返答する。
「いまは忙しい。義父(ちち)の考えた機工を、一刻も早く形に成すのだ!」
「いい加減、義父(ちち)放れしてはどうか。」
「何だって…!?」
明らかに険しい表情をする“二代目”。義父が出張中なのを良いことに、秀島が挑発をしてきた…と受け取った。
――“二代目”にとって、尊敬する初代・儀右衛門(田中久重)の設計は絶対である。
秀島に悪気は無かった。技術者として自身の考えで動けば良い…と言いたかったのだ。
「だから、時が無い!今は“蒸気仕掛け”を急いでおるのだ!」
二代目・儀右衛門が、余計につむじを曲げる。
「少し見聞したいだけだ。手を貸してくれ!」
秀島も、長崎に向かわねばならないが、何とか事前に知識を得たいようだ。

――長崎への出立が遅れていた、翻訳家・石黒寛次が2人の様子を伺う。
「そこに居るんは、秀島さんやないか。まだ残っていたんか。」
石黒が声をかけたが、秀島は“二代目”との議論に集中して気付かない。
「…これは、当分、終わらんな。」
石黒は、たまたま現れた江藤新平と雑談をしていただけだが、この“大論戦”に関係していると勘違いされて、長崎に出る一行から置いていかれたらしい。
「二代目!儂も長崎に向かうで!」
「石黒さん!お気をつけて!」
秀島と一緒に、長崎に行くべきかと考えたが、かなり熱が入っていて難しそうだ。まだ冷静な“二代目”に、声をかけると石黒は一人、長崎への旅路を急ぐ。
――佐賀藩の“精錬方”。いつもの最先端研究のパターンはこうだ。
まず、石黒が洋書を翻訳し、科学者・中村奇輔が理論を解明する。
主に製造を担当するのが、“からくり儀右衛門”父子である。田中久重(初代)が機械を設計し、養子の二代目・儀右衛門が精密部品を加工する。
このメンバー全員をスカウトしてきたのが佐野栄寿(常民)。研究プロジェクトを管理するリーダーである。
――対して、秀島藤之助は、佐賀藩の鉄製大砲の改良を担当する。
秀島とて、新進気鋭の技術者である。しかし、経験値では“精錬方”のメンバーには劣る。孤高の天才と言うべき秀島は、必死で技術情報を収集していた。
「あいつら、大丈夫かな…」
“二代目”儀右衛門と秀島藤之助の議論の行方は気になるが、石黒は、すでに長崎の海軍伝習に向かう集団から出遅れているのだ。

――牛津宿。“西の浪花”(大坂)とまで呼ばれる商人の町。
石黒は、長崎の海軍伝習に向かう“蘭学寮”の若手に追いついた。現代で言えば高校生くらいの男子たちである。ちょっと道草をして、団子など食っていた。
「あ…石黒さま。お取込み中とお見受けし、お声もかけず失礼を。」
石丸虎五郎(安世)。のちに英語の達人になって、日本に電信網を築く人物。
「…我らがご城下を出た時から計ると…かなりの早足でお着きですね。」
中牟田倉之助である。のちに海軍で活躍する。算術が得意だ。
――ほかの若手も反応する「おおっ、精錬方の石黒さまだ」と。
佐賀藩の先端研究を支える“翻訳家”に、どよめく“蘭学寮”の若手たち。
石黒も、賢い若手たちからの反応なので、まんざら悪い気はしない。
「いや…儂など、小屋に籠(こも)って、洋書と“にらめっこ”しとるだけやで。」
「まさか、石黒先生と道中、ご一緒できるとは!」
「色々とご教示ください!」
――何やら楽しい道中で、すっかり気分良く長崎に到着した、石黒。
「佐野!中村~っ!儂も長崎に来たで!」
石黒は長崎の宿舎に着くや、元気よく京都時代からの旧友2人を呼んだ。しかし、2人はすでに不在だった。
「また、どこかに行っちゃっとる…」
このとき、佐野栄寿(常民)と中村奇輔の2人は、石黒の予想だにしない場所に居たのである。
(続く)
第14話「遣米使節」は、主に幕末期に海外に渡った人物のお話です。長い“鎖国”の時代を経て、彼らが得た西洋の知識は、のちに明治を開く力となります。
――佐賀城下。佐賀藩の理化学研究所である“精錬方”。
ここにも熱く語る青年がいる。名を秀島藤之助という。
「螺旋(らせん)の切り込みを入れた“試作砲”を、ぜひ見たい!」
二代目・儀右衛門(田中久重の養子)が短く返答する。
「いまは忙しい。義父(ちち)の考えた機工を、一刻も早く形に成すのだ!」
「いい加減、義父(ちち)放れしてはどうか。」
「何だって…!?」
明らかに険しい表情をする“二代目”。義父が出張中なのを良いことに、秀島が挑発をしてきた…と受け取った。
――“二代目”にとって、尊敬する初代・儀右衛門(田中久重)の設計は絶対である。
秀島に悪気は無かった。技術者として自身の考えで動けば良い…と言いたかったのだ。
「だから、時が無い!今は“蒸気仕掛け”を急いでおるのだ!」
二代目・儀右衛門が、余計につむじを曲げる。
「少し見聞したいだけだ。手を貸してくれ!」
秀島も、長崎に向かわねばならないが、何とか事前に知識を得たいようだ。
――長崎への出立が遅れていた、翻訳家・石黒寛次が2人の様子を伺う。
「そこに居るんは、秀島さんやないか。まだ残っていたんか。」
石黒が声をかけたが、秀島は“二代目”との議論に集中して気付かない。
「…これは、当分、終わらんな。」
石黒は、たまたま現れた江藤新平と雑談をしていただけだが、この“大論戦”に関係していると勘違いされて、長崎に出る一行から置いていかれたらしい。
「二代目!儂も長崎に向かうで!」
「石黒さん!お気をつけて!」
秀島と一緒に、長崎に行くべきかと考えたが、かなり熱が入っていて難しそうだ。まだ冷静な“二代目”に、声をかけると石黒は一人、長崎への旅路を急ぐ。
――佐賀藩の“精錬方”。いつもの最先端研究のパターンはこうだ。
まず、石黒が洋書を翻訳し、科学者・中村奇輔が理論を解明する。
主に製造を担当するのが、“からくり儀右衛門”父子である。田中久重(初代)が機械を設計し、養子の二代目・儀右衛門が精密部品を加工する。
このメンバー全員をスカウトしてきたのが佐野栄寿(常民)。研究プロジェクトを管理するリーダーである。
――対して、秀島藤之助は、佐賀藩の鉄製大砲の改良を担当する。
秀島とて、新進気鋭の技術者である。しかし、経験値では“精錬方”のメンバーには劣る。孤高の天才と言うべき秀島は、必死で技術情報を収集していた。
「あいつら、大丈夫かな…」
“二代目”儀右衛門と秀島藤之助の議論の行方は気になるが、石黒は、すでに長崎の海軍伝習に向かう集団から出遅れているのだ。
――牛津宿。“西の浪花”(大坂)とまで呼ばれる商人の町。
石黒は、長崎の海軍伝習に向かう“蘭学寮”の若手に追いついた。現代で言えば高校生くらいの男子たちである。ちょっと道草をして、団子など食っていた。
「あ…石黒さま。お取込み中とお見受けし、お声もかけず失礼を。」
石丸虎五郎(安世)。のちに英語の達人になって、日本に電信網を築く人物。
「…我らがご城下を出た時から計ると…かなりの早足でお着きですね。」
中牟田倉之助である。のちに海軍で活躍する。算術が得意だ。
――ほかの若手も反応する「おおっ、精錬方の石黒さまだ」と。
佐賀藩の先端研究を支える“翻訳家”に、どよめく“蘭学寮”の若手たち。
石黒も、賢い若手たちからの反応なので、まんざら悪い気はしない。
「いや…儂など、小屋に籠(こも)って、洋書と“にらめっこ”しとるだけやで。」
「まさか、石黒先生と道中、ご一緒できるとは!」
「色々とご教示ください!」
――何やら楽しい道中で、すっかり気分良く長崎に到着した、石黒。
「佐野!中村~っ!儂も長崎に来たで!」
石黒は長崎の宿舎に着くや、元気よく京都時代からの旧友2人を呼んだ。しかし、2人はすでに不在だった。
「また、どこかに行っちゃっとる…」
このとき、佐野栄寿(常民)と中村奇輔の2人は、石黒の予想だにしない場所に居たのである。
(続く)