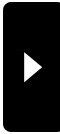2020年06月30日
「主に基山町民・鳥栖市民の方を対象にしたつぶやき」
こんばんは。
前回は「幕末佐賀と4つの“口”」というタイトルでした。
このテーマを意識しながら、「佐賀県内の各地域の皆様に向けた“つぶやき”」を試みます。
――初回は“対馬口”の特集です。朝鮮半島への交流ルートとしての長い歴史があります。
ここで、数少ない県外の読者の方に補足なのですが、佐賀県=佐賀藩ではありません。
佐賀県の東端にある基山町。そして隣接する鳥栖市の東部。
江戸時代は、対馬藩の領地でした。
長崎県の対馬が本拠地。対馬府中藩、厳原藩とも呼ばれたようです。

――写真は長崎街道(佐賀市内)です。この道を東に進めば、鳥栖・基山へと続きます。
今のところ“本編”で一番アクセスのあった記事は、殿・鍋島直正のお国入りの場面。
鳥栖市(東部)の田代(たじろ)宿までは、対馬藩領。
殿・直正は、ここまでは駕籠に乗って移動したことでしょう。
国境を越え、鳥栖市(西部)の轟木(とどろき)宿からは、颯爽と馬に跨ります。
そして、佐賀藩の領民たちから万雷の歓声で迎えられる…というお話でした。
また“団にょん”こと島義勇は、まず長崎街道を東上し、蝦夷地への探検に向かっています。
佐賀藩の東端から旅立つときには、何を想ったのでしょうか。
――そんな佐賀藩との“国境の街”だった、この地域の名称は“対馬藩・田代領”。
田代領は、離島を本拠地とする対馬藩にとって“台所”。いわば経済の中心としての役回りがあったようです。
対馬藩の田代領は、“白蝋(ろう)”などの品質管理が徹底していた佐賀藩に比べれば統制が緩やか。
“薬種”になる商品作物の売買も、融通がきいたようです。
――長崎街道の田代宿は賑わいのある宿場町。
鳥栖と言えば、交通・物流の重要ポイントであることは変わらないようです。
現在でも鳥栖近辺は製薬業が強い地域ですが、“田代の薬”は日本4大売薬の一角を占めたとか。
…ちなみに他の3大売薬は、富山、大和(奈良)、近江(滋賀)のようですね。この3強に並ぶとは、田代の売薬…かなりの実力者です。
――そして、対馬藩田代領も、幕末の動乱に巻き込まれていきます。
江戸時代も「対馬口」として、朝鮮半島との交流拠点だった対馬藩。
しかし、日本海上の要衝にある、この対馬を諸外国が放っておくわけがありません。
次々に現れる、西洋列強の影。
対馬藩も、佐賀藩に大砲を発注するなど、防備を固めていきます。
――1860年代。“本編”では第14話ぐらいで描けるかどうか…
対馬藩は、イギリスとロシアの争いに巻き込まれていきます。
ロシア船が、対馬に上陸する非常事態。
佐賀海軍も新鋭艦を出動させ、伊万里沖で待機。
幕府はロシアと敵対するイギリスを通じて圧力をかけます。
――もちろん対馬が脅かされれば、田代領の侍たちも黙っていません。
「攘夷じゃ!」
「夷狄(いてき)ば、追い払わんばならん!」
田代領の侍たちは、対馬に馳せ参じ、ロシア船との戦闘に備えます。ロシア船が退去した後は、攘夷の急先鋒、長州藩(山口)に接近していきます。
そして、対長同盟(対馬と長州の同盟)の締結に至ります!

…いかがでしょうか。基山町・鳥栖市(東部)の激動の幕末。
私も調べるまで、全然知りませんでした。九州北部には語られなかった“幕末”が数多くありそうです。
古代の山城・基肄(きい)城が、基山町の名所と聞きます。福岡の大野城とともに、大宰府の守りを固める役割があったそうです。
元寇でも最前線に立った、対馬藩の領地だったこともあり、より国を守る気概が強かったのかもしれません…
2018年の「さが幕末維新博覧会」。基山町による「基山の日」というイベントがあったようですが、どちらかと言えば、基山町そのもののPRの色合いが強かったようです。
壮絶な運命を辿った対馬藩田代領の侍たち。少しでも話題になれば良いなと思います。
前回は「幕末佐賀と4つの“口”」というタイトルでした。
このテーマを意識しながら、「佐賀県内の各地域の皆様に向けた“つぶやき”」を試みます。
――初回は“対馬口”の特集です。朝鮮半島への交流ルートとしての長い歴史があります。
ここで、数少ない県外の読者の方に補足なのですが、佐賀県=佐賀藩ではありません。
佐賀県の東端にある基山町。そして隣接する鳥栖市の東部。
江戸時代は、対馬藩の領地でした。
長崎県の対馬が本拠地。対馬府中藩、厳原藩とも呼ばれたようです。
――写真は長崎街道(佐賀市内)です。この道を東に進めば、鳥栖・基山へと続きます。
今のところ“本編”で一番アクセスのあった記事は、殿・鍋島直正のお国入りの場面。
鳥栖市(東部)の田代(たじろ)宿までは、対馬藩領。
殿・直正は、ここまでは駕籠に乗って移動したことでしょう。
国境を越え、鳥栖市(西部)の轟木(とどろき)宿からは、颯爽と馬に跨ります。
そして、佐賀藩の領民たちから万雷の歓声で迎えられる…というお話でした。
また“団にょん”こと島義勇は、まず長崎街道を東上し、蝦夷地への探検に向かっています。
佐賀藩の東端から旅立つときには、何を想ったのでしょうか。
――そんな佐賀藩との“国境の街”だった、この地域の名称は“対馬藩・田代領”。
田代領は、離島を本拠地とする対馬藩にとって“台所”。いわば経済の中心としての役回りがあったようです。
対馬藩の田代領は、“白蝋(ろう)”などの品質管理が徹底していた佐賀藩に比べれば統制が緩やか。
“薬種”になる商品作物の売買も、融通がきいたようです。
――長崎街道の田代宿は賑わいのある宿場町。
鳥栖と言えば、交通・物流の重要ポイントであることは変わらないようです。
現在でも鳥栖近辺は製薬業が強い地域ですが、“田代の薬”は日本4大売薬の一角を占めたとか。
…ちなみに他の3大売薬は、富山、大和(奈良)、近江(滋賀)のようですね。この3強に並ぶとは、田代の売薬…かなりの実力者です。
――そして、対馬藩田代領も、幕末の動乱に巻き込まれていきます。
江戸時代も「対馬口」として、朝鮮半島との交流拠点だった対馬藩。
しかし、日本海上の要衝にある、この対馬を諸外国が放っておくわけがありません。
次々に現れる、西洋列強の影。
対馬藩も、佐賀藩に大砲を発注するなど、防備を固めていきます。
――1860年代。“本編”では第14話ぐらいで描けるかどうか…
対馬藩は、イギリスとロシアの争いに巻き込まれていきます。
ロシア船が、対馬に上陸する非常事態。
佐賀海軍も新鋭艦を出動させ、伊万里沖で待機。
幕府はロシアと敵対するイギリスを通じて圧力をかけます。
――もちろん対馬が脅かされれば、田代領の侍たちも黙っていません。
「攘夷じゃ!」
「夷狄(いてき)ば、追い払わんばならん!」
田代領の侍たちは、対馬に馳せ参じ、ロシア船との戦闘に備えます。ロシア船が退去した後は、攘夷の急先鋒、長州藩(山口)に接近していきます。
そして、対長同盟(対馬と長州の同盟)の締結に至ります!
…いかがでしょうか。基山町・鳥栖市(東部)の激動の幕末。
私も調べるまで、全然知りませんでした。九州北部には語られなかった“幕末”が数多くありそうです。
古代の山城・基肄(きい)城が、基山町の名所と聞きます。福岡の大野城とともに、大宰府の守りを固める役割があったそうです。
元寇でも最前線に立った、対馬藩の領地だったこともあり、より国を守る気概が強かったのかもしれません…
2018年の「さが幕末維新博覧会」。基山町による「基山の日」というイベントがあったようですが、どちらかと言えば、基山町そのもののPRの色合いが強かったようです。
壮絶な運命を辿った対馬藩田代領の侍たち。少しでも話題になれば良いなと思います。
2020年06月29日
「幕末佐賀と4つの“口”」
こんばんは。
今回のタイトルですが、怪奇小説でもSFファンタジー映画でもありません。
…但し、佐賀県の歴史に詳しい人ならば、たぶん先の展開を推理することができます。
――江戸時代、日本が取った対外政策は“鎖国”と呼ばれます。
そのまま読めば、国を閉ざし、外国との交流を断つということです。
しかし、長崎では、オランダや清国との交易が盛んに行われていました。“鎖国”の例外である“長崎口”です。

※現在の長崎(眼鏡橋)付近
――ここで、気づいた方もいるかもしれません。
4つの“口”?…残る“口”は、あと3つ。
当時の日本には、他にも国際交流の窓口があった…というお話です。
――では、一気にご紹介します。
「長崎口」…幕府直轄。西洋(オランダ)との交易が許された唯一の港。
「対馬口」…対馬藩(厳原藩)を介して成立する。朝鮮半島との交流ルート。
「薩摩口」…薩摩藩が独占する。琉球王国を通じて、清国や世界とも繋がる。
「松前口」…松前藩が仕切る、樺太やロシアにも居住域を持つアイヌへの窓口。
――以上、不正確を恐れず、ざっくりとした説明を試みました。
これから何回か「県内各地域の皆様へのつぶやき」を投稿していく予定です。
今回は、あえて幕末“佐賀”というタイトルにしています。
「もう、お見通しばい!こん地域と…あん地域ば、投稿すっとね!」という方もいるかもしれません。
 ※現在の佐賀県庁付近。
※現在の佐賀県庁付近。
試行錯誤の投稿ですが、該当地域の皆様、温かくお読みいただければ幸いです。
今回のタイトルですが、怪奇小説でもSFファンタジー映画でもありません。
…但し、佐賀県の歴史に詳しい人ならば、たぶん先の展開を推理することができます。
――江戸時代、日本が取った対外政策は“鎖国”と呼ばれます。
そのまま読めば、国を閉ざし、外国との交流を断つということです。
しかし、長崎では、オランダや清国との交易が盛んに行われていました。“鎖国”の例外である“長崎口”です。
※現在の長崎(眼鏡橋)付近
――ここで、気づいた方もいるかもしれません。
4つの“口”?…残る“口”は、あと3つ。
当時の日本には、他にも国際交流の窓口があった…というお話です。
――では、一気にご紹介します。
「長崎口」…幕府直轄。西洋(オランダ)との交易が許された唯一の港。
「対馬口」…対馬藩(厳原藩)を介して成立する。朝鮮半島との交流ルート。
「薩摩口」…薩摩藩が独占する。琉球王国を通じて、清国や世界とも繋がる。
「松前口」…松前藩が仕切る、樺太やロシアにも居住域を持つアイヌへの窓口。
――以上、不正確を恐れず、ざっくりとした説明を試みました。
これから何回か「県内各地域の皆様へのつぶやき」を投稿していく予定です。
今回は、あえて幕末“佐賀”というタイトルにしています。
「もう、お見通しばい!こん地域と…あん地域ば、投稿すっとね!」という方もいるかもしれません。
試行錯誤の投稿ですが、該当地域の皆様、温かくお読みいただければ幸いです。
2020年06月27日
「発心の剣」
こんにちは。
お読みいただいている皆様、第11話「蝦夷探検」はいかがだったでしょうか。
今年も大雨への心配が尽きないシーズンですね。あらためて自然の大きさを感じるのは、こういう時なのかもしれません。
――さて、本日は息抜きに投稿しております「望郷の剣」シリーズです。
帰るに帰れない郷里・佐賀を想いながら、現代の大都市圏で生きる…ある佐賀藩士(?)の物語。
同シリーズのエピソード・ゼロ(前日譚)にあたる“出会い”を描いてみます。たぶん2~3年前の出来事です。
――「今日の仕事も終わった。いや、終わらせた…」夜の帰路を急ぐ。電車には乗り遅れ、途中からの最終バスも逃した。
日中の強い日差しが、余韻を残している。
アスファルトで固められたような街に、乾いた砂ぼこりが舞う。
大都市圏であれば、人の数は居る。物は集まる。むろん情報やお金の流れもある。
但し、そこで暮らす人生が、“豊か”であるかは、別の問題だ。

――早く帰って眠りたい。私は時間をかけて歩くのをあきらめ、タクシーを選ぶことが増えていた。
広い道である。何台かのタクシーが直進し、通り過ぎていった。
運転手と目の合った1台が、手前まで寄ってくれる。
「こんばんは。」
簡単な挨拶を交わすと、私は目的地を告げた。
「この道を左に曲がってください。」
とりあえず、少しは早く帰れそうだ。私はホッと一息をついた。
――しばしの沈黙のあと、運転手が口を開く。ドライバーによって個性が出る“タクシー車内の雑談”である。
しかし、今日はいつもと勝手が違う。
急に、ぶしつけな質問が飛んできたのだ。
「兄さん、どこの人ね。」
私の疲れた頭はこう考えた。
「タクシーの呼び止め方が…当地の作法と違ったのか?」と。
おそらくは“出身地”に関する問いだ。まず、こう答えよう。
「生まれは、九州です。」
すると想定以上のトーン(声量)で、さらに質問が来る。
「九州のどこね!?」
――ここで「佐賀県です」と答えればよいのだが、私には躊躇があった。
それまでの私の人生で、佐賀出身と伝えたときの経験によるが、
「え、何県だって?」→「佐賀県です!」
「どこにあるんだ?」→「九州にあります!」
…という展開が多い。あまり芳しくない傾向がある。
この運転手さんの質問だと、その展開に陥る心配はない。
「…出身は、佐賀です。」
「そうね!やっぱり、そうね!佐賀のどこね!?」
――タクシーの運転手さんは、佐賀の出身者だった。そして故郷を離れてから、かなりの歳月が流れていると想像できた。
私に“さがんもん”の気配を感じ取り、積極的な質問に至ったようだ。
彼は「望郷の念」を強く持つ者であったらしい。私が佐賀の出身と知るや、嬉々としている。
「特急“かもめ”号のシートは、よかたい!」
…それが、佐賀の自慢になるのかは定かではない。しかし、喜んで語っている気持ちは良く伝わった。
――日中と違い、夜は空いた道である。目的地にはアッという間に辿り着いた。
私は、タクシーの運転手さんに料金を支払い、礼を述べる。
佐賀の話が、楽しかったと申し添えて。
…家まで少し歩く間に、色々なことを考えた。
私は、わずか二言を発しただけで“佐賀出身”と見抜かれている。
――当時の私に、“佐賀”を意識する機会は、ほとんど無かった。
だが、見る人が見れば、一瞬で“さがんもん”と判るという事実が突き付けられたのである。
これが、運転手さんの能力によるものなのか、よほど私が“佐賀”っぽい雰囲気を纏(まと)って生きているのか…これは、今のところ分からない。
ある年配のタクシードライバーの「望郷の想い」。おそらくは、私の現在の行動につながっているのである。
お読みいただいている皆様、第11話「蝦夷探検」はいかがだったでしょうか。
今年も大雨への心配が尽きないシーズンですね。あらためて自然の大きさを感じるのは、こういう時なのかもしれません。
――さて、本日は息抜きに投稿しております「望郷の剣」シリーズです。
帰るに帰れない郷里・佐賀を想いながら、現代の大都市圏で生きる…ある佐賀藩士(?)の物語。
同シリーズのエピソード・ゼロ(前日譚)にあたる“出会い”を描いてみます。たぶん2~3年前の出来事です。
――「今日の仕事も終わった。いや、終わらせた…」夜の帰路を急ぐ。電車には乗り遅れ、途中からの最終バスも逃した。
日中の強い日差しが、余韻を残している。
アスファルトで固められたような街に、乾いた砂ぼこりが舞う。
大都市圏であれば、人の数は居る。物は集まる。むろん情報やお金の流れもある。
但し、そこで暮らす人生が、“豊か”であるかは、別の問題だ。

――早く帰って眠りたい。私は時間をかけて歩くのをあきらめ、タクシーを選ぶことが増えていた。
広い道である。何台かのタクシーが直進し、通り過ぎていった。
運転手と目の合った1台が、手前まで寄ってくれる。
「こんばんは。」
簡単な挨拶を交わすと、私は目的地を告げた。
「この道を左に曲がってください。」
とりあえず、少しは早く帰れそうだ。私はホッと一息をついた。
――しばしの沈黙のあと、運転手が口を開く。ドライバーによって個性が出る“タクシー車内の雑談”である。
しかし、今日はいつもと勝手が違う。
急に、ぶしつけな質問が飛んできたのだ。
「兄さん、どこの人ね。」
私の疲れた頭はこう考えた。
「タクシーの呼び止め方が…当地の作法と違ったのか?」と。
おそらくは“出身地”に関する問いだ。まず、こう答えよう。
「生まれは、九州です。」
すると想定以上のトーン(声量)で、さらに質問が来る。
「九州のどこね!?」
――ここで「佐賀県です」と答えればよいのだが、私には躊躇があった。
それまでの私の人生で、佐賀出身と伝えたときの経験によるが、
「え、何県だって?」→「佐賀県です!」
「どこにあるんだ?」→「九州にあります!」
…という展開が多い。あまり芳しくない傾向がある。
この運転手さんの質問だと、その展開に陥る心配はない。
「…出身は、佐賀です。」
「そうね!やっぱり、そうね!佐賀のどこね!?」
――タクシーの運転手さんは、佐賀の出身者だった。そして故郷を離れてから、かなりの歳月が流れていると想像できた。
私に“さがんもん”の気配を感じ取り、積極的な質問に至ったようだ。
彼は「望郷の念」を強く持つ者であったらしい。私が佐賀の出身と知るや、嬉々としている。
「特急“かもめ”号のシートは、よかたい!」
…それが、佐賀の自慢になるのかは定かではない。しかし、喜んで語っている気持ちは良く伝わった。
――日中と違い、夜は空いた道である。目的地にはアッという間に辿り着いた。
私は、タクシーの運転手さんに料金を支払い、礼を述べる。
佐賀の話が、楽しかったと申し添えて。
…家まで少し歩く間に、色々なことを考えた。
私は、わずか二言を発しただけで“佐賀出身”と見抜かれている。
――当時の私に、“佐賀”を意識する機会は、ほとんど無かった。
だが、見る人が見れば、一瞬で“さがんもん”と判るという事実が突き付けられたのである。
これが、運転手さんの能力によるものなのか、よほど私が“佐賀”っぽい雰囲気を纏(まと)って生きているのか…これは、今のところ分からない。
ある年配のタクシードライバーの「望郷の想い」。おそらくは、私の現在の行動につながっているのである。
2020年06月25日
第11話「蝦夷探検」⑩(“開拓神”の降臨)
こんばんは。
のちに大都市・札幌の基礎を築く島義勇。
佐賀で調べを進めると“団にょん”さんと親しまれ、やや“面白い人”扱いに感じます。
しかし、北海道では同じ人が“判官さま”と敬愛されている様子。そのためか佐賀の島義勇像は等身大ですが、“北海道神宮”の銅像は4メートルと巨大…のようです。
今回で、その偉大さの片鱗が描ければ良いのですが…
――安政4年(1857年)旧暦5月。
松浦武四郎の手引きで、箱館奉行所の“蝦夷調査”に加わった島義勇(団右衛門)。
箱館(函館)から北に向かい、“石狩”地域に足を踏み入れる。
フゥー、フゥー♪
何やら楽し気な歌舞音曲が聞こえる。
寒い“蝦夷地”にも初夏の気配がする。
自然とともに生きる土地の民。“アイヌ”の者たちの祈りの舞いである。
「松浦どの!ワシも踊りたくなっておる♪」
島義勇は愉快な気分で、松浦武四郎に話しかける。
「アイヌの者たちは、自然の全てに感謝を捧げておる。俺は人間はそうあるべきだと思う。」
陽気な“団にょん”に対して、松浦は深いことを語る。
――松浦は幾度もの“蝦夷探検”を経て、アイヌの暮らしに敬意を持っている。
「我々は自然への畏敬の念を捨て、思い上がっているだけではないか…」
「ほうほう…」
丸い目をさらに丸くして、松浦の話に聞き入る“団にょん”。
「島どの。お主は、やはり変わった男だ。」
「何がじゃ。ワシは至って真面目じゃぞ!」
「真っ直ぐな奴め…」
松浦は愉快そうに笑う。

――さらに、石狩周辺の調査は進む。湖のほとり、美しい景色と出会う。
「おおっ、“ピリカ”であるな。」
松浦、清々しい水辺に感銘を受ける。
「ピリカ…!?ピリカとは、なんじゃ?」
島義勇、いろいろな話に反応する。
殿・鍋島直正の「目となり、足となって“蝦夷地”を知る!」がスローガンなのだ。
「ピリカとはな…美しい!とか素晴らしい!という、アイヌの言葉だ。」
「そうか、このような風情を“ピリカ”と呼ぶのだな!」
こうして“団にょん”は、ピリカという言葉を胸に刻み込む。
――箱館奉行所の一行は、小高い丘に差し掛かった。
ガイドとして同行していた、アイヌの村の者が緊迫した表情をする。
「向こうにヒグマがいる…、皆、近くに揃っているか!」
島と松浦が列にいない。
「いかん…、先を行く者は、おそらく気づいておらん。」
奉行所の役人が、先行していた2人に気づく。
――その頃、“団にょん”は丘のてっぺんに差し掛かっていた。
「おおっ、これは美しい!このような時には、あの言葉じゃ!」
陽の光の加減で、広い大地の色が移ろう。

「ピ-リカ~っ!」
思い切り“ピリカ”を叫んだ“団にょん”。
その刹那、丘の袂(たもと)でビクッと震えた、黒い影があった。ヒグマである。
――島義勇、壮大な心持ちで、右手に大鑓(やり)を携え、左手の掌を高く掲げている。むろんクマには気づいていない。
「ここで走って逃げるのは、命取りじゃ…」
うっかりとした動きはできない。遠目に“団にょん”の様子を見守る奉行所の一同。
アイヌの者は、短刀を構えている。
「クマが動けば…隙を見て、死角から突く!」
厳しい環境である“蝦夷地”での暮らし。
自然への畏敬は、自然との苦闘の中で育まれているのだ。
――そして、移ろう陽の光が、島義勇の背を照らし始めた。
クマにとっては逆光になる。
浮かびあがるシルエット(影)は、長く伸びる。
「…島どのが大きく見えませぬか!?」
奉行所の役人が、不思議なことを言う。
クマの反応も不自然だ。
島を見上げるや、ビクン!としたかと思うと、ゆっくりと背を向けた。
そして、帰るべき場所へと引き返していったのである。
「“団にょん”…何やら神々しいな…」
途中からクマの存在に気づき、事の一部始終を見守っていた、松浦がつぶやく。
「おぉ、松浦どの!何が、あったとね!?」
しかし、丘から戻ってきたのは、いつもの“団にょん”だった。

――島義勇は、石狩を調査中に病を得た。“千歳(ちとせ)”のベースキャンプ(拠点)にて一時療養する。
すでに佐賀を発ってから9か月が過ぎようとしていた。
極寒の東北を経て、蝦夷地に至り、探検を開始するスケジュールでは、さすがに体に負担も来る。
全身の痛みに、痒み…夜も熟睡できない。
――ふと、眼前に浮かぶ景色があった。
碁盤の目のような通りに、整然と石造りの建屋が並ぶ巨大な街である。
祭礼の日であろうか、集う人々の様子は佐賀と大差は感じられない。但し、西洋風の衣服を纏っている。皆、道なりに飾られた、大きな雪像を眺めて、楽し気である。
「何と豊かなことじゃ!」
「これこそ…五州(世界)第一の都ではないか!」
夢うつつに“団にょん”は大声を張り上げた。
――そこに今回の小調査を完了した、箱館奉行所の面々が戻ってくる。
「おおっ!島どの。加減は良いのか。」
奉行所の役人が、島を気遣って声をかけた。
「“団にょん”!こう言うのを、鬼の霍乱(おにのかくらん)とでも言うのかのぅ。」
松浦武四郎が、ちょっとした皮肉を言う。
「…まぁ、そがん言われたら、面目なかばい!」
島義勇、苦笑する。
「良き場所であったぞ、土地の者は“サッ・ポロ”とか呼んでおった。」
箱館奉行所の調査では、開拓に向いた土地であるらしい。
「サッ・ポロ…」
島は、夢うつつの中で見た街の姿を思い浮かべていた。
(第12話「海軍伝習」に続く)
のちに大都市・札幌の基礎を築く島義勇。
佐賀で調べを進めると“団にょん”さんと親しまれ、やや“面白い人”扱いに感じます。
しかし、北海道では同じ人が“判官さま”と敬愛されている様子。そのためか佐賀の島義勇像は等身大ですが、“北海道神宮”の銅像は4メートルと巨大…のようです。
今回で、その偉大さの片鱗が描ければ良いのですが…
――安政4年(1857年)旧暦5月。
松浦武四郎の手引きで、箱館奉行所の“蝦夷調査”に加わった島義勇(団右衛門)。
箱館(函館)から北に向かい、“石狩”地域に足を踏み入れる。
フゥー、フゥー♪
何やら楽し気な歌舞音曲が聞こえる。
寒い“蝦夷地”にも初夏の気配がする。
自然とともに生きる土地の民。“アイヌ”の者たちの祈りの舞いである。
「松浦どの!ワシも踊りたくなっておる♪」
島義勇は愉快な気分で、松浦武四郎に話しかける。
「アイヌの者たちは、自然の全てに感謝を捧げておる。俺は人間はそうあるべきだと思う。」
陽気な“団にょん”に対して、松浦は深いことを語る。
――松浦は幾度もの“蝦夷探検”を経て、アイヌの暮らしに敬意を持っている。
「我々は自然への畏敬の念を捨て、思い上がっているだけではないか…」
「ほうほう…」
丸い目をさらに丸くして、松浦の話に聞き入る“団にょん”。
「島どの。お主は、やはり変わった男だ。」
「何がじゃ。ワシは至って真面目じゃぞ!」
「真っ直ぐな奴め…」
松浦は愉快そうに笑う。
――さらに、石狩周辺の調査は進む。湖のほとり、美しい景色と出会う。
「おおっ、“ピリカ”であるな。」
松浦、清々しい水辺に感銘を受ける。
「ピリカ…!?ピリカとは、なんじゃ?」
島義勇、いろいろな話に反応する。
殿・鍋島直正の「目となり、足となって“蝦夷地”を知る!」がスローガンなのだ。
「ピリカとはな…美しい!とか素晴らしい!という、アイヌの言葉だ。」
「そうか、このような風情を“ピリカ”と呼ぶのだな!」
こうして“団にょん”は、ピリカという言葉を胸に刻み込む。
――箱館奉行所の一行は、小高い丘に差し掛かった。
ガイドとして同行していた、アイヌの村の者が緊迫した表情をする。
「向こうにヒグマがいる…、皆、近くに揃っているか!」
島と松浦が列にいない。
「いかん…、先を行く者は、おそらく気づいておらん。」
奉行所の役人が、先行していた2人に気づく。
――その頃、“団にょん”は丘のてっぺんに差し掛かっていた。
「おおっ、これは美しい!このような時には、あの言葉じゃ!」
陽の光の加減で、広い大地の色が移ろう。
「ピ-リカ~っ!」
思い切り“ピリカ”を叫んだ“団にょん”。
その刹那、丘の袂(たもと)でビクッと震えた、黒い影があった。ヒグマである。
――島義勇、壮大な心持ちで、右手に大鑓(やり)を携え、左手の掌を高く掲げている。むろんクマには気づいていない。
「ここで走って逃げるのは、命取りじゃ…」
うっかりとした動きはできない。遠目に“団にょん”の様子を見守る奉行所の一同。
アイヌの者は、短刀を構えている。
「クマが動けば…隙を見て、死角から突く!」
厳しい環境である“蝦夷地”での暮らし。
自然への畏敬は、自然との苦闘の中で育まれているのだ。
――そして、移ろう陽の光が、島義勇の背を照らし始めた。
クマにとっては逆光になる。
浮かびあがるシルエット(影)は、長く伸びる。
「…島どのが大きく見えませぬか!?」
奉行所の役人が、不思議なことを言う。
クマの反応も不自然だ。
島を見上げるや、ビクン!としたかと思うと、ゆっくりと背を向けた。
そして、帰るべき場所へと引き返していったのである。
「“団にょん”…何やら神々しいな…」
途中からクマの存在に気づき、事の一部始終を見守っていた、松浦がつぶやく。
「おぉ、松浦どの!何が、あったとね!?」
しかし、丘から戻ってきたのは、いつもの“団にょん”だった。

――島義勇は、石狩を調査中に病を得た。“千歳(ちとせ)”のベースキャンプ(拠点)にて一時療養する。
すでに佐賀を発ってから9か月が過ぎようとしていた。
極寒の東北を経て、蝦夷地に至り、探検を開始するスケジュールでは、さすがに体に負担も来る。
全身の痛みに、痒み…夜も熟睡できない。
――ふと、眼前に浮かぶ景色があった。
碁盤の目のような通りに、整然と石造りの建屋が並ぶ巨大な街である。
祭礼の日であろうか、集う人々の様子は佐賀と大差は感じられない。但し、西洋風の衣服を纏っている。皆、道なりに飾られた、大きな雪像を眺めて、楽し気である。
「何と豊かなことじゃ!」
「これこそ…五州(世界)第一の都ではないか!」
夢うつつに“団にょん”は大声を張り上げた。
――そこに今回の小調査を完了した、箱館奉行所の面々が戻ってくる。
「おおっ!島どの。加減は良いのか。」
奉行所の役人が、島を気遣って声をかけた。
「“団にょん”!こう言うのを、鬼の霍乱(おにのかくらん)とでも言うのかのぅ。」
松浦武四郎が、ちょっとした皮肉を言う。
「…まぁ、そがん言われたら、面目なかばい!」
島義勇、苦笑する。
「良き場所であったぞ、土地の者は“サッ・ポロ”とか呼んでおった。」
箱館奉行所の調査では、開拓に向いた土地であるらしい。
「サッ・ポロ…」
島は、夢うつつの中で見た街の姿を思い浮かべていた。
(第12話「海軍伝習」に続く)
2020年06月23日
第11話「蝦夷探検」⑨(“犬塚”の別れ)
こんばんは。
札幌を創った男・島義勇、そして同僚の犬塚与七郎。2人の佐賀藩士の“蝦夷地”への旅路を描いています。
どんどん雪国に入って行きますので、「とにかく寒い!」と思いながら、ご覧いただければ幸いです。

――安政4年(1857年)旧暦2月。極寒の東北。現在の盛岡辺り。
「うう”っ…寒かごだぁ~」
温暖の地に慣れている“さがんもん”2人。
東北の真冬の寒さは半端ではない。特に犬塚には応えている様子だ。
「もう駄目じゃ…」
「ほら、犬が温かごたぞ!しっかりせんね。」
島義勇(団にょん)が声を掛ける。
「だがら…“犬”じゃなか!犬塚ですばい…」
寒さに悶絶しながらも、いつもの反応を返す、犬塚。
――島が差し出したのは、毛並みのモフモフとした子犬である。
「そこの屋敷の者に借りてきた。」
犬種としては、秋田犬に近い類であろうか。うっかり近づくと、噛まれるのだが、そこは“団にょん”である。既に馴染んでいる様子だ。
ハッ、ハッ!
白い息を吐く犬。まるで“暖房器具”の扱いだ。クルクルとした目である。
「ありがたかです…」
冷え切った手を温める、犬塚。
尻尾を振る犬。将来は、立派な猟犬に育つのであろう。
――安政4年(1857年)旧暦3月。佐賀を出立しておよそ半年。ようやく箱館(函館)に到着する。
ここまで海岸線の防衛と、特産品の販路などをイメージしながら、各地域の調査を続けながら北上してきた。
「険しか道のりでしたね。」
「めったに目にできぬ諸国の様子が知れたのだ。有難いことじゃ。」
「たしかに、そがんですね。」
「ワシも、殿の目となり、足となったつもりじゃ。」
島義勇。初心を忘れていない。

――開港後は、異国船の“補給基地”としても賑わう箱館(函館)。この街で会うべき人物がいる。
「肥前佐賀、鍋島家中の者で、島団右衛門と申す!」
「同じく、犬塚与七郎にござる。」
2人が仰々しく、挨拶をしている相手が、“松浦武四郎”だ。
“蝦夷地”のエキスパートとして、幕府に雇われている。
「堅苦しいご挨拶は苦手でな。手短かにお願いしたい。」
当時の松浦は、“箱館奉行所”の関係者とお考えいただきたい。
――松浦は、十代の頃から旅から旅に生きている。自分の感性を大事にする“探検家”である。
「俺も若い時分には、長崎に居たこともある。佐賀の者は、真面目で賢いが…面白味は無いな。」
「なんだと!」
その言葉を聞くなり、“団にょん”が立ち上がる。真っ直ぐな分、カッと来やすいタイプである。
「待たんね、“団にょん”さん!わりと褒められとるばい!」
犬塚が言葉を掛ける。
「…ん!?」
一時停止する“団にょん”。
「真面目で賢い…そうじゃな!松浦どの、わかっておるではないか!」
くるりと表情が変わる。笑顔だ。
――「ハッハッハ…!」笑い始める、松浦武四郎。
「たしか、島どの…であったか。俺は前言を取り消す。」
まだ、笑いが止まらない松浦。
「ほう、なんじゃ!?」
「面白味のある…佐賀の者もいるようだ!」
「箱館奉行所には口を利いておく。“御調べ”に加わってみるか。」
松浦は、普通の侍ではない。ほどなく島義勇と犬塚与七郎は、奉行所の“蝦夷探索”に加わる許可を得た。

――しかし、箱館および蝦夷地の様子は、島義勇たちの想像を超えていた。
「“団にょん”さん。あの男…どうやら長州(山口)者のごたです。」
「犬塚。そう言えば、ワシは宇和島(愛媛)から来た者を見かけたぞ。」
この頃、外様の“雄藩”も、次々に家臣たちを“蝦夷地”に派遣していた。
情報を集めても、幕府への手続きで、先手を取られては圧倒的に不利である。
――箱館の滞在中に明らかになってくる、沿海の諸藩の動き。
「犬塚。これは二手に分かれた方が良いかもしれぬな…」
「“団にょん”さん。今日は冴えとりますね。どがんしたとですか。」
「“犬っ”!ワシはいつでも冴えとるばい!」
「犬じゃなかです…、犬塚たい…。“団にょん”さん、“蝦夷地”は厳しか所です。くれぐれもお気をつけて。」
――こうして、島と犬塚の2人は、別行動を取ることを決めたのである。
名残り惜しそうな、犬塚与七郎。“蝦夷地”で見聞した現況を、佐賀に持ち帰って準備を進める役回りを引き受けた。
ここまで辛い旅路を乗り越えてきた“相棒”。見送る島義勇も涙目だった。
「犬塚…お主も、帰りの道中、達者でな…」
そして島義勇は、松浦武四郎らとともに“蝦夷地”の探索に入るのである。
(続く)
札幌を創った男・島義勇、そして同僚の犬塚与七郎。2人の佐賀藩士の“蝦夷地”への旅路を描いています。
どんどん雪国に入って行きますので、「とにかく寒い!」と思いながら、ご覧いただければ幸いです。

――安政4年(1857年)旧暦2月。極寒の東北。現在の盛岡辺り。
「うう”っ…寒かごだぁ~」
温暖の地に慣れている“さがんもん”2人。
東北の真冬の寒さは半端ではない。特に犬塚には応えている様子だ。
「もう駄目じゃ…」
「ほら、犬が温かごたぞ!しっかりせんね。」
島義勇(団にょん)が声を掛ける。
「だがら…“犬”じゃなか!犬塚ですばい…」
寒さに悶絶しながらも、いつもの反応を返す、犬塚。
――島が差し出したのは、毛並みのモフモフとした子犬である。
「そこの屋敷の者に借りてきた。」
犬種としては、秋田犬に近い類であろうか。うっかり近づくと、噛まれるのだが、そこは“団にょん”である。既に馴染んでいる様子だ。
ハッ、ハッ!
白い息を吐く犬。まるで“暖房器具”の扱いだ。クルクルとした目である。
「ありがたかです…」
冷え切った手を温める、犬塚。
尻尾を振る犬。将来は、立派な猟犬に育つのであろう。
――安政4年(1857年)旧暦3月。佐賀を出立しておよそ半年。ようやく箱館(函館)に到着する。
ここまで海岸線の防衛と、特産品の販路などをイメージしながら、各地域の調査を続けながら北上してきた。
「険しか道のりでしたね。」
「めったに目にできぬ諸国の様子が知れたのだ。有難いことじゃ。」
「たしかに、そがんですね。」
「ワシも、殿の目となり、足となったつもりじゃ。」
島義勇。初心を忘れていない。

――開港後は、異国船の“補給基地”としても賑わう箱館(函館)。この街で会うべき人物がいる。
「肥前佐賀、鍋島家中の者で、島団右衛門と申す!」
「同じく、犬塚与七郎にござる。」
2人が仰々しく、挨拶をしている相手が、“松浦武四郎”だ。
“蝦夷地”のエキスパートとして、幕府に雇われている。
「堅苦しいご挨拶は苦手でな。手短かにお願いしたい。」
当時の松浦は、“箱館奉行所”の関係者とお考えいただきたい。
――松浦は、十代の頃から旅から旅に生きている。自分の感性を大事にする“探検家”である。
「俺も若い時分には、長崎に居たこともある。佐賀の者は、真面目で賢いが…面白味は無いな。」
「なんだと!」
その言葉を聞くなり、“団にょん”が立ち上がる。真っ直ぐな分、カッと来やすいタイプである。
「待たんね、“団にょん”さん!わりと褒められとるばい!」
犬塚が言葉を掛ける。
「…ん!?」
一時停止する“団にょん”。
「真面目で賢い…そうじゃな!松浦どの、わかっておるではないか!」
くるりと表情が変わる。笑顔だ。
――「ハッハッハ…!」笑い始める、松浦武四郎。
「たしか、島どの…であったか。俺は前言を取り消す。」
まだ、笑いが止まらない松浦。
「ほう、なんじゃ!?」
「面白味のある…佐賀の者もいるようだ!」
「箱館奉行所には口を利いておく。“御調べ”に加わってみるか。」
松浦は、普通の侍ではない。ほどなく島義勇と犬塚与七郎は、奉行所の“蝦夷探索”に加わる許可を得た。
――しかし、箱館および蝦夷地の様子は、島義勇たちの想像を超えていた。
「“団にょん”さん。あの男…どうやら長州(山口)者のごたです。」
「犬塚。そう言えば、ワシは宇和島(愛媛)から来た者を見かけたぞ。」
この頃、外様の“雄藩”も、次々に家臣たちを“蝦夷地”に派遣していた。
情報を集めても、幕府への手続きで、先手を取られては圧倒的に不利である。
――箱館の滞在中に明らかになってくる、沿海の諸藩の動き。
「犬塚。これは二手に分かれた方が良いかもしれぬな…」
「“団にょん”さん。今日は冴えとりますね。どがんしたとですか。」
「“犬っ”!ワシはいつでも冴えとるばい!」
「犬じゃなかです…、犬塚たい…。“団にょん”さん、“蝦夷地”は厳しか所です。くれぐれもお気をつけて。」
――こうして、島と犬塚の2人は、別行動を取ることを決めたのである。
名残り惜しそうな、犬塚与七郎。“蝦夷地”で見聞した現況を、佐賀に持ち帰って準備を進める役回りを引き受けた。
ここまで辛い旅路を乗り越えてきた“相棒”。見送る島義勇も涙目だった。
「犬塚…お主も、帰りの道中、達者でな…」
そして島義勇は、松浦武四郎らとともに“蝦夷地”の探索に入るのである。
(続く)
2020年06月21日
第11話「蝦夷探検」⑧(伊勢街道の“旅人”)
こんにちは。
昨年、NHKで放送された「永遠のニシパ」というドラマをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。
「北海道150周年記念」で製作された番組。“嵐”の松本潤さんが主役で、“北海道”の命名者“松浦武四郎”を演じました。
ここから数回、“団にょん(島義勇)”さんが街道を、雪原を、そして荒野を行く、ロードムービーのような展開になります。先ほどのドラマを見ていた方には、「おっ!?」と思う場面があるかもしれません…
――安政3年(1856年)旧暦9月。佐賀城下。
「“団にょん”さん、気ばつけていかんね!」
「体を厭(いと)いんしゃい!」
北へ向けて旅立つ、島義勇を佐賀の人々が見送る。
「見送り、ご苦労!いざ“蝦夷地”に行って参るぞ!」
島は高揚している。無理もない…かなりの大冒険になるのだ。
「では、行こうか!“犬っ”!」
「“犬”じゃなかばい!おいは、犬塚たい!」
「すまん、すまん…以後、気を付ける!」
島義勇とともに、同僚の犬塚与七郎も“蝦夷地”の探索に向かうのである。
――幕末、まだ陸路での旅が一般的な時代。島と犬塚の2人は佐賀から長崎街道を東へ。
秋の気配は少しずつ深まっていく。
双方とも健脚である。まずは3日間で下関に到着し、山陰道に入る。
…萩、津和野、米子、鳥取…
出立から1か月後、10月に入って城崎(兵庫)に到着した。
ひととき、城崎の温泉で疲れを癒す。
「“団にょん”さん!城崎の湯は、よかですね!」
「まぁ“武雄の湯”の次くらいかのう!」
…“団にょん”の地元びいきである。
佐賀には武雄温泉以外にも、“嬉野”や“古湯”など名湯も多いが、ここでは殿・鍋島直正のお気に入りを推しておこう。
この後、日本海沿いに小浜(福井)まで進み、南下。京都からは東海道に入る。
――出立から2か月後、11月に入る。桑名(三重)に差し掛かった2人。
「おおっ!犬じゃ!」
先を歩く、島義勇が声を出す。
「おいは、犬塚たい!…あっ、本当に犬の話でしたか…」
ここで犬塚与七郎にも、こちらに歩いてくる犬の姿が目に入った。参拝客たちと一緒に、東海道を西に向かってくる。
――三重といえば、“伊勢神宮”を思い浮かべる方も多いだろう。

江戸時代には“お伊勢参り”は「一生に一度は行きたいビックイベント」であった。しかし、日々の暮らしに追われる、大半の庶民にとっては叶わぬ夢…
――そして、江戸などに住む庶民は「お伊勢さんに行きたい!」想いを、地域の代表者や“犬”に託すこともあった!
ワンワン!
きつね色の毛並み、三角に立った両耳、クルンと巻いた尻尾。
典型的な“柴犬”である!
「お伊勢さんまで、あと少しじゃ!お前も頑張れよ!」
「お~よしよし、ワシの飯の残りじゃが、少し食べるか!」
伊勢に向かう人々のサポートを受けて、目的地を目指す犬。
クゥーン…!
こうして、お伊勢さんには、“犬”も参拝できた。
――彼らは“おかげ犬”と呼ばれ、親切にすると功徳(くどく)を積むことができると信じられ、大事にされた。
そして、犬たちも参拝客や沿道の人々に支えられて、伊勢を目指すのである。
「さすが、お伊勢さんが近いと賑やかなもんじゃのう!」
「そういえば、この辺りの生まれで、たいそう“蝦夷地”に詳しい者が居っとです!」
この頃“松浦武四郎”という人物が、“蝦夷地”に関する書籍を次々に発行していた。その松浦は、“伊勢商人”で有名な、松坂(三重)の出身である。
伊勢街道を往来する人々を、間近に眺めて育った、松浦武四郎。
自身も旅から旅への人生を選んでいったのである。
――島と犬塚の2人は、そのまま東海道を進む。途中、黒船来航の地・浦賀などを経て、江戸にある佐賀藩の屋敷に到着する。
9月に佐賀を発ち、12月に江戸入り。概ね3か月の旅路だった。
「“蝦夷地”に入った折は、まず箱館に留まれ。そして“松浦武四郎”と接触を試みよ!」
江戸では、さらに詳細な指示が与えられた。
沿海の各藩が、すでに“蝦夷地”の探索に乗り出している。
幕府の箱館奉行所、松前藩(蝦夷地の一部を統治)…そして、各藩。“蝦夷地”への目論見は様々である。
そして、現地で自由に動くためには、伝手(つて)が要る。佐賀藩は、既に“蝦夷地”を3度も探検し、当代随一の“蝦夷通”である松浦武四郎に着目していた。
――現地での接触は、おそらく“出たとこ勝負”になる。ある意味で、直線的な突破型の“団にょん”に向いた仕事である。
「陸奥(みちのく)の冬は厳しい。道中、気を付けて行かれよ。」
同じ佐賀藩でも、江戸屋敷の見送りは、やや“都会的”である。
「お見送り、忝(かたじけ)のうございます。」
そして島義勇、冬の東北に向かう。

まず水戸街道を北へ。かつて島が、水戸(茨城)に出向いたときにも通った道だ。
安政の江戸地震で、藤田東湖をはじめ政務の中心人物を失った水戸藩。不穏な空気が漂い始めていた。
「…やはり、人なのじゃな。大事なものは…」
島義勇は、東北へと続く空を見上げた。
ピ-ヒョロロ-
冬の寒空を、鳶(トンビ)が鳴き声を上げて、旋回していた。
(続く)
昨年、NHKで放送された「永遠のニシパ」というドラマをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。
「北海道150周年記念」で製作された番組。“嵐”の松本潤さんが主役で、“北海道”の命名者“松浦武四郎”を演じました。
ここから数回、“団にょん(島義勇)”さんが街道を、雪原を、そして荒野を行く、ロードムービーのような展開になります。先ほどのドラマを見ていた方には、「おっ!?」と思う場面があるかもしれません…
――安政3年(1856年)旧暦9月。佐賀城下。
「“団にょん”さん、気ばつけていかんね!」
「体を厭(いと)いんしゃい!」
北へ向けて旅立つ、島義勇を佐賀の人々が見送る。
「見送り、ご苦労!いざ“蝦夷地”に行って参るぞ!」
島は高揚している。無理もない…かなりの大冒険になるのだ。
「では、行こうか!“犬っ”!」
「“犬”じゃなかばい!おいは、犬塚たい!」
「すまん、すまん…以後、気を付ける!」
島義勇とともに、同僚の犬塚与七郎も“蝦夷地”の探索に向かうのである。
――幕末、まだ陸路での旅が一般的な時代。島と犬塚の2人は佐賀から長崎街道を東へ。
秋の気配は少しずつ深まっていく。
双方とも健脚である。まずは3日間で下関に到着し、山陰道に入る。
…萩、津和野、米子、鳥取…
出立から1か月後、10月に入って城崎(兵庫)に到着した。
ひととき、城崎の温泉で疲れを癒す。
「“団にょん”さん!城崎の湯は、よかですね!」
「まぁ“武雄の湯”の次くらいかのう!」
…“団にょん”の地元びいきである。
佐賀には武雄温泉以外にも、“嬉野”や“古湯”など名湯も多いが、ここでは殿・鍋島直正のお気に入りを推しておこう。
この後、日本海沿いに小浜(福井)まで進み、南下。京都からは東海道に入る。
――出立から2か月後、11月に入る。桑名(三重)に差し掛かった2人。
「おおっ!犬じゃ!」
先を歩く、島義勇が声を出す。
「おいは、犬塚たい!…あっ、本当に犬の話でしたか…」
ここで犬塚与七郎にも、こちらに歩いてくる犬の姿が目に入った。参拝客たちと一緒に、東海道を西に向かってくる。
――三重といえば、“伊勢神宮”を思い浮かべる方も多いだろう。
江戸時代には“お伊勢参り”は「一生に一度は行きたいビックイベント」であった。しかし、日々の暮らしに追われる、大半の庶民にとっては叶わぬ夢…
――そして、江戸などに住む庶民は「お伊勢さんに行きたい!」想いを、地域の代表者や“犬”に託すこともあった!
ワンワン!
きつね色の毛並み、三角に立った両耳、クルンと巻いた尻尾。
典型的な“柴犬”である!
「お伊勢さんまで、あと少しじゃ!お前も頑張れよ!」
「お~よしよし、ワシの飯の残りじゃが、少し食べるか!」
伊勢に向かう人々のサポートを受けて、目的地を目指す犬。
クゥーン…!
こうして、お伊勢さんには、“犬”も参拝できた。
――彼らは“おかげ犬”と呼ばれ、親切にすると功徳(くどく)を積むことができると信じられ、大事にされた。
そして、犬たちも参拝客や沿道の人々に支えられて、伊勢を目指すのである。
「さすが、お伊勢さんが近いと賑やかなもんじゃのう!」
「そういえば、この辺りの生まれで、たいそう“蝦夷地”に詳しい者が居っとです!」
この頃“松浦武四郎”という人物が、“蝦夷地”に関する書籍を次々に発行していた。その松浦は、“伊勢商人”で有名な、松坂(三重)の出身である。
伊勢街道を往来する人々を、間近に眺めて育った、松浦武四郎。
自身も旅から旅への人生を選んでいったのである。
――島と犬塚の2人は、そのまま東海道を進む。途中、黒船来航の地・浦賀などを経て、江戸にある佐賀藩の屋敷に到着する。
9月に佐賀を発ち、12月に江戸入り。概ね3か月の旅路だった。
「“蝦夷地”に入った折は、まず箱館に留まれ。そして“松浦武四郎”と接触を試みよ!」
江戸では、さらに詳細な指示が与えられた。
沿海の各藩が、すでに“蝦夷地”の探索に乗り出している。
幕府の箱館奉行所、松前藩(蝦夷地の一部を統治)…そして、各藩。“蝦夷地”への目論見は様々である。
そして、現地で自由に動くためには、伝手(つて)が要る。佐賀藩は、既に“蝦夷地”を3度も探検し、当代随一の“蝦夷通”である松浦武四郎に着目していた。
――現地での接触は、おそらく“出たとこ勝負”になる。ある意味で、直線的な突破型の“団にょん”に向いた仕事である。
「陸奥(みちのく)の冬は厳しい。道中、気を付けて行かれよ。」
同じ佐賀藩でも、江戸屋敷の見送りは、やや“都会的”である。
「お見送り、忝(かたじけ)のうございます。」
そして島義勇、冬の東北に向かう。

まず水戸街道を北へ。かつて島が、水戸(茨城)に出向いたときにも通った道だ。
安政の江戸地震で、藤田東湖をはじめ政務の中心人物を失った水戸藩。不穏な空気が漂い始めていた。
「…やはり、人なのじゃな。大事なものは…」
島義勇は、東北へと続く空を見上げた。
ピ-ヒョロロ-
冬の寒空を、鳶(トンビ)が鳴き声を上げて、旋回していた。
(続く)
2020年06月19日
第11話「蝦夷探検」⑦(“拓北”の決意)
こんばんは。
前回、藩校の大乱闘事件・“南北騒動”の中心にいた、大隈八太郎(重信)。藩校・“弘道館”を退学になった大隈は、学びの場を求めて、枝吉神陽を訪ねます。
災害が頻発した安政年間は、幕府が大きく揺らいだ時期でもあります。長文ですので、落ち着いたときにお読みいただければと思います。
――1855年。佐賀城下。
枝吉家の門前に立つ、少年が声を張る。
「大隈八太郎です!神陽先生、こんにちは。」
いつもの大隈らしからぬ緊張ぶりである。
佐賀で枝吉神陽と言えば、志ある若者たちの“カリスマ”なのである。
「構わぬぞ!表より入るが良い。」
「はい、失礼します!」
――神陽の声は清々しく辺りに響いた。大隈八太郎も元気よく返す。
「八太郎か!大きくなったな。」
「はい!」
この辺りの感じは、幼児のときに母・三井子に連れられて、神陽先生に会ったときと変わらない。
しかし、大隈八太郎、今ではかなりの長身である。まさに“大きくなった”のだ。
神陽は、八太郎を一瞥(いちべつ)すると、軽く微笑んだ。
「“弘道館”では、随分と暴れたそうではないか!」
「はい…」
――年を経る毎に、神陽先生の“義祭同盟”は存在感が高まり、有望な若者が多く集う。
最近の大隈八太郎は、その末席に居るような状況である。
オーラがある神陽先生に、あまり馴れ馴れしくも話しかけられず、しばらく様子を見守る。
「…うむ。」
「神陽先生!いかがなさいましたか!」
読みかけであった手紙を見ながら、眉間にしわを寄せる神陽先生。
手紙の内容が気になって仕方がない八太郎が問う。
「八太郎よ。存じておるか。ここ1年ばかり天変地異が続いておる。」
――当時、日米和親条約の締結の年(1854年)から災害が続いた。代表的なものは、安政の東海地震および南海地震である。
新暦で言えば12月下旬。初冬に立て続けに起きた、2つの巨大地震。あまりに災害が続くので、元号を“嘉永”から“安政”に改めたのである。
このような経過で、歴史上は1854年は年始から“安政元年”だったという扱いになっている。
「公儀(幕府)の費え(支出)は莫大になるだろう。いかに建て直すか…であろうな」
神陽は、幕府の安定を揺るがす、財政負担に考えを巡らせる。
大隈八太郎は「やはり神陽先生は、“弘道館”の教師たちとは違う!今を見ておられる!」と目を輝かせた。
ここで、いつもなら“鐘の鳴る”ような声量で言葉を発する神陽が、いつになく訥々(とつとつ)とつぶやく。
「何やら、良からぬ胸騒ぎがいたすな…」
――不幸なことに、この年(1855年)も“天変地異”は続いた。そして、大都市・江戸を大きな揺れが襲ったのである。

前年の初冬に起きた2つの巨大地震から1年も経たない、晩秋。
江戸の小石川にある水戸藩の屋敷。
島義勇(団右衛門)の先生でもある、藤田東湖は“安政の江戸地震”の真っ只中にいた。
「浮足(うきあし)立つな!気を鎮めて、事にあたれ!!」
藤田東湖が、落ち着いた声で指示を出す。
「はっ!」
激しい揺れに驚いた水戸藩士たちも、藤田の言葉に正気を取り戻す。避難誘導は順調である。
――水戸の屋敷には、藤田東湖の母・梅子もいた。年老いてはいるが避難には問題ない。
しかし、藤田の母は、屋敷が延焼する危険に気付いた。
「いけない…火鉢をそのままにしておる!辺りに火が廻ってしまう!」
責任感の強い、藤田の母は慌てて屋敷に引き返そうとする。
ここで藤田東湖は、母の動きに気付いた。
「いかん!母上、お戻りなされ!」
――先ほどの揺れで、屋敷の建屋が崩れかかっている。
ガラガラッ…ズン!
屋敷の梁(はり)が、落下する。
ガシッ!
藤田東湖は、“神道無念流”の剣の達人である。
無駄のない足運びで、崩れゆく梁の下に潜り込み、肩で受け止めた。
「むっ…ぐぐ…っ」
「…母上…お逃げなされ!」
「“虎っ”…!」
藤田東湖の幼名は“虎之助”であったと言う。
年老いた母・梅子は、東湖の身を挺した動きにより、難を逃れたのである。
――佐賀城下。島義勇(団右衛門)のもとに、同僚の犬塚が駆け込んでくる。

「おおっ、どうした犬っ!何かあったのか!?」
「犬じゃなか!犬塚たい。」
「いや…そいどころじゃなか!“団にょん”さん!落ち着いて聞かんね。」
犬塚は、人には「落ち着け」と言いながら、明らかに慌てている。
「もしや!江戸に関わる話か…」
江戸で、発生した巨大地震について、凄まじい被害状況が伝わり始めていた。
「実は、お主の親しかった、水戸の藤田さまが…」
先ほどまで軽口をたたいていた“団にょん”の表情が変わる。
藤田東湖の逝去が伝わった。
島義勇。無言のまま、はらはらと涙を落した。
――後日、佐賀城の本丸。殿・鍋島直正から呼び出しを受け、島義勇が登城していた。
「水戸の藤田は、最後まで立派な士(さむらい)であったようだな。」
「はい、ご母堂を庇(かば)って、お亡くなりに…」
「藤田とお主の二人で整えた、貢姫の縁組み。既に川越(藩)との話に進んでおり、盤石である。」
「藤田には、一言、礼を申したかったな。」
「はっ!」
――殿のお褒めを受け、島は「藤田東湖との“仕事”が形になった」と感じる。少し救われた想いである。
ここから、殿・直正は呼び出しの用件を伝える。
「此度の地震で、江戸の屋敷も無傷ではない。しかし時勢は動いておる。立ち止まってもおれん。」
――ついに殿から直々に、島義勇へ“蝦夷地探索”の命が下ったのである。

この頃、箱館(函館)が開港した影響で、沿海の諸藩が一斉に“蝦夷地”を目指していた。
「どの者を“蝦夷地”に派するか、迷うておったが…お主に決めた。」
「はっ!ワシ…いや、拙者にお命じいただいたのは、何故でございますか。」
「目じゃな!」
「はっ…?目でございますか。」
「あとは、足であろうな。」
「ははっ、ありがたき幸せ!この一身にて、蝦夷地を見聞いたしまする!」
――藤田東湖は“尊王”の志を説いたが、その後ろ姿で島義勇に伝えたことは、むしろ“殿様の懐刀”としての生き様である。
殿・直正からの「余の目となり、足となって働いて来い!」という指示は、まさに島が望むものであった。
“蝦夷地”で待つものは、広大な土地、豊かな天然資源、特産品の新しい販路…
こうして、“情熱の開拓者”・島義勇の冒険が始まるのである。
(続く)
前回、藩校の大乱闘事件・“南北騒動”の中心にいた、大隈八太郎(重信)。藩校・“弘道館”を退学になった大隈は、学びの場を求めて、枝吉神陽を訪ねます。
災害が頻発した安政年間は、幕府が大きく揺らいだ時期でもあります。長文ですので、落ち着いたときにお読みいただければと思います。
――1855年。佐賀城下。
枝吉家の門前に立つ、少年が声を張る。
「大隈八太郎です!神陽先生、こんにちは。」
いつもの大隈らしからぬ緊張ぶりである。
佐賀で枝吉神陽と言えば、志ある若者たちの“カリスマ”なのである。
「構わぬぞ!表より入るが良い。」
「はい、失礼します!」
――神陽の声は清々しく辺りに響いた。大隈八太郎も元気よく返す。
「八太郎か!大きくなったな。」
「はい!」
この辺りの感じは、幼児のときに母・三井子に連れられて、神陽先生に会ったときと変わらない。
しかし、大隈八太郎、今ではかなりの長身である。まさに“大きくなった”のだ。
神陽は、八太郎を一瞥(いちべつ)すると、軽く微笑んだ。
「“弘道館”では、随分と暴れたそうではないか!」
「はい…」
――年を経る毎に、神陽先生の“義祭同盟”は存在感が高まり、有望な若者が多く集う。
最近の大隈八太郎は、その末席に居るような状況である。
オーラがある神陽先生に、あまり馴れ馴れしくも話しかけられず、しばらく様子を見守る。
「…うむ。」
「神陽先生!いかがなさいましたか!」
読みかけであった手紙を見ながら、眉間にしわを寄せる神陽先生。
手紙の内容が気になって仕方がない八太郎が問う。
「八太郎よ。存じておるか。ここ1年ばかり天変地異が続いておる。」
――当時、日米和親条約の締結の年(1854年)から災害が続いた。代表的なものは、安政の東海地震および南海地震である。
新暦で言えば12月下旬。初冬に立て続けに起きた、2つの巨大地震。あまりに災害が続くので、元号を“嘉永”から“安政”に改めたのである。
このような経過で、歴史上は1854年は年始から“安政元年”だったという扱いになっている。
「公儀(幕府)の費え(支出)は莫大になるだろう。いかに建て直すか…であろうな」
神陽は、幕府の安定を揺るがす、財政負担に考えを巡らせる。
大隈八太郎は「やはり神陽先生は、“弘道館”の教師たちとは違う!今を見ておられる!」と目を輝かせた。
ここで、いつもなら“鐘の鳴る”ような声量で言葉を発する神陽が、いつになく訥々(とつとつ)とつぶやく。
「何やら、良からぬ胸騒ぎがいたすな…」
――不幸なことに、この年(1855年)も“天変地異”は続いた。そして、大都市・江戸を大きな揺れが襲ったのである。

前年の初冬に起きた2つの巨大地震から1年も経たない、晩秋。
江戸の小石川にある水戸藩の屋敷。
島義勇(団右衛門)の先生でもある、藤田東湖は“安政の江戸地震”の真っ只中にいた。
「浮足(うきあし)立つな!気を鎮めて、事にあたれ!!」
藤田東湖が、落ち着いた声で指示を出す。
「はっ!」
激しい揺れに驚いた水戸藩士たちも、藤田の言葉に正気を取り戻す。避難誘導は順調である。
――水戸の屋敷には、藤田東湖の母・梅子もいた。年老いてはいるが避難には問題ない。
しかし、藤田の母は、屋敷が延焼する危険に気付いた。
「いけない…火鉢をそのままにしておる!辺りに火が廻ってしまう!」
責任感の強い、藤田の母は慌てて屋敷に引き返そうとする。
ここで藤田東湖は、母の動きに気付いた。
「いかん!母上、お戻りなされ!」
――先ほどの揺れで、屋敷の建屋が崩れかかっている。
ガラガラッ…ズン!
屋敷の梁(はり)が、落下する。
ガシッ!
藤田東湖は、“神道無念流”の剣の達人である。
無駄のない足運びで、崩れゆく梁の下に潜り込み、肩で受け止めた。
「むっ…ぐぐ…っ」
「…母上…お逃げなされ!」
「“虎っ”…!」
藤田東湖の幼名は“虎之助”であったと言う。
年老いた母・梅子は、東湖の身を挺した動きにより、難を逃れたのである。
――佐賀城下。島義勇(団右衛門)のもとに、同僚の犬塚が駆け込んでくる。

「おおっ、どうした犬っ!何かあったのか!?」
「犬じゃなか!犬塚たい。」
「いや…そいどころじゃなか!“団にょん”さん!落ち着いて聞かんね。」
犬塚は、人には「落ち着け」と言いながら、明らかに慌てている。
「もしや!江戸に関わる話か…」
江戸で、発生した巨大地震について、凄まじい被害状況が伝わり始めていた。
「実は、お主の親しかった、水戸の藤田さまが…」
先ほどまで軽口をたたいていた“団にょん”の表情が変わる。
藤田東湖の逝去が伝わった。
島義勇。無言のまま、はらはらと涙を落した。
――後日、佐賀城の本丸。殿・鍋島直正から呼び出しを受け、島義勇が登城していた。
「水戸の藤田は、最後まで立派な士(さむらい)であったようだな。」
「はい、ご母堂を庇(かば)って、お亡くなりに…」
「藤田とお主の二人で整えた、貢姫の縁組み。既に川越(藩)との話に進んでおり、盤石である。」
「藤田には、一言、礼を申したかったな。」
「はっ!」
――殿のお褒めを受け、島は「藤田東湖との“仕事”が形になった」と感じる。少し救われた想いである。
ここから、殿・直正は呼び出しの用件を伝える。
「此度の地震で、江戸の屋敷も無傷ではない。しかし時勢は動いておる。立ち止まってもおれん。」
――ついに殿から直々に、島義勇へ“蝦夷地探索”の命が下ったのである。
この頃、箱館(函館)が開港した影響で、沿海の諸藩が一斉に“蝦夷地”を目指していた。
「どの者を“蝦夷地”に派するか、迷うておったが…お主に決めた。」
「はっ!ワシ…いや、拙者にお命じいただいたのは、何故でございますか。」
「目じゃな!」
「はっ…?目でございますか。」
「あとは、足であろうな。」
「ははっ、ありがたき幸せ!この一身にて、蝦夷地を見聞いたしまする!」
――藤田東湖は“尊王”の志を説いたが、その後ろ姿で島義勇に伝えたことは、むしろ“殿様の懐刀”としての生き様である。
殿・直正からの「余の目となり、足となって働いて来い!」という指示は、まさに島が望むものであった。
“蝦夷地”で待つものは、広大な土地、豊かな天然資源、特産品の新しい販路…
こうして、“情熱の開拓者”・島義勇の冒険が始まるのである。
(続く)
2020年06月17日
第11話「蝦夷探検」⑥(南北騒動始末)
こんばんは。前回の続きです。
藩校「弘道館」の“内生寮”で学生たちの人気者、大隈八太郎(重信)に関わって騒動が発生します。
――“南寮”側で先頭に立つ学生が、よく通る大声を張り上げる。
“北寮”に乗り込んできた理由の宣言をしているのだ。まるで“討ち入り”である。
「大隈八太郎は、南寮の学生である。引き渡してもらおうか!」
「何ね!?大隈は物じゃなか!人たい!」
「そうじゃ!居たかところに、おるんが道理ばい!」
北寮の学生たちが、寮の建屋の階上から“やいやい”と反論する。
――先ほどまで、談話の中心にいた大隈。いまや南北の寮で“争奪戦”の対象となっている。
「にゃあ…居心地の悪かごた!」
さすがの大隈八太郎も、このシチュエーション(状況)は勘弁してほしい。
「さて、どがんすっかね…」
思案する大隈。おそらく答えは“良からぬ方法”になりそうな気配だ。
――そして、南寮側は“前線”に、続々と屈強な学生を投入し始めた。
いわば北寮の学生は“籠城”する側である。
階上から、玄関前に集まる南寮側の動きを見張る。
おそらくは、幾つかある階段が、“防衛ライン”となるのであろう。
「申し上げます!南寮の連中は、さらに数を増やしています!」
いつの間にか、“北寮”の学生の間に、“指揮命令”系統が出来上がっている。

――ここで、大隈の脳裏に浮かんだのは、幼い頃、母・三井子が朗読してくれた『太平記』である。
南北朝時代の軍記物『太平記』。
幼き日の大隈八太郎は“南朝”の忠臣・楠木正成に憧れた。
「いかん!儂は“南寮方”につかんばならんぞ!」
ここで北寮側から見れば、急に寝返った大隈八太郎。
しかし、もともとの所属は“南寮”なのだから、表返ったと言うべきか。
――ほどなく大隈の思惑とは関係なく、戦いの火ぶたは切られた。
「おおーっ!」
「大隈を奪い返せ!」
北寮の玄関から、勢いよく階段を駆け上がる“南寮生”たち。
ダンダンダン…迫る足音。狭い階段が軋(きし)む。
「落ち着け!“地の利”は我ら“北寮”にあるぞ!」
“北寮生”は、階上から応戦を開始する。
「これで、どがんね!」
ドシン!ガツン!
火鉢やら、行灯(あんどん)やら、階段上から、色々の物が投げ落とされる。

「痛てて…」
「怯(ひる)むな!一歩も引くな!」
攻める南寮側の上級生が、檄(げき)を飛ばす。
――階段を舞台にした乱戦中、大隈八太郎が、顔見知りの“南寮”の先輩に声を掛ける。
「先輩!階段は向こうにもございます!」
大隈、結局は“南寮”側で乱闘に加わっている。
「大隈っ!助かるぞ!」
“南寮”の先輩は、軽く手を上げて応える。
慌てたのは“北寮”の学生たちである。
「いかん!大隈が寝返った。」
「いや…待て。もともと大隈は南寮の者だぞ。我らが油断しておったのかもな!」
南北、双方の寮とも、いつもは抑制の効いた生活をしている寮生たち。“水を得た魚”のように“合戦ごっこ”に興じる。
――大隈の離反により、北寮側の連携には、綻(ほころ)びが見える。
「よし、ここで一気に“北寮”を攻め落とすぞ!」
「おおーっ!」
大隈の“帰還”も得て、勢いに乗る“南寮生”たち。
敵も味方も皆、何やらキラキラとしている様子も感じられる。
窮屈な日常からの解放…なのであろう。
「よかごたぁ!!」
…そして、おそらく一番楽しんでいるのは、大隈八太郎である。
――しかし、ここで乱闘する学生たちを脅かす“影”も集結していた。壮大な声が響く。
「こん馬鹿者どもがっ!!」
武術の教授を中心とした、藩校教師たちが騒動の鎮圧に乗り出したのである。
「この騒ぎの…首謀者は誰だ!」
こうして“弘道館”の南北寮生による、青春のエネルギーをぶつけ合った“お祭り”。平たく言うと、乱闘騒ぎは終幕となった。
そして、祭りの中心、言わば“神輿(みこし)”のような存在であったのは、大隈八太郎。ごく自然な流れで、藩校を退学処分となってしまったのである。

――数日後、母・大隈三井子は、たまたま道で行き会った人物に、この騒動の一部始終を語った。
「ハッハッハッ…」
1人の落ち着いた感じの青年が、柄にもなく爆笑している。いつもは冷静な枝吉次郎(副島種臣)である。
「笑い事ではございませぬ。退学なのですよ!」
大隈三井子である。“ちゃんと聞いてくださいな!”という表情をする。
「…失礼。相変わらず、八太郎くんは面白い子ですね。」
次郎は何やら久しぶりに愉快だったようで、“笑いを止める方法がわからない”といった様子だ。
――枝吉次郎(副島種臣)は、大隈八太郎と9つばかり歳が離れている。
かつては大隈家にも遊びに来ていた次郎だが、いまや学識の高い立派な青年。
思わず愚痴をこぼす三井子。
「そうだ、兄上のもとを訪ねてみてはいかがでしょうか。」
「神陽先生を!?」
「ええ、きっと兄も面白がると思いますよ。それに八太郎くんにも学びの場があった方がいい。」
「そういえば!次郎さまも“副島”の家を継がれるのですね。」
「はい…立派な跡取りになるべく精進いたします…」
「次郎さま…まだ、可笑しいのですか。“笑い”が抜けておりませぬよ…」
八太郎の騒動の顛末(てんまつ)を聞いて、もはや数年分は笑ったと思われる、枝吉次郎(副島種臣)。
いつもクールな次郎があまり笑うので、膨れっ面をする三井子だった。
(続く)
藩校「弘道館」の“内生寮”で学生たちの人気者、大隈八太郎(重信)に関わって騒動が発生します。
――“南寮”側で先頭に立つ学生が、よく通る大声を張り上げる。
“北寮”に乗り込んできた理由の宣言をしているのだ。まるで“討ち入り”である。
「大隈八太郎は、南寮の学生である。引き渡してもらおうか!」
「何ね!?大隈は物じゃなか!人たい!」
「そうじゃ!居たかところに、おるんが道理ばい!」
北寮の学生たちが、寮の建屋の階上から“やいやい”と反論する。
――先ほどまで、談話の中心にいた大隈。いまや南北の寮で“争奪戦”の対象となっている。
「にゃあ…居心地の悪かごた!」
さすがの大隈八太郎も、このシチュエーション(状況)は勘弁してほしい。
「さて、どがんすっかね…」
思案する大隈。おそらく答えは“良からぬ方法”になりそうな気配だ。
――そして、南寮側は“前線”に、続々と屈強な学生を投入し始めた。
いわば北寮の学生は“籠城”する側である。
階上から、玄関前に集まる南寮側の動きを見張る。
おそらくは、幾つかある階段が、“防衛ライン”となるのであろう。
「申し上げます!南寮の連中は、さらに数を増やしています!」
いつの間にか、“北寮”の学生の間に、“指揮命令”系統が出来上がっている。
――ここで、大隈の脳裏に浮かんだのは、幼い頃、母・三井子が朗読してくれた『太平記』である。
南北朝時代の軍記物『太平記』。
幼き日の大隈八太郎は“南朝”の忠臣・楠木正成に憧れた。
「いかん!儂は“南寮方”につかんばならんぞ!」
ここで北寮側から見れば、急に寝返った大隈八太郎。
しかし、もともとの所属は“南寮”なのだから、表返ったと言うべきか。
――ほどなく大隈の思惑とは関係なく、戦いの火ぶたは切られた。
「おおーっ!」
「大隈を奪い返せ!」
北寮の玄関から、勢いよく階段を駆け上がる“南寮生”たち。
ダンダンダン…迫る足音。狭い階段が軋(きし)む。
「落ち着け!“地の利”は我ら“北寮”にあるぞ!」
“北寮生”は、階上から応戦を開始する。
「これで、どがんね!」
ドシン!ガツン!
火鉢やら、行灯(あんどん)やら、階段上から、色々の物が投げ落とされる。
「痛てて…」
「怯(ひる)むな!一歩も引くな!」
攻める南寮側の上級生が、檄(げき)を飛ばす。
――階段を舞台にした乱戦中、大隈八太郎が、顔見知りの“南寮”の先輩に声を掛ける。
「先輩!階段は向こうにもございます!」
大隈、結局は“南寮”側で乱闘に加わっている。
「大隈っ!助かるぞ!」
“南寮”の先輩は、軽く手を上げて応える。
慌てたのは“北寮”の学生たちである。
「いかん!大隈が寝返った。」
「いや…待て。もともと大隈は南寮の者だぞ。我らが油断しておったのかもな!」
南北、双方の寮とも、いつもは抑制の効いた生活をしている寮生たち。“水を得た魚”のように“合戦ごっこ”に興じる。
――大隈の離反により、北寮側の連携には、綻(ほころ)びが見える。
「よし、ここで一気に“北寮”を攻め落とすぞ!」
「おおーっ!」
大隈の“帰還”も得て、勢いに乗る“南寮生”たち。
敵も味方も皆、何やらキラキラとしている様子も感じられる。
窮屈な日常からの解放…なのであろう。
「よかごたぁ!!」
…そして、おそらく一番楽しんでいるのは、大隈八太郎である。
――しかし、ここで乱闘する学生たちを脅かす“影”も集結していた。壮大な声が響く。
「こん馬鹿者どもがっ!!」
武術の教授を中心とした、藩校教師たちが騒動の鎮圧に乗り出したのである。
「この騒ぎの…首謀者は誰だ!」
こうして“弘道館”の南北寮生による、青春のエネルギーをぶつけ合った“お祭り”。平たく言うと、乱闘騒ぎは終幕となった。
そして、祭りの中心、言わば“神輿(みこし)”のような存在であったのは、大隈八太郎。ごく自然な流れで、藩校を退学処分となってしまったのである。

――数日後、母・大隈三井子は、たまたま道で行き会った人物に、この騒動の一部始終を語った。
「ハッハッハッ…」
1人の落ち着いた感じの青年が、柄にもなく爆笑している。いつもは冷静な枝吉次郎(副島種臣)である。
「笑い事ではございませぬ。退学なのですよ!」
大隈三井子である。“ちゃんと聞いてくださいな!”という表情をする。
「…失礼。相変わらず、八太郎くんは面白い子ですね。」
次郎は何やら久しぶりに愉快だったようで、“笑いを止める方法がわからない”といった様子だ。
――枝吉次郎(副島種臣)は、大隈八太郎と9つばかり歳が離れている。
かつては大隈家にも遊びに来ていた次郎だが、いまや学識の高い立派な青年。
思わず愚痴をこぼす三井子。
「そうだ、兄上のもとを訪ねてみてはいかがでしょうか。」
「神陽先生を!?」
「ええ、きっと兄も面白がると思いますよ。それに八太郎くんにも学びの場があった方がいい。」
「そういえば!次郎さまも“副島”の家を継がれるのですね。」
「はい…立派な跡取りになるべく精進いたします…」
「次郎さま…まだ、可笑しいのですか。“笑い”が抜けておりませぬよ…」
八太郎の騒動の顛末(てんまつ)を聞いて、もはや数年分は笑ったと思われる、枝吉次郎(副島種臣)。
いつもクールな次郎があまり笑うので、膨れっ面をする三井子だった。
(続く)
2020年06月15日
第11話「蝦夷探検」⑤(演説者の目覚め)
こんばんは。
藩校「弘道館」は、“内生寮”と呼ばれる全寮制の学校が主軸です。
この頃、藩校の生徒数は600人を超えていたとも言われ、大人数となった学生の寮も南北に分けています。
エネルギーに満ち溢れた男子校で、南北の二寮が並び立つ…
ライバル関係となることは必定と言えるでしょう。
――普段は“南寮”に寄宿している寮生が1人。何故か“北寮”で弁舌を奮っていた。
「その黒船たるや、蒸気仕掛けにて船足早く、進退も自在なり…」
いわば演説を続ける“南寮の学生”に、“北寮”の聴衆たちも夢中である。
「長崎の港を避け、メリケン(アメリカ)の提督ペルリは江戸のほど近く、浦賀沖に現れたんである!」
「ほうほう!」
――黒船来航の経過について、こと細かに語るのは、大隈八太郎(重信)。
上背高く、目元涼しく、弁舌は巧み…現代風に言えば、“ハイスペック”な高校生に成長した。ただ、いかんせん幕末なので、より志は高く、気性は暑苦しいところがある。
「大隈っ!そのような話をどこで仕入れた!」
聴衆から質問が飛ぶ。
「さて、志高くあれば、自然(じねん)、有用な話が集まるんである!」
少し気取っている大隈。

――母・大隈三井子の手料理に釣られてか、以前から大隈家には優秀な先輩たちがよく集まった。
例えば“いつもの3人組”を、覚えておいでであろうか。
年の順で大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人である。
「あら、いらっしゃい。」
これは母・三井子の思惑どおりである。藩校の中でも優秀な先輩がよく来るのも、計算どおりなのであろうか。
子・八太郎は、自宅で先輩の話を聞いているだけで、様々な知識を吸収し、成長してきた。
先ほど、1つ目の話の“仕入れ先”は、学校の教師から藩の上層部まで、顔の効く“事情通”・中野方蔵。
尊王の志厚く、“政治的”な小回りもできる要領の良い若者である。
――聴衆から「では大隈よ!そん異国どもを、どがんすっとね!?」と質問が上がる。
「やはり、攘夷か!」
他の聴衆からも声が上がり、続々と“北寮”の学生たちが、大隈の話を聞くために集まる。
「…いや、すぐさま“打払い”に走るのは、短慮である!」
大隈は少し間を溜めて言い放った。
「それでは、腰抜けではないか!」
聴衆から、反論の声が上がる。
「“蛮勇”は、いかんばい!残念なことであるが、いまの我が国に、“夷狄”(いてき)を無傷で払う力は無い!」
――いま異国と戦うのは危うい、大隈は“攘夷”の危険性を指摘した。「おおっ!」とまた、聴衆がどよめく。
「もし“打払い”に踏み出せば、戦に民は傷つき、国は疲弊してしまうであろう!」
「まず、異国との“商い”で力を蓄える。しかる後に、野蛮なる夷狄(いてき)があらば打払うんである!」
「なるほど…たしかに、そのとおりか…」
「大隈っ!いいぞ。」
「そして蝦夷地の箱館で、異国に港が開いた!これからは“拓北”(たくほく)である!」
――大隈は“拓北”という言葉を示した。これは、北海道を開拓し、今後の通商の展開に対応していくと言ったところであろう。

「すごかっ!大隈、もっと話ば、聞かせんね!」
「…いや、この話はここまでとしよう!」
この2つ目の話。“理論派”・江藤新平から聞いた内容が元になっている。ここで、大隈八太郎は、ひとまず話を切り上げた。
江藤は“図海策”という論文を構想中である。今のところ、大隈もここまでしか話を聞いていない。
――“北寮”の聴衆たちは、「大隈の話は面白かね!」と、ひとしきり盛り上がっている。
「そうじゃ!“葉隠”ばかりでは、つまらんばい!」
「こら、滅多なことを申すな。」
北寮の学生たちの間でも、議論が始まる。
一言で表せば“我慢の教え”である、佐賀武士の教典“葉隠”。
学生たちの中にも「窮屈な教育だ!」と感じる者も多いようだ。
――そして、大隈八太郎は、その最たる1人であった。藩校での教育内容に不満がある。
「然り(しかり)!いまの“弘道館”の在り方は好ましくない!」
「そして、佐賀では“科挙”よりも苛烈な試験が行われておる!」
大隈が新しい話題に参加する。古代より中国では、科挙(かきょ)と言われる役人登用試験があった。
――そして、佐賀藩には“文武課業法”という規則があった。
「藩が決めた課程で、所定の成績を修めなければ、お役目に就けない」のだ。
大隈は「面白味の無い人材を作ってしまう」と、この制度に疑問を持っていた。
3つ目の話は、聴衆との対話から始めたものだ。大隈が古代中国をはじめ教育制度に詳しいのは、“学識者”・大木喬任の影響だった。
――ここで、にわかに“北寮”の玄関口が騒々しくなる。
「大隈八太郎は、"南寮"のもん(者)じゃ!ええ加減に返さんね!」
南寮の学生たちが、大声を張り上げる。
なかなか帰って来ない、南寮の人気者・大隈八太郎を奪還しに来たのである。
(続く)
藩校「弘道館」は、“内生寮”と呼ばれる全寮制の学校が主軸です。
この頃、藩校の生徒数は600人を超えていたとも言われ、大人数となった学生の寮も南北に分けています。
エネルギーに満ち溢れた男子校で、南北の二寮が並び立つ…
ライバル関係となることは必定と言えるでしょう。
――普段は“南寮”に寄宿している寮生が1人。何故か“北寮”で弁舌を奮っていた。
「その黒船たるや、蒸気仕掛けにて船足早く、進退も自在なり…」
いわば演説を続ける“南寮の学生”に、“北寮”の聴衆たちも夢中である。
「長崎の港を避け、メリケン(アメリカ)の提督ペルリは江戸のほど近く、浦賀沖に現れたんである!」
「ほうほう!」
――黒船来航の経過について、こと細かに語るのは、大隈八太郎(重信)。
上背高く、目元涼しく、弁舌は巧み…現代風に言えば、“ハイスペック”な高校生に成長した。ただ、いかんせん幕末なので、より志は高く、気性は暑苦しいところがある。
「大隈っ!そのような話をどこで仕入れた!」
聴衆から質問が飛ぶ。
「さて、志高くあれば、自然(じねん)、有用な話が集まるんである!」
少し気取っている大隈。

――母・大隈三井子の手料理に釣られてか、以前から大隈家には優秀な先輩たちがよく集まった。
例えば“いつもの3人組”を、覚えておいでであろうか。
年の順で大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人である。
「あら、いらっしゃい。」
これは母・三井子の思惑どおりである。藩校の中でも優秀な先輩がよく来るのも、計算どおりなのであろうか。
子・八太郎は、自宅で先輩の話を聞いているだけで、様々な知識を吸収し、成長してきた。
先ほど、1つ目の話の“仕入れ先”は、学校の教師から藩の上層部まで、顔の効く“事情通”・中野方蔵。
尊王の志厚く、“政治的”な小回りもできる要領の良い若者である。
――聴衆から「では大隈よ!そん異国どもを、どがんすっとね!?」と質問が上がる。
「やはり、攘夷か!」
他の聴衆からも声が上がり、続々と“北寮”の学生たちが、大隈の話を聞くために集まる。
「…いや、すぐさま“打払い”に走るのは、短慮である!」
大隈は少し間を溜めて言い放った。
「それでは、腰抜けではないか!」
聴衆から、反論の声が上がる。
「“蛮勇”は、いかんばい!残念なことであるが、いまの我が国に、“夷狄”(いてき)を無傷で払う力は無い!」
――いま異国と戦うのは危うい、大隈は“攘夷”の危険性を指摘した。「おおっ!」とまた、聴衆がどよめく。
「もし“打払い”に踏み出せば、戦に民は傷つき、国は疲弊してしまうであろう!」
「まず、異国との“商い”で力を蓄える。しかる後に、野蛮なる夷狄(いてき)があらば打払うんである!」
「なるほど…たしかに、そのとおりか…」
「大隈っ!いいぞ。」
「そして蝦夷地の箱館で、異国に港が開いた!これからは“拓北”(たくほく)である!」
――大隈は“拓北”という言葉を示した。これは、北海道を開拓し、今後の通商の展開に対応していくと言ったところであろう。
「すごかっ!大隈、もっと話ば、聞かせんね!」
「…いや、この話はここまでとしよう!」
この2つ目の話。“理論派”・江藤新平から聞いた内容が元になっている。ここで、大隈八太郎は、ひとまず話を切り上げた。
江藤は“図海策”という論文を構想中である。今のところ、大隈もここまでしか話を聞いていない。
――“北寮”の聴衆たちは、「大隈の話は面白かね!」と、ひとしきり盛り上がっている。
「そうじゃ!“葉隠”ばかりでは、つまらんばい!」
「こら、滅多なことを申すな。」
北寮の学生たちの間でも、議論が始まる。
一言で表せば“我慢の教え”である、佐賀武士の教典“葉隠”。
学生たちの中にも「窮屈な教育だ!」と感じる者も多いようだ。
――そして、大隈八太郎は、その最たる1人であった。藩校での教育内容に不満がある。
「然り(しかり)!いまの“弘道館”の在り方は好ましくない!」
「そして、佐賀では“科挙”よりも苛烈な試験が行われておる!」
大隈が新しい話題に参加する。古代より中国では、科挙(かきょ)と言われる役人登用試験があった。
――そして、佐賀藩には“文武課業法”という規則があった。
「藩が決めた課程で、所定の成績を修めなければ、お役目に就けない」のだ。
大隈は「面白味の無い人材を作ってしまう」と、この制度に疑問を持っていた。
3つ目の話は、聴衆との対話から始めたものだ。大隈が古代中国をはじめ教育制度に詳しいのは、“学識者”・大木喬任の影響だった。
――ここで、にわかに“北寮”の玄関口が騒々しくなる。
「大隈八太郎は、"南寮"のもん(者)じゃ!ええ加減に返さんね!」
南寮の学生たちが、大声を張り上げる。
なかなか帰って来ない、南寮の人気者・大隈八太郎を奪還しに来たのである。
(続く)
2020年06月13日
第11話「蝦夷探検」④(保守派の賢人)
こんばんは。
舞台は江戸から移り、佐賀城の本丸です。殿・鍋島直正の面前にて、佐賀藩の重役たちが詰めの協議中です。議題は「蒸気船の購入について」です。
――まず、口を開いたのは、藩政ナンバー2の請役・鍋島安房である。
「では、“蒸気船”を用立てる算段について話し合いたい。」
鍋島安房は、長崎へのロシア船来航の際、長崎御番の調整役で、走り回った人物に声をかける。
「池田半九郎、そなたの思うところを申してほしい。」
――安房より発言を促された、池田半九郎。もとは下級藩士だが、いまや殿・直正の側近である。
「はっ!僭越(せんえつ)ながら、申し上げます。」
以前は佐賀城下の区画整備に活躍し、“雨戸すら不要”とまで言われた治安の良い街づくりを実現した。
「長崎にて、露西亜(ロシア)の“蒸気船”を見分いたしました。」
池田は、ロシアのプチャーチン艦隊の“ボストーク号”のことを報告する。
「話に聞くペルリの黒船と違い、“外輪”で動く蒸気船ではございません。」
“ボストーク号”は、最新鋭のスクリュー推進式蒸気船だった。ロシアは、今後の戦略を練るため、機動力の高い“ボストーク号”を日本近海の調査に投入していた。

――池田の報告に反応したのが、鍋島夏雲(市佑)。現在の佐賀県上峰町付近に領地を持つ。
「ペルリの黒船は巨大なり。プゥーチャーチンの蒸気船は小振りなれど、新しき仕掛けにて動く…」
「此度は“大砲”のように、船を一から仕立てておっては、間に合いませぬな…」
鍋島夏雲は、殿の傍に長く仕える。几帳面で冷静な側近のようだ。話の整理に努める。
佐賀藩には洋書を翻訳し、鉄製大砲を自力で作り上げた成功例がある。これが技術的に、佐賀が“トップランナー”である1つの要因だが、大きい労力を伴ったことも事実である。
――ここで、保守派で頭角を現している、原田小四郎が「よろしいか」と発言を求める。
「公儀(幕府)から“大船建造”のお許しも出ております。黒船を持つに障りはございません。」
「もはや“洋船”を如何なる算段で、手にするかを論じるべきでございます。」
保守派の原田ですら、幕府が諸大名への“大型船の所有禁止”を解いた今、蒸気船を買うことを、早急に進めることを提言する。
――議題への重臣たちの反応を見ていた、殿・直正が、話のまとめに入る。
「原田、お主には“算段”があるようじゃな。」
「はっ、交易に用いる“白蝋”でございます。」
「良き品であれば、それだけ値打ちが高まります。厳しく品定めを致すべきかと。」
当時、西洋船の購入には、代金を“白蝋”で支払うこともできたため、品質が高ければ有利になる。現代的に言えば、ブランド力を付けるため、検品の労力を惜しまないとの提案である。
もともと佐賀藩は、“陶磁器”の徹底した品質管理で有名である。しかし、陶磁器や白蝋などの“佐賀ブランド”を守るため、生産者たちも必死の努力をせねばならなかった。

――こうして、蒸気船購入の方向性は定まった。のちに、この原田小四郎が“改革派”にとっては高い壁となっていく。
「安房さま。少々、お話をよろしいでしょうか。」
「おおっ、原田よ。先ほどは見事な算段であったな。」
「お褒めに預かり、恐縮です。お話と申しますのは、枝吉神陽についてでございます。」
「神陽のことか…」
請役・鍋島安房は、神陽が主導する「楠公義祭同盟」の活動に理解がある。
原田小四郎が、このようなトーンで話を持ってくるときは、大体が“忠臣からのお小言”である。保守派には、枝吉神陽や弟子たちの意見に耳を傾ける、鍋島安房に苦言を呈する者もいた。
この頃、藩校の教師であった枝吉神陽は、「弘道館」から距離を置き、「義祭同盟」に注力していた。自身の信ずるところで、若者たちを導き始めていたのである。
(続く)
舞台は江戸から移り、佐賀城の本丸です。殿・鍋島直正の面前にて、佐賀藩の重役たちが詰めの協議中です。議題は「蒸気船の購入について」です。
――まず、口を開いたのは、藩政ナンバー2の請役・鍋島安房である。
「では、“蒸気船”を用立てる算段について話し合いたい。」
鍋島安房は、長崎へのロシア船来航の際、長崎御番の調整役で、走り回った人物に声をかける。
「池田半九郎、そなたの思うところを申してほしい。」
――安房より発言を促された、池田半九郎。もとは下級藩士だが、いまや殿・直正の側近である。
「はっ!僭越(せんえつ)ながら、申し上げます。」
以前は佐賀城下の区画整備に活躍し、“雨戸すら不要”とまで言われた治安の良い街づくりを実現した。
「長崎にて、露西亜(ロシア)の“蒸気船”を見分いたしました。」
池田は、ロシアのプチャーチン艦隊の“ボストーク号”のことを報告する。
「話に聞くペルリの黒船と違い、“外輪”で動く蒸気船ではございません。」
“ボストーク号”は、最新鋭のスクリュー推進式蒸気船だった。ロシアは、今後の戦略を練るため、機動力の高い“ボストーク号”を日本近海の調査に投入していた。
――池田の報告に反応したのが、鍋島夏雲(市佑)。現在の佐賀県上峰町付近に領地を持つ。
「ペルリの黒船は巨大なり。プゥーチャーチンの蒸気船は小振りなれど、新しき仕掛けにて動く…」
「此度は“大砲”のように、船を一から仕立てておっては、間に合いませぬな…」
鍋島夏雲は、殿の傍に長く仕える。几帳面で冷静な側近のようだ。話の整理に努める。
佐賀藩には洋書を翻訳し、鉄製大砲を自力で作り上げた成功例がある。これが技術的に、佐賀が“トップランナー”である1つの要因だが、大きい労力を伴ったことも事実である。
――ここで、保守派で頭角を現している、原田小四郎が「よろしいか」と発言を求める。
「公儀(幕府)から“大船建造”のお許しも出ております。黒船を持つに障りはございません。」
「もはや“洋船”を如何なる算段で、手にするかを論じるべきでございます。」
保守派の原田ですら、幕府が諸大名への“大型船の所有禁止”を解いた今、蒸気船を買うことを、早急に進めることを提言する。
――議題への重臣たちの反応を見ていた、殿・直正が、話のまとめに入る。
「原田、お主には“算段”があるようじゃな。」
「はっ、交易に用いる“白蝋”でございます。」
「良き品であれば、それだけ値打ちが高まります。厳しく品定めを致すべきかと。」
当時、西洋船の購入には、代金を“白蝋”で支払うこともできたため、品質が高ければ有利になる。現代的に言えば、ブランド力を付けるため、検品の労力を惜しまないとの提案である。
もともと佐賀藩は、“陶磁器”の徹底した品質管理で有名である。しかし、陶磁器や白蝋などの“佐賀ブランド”を守るため、生産者たちも必死の努力をせねばならなかった。

――こうして、蒸気船購入の方向性は定まった。のちに、この原田小四郎が“改革派”にとっては高い壁となっていく。
「安房さま。少々、お話をよろしいでしょうか。」
「おおっ、原田よ。先ほどは見事な算段であったな。」
「お褒めに預かり、恐縮です。お話と申しますのは、枝吉神陽についてでございます。」
「神陽のことか…」
請役・鍋島安房は、神陽が主導する「楠公義祭同盟」の活動に理解がある。
原田小四郎が、このようなトーンで話を持ってくるときは、大体が“忠臣からのお小言”である。保守派には、枝吉神陽や弟子たちの意見に耳を傾ける、鍋島安房に苦言を呈する者もいた。
この頃、藩校の教師であった枝吉神陽は、「弘道館」から距離を置き、「義祭同盟」に注力していた。自身の信ずるところで、若者たちを導き始めていたのである。
(続く)