2022年05月07日
「幕末!京都事件ファイル③〔後編〕」
こんばんは。
最初から意図したわけではないのですが『幕末!京都事件ファイル』の3部作は、前編・薩摩(鹿児島)、中編・土佐(高知)、後編・長州と関わる展開に。
…とはいえ今回は長州(山口)の尊王攘夷派に大打撃だった出来事の特集。江藤新平の脱藩から2年後、1864年(文久四年・元治元年)夏の事件です。
長州藩で出世し、強い影響力を持つものの、尊攘派の過激な動きとは、一線を画す慎重な態度を取っていたのが、桂小五郎(のちの木戸孝允)。
第18話のカギとなる人物・桂小五郎は、近々“本編”にも登場予定ですので、今回は“新選組”を軸とした話にしています。

――では、「幕末!京都事件ファイル③」。
「③池田屋事件」は新選組の“晴れ舞台”との位置づけが多く見られ、響きは「②寺田屋事件」と似ていますが、よく幕府寄りの視点で描かれる印象です。
発生時期は前回までの①と②の事件の間、1864年(元治元年)旧暦六月。新暦では夏の7月頃。現場は、東海道の終点・三条大橋に近い京の市街地。
この事件では、幕府側の会津藩(福島)配下となった“新選組”が尊王攘夷派を急襲し、その企てを阻止したというのが一般的な筋書き。
肥後熊本藩士・宮部鼎蔵や、長州藩士・吉田稔麿ら有力な志士が新選組との死闘を経て落命します。
この事件により、明治維新の到来時期が数年遅くなったとも、逆に早まったとも…そこは諸説あるようですが、衝撃の事件だったことは確かでしょう。
――2004年大河ドラマ『新選組!』では、
やや記憶頼みですが、以下のような話の流れだったと思います。
市中の取締りを続ける中、尊王攘夷派が京の街に火を放ち、混乱に乗じて帝を長州に連れ去るという、大規模な企てを察知した新選組。
京都では1か月ほど続くという夏の風物詩・祇園祭。お囃子が流れる宵の街。新選組は繁華街の地域を分担し、北上しながら探索にあたります。

捜索を二手に分かれて行う中、先に情報を掴んだのは、新選組局長・近藤勇〔演:香取慎吾〕が率いる一団。
――三条小橋の旅籠「池田屋」に尊攘派が集結。
その一報を受けて、急ぎ池田屋にたどりついたのは、局長の近藤以下わずか数名。少ない手勢ですが「御用改めである!」と乗り込みます。
階段を昇った2階には、抜刀した尊王攘夷の過激派志士が多数待ち構えて…という、新選組ファンが最も盛り上がりそうな場面。
暗闇での熾烈な戦い。急襲を受けた志士たちも猛然と反撃し、数に劣る中、精鋭ぞろいの新選組隊士も苦戦します。
そこで、副長・土方歳三〔演:山本耕史〕の率いる別動隊が「待たせたな。」の一声とともに合流する…と概ね、こんな描き方だったと思います。

――そして“本編”では、新選組は描けるか。
これも、なかなか難しい注文で「幕末佐賀藩の大河ドラマ」は、あまり新選組の出番を作れなさそうです。
例えば、江藤新平が脱藩して京の情勢を探った、文久二年(1862年)時点では新選組(壬生浪士組)は、まだ京都に存在していません。
一方で副島種臣・大隈重信らが脱藩した、幕末も大詰めの時期には、新選組は京で活動していました。
――しかし、幕府側の立場では、
西国の雄藩が次々と“倒幕”寄りとなる中で、佐賀藩(鍋島家)は何とか味方にしておきたかったはず。しかも佐賀藩士はあまり乱暴な手段を用いない傾向。
政治工作を仕掛けて藩に送還されることはありますが、あえて新選組が追いかけ回す必要があるかというと…。
そんな事情で、ほぼ佐賀藩は関わらない見通しですが、“新選組”を描く予定は一応あります。あまり期待せずにお待ちください。

――ここ3回は、GW特別企画をお送りしました。
『幕末!京都事件ファイル』の調査報告として「佐賀藩を語りたい立場」からのまとめに入ります。
佐賀では前藩主・鍋島直正(閑叟)の統率力が効いているのか、今回ご紹介した「幕末京都の“事件現場”」には、配下の佐賀藩士は姿を見せません。
私はこれを「のちに日本近代化の礎になるべき、藩士たちを守りたい」という、直正公から家臣への“親心にも似た愛”の結果なのだと考えております。
〔参照:第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)〕
――この“優等生”ぶりが、佐賀藩の特徴でもあるのですが、
ドラマ的には“見せ場”が作りにくく、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を見たい私にとっては、そのイメージをどう描くか、工夫を要するポイントになっています。
では、なぜ幕末期に京都の「事件現場」に姿を見せなかった肥前佐賀藩が、薩長土肥の一角となり得たか。
そこには、佐賀藩の科学技術と実務能力以外に、もう1つの要因があるように考え始めました。

――“倒幕”運動では影の薄い、佐賀藩。
結局、“鳥羽・伏見の戦い”にも参陣していません。「出遅れた」と評されるように、内戦を避けたかった佐賀藩の立ち位置は、最終局面まで不明確でした。
近代化の進んだ雄藩ながら、積極的に戦わない佐賀。しかし、その中途半端さゆえ、明治初頭に日本を救う役回りがあった…と仮説を立てています。
こうして『事件ファイル』の調査を経て、新たな展開も見えてきましたが、私の探索は長い道のりになりそうです。
最初から意図したわけではないのですが『幕末!京都事件ファイル』の3部作は、前編・薩摩(鹿児島)、中編・土佐(高知)、後編・長州と関わる展開に。
…とはいえ今回は長州(山口)の尊王攘夷派に大打撃だった出来事の特集。江藤新平の脱藩から2年後、1864年(文久四年・元治元年)夏の事件です。
長州藩で出世し、強い影響力を持つものの、尊攘派の過激な動きとは、一線を画す慎重な態度を取っていたのが、桂小五郎(のちの木戸孝允)。
第18話のカギとなる人物・桂小五郎は、近々“本編”にも登場予定ですので、今回は“新選組”を軸とした話にしています。

――では、「幕末!京都事件ファイル③」。
「③池田屋事件」は新選組の“晴れ舞台”との位置づけが多く見られ、響きは「②寺田屋事件」と似ていますが、よく幕府寄りの視点で描かれる印象です。
発生時期は前回までの①と②の事件の間、1864年(元治元年)旧暦六月。新暦では夏の7月頃。現場は、東海道の終点・三条大橋に近い京の市街地。
この事件では、幕府側の会津藩(福島)配下となった“新選組”が尊王攘夷派を急襲し、その企てを阻止したというのが一般的な筋書き。
肥後熊本藩士・宮部鼎蔵や、長州藩士・吉田稔麿ら有力な志士が新選組との死闘を経て落命します。
この事件により、明治維新の到来時期が数年遅くなったとも、逆に早まったとも…そこは諸説あるようですが、衝撃の事件だったことは確かでしょう。
――2004年大河ドラマ『新選組!』では、
やや記憶頼みですが、以下のような話の流れだったと思います。
市中の取締りを続ける中、尊王攘夷派が京の街に火を放ち、混乱に乗じて帝を長州に連れ去るという、大規模な企てを察知した新選組。
京都では1か月ほど続くという夏の風物詩・祇園祭。お囃子が流れる宵の街。新選組は繁華街の地域を分担し、北上しながら探索にあたります。

捜索を二手に分かれて行う中、先に情報を掴んだのは、新選組局長・近藤勇〔演:香取慎吾〕が率いる一団。
――三条小橋の旅籠「池田屋」に尊攘派が集結。
その一報を受けて、急ぎ池田屋にたどりついたのは、局長の近藤以下わずか数名。少ない手勢ですが「御用改めである!」と乗り込みます。
階段を昇った2階には、抜刀した尊王攘夷の過激派志士が多数待ち構えて…という、新選組ファンが最も盛り上がりそうな場面。
暗闇での熾烈な戦い。急襲を受けた志士たちも猛然と反撃し、数に劣る中、精鋭ぞろいの新選組隊士も苦戦します。
そこで、副長・土方歳三〔演:山本耕史〕の率いる別動隊が「待たせたな。」の一声とともに合流する…と概ね、こんな描き方だったと思います。

――そして“本編”では、新選組は描けるか。
これも、なかなか難しい注文で「幕末佐賀藩の大河ドラマ」は、あまり新選組の出番を作れなさそうです。
例えば、江藤新平が脱藩して京の情勢を探った、文久二年(1862年)時点では新選組(壬生浪士組)は、まだ京都に存在していません。
一方で副島種臣・大隈重信らが脱藩した、幕末も大詰めの時期には、新選組は京で活動していました。
――しかし、幕府側の立場では、
西国の雄藩が次々と“倒幕”寄りとなる中で、佐賀藩(鍋島家)は何とか味方にしておきたかったはず。しかも佐賀藩士はあまり乱暴な手段を用いない傾向。
政治工作を仕掛けて藩に送還されることはありますが、あえて新選組が追いかけ回す必要があるかというと…。
そんな事情で、ほぼ佐賀藩は関わらない見通しですが、“新選組”を描く予定は一応あります。あまり期待せずにお待ちください。

――ここ3回は、GW特別企画をお送りしました。
『幕末!京都事件ファイル』の調査報告として「佐賀藩を語りたい立場」からのまとめに入ります。
佐賀では前藩主・鍋島直正(閑叟)の統率力が効いているのか、今回ご紹介した「幕末京都の“事件現場”」には、配下の佐賀藩士は姿を見せません。
私はこれを「のちに日本近代化の礎になるべき、藩士たちを守りたい」という、直正公から家臣への“親心にも似た愛”の結果なのだと考えております。
〔参照:
――この“優等生”ぶりが、佐賀藩の特徴でもあるのですが、
ドラマ的には“見せ場”が作りにくく、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を見たい私にとっては、そのイメージをどう描くか、工夫を要するポイントになっています。
では、なぜ幕末期に京都の「事件現場」に姿を見せなかった肥前佐賀藩が、薩長土肥の一角となり得たか。
そこには、佐賀藩の科学技術と実務能力以外に、もう1つの要因があるように考え始めました。

――“倒幕”運動では影の薄い、佐賀藩。
結局、“鳥羽・伏見の戦い”にも参陣していません。「出遅れた」と評されるように、内戦を避けたかった佐賀藩の立ち位置は、最終局面まで不明確でした。
近代化の進んだ雄藩ながら、積極的に戦わない佐賀。しかし、その中途半端さゆえ、明治初頭に日本を救う役回りがあった…と仮説を立てています。
こうして『事件ファイル』の調査を経て、新たな展開も見えてきましたが、私の探索は長い道のりになりそうです。
2022年05月03日
「幕末!京都事件ファイル②〔中編〕」
こんばんは。
ゴールデンウィーク特別企画なので、現在の“本編”から数年後の話になるのですが、幕末の有名人の方々を取り巻く事件についても触れておきます。
『新選組!』や『龍馬伝』等は幕末の大河ドラマで特に人気の作品。しかし、明治期に存命でなかった人物は、佐賀藩士とは接点が少ない傾向です。
過去の大河ドラマで名作の主人公だった人物を「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で、どう描くかには、ひと工夫が要ると考えているところです。

――ここで、前編に続き「幕末!京都事件ファイル②」
京・伏見の船宿“寺田屋”で発生した著名な事件がもう1つ。「②寺田屋事件」についても触れたいと思います。
事件発生の現場は、前編で取り上げた「①寺田屋騒動」と同じ場所。時期は、慶応二年(1866年)一月。新暦でいえば春の三月頃のようです。
こちらの「②寺田屋事件」は幕府の伏見奉行所が、薩摩や長州に関わる土佐(高知)の脱藩浪士・坂本龍馬を急襲した事件と表す方が通りが良いでしょう。
この事件には「寺田屋遭難」という呼び名もあるようです。
事件現場として度々登場する、川の港町・伏見は重要な拠点。なお佐賀藩は朝廷に伏見の警備を突然申し出て、薩摩藩との間が不穏になったようです。
――そして、2010年大河ドラマ『龍馬伝』でも描かれた“事件”の場面。
寺田屋にいた女性・お龍〔演:真木よう子〕は、1階で入浴中に周囲が奉行所の捕方に囲まれていることに気付きました。
なりふり構わず階段を駆け上がったお龍は、坂本龍馬〔演:福山雅治〕に危機を知らせます。
多数の捕方に対して、龍馬は拳銃を発砲して応戦のすえに逃走。手傷を負い、生命の危機に瀕して、薩摩藩に救出される…あの事件です。
負傷した龍馬が物陰に身を潜めながら、夜空を見上げてつぶやいていた印象的な場面があったように思います。

――坂本龍馬が、土佐を脱藩した時期は、
この場面から四年ほど前。文久二年(1862年)で、龍馬は最終的に江戸に向かいました。この年に、江藤新平は佐賀を脱藩して京都で活動しています。
『龍馬伝』で視聴した時の記憶が曖昧ですが、以前留学していた江戸の剣術道場を拠点に人脈を広げ、幕臣・勝海舟に弟子入りした時期のようです。
ちなみに身内から脱藩を警戒された龍馬は一時、刀を取り上げられていたものの、姉が家で秘蔵していた“肥前忠広”を持ち出し、龍馬に渡したそうです。
――“肥前忠広”といえば、佐賀の刀工として著名です。
佐賀では県立博物館で展示会などもあり、近年では“擬人化”され、ゲーム等でも人気の刀剣と聞きますが、土佐(高知)でも秘蔵されていたのですね。
龍馬はのちに、その刀を師匠・勝海舟の警護も任せた、同郷の岡田以蔵に託していたとか…これも事件の予感がします。
そういえば、『龍馬伝』では佐藤健さんが演じた岡田以蔵が、とても健気で悲壮感がある、“予想外”の描き方だったので記憶に残っています。

――その名が出た、ついでのような形で恐縮ですが
“肥前忠広”の話を少し続けます。幕末期には、いかにも佐賀の刀工らしい、剣に留まらない働きもありました。
佐賀藩の鉄製大砲開発チーム“鋳立方の七人”の一員・橋本新左衛門は、幕末期に佐賀で活躍した刀鍛冶でした。
〔参照:第6話「鉄製大砲」⑤〕
“本編”で書いた時点ではよくわかっていませんでしたが、この方が“肥前忠広(忠吉)”の継承者だったようです。
その技術を、日本の近代化につながる方向にも発揮した佐賀の刀工。
郷里から太平洋を望んで、世界の海を想った、土佐藩士たちもその刀を所持していたと思うと、浪漫があるような気がします。
――もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現したら、
土佐(高知)が誇る、二度の大河ドラマ主人公・坂本龍馬はどう描かれるか。
なお、私が書いている“本編”での描き方も、まだ具体的ではないです。
「凄腕の代理人(エージェント)として、噂だけが流れている」という書き方が、私好みかもしれません。

――人気の幅が広く、熱烈なファンも多い坂本龍馬。
登場するかどうかで物語のバランスにも影響がありそうです。2021年『青天を衝け』では見かけず、2013年『八重の桜』は後ろ姿での描写と記憶します。
“特別出演”的に有名俳優を起用するか、もしくは半端なキャスティングはあきらめ、“存在”のみを描くというパターンもあり得ると思います。
幕末の長崎でも活動した人物であり、大隈重信と接点はあったようです。
「佐賀の大河ドラマ」における坂本龍馬の描き方は“未解決”として残る一方、例示したもう1つの名作の足跡を追って、『事件ファイル』は後編に続きます。
参考情報:2015年『花燃ゆ』では伊原剛志さん、2018年『西郷どん』では『鎌倉殿の13人』主演の小栗旬さんが、坂本龍馬を演じていました。
ゴールデンウィーク特別企画なので、現在の“本編”から数年後の話になるのですが、幕末の有名人の方々を取り巻く事件についても触れておきます。
『新選組!』や『龍馬伝』等は幕末の大河ドラマで特に人気の作品。しかし、明治期に存命でなかった人物は、佐賀藩士とは接点が少ない傾向です。
過去の大河ドラマで名作の主人公だった人物を「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で、どう描くかには、ひと工夫が要ると考えているところです。

――ここで、前編に続き「幕末!京都事件ファイル②」
京・伏見の船宿“寺田屋”で発生した著名な事件がもう1つ。「②寺田屋事件」についても触れたいと思います。
事件発生の現場は、前編で取り上げた「①寺田屋騒動」と同じ場所。時期は、慶応二年(1866年)一月。新暦でいえば春の三月頃のようです。
こちらの「②寺田屋事件」は幕府の伏見奉行所が、薩摩や長州に関わる土佐(高知)の脱藩浪士・坂本龍馬を急襲した事件と表す方が通りが良いでしょう。
この事件には「寺田屋遭難」という呼び名もあるようです。
事件現場として度々登場する、川の港町・伏見は重要な拠点。なお佐賀藩は朝廷に伏見の警備を突然申し出て、薩摩藩との間が不穏になったようです。
――そして、2010年大河ドラマ『龍馬伝』でも描かれた“事件”の場面。
寺田屋にいた女性・お龍〔演:真木よう子〕は、1階で入浴中に周囲が奉行所の捕方に囲まれていることに気付きました。
なりふり構わず階段を駆け上がったお龍は、坂本龍馬〔演:福山雅治〕に危機を知らせます。
多数の捕方に対して、龍馬は拳銃を発砲して応戦のすえに逃走。手傷を負い、生命の危機に瀕して、薩摩藩に救出される…あの事件です。
負傷した龍馬が物陰に身を潜めながら、夜空を見上げてつぶやいていた印象的な場面があったように思います。

――坂本龍馬が、土佐を脱藩した時期は、
この場面から四年ほど前。文久二年(1862年)で、龍馬は最終的に江戸に向かいました。この年に、江藤新平は佐賀を脱藩して京都で活動しています。
『龍馬伝』で視聴した時の記憶が曖昧ですが、以前留学していた江戸の剣術道場を拠点に人脈を広げ、幕臣・勝海舟に弟子入りした時期のようです。
ちなみに身内から脱藩を警戒された龍馬は一時、刀を取り上げられていたものの、姉が家で秘蔵していた“肥前忠広”を持ち出し、龍馬に渡したそうです。
――“肥前忠広”といえば、佐賀の刀工として著名です。
佐賀では県立博物館で展示会などもあり、近年では“擬人化”され、ゲーム等でも人気の刀剣と聞きますが、土佐(高知)でも秘蔵されていたのですね。
龍馬はのちに、その刀を師匠・勝海舟の警護も任せた、同郷の岡田以蔵に託していたとか…これも事件の予感がします。
そういえば、『龍馬伝』では佐藤健さんが演じた岡田以蔵が、とても健気で悲壮感がある、“予想外”の描き方だったので記憶に残っています。
――その名が出た、ついでのような形で恐縮ですが
“肥前忠広”の話を少し続けます。幕末期には、いかにも佐賀の刀工らしい、剣に留まらない働きもありました。
佐賀藩の鉄製大砲開発チーム“鋳立方の七人”の一員・橋本新左衛門は、幕末期に佐賀で活躍した刀鍛冶でした。
〔参照:
“本編”で書いた時点ではよくわかっていませんでしたが、この方が“肥前忠広(忠吉)”の継承者だったようです。
その技術を、日本の近代化につながる方向にも発揮した佐賀の刀工。
郷里から太平洋を望んで、世界の海を想った、土佐藩士たちもその刀を所持していたと思うと、浪漫があるような気がします。
――もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現したら、
土佐(高知)が誇る、二度の大河ドラマ主人公・坂本龍馬はどう描かれるか。
なお、私が書いている“本編”での描き方も、まだ具体的ではないです。
「凄腕の代理人(エージェント)として、噂だけが流れている」という書き方が、私好みかもしれません。

――人気の幅が広く、熱烈なファンも多い坂本龍馬。
登場するかどうかで物語のバランスにも影響がありそうです。2021年『青天を衝け』では見かけず、2013年『八重の桜』は後ろ姿での描写と記憶します。
“特別出演”的に有名俳優を起用するか、もしくは半端なキャスティングはあきらめ、“存在”のみを描くというパターンもあり得ると思います。
幕末の長崎でも活動した人物であり、大隈重信と接点はあったようです。
「佐賀の大河ドラマ」における坂本龍馬の描き方は“未解決”として残る一方、例示したもう1つの名作の足跡を追って、『事件ファイル』は後編に続きます。
参考情報:2015年『花燃ゆ』では伊原剛志さん、2018年『西郷どん』では『鎌倉殿の13人』主演の小栗旬さんが、坂本龍馬を演じていました。
2022年04月30日
「幕末!京都事件ファイル①〔前編〕」
こんばんは。
現在、当ブログでは“本編”・第18話「京都見聞」を書き進めていますが、ここから3回ほど、ゴールデンウィーク特別企画です。
私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージ、佐賀県にある各地域の風景や人物の描き方、隣県の福岡や長崎の幕末期をどう表現するか…
また幕末期が題材の大河ドラマ作品の中で、どのような立ち位置を選択するか…という各種の課題があり、足らない才能の限界を顧みずに挑んでいます。
――さて、文久二年(1862年)夏頃。
第2部の主人公である江藤新平が国元・佐賀を脱藩し、京都での活動を開始しました。ここが“本編”の現在地です。
前回、京都(伏見)に到着したばかりの江藤の前に“祇園太郎”と名乗る男が現れました。謎の男のはずが、途中から「佐賀ことば」で語り出す展開に。
〔参照:第18話「京都見聞」⑥(もう1人の脱藩者)〕
“祇園太郎”は「九州の小京都」とも称される小城出身の実在人物。活動内容等には謎が多いようで、この時点では長崎に居た可能性もあるようです。

しかし、ここで数年前から上方(京・大坂)で活動した人物が登場したことには、江藤にも協力者がいたのではないかという推測と、構成上の都合があります。
不穏な空気の漂う京の都。新選組などの幕末の大河ドラマの“常連組”が、出揃う前の時期。そこには、激動の始まりとでも言うべき事件がありました。
――ここで、「幕末!京都事件ファイル①」です。
前回描いた「①寺田屋騒動」から。薩摩藩(鹿児島)の同士討ちの事件ですが、現在の“福岡県”の志士たちとも関わりが深いです。
〔参照:第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕
「寺田屋事件」と呼ばれることもありますが、他にも同名称の事件があるため、“本編”では「寺田屋騒動」で通しています。
事件の発生時期は、文久二年(1862年)四月。新暦でいえば初夏の5月頃。場所は現・京都市南部。“川の港町”として栄えた水運の拠点・伏見です。

――この「①寺田屋騒動」は
「薩摩藩志士粛清事件」という事件名でも表されるようです。
伏見の船宿・寺田屋に集結した薩摩の勤王派志士が、幕府寄りの公家だった関白・九条尚忠の暗殺を計画したことが事件の背景にあります。
その動機は幕府に近い要人の襲撃を強行し、薩摩の国父(藩主の父)・島津久光が「もう“倒幕”に立つしかない状況」を作り出す事。
しかし、国父・島津久光の狙いは“公武合体”による幕府の改革で、主導権を取ること。亡兄・島津斉彬が熱心だった“一橋派”の復権運動にも見えます。
〔参照:「将軍継嗣問題をどう描くか?(後編)」〕
そして、“倒幕”は考えていなかったようです。逆に薩摩藩側は過激な志士たちを制圧するため、剣術に長けた藩士を派遣し、事態の収拾をはかります。
――鎮撫(制圧)する側の薩摩藩士は、
結局、説得に応じない勤王派に斬りかかりました。
制圧に赴いた側にも犠牲者が出ましたが、勤王派の被害は凄まじく、斬り合いの時点だけで6名が落命したそうです。
この壮絶な場面は、2018年大河ドラマ『西郷どん』でも描かれました。薩摩藩士・有馬新七〔演:増田修一郎〕が印象的だったように思います。
〔参照(中盤):「新キャストを考える④」(“絶望”を越えて行け)〕
倒幕への熱すぎる想いのもとで、同士討ちに散った“勤王派”。
同郷の者たちが残した“無念”が、のちに薩摩藩士たちが“武力倒幕”に執念を燃やす伏線とも考えられます。

――なお、同じ寺田屋には、
薩摩藩士のほか、公家の関係者、現在は福岡県内にあたる久留米藩、秋月藩などの志士も居ました。
久留米の真木和泉などは自藩に引き渡されたようですが、秋月の海賀宮門など薩摩方面に送られる方々も…。この辺り、本編でも表現を試みたいです。
本編によく名前が出る福岡の志士・平野国臣は、福岡藩も“倒幕”に協力するよう工作に動いており、事件現場には不在だったようです。
――こうして薩摩藩は、勤王派を追放し…
「幕府寄り・開国受容の薩摩 VS 倒幕派・攘夷実行の長州」という対立軸が、しばらく展開するようです。
そんな中、佐賀藩のある動きにより、薩摩藩との間に軋轢(あつれき)が生じるのですが、続きは“本編”の展開にあわせて書こうと思います。
なお、この『事件ファイル』は、中編に続く予定です。
現在、当ブログでは“本編”・第18話「京都見聞」を書き進めていますが、ここから3回ほど、ゴールデンウィーク特別企画です。
私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージ、佐賀県にある各地域の風景や人物の描き方、隣県の福岡や長崎の幕末期をどう表現するか…
また幕末期が題材の大河ドラマ作品の中で、どのような立ち位置を選択するか…という各種の課題があり、足らない才能の限界を顧みずに挑んでいます。
――さて、文久二年(1862年)夏頃。
第2部の主人公である江藤新平が国元・佐賀を脱藩し、京都での活動を開始しました。ここが“本編”の現在地です。
前回、京都(伏見)に到着したばかりの江藤の前に“祇園太郎”と名乗る男が現れました。謎の男のはずが、途中から「佐賀ことば」で語り出す展開に。
〔参照:
“祇園太郎”は「九州の小京都」とも称される小城出身の実在人物。活動内容等には謎が多いようで、この時点では長崎に居た可能性もあるようです。

しかし、ここで数年前から上方(京・大坂)で活動した人物が登場したことには、江藤にも協力者がいたのではないかという推測と、構成上の都合があります。
不穏な空気の漂う京の都。新選組などの幕末の大河ドラマの“常連組”が、出揃う前の時期。そこには、激動の始まりとでも言うべき事件がありました。
――ここで、「幕末!京都事件ファイル①」です。
前回描いた「①寺田屋騒動」から。薩摩藩(鹿児島)の同士討ちの事件ですが、現在の“福岡県”の志士たちとも関わりが深いです。
〔参照:
「寺田屋事件」と呼ばれることもありますが、他にも同名称の事件があるため、“本編”では「寺田屋騒動」で通しています。
事件の発生時期は、文久二年(1862年)四月。新暦でいえば初夏の5月頃。場所は現・京都市南部。“川の港町”として栄えた水運の拠点・伏見です。

――この「①寺田屋騒動」は
「薩摩藩志士粛清事件」という事件名でも表されるようです。
伏見の船宿・寺田屋に集結した薩摩の勤王派志士が、幕府寄りの公家だった関白・九条尚忠の暗殺を計画したことが事件の背景にあります。
その動機は幕府に近い要人の襲撃を強行し、薩摩の国父(藩主の父)・島津久光が「もう“倒幕”に立つしかない状況」を作り出す事。
しかし、国父・島津久光の狙いは“公武合体”による幕府の改革で、主導権を取ること。亡兄・島津斉彬が熱心だった“一橋派”の復権運動にも見えます。
〔参照:
そして、“倒幕”は考えていなかったようです。逆に薩摩藩側は過激な志士たちを制圧するため、剣術に長けた藩士を派遣し、事態の収拾をはかります。
――鎮撫(制圧)する側の薩摩藩士は、
結局、説得に応じない勤王派に斬りかかりました。
制圧に赴いた側にも犠牲者が出ましたが、勤王派の被害は凄まじく、斬り合いの時点だけで6名が落命したそうです。
この壮絶な場面は、2018年大河ドラマ『西郷どん』でも描かれました。薩摩藩士・有馬新七〔演:増田修一郎〕が印象的だったように思います。
〔参照(中盤):
倒幕への熱すぎる想いのもとで、同士討ちに散った“勤王派”。
同郷の者たちが残した“無念”が、のちに薩摩藩士たちが“武力倒幕”に執念を燃やす伏線とも考えられます。

――なお、同じ寺田屋には、
薩摩藩士のほか、公家の関係者、現在は福岡県内にあたる久留米藩、秋月藩などの志士も居ました。
久留米の真木和泉などは自藩に引き渡されたようですが、秋月の海賀宮門など薩摩方面に送られる方々も…。この辺り、本編でも表現を試みたいです。
本編によく名前が出る福岡の志士・平野国臣は、福岡藩も“倒幕”に協力するよう工作に動いており、事件現場には不在だったようです。
――こうして薩摩藩は、勤王派を追放し…
「幕府寄り・開国受容の薩摩 VS 倒幕派・攘夷実行の長州」という対立軸が、しばらく展開するようです。
そんな中、佐賀藩のある動きにより、薩摩藩との間に軋轢(あつれき)が生じるのですが、続きは“本編”の展開にあわせて書こうと思います。
なお、この『事件ファイル』は、中編に続く予定です。
2021年03月07日
「“鎖国”してたね?(開国編)」
こんばんは。
幕末の大河ドラマ「青天を衝け」で特大の違和感を物ともせず、冒頭を仕切る、徳川家康(演:北大路欣也)。今夜の放送も、楽しみです。
先週(第3回)の冒頭は渋沢栄一(演:吉沢亮)。「家康公の登場は無しか…」と油断した私に、オープニング直後「こんばんは、徳川家康です」の声。
「今日は私のお気に入りの外国人を紹介したい。」と話を進めます。「なんて自由な“天下人”なんだ…」と思った私でした。
――なお、家康公の没年は1616年。
家康公が自ら“三浦按針”の名を与えたウィリアム・アダムスや、過去のマルコ・ポーロはともかく、未来(!)の外国人(ラナルド・マクドナルド)までお気に入り。
家康存命時の『鎖国』の進捗ですが、まだキリスト教宣教師の追放、長崎・平戸への貿易港の制限…という段階。
『鎖国』の完成は、かなり先。3代将軍・徳川家光の時代。家康公には、まだまだ海外への強い興味があったのでしょう。まさか未来まで見ておられるとは…

――『開国』への道を考える。序盤(1800年代~)。
以降、200年ばかり続いた『鎖国』と言われます。しかし、特に幕末に近づくにつれて、主に長崎で色々ありました。もちろん、当ブログでは佐賀藩の視点です。
1804年 ロシアのレザノフが長崎で通商要求
長崎警備担当の佐賀藩は、千人規模で守りを固めます。長崎は無事でしたが、レザノフは、幕府の対応に不満を持ったようで、北方で暴れます。
1808年 イギリス船の長崎港侵入事件
私は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の第1話に設定した“フェートン号事件”です。
〔参照:第1話「長崎警護」④〕
1825年 異国船打払令
“本編”第2話では、佐賀藩の台場(砲台)担当者の目線で表現しました。
〔参照:第2話「算盤大名」①〕
――続いて、危機意識を持つ佐賀藩。中盤(1830年代~)
蘭癖(西洋かぶれ)の武雄領主・鍋島茂義が先導し、長崎の町役人・高島秋帆から佐賀藩は西洋砲術を学びます。最新技術を得るには、長崎に近いと有利。
〔参照:第3話「西洋砲術」②〕
1840年 アヘン戦争
清国(中国)がイギリスに敗北し、日本の知識人は驚きます。「青天を衝け」でも、見かけた場面です。
1844年 オランダ国王の開国勧告
“親書”を持って「開国のススメ」を行うオランダですが幕府の反応は鈍いです。オランダが返事を待つ間に佐賀の殿・鍋島直正は蒸気船に乗せてもらいます。
――そして、アメリカもロシアも来る。終盤(1850年代~)
長崎に台場(砲台)を築き、鉄製大砲を完成した佐賀藩。外国と向き合います。
1853年 アメリカのペリーが浦賀に来航
幕府老中・阿部正弘は、佐賀藩が国内で唯一製造できる“鉄製大砲”を発注。
〔参照(後半):第8話「黒船来航」⑩〕
続いて同年 ロシアのプチャーチンが長崎に来航。
鍋島直正の決断で築いた「長崎砲台」。ロシア船に睨(にら)みを利かせます。
〔参照:第9話「和親条約」⑦〕

1854年 アメリカのペリーが再来航。
横浜に上陸しての『日米和親条約』の交渉。内容は下田・箱館の2港を開港し領事駐在。燃料・食料の補給。難破船の救助など…外国船の支援寄りです。
幕府は“通商”を「本筋と関係ない」、“2港以外の開港”を「国書に記載無し」と拒絶したようです。弱腰のイメージで語られますが、意外と「NO」も言います。
〔参照(中盤):第9話「和親条約」⑩〕
――時代は『開国』通商へ。“新しい港町”も登場。
1856年 アロー戦争
清国(中国)とイギリス・フランスとの戦闘。第2次アヘン戦争とも呼ばれ、清国が凄まじく不利な条約を結ぶに至ります。
1858年 アメリカの総領事ハリスと、『日米修好通商条約』調印。
幕府の大老・井伊直弼は朝廷の許し(勅許)を得てから条約調印を望んだとも。英仏の脅威が迫る中、時間は有限…と、井伊は条約締結を決断したようです。
…この通商も含めた『開国』により、巨大都市・江戸に近い横浜港が開かれて、大発展を遂げます。
一方で、日本の“絶対的”表玄関だった長崎港。独占的立場は失われますが、この後も幕末の舞台として存在感を示していきます。
幕末の大河ドラマ「青天を衝け」で特大の違和感を物ともせず、冒頭を仕切る、徳川家康(演:北大路欣也)。今夜の放送も、楽しみです。
先週(第3回)の冒頭は渋沢栄一(演:吉沢亮)。「家康公の登場は無しか…」と油断した私に、オープニング直後「こんばんは、徳川家康です」の声。
「今日は私のお気に入りの外国人を紹介したい。」と話を進めます。「なんて自由な“天下人”なんだ…」と思った私でした。
――なお、家康公の没年は1616年。
家康公が自ら“三浦按針”の名を与えたウィリアム・アダムスや、過去のマルコ・ポーロはともかく、未来(!)の外国人(ラナルド・マクドナルド)までお気に入り。
家康存命時の『鎖国』の進捗ですが、まだキリスト教宣教師の追放、長崎・平戸への貿易港の制限…という段階。
『鎖国』の完成は、かなり先。3代将軍・徳川家光の時代。家康公には、まだまだ海外への強い興味があったのでしょう。まさか未来まで見ておられるとは…
――『開国』への道を考える。序盤(1800年代~)。
以降、200年ばかり続いた『鎖国』と言われます。しかし、特に幕末に近づくにつれて、主に長崎で色々ありました。もちろん、当ブログでは佐賀藩の視点です。
1804年 ロシアのレザノフが長崎で通商要求
長崎警備担当の佐賀藩は、千人規模で守りを固めます。長崎は無事でしたが、レザノフは、幕府の対応に不満を持ったようで、北方で暴れます。
1808年 イギリス船の長崎港侵入事件
私は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の第1話に設定した“フェートン号事件”です。
〔参照:
1825年 異国船打払令
“本編”第2話では、佐賀藩の台場(砲台)担当者の目線で表現しました。
〔参照:
――続いて、危機意識を持つ佐賀藩。中盤(1830年代~)
蘭癖(西洋かぶれ)の武雄領主・鍋島茂義が先導し、長崎の町役人・高島秋帆から佐賀藩は西洋砲術を学びます。最新技術を得るには、長崎に近いと有利。
〔参照:
1840年 アヘン戦争
清国(中国)がイギリスに敗北し、日本の知識人は驚きます。「青天を衝け」でも、見かけた場面です。
1844年 オランダ国王の開国勧告
“親書”を持って「開国のススメ」を行うオランダですが幕府の反応は鈍いです。オランダが返事を待つ間に佐賀の殿・鍋島直正は蒸気船に乗せてもらいます。
――そして、アメリカもロシアも来る。終盤(1850年代~)
長崎に台場(砲台)を築き、鉄製大砲を完成した佐賀藩。外国と向き合います。
1853年 アメリカのペリーが浦賀に来航
幕府老中・阿部正弘は、佐賀藩が国内で唯一製造できる“鉄製大砲”を発注。
〔参照(後半):
続いて同年 ロシアのプチャーチンが長崎に来航。
鍋島直正の決断で築いた「長崎砲台」。ロシア船に睨(にら)みを利かせます。
〔参照:
1854年 アメリカのペリーが再来航。
横浜に上陸しての『日米和親条約』の交渉。内容は下田・箱館の2港を開港し領事駐在。燃料・食料の補給。難破船の救助など…外国船の支援寄りです。
幕府は“通商”を「本筋と関係ない」、“2港以外の開港”を「国書に記載無し」と拒絶したようです。弱腰のイメージで語られますが、意外と「NO」も言います。
〔参照(中盤):
――時代は『開国』通商へ。“新しい港町”も登場。
1856年 アロー戦争
清国(中国)とイギリス・フランスとの戦闘。第2次アヘン戦争とも呼ばれ、清国が凄まじく不利な条約を結ぶに至ります。
1858年 アメリカの総領事ハリスと、『日米修好通商条約』調印。
幕府の大老・井伊直弼は朝廷の許し(勅許)を得てから条約調印を望んだとも。英仏の脅威が迫る中、時間は有限…と、井伊は条約締結を決断したようです。
…この通商も含めた『開国』により、巨大都市・江戸に近い横浜港が開かれて、大発展を遂げます。
一方で、日本の“絶対的”表玄関だった長崎港。独占的立場は失われますが、この後も幕末の舞台として存在感を示していきます。
2021年03月05日
「“鎖国”してたね?(鎖国編)」
こんばんは。
以前、大河ドラマ「青天を衝け」の冒頭が気になる…という話をしました。
「こんばんは、徳川家康です。私の開いた江戸幕府は、よく『鎖国してたね?』なんて言われますが…」(第2回「栄一、踊る」より)
初回で「日本の歴史」を紹介したかと思えば、そのあとも天下御免で登場。さすが“天下人”ですが、この家康公は気難しい感じもなく親しみやすい印象です。
――もうすぐ、新年度。出会いの季節でもあります。
私はこの家康公(演:北大路欣也)がすでに毎週の楽しみです。「新しい職場や学校でも、あっと言う間に人気者」という、親しみやすい家康像(?)でしょうか。
なんだか友達多そう。たくさんの人から「鎖国してたね?」と言われている感じの、家康公…さて、ここからが本題ですが、『鎖国と開国』をテーマに考えます。

――まず『鎖国』を教科書っぽく。一言で語ると…
江戸幕府の「キリスト教の禁圧」と「対外関係の制限」の政策…でしょうか。
『鎖国』が完成に向かうのは、1633年~1639年頃。日本船の海外渡航の禁止、外国船が来航する港の限定が徹底されます。
――途中、1637年「島原の乱」が起きます。
西九州での戦いなので、佐賀藩兵も前線に出ることに。キリスト教徒の結束を見せつけられ、幕府はさらに警戒を強めます。
幕府が布教の思惑ありと判断したか、1639年にはポルトガル船は来航禁止。ヨーロッパの国では、“商売第一”のオランダとだけ交易を続けます。
――1641年。オランダ人も平戸から、長崎・出島に移されます。
この6年ほど前、明(中国)船も長崎港への来航に制限されているので、これで鎖国完成と言ってよいでしょう。日本の表玄関は、長崎だけ…になりました。
でも、家康公が語ったように。長崎以外にも、大名を通じた交易ルートが3箇所あることは知られています。
〔参照(後半):「幕末佐賀と4つの“口”」〕
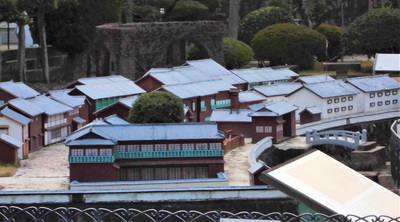
――江戸期を通じて、表玄関・長崎の警備担当は…
佐賀藩と福岡藩が、原則1年交代で務めました。莫大な費用がかかりますが、進んだ西洋の情報に触れることができました。
ちなみに、この2つの藩。有力な外様大名なので、監視役が付きます。幕府寄りの大名が入った唐津藩が、警備担当の2藩の動きを見張ります。
――そうです、その唐津藩も現在は“佐賀県”(唐津市周辺)です。
ちなみに“本編”第16話は「攘夷沸騰」というタイトルで考えています。いつから開始できるかは未定です。
そろそろ唐津藩ゆかりの方々の登場も狙っております。“佐賀県”を徹底して描くと、幕末という時代が浮かび上がってくる…そんな話も書いてみたいです。
〔参照(後半):「主に唐津市民の方を対象にしたつぶやき」〕
以前、大河ドラマ「青天を衝け」の冒頭が気になる…という話をしました。
「こんばんは、徳川家康です。私の開いた江戸幕府は、よく『鎖国してたね?』なんて言われますが…」(第2回「栄一、踊る」より)
初回で「日本の歴史」を紹介したかと思えば、そのあとも天下御免で登場。さすが“天下人”ですが、この家康公は気難しい感じもなく親しみやすい印象です。
――もうすぐ、新年度。出会いの季節でもあります。
私はこの家康公(演:北大路欣也)がすでに毎週の楽しみです。「新しい職場や学校でも、あっと言う間に人気者」という、親しみやすい家康像(?)でしょうか。
なんだか友達多そう。たくさんの人から「鎖国してたね?」と言われている感じの、家康公…さて、ここからが本題ですが、『鎖国と開国』をテーマに考えます。
――まず『鎖国』を教科書っぽく。一言で語ると…
江戸幕府の「キリスト教の禁圧」と「対外関係の制限」の政策…でしょうか。
『鎖国』が完成に向かうのは、1633年~1639年頃。日本船の海外渡航の禁止、外国船が来航する港の限定が徹底されます。
――途中、1637年「島原の乱」が起きます。
西九州での戦いなので、佐賀藩兵も前線に出ることに。キリスト教徒の結束を見せつけられ、幕府はさらに警戒を強めます。
幕府が布教の思惑ありと判断したか、1639年にはポルトガル船は来航禁止。ヨーロッパの国では、“商売第一”のオランダとだけ交易を続けます。
――1641年。オランダ人も平戸から、長崎・出島に移されます。
この6年ほど前、明(中国)船も長崎港への来航に制限されているので、これで鎖国完成と言ってよいでしょう。日本の表玄関は、長崎だけ…になりました。
でも、家康公が語ったように。長崎以外にも、大名を通じた交易ルートが3箇所あることは知られています。
〔参照(後半):
――江戸期を通じて、表玄関・長崎の警備担当は…
佐賀藩と福岡藩が、原則1年交代で務めました。莫大な費用がかかりますが、進んだ西洋の情報に触れることができました。
ちなみに、この2つの藩。有力な外様大名なので、監視役が付きます。幕府寄りの大名が入った唐津藩が、警備担当の2藩の動きを見張ります。
――そうです、その唐津藩も現在は“佐賀県”(唐津市周辺)です。
ちなみに“本編”第16話は「攘夷沸騰」というタイトルで考えています。いつから開始できるかは未定です。
そろそろ唐津藩ゆかりの方々の登場も狙っております。“佐賀県”を徹底して描くと、幕末という時代が浮かび上がってくる…そんな話も書いてみたいです。
〔参照(後半):
2021年03月03日
「花の生涯…」
こんばんは。
本日は、3月3日ですね。
旧暦ですが、幕末の大事件「桜田門外の変」が起きた日でもあります。現代の暦(季節感)では、3月下旬頃になります。
…華やかな気分の“ひな祭り”に、なんだか物騒な話始めで恐縮です。
――今日のタイトルは、大河ドラマ第1作『花の生涯』から…
実は、初めて「大河ドラマ」の主人公になった方が、井伊直弼です。
当時の映像は、一部しか現存しないそうです。放映は、1963年(昭和38年)。この翌年には、東京オリンピックが開催されたのですね。
…実際に視聴した方の記憶の中には“名作”として刻まれていることでしょう。
以前、歴代「大河ドラマ」の主人公と、佐賀の主役候補をつなぐ…という投稿をしたことがあり、井伊直弼と鍋島直正の関わりも少し書いています。
〔参照:「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③‐1鍋島直正編)〕
――“本編”の直近の投稿は、かなり井伊直弼の立場に寄っています。
「井伊さまの地元・彦根(滋賀)の皆様にも届け!」という想いで書き進めました。
大河ドラマ「青天を衝け」では、水戸藩が準主役と言って良いでしょう。敵対する井伊大老は、あまり良く描いてもらえないと想像し、より気合が入りました。
〔参照:第15話「江戸動乱」⑭(“赤鬼”が背負うもの)〕
…ここは、“青天”の井伊直弼役・岸谷五朗さんの熱演にも期待したいです。

――ちなみに「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば…
大老・井伊直弼は、好意的に描けると思います。殿・鍋島直正が見込んだ「国を背負うべき士」みたく表現できそうです。
彦根(滋賀)の情報も参照してみましたが、井伊直弼は「志士の弾圧」と「開国の英断」で評価が両極端。もう少し冷静に見てほしい…という声もあるようです。
キーワードは「朝廷への工作で、政治の体制を揺るがした」と判断された“戊午(ぼご)の密勅”。ここの経緯を丁寧に追う必要があるという意見でした。
〔参照:「京の宵闇」〕
…幕府のルールを大事にし、決断をした責任は背負う。井伊直弼が地道に頑張るタイプならば、佐賀の殿・鍋島直正とは、やっぱり気が合うように思います。
――何やら「彦根市民の皆様へのつぶやき」になっていますが…
幕末期。“安政の大獄”の際、京都では井伊直弼の側近が指揮にあたり、親しかった女性まで“密偵”として活動したそうです。
そして京都を守備する彦根藩士たちが、主力として探索にあたった結果。尊王攘夷の志士たちも、まず彦根城に囚われる事が多かったと聞きます。
〔参照(終盤):第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)〕
その後、井伊直弼がいなくなった彦根藩。幕府からの扱いは冷たいものでした。こうして戊辰戦争時には、早々と新政府側に付くことになります。

――そして現在、“国宝”の天守を持つ彦根城。
いまや、ゆるキャラ界の大物“ひこにゃん”も有する、強力観光スポットですが、この彦根城にもピンチがありました。
かつて明治初期に無用扱いとなった、江戸期の城郭は、全国で壊されました。
「城さえ残っていれば…」と涙を流す、各地の観光関係者も少なくないはず。
しかし彦根には救いのヒーローが現れます。明治天皇の北陸巡幸に随行した、大隈重信が、解体準備が進む、彦根城に立ち寄ったのです。
大隈は「こん城の消失は惜しか。保存せんばならんばい!」とか決意したのか、天皇に保存を奏上します。…なかなか美味しいところを持っていく大隈さん。
…高い価値が守られた彦根城。井伊直弼の旧暦命日に見つけたお話でした。
本日は、3月3日ですね。
旧暦ですが、幕末の大事件「桜田門外の変」が起きた日でもあります。現代の暦(季節感)では、3月下旬頃になります。
…華やかな気分の“ひな祭り”に、なんだか物騒な話始めで恐縮です。
――今日のタイトルは、大河ドラマ第1作『花の生涯』から…
実は、初めて「大河ドラマ」の主人公になった方が、井伊直弼です。
当時の映像は、一部しか現存しないそうです。放映は、1963年(昭和38年)。この翌年には、東京オリンピックが開催されたのですね。
…実際に視聴した方の記憶の中には“名作”として刻まれていることでしょう。
以前、歴代「大河ドラマ」の主人公と、佐賀の主役候補をつなぐ…という投稿をしたことがあり、井伊直弼と鍋島直正の関わりも少し書いています。
〔参照:
――“本編”の直近の投稿は、かなり井伊直弼の立場に寄っています。
「井伊さまの地元・彦根(滋賀)の皆様にも届け!」という想いで書き進めました。
大河ドラマ「青天を衝け」では、水戸藩が準主役と言って良いでしょう。敵対する井伊大老は、あまり良く描いてもらえないと想像し、より気合が入りました。
〔参照:
…ここは、“青天”の井伊直弼役・岸谷五朗さんの熱演にも期待したいです。
――ちなみに「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば…
大老・井伊直弼は、好意的に描けると思います。殿・鍋島直正が見込んだ「国を背負うべき士」みたく表現できそうです。
彦根(滋賀)の情報も参照してみましたが、井伊直弼は「志士の弾圧」と「開国の英断」で評価が両極端。もう少し冷静に見てほしい…という声もあるようです。
キーワードは「朝廷への工作で、政治の体制を揺るがした」と判断された“戊午(ぼご)の密勅”。ここの経緯を丁寧に追う必要があるという意見でした。
〔参照:
…幕府のルールを大事にし、決断をした責任は背負う。井伊直弼が地道に頑張るタイプならば、佐賀の殿・鍋島直正とは、やっぱり気が合うように思います。
――何やら「彦根市民の皆様へのつぶやき」になっていますが…
幕末期。“安政の大獄”の際、京都では井伊直弼の側近が指揮にあたり、親しかった女性まで“密偵”として活動したそうです。
そして京都を守備する彦根藩士たちが、主力として探索にあたった結果。尊王攘夷の志士たちも、まず彦根城に囚われる事が多かったと聞きます。
〔参照(終盤):
その後、井伊直弼がいなくなった彦根藩。幕府からの扱いは冷たいものでした。こうして戊辰戦争時には、早々と新政府側に付くことになります。
――そして現在、“国宝”の天守を持つ彦根城。
いまや、ゆるキャラ界の大物“ひこにゃん”も有する、強力観光スポットですが、この彦根城にもピンチがありました。
かつて明治初期に無用扱いとなった、江戸期の城郭は、全国で壊されました。
「城さえ残っていれば…」と涙を流す、各地の観光関係者も少なくないはず。
しかし彦根には救いのヒーローが現れます。明治天皇の北陸巡幸に随行した、大隈重信が、解体準備が進む、彦根城に立ち寄ったのです。
大隈は「こん城の消失は惜しか。保存せんばならんばい!」とか決意したのか、天皇に保存を奏上します。…なかなか美味しいところを持っていく大隈さん。
…高い価値が守られた彦根城。井伊直弼の旧暦命日に見つけたお話でした。
タグ :大河ドラマ
2021年02月21日
「“安政の大獄”をどう描くか?」
こんばんは。“本編”に戻るために助走をつけます。
明治維新で、際立った“勝者側”となったのは、薩摩藩・長州藩でしょう。同じく“新政府側”でも土佐藩や佐賀藩は、かなり当初の思惑が外れたようです。
――反面、勝者の“敵役”である幕府方は、悪く描かれがち…
こちらの代表格には、会津藩を挙げます。2013年の大河ドラマ「八重の桜」は“敗者側”からの視点で描かれ、かなり斬新な印象でした。
現在、放送中の大河ドラマ「青天を衝け」の主人公は幕臣・渋沢栄一です。
番組の案内役・徳川家康(演:北大路欣也)が第1話から強い目力で語ります。
「今につながる日本を開いた人物こそ、わが徳川の家臣であったと…ご存じだったかな?」
…今後、どのような立ち位置で、激動の時代を読み解くか注目しています。
――ここから本題に入ります。大弾圧と語られる「安政の大獄」。
刑罰の軽重はありますが、対象(連座)者は100人を超えるそうです。処刑または獄中で亡くなった方も13人を数えると聞きます。1858年からの出来事です。
幕府目線で、ざっくりと各藩における“罪状”のご報告を試みます。
「朝廷に裏工作を仕掛けた、水戸藩!」
「尊王攘夷の過激派がいる、長州藩!」
「次期将軍の選定に口出し、薩摩藩&福井藩!」

――こうして周囲は敵だらけとなった、大老・井伊直弼。
幕府内部の主導権争いもあり、井伊直弼の数少ない“味方”を2藩だけ紹介。
江戸幕府の運営側、徳川に近い大名が集う“溜間詰”の中で信用できるのは…
「幕府に忠節を尽くす、会津藩!」
そして、外様大名など諸侯が集う“大広間”の中で頼りになるのが…
「外交の良き理解者、佐賀藩!」
…私も、調べ始めた当初は「あれっ!?佐賀藩、意外に幕府寄り?」という印象でした。殿・鍋島直正は秩序を大事にするので、良くも悪くも優等生的なのです。
――さて、「安政の大獄」の基準はどうだったか…
「老中を暗殺する計画を話し合っていました!」
(長州藩・吉田松陰)
…尋ねられてもいない計画を、あえて語ったそうです。
吉田松陰が暗殺対象と語ったのは、老中・間部詮勝。意外や井伊直弼の評価は高く「彦根の殿様は、憐(あわ)れみのある名君!」とか語ったようです。
もし吉田松陰の言動が、大老・井伊直弼への期待で「幕府を改革してみな!」という“挑戦状”を叩きつけた…と想像すると、ドラマチックな感じがします。
――いかにも幕府らしい“サムライ”的な基準も…
「殿(松平春嶽)に言われた通りに活動しました!」
(福井藩・橋本左内)
…こう語って「殿様のせいにするとは何事だ!」と責められたそうです。
橋本左内は、真っ直ぐに事実を語ったのかもしれません。福井藩の殿様・松平春嶽は、一橋慶喜を次期将軍に強く推し、左内も熱心に活動していました。
予想を超える厳罰。福井藩の誇る天才、ここで歴史の舞台から姿を消します。

――そもそも「安政の大獄」のきっかけの1つが…
大老・井伊直弼が「朝廷の許可なく開国した!」と、江戸城へ抗議に押し掛ける一橋派の殿様たち。将軍選びの主導権を狙う意図も見えます。
騒ぎの中心は“水戸烈公”こと徳川斉昭。幕府のルールでは、定めの無い日に、江戸城に来るのは禁止。「不時登城」という立派な罪だそうです。
そして朝廷への裏工作を主導した水戸藩は、集中的に処罰されました。これで尊王攘夷運動はさらに“狂熱化”したと語られます。
――以上、“本編”で描くには厳しい情報量ですので、まとめて書きました!
私の調べは、話を進めるためのスピード重視のものですので、独断と偏見による解釈、不確かな出典による誤り等も、かなり含まれる前提でお読みください。
…あと、3回くらいで第15話「江戸動乱」をまとめたいです。今回は難しい!
明治維新で、際立った“勝者側”となったのは、薩摩藩・長州藩でしょう。同じく“新政府側”でも土佐藩や佐賀藩は、かなり当初の思惑が外れたようです。
――反面、勝者の“敵役”である幕府方は、悪く描かれがち…
こちらの代表格には、会津藩を挙げます。2013年の大河ドラマ「八重の桜」は“敗者側”からの視点で描かれ、かなり斬新な印象でした。
現在、放送中の大河ドラマ「青天を衝け」の主人公は幕臣・渋沢栄一です。
番組の案内役・徳川家康(演:北大路欣也)が第1話から強い目力で語ります。
「今につながる日本を開いた人物こそ、わが徳川の家臣であったと…ご存じだったかな?」
…今後、どのような立ち位置で、激動の時代を読み解くか注目しています。
――ここから本題に入ります。大弾圧と語られる「安政の大獄」。
刑罰の軽重はありますが、対象(連座)者は100人を超えるそうです。処刑または獄中で亡くなった方も13人を数えると聞きます。1858年からの出来事です。
幕府目線で、ざっくりと各藩における“罪状”のご報告を試みます。
「朝廷に裏工作を仕掛けた、水戸藩!」
「尊王攘夷の過激派がいる、長州藩!」
「次期将軍の選定に口出し、薩摩藩&福井藩!」
――こうして周囲は敵だらけとなった、大老・井伊直弼。
幕府内部の主導権争いもあり、井伊直弼の数少ない“味方”を2藩だけ紹介。
江戸幕府の運営側、徳川に近い大名が集う“溜間詰”の中で信用できるのは…
「幕府に忠節を尽くす、会津藩!」
そして、外様大名など諸侯が集う“大広間”の中で頼りになるのが…
「外交の良き理解者、佐賀藩!」
…私も、調べ始めた当初は「あれっ!?佐賀藩、意外に幕府寄り?」という印象でした。殿・鍋島直正は秩序を大事にするので、良くも悪くも優等生的なのです。
――さて、「安政の大獄」の基準はどうだったか…
「老中を暗殺する計画を話し合っていました!」
(長州藩・吉田松陰)
…尋ねられてもいない計画を、あえて語ったそうです。
吉田松陰が暗殺対象と語ったのは、老中・間部詮勝。意外や井伊直弼の評価は高く「彦根の殿様は、憐(あわ)れみのある名君!」とか語ったようです。
もし吉田松陰の言動が、大老・井伊直弼への期待で「幕府を改革してみな!」という“挑戦状”を叩きつけた…と想像すると、ドラマチックな感じがします。
――いかにも幕府らしい“サムライ”的な基準も…
「殿(松平春嶽)に言われた通りに活動しました!」
(福井藩・橋本左内)
…こう語って「殿様のせいにするとは何事だ!」と責められたそうです。
橋本左内は、真っ直ぐに事実を語ったのかもしれません。福井藩の殿様・松平春嶽は、一橋慶喜を次期将軍に強く推し、左内も熱心に活動していました。
予想を超える厳罰。福井藩の誇る天才、ここで歴史の舞台から姿を消します。
――そもそも「安政の大獄」のきっかけの1つが…
大老・井伊直弼が「朝廷の許可なく開国した!」と、江戸城へ抗議に押し掛ける一橋派の殿様たち。将軍選びの主導権を狙う意図も見えます。
騒ぎの中心は“水戸烈公”こと徳川斉昭。幕府のルールでは、定めの無い日に、江戸城に来るのは禁止。「不時登城」という立派な罪だそうです。
そして朝廷への裏工作を主導した水戸藩は、集中的に処罰されました。これで尊王攘夷運動はさらに“狂熱化”したと語られます。
――以上、“本編”で描くには厳しい情報量ですので、まとめて書きました!
私の調べは、話を進めるためのスピード重視のものですので、独断と偏見による解釈、不確かな出典による誤り等も、かなり含まれる前提でお読みください。
…あと、3回くらいで第15話「江戸動乱」をまとめたいです。今回は難しい!
2021年02月10日
「京の宵闇」
こんばんは。
「麒麟がくる」の最終回の余韻(よいん)に浸っていたくもありますが、今週末には「青天を衝け」も始まるので、また“戦国”から“幕末”に視点を戻します。
――まず、直近の“本編”を振り返ります。
公家・伊丹重賢のもとに、屈強な侍たちが詰めかけていました。
〔参照(終盤):第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)〕
伊丹さまですが、副島種臣(枝吉次郎)と佐賀藩の京都出兵を話していた方。青蓮院宮という身分の高い公家に仕えています。
――この頃、「安政の大獄」が始まっています。
1858年。朝廷から、主に水戸藩を対象とした「戊午の密勅」が下されます。
朝廷が各藩に直接「幕府の改革」と「攘夷の実行」を指示する内容。幕府の頭ごなしに、各藩への命令。大荒れ間違いなしです。
大老・井伊直弼や老中・間部詮勝ら幕府首脳は、探索を指示します。出典は不確かですが「井伊の赤鬼、間部の青鬼」と呼ばれていたという話もあるようです。

――井伊の側近・長野主膳らの捜査で…
首謀者とされた梅田雲浜は、若狭国(福井県南部)の人。元は武士(小浜藩士)でしたが、この時点では尊王攘夷の活動家。
幕府を激しく批判し“密勅”が出るよう暗躍。商才もあり、資金力も備えた様子。「安政の大獄」の逮捕者・第一号扱いとなっているようです。
――“鬼”呼ばわりされた幕府側の捜査は、さらに進展。
芋づる式に関係者が捕縛されています。先ほどの梅田雲浜と関わる人物が、次々と“捜査線上”に浮かびます。
主に捜査に動くのは、井伊直弼の領国(滋賀)の「彦根藩士」。そして、幕府の“京都支店”である「京都所司代」。
――尊攘活動家・梅田雲浜と接点のあった人物。
例えば、長州藩(山口)の吉田松陰も有名ですね。地元・萩で梅田雲浜と会った際に、幕府の重要人物である「老中・間部詮勝の暗殺」を相談していたとか…
攘夷志士たちの相談事…やはり過激です。吉田松陰は、あえて“その計画”を自白したため処刑となったそうです。

――そして、捜査の手は“一橋派”へ…
福井藩の橋本左内、薩摩藩(鹿児島)の西郷吉之助。大河ドラマ「西郷どん」では「次の将軍は、一橋慶喜公に!」と熱心な2人が描かれました。
“安政の大獄”では「幕臣でも無いのに、将軍選びに口出しした者」も追われる展開に。「西郷どん」では、風間俊介さんと鈴木亮平さんが逃走する場面です。
――でも、「佐賀藩の大河ドラマ」なので…
ここは、あえて伊丹重賢という人物に注目しました。佐賀への出兵要請で、副島種臣と関わっています。
副島の「佐賀から兵を出しましょう!」という提案に応じない殿・鍋島直正。この「安政の大獄」の展開を読んでいた…ように考えています。
――では、屈強な侍に囲まれた、伊丹重賢の運命やいかに…
次の時代へ生き延びます。伊丹さまの次男が、伊丹二郎というお名前。実業家として大正・昭和初期に「麒麟麦酒(キリンビール)」の会長を長く務めたとか。
…まだ「麒麟がくる」を引きずっていますが、大河ドラマの中でも“公家”を丁寧に描いた作品と思います。幕末期も、公家同士の派閥争いが政局に影響します。
「京の宵闇」で沸騰する尊攘志士たちの想い、交錯する公家たちの思惑…今日は、たぶん“本編”では描けない話をお送りしました。
「麒麟がくる」の最終回の余韻(よいん)に浸っていたくもありますが、今週末には「青天を衝け」も始まるので、また“戦国”から“幕末”に視点を戻します。
――まず、直近の“本編”を振り返ります。
公家・伊丹重賢のもとに、屈強な侍たちが詰めかけていました。
〔参照(終盤):
伊丹さまですが、副島種臣(枝吉次郎)と佐賀藩の京都出兵を話していた方。青蓮院宮という身分の高い公家に仕えています。
――この頃、「安政の大獄」が始まっています。
1858年。朝廷から、主に水戸藩を対象とした「戊午の密勅」が下されます。
朝廷が各藩に直接「幕府の改革」と「攘夷の実行」を指示する内容。幕府の頭ごなしに、各藩への命令。大荒れ間違いなしです。
大老・井伊直弼や老中・間部詮勝ら幕府首脳は、探索を指示します。出典は不確かですが「井伊の赤鬼、間部の青鬼」と呼ばれていたという話もあるようです。

――井伊の側近・長野主膳らの捜査で…
首謀者とされた梅田雲浜は、若狭国(福井県南部)の人。元は武士(小浜藩士)でしたが、この時点では尊王攘夷の活動家。
幕府を激しく批判し“密勅”が出るよう暗躍。商才もあり、資金力も備えた様子。「安政の大獄」の逮捕者・第一号扱いとなっているようです。
――“鬼”呼ばわりされた幕府側の捜査は、さらに進展。
芋づる式に関係者が捕縛されています。先ほどの梅田雲浜と関わる人物が、次々と“捜査線上”に浮かびます。
主に捜査に動くのは、井伊直弼の領国(滋賀)の「彦根藩士」。そして、幕府の“京都支店”である「京都所司代」。
――尊攘活動家・梅田雲浜と接点のあった人物。
例えば、長州藩(山口)の吉田松陰も有名ですね。地元・萩で梅田雲浜と会った際に、幕府の重要人物である「老中・間部詮勝の暗殺」を相談していたとか…
攘夷志士たちの相談事…やはり過激です。吉田松陰は、あえて“その計画”を自白したため処刑となったそうです。
――そして、捜査の手は“一橋派”へ…
福井藩の橋本左内、薩摩藩(鹿児島)の西郷吉之助。大河ドラマ「西郷どん」では「次の将軍は、一橋慶喜公に!」と熱心な2人が描かれました。
“安政の大獄”では「幕臣でも無いのに、将軍選びに口出しした者」も追われる展開に。「西郷どん」では、風間俊介さんと鈴木亮平さんが逃走する場面です。
――でも、「佐賀藩の大河ドラマ」なので…
ここは、あえて伊丹重賢という人物に注目しました。佐賀への出兵要請で、副島種臣と関わっています。
副島の「佐賀から兵を出しましょう!」という提案に応じない殿・鍋島直正。この「安政の大獄」の展開を読んでいた…ように考えています。
――では、屈強な侍に囲まれた、伊丹重賢の運命やいかに…
次の時代へ生き延びます。伊丹さまの次男が、伊丹二郎というお名前。実業家として大正・昭和初期に「麒麟麦酒(キリンビール)」の会長を長く務めたとか。
…まだ「麒麟がくる」を引きずっていますが、大河ドラマの中でも“公家”を丁寧に描いた作品と思います。幕末期も、公家同士の派閥争いが政局に影響します。
「京の宵闇」で沸騰する尊攘志士たちの想い、交錯する公家たちの思惑…今日は、たぶん“本編”では描けない話をお送りしました。
2020年11月18日
「開港の夜」
こんばんは。
まだ新型コロナという言葉も聞かなかった昨秋。
旅の記録を“連続ブログ小説”として綴りました。
第1シリーズ「佐賀への旅立ち~佐野常民記念館」編が完了したところです。
第2シリーズは「大隈重信記念館~長崎街道の夜」編
第3シリーズは「朝の長崎街道~さが維新まつり」編
…と、続編の予定があります。
――さて、肝心の「大河ドラマのイメージ」の現在地は…
“本編”の年代ですが、1858年の“日米修好通商条約”締結の前後のお話を進めています。第14話「遣米使節」は1855年~1860年のお話でした。
同じ時期を「行ったり来たり」しますが、“激動の時代”を様々な角度から描く試みです。佐賀藩が“三重津海軍所”を本格的に整備し始めたのもこの時期です。
通商条約は、大老・井伊直弼が「調印を強行した」と語られます。“開国”止む無しの状況で、井伊も朝廷との調整に苦心していた…との見解もあります。
――こうして、一気に西洋文明の波が日本に押し寄せますが…
アメリカを含む5か国との通商条約の締結。神奈川・長崎・箱(函)館・新潟・兵庫の5箇所の開港予定での交渉が行われます。
それまで、日本の世界への“窓口”は、長崎の独占状態でした。もちろん国際都市・長崎も開港しますが、強力なライバルが出現したとも言えます。
――当初の開港は、長崎・横浜・箱館の3箇所。
宿場町・神奈川を避け、開港地に選ばれた横浜。江戸にも近く、スタートダッシュです。条約締結の翌年1859年の開港で、早々に英語が飛び交います。
〔参考記事:「横浜村-1854年-(第11話プロローグ)」〕
第14話「遣米使節」に登場した佐賀藩士にも、小出千之助らオランダ語の達人が多数いましたが、アメリカに渡航したことで、英語の活用に舵を切ります。

――横浜に比べて、スロースターターだった港も…
幕末からおよそ700年もの昔。平清盛の時代からの港町・兵庫。京の都に近く、朝廷の意向が強く作用します。簡単には開港できません。
兵庫開港は1868年。10年ほどが経過し、すでに明治維新の直前期。旧来の兵庫港の隣地に港が開け、外国人居留地が広がり、名も神戸港と改めます。
いまや横浜・神戸の双方とも、国際貿易港として知られます。
――こんな背景を考えながら「第1部・幕末黎明編」をどこまで続けるか…
今のところ、第15話は「江戸動乱」、第16話を「攘夷沸騰」というタイトルで考えています。続く第17話で、“第1部”はひとまず完結させたい…と計画中です。
“本編”の再開まで、色々と投稿をしながら練っていきたいと思います。現時点の仮スケジュールでは、第1部を書き終えるのは、3月近くになりそうです。
あちこちに話が飛びますが、引き続きご覧いただければ幸いです。
まだ新型コロナという言葉も聞かなかった昨秋。
旅の記録を“連続ブログ小説”として綴りました。
第1シリーズ「佐賀への旅立ち~佐野常民記念館」編が完了したところです。
第2シリーズは「大隈重信記念館~長崎街道の夜」編
第3シリーズは「朝の長崎街道~さが維新まつり」編
…と、続編の予定があります。
――さて、肝心の「大河ドラマのイメージ」の現在地は…
“本編”の年代ですが、1858年の“日米修好通商条約”締結の前後のお話を進めています。第14話「遣米使節」は1855年~1860年のお話でした。
同じ時期を「行ったり来たり」しますが、“激動の時代”を様々な角度から描く試みです。佐賀藩が“三重津海軍所”を本格的に整備し始めたのもこの時期です。
通商条約は、大老・井伊直弼が「調印を強行した」と語られます。“開国”止む無しの状況で、井伊も朝廷との調整に苦心していた…との見解もあります。
――こうして、一気に西洋文明の波が日本に押し寄せますが…
アメリカを含む5か国との通商条約の締結。神奈川・長崎・箱(函)館・新潟・兵庫の5箇所の開港予定での交渉が行われます。
それまで、日本の世界への“窓口”は、長崎の独占状態でした。もちろん国際都市・長崎も開港しますが、強力なライバルが出現したとも言えます。
――当初の開港は、長崎・横浜・箱館の3箇所。
宿場町・神奈川を避け、開港地に選ばれた横浜。江戸にも近く、スタートダッシュです。条約締結の翌年1859年の開港で、早々に英語が飛び交います。
〔参考記事:
第14話「遣米使節」に登場した佐賀藩士にも、小出千之助らオランダ語の達人が多数いましたが、アメリカに渡航したことで、英語の活用に舵を切ります。
――横浜に比べて、スロースターターだった港も…
幕末からおよそ700年もの昔。平清盛の時代からの港町・兵庫。京の都に近く、朝廷の意向が強く作用します。簡単には開港できません。
兵庫開港は1868年。10年ほどが経過し、すでに明治維新の直前期。旧来の兵庫港の隣地に港が開け、外国人居留地が広がり、名も神戸港と改めます。
いまや横浜・神戸の双方とも、国際貿易港として知られます。
――こんな背景を考えながら「第1部・幕末黎明編」をどこまで続けるか…
今のところ、第15話は「江戸動乱」、第16話を「攘夷沸騰」というタイトルで考えています。続く第17話で、“第1部”はひとまず完結させたい…と計画中です。
“本編”の再開まで、色々と投稿をしながら練っていきたいと思います。現時点の仮スケジュールでは、第1部を書き終えるのは、3月近くになりそうです。
あちこちに話が飛びますが、引き続きご覧いただければ幸いです。
2020年09月17日
「将軍継嗣問題をどう描くか?(後編)」
こんばんは。
前回は、佐賀藩の“ご正室”と“大奥”のつながりにも触れてみました。
――さて、次(第14代)の将軍に誰を推すかのバトルの続きです。
一橋慶喜を推すグループには、福井の松平、薩摩の島津、土佐の山内、宇和島の伊達…などの雄藩がずらりと揃います。
幕府主導の政治から、雄藩の連合政権への転換を目指します。
――しかし“一橋派”には、幾つかの問題がありました…
このグループの有力者には、将軍候補・一橋慶喜の実父がいます。“本編”でも時々現れては、強いインパクトを残していく、水戸の“烈公”こと徳川斉昭です。
〔参照:第4話「諸国遊学」③,第9話「和親条約」③〕
“一橋派”には“開国派”を兼ねるメンバーも多いのですが、ご実父は“攘夷派”の首領格。

――威勢の良いコメントで“攘夷派”が熱狂する“水戸烈公”。
途中までは老中・阿部正弘が、うまくコントロールしていました。
「そうだ!水戸さまのお力で、異国にも負けない大船を造られては!」
政権の中心人物からおだてられると、水戸さまも悪い気はしません。
「まぁ、良かろう。儂に任せよ!」…という感じです。
しかし、働きすぎが原因だったのか、安全装置だった阿部正弘は急逝します。
〔参照:第13話「通商条約」⑩(扇の要が外れるとき…)〕
名実ともに老中首座となった堀田正睦は、洋学の素晴らしさを知る“開国派”。過激な“攘夷派”・徳川斉昭と折り合いを付けるのは難しい。
――そして色んな意味で激しい“水戸烈公”・徳川斉昭は…
一言で語れば、“大奥”から“女の敵”認定をされています。これには、そう判断される行状もあるようです。
こうして“大奥”では、その子・一橋慶喜まで徹底して不人気です。また、慶喜は頭が良過ぎるところがあり、何が本音なのかも理解されにくいタイプです。

――井伊直弼ら“南紀派”が推すのは、紀州(和歌山)の徳川慶福(家茂)。
素直で性格も良く、血統も申し分ない。しかも、甘い物が大好き…“女子ウケ”抜群の貴公子です。もちろん“大奥”でも大人気。
のちの第14代将軍・徳川家茂です。幕府のために皇女・和宮と“超”が付くほどの政略結婚で夫婦になりますが、すごく仲が良かったようです。
“南紀派”は、水戸・徳川斉昭が影の支配者になりそうな連合政権を否定。伝統の将軍選定ルールを守って、幕府主導の強化を図ります。
――では、佐賀の殿・鍋島直正の立ち位置はどちらか?
殿と“一橋派”とは縁戚関係だらけです。
当時のご正室(妻)・筆姫さまは松平慶永(春嶽)の妹。薩摩の島津斉彬は、母方のいとこ。宇和島の伊達宗城は、姉の夫(義兄)。
しかも殿の愛娘・貢姫の夫で、川越藩主・松平直侯は、一橋慶喜の弟です。
――ところが“一橋派”と距離を取り、政治工作に関わらない殿・直正。
“南紀派”のリーダー井伊直弼と、意見が近かったようです。
秩序を大事にして国をまとめ、外国に対峙するという考え方。
欧米列強と通商して富を蓄え、武装して有事に備える…これは“武備開国”と表現されることも。明治時代の「富国強兵」の先取りなのかもしれません。
――“大河ドラマ”の第1作目「花の生涯」の主人公は、井伊直弼でした。
幕府主導での決断を続けた、大老・井伊直弼には「悪役」のイメージが付きまといます。
しかし「条約の調印を強行した」とか、「安政の大獄で弾圧を行った」とかは、幕府の先例に基づき、仕事の責任を背負っただけ…という説もあります。
茶道や居合で“流派”を起こすほど、文武両道に秀でた人物。少しカッコよく描いてみたい気がしています。
前回は、佐賀藩の“ご正室”と“大奥”のつながりにも触れてみました。
――さて、次(第14代)の将軍に誰を推すかのバトルの続きです。
一橋慶喜を推すグループには、福井の松平、薩摩の島津、土佐の山内、宇和島の伊達…などの雄藩がずらりと揃います。
幕府主導の政治から、雄藩の連合政権への転換を目指します。
――しかし“一橋派”には、幾つかの問題がありました…
このグループの有力者には、将軍候補・一橋慶喜の実父がいます。“本編”でも時々現れては、強いインパクトを残していく、水戸の“烈公”こと徳川斉昭です。
〔参照:
“一橋派”には“開国派”を兼ねるメンバーも多いのですが、ご実父は“攘夷派”の首領格。

――威勢の良いコメントで“攘夷派”が熱狂する“水戸烈公”。
途中までは老中・阿部正弘が、うまくコントロールしていました。
「そうだ!水戸さまのお力で、異国にも負けない大船を造られては!」
政権の中心人物からおだてられると、水戸さまも悪い気はしません。
「まぁ、良かろう。儂に任せよ!」…という感じです。
しかし、働きすぎが原因だったのか、安全装置だった阿部正弘は急逝します。
〔参照:
名実ともに老中首座となった堀田正睦は、洋学の素晴らしさを知る“開国派”。過激な“攘夷派”・徳川斉昭と折り合いを付けるのは難しい。
――そして色んな意味で激しい“水戸烈公”・徳川斉昭は…
一言で語れば、“大奥”から“女の敵”認定をされています。これには、そう判断される行状もあるようです。
こうして“大奥”では、その子・一橋慶喜まで徹底して不人気です。また、慶喜は頭が良過ぎるところがあり、何が本音なのかも理解されにくいタイプです。
――井伊直弼ら“南紀派”が推すのは、紀州(和歌山)の徳川慶福(家茂)。
素直で性格も良く、血統も申し分ない。しかも、甘い物が大好き…“女子ウケ”抜群の貴公子です。もちろん“大奥”でも大人気。
のちの第14代将軍・徳川家茂です。幕府のために皇女・和宮と“超”が付くほどの政略結婚で夫婦になりますが、すごく仲が良かったようです。
“南紀派”は、水戸・徳川斉昭が影の支配者になりそうな連合政権を否定。伝統の将軍選定ルールを守って、幕府主導の強化を図ります。
――では、佐賀の殿・鍋島直正の立ち位置はどちらか?
殿と“一橋派”とは縁戚関係だらけです。
当時のご正室(妻)・筆姫さまは松平慶永(春嶽)の妹。薩摩の島津斉彬は、母方のいとこ。宇和島の伊達宗城は、姉の夫(義兄)。
しかも殿の愛娘・貢姫の夫で、川越藩主・松平直侯は、一橋慶喜の弟です。
――ところが“一橋派”と距離を取り、政治工作に関わらない殿・直正。
“南紀派”のリーダー井伊直弼と、意見が近かったようです。
秩序を大事にして国をまとめ、外国に対峙するという考え方。
欧米列強と通商して富を蓄え、武装して有事に備える…これは“武備開国”と表現されることも。明治時代の「富国強兵」の先取りなのかもしれません。
――“大河ドラマ”の第1作目「花の生涯」の主人公は、井伊直弼でした。
幕府主導での決断を続けた、大老・井伊直弼には「悪役」のイメージが付きまといます。
しかし「条約の調印を強行した」とか、「安政の大獄で弾圧を行った」とかは、幕府の先例に基づき、仕事の責任を背負っただけ…という説もあります。
茶道や居合で“流派”を起こすほど、文武両道に秀でた人物。少しカッコよく描いてみたい気がしています。
2020年09月15日
「将軍継嗣問題をどう描くか?(前編)」
こんばんは。
全国的に残暑も和らぎ、ようやく秋の気配…といったところでしょうか。
週末(日曜)は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」のライブ配信で、随分ヒートアップしてしまいました。
当ブログを始めてから9か月ほどが経っていますが、1日に3本も投稿したのは、今のところ同日だけです…
――さて、今回は少し“クールダウン”を図ります。
…とはいえ「八賢人おもてなし隊」の演劇の余韻も残っているので、関連した話をします。今回、同隊の演目で“女性キャスト”が登場したのを、初めて見ました。
5本目「あまねく人を。2020バージョン」というタイトルで、西洋医学に取り組んだ佐賀の先進性を示した演目です。
唯一登場した女性キャストが、殿・鍋島直正の“ご正室”・筆姫さま。当日のトークでMCを担当する女性が、急に姫の格好で現れたのもサプライズでした。
なお、詳細が気になる方は前回の投稿からリンク先をご覧ください…
〔参照(文末):佐賀城からのライブ配信の感想など④⑤〕
――さて、全国各藩の“ご正室”には、重要なお仕事がありました。
それは“大奥”を通じて、国(藩)のために“外交”を行うこと。徳川将軍家の私的空間である“大奥”とのつながりは、いざというときの政治力を高めます。
大奥の事務方トップは、老中に匹敵する権力を持っていたとか。江戸の街では、女の子たちの遊びに“大奥”出世すごろく…まで存在したようです。
――佐賀藩の筆姫さまも“大奥”と贈答品のやり取りなど交流に励んだ様子。
当時も伊万里で作られていた“鍋島焼”。こういう場面でも、贈答品として威力を発揮したと想像しています。
もともと殿・鍋島直正の最初の“ご正室”は、盛姫さまという方です。第11代将軍・徳川家斉の愛娘で、大事に育てられたお姫様でした。
“本編”では、はじめて佐賀に向かう直正を心配する…という描き方をしました。
〔参照:第2話「算盤大名」③-1〕

将軍の娘・盛姫さまには“大奥”はホームグラウンド。佐賀城が火災に遭った際も再建費用の借入に成功するなど、佐賀のために力を発揮したと推察します。
〔参照:第3話「西洋砲術」①-2〕
しかし、盛姫さまは30代後半の若さで亡くなられたため、殿は再婚することになりました。このあたりは、“本編”には描けていません。
――筆姫さまには、その“後継者”としての役割も期待されたと考えます。
筆姫さまも、将軍家に連なる家系のお姫様でした。
徳川御三家に次ぐ“御三卿”の1つ・田安家の出身です。
そして福井藩主・松平慶永(春嶽)の妹でもあります。一橋慶喜を次期将軍に推すグループのまとめ役ですね。
〔参照:第13話「通商条約」①(影の“内閣”)〕
薩摩の島津斉彬、土佐の山内豊信(容堂)、宇和島の伊達宗城…著名なメンバー揃いですが、次期将軍の擁立では、この“一橋派”は“南紀派”に敗れます。
その要因は次回でも考えていきたいと思います。
全国的に残暑も和らぎ、ようやく秋の気配…といったところでしょうか。
週末(日曜)は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」のライブ配信で、随分ヒートアップしてしまいました。
当ブログを始めてから9か月ほどが経っていますが、1日に3本も投稿したのは、今のところ同日だけです…
――さて、今回は少し“クールダウン”を図ります。
…とはいえ「八賢人おもてなし隊」の演劇の余韻も残っているので、関連した話をします。今回、同隊の演目で“女性キャスト”が登場したのを、初めて見ました。
5本目「あまねく人を。2020バージョン」というタイトルで、西洋医学に取り組んだ佐賀の先進性を示した演目です。
唯一登場した女性キャストが、殿・鍋島直正の“ご正室”・筆姫さま。当日のトークでMCを担当する女性が、急に姫の格好で現れたのもサプライズでした。
なお、詳細が気になる方は前回の投稿からリンク先をご覧ください…
〔参照(文末):
――さて、全国各藩の“ご正室”には、重要なお仕事がありました。
それは“大奥”を通じて、国(藩)のために“外交”を行うこと。徳川将軍家の私的空間である“大奥”とのつながりは、いざというときの政治力を高めます。
大奥の事務方トップは、老中に匹敵する権力を持っていたとか。江戸の街では、女の子たちの遊びに“大奥”出世すごろく…まで存在したようです。
――佐賀藩の筆姫さまも“大奥”と贈答品のやり取りなど交流に励んだ様子。
当時も伊万里で作られていた“鍋島焼”。こういう場面でも、贈答品として威力を発揮したと想像しています。
もともと殿・鍋島直正の最初の“ご正室”は、盛姫さまという方です。第11代将軍・徳川家斉の愛娘で、大事に育てられたお姫様でした。
“本編”では、はじめて佐賀に向かう直正を心配する…という描き方をしました。
〔参照:

将軍の娘・盛姫さまには“大奥”はホームグラウンド。佐賀城が火災に遭った際も再建費用の借入に成功するなど、佐賀のために力を発揮したと推察します。
〔参照:
しかし、盛姫さまは30代後半の若さで亡くなられたため、殿は再婚することになりました。このあたりは、“本編”には描けていません。
――筆姫さまには、その“後継者”としての役割も期待されたと考えます。
筆姫さまも、将軍家に連なる家系のお姫様でした。
徳川御三家に次ぐ“御三卿”の1つ・田安家の出身です。
そして福井藩主・松平慶永(春嶽)の妹でもあります。一橋慶喜を次期将軍に推すグループのまとめ役ですね。
〔参照:
薩摩の島津斉彬、土佐の山内豊信(容堂)、宇和島の伊達宗城…著名なメンバー揃いですが、次期将軍の擁立では、この“一橋派”は“南紀派”に敗れます。
その要因は次回でも考えていきたいと思います。
2020年07月22日
「井伊の“赤鬼”ふたたび」
こんばんは。
“本編”に戻る前に、また補足を入れていきます。
今日も“井伊家”について語ります。もちろん昨日「おんな城主直虎」について語った影響が残っています。
私はこの大河ドラマもかなりの名作だと思っています。
脚本の森下佳子さんは、TBS系ドラマ「JIN-仁-」で幕末も描いている方です。
――さて、幕末の話で“井伊家”と言えば、あの方。大老・井伊直弼の話をせねばなりません。
現在の“本編”は1854年~1857年あたりを色んな視点で描いています。
当時の老中・阿部正弘は、何とか“黒船来航”の危機を乗り切りました。
「諸侯の力を集め、国を守らねば…」
ペリーが来たときに、諸大名に意見を募った姿勢は変わりません。超・調整型リーダーです。
どこが“超”なのかというと、物凄く人の話を聞きます。最善手を見つけるまで、色んな人に聞きます。
――老中・阿部正弘、沿海の防備強化から欧米との外交まで、次々に人材を登用します。
まず、高島秋帆、江川英龍ら、砲術などの専門知識がある人物を重視。
そして、外交では川路聖謨や岩瀬忠震ら“切れ者”の官僚を見出します。
開国後は、オランダに意見を求めて、海軍の創設に舵を切ります。長崎海軍伝習所が出来たのも、この方針に拠ります。
この流れで、勝海舟や榎本武揚などが頭角を現します。
――“ご老中”のオープンな姿勢に、大名たちも次々に政治参加。
幕府は海岸沿いに領地を持つ雄藩と連携を深めます。とくに活発に動いたのは、福井藩の松平春嶽らのグループ。
薩摩藩・島津斉彬
土佐藩・山内容堂
宇和島藩・伊達宗城
諸侯で政治を担う時代に向けて、老中・阿部正弘は、以上の通称「幕末の四賢侯」とも話合いを重ねます。
この会合でも「外交は、佐賀の鍋島に受け持ってもらってはどうか」という議論だったようです。
薩摩の島津斉彬は鍋島直正のいとこ、宇和島の伊達宗城は直正の義兄。一応、縁戚関係もあるのですが、何より実力による評価です。
――この面々が皆で「賢いから、次の将軍に!」と考えたのが、一橋慶喜です。
ところが結集の軸であった老中・阿部正弘が1857年に、この世を去ります。
存命であれば、幕府のもとで「全国の大名の力を集めた政治が出来ただろう。」とか、「すなわち“安政維新”が可能であった!」という主張まで見かけます。
阿部正弘は開国を先導しつつも、過激な攘夷思想の水戸藩・徳川斉昭とも折り合いをつけました。恐るべき調整能力だったのでしょう。
――これだけの面々が一斉に推した、一橋慶喜ですが、次の将軍にはなっていません。
そのあとに幕府の大老になった彦根藩主・井伊直弼が、“一橋派の面々”を一気に抑え込みました。紀州藩・徳川慶福(家茂)を第14代将軍に付けたのです。
大名の結集ではなく、幕府の力で国を引っ張って行こうとした“剛腕”。
かつて、徳川家康に仕えた四天王・井伊直政は“井伊の赤鬼”とまで恐れられました。しかし、ご子孫も負けていないように思われます。
――そんな“井伊の赤鬼”の末裔・井伊直弼から例外的に信頼されていた、外様大名がいます。
またしても、肥前佐賀藩主・鍋島直正です。
当時、松平姓を名乗ったり、斉正という名であったりと、何かと徳川家に近い立場です。
開国通商で、国力の増強を図ろうとした大老・井伊直弼。
海軍の整備が必須と考えており、直正に相談を持ちかけていたようです。
敵の多い大老だったので「会津と佐賀くらいしか私の心を理解してくれない…」と言っていたとか。
佐賀の話を中心に描きたいので、次話「通商条約」までの時代背景の参考です。第12話「海軍伝習」もあと3回くらいで終わらせるのが目安です。
本日の内容は、以前の投稿と少し重複してしまいました。書きたいことは、色々とあるのですが、まとめるのが難しい…です。
“本編”に戻る前に、また補足を入れていきます。
今日も“井伊家”について語ります。もちろん昨日「おんな城主直虎」について語った影響が残っています。
私はこの大河ドラマもかなりの名作だと思っています。
脚本の森下佳子さんは、TBS系ドラマ「JIN-仁-」で幕末も描いている方です。
――さて、幕末の話で“井伊家”と言えば、あの方。大老・井伊直弼の話をせねばなりません。
現在の“本編”は1854年~1857年あたりを色んな視点で描いています。
当時の老中・阿部正弘は、何とか“黒船来航”の危機を乗り切りました。
「諸侯の力を集め、国を守らねば…」
ペリーが来たときに、諸大名に意見を募った姿勢は変わりません。超・調整型リーダーです。
どこが“超”なのかというと、物凄く人の話を聞きます。最善手を見つけるまで、色んな人に聞きます。
――老中・阿部正弘、沿海の防備強化から欧米との外交まで、次々に人材を登用します。
まず、高島秋帆、江川英龍ら、砲術などの専門知識がある人物を重視。
そして、外交では川路聖謨や岩瀬忠震ら“切れ者”の官僚を見出します。
開国後は、オランダに意見を求めて、海軍の創設に舵を切ります。長崎海軍伝習所が出来たのも、この方針に拠ります。
この流れで、勝海舟や榎本武揚などが頭角を現します。
――“ご老中”のオープンな姿勢に、大名たちも次々に政治参加。
幕府は海岸沿いに領地を持つ雄藩と連携を深めます。とくに活発に動いたのは、福井藩の松平春嶽らのグループ。
薩摩藩・島津斉彬
土佐藩・山内容堂
宇和島藩・伊達宗城
諸侯で政治を担う時代に向けて、老中・阿部正弘は、以上の通称「幕末の四賢侯」とも話合いを重ねます。
この会合でも「外交は、佐賀の鍋島に受け持ってもらってはどうか」という議論だったようです。
薩摩の島津斉彬は鍋島直正のいとこ、宇和島の伊達宗城は直正の義兄。一応、縁戚関係もあるのですが、何より実力による評価です。
――この面々が皆で「賢いから、次の将軍に!」と考えたのが、一橋慶喜です。
ところが結集の軸であった老中・阿部正弘が1857年に、この世を去ります。
存命であれば、幕府のもとで「全国の大名の力を集めた政治が出来ただろう。」とか、「すなわち“安政維新”が可能であった!」という主張まで見かけます。
阿部正弘は開国を先導しつつも、過激な攘夷思想の水戸藩・徳川斉昭とも折り合いをつけました。恐るべき調整能力だったのでしょう。
――これだけの面々が一斉に推した、一橋慶喜ですが、次の将軍にはなっていません。
そのあとに幕府の大老になった彦根藩主・井伊直弼が、“一橋派の面々”を一気に抑え込みました。紀州藩・徳川慶福(家茂)を第14代将軍に付けたのです。
大名の結集ではなく、幕府の力で国を引っ張って行こうとした“剛腕”。
かつて、徳川家康に仕えた四天王・井伊直政は“井伊の赤鬼”とまで恐れられました。しかし、ご子孫も負けていないように思われます。
――そんな“井伊の赤鬼”の末裔・井伊直弼から例外的に信頼されていた、外様大名がいます。
またしても、肥前佐賀藩主・鍋島直正です。
当時、松平姓を名乗ったり、斉正という名であったりと、何かと徳川家に近い立場です。
開国通商で、国力の増強を図ろうとした大老・井伊直弼。
海軍の整備が必須と考えており、直正に相談を持ちかけていたようです。
敵の多い大老だったので「会津と佐賀くらいしか私の心を理解してくれない…」と言っていたとか。
佐賀の話を中心に描きたいので、次話「通商条約」までの時代背景の参考です。第12話「海軍伝習」もあと3回くらいで終わらせるのが目安です。
本日の内容は、以前の投稿と少し重複してしまいました。書きたいことは、色々とあるのですが、まとめるのが難しい…です。
2020年07月12日
「“大災害”と微かな希望」
こんばんは。
“本編”を描くにあたって「映像で見たいイメージ」を「文章で表現する」のは難しい!…と日々想っています。
テレビの画面ならば、一瞬で見せられるもの…
私の文章力では、皆様に伝わらないことも多いと思います。
――その一方で、皆様がお読みいだたくときは、人生の中で培ってきた経験が加味されて、映像が浮かんでいることと思います。
私が想像するより、遥かに凄い人物、美しい景色、楽しい場面が展開されているかも知れず…
受け手の皆様が、自由にイメージを持てることも、文章で伝える面白さなのかもしれません。今後ともよろしくお願いします。
――さて、経験の有無で、見える世界が変わってしまう…“災害”はその最たるものなのかもしれません。
正直、日曜の夜に持ってくる投稿としては重い!と思いましたが、“本編”の時代背景でもある“安政の大地震”について、ナレーションを入れているとお考えください。
――なるべく、その時代に生きた人間の知恵や美しい振舞いを、拾っていきたいと思います。
一般に“安政地震”と言えば、1854年から1860年に起きた一連の地震を指すようです。
そのうち、「安政の三大地震」と呼ばれる東海・南海・江戸地震が特に甚大な被害をもたらしました。
〇安政東海地震(安政元年11月4日)
西暦で言えば1854年12月23日に発生した地震。
関東地方から、四国まで広範囲に津波が到達。駿府城(静岡)や東海道の宿場町では、建物が大被害を受けていたようです。
このとき、日露和親条約の締結交渉のため、伊豆の下田(静岡)に停泊していたロシア船がありました。
ロシアの提督プチャーチンが乗る新鋭艦。“ディアナ号”という大型帆船です。

※プチャーチンが長崎に来航したときは、老朽艦“パルラダ号”に搭乗していました。
――しかし、東海地震の津波が襲来。
押し寄せる津波に“ディアナ号”は、42回転したとも言われているようです。はたして数えることは可能だったのか…という疑問は残ります。
即時、大破しなかったのは、さすがは新鋭艦というところでしょうか。しかし、船体の損傷は著しく、荒天の影響もあり、港への曳航中に“ディアナ号”は沈んでいきます…
――この状況下で提督プチャーチンが、紳士の振舞いを見せます。
なんと、自分たちの船が破損しているにも関わらず、
「船医!地元の者を診てやれ!」と指示を出します。
地震と津波で、負傷した下田の人々の救護を手伝ったようです。
さすがは提督プチャーチン。のちにロシアで教育大臣を務めるほどの人物。
このたび「大河ドラマ」登場が決まった、幕府の勘定奉行・川路聖謨もその人格を評価しています。
…その前にプチャーチンが大坂の湾内に現れたことで攘夷は過激化してますし、ロシアそのものは、かなり油断ならない動きをしていますが…
〇安政南海地震(安政元年11月5日)
西暦で言えば1854年12月24日に発生した地震。
紀州(和歌山)や摂津(大阪)など、関西地方に甚大な被害の地震。
なにせ東海地震の翌日に発生しています。そして、津波の到達。
――たぶん“本編”には登場しませんが、ここ、和歌山にも男気を見せる人物が現れます。

和歌山と言えば、湯浅という“醤油”の名産地があります。“ヤマサ醤油”の7代目・濱口儀兵衛がモデルとなった出来事があります。
「稲むらの火」という逸話をご存じでしょうか。
昔は国語の教科書に載っていたお話のようです。
――高台に住む庄屋が、津波到達の予兆に気付く。
「いかん…もはや皆に知らせるには時が無い!」
稲むらに火を放ち、村人たちに危険を知らせる庄屋。異変に気付いて避難する村人たち。
急ぎ高台に避難した村人たちが、足元を見下ろすと、津波が村を飲み込んでいた。命を救われたことに気付いた村人たちは、庄屋の判断に感謝し、ひざまずいて感謝を示した…
…モデルの方は街中に住む商人なので「津波から逃れる避難路を“稲むら”に点火して知らせた。」というのが史実に近いようです。方法の差異はあれ、命を救っていることに違いはなく…
そういえば、TBS系の「JIN-仁-」にも登場していた方のようですね。
〇安政江戸地震(安政2年10月2日)
西暦で言えば1855年11月11日に発生した地震。
東海・南海地震の翌年に、大都市・江戸で起きた直下地震。
この地震に関わるエピソードは、第11話「蝦夷探検」でも取り上げています。
――水戸藩・藤田東湖が自らの身を呈して、母を救った出来事が伝えられています。
“本編”の記事は、前回の投稿でも触れていますが、少し別の視点で。
(参考:第11話「蝦夷探検」⑦(“拓北”の決意))
地震続きによる幕府財政の窮乏について考える、枝吉神陽を描きました。
藩校で“乱闘騒ぎ”を起こした…現在で言えば、退学になった高校生(?)・大隈八太郎が神陽先生を訪ねてくる場面です。
――東海・南海地震で、各大名に対する復興費用の貸付などで、幕府の財政はかなり疲弊していたことでしょう。
そのうえで、幕府の本拠地・江戸に大地震が来てしまっては…幕府の首脳陣たちも頭を抱えたことと思います。
今までは、私もほぼ詳細を知りませんでした。
しかし、安政の大地震が無ければ、幕府の安定感はかなり違い、歴史は変わっていたかもしれません。
“本編”を描くにあたって「映像で見たいイメージ」を「文章で表現する」のは難しい!…と日々想っています。
テレビの画面ならば、一瞬で見せられるもの…
私の文章力では、皆様に伝わらないことも多いと思います。
――その一方で、皆様がお読みいだたくときは、人生の中で培ってきた経験が加味されて、映像が浮かんでいることと思います。
私が想像するより、遥かに凄い人物、美しい景色、楽しい場面が展開されているかも知れず…
受け手の皆様が、自由にイメージを持てることも、文章で伝える面白さなのかもしれません。今後ともよろしくお願いします。
――さて、経験の有無で、見える世界が変わってしまう…“災害”はその最たるものなのかもしれません。
正直、日曜の夜に持ってくる投稿としては重い!と思いましたが、“本編”の時代背景でもある“安政の大地震”について、ナレーションを入れているとお考えください。
――なるべく、その時代に生きた人間の知恵や美しい振舞いを、拾っていきたいと思います。
一般に“安政地震”と言えば、1854年から1860年に起きた一連の地震を指すようです。
そのうち、「安政の三大地震」と呼ばれる東海・南海・江戸地震が特に甚大な被害をもたらしました。
〇安政東海地震(安政元年11月4日)
西暦で言えば1854年12月23日に発生した地震。
関東地方から、四国まで広範囲に津波が到達。駿府城(静岡)や東海道の宿場町では、建物が大被害を受けていたようです。
このとき、日露和親条約の締結交渉のため、伊豆の下田(静岡)に停泊していたロシア船がありました。
ロシアの提督プチャーチンが乗る新鋭艦。“ディアナ号”という大型帆船です。

※プチャーチンが長崎に来航したときは、老朽艦“パルラダ号”に搭乗していました。
――しかし、東海地震の津波が襲来。
押し寄せる津波に“ディアナ号”は、42回転したとも言われているようです。はたして数えることは可能だったのか…という疑問は残ります。
即時、大破しなかったのは、さすがは新鋭艦というところでしょうか。しかし、船体の損傷は著しく、荒天の影響もあり、港への曳航中に“ディアナ号”は沈んでいきます…
――この状況下で提督プチャーチンが、紳士の振舞いを見せます。
なんと、自分たちの船が破損しているにも関わらず、
「船医!地元の者を診てやれ!」と指示を出します。
地震と津波で、負傷した下田の人々の救護を手伝ったようです。
さすがは提督プチャーチン。のちにロシアで教育大臣を務めるほどの人物。
このたび「大河ドラマ」登場が決まった、幕府の勘定奉行・川路聖謨もその人格を評価しています。
…その前にプチャーチンが大坂の湾内に現れたことで攘夷は過激化してますし、ロシアそのものは、かなり油断ならない動きをしていますが…
〇安政南海地震(安政元年11月5日)
西暦で言えば1854年12月24日に発生した地震。
紀州(和歌山)や摂津(大阪)など、関西地方に甚大な被害の地震。
なにせ東海地震の翌日に発生しています。そして、津波の到達。
――たぶん“本編”には登場しませんが、ここ、和歌山にも男気を見せる人物が現れます。
和歌山と言えば、湯浅という“醤油”の名産地があります。“ヤマサ醤油”の7代目・濱口儀兵衛がモデルとなった出来事があります。
「稲むらの火」という逸話をご存じでしょうか。
昔は国語の教科書に載っていたお話のようです。
――高台に住む庄屋が、津波到達の予兆に気付く。
「いかん…もはや皆に知らせるには時が無い!」
稲むらに火を放ち、村人たちに危険を知らせる庄屋。異変に気付いて避難する村人たち。
急ぎ高台に避難した村人たちが、足元を見下ろすと、津波が村を飲み込んでいた。命を救われたことに気付いた村人たちは、庄屋の判断に感謝し、ひざまずいて感謝を示した…
…モデルの方は街中に住む商人なので「津波から逃れる避難路を“稲むら”に点火して知らせた。」というのが史実に近いようです。方法の差異はあれ、命を救っていることに違いはなく…
そういえば、TBS系の「JIN-仁-」にも登場していた方のようですね。
〇安政江戸地震(安政2年10月2日)
西暦で言えば1855年11月11日に発生した地震。
東海・南海地震の翌年に、大都市・江戸で起きた直下地震。
この地震に関わるエピソードは、第11話「蝦夷探検」でも取り上げています。
――水戸藩・藤田東湖が自らの身を呈して、母を救った出来事が伝えられています。
“本編”の記事は、前回の投稿でも触れていますが、少し別の視点で。
(参考:
地震続きによる幕府財政の窮乏について考える、枝吉神陽を描きました。
藩校で“乱闘騒ぎ”を起こした…現在で言えば、退学になった高校生(?)・大隈八太郎が神陽先生を訪ねてくる場面です。
――東海・南海地震で、各大名に対する復興費用の貸付などで、幕府の財政はかなり疲弊していたことでしょう。
そのうえで、幕府の本拠地・江戸に大地震が来てしまっては…幕府の首脳陣たちも頭を抱えたことと思います。
今までは、私もほぼ詳細を知りませんでした。
しかし、安政の大地震が無ければ、幕府の安定感はかなり違い、歴史は変わっていたかもしれません。
2020年06月06日
「横浜村-1854年-(第11話プロローグ)」
こんばんは。
“本編”の現在位置ですが、幕末の1854年です。
この年明けには、長崎からロシアのプチャーチンが退去。
すぐさま、アメリカのペリーが浦賀に再来航というドタバタした新年でした。
――このとき幕府は、ペリーとの交渉場所に悩みます。
「交渉は、なるべく江戸の近くで!」というのがペリーの要求。
しかし、神奈川宿など“街道沿い”は、近隣の民衆が関わるのでマズい。
選ばれた場所が「半農半漁の寒村」とよく表現される当時の“横浜村”です。幕府はここで、ペリーと“丁々発止”のやり取りを繰り広げました。

――開港後に、すごい勢いで“国際貿易都市”となった横浜。いまや日本でも屈指の大都市です。
現地では「海のそばまで、山が迫っている街」という印象があります。
農業生産には、不向きな土地だったことと察します。逆に都市化は容易だったのかもしれません。
――そして、条約締結の交渉中に、アメリカのペリーも、ロシアのプチャーチンと同じことをします。
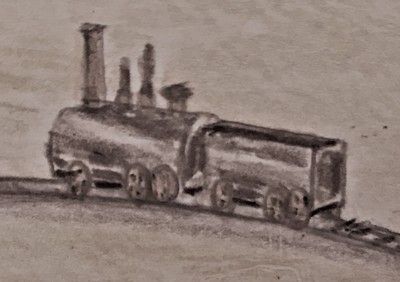
「蒸気機関車(模型)を見せつけて、技術力の差をアピール!」です。前年(1853年)に、長崎でロシアも同じアピ―ルを仕掛けています。
“本編”では佐賀藩に就職した科学者・中村奇輔が「何とか構造を見抜いてやる…」と息巻いていました。さすが佐野栄寿(常民)、よい人材をスカウトしてきています。
――ペリーの要求をなるべく最小限に抑えて、条約を締結した幕府。
1854年日米和親条約の段階では、神奈川(横浜)は開港の対象ではありません。アメリカから太平洋を渡り、航海する船に不可欠な2港だけを開きました。
・下田(大陸貿易の中継拠点)
・函館(捕鯨船の補給拠点)
この時点では、ひとまず通商の要求は拒絶しています。
少し先取りすると、日米修好通商条約の締結は、4年後の1858年です。
横浜(当初は神奈川)の開港は、この時点で決まりました。

――和親条約で、蝦夷地(北海道)の“函館”が開港されたことが、今後の展開に大きく関わります。
豊富な天然資源、広大な土地、販路としての魅力…
それに、北と言えばロシアの動きも気になります。
もともと関心の高かった蝦夷地に“国際港・函館”が出現しました。
全国の雄藩が一斉に注目したのは、言うまでもありません。
――第11話は「蝦夷探検」というタイトルにしたいと思います。
いよいよ“鎖国”状態から、日本は国際社会の荒波に入り込んでいきます。
この頃、幕府は諸大名への「大船建造の禁止」を解除しました。そして、肥前佐賀35万7千石の殿・鍋島直正が動き出します!
…幕末佐賀藩の大河ドラマは、たぶん“海”の物語でもあるのです。
なかなか情報量も多くて整理が追い付かず、“本編”に入れると長文になりがちです。今後は、本編中にも色々つぶやいていこうかな…と思っています。
“ナレーション”みたいに思っていただければ幸いです。
“本編”の現在位置ですが、幕末の1854年です。
この年明けには、長崎からロシアのプチャーチンが退去。
すぐさま、アメリカのペリーが浦賀に再来航というドタバタした新年でした。
――このとき幕府は、ペリーとの交渉場所に悩みます。
「交渉は、なるべく江戸の近くで!」というのがペリーの要求。
しかし、神奈川宿など“街道沿い”は、近隣の民衆が関わるのでマズい。
選ばれた場所が「半農半漁の寒村」とよく表現される当時の“横浜村”です。幕府はここで、ペリーと“丁々発止”のやり取りを繰り広げました。
――開港後に、すごい勢いで“国際貿易都市”となった横浜。いまや日本でも屈指の大都市です。
現地では「海のそばまで、山が迫っている街」という印象があります。
農業生産には、不向きな土地だったことと察します。逆に都市化は容易だったのかもしれません。
――そして、条約締結の交渉中に、アメリカのペリーも、ロシアのプチャーチンと同じことをします。
「蒸気機関車(模型)を見せつけて、技術力の差をアピール!」です。前年(1853年)に、長崎でロシアも同じアピ―ルを仕掛けています。
“本編”では佐賀藩に就職した科学者・中村奇輔が「何とか構造を見抜いてやる…」と息巻いていました。さすが佐野栄寿(常民)、よい人材をスカウトしてきています。
――ペリーの要求をなるべく最小限に抑えて、条約を締結した幕府。
1854年日米和親条約の段階では、神奈川(横浜)は開港の対象ではありません。アメリカから太平洋を渡り、航海する船に不可欠な2港だけを開きました。
・下田(大陸貿易の中継拠点)
・函館(捕鯨船の補給拠点)
この時点では、ひとまず通商の要求は拒絶しています。
少し先取りすると、日米修好通商条約の締結は、4年後の1858年です。
横浜(当初は神奈川)の開港は、この時点で決まりました。
――和親条約で、蝦夷地(北海道)の“函館”が開港されたことが、今後の展開に大きく関わります。
豊富な天然資源、広大な土地、販路としての魅力…
それに、北と言えばロシアの動きも気になります。
もともと関心の高かった蝦夷地に“国際港・函館”が出現しました。
全国の雄藩が一斉に注目したのは、言うまでもありません。
――第11話は「蝦夷探検」というタイトルにしたいと思います。
いよいよ“鎖国”状態から、日本は国際社会の荒波に入り込んでいきます。
この頃、幕府は諸大名への「大船建造の禁止」を解除しました。そして、肥前佐賀35万7千石の殿・鍋島直正が動き出します!
…幕末佐賀藩の大河ドラマは、たぶん“海”の物語でもあるのです。
なかなか情報量も多くて整理が追い付かず、“本編”に入れると長文になりがちです。今後は、本編中にも色々つぶやいていこうかな…と思っています。
“ナレーション”みたいに思っていただければ幸いです。
2020年01月03日
「県内の各地域を表現する②」(須古編)
こんにちは。
私事ですが、昨日、友人たちと会って来ました。
――そして友人Aから指摘を受けました。
「幕末の佐賀では、登場人物の情報を検索しなければわからない。その時点でドラマ化は難しいのではないか」
…これが“教科書本文”に掲載の賢人で物語をつなぎたい理由の1つです。
参照記事:(「STEP2:幕末の俊英たち」、「佐賀の物語を描け!(独自色③)」)
――さらに友人Aは続けます。
「佐賀を舞台にするなら“超古代ファンタジー”がいいと思うけどね。」
…たしかに佐賀には “吉野ヶ里遺跡”や“徐福伝説”もあります。
佐賀の“古代史における潜在能力”が付加価値を生み出す可能性も否めません。
――さて、“超古代ファンタジー”に限らず、佐賀には“戦国”にも語るべき歴史があります。

※須古領(現:佐賀県白石町西部)の風景
佐賀の原風景である田園地帯が見えます。
しかし、ご注目いただきたいのは写真の撮影を行っている高台です。
この高台は、今を遡ること約450年ほど昔、城攻めの死闘が行われた場所。
“肥前の熊”と呼ばれた猛将“龍造寺隆信”様が獲得した「須古城」です。
――なんだ?幕末の話ではないのか?と思われた方。少々お待ちください。ここからです。
豪放磊落な猛将龍造寺隆信様には、相棒と呼ぶべき存在がいました。
それが、冷静沈着な智将鍋島直茂様。
双璧である二将の存在により「須古城」を拠点とした龍造寺氏は北部九州の覇権を握りました。
しかし、後に戦国の勝者・徳川家康公が語ったように、
「勝つことのみ知りて負けること知らざれば害その身に至る…」との警句もあります。
――これが戦国時代…
ある戦いで龍造寺隆信様は、鍋島直茂様の忠告を聞かずに敵陣(島津軍)に深入りし過ぎ、罠に嵌ります。そして、帰らぬ人となりました。
“猛将”の代わりとなる人物のいない龍造寺氏は、実質的に鍋島直茂様が率いていくこととなりました。後に「化け猫騒動」と呼ばれる伝説が生じたように、複雑な事情も色々とあったことでしょう。
紆余曲折を経たものの、こうして佐賀藩が成立します。
龍造寺氏の家臣団をそのまま引き継いだため、佐賀藩は龍造寺一門に“自治領”を配分しました。
これが前回の“武雄領”、今回の“須古領”の起こりです。
〇須古領~“努力一徹の補佐役”鍋島安房~
――そして、幕末。
“須古領主”の家に後継ぎの男子がいなかったため、佐賀本藩より養子が迎えられます。この方が後に“殿”鍋島直正様を補佐する佐賀藩のナンバー2になります。
「鍋島安房」と呼ばれることが多い“鍋島茂真”様。実は“殿”の異母兄で、1歳年上です。

※須古領主の屋敷は「須古城」の登り口の近くにありました。
財政再建と教育改革の両方の責任者を務める、いわば“殿”の右腕。
佐賀藩を支えた“努力一徹の補佐役”です。
仕事の成果は目覚ましく、
・藩の借財整理の実行役
・ハゼ蝋や陶器など特産開発
・組織改革で経費を節減
…長崎警備の負担等で大赤字だった、佐賀藩の財政を見事に立て直します。
――また、教育改革の責任者でもあります。
仕事が終われば若い藩士に混じって藩校・弘道館で猛勉強します。
責任者が模範を示して、真剣に努力するものだから、若い藩士も頑張るしかありません。
“幕末最高の実務能力”を育てた「猛勉強する佐賀藩」の雰囲気はこの方が作ったと言っても良いでしょう。
いずれ詳しくお話しする“義祭同盟”のきっかけになる“尊王の象徴”「楠木正成」公の像を設置したのも、鍋島安房様です。
佐賀の県庁通りには、佐賀の偉人たちの銅像が並んでいます。
残念ながら、現時点では鍋島安房様の銅像はありません。
しかし、地元・白石町を始め、佐賀県内の皆様に広く業績を知っていただきたい方です。
私事ですが、昨日、友人たちと会って来ました。
――そして友人Aから指摘を受けました。
「幕末の佐賀では、登場人物の情報を検索しなければわからない。その時点でドラマ化は難しいのではないか」
…これが“教科書本文”に掲載の賢人で物語をつなぎたい理由の1つです。
参照記事:(「STEP2:幕末の俊英たち」、「佐賀の物語を描け!(独自色③)」)
――さらに友人Aは続けます。
「佐賀を舞台にするなら“超古代ファンタジー”がいいと思うけどね。」
…たしかに佐賀には “吉野ヶ里遺跡”や“徐福伝説”もあります。
佐賀の“古代史における潜在能力”が付加価値を生み出す可能性も否めません。
――さて、“超古代ファンタジー”に限らず、佐賀には“戦国”にも語るべき歴史があります。

※須古領(現:佐賀県白石町西部)の風景
佐賀の原風景である田園地帯が見えます。
しかし、ご注目いただきたいのは写真の撮影を行っている高台です。
この高台は、今を遡ること約450年ほど昔、城攻めの死闘が行われた場所。
“肥前の熊”と呼ばれた猛将“龍造寺隆信”様が獲得した「須古城」です。
――なんだ?幕末の話ではないのか?と思われた方。少々お待ちください。ここからです。
豪放磊落な猛将龍造寺隆信様には、相棒と呼ぶべき存在がいました。
それが、冷静沈着な智将鍋島直茂様。
双璧である二将の存在により「須古城」を拠点とした龍造寺氏は北部九州の覇権を握りました。
しかし、後に戦国の勝者・徳川家康公が語ったように、
「勝つことのみ知りて負けること知らざれば害その身に至る…」との警句もあります。
――これが戦国時代…
ある戦いで龍造寺隆信様は、鍋島直茂様の忠告を聞かずに敵陣(島津軍)に深入りし過ぎ、罠に嵌ります。そして、帰らぬ人となりました。
“猛将”の代わりとなる人物のいない龍造寺氏は、実質的に鍋島直茂様が率いていくこととなりました。後に「化け猫騒動」と呼ばれる伝説が生じたように、複雑な事情も色々とあったことでしょう。
紆余曲折を経たものの、こうして佐賀藩が成立します。
龍造寺氏の家臣団をそのまま引き継いだため、佐賀藩は龍造寺一門に“自治領”を配分しました。
これが前回の“武雄領”、今回の“須古領”の起こりです。
〇須古領~“努力一徹の補佐役”鍋島安房~
――そして、幕末。
“須古領主”の家に後継ぎの男子がいなかったため、佐賀本藩より養子が迎えられます。この方が後に“殿”鍋島直正様を補佐する佐賀藩のナンバー2になります。
「鍋島安房」と呼ばれることが多い“鍋島茂真”様。実は“殿”の異母兄で、1歳年上です。

※須古領主の屋敷は「須古城」の登り口の近くにありました。
財政再建と教育改革の両方の責任者を務める、いわば“殿”の右腕。
佐賀藩を支えた“努力一徹の補佐役”です。
仕事の成果は目覚ましく、
・藩の借財整理の実行役
・ハゼ蝋や陶器など特産開発
・組織改革で経費を節減
…長崎警備の負担等で大赤字だった、佐賀藩の財政を見事に立て直します。
――また、教育改革の責任者でもあります。
仕事が終われば若い藩士に混じって藩校・弘道館で猛勉強します。
責任者が模範を示して、真剣に努力するものだから、若い藩士も頑張るしかありません。
“幕末最高の実務能力”を育てた「猛勉強する佐賀藩」の雰囲気はこの方が作ったと言っても良いでしょう。
いずれ詳しくお話しする“義祭同盟”のきっかけになる“尊王の象徴”「楠木正成」公の像を設置したのも、鍋島安房様です。
佐賀の県庁通りには、佐賀の偉人たちの銅像が並んでいます。
残念ながら、現時点では鍋島安房様の銅像はありません。
しかし、地元・白石町を始め、佐賀県内の皆様に広く業績を知っていただきたい方です。
2020年01月02日
「県内の各地域を表現する①」(武雄編)
こんにちは。
ドラマの再放送を見過ぎて疲れ気味…という方も、「いや、もう仕事してます」という方もご機嫌いかがでしょうか。
さて“幕末の大河ドラマ”は「佐賀市内の話でしょ。あまり関係がない…」とお考えの県内(各地域)の皆様にお届けするシリーズを企画しました。
江戸時代の佐賀藩には“支藩”や“自治領”が多くあり、“佐賀本藩”の規模は大きくない…という特徴があります。
各地域のご領主様が領民を治めるというスタイルです。幕末に、各地域の領主も活躍します。今回は、武雄編です。
①武雄領〔前編〕~“蘭学の先駆者”鍋島茂義~
佐賀藩主“鍋島直正”様が日本の近代化を牽引した!というのが、「私の見たい大河ドラマ」第1部です。
そこで序盤で描くべき先駆者をおさらいしておきましょう。

先日、この記事(STEP1「名君の登場まで」)でご紹介した武雄領主・鍋島茂義様です。自分で西洋砲術を学んでしまう、行動力抜群の領主様です。
佐賀県西部にあり、地理的には佐賀よりさらに長崎に近い武雄。
茂義様は、西洋の文物の収集がご趣味で「お買い物リスト」が残っています。
ちなみに“蘭学兄貴”なんてお呼びしているのは、“殿”の姉上の夫(義兄)だからです。この14歳年上の“兄貴”が“鍋島直正”様に強い影響を与え、日本の近代化につながっていきます。
②武雄領〔後編〕~“朴訥な武人”鍋島茂昌~
佐賀藩の“秘密研究所”のような“武雄領”。
その真価は「私の見たい大河ドラマ」では第2部で発揮されます。
明治初期には“幕末最強の軍事技術”を持つ佐賀藩の中でも、武雄領の部隊は“武芸第一”と言われていました。
父・茂義様とは違い、洋学より武芸の子・鍋島茂昌様。
当時の佐賀藩の軍事責任者として“朴訥な武人”が部隊を率います。
 戊辰戦争が東北で続くなか、武雄部隊は天皇の“御親兵”として東京を警備していました。
戊辰戦争が東北で続くなか、武雄部隊は天皇の“御親兵”として東京を警備していました。
しかし、その頃東北では旧幕府側で最強と言われる庄内藩(山形)が新政府軍を次々と打ち破っていました。
庄内藩には大富豪・本間家があり、資金は潤沢です。そのため装備は最新式で、新政府側についた東北諸藩だけでなく、新政府軍も歯が立ちません。
しかも大名・商人・領民が一体となり、鉄の結束を誇っています。
新政府はついに佐賀藩(武雄部隊)の投入を決断しました。
武雄部隊は、新政府側に付いて窮地に陥っている久保田藩(秋田)の救援に向かいます。
そのミッションは「…無敵の庄内藩を止め、久保田藩を救うこと。」
…詳しくはいずれ語りたいと思います。このときの縁で現在も秋田市と武雄市の間には交流が続いています。
今回は以上です。一度、武雄領についても語ってみたかったので、掲載しました。いつも以上に知識が浅い点はご容赦ください。
佐賀藩のドラマをイメージすると、魅力的な登場人物・エピソードが多いので、まとめ方が難しいところです。
しかし、何とか“武雄地域”の活躍も“見たい!”ものです。
ドラマの再放送を見過ぎて疲れ気味…という方も、「いや、もう仕事してます」という方もご機嫌いかがでしょうか。
さて“幕末の大河ドラマ”は「佐賀市内の話でしょ。あまり関係がない…」とお考えの県内(各地域)の皆様にお届けするシリーズを企画しました。
江戸時代の佐賀藩には“支藩”や“自治領”が多くあり、“佐賀本藩”の規模は大きくない…という特徴があります。
各地域のご領主様が領民を治めるというスタイルです。幕末に、各地域の領主も活躍します。今回は、武雄編です。
①武雄領〔前編〕~“蘭学の先駆者”鍋島茂義~
佐賀藩主“鍋島直正”様が日本の近代化を牽引した!というのが、「私の見たい大河ドラマ」第1部です。
そこで序盤で描くべき先駆者をおさらいしておきましょう。

先日、この記事(STEP1「名君の登場まで」)でご紹介した武雄領主・鍋島茂義様です。自分で西洋砲術を学んでしまう、行動力抜群の領主様です。
佐賀県西部にあり、地理的には佐賀よりさらに長崎に近い武雄。
茂義様は、西洋の文物の収集がご趣味で「お買い物リスト」が残っています。
ちなみに“蘭学兄貴”なんてお呼びしているのは、“殿”の姉上の夫(義兄)だからです。この14歳年上の“兄貴”が“鍋島直正”様に強い影響を与え、日本の近代化につながっていきます。
②武雄領〔後編〕~“朴訥な武人”鍋島茂昌~
佐賀藩の“秘密研究所”のような“武雄領”。
その真価は「私の見たい大河ドラマ」では第2部で発揮されます。
明治初期には“幕末最強の軍事技術”を持つ佐賀藩の中でも、武雄領の部隊は“武芸第一”と言われていました。
父・茂義様とは違い、洋学より武芸の子・鍋島茂昌様。
当時の佐賀藩の軍事責任者として“朴訥な武人”が部隊を率います。

しかし、その頃東北では旧幕府側で最強と言われる庄内藩(山形)が新政府軍を次々と打ち破っていました。
庄内藩には大富豪・本間家があり、資金は潤沢です。そのため装備は最新式で、新政府側についた東北諸藩だけでなく、新政府軍も歯が立ちません。
しかも大名・商人・領民が一体となり、鉄の結束を誇っています。
新政府はついに佐賀藩(武雄部隊)の投入を決断しました。
武雄部隊は、新政府側に付いて窮地に陥っている久保田藩(秋田)の救援に向かいます。
そのミッションは「…無敵の庄内藩を止め、久保田藩を救うこと。」
…詳しくはいずれ語りたいと思います。このときの縁で現在も秋田市と武雄市の間には交流が続いています。
今回は以上です。一度、武雄領についても語ってみたかったので、掲載しました。いつも以上に知識が浅い点はご容赦ください。
佐賀藩のドラマをイメージすると、魅力的な登場人物・エピソードが多いので、まとめ方が難しいところです。
しかし、何とか“武雄地域”の活躍も“見たい!”ものです。




