2025年02月18日
「シリーズ・増える賢人の謎(⑥25賢人・駅前中央通り)」
こんばんは。年始から「今年は、佐賀の話を集中して書こう!」と始めた企画。
本シリーズも、前回から「佐賀の25賢人」の特集に入っていますが、あえて、県内でも聞かない「25賢人」という表現を試みます。
――きっかけは、県内で2018年(平成30年)に開催された、
明治維新150周年の記念イベント(「肥前さが幕末維新博覧会」)のとき。
「佐賀ゆかりの偉人・25名」の等身大のモニュメントが、佐賀駅から博覧会のメイン会場までの通りに設置されたそうです。
幕末・明治以降に活躍した、県内にゆかりのある近代の偉人たちを本シリーズでは「佐賀の“25賢人”」として振り返ってみます。

――では、佐賀駅前からの中央通りを南へと進んで参ります。
佐賀駅の南口から歩いて少し、「駅前まちかど広場」に出てきますと、この場に10名の賢人たちのモニュメントが集結しています。
幕末・明治期から受け継がれる何かがある…この風景を見ると、私は「佐賀に帰ってきた」という気分になります。
さて、この場所に集う10名。いわゆる『佐賀の七賢人』より3名多いわけですが、1人は「賢人たち」の師匠・枝吉神陽。ここまでで『八賢人』。
――残る2名も、幕末期の人物です。
以前、時代をも超えた『佐賀の12賢人』を説明しましたが、大通りにモニュメントのある25名は、先ほど語ったように、近代(幕末期以降)の方々です。
今回、紹介する2名は「名君・鍋島直正を支えた賢人たち」という立ち位置。

向かって左側が直正公の師匠・古賀穀堂先生。右側が直正公の“兄貴分”。当時の武雄領主・鍋島茂義公です。
――まず、名君の先生・古賀穀堂について
同じく江戸後期になりますが、少し時代を遡って「寛政の三博士」と呼ばれたうちの1人・古賀精里という人物が、穀堂先生の父親です。
佐賀藩出身ですが、幕府に登用され「寛政の改革」の時代に活躍した人物。今年の大河ドラマ(「べらぼう」)には登場機会があるかも…と少し期待します。
しかし、老中・松平定信とも関わりがあり、お堅い印象の強い儒学者ですので、もし登場しても同作品では良い描かれ方は無いだろう…とは思います。
――もう少しだけ、古賀穀堂先生の一族の話。
他のご家族も、どれだけ優秀だったか、に少し触れておきます。
弟・侗庵は父同様に幕府に重用され、国際情勢を熱心に研究。西洋列強との装備の実力差を理解し、「徳川政権の近代化」のために尽くします。
侗庵の子(穀堂の甥)・古賀謹一郎は、ほぼ洋学者という印象です。外国との交渉にもあたり、のち東京大学の源流になる“洋学所”の頭取に任じられます。
こうして、古賀家は三代にわたって、江戸後期から幕末の時代に日本の中枢で活躍した学者を輩出することになりました。

――そして、佐賀藩に残った古賀穀堂は、
幕末期、“近代化のトップランナー”になった佐賀ですが、その「先導役」と言ってもよい存在です。
古賀穀堂は1777年生まれですから、今年の大河ドラマの後半(寛政年間は、1789年~)あたりでは、10代の若者だと思います。
佐賀の藩校(弘道館)への着任が1806(文化3)年頃、2年後に長崎での異国船(フェートン号)侵入事件が発生、列強の動向に危機感を持ったはず。
その後、鍋島直正公が誕生すると幼少期から教育係に就きます。当時は窮地にあった、佐賀の藩政の立て直しへと“秘策”を授けていくのですね。

――もう一人は名君の兄貴分、武雄領主の鍋島茂義公。
古賀先生が「佐賀藩に蘭学の導入を働きかけた人」ならば、茂義公は「佐賀に西洋技術の導入を始めた人」でしょうか。
佐賀(本藩)に先駆け、自身の治める武雄領で、西洋式砲術や軍備を中心に蘭学を取り入れていきます。
「今から200年ほど前、佐賀の武雄には最先端技術の集積があった」と語ってもよさそうです。その存在は、まるで日本近代化への「第一走者」。
なお、佐賀藩には、現在では長崎県にある「諫早領」がありましたから、当時、日本唯一の西洋への窓口・長崎とは直結していたのですね。
――そして、武雄領主・鍋島茂義公の“蘭癖”(西洋かぶれ)が…
14歳ほど年下の鍋島直正公には相当な影響を与えたはずで、義兄(姉の夫)という関係性もあり、当ブログではよく「蘭学兄貴」と表現します。
伊豆(静岡県)の韮山反射炉で知られる、江川英龍が武雄に視察に寄るなど、幕府の開明派との関わりも深かったようです。

――“明治維新”のイメージにより案外と見過ごされがちですが、
徳川政権も欧米列強にどうにか対応していて、近代化も結構進めていたという見解もあります。その影に見え隠れする、トップランナー・佐賀藩の存在。
佐賀駅前のまちかどには幕末・明治期の『佐賀の八賢人』に、幕末黎明期の「先導役と、第一走者」を含めた10名が集っている…と見ています。
本シリーズも、前回から「佐賀の25賢人」の特集に入っていますが、あえて、県内でも聞かない「25賢人」という表現を試みます。
――きっかけは、県内で2018年(平成30年)に開催された、
明治維新150周年の記念イベント(「肥前さが幕末維新博覧会」)のとき。
「佐賀ゆかりの偉人・25名」の等身大のモニュメントが、佐賀駅から博覧会のメイン会場までの通りに設置されたそうです。
幕末・明治以降に活躍した、県内にゆかりのある近代の偉人たちを本シリーズでは「佐賀の“25賢人”」として振り返ってみます。
――では、佐賀駅前からの中央通りを南へと進んで参ります。
佐賀駅の南口から歩いて少し、「駅前まちかど広場」に出てきますと、この場に10名の賢人たちのモニュメントが集結しています。
幕末・明治期から受け継がれる何かがある…この風景を見ると、私は「佐賀に帰ってきた」という気分になります。
さて、この場所に集う10名。いわゆる『佐賀の七賢人』より3名多いわけですが、1人は「賢人たち」の師匠・枝吉神陽。ここまでで『八賢人』。
――残る2名も、幕末期の人物です。
以前、時代をも超えた『佐賀の12賢人』を説明しましたが、大通りにモニュメントのある25名は、先ほど語ったように、近代(幕末期以降)の方々です。
今回、紹介する2名は「名君・鍋島直正を支えた賢人たち」という立ち位置。

向かって左側が直正公の師匠・古賀穀堂先生。右側が直正公の“兄貴分”。当時の武雄領主・鍋島茂義公です。
――まず、名君の先生・古賀穀堂について
同じく江戸後期になりますが、少し時代を遡って「寛政の三博士」と呼ばれたうちの1人・古賀精里という人物が、穀堂先生の父親です。
佐賀藩出身ですが、幕府に登用され「寛政の改革」の時代に活躍した人物。今年の大河ドラマ(「べらぼう」)には登場機会があるかも…と少し期待します。
しかし、老中・松平定信とも関わりがあり、お堅い印象の強い儒学者ですので、もし登場しても同作品では良い描かれ方は無いだろう…とは思います。
――もう少しだけ、古賀穀堂先生の一族の話。
他のご家族も、どれだけ優秀だったか、に少し触れておきます。
弟・侗庵は父同様に幕府に重用され、国際情勢を熱心に研究。西洋列強との装備の実力差を理解し、「徳川政権の近代化」のために尽くします。
侗庵の子(穀堂の甥)・古賀謹一郎は、ほぼ洋学者という印象です。外国との交渉にもあたり、のち東京大学の源流になる“洋学所”の頭取に任じられます。
こうして、古賀家は三代にわたって、江戸後期から幕末の時代に日本の中枢で活躍した学者を輩出することになりました。
――そして、佐賀藩に残った古賀穀堂は、
幕末期、“近代化のトップランナー”になった佐賀ですが、その「先導役」と言ってもよい存在です。
古賀穀堂は1777年生まれですから、今年の大河ドラマの後半(寛政年間は、1789年~)あたりでは、10代の若者だと思います。
佐賀の藩校(弘道館)への着任が1806(文化3)年頃、2年後に長崎での異国船(フェートン号)侵入事件が発生、列強の動向に危機感を持ったはず。
その後、鍋島直正公が誕生すると幼少期から教育係に就きます。当時は窮地にあった、佐賀の藩政の立て直しへと“秘策”を授けていくのですね。
――もう一人は名君の兄貴分、武雄領主の鍋島茂義公。
古賀先生が「佐賀藩に蘭学の導入を働きかけた人」ならば、茂義公は「佐賀に西洋技術の導入を始めた人」でしょうか。
佐賀(本藩)に先駆け、自身の治める武雄領で、西洋式砲術や軍備を中心に蘭学を取り入れていきます。
「今から200年ほど前、佐賀の武雄には最先端技術の集積があった」と語ってもよさそうです。その存在は、まるで日本近代化への「第一走者」。
なお、佐賀藩には、現在では長崎県にある「諫早領」がありましたから、当時、日本唯一の西洋への窓口・長崎とは直結していたのですね。
――そして、武雄領主・鍋島茂義公の“蘭癖”(西洋かぶれ)が…
14歳ほど年下の鍋島直正公には相当な影響を与えたはずで、義兄(姉の夫)という関係性もあり、当ブログではよく「蘭学兄貴」と表現します。
伊豆(静岡県)の韮山反射炉で知られる、江川英龍が武雄に視察に寄るなど、幕府の開明派との関わりも深かったようです。
――“明治維新”のイメージにより案外と見過ごされがちですが、
徳川政権も欧米列強にどうにか対応していて、近代化も結構進めていたという見解もあります。その影に見え隠れする、トップランナー・佐賀藩の存在。
佐賀駅前のまちかどには幕末・明治期の『佐賀の八賢人』に、幕末黎明期の「先導役と、第一走者」を含めた10名が集っている…と見ています。
2025年02月04日
「シリーズ・増える賢人の謎(⑤佐賀の“25賢人”序章)」
こんばんは。淡々と進めて参ります、本シリーズ。とても寒い2月に入り、佐賀でも「雪の、積もるとね?積もらんとね?」と気をもむ事も多いことでしょう。
そんな佐賀の風を感じられぬまま、私の遠い街での歳月は流れていきます。
なお、当ブログを見慣れた方はお気付きかもしれませんが、今回は「書きたいように書く」パターンの記事です。
――さて、私の住む街で「佐賀」という地名を聞くことは…
極端に少ないのですが、佐賀県庁もPRを頑張ってくださっているようです。
最近、もっとも衝撃を受けた企画が、題して『ベルサイユの“さが”』。
参考(外部リンク先):佐賀県庁ホームページ
あの超有名な少女漫画の名作『ベルサイユのばら』が、50周年記念の映画を公開する時期にあわせて…
佐賀県がコラボを仕掛けるという“暴挙”に出ています。(もちろん、内心では“快挙”だと思っています。)
――今年(2025年)の大河ドラマ『べらぼう』っぽく語れば、
「県庁のやろう、まったく油断も隙もありゃしねぇな!この、べらぼうめ!」とでも言うのでしょうか。
佐賀県庁のコラボ(共同の企画)は、結構“攻めた”広報が多いのが特色らしく、私がこういう企画を大変面白がっているのは、言うまでもありません。

※有田ポーセリンパーク(ベルサイユ宮殿ではありません)
――なお、『ベルサイユのばら』の時代設定は…
主にフランス革命(1789年)までの時期だと思われますので、わりと大河ドラマ『べらぼう』の時代設定とかぶっています。
日本では“綺麗事よりも経済”の田沼意次が失脚し、“清廉潔白・質素倹約”の松平定信が寛政の改革を指揮した頃ですね。
いま大河ドラマを視聴されている方は、それぞれ渡辺謙さんと、寺田心さんに置き換えていただけると、人物のイメージが掴みやすいかもしれません。
――そのフランス革命により、“ルイ王朝”は滅び…
『ベルサイユのばら』の登場人物たちは、この革命の嵐の中で、美しく散っていく設定のようです。
10年ばかり続いたという、その革命期の混乱を収拾し、皇帝の座に就いたのが、ナポレオン1世。
「余の辞書に不可能の文字は無い」とばかりに、全ヨーロッパの征服を目指して戦い続けます。
――なんと、その余波は日本の長崎港にまで及び…

のちに江戸幕府の「鎖国」と語られる、徳川政権による外交の管理体制。唯一、西洋への窓口だった国はオランダ。
しかし、このときのオランダと言えば、実質的にフランス(皇帝はナポレオン)の支配下にあったそうです。
ナポレオンと全面対決をしていたイギリスは、敵国陣営にいるオランダ船も世界中で追いかけ回しており…その他諸事情あって、イギリスの軍艦・フェートン号は、長崎港に侵入してきます。
――その運命の1808年。長崎港の警備担当は、佐賀藩。
「ずっと長崎ば警備しよったら、予算の足らんもんね~」とばかりに、佐賀は人員体制を勝手に10分の1に減らしていました。
武装も劣るうえに、軍勢も投入できない。幕府の長崎奉行所は、イギリス船に対して為す術がありません。
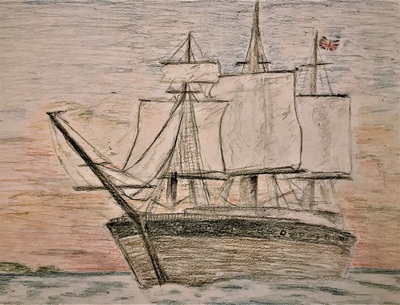
「この、べらぼうめ!」でお叱りが済むわけがなく、幕府から佐賀は、第九代藩主の謹慎・責任者の切腹など厳しい処罰を受けます。
――ここから一足早く、佐賀藩の幕末が始まった…
はい、ここでようやく本題に戻ります。
次回から、「佐賀県の偉人・25人」の特集に入る予定です。「佐賀の七賢人」より前の世代の2名から紹介していきたいと思います。
※本記事について、私はヨーロッパ史に疎く(「ブルボン朝」の史実寄りに書くか迷いました)、『ベルばら』も、ほぼ見たことが無いので、中途半端な記述は「この、べらぼうめ!」ぐらいのお言葉にて、ご容赦ください。
また、2025年大河ドラマの正式名称は『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』ですが省略して記載しています。
そんな佐賀の風を感じられぬまま、私の遠い街での歳月は流れていきます。
なお、当ブログを見慣れた方はお気付きかもしれませんが、今回は「書きたいように書く」パターンの記事です。
――さて、私の住む街で「佐賀」という地名を聞くことは…
極端に少ないのですが、佐賀県庁もPRを頑張ってくださっているようです。
最近、もっとも衝撃を受けた企画が、題して『ベルサイユの“さが”』。
参考(外部リンク先):佐賀県庁ホームページ
あの超有名な少女漫画の名作『ベルサイユのばら』が、50周年記念の映画を公開する時期にあわせて…
佐賀県がコラボを仕掛けるという“暴挙”に出ています。(もちろん、内心では“快挙”だと思っています。)
――今年(2025年)の大河ドラマ『べらぼう』っぽく語れば、
「県庁のやろう、まったく油断も隙もありゃしねぇな!この、べらぼうめ!」とでも言うのでしょうか。
佐賀県庁のコラボ(共同の企画)は、結構“攻めた”広報が多いのが特色らしく、私がこういう企画を大変面白がっているのは、言うまでもありません。
※有田ポーセリンパーク(ベルサイユ宮殿ではありません)
――なお、『ベルサイユのばら』の時代設定は…
主にフランス革命(1789年)までの時期だと思われますので、わりと大河ドラマ『べらぼう』の時代設定とかぶっています。
日本では“綺麗事よりも経済”の田沼意次が失脚し、“清廉潔白・質素倹約”の松平定信が寛政の改革を指揮した頃ですね。
いま大河ドラマを視聴されている方は、それぞれ渡辺謙さんと、寺田心さんに置き換えていただけると、人物のイメージが掴みやすいかもしれません。
――そのフランス革命により、“ルイ王朝”は滅び…
『ベルサイユのばら』の登場人物たちは、この革命の嵐の中で、美しく散っていく設定のようです。
10年ばかり続いたという、その革命期の混乱を収拾し、皇帝の座に就いたのが、ナポレオン1世。
「余の辞書に不可能の文字は無い」とばかりに、全ヨーロッパの征服を目指して戦い続けます。
――なんと、その余波は日本の長崎港にまで及び…

のちに江戸幕府の「鎖国」と語られる、徳川政権による外交の管理体制。唯一、西洋への窓口だった国はオランダ。
しかし、このときのオランダと言えば、実質的にフランス(皇帝はナポレオン)の支配下にあったそうです。
ナポレオンと全面対決をしていたイギリスは、敵国陣営にいるオランダ船も世界中で追いかけ回しており…その他諸事情あって、イギリスの軍艦・フェートン号は、長崎港に侵入してきます。
――その運命の1808年。長崎港の警備担当は、佐賀藩。
「ずっと長崎ば警備しよったら、予算の足らんもんね~」とばかりに、佐賀は人員体制を勝手に10分の1に減らしていました。
武装も劣るうえに、軍勢も投入できない。幕府の長崎奉行所は、イギリス船に対して為す術がありません。
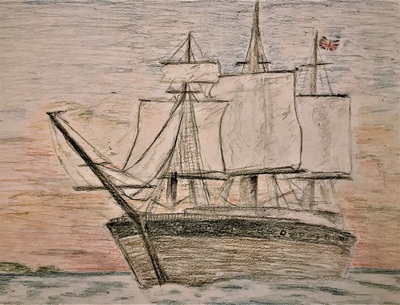
「この、べらぼうめ!」でお叱りが済むわけがなく、幕府から佐賀は、第九代藩主の謹慎・責任者の切腹など厳しい処罰を受けます。
――ここから一足早く、佐賀藩の幕末が始まった…
はい、ここでようやく本題に戻ります。
次回から、「佐賀県の偉人・25人」の特集に入る予定です。「佐賀の七賢人」より前の世代の2名から紹介していきたいと思います。
※本記事について、私はヨーロッパ史に疎く(「ブルボン朝」の史実寄りに書くか迷いました)、『ベルばら』も、ほぼ見たことが無いので、中途半端な記述は「この、べらぼうめ!」ぐらいのお言葉にて、ご容赦ください。
また、2025年大河ドラマの正式名称は『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』ですが省略して記載しています。




