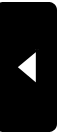2020年03月18日
第6話「鉄製大砲」⑨
こんばんは。
大隈重信(八太郎)は、後に貿易や財政で活躍します。そんな「数字に強い」大隈は、父・信保の能力を受け継いだのかもしれません。
――佐賀城下の“築地”で、反射炉の建設が進んでいた頃。
鋳造が進めば、大砲の試験の回数も増える。実際に砲弾を扱う部隊も大忙しとなっていた。
砲術の部隊長である大隈信保。演習場で作業を仕切る。
「倉庫の中身を入れ替えいたすぞ!」
「はっ!」
部下たちが倉庫から荷物を運び出す。
「ひと息入れるか…」
信保は、ふと気を抜いた。
――季節は、初夏である。この日は照り付ける陽射しが厳しい。
何気なく、信保が日陰に入った。そのとき。
グワァン…グワァン…
一時置きしていた資材が倒れ込んできた。
「!」
気づいたときには、頭を強打していた信保。
その場に倒れ込んだ。
――大隈さま!しっかりなさいませ!
部下たちの声が遠く聞こえる。
目を開けた大隈信保。
「いかん…いかん。まるで一本取られたようじゃな…」
まるで剣術の稽古で負けたような事を言う。
「大隈さん!驚かさないでくださいよ!」
ベテランの部下が助け起こす。信保に冗談を言う余裕があると見て、苦笑する。
――その日は予定を切り上げ、帰宅した大隈信保。

「いま、戻った。」
信保は、いつものように帰宅を告げる。
「お帰りなさいませ、父上!」
子の八太郎は、藩校から帰ってきていた。
「少し…疲れているようだ。母上によろしくな。」
信保は、そのまま横になった。
そして、二度と目を開けることはなかった。
――佐賀城下・築地に話を戻す。
「鋳立方の七人」にも、大隈信保の訃報が届いた。
「大隈どの…なにゆえだ…」
信保から絶大な評価をされていた、算術家の馬場が嘆く。
そして、第一報を聞いた、会計の田代もうつむいたままだ。
“数字”に関わる仕事の2人には、信保は数少ない“理解者”だった。
重苦しい空気が“チーム”全体を包む。
リーダー・本島は、振り絞るように言った。
「作業を…、進めよう。」
――ほどなく構築中の反射炉では、充分な熱を得られないと判明した。
設計は見直しを余儀なくされていた。
まず、高温を出すために、炉の構造など調整が要る。
「いま一度、計算いたす…」
算術家の馬場。あまり元気が無いが、再び筆を手にした。

――そして、季節は移ろい、冬となっていた。
刀鍛冶・橋本、無言で炉を見つめる。
周囲の空気にも高熱が伝播する。真っ赤な銑鉄。
「やはり鉄が、溶けきっておらんばい。」
「素材の見直しも、手配せねばなりませぬな。」
会計の田代は、いつもの冷静さを取り戻していた。
あらためて島根から銑鉄を、肥後(熊本)から良質の木炭を調達する段取りを始めた。
日本初の実用反射炉、何とか「鉄を溶かす」段取りは整い始めた。
しかし、この“プロジェクト”には、さらなる苦難が待ち受けているのである。
(続く)
大隈重信(八太郎)は、後に貿易や財政で活躍します。そんな「数字に強い」大隈は、父・信保の能力を受け継いだのかもしれません。
――佐賀城下の“築地”で、反射炉の建設が進んでいた頃。
鋳造が進めば、大砲の試験の回数も増える。実際に砲弾を扱う部隊も大忙しとなっていた。
砲術の部隊長である大隈信保。演習場で作業を仕切る。
「倉庫の中身を入れ替えいたすぞ!」
「はっ!」
部下たちが倉庫から荷物を運び出す。
「ひと息入れるか…」
信保は、ふと気を抜いた。
――季節は、初夏である。この日は照り付ける陽射しが厳しい。
何気なく、信保が日陰に入った。そのとき。
グワァン…グワァン…
一時置きしていた資材が倒れ込んできた。
「!」
気づいたときには、頭を強打していた信保。
その場に倒れ込んだ。
――大隈さま!しっかりなさいませ!
部下たちの声が遠く聞こえる。
目を開けた大隈信保。
「いかん…いかん。まるで一本取られたようじゃな…」
まるで剣術の稽古で負けたような事を言う。
「大隈さん!驚かさないでくださいよ!」
ベテランの部下が助け起こす。信保に冗談を言う余裕があると見て、苦笑する。
――その日は予定を切り上げ、帰宅した大隈信保。

「いま、戻った。」
信保は、いつものように帰宅を告げる。
「お帰りなさいませ、父上!」
子の八太郎は、藩校から帰ってきていた。
「少し…疲れているようだ。母上によろしくな。」
信保は、そのまま横になった。
そして、二度と目を開けることはなかった。
――佐賀城下・築地に話を戻す。
「鋳立方の七人」にも、大隈信保の訃報が届いた。
「大隈どの…なにゆえだ…」
信保から絶大な評価をされていた、算術家の馬場が嘆く。
そして、第一報を聞いた、会計の田代もうつむいたままだ。
“数字”に関わる仕事の2人には、信保は数少ない“理解者”だった。
重苦しい空気が“チーム”全体を包む。
リーダー・本島は、振り絞るように言った。
「作業を…、進めよう。」
――ほどなく構築中の反射炉では、充分な熱を得られないと判明した。
設計は見直しを余儀なくされていた。
まず、高温を出すために、炉の構造など調整が要る。
「いま一度、計算いたす…」
算術家の馬場。あまり元気が無いが、再び筆を手にした。
――そして、季節は移ろい、冬となっていた。
刀鍛冶・橋本、無言で炉を見つめる。
周囲の空気にも高熱が伝播する。真っ赤な銑鉄。
「やはり鉄が、溶けきっておらんばい。」
「素材の見直しも、手配せねばなりませぬな。」
会計の田代は、いつもの冷静さを取り戻していた。
あらためて島根から銑鉄を、肥後(熊本)から良質の木炭を調達する段取りを始めた。
日本初の実用反射炉、何とか「鉄を溶かす」段取りは整い始めた。
しかし、この“プロジェクト”には、さらなる苦難が待ち受けているのである。
(続く)
2020年03月17日
第6話「鉄製大砲」⑧
こんばんは。
殿・鍋島直正の気迫が届いたのか、幕府は長崎の沖合に佐賀藩の砲台を築く許可を出しました。
――リーダー本島が、岩田(神埼)の演習場に駆け込む。
「公儀(幕府)からお許しが出た!」
読解の鉄人・田中。落ち着いたまとめ役でもある。
「皆様方!いよいよでござるな。」
「腕が鳴るったい!」
肥前刀鍛冶・橋本である。“鉄を溶かす”担当。
橋本は、この事業の花形の1人と言っていい。
なぜなら“反射炉”は鉄を溶かす設備だからだ。
――砲台には、備え付ける大砲が必要である。そして、佐賀城下の“築地(ついじ)”に日本初の実用反射炉を築くことになった。
「絵図面(設計図)は、こちらにござる。」
算術家・馬場栄作。
まず、高温を出せる炉の設計を行っていた。
「では、手筈(てはず)どおり、煉瓦(レンガ)の支度を!」
会計の田代である。
物品を手配する度に“お金”が要るため、進捗の管理は田代の仕事になっていた。
「炉造りに長けた者は、一通り集めておるばい。」
鋳物師・谷口。
有田や伊万里から、炉の構築に定評のある陶工を選び、打合せを進めている。
――ついに「鋳立方の七人」が集結!…いや1人足りない。

翻訳の達人・杉谷雍助。長崎に来ている。
杉谷は、翻訳した内容が技術的に正しいか、出島まで専門家の意見を聴きにきていた。
「ここに、我らの砲が据え付けられるのだな!」
長崎の海を見遣る。
実は、砲台の建設現場にも足を伸ばしていた。
――ドボン!ドボン!
神ノ島地区の“四郎ケ島”である。
浅瀬に次々と大石が投げ込まれる。
佐賀藩は長崎でも、海に通路を造る大工事に着手していた。
神ノ島と隣接する“四郎ケ島”を地続きにしてしまい防備を固める。
「台場はお任せあれ!目の覚めるような“鉄銃”(大砲)をお届けいただきたい!」
大勢の人足を動員し、工事を仕切る担当者。
ニッ!と笑って、大砲への期待を口にした。
――佐賀城下・築地に拠点を移し、反射炉の建設が進む。

積みあがっていく耐火レンガ。
慌ただしく、現場が動いていく。
「まず、鉄を溶かさねば、話にならぬ…」
リーダー・本島は、伊豆の韮山で実験用反射炉を見学している。
温度が上がらず、あまり鉄が溶けていなかった。
「私が幾度でも計算しなおそう。正しき答えが出るまで。」
算術家・馬場から話しかけてくるのは、珍しい。
「かたじけない。馬場どの、頼りにしておる。」
本島にかかるリーダーの重圧。周囲もそれを分かっている様子だ。
――そこで、会計の田代が走り込んでくる。
「大変です!」
「田代どの!いかがした…」
いつも冷静な田代が慌てている。本島は息を呑んだ。
「大隈どのが…」
大隈信保は大砲が鋳造できた後に、試射を行い実験を担当する役割である。田代の表情から、良くない知らせであることは明らかだった。
(続く)
殿・鍋島直正の気迫が届いたのか、幕府は長崎の沖合に佐賀藩の砲台を築く許可を出しました。
――リーダー本島が、岩田(神埼)の演習場に駆け込む。
「公儀(幕府)からお許しが出た!」
読解の鉄人・田中。落ち着いたまとめ役でもある。
「皆様方!いよいよでござるな。」
「腕が鳴るったい!」
肥前刀鍛冶・橋本である。“鉄を溶かす”担当。
橋本は、この事業の花形の1人と言っていい。
なぜなら“反射炉”は鉄を溶かす設備だからだ。
――砲台には、備え付ける大砲が必要である。そして、佐賀城下の“築地(ついじ)”に日本初の実用反射炉を築くことになった。
「絵図面(設計図)は、こちらにござる。」
算術家・馬場栄作。
まず、高温を出せる炉の設計を行っていた。
「では、手筈(てはず)どおり、煉瓦(レンガ)の支度を!」
会計の田代である。
物品を手配する度に“お金”が要るため、進捗の管理は田代の仕事になっていた。
「炉造りに長けた者は、一通り集めておるばい。」
鋳物師・谷口。
有田や伊万里から、炉の構築に定評のある陶工を選び、打合せを進めている。
――ついに「鋳立方の七人」が集結!…いや1人足りない。

翻訳の達人・杉谷雍助。長崎に来ている。
杉谷は、翻訳した内容が技術的に正しいか、出島まで専門家の意見を聴きにきていた。
「ここに、我らの砲が据え付けられるのだな!」
長崎の海を見遣る。
実は、砲台の建設現場にも足を伸ばしていた。
――ドボン!ドボン!
神ノ島地区の“四郎ケ島”である。
浅瀬に次々と大石が投げ込まれる。
佐賀藩は長崎でも、海に通路を造る大工事に着手していた。
神ノ島と隣接する“四郎ケ島”を地続きにしてしまい防備を固める。
「台場はお任せあれ!目の覚めるような“鉄銃”(大砲)をお届けいただきたい!」
大勢の人足を動員し、工事を仕切る担当者。
ニッ!と笑って、大砲への期待を口にした。
――佐賀城下・築地に拠点を移し、反射炉の建設が進む。

積みあがっていく耐火レンガ。
慌ただしく、現場が動いていく。
「まず、鉄を溶かさねば、話にならぬ…」
リーダー・本島は、伊豆の韮山で実験用反射炉を見学している。
温度が上がらず、あまり鉄が溶けていなかった。
「私が幾度でも計算しなおそう。正しき答えが出るまで。」
算術家・馬場から話しかけてくるのは、珍しい。
「かたじけない。馬場どの、頼りにしておる。」
本島にかかるリーダーの重圧。周囲もそれを分かっている様子だ。
――そこで、会計の田代が走り込んでくる。
「大変です!」
「田代どの!いかがした…」
いつも冷静な田代が慌てている。本島は息を呑んだ。
「大隈どのが…」
大隈信保は大砲が鋳造できた後に、試射を行い実験を担当する役割である。田代の表情から、良くない知らせであることは明らかだった。
(続く)
2020年03月16日
第6話「鉄製大砲」⑦
こんばんは。本日は鍋島直正の嫡子、淳一郎が登場します。
――そわそわする、殿・鍋島直正。
目の前には蘭方医、そして、4歳ぐらいの男の子。
貢姫(みつひめ)の弟で、淳一郎という。
「えすか(怖い)です、おちちうえさま…」
“種痘”とは、“天然痘”の予防接種である。
「淳一郎よ!そなたは、我が後継ぎであるぞ。堂々としておれ。」
直正は“種痘”を受ける、淳一郎に対して「恐れるな」と諭す。
「はい、おちちうえさま。」
若君の淳一郎は、後にイタリア公使となる鍋島直大である。
但し、今は“謎の注射”を怖がる男の子と思ってほしい。
――このワクチンの素は、オランダから長崎を通じて手に入れた。
佐賀の藩医・楢林宗建。入手までの困難に立ち向かった。
「何だ!これは!腐っておったのか…」
もとはウシの“天然痘”の膿から、ワクチン(痘苗)を作る予定だった。しかし、海外から運んでいるうちにダメになってしまう。
「水分があるからいかんのだ…。」
楢林の知恵で、液状の膿ではなく、乾燥した“かさぶた”を取り寄せ、ワクチンを製造したのである。
――その時、日本を救うワクチンは佐賀にあった。いま若君に“種痘”を施す。西洋医学の夜明けである。

「淳一郎よ!先生を信じよ!」
「はい!おちちうえさま!」
鍋島直正、嫡子・淳一郎には、厳しい父親であろうとした。
ただ、心配がまるで隠せていない。
「淳一郎よ!落ち着け。」
むしろ、淳一郎は落ち着いている。担当する藩医・大石良英が直正を諭す。
「殿、お静かに。」
――さて、大砲の話に戻る。佐賀ではドタバタしたが、江戸での直正を見てほしい。
江戸城。直正が強い調子で語っている。
「かねてからのお願いでござる。長崎の台場は、国の存亡に関わる急務でござる。」
話している相手は、老中首座・阿部正弘である。
「肥前守(直正)どの、さすがの見識にござる。」
直正が続ける。
「異国船と相対するには、沖合から守ることが肝要でござる!」
阿部正弘は、そのまま直正の話を聞き続ける。
「恐れ入った。感服いたすばかりじゃ。」
――この阿部正弘。いわゆる“調整型”リーダーである。ほぼ自己主張をしない。
周囲の意見を聴きまくって、その中から“最善手”を選ぶタイプである。
直正の熱弁を聴き続ける、阿部。やや太めで温厚な印象である。
「肥前(直正)どのは、実に頼もしい。」
直正は、ふと不安になった。
「阿部さまは、本当に分かっているのだろうか。」という心の声は封じ込めて、砲台の重要性を説く。
また返事は先延ばしになったが、直正の「佐賀藩の独力でやります!」との宣言は効いていたようだ。ほどなく長崎の沖合にある、伊王島・神ノ島の砲台整備の許可が出たのである。
(続く)
――そわそわする、殿・鍋島直正。
目の前には蘭方医、そして、4歳ぐらいの男の子。
貢姫(みつひめ)の弟で、淳一郎という。
「えすか(怖い)です、おちちうえさま…」
“種痘”とは、“天然痘”の予防接種である。
「淳一郎よ!そなたは、我が後継ぎであるぞ。堂々としておれ。」
直正は“種痘”を受ける、淳一郎に対して「恐れるな」と諭す。
「はい、おちちうえさま。」
若君の淳一郎は、後にイタリア公使となる鍋島直大である。
但し、今は“謎の注射”を怖がる男の子と思ってほしい。
――このワクチンの素は、オランダから長崎を通じて手に入れた。
佐賀の藩医・楢林宗建。入手までの困難に立ち向かった。
「何だ!これは!腐っておったのか…」
もとはウシの“天然痘”の膿から、ワクチン(痘苗)を作る予定だった。しかし、海外から運んでいるうちにダメになってしまう。
「水分があるからいかんのだ…。」
楢林の知恵で、液状の膿ではなく、乾燥した“かさぶた”を取り寄せ、ワクチンを製造したのである。
――その時、日本を救うワクチンは佐賀にあった。いま若君に“種痘”を施す。西洋医学の夜明けである。

「淳一郎よ!先生を信じよ!」
「はい!おちちうえさま!」
鍋島直正、嫡子・淳一郎には、厳しい父親であろうとした。
ただ、心配がまるで隠せていない。
「淳一郎よ!落ち着け。」
むしろ、淳一郎は落ち着いている。担当する藩医・大石良英が直正を諭す。
「殿、お静かに。」
――さて、大砲の話に戻る。佐賀ではドタバタしたが、江戸での直正を見てほしい。
江戸城。直正が強い調子で語っている。
「かねてからのお願いでござる。長崎の台場は、国の存亡に関わる急務でござる。」
話している相手は、老中首座・阿部正弘である。
「肥前守(直正)どの、さすがの見識にござる。」
直正が続ける。
「異国船と相対するには、沖合から守ることが肝要でござる!」
阿部正弘は、そのまま直正の話を聞き続ける。
「恐れ入った。感服いたすばかりじゃ。」
――この阿部正弘。いわゆる“調整型”リーダーである。ほぼ自己主張をしない。
周囲の意見を聴きまくって、その中から“最善手”を選ぶタイプである。
直正の熱弁を聴き続ける、阿部。やや太めで温厚な印象である。
「肥前(直正)どのは、実に頼もしい。」
直正は、ふと不安になった。
「阿部さまは、本当に分かっているのだろうか。」という心の声は封じ込めて、砲台の重要性を説く。
また返事は先延ばしになったが、直正の「佐賀藩の独力でやります!」との宣言は効いていたようだ。ほどなく長崎の沖合にある、伊王島・神ノ島の砲台整備の許可が出たのである。
(続く)
2020年03月15日
第6話「鉄製大砲」⑥
こんにちは。前回の続きです。
舞台は、佐賀藩の砲術演習場の片隅からスタートします。
――火薬庫や部品を保管する倉庫で、ガサガサと音がする。
事務方の侍・田代が、火薬等の在庫の確認を行う。
「大隈さま、ちょうど良いところに。」
「田代どのか。ご苦労であるな。」と大隈が応じる。
「この“硝石”の仕入値は、何処を見ればわかりますか。」
「それは、長崎で仕入れた物だが…」
――田代は、原材料の仕入先や値段を調査し、製造・試験の工程そのものを検証していた。
「田代どの…もしや。」
「ええ、早晩“火術方”の資金は底をつきます。」
未知の領域に挑むため、佐賀藩の研究費はきわめて高額だった。
たとえ殿の命令でも、資金が不足となれば、藩内の保守派から風当たりは強まる。「お前たちが懐に入れているのではないか!」という目で見られるだろう。
――「鋳立方の七人」の七人目は、田代孫三郎。会計担当である。
「田代どの!やはり“数字”は大切でござるな!」
“算術”や“会計”に、やたらと感銘を受ける大隈信保。
大隈が好意的なので、田代も喜んでいる様子だ。
「ええ、先を見通すには、お金の回りを掴むことと心得ております。」
もともと田代は、長崎砲台の経費を削るために「倹約の鬼」として、勘定方に育成された。そして“蘭学の勘所(ポイント)”を抑え、冷たい視点で製造部門を見つめてきた。
今や“火術方”に引き抜かれた、田代。かえって製造・開発側の強い味方となったのである。
――舞台は、佐賀城下に戻る。
藩校に通う子どもたちが遊んでいる。しかし、徐々に雲行きがあやしくなり、喧嘩の予感が漂う。
「やい、八太郎!」
距離を取って、大隈八太郎が対立するグループのリーダー(通称:たかうじ)と向かい合う。
――ここで、八太郎は母の言葉を思い出す。
「いいですか!八太郎。喧嘩になりそうな時には、まず“お念仏”を十回唱えなさい!」
母との約束だ。八太郎は「なむ…なむ…」と、実に小声で念仏を唱えた。

――すると、樹の間をスーッと風が抜ける音がした。
ふと八太郎は、以前、母の読んでくれた「太平記」の一節を想い出す。戦の場面ではなかったので、あまり面白くなかった所だ。
以下、八太郎の回想(母・三井子の朗読)である。
~「太平記」より“正成の進言”~
――時は南北朝時代。
後醍醐天皇の軍勢は、一旦、足利尊氏を都から追い出した。
しかし、九州で力を盛り返した足利方は、再び都に攻め上る構えである。
――朝廷の会議の席である。
楠木正成が話を切り出す。
「武士たちは、足利尊氏を慕っております。」
帝の取り巻きの公家たちがどよめく。
「帝のご威光よりも、尊氏ごときを慕うと申すか!」
正成は続ける。
「ここは争いを避け、帝の臣下の列に、尊氏を戻すべきかと存じます。」
公家たちはさらに騒ぐ。
「尊氏と和睦しろと申すか!」
「楠木は、臆病者じゃ!」
戦の現実が見えていない公家たち。楠木正成に罵声を浴びせたのである。
~八太郎の回想の設定終了~
――サワサワと樹の枝が揺れる。
相手方が、やいやいと挑発してくる。
「八太郎!やるか!」
八太郎は、ビシッと一言を放った。
「いや、戦わない!」
相手は意表を突かれて、一瞬呆けたようになった。
「…お…おぅ、そうか。戦わないか…まぁ、いいだろう。」
――大隈家。父・信保が帰宅する。
「おう、八太郎!帰ったぞ。」
「父上!」
「今日は、傷を負うておらぬな!」
「はい。八太郎は争いませんでした!」
「そうか。八太郎も少し“お兄さん”になったな。偉いぞ。」
大隈信保、子・八太郎の両肩をポンポンと叩く。
八太郎は、少し照れて笑った。
(続く)
舞台は、佐賀藩の砲術演習場の片隅からスタートします。
――火薬庫や部品を保管する倉庫で、ガサガサと音がする。
事務方の侍・田代が、火薬等の在庫の確認を行う。
「大隈さま、ちょうど良いところに。」
「田代どのか。ご苦労であるな。」と大隈が応じる。
「この“硝石”の仕入値は、何処を見ればわかりますか。」
「それは、長崎で仕入れた物だが…」
――田代は、原材料の仕入先や値段を調査し、製造・試験の工程そのものを検証していた。
「田代どの…もしや。」
「ええ、早晩“火術方”の資金は底をつきます。」
未知の領域に挑むため、佐賀藩の研究費はきわめて高額だった。
たとえ殿の命令でも、資金が不足となれば、藩内の保守派から風当たりは強まる。「お前たちが懐に入れているのではないか!」という目で見られるだろう。
――「鋳立方の七人」の七人目は、田代孫三郎。会計担当である。
「田代どの!やはり“数字”は大切でござるな!」
“算術”や“会計”に、やたらと感銘を受ける大隈信保。
大隈が好意的なので、田代も喜んでいる様子だ。
「ええ、先を見通すには、お金の回りを掴むことと心得ております。」
もともと田代は、長崎砲台の経費を削るために「倹約の鬼」として、勘定方に育成された。そして“蘭学の勘所(ポイント)”を抑え、冷たい視点で製造部門を見つめてきた。
今や“火術方”に引き抜かれた、田代。かえって製造・開発側の強い味方となったのである。
――舞台は、佐賀城下に戻る。
藩校に通う子どもたちが遊んでいる。しかし、徐々に雲行きがあやしくなり、喧嘩の予感が漂う。
「やい、八太郎!」
距離を取って、大隈八太郎が対立するグループのリーダー(通称:たかうじ)と向かい合う。
――ここで、八太郎は母の言葉を思い出す。
「いいですか!八太郎。喧嘩になりそうな時には、まず“お念仏”を十回唱えなさい!」
母との約束だ。八太郎は「なむ…なむ…」と、実に小声で念仏を唱えた。
――すると、樹の間をスーッと風が抜ける音がした。
ふと八太郎は、以前、母の読んでくれた「太平記」の一節を想い出す。戦の場面ではなかったので、あまり面白くなかった所だ。
以下、八太郎の回想(母・三井子の朗読)である。
~「太平記」より“正成の進言”~
――時は南北朝時代。
後醍醐天皇の軍勢は、一旦、足利尊氏を都から追い出した。
しかし、九州で力を盛り返した足利方は、再び都に攻め上る構えである。
――朝廷の会議の席である。
楠木正成が話を切り出す。
「武士たちは、足利尊氏を慕っております。」
帝の取り巻きの公家たちがどよめく。
「帝のご威光よりも、尊氏ごときを慕うと申すか!」
正成は続ける。
「ここは争いを避け、帝の臣下の列に、尊氏を戻すべきかと存じます。」
公家たちはさらに騒ぐ。
「尊氏と和睦しろと申すか!」
「楠木は、臆病者じゃ!」
戦の現実が見えていない公家たち。楠木正成に罵声を浴びせたのである。
~八太郎の回想の設定終了~
――サワサワと樹の枝が揺れる。
相手方が、やいやいと挑発してくる。
「八太郎!やるか!」
八太郎は、ビシッと一言を放った。
「いや、戦わない!」
相手は意表を突かれて、一瞬呆けたようになった。
「…お…おぅ、そうか。戦わないか…まぁ、いいだろう。」
――大隈家。父・信保が帰宅する。
「おう、八太郎!帰ったぞ。」
「父上!」
「今日は、傷を負うておらぬな!」
「はい。八太郎は争いませんでした!」
「そうか。八太郎も少し“お兄さん”になったな。偉いぞ。」
大隈信保、子・八太郎の両肩をポンポンと叩く。
八太郎は、少し照れて笑った。
(続く)
2020年03月14日
第6話「鉄製大砲」⑤
こんにちは。
前回の投稿で登場した伊東玄朴。幕末期に、不治の伝染病だった“天然痘”の対策を進めた蘭方医です。
玄朴が江戸に作った“西洋医学所”は、後に幕府の直営となり、現在の東京大学医学部のルーツになっていきます。この方も佐賀藩出身。神埼の生まれです。
――伊東玄朴は、佐賀の藩医でもある。江戸の藩邸にて。
参勤交代で江戸に来ている鍋島直正。
「おお、玄朴先生か。儂に伝えたいこととは何か。」
玄朴は藩医として、直正に進言することとした。
「殿は、“天然痘”に苦しむ民に、心を痛めておられると…」
直正は、ため息をついた。
「そうなのじゃ。幾度、治まっても繰り返してしまう。」
“天然痘”は、江戸時代の死因の一位とも言われる。玄朴は提案する。
「良い方法がございます。“牛痘”を使うのです。」
平たく言えば、ウシの天然痘に感染した牛から痘苗(ワクチン)をつくる。玄朴は強く思っていた。
「殿ならば…きっとお分かりいただける。」
――直正は、農業の立て直しにも心を砕いてきた。
直正は「小作料の猶予」などで地主の権利を抑え、百姓を守っていく。そして、衰えた農村は活力を取り戻し、佐賀の農業は再び豊かになった。
次は、農村部を含む疫病対策である。直正は玄朴に問い直す。
「牛…と申すか。」
玄朴は答える。
「牛でございます。人から“植え継ぐ”と発病することも多きゆえ。」
ヒト由来の痘苗(ワクチン)では、発症者を増やす恐れがあったのである。
直正は玄朴の意見を聞き届けた。
「相分かった。長崎の“楢林”に伝えておく。」
“天然痘”への対策は急務だった。楢林は長崎在住だが、佐賀藩医である。
そして、ワクチンの素は長崎でオランダから取り寄せることとなった。
――さて、佐賀藩の“プロジェクトチーム”に話を戻す。
リーダー・本島が出張中の「鋳立方の七人」。
あらためて残りのメンバーを紹介していく。

――早朝、砲術演習場の小屋。翻訳担当の2人が“出勤”する
「田中さま、おはようございます!」
江戸で伊東玄朴に学んだ、翻訳の達人・杉谷である。
もともと、オランダの砲術書は、この杉谷雍助が持ち帰ったものだ。
「おお、杉谷どのも早いな。」
少し年上の田中虎六郎が挨拶を返す。
読解の鉄人・田中と呼んでおこう。
田中は、杉谷の翻訳を実用できる“技術書”に編集していく。
――しかし、小屋には先客がいた。相変わらず“計算”を行っている。
「おおっ、馬場さま!もう、来ておられましたか。」
杉谷が驚く。
もう随分と“和算”の数式が紙に並んでいる。
「ふふふ…ちょうど、ひと区切り付いたところじゃ。」
算術家・馬場栄作である。
いつも計算をしているので、めったにしゃべらない。
ここで翻訳の内容を、数字に落とし込む。
できるところから“反射炉”設計の計算を始めているらしい。
――そして、彼らの成果を形(物体)にする者たち。
技術リーダー2人の朝は、もっと早かった様子だ。
「“小屋組”、遅かよ!」
鉄を溶かす担当。肥前刀鍛冶・橋本新左衛門である。
翻訳や計算の担当を“小屋組”と一括りで呼んだ。この小屋は「事務所棟」と言った扱いである。
橋本は、作業を進めるため、早く資料が欲しいようだ。
現時点では“反射炉”は無いので、橋本は、もっぱら金属の“溶化”の研究中である。
「まぁ、待たんね、橋本さん。この人たちは晩まで働いておるばい。」
金属を成型する担当。鋳物師・谷口弥右衛門である。
谷口は鉄が溶けるまでは、青銅砲の鋳造を続ければよいので、気持ちにゆとりがあるようだ。
――以上が、「鋳立方の七人」のうち、五名である。あとは出張中の本島と…もう1人。
七人目の田代は、向こうの倉庫で、大隈信保と話している様子だ。
もともと佐賀の蘭学は、長崎で西洋医学を学ぶことが中心だった。一冊のオランダ語の書物から大砲を造るプロジェクトも、その蓄積あってのことである。
(続く)
前回の投稿で登場した伊東玄朴。幕末期に、不治の伝染病だった“天然痘”の対策を進めた蘭方医です。
玄朴が江戸に作った“西洋医学所”は、後に幕府の直営となり、現在の東京大学医学部のルーツになっていきます。この方も佐賀藩出身。神埼の生まれです。
――伊東玄朴は、佐賀の藩医でもある。江戸の藩邸にて。
参勤交代で江戸に来ている鍋島直正。
「おお、玄朴先生か。儂に伝えたいこととは何か。」
玄朴は藩医として、直正に進言することとした。
「殿は、“天然痘”に苦しむ民に、心を痛めておられると…」
直正は、ため息をついた。
「そうなのじゃ。幾度、治まっても繰り返してしまう。」
“天然痘”は、江戸時代の死因の一位とも言われる。玄朴は提案する。
「良い方法がございます。“牛痘”を使うのです。」
平たく言えば、ウシの天然痘に感染した牛から痘苗(ワクチン)をつくる。玄朴は強く思っていた。
「殿ならば…きっとお分かりいただける。」
――直正は、農業の立て直しにも心を砕いてきた。
直正は「小作料の猶予」などで地主の権利を抑え、百姓を守っていく。そして、衰えた農村は活力を取り戻し、佐賀の農業は再び豊かになった。
次は、農村部を含む疫病対策である。直正は玄朴に問い直す。
「牛…と申すか。」
玄朴は答える。
「牛でございます。人から“植え継ぐ”と発病することも多きゆえ。」
ヒト由来の痘苗(ワクチン)では、発症者を増やす恐れがあったのである。
直正は玄朴の意見を聞き届けた。
「相分かった。長崎の“楢林”に伝えておく。」
“天然痘”への対策は急務だった。楢林は長崎在住だが、佐賀藩医である。
そして、ワクチンの素は長崎でオランダから取り寄せることとなった。
――さて、佐賀藩の“プロジェクトチーム”に話を戻す。
リーダー・本島が出張中の「鋳立方の七人」。
あらためて残りのメンバーを紹介していく。

――早朝、砲術演習場の小屋。翻訳担当の2人が“出勤”する
「田中さま、おはようございます!」
江戸で伊東玄朴に学んだ、翻訳の達人・杉谷である。
もともと、オランダの砲術書は、この杉谷雍助が持ち帰ったものだ。
「おお、杉谷どのも早いな。」
少し年上の田中虎六郎が挨拶を返す。
読解の鉄人・田中と呼んでおこう。
田中は、杉谷の翻訳を実用できる“技術書”に編集していく。
――しかし、小屋には先客がいた。相変わらず“計算”を行っている。
「おおっ、馬場さま!もう、来ておられましたか。」
杉谷が驚く。
もう随分と“和算”の数式が紙に並んでいる。
「ふふふ…ちょうど、ひと区切り付いたところじゃ。」
算術家・馬場栄作である。
いつも計算をしているので、めったにしゃべらない。
ここで翻訳の内容を、数字に落とし込む。
できるところから“反射炉”設計の計算を始めているらしい。
――そして、彼らの成果を形(物体)にする者たち。
技術リーダー2人の朝は、もっと早かった様子だ。
「“小屋組”、遅かよ!」
鉄を溶かす担当。肥前刀鍛冶・橋本新左衛門である。
翻訳や計算の担当を“小屋組”と一括りで呼んだ。この小屋は「事務所棟」と言った扱いである。
橋本は、作業を進めるため、早く資料が欲しいようだ。
現時点では“反射炉”は無いので、橋本は、もっぱら金属の“溶化”の研究中である。
「まぁ、待たんね、橋本さん。この人たちは晩まで働いておるばい。」
金属を成型する担当。鋳物師・谷口弥右衛門である。
谷口は鉄が溶けるまでは、青銅砲の鋳造を続ければよいので、気持ちにゆとりがあるようだ。
――以上が、「鋳立方の七人」のうち、五名である。あとは出張中の本島と…もう1人。
七人目の田代は、向こうの倉庫で、大隈信保と話している様子だ。
もともと佐賀の蘭学は、長崎で西洋医学を学ぶことが中心だった。一冊のオランダ語の書物から大砲を造るプロジェクトも、その蓄積あってのことである。
(続く)
2020年03月13日
第6話「鉄製大砲」④
こんばんは。
昨日の続きです。プロジェクトチーム「鋳立方の七人」のリーダー・本島は伊豆に出張中。医術修業中の佐野常民も久しぶりに登場します。
――ピーヒョロロー♪
空高くトンビが舞っている。
「えっさ~、ほいさぁ…」
街道沿いを走る飛脚とすれ違う。
まもなく本島藤太夫は、伊豆(静岡)・韮山に到着する。
幕府が実験用に作った“反射炉”を視察するためだ。
――天領(幕府の領地)伊豆・韮山。
「本島どの、よくお越しになった。」
幕府の伊豆韮山の代官、江川英龍(太郎左衛門)である。
日本で初めて近代的なパンを焼いた人物とされ、後世では“パン祖”とも呼ばれている。本編では、第3話「西洋砲術」で佐賀(武雄)に来ている。
――早速、実験用の反射炉を見学する、本島藤太夫。
剣の腕も立ち、豪傑でもある江川。しかし、何かを言いづらそうな様子だ。
「いや、本島どのには話しておくがな…実はのう。」
本島は続く言葉を予測した。
「もしや、炉の温度が足りませぬか…。」
江川が残念そうに言う。
「ご名答だ。思うように鉄が溶けないのだ。」
――本島は、今のところ“残念な反射炉”を見学する。
たとえ性能が不足していても、実験用でも、反射炉の実物が目の前にある。問題点まで含め、つぶさに観察しておかねばならない。
「江川さま、我々は諦めてはならんのです。」
本島は熱く語る。傍に仕えるうちに、鍋島直正の口ぐせが移ったかのようだ。
「本島どの、良いことを言う!」
江川が本島の言葉に応じる、もはや“同志”である。
こうして佐賀藩と伊豆・韮山の技術交流は続く。江川英龍は幕府の開明派だが、“攘夷”を旨とする「海防論者」でもあったという。
――本島は一旦、江戸に立ち寄る。

本島が立ち寄ったのは、”蘭学塾”である。
江戸では、伊東玄朴(げんぼく)が開いた、蘭学塾・象先堂が評判となっていた。
ちなみに伊東玄朴は、佐賀(神埼)の農村の生まれ。
長崎でシーボルトに蘭学と医術を学び、実力は佐賀藩のみならず幕府にも信頼されていた。
「玄朴先生!」
「おぉ、本島どのか。杉谷は元気にやっておるか。」
鋳立方の若き翻訳家・杉谷も、この塾でオランダ語を学んだ。
――伊東玄朴はふと何かを思いついた様子だ。
「本島どの、ちょうど佐賀の者が居るから紹介しておこう。」
「佐野~っ!佐賀の方が来ておる!ご挨拶しておけ!」
「はい!ただいま。」
佐野常民(栄寿)は、京都、大坂、江戸…様々な地域で修業している。
当時の蘭方医は西洋医学を普及するため、強力なネットワークを形成していた。この伊東玄朴は、既に幕府のお気に入りで、トップランナーと言ってよい存在だ。
「佐野栄寿と申します!医術修業中の身でございます!」
当時の医者は衛生面を考慮してか、丸坊主のことが多い。
佐野も髪をツルツルにしていた。
(続く)
昨日の続きです。プロジェクトチーム「鋳立方の七人」のリーダー・本島は伊豆に出張中。医術修業中の佐野常民も久しぶりに登場します。
――ピーヒョロロー♪
空高くトンビが舞っている。
「えっさ~、ほいさぁ…」
街道沿いを走る飛脚とすれ違う。
まもなく本島藤太夫は、伊豆(静岡)・韮山に到着する。
幕府が実験用に作った“反射炉”を視察するためだ。
――天領(幕府の領地)伊豆・韮山。
「本島どの、よくお越しになった。」
幕府の伊豆韮山の代官、江川英龍(太郎左衛門)である。
日本で初めて近代的なパンを焼いた人物とされ、後世では“パン祖”とも呼ばれている。本編では、第3話「西洋砲術」で佐賀(武雄)に来ている。
――早速、実験用の反射炉を見学する、本島藤太夫。
剣の腕も立ち、豪傑でもある江川。しかし、何かを言いづらそうな様子だ。
「いや、本島どのには話しておくがな…実はのう。」
本島は続く言葉を予測した。
「もしや、炉の温度が足りませぬか…。」
江川が残念そうに言う。
「ご名答だ。思うように鉄が溶けないのだ。」
――本島は、今のところ“残念な反射炉”を見学する。
たとえ性能が不足していても、実験用でも、反射炉の実物が目の前にある。問題点まで含め、つぶさに観察しておかねばならない。
「江川さま、我々は諦めてはならんのです。」
本島は熱く語る。傍に仕えるうちに、鍋島直正の口ぐせが移ったかのようだ。
「本島どの、良いことを言う!」
江川が本島の言葉に応じる、もはや“同志”である。
こうして佐賀藩と伊豆・韮山の技術交流は続く。江川英龍は幕府の開明派だが、“攘夷”を旨とする「海防論者」でもあったという。
――本島は一旦、江戸に立ち寄る。

本島が立ち寄ったのは、”蘭学塾”である。
江戸では、伊東玄朴(げんぼく)が開いた、蘭学塾・象先堂が評判となっていた。
ちなみに伊東玄朴は、佐賀(神埼)の農村の生まれ。
長崎でシーボルトに蘭学と医術を学び、実力は佐賀藩のみならず幕府にも信頼されていた。
「玄朴先生!」
「おぉ、本島どのか。杉谷は元気にやっておるか。」
鋳立方の若き翻訳家・杉谷も、この塾でオランダ語を学んだ。
――伊東玄朴はふと何かを思いついた様子だ。
「本島どの、ちょうど佐賀の者が居るから紹介しておこう。」
「佐野~っ!佐賀の方が来ておる!ご挨拶しておけ!」
「はい!ただいま。」
佐野常民(栄寿)は、京都、大坂、江戸…様々な地域で修業している。
当時の蘭方医は西洋医学を普及するため、強力なネットワークを形成していた。この伊東玄朴は、既に幕府のお気に入りで、トップランナーと言ってよい存在だ。
「佐野栄寿と申します!医術修業中の身でございます!」
当時の医者は衛生面を考慮してか、丸坊主のことが多い。
佐野も髪をツルツルにしていた。
(続く)
2020年03月12日
第6話「鉄製大砲」③
こんばんは。
幕末の佐賀藩には、反射炉で鉄製大砲を造った「伝説のプロジェクトチーム」が存在しました。“佐賀の七賢人”と区別するため、当ブログでは「鋳立方(いたてかた)の七人」と呼称します。
ちなみに今日、タイプの違う“語学の達人”を2人追加し、全てのメンバーが出揃います。実は、他の5名は「過去の投稿で既に出ている人」です。
――岩田(現在の神埼市)にある佐賀藩の砲術演習場。
大隈八太郎(重信)の父・信保は“砲術長”の役職にある。
本日から、試作された青銅砲の実験である。
「おや、本島さまは居られないのかな。」
田代という事務方の侍が応える。
「本島さまは伊豆の国・韮山へと視察に出向いております。」
本島藤太夫は、鍋島直正の側近であり、長崎の砲台の担当者でもある。この頃、幕府も鉄製大砲の鋳造を計画しており、韮山には実験用の反射炉がある。
――大隈信保は、演習場の小屋を気にする。
先日、算術家・馬場の集中力に感銘を受け、子の八太郎に「“夢中になれる学問”が見つかると良いな」と語った。
「馬場どのは、あちらの小屋でござるか。」
田代が答える。
「はい、馬場どの以外の方々も居られますが…」
――小屋から何やら「ぶつぶつ…」と声がする。
大隈信保が小屋を覗き込む。
まだ若い、頭の良さそうな男。オランダ語の書物を片手に語る。
「田中さま、この単語はこのように訳してみました。」
「杉谷どの、それでは何の“部品”か、意味がわからぬぞ。」
田中という男が応える。杉谷より年上であるらしい。
「それは“密閉する”という意味か。」
「意外に“空気”に類する言葉かもしれませぬ。」
「“泡”とかそういう類ではないか。」
「…なれば“空気の泡”でどうでしょう。」
田中がポンと手を打つ。杉谷の提案を受け入れた。
「それだ!」
――2人が読んでいるのは、佐賀藩がオランダから入手した大砲鋳造書。
「未知の技術を書いている、外国語の書物の解読」という無茶に挑む2人。
専門用語が多数出てくるため、そもそも単語もわからず、しかも普通に訳しても理解は不能である。
若い方“杉谷雍助”が、直訳・分析の担当。いわば“切り込み役”である。長崎や江戸での語学修業で鍛えている。
年上の“田中虎六郎”が、意訳・監修の担当。いわば“指南役”タイプである。漢学の知識も豊富で、言語の運用能力に優れる。
「本島さま…また凄い人たちを連れてきたな。」
大隈信保は驚いていた。
――今回の試射実験も無事終了し、しばらくぶりに帰宅する大隈信保。

「ぶつぶつ…」
家の中から、何やら声がする。
「田中どの、杉谷どのに挟まれ過ぎたのか…いまだ“ぶつぶつ”と何やら聞こえるようじゃ。」
苦笑する信保。
「なーまんだぶ…なーまんだぶ…」
声の主は信保の妻子、三井子と八太郎のようだ。
「念仏ではないか!いかがしたのか!?」
やや表情が引きつる信保。
――居間で三井子が、喧嘩をしてきた八太郎を何やら諭しているようだ。
「いいですか!八太郎!」
「男の子ですから、喧嘩をするなとは言いませぬ。」
一応、叱られているわけではない。しかし、三井子の勢いに押される八太郎。
「はい…」
「せめて、本当にすべき喧嘩なのか、お念仏を十回唱えて見極めるのです。」
「なーまんだぶ…なーまんだーぶ…」
「一回足りませぬ。もっと真摯に数えるのです。」
――信保の考えは回った。三井子は本当に信心深いのだろうか…この“お念仏”の用法は誤っているのでは…いや、心の平安こそが仏の願いでは…
そして心の声はともかく信保は朗らかにこう言った。
「おお、お念仏か。ちゃんと手も合わせるのだぞ。」
八太郎は、父・信保の登場にやや安堵したらしく、元気に返事をする。
「はい、父上!」
(続く)
幕末の佐賀藩には、反射炉で鉄製大砲を造った「伝説のプロジェクトチーム」が存在しました。“佐賀の七賢人”と区別するため、当ブログでは「鋳立方(いたてかた)の七人」と呼称します。
ちなみに今日、タイプの違う“語学の達人”を2人追加し、全てのメンバーが出揃います。実は、他の5名は「過去の投稿で既に出ている人」です。
――岩田(現在の神埼市)にある佐賀藩の砲術演習場。
大隈八太郎(重信)の父・信保は“砲術長”の役職にある。
本日から、試作された青銅砲の実験である。
「おや、本島さまは居られないのかな。」
田代という事務方の侍が応える。
「本島さまは伊豆の国・韮山へと視察に出向いております。」
本島藤太夫は、鍋島直正の側近であり、長崎の砲台の担当者でもある。この頃、幕府も鉄製大砲の鋳造を計画しており、韮山には実験用の反射炉がある。
――大隈信保は、演習場の小屋を気にする。
先日、算術家・馬場の集中力に感銘を受け、子の八太郎に「“夢中になれる学問”が見つかると良いな」と語った。
「馬場どのは、あちらの小屋でござるか。」
田代が答える。
「はい、馬場どの以外の方々も居られますが…」
――小屋から何やら「ぶつぶつ…」と声がする。
大隈信保が小屋を覗き込む。
まだ若い、頭の良さそうな男。オランダ語の書物を片手に語る。
「田中さま、この単語はこのように訳してみました。」
「杉谷どの、それでは何の“部品”か、意味がわからぬぞ。」
田中という男が応える。杉谷より年上であるらしい。
「それは“密閉する”という意味か。」
「意外に“空気”に類する言葉かもしれませぬ。」
「“泡”とかそういう類ではないか。」
「…なれば“空気の泡”でどうでしょう。」
田中がポンと手を打つ。杉谷の提案を受け入れた。
「それだ!」
――2人が読んでいるのは、佐賀藩がオランダから入手した大砲鋳造書。
「未知の技術を書いている、外国語の書物の解読」という無茶に挑む2人。
専門用語が多数出てくるため、そもそも単語もわからず、しかも普通に訳しても理解は不能である。
若い方“杉谷雍助”が、直訳・分析の担当。いわば“切り込み役”である。長崎や江戸での語学修業で鍛えている。
年上の“田中虎六郎”が、意訳・監修の担当。いわば“指南役”タイプである。漢学の知識も豊富で、言語の運用能力に優れる。
「本島さま…また凄い人たちを連れてきたな。」
大隈信保は驚いていた。
――今回の試射実験も無事終了し、しばらくぶりに帰宅する大隈信保。

「ぶつぶつ…」
家の中から、何やら声がする。
「田中どの、杉谷どのに挟まれ過ぎたのか…いまだ“ぶつぶつ”と何やら聞こえるようじゃ。」
苦笑する信保。
「なーまんだぶ…なーまんだぶ…」
声の主は信保の妻子、三井子と八太郎のようだ。
「念仏ではないか!いかがしたのか!?」
やや表情が引きつる信保。
――居間で三井子が、喧嘩をしてきた八太郎を何やら諭しているようだ。
「いいですか!八太郎!」
「男の子ですから、喧嘩をするなとは言いませぬ。」
一応、叱られているわけではない。しかし、三井子の勢いに押される八太郎。
「はい…」
「せめて、本当にすべき喧嘩なのか、お念仏を十回唱えて見極めるのです。」
「なーまんだぶ…なーまんだーぶ…」
「一回足りませぬ。もっと真摯に数えるのです。」
――信保の考えは回った。三井子は本当に信心深いのだろうか…この“お念仏”の用法は誤っているのでは…いや、心の平安こそが仏の願いでは…
そして心の声はともかく信保は朗らかにこう言った。
「おお、お念仏か。ちゃんと手も合わせるのだぞ。」
八太郎は、父・信保の登場にやや安堵したらしく、元気に返事をする。
「はい、父上!」
(続く)
2020年03月11日
第6話「鉄製大砲」②
こんばんは。
ブログの更新にあたり、毎日のように通勤電車で構想を練っています。今回は佐賀が誇る“天才数学者”が登場しますが…
――鍋島直正から、大砲の鋳造計画を急ぐよう指示があった。
“アヘン戦争”は1842年に終結している。
結果は、近代兵器を備えたイギリスが清国に圧勝した。
清国は、まず香港(ホンコン)をイギリスに取られる。
また主要な港湾をコントロールされ、多額の賠償金も要求された。
あの、東洋の大国・清が、西洋にあっさりと打ち負かされている恐怖。その矛先が日本に向くのは、時間の問題と思われた。
――しかも先年(1844年)にはオランダ国王から開国も勧告されている。さすがに幕府は、危機感を持った。
日本の表玄関・長崎を守る佐賀藩と福岡藩に意見を求める。
佐賀藩主・鍋島直正が声を上げる。
「長崎の湾口で異国船を打ち損じれば、もはや為すすべがない!」
オランダ軍船にも乗ったことのある直正、西洋との差が見えている。
「もっと、沖合で阻止できる台場を築くことが肝要でござる!」
――しかし、交代で長崎を守る“福岡藩”の反応を平たく言うと…
「砲台の予定地の伊王島と神ノ島、佐賀藩の領地ですよね。関わりたくないです。」という態度だった。
幕府も「鍋島の言い分もわかるが、離島への砲台建設は…金がかかる。」と急に消極的になった。
どうやら援護は期待できない様子だ。
直正は「この際、佐賀の力だけで、強い砲台を作り上げて見せる!」と決意した。こうして、本島藤太夫は“プロジェクトチーム”の組成を命じられた。
――佐賀藩“火術方”の演習拠点・岩田(神埼)。
砲術の担当者大隈信保が、本島を見かける。
「本島さま!凄い方を連れて来られましたな!」
信保も八太郎の父だけに、人懐っこいところがある。
“あっち、あっち”とばかりに小屋の方を指し示す。
「はて!?」
本島が小屋を覗き込む。
――すると、凄い勢いで何やら筆記している男がいる。
サッサッサッ…ザッザッ
現代ならば、ペンやチョークの音が似つかわしいかもしれない。筆で書き連ねているので、この効果音。ひたすら数式を書き連ねているのだ。
何やら「構造計算」のようなことをしているらしい。
ちなみに、当時は“和算”である。
――技術への応用で、西洋数学に遅れを取ったが、日本の数学“和算”もハイレベルなものだったという。
「馬場どの!」
本島の声かけに、算術家・“馬場栄作”はまったく反応しない。ひたすら数式を書いている。
大隈信保は、本島にこう言った。
「馬場さまは凄い。あの寝食を忘れている感じが、本物です。」
妙なところに感心する、大隈信保。彼もまた“理系人材”ということだろう。
――仕事にひと区切りが付いて、大隈家に帰る信保。

「今、戻った。ところで、八太郎はどうした。」
大隈三井子は、夕飯の支度中である。
「二階で勉強をしておるはず。様子を見てきてもらえますか。」
――ギシギシ…
階段を上がる、信保。
見ると八太郎が、前後に首を揺らしている。
眠くなって「船を漕いでいる」状態である。
――ゴツン!
「痛っ!」
目を覚ます、八太郎。
八太郎の勉強机には、母・三井子特製の“眠気覚まし”装置が付いていた。わが子の姿勢と居眠りの特性を把握し、必ず頭を打つポジションに出っ張りを仕掛けてある。
「はっはっは!」
八太郎の後で爆笑する、大隈信保。
「あ…父上。」
「八太郎!勉強は面白くないか?」
「父上、八太郎は“葉隠”が好きではありません。」
――藩校に通い出して、少し言葉遣いが“お兄さん”になった八太郎。
佐賀武士の教典“葉隠”。
八太郎は「我慢ばかりの窮屈な教え」と見ているようだ。
「そうか。でも将来のお役目(仕事)に我慢は付き物だぞ。」
「はい…」
信保は、八太郎の目を見て続ける。
「しかし、お前に合った学問もきっとあるだろう。」
「寝食を忘れ、励みたくなる学問に出会えると良いな!」
八太郎の肩をポンポンと叩く信保。
「はい!父上!」
…算術家・馬場栄作、一言も語らずとも大隈父子には、何かを伝えたようである。
(続く)
ブログの更新にあたり、毎日のように通勤電車で構想を練っています。今回は佐賀が誇る“天才数学者”が登場しますが…
――鍋島直正から、大砲の鋳造計画を急ぐよう指示があった。
“アヘン戦争”は1842年に終結している。
結果は、近代兵器を備えたイギリスが清国に圧勝した。
清国は、まず香港(ホンコン)をイギリスに取られる。
また主要な港湾をコントロールされ、多額の賠償金も要求された。
あの、東洋の大国・清が、西洋にあっさりと打ち負かされている恐怖。その矛先が日本に向くのは、時間の問題と思われた。
――しかも先年(1844年)にはオランダ国王から開国も勧告されている。さすがに幕府は、危機感を持った。
日本の表玄関・長崎を守る佐賀藩と福岡藩に意見を求める。
佐賀藩主・鍋島直正が声を上げる。
「長崎の湾口で異国船を打ち損じれば、もはや為すすべがない!」
オランダ軍船にも乗ったことのある直正、西洋との差が見えている。
「もっと、沖合で阻止できる台場を築くことが肝要でござる!」
――しかし、交代で長崎を守る“福岡藩”の反応を平たく言うと…
「砲台の予定地の伊王島と神ノ島、佐賀藩の領地ですよね。関わりたくないです。」という態度だった。
幕府も「鍋島の言い分もわかるが、離島への砲台建設は…金がかかる。」と急に消極的になった。
どうやら援護は期待できない様子だ。
直正は「この際、佐賀の力だけで、強い砲台を作り上げて見せる!」と決意した。こうして、本島藤太夫は“プロジェクトチーム”の組成を命じられた。
――佐賀藩“火術方”の演習拠点・岩田(神埼)。
砲術の担当者大隈信保が、本島を見かける。
「本島さま!凄い方を連れて来られましたな!」
信保も八太郎の父だけに、人懐っこいところがある。
“あっち、あっち”とばかりに小屋の方を指し示す。
「はて!?」
本島が小屋を覗き込む。
――すると、凄い勢いで何やら筆記している男がいる。
サッサッサッ…ザッザッ
現代ならば、ペンやチョークの音が似つかわしいかもしれない。筆で書き連ねているので、この効果音。ひたすら数式を書き連ねているのだ。
何やら「構造計算」のようなことをしているらしい。
ちなみに、当時は“和算”である。
――技術への応用で、西洋数学に遅れを取ったが、日本の数学“和算”もハイレベルなものだったという。
「馬場どの!」
本島の声かけに、算術家・“馬場栄作”はまったく反応しない。ひたすら数式を書いている。
大隈信保は、本島にこう言った。
「馬場さまは凄い。あの寝食を忘れている感じが、本物です。」
妙なところに感心する、大隈信保。彼もまた“理系人材”ということだろう。
――仕事にひと区切りが付いて、大隈家に帰る信保。

「今、戻った。ところで、八太郎はどうした。」
大隈三井子は、夕飯の支度中である。
「二階で勉強をしておるはず。様子を見てきてもらえますか。」
――ギシギシ…
階段を上がる、信保。
見ると八太郎が、前後に首を揺らしている。
眠くなって「船を漕いでいる」状態である。
――ゴツン!
「痛っ!」
目を覚ます、八太郎。
八太郎の勉強机には、母・三井子特製の“眠気覚まし”装置が付いていた。わが子の姿勢と居眠りの特性を把握し、必ず頭を打つポジションに出っ張りを仕掛けてある。
「はっはっは!」
八太郎の後で爆笑する、大隈信保。
「あ…父上。」
「八太郎!勉強は面白くないか?」
「父上、八太郎は“葉隠”が好きではありません。」
――藩校に通い出して、少し言葉遣いが“お兄さん”になった八太郎。
佐賀武士の教典“葉隠”。
八太郎は「我慢ばかりの窮屈な教え」と見ているようだ。
「そうか。でも将来のお役目(仕事)に我慢は付き物だぞ。」
「はい…」
信保は、八太郎の目を見て続ける。
「しかし、お前に合った学問もきっとあるだろう。」
「寝食を忘れ、励みたくなる学問に出会えると良いな!」
八太郎の肩をポンポンと叩く信保。
「はい!父上!」
…算術家・馬場栄作、一言も語らずとも大隈父子には、何かを伝えたようである。
(続く)
2020年03月10日
第6話「鉄製大砲」①
こんばんは。
日々、様々な人物が走り回る「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージですが、書いている方もバタバタしています。
走りながら考える…幕末の佐賀藩士の気分が少し味わえているのかもしれません。とりあえず今回から第6話「鉄製大砲」に入ります。
――鍋島直正は、憔悴していた。
「永山…なにゆえだ…」
1845年。直正の側近の1人、永山十兵衛が急逝する。
藩校「弘道館」の教師であり、直正の師匠・古賀穀堂が亡くなったあとを引き継ぐ存在だった。直正が不眠に悩めば、一緒に“呼吸法”の鍛錬を行うなど、“心の支え”でもあった。
永山は、東北地方を調査するなど激務をこなしていたのも事実であった。
直正の目となり、耳となって情報収集にあたる気構えは、藩校の生徒たちを奮わせた。
影響されやすい“団にょん”こと島義勇などは、永山の話を糧にズンズンと諸国を歩き回っている。
――永山十兵衛が欠けたことにより、直正の心にぽっかりと穴が空く。
「すでに穀堂先生は居られぬ。儂は何を標(しるべ)とすれば良いのだ。」
直正は、もともと潔癖症ではあるが、さらに手を洗う回数が増えてきた。桶に溜めた水で、ガシガシと手を擦り合わせる。
「殿…何たる落ち込みよう。与一は心配です。」
古川与一(松根)は、直正の身の回りの世話をする執事役である。
文化的な教養は高いが、さすがに学問の師匠たちの代わりはできない。
そこに佐賀城で女性の生活空間である“奥”との取次役が現れる。
「実は…姫さまが、殿にお目通りを願い出ておられます。」
――鍋島直正は、なかなか子に恵まれなかった。
将軍家の姫だった正室・盛姫との間に子の誕生はなく、歳月は過ぎていった。側室との間にようやく子(長女)が生まれたのは、直正が26歳のとき。
長女の名は“貢姫(みつひめ)”という。
古川与一は、直正に「貢姫が会いたがっている」と伝えた。
憔悴している直正だが、よろよろと立ち上がる。
「そうじゃな。落ち込んでばかりもおれん…、お貢(みつ)の顔でも見てくるか。」

――佐賀城本丸“奥”にて。
年の頃、5歳くらいの女の子がニコニコと笑っている。直正の長女・貢姫である。
「おちちうえさま!」
「おぉ、お貢よ。変わりはないか。」
「はい!」
貢姫に不調を悟られてはならない。直正は無理に平静を装った。
「おちちうえさま!これをおうけとりください!」
「ほう、これは何かのぅ。」
「ヘビよけのおまもりです!“みつ”がつくりました!」
「なんと!」
――以前、紹介したことがあるが、直正はヘビが大の苦手である。
直正は、幼い貢姫から“蛇除けのお守り”を受け取った。
すると永山を亡くしてから、止まっていた頭が急に動き出した。
以降は、直正の心の声である。
「儂は…止まっている場合なのか。異国船の脅威は日々迫っているのだぞ。」
「そして儂は貢姫の父親じゃ。お貢を守らねばならぬ。」
「いや、その前に儂は佐賀の殿様だぞ、家来を…何より、民を守る責務があるではないか。」
――次第に、直正の目に光が戻っていく。
「お貢よ!“蛇除け”大切にいたすぞ。礼を申す。」
「どういたしまして」
貢姫は、小さく礼をする。
「父は、政務に戻らねばならん。お貢よ、またな。」
直正は照れ隠しで、そのまま背を向ける。
そして湧きあがった情熱で、仕事場である“表”に戻っていった。
「おかしな、おちちうえさま。」
貢姫は小首を傾げていた。
――そして、佐賀城本丸の“表”。
急に“仕事モード”で帰ってきた直正。
「本島はおるか!長崎の台場に備える砲の鋳造を急がねばならん!」
佐賀藩の製砲主任である本島藤太夫が応じる。
「殿からお声掛けいただけるとは、有難きことにございます!」
直正が力強く戻ってきたのを見届け、古川与一がつぶやく。
「さすがは貢姫さま…、素晴らしい力をお持ちですな。」
(続く)
日々、様々な人物が走り回る「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージですが、書いている方もバタバタしています。
走りながら考える…幕末の佐賀藩士の気分が少し味わえているのかもしれません。とりあえず今回から第6話「鉄製大砲」に入ります。
――鍋島直正は、憔悴していた。
「永山…なにゆえだ…」
1845年。直正の側近の1人、永山十兵衛が急逝する。
藩校「弘道館」の教師であり、直正の師匠・古賀穀堂が亡くなったあとを引き継ぐ存在だった。直正が不眠に悩めば、一緒に“呼吸法”の鍛錬を行うなど、“心の支え”でもあった。
永山は、東北地方を調査するなど激務をこなしていたのも事実であった。
直正の目となり、耳となって情報収集にあたる気構えは、藩校の生徒たちを奮わせた。
影響されやすい“団にょん”こと島義勇などは、永山の話を糧にズンズンと諸国を歩き回っている。
――永山十兵衛が欠けたことにより、直正の心にぽっかりと穴が空く。
「すでに穀堂先生は居られぬ。儂は何を標(しるべ)とすれば良いのだ。」
直正は、もともと潔癖症ではあるが、さらに手を洗う回数が増えてきた。桶に溜めた水で、ガシガシと手を擦り合わせる。
「殿…何たる落ち込みよう。与一は心配です。」
古川与一(松根)は、直正の身の回りの世話をする執事役である。
文化的な教養は高いが、さすがに学問の師匠たちの代わりはできない。
そこに佐賀城で女性の生活空間である“奥”との取次役が現れる。
「実は…姫さまが、殿にお目通りを願い出ておられます。」
――鍋島直正は、なかなか子に恵まれなかった。
将軍家の姫だった正室・盛姫との間に子の誕生はなく、歳月は過ぎていった。側室との間にようやく子(長女)が生まれたのは、直正が26歳のとき。
長女の名は“貢姫(みつひめ)”という。
古川与一は、直正に「貢姫が会いたがっている」と伝えた。
憔悴している直正だが、よろよろと立ち上がる。
「そうじゃな。落ち込んでばかりもおれん…、お貢(みつ)の顔でも見てくるか。」

――佐賀城本丸“奥”にて。
年の頃、5歳くらいの女の子がニコニコと笑っている。直正の長女・貢姫である。
「おちちうえさま!」
「おぉ、お貢よ。変わりはないか。」
「はい!」
貢姫に不調を悟られてはならない。直正は無理に平静を装った。
「おちちうえさま!これをおうけとりください!」
「ほう、これは何かのぅ。」
「ヘビよけのおまもりです!“みつ”がつくりました!」
「なんと!」
――以前、紹介したことがあるが、直正はヘビが大の苦手である。
直正は、幼い貢姫から“蛇除けのお守り”を受け取った。
すると永山を亡くしてから、止まっていた頭が急に動き出した。
以降は、直正の心の声である。
「儂は…止まっている場合なのか。異国船の脅威は日々迫っているのだぞ。」
「そして儂は貢姫の父親じゃ。お貢を守らねばならぬ。」
「いや、その前に儂は佐賀の殿様だぞ、家来を…何より、民を守る責務があるではないか。」
――次第に、直正の目に光が戻っていく。
「お貢よ!“蛇除け”大切にいたすぞ。礼を申す。」
「どういたしまして」
貢姫は、小さく礼をする。
「父は、政務に戻らねばならん。お貢よ、またな。」
直正は照れ隠しで、そのまま背を向ける。
そして湧きあがった情熱で、仕事場である“表”に戻っていった。
「おかしな、おちちうえさま。」
貢姫は小首を傾げていた。
――そして、佐賀城本丸の“表”。
急に“仕事モード”で帰ってきた直正。
「本島はおるか!長崎の台場に備える砲の鋳造を急がねばならん!」
佐賀藩の製砲主任である本島藤太夫が応じる。
「殿からお声掛けいただけるとは、有難きことにございます!」
直正が力強く戻ってきたのを見届け、古川与一がつぶやく。
「さすがは貢姫さま…、素晴らしい力をお持ちですな。」
(続く)
2020年03月09日
第5話「藩校立志」⑩
こんばんは。
進学や就職で春は出会いの季節ですね。もっとも今春は新型コロナがいささか不安ではあります。さて、本編でも“ある出会い”を描きます。
このブログをご覧の方には、たぶん現役の学生はいないかなと思うので、想い出してみてください。新しいクラスで「なんとなくコイツと友達になりたいな。」と感じるような人はいませんでしたか?
――藩校「弘道館」が移転し、拡充されてから数年。
熱の入った授業が続く。そして、こんなこともある。
「諸君、何か質問はありますか?」
殿・鍋島直正の“メンタルトレーナー”でもある永山十兵衛が講義を行う。
「私から質問してもよいか。」
生徒たちの後ろから、声がする。年の頃30代。普通の生徒ではない。
「安房様、ご質問を承ります。」
藩校の責任者・鍋島安房。なんと“校長”が授業に出席している。
「えっ!!」
まさか”校長”も一緒に受講していたとは…生徒がどよめく。
――鍋島安房は、藩のナンバー2で、行政のトップである請役。
机を並べて勉強し、優秀さが目に留まったりすれば…立身出世できると思うのは自然な発想だろう。
藩校での学問は、大学受験と就職活動の役員面接が、日々実施されているくらい重みがある。
直正もよく藩校に来るが、鍋島安房にいたっては、城での執務以外は大体「弘道館」にいる。
安房はものすごい勢いで勉強し、生徒たちを驚愕させていた。その副作用で常に寝不足である。
――そして、鍋島安房の質問の内容である。
永山十兵衛は、水戸藩の大学者・藤田東湖と親しい。
安房は、話の流れから「水戸藩での尊王論」の展開について尋ねていた。
「そもそも水戸学派は“徳川光圀”公より始まり…」
あの水戸黄門である。“大日本史”という歴史書を編纂し始めたことで有名である。
――水戸黄門は、尊王の象徴として楠木正成を崇めた。
そして“助さん”(佐々介三郎)を、正成の最期の地・湊川(現在の神戸市)に派遣した。
黄門様は“助さん”に命じた。
「助さん!楠公さまの墓碑を建ててきなさい!」
そして、碑文では「あぁ忠臣・楠木正成…」と、後醍醐天皇のために戦った正成を讃えた。
「よく分かった。佐賀でもぜひ、楠公(なんこう)様を讃えたいものだ。」
30代の学生・鍋島安房も、永山先生の講義を心に刻んだようだ。
――藩校「弘道館」の日々は続く。そして、こんな出会いが。
広大な藩校の敷地を江藤新平(胤雄)が行く。

すると、ヌッとやや大柄な男子学生が現れる。
「俺は大木という。」
突然現れた、大木幡六(喬任)。言葉を続ける。
「お主、江藤と言ったな。」
「いかにも江藤ですが、何か用ですか。」
――前提の情報を入れておく。大木は江藤より2歳年上である。高3と高1の感じで見てほしい。
ちなみに大木は、あまり口がうまくない。
「それはだな…。」
大木は、思い付いたように言った。
「そうだ!お主、賢いな!」
江藤が、大木の言葉に反応する。
「賢いと言われて悪い気はしませぬが、やはり何用ですか。」
――意外に「友達になってくれ!」というのは勇気がいる。
まして大木は口下手である。
「そうだ!お主、昨今の国家の情勢をどうみる!」
なんとか、それらしい言葉を切り出した大木。
知識はたくさんあるが、適切な話題の選択は難しい。
江藤がふと、気づいたように語る。
「大木さん…と言いましたか。今、我々が為すべきことは…」
――大木が江藤の言葉に耳を傾ける。
やはり、この男は何かが違う。その辺の“つまらん奴”ではない。大木は次の言葉に期待した。
「なんだ、早く言ってくれ!」
江藤はスッと言い放つ。
「そろそろ昼飯の時間です!」
肩透かしを食う、大木。
「それかっ!まぁ、そうだな。」
江藤は言葉を続ける。
「我々は出遅れました!大木さん、もはや走らんといかんとです!」
「お…おう!」
とりあえず、江藤に続いて、走り出した大木。
――何にせよ、江藤と大木は、飯場に走っていた。
佐賀藩出身、後に海軍中将となる中牟田倉之助によると、概ねこうだ。
「弘道館の昼飯時は、イナゴの群れが、稲を食べ尽くすがごた…」と。
もはや、一時の猶予もない。
飯櫃が空になるそのときまでに、何とか追いつかねばねばならない。
この2人の激走は、日本の司法と教育を、近代国家のものに変えていく。
しかし、それはまだ先の話。今は昼飯に走るただの男子学生である。
(第6話:「鉄製大砲」に続く)
進学や就職で春は出会いの季節ですね。もっとも今春は新型コロナがいささか不安ではあります。さて、本編でも“ある出会い”を描きます。
このブログをご覧の方には、たぶん現役の学生はいないかなと思うので、想い出してみてください。新しいクラスで「なんとなくコイツと友達になりたいな。」と感じるような人はいませんでしたか?
――藩校「弘道館」が移転し、拡充されてから数年。
熱の入った授業が続く。そして、こんなこともある。
「諸君、何か質問はありますか?」
殿・鍋島直正の“メンタルトレーナー”でもある永山十兵衛が講義を行う。
「私から質問してもよいか。」
生徒たちの後ろから、声がする。年の頃30代。普通の生徒ではない。
「安房様、ご質問を承ります。」
藩校の責任者・鍋島安房。なんと“校長”が授業に出席している。
「えっ!!」
まさか”校長”も一緒に受講していたとは…生徒がどよめく。
――鍋島安房は、藩のナンバー2で、行政のトップである請役。
机を並べて勉強し、優秀さが目に留まったりすれば…立身出世できると思うのは自然な発想だろう。
藩校での学問は、大学受験と就職活動の役員面接が、日々実施されているくらい重みがある。
直正もよく藩校に来るが、鍋島安房にいたっては、城での執務以外は大体「弘道館」にいる。
安房はものすごい勢いで勉強し、生徒たちを驚愕させていた。その副作用で常に寝不足である。
――そして、鍋島安房の質問の内容である。
永山十兵衛は、水戸藩の大学者・藤田東湖と親しい。
安房は、話の流れから「水戸藩での尊王論」の展開について尋ねていた。
「そもそも水戸学派は“徳川光圀”公より始まり…」
あの水戸黄門である。“大日本史”という歴史書を編纂し始めたことで有名である。
――水戸黄門は、尊王の象徴として楠木正成を崇めた。
そして“助さん”(佐々介三郎)を、正成の最期の地・湊川(現在の神戸市)に派遣した。
黄門様は“助さん”に命じた。
「助さん!楠公さまの墓碑を建ててきなさい!」
そして、碑文では「あぁ忠臣・楠木正成…」と、後醍醐天皇のために戦った正成を讃えた。
「よく分かった。佐賀でもぜひ、楠公(なんこう)様を讃えたいものだ。」
30代の学生・鍋島安房も、永山先生の講義を心に刻んだようだ。
――藩校「弘道館」の日々は続く。そして、こんな出会いが。
広大な藩校の敷地を江藤新平(胤雄)が行く。

すると、ヌッとやや大柄な男子学生が現れる。
「俺は大木という。」
突然現れた、大木幡六(喬任)。言葉を続ける。
「お主、江藤と言ったな。」
「いかにも江藤ですが、何か用ですか。」
――前提の情報を入れておく。大木は江藤より2歳年上である。高3と高1の感じで見てほしい。
ちなみに大木は、あまり口がうまくない。
「それはだな…。」
大木は、思い付いたように言った。
「そうだ!お主、賢いな!」
江藤が、大木の言葉に反応する。
「賢いと言われて悪い気はしませぬが、やはり何用ですか。」
――意外に「友達になってくれ!」というのは勇気がいる。
まして大木は口下手である。
「そうだ!お主、昨今の国家の情勢をどうみる!」
なんとか、それらしい言葉を切り出した大木。
知識はたくさんあるが、適切な話題の選択は難しい。
江藤がふと、気づいたように語る。
「大木さん…と言いましたか。今、我々が為すべきことは…」
――大木が江藤の言葉に耳を傾ける。
やはり、この男は何かが違う。その辺の“つまらん奴”ではない。大木は次の言葉に期待した。
「なんだ、早く言ってくれ!」
江藤はスッと言い放つ。
「そろそろ昼飯の時間です!」
肩透かしを食う、大木。
「それかっ!まぁ、そうだな。」
江藤は言葉を続ける。
「我々は出遅れました!大木さん、もはや走らんといかんとです!」
「お…おう!」
とりあえず、江藤に続いて、走り出した大木。
――何にせよ、江藤と大木は、飯場に走っていた。
佐賀藩出身、後に海軍中将となる中牟田倉之助によると、概ねこうだ。
「弘道館の昼飯時は、イナゴの群れが、稲を食べ尽くすがごた…」と。
もはや、一時の猶予もない。
飯櫃が空になるそのときまでに、何とか追いつかねばねばならない。
この2人の激走は、日本の司法と教育を、近代国家のものに変えていく。
しかし、それはまだ先の話。今は昼飯に走るただの男子学生である。
(第6話:「鉄製大砲」に続く)