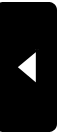2020年03月08日
第5話「藩校立志」⑨
こんばんは。
当ブログも、開始から3か月が経過しました。
時折バテ気味になるので、投稿が止まることもありますが、引き続きよろしくお願いします。
今回から日本の近代司法制度を築いた、“佐賀の七賢人”(その6)江藤新平が本編に登場します。当時は“胤雄”と名乗っており、この名は明治新政府に出仕したときにも用いたようです。
――佐賀城の北の堀端に建つ藩校「弘道館」。
あの“フェートン号事件”が起きる前から、鍋島直正の師匠・古賀穀堂は教育改革を訴えていた。それから30余年の歳月を経て、藩校は目に見える形でバージョンアップを果たした。
藩校の敷地は3倍近く、経費は4倍とも言われる藩校の拡充である。
そして、藩士の子弟は、小学生に相当する6、7歳頃から通学で学ぶことになる。佐賀城下に住む八太郎くんが通っているのは、この“蒙養舎”である。
高校生くらいの年齢になると通学、もしくは寄宿舎に入っての学習である。勉強の時間として定められているのは、午前6時から午後10時という猛烈なものだった。
「ここを自分の家だと思って、学問に励むように!」
このような殿・直正の訓示により、新しい藩校はスタートしたのである。
――藩校「弘道館」の生徒数はおよそ千人。
とくに寄宿制の「内生寮」にいる若者たちは、学校に住んでいるのである。現代で言えば、男子高校生ぐらい年齢の者が集まっている。
武道場での鍛錬もあり、良く言えば賑やか、悪く言えば騒々しい。とにかく活気のある“男子校”をイメージしてほしい。
そこに一際、身なりの粗末な少年がいた。
背筋正しく、眼光鋭く、それでいて…何を考えているのか判然としない。
――その粗末な身なりの少年。武道場にて剣術の稽古中であるらしい。

佐賀藩でよく稽古されていた剣術の流派は“新陰流”“タイ捨流”などが知られる。地元の道場で学んだ形を大事にする者から、個性を活かした戦い方をする者まで…色々と差異はあったと思われる。
先ほどの少年は、身なりが小ぎれいな相手と立ち会っている。
「キェーッ!」
先に動く相手。気合を発し、様子を伺う。
はっきり言えば、みすぼらしい身なりの少年。相手の気合には動じない。
そして、一言鋭く発した。
「隙ありっ!」
声は一筋、鋭い矢のように飛んだ。
ビリッ!と電流が走ったように、微細に相手が震える。
――シュッ!少年は、木剣を振り下ろす。
「勝負あり!江藤の勝ちだ。」
審判役の少年が、粗末な身なりの少年・江藤を勝者と告げた。
「おい…江藤と言ったか、お主の声に負けてしもうたばい。」
負けた方の少年もサバサバしている。江藤の実力を認めたらしい。
「声で勝負をしているつもりは無かです。」
江藤という少年。無自覚であるらしい。
「まぁ、よか。剣の腕そのものも、お主が上のようじゃし。」
少年はカラカラと笑った。
――もちろん、藩校では学問もみっちりと詰め込まれるが…
儒学の教典“大学”の講義があった。
「では、江藤。その一節を黙読してから、答えるように。」
しかし、江藤はすぐ答えを返した。
「“大学”の内容は、概ね頭に入っておりますゆえ。」
教師は感心した。
「おお、よく学んでおるな。」
授業後、他の生徒が尋ねる。
「お主、藩校には入ったばかりではないのか。いつの間に学んだのだ。」
江藤が答える。
「母から習い申した。」
尋ねた生徒が驚く。
「母!?お主の母上は、一体何者なのじゃ?」
――江藤家は“手明鑓”と呼ばれる侍と、どうにか同格扱いの下級武士。
江藤の父は、才能はあったが実直過ぎる性格が災いし、役職を解かれていた。そのため、江藤家は佐賀城下を離れ、縁のある小城にて江藤は育ってきた。
学問のある江藤の母は、近所の子どもたちに手習いを教え、生計を支えたと言う。
このたび父が役職に付くことができたため、江藤は佐賀城下に戻り、藩校に入学したのである。
(続く)
当ブログも、開始から3か月が経過しました。
時折バテ気味になるので、投稿が止まることもありますが、引き続きよろしくお願いします。
今回から日本の近代司法制度を築いた、“佐賀の七賢人”(その6)江藤新平が本編に登場します。当時は“胤雄”と名乗っており、この名は明治新政府に出仕したときにも用いたようです。
――佐賀城の北の堀端に建つ藩校「弘道館」。
あの“フェートン号事件”が起きる前から、鍋島直正の師匠・古賀穀堂は教育改革を訴えていた。それから30余年の歳月を経て、藩校は目に見える形でバージョンアップを果たした。
藩校の敷地は3倍近く、経費は4倍とも言われる藩校の拡充である。
そして、藩士の子弟は、小学生に相当する6、7歳頃から通学で学ぶことになる。佐賀城下に住む八太郎くんが通っているのは、この“蒙養舎”である。
高校生くらいの年齢になると通学、もしくは寄宿舎に入っての学習である。勉強の時間として定められているのは、午前6時から午後10時という猛烈なものだった。
「ここを自分の家だと思って、学問に励むように!」
このような殿・直正の訓示により、新しい藩校はスタートしたのである。
――藩校「弘道館」の生徒数はおよそ千人。
とくに寄宿制の「内生寮」にいる若者たちは、学校に住んでいるのである。現代で言えば、男子高校生ぐらい年齢の者が集まっている。
武道場での鍛錬もあり、良く言えば賑やか、悪く言えば騒々しい。とにかく活気のある“男子校”をイメージしてほしい。
そこに一際、身なりの粗末な少年がいた。
背筋正しく、眼光鋭く、それでいて…何を考えているのか判然としない。
――その粗末な身なりの少年。武道場にて剣術の稽古中であるらしい。

佐賀藩でよく稽古されていた剣術の流派は“新陰流”“タイ捨流”などが知られる。地元の道場で学んだ形を大事にする者から、個性を活かした戦い方をする者まで…色々と差異はあったと思われる。
先ほどの少年は、身なりが小ぎれいな相手と立ち会っている。
「キェーッ!」
先に動く相手。気合を発し、様子を伺う。
はっきり言えば、みすぼらしい身なりの少年。相手の気合には動じない。
そして、一言鋭く発した。
「隙ありっ!」
声は一筋、鋭い矢のように飛んだ。
ビリッ!と電流が走ったように、微細に相手が震える。
――シュッ!少年は、木剣を振り下ろす。
「勝負あり!江藤の勝ちだ。」
審判役の少年が、粗末な身なりの少年・江藤を勝者と告げた。
「おい…江藤と言ったか、お主の声に負けてしもうたばい。」
負けた方の少年もサバサバしている。江藤の実力を認めたらしい。
「声で勝負をしているつもりは無かです。」
江藤という少年。無自覚であるらしい。
「まぁ、よか。剣の腕そのものも、お主が上のようじゃし。」
少年はカラカラと笑った。
――もちろん、藩校では学問もみっちりと詰め込まれるが…
儒学の教典“大学”の講義があった。
「では、江藤。その一節を黙読してから、答えるように。」
しかし、江藤はすぐ答えを返した。
「“大学”の内容は、概ね頭に入っておりますゆえ。」
教師は感心した。
「おお、よく学んでおるな。」
授業後、他の生徒が尋ねる。
「お主、藩校には入ったばかりではないのか。いつの間に学んだのだ。」
江藤が答える。
「母から習い申した。」
尋ねた生徒が驚く。
「母!?お主の母上は、一体何者なのじゃ?」
――江藤家は“手明鑓”と呼ばれる侍と、どうにか同格扱いの下級武士。
江藤の父は、才能はあったが実直過ぎる性格が災いし、役職を解かれていた。そのため、江藤家は佐賀城下を離れ、縁のある小城にて江藤は育ってきた。
学問のある江藤の母は、近所の子どもたちに手習いを教え、生計を支えたと言う。
このたび父が役職に付くことができたため、江藤は佐賀城下に戻り、藩校に入学したのである。
(続く)
2020年03月07日
第5話「藩校立志」⑧
こんにちは。
新型コロナウイルスへの対策のため、小中学校が休校となり、「さがファンブログ」内でも様々な意見を見かけます。
現在では、あって当然の“義務教育”ですが、もともと明治時代に佐賀の人の主導により進められたものです。
今回は、“佐賀の七賢人”(その5)大木喬任(たかとう)が初登場します。
但し、“義務教育”を創った人らしくないエピソードから描きますので、ご容赦のほどを。
――大隈八太郎は、7歳で藩校「弘道館」に通い始めた。
藩士の子弟が通う、年少のクラスである。
「太平記」など軍記物語が効き過ぎて、かつての“甘えん坊”は、すっかり“暴れん坊”になっている。
八太郎たちが“合戦ごっこ”をする。
「そこにおったか!かくご!」
――「ペチッ!パチッ!」と賑やかな音がする。
「ビェ~ン…!!」
八太郎は、「太平記」の英雄・楠木正成に成りきっているので、素早く策を用いる。悪く言えば、わりとズルい攻撃もするので、相手を泣かしてしまうこともあった。
「はちたろう!ひきょうなり!」
大勢で反撃に来る。
「まずい!ひとまず、引くぞ!」
多勢に無勢。逃げ出す八太郎と、その友達。
――大隈の母、三井子は悩んでいた。
「八太郎!なぜに喧嘩ばかり…」
強い子になってほしくて、勇ましい武将の物語を読んだら効き過ぎた。子育ては、数学のようにはハッキリと答えが出ない。
「なむあみだぶつ…」
三井子は、とりあえず幾度か念仏を唱えた。神に祈ったり、仏にすがったり…いろいろ信心深い。
「まぁ、八太郎も男の子だ。喧嘩もするだろうさ。」
父・信保は、弾道計算や火薬調合も担当しており、現代で言えば理系人材。わりと冷静である。
「たまに喧嘩は良いのです!毎日、傷だらけで帰って来るのですよ!誰に似たのだか…」
三井子は“女丈夫”とも呼ばれ「強い女性」としても評判だったらしい。八太郎の気性の荒い部分は、母譲りだったのかもしれない。
――そんな喧嘩ばかりの八太郎の通学路である。
八太郎は、年長の2人の男子が、やや大柄な男の子をからかっているのを目撃する。
「幡六だ…。何やら馬鹿にされておるのか?」
幡六とは、後の大木喬任。
八太郎の6歳年上。母方の親戚であるため、面識があった。
大木幡六は先年、父を亡くしている。何やら、父がいないことを揶揄(やゆ)されているようだ。
いわば小学生が中学生のケンカを目撃している状況。年長者同士の争いに関わるのは無用だ。でも、八太郎には興味がある。物影から見守った。
――と、その時。「ベチッ!!」と鈍い音がした。
大木の右手が、からかっていた相手の鼻っ柱を捉えていた。ほどなく、相手の鼻から血が流れ出る。

――ドシン!
大木は、すかさず相手の着物の前襟をつかむと、そのまま塀まで押し込んだ。そして、右腕と壁で相手の首を挟み、圧迫する。
「…く、苦しい…」
流れ続ける鼻血。壁と右腕に挟まれて、足も浮き上がる。相手は呼吸が難しい。
大木を愚鈍とみて、一緒になってからかっていたもう1人は、完全に戦意を喪失している。仲間を助けに来ようともしない。
――ドサッ!
大木は、これ以上戦う価値すら無いと感じた。壁に押し当てていた右腕を緩め、相手を手前に強く引き倒す。
「ひえっ!」
相手は前のめりで倒れる。鼻血ダラダラである。
――ここまで一切、言葉を発しなかった大木。
大声で一言。
「つまらん!!」
捨て台詞を発して、その場を去る大木。
何も怒りは治まっていないようだった。
「つまらん!つまらん奴ばかりだ。」
――当時の大木幡六(喬任)は、いろいろ強がっていた。
“漢学”の教養が高かった父を、11歳の時点で亡くしたことが、大木の心に影を落としていた。
しかも、大木はあまり口がうまくない。
いくら勉強を積んでも、自在に表現ができず鬱積する一方だった。
そんな大木が、心を熱くする友と出会うのは、数年後になる。
その友とは、佐賀の七賢人(その6)江藤新平である。
――そして、佐賀の七賢人(その7)は、一部始終を物影で見ていたこの子。
「えすか(怖い)けん!幡六とはケンカできんばい!」
大隈八太郎(重信)である。
八太郎たちの賑やかな喧嘩とは全く違い、ただ痛そうな戦い方である。大木とは喧嘩をしないことにした。
これで、本編でも“佐賀の七賢人”の名が出揃った。
…“よそ行き”の言葉と“佐賀ことば”の使い方が難しいが、そこは大目にみていただきたい。
(続く)
新型コロナウイルスへの対策のため、小中学校が休校となり、「さがファンブログ」内でも様々な意見を見かけます。
現在では、あって当然の“義務教育”ですが、もともと明治時代に佐賀の人の主導により進められたものです。
今回は、“佐賀の七賢人”(その5)大木喬任(たかとう)が初登場します。
但し、“義務教育”を創った人らしくないエピソードから描きますので、ご容赦のほどを。
――大隈八太郎は、7歳で藩校「弘道館」に通い始めた。
藩士の子弟が通う、年少のクラスである。
「太平記」など軍記物語が効き過ぎて、かつての“甘えん坊”は、すっかり“暴れん坊”になっている。
八太郎たちが“合戦ごっこ”をする。
「そこにおったか!かくご!」
――「ペチッ!パチッ!」と賑やかな音がする。
「ビェ~ン…!!」
八太郎は、「太平記」の英雄・楠木正成に成りきっているので、素早く策を用いる。悪く言えば、わりとズルい攻撃もするので、相手を泣かしてしまうこともあった。
「はちたろう!ひきょうなり!」
大勢で反撃に来る。
「まずい!ひとまず、引くぞ!」
多勢に無勢。逃げ出す八太郎と、その友達。
――大隈の母、三井子は悩んでいた。
「八太郎!なぜに喧嘩ばかり…」
強い子になってほしくて、勇ましい武将の物語を読んだら効き過ぎた。子育ては、数学のようにはハッキリと答えが出ない。
「なむあみだぶつ…」
三井子は、とりあえず幾度か念仏を唱えた。神に祈ったり、仏にすがったり…いろいろ信心深い。
「まぁ、八太郎も男の子だ。喧嘩もするだろうさ。」
父・信保は、弾道計算や火薬調合も担当しており、現代で言えば理系人材。わりと冷静である。
「たまに喧嘩は良いのです!毎日、傷だらけで帰って来るのですよ!誰に似たのだか…」
三井子は“女丈夫”とも呼ばれ「強い女性」としても評判だったらしい。八太郎の気性の荒い部分は、母譲りだったのかもしれない。
――そんな喧嘩ばかりの八太郎の通学路である。
八太郎は、年長の2人の男子が、やや大柄な男の子をからかっているのを目撃する。
「幡六だ…。何やら馬鹿にされておるのか?」
幡六とは、後の大木喬任。
八太郎の6歳年上。母方の親戚であるため、面識があった。
大木幡六は先年、父を亡くしている。何やら、父がいないことを揶揄(やゆ)されているようだ。
いわば小学生が中学生のケンカを目撃している状況。年長者同士の争いに関わるのは無用だ。でも、八太郎には興味がある。物影から見守った。
――と、その時。「ベチッ!!」と鈍い音がした。
大木の右手が、からかっていた相手の鼻っ柱を捉えていた。ほどなく、相手の鼻から血が流れ出る。
――ドシン!
大木は、すかさず相手の着物の前襟をつかむと、そのまま塀まで押し込んだ。そして、右腕と壁で相手の首を挟み、圧迫する。
「…く、苦しい…」
流れ続ける鼻血。壁と右腕に挟まれて、足も浮き上がる。相手は呼吸が難しい。
大木を愚鈍とみて、一緒になってからかっていたもう1人は、完全に戦意を喪失している。仲間を助けに来ようともしない。
――ドサッ!
大木は、これ以上戦う価値すら無いと感じた。壁に押し当てていた右腕を緩め、相手を手前に強く引き倒す。
「ひえっ!」
相手は前のめりで倒れる。鼻血ダラダラである。
――ここまで一切、言葉を発しなかった大木。
大声で一言。
「つまらん!!」
捨て台詞を発して、その場を去る大木。
何も怒りは治まっていないようだった。
「つまらん!つまらん奴ばかりだ。」
――当時の大木幡六(喬任)は、いろいろ強がっていた。
“漢学”の教養が高かった父を、11歳の時点で亡くしたことが、大木の心に影を落としていた。
しかも、大木はあまり口がうまくない。
いくら勉強を積んでも、自在に表現ができず鬱積する一方だった。
そんな大木が、心を熱くする友と出会うのは、数年後になる。
その友とは、佐賀の七賢人(その6)江藤新平である。
――そして、佐賀の七賢人(その7)は、一部始終を物影で見ていたこの子。
「えすか(怖い)けん!幡六とはケンカできんばい!」
大隈八太郎(重信)である。
八太郎たちの賑やかな喧嘩とは全く違い、ただ痛そうな戦い方である。大木とは喧嘩をしないことにした。
これで、本編でも“佐賀の七賢人”の名が出揃った。
…“よそ行き”の言葉と“佐賀ことば”の使い方が難しいが、そこは大目にみていただきたい。
(続く)
2020年03月05日
第5話「藩校立志」⑦
こんばんは。
新型肺炎のニュースの合間に、米大統領選の候補者選びのヤマ場「スーパーチューズデー」のニュースが入っていました。
佐賀の七賢人(その4)副島種臣ですが、なんと幕末期に長崎でアメリカ合衆国憲法を学んでいます。
この知識が明治新国家の組織を構築し、方向性を定めるのに大きな力となります。しかし本編の副島種臣は、まだ“偉大な兄さん”の存在にプレッシャーを感じる弟、“次郎さん”です。
――佐賀の藩校「弘道館」は数年前(1840年)に大幅に拡充された。
殿・鍋島直正が頻繁に訪れ、佐賀藩ナンバー2の請役・鍋島安房が責任者を務める。
この藩校の拡充は、直正の師匠・古賀穀堂の残した意見書「学政管見」によるものだった。
「穀堂先生!この学舎で、先生のご期待に沿う“学ぶ者”を育てますぞ!」
直正はグッと右拳を握る。
――古賀穀堂は、藩校拡充の数年前、佐賀城の再建が始まった頃にこの世を去っていた。
城に戻る直正、藩校に向かう鍋島安房と城の堀端ですれ違う。

藩校「弘道館」は、“四十間堀”とも言われる、佐賀城の広大な堀の目前にある。
「おおっ、安房よ!頑張っておるな。」
――働き過ぎの鍋島安房。“城での政務”と“藩校の責任者”の双方ともこなしている。
「殿っ、ごきげんうるわしゅう…ござる。」
明らかに睡眠が足りていない。さすがに直正が一声かける。
「安房よ…熱心なのは良いが、たまには寝るのだぞ。」
――さて、副島種臣(枝吉次郎)の話に戻る。藩校「弘道館」にて。
次郎が、藩校の学生たちと話をしている。
「日本の君主は、帝お一人!しかし、身分に応じた上下の秩序も…。」
何やら次郎の言葉は、歯切れが悪い。少し整理しよう。
次郎の家、枝吉家の“国学”の考え方で言えば「日本の君主は天皇ただ1人」である。
しかし、藩校で主に学ぶ“朱子学”では、身分の序列が大事なのである。
たとえば、将軍や大名たち、各藩の中の主従関係、士農工商など…幕府の基本原理に合う学問だった。
――次郎は迷っていた。評判の天才である兄・枝吉神陽の顔に泥を塗ってはいけない。
優等生になるためには、幕府の公式学問“朱子学”をよく学ぶことだ。
また、佐賀武士の教典“葉隠”も自分の使える主君への忠義を大事にする。
次郎は、結局あたりさわりの無いことを言った。
「やはり…身分の序列は大事であるな。殿への忠義が一番である。」
周囲の学生たちは、拍子抜けした。
「勿体ぶって当たり前のことを言う。枝吉神陽の弟にしては、冴えないのう。」
この反応が枝吉次郎(副島種臣)が、悩んでいる理由である。
たしかに大隈八太郎たちのような“お子さま”にはわからないかもしれない。
――この頃、兄・枝吉神陽は、江戸から佐賀に一時、戻っていた。
枝吉神陽も、弟の勉強の進みは気になる。
「次郎よ、学問は進んでおるか。」
「はっ、まずまずでございます。」
相変わらず神陽の声はよく通る。しかも江戸での修業で風格が増している。
「今は、何を学んでおる。」
次郎は小さい声でボソボソと答えた。
「朱子学や、葉隠を。」
――次第に兄・枝吉神陽の表情が険しくなる。
「では今、学んでいることをどう活かしていくのか。」
次郎はやむを得ず答える。
「藩校の推奨する学問で、周りの者にも映りがよいので。」
神陽は、次郎を一喝した。
「お前は何のために学問をしておるのだ!人に見せるためか!」
次郎には返す言葉が無い。
後に、副島種臣は「あの時の兄さんが何より怖かった…」と語るほどだった。
神陽も、次郎が学問に迷っていることは見抜いていた。
見栄えのための勉強では、先につながっていかない。あえて強く戒めたのである。
(続く)
新型肺炎のニュースの合間に、米大統領選の候補者選びのヤマ場「スーパーチューズデー」のニュースが入っていました。
佐賀の七賢人(その4)副島種臣ですが、なんと幕末期に長崎でアメリカ合衆国憲法を学んでいます。
この知識が明治新国家の組織を構築し、方向性を定めるのに大きな力となります。しかし本編の副島種臣は、まだ“偉大な兄さん”の存在にプレッシャーを感じる弟、“次郎さん”です。
――佐賀の藩校「弘道館」は数年前(1840年)に大幅に拡充された。
殿・鍋島直正が頻繁に訪れ、佐賀藩ナンバー2の請役・鍋島安房が責任者を務める。
この藩校の拡充は、直正の師匠・古賀穀堂の残した意見書「学政管見」によるものだった。
「穀堂先生!この学舎で、先生のご期待に沿う“学ぶ者”を育てますぞ!」
直正はグッと右拳を握る。
――古賀穀堂は、藩校拡充の数年前、佐賀城の再建が始まった頃にこの世を去っていた。
城に戻る直正、藩校に向かう鍋島安房と城の堀端ですれ違う。

藩校「弘道館」は、“四十間堀”とも言われる、佐賀城の広大な堀の目前にある。
「おおっ、安房よ!頑張っておるな。」
――働き過ぎの鍋島安房。“城での政務”と“藩校の責任者”の双方ともこなしている。
「殿っ、ごきげんうるわしゅう…ござる。」
明らかに睡眠が足りていない。さすがに直正が一声かける。
「安房よ…熱心なのは良いが、たまには寝るのだぞ。」
――さて、副島種臣(枝吉次郎)の話に戻る。藩校「弘道館」にて。
次郎が、藩校の学生たちと話をしている。
「日本の君主は、帝お一人!しかし、身分に応じた上下の秩序も…。」
何やら次郎の言葉は、歯切れが悪い。少し整理しよう。
次郎の家、枝吉家の“国学”の考え方で言えば「日本の君主は天皇ただ1人」である。
しかし、藩校で主に学ぶ“朱子学”では、身分の序列が大事なのである。
たとえば、将軍や大名たち、各藩の中の主従関係、士農工商など…幕府の基本原理に合う学問だった。
――次郎は迷っていた。評判の天才である兄・枝吉神陽の顔に泥を塗ってはいけない。
優等生になるためには、幕府の公式学問“朱子学”をよく学ぶことだ。
また、佐賀武士の教典“葉隠”も自分の使える主君への忠義を大事にする。
次郎は、結局あたりさわりの無いことを言った。
「やはり…身分の序列は大事であるな。殿への忠義が一番である。」
周囲の学生たちは、拍子抜けした。
「勿体ぶって当たり前のことを言う。枝吉神陽の弟にしては、冴えないのう。」
この反応が枝吉次郎(副島種臣)が、悩んでいる理由である。
たしかに大隈八太郎たちのような“お子さま”にはわからないかもしれない。
――この頃、兄・枝吉神陽は、江戸から佐賀に一時、戻っていた。
枝吉神陽も、弟の勉強の進みは気になる。
「次郎よ、学問は進んでおるか。」
「はっ、まずまずでございます。」
相変わらず神陽の声はよく通る。しかも江戸での修業で風格が増している。
「今は、何を学んでおる。」
次郎は小さい声でボソボソと答えた。
「朱子学や、葉隠を。」
――次第に兄・枝吉神陽の表情が険しくなる。
「では今、学んでいることをどう活かしていくのか。」
次郎はやむを得ず答える。
「藩校の推奨する学問で、周りの者にも映りがよいので。」
神陽は、次郎を一喝した。
「お前は何のために学問をしておるのだ!人に見せるためか!」
次郎には返す言葉が無い。
後に、副島種臣は「あの時の兄さんが何より怖かった…」と語るほどだった。
神陽も、次郎が学問に迷っていることは見抜いていた。
見栄えのための勉強では、先につながっていかない。あえて強く戒めたのである。
(続く)
2020年03月04日
第5話「藩校立志」⑥
こんばんは。
民間の調査会社が実施している「都道府県魅力度ランキング」がよく話題になります。2019年、なんと佐賀県は46位でした。そして最下位の47位は…茨城県です。
この二者ですが、幕末には“科学技術”の佐賀藩と“尊王思想”の水戸藩。双方ともトップランナーと言って良い存在でした。
魅力度ランキングへの「異議あり!」はさておき、本編に戻ります。
今回は、“団にょん”こと島義勇が、水戸藩(茨城)に立ち寄るところから。
――後に札幌を創る男、諸国遊学中に水戸(茨城)に立ち寄る。
島義勇、水戸藩の尊王思想家・藤田東湖に面会を許される。
「島と申します!藤田先生にお目にかかれるとは、光栄の至りです!」
いつになく畏まっている“団にょん”である。
「島くんと言ったか。佐賀の者と聞いたのでな。」
藤田東湖は、いかにも一角(ひとかど)の人物とわかるような風貌である。
「はっ、恐縮でございます!」
――島がここまで敬意を払う理由は、著名な思想家であるだけではない。
藤田東湖は、御三家・水戸藩の徳川斉昭を支える“政策ブレーン”でもあるのだ。
そして江戸で修業してきた佐賀藩士たちとも親しいらしい。
「そうだな。永山十兵衛どのはお元気か。」
「永山先生には、藩校でご教授をいただきました。」
殿(鍋島直正)の命令で、永山は東北地方を調査した。
その言葉は、まっすぐ島の心に届いたのである。
「そうだ、枝吉神陽も佐賀じゃな。あの男は賢いのう!」
「枝吉は親族ではございますが、飛びぬけておりまして…」
…あれっ、藤田様からの近況伺いだけで、話が終わってしまったぞ。
まだまだじゃな!がんばれ“団にょん”!
――やや“朝ドラ”風のナレーションが入ったところで、舞台は、佐賀城下に戻る。

「新田(にった)どの!ぬかるなよ、はさみうちじゃ!」
楠木正成に成りきった男の子が駆ける。少し成長した大隈八太郎である。
「楠木(くすのき)どの!こころえた!」
同じ南朝の武将“新田義貞”役は、八太郎の友達である。
「尊氏(たかうじ)そこにいたか、かくご!」
「直義(ただよし)!おいつめたぞ!」
足利勢に見立てた2人と戦っているのだ。
――この南北朝時代の“合戦ごっこ”、相手方が乗り気でない。
「待たんね!わしも楠公(なんこう)さんが、よかごた!」
「そうたい、南朝方(なんちょうがた)がよか!」
歴史上は、北朝方の足利尊氏が勝者とされる。
しかし佐賀では、南朝方の楠木正成が人気のようだ。
――そこに、15歳ぐらいの男子が通りがかる。うつむき加減である。
いきなり登場した佐賀の七賢人(その4)副島種臣である。何やら呟(つぶや)いている。
「また、恥をかいてしもうた…」
後に副島家の養子になるのだが、この頃の名は“枝吉次郎”。
あの佐賀藩の誇る天才・枝吉神陽の弟である。
そんな次郎の耳に、子どもたちの声が入ってくる…
「八太郎ばかり、楠公(なんこう)さんで、ずるか!!」
「そうたい!楠公(なんこう)さんがよかたい!」
――結局、子どもたちは“合戦ごっこ”から“喧嘩”を始める。
激しいつかみ合いをする、八太郎くんたち。
次郎は独り言をつぶやく。
「あ~、子どもは良かね!悩みが無うて!」
「やはり楠公さんが、大人気なのも兄上の影響かのう…」
兄貴は、偉大な枝吉神陽。
弟の次郎(副島種臣)、出てくるなり何やら悩みが深い…
(続く)
民間の調査会社が実施している「都道府県魅力度ランキング」がよく話題になります。2019年、なんと佐賀県は46位でした。そして最下位の47位は…茨城県です。
この二者ですが、幕末には“科学技術”の佐賀藩と“尊王思想”の水戸藩。双方ともトップランナーと言って良い存在でした。
魅力度ランキングへの「異議あり!」はさておき、本編に戻ります。
今回は、“団にょん”こと島義勇が、水戸藩(茨城)に立ち寄るところから。
――後に札幌を創る男、諸国遊学中に水戸(茨城)に立ち寄る。
島義勇、水戸藩の尊王思想家・藤田東湖に面会を許される。
「島と申します!藤田先生にお目にかかれるとは、光栄の至りです!」
いつになく畏まっている“団にょん”である。
「島くんと言ったか。佐賀の者と聞いたのでな。」
藤田東湖は、いかにも一角(ひとかど)の人物とわかるような風貌である。
「はっ、恐縮でございます!」
――島がここまで敬意を払う理由は、著名な思想家であるだけではない。
藤田東湖は、御三家・水戸藩の徳川斉昭を支える“政策ブレーン”でもあるのだ。
そして江戸で修業してきた佐賀藩士たちとも親しいらしい。
「そうだな。永山十兵衛どのはお元気か。」
「永山先生には、藩校でご教授をいただきました。」
殿(鍋島直正)の命令で、永山は東北地方を調査した。
その言葉は、まっすぐ島の心に届いたのである。
「そうだ、枝吉神陽も佐賀じゃな。あの男は賢いのう!」
「枝吉は親族ではございますが、飛びぬけておりまして…」
…あれっ、藤田様からの近況伺いだけで、話が終わってしまったぞ。
まだまだじゃな!がんばれ“団にょん”!
――やや“朝ドラ”風のナレーションが入ったところで、舞台は、佐賀城下に戻る。
「新田(にった)どの!ぬかるなよ、はさみうちじゃ!」
楠木正成に成りきった男の子が駆ける。少し成長した大隈八太郎である。
「楠木(くすのき)どの!こころえた!」
同じ南朝の武将“新田義貞”役は、八太郎の友達である。
「尊氏(たかうじ)そこにいたか、かくご!」
「直義(ただよし)!おいつめたぞ!」
足利勢に見立てた2人と戦っているのだ。
――この南北朝時代の“合戦ごっこ”、相手方が乗り気でない。
「待たんね!わしも楠公(なんこう)さんが、よかごた!」
「そうたい、南朝方(なんちょうがた)がよか!」
歴史上は、北朝方の足利尊氏が勝者とされる。
しかし佐賀では、南朝方の楠木正成が人気のようだ。
――そこに、15歳ぐらいの男子が通りがかる。うつむき加減である。
いきなり登場した佐賀の七賢人(その4)副島種臣である。何やら呟(つぶや)いている。
「また、恥をかいてしもうた…」
後に副島家の養子になるのだが、この頃の名は“枝吉次郎”。
あの佐賀藩の誇る天才・枝吉神陽の弟である。
そんな次郎の耳に、子どもたちの声が入ってくる…
「八太郎ばかり、楠公(なんこう)さんで、ずるか!!」
「そうたい!楠公(なんこう)さんがよかたい!」
――結局、子どもたちは“合戦ごっこ”から“喧嘩”を始める。
激しいつかみ合いをする、八太郎くんたち。
次郎は独り言をつぶやく。
「あ~、子どもは良かね!悩みが無うて!」
「やはり楠公さんが、大人気なのも兄上の影響かのう…」
兄貴は、偉大な枝吉神陽。
弟の次郎(副島種臣)、出てくるなり何やら悩みが深い…
(続く)
2020年03月03日
第5話「藩校立志」⑤
こんばんは。
前回の続きです。“佐賀ことば”の導入テストも兼ねております…
――長崎奉行所に対して、オランダの軍船に乗り込む交渉をしている時。
鍋島直正が、“新・長崎御番の侍”・本島藤太夫を呼び寄せる。
「本島よ!“火術方の者”に鉄(くろがね)の砲を見せておきたいのう…」
直正は、藩の学校や大砲の実験場に自ら足を運ぶ。“現場主義”のリーダーである。
鉄製の大砲を備えるという“パレンバン号”。
「ぜひ技術者に見せておきたい」というのが、直正の意向である。
直正は、佐賀藩の“火術方”で製造を担当する「刀鍛冶」や「鋳物師」のリーダーを務める2人を同行させるつもりだ。
「はっ、殿の仰せとあらば。私が見守ります。」
――そして当日、技術者(職人)もオランダ軍船に乗り込むことに。
本島が、技術者2人に言葉をかける。
「不慣れな場であると思う。まずは振る舞いに気をつけてほしい。」
外交儀礼を重んじる奉行所の手前、行動に気をつけるよう念押しである。
技術第一の“職人モード”はできれば抑えてほしい。
「こん船は陸(おか)のごたぁ!」
橋本という。肥前の名刀を打つ“刀鍛冶”である。
巨大なオランダ軍船の安定感に驚いている。

まるで揺るぎない大地から海を眺めているようだ。
「鉄(くろがね)の大筒、早く見たかですばい。」
こちらは“鋳物師”。名を谷口という。
彼らの“技術”を見る目は本物だが、本島には不安があった。
――そして2人がパレンバン号の“鉄製大砲”を見た瞬間、本島の心配は的中した。
まず、口火を切ったのは谷口の方だった。
「凄かっ!こがん鋳物は見たことなかばい!」
そして、橋本が続く。形は違えど“刀鍛冶”魂が抑えられない。
「どがん鍛(きた)えっとね!」
“鉄製大砲”前で大騒ぎしている2人。もはや止まる気配がない。
苦笑するオランダの水兵たち。
本島は頭を抱えた。そして、気づく。
「はっ、そういえば、殿はいずこに…」
――そして大騒ぎしているのは、彼らの殿様も一緒だった。
通詞(通訳)へ矢継ぎ早に、言葉を放つ直正。
「これは、どう撃つのじゃ。弾はどのように込めるのじゃ!」
“肥前(直正)様”の異様な好奇心は、オランダ士官の想定をはるかに超える。
オランダ士官が、やや当惑しながら手本を示す。
「…ハイ、コノ小銃ハデスネ。コノヨウニ…」
直正に記録係として付いてきた、古川与一(松根)。
「殿…絵には、もう少し落ち着いた姿で描きまする…」
――このとき、古川は“パレンバン号”乗船の記録として多数の絵を残している。
直正は意欲に溢れる視察を続ける。
「次は、鉄の大筒を見たいぞ!案内(あない)いたせ!」
とうとうオランダ士官と直接コミュニケーションを取り始めた直正。
「通訳ヲ入レズトモ、肥前サマガ何ヲ見タイカ、伝ワッテマス…」
直正は大砲の前で見学を続ける、鋳物師・谷口と刀鍛冶・橋本と出会う。
「おおっ、殿もお越しじゃ。」
「殿!こん大筒、がばい凄かです!」
下級藩士とも直接、技術談義を始めてしまう直正。
「おお、かように凄いか!」
「すごかですばい!」
――本島は、とりあえず長崎奉行所の役人に気を遣っておく。
「このたびは、貴重な乗船をお認めいただき、まことに忝(かたじけな)く存じます!」
「おお、本島どのか。そなたもご苦労であるな…やはり佐賀の者にはついて行けん。」
――幕府の煮え切らない態度にイライラしていた、艦長コープスは、かえって上機嫌になった。
“パレンバン号”艦長コープス。直正の来訪に、盛大な接待の席を設けた。
「はっはっは。この国に、このような領主(大名)がいらっしゃるとは!すごい好奇心だ!」
傍にいた士官が報告する。
「大砲、水兵の訓練、医務室…家畜小屋から酒蔵まで、全部ご案内しています!」
ふと冷静になった艦長コープス。ポツリと言葉を発する。
「肥前様について、本国(オランダ)に報告しておこう。この国を動かす人物かもしれない。」
(続く)
前回の続きです。“佐賀ことば”の導入テストも兼ねております…
――長崎奉行所に対して、オランダの軍船に乗り込む交渉をしている時。
鍋島直正が、“新・長崎御番の侍”・本島藤太夫を呼び寄せる。
「本島よ!“火術方の者”に鉄(くろがね)の砲を見せておきたいのう…」
直正は、藩の学校や大砲の実験場に自ら足を運ぶ。“現場主義”のリーダーである。
鉄製の大砲を備えるという“パレンバン号”。
「ぜひ技術者に見せておきたい」というのが、直正の意向である。
直正は、佐賀藩の“火術方”で製造を担当する「刀鍛冶」や「鋳物師」のリーダーを務める2人を同行させるつもりだ。
「はっ、殿の仰せとあらば。私が見守ります。」
――そして当日、技術者(職人)もオランダ軍船に乗り込むことに。
本島が、技術者2人に言葉をかける。
「不慣れな場であると思う。まずは振る舞いに気をつけてほしい。」
外交儀礼を重んじる奉行所の手前、行動に気をつけるよう念押しである。
技術第一の“職人モード”はできれば抑えてほしい。
「こん船は陸(おか)のごたぁ!」
橋本という。肥前の名刀を打つ“刀鍛冶”である。
巨大なオランダ軍船の安定感に驚いている。

まるで揺るぎない大地から海を眺めているようだ。
「鉄(くろがね)の大筒、早く見たかですばい。」
こちらは“鋳物師”。名を谷口という。
彼らの“技術”を見る目は本物だが、本島には不安があった。
――そして2人がパレンバン号の“鉄製大砲”を見た瞬間、本島の心配は的中した。
まず、口火を切ったのは谷口の方だった。
「凄かっ!こがん鋳物は見たことなかばい!」
そして、橋本が続く。形は違えど“刀鍛冶”魂が抑えられない。
「どがん鍛(きた)えっとね!」
“鉄製大砲”前で大騒ぎしている2人。もはや止まる気配がない。
苦笑するオランダの水兵たち。
本島は頭を抱えた。そして、気づく。
「はっ、そういえば、殿はいずこに…」
――そして大騒ぎしているのは、彼らの殿様も一緒だった。
通詞(通訳)へ矢継ぎ早に、言葉を放つ直正。
「これは、どう撃つのじゃ。弾はどのように込めるのじゃ!」
“肥前(直正)様”の異様な好奇心は、オランダ士官の想定をはるかに超える。
オランダ士官が、やや当惑しながら手本を示す。
「…ハイ、コノ小銃ハデスネ。コノヨウニ…」
直正に記録係として付いてきた、古川与一(松根)。
「殿…絵には、もう少し落ち着いた姿で描きまする…」
――このとき、古川は“パレンバン号”乗船の記録として多数の絵を残している。
直正は意欲に溢れる視察を続ける。
「次は、鉄の大筒を見たいぞ!案内(あない)いたせ!」
とうとうオランダ士官と直接コミュニケーションを取り始めた直正。
「通訳ヲ入レズトモ、肥前サマガ何ヲ見タイカ、伝ワッテマス…」
直正は大砲の前で見学を続ける、鋳物師・谷口と刀鍛冶・橋本と出会う。
「おおっ、殿もお越しじゃ。」
「殿!こん大筒、がばい凄かです!」
下級藩士とも直接、技術談義を始めてしまう直正。
「おお、かように凄いか!」
「すごかですばい!」
――本島は、とりあえず長崎奉行所の役人に気を遣っておく。
「このたびは、貴重な乗船をお認めいただき、まことに忝(かたじけな)く存じます!」
「おお、本島どのか。そなたもご苦労であるな…やはり佐賀の者にはついて行けん。」
――幕府の煮え切らない態度にイライラしていた、艦長コープスは、かえって上機嫌になった。
“パレンバン号”艦長コープス。直正の来訪に、盛大な接待の席を設けた。
「はっはっは。この国に、このような領主(大名)がいらっしゃるとは!すごい好奇心だ!」
傍にいた士官が報告する。
「大砲、水兵の訓練、医務室…家畜小屋から酒蔵まで、全部ご案内しています!」
ふと冷静になった艦長コープス。ポツリと言葉を発する。
「肥前様について、本国(オランダ)に報告しておこう。この国を動かす人物かもしれない。」
(続く)
2020年03月01日
第5話「藩校立志」④
こんばんは。
前回の続きです。
――江戸幕府「究極の水際対策」である“鎖国”の完成から、およそ200年が経過していた。
徳川政権は秩序の維持に“鎖国”を機能させ、世界史上でも稀にみるほど、平和な時代を作ったとも言われる。
しかし、直前のアヘン戦争、そして次々に日本沿海に現れる西洋列強の船。時代の流れは“鎖国”の維持を許さない方向に進んでいく。
――“パレンバン号”入港に際し、長崎警護に各藩から集められた兵員は4千人ほどと言われる。
当番の佐賀藩が主力として、福岡藩や近隣諸藩からも兵が動員されていた。長崎港を囲む各陣地で、厳戒態勢が取られる。
――パレンバン号の艦長コープスは、オランダ国王ウィレム二世の親書を携えていた。
オランダ国王よりのお手紙の趣旨は大体こうである。
~親愛なる日本の大君(将軍)さまへ~
「わがオランダ国は日本と長いお付き合いをいたしております。」
「それゆえ、心配をしているのです。そろそろ開国した方が良い情勢です。」
「あまり強硬に“鎖国”にこだわると、アヘン戦争での清国の二の舞になりますよ。」
概ね以上である。

長崎奉行所は、オランダの国書を受け取り、江戸にお伺いを立てた。
――江戸。このオランダ国書に対し、幕府の議論は紛糾。まったく話が進まない。
当時、幕政の中心は「天保の改革」の失敗で、一度、政権を追われた水野忠邦。前の老中・土井が火災の事後処理に失敗し、急遽、再登板となっている。
一旦、権力を取り戻した水野。
まず、以前裏切った鳥居耀蔵を遠方に飛ばす。
ここで、また厄介事である。
もはや水野に政権維持への意欲は湧いてこない。
「待たせよ!とりあえず先送りせよ!」
――長崎。そして、待たされる“パレンバン号”艦長のコープス。
ここからはオランダ語である。苛立つコープス艦長。
「江戸はいつまで待たせるつもりだ!」
士官の1人が挙手する。
「コープス艦長!こういうのを“優柔不断”と言うのでしょうか!」
「あぁ、そうだな。この国では良くあることらしい。」
他の士官が甲板に上がってくる。
「ご報告します!“肥前の国”の領主が、我が艦を見学したい!と打診してきています。」
コープス艦長の眉が動く。
「何、我が艦を見たいと…そんな領主(大名)がいるのか?」
――それが、いるのである。肥前佐賀(35万7千石)・鍋島直正。
直正は、幼い頃からの側近、古川与一に喜びを語る。
「与一よ、ついに見られるぞ!オランダの軍船じゃ!」
「それは、ようございましたね。」
古川与一(松根)は主に直正の世話を担当する側近。現代風に言えば“執事”であろうか。
直正は「与一が1日でもいないと不便である!」と語るほどだった。
――さて、直正は、その古川与一(松根)に指示を出す。
「与一よ、“パレンバン号”に同乗し、記録を残してほしい。」
現代で言えば“写真係”の依頼である。
カメラがあるわけではないので、古川与一は現場を絵に描き起こす。
与一は、和歌、書、そして絵画…芸術系の才に恵まれる。文化人・古川松根としても著名である。
「与一よ!装束(服)は、これが良いか!」
直正は、ビシッと赤い袴を着こなす。
「殿、お似合いですぞ!オランダ国の者にも威厳は示さねばなりませぬ。」
古川与一は、直正の服飾コーディネートも担当していた。
――そして、直正はオランダ軍船に向かう小舟に乗り込む。
「余すところなく、異国船を見聞するぞ!」
直正は同行の家来たちに、激を飛ばす。
「おお―っ!」
そして直正の言葉に沸く“蘭学大好き”佐賀藩士たち。
「…何やら、佐賀の者たちにはついて行けぬな。」
長崎奉行所の役人たちは、佐賀藩の“熱”に、引き気味であった。
(続く)
前回の続きです。
――江戸幕府「究極の水際対策」である“鎖国”の完成から、およそ200年が経過していた。
徳川政権は秩序の維持に“鎖国”を機能させ、世界史上でも稀にみるほど、平和な時代を作ったとも言われる。
しかし、直前のアヘン戦争、そして次々に日本沿海に現れる西洋列強の船。時代の流れは“鎖国”の維持を許さない方向に進んでいく。
――“パレンバン号”入港に際し、長崎警護に各藩から集められた兵員は4千人ほどと言われる。
当番の佐賀藩が主力として、福岡藩や近隣諸藩からも兵が動員されていた。長崎港を囲む各陣地で、厳戒態勢が取られる。
――パレンバン号の艦長コープスは、オランダ国王ウィレム二世の親書を携えていた。
オランダ国王よりのお手紙の趣旨は大体こうである。
~親愛なる日本の大君(将軍)さまへ~
「わがオランダ国は日本と長いお付き合いをいたしております。」
「それゆえ、心配をしているのです。そろそろ開国した方が良い情勢です。」
「あまり強硬に“鎖国”にこだわると、アヘン戦争での清国の二の舞になりますよ。」
概ね以上である。

長崎奉行所は、オランダの国書を受け取り、江戸にお伺いを立てた。
――江戸。このオランダ国書に対し、幕府の議論は紛糾。まったく話が進まない。
当時、幕政の中心は「天保の改革」の失敗で、一度、政権を追われた水野忠邦。前の老中・土井が火災の事後処理に失敗し、急遽、再登板となっている。
一旦、権力を取り戻した水野。
まず、以前裏切った鳥居耀蔵を遠方に飛ばす。
ここで、また厄介事である。
もはや水野に政権維持への意欲は湧いてこない。
「待たせよ!とりあえず先送りせよ!」
――長崎。そして、待たされる“パレンバン号”艦長のコープス。
ここからはオランダ語である。苛立つコープス艦長。
「江戸はいつまで待たせるつもりだ!」
士官の1人が挙手する。
「コープス艦長!こういうのを“優柔不断”と言うのでしょうか!」
「あぁ、そうだな。この国では良くあることらしい。」
他の士官が甲板に上がってくる。
「ご報告します!“肥前の国”の領主が、我が艦を見学したい!と打診してきています。」
コープス艦長の眉が動く。
「何、我が艦を見たいと…そんな領主(大名)がいるのか?」
――それが、いるのである。肥前佐賀(35万7千石)・鍋島直正。
直正は、幼い頃からの側近、古川与一に喜びを語る。
「与一よ、ついに見られるぞ!オランダの軍船じゃ!」
「それは、ようございましたね。」
古川与一(松根)は主に直正の世話を担当する側近。現代風に言えば“執事”であろうか。
直正は「与一が1日でもいないと不便である!」と語るほどだった。
――さて、直正は、その古川与一(松根)に指示を出す。
「与一よ、“パレンバン号”に同乗し、記録を残してほしい。」
現代で言えば“写真係”の依頼である。
カメラがあるわけではないので、古川与一は現場を絵に描き起こす。
与一は、和歌、書、そして絵画…芸術系の才に恵まれる。文化人・古川松根としても著名である。
「与一よ!装束(服)は、これが良いか!」
直正は、ビシッと赤い袴を着こなす。
「殿、お似合いですぞ!オランダ国の者にも威厳は示さねばなりませぬ。」
古川与一は、直正の服飾コーディネートも担当していた。
――そして、直正はオランダ軍船に向かう小舟に乗り込む。
「余すところなく、異国船を見聞するぞ!」
直正は同行の家来たちに、激を飛ばす。
「おお―っ!」
そして直正の言葉に沸く“蘭学大好き”佐賀藩士たち。
「…何やら、佐賀の者たちにはついて行けぬな。」
長崎奉行所の役人たちは、佐賀藩の“熱”に、引き気味であった。
(続く)