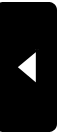2020年12月18日
「如月・二月」(歳末反省会④)
こんばんは。
2020年(令和2年)2月を振り返る、個人的な反省会です。
政府の新型コロナ対策本部が動き出したのは、1月末。
見えざる脅威が、日本にも迫ってきた時期でした。
――この時期、私は佐賀での取材を検討していました…
もしもの時は、仕事への影響も考えねばならず、軽率な行動は取れません。
しばらく様子見をすることにしました。
その分「幕末佐賀藩の大河ドラマ」イメージを立て続けに投稿します。
――おそらく“本編”が最も進んだ時期。
現在、“本編”は第14話「遣米使節」で止まっています。もし、この時の勢いで投稿し続けていたら、第20話くらいまでは進んでいたかもしれません。
ちなみに第1話「長崎警護」は、1808年のフェートン号事件の話が中心で、佐賀藩は“いいところ無し”…でしたが、少しは“主役”を立てねばなりません。

――第1話の最終盤に、幼少期の鍋島直正が登場します。
この段階(1820年頃)は、幼少の直正(貞丸)の教育係・古賀穀堂の目線です。
まだ7~8歳ぐらいの設定ですが、とても賢い若様に希望を見い出します。
〔参照:第1話「長崎警護」⑦〕
第2話「算盤大名」に突入すると年代は、もう1825年。幕府が「異国船打払令」を出したので、長崎の警備担当・佐賀藩もザワザワしています。
〔参照:第2話「算盤大名」①〕
――2月初日の投稿では、すでに殿・直正は17歳。
この佐賀へのお国入りの場面。“本編”に限れば、一番人気の記事です。第1話が長崎寄りのエピソードだったので、第2話はなるべく佐賀にこだわりました。
〔参照:第2話「算盤大名」③-3〕
第2話ラストの投稿は、1835年に佐賀城で起きた火災を題材にしています。
〔参照:第2話「算盤大名」⑤-2〕
――同じ月に、第3話「西洋砲術」と第4話「諸国遊学」も続けています。
最近の投稿は、一応は“歳末反省会”と銘打っています。
「今年の2月は結構、頑張ったかも…」というのが自己評価です。
2020年(令和2年)2月を振り返る、個人的な反省会です。
政府の新型コロナ対策本部が動き出したのは、1月末。
見えざる脅威が、日本にも迫ってきた時期でした。
――この時期、私は佐賀での取材を検討していました…
もしもの時は、仕事への影響も考えねばならず、軽率な行動は取れません。
しばらく様子見をすることにしました。
その分「幕末佐賀藩の大河ドラマ」イメージを立て続けに投稿します。
――おそらく“本編”が最も進んだ時期。
現在、“本編”は第14話「遣米使節」で止まっています。もし、この時の勢いで投稿し続けていたら、第20話くらいまでは進んでいたかもしれません。
ちなみに第1話「長崎警護」は、1808年のフェートン号事件の話が中心で、佐賀藩は“いいところ無し”…でしたが、少しは“主役”を立てねばなりません。

――第1話の最終盤に、幼少期の鍋島直正が登場します。
この段階(1820年頃)は、幼少の直正(貞丸)の教育係・古賀穀堂の目線です。
まだ7~8歳ぐらいの設定ですが、とても賢い若様に希望を見い出します。
〔参照:
第2話「算盤大名」に突入すると年代は、もう1825年。幕府が「異国船打払令」を出したので、長崎の警備担当・佐賀藩もザワザワしています。
〔参照:
――2月初日の投稿では、すでに殿・直正は17歳。
この佐賀へのお国入りの場面。“本編”に限れば、一番人気の記事です。第1話が長崎寄りのエピソードだったので、第2話はなるべく佐賀にこだわりました。
〔参照:
第2話ラストの投稿は、1835年に佐賀城で起きた火災を題材にしています。
〔参照:
――同じ月に、第3話「西洋砲術」と第4話「諸国遊学」も続けています。
最近の投稿は、一応は“歳末反省会”と銘打っています。
「今年の2月は結構、頑張ったかも…」というのが自己評価です。
2020年12月16日
「第1話・長崎警護」を振り返る(歳末反省会③)
こんばんは。
反省会が続きます。時期は1月後半。
「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」との想いが強くなりすぎて、私は自分のイメージを文章化し始めました。
――「佐賀の大河ドラマ」と銘打っていますが…
第1話でドラマが動く舞台は、ほとんど長崎です。
しかも、オープニングで会話しているのは、イギリス人水兵。
「一体、誰だ!テッドとグレッグって…」
思わずツッコミを入れたくなる方も居たかもしれません。
〔参照:第1話「長崎警護」①〕
――ところが、この2名も侮れません。
“フェートン号”の船員名簿を調べたわけもなく、名前の設定は架空。意外に凄腕で、あっと言う間にオランダ商館員を人質に取ります。
〔参照:第1話「長崎警護」③〕
このとき、オランダと対立していたイギリス。
長崎近海でも、英国船がオランダ船を追い回していたようです。

――困難に立ち向かう、長崎奉行・松平康英。
頼みの綱は、長崎の警備担当・佐賀藩(鍋島家)の兵員。しかし、ほとんど(9割ぐらい)が、佐賀に帰っていて不在!
この第1話では、主役の佐賀藩は“いいところ無し”の展開です。佐賀城下も、ひたすらバタバタしています。
〔参照:第1話「長崎警護」⑥-1〕
逆にカッコ良いのは、肥前大村藩。
――長崎の方も、きっとわかってくれるはず…
“佐賀の大河ドラマ”の実現は、長崎にとっても、ビッグチャンスですよ。
本来の警備部隊がいないことで、苦しむ長崎奉行所。
まだ夜明け前に颯爽と現れたのが、大村藩主・大村純昌。
私の勝手なイメージでは、いかにも“海の大名”な感じで見たいです。「褐色の肌に白い歯」って俳優さんに演じてほしいです。
〔参照:第1話「長崎警護」⑥-2〕

――ちなみに現在の長崎県大村市あたりのお殿様。
この“海の大名”。長崎奉行所と一緒に“フェートン号”撃退作戦を計画します。
「正面から戦っても厳しいから、大村の小舟で敵船に乗り移ろう!」
「そして“フェートン号”を内側から燃やしてしまえ!」というワイルドな作戦です。
――そのとき“フェートン号”が退去します。
危険を察知したのか、まずは水・食料を確保できたからか。いずれにしても長崎港から出ていきます。
こうして、特大の不始末をやらかした、我らが佐賀藩。
さっき城下でドタバタしていた、長崎御番の若侍は信頼する上役が処罰される直前に、面会を許されます。
〔参照:第1話「長崎警護」⑥-3〕
――これは、ドラマ要素が欲しかったので…
”ご都合主義”になりますが、この若侍。のちに、上役の娘と夫婦になっているという設定があります。
(次話以降で、たしか同僚が一言つぶやいていたと思います。)
「“無法な異国船”は、義父の仇(かたき)…」
長崎御番の若侍は、後々“蘭学じじい”と呼ばれるまで、佐賀藩の技術開発を支えていく…というサイドストーリーです。
――ところで、この“長崎御番の若侍”とは何者か…
この話を作るときに、色々考えたのです。
のちに長崎砲台の責任者になる“伊東次兵衛”。1808年時点では幼児です…
佐賀藩の製砲主任になる、本島藤太夫の誕生も、まだ6年ばかり後です。
――この方々の“先輩”としてオリジナルキャラで描くことに。
もっと調べれば、かなり設定に近い人物は出て来そうな予感がします。
…ちなみに前回も触れましたが、第1話には弟の描いた挿絵がよく使われています。ありがとう、弟。
反省会が続きます。時期は1月後半。
「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」との想いが強くなりすぎて、私は自分のイメージを文章化し始めました。
――「佐賀の大河ドラマ」と銘打っていますが…
第1話でドラマが動く舞台は、ほとんど長崎です。
しかも、オープニングで会話しているのは、イギリス人水兵。
「一体、誰だ!テッドとグレッグって…」
思わずツッコミを入れたくなる方も居たかもしれません。
〔参照:
――ところが、この2名も侮れません。
“フェートン号”の船員名簿を調べたわけもなく、名前の設定は架空。意外に凄腕で、あっと言う間にオランダ商館員を人質に取ります。
〔参照:
このとき、オランダと対立していたイギリス。
長崎近海でも、英国船がオランダ船を追い回していたようです。

――困難に立ち向かう、長崎奉行・松平康英。
頼みの綱は、長崎の警備担当・佐賀藩(鍋島家)の兵員。しかし、ほとんど(9割ぐらい)が、佐賀に帰っていて不在!
この第1話では、主役の佐賀藩は“いいところ無し”の展開です。佐賀城下も、ひたすらバタバタしています。
〔参照:
逆にカッコ良いのは、肥前大村藩。
――長崎の方も、きっとわかってくれるはず…
“佐賀の大河ドラマ”の実現は、長崎にとっても、ビッグチャンスですよ。
本来の警備部隊がいないことで、苦しむ長崎奉行所。
まだ夜明け前に颯爽と現れたのが、大村藩主・大村純昌。
私の勝手なイメージでは、いかにも“海の大名”な感じで見たいです。「褐色の肌に白い歯」って俳優さんに演じてほしいです。
〔参照:

――ちなみに現在の長崎県大村市あたりのお殿様。
この“海の大名”。長崎奉行所と一緒に“フェートン号”撃退作戦を計画します。
「正面から戦っても厳しいから、大村の小舟で敵船に乗り移ろう!」
「そして“フェートン号”を内側から燃やしてしまえ!」というワイルドな作戦です。
――そのとき“フェートン号”が退去します。
危険を察知したのか、まずは水・食料を確保できたからか。いずれにしても長崎港から出ていきます。
こうして、特大の不始末をやらかした、我らが佐賀藩。
さっき城下でドタバタしていた、長崎御番の若侍は信頼する上役が処罰される直前に、面会を許されます。
〔参照:
――これは、ドラマ要素が欲しかったので…
”ご都合主義”になりますが、この若侍。のちに、上役の娘と夫婦になっているという設定があります。
(次話以降で、たしか同僚が一言つぶやいていたと思います。)
「“無法な異国船”は、義父の仇(かたき)…」
長崎御番の若侍は、後々“蘭学じじい”と呼ばれるまで、佐賀藩の技術開発を支えていく…というサイドストーリーです。
――ところで、この“長崎御番の若侍”とは何者か…
この話を作るときに、色々考えたのです。
のちに長崎砲台の責任者になる“伊東次兵衛”。1808年時点では幼児です…
佐賀藩の製砲主任になる、本島藤太夫の誕生も、まだ6年ばかり後です。
――この方々の“先輩”としてオリジナルキャラで描くことに。
もっと調べれば、かなり設定に近い人物は出て来そうな予感がします。
…ちなみに前回も触れましたが、第1話には弟の描いた挿絵がよく使われています。ありがとう、弟。
2020年12月15日
「睦月・一月」(歳末反省会②)
こんばんは。前回の続きです。
――2020年(令和2年)1月。
“新型コロナ”という言葉が聞こえ始めた頃。
不穏な空気が漂ってきた時期ですが、私は投稿に熱を入れていました。まさか「年間を通じて、佐賀に帰藩できない!」とも知らずに。
――その年末から、お正月にかけては…
”佐賀七賢人”の人物紹介編を何とか書き終えて、次の展開へと移りました。
私のブログでアクセス数第1位の記事は、ブログ開始時の“ご挨拶”。
第2位は新年のご挨拶も兼ねた、この記事です。
〔参照:「佐賀の物語を描け!」(独自色③)〕
――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」は、3部構成で見たい!
新年早々に暑苦しい投稿でしたが、そこそこ共感は得られたようです。
年末年始に佐賀の名言、功績…そして物語!と連続で語りました。
〔参照:「佐賀の名言を探せ!」(独自色①),「佐賀の功績を語れ!」(独自色②)〕
――そこからは、迷いが生じました。
正月休み中に武雄市、白石町など各地域にフォーカスした記事を投稿。
このあたりまでは、勢いがあったのですが、その後、急に失速します。
歴代の「大河ドラマ」を意識した記事を入れてみますが、停滞は否めません。

――ここで、私は遠大なチャレンジを試みます。
「私に、才能は…たぶん無い!」
“幕末佐賀藩の大河ドラマ”について考え始めたとき、年表を並べ「放送47話(年間の目安)では収まらない情報量」をどう捌くかが課題と感じました。
幕末・明治期における、佐賀の先人たちの活躍。素材は豊富にある。
どんな脚本家の方が書けば、面白い話になるだろうか…と考えていました。
――しかし、私に脚本家への伝手(つて)はありません。
「この際だから、自分でも書いてみよう!」
当初は“場面解説”だけのイメージでしたが、これが“本編”の始まりです。
また、写真素材が足りず、思案することに。
そして「弟に描いてもらうか…」との結論に至りました。
――とりあえず、弟に電話する、私。
「ひとまず“フェートン号”と、長崎奉行所がほしい!」
電話なので、弟の表情は見えていません。たぶん豆鉄砲をくらった、柴犬のように、きょとんとした顔をした事と思います。
「兄貴は…相変わらず、おかしな事を言う…」
こうして弟がカリカリと描いた絵。序盤の写真不足を支えることになります。
…長文になったので、第1話「長崎警護」については、あらためて振り返ります。
――2020年(令和2年)1月。
“新型コロナ”という言葉が聞こえ始めた頃。
不穏な空気が漂ってきた時期ですが、私は投稿に熱を入れていました。まさか「年間を通じて、佐賀に帰藩できない!」とも知らずに。
――その年末から、お正月にかけては…
”佐賀七賢人”の人物紹介編を何とか書き終えて、次の展開へと移りました。
私のブログでアクセス数第1位の記事は、ブログ開始時の“ご挨拶”。
第2位は新年のご挨拶も兼ねた、この記事です。
〔参照:
――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」は、3部構成で見たい!
新年早々に暑苦しい投稿でしたが、そこそこ共感は得られたようです。
年末年始に佐賀の名言、功績…そして物語!と連続で語りました。
〔参照:
――そこからは、迷いが生じました。
正月休み中に武雄市、白石町など各地域にフォーカスした記事を投稿。
このあたりまでは、勢いがあったのですが、その後、急に失速します。
歴代の「大河ドラマ」を意識した記事を入れてみますが、停滞は否めません。

――ここで、私は遠大なチャレンジを試みます。
「私に、才能は…たぶん無い!」
“幕末佐賀藩の大河ドラマ”について考え始めたとき、年表を並べ「放送47話(年間の目安)では収まらない情報量」をどう捌くかが課題と感じました。
幕末・明治期における、佐賀の先人たちの活躍。素材は豊富にある。
どんな脚本家の方が書けば、面白い話になるだろうか…と考えていました。
――しかし、私に脚本家への伝手(つて)はありません。
「この際だから、自分でも書いてみよう!」
当初は“場面解説”だけのイメージでしたが、これが“本編”の始まりです。
また、写真素材が足りず、思案することに。
そして「弟に描いてもらうか…」との結論に至りました。
――とりあえず、弟に電話する、私。
「ひとまず“フェートン号”と、長崎奉行所がほしい!」
電話なので、弟の表情は見えていません。たぶん豆鉄砲をくらった、柴犬のように、きょとんとした顔をした事と思います。
「兄貴は…相変わらず、おかしな事を言う…」
こうして弟がカリカリと描いた絵。序盤の写真不足を支えることになります。
…長文になったので、第1話「長崎警護」については、あらためて振り返ります。
2020年12月14日
「師走・十二月」(歳末反省会①)
こんばんは。
壮大な前振りから始まった、単なる反省会。
――ブログを始めたばかりの1年前(12月)。
正直なところを言えば、表現の場を得たことにウキウキしておりました。
これで、思う存分「幕末の佐賀藩を語れる!」と。
おそるおそる1本目(ご挨拶)を投稿したかと思えば、すかさず2本目。
〔参照:敬意をこめて〕
2012年立ち上げの「佐賀の八賢人おもてなし隊」に敬意を表した投稿です。
当ブログに興味がある方が観れば、きっと感涙ものの演劇を展開されています。
――寒くなってきたかと思えば…
「反射炉!鉄製大砲!蒸気機関…、ほら、暖かくなりましたよね!」
…と、無茶苦茶を言ってるのが、3本目の投稿です。
〔参照:お話にあたって〕
まだ、投稿が楽しくてしょうがなかった時期です。
続けていくと、それなりに大変になりますよね。
――続いて、偉大な賢人たちの銅像と語るシリーズ。
写真はライトアップバージョンです。
なお、私の近辺にも豪奢なイルミネーションはあります。
しかし「サガ・ライトファンタジー」は、私にとっては特別なのです。

――名君過ぎて、後光がさしたように見える殿・鍋島直正。
ちなみに右隣は蘭学の先駆者。武雄領主・鍋島茂義。
殿・直正の義兄で、その名君に“背中で語ってきた”人物です。
左隣は、直正の教育係・古賀穀堂です。
この、お三方を表現しようと試みた記事が4本目です。
〔参照:STEP1:名君の登場まで〕
――当ブログ内で、銅像と会話しがちな私…
振り返ってみて、序盤からその傾向はあった事に気付きました。さらに進んで、「佐賀七賢人と直接、話してみたらどうなるか?」というシリーズも展開しました。
この人物紹介編は、前編はちょっとしたドラマ仕立て。
〔参照(例):「江藤新平」(賢人その6)<前編>〕
後編は真面目に業績の紹介を試みています。
〔参照(例):「江藤新平」(賢人その6)<後編>〕
年末に「1年を顧みて、その反省を活かせば、翌年につながる…」と考えました。
次回からも、こんな調子で振り返っていきたいと思います。
壮大な前振りから始まった、単なる反省会。
――ブログを始めたばかりの1年前(12月)。
正直なところを言えば、表現の場を得たことにウキウキしておりました。
これで、思う存分「幕末の佐賀藩を語れる!」と。
おそるおそる1本目(
〔参照:
2012年立ち上げの「佐賀の八賢人おもてなし隊」に敬意を表した投稿です。
当ブログに興味がある方が観れば、きっと感涙ものの演劇を展開されています。
――寒くなってきたかと思えば…
「反射炉!鉄製大砲!蒸気機関…、ほら、暖かくなりましたよね!」
…と、無茶苦茶を言ってるのが、3本目の投稿です。
〔参照:
まだ、投稿が楽しくてしょうがなかった時期です。
続けていくと、それなりに大変になりますよね。
――続いて、偉大な賢人たちの銅像と語るシリーズ。
写真はライトアップバージョンです。
なお、私の近辺にも豪奢なイルミネーションはあります。
しかし「サガ・ライトファンタジー」は、私にとっては特別なのです。
――名君過ぎて、後光がさしたように見える殿・鍋島直正。
ちなみに右隣は蘭学の先駆者。武雄領主・鍋島茂義。
殿・直正の義兄で、その名君に“背中で語ってきた”人物です。
左隣は、直正の教育係・古賀穀堂です。
この、お三方を表現しようと試みた記事が4本目です。
〔参照:
――当ブログ内で、銅像と会話しがちな私…
振り返ってみて、序盤からその傾向はあった事に気付きました。さらに進んで、「佐賀七賢人と直接、話してみたらどうなるか?」というシリーズも展開しました。
この人物紹介編は、前編はちょっとしたドラマ仕立て。
〔参照(例):
後編は真面目に業績の紹介を試みています。
〔参照(例):
年末に「1年を顧みて、その反省を活かせば、翌年につながる…」と考えました。
次回からも、こんな調子で振り返っていきたいと思います。
2020年12月13日
「内省の剣」
こんばんは。
今年も、残り3週間を切りましたね…
師走の風景は、例年と異なっています。“コロナ禍”が収まる気配は感じられず、仕事にも、何らかの影響が出ている方が大半だと思います。
――そんな年の瀬だからこそ、気持ちだけでも。
1年以上、佐賀に帰藩できていません。これは「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を、イメージしたい私には厳しい状況です。
やはり、現地に行ってこその感動がありますから。
 ※サガ・ライトファンタジー(2019年)
※サガ・ライトファンタジー(2019年)
――それでも今までの蓄積と、今あるつながりで…
私の手元には、昨年に集めていた「佐賀の記憶」が残っています。
この歳になって、これだけ夢中になれるもの。そうは無い…
たとえ現実が憂鬱でも、この力で乗り越えてゆく。
――まさに「望郷の剣」を手にした私…
ただ、この1年間。無茶苦茶な“剣の振り方”をした気がします。もう突っ走れるほど、若くはありません。
若さに代わって、私が得たものは何か…
「そうだ。若い時よりは、冷静に振り返ることができるはず!」
…壮大な前振りになりましたが、次回より“歳末反省会”シリーズを試みます。
今年も、残り3週間を切りましたね…
師走の風景は、例年と異なっています。“コロナ禍”が収まる気配は感じられず、仕事にも、何らかの影響が出ている方が大半だと思います。
――そんな年の瀬だからこそ、気持ちだけでも。
1年以上、佐賀に帰藩できていません。これは「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を、イメージしたい私には厳しい状況です。
やはり、現地に行ってこその感動がありますから。
――それでも今までの蓄積と、今あるつながりで…
私の手元には、昨年に集めていた「佐賀の記憶」が残っています。
この歳になって、これだけ夢中になれるもの。そうは無い…
たとえ現実が憂鬱でも、この力で乗り越えてゆく。
――まさに「望郷の剣」を手にした私…
ただ、この1年間。無茶苦茶な“剣の振り方”をした気がします。もう突っ走れるほど、若くはありません。
若さに代わって、私が得たものは何か…
「そうだ。若い時よりは、冷静に振り返ることができるはず!」
…壮大な前振りになりましたが、次回より“歳末反省会”シリーズを試みます。
2020年12月12日
「あゝ西洋菓子(西)」
こんばんは。
佐賀の三大産業と言えば、農業・窯業・製薬業という見方があります。その産業の“柱”の1つ、製薬業は、とくに佐賀県東部で有力です。
幕末の佐賀藩では、蝋燭(ろうそく)の原料・ハゼノキに限らず、“薬種”になる商品作物の栽培も奨励したようです。
佐賀藩との国境を越えた東隣り。対馬藩・田代領も、現在は佐賀県内(鳥栖市・基山町)。“田代売薬”で知られ、現在も製薬会社が強い地域です。
――東があれば、西もある…
前回の江崎利一は、薬種業(生薬を商う)の知識で、牡蠣(カキ)の栄養分から“グリコ”を製作。佐賀東部の製薬業の伝統と、有明海の恵みを活かします。
では、佐賀西部の力とは。やはり窯業(陶磁器)でしょう。前々回でも登場いただいた、伊万里の偉人・森永太一郎を通じて語ります。
〔参照記事:「おかげさまで1周年。」〕

――全国でも著名な、佐賀の陶磁器産業。
「佐賀の窯業は、産業の“柱”である強者。言うなれば“陶柱”か…。」
今年、流行ったアニメ(鬼滅の刃)っぽい表現。とくに本筋には関係しません。
幕末期、世界へと近づいていく日本。
肥前(佐賀・長崎)の陶磁器は、輸出品として注目を集めます。
そして佐賀藩が陶磁器の“秘密工場”(御用窯)を置き、製品積出港とした街…
――1865年(慶応元年)。伊万里。
この街で、陶器問屋を営む商家に男子が誕生します。のちに日本で西洋菓子の先駆者となる、森永製菓の創業者・森永太一郎です。
しかし、幼年のうちに父を亡くした太一郎。そのまま家業は衰退。母方の実家に身を寄せたと言います。
――生計を立てるため、叔父から商売を学ぶ、太一郎。
「商売で大事なのは、誠実であること。」
…という叔父の教えを受け、力強く成長。アメリカに渡ることを決意します。
そして、太一郎24歳のとき、陶器商としてサンフランシスコに渡ります。ちなみに、“本編”で佐賀藩士たちが渡米した時期から、30年近く経過しています。
〔参考記事(本編):第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)〕

――“陶器商”としての渡米は、散々なものでした。
あの佐野常民も、幕末にパリ万博への出展時、熟練の陶器商たちとチームを組みますが、ヨーロッパでの売れ筋を見誤り、散々に在庫を抱え込んでいます。
佐野常民たちは、明治のウィーン万博では、周到に戦略を練り、ようやく出展としては成功を収めますが、それだけ海外展開は難しいのです。
たとえ、商品が優れていても、アメリカ市場に飛び込んだ若者・森永太一郎の勝算は薄かったのでしょう。しかし、この若者には“秘めたる力”がありました。
――異国で感じる絶望の中。太一郎は…
現地のご婦人から頂いた一粒の菓子を口にしたそうです。これが、森永太一郎を覚醒させます。まさに希望の味。
「やさしい甘さだ…。日本でも、こんな西洋菓子を作りたい。」
…この瞬間が、現代の森永製菓につながったようです。もちろん様々な困難が続きますが、そのたび何度でも立ち上がる太一郎。
品質に妥協しない、頑固さと誠実さ。それは、もはや商才と言うよりも、“本物”を作り続ける陶磁器の職人に通ずるものだったのかもしれません。
佐賀の三大産業と言えば、農業・窯業・製薬業という見方があります。その産業の“柱”の1つ、製薬業は、とくに佐賀県東部で有力です。
幕末の佐賀藩では、蝋燭(ろうそく)の原料・ハゼノキに限らず、“薬種”になる商品作物の栽培も奨励したようです。
佐賀藩との国境を越えた東隣り。対馬藩・田代領も、現在は佐賀県内(鳥栖市・基山町)。“田代売薬”で知られ、現在も製薬会社が強い地域です。
――東があれば、西もある…
前回の江崎利一は、薬種業(生薬を商う)の知識で、牡蠣(カキ)の栄養分から“グリコ”を製作。佐賀東部の製薬業の伝統と、有明海の恵みを活かします。
では、佐賀西部の力とは。やはり窯業(陶磁器)でしょう。前々回でも登場いただいた、伊万里の偉人・森永太一郎を通じて語ります。
〔参照記事:「おかげさまで1周年。」〕

――全国でも著名な、佐賀の陶磁器産業。
「佐賀の窯業は、産業の“柱”である強者。言うなれば“陶柱”か…。」
今年、流行ったアニメ(鬼滅の刃)っぽい表現。とくに本筋には関係しません。
幕末期、世界へと近づいていく日本。
肥前(佐賀・長崎)の陶磁器は、輸出品として注目を集めます。
そして佐賀藩が陶磁器の“秘密工場”(御用窯)を置き、製品積出港とした街…
――1865年(慶応元年)。伊万里。
この街で、陶器問屋を営む商家に男子が誕生します。のちに日本で西洋菓子の先駆者となる、森永製菓の創業者・森永太一郎です。
しかし、幼年のうちに父を亡くした太一郎。そのまま家業は衰退。母方の実家に身を寄せたと言います。
――生計を立てるため、叔父から商売を学ぶ、太一郎。
「商売で大事なのは、誠実であること。」
…という叔父の教えを受け、力強く成長。アメリカに渡ることを決意します。
そして、太一郎24歳のとき、陶器商としてサンフランシスコに渡ります。ちなみに、“本編”で佐賀藩士たちが渡米した時期から、30年近く経過しています。
〔参考記事(本編):
――“陶器商”としての渡米は、散々なものでした。
あの佐野常民も、幕末にパリ万博への出展時、熟練の陶器商たちとチームを組みますが、ヨーロッパでの売れ筋を見誤り、散々に在庫を抱え込んでいます。
佐野常民たちは、明治のウィーン万博では、周到に戦略を練り、ようやく出展としては成功を収めますが、それだけ海外展開は難しいのです。
たとえ、商品が優れていても、アメリカ市場に飛び込んだ若者・森永太一郎の勝算は薄かったのでしょう。しかし、この若者には“秘めたる力”がありました。
――異国で感じる絶望の中。太一郎は…
現地のご婦人から頂いた一粒の菓子を口にしたそうです。これが、森永太一郎を覚醒させます。まさに希望の味。
「やさしい甘さだ…。日本でも、こんな西洋菓子を作りたい。」
…この瞬間が、現代の森永製菓につながったようです。もちろん様々な困難が続きますが、そのたび何度でも立ち上がる太一郎。
品質に妥協しない、頑固さと誠実さ。それは、もはや商才と言うよりも、“本物”を作り続ける陶磁器の職人に通ずるものだったのかもしれません。
タグ :伊万里
2020年12月10日
「あゝ西洋菓子(東)」
こんばんは。
何とか開設1周年を迎えた、当ブログ。しかし、例の感染症の蔓延はこの間も、不穏な影を落とし続けていました。
今、大都市圏に住む私にとって、かなり危うい状況なのは言うまでもありません。ここは気持ちを切り替え、12月らしい西洋菓子の話(?)を…
――朝、仕事に向かう。最近では電車に乗るのも億劫(おっくう)だ。
「どうした、浮かない顔だな。今日も創意工夫で乗り切れ!」
声の主が右手に持つのは、キャラメル菓子の箱だ。
「それは、一粒300メートルで有名な…グリコ?」
おまけに“創意工夫”は、この方の会社の大事な精神らしい。
「そうだとも。おいしくて、つよくなるぞ!」
力強い“ビスコ”のキャッチコピーだ。よく買う江崎グリコの商品。
「おおっ。その言葉を聞くだけで、何やら少し力が湧く…。」

――以上が朝の電車で、まだボーっとしている私の妄想。
行きの電車を待つ間に調べたのは、佐賀市(蓮池町)出身の偉人・江崎利一。言うまでもなく、江崎グリコの創業者様です。
その生まれは1882年(明治十五年)。当ブログの“本編”の現在地より、20年以上も現代に近づきます。
明治政府から追われた大隈重信が、負けじと政党を結成したり、学校(のちの早稲田大学)を創ったりと頑張っている時期です。
――佐賀の蓮池。江崎家は、薬種(生薬)を商う家。
各家庭を回り、健康相談をして生薬を売る事業だったそうです。江崎家はあまり裕福では無く、しかも早くに父を亡くした長男・利一は、一家を背負う立場に。
「俺は長男だから耐えられる。もし次男だったら耐えられなかった。」
…とばかりに家族を支えていったようです。

――わかる人にはわかりますが、先ほどのセリフには“元ネタ”があります。
そして大正期。その“元ネタ”である流行りのアニメ(鬼滅の刃)の舞台でもある時代。こちらも、健気に頑張る長男・江崎利一にも転機が訪れます。
佐賀の蓮池は、有明海にも近い場所。有明の牡蠣(カキ)は有名ですが、利一は捨てられているカキの煮汁に着目します。
「“薬種”の新聞で見た“グリコーゲン”が抽出できるのでは?」
――おそらくは、有明海の力を味方に付けた、この瞬間。
現在の江崎グリコへの道が始まったのでしょう。
こうして“滋養強壮”の目的を持つお菓子“グリコ”が誕生します。
虚弱な人だけでなく、いま健康な人にも病気の予防を。
現代でも“10万人あたりの調剤薬局数が全国一”という佐賀の人らしい着想だったのかもしれません。
何とか開設1周年を迎えた、当ブログ。しかし、例の感染症の蔓延はこの間も、不穏な影を落とし続けていました。
今、大都市圏に住む私にとって、かなり危うい状況なのは言うまでもありません。ここは気持ちを切り替え、12月らしい西洋菓子の話(?)を…
――朝、仕事に向かう。最近では電車に乗るのも億劫(おっくう)だ。
「どうした、浮かない顔だな。今日も創意工夫で乗り切れ!」
声の主が右手に持つのは、キャラメル菓子の箱だ。
「それは、一粒300メートルで有名な…グリコ?」
おまけに“創意工夫”は、この方の会社の大事な精神らしい。
「そうだとも。おいしくて、つよくなるぞ!」
力強い“ビスコ”のキャッチコピーだ。よく買う江崎グリコの商品。
「おおっ。その言葉を聞くだけで、何やら少し力が湧く…。」
――以上が朝の電車で、まだボーっとしている私の妄想。
行きの電車を待つ間に調べたのは、佐賀市(蓮池町)出身の偉人・江崎利一。言うまでもなく、江崎グリコの創業者様です。
その生まれは1882年(明治十五年)。当ブログの“本編”の現在地より、20年以上も現代に近づきます。
明治政府から追われた大隈重信が、負けじと政党を結成したり、学校(のちの早稲田大学)を創ったりと頑張っている時期です。
――佐賀の蓮池。江崎家は、薬種(生薬)を商う家。
各家庭を回り、健康相談をして生薬を売る事業だったそうです。江崎家はあまり裕福では無く、しかも早くに父を亡くした長男・利一は、一家を背負う立場に。
「俺は長男だから耐えられる。もし次男だったら耐えられなかった。」
…とばかりに家族を支えていったようです。
――わかる人にはわかりますが、先ほどのセリフには“元ネタ”があります。
そして大正期。その“元ネタ”である流行りのアニメ(鬼滅の刃)の舞台でもある時代。こちらも、健気に頑張る長男・江崎利一にも転機が訪れます。
佐賀の蓮池は、有明海にも近い場所。有明の牡蠣(カキ)は有名ですが、利一は捨てられているカキの煮汁に着目します。
「“薬種”の新聞で見た“グリコーゲン”が抽出できるのでは?」
――おそらくは、有明海の力を味方に付けた、この瞬間。
現在の江崎グリコへの道が始まったのでしょう。
こうして“滋養強壮”の目的を持つお菓子“グリコ”が誕生します。
虚弱な人だけでなく、いま健康な人にも病気の予防を。
現代でも“10万人あたりの調剤薬局数が全国一”という佐賀の人らしい着想だったのかもしれません。
2020年12月08日
「おかげさまで1周年。」
こんばんは。
1年前の今日。おそるおそる1本の記事を投稿しました。
〔参照記事(初回):ご挨拶〕
今は概ね2日に1度くらい、時折は毎日!というペースで更新しています。
タイトルどおり「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」がメインテーマです。
拙い知識や想像も含めて、語り続けてきました。
――この1年間、色々とありました。
しかし、私に落ち込んでいる暇はありませんでした。
幕末・明治期の佐賀の偉業と、いまの佐賀にある魅力。
過去と現在に渡って、佐賀の事を考えるので忙しいのです。

――例えば、今日は仕事がうまく行かなかった…
帰りの電車を待つ間に、伊万里の偉人・森永太一郎を調べる。
「…すごく苦労人…」
乾いた日常にさらされる私の目にも、ウルウルと潤いが戻るわけです。念のための補足ですが、佐賀(伊万里)出身の森永製菓の創業者様です。
「なんだ!挫けそうなのか。甘い物が好きなら、キャラメルでも食べるといい!」
…と、何やら励まされている気がします。
――いつも、当ブログをご覧いただいている皆様へ。
話はあちこちに飛びますし“歴史系”ブログとしては調べが甘いです。おまけに創作要素も強いわりには、書く人の“シナリオ作成”能力がいまいち…
…という弱点の多いブログですが、
それを補っているのが、皆様の温かい視線であることは言うまでもありません。
――とくに「さがファンブログ」で、お世話になっている方々。
いまや簡単に帰れない私と、郷里・佐賀を日々つなげているもの…
それは、たぶん佐賀の各地域に暮らす皆様の投稿なのです。
今後とも、よろしくお願いします。
1年前の今日。おそるおそる1本の記事を投稿しました。
〔参照記事(初回):
今は概ね2日に1度くらい、時折は毎日!というペースで更新しています。
タイトルどおり「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」がメインテーマです。
拙い知識や想像も含めて、語り続けてきました。
――この1年間、色々とありました。
しかし、私に落ち込んでいる暇はありませんでした。
幕末・明治期の佐賀の偉業と、いまの佐賀にある魅力。
過去と現在に渡って、佐賀の事を考えるので忙しいのです。
――例えば、今日は仕事がうまく行かなかった…
帰りの電車を待つ間に、伊万里の偉人・森永太一郎を調べる。
「…すごく苦労人…」
乾いた日常にさらされる私の目にも、ウルウルと潤いが戻るわけです。念のための補足ですが、佐賀(伊万里)出身の森永製菓の創業者様です。
「なんだ!挫けそうなのか。甘い物が好きなら、キャラメルでも食べるといい!」
…と、何やら励まされている気がします。
――いつも、当ブログをご覧いただいている皆様へ。
話はあちこちに飛びますし“歴史系”ブログとしては調べが甘いです。おまけに創作要素も強いわりには、書く人の“シナリオ作成”能力がいまいち…
…という弱点の多いブログですが、
それを補っているのが、皆様の温かい視線であることは言うまでもありません。
――とくに「さがファンブログ」で、お世話になっている方々。
いまや簡単に帰れない私と、郷里・佐賀を日々つなげているもの…
それは、たぶん佐賀の各地域に暮らす皆様の投稿なのです。
今後とも、よろしくお願いします。
2020年12月06日
「主に小城市民の皆様を対象としたつぶやき 2」
こんばんは。
前回まで、私が佐賀市内で駆け回る話を綴りました。このとき他の地域まで足を運ぶ時間は取れていません。
しかし、佐賀城へと続く大通りには、県内各地に“想いを飛ばす”ことが出来る場所が!…ありました。
――さすが、バルーン(気球)で有名な佐賀。
“飛ばす”のは、お手の物でしょうか。まるで“ワープゾーン”みたいな言い方ですが、ここから小城に話が飛びます。
ちなみに、この銅像の設置場所は佐賀市の唐人町。
小城が誇る書家・中林梧竹先生です。
初見では「何だか1人で、さびしそう。」と感じました。
しかし明治期に“東洋一の書聖”とまで呼ばれた人物と聞くと…
「書に集中したいので、人払いを願おうかな…」と風格を感じます。

――清国(中国)にも渡り、ひたすらに書の修業を積んだそうです。
中林梧竹は、佐賀七賢人の1人・副島種臣とほぼ同年代。清国に詳しく、書の達人どうし…立場は違えど、共通点があり親しかったようです。
小城市には、中林梧竹記念館があると知りました。また、県内では副島種臣(蒼海)と、2人の名を冠した「梧竹・蒼海書道展」まで開催されているとか。
――さて、佐賀の小京都・小城についての思索は続きます。
以下の記事でも考えましたが、未だ結論に至っておりません。
〔参照:「醒覚の剣(都風)」〕
この記事は「佐賀に帰れない私に、叔父上から小城の土産が来る話」でした。村岡総本舗が復刻した、大正時代のハイカラ菓子“シベリア”を語りました。

――そして、やはり小城といえば、羊羹。
これは叔父上の絶妙なバランス感覚なのか、同時に届いた抹茶羊羹。なぜか村岡総本舗ではなく、水田羊羹本舗の品でした。
「小城の羊羹は、“村岡”だけではなかよ。」
…叔父上は、小城の羊羹には、さらに広くて深い世界があることを教えたかったのかもしれません。
その抹茶羊羹は、まだ日持ちするので、後の楽しみに置いています。小城名物の担い手は、その選手層も厚いようです。
――そろそろ、結論に向かいたいところですが…
さらに、小城の攻勢は続きます。
私も大好きな氷菓子“ブラックモンブラン”の竹下製菓の本社も、小城。このたび埼玉のメーカーを子会社化し、関東への販路強化のニュースもありました。
また“こどもびいる”等が、全国に知られるサイダー・ラムネ等の飲料メーカー。友桝飲料も、小城の会社。
――こうして私なりの、1つの結論が出ました。
佐賀の“小京都”と呼ばれる、小城。
…そこには「“砂糖”を自在に操る力があるに違いない」と。
こうして私は“小京都”・小城を「糖(とう)の都」と考えるに至ります。
今後も小城から発信される“佐賀ブランド”が、全国で勢力を伸ばすことを期待しています。
前回まで、私が佐賀市内で駆け回る話を綴りました。このとき他の地域まで足を運ぶ時間は取れていません。
しかし、佐賀城へと続く大通りには、県内各地に“想いを飛ばす”ことが出来る場所が!…ありました。
――さすが、バルーン(気球)で有名な佐賀。
“飛ばす”のは、お手の物でしょうか。まるで“ワープゾーン”みたいな言い方ですが、ここから小城に話が飛びます。
ちなみに、この銅像の設置場所は佐賀市の唐人町。
小城が誇る書家・中林梧竹先生です。
初見では「何だか1人で、さびしそう。」と感じました。
しかし明治期に“東洋一の書聖”とまで呼ばれた人物と聞くと…
「書に集中したいので、人払いを願おうかな…」と風格を感じます。
――清国(中国)にも渡り、ひたすらに書の修業を積んだそうです。
中林梧竹は、佐賀七賢人の1人・副島種臣とほぼ同年代。清国に詳しく、書の達人どうし…立場は違えど、共通点があり親しかったようです。
小城市には、中林梧竹記念館があると知りました。また、県内では副島種臣(蒼海)と、2人の名を冠した「梧竹・蒼海書道展」まで開催されているとか。
――さて、佐賀の小京都・小城についての思索は続きます。
以下の記事でも考えましたが、未だ結論に至っておりません。
〔参照:
この記事は「佐賀に帰れない私に、叔父上から小城の土産が来る話」でした。村岡総本舗が復刻した、大正時代のハイカラ菓子“シベリア”を語りました。
――そして、やはり小城といえば、羊羹。
これは叔父上の絶妙なバランス感覚なのか、同時に届いた抹茶羊羹。なぜか村岡総本舗ではなく、水田羊羹本舗の品でした。
「小城の羊羹は、“村岡”だけではなかよ。」
…叔父上は、小城の羊羹には、さらに広くて深い世界があることを教えたかったのかもしれません。
その抹茶羊羹は、まだ日持ちするので、後の楽しみに置いています。小城名物の担い手は、その選手層も厚いようです。
――そろそろ、結論に向かいたいところですが…
さらに、小城の攻勢は続きます。
私も大好きな氷菓子“ブラックモンブラン”の竹下製菓の本社も、小城。このたび埼玉のメーカーを子会社化し、関東への販路強化のニュースもありました。
また“こどもびいる”等が、全国に知られるサイダー・ラムネ等の飲料メーカー。友桝飲料も、小城の会社。
――こうして私なりの、1つの結論が出ました。
佐賀の“小京都”と呼ばれる、小城。
…そこには「“砂糖”を自在に操る力があるに違いない」と。
こうして私は“小京都”・小城を「糖(とう)の都」と考えるに至ります。
今後も小城から発信される“佐賀ブランド”が、全国で勢力を伸ばすことを期待しています。
タグ :小城
2020年12月05日
連続ブログ小説「旅立の剣」(18)憩いのシシリアン
こんばんは。
1年前には“コロナ禍”という言葉も無く「大河ドラマ」と言えば経済効果も!…と素直に期待できる状況でした。
前回に「佐賀の大河ドラマで、一番、潤うのは長崎かも知れん。」という言葉に込めた想いは、また、いずれ語りたいと思います。
昨秋の1泊2日の行程を追った“連続ブログ小説”も、今回で初日分(第1・2シリーズ)終了です。その翌日は「第2回さが維新まつり」が控えていました。
――白山通りのアーケードの下を行く。
12時間くらい移動と見学を繰り返した。さすがに疲労感が積もる。
行きの早足と違って、ゆっくりと県庁通りへと戻る。
「まぁ、今日のところは為すべきことは果たしたか…」
ある作家が「青春とは阿呆である」と語ったという。たしかに、この終日の行動は、まさしく“阿呆”の所業であったかもしれない。
言い換えれば、その一日、私は“青春”の真っ只中にあったのだ。
――佐賀玉屋前に戻った。「中の小路」バス停。
乗り込んだバスの座席。佐賀市営バスの一日乗車券を改めて見つめる。
「一日、世話になった…」
最初の佐野常民記念館との往復で、ほぼ元は取れている。お得だった。
金曜の夕刻。ちょうどオフィス街からの帰宅ラッシュと重なる。佐賀駅前に近づくと、ちょっとした渋滞。ターミナルへの道をバスもゆっくりと進む。

――私が日常、見慣れない景色。不思議な感覚だ。
佐賀駅バスターミナルに入ると「ふーっ」とひと息をついて宿に向かう。もはや、気力は使いきった。そして、明日も早い。
私は、強い空腹感を感じていた。部屋に入ると、佐賀玉屋の地下街“玉ちか”の紙袋から楽しみにしていた品を出した。
佐賀名物のB級グルメ“シシリアンライス”である。県外向けに説明を試みると、“甘辛焼肉サラダ丼”だろうか。
「美味い…!」
その日、ラストの写真。撮影時刻は18:30を回っていた。
(第3シリーズに続く)
1年前には“コロナ禍”という言葉も無く「大河ドラマ」と言えば経済効果も!…と素直に期待できる状況でした。
前回に「佐賀の大河ドラマで、一番、潤うのは長崎かも知れん。」という言葉に込めた想いは、また、いずれ語りたいと思います。
昨秋の1泊2日の行程を追った“連続ブログ小説”も、今回で初日分(第1・2シリーズ)終了です。その翌日は「第2回さが維新まつり」が控えていました。
――白山通りのアーケードの下を行く。
12時間くらい移動と見学を繰り返した。さすがに疲労感が積もる。
行きの早足と違って、ゆっくりと県庁通りへと戻る。
「まぁ、今日のところは為すべきことは果たしたか…」
ある作家が「青春とは阿呆である」と語ったという。たしかに、この終日の行動は、まさしく“阿呆”の所業であったかもしれない。
言い換えれば、その一日、私は“青春”の真っ只中にあったのだ。
――佐賀玉屋前に戻った。「中の小路」バス停。
乗り込んだバスの座席。佐賀市営バスの一日乗車券を改めて見つめる。
「一日、世話になった…」
最初の佐野常民記念館との往復で、ほぼ元は取れている。お得だった。
金曜の夕刻。ちょうどオフィス街からの帰宅ラッシュと重なる。佐賀駅前に近づくと、ちょっとした渋滞。ターミナルへの道をバスもゆっくりと進む。
――私が日常、見慣れない景色。不思議な感覚だ。
佐賀駅バスターミナルに入ると「ふーっ」とひと息をついて宿に向かう。もはや、気力は使いきった。そして、明日も早い。
私は、強い空腹感を感じていた。部屋に入ると、佐賀玉屋の地下街“玉ちか”の紙袋から楽しみにしていた品を出した。
佐賀名物のB級グルメ“シシリアンライス”である。県外向けに説明を試みると、“甘辛焼肉サラダ丼”だろうか。
「美味い…!」
その日、ラストの写真。撮影時刻は18:30を回っていた。
(第3シリーズに続く)