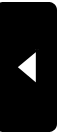2020年11月12日
連続ブログ小説「旅立の剣」(8)“見た目”より中身
こんばんは。前回の続きです。
「見えない世界遺産」と呼ばれる三重津海軍所跡では、仮想現実(バーチャルリアリティ)で当時の姿が映し出される仕組みです。
見学場所ごとに“みえつスコープ”を装着。施設の方から解説もありました。
目で見て、耳で聞き、風に触れる…幕末の佐賀が、すぐ傍に感じられます。
――“時を超える双眼鏡”から見える景色。
今は何もない“稽古場”の跡。ここで、佐賀藩士たちは欧米列強に対抗する力を得るべく、鉄製大砲や新式銃の訓練に勤しんだことだろう。
漂うのは火薬の匂いか。西洋式銃砲の威力は、幕末の動乱期に最後の輝きを見せた刀槍の時代を終わらせた。
幕末、佐賀藩士は近代化を目指して技術開発に打ち込んだ。サムライたちの努力は、その時代の終焉へとつながっていく。

――“スコープ”を構えると、読込時間があって映像が展開する。
蒸気船の“修覆場”の製造ライン、木造の小屋が見える。ボイラ-製造など近代的な金属加工の場。建物の見た目は…最先端ではない。
ふと、“さがんもん”の気質に思い当たる。佐賀藩は倹約を大事にした。最新鋭の砲兵部隊でさえ野袴を着用したと聞く。技術は一流でも見た目は質素だ。
おそらく佐賀人は無い物ねだりをしない。いま使えるもので何とかするのだ。
説明も「確かな情報」を重視する印象だ。“観光向き”の派手な幕末ではない。
――“見た目”より中身が大事。それも佐賀らしくはある。
まだ、三重津海軍所で躍動する佐野常民(栄寿)の姿は見えて来ない。それが、その時点での私の力量でもあった。
スタッフの方の説明に集中する。その言葉は、佐野先生のものと思うべきだ。
「まずは情報の収集だ。然(しか)る後に“大河ドラマ”のイメージに変換する!」
船屋地区(船の停泊)→稽古場地区(海軍の訓練)→修覆場地区(洋式船の修理)と見学は進む。記念館に戻り、私は施設スタッフの方に“ある質問”をした。
(続く)
〔関連記事:「佐野常民」(賢人その2)<前編>〕
※“本編”の開始前に“佐賀七賢人”のキャラクターを把握するために書いていたシリーズです。当時は、佐野常民編が一番描きづらかった…という記憶があります。
「見えない世界遺産」と呼ばれる三重津海軍所跡では、仮想現実(バーチャルリアリティ)で当時の姿が映し出される仕組みです。
見学場所ごとに“みえつスコープ”を装着。施設の方から解説もありました。
目で見て、耳で聞き、風に触れる…幕末の佐賀が、すぐ傍に感じられます。
――“時を超える双眼鏡”から見える景色。
今は何もない“稽古場”の跡。ここで、佐賀藩士たちは欧米列強に対抗する力を得るべく、鉄製大砲や新式銃の訓練に勤しんだことだろう。
漂うのは火薬の匂いか。西洋式銃砲の威力は、幕末の動乱期に最後の輝きを見せた刀槍の時代を終わらせた。
幕末、佐賀藩士は近代化を目指して技術開発に打ち込んだ。サムライたちの努力は、その時代の終焉へとつながっていく。
――“スコープ”を構えると、読込時間があって映像が展開する。
蒸気船の“修覆場”の製造ライン、木造の小屋が見える。ボイラ-製造など近代的な金属加工の場。建物の見た目は…最先端ではない。
ふと、“さがんもん”の気質に思い当たる。佐賀藩は倹約を大事にした。最新鋭の砲兵部隊でさえ野袴を着用したと聞く。技術は一流でも見た目は質素だ。
おそらく佐賀人は無い物ねだりをしない。いま使えるもので何とかするのだ。
説明も「確かな情報」を重視する印象だ。“観光向き”の派手な幕末ではない。
――“見た目”より中身が大事。それも佐賀らしくはある。
まだ、三重津海軍所で躍動する佐野常民(栄寿)の姿は見えて来ない。それが、その時点での私の力量でもあった。
スタッフの方の説明に集中する。その言葉は、佐野先生のものと思うべきだ。
「まずは情報の収集だ。然(しか)る後に“大河ドラマ”のイメージに変換する!」
船屋地区(船の停泊)→稽古場地区(海軍の訓練)→修覆場地区(洋式船の修理)と見学は進む。記念館に戻り、私は施設スタッフの方に“ある質問”をした。
(続く)
〔関連記事:
※“本編”の開始前に“佐賀七賢人”のキャラクターを把握するために書いていたシリーズです。当時は、佐野常民編が一番描きづらかった…という記憶があります。
2020年11月10日
連続ブログ小説「旅立の剣」(7)時を超える“双眼鏡”
こんばんは。
昨秋に実行した、佐賀での調査活動を綴るシリーズを続けています。
時刻は、正午を回り12:10頃。
雨が止んだ“早津江”の地。世界文化遺産“三重津海軍所跡”の見学が可能になった。記念館の外に出ると、湿気を含んだ風を感じる。
――見学のスタートに立つ。私には“みえつスコープ”が貸与された。
これが「見えない世界遺産」を見るための道具。
いわば“時を超える双眼鏡”を手に取り、施設スタッフの方と話す。
「あれほどの雨が止むとは…ここまで来た甲斐がありました。」
「わざわざ海軍所の見学に、佐賀まで?」
「佐賀の出身なので、気になってましてね。」
スタッフの方も“あぁ、なるほど”と言った表情を見せた。

――利用者の来所のきっかけは、施設が抑えておきたいところ。
経過は失念したが、私が“佐賀に戻る可能性”についての話となる。
「そう簡単には戻れませんね。あるいは…」
…私の想いから出た言葉は伏せておく。それは、施設の方にも予想外の一言だったはずだ。
生活の基盤が定まれば、拠点となる土地からは離れがたい。私の来歴では、郷里に帰ることは容易ではない。今までは、そこに思い至ることすら無かった。
――大都市圏には、様々な経緯で地方から人が集まる。
“巻き取っていく”と形容しても良いかもしれない。もちろん都会生活に馴染み、帰りたくない人が多数いるのは事実だろう。
逆に“望郷の想い”を抱く者にも、郷里に帰る道は険しいようだ。そんな記憶が過(よ)ぎる中、スタッフの方から“みえつスコープ”の使い方の説明を受けた。
この時を超える双眼鏡で、本当に強かった佐賀の姿は見えるのだろうか。
(続く)
〔関連記事:「発心の剣」〕
昨秋に実行した、佐賀での調査活動を綴るシリーズを続けています。
時刻は、正午を回り12:10頃。
雨が止んだ“早津江”の地。世界文化遺産“三重津海軍所跡”の見学が可能になった。記念館の外に出ると、湿気を含んだ風を感じる。
――見学のスタートに立つ。私には“みえつスコープ”が貸与された。
これが「見えない世界遺産」を見るための道具。
いわば“時を超える双眼鏡”を手に取り、施設スタッフの方と話す。
「あれほどの雨が止むとは…ここまで来た甲斐がありました。」
「わざわざ海軍所の見学に、佐賀まで?」
「佐賀の出身なので、気になってましてね。」
スタッフの方も“あぁ、なるほど”と言った表情を見せた。
――利用者の来所のきっかけは、施設が抑えておきたいところ。
経過は失念したが、私が“佐賀に戻る可能性”についての話となる。
「そう簡単には戻れませんね。あるいは…」
…私の想いから出た言葉は伏せておく。それは、施設の方にも予想外の一言だったはずだ。
生活の基盤が定まれば、拠点となる土地からは離れがたい。私の来歴では、郷里に帰ることは容易ではない。今までは、そこに思い至ることすら無かった。
――大都市圏には、様々な経緯で地方から人が集まる。
“巻き取っていく”と形容しても良いかもしれない。もちろん都会生活に馴染み、帰りたくない人が多数いるのは事実だろう。
逆に“望郷の想い”を抱く者にも、郷里に帰る道は険しいようだ。そんな記憶が過(よ)ぎる中、スタッフの方から“みえつスコープ”の使い方の説明を受けた。
この時を超える双眼鏡で、本当に強かった佐賀の姿は見えるのだろうか。
(続く)
〔関連記事:
2020年11月09日
連続ブログ小説「旅立の剣」(6)ささやかな幸福
こんばんは。
「幕末佐賀藩を大河ドラマで見たい!」と発心した私。昨秋、佐賀での取材を開始した頃の話です。
私の周りに「なんと無意味なことを!」と言う人はいませんでした。ただ、呆気に取られていただけ…という可能性は残ります。
最初の目的地は“佐野常民記念館”。屋外は降りしきる雨。他に来館者の姿はなく、私のためだけに“みえつドームシアター”の上映が始まります。
――船底から煽るように見上げる、大型の艦船。
長さ45.5メートルの船体がリアルに迫ってくる。
映し出されるのは、佐賀藩海軍の主力艦・“電流丸”。
“電流丸”は、佐賀藩がオランダから購入した蒸気船。アメリカに渡った幕府の“咸臨丸”と同じく、スクリュー推進式の新鋭艦だった。
――空を舞う、鳥の目も用いて“電流丸”を眺める。
有明海の干満の差を利用して船を曳き込み、整備を行う“ドライドック”の紹介。西洋の技術だけでなく、日本古来の工法も活きているのが渋い。
佐賀藩は、国産初の実用蒸気船“凌風丸”を建造した。有明の海を駆け回った小型蒸気船。蒸気機関の修繕も自力で行えるのが、佐賀の強みだった。

――この映像が見られるだけでも、ここまで来た甲斐はあった…
ささやかな幸福感に浸る私に吉報が続く。
「雨、止んだみたいですよ。」
風雨は治まり、曇り空が広がる。
私は「見えない世界遺産」“三重津海軍所跡”を見聞する機会を得た。
(続く)
〔関連記事(後半):「主に伊万里市民の方を対象にしたつぶやき」〕
「幕末佐賀藩を大河ドラマで見たい!」と発心した私。昨秋、佐賀での取材を開始した頃の話です。
私の周りに「なんと無意味なことを!」と言う人はいませんでした。ただ、呆気に取られていただけ…という可能性は残ります。
最初の目的地は“佐野常民記念館”。屋外は降りしきる雨。他に来館者の姿はなく、私のためだけに“みえつドームシアター”の上映が始まります。
――船底から煽るように見上げる、大型の艦船。
長さ45.5メートルの船体がリアルに迫ってくる。
映し出されるのは、佐賀藩海軍の主力艦・“電流丸”。
“電流丸”は、佐賀藩がオランダから購入した蒸気船。アメリカに渡った幕府の“咸臨丸”と同じく、スクリュー推進式の新鋭艦だった。
――空を舞う、鳥の目も用いて“電流丸”を眺める。
有明海の干満の差を利用して船を曳き込み、整備を行う“ドライドック”の紹介。西洋の技術だけでなく、日本古来の工法も活きているのが渋い。
佐賀藩は、国産初の実用蒸気船“凌風丸”を建造した。有明の海を駆け回った小型蒸気船。蒸気機関の修繕も自力で行えるのが、佐賀の強みだった。
――この映像が見られるだけでも、ここまで来た甲斐はあった…
ささやかな幸福感に浸る私に吉報が続く。
「雨、止んだみたいですよ。」
風雨は治まり、曇り空が広がる。
私は「見えない世界遺産」“三重津海軍所跡”を見聞する機会を得た。
(続く)
〔関連記事(後半):
2020年11月08日
連続ブログ小説「旅立の剣」(5)雨に打たれても
こんばんは。
「佐野常民記念館入口」バス停から、同施設までは徒歩5分とあります。
ほぼ1年前の訪問時、この短い道のりも、風雨に見舞われて長く感じました。
――“佐野常民記念館”にたどり着いた。時刻は12時前。
私が玄関口に着いたときには、雨でずぶ濡れだった。
「…こんにちは。」
見渡す範囲では、現在の訪問者は私1人。とくに不思議はない。平日(金曜)でもあるし、この天気だ。
私の風体では佐賀への出張ついでに立ち寄ったと見えるだろうか。“佐野常民記念館”も目的地の1つだが、このスケジュールを決めた要因は別にあった。
――外は引き続き、雨。
雨天の場合、屋外での“三重津海軍所跡”の見学はできない様子だ。天気が回復しないときは、施設内を見学次第、すぐに市街地へ戻る事も考える。
帰りのバスの時刻を確認した。私の活動時間は限られる一方、佐賀で調査すべきポイントは多い。佐賀での一刻には、非常に重みがあるのだ。

――そんな思案を始めたところ、スタッフの方から声がかかる。
「まずは、こちらにどうぞ。」
“みえつドームシアター”に案内される。半球体状の映像空間だ。
こうして私1人に向けた“幕末佐賀藩の海軍物語”の上映が始まった。
「おおっ!いきなり、こう来たか…」
朝から移動し続け、雨にも降られたが、肝心の調査はこれからだ。
(続く)
「佐野常民記念館入口」バス停から、同施設までは徒歩5分とあります。
ほぼ1年前の訪問時、この短い道のりも、風雨に見舞われて長く感じました。
――“佐野常民記念館”にたどり着いた。時刻は12時前。
私が玄関口に着いたときには、雨でずぶ濡れだった。
「…こんにちは。」
見渡す範囲では、現在の訪問者は私1人。とくに不思議はない。平日(金曜)でもあるし、この天気だ。
私の風体では佐賀への出張ついでに立ち寄ったと見えるだろうか。“佐野常民記念館”も目的地の1つだが、このスケジュールを決めた要因は別にあった。
――外は引き続き、雨。
雨天の場合、屋外での“三重津海軍所跡”の見学はできない様子だ。天気が回復しないときは、施設内を見学次第、すぐに市街地へ戻る事も考える。
帰りのバスの時刻を確認した。私の活動時間は限られる一方、佐賀で調査すべきポイントは多い。佐賀での一刻には、非常に重みがあるのだ。
――そんな思案を始めたところ、スタッフの方から声がかかる。
「まずは、こちらにどうぞ。」
“みえつドームシアター”に案内される。半球体状の映像空間だ。
こうして私1人に向けた“幕末佐賀藩の海軍物語”の上映が始まった。
「おおっ!いきなり、こう来たか…」
朝から移動し続け、雨にも降られたが、肝心の調査はこれからだ。
(続く)
2020年11月07日
連続ブログ小説「旅立の剣」(4)早津江の嵐
こんばんは。
わずか2日間。30時間にも満たない短い滞在。
佐賀での調査活動の様子を綴る“連続ブログ小説”です。
昨秋10月の、ある金曜日。時刻は11:40を過ぎた。
私は、早津江行きのバスから下車した。
――ポッ、ポッと降っていた雨。
雨の勢いが増した頃、バス停に降りた私。
バス停の名は「“佐野常民”記念館」の最寄りを示すが、施設は見当たらない。
田園風景の中、徒歩での移動を開始したとき、雨足が強まる。
雨だけならまだしも、風の吹く音も響いてきた。

――まず、退避できる場所を探さねば…
疾風の勢いに乗り、横殴りとなった雨。どしゃ降りの域に達する。
傘を盾として雨を受けるが、かなりの風圧を感じる。
幕末と言えば“蒸気船”だが、当時は、帆走での航海が併用された。
海軍力に長じた佐賀藩。先人たちも風を読む力を学んだのだろう。
――後ろからの追い風。傘を強く叩く雨。
まるで“嵐の幕末”だが、このまま濡れ続けるのも不本意だ。
私は退避できる場所を見つけ、身を隠した。
「秋雨も良いが、これは度が過ぎているな…」と一息をつく。
降りしきる雨の向こう側。“佐野常民”記念館の建物は、眼前に現れていた。
(続く)
〔関連記事(後半):第12話「海軍伝習」⑩-1(負けんばい!・前編)〕
わずか2日間。30時間にも満たない短い滞在。
佐賀での調査活動の様子を綴る“連続ブログ小説”です。
昨秋10月の、ある金曜日。時刻は11:40を過ぎた。
私は、早津江行きのバスから下車した。
――ポッ、ポッと降っていた雨。
雨の勢いが増した頃、バス停に降りた私。
バス停の名は「“佐野常民”記念館」の最寄りを示すが、施設は見当たらない。
田園風景の中、徒歩での移動を開始したとき、雨足が強まる。
雨だけならまだしも、風の吹く音も響いてきた。
――まず、退避できる場所を探さねば…
疾風の勢いに乗り、横殴りとなった雨。どしゃ降りの域に達する。
傘を盾として雨を受けるが、かなりの風圧を感じる。
幕末と言えば“蒸気船”だが、当時は、帆走での航海が併用された。
海軍力に長じた佐賀藩。先人たちも風を読む力を学んだのだろう。
――後ろからの追い風。傘を強く叩く雨。
まるで“嵐の幕末”だが、このまま濡れ続けるのも不本意だ。
私は退避できる場所を見つけ、身を隠した。
「秋雨も良いが、これは度が過ぎているな…」と一息をつく。
降りしきる雨の向こう側。“佐野常民”記念館の建物は、眼前に現れていた。
(続く)
〔関連記事(後半):
2020年11月06日
連続ブログ小説「旅立の剣」(3)流れる景色を
こんばんは。
本シリーズでは、1年ちょっと前の話をお送りしています。
2019年10月の金曜日。佐賀駅到着から30分ほどが経過。
時刻は、午前の11:00を回った。
――場所は、佐賀駅前バスターミナル。
私は“早津江”行きのバスを待っていた。
佐賀は故郷だが、いまの私には“遠征”である。
そのため、私は荷物を背負って移動する。
目的地に向かうバスは30分に1本程度だ。

――各地行きのバスが乗り場を周回する。
ターミナルという名に、ふさわしい光景。
待ち時間に、次からの行動を算段する。
私が“早津江”に向かうのは、佐野常民の足跡をたどるため。
佐賀藩が、近代化の先駆けだったことが体感できるはずだ。
――バスの車窓に流れていく景色。
私の目に写る景色は、大都市圏とは異なっていた。
沿道が“栄えている”と言い張るのは強弁だろう。
だが、何やらホッとする感覚がある。
この落ち着きを保ったまま、佐賀が力を取り戻す日を想った。
(続く)
〔関連記事(写真):「望郷の剣2」〕
本シリーズでは、1年ちょっと前の話をお送りしています。
2019年10月の金曜日。佐賀駅到着から30分ほどが経過。
時刻は、午前の11:00を回った。
――場所は、佐賀駅前バスターミナル。
私は“早津江”行きのバスを待っていた。
佐賀は故郷だが、いまの私には“遠征”である。
そのため、私は荷物を背負って移動する。
目的地に向かうバスは30分に1本程度だ。
――各地行きのバスが乗り場を周回する。
ターミナルという名に、ふさわしい光景。
待ち時間に、次からの行動を算段する。
私が“早津江”に向かうのは、佐野常民の足跡をたどるため。
佐賀藩が、近代化の先駆けだったことが体感できるはずだ。
――バスの車窓に流れていく景色。
私の目に写る景色は、大都市圏とは異なっていた。
沿道が“栄えている”と言い張るのは強弁だろう。
だが、何やらホッとする感覚がある。
この落ち着きを保ったまま、佐賀が力を取り戻す日を想った。
(続く)
〔関連記事(写真):
2020年11月05日
連続ブログ小説「旅立の剣」(2)バスターミナルにて
こんばんは。
にわかに始まった「連続ブログ小説」です。淡々と続きます。
2019年10月。
ある金曜日の朝。時刻は10:30を回った。
雲行きはあやしくも、明るさを残す空。
ほどよい潤いを含んだ風が、清々しい。
――佐賀駅前に降り立った。
計画どおり、午前中の佐賀入りを果たす。
まず、第一段階は成功と言って良い。
私が佐賀で活動できる時間は限られる。
可能な限り、迅速な行動を要す。
――駅前バスターミナルへの移動。
私を出迎えたのは“賢人たち”の案内板だった。
やはり佐賀は、私の期待に応えてくれるようだ。
ターミナルが日常である人は、おそらく気に留めない。
日々が積もれば、ただのバス乗り場の表示。何も不思議はない。

――佐賀は故郷だが、私には“非日常”の世界。
2018年の“さが幕末維新博”。
その盛況は伝え聞くのみ。「行きたかった!」と悔やむばかりだった。
佐賀から遠い不利、ピークを外した悲しみ。
逆説的だが、これらは私の“強み”になり得る。
(続く)
〔関連記事(中盤):「“麒麟(きりん)”とともに走る」〕
にわかに始まった「連続ブログ小説」です。淡々と続きます。
2019年10月。
ある金曜日の朝。時刻は10:30を回った。
雲行きはあやしくも、明るさを残す空。
ほどよい潤いを含んだ風が、清々しい。
――佐賀駅前に降り立った。
計画どおり、午前中の佐賀入りを果たす。
まず、第一段階は成功と言って良い。
私が佐賀で活動できる時間は限られる。
可能な限り、迅速な行動を要す。
――駅前バスターミナルへの移動。
私を出迎えたのは“賢人たち”の案内板だった。
やはり佐賀は、私の期待に応えてくれるようだ。
ターミナルが日常である人は、おそらく気に留めない。
日々が積もれば、ただのバス乗り場の表示。何も不思議はない。
――佐賀は故郷だが、私には“非日常”の世界。
2018年の“さが幕末維新博”。
その盛況は伝え聞くのみ。「行きたかった!」と悔やむばかりだった。
佐賀から遠い不利、ピークを外した悲しみ。
逆説的だが、これらは私の“強み”になり得る。
(続く)
〔関連記事(中盤):
2020年11月04日
連続ブログ小説「旅立の剣」(1)佐賀への旅立ち
こんばんは。
“文章の瞬発力”を鍛えたい意図もある、このシリーズ。
いつもより短い文章を投稿していきます。
初見の皆様にもご説明します。「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と決意し、密かに活動を始めたころの話です。
このシリーズは、表向きはサラリーマンの…佐賀藩士(?)が、情報収集のため奔走した2日間の記録です。
――2019年(令和元年)初夏。
私は周到に準備を始めた。
手元には、10月のカレンダー。
「ここだ。ここしかない。」
この週末だけは、必ず休みを取る…
きっと様々な障壁があるだろう。
しかし、外してはならない。
この機会を逃せば、計画(夜明け)は1年後れるのだ。
――乾いた街で続いた消耗戦…
気付けば、私も歳をとった。
ここ数年、身を削って仕事に打ち込んできた。
ある意味で‟戦って”はいたのかもしれない。
いったい何が残ったというのか。

――空っぽになった気持ち。
心を満たすものは、遠く離れた故郷・佐賀にある。
遡ること5か月ほど前。時代が平成から令和に変わる直前。
私は、佐賀に新たな価値を見出していた。
(続く)
〔関連記事(後半):「慈雨の剣」〕
“文章の瞬発力”を鍛えたい意図もある、このシリーズ。
いつもより短い文章を投稿していきます。
初見の皆様にもご説明します。「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と決意し、密かに活動を始めたころの話です。
このシリーズは、表向きはサラリーマンの…佐賀藩士(?)が、情報収集のため奔走した2日間の記録です。
――2019年(令和元年)初夏。
私は周到に準備を始めた。
手元には、10月のカレンダー。
「ここだ。ここしかない。」
この週末だけは、必ず休みを取る…
きっと様々な障壁があるだろう。
しかし、外してはならない。
この機会を逃せば、計画(夜明け)は1年後れるのだ。
――乾いた街で続いた消耗戦…
気付けば、私も歳をとった。
ここ数年、身を削って仕事に打ち込んできた。
ある意味で‟戦って”はいたのかもしれない。
いったい何が残ったというのか。
――空っぽになった気持ち。
心を満たすものは、遠く離れた故郷・佐賀にある。
遡ること5か月ほど前。時代が平成から令和に変わる直前。
私は、佐賀に新たな価値を見出していた。
(続く)
〔関連記事(後半):
2020年11月03日
「“連続ブログ小説”を試みる」
こんばんは。
当ブログを開始してから11か月ほどの期間が経過しました。
ほぼ毎日、連続して投稿できていたのは、当初の半年足らず。
最近では“2日に1度”の投稿ペースを意識しています。
――ご覧いただいている皆様のおかげで
当初の計画で目標とした、第1段階を達成できました。
かなり流動的ですが「佐賀 大河ドラマ」と検索した際、当ブログが1ページ目でヒットすることも増えてきています。
“本編”第1部「幕末黎明編」も、いよいよ大詰めです。第17話~第18話ぐらいで、1つの区切りにしたいと考えています。

――しかし、ここで幾つかの問題が
ごく当然の話ですが、私の能力は“佐賀の賢人たち”に遥かに及びません。
そのため“賢人たち”の活躍をリアルに再現するのは難しいです。
それを補うため、「大河ドラマ」の映像をイメージしてから、文章化しています。
投稿するエピソードによっては、かなり創作の要素が強い場合もあります。
「佐賀には、こんな凄い人もいた!」と感動しながら、その勢いで書く…というのが、よくあるパターンです。
――こうして、開始から1年近くが、経過した今…
流行のアニメから言葉を拝借すると“全集中”を繰り返し、少々息切れしています。私のブログのテーマだと、情報収集と文案作成に負荷がかかります。
但し“佐賀の賢人たち”の業績は豊富ですから、“ネタ切れ”の心配は無いようです。そのため、時間と体力の制約のみが厳しいところです。
――しばらく、更新を見合わせることも検討しました。
ここは“継続は力なり”と考え、“省エネ”で投稿できる方法を選択します。
私には“さがファンブログ”の先達各位のような、楽しい日記は書けません。
日常で面白いネタを確保することも困難です。
当ブログには唯一、私とその周辺を題材とした「望郷の剣」シリーズがあります。
これを応用して、何とか切り抜けます。
――「大河ドラマ」と並ぶ、NHKの看板番組のイメージで…
次回から連続ブログ小説「旅立の剣」を投稿します。
休養代わりの記事ですが、“本編”の補足も兼ねています。
昨秋、たった2日間の佐賀滞在の話。
一応、サブテーマは“挫折からの再生”としています。
当ブログを開始してから11か月ほどの期間が経過しました。
ほぼ毎日、連続して投稿できていたのは、当初の半年足らず。
最近では“2日に1度”の投稿ペースを意識しています。
――ご覧いただいている皆様のおかげで
当初の計画で目標とした、第1段階を達成できました。
かなり流動的ですが「佐賀 大河ドラマ」と検索した際、当ブログが1ページ目でヒットすることも増えてきています。
“本編”第1部「幕末黎明編」も、いよいよ大詰めです。第17話~第18話ぐらいで、1つの区切りにしたいと考えています。
――しかし、ここで幾つかの問題が
ごく当然の話ですが、私の能力は“佐賀の賢人たち”に遥かに及びません。
そのため“賢人たち”の活躍をリアルに再現するのは難しいです。
それを補うため、「大河ドラマ」の映像をイメージしてから、文章化しています。
投稿するエピソードによっては、かなり創作の要素が強い場合もあります。
「佐賀には、こんな凄い人もいた!」と感動しながら、その勢いで書く…というのが、よくあるパターンです。
――こうして、開始から1年近くが、経過した今…
流行のアニメから言葉を拝借すると“全集中”を繰り返し、少々息切れしています。私のブログのテーマだと、情報収集と文案作成に負荷がかかります。
但し“佐賀の賢人たち”の業績は豊富ですから、“ネタ切れ”の心配は無いようです。そのため、時間と体力の制約のみが厳しいところです。
――しばらく、更新を見合わせることも検討しました。
ここは“継続は力なり”と考え、“省エネ”で投稿できる方法を選択します。
私には“さがファンブログ”の先達各位のような、楽しい日記は書けません。
日常で面白いネタを確保することも困難です。
当ブログには唯一、私とその周辺を題材とした「望郷の剣」シリーズがあります。
これを応用して、何とか切り抜けます。
――「大河ドラマ」と並ぶ、NHKの看板番組のイメージで…
次回から連続ブログ小説「旅立の剣」を投稿します。
休養代わりの記事ですが、“本編”の補足も兼ねています。
昨秋、たった2日間の佐賀滞在の話。
一応、サブテーマは“挫折からの再生”としています。
2020年11月01日
「主に吉野ヶ里町民の皆様を対象としたつぶやき」
こんばんは。
第15話「遣米使節」で、ついに佐賀藩士たちが、日本を飛び出します。幕末期、多くの佐賀の人々が海外に渡り、新たな知識を得て、日本近代化を牽引します。
対外使節への同行のほか、軍事関係や商業の調査、語学や工業技術のための留学、万国博覧会への出展など…その目的はさまざま。
…殿・鍋島直正は、本当は自分の目で海外を見たかったようです。殿が家臣たちを各国に派遣するので、空間的にスケールの大きい話になっていきます。
――空間だけでなく、時間的にもスケールの大きい話を目指していこう!
…今回は吉野ヶ里町の皆様へのつぶやきなので、思い切って“古代”まで飛んでみました。文末までには、幕末・明治の話につなげるので、ご安心ください。
“吉野ケ里歴史公園”です。佐賀でも最強クラスの知名度を誇る観光スポット。ここは外せないですね。

――弥生時代の遺跡を見つめ、現在まで通じるテーマを考えます。
「豊かな暮らしを、どう実現するか」
「そのために国は、どうあるべきか」
…たぶん、この辺りはどの時代にも関係するのかな、と思います。
この「歴史公園」は凄いです。広大な敷地に、復元した巨大集落。長崎本線の車窓からでも、初見の人をアッと言わせるだけのインパクトがあります。
たぶん歴史公園の趣旨から外れますが、幕末の動乱期にも“防護柵”は各地で使用されたでしょうから…“ロケ地”としても見映えするかも…とか空想します。
――次は、戦国時代。佐賀には“治水の神様”と言われた人物がいました。
「みやき町民の皆様」への記事でも、お名前が上がった方。
〔参照(前半):「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」〕
佐賀藩ご初代・鍋島勝茂公の側近・成富兵庫茂安さまです。
筑前(福岡)に向かう水を肥前(佐賀)へ流すための水路・“蛤水道”(はまぐりすいどう)を築いています。
――“戦国の曲者(くせもの)”との評価もある、成富兵庫茂安。
優れた“治水家”の茂安ですが、策略家の一面も伝わります。佐賀の発展のために、水を確保する抜け目の無さも感じます。
こうして背振山系からの豊富な水は、吉野ヶ里の大地を潤すことになります。
肥後(熊本)の加藤清正から、ぜひ「わが家臣に!」と誘いがあったようですが、
茂安は、「たとえ肥後の一国を頂いても、お受けできない」と拒絶したとか。
戦国の策士ですが、主君は裏切らない…これはカッコ良い“さがんもん”ですね。

――さて、戦国時代の話を続けますが、ここから幕末につなげます。
吉野ヶ里町にある、“西往寺”というお寺。豊臣秀吉の九州平定後、吉野ヶ里に移り、ここを“菩提寺”とした武将がいました。
元・筑後(福岡)の大木城主・大木知光。佐賀七賢人(八賢人)の1人・大木喬任のご先祖です。
大木にも「今は鍋島家に仕えているが、こちらも元は城主の家系!」という気概はあったかもしれません。
――そして、時代が幕末を経て、明治に進んだとき…
大木たちの師匠・枝吉神陽は、“尊王思想”を弟子である佐賀の賢人たちに説き、のちに実弟・副島種臣らにより、「明治新政府の方向性」として結実します。
その思想は、将軍や大名、その家臣…などの主従関係はなくなり、「天皇のもとに皆が集う」という政治の“あるべき姿”を求めます。
――そのためか、明治維新の英語表記は“the Meiji Restoration”。
直訳すると“明治復古”。欧米諸国の理解では、体制一新を意味する“維新”ではなく、“復古”となっています。
アメリカ合衆国など西洋の政治体制を取り入れながらも、「日本は本来の政権に戻った!」と欧米諸国に説明したことが伺えます。
――大木は新政府の創成期に、文部卿(大臣)・司法卿などの重職を歴任。
才気溢れる改革者である江藤新平が着手した仕事を、手堅い実務能力で形にしていった大木喬任。
大木は、国政を統括する“参議”の1人として長く務め、“筆頭参議”となります。江戸時代ならば“老中首座”。現代なら“総理大臣”に類するポジションでしょう。
――しかしながら、“地味”と語られがちな大木喬任。
大木は、東京遷都の立役者と言ってよいでしょうし、義務教育の制度まで築いています。業績のわりに、あまり知られていない…という印象です。
「ご先祖は城持ちの武将!」…というのは、様々な苦難に耐え続けた大木喬任の誇りでもあったでしょう。
“本編”では大木喬任を「無愛想だが、面倒見のよい兄貴分」という感じで描いています。「大河ドラマ」を意識すると配役に悩む人物の1人です。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を目指すには、大木先生の知名度も引き上げたいので「吉野ヶ里町とは、少し縁がある人」として、皆様の記憶に留めていただければ幸いです。
第15話「遣米使節」で、ついに佐賀藩士たちが、日本を飛び出します。幕末期、多くの佐賀の人々が海外に渡り、新たな知識を得て、日本近代化を牽引します。
対外使節への同行のほか、軍事関係や商業の調査、語学や工業技術のための留学、万国博覧会への出展など…その目的はさまざま。
…殿・鍋島直正は、本当は自分の目で海外を見たかったようです。殿が家臣たちを各国に派遣するので、空間的にスケールの大きい話になっていきます。
――空間だけでなく、時間的にもスケールの大きい話を目指していこう!
…今回は吉野ヶ里町の皆様へのつぶやきなので、思い切って“古代”まで飛んでみました。文末までには、幕末・明治の話につなげるので、ご安心ください。
“吉野ケ里歴史公園”です。佐賀でも最強クラスの知名度を誇る観光スポット。ここは外せないですね。
――弥生時代の遺跡を見つめ、現在まで通じるテーマを考えます。
「豊かな暮らしを、どう実現するか」
「そのために国は、どうあるべきか」
…たぶん、この辺りはどの時代にも関係するのかな、と思います。
この「歴史公園」は凄いです。広大な敷地に、復元した巨大集落。長崎本線の車窓からでも、初見の人をアッと言わせるだけのインパクトがあります。
たぶん歴史公園の趣旨から外れますが、幕末の動乱期にも“防護柵”は各地で使用されたでしょうから…“ロケ地”としても見映えするかも…とか空想します。
――次は、戦国時代。佐賀には“治水の神様”と言われた人物がいました。
「みやき町民の皆様」への記事でも、お名前が上がった方。
〔参照(前半):
佐賀藩ご初代・鍋島勝茂公の側近・成富兵庫茂安さまです。
筑前(福岡)に向かう水を肥前(佐賀)へ流すための水路・“蛤水道”(はまぐりすいどう)を築いています。
――“戦国の曲者(くせもの)”との評価もある、成富兵庫茂安。
優れた“治水家”の茂安ですが、策略家の一面も伝わります。佐賀の発展のために、水を確保する抜け目の無さも感じます。
こうして背振山系からの豊富な水は、吉野ヶ里の大地を潤すことになります。
肥後(熊本)の加藤清正から、ぜひ「わが家臣に!」と誘いがあったようですが、
茂安は、「たとえ肥後の一国を頂いても、お受けできない」と拒絶したとか。
戦国の策士ですが、主君は裏切らない…これはカッコ良い“さがんもん”ですね。
――さて、戦国時代の話を続けますが、ここから幕末につなげます。
吉野ヶ里町にある、“西往寺”というお寺。豊臣秀吉の九州平定後、吉野ヶ里に移り、ここを“菩提寺”とした武将がいました。
元・筑後(福岡)の大木城主・大木知光。佐賀七賢人(八賢人)の1人・大木喬任のご先祖です。
大木にも「今は鍋島家に仕えているが、こちらも元は城主の家系!」という気概はあったかもしれません。
――そして、時代が幕末を経て、明治に進んだとき…
大木たちの師匠・枝吉神陽は、“尊王思想”を弟子である佐賀の賢人たちに説き、のちに実弟・副島種臣らにより、「明治新政府の方向性」として結実します。
その思想は、将軍や大名、その家臣…などの主従関係はなくなり、「天皇のもとに皆が集う」という政治の“あるべき姿”を求めます。
――そのためか、明治維新の英語表記は“the Meiji Restoration”。
直訳すると“明治復古”。欧米諸国の理解では、体制一新を意味する“維新”ではなく、“復古”となっています。
アメリカ合衆国など西洋の政治体制を取り入れながらも、「日本は本来の政権に戻った!」と欧米諸国に説明したことが伺えます。
――大木は新政府の創成期に、文部卿(大臣)・司法卿などの重職を歴任。
才気溢れる改革者である江藤新平が着手した仕事を、手堅い実務能力で形にしていった大木喬任。
大木は、国政を統括する“参議”の1人として長く務め、“筆頭参議”となります。江戸時代ならば“老中首座”。現代なら“総理大臣”に類するポジションでしょう。
――しかしながら、“地味”と語られがちな大木喬任。
大木は、東京遷都の立役者と言ってよいでしょうし、義務教育の制度まで築いています。業績のわりに、あまり知られていない…という印象です。
「ご先祖は城持ちの武将!」…というのは、様々な苦難に耐え続けた大木喬任の誇りでもあったでしょう。
“本編”では大木喬任を「無愛想だが、面倒見のよい兄貴分」という感じで描いています。「大河ドラマ」を意識すると配役に悩む人物の1人です。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を目指すには、大木先生の知名度も引き上げたいので「吉野ヶ里町とは、少し縁がある人」として、皆様の記憶に留めていただければ幸いです。