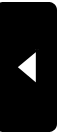2020年01月08日
「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③‐3大隈重信編)
こんばんは。
早くも再来年の「大河ドラマ」が発表されましたね。気になる主役は…
北条義時:大河ドラマ第61作「鎌倉殿の13人」(2022年)
脚本は“三谷幸喜”氏、主演は“小栗旬”氏という豪華な布陣です。
…2024年くらいには幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!と思いつつ、いつものブログに戻ります。
第3部明治飛翔編
佐賀藩士“大隈重信”編です。
大河ドラマ作品の“主役”に連なる人脈があります。
①大隈重信を新政府に引き込んだ人
小松帯刀:大河ドラマ第47作「篤姫」(2008年)※準主役
薩摩・島津家の分家に生まれた篤姫は、薩摩藩主・島津斉彬の養女となり、徳川13代将軍の正室となりました。 倒幕の時代の渦に巻き込まれながらも、江戸城を無血開城へと導きます。
のちに薩摩藩の家老となる小松帯刀は篤姫に恋心を抱く設定で描かれ、大人気となりました。
…小松帯刀は明治初期に病となり、明治新政府での仕事の後継に大隈重信を推挙します。
大隈は諸外国との交渉等で活躍していましたが、小松と特に親しかったわけではなく、小松の能力で人を評価する姿勢に、大隈は感銘を受けたと伝わります。
②大隈重信が新政府に引き込んだ人
渋沢栄一:大河ドラマ第60作「青天を衝け」(2021年)
幕府から派遣されたバリ万博でフランスに滞在中に“株式会社”という仕組みを知った渋沢栄一。 “日本資本主義の父”とも言われ、銀行家・実業家として多数の会社を設立。新一万円札の肖像になる人物です。
…徳川の家臣になっていた渋沢栄一は、財政を担当する大隈重信の説得に応じて、新政府に出仕します。
後に大隈と渋沢は、対立したり協力したり、双方とも明治の時代を生き抜いて日本の近代化に貢献しています。
…大隈重信先生、もはや“主役”と呼んで良い気がするのです。
ちなみに「青天を衝け」(2021年予定)の発表は、たしか昨年9月だったので、わずか4か月ほどで次回作の発表。
…正直、とても驚きました。
注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。
早くも再来年の「大河ドラマ」が発表されましたね。気になる主役は…
北条義時:大河ドラマ第61作「鎌倉殿の13人」(2022年)
脚本は“三谷幸喜”氏、主演は“小栗旬”氏という豪華な布陣です。
…2024年くらいには幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!と思いつつ、いつものブログに戻ります。
第3部明治飛翔編
佐賀藩士“大隈重信”編です。
大河ドラマ作品の“主役”に連なる人脈があります。
①大隈重信を新政府に引き込んだ人
小松帯刀:大河ドラマ第47作「篤姫」(2008年)※準主役
薩摩・島津家の分家に生まれた篤姫は、薩摩藩主・島津斉彬の養女となり、徳川13代将軍の正室となりました。 倒幕の時代の渦に巻き込まれながらも、江戸城を無血開城へと導きます。
のちに薩摩藩の家老となる小松帯刀は篤姫に恋心を抱く設定で描かれ、大人気となりました。
…小松帯刀は明治初期に病となり、明治新政府での仕事の後継に大隈重信を推挙します。
大隈は諸外国との交渉等で活躍していましたが、小松と特に親しかったわけではなく、小松の能力で人を評価する姿勢に、大隈は感銘を受けたと伝わります。
②大隈重信が新政府に引き込んだ人
渋沢栄一:大河ドラマ第60作「青天を衝け」(2021年)
幕府から派遣されたバリ万博でフランスに滞在中に“株式会社”という仕組みを知った渋沢栄一。 “日本資本主義の父”とも言われ、銀行家・実業家として多数の会社を設立。新一万円札の肖像になる人物です。
…徳川の家臣になっていた渋沢栄一は、財政を担当する大隈重信の説得に応じて、新政府に出仕します。
後に大隈と渋沢は、対立したり協力したり、双方とも明治の時代を生き抜いて日本の近代化に貢献しています。
…大隈重信先生、もはや“主役”と呼んで良い気がするのです。
ちなみに「青天を衝け」(2021年予定)の発表は、たしか昨年9月だったので、わずか4か月ほどで次回作の発表。
…正直、とても驚きました。
注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。
2020年01月07日
「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③-2江藤新平編)
こんばんは。
昨日に続く第2部。江藤新平編です。
大河ドラマ第57作「西郷どん」(2018年)での“迫田孝也”氏の熱演も記憶に新しいところです。
第2部維新回天編について
佐賀藩士“江藤新平”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ才能がありました。
①江藤新平と相性が良かった人
大村益次郎:大河ドラマ第15作「花神」(1977年)
幕末の長州藩に生まれ、元は“村医者”でありながら、倒幕の司令官となった“天才軍人”大村益次郎。 徹底した合理主義で近代軍制を作り上げる。長州藩の視点から激動の幕末を描いた青春群像劇。
…大村益次郎は、江藤新平の能力を信頼していたようです。また、江藤も大村の才能を絶賛。大村は、江藤に「上野戦争」(江戸での旧幕府軍“彰義隊”との戦い)の作戦を明かしていました。
まず佐賀藩のアームストロング砲で、上野の敵陣に砲撃。そこで隠密行動の長州藩が突入、一気に決着。新政府を苦しめた“彰義隊”は大村のシナリオ通りに、およそ半日で壊滅。新政府は江戸の支配を固めました。
②江藤新平と相性が悪かった人
大久保利通:大河ドラマ第28作「翔ぶが如く」(1990年)
幕末から明治を舞台に変革の時代をリードした2人の薩摩藩士、西郷隆盛と大久保利通の友情と対立を描きます。やがて袂を分かった2人は「西南戦争」で敵味方となり、永遠の別れとなります。
…大久保利通と“岩倉使節団”が欧米に渡航。日本に残った西郷隆盛と江藤新平たちは“留守政府”と呼ばれます。 江藤が司法制度を作り上げたほか、“留守政府”は急速に日本を近代国家とする仕組みづくりを進めます。
結局、海外視察だけに終わった“岩倉使節団”。留守の間に近代化を進めた佐賀や土佐(高知)に脅威を感じ、主導権を奪うために策略を巡らせます。
…権力の集中こそが近代化の力と考える大久保利通にとって、江藤新平の才能、“司法による権力の抑制”は脅威でした。
本日は以上です。
今回の特集は“維新回天”の功労者、しかし悲劇的な最期を迎えている方々…と言えるかもしれません。
佐賀県内で情報収集をしているとき「大久保が帰って来なきゃよかったのに!」という意見もありました。
…斬新な視点です。いろいろ考えさせられました。
注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。
昨日に続く第2部。江藤新平編です。
大河ドラマ第57作「西郷どん」(2018年)での“迫田孝也”氏の熱演も記憶に新しいところです。
第2部維新回天編について
佐賀藩士“江藤新平”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ才能がありました。
①江藤新平と相性が良かった人
大村益次郎:大河ドラマ第15作「花神」(1977年)
幕末の長州藩に生まれ、元は“村医者”でありながら、倒幕の司令官となった“天才軍人”大村益次郎。 徹底した合理主義で近代軍制を作り上げる。長州藩の視点から激動の幕末を描いた青春群像劇。
…大村益次郎は、江藤新平の能力を信頼していたようです。また、江藤も大村の才能を絶賛。大村は、江藤に「上野戦争」(江戸での旧幕府軍“彰義隊”との戦い)の作戦を明かしていました。
まず佐賀藩のアームストロング砲で、上野の敵陣に砲撃。そこで隠密行動の長州藩が突入、一気に決着。新政府を苦しめた“彰義隊”は大村のシナリオ通りに、およそ半日で壊滅。新政府は江戸の支配を固めました。
②江藤新平と相性が悪かった人
大久保利通:大河ドラマ第28作「翔ぶが如く」(1990年)
幕末から明治を舞台に変革の時代をリードした2人の薩摩藩士、西郷隆盛と大久保利通の友情と対立を描きます。やがて袂を分かった2人は「西南戦争」で敵味方となり、永遠の別れとなります。
…大久保利通と“岩倉使節団”が欧米に渡航。日本に残った西郷隆盛と江藤新平たちは“留守政府”と呼ばれます。 江藤が司法制度を作り上げたほか、“留守政府”は急速に日本を近代国家とする仕組みづくりを進めます。
結局、海外視察だけに終わった“岩倉使節団”。留守の間に近代化を進めた佐賀や土佐(高知)に脅威を感じ、主導権を奪うために策略を巡らせます。
…権力の集中こそが近代化の力と考える大久保利通にとって、江藤新平の才能、“司法による権力の抑制”は脅威でした。
本日は以上です。
今回の特集は“維新回天”の功労者、しかし悲劇的な最期を迎えている方々…と言えるかもしれません。
佐賀県内で情報収集をしているとき「大久保が帰って来なきゃよかったのに!」という意見もありました。
…斬新な視点です。いろいろ考えさせられました。
注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。
2020年01月06日
「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③‐1鍋島直正編)
こんばんは。
新年の大河ドラマ「麒麟がくる」のPRにあたり、過去の作品にも注目がされる時期です。
この流れに乗じて、幕末佐賀藩と大河ドラマ作品の“主役”との関わりを考えてみます。
第1部幕末黎明編について
佐賀藩主“鍋島直正”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ存在感があります。
①鍋島直正が期待した人
井伊直弼:大河ドラマ第1作「花の生涯」(1963年)
幕末、開国か攘夷か!の激動の時代。幕府の大老となった井伊直弼は、攘夷論に対して開国を主張します。
強い幕府を目指して戦い続け、“桜田門外の変”で命を落とすまでの激動の物語。
…井伊直弼と鍋島直正は、外国の知識を取り入れ、強い日本を創ろうという点で同志でした。
幕府の大老でありながら、井伊直弼は佐賀藩邸にも足を運んでいます。鍋島直正にとっては良き理解者でした。
②鍋島直正に期待した人
徳川慶喜:大河ドラマ第37作「徳川慶喜」(1998年)
水戸徳川家に生まれ、江戸幕府の第15代将軍となった徳川慶喜は、やがて大政奉還を決意します。
“最後の将軍”として、幕府の終わりを見届けた波乱の半生の物語。
…徳川慶喜は、反幕府勢力を抑えるため、江戸には入らず上方(京・大坂)にいた将軍です。佐賀藩の軍事力に注目し、鍋島直正に呼出をかけます。
鍋島直正は蒸気船で大坂に入り、慶喜に会いますが、政争には深入りを避けます。 晩年、慶喜は直正を「利口」とも「ずるい人」とも評したようです。
…鍋島直正の存在感は、幕末が終わり、明治が始まっても発揮されます。
本日は以上です。
大河ドラマの主役は1人とは限りません。
複数の主人公でつないでこそ、幕末佐賀藩の魅力は伝わる…と信じて、続けます。
注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。
新年の大河ドラマ「麒麟がくる」のPRにあたり、過去の作品にも注目がされる時期です。
この流れに乗じて、幕末佐賀藩と大河ドラマ作品の“主役”との関わりを考えてみます。
第1部幕末黎明編について
佐賀藩主“鍋島直正”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ存在感があります。
①鍋島直正が期待した人
井伊直弼:大河ドラマ第1作「花の生涯」(1963年)
幕末、開国か攘夷か!の激動の時代。幕府の大老となった井伊直弼は、攘夷論に対して開国を主張します。
強い幕府を目指して戦い続け、“桜田門外の変”で命を落とすまでの激動の物語。
…井伊直弼と鍋島直正は、外国の知識を取り入れ、強い日本を創ろうという点で同志でした。
幕府の大老でありながら、井伊直弼は佐賀藩邸にも足を運んでいます。鍋島直正にとっては良き理解者でした。
②鍋島直正に期待した人
徳川慶喜:大河ドラマ第37作「徳川慶喜」(1998年)
水戸徳川家に生まれ、江戸幕府の第15代将軍となった徳川慶喜は、やがて大政奉還を決意します。
“最後の将軍”として、幕府の終わりを見届けた波乱の半生の物語。
…徳川慶喜は、反幕府勢力を抑えるため、江戸には入らず上方(京・大坂)にいた将軍です。佐賀藩の軍事力に注目し、鍋島直正に呼出をかけます。
鍋島直正は蒸気船で大坂に入り、慶喜に会いますが、政争には深入りを避けます。 晩年、慶喜は直正を「利口」とも「ずるい人」とも評したようです。
…鍋島直正の存在感は、幕末が終わり、明治が始まっても発揮されます。
本日は以上です。
大河ドラマの主役は1人とは限りません。
複数の主人公でつないでこそ、幕末佐賀藩の魅力は伝わる…と信じて、続けます。
注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。
2020年01月05日
「“主要な人物”をどう繋ぐか?」(関係性②)
こんにちは。
当ブログでは、幕末の佐賀藩を題材とした3部構成の作品をイメージしています。
参考:「佐賀の物語を描け!」(独自色③)
そのうちに「私が見たい大河ドラマ」全47話を順を追って、お伝えできればと考えています。強くイメージをすれば実現することもある…かもしれないので。
例年ならば、年明けは大河ドラマの開始時期ですね。
「麒麟がくる」まで、もう少し待ち時間があるようですので、心して待ちましょう。
今回は、「第1部 幕末黎明編」をベースとした主要人物の関係について考えてみたいと思います。
賢人たちを語るとどうしても“様”をつけたくなるのですが、今回こそ歴史ドラマとして“敬称略”で記述します。
佐賀藩主鍋島直正が“伝説の管理職”として藩士たちを自由自在に動かします。
優秀な藩士と見れば、身分に関らず、長崎・江戸・大坂はもちろん、蝦夷地にまで派遣します。佐賀藩からの“留学時代”の到来です。
①メインテーマ:“技術”の近代化
“殿”の義兄鍋島茂義(武雄領主)が先陣を切った佐賀藩の洋学研究。
鍋島直正は“万能の研究主任”佐野 常民を見出します。
佐野常民は、機械・化学・翻訳…あらゆる専門人材をスカウト。プロジェクトを組成し、鉄製大砲、蒸気機関、近代海軍まで作り、科学技術の佐賀藩を引っ張ります。
②サブテーマ:“教育沸騰”の佐賀藩
“殿”の右腕鍋島安房(須古領主)が猛勉強で率いる佐賀藩の教育改革。
鍋島直正は“尊王のカリスマ指導者”枝吉 神陽に期待します。
枝吉神陽が主導する“義祭同盟”は、天皇に忠義を尽くした「楠木正成」公を祀る秘密結社!…のはずが、藩のナンバー2・鍋島安房を筆頭に上層部からも参加が多数。
“義祭同盟”には神陽先生と同級生の島義勇をはじめ、実弟の副島種臣、大木喬任や江藤新平も参加。そして、最年少の大隈八太郎(重信)も加わります。神陽先生は、次世代である副島、大木、江藤、大隈を鍛えます。
③番外編:“蝦夷地”を幕府とともに探索
“殿”の命令で島 義勇が蝦夷地の探索のほか、日本沿岸をおよそ2年かけて調査します。
北の大地は国の守り、富の宝庫として重要な場所。島義勇の冒険に“義祭同盟”の後輩たちからも熱い視線が注がれます。
以上です。
副島 種臣は少し年長なのですが、この段階では大木喬任、江藤新平、大隈八太郎(重信)は、まだ学生とお考えください。
ちなみに“義祭同盟”が結成されたのは、佐賀藩の反射炉が着工したのとほぼ同時期(1850年)です。
では、本日の締めくくりに、その頃の(1850年)の”佐賀の七賢人”の年齢を考えてみましょう。ちなみに、枝吉神陽先生は佐野・島と同級生です。
鍋島 直正…35歳
佐野 常民…27歳
島 義勇 …27歳
副島 種臣…21歳
大木 喬任…17歳
江藤 新平…15歳
大隈 重信…13歳
…まさに“佐賀藩の青春”ですね。若いって素晴らしい。
さて、既にお仕事を始めている方も多いかもしれませんが、明日からも頑張りましょう!
当ブログでは、幕末の佐賀藩を題材とした3部構成の作品をイメージしています。
参考:「佐賀の物語を描け!」(独自色③)
そのうちに「私が見たい大河ドラマ」全47話を順を追って、お伝えできればと考えています。強くイメージをすれば実現することもある…かもしれないので。
例年ならば、年明けは大河ドラマの開始時期ですね。
「麒麟がくる」まで、もう少し待ち時間があるようですので、心して待ちましょう。
今回は、「第1部 幕末黎明編」をベースとした主要人物の関係について考えてみたいと思います。
賢人たちを語るとどうしても“様”をつけたくなるのですが、今回こそ歴史ドラマとして“敬称略”で記述します。
佐賀藩主鍋島直正が“伝説の管理職”として藩士たちを自由自在に動かします。
優秀な藩士と見れば、身分に関らず、長崎・江戸・大坂はもちろん、蝦夷地にまで派遣します。佐賀藩からの“留学時代”の到来です。
①メインテーマ:“技術”の近代化
“殿”の義兄鍋島茂義(武雄領主)が先陣を切った佐賀藩の洋学研究。
鍋島直正は“万能の研究主任”佐野 常民を見出します。
佐野常民は、機械・化学・翻訳…あらゆる専門人材をスカウト。プロジェクトを組成し、鉄製大砲、蒸気機関、近代海軍まで作り、科学技術の佐賀藩を引っ張ります。
②サブテーマ:“教育沸騰”の佐賀藩
“殿”の右腕鍋島安房(須古領主)が猛勉強で率いる佐賀藩の教育改革。
鍋島直正は“尊王のカリスマ指導者”枝吉 神陽に期待します。
枝吉神陽が主導する“義祭同盟”は、天皇に忠義を尽くした「楠木正成」公を祀る秘密結社!…のはずが、藩のナンバー2・鍋島安房を筆頭に上層部からも参加が多数。
“義祭同盟”には神陽先生と同級生の島義勇をはじめ、実弟の副島種臣、大木喬任や江藤新平も参加。そして、最年少の大隈八太郎(重信)も加わります。神陽先生は、次世代である副島、大木、江藤、大隈を鍛えます。
③番外編:“蝦夷地”を幕府とともに探索
“殿”の命令で島 義勇が蝦夷地の探索のほか、日本沿岸をおよそ2年かけて調査します。
北の大地は国の守り、富の宝庫として重要な場所。島義勇の冒険に“義祭同盟”の後輩たちからも熱い視線が注がれます。
以上です。
副島 種臣は少し年長なのですが、この段階では大木喬任、江藤新平、大隈八太郎(重信)は、まだ学生とお考えください。
ちなみに“義祭同盟”が結成されたのは、佐賀藩の反射炉が着工したのとほぼ同時期(1850年)です。
では、本日の締めくくりに、その頃の(1850年)の”佐賀の七賢人”の年齢を考えてみましょう。ちなみに、枝吉神陽先生は佐野・島と同級生です。
鍋島 直正…35歳
佐野 常民…27歳
島 義勇 …27歳
副島 種臣…21歳
大木 喬任…17歳
江藤 新平…15歳
大隈 重信…13歳
…まさに“佐賀藩の青春”ですね。若いって素晴らしい。
さて、既にお仕事を始めている方も多いかもしれませんが、明日からも頑張りましょう!
2020年01月04日
「“女性の活躍”をどう描くか?」(関係性①)
こんにちは。
前回まで、第1部「幕末黎明編」の前に語っておきたい2地域(武雄、須古)を特集しました。
さて“大河ドラマ”作品の傾向として、主人公の性別が男→女→男→女…と隔年で繰り返していた時期がありました。
既にお気づきの方もいるかもしれません。当ブログ開設以来、女性の登場人物が、ほぼ出てきていないのです。(大隈の母…ぐらいかなと思います。)
これでは「幕末佐賀藩を描いた大河ドラマ」が実現しづらくなってしまいます。今回も強い“妄想”を武器に、このテーマに挑んでみたいと思います。
では、第1部から第3部まで順を追って、ご覧ください。
①幕末黎明編 ~姫たちの幕末~
鍋島直正様には、もはや“溺愛”と言って良いほど大事な姫がいます。川越(埼玉)の松平家に嫁いだ愛娘を心配するあまり、送った手紙は200通とも言われます。
その名は“貢姫”様。見たところ“お父様似”のお顔立ちと私は思っています。父親にとって、自分の面影が写る娘ほど可愛いものはない!とご推察いたします。
…2019年の第2回さが維新まつりには、佐賀の偉人に扮して行列するイベントがありました。鍋島直正様の役には応募条件があり、妻と娘(小学校高学年)が一緒に参加することでした。
これは貢姫様がいなければ、鍋島直正様の描き方としては不完全!という佐賀県のメッセージなのかもしれません。
②維新回天編 ~妻たちの維新~
江藤新平様は、おそらく女性に脇目も振らず、学問と実践に打ち込んだのでしょう。結果、忙しい江藤様の妻となったのは、年上の従姉妹“江口千代子”様でした。
“押しかけ女房”的な説もあるようですが、面倒見の良い理解者と語った方が実情に合っているようです。
江藤様は超働き者で何事にも無頓着ですが、家庭は大事にしています。
各種エピソードからの推測ですが、江藤様は「女性が放っておけない雰囲気」を持っていたのでは?と考えています。(但し、自覚は無いと思われます。)
女子の教育が近代国家につながると説き、搾取される女性たちの権利も取り戻そうとした人。
…“悲劇のヒーロー”は、タカラヅカ歌劇など舞台演劇での題材にも適した人物だと思います。
タイトルは「正義なりしがゆえに」とかどうでしょう。「私の見たい大河ドラマ」ではそんな感じの描き方のイメージです。
③明治飛翔編 ~新しい女性の明治~
大隈重信様の周りには強い女性が集まるようです。母・大隈三井子様は信念を持った教育ママ。大隈様の学習環境を全力で整えます。
妻は“明治の女傑”こと大隈綾子様。皆が西洋の真似に必死のなか、堂々と和服で闊歩できる大物です。
…大隈様は自宅を溜まり場として、幕末には先輩たちと学問を磨き、明治には政治家や官僚と政策を練り上げます。
家をマネジメントする女性の力があって、はじめて本領を発揮する人物と考えています。
また、明治期には佐野常民様の設立した日本赤十字社では“新島八重”様が社員として活躍します。大河ドラマ「八重の桜」の主役・綾瀬はるか氏を想い出してしまう方も多いでしょう。
他にも佐賀に関わる女性には、“外交で活躍した貴婦人”や“日本初の女性科学者”もいますので、様々な描き方が可能です。
“佐賀の七賢人”を中心としたドラマは、男性が主役の物語に分類されるでしょう。
しかし、並行して「女性の活躍」の変遷を描けば、“時代の変化”そのものが表現できると考えています。
前回まで、第1部「幕末黎明編」の前に語っておきたい2地域(武雄、須古)を特集しました。
さて“大河ドラマ”作品の傾向として、主人公の性別が男→女→男→女…と隔年で繰り返していた時期がありました。
既にお気づきの方もいるかもしれません。当ブログ開設以来、女性の登場人物が、ほぼ出てきていないのです。(大隈の母…ぐらいかなと思います。)
これでは「幕末佐賀藩を描いた大河ドラマ」が実現しづらくなってしまいます。今回も強い“妄想”を武器に、このテーマに挑んでみたいと思います。
では、第1部から第3部まで順を追って、ご覧ください。
①幕末黎明編 ~姫たちの幕末~
鍋島直正様には、もはや“溺愛”と言って良いほど大事な姫がいます。川越(埼玉)の松平家に嫁いだ愛娘を心配するあまり、送った手紙は200通とも言われます。
その名は“貢姫”様。見たところ“お父様似”のお顔立ちと私は思っています。父親にとって、自分の面影が写る娘ほど可愛いものはない!とご推察いたします。
…2019年の第2回さが維新まつりには、佐賀の偉人に扮して行列するイベントがありました。鍋島直正様の役には応募条件があり、妻と娘(小学校高学年)が一緒に参加することでした。
これは貢姫様がいなければ、鍋島直正様の描き方としては不完全!という佐賀県のメッセージなのかもしれません。
②維新回天編 ~妻たちの維新~
江藤新平様は、おそらく女性に脇目も振らず、学問と実践に打ち込んだのでしょう。結果、忙しい江藤様の妻となったのは、年上の従姉妹“江口千代子”様でした。
“押しかけ女房”的な説もあるようですが、面倒見の良い理解者と語った方が実情に合っているようです。
江藤様は超働き者で何事にも無頓着ですが、家庭は大事にしています。
各種エピソードからの推測ですが、江藤様は「女性が放っておけない雰囲気」を持っていたのでは?と考えています。(但し、自覚は無いと思われます。)
女子の教育が近代国家につながると説き、搾取される女性たちの権利も取り戻そうとした人。
…“悲劇のヒーロー”は、タカラヅカ歌劇など舞台演劇での題材にも適した人物だと思います。
タイトルは「正義なりしがゆえに」とかどうでしょう。「私の見たい大河ドラマ」ではそんな感じの描き方のイメージです。
③明治飛翔編 ~新しい女性の明治~
大隈重信様の周りには強い女性が集まるようです。母・大隈三井子様は信念を持った教育ママ。大隈様の学習環境を全力で整えます。
妻は“明治の女傑”こと大隈綾子様。皆が西洋の真似に必死のなか、堂々と和服で闊歩できる大物です。
…大隈様は自宅を溜まり場として、幕末には先輩たちと学問を磨き、明治には政治家や官僚と政策を練り上げます。
家をマネジメントする女性の力があって、はじめて本領を発揮する人物と考えています。
また、明治期には佐野常民様の設立した日本赤十字社では“新島八重”様が社員として活躍します。大河ドラマ「八重の桜」の主役・綾瀬はるか氏を想い出してしまう方も多いでしょう。
他にも佐賀に関わる女性には、“外交で活躍した貴婦人”や“日本初の女性科学者”もいますので、様々な描き方が可能です。
“佐賀の七賢人”を中心としたドラマは、男性が主役の物語に分類されるでしょう。
しかし、並行して「女性の活躍」の変遷を描けば、“時代の変化”そのものが表現できると考えています。
2020年01月03日
「県内の各地域を表現する②」(須古編)
こんにちは。
私事ですが、昨日、友人たちと会って来ました。
――そして友人Aから指摘を受けました。
「幕末の佐賀では、登場人物の情報を検索しなければわからない。その時点でドラマ化は難しいのではないか」
…これが“教科書本文”に掲載の賢人で物語をつなぎたい理由の1つです。
参照記事:(「STEP2:幕末の俊英たち」、「佐賀の物語を描け!(独自色③)」)
――さらに友人Aは続けます。
「佐賀を舞台にするなら“超古代ファンタジー”がいいと思うけどね。」
…たしかに佐賀には “吉野ヶ里遺跡”や“徐福伝説”もあります。
佐賀の“古代史における潜在能力”が付加価値を生み出す可能性も否めません。
――さて、“超古代ファンタジー”に限らず、佐賀には“戦国”にも語るべき歴史があります。

※須古領(現:佐賀県白石町西部)の風景
佐賀の原風景である田園地帯が見えます。
しかし、ご注目いただきたいのは写真の撮影を行っている高台です。
この高台は、今を遡ること約450年ほど昔、城攻めの死闘が行われた場所。
“肥前の熊”と呼ばれた猛将“龍造寺隆信”様が獲得した「須古城」です。
――なんだ?幕末の話ではないのか?と思われた方。少々お待ちください。ここからです。
豪放磊落な猛将龍造寺隆信様には、相棒と呼ぶべき存在がいました。
それが、冷静沈着な智将鍋島直茂様。
双璧である二将の存在により「須古城」を拠点とした龍造寺氏は北部九州の覇権を握りました。
しかし、後に戦国の勝者・徳川家康公が語ったように、
「勝つことのみ知りて負けること知らざれば害その身に至る…」との警句もあります。
――これが戦国時代…
ある戦いで龍造寺隆信様は、鍋島直茂様の忠告を聞かずに敵陣(島津軍)に深入りし過ぎ、罠に嵌ります。そして、帰らぬ人となりました。
“猛将”の代わりとなる人物のいない龍造寺氏は、実質的に鍋島直茂様が率いていくこととなりました。後に「化け猫騒動」と呼ばれる伝説が生じたように、複雑な事情も色々とあったことでしょう。
紆余曲折を経たものの、こうして佐賀藩が成立します。
龍造寺氏の家臣団をそのまま引き継いだため、佐賀藩は龍造寺一門に“自治領”を配分しました。
これが前回の“武雄領”、今回の“須古領”の起こりです。
〇須古領~“努力一徹の補佐役”鍋島安房~
――そして、幕末。
“須古領主”の家に後継ぎの男子がいなかったため、佐賀本藩より養子が迎えられます。この方が後に“殿”鍋島直正様を補佐する佐賀藩のナンバー2になります。
「鍋島安房」と呼ばれることが多い“鍋島茂真”様。実は“殿”の異母兄で、1歳年上です。

※須古領主の屋敷は「須古城」の登り口の近くにありました。
財政再建と教育改革の両方の責任者を務める、いわば“殿”の右腕。
佐賀藩を支えた“努力一徹の補佐役”です。
仕事の成果は目覚ましく、
・藩の借財整理の実行役
・ハゼ蝋や陶器など特産開発
・組織改革で経費を節減
…長崎警備の負担等で大赤字だった、佐賀藩の財政を見事に立て直します。
――また、教育改革の責任者でもあります。
仕事が終われば若い藩士に混じって藩校・弘道館で猛勉強します。
責任者が模範を示して、真剣に努力するものだから、若い藩士も頑張るしかありません。
“幕末最高の実務能力”を育てた「猛勉強する佐賀藩」の雰囲気はこの方が作ったと言っても良いでしょう。
いずれ詳しくお話しする“義祭同盟”のきっかけになる“尊王の象徴”「楠木正成」公の像を設置したのも、鍋島安房様です。
佐賀の県庁通りには、佐賀の偉人たちの銅像が並んでいます。
残念ながら、現時点では鍋島安房様の銅像はありません。
しかし、地元・白石町を始め、佐賀県内の皆様に広く業績を知っていただきたい方です。
私事ですが、昨日、友人たちと会って来ました。
――そして友人Aから指摘を受けました。
「幕末の佐賀では、登場人物の情報を検索しなければわからない。その時点でドラマ化は難しいのではないか」
…これが“教科書本文”に掲載の賢人で物語をつなぎたい理由の1つです。
参照記事:(「STEP2:幕末の俊英たち」、「佐賀の物語を描け!(独自色③)」)
――さらに友人Aは続けます。
「佐賀を舞台にするなら“超古代ファンタジー”がいいと思うけどね。」
…たしかに佐賀には “吉野ヶ里遺跡”や“徐福伝説”もあります。
佐賀の“古代史における潜在能力”が付加価値を生み出す可能性も否めません。
――さて、“超古代ファンタジー”に限らず、佐賀には“戦国”にも語るべき歴史があります。

※須古領(現:佐賀県白石町西部)の風景
佐賀の原風景である田園地帯が見えます。
しかし、ご注目いただきたいのは写真の撮影を行っている高台です。
この高台は、今を遡ること約450年ほど昔、城攻めの死闘が行われた場所。
“肥前の熊”と呼ばれた猛将“龍造寺隆信”様が獲得した「須古城」です。
――なんだ?幕末の話ではないのか?と思われた方。少々お待ちください。ここからです。
豪放磊落な猛将龍造寺隆信様には、相棒と呼ぶべき存在がいました。
それが、冷静沈着な智将鍋島直茂様。
双璧である二将の存在により「須古城」を拠点とした龍造寺氏は北部九州の覇権を握りました。
しかし、後に戦国の勝者・徳川家康公が語ったように、
「勝つことのみ知りて負けること知らざれば害その身に至る…」との警句もあります。
――これが戦国時代…
ある戦いで龍造寺隆信様は、鍋島直茂様の忠告を聞かずに敵陣(島津軍)に深入りし過ぎ、罠に嵌ります。そして、帰らぬ人となりました。
“猛将”の代わりとなる人物のいない龍造寺氏は、実質的に鍋島直茂様が率いていくこととなりました。後に「化け猫騒動」と呼ばれる伝説が生じたように、複雑な事情も色々とあったことでしょう。
紆余曲折を経たものの、こうして佐賀藩が成立します。
龍造寺氏の家臣団をそのまま引き継いだため、佐賀藩は龍造寺一門に“自治領”を配分しました。
これが前回の“武雄領”、今回の“須古領”の起こりです。
〇須古領~“努力一徹の補佐役”鍋島安房~
――そして、幕末。
“須古領主”の家に後継ぎの男子がいなかったため、佐賀本藩より養子が迎えられます。この方が後に“殿”鍋島直正様を補佐する佐賀藩のナンバー2になります。
「鍋島安房」と呼ばれることが多い“鍋島茂真”様。実は“殿”の異母兄で、1歳年上です。

※須古領主の屋敷は「須古城」の登り口の近くにありました。
財政再建と教育改革の両方の責任者を務める、いわば“殿”の右腕。
佐賀藩を支えた“努力一徹の補佐役”です。
仕事の成果は目覚ましく、
・藩の借財整理の実行役
・ハゼ蝋や陶器など特産開発
・組織改革で経費を節減
…長崎警備の負担等で大赤字だった、佐賀藩の財政を見事に立て直します。
――また、教育改革の責任者でもあります。
仕事が終われば若い藩士に混じって藩校・弘道館で猛勉強します。
責任者が模範を示して、真剣に努力するものだから、若い藩士も頑張るしかありません。
“幕末最高の実務能力”を育てた「猛勉強する佐賀藩」の雰囲気はこの方が作ったと言っても良いでしょう。
いずれ詳しくお話しする“義祭同盟”のきっかけになる“尊王の象徴”「楠木正成」公の像を設置したのも、鍋島安房様です。
佐賀の県庁通りには、佐賀の偉人たちの銅像が並んでいます。
残念ながら、現時点では鍋島安房様の銅像はありません。
しかし、地元・白石町を始め、佐賀県内の皆様に広く業績を知っていただきたい方です。
2020年01月02日
「県内の各地域を表現する①」(武雄編)
こんにちは。
ドラマの再放送を見過ぎて疲れ気味…という方も、「いや、もう仕事してます」という方もご機嫌いかがでしょうか。
さて“幕末の大河ドラマ”は「佐賀市内の話でしょ。あまり関係がない…」とお考えの県内(各地域)の皆様にお届けするシリーズを企画しました。
江戸時代の佐賀藩には“支藩”や“自治領”が多くあり、“佐賀本藩”の規模は大きくない…という特徴があります。
各地域のご領主様が領民を治めるというスタイルです。幕末に、各地域の領主も活躍します。今回は、武雄編です。
①武雄領〔前編〕~“蘭学の先駆者”鍋島茂義~
佐賀藩主“鍋島直正”様が日本の近代化を牽引した!というのが、「私の見たい大河ドラマ」第1部です。
そこで序盤で描くべき先駆者をおさらいしておきましょう。

先日、この記事(STEP1「名君の登場まで」)でご紹介した武雄領主・鍋島茂義様です。自分で西洋砲術を学んでしまう、行動力抜群の領主様です。
佐賀県西部にあり、地理的には佐賀よりさらに長崎に近い武雄。
茂義様は、西洋の文物の収集がご趣味で「お買い物リスト」が残っています。
ちなみに“蘭学兄貴”なんてお呼びしているのは、“殿”の姉上の夫(義兄)だからです。この14歳年上の“兄貴”が“鍋島直正”様に強い影響を与え、日本の近代化につながっていきます。
②武雄領〔後編〕~“朴訥な武人”鍋島茂昌~
佐賀藩の“秘密研究所”のような“武雄領”。
その真価は「私の見たい大河ドラマ」では第2部で発揮されます。
明治初期には“幕末最強の軍事技術”を持つ佐賀藩の中でも、武雄領の部隊は“武芸第一”と言われていました。
父・茂義様とは違い、洋学より武芸の子・鍋島茂昌様。
当時の佐賀藩の軍事責任者として“朴訥な武人”が部隊を率います。
 戊辰戦争が東北で続くなか、武雄部隊は天皇の“御親兵”として東京を警備していました。
戊辰戦争が東北で続くなか、武雄部隊は天皇の“御親兵”として東京を警備していました。
しかし、その頃東北では旧幕府側で最強と言われる庄内藩(山形)が新政府軍を次々と打ち破っていました。
庄内藩には大富豪・本間家があり、資金は潤沢です。そのため装備は最新式で、新政府側についた東北諸藩だけでなく、新政府軍も歯が立ちません。
しかも大名・商人・領民が一体となり、鉄の結束を誇っています。
新政府はついに佐賀藩(武雄部隊)の投入を決断しました。
武雄部隊は、新政府側に付いて窮地に陥っている久保田藩(秋田)の救援に向かいます。
そのミッションは「…無敵の庄内藩を止め、久保田藩を救うこと。」
…詳しくはいずれ語りたいと思います。このときの縁で現在も秋田市と武雄市の間には交流が続いています。
今回は以上です。一度、武雄領についても語ってみたかったので、掲載しました。いつも以上に知識が浅い点はご容赦ください。
佐賀藩のドラマをイメージすると、魅力的な登場人物・エピソードが多いので、まとめ方が難しいところです。
しかし、何とか“武雄地域”の活躍も“見たい!”ものです。
ドラマの再放送を見過ぎて疲れ気味…という方も、「いや、もう仕事してます」という方もご機嫌いかがでしょうか。
さて“幕末の大河ドラマ”は「佐賀市内の話でしょ。あまり関係がない…」とお考えの県内(各地域)の皆様にお届けするシリーズを企画しました。
江戸時代の佐賀藩には“支藩”や“自治領”が多くあり、“佐賀本藩”の規模は大きくない…という特徴があります。
各地域のご領主様が領民を治めるというスタイルです。幕末に、各地域の領主も活躍します。今回は、武雄編です。
①武雄領〔前編〕~“蘭学の先駆者”鍋島茂義~
佐賀藩主“鍋島直正”様が日本の近代化を牽引した!というのが、「私の見たい大河ドラマ」第1部です。
そこで序盤で描くべき先駆者をおさらいしておきましょう。

先日、この記事(STEP1「名君の登場まで」)でご紹介した武雄領主・鍋島茂義様です。自分で西洋砲術を学んでしまう、行動力抜群の領主様です。
佐賀県西部にあり、地理的には佐賀よりさらに長崎に近い武雄。
茂義様は、西洋の文物の収集がご趣味で「お買い物リスト」が残っています。
ちなみに“蘭学兄貴”なんてお呼びしているのは、“殿”の姉上の夫(義兄)だからです。この14歳年上の“兄貴”が“鍋島直正”様に強い影響を与え、日本の近代化につながっていきます。
②武雄領〔後編〕~“朴訥な武人”鍋島茂昌~
佐賀藩の“秘密研究所”のような“武雄領”。
その真価は「私の見たい大河ドラマ」では第2部で発揮されます。
明治初期には“幕末最強の軍事技術”を持つ佐賀藩の中でも、武雄領の部隊は“武芸第一”と言われていました。
父・茂義様とは違い、洋学より武芸の子・鍋島茂昌様。
当時の佐賀藩の軍事責任者として“朴訥な武人”が部隊を率います。

しかし、その頃東北では旧幕府側で最強と言われる庄内藩(山形)が新政府軍を次々と打ち破っていました。
庄内藩には大富豪・本間家があり、資金は潤沢です。そのため装備は最新式で、新政府側についた東北諸藩だけでなく、新政府軍も歯が立ちません。
しかも大名・商人・領民が一体となり、鉄の結束を誇っています。
新政府はついに佐賀藩(武雄部隊)の投入を決断しました。
武雄部隊は、新政府側に付いて窮地に陥っている久保田藩(秋田)の救援に向かいます。
そのミッションは「…無敵の庄内藩を止め、久保田藩を救うこと。」
…詳しくはいずれ語りたいと思います。このときの縁で現在も秋田市と武雄市の間には交流が続いています。
今回は以上です。一度、武雄領についても語ってみたかったので、掲載しました。いつも以上に知識が浅い点はご容赦ください。
佐賀藩のドラマをイメージすると、魅力的な登場人物・エピソードが多いので、まとめ方が難しいところです。
しかし、何とか“武雄地域”の活躍も“見たい!”ものです。
2020年01月01日
「佐賀の物語を描け!」(独自色③)
明けましておめでとうございます。
皆さま、清々しい新年をお迎えでしょうか。
そして、あまり芳しくない年明けの方も頑張っていきましょう!
初めてお目にかかる方にもご挨拶を。
当ブログでは、「佐賀の大河ドラマ」に関する“妄想”を延々とお送りしています。よろしくお願いいたします。
さて、年末からここまで駆け足で来ましたが、そもそもどんな“大河ドラマ”をイメージしているのかのお話をしていませんでした。
実は、以下のような3部構成の作品が見たいのです。
①幕末黎明編 ~“技術”の近代化~
佐賀藩主“鍋島直正”が牽引した日本の科学技術
②維新回天編 ~“外交”の近代化~
“江藤新平”と佐賀藩士たちが構築する近代国家
③明治飛翔編 ~“意識”の近代化~
“大隈重信”と佐賀出身者の現代につながる奮闘
明治新国家の“心技体”すべてを創ることを先導した佐賀藩!
…という描き方のご提案です。
まぁ、並びとしては、技→体→心の順番でできあがってますけど…
年の初めなので、書初めの気分で大風呂敷を広げてみました。
いつも、お読みいただいている皆様。
今年もよろしくお願いいたします。
皆さま、清々しい新年をお迎えでしょうか。
そして、あまり芳しくない年明けの方も頑張っていきましょう!
初めてお目にかかる方にもご挨拶を。
当ブログでは、「佐賀の大河ドラマ」に関する“妄想”を延々とお送りしています。よろしくお願いいたします。
さて、年末からここまで駆け足で来ましたが、そもそもどんな“大河ドラマ”をイメージしているのかのお話をしていませんでした。
実は、以下のような3部構成の作品が見たいのです。
①幕末黎明編 ~“技術”の近代化~
佐賀藩主“鍋島直正”が牽引した日本の科学技術
②維新回天編 ~“外交”の近代化~
“江藤新平”と佐賀藩士たちが構築する近代国家
③明治飛翔編 ~“意識”の近代化~
“大隈重信”と佐賀出身者の現代につながる奮闘
明治新国家の“心技体”すべてを創ることを先導した佐賀藩!
…という描き方のご提案です。
まぁ、並びとしては、技→体→心の順番でできあがってますけど…
年の初めなので、書初めの気分で大風呂敷を広げてみました。
いつも、お読みいただいている皆様。
今年もよろしくお願いいたします。