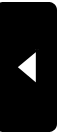2020年09月13日
佐賀城からのライブ配信の感想など②③
こんにちは。
「本日は祭りである…」とか言っていますが、今日2本目の投稿です。
今日は「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の8周年記念のイベントが、佐賀城本丸歴史館よりライブ配信されています。
――次の演目が始まってしまうので、ざっくりと振り返ります。
2本目「夜ば、あけとけ」と3本目「茶飲みに来んか?」は、毎週日曜に定例的に上演されている、いわば“定番”の演目のようです。
私も以前から「ぜひ見たい」と思っていた2つの演目。佐賀城の会場ではまだ観れていませんが、今日、視聴できたことで、大変得をした気分でおります。
――まず、2本目の「夜ば、あけとけ」について
これは“義祭同盟”が成立する前日譚と聞いていましたが、予想に反して島義勇と副島種臣の「愚痴大会」…というコミカルな要素が多いお話でした。
これも「三夜待ち」という佐賀の伝統的な風習と絡めて、尊王のカリスマ・枝吉神陽の人物像を浮き彫りにする快作だったと思います。

――3本目の「茶飲みに来んか?」について
明治に入って、一時、佐賀で隠居生活を送っていた殿・鍋島直正のもとに、大木喬任と江藤新平が訪ね、“助言”を求める…といった内容でした。
舞台が、佐賀の神野にある直正の別宅。題材は、東京への遷都というのが良い設定だな…と思います。神野公園を訪れたくなる出来栄えでした。
思ったことをバンバン発言する江藤と、練りに練ってから口に出す大木…そして、両者を丸ごと受け止める殿…バランスの取れた関係性だなと思いました。
――次の演目の配信が始まったようなので、この辺で…
14:30からの演目は、とくに鹿島市へのエールだそうですね。
16:00からの演目は、個人的に神埼市の方にお勧めしたいと思います。
【参考情報】
配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。
https://www.facebook.com/hachikenjin/
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)
演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。
https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)
「本日は祭りである…」とか言っていますが、今日2本目の投稿です。
今日は「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の8周年記念のイベントが、佐賀城本丸歴史館よりライブ配信されています。
――次の演目が始まってしまうので、ざっくりと振り返ります。
2本目「夜ば、あけとけ」と3本目「茶飲みに来んか?」は、毎週日曜に定例的に上演されている、いわば“定番”の演目のようです。
私も以前から「ぜひ見たい」と思っていた2つの演目。佐賀城の会場ではまだ観れていませんが、今日、視聴できたことで、大変得をした気分でおります。
――まず、2本目の「夜ば、あけとけ」について
これは“義祭同盟”が成立する前日譚と聞いていましたが、予想に反して島義勇と副島種臣の「愚痴大会」…というコミカルな要素が多いお話でした。
これも「三夜待ち」という佐賀の伝統的な風習と絡めて、尊王のカリスマ・枝吉神陽の人物像を浮き彫りにする快作だったと思います。

――3本目の「茶飲みに来んか?」について
明治に入って、一時、佐賀で隠居生活を送っていた殿・鍋島直正のもとに、大木喬任と江藤新平が訪ね、“助言”を求める…といった内容でした。
舞台が、佐賀の神野にある直正の別宅。題材は、東京への遷都というのが良い設定だな…と思います。神野公園を訪れたくなる出来栄えでした。
思ったことをバンバン発言する江藤と、練りに練ってから口に出す大木…そして、両者を丸ごと受け止める殿…バランスの取れた関係性だなと思いました。
――次の演目の配信が始まったようなので、この辺で…
14:30からの演目は、とくに鹿島市へのエールだそうですね。
16:00からの演目は、個人的に神埼市の方にお勧めしたいと思います。
【参考情報】
配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。
https://www.facebook.com/hachikenjin/
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)
演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。
https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)
タグ :八賢人おもてなし隊
2020年09月13日
佐賀城からのライブ配信の感想など①
おはようございます。
昨日の投稿をご覧いただいた方には「本日は私にとって祭のようなものである」旨をお伝えしていました。
今日13日(日)、いつもならば、佐賀に帰らねば観ることができない「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇を全国で見ることができるライブ配信が行われています。
――先ほど10時から上演された「もぐら打ち」という演目を観ました。
子役2人が参加する同隊が普段行っていないタイプの珍しい演目。
この活動を続けていくための“次世代育成”の意図もあるということに感服していたところです。

――お話の感想としては…
11歳の子どもの時点を描いた、大木幡六(喬任)がすごく優しい子!さらに年少の大隈八太郎(重信)は、元気いっぱいに暴れ回っていました。
――「八賢人おもてなし隊」の演目では、“もぐら打ち”という、伝統行事を織り込むことで、子役を前面に出していました。
無益な“つぶし合い”を徹底して回避しようとした、佐賀の“優しさ”も示した良作だったと思います。
…11時30分からは、またライブ配信で“義祭同盟”が成立する前日譚があるようですね。そろそろMCトークが開始されるようですが、楽しみです。
――ちなみに、この2人を私が描くと…
意外に怒らせると怖い大木喬任を表現するために、こんな描写になります。〔参照(後半):第5話「藩校立志」⑧〕
う~ん、殺伐としてますね…私の作品。
【参考情報】
配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。
https://www.facebook.com/hachikenjin/
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)
演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。
https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)
昨日の投稿をご覧いただいた方には「本日は私にとって祭のようなものである」旨をお伝えしていました。
今日13日(日)、いつもならば、佐賀に帰らねば観ることができない「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇を全国で見ることができるライブ配信が行われています。
――先ほど10時から上演された「もぐら打ち」という演目を観ました。
子役2人が参加する同隊が普段行っていないタイプの珍しい演目。
この活動を続けていくための“次世代育成”の意図もあるということに感服していたところです。

――お話の感想としては…
11歳の子どもの時点を描いた、大木幡六(喬任)がすごく優しい子!さらに年少の大隈八太郎(重信)は、元気いっぱいに暴れ回っていました。
――「八賢人おもてなし隊」の演目では、“もぐら打ち”という、伝統行事を織り込むことで、子役を前面に出していました。
無益な“つぶし合い”を徹底して回避しようとした、佐賀の“優しさ”も示した良作だったと思います。
…11時30分からは、またライブ配信で“義祭同盟”が成立する前日譚があるようですね。そろそろMCトークが開始されるようですが、楽しみです。
――ちなみに、この2人を私が描くと…
意外に怒らせると怖い大木喬任を表現するために、こんな描写になります。〔参照(後半):
う~ん、殺伐としてますね…私の作品。
【参考情報】
配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。
https://www.facebook.com/hachikenjin/
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)
演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。
https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)
タグ :八賢人おもてなし隊
2020年09月12日
「これは見たい!!」
こんにちは。
「さがファンブログ」の記事から、ある情報に行き当たりました。
明日13日(日)に佐賀城本丸歴史館で行われる「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」に関する、イベントのお知らせです。
当ブログは、ほぼ同隊と共通の題材を扱うため、その活動については、つねづね目が離せません。
今のところ私は、似通った文章や人物描写になるのを避けるため、幕末・明治の佐賀を題材にした小説などはなるべく、読むのを控えています。
しかし、どう形容すべきか難しいのですが「八賢人おもてなし隊」が演じる歴史寸劇の描き方は真似ができない気がするので、観てもよいことにしています。
〔参照:敬意をこめて,「算盤大名」紀行~佐賀城・本丸~〕
――念のため言及しますが、私は「八賢人おもてなし隊」の“関係者”ではありません。
そのため、ここからは1人のファンの個人的なお話です。
話の発端は、1年ほど前に遡ります。
「幕末の佐賀藩には、現代に活かすべき価値がある!」と発心した私。
しかし、私は遠方におり、簡単に佐賀へ帰ることが出来ません。何らかの行動を起こすべく、まず調査と資料の作成を続けていました。
私がこの“想い”に至ったとき、2018年に開催され大盛況だった“肥前さが幕末維新博覧会”は既に終了しています。ある意味、時機を逸した周回遅れのスタートだったとも言えます。
――“先行事例調査”として「佐賀の八賢人おもてなし隊」も、一度は見に行かねば…と考えたのです。
今考えると不遜な態度なわけですが、正直、あまり期待していなかったのです。
いまや全国各地の城や史跡に“おもてなし武将隊”が存在しています。しかし、テレビなどで拝見すると、見ているこちらがヒヤヒヤしてしまうことも…
「頑張って成りきっているのだから、温かい目で見てあげねばならない!」
そのような可能性まで考えていました。
しかも“戦国系の武将隊”ならば、鎧兜に身を固めて刀槍を派手に振れば、それだけでカッコいい。「佐賀の八賢人おもてなし隊」には、そんな優位性(アドバンテージ)も無さそうです。

――ある日曜、佐賀城本丸歴史館。私の“心配”は全くの杞憂(きゆう)に終わりました。
その演劇は、私の想定を遥かに超える完成度でした。
何と言いますか、最初は少しイメージとは違いましたが、演目が始まると…
「佐賀の殿様や賢人たちが、そこに居るのが見えた」のですね。
構成も巧みであり、初回から涙腺に来ました。
「これは見るべきだ!やはり佐賀に来るなら日曜日だ!」
…という感じになったわけです。
こうして佐賀で調査スケジュールを組むたびに“観劇の時間”を優先的に設定するという現象が起きました。
――13日(日)は、この「八賢人おもてなし隊」の演劇がネットでライブ配信されるそうです。
たしかに演劇は“生もの”でしょう。会場の空気あってこその感動や笑い…その臨場感には代えがたいものがあります。
しかし、文章と写真イメージのみで成り立つ当ブログですら、読んでいただける皆様ならば…きっと面白くご覧いただけるのではと思います。
当日の配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できるようですが、
https://www.facebook.com/hachikenjin/
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)
演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。
https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)
――ちなみにライブ配信開始の9:40から夕方まで、特別上演を含む5本の演目が予定されているようです。
本当は佐賀城本丸で見たいのですが、遠方からでも鑑賞できるのは幸いです。
私にとっては、明日はもはや“お祭り”に等しいので、問題なく鑑賞できれば、個人的な感想を書いたりもしようと思います。
…全国各地で“望郷の想い”を秘め、日々を生きる佐賀藩士(?)たちにも、どこかで届くことを願って。
「さがファンブログ」の記事から、ある情報に行き当たりました。
明日13日(日)に佐賀城本丸歴史館で行われる「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」に関する、イベントのお知らせです。
当ブログは、ほぼ同隊と共通の題材を扱うため、その活動については、つねづね目が離せません。
今のところ私は、似通った文章や人物描写になるのを避けるため、幕末・明治の佐賀を題材にした小説などはなるべく、読むのを控えています。
しかし、どう形容すべきか難しいのですが「八賢人おもてなし隊」が演じる歴史寸劇の描き方は真似ができない気がするので、観てもよいことにしています。
〔参照:
――念のため言及しますが、私は「八賢人おもてなし隊」の“関係者”ではありません。
そのため、ここからは1人のファンの個人的なお話です。
話の発端は、1年ほど前に遡ります。
「幕末の佐賀藩には、現代に活かすべき価値がある!」と発心した私。
しかし、私は遠方におり、簡単に佐賀へ帰ることが出来ません。何らかの行動を起こすべく、まず調査と資料の作成を続けていました。
私がこの“想い”に至ったとき、2018年に開催され大盛況だった“肥前さが幕末維新博覧会”は既に終了しています。ある意味、時機を逸した周回遅れのスタートだったとも言えます。
――“先行事例調査”として「佐賀の八賢人おもてなし隊」も、一度は見に行かねば…と考えたのです。
今考えると不遜な態度なわけですが、正直、あまり期待していなかったのです。
いまや全国各地の城や史跡に“おもてなし武将隊”が存在しています。しかし、テレビなどで拝見すると、見ているこちらがヒヤヒヤしてしまうことも…
「頑張って成りきっているのだから、温かい目で見てあげねばならない!」
そのような可能性まで考えていました。
しかも“戦国系の武将隊”ならば、鎧兜に身を固めて刀槍を派手に振れば、それだけでカッコいい。「佐賀の八賢人おもてなし隊」には、そんな優位性(アドバンテージ)も無さそうです。
――ある日曜、佐賀城本丸歴史館。私の“心配”は全くの杞憂(きゆう)に終わりました。
その演劇は、私の想定を遥かに超える完成度でした。
何と言いますか、最初は少しイメージとは違いましたが、演目が始まると…
「佐賀の殿様や賢人たちが、そこに居るのが見えた」のですね。
構成も巧みであり、初回から涙腺に来ました。
「これは見るべきだ!やはり佐賀に来るなら日曜日だ!」
…という感じになったわけです。
こうして佐賀で調査スケジュールを組むたびに“観劇の時間”を優先的に設定するという現象が起きました。
――13日(日)は、この「八賢人おもてなし隊」の演劇がネットでライブ配信されるそうです。
たしかに演劇は“生もの”でしょう。会場の空気あってこその感動や笑い…その臨場感には代えがたいものがあります。
しかし、文章と写真イメージのみで成り立つ当ブログですら、読んでいただける皆様ならば…きっと面白くご覧いただけるのではと思います。
当日の配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できるようですが、
https://www.facebook.com/hachikenjin/
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)
演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。
https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html
(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)
――ちなみにライブ配信開始の9:40から夕方まで、特別上演を含む5本の演目が予定されているようです。
本当は佐賀城本丸で見たいのですが、遠方からでも鑑賞できるのは幸いです。
私にとっては、明日はもはや“お祭り”に等しいので、問題なく鑑賞できれば、個人的な感想を書いたりもしようと思います。
…全国各地で“望郷の想い”を秘め、日々を生きる佐賀藩士(?)たちにも、どこかで届くことを願って。
タグ :八賢人おもてなし隊
2020年09月10日
「主に上峰町民の方を対象にしたつぶやき」
こんばんは。
第13話「通商条約」の投稿が、ようやく完了しました。
新型コロナの第2波もあり、台風9・10号が立て続けに現れたり…と大変な夏でしたね。
ちなみに当ブログは、昨年12月にスタートしています。
それ以来、佐賀に一度も帰れていません。
昨年の秋は、現地取材に勤しむことも可能だったのですが…
――そんな昨秋、佐賀で見学しそこなった場所の1つ。
いわば鍋島家の博物館である「徴古館」です。
立ち寄ったのが早朝だったため、まだオープン前の時間でした。

――本編では“鍋島”姓の主要な人物が幾人か登場しています。
まず、第1部の主人公である、殿・鍋島直正。
武雄領主で、直正の義兄(姉の夫)
“蘭学の先駆者”・鍋島茂義。
須古領主で、直正の庶兄(母違いの兄)
“藩政ナンバー2”の請役・鍋島安房。
…序盤では、まだ若かったこの3人を中心に佐賀藩をどう建て直すか、策を練っていましたね。自分で書いてて何ですが、とても懐かしい…
〔参照:第2話「算盤大名」④〕
――本日のテーマは「鍋島夏雲(市佑)」という上峰町ゆかりの方。
この方は殿・鍋島直正直属の配下で、独立した自治領主ではありません。殿に側近として仕えること30年。
現在の上峰町に領地を有した上級武士。側近の筆頭格のようです。
――“本編”では、歴史的に重要な局面でお名前が出てきます。
ペリーの黒船来航で、幕府から“大砲200門”を発注されたとき
〔参照(文末):第8話「黒船来航」⑩〕
ロシアのプチャーチンとアメリカのペリーが立て続けに来航
〔参照(中盤):第11話「蝦夷探検」④(保守派の賢人)〕
そして、最新の13話では、老中・阿部正弘の急逝の一報
〔参照(前半):第13話「通商条約」⑩(扇の要が外れるとき…)〕
――何で歴史の転換点ばかりに、ちょっとずつ登場するかと言えば…
「鍋島夏雲日記」という“幕末の記録”を残しているからです。
この日記は「明治維新150周年記念事業」として活字化もされて、上峰町内の学校に配布されたとか。
…私も見たいです。上峰町民の皆様、この書籍を大切になさってください。
――コツコツと歴史的に価値ある情報を記録しておられたのですね。
おかげで“本編”では「几帳面な方」というキャラクター設定になってしまいました。
しかも、あのフェートン号事件が1808年で、鍋島夏雲は1802年生まれです。
“本編”で言えば、第1話よりも前に誕生し、第13話では50代ということに。それだけ長く、激動の時代を見てきている方です。
――私の調べでは、人物像がいまいち掴めていないのですが…
あるテレビ番組で、歴史学者の磯田道史さんが幕末期の古文書調査を振り返っていたとき。
「最初から佐賀に行けば良かった。すべての情報が集まっていた」旨の発言があったと記憶します。
この記憶と“鍋島夏雲”という人物をつなげて見ると「情報収集に長けた佐賀藩」のイメージが浮かびます。
「鍋島夏雲日記」も、自ら積極的に収集した情報だとすれば…
――実像は、几帳面な“書記官”のイメージと全く異なるかもしれません。
スパイ映画ならば“諜報機関の長官”、娯楽時代劇ならば“御庭番衆の御頭(おかしら)”みたいな…描き方もできそうに思います。
「幕末佐賀藩と、情報戦(インテリジェンス)」…
上峰町民の皆様へのつぶやき、やや空想の域を出ない内容も含まれましたが、面白いと共感いただける方がいれば幸いです。
第13話「通商条約」の投稿が、ようやく完了しました。
新型コロナの第2波もあり、台風9・10号が立て続けに現れたり…と大変な夏でしたね。
ちなみに当ブログは、昨年12月にスタートしています。
それ以来、佐賀に一度も帰れていません。
昨年の秋は、現地取材に勤しむことも可能だったのですが…
――そんな昨秋、佐賀で見学しそこなった場所の1つ。
いわば鍋島家の博物館である「徴古館」です。
立ち寄ったのが早朝だったため、まだオープン前の時間でした。
――本編では“鍋島”姓の主要な人物が幾人か登場しています。
まず、第1部の主人公である、殿・鍋島直正。
武雄領主で、直正の義兄(姉の夫)
“蘭学の先駆者”・鍋島茂義。
須古領主で、直正の庶兄(母違いの兄)
“藩政ナンバー2”の請役・鍋島安房。
…序盤では、まだ若かったこの3人を中心に佐賀藩をどう建て直すか、策を練っていましたね。自分で書いてて何ですが、とても懐かしい…
〔参照:
――本日のテーマは「鍋島夏雲(市佑)」という上峰町ゆかりの方。
この方は殿・鍋島直正直属の配下で、独立した自治領主ではありません。殿に側近として仕えること30年。
現在の上峰町に領地を有した上級武士。側近の筆頭格のようです。
――“本編”では、歴史的に重要な局面でお名前が出てきます。
ペリーの黒船来航で、幕府から“大砲200門”を発注されたとき
〔参照(文末):
ロシアのプチャーチンとアメリカのペリーが立て続けに来航
〔参照(中盤):
そして、最新の13話では、老中・阿部正弘の急逝の一報
〔参照(前半):
――何で歴史の転換点ばかりに、ちょっとずつ登場するかと言えば…
「鍋島夏雲日記」という“幕末の記録”を残しているからです。
この日記は「明治維新150周年記念事業」として活字化もされて、上峰町内の学校に配布されたとか。
…私も見たいです。上峰町民の皆様、この書籍を大切になさってください。
――コツコツと歴史的に価値ある情報を記録しておられたのですね。
おかげで“本編”では「几帳面な方」というキャラクター設定になってしまいました。
しかも、あのフェートン号事件が1808年で、鍋島夏雲は1802年生まれです。
“本編”で言えば、第1話よりも前に誕生し、第13話では50代ということに。それだけ長く、激動の時代を見てきている方です。
――私の調べでは、人物像がいまいち掴めていないのですが…
あるテレビ番組で、歴史学者の磯田道史さんが幕末期の古文書調査を振り返っていたとき。
「最初から佐賀に行けば良かった。すべての情報が集まっていた」旨の発言があったと記憶します。
この記憶と“鍋島夏雲”という人物をつなげて見ると「情報収集に長けた佐賀藩」のイメージが浮かびます。
「鍋島夏雲日記」も、自ら積極的に収集した情報だとすれば…
――実像は、几帳面な“書記官”のイメージと全く異なるかもしれません。
スパイ映画ならば“諜報機関の長官”、娯楽時代劇ならば“御庭番衆の御頭(おかしら)”みたいな…描き方もできそうに思います。
「幕末佐賀藩と、情報戦(インテリジェンス)」…
上峰町民の皆様へのつぶやき、やや空想の域を出ない内容も含まれましたが、面白いと共感いただける方がいれば幸いです。
2020年09月08日
第13話「通商条約」⑬(豪腕、唸〔うな〕る)
こんばんは。
超大型だった台風10号、さすがに無傷とは行かないようですね。九州の各地で大暴れし、ダメージを残したことが報じられています。
皆様が充分に備えたからこそ、被害は最小限に抑えられたのだと思います。私には、それも“佐賀の強さ”に見えるわけです。
今回が、第13話「通商条約」の最終投稿です。“全国の情勢”の描き方は少し工夫せねば…と考えさせられました。
――幕政のトップである老中首座・堀田正睦が、京の都に出向く。
朝廷の意思決定に関わる、有力な公家を味方に付けるためである。
「異国は嫌どすなぁ。」
最初から拒絶反応を示す公家たち。堀田が自ら、通商の価値を説いた。
「メリケン(アメリカ)は強国にて、文明も進んでおります。」
そして、ハリスとの交渉役・岩瀬も言葉を続ける。
「交易すれば、我が国にも利益をもたらしましょう。」
――しかし、公家たちの返事は“開明派の2人”の想像を遥かに超えた。
「メリケン(アメリカ)とは何でっしゃろ…バテレン(宣教師)どすか?」
「交易?…商人(あきんど)のことなど、わからしまへん。」
江戸時代を通じて、政治や経済から遠ざけられてきた、京の公家。
しっかりと“世界”が見えている、堀田や岩瀬の話は通じなかった。
「かくなるうえは、ご助力だけでもいただこう!」
老中首座・堀田は方針を転換する。条約締結への朝廷のお墨付き・“勅許”さえあれば、話は進むのである。
――だが、公家たちには“攘夷派”から、手が回っていた。
「“水戸はん”から江戸(幕府)の“口車”には気を付けや…と聞きますもんでな。」
この言葉に驚愕する、堀田正睦。
「お引き取りあれ。」
冷たい言葉を放つ公家たち。
ここで水戸藩・徳川斉昭からの“逆襲”が待っていたのである。
「いかんぞ!かくなるうえは…」
堀田は“工作資金”を使い、味方を増やす策に出た。
しかし、これも幕府への“不信感”を増大させた。

――慌ただしさを増していく京都。情勢は“国学”で得た人脈で、副島種臣にも伝わっていた。
「もはや公儀(幕府)が国を束ねるより、あるべき姿に戻すべき時節であろう。」
「枝吉はん、いかがなさいますのや?」
この頃、副島種臣(枝吉次郎)は、公家だけでなく、尊王活動家との付き合いを広げていた。
「一度、佐賀に立ち戻り、建白すべき事柄を整える。」
副島は自身が練った案を兄・枝吉神陽に相談するつもりだった。
――幕府を廃して、天皇が直接政治を行い、諸侯が集う…
副島の案は、将軍から朝廷への政権返上である“大政奉還”の原型とも言える。
のちに明治新政府の組織づくりを先導し、その“方向性”を定める副島種臣。
この時、西洋の学問は未習だが“新国家”のあるべき姿は早々と考えていた。
「いざ、佐賀へ戻らん!兄上、この次郎に力をお貸しください!」
一方で“枝吉神陽の弟”から抜けきれないのも、当時の副島種臣であった。

――京の都で、打つ手が無くなった、堀田正睦は失脚する。
幕府にとって厳しい局面で、臨時の役職である“大老”に就任したのが、彦根藩主・井伊直弼である。
井伊には期するところがあった。
もともと幕府が条約を結ぶのに、朝廷の許諾は不要なのである。
「堀田どのは、悪手を打ったのみ…」
手元に置いた囲碁の盤を見つめて、井伊は決断する。
「もはや後手に回っては勝てぬのだ!」
――井伊直弼は“朝廷の勅許なし”で「日米修好通商条約」の締結に踏み切った。
大老として“豪腕”を振るい始めた井伊直弼。
江戸の彦根藩邸に、ある人物を招いた。
「まずは異国に負けぬため、“通商”により国を富ませる!」
「然るのち、異国が横暴をはたらけぬよう、武備をさらに整える!…という事だ。」
ひとしきり熱く想いを語った井伊に、ある人物が言葉を返す。
「良きお考えにございますな。」
「随分と惚(とぼ)けた申し様じゃな。鍋島肥前…其方(そなた)が、既に進めておる事ではないか。」
――再び、強い幕府で国を束ねる。それが井伊の決意。頼れる“味方”が必要だった。
「あらためて申す。肥前(直正)の“先見の明”には、つねづね感服しておった。」
「勿体(もったい)なきお言葉。井伊さまには、折り入ってお話ししたき儀もござる。」
鍋島直正にも期するところがあった。
開国は良いのだが、異国が秩序を乱せば、抑えねばならない。
「相分かった。我らの想いは近いところにある。鍋島肥前、頼りにしておるぞ。」
幕閣のエリートである井伊直弼が信頼した外様大名。それが佐賀の鍋島直正だったのである。
(第14話「遣米使節」に続く)
超大型だった台風10号、さすがに無傷とは行かないようですね。九州の各地で大暴れし、ダメージを残したことが報じられています。
皆様が充分に備えたからこそ、被害は最小限に抑えられたのだと思います。私には、それも“佐賀の強さ”に見えるわけです。
今回が、第13話「通商条約」の最終投稿です。“全国の情勢”の描き方は少し工夫せねば…と考えさせられました。
――幕政のトップである老中首座・堀田正睦が、京の都に出向く。
朝廷の意思決定に関わる、有力な公家を味方に付けるためである。
「異国は嫌どすなぁ。」
最初から拒絶反応を示す公家たち。堀田が自ら、通商の価値を説いた。
「メリケン(アメリカ)は強国にて、文明も進んでおります。」
そして、ハリスとの交渉役・岩瀬も言葉を続ける。
「交易すれば、我が国にも利益をもたらしましょう。」
――しかし、公家たちの返事は“開明派の2人”の想像を遥かに超えた。
「メリケン(アメリカ)とは何でっしゃろ…バテレン(宣教師)どすか?」
「交易?…商人(あきんど)のことなど、わからしまへん。」
江戸時代を通じて、政治や経済から遠ざけられてきた、京の公家。
しっかりと“世界”が見えている、堀田や岩瀬の話は通じなかった。
「かくなるうえは、ご助力だけでもいただこう!」
老中首座・堀田は方針を転換する。条約締結への朝廷のお墨付き・“勅許”さえあれば、話は進むのである。
――だが、公家たちには“攘夷派”から、手が回っていた。
「“水戸はん”から江戸(幕府)の“口車”には気を付けや…と聞きますもんでな。」
この言葉に驚愕する、堀田正睦。
「お引き取りあれ。」
冷たい言葉を放つ公家たち。
ここで水戸藩・徳川斉昭からの“逆襲”が待っていたのである。
「いかんぞ!かくなるうえは…」
堀田は“工作資金”を使い、味方を増やす策に出た。
しかし、これも幕府への“不信感”を増大させた。
――慌ただしさを増していく京都。情勢は“国学”で得た人脈で、副島種臣にも伝わっていた。
「もはや公儀(幕府)が国を束ねるより、あるべき姿に戻すべき時節であろう。」
「枝吉はん、いかがなさいますのや?」
この頃、副島種臣(枝吉次郎)は、公家だけでなく、尊王活動家との付き合いを広げていた。
「一度、佐賀に立ち戻り、建白すべき事柄を整える。」
副島は自身が練った案を兄・枝吉神陽に相談するつもりだった。
――幕府を廃して、天皇が直接政治を行い、諸侯が集う…
副島の案は、将軍から朝廷への政権返上である“大政奉還”の原型とも言える。
のちに明治新政府の組織づくりを先導し、その“方向性”を定める副島種臣。
この時、西洋の学問は未習だが“新国家”のあるべき姿は早々と考えていた。
「いざ、佐賀へ戻らん!兄上、この次郎に力をお貸しください!」
一方で“枝吉神陽の弟”から抜けきれないのも、当時の副島種臣であった。
――京の都で、打つ手が無くなった、堀田正睦は失脚する。
幕府にとって厳しい局面で、臨時の役職である“大老”に就任したのが、彦根藩主・井伊直弼である。
井伊には期するところがあった。
もともと幕府が条約を結ぶのに、朝廷の許諾は不要なのである。
「堀田どのは、悪手を打ったのみ…」
手元に置いた囲碁の盤を見つめて、井伊は決断する。
「もはや後手に回っては勝てぬのだ!」
――井伊直弼は“朝廷の勅許なし”で「日米修好通商条約」の締結に踏み切った。
大老として“豪腕”を振るい始めた井伊直弼。
江戸の彦根藩邸に、ある人物を招いた。
「まずは異国に負けぬため、“通商”により国を富ませる!」
「然るのち、異国が横暴をはたらけぬよう、武備をさらに整える!…という事だ。」
ひとしきり熱く想いを語った井伊に、ある人物が言葉を返す。
「良きお考えにございますな。」
「随分と惚(とぼ)けた申し様じゃな。鍋島肥前…其方(そなた)が、既に進めておる事ではないか。」
――再び、強い幕府で国を束ねる。それが井伊の決意。頼れる“味方”が必要だった。
「あらためて申す。肥前(直正)の“先見の明”には、つねづね感服しておった。」
「勿体(もったい)なきお言葉。井伊さまには、折り入ってお話ししたき儀もござる。」
鍋島直正にも期するところがあった。
開国は良いのだが、異国が秩序を乱せば、抑えねばならない。
「相分かった。我らの想いは近いところにある。鍋島肥前、頼りにしておるぞ。」
幕閣のエリートである井伊直弼が信頼した外様大名。それが佐賀の鍋島直正だったのである。
(第14話「遣米使節」に続く)
2020年09月06日
第13話「通商条約」⑫(禁断の一手)
こんばんは。
台風10号…遠方からモヤモヤした気持ちで、九州各地の映像を見ています。
皆様のブログを拝見すると、最大級の警戒と準備をなさっているご様子。もはや「人事を尽くして天命を待つ」という心境なのでしょうか。
今夜から明朝、台風がどう影響するか…非常に心配なところです。明日以降に皆様が、この投稿をゆっくりご覧いただける状況であることを切に願います。
――老中・阿部正弘の抑えがなくなり、水戸藩・徳川斉昭が動き出した。
「通商など論外じゃ!富が異国に持ち去られるだけよ!」
“水戸さま”は、次々に歯切れのよい攘夷論を繰り出す。
大名から下級武士まで、熱狂する者は多数。
海外事情に通じる幕政のトップ・堀田正睦から見れば、異国に攻撃的な“水戸さま”の意見は危険極まりない。
「この国は取り残されるばかり…かくなるうえは!」
――堀田は、老中首座の強権を発動し、徳川斉昭を幕政から遠ざける。
「おのれ!堀田。」
“逆襲”を画策する徳川斉昭。
水戸藩はかねてから、尊王論の中心でもある。
“攘夷”を期待する、京都の公家たちとの連携を強めていく。

――その頃、堀田は、アメリカ総領事・ハリスと交渉を進めている、幕府の役人・岩瀬を呼び出した。
「条約の骨子は固まったか。」
「はい、幾度も手直しを経て、概ねは決まり申した。」
交渉役の岩瀬忠震(ただなり)は、ハリスの提示した条約案に、真っ黒になるまで書き込みを入れ、修正した。
“和親条約”のときと同様、アメリカと真っ当な外交交渉が出来ていたのである。
ハリスは、このように語ったそうだ。
「日本の国民は、岩瀬のような“外交官”を持って幸せである」と。
――幕府が締結した“不平等条約”と語られる、日米修好通商条約だが、諸外国との力の差を考慮すると健闘したとの見方もある。
不平等な部分と言えば「領事裁判権を認め、関税自主権が無い」のだが、これは幕府が交渉を失敗したというより、当時の日本が“近代国家”として体を成していなかったことに起因するようである。
江戸時代の刑罰で裁かれたくない外国人の心情、200年以上続いた“鎖国”による貿易体制の不備…なども考慮すべきかもしれない。
のちの明治期には、“外交”では副島種臣、“法律”では江藤新平、“財政”では大隈重信、“教育”では大木喬任など…佐賀藩士たちは、近代国家を築き、欧米との差を埋めるべく奮闘することになる。
――交渉役・岩瀬の報告を受け、老中首座・堀田は「うむ!よくやってくれた。」と頷(うなづ)く。
「早急に、調印の手筈(てはず)を整えねばならぬ。」
「水戸さまが“否”と仰せになるかと。説き伏せるには、いかがなさいますか。」
「岩瀬よ。儂は、ある“手立て”に思い至った。」
堀田の考える“秘策”。それは朝廷から条約締結の勅許を得ることである。
“尊王”の志が高い、水戸藩。
水戸が崇敬する「朝廷の承諾」があれば、徳川斉昭も説得できる…はずというのが、堀田の考えである。

――江戸時代を通じて、静かだった京の都。
幕府や諸藩は、「朝廷の権威」を政治的に利用しようと動き始めていた。朝廷に仕える公家たちにも、接触を試みるようになったのである。
「枝吉はん。近頃、公儀(幕府)の者をよく見かけますのや。」
「漸く(ようやく)、時節が参ったということですね…」
ここ数年、副島種臣(枝吉次郎)は、京で国学を学んできた。
国学は日本古来の思想を探求することから、“尊王論”と強く結び付くのである。
――公家たちも、俄(にわ)かに騒がしくなる京(みやこ)に戸惑いを見せる。
「もはや動くべき時が近い。兄上にも、ご相談をせねば…」
副島種臣(枝吉次郎)は、佐賀にいる兄・枝吉神陽に手紙を書き送る。
副島の想いは「朝廷の政治利用」ではない。天皇のもとに徳川を含めた諸大名が集う「新しい国の形」にまで進んでいる。
アメリカとの通商条約の交渉が大詰めを迎える中、京都の朝廷は急激に存在感を増していた。
そして、老中首座・堀田が朝廷への工作を試みたことは、幕府にとって“禁断の一手”だったのである。
(続く)
台風10号…遠方からモヤモヤした気持ちで、九州各地の映像を見ています。
皆様のブログを拝見すると、最大級の警戒と準備をなさっているご様子。もはや「人事を尽くして天命を待つ」という心境なのでしょうか。
今夜から明朝、台風がどう影響するか…非常に心配なところです。明日以降に皆様が、この投稿をゆっくりご覧いただける状況であることを切に願います。
――老中・阿部正弘の抑えがなくなり、水戸藩・徳川斉昭が動き出した。
「通商など論外じゃ!富が異国に持ち去られるだけよ!」
“水戸さま”は、次々に歯切れのよい攘夷論を繰り出す。
大名から下級武士まで、熱狂する者は多数。
海外事情に通じる幕政のトップ・堀田正睦から見れば、異国に攻撃的な“水戸さま”の意見は危険極まりない。
「この国は取り残されるばかり…かくなるうえは!」
――堀田は、老中首座の強権を発動し、徳川斉昭を幕政から遠ざける。
「おのれ!堀田。」
“逆襲”を画策する徳川斉昭。
水戸藩はかねてから、尊王論の中心でもある。
“攘夷”を期待する、京都の公家たちとの連携を強めていく。
――その頃、堀田は、アメリカ総領事・ハリスと交渉を進めている、幕府の役人・岩瀬を呼び出した。
「条約の骨子は固まったか。」
「はい、幾度も手直しを経て、概ねは決まり申した。」
交渉役の岩瀬忠震(ただなり)は、ハリスの提示した条約案に、真っ黒になるまで書き込みを入れ、修正した。
“和親条約”のときと同様、アメリカと真っ当な外交交渉が出来ていたのである。
ハリスは、このように語ったそうだ。
「日本の国民は、岩瀬のような“外交官”を持って幸せである」と。
――幕府が締結した“不平等条約”と語られる、日米修好通商条約だが、諸外国との力の差を考慮すると健闘したとの見方もある。
不平等な部分と言えば「領事裁判権を認め、関税自主権が無い」のだが、これは幕府が交渉を失敗したというより、当時の日本が“近代国家”として体を成していなかったことに起因するようである。
江戸時代の刑罰で裁かれたくない外国人の心情、200年以上続いた“鎖国”による貿易体制の不備…なども考慮すべきかもしれない。
のちの明治期には、“外交”では副島種臣、“法律”では江藤新平、“財政”では大隈重信、“教育”では大木喬任など…佐賀藩士たちは、近代国家を築き、欧米との差を埋めるべく奮闘することになる。
――交渉役・岩瀬の報告を受け、老中首座・堀田は「うむ!よくやってくれた。」と頷(うなづ)く。
「早急に、調印の手筈(てはず)を整えねばならぬ。」
「水戸さまが“否”と仰せになるかと。説き伏せるには、いかがなさいますか。」
「岩瀬よ。儂は、ある“手立て”に思い至った。」
堀田の考える“秘策”。それは朝廷から条約締結の勅許を得ることである。
“尊王”の志が高い、水戸藩。
水戸が崇敬する「朝廷の承諾」があれば、徳川斉昭も説得できる…はずというのが、堀田の考えである。
――江戸時代を通じて、静かだった京の都。
幕府や諸藩は、「朝廷の権威」を政治的に利用しようと動き始めていた。朝廷に仕える公家たちにも、接触を試みるようになったのである。
「枝吉はん。近頃、公儀(幕府)の者をよく見かけますのや。」
「漸く(ようやく)、時節が参ったということですね…」
ここ数年、副島種臣(枝吉次郎)は、京で国学を学んできた。
国学は日本古来の思想を探求することから、“尊王論”と強く結び付くのである。
――公家たちも、俄(にわ)かに騒がしくなる京(みやこ)に戸惑いを見せる。
「もはや動くべき時が近い。兄上にも、ご相談をせねば…」
副島種臣(枝吉次郎)は、佐賀にいる兄・枝吉神陽に手紙を書き送る。
副島の想いは「朝廷の政治利用」ではない。天皇のもとに徳川を含めた諸大名が集う「新しい国の形」にまで進んでいる。
アメリカとの通商条約の交渉が大詰めを迎える中、京都の朝廷は急激に存在感を増していた。
そして、老中首座・堀田が朝廷への工作を試みたことは、幕府にとって“禁断の一手”だったのである。
(続く)
2020年09月04日
「歴史からの警鐘」
こんばんは。
また台風の接近…今度の台風10号はさらに巨大である様子。気になって仕方ないので、しばらく“本編”を休んで様子を見守ります。
“本編”の掲載年代は1808年から始まりました。もうすぐ1858年の日米修好通商条約の締結に触れる予定です。
幕末の佐賀について、半端な調べと拙い文章ではありますが、足かけ50年分を書いてみたことになります。
――この間に“猛烈な台風”に分類される風水害もありました。
いま考えたくない話なのですが、1828年のいわゆる“シーボルト台風”です。
殿・鍋島直正が、佐賀藩主に就任する2年前の話です。
この台風は、福岡の久留米藩や長崎の大村藩にも甚大な被害をもたらしました。そして、最大級のダメージを受けたのは佐賀藩でした。
――本日、とくに強調したいのは…
真面目な佐賀藩士・領民の伝統を受け継ぐ皆様。
今回の台風は、極めて危険のようです。
暴風雨が強まった際、持ち前の責任感で見回りなどなされませぬよう…

――そして、まるでNHKみたいなことを言います。
早めの対策を講じた後は「ご自身とご家族の命」を守ることに専念していただきたい…と考えます。
当ブログで「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを書き連ねるうちに、もはや遠い故郷だったはずの佐賀をすっかり身近に感じます。
こうして台風の予報円が、佐賀に近づくと「来るな!去れ!!」と強く念じるわけです。
…皆様も、くれぐれもご無事で。
また台風の接近…今度の台風10号はさらに巨大である様子。気になって仕方ないので、しばらく“本編”を休んで様子を見守ります。
“本編”の掲載年代は1808年から始まりました。もうすぐ1858年の日米修好通商条約の締結に触れる予定です。
幕末の佐賀について、半端な調べと拙い文章ではありますが、足かけ50年分を書いてみたことになります。
――この間に“猛烈な台風”に分類される風水害もありました。
いま考えたくない話なのですが、1828年のいわゆる“シーボルト台風”です。
殿・鍋島直正が、佐賀藩主に就任する2年前の話です。
この台風は、福岡の久留米藩や長崎の大村藩にも甚大な被害をもたらしました。そして、最大級のダメージを受けたのは佐賀藩でした。
――本日、とくに強調したいのは…
真面目な佐賀藩士・領民の伝統を受け継ぐ皆様。
今回の台風は、極めて危険のようです。
暴風雨が強まった際、持ち前の責任感で見回りなどなされませぬよう…
――そして、まるでNHKみたいなことを言います。
早めの対策を講じた後は「ご自身とご家族の命」を守ることに専念していただきたい…と考えます。
当ブログで「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを書き連ねるうちに、もはや遠い故郷だったはずの佐賀をすっかり身近に感じます。
こうして台風の予報円が、佐賀に近づくと「来るな!去れ!!」と強く念じるわけです。
…皆様も、くれぐれもご無事で。
2020年09月02日
第13話「通商条約」⑪(名君たちの“未来”)
こんばんは。
前回は、老中・阿部正弘の急逝の一報が届いた様子を描きました。原因については諸説あるようで、有力な説の1つが、幕政の中心で働き詰めだったことによる…いわゆる“過労死”だそうです。
英明と評判の一橋慶喜を将軍として、有力な諸大名が幕府のもとに集まる。これが“一橋派”の目指す新しい国家の姿でした。
“一橋派”に好意的だった老中・阿部正弘。その援護を期待していた、“一橋派”にとっては大打撃です。そんな中、派閥の主軸の1人である薩摩(鹿児島)の島津斉彬が、鍋島直正に声をかけます。
――当時、薩摩藩も島津斉彬のもと、科学技術の振興に力を入れていた。
「肥前どの。何かと気忙しき折だが、幼き頃の如く、ゆるりと話をしたいものだ。」
斉彬は、遠い昔を見遣るような目をした。
この2人、ともに母は、鳥取藩・池田家の姫君。
戦国からの武勇で知られる家系でつながった“母方のいとこ”なのである。
「聡明なる薩摩さまには、様々なことをお教えいただいた。」
子供の頃は“貞丸”という名で、好奇心旺盛な若君だった、直正。

――島津斉彬は“年上のいとこ”である。幼い頃は、母方のつながりで一緒に遊んだりしている。
西洋の文物にも詳しい斉彬は、直正にも影響を与えたのだ。
「いまや肥前(直正)から教わることも多い。おかげで、“炉”も用を成しておる。」
「それは、良うございました。」
この頃、薩摩の反射炉は、佐賀に続く2番手で実用化されていた。少しとぼけて答えているが、その影には直正の動きがある。
――佐賀が翻訳した“虎の巻”(技術書)の提供など、薩摩には協力を行っていたようだ。
「“西洋人も…佐賀人も同じ人間だ!お主らにも出来ぬはずが無い!”…と。家来たちには、随分な無理を申した。」
島津斉彬が、苦笑しながら語る。
当時、佐賀には“精錬方”という理化学の研究所があるが、薩摩では“集成館”という西洋式の工場の事業を進めていた。
「いや…大船建造など、ぜひ薩摩から学びたいと思うております。」
そう言うと、鍋島直正は、少し真剣な表情に戻った。
造船においては、薩摩に一日の長があるようだ。薩摩は琉球(沖縄)付近で、事実上の対外貿易を行っている。外洋航海にも慣れているのだ。
――このように幕末の近代化は、佐賀と薩摩の“いとこ”同士で競い合って牽引していた。
「そうだ!薩摩の“紅びいどろ”も、ご覧に入れたい。」
島津斉彬には、人を惹きつける魅力がある。直正も、いつになく楽し気である。
この“紅びいどろ”は、赤の色味が映えるガラス工芸品“薩摩切子”へと発展した。
「“吉之助”に、肥前の屋敷へ持たせても良いが…いかん、あの男、いま江戸におらぬな。」
この頃、斉彬は、西郷吉之助という側近を伝令役として方々に走らせていた。薩摩の殿による御遣い(おつかい)にも、随分と遠方のものがあるらしい。

――この斉彬の側近・吉之助が、のちに西郷隆盛である。大柄のわりに、よく小回りの効く者であった。
「薩摩さま、御自慢の“紅びいどろ”なれば、ご一緒に見とうございますな。」
鍋島直正、斉彬とゆっくり話をする機会を持ちたい様子だ。
「肥前どの…嬉しいことを言う。」
「その際は、華麗な薩摩の品には及びませぬが、肥前の“びいどろ”(ガラス)もお持ちしましょう。」
とくに火薬などの調合には“化学実験”が重要なため、佐賀藩でもビーカーやフラスコなどガラス加工品を製造していた。
――その伝統は、佐賀の“肥前びいどろ”として、現代にも続く。
「楽しみなことだ。」
斉彬は、愉快そうに笑った。
「ご壮健な様子で、安堵いたしました。必ずや、お伺いいたしましょう。」
直正は、斉彬との再会を約束した。
地道な調整で、幕府や諸大名をまとめ上げた老中・阿部正弘はもういない。
しかし、直正は、ともに日本の近代化を進めて、国を守る“同志”がいることに、心強い想いをしたのである。
(続く)
前回は、老中・阿部正弘の急逝の一報が届いた様子を描きました。原因については諸説あるようで、有力な説の1つが、幕政の中心で働き詰めだったことによる…いわゆる“過労死”だそうです。
英明と評判の一橋慶喜を将軍として、有力な諸大名が幕府のもとに集まる。これが“一橋派”の目指す新しい国家の姿でした。
“一橋派”に好意的だった老中・阿部正弘。その援護を期待していた、“一橋派”にとっては大打撃です。そんな中、派閥の主軸の1人である薩摩(鹿児島)の島津斉彬が、鍋島直正に声をかけます。
――当時、薩摩藩も島津斉彬のもと、科学技術の振興に力を入れていた。
「肥前どの。何かと気忙しき折だが、幼き頃の如く、ゆるりと話をしたいものだ。」
斉彬は、遠い昔を見遣るような目をした。
この2人、ともに母は、鳥取藩・池田家の姫君。
戦国からの武勇で知られる家系でつながった“母方のいとこ”なのである。
「聡明なる薩摩さまには、様々なことをお教えいただいた。」
子供の頃は“貞丸”という名で、好奇心旺盛な若君だった、直正。
――島津斉彬は“年上のいとこ”である。幼い頃は、母方のつながりで一緒に遊んだりしている。
西洋の文物にも詳しい斉彬は、直正にも影響を与えたのだ。
「いまや肥前(直正)から教わることも多い。おかげで、“炉”も用を成しておる。」
「それは、良うございました。」
この頃、薩摩の反射炉は、佐賀に続く2番手で実用化されていた。少しとぼけて答えているが、その影には直正の動きがある。
――佐賀が翻訳した“虎の巻”(技術書)の提供など、薩摩には協力を行っていたようだ。
「“西洋人も…佐賀人も同じ人間だ!お主らにも出来ぬはずが無い!”…と。家来たちには、随分な無理を申した。」
島津斉彬が、苦笑しながら語る。
当時、佐賀には“精錬方”という理化学の研究所があるが、薩摩では“集成館”という西洋式の工場の事業を進めていた。
「いや…大船建造など、ぜひ薩摩から学びたいと思うております。」
そう言うと、鍋島直正は、少し真剣な表情に戻った。
造船においては、薩摩に一日の長があるようだ。薩摩は琉球(沖縄)付近で、事実上の対外貿易を行っている。外洋航海にも慣れているのだ。
――このように幕末の近代化は、佐賀と薩摩の“いとこ”同士で競い合って牽引していた。
「そうだ!薩摩の“紅びいどろ”も、ご覧に入れたい。」
島津斉彬には、人を惹きつける魅力がある。直正も、いつになく楽し気である。
この“紅びいどろ”は、赤の色味が映えるガラス工芸品“薩摩切子”へと発展した。
「“吉之助”に、肥前の屋敷へ持たせても良いが…いかん、あの男、いま江戸におらぬな。」
この頃、斉彬は、西郷吉之助という側近を伝令役として方々に走らせていた。薩摩の殿による御遣い(おつかい)にも、随分と遠方のものがあるらしい。

――この斉彬の側近・吉之助が、のちに西郷隆盛である。大柄のわりに、よく小回りの効く者であった。
「薩摩さま、御自慢の“紅びいどろ”なれば、ご一緒に見とうございますな。」
鍋島直正、斉彬とゆっくり話をする機会を持ちたい様子だ。
「肥前どの…嬉しいことを言う。」
「その際は、華麗な薩摩の品には及びませぬが、肥前の“びいどろ”(ガラス)もお持ちしましょう。」
とくに火薬などの調合には“化学実験”が重要なため、佐賀藩でもビーカーやフラスコなどガラス加工品を製造していた。
――その伝統は、佐賀の“肥前びいどろ”として、現代にも続く。
「楽しみなことだ。」
斉彬は、愉快そうに笑った。
「ご壮健な様子で、安堵いたしました。必ずや、お伺いいたしましょう。」
直正は、斉彬との再会を約束した。
地道な調整で、幕府や諸大名をまとめ上げた老中・阿部正弘はもういない。
しかし、直正は、ともに日本の近代化を進めて、国を守る“同志”がいることに、心強い想いをしたのである。
(続く)