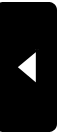2020年08月15日
「“湖東焼”ミステリー(滋賀県)」
こんにちは。
例年とは違ったお盆で、色々と大変な方も多いのではないでしょうか。
現在、本編の第13話「通商条約」を更新中です。調べながら書いていることもありますが、全国の大名が出てくるお話は表現が難しいです。
〔参照:第13話「通商条約」①(影の“内閣”)〕
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”。
今までは、佐賀・長崎・江戸でほとんどの内容が進んで来ました。
――話が進むにつれて、関わる地域も増えていきます。
佐賀県内のみならず、全国各地との繋がりを探って、今後に活かせないか…と思うようになりました。
ところで第13話の2本目で「井伊直弼が“鍋島焼”を見て、佐賀や鍋島直正について考える…」という投稿をしています。
〔参照:第13話「通商条約」②(埋木に陽が当たるとき)〕
――井伊家と言えば、現在の滋賀県にある彦根藩主。
有名な“ゆるキャラ”である「ひこにゃん」をご存じの方も多いでしょう。
補足ですが“井伊の赤備え”と称される甲冑にあわせた、赤い兜をかぶっている白ネコのキャラクターです。
江戸初期に井伊家のお殿様が、雷を避けられるよう、手招きをした猫が居たらしく…そのネコがモデルとして採用されたようです。
――さて、先ほどのお話です。ときの彦根藩主・井伊直弼に陶磁器を見る目があったか…
井伊直弼は茶の湯に詳しい文化人であるうえに、彦根藩は“陶磁器”に凄く熱心だったのです。
彦根は滋賀県東部にある、琵琶湖に面した街。
母なる湖・琵琶湖の東岸で作られていたのは…
“湖東焼”と呼ばれる、磁器を中心とした幻の“焼き物”。

――なぜ、幻かと言えば“湖東焼”の流れが150年ほど前に途絶えたからです。
井伊直弼の時代が、彦根の磁器製造のピークだったようです。
幕末の政局はやがて抗争となり、動乱は激しさを増します。全国各地で起きる壮絶な“つぶし合い”。
日本国内での戦いを避けたい、佐賀藩には厳しい状況が続くことになります。
歴史に詳しい方は予測できると思いますが、彦根藩は焼き物の生産に注力できなくなります。
現在の滋賀県内では、このとき失われた“湖東焼”を惜しみ、現代に甦らせようとの動きもあるようです。
――そもそも滋賀の焼き物“湖東焼”と、佐賀とは何の関係が…!?
もともと井伊直弼を調べていたときに、たまたま見つかった“湖東焼”の記述。
ここで、ようやく佐賀が出て来ます。
“伊万里”の職人が、彦根に招かれ、“湖東焼”の成立に関わったとありました。
――最近、私は“伊万里”に2つの意味があると知りました。
①佐賀・長崎を含む“肥前陶磁器”の代名詞。
②佐賀藩の機密事項、至高の献上品・鍋島焼。
…ここでの“伊万里”の意味は①だと考えています。「有田から来た“伊万里”の職人」と記述する情報も見られます。
もし②の「鍋島焼の職人」が彦根に派遣されたとしたら、“企業機密”を教えるほど、鍋島と井伊には深い関わりがあったことになります…
――ちなみに私には陶磁器を正しく語れる“審美眼”の持ち合わせがありません。
しかし、陶磁器の概要や経過を調べていくことはできそうです。
これを長崎での海外貿易や、幕末のパリ万博の話に活用すれば、国際情勢や商業活動の視点も入った話になるのでは…と考えます。
投稿を続けるにつれ、私には“作家”としての資質が乏しく、正面突破は難しいと痛感します。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」へのアプローチには、様々な方法を取りうると思います。その中で、現在の佐賀県が強くなるヒントでも見つかれば幸いです。
例年とは違ったお盆で、色々と大変な方も多いのではないでしょうか。
現在、本編の第13話「通商条約」を更新中です。調べながら書いていることもありますが、全国の大名が出てくるお話は表現が難しいです。
〔参照:
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”。
今までは、佐賀・長崎・江戸でほとんどの内容が進んで来ました。
――話が進むにつれて、関わる地域も増えていきます。
佐賀県内のみならず、全国各地との繋がりを探って、今後に活かせないか…と思うようになりました。
ところで第13話の2本目で「井伊直弼が“鍋島焼”を見て、佐賀や鍋島直正について考える…」という投稿をしています。
〔参照:
――井伊家と言えば、現在の滋賀県にある彦根藩主。
有名な“ゆるキャラ”である「ひこにゃん」をご存じの方も多いでしょう。
補足ですが“井伊の赤備え”と称される甲冑にあわせた、赤い兜をかぶっている白ネコのキャラクターです。
江戸初期に井伊家のお殿様が、雷を避けられるよう、手招きをした猫が居たらしく…そのネコがモデルとして採用されたようです。
――さて、先ほどのお話です。ときの彦根藩主・井伊直弼に陶磁器を見る目があったか…
井伊直弼は茶の湯に詳しい文化人であるうえに、彦根藩は“陶磁器”に凄く熱心だったのです。
彦根は滋賀県東部にある、琵琶湖に面した街。
母なる湖・琵琶湖の東岸で作られていたのは…
“湖東焼”と呼ばれる、磁器を中心とした幻の“焼き物”。
――なぜ、幻かと言えば“湖東焼”の流れが150年ほど前に途絶えたからです。
井伊直弼の時代が、彦根の磁器製造のピークだったようです。
幕末の政局はやがて抗争となり、動乱は激しさを増します。全国各地で起きる壮絶な“つぶし合い”。
日本国内での戦いを避けたい、佐賀藩には厳しい状況が続くことになります。
歴史に詳しい方は予測できると思いますが、彦根藩は焼き物の生産に注力できなくなります。
現在の滋賀県内では、このとき失われた“湖東焼”を惜しみ、現代に甦らせようとの動きもあるようです。
――そもそも滋賀の焼き物“湖東焼”と、佐賀とは何の関係が…!?
もともと井伊直弼を調べていたときに、たまたま見つかった“湖東焼”の記述。
ここで、ようやく佐賀が出て来ます。
“伊万里”の職人が、彦根に招かれ、“湖東焼”の成立に関わったとありました。
――最近、私は“伊万里”に2つの意味があると知りました。
①佐賀・長崎を含む“肥前陶磁器”の代名詞。
②佐賀藩の機密事項、至高の献上品・鍋島焼。
…ここでの“伊万里”の意味は①だと考えています。「有田から来た“伊万里”の職人」と記述する情報も見られます。
もし②の「鍋島焼の職人」が彦根に派遣されたとしたら、“企業機密”を教えるほど、鍋島と井伊には深い関わりがあったことになります…
――ちなみに私には陶磁器を正しく語れる“審美眼”の持ち合わせがありません。
しかし、陶磁器の概要や経過を調べていくことはできそうです。
これを長崎での海外貿易や、幕末のパリ万博の話に活用すれば、国際情勢や商業活動の視点も入った話になるのでは…と考えます。
投稿を続けるにつれ、私には“作家”としての資質が乏しく、正面突破は難しいと痛感します。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」へのアプローチには、様々な方法を取りうると思います。その中で、現在の佐賀県が強くなるヒントでも見つかれば幸いです。
2020年08月13日
第13話「通商条約」③(医者の言葉は聞いて)
こんばんは。
幕末の政局から、ひとまず話を佐賀に戻します。
今回、殿・鍋島直正の“執事”や“主治医”が再登場します。
“執事”と言える側近・古川与一(松根)は、幼少期からずっと殿の傍にいますので、本編でも序盤から登場しています。
そして“主治医”・大石良英の方は、今まで登場は1回だけだったかと思います。このときは若君・淳一郎(のちの鍋島直大)に“種痘”を施しました。
〔参考(中盤):第6話「鉄製大砲」⑦〕
藩医・大石は、現在のみやき町を治める“白石鍋島家”に属しましたが、蘭方(西洋医学)に長じていたので、“佐賀本藩”に登用されたようです。
――殿・直正は、佐賀の空を見上げて、ぼんやりとしていた。
「お貢(みつ)…息災にしておるかのう…」
直正の長女・貢姫は、17歳で川越藩(埼玉)に嫁いだ。
お相手は、姫と同い年の貴公子・松平直侯。
なぜ“貴公子”と呼んだかと言えば血統が良いのだ。
御三家・水戸藩の徳川斉昭の子であり、一橋慶喜の弟である。

――言い換えれば、“攘夷派”首領の子であり、将軍候補の弟。
川越藩主となった松平直侯の周囲には、色々と政治的な思惑がはたらく。
他家から来た“跡取り”には、強い期待もかかるだろう。
直正は、嫁入りした貢姫の心中を思う…
「貢(みつ)が気掛かりじゃ!文(ふみ)を書いて励ますとしよう。」
殿・直正、ここでは単なる心配性の父親である。
――幼少の頃からの側近・古川与一(松根)が柱の影から見守る。
「殿、貢姫さまへの文でござるな。定めしご心配でありましょう…」
毎度、誰より殿の気持ちを察する、よく出来た“執事”である。
ここで10年ほど前の話に触れておく。貢姫は7歳の頃に佐賀から江戸に移った。これは大名の正室として、通用する力を身に付けるための“留学”である。
殿・直正が“教育係”として頼ったのは、“将軍の娘”だった正室・盛姫。幕府への頼み事を、大奥の人脈で通すなど“ファーストレディ”としての存在感があった。
――しかし、貢姫が江戸に移ってからわずか2年、頼りになった正室・盛姫が急逝してしまう。
古川与一の回想は続いた…
「殿にはお辛いときだったが、貢姫さまがお支えくだされた…」
この頃の直正は学問に優れた側近を病で失うなど心痛が重なっていた。
江戸では「貢姫に会える」事が、直正の精神的な支えとなっていたのである。

――そして、成長した愛娘・貢姫が嫁いだ今、簡単には会いに行けない。父・鍋島直正は手紙を書き送って、繋がりを保つのであった。
幕末の殿様には強いストレスがかかる。“心の支え”が弱まることは健康面にも影響を及ぼす。
そんなある日、直正の主治医、大石良英が問診をしている。
「殿、お身体の加減はいかかでしょうか。」
「近頃、胃の腑(ふ)に軽い痛みを感じるのう…」
「ほう、先だってもお伺いしました。未だ治まりませぬか。」
異国の動きを睨みながら、佐賀の技術開発、産業振興を進める、直正。最近では、佐賀の力を認める幕府や雄藩に注目され、幕末の政局にも巻き込まれがちである。
――西洋の事情が良く見えている、直正。いつも、気が急いていた。
「殿、あのように食事を早く召し上がられては、胃に堪えるは道理にございます。」
藩医・大石良英、けっこう言葉が厳しい。
言うなれば、ホームドクターが、“早食い”を戒めているのだ。
「…して、いかがすれば良いか。」
何やら、主治医に叱られている感じの殿様。
「ゆっくり、しっかり噛むのです!」
藩医・大石は全力で、普通の事を言った。
「…心得た。」
“普通の事”を普通に行うのは、意外と難しいのである。
(続く)
幕末の政局から、ひとまず話を佐賀に戻します。
今回、殿・鍋島直正の“執事”や“主治医”が再登場します。
“執事”と言える側近・古川与一(松根)は、幼少期からずっと殿の傍にいますので、本編でも序盤から登場しています。
そして“主治医”・大石良英の方は、今まで登場は1回だけだったかと思います。このときは若君・淳一郎(のちの鍋島直大)に“種痘”を施しました。
〔参考(中盤):
藩医・大石は、現在のみやき町を治める“白石鍋島家”に属しましたが、蘭方(西洋医学)に長じていたので、“佐賀本藩”に登用されたようです。
――殿・直正は、佐賀の空を見上げて、ぼんやりとしていた。
「お貢(みつ)…息災にしておるかのう…」
直正の長女・貢姫は、17歳で川越藩(埼玉)に嫁いだ。
お相手は、姫と同い年の貴公子・松平直侯。
なぜ“貴公子”と呼んだかと言えば血統が良いのだ。
御三家・水戸藩の徳川斉昭の子であり、一橋慶喜の弟である。

――言い換えれば、“攘夷派”首領の子であり、将軍候補の弟。
川越藩主となった松平直侯の周囲には、色々と政治的な思惑がはたらく。
他家から来た“跡取り”には、強い期待もかかるだろう。
直正は、嫁入りした貢姫の心中を思う…
「貢(みつ)が気掛かりじゃ!文(ふみ)を書いて励ますとしよう。」
殿・直正、ここでは単なる心配性の父親である。
――幼少の頃からの側近・古川与一(松根)が柱の影から見守る。
「殿、貢姫さまへの文でござるな。定めしご心配でありましょう…」
毎度、誰より殿の気持ちを察する、よく出来た“執事”である。
ここで10年ほど前の話に触れておく。貢姫は7歳の頃に佐賀から江戸に移った。これは大名の正室として、通用する力を身に付けるための“留学”である。
殿・直正が“教育係”として頼ったのは、“将軍の娘”だった正室・盛姫。幕府への頼み事を、大奥の人脈で通すなど“ファーストレディ”としての存在感があった。
――しかし、貢姫が江戸に移ってからわずか2年、頼りになった正室・盛姫が急逝してしまう。
古川与一の回想は続いた…
「殿にはお辛いときだったが、貢姫さまがお支えくだされた…」
この頃の直正は学問に優れた側近を病で失うなど心痛が重なっていた。
江戸では「貢姫に会える」事が、直正の精神的な支えとなっていたのである。

――そして、成長した愛娘・貢姫が嫁いだ今、簡単には会いに行けない。父・鍋島直正は手紙を書き送って、繋がりを保つのであった。
幕末の殿様には強いストレスがかかる。“心の支え”が弱まることは健康面にも影響を及ぼす。
そんなある日、直正の主治医、大石良英が問診をしている。
「殿、お身体の加減はいかかでしょうか。」
「近頃、胃の腑(ふ)に軽い痛みを感じるのう…」
「ほう、先だってもお伺いしました。未だ治まりませぬか。」
異国の動きを睨みながら、佐賀の技術開発、産業振興を進める、直正。最近では、佐賀の力を認める幕府や雄藩に注目され、幕末の政局にも巻き込まれがちである。
――西洋の事情が良く見えている、直正。いつも、気が急いていた。
「殿、あのように食事を早く召し上がられては、胃に堪えるは道理にございます。」
藩医・大石良英、けっこう言葉が厳しい。
言うなれば、ホームドクターが、“早食い”を戒めているのだ。
「…して、いかがすれば良いか。」
何やら、主治医に叱られている感じの殿様。
「ゆっくり、しっかり噛むのです!」
藩医・大石は全力で、普通の事を言った。
「…心得た。」
“普通の事”を普通に行うのは、意外と難しいのである。
(続く)
2020年08月12日
第13話「通商条約」②(埋木に陽が当たるとき)
こんばんは。
前回より幕末の政局を中心としてお話を進めています。「誰が次期(14代)将軍になるのか?」がメインテーマです。
佐賀藩士たちを描く方が楽しいのですが、「一橋派」と「南紀派」の対立は重要なポイントなので頑張って続けます。
前回投稿で「影の“内閣”」に例えて登場したのが「一橋派」。
老中・阿部正弘の方針で、政治参加を進める雄藩の代表たちです。
今回紹介するのは、「南紀派」のリーダー格・井伊直弼。
この派閥は幕府政治を主導していた譜代大名たちが中心です。
――江戸の彦根藩邸。近江(滋賀)にある彦根を治める、井伊家の屋敷。
井伊と言えば、江戸幕府の創始者・徳川家康のもとで戦った“徳川四天王”の名門。当代の藩主は井伊直弼であった。
「主膳よ。ようやっと儂はここまで来たのだな。」
「はっ。やはり天は、殿を埋もれさせては置きませんでしたな。」
――井伊直弼が話している相手は、彦根藩士・長野主膳という。直弼の側近である。
「剣の腕を磨き、茶を嗜み、禅を行じてきた…」
直弼は、先々代の藩主の子であるが、家督を継ぐ可能性は低い立場にいた。
こうして彦根城下で、鬱屈とした青年期を過ごした、井伊直弼。
如何に修練して、己を高めても、陽の当たる存在になることは無いと思われた。
「想い出しますなぁ…、埋木舎(うもれぎのや)での歳月を…」
かく言う長野主膳も、その主君・井伊直弼も40代前半。
彦根城下の片隅に埋もれた日々から、10年ほどで幕府の中で頭角を現した。
「感傷に浸っておる暇は無いぞ。我らが公儀(幕府)を導かねばならんのだ。」
――自身を花の咲かない“埋木”(うもれぎ)に例えていた青年が、いまや幕閣の有力者の1人。
ついに陽の当たる場所に出た、井伊直弼。
「伊勢守(阿部正弘)さまは、表(大名たち)の機嫌を伺い過ぎじゃ。」
「御意!」
「今こそ、公儀は毅然と力を示さねばならん。」
「仰せの通り。この主膳、嬉しゅうございますぞ。」
長野主膳は国学者である。
側近であるだけでなく、井伊直弼の学問の師でもあった。

――井伊直弼が推す将軍候補は、徳川御三家の紀州(和歌山)の若君。
「紀州の慶福さまは、上様とも縁も近い。我らがお支えするに相応しい。」
「左様にござる。一橋(慶喜)さまでは、纏(まと)まらなくなりましょう。」
この彦根藩の主従は、諸大名の結集は、却って混乱を招くとの見解である。
異国に対抗するには、幕府が強いリーダーシップで日本を率いるべきと考えた。
――ささやかなそよ風が吹き、風鈴の音が鳴る。
文化人としての顔を持つ、井伊直弼。
床の間には立派な磁器が飾られていた。
「“鍋島(焼)”だな…」
「はっ、華麗な色味にございますな。」
「主膳よ。公儀(幕府)を支えるにあたり、信の置ける国は何処だと思うか。」
「まずは、会津(福島)にございましょうな。」
井伊直弼は、会津藩の先代・松平容敬に何かと世話になってきた。そして、その養子の松平容保の面倒もよく見ていた。いわゆる“恩返し”である。
――透き通った白に色味が映える、床の間の磁器。
「そして肥前佐賀…、鍋島じゃ。」
「佐賀にございますか。たしかに異国の業(わざ)に通じておりますが…」
長野主膳は、いまいち得心がいかない様子だ。
「鍋島肥前は大層な“蘭癖”(西洋かぶれ)。異国に囲まれる昨今、役には立ちましょうが…」
「信は置けぬと考えるか。」
「肥前は、何を企んでおるか…判然とせぬとも聞きますぞ。」
――手に持った扇で磁器を指し示す、井伊直弼。上絵の赤が鮮やかである。
「儂はな…鍋島を、あのように考えておる。」
「鍋島肥前が、あの“伊万里”(鍋島焼)の如しと…?」
直弼も幕閣で経験を積み、長野主膳の発想を超えてきたところがある。
「裏はあるが、嘘は無い…と言ったところか。」
“鍋島焼”は、佐賀藩の機密事項の1つである。
その製法は極秘とされ、厳しい管理により藩外に流出することは無い。その裏には壮絶な歴史があった。
――佐賀藩の技術立国は、徹底した秘密の管理により成り立っていたのである。
「佐賀が造り出すのは、真っ直ぐな“本物”のみ…」
この頃、井伊が治める彦根藩も、陶磁器産業に力を入れていた。
「“慣れ合い”の中からは、生じぬ物があるという事じゃ。」
井伊直弼の厳しい目は、佐賀藩そして鍋島直正を“本物”と判じたのである。
(続く)
前回より幕末の政局を中心としてお話を進めています。「誰が次期(14代)将軍になるのか?」がメインテーマです。
佐賀藩士たちを描く方が楽しいのですが、「一橋派」と「南紀派」の対立は重要なポイントなので頑張って続けます。
前回投稿で「影の“内閣”」に例えて登場したのが「一橋派」。
老中・阿部正弘の方針で、政治参加を進める雄藩の代表たちです。
今回紹介するのは、「南紀派」のリーダー格・井伊直弼。
この派閥は幕府政治を主導していた譜代大名たちが中心です。
――江戸の彦根藩邸。近江(滋賀)にある彦根を治める、井伊家の屋敷。
井伊と言えば、江戸幕府の創始者・徳川家康のもとで戦った“徳川四天王”の名門。当代の藩主は井伊直弼であった。
「主膳よ。ようやっと儂はここまで来たのだな。」
「はっ。やはり天は、殿を埋もれさせては置きませんでしたな。」
――井伊直弼が話している相手は、彦根藩士・長野主膳という。直弼の側近である。
「剣の腕を磨き、茶を嗜み、禅を行じてきた…」
直弼は、先々代の藩主の子であるが、家督を継ぐ可能性は低い立場にいた。
こうして彦根城下で、鬱屈とした青年期を過ごした、井伊直弼。
如何に修練して、己を高めても、陽の当たる存在になることは無いと思われた。
「想い出しますなぁ…、埋木舎(うもれぎのや)での歳月を…」
かく言う長野主膳も、その主君・井伊直弼も40代前半。
彦根城下の片隅に埋もれた日々から、10年ほどで幕府の中で頭角を現した。
「感傷に浸っておる暇は無いぞ。我らが公儀(幕府)を導かねばならんのだ。」
――自身を花の咲かない“埋木”(うもれぎ)に例えていた青年が、いまや幕閣の有力者の1人。
ついに陽の当たる場所に出た、井伊直弼。
「伊勢守(阿部正弘)さまは、表(大名たち)の機嫌を伺い過ぎじゃ。」
「御意!」
「今こそ、公儀は毅然と力を示さねばならん。」
「仰せの通り。この主膳、嬉しゅうございますぞ。」
長野主膳は国学者である。
側近であるだけでなく、井伊直弼の学問の師でもあった。
――井伊直弼が推す将軍候補は、徳川御三家の紀州(和歌山)の若君。
「紀州の慶福さまは、上様とも縁も近い。我らがお支えするに相応しい。」
「左様にござる。一橋(慶喜)さまでは、纏(まと)まらなくなりましょう。」
この彦根藩の主従は、諸大名の結集は、却って混乱を招くとの見解である。
異国に対抗するには、幕府が強いリーダーシップで日本を率いるべきと考えた。
――ささやかなそよ風が吹き、風鈴の音が鳴る。
文化人としての顔を持つ、井伊直弼。
床の間には立派な磁器が飾られていた。
「“鍋島(焼)”だな…」
「はっ、華麗な色味にございますな。」
「主膳よ。公儀(幕府)を支えるにあたり、信の置ける国は何処だと思うか。」
「まずは、会津(福島)にございましょうな。」
井伊直弼は、会津藩の先代・松平容敬に何かと世話になってきた。そして、その養子の松平容保の面倒もよく見ていた。いわゆる“恩返し”である。
――透き通った白に色味が映える、床の間の磁器。
「そして肥前佐賀…、鍋島じゃ。」
「佐賀にございますか。たしかに異国の業(わざ)に通じておりますが…」
長野主膳は、いまいち得心がいかない様子だ。
「鍋島肥前は大層な“蘭癖”(西洋かぶれ)。異国に囲まれる昨今、役には立ちましょうが…」
「信は置けぬと考えるか。」
「肥前は、何を企んでおるか…判然とせぬとも聞きますぞ。」
――手に持った扇で磁器を指し示す、井伊直弼。上絵の赤が鮮やかである。
「儂はな…鍋島を、あのように考えておる。」
「鍋島肥前が、あの“伊万里”(鍋島焼)の如しと…?」
直弼も幕閣で経験を積み、長野主膳の発想を超えてきたところがある。
「裏はあるが、嘘は無い…と言ったところか。」
“鍋島焼”は、佐賀藩の機密事項の1つである。
その製法は極秘とされ、厳しい管理により藩外に流出することは無い。その裏には壮絶な歴史があった。
――佐賀藩の技術立国は、徹底した秘密の管理により成り立っていたのである。
「佐賀が造り出すのは、真っ直ぐな“本物”のみ…」
この頃、井伊が治める彦根藩も、陶磁器産業に力を入れていた。
「“慣れ合い”の中からは、生じぬ物があるという事じゃ。」
井伊直弼の厳しい目は、佐賀藩そして鍋島直正を“本物”と判じたのである。
(続く)
2020年08月10日
第13話「通商条約」①(影の“内閣”)
こんばんは。
本日より第13話「通商条約」をスタートします。初回の投稿ですが、登場する人物が多いです。
ご年配の方は、読み終わった後に登場人物名を想い出すと“脳トレ”になりそうなぐらいです。以前の大河ドラマで演じた俳優さんなどをイメージしながらご覧いただけると…少しは読みやすくなるかもしれません。
――江戸。福井藩主・松平慶永(春嶽)が親しい大名と寄り合っている。
「これは越前(松平)さま。お久しゅうござる。」
口を開いたのは、土佐の山内豊信(容堂)。
古くから土佐(高知)には酒豪が多いと聞くが、殿様からしてその様子。前日の酒が残って…いや、先だってまで飲んでいたような気配である。
「はっはっは…、これは随分と出来上がっておられるな。」
伊予(愛媛)の宇和島藩主・伊達宗城。
洋式船の建造に興味を持つなど開明派で知られる。土佐の殿様の呑み過ぎに苦笑いである。
――松平慶永(春嶽)が場を仕切る。「あと、お一方(ひとかた)おいでになる」と、座長のような立ち位置だ。
「所用により遅くなり、失礼をいたした。」
静かな登場だが、言葉には覇気が感じられる。
薩摩藩主・島津斉彬である。
「薩摩(斉彬)さまにもお運びいただいた。早速ではござるが…」
話を先に進める、松平慶永(春嶽)。
松平慶永は、適塾などで学んだ藩医・橋本左内を重用していた。この福井藩・橋本左内が、薩摩藩・西郷吉之助(隆盛)らと進めている政治活動があった。
殿様同士の集まりだが、側近の藩士たちの想いは反映しているのである。
――黒船来航で緊迫した外交、大地震などの自然災害…相次ぐ難局を打開する策。
「もはや一橋さまに、将軍職を継いでいただくほかない。」
松平慶永は次の将軍に一橋慶喜を推した。
「然り。英明で聞こえた一橋さまならば、我らの存念も届くであろう。」
宇和島藩・伊達宗城は、瀬戸内海の要衝に領地を持つ。沿岸の防備にも危機感があるのだ。
「御台所(篤姫)さまより、上様へのお取次ぎをいただきたい。」
第13代将軍の徳川家定には、薩摩より島津斉彬の養女・篤姫が嫁いでいた。
「相分かった。最善を尽くそう。」
――数年前から老中・阿部正弘が取った「大名にも広く意見を聴く」方針。
アメリカのペリーなどの各国の“黒船”が、次々と来航する危難。挙国一致を目指した、当時の老中首座・阿部正弘は各藩から意見を募った。
以前ならば、幕府から「政(まつりごと)に口出しをするな」と叱責されるところである。しかし、いまや雄藩(有力大名)の国政への参加の流れは止まらない。
これには、老中・阿部正弘の後押しがあった。老中首座は堀田正睦に譲ったが、阿部は自身の領国・福山(広島)には一度帰ったっきりで、国政に心血を注いでいた。

――第13代将軍・家定は病弱で、とても危機的状況に対応できる将軍ではない…世間でも辛辣な批判が多くあった。
そして次の将軍に誰が就くかは、多くの大名たちの関心事でもあった。
「新らしき政(まつりごと)を、このように思案しておる。」
現在の“内閣”のように政治体制のイメージを作り始めていた“四賢侯”。
「まず、一橋さまを将軍として奉じ、我らがお支えすると。」
「これは良い…立派な上様のもとで存分な働きができそうじゃ。」
目もとがニヤリと笑う、山内豊信(容堂)。その真意は充分に測れない。
――その試案で“国内事務宰相”として予定されたのは3人。
・集まりの主宰者。福井の松平慶永。
・外様大名の代表。薩摩の島津斉彬。
・一橋慶喜の実父で、攘夷派の頭目。水戸の徳川斉昭。
将軍となった一橋慶喜の周囲を固め、挙国一致の体制を取る戦略である。
――次は“外国事務宰相”を務める大名の人選。困難な局面にある外交の担当である。
「…肥前佐賀の鍋島しかあるまい。」
「然り。」
「異論があろうはずもない。」

外国からの圧力を予測し、長崎での砲台整備。先んじて反射炉の設置と、鉄製大砲の開発。オランダとの付き合いも深く、西洋事情に通じる。
はじめから佐賀の鍋島直正をおいて、適任者が考えられない状況であった。
――いわば“影の内閣”を作る相談事が進む中、殿・鍋島直正は淡々としていた。
「…そうだな。長崎の固め(警備)で、忙しいとでも伝えておくか。」
「それが宜しいかと。公儀(幕府)が決するべき事への深入りはなりませぬ。」
保守派の側近、原田小四郎が応じた。殿の発言に大きく頷(うなず)く。
“国政”からは距離を置き、ひたすら先を見据える直正。
そして佐賀藩は、国を富ませる産業振興と、有事に備える技術開発を進めるのに忙しい。
直正とすれば、殿様として為すべきことを行っているだけである。しかし、周囲はそのコツコツとした地道さを「何の思惑があるのか?」と勝手に恐れたのである。
(続く)
本日より第13話「通商条約」をスタートします。初回の投稿ですが、登場する人物が多いです。
ご年配の方は、読み終わった後に登場人物名を想い出すと“脳トレ”になりそうなぐらいです。以前の大河ドラマで演じた俳優さんなどをイメージしながらご覧いただけると…少しは読みやすくなるかもしれません。
――江戸。福井藩主・松平慶永(春嶽)が親しい大名と寄り合っている。
「これは越前(松平)さま。お久しゅうござる。」
口を開いたのは、土佐の山内豊信(容堂)。
古くから土佐(高知)には酒豪が多いと聞くが、殿様からしてその様子。前日の酒が残って…いや、先だってまで飲んでいたような気配である。
「はっはっは…、これは随分と出来上がっておられるな。」
伊予(愛媛)の宇和島藩主・伊達宗城。
洋式船の建造に興味を持つなど開明派で知られる。土佐の殿様の呑み過ぎに苦笑いである。
――松平慶永(春嶽)が場を仕切る。「あと、お一方(ひとかた)おいでになる」と、座長のような立ち位置だ。
「所用により遅くなり、失礼をいたした。」
静かな登場だが、言葉には覇気が感じられる。
薩摩藩主・島津斉彬である。
「薩摩(斉彬)さまにもお運びいただいた。早速ではござるが…」
話を先に進める、松平慶永(春嶽)。
松平慶永は、適塾などで学んだ藩医・橋本左内を重用していた。この福井藩・橋本左内が、薩摩藩・西郷吉之助(隆盛)らと進めている政治活動があった。
殿様同士の集まりだが、側近の藩士たちの想いは反映しているのである。
――黒船来航で緊迫した外交、大地震などの自然災害…相次ぐ難局を打開する策。
「もはや一橋さまに、将軍職を継いでいただくほかない。」
松平慶永は次の将軍に一橋慶喜を推した。
「然り。英明で聞こえた一橋さまならば、我らの存念も届くであろう。」
宇和島藩・伊達宗城は、瀬戸内海の要衝に領地を持つ。沿岸の防備にも危機感があるのだ。
「御台所(篤姫)さまより、上様へのお取次ぎをいただきたい。」
第13代将軍の徳川家定には、薩摩より島津斉彬の養女・篤姫が嫁いでいた。
「相分かった。最善を尽くそう。」
――数年前から老中・阿部正弘が取った「大名にも広く意見を聴く」方針。
アメリカのペリーなどの各国の“黒船”が、次々と来航する危難。挙国一致を目指した、当時の老中首座・阿部正弘は各藩から意見を募った。
以前ならば、幕府から「政(まつりごと)に口出しをするな」と叱責されるところである。しかし、いまや雄藩(有力大名)の国政への参加の流れは止まらない。
これには、老中・阿部正弘の後押しがあった。老中首座は堀田正睦に譲ったが、阿部は自身の領国・福山(広島)には一度帰ったっきりで、国政に心血を注いでいた。

――第13代将軍・家定は病弱で、とても危機的状況に対応できる将軍ではない…世間でも辛辣な批判が多くあった。
そして次の将軍に誰が就くかは、多くの大名たちの関心事でもあった。
「新らしき政(まつりごと)を、このように思案しておる。」
現在の“内閣”のように政治体制のイメージを作り始めていた“四賢侯”。
「まず、一橋さまを将軍として奉じ、我らがお支えすると。」
「これは良い…立派な上様のもとで存分な働きができそうじゃ。」
目もとがニヤリと笑う、山内豊信(容堂)。その真意は充分に測れない。
――その試案で“国内事務宰相”として予定されたのは3人。
・集まりの主宰者。福井の松平慶永。
・外様大名の代表。薩摩の島津斉彬。
・一橋慶喜の実父で、攘夷派の頭目。水戸の徳川斉昭。
将軍となった一橋慶喜の周囲を固め、挙国一致の体制を取る戦略である。
――次は“外国事務宰相”を務める大名の人選。困難な局面にある外交の担当である。
「…肥前佐賀の鍋島しかあるまい。」
「然り。」
「異論があろうはずもない。」
外国からの圧力を予測し、長崎での砲台整備。先んじて反射炉の設置と、鉄製大砲の開発。オランダとの付き合いも深く、西洋事情に通じる。
はじめから佐賀の鍋島直正をおいて、適任者が考えられない状況であった。
――いわば“影の内閣”を作る相談事が進む中、殿・鍋島直正は淡々としていた。
「…そうだな。長崎の固め(警備)で、忙しいとでも伝えておくか。」
「それが宜しいかと。公儀(幕府)が決するべき事への深入りはなりませぬ。」
保守派の側近、原田小四郎が応じた。殿の発言に大きく頷(うなず)く。
“国政”からは距離を置き、ひたすら先を見据える直正。
そして佐賀藩は、国を富ませる産業振興と、有事に備える技術開発を進めるのに忙しい。
直正とすれば、殿様として為すべきことを行っているだけである。しかし、周囲はそのコツコツとした地道さを「何の思惑があるのか?」と勝手に恐れたのである。
(続く)
2020年08月09日
「主に伊万里市民の方を対象にしたつぶやき」
おはようございます。
今回は伊万里市の皆様に向けた投稿を準備しました。
当ブログを始めたばかりのとき、幾人か伊万里の方に閲覧の“足あと”を残していただき、大変励みになったことを想い出します。
最近、流行りのセリフで言えば、これは私なりの“恩返し”です。
…とはいえ、大したものはお返しできません。
今後の本編に備えて、私が「伊万里」について考えている内容をつぶやきます。よろしければご覧ください。
――まず、陶磁器について無知な私が困惑した“古伊万里”という名称。
この名は伊万里が、江戸時代より「港湾都市」だったため付いたようです。
最近、知ったのですが、有田焼・平戸焼・波佐見焼…いずれも主な積出し港は“伊万里”なのですね。
――これは商品の受け手、とくに外国人からすれば…
「これは、どこの磁器だね?」
「“オールド・イマリ”だよ!」
「その品質は確かだ。買い求めるとしよう。」
…ヨーロッパなど陶磁器の消費地では、こんな会話があったのではと想像します。“伊万里”の名で、日本の陶磁器は世界に羽ばたいていきます。
――こうして海外で“伊万里”は、陶磁器の代名詞として知られることに。
学術的には「肥前磁器」と呼ぶべきとの見解もあるようです。また、陶磁器の近代産業化という観点では“有田”のイメージが強いです。
しかし、伊万里には「港湾都市」以外にも、取っておきの力があります。それは佐賀の“誇り”に直結するものです。
――伊万里の“秘技”は、佐賀のお殿様「鍋島家」の名を冠した磁器。
江戸時代を通じ、佐賀藩から将軍や幕閣に献上された品。
当時、献上品は、藩の命運を左右することすら有り得た…と推測します。
肥前佐賀藩が門外不出、採算度外視で作り上げた“至高の磁器”。
「鍋島焼」の名は“必勝の品”である事を意味しているのでしょう。
――さて「伊万里港」と「鍋島焼」のお話をしたところで、本編を振り返ります。
第12話「海軍伝習」のラストで登場した佐賀藩の蒸気軍艦。その全長は45メートル、当時の最新式である水面下のスクリューで推進する艦船です。
〔参照:第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕

その名を“電流丸”と言います。
オランダからこの軍艦を入手したとき、殿・鍋島直正は、愛娘・貢姫にこんな手紙を送ります。
「オランダに発注した軍艦が届いた。それはそれは飛び立つように嬉しく…」
わりとお茶目な殿。それだけ喜びが伝わるようです。
――幕末の動乱期。佐賀、そして日本のために海を駆ける“電流丸”。
ロシアが対馬に上陸すれば緊急出動し、伊万里から警戒にあたります。
〔参考(後半):「主に基山町民・鳥栖市民の方を対象にしたつぶやき」〕
「露西亜(ロシア)の動きによっては、一戦交えんばならんか…」
ちなみに第12話では、“数学の子”として登場した中牟田倉之助。佐賀海軍で活躍します。“電流丸”の艦長も務めていたようです。
〔参照:第12話「海軍伝習」⑥(数学の子)〕
西洋列強が沿海で活動する中、幕末の日本は、常に緊張状態にありました。その対外的な危うさを一番理解していたのは、おそらくは佐賀藩。
――対立を深める幕府と雄藩。佐賀の殿・鍋島直正は「外国に付け入る隙を与えるから、内戦は回避しなければならない」と考えたようです。
“幕末最強”の軍事技術を持ちながら、佐賀藩が積極的に戦わなかった理由もそこに求められます。
「日本人同士でつぶし合うべきではない。」
そんな殿の気持ちを乗せて、電流丸はひた走ります。
佐賀で海軍と言えば三重津が有名ですが、有明海は内湾なので、伊万里港からの出発も多かったようです。あるときは殿・直正を乗せ、大坂に入港しました。
「見なはれ!佐賀の殿様が“黒船”に乗って来ましたで!」
大坂の町衆たちが、見物のため港に詰めかけます。
――時代は明治になり、走り続けた“電流丸”は老朽艦となっていました。
その最後の地となったのが、伊万里港だったようです。
殿・鍋島直正がこの世を去った、わずか数か月後。後を追うように“電流丸”も、その使命を終えることになります。
少し寂しい展開なのですが、“電流丸”は、天寿を全うしたと言っても良いのかもしれません。
――なお、私は佐賀に帰藩するときに限り、携帯の待ち受けを“電流丸”に変えています。
いまは新型コロナの感染拡大により、現地に行くことは差し控えております。
もし、私が伊万里港を眺めれば、こんな感慨を持つことでしょう。
「“電流丸”ここに眠る…」と。
陶磁器の積出の活気と、佐賀海軍の躍動の歴史がある港。
港湾都市・伊万里の価値にも注目していきたいと思っています。
今回は伊万里市の皆様に向けた投稿を準備しました。
当ブログを始めたばかりのとき、幾人か伊万里の方に閲覧の“足あと”を残していただき、大変励みになったことを想い出します。
最近、流行りのセリフで言えば、これは私なりの“恩返し”です。
…とはいえ、大したものはお返しできません。
今後の本編に備えて、私が「伊万里」について考えている内容をつぶやきます。よろしければご覧ください。
――まず、陶磁器について無知な私が困惑した“古伊万里”という名称。
この名は伊万里が、江戸時代より「港湾都市」だったため付いたようです。
最近、知ったのですが、有田焼・平戸焼・波佐見焼…いずれも主な積出し港は“伊万里”なのですね。
――これは商品の受け手、とくに外国人からすれば…
「これは、どこの磁器だね?」
「“オールド・イマリ”だよ!」
「その品質は確かだ。買い求めるとしよう。」
…ヨーロッパなど陶磁器の消費地では、こんな会話があったのではと想像します。“伊万里”の名で、日本の陶磁器は世界に羽ばたいていきます。
――こうして海外で“伊万里”は、陶磁器の代名詞として知られることに。
学術的には「肥前磁器」と呼ぶべきとの見解もあるようです。また、陶磁器の近代産業化という観点では“有田”のイメージが強いです。
しかし、伊万里には「港湾都市」以外にも、取っておきの力があります。それは佐賀の“誇り”に直結するものです。
――伊万里の“秘技”は、佐賀のお殿様「鍋島家」の名を冠した磁器。
江戸時代を通じ、佐賀藩から将軍や幕閣に献上された品。
当時、献上品は、藩の命運を左右することすら有り得た…と推測します。
肥前佐賀藩が門外不出、採算度外視で作り上げた“至高の磁器”。
「鍋島焼」の名は“必勝の品”である事を意味しているのでしょう。
――さて「伊万里港」と「鍋島焼」のお話をしたところで、本編を振り返ります。
第12話「海軍伝習」のラストで登場した佐賀藩の蒸気軍艦。その全長は45メートル、当時の最新式である水面下のスクリューで推進する艦船です。
〔参照:
その名を“電流丸”と言います。
オランダからこの軍艦を入手したとき、殿・鍋島直正は、愛娘・貢姫にこんな手紙を送ります。
「オランダに発注した軍艦が届いた。それはそれは飛び立つように嬉しく…」
わりとお茶目な殿。それだけ喜びが伝わるようです。
――幕末の動乱期。佐賀、そして日本のために海を駆ける“電流丸”。
ロシアが対馬に上陸すれば緊急出動し、伊万里から警戒にあたります。
〔参考(後半):
「露西亜(ロシア)の動きによっては、一戦交えんばならんか…」
ちなみに第12話では、“数学の子”として登場した中牟田倉之助。佐賀海軍で活躍します。“電流丸”の艦長も務めていたようです。
〔参照:
西洋列強が沿海で活動する中、幕末の日本は、常に緊張状態にありました。その対外的な危うさを一番理解していたのは、おそらくは佐賀藩。
――対立を深める幕府と雄藩。佐賀の殿・鍋島直正は「外国に付け入る隙を与えるから、内戦は回避しなければならない」と考えたようです。
“幕末最強”の軍事技術を持ちながら、佐賀藩が積極的に戦わなかった理由もそこに求められます。
「日本人同士でつぶし合うべきではない。」
そんな殿の気持ちを乗せて、電流丸はひた走ります。
佐賀で海軍と言えば三重津が有名ですが、有明海は内湾なので、伊万里港からの出発も多かったようです。あるときは殿・直正を乗せ、大坂に入港しました。
「見なはれ!佐賀の殿様が“黒船”に乗って来ましたで!」
大坂の町衆たちが、見物のため港に詰めかけます。
――時代は明治になり、走り続けた“電流丸”は老朽艦となっていました。
その最後の地となったのが、伊万里港だったようです。
殿・鍋島直正がこの世を去った、わずか数か月後。後を追うように“電流丸”も、その使命を終えることになります。
少し寂しい展開なのですが、“電流丸”は、天寿を全うしたと言っても良いのかもしれません。
――なお、私は佐賀に帰藩するときに限り、携帯の待ち受けを“電流丸”に変えています。
いまは新型コロナの感染拡大により、現地に行くことは差し控えております。
もし、私が伊万里港を眺めれば、こんな感慨を持つことでしょう。
「“電流丸”ここに眠る…」と。
陶磁器の積出の活気と、佐賀海軍の躍動の歴史がある港。
港湾都市・伊万里の価値にも注目していきたいと思っています。
2020年08月07日
「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(後編)」
こんばんは。
有田町についてのつぶやき…後編です。
これも数年前なのですが、私はモヤモヤとしておりました。それは、NHKのある番組のことです。
「なぜ“ブラタモリ”は、佐賀に来ないのか…」
ご存じない方もおられるかもしれないので、一応、説明しておきましょう。但し、私の主観が入った解説です…
――長年続いた「笑っていいとも!」の重圧から解放された(…と思われる)タモリこと、森田一義さん。
長寿番組を終えても、さすがは一流の芸能人。
ご自身の興味の赴くまま動ける番組で、格の違いを見せます。全国各地の地形・地質、およそ一般の旅番組とは程遠い世界が展開します。
…あれだけ眠たかった地理や地学の授業と、似たような中身を扱う教養番組なのに、これが楽しいのです。
――そんな“ブラタモリ”。なかなか佐賀を訪れてはくれませんでした。
そして、ネット上では「佐賀は、この番組でも“未踏の地”」と揶揄(やゆ)されていた様子。また「悔しかごたぁ!」…と大声を出しそうになるところです。
同番組を視聴している方はご存じでしょう。ここで“救世主”が登場します。
…言うまでもありません。有田町です。
しかも「有田焼」と「有田焼・世界へ」の2週連続の放映。
――繰り広げられた話は、陶石を採掘する山の成り立ちや、磁器を製造するのに適した環境など。
この辺りは、いつもの“ブラタモリ”らしい展開。
そして、有田ポーセリンパークでは、当時のアシスタントの林田アナウンサーが“特技”を使います。陶器と磁器の違いを体感するため、各々を叩いた音を比べる場面です。
林田アナは絶対音感の持ち主らしく、陶器と磁器を叩いた音を、それぞれ見事に音階で表現しました。
この有田を特集した2週を一言で語ると、「有田に行きたくなる」仕上がりでした。

――そして、タモリさんが物凄く興味を示したのが“碍子”。
“碍子”は「ガイシ」と読みます。電柱などに絶縁体として配置される“白い物体”です。
日本が幕末を経て、新時代・明治に入ったとき、電信の架設も進んでいきました。電気をコントロールするには“絶縁体”が重要です。
コストのかかる外国産を大量に使用することはできず、有田の磁器製造の技術で、碍子(ガイシ)を製造します。これが今も使われている磁器碍子です。
――日本の近代化、そして有田の技術…と来れば、関わったのは佐賀藩士です。
明治の日本で活躍した“逓信四天王”の1人と称される、石丸安世(虎五郎)。本編では第12話から、登場しています。まずは“蘭学寮”で、江藤新平に一目おかれる存在として描きました。
〔参照(後半):第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕
その後、長崎の海軍伝習に参加。洋式帆船を建造するときも、嬉々として鋼線(ワイヤー)を張っていた若手伝習生…という感じの表現にしています。
〔参照:第12話「海軍伝習」⑨-1(悔しかごたぁ・前編)、第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕
――のちに石丸安世はイギリスに密航し、佐賀藩随一の英語の達人になります。
海軍伝習で引っ張ってくれたリーダー・佐野常民(栄寿)が、パリ万博で困難に見舞われているとき、ハイレベルな英語力を身に着けた石丸安世が、イギリスより颯爽(さっそう)と現れます。
当時は、西洋の事情に通じていても、オランダ語しか話せないことが多く、佐野にとって石丸の合流は心強かったことでしょう。
…これが本来の「施されたら施し返す、恩返しです」の精神でしょうか。
――電信架設に必須だった絶縁体・碍子。明治に工部省の電信頭となった、石丸安世が用いたのは有田の力。
当時、東京-長崎間の電信線架設は、「破天荒の大事業」とまで言われたそうです。
そして、日本各地への情報通信網の整備に、有田の磁器は欠かせない要素となったのです。
――後編の石丸安世は、かなり直接的に明治期の有田、そして陶磁器産業に関わっているのですね。
なお、前編の久米邦武も、“香蘭社”設立に関わるなど産業の仕組みづくりで、有田とは深い関わりを続けました。
私が語らずとも、既に有田町ではよく知られた話なのかもしれません。
あらためて有田町の皆様には、親しみを持ってほしい佐賀藩士の2人です。
有田町についてのつぶやき…後編です。
これも数年前なのですが、私はモヤモヤとしておりました。それは、NHKのある番組のことです。
「なぜ“ブラタモリ”は、佐賀に来ないのか…」
ご存じない方もおられるかもしれないので、一応、説明しておきましょう。但し、私の主観が入った解説です…
――長年続いた「笑っていいとも!」の重圧から解放された(…と思われる)タモリこと、森田一義さん。
長寿番組を終えても、さすがは一流の芸能人。
ご自身の興味の赴くまま動ける番組で、格の違いを見せます。全国各地の地形・地質、およそ一般の旅番組とは程遠い世界が展開します。
…あれだけ眠たかった地理や地学の授業と、似たような中身を扱う教養番組なのに、これが楽しいのです。
――そんな“ブラタモリ”。なかなか佐賀を訪れてはくれませんでした。
そして、ネット上では「佐賀は、この番組でも“未踏の地”」と揶揄(やゆ)されていた様子。また「悔しかごたぁ!」…と大声を出しそうになるところです。
同番組を視聴している方はご存じでしょう。ここで“救世主”が登場します。
…言うまでもありません。有田町です。
しかも「有田焼」と「有田焼・世界へ」の2週連続の放映。
――繰り広げられた話は、陶石を採掘する山の成り立ちや、磁器を製造するのに適した環境など。
この辺りは、いつもの“ブラタモリ”らしい展開。
そして、有田ポーセリンパークでは、当時のアシスタントの林田アナウンサーが“特技”を使います。陶器と磁器の違いを体感するため、各々を叩いた音を比べる場面です。
林田アナは絶対音感の持ち主らしく、陶器と磁器を叩いた音を、それぞれ見事に音階で表現しました。
この有田を特集した2週を一言で語ると、「有田に行きたくなる」仕上がりでした。
――そして、タモリさんが物凄く興味を示したのが“碍子”。
“碍子”は「ガイシ」と読みます。電柱などに絶縁体として配置される“白い物体”です。
日本が幕末を経て、新時代・明治に入ったとき、電信の架設も進んでいきました。電気をコントロールするには“絶縁体”が重要です。
コストのかかる外国産を大量に使用することはできず、有田の磁器製造の技術で、碍子(ガイシ)を製造します。これが今も使われている磁器碍子です。
――日本の近代化、そして有田の技術…と来れば、関わったのは佐賀藩士です。
明治の日本で活躍した“逓信四天王”の1人と称される、石丸安世(虎五郎)。本編では第12話から、登場しています。まずは“蘭学寮”で、江藤新平に一目おかれる存在として描きました。
〔参照(後半):
その後、長崎の海軍伝習に参加。洋式帆船を建造するときも、嬉々として鋼線(ワイヤー)を張っていた若手伝習生…という感じの表現にしています。
〔参照:
――のちに石丸安世はイギリスに密航し、佐賀藩随一の英語の達人になります。
海軍伝習で引っ張ってくれたリーダー・佐野常民(栄寿)が、パリ万博で困難に見舞われているとき、ハイレベルな英語力を身に着けた石丸安世が、イギリスより颯爽(さっそう)と現れます。
当時は、西洋の事情に通じていても、オランダ語しか話せないことが多く、佐野にとって石丸の合流は心強かったことでしょう。
…これが本来の「施されたら施し返す、恩返しです」の精神でしょうか。
――電信架設に必須だった絶縁体・碍子。明治に工部省の電信頭となった、石丸安世が用いたのは有田の力。
当時、東京-長崎間の電信線架設は、「破天荒の大事業」とまで言われたそうです。
そして、日本各地への情報通信網の整備に、有田の磁器は欠かせない要素となったのです。
――後編の石丸安世は、かなり直接的に明治期の有田、そして陶磁器産業に関わっているのですね。
なお、前編の久米邦武も、“香蘭社”設立に関わるなど産業の仕組みづくりで、有田とは深い関わりを続けました。
私が語らずとも、既に有田町ではよく知られた話なのかもしれません。
あらためて有田町の皆様には、親しみを持ってほしい佐賀藩士の2人です。
2020年08月05日
「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(前編)」
こんばんは。
第12話の振り返りを兼ねて、今回は有田町について考えてみたいと思います。あわせて語りたい人物も2人いますので、前・後編でお送りします。
――数年前。私が佐賀出身者と知ったときの周囲の反応です。
当時の職場の同僚たちとの会話を想い起こしてみます。
「SRさん。故郷は佐賀なんですね。」
…と、ある同僚の女性。
「…佐賀…、何がありますかね。」
そして、会話に加わったもう1人。
佐賀に対して、何も“イメージ”が浮かばない様子でした。
――ここで、先ほどの同僚女性の表情が、パッと変わります。
「佐賀と言ったら、有田の陶器市がありますよね!」
これは一般的な佐賀への反応としては、かなり好意的なものです。
さすがは“有田”ブランド。
しかし、残念なのは私の反応でした。
「たしかに有田は佐賀ですが、陶磁器には詳しくないんですよね。」
――以前「伊万里市民・有田町民」の皆様へのつぶやきでも触れていますが…
私は陶磁器について、まったく知識が無かったのです。
…こうして私は“佐賀の価値”について、他県の方に語る機会を逸しました。
かつて、佐賀の殿様はこう語ったといいます。
「私の家来は、とにかく学ばねばならんのだ。」と。
――これでは殿に「ボーッと生きていてはならぬ!」と、お叱りを受けます。
次に有田の話題が来たら、今度は不覚を取るつもりはありません。佐賀の魅力として伝えきる所存です。
…というわけで、有田の陶山神社の写真を入手しました。

“陶山神社”は、江戸時代に有田にあった佐賀藩の“有田皿山”の代官所が建立したそうです。
この“代官所”に縁のある人物が、第12話で初登場した、久米丈一郎(邦武)。
“義祭同盟”について語り合える同年代の友達を探していた、大隈八太郎(重信)。その眼前に現れた、賢そうな子が久米丈一郎(邦武)…という場面設定にしました。〔参照:第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕
――この久米丈一郎(邦武)は、日本の近代歴史学の扉を開く人物。
久米の父・邦郷は、有田皿山の代官を務める、有能な実務家。
そのご子息なので、本編では“有田の坊ちゃん”というサブタイトルを付けました。
伝統的な“儒学”などを「面白くない」として嫌う大隈八太郎(重信)。しかし、新しくできた友達の久米丈一郎(邦武)は古典に学ぶことが大好きです。
この2人、高校生くらいで出会ったといい、老人になっても友達だったのですが、何やら最初の方向性はズレています…そのくらいが長く友達でいるためには良いのかもしれません。
――久米の父・邦郷は、佐賀藩の近代産業に貢献したエリートだったようです。やはり経済感覚に優れます。
「儒学などの古い本はつまらん」という考え方の父・邦郷。
これに反発した久米丈一郎(邦武)は、藩校「弘道館」で書物を読みまくります。
のちの明治の世。学識のある久米は、西洋に渡る“使節団”には書記官として同行しました。久米が作成した報告書「米欧回覧実記」は、まるで西洋近代文明の百科事典と言われます。
――久米邦武は「私が注意深く資料を扱うのは、実務家の父親譲りだった…」という回想をしたそうです。
父親として“しっかり生きてきたか”。その真価が問われるのは、子どもが歳を経てから…なのかもしれません。
第12話の振り返りを兼ねて、今回は有田町について考えてみたいと思います。あわせて語りたい人物も2人いますので、前・後編でお送りします。
――数年前。私が佐賀出身者と知ったときの周囲の反応です。
当時の職場の同僚たちとの会話を想い起こしてみます。
「SRさん。故郷は佐賀なんですね。」
…と、ある同僚の女性。
「…佐賀…、何がありますかね。」
そして、会話に加わったもう1人。
佐賀に対して、何も“イメージ”が浮かばない様子でした。
――ここで、先ほどの同僚女性の表情が、パッと変わります。
「佐賀と言ったら、有田の陶器市がありますよね!」
これは一般的な佐賀への反応としては、かなり好意的なものです。
さすがは“有田”ブランド。
しかし、残念なのは私の反応でした。
「たしかに有田は佐賀ですが、陶磁器には詳しくないんですよね。」
――以前「伊万里市民・有田町民」の皆様へのつぶやきでも触れていますが…
私は陶磁器について、まったく知識が無かったのです。
…こうして私は“佐賀の価値”について、他県の方に語る機会を逸しました。
かつて、佐賀の殿様はこう語ったといいます。
「私の家来は、とにかく学ばねばならんのだ。」と。
――これでは殿に「ボーッと生きていてはならぬ!」と、お叱りを受けます。
次に有田の話題が来たら、今度は不覚を取るつもりはありません。佐賀の魅力として伝えきる所存です。
…というわけで、有田の陶山神社の写真を入手しました。
“陶山神社”は、江戸時代に有田にあった佐賀藩の“有田皿山”の代官所が建立したそうです。
この“代官所”に縁のある人物が、第12話で初登場した、久米丈一郎(邦武)。
“義祭同盟”について語り合える同年代の友達を探していた、大隈八太郎(重信)。その眼前に現れた、賢そうな子が久米丈一郎(邦武)…という場面設定にしました。〔参照:
――この久米丈一郎(邦武)は、日本の近代歴史学の扉を開く人物。
久米の父・邦郷は、有田皿山の代官を務める、有能な実務家。
そのご子息なので、本編では“有田の坊ちゃん”というサブタイトルを付けました。
伝統的な“儒学”などを「面白くない」として嫌う大隈八太郎(重信)。しかし、新しくできた友達の久米丈一郎(邦武)は古典に学ぶことが大好きです。
この2人、高校生くらいで出会ったといい、老人になっても友達だったのですが、何やら最初の方向性はズレています…そのくらいが長く友達でいるためには良いのかもしれません。
――久米の父・邦郷は、佐賀藩の近代産業に貢献したエリートだったようです。やはり経済感覚に優れます。
「儒学などの古い本はつまらん」という考え方の父・邦郷。
これに反発した久米丈一郎(邦武)は、藩校「弘道館」で書物を読みまくります。
のちの明治の世。学識のある久米は、西洋に渡る“使節団”には書記官として同行しました。久米が作成した報告書「米欧回覧実記」は、まるで西洋近代文明の百科事典と言われます。
――久米邦武は「私が注意深く資料を扱うのは、実務家の父親譲りだった…」という回想をしたそうです。
父親として“しっかり生きてきたか”。その真価が問われるのは、子どもが歳を経てから…なのかもしれません。
2020年08月03日
「暑中お見舞い申し上げます。」
こんばんは。
今年は、各地のお祭りなど、夏を感じさせる行事が大幅に減っていますね。少し前まで梅雨でしたし、急に八月になったかのような戸惑いを感じます。
「暑中のお見舞いは、立秋までに…」と言いますので、今日この場をお借りして。
いつも文章が長くなりがちなので、少し簡潔に書く練習も兼ねたいと思います。
――さて、最近では“本編”の各話を書き終えるのに、概ね1か月かかってます…
だいたい1話あたり10本ほど投稿しています。
序盤はまだシンプルな話だったのですが、最近は誰をどの場面で登場させるか…なかなか悩ましいところです。
たぶん主人公をハッキリ固定させれば、書きやすくなるのだと思います。
しかし、私は1人の主人公が際立った作品より、複数のキャラクターが活躍する物語が好きなのです。
幕末佐賀藩を書きたくなる理由は、多分ここにもあります。
――各投稿ごとに何となく映像をイメージしてから、文章に書き起こしています。
すごく疲れるのですが、書いているときには“仕事”のことは忘れています。ある意味では、贅沢な時間なのかもしれません。
そして、頭を使うときに、私が強く欲しているもの…
――それは“糖分”です。甘い物が好きなのです。
プロフィールにも“丸ぼうろ”と“ブラックモンブラン”を例示しているので、お察しいただいている方もいるかもしれません。

昨年の初夏には、県庁通りの“村岡総本舗”さんで、こんなものを食べていました。
「バナナ羊羹アイスキャンデー!!」
これが“シュガーロード”と呼ばれる長崎街道がつないでいくもの。
そして佐賀のソウルフード“小城羊羹”の底力であろうと思います。
――“暑中見舞い”を語るならば、少しでも涼しい投稿を…と考えた結果がこうなりました。
急激な猛暑の到来、今夏はマスクの着用で、さらに暑い場面も多いでしょう。皆様、くれぐれもご自愛ください。
今年は、各地のお祭りなど、夏を感じさせる行事が大幅に減っていますね。少し前まで梅雨でしたし、急に八月になったかのような戸惑いを感じます。
「暑中のお見舞いは、立秋までに…」と言いますので、今日この場をお借りして。
いつも文章が長くなりがちなので、少し簡潔に書く練習も兼ねたいと思います。
――さて、最近では“本編”の各話を書き終えるのに、概ね1か月かかってます…
だいたい1話あたり10本ほど投稿しています。
序盤はまだシンプルな話だったのですが、最近は誰をどの場面で登場させるか…なかなか悩ましいところです。
たぶん主人公をハッキリ固定させれば、書きやすくなるのだと思います。
しかし、私は1人の主人公が際立った作品より、複数のキャラクターが活躍する物語が好きなのです。
幕末佐賀藩を書きたくなる理由は、多分ここにもあります。
――各投稿ごとに何となく映像をイメージしてから、文章に書き起こしています。
すごく疲れるのですが、書いているときには“仕事”のことは忘れています。ある意味では、贅沢な時間なのかもしれません。
そして、頭を使うときに、私が強く欲しているもの…
――それは“糖分”です。甘い物が好きなのです。
プロフィールにも“丸ぼうろ”と“ブラックモンブラン”を例示しているので、お察しいただいている方もいるかもしれません。
昨年の初夏には、県庁通りの“村岡総本舗”さんで、こんなものを食べていました。
「バナナ羊羹アイスキャンデー!!」
これが“シュガーロード”と呼ばれる長崎街道がつないでいくもの。
そして佐賀のソウルフード“小城羊羹”の底力であろうと思います。
――“暑中見舞い”を語るならば、少しでも涼しい投稿を…と考えた結果がこうなりました。
急激な猛暑の到来、今夏はマスクの着用で、さらに暑い場面も多いでしょう。皆様、くれぐれもご自愛ください。
2020年08月02日
「慈雨の剣」
こんばんは。
前回の投稿で、うっかり「写真素材が無い!」とつぶやいてしまったので、色々とお気遣いの言葉をいただきました。
「望郷の剣」というタイトルでの投稿もシリーズ化しています。今では少し距離が遠くても、新型コロナの影響で隔てられても、佐賀がとても近くに感じられます。これは皆様のおかげであると思います。
…というわけで、今日もある佐賀藩士(?)の想いを描く同シリーズの投稿です。
ちなみに“本編”の第13話は「通商条約」の予定ですが、話の構成を迷うところです。準備期間として、色々と投稿しながら考えていきたいと思います。
――さて、豪雨は困りますが、猛暑に見舞われ出すと、穏やかな雨を懐かしく想います。
思えば元号が“令和”になってから、まだ1年ちょっとしか経っていません。
今日は、いきなり“平成”ラストの一日に話が戻るのですが…この日、皆様は何か特別な過ごし方をなさっていたでしょうか。
以前「発心の剣」というタイトルで、私が“佐賀出身”であると、一瞬で見抜かれた話を投稿しました。今回は、私が佐賀藩士(?)として、活動し始める契機になった日のお話です。
――“平成”最後の日、早朝。佐賀市内には霧のような優しい雨が降っていた。
私が佐賀に帰ってきたのは、祖父の墓参りをするためだった。
ごく幼少の頃に祖父とは死別した。
それゆえ私は、はっきりと祖父の姿を覚えているわけではない。
しかし、受け継いだ…あるいは受け継いでしまったものは確かにあるらしい。
――しかし、先んじて墓参りの際は、滝のような雨に見舞われた。
「わざわざ孫が墓参りにきたので、感激の涙雨ではないか…」
…などと他愛のない会話をしながら、慌ただしい墓参となったのである。
こうして主たる用事が終わり、佐賀での滞在の最終日。
早朝に目が覚めてしまった。特に為すべきこともないので、まだ人通りもほとんどない県庁通りを歩いた。

――そのまま南下し、佐賀城公園に向かったのである。
雨はポツポツと降り続いていた。
ただ、お堀端を歩く。どの場所も丁寧に掃除が行き届いている様子だ。
このお城が、いかに周りの市民から愛されているかが伝わってくる。本丸歴史館が開くまでには、まだ随分と時間があった。
――涼しい雨を傘で受けながら、おそらくは贅沢な時間を過ごした。
「やはり、ここは私にとっては“特別な場所”なのだ…」
そう感じずにはいられなかった。
時計の針が進むのも忘れたかのような時間を過ごした。
あと15時間ほどが経てば“元号”も変わるのだ…それが、より一層の特別感を醸し出していた。
――ほどなく本丸歴史館が開く。
佐賀藩についての知識が得たくて、設置されているモニターの前に座る。
「幕末期、日本の近代化の先駆けとなった肥前佐賀藩…」
概ね、このような解説だっただろうか。
その前年の大河ドラマが「西郷どん」だったので、少なくとも“佐賀七賢人”のうち3人は登場した。その辺りの情報は、少し調べていた。
――しかし、モニターの音声は、予想外の人物の解説を始めた。
「財政、教育を担当した藩の請役(ナンバー2)で、須古領主の鍋島安房…」
私は完全に隙を突かれた。まったくノーマークだった人物の名が出てくる。

しかも財政再建と教育改革を成し遂げた、殿・鍋島直正の“右腕”のような補佐役とは…幕末の佐賀藩において、極めて重要なところである。
その衝撃はハッキリと覚えているが、その後、資料館内で何を調べたかの記憶は曖昧である。ただ「幕末佐賀藩の活躍は、もっと広く知られるべきだ!」という気持ちは確信に変わった。
――全国が“新しい時代へのカウントダウン”で浮き立っていた、その日。私は佐賀を発った。
こうして今度は佐賀出身者であるだけでなく、佐賀藩士(?)としての気付きを得てしまった私。大都市圏に戻っての活動が始まった。
まず“令和”に元号が変わった次の日から、本棚の奥にあった古い日本史の教科書を引っ張り出した。そして、おもむろに佐賀藩の年表と見比べたのである。
…クールダウンを意識してみましたが、やはり佐賀藩の話に言及すると多少は熱くなるようです…しばらくの間、忙しくなりそうなのですが、休み休みになっても、何とか続けていきたいと思います。
前回の投稿で、うっかり「写真素材が無い!」とつぶやいてしまったので、色々とお気遣いの言葉をいただきました。
「望郷の剣」というタイトルでの投稿もシリーズ化しています。今では少し距離が遠くても、新型コロナの影響で隔てられても、佐賀がとても近くに感じられます。これは皆様のおかげであると思います。
…というわけで、今日もある佐賀藩士(?)の想いを描く同シリーズの投稿です。
ちなみに“本編”の第13話は「通商条約」の予定ですが、話の構成を迷うところです。準備期間として、色々と投稿しながら考えていきたいと思います。
――さて、豪雨は困りますが、猛暑に見舞われ出すと、穏やかな雨を懐かしく想います。
思えば元号が“令和”になってから、まだ1年ちょっとしか経っていません。
今日は、いきなり“平成”ラストの一日に話が戻るのですが…この日、皆様は何か特別な過ごし方をなさっていたでしょうか。
以前「発心の剣」というタイトルで、私が“佐賀出身”であると、一瞬で見抜かれた話を投稿しました。今回は、私が佐賀藩士(?)として、活動し始める契機になった日のお話です。
――“平成”最後の日、早朝。佐賀市内には霧のような優しい雨が降っていた。
私が佐賀に帰ってきたのは、祖父の墓参りをするためだった。
ごく幼少の頃に祖父とは死別した。
それゆえ私は、はっきりと祖父の姿を覚えているわけではない。
しかし、受け継いだ…あるいは受け継いでしまったものは確かにあるらしい。
――しかし、先んじて墓参りの際は、滝のような雨に見舞われた。
「わざわざ孫が墓参りにきたので、感激の涙雨ではないか…」
…などと他愛のない会話をしながら、慌ただしい墓参となったのである。
こうして主たる用事が終わり、佐賀での滞在の最終日。
早朝に目が覚めてしまった。特に為すべきこともないので、まだ人通りもほとんどない県庁通りを歩いた。
――そのまま南下し、佐賀城公園に向かったのである。
雨はポツポツと降り続いていた。
ただ、お堀端を歩く。どの場所も丁寧に掃除が行き届いている様子だ。
このお城が、いかに周りの市民から愛されているかが伝わってくる。本丸歴史館が開くまでには、まだ随分と時間があった。
――涼しい雨を傘で受けながら、おそらくは贅沢な時間を過ごした。
「やはり、ここは私にとっては“特別な場所”なのだ…」
そう感じずにはいられなかった。
時計の針が進むのも忘れたかのような時間を過ごした。
あと15時間ほどが経てば“元号”も変わるのだ…それが、より一層の特別感を醸し出していた。
――ほどなく本丸歴史館が開く。
佐賀藩についての知識が得たくて、設置されているモニターの前に座る。
「幕末期、日本の近代化の先駆けとなった肥前佐賀藩…」
概ね、このような解説だっただろうか。
その前年の大河ドラマが「西郷どん」だったので、少なくとも“佐賀七賢人”のうち3人は登場した。その辺りの情報は、少し調べていた。
――しかし、モニターの音声は、予想外の人物の解説を始めた。
「財政、教育を担当した藩の請役(ナンバー2)で、須古領主の鍋島安房…」
私は完全に隙を突かれた。まったくノーマークだった人物の名が出てくる。
しかも財政再建と教育改革を成し遂げた、殿・鍋島直正の“右腕”のような補佐役とは…幕末の佐賀藩において、極めて重要なところである。
その衝撃はハッキリと覚えているが、その後、資料館内で何を調べたかの記憶は曖昧である。ただ「幕末佐賀藩の活躍は、もっと広く知られるべきだ!」という気持ちは確信に変わった。
――全国が“新しい時代へのカウントダウン”で浮き立っていた、その日。私は佐賀を発った。
こうして今度は佐賀出身者であるだけでなく、佐賀藩士(?)としての気付きを得てしまった私。大都市圏に戻っての活動が始まった。
まず“令和”に元号が変わった次の日から、本棚の奥にあった古い日本史の教科書を引っ張り出した。そして、おもむろに佐賀藩の年表と見比べたのである。
…クールダウンを意識してみましたが、やはり佐賀藩の話に言及すると多少は熱くなるようです…しばらくの間、忙しくなりそうなのですが、休み休みになっても、何とか続けていきたいと思います。
2020年08月01日
「望郷の剣3」
こんにちは。
お読みいただいた方、第12話「海軍伝習」いかがだったでしょうか。今年も8月になってしまいました。
本日は、ある佐賀藩士(?)の想いを描く「望郷の剣」シリーズです。
――私の個人的な事情だが、周辺環境の変化により、4月以降の活動は苦戦を強いられている。
「この展開は予期できなかった…」
ブログ開始時の想定に比べて、現在の私を取り巻く状況は厳しい。いまや2日に1度の投稿ペースを守るのに手一杯である。
「いかん…写真の素材も無い!」
また新型コロナの蔓延により、佐賀に帰藩して行うはずの事柄が実施できない。いまや情報の収集にも高いハードルが生じている。
――しかし、そのことは私の“望郷の念”をより強いものとしている。
いろいろ疑問符(?)が付くとはいえ、仮にも“佐賀藩士”を名乗るならば、この程度の困難に屈してはならない。
これまでの「望郷の剣」の続きになるが、帰藩が叶わずとも、動く手立てはある。まずは“消費行動”で、佐賀の価値を示すのである。
――こうして我が家の食卓には、嬉野茶、伊万里梨、白石産“玉ねぎ”が並ぶこととなった。
佐賀県の農産物は生産高でトップは取れなくても、ランキング高順位の品目が多い。良い位置に付けているのだ。もちろん品質は申し分ない。
これに小城の工場で製造される“ブラックモンブラン”、佐賀市内の製菓店の“丸ぼうろ”を加えれば、さらに彩りが増すことであろう。
――今年6月。新商業施設“コムボックス”がオープンし、佐賀駅前が少し賑わっていると聞く。
私が“帰藩”できた時期は、まだ工事中だったのが、ついに動き始めたのだ。

今まで「インバウンド」という言葉は、主に“観光用語”として使われてきた。外国人観光客による消費を指して使われている経過がある。
しかし「インバウンド」にはもう1つの意味があるらしい。“ビジネス用語”では、国内外を問わず「顧客から企業にアプローチしてくる動き」全般を指すという。
――例えば、有田焼で特定の窯元のファンが直接訪ねて来る…という動きは、もう1つの「インバウンド」であるようだ。
駅前の新商業施設には、観光・県産品案内の拠点“SAGA MADO”があり、特産品の展示ブースがあると聞く。いわば常設の見本市ができた。
これにより県内外の方と、佐賀の特産品との“出会い”の場が創り出されるはず…そんな展開に期待している。
佐賀県内の「この地域、この商品」のファンが増えれば、まず県内の生産者が潤う。苦境にある地元の飲食業や温泉などの観光業にも、安定した資金が回る好循環を作り出せないか…
――「私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマ」を追う中で、佐賀を主役にした“新しい消費行動”の実現を想うようになった。
もちろん、幕末期に佐賀藩が行った政策のイメージに感化されている。
まずは全国各地に散らばっている佐賀藩士(?)に呼び掛けを試みたい。
「佐賀産の品物を選択すべし!」と。
小さなところから、各々の“決起”を促すことも大事だと思うのである。
――以上です。最後にブログをお読みの皆様で、主に大都市圏に親族がいらっしゃる方へのつぶやきです。
たとえお盆の帰省は自粛しても、このような佐賀との繋がり方もあります。
新型コロナへの心配で、帰省を迷っている親族をお持ちの皆様には、ひとまず特産品を通じて“望郷の想い”を満たす方法もあるのではないかと思います。
…わずかでも佐賀の経済にプラスにはたらきますし、大都市圏に“佐賀への想い”を持つ同志(?)が増えれば、私も心強いです。
今は好機の到来を待つことにします。
お読みいただいた方、第12話「海軍伝習」いかがだったでしょうか。今年も8月になってしまいました。
本日は、ある佐賀藩士(?)の想いを描く「望郷の剣」シリーズです。
――私の個人的な事情だが、周辺環境の変化により、4月以降の活動は苦戦を強いられている。
「この展開は予期できなかった…」
ブログ開始時の想定に比べて、現在の私を取り巻く状況は厳しい。いまや2日に1度の投稿ペースを守るのに手一杯である。
「いかん…写真の素材も無い!」
また新型コロナの蔓延により、佐賀に帰藩して行うはずの事柄が実施できない。いまや情報の収集にも高いハードルが生じている。
――しかし、そのことは私の“望郷の念”をより強いものとしている。
いろいろ疑問符(?)が付くとはいえ、仮にも“佐賀藩士”を名乗るならば、この程度の困難に屈してはならない。
これまでの「望郷の剣」の続きになるが、帰藩が叶わずとも、動く手立てはある。まずは“消費行動”で、佐賀の価値を示すのである。
――こうして我が家の食卓には、嬉野茶、伊万里梨、白石産“玉ねぎ”が並ぶこととなった。
佐賀県の農産物は生産高でトップは取れなくても、ランキング高順位の品目が多い。良い位置に付けているのだ。もちろん品質は申し分ない。
これに小城の工場で製造される“ブラックモンブラン”、佐賀市内の製菓店の“丸ぼうろ”を加えれば、さらに彩りが増すことであろう。
――今年6月。新商業施設“コムボックス”がオープンし、佐賀駅前が少し賑わっていると聞く。
私が“帰藩”できた時期は、まだ工事中だったのが、ついに動き始めたのだ。
今まで「インバウンド」という言葉は、主に“観光用語”として使われてきた。外国人観光客による消費を指して使われている経過がある。
しかし「インバウンド」にはもう1つの意味があるらしい。“ビジネス用語”では、国内外を問わず「顧客から企業にアプローチしてくる動き」全般を指すという。
――例えば、有田焼で特定の窯元のファンが直接訪ねて来る…という動きは、もう1つの「インバウンド」であるようだ。
駅前の新商業施設には、観光・県産品案内の拠点“SAGA MADO”があり、特産品の展示ブースがあると聞く。いわば常設の見本市ができた。
これにより県内外の方と、佐賀の特産品との“出会い”の場が創り出されるはず…そんな展開に期待している。
佐賀県内の「この地域、この商品」のファンが増えれば、まず県内の生産者が潤う。苦境にある地元の飲食業や温泉などの観光業にも、安定した資金が回る好循環を作り出せないか…
――「私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマ」を追う中で、佐賀を主役にした“新しい消費行動”の実現を想うようになった。
もちろん、幕末期に佐賀藩が行った政策のイメージに感化されている。
まずは全国各地に散らばっている佐賀藩士(?)に呼び掛けを試みたい。
「佐賀産の品物を選択すべし!」と。
小さなところから、各々の“決起”を促すことも大事だと思うのである。
――以上です。最後にブログをお読みの皆様で、主に大都市圏に親族がいらっしゃる方へのつぶやきです。
たとえお盆の帰省は自粛しても、このような佐賀との繋がり方もあります。
新型コロナへの心配で、帰省を迷っている親族をお持ちの皆様には、ひとまず特産品を通じて“望郷の想い”を満たす方法もあるのではないかと思います。
…わずかでも佐賀の経済にプラスにはたらきますし、大都市圏に“佐賀への想い”を持つ同志(?)が増えれば、私も心強いです。
今は好機の到来を待つことにします。