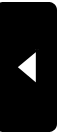2021年06月20日
「【速報】『青天を衝け』に殿の名が。」
こんばんは。
本日は、ニュース速報っぽく、すぐにお伝えします。
NHK総合テレビで放送された大河ドラマ『青天を衝け』からの情報です。放送開始から24分ほど経過した頃。
今までその存在が見えなかった、佐賀の殿・鍋島直正さまが史実どおり、活躍されていたことが確認されました。
…内容がピンポイントなので、筋書きに関する“ネタバレ”にはならないかと思いますが、気になる方は視聴後にご覧ください。
――なお、明らかになった情報は…
“過去の回想”によるエピソードで判明したものです。福井藩の松平春嶽〔演:要潤〕と、同藩士・橋本左内〔演:小池徹平〕が会話する場面。
“安政の大獄”で1859年に落命した橋本左内ですが、当時は“一橋派”の活動で走り回っていました。
――“新たな政権”を目指して…
その橋本左内が、福井の殿・松平春嶽に対して、政権に入るべき主要な人物を笑顔で語る場面。
自身の主君への信頼なのか、幸せ感いっぱいに夢を語るような、小池徹平さんの表情が光ります。でも、あとの展開を考えると、この演出は辛い…
「まず、一橋さまという優れた方を、公方(将軍)さまに定め…」
――なぜ、金平糖(こんぺいとう)を置きながら語るのか…
何だか楽し気な橋本左内〔演:小池徹平〕ですが、セリフの内容に注目。
「事務宰相は、わが殿(松平慶永)と水戸のご老公(徳川斉昭)。そして島津どの(島津斉彬)の三人。」
次の一言が重要なのです。
「…外国宰相には、佐賀の鍋島閑叟(直正)さま。」

――ここで、テレビの前では…
「殿っ!よくぞ、ご無事で。安堵(あんど)いたしました!」
今までの放送では、その存在が触れられて来なかった佐賀藩と殿・直正公。
…現代を生きる佐賀藩士(?)の中にはその安否を気遣う声もあったようです。
当時、政権を争った“一橋派”と“南紀派”。その両方から外国への抑えと期待されたのが、長崎警備担当の佐賀藩の殿・鍋島直正です。
〔参照(終盤):第13話「通商条約」①(影の“内閣”)〕
――ちなみに“閑叟”(かんそう)という、お名前(号)について。
鍋島直正が、その名をを正式に名乗るのは、隠居してからのようです。しかし当時、表向きには“松平肥前守斉正”となるのでは…という心配があります。
もはや誰だかわからなくなりそう。「閑叟さま」が無難なのでしょう。小池徹平さんがあふれる笑顔で、その名を語ってくれたことが素直に嬉しいです。
見逃した方、聞き逃した方。土曜日の再放送でご覧になって、今年の大河ドラマでは、まだ見えていない佐賀藩の活躍に想いを馳せていただければ幸いです。
本日は、ニュース速報っぽく、すぐにお伝えします。
NHK総合テレビで放送された大河ドラマ『青天を衝け』からの情報です。放送開始から24分ほど経過した頃。
今までその存在が見えなかった、佐賀の殿・鍋島直正さまが史実どおり、活躍されていたことが確認されました。
…内容がピンポイントなので、筋書きに関する“ネタバレ”にはならないかと思いますが、気になる方は視聴後にご覧ください。
――なお、明らかになった情報は…
“過去の回想”によるエピソードで判明したものです。福井藩の松平春嶽〔演:要潤〕と、同藩士・橋本左内〔演:小池徹平〕が会話する場面。
“安政の大獄”で1859年に落命した橋本左内ですが、当時は“一橋派”の活動で走り回っていました。
――“新たな政権”を目指して…
その橋本左内が、福井の殿・松平春嶽に対して、政権に入るべき主要な人物を笑顔で語る場面。
自身の主君への信頼なのか、幸せ感いっぱいに夢を語るような、小池徹平さんの表情が光ります。でも、あとの展開を考えると、この演出は辛い…
「まず、一橋さまという優れた方を、公方(将軍)さまに定め…」
――なぜ、金平糖(こんぺいとう)を置きながら語るのか…
何だか楽し気な橋本左内〔演:小池徹平〕ですが、セリフの内容に注目。
「事務宰相は、わが殿(松平慶永)と水戸のご老公(徳川斉昭)。そして島津どの(島津斉彬)の三人。」
次の一言が重要なのです。
「…外国宰相には、佐賀の鍋島閑叟(直正)さま。」
――ここで、テレビの前では…
「殿っ!よくぞ、ご無事で。安堵(あんど)いたしました!」
今までの放送では、その存在が触れられて来なかった佐賀藩と殿・直正公。
…現代を生きる佐賀藩士(?)の中にはその安否を気遣う声もあったようです。
当時、政権を争った“一橋派”と“南紀派”。その両方から外国への抑えと期待されたのが、長崎警備担当の佐賀藩の殿・鍋島直正です。
〔参照(終盤):
――ちなみに“閑叟”(かんそう)という、お名前(号)について。
鍋島直正が、その名をを正式に名乗るのは、隠居してからのようです。しかし当時、表向きには“松平肥前守斉正”となるのでは…という心配があります。
もはや誰だかわからなくなりそう。「閑叟さま」が無難なのでしょう。小池徹平さんがあふれる笑顔で、その名を語ってくれたことが素直に嬉しいです。
見逃した方、聞き逃した方。土曜日の再放送でご覧になって、今年の大河ドラマでは、まだ見えていない佐賀藩の活躍に想いを馳せていただければ幸いです。
2021年06月12日
「新キャストを考える③」(青天に、佐賀藩士がくる)
こんばんは。
先日の発表で大河ドラマ『青天を衝け』に待望の佐賀藩士の登場が明らかに。
主人公・渋沢栄一〔演:吉沢亮〕を明治新政府に引っ張り込む役回りですから、この方は出演するはずと確信していました。
――では、新キャストとしての大隈重信の紹介です。
『青天を衝け』を紹介するNHK公式サイトでは佐賀藩士族と記載されています。藩校で騒動を起こして、長崎で英語を勉強してきた…との経歴まで掲載。
https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/449714.html(外部サイト)
わりと佐賀藩士・大隈重信としてのプロフィールが前面に出ている印象。
豪放磊落(らいらく)とも表現される大隈重信を演じるのは、大倉孝二さん。出演作品ごとに、強いインパクトを残す俳優さんというのが個人的なイメージです。
――しかも、出演者としてのコメントが…
大隈重信役につき「大変なことです」と語り、あえてもう一度「大変なことです」と、念押しまで入れてくる大倉さん。
「明治大正のビックネームである、大隈重信を演じるなんて!」という気持ちが伝わるような、熱い想いを感じるコメントです。
高身長の大倉孝二さん。実際の大隈も180センチほど背丈があったようです。欧米人に劣らない長身は外交にあたる際にも有利に働いたのかもしれません。

――そういえば「ノッポな」東京タワーのある港区。
港区内に、開業時『高輪ゲートウェイ』という名称が話題になった駅があります。その駅の傍で大発見が。
明治初期に、“鉄道の敷設”を先導した大隈重信の決断の“遺構”が出土したのです。半年前ぐらい前には、その発見が報じられていました。
大隈は1870(明治3)年頃、東京・高輪付近に鉄道を通すにあたって“海上”を通るルートを設定。「高輪築堤」整備の命令を出したそうです。
――これは佐賀県としても、タイムリーな話題。
大隈重信の没後100年の記念事業を展開する佐賀県。歴史的価値の高い近代化遺産「高輪築堤」の保存を求めて活動中との報道も見かけました。
1872(明治5)年には新橋~横浜間で日本初の鉄道が開業。当時の“報道写真”である錦絵には、海上の築堤を走る蒸気機関車の姿が描かれています。
現在の田町駅付近から品川駅付近。約2.7キロ分の土地が確保できない状況を見て、大隈は東京湾の浅瀬に堤を築いて線路を敷くことを決断したようです。
堤の側面を固めた四角い石は整然と並び、近代的な“石垣”の姿が残ります。

※大隈重信侯の銅像(佐賀市内)
――なんとも明治期の浪漫(ロマン)が漂う話。
幕末からの激動期、外交ができる人材として新政府に抜擢された大隈重信。
イギリス公使・パークスと真正面から折衝する大隈の姿。「佐賀の大河ドラマ」が実現すれば、ぜひ見たい場面です。
『青天を衝け』では、“大蔵大輔(だゆう)”として大隈が実質的に仕切る大蔵省への出仕を求め、旧・幕臣の渋沢栄一を説得します。
まとめると「大蔵(おおくら)省の大隈(おおくま)を演じる大倉(おおくら)さん…。」わかりやすく説明したつもりが、かえってややこしくなるようです。
――そんな“言葉遊び”は、さておき…
公式サイトで見る限り、弁舌の立つ大隈重信を演じる大倉孝二さん。渋沢栄一との関係性で、必ずしも良くばかりは描いてもらえないかもしれません。
その時は、大隈先生を甘く見ておられる方に“ガツン”と響くような辛口(?)でも良いです。大倉さんの個性を活かした、記憶に残る大隈に期待します。
先日の発表で大河ドラマ『青天を衝け』に待望の佐賀藩士の登場が明らかに。
主人公・渋沢栄一〔演:吉沢亮〕を明治新政府に引っ張り込む役回りですから、この方は出演するはずと確信していました。
――では、新キャストとしての大隈重信の紹介です。
『青天を衝け』を紹介するNHK公式サイトでは佐賀藩士族と記載されています。藩校で騒動を起こして、長崎で英語を勉強してきた…との経歴まで掲載。
https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/449714.html(外部サイト)
わりと佐賀藩士・大隈重信としてのプロフィールが前面に出ている印象。
豪放磊落(らいらく)とも表現される大隈重信を演じるのは、大倉孝二さん。出演作品ごとに、強いインパクトを残す俳優さんというのが個人的なイメージです。
――しかも、出演者としてのコメントが…
大隈重信役につき「大変なことです」と語り、あえてもう一度「大変なことです」と、念押しまで入れてくる大倉さん。
「明治大正のビックネームである、大隈重信を演じるなんて!」という気持ちが伝わるような、熱い想いを感じるコメントです。
高身長の大倉孝二さん。実際の大隈も180センチほど背丈があったようです。欧米人に劣らない長身は外交にあたる際にも有利に働いたのかもしれません。
――そういえば「ノッポな」東京タワーのある港区。
港区内に、開業時『高輪ゲートウェイ』という名称が話題になった駅があります。その駅の傍で大発見が。
明治初期に、“鉄道の敷設”を先導した大隈重信の決断の“遺構”が出土したのです。半年前ぐらい前には、その発見が報じられていました。
大隈は1870(明治3)年頃、東京・高輪付近に鉄道を通すにあたって“海上”を通るルートを設定。「高輪築堤」整備の命令を出したそうです。
――これは佐賀県としても、タイムリーな話題。
大隈重信の没後100年の記念事業を展開する佐賀県。歴史的価値の高い近代化遺産「高輪築堤」の保存を求めて活動中との報道も見かけました。
1872(明治5)年には新橋~横浜間で日本初の鉄道が開業。当時の“報道写真”である錦絵には、海上の築堤を走る蒸気機関車の姿が描かれています。
現在の田町駅付近から品川駅付近。約2.7キロ分の土地が確保できない状況を見て、大隈は東京湾の浅瀬に堤を築いて線路を敷くことを決断したようです。
堤の側面を固めた四角い石は整然と並び、近代的な“石垣”の姿が残ります。
※大隈重信侯の銅像(佐賀市内)
――なんとも明治期の浪漫(ロマン)が漂う話。
幕末からの激動期、外交ができる人材として新政府に抜擢された大隈重信。
イギリス公使・パークスと真正面から折衝する大隈の姿。「佐賀の大河ドラマ」が実現すれば、ぜひ見たい場面です。
『青天を衝け』では、“大蔵大輔(だゆう)”として大隈が実質的に仕切る大蔵省への出仕を求め、旧・幕臣の渋沢栄一を説得します。
まとめると「大蔵(おおくら)省の大隈(おおくま)を演じる大倉(おおくら)さん…。」わかりやすく説明したつもりが、かえってややこしくなるようです。
――そんな“言葉遊び”は、さておき…
公式サイトで見る限り、弁舌の立つ大隈重信を演じる大倉孝二さん。渋沢栄一との関係性で、必ずしも良くばかりは描いてもらえないかもしれません。
その時は、大隈先生を甘く見ておられる方に“ガツン”と響くような辛口(?)でも良いです。大倉さんの個性を活かした、記憶に残る大隈に期待します。
2021年06月09日
「新キャストを考える②」(江藤が不機嫌な理由)
こんばんは。
大河ドラマ『青天を衝け』の新キャストを語るシリーズの第2弾。
本日のタイトルで「え、江藤さん…出とったかね?」と思った方も多いでしょう。今回のキャスト紹介は、私の“空想”とともにお送りしますので、ご容赦ください。
――さて、2人目の新キャスト紹介。
のちの初代内閣総理大臣・伊藤博文を演じるのは、山崎育三郎さん。“ミュージカル界のプリンス”とも呼ばれる山崎さん、大河ドラマは初出演だそうです。
伊藤博文は長州藩で「周旋の才あり」と言われた人物。“周旋”とは、文字通りグルグル巡ること。非常に小回りが効く、仲介者というイメージでしょうか。
――なにゆえ、江藤新平の存在を示唆するのか
論理的で融通の利かない真っ直ぐな人。先述の伊藤博文と対照的に思えます。
幕末期にも、この2人には接点がありました。
この話は、江藤新平が仏頂面で写った肖像写真につながっていきます。佐賀を脱藩して京に上った頃(1862年)から、江藤と長州藩との接点は強まります。

――いつも、服装に気を遣わない江藤。
江藤に着物を手配したり、写真を撮りに連れて行ったことも…と小回りの世話をした人物が、桂小五郎の手下として動いていた伊藤博文だったと言われます。
写真は“ありがた迷惑”だったのか無愛想な表情のものが伝わります。ここで爽やかな笑顔でも見せれば、江藤新平のイメージも随分違ったと思いますが…
この辺りに気を遣わないのが、江藤新平らしさなのかも知れません。おそらくは江藤の方が風変わりな人、伊藤が世間に慣れていると言うべきでしょう。
――“佐賀の七賢人”の中でも…
江藤新平・大木喬任は、わりと長州藩士と関わります。会合を持った場所には久留米などの地名が見えます。現在は福岡県内ですね。
九州を出てすぐの山口県。長州藩士はピンチの時、福岡に駆け込む傾向も見られ、福岡の平野国臣、久留米の真木和泉など、勤王志士の名も知られます。
『青天を衝け』で放送中の年代(1864年頃)では、水戸天狗党の影に隠れていますが、当時は福岡出身の方々も、各地で壮絶な闘いを繰り広げていました。

――時には佐賀だけでなく、九州の話にも引き込みます。
尊王攘夷派との接点少なめの佐賀藩士も、九州者同士だと心安かった(?)のかもしれませんね。
少し話を戻します。幕末に横浜で起きたイギリス公使館襲撃事件(1862年)。この騒動には、伊藤博文も参加。その翌年には密航してイギリスに留学。
日曜放送の『青天を衝け』で一瞬出た「四国艦隊 下関砲撃事件」(1864年)。
――長州藩の使者として登場する2人。
井上馨〔演:福士誠治〕と伊藤博文〔演:山崎育三郎〕。身に付けた英語を使っての交渉でしたがイギリスは説得できず、下関は砲撃されます。
しかし、特筆すべきは「攘夷派から開国派への変わり身が早い…」ことだと思います。この柔軟性が、長州の大きな武器だったのでしょう。

――ここから本日、一番言いたかったことを言います!
今回は演じる対象の人物ではなく、役者さんへの今後の期待を語ります。まず江藤新平の活躍を“フィクション”でも見たいという気持ちを書いた記事から。
〔参照(中盤):「帰らんば、あの世界へ。」〕
私は山崎育三郎さんを「佐賀の大河ドラマ」の主要キャストの有力候補と見ており、今回の発表を見て動揺しました。「…そう来たか」という感じです。
伊藤博文が「周旋の才あり」と言われたことを引き合いに「人と人とのつながりを大切に」演じたいと語る、山崎さん。これからの出演も楽しみなのですが…
――私は、すでに“次の展開”を見据えていたりします…
“ミュージカル界のプリンス”との異名を持つ、山崎育三郎さん。以前から私は、江藤新平の生涯が舞台の題材として“映える”と確信してます。
〔参照(中盤②):「“女性の活躍”をどう描くか?」(関係性①)〕
まずは「大河ドラマ」で見たい、いずれミュージカルの名作に。「もし、この方が江藤を演じる機会があれば…」そんな展開も夢ではないと思うのです。
『青天を衝け』に「佐賀の大河ドラマ」への想いを重ねる私。純粋な「大河ドラマ」のファンとしては、『麒麟がくる』の方が集中できていたのかもしれません…
〔参照:「二つの感想」〕
大河ドラマ『青天を衝け』の新キャストを語るシリーズの第2弾。
本日のタイトルで「え、江藤さん…出とったかね?」と思った方も多いでしょう。今回のキャスト紹介は、私の“空想”とともにお送りしますので、ご容赦ください。
――さて、2人目の新キャスト紹介。
のちの初代内閣総理大臣・伊藤博文を演じるのは、山崎育三郎さん。“ミュージカル界のプリンス”とも呼ばれる山崎さん、大河ドラマは初出演だそうです。
伊藤博文は長州藩で「周旋の才あり」と言われた人物。“周旋”とは、文字通りグルグル巡ること。非常に小回りが効く、仲介者というイメージでしょうか。
――なにゆえ、江藤新平の存在を示唆するのか
論理的で融通の利かない真っ直ぐな人。先述の伊藤博文と対照的に思えます。
幕末期にも、この2人には接点がありました。
この話は、江藤新平が仏頂面で写った肖像写真につながっていきます。佐賀を脱藩して京に上った頃(1862年)から、江藤と長州藩との接点は強まります。
――いつも、服装に気を遣わない江藤。
江藤に着物を手配したり、写真を撮りに連れて行ったことも…と小回りの世話をした人物が、桂小五郎の手下として動いていた伊藤博文だったと言われます。
写真は“ありがた迷惑”だったのか無愛想な表情のものが伝わります。ここで爽やかな笑顔でも見せれば、江藤新平のイメージも随分違ったと思いますが…
この辺りに気を遣わないのが、江藤新平らしさなのかも知れません。おそらくは江藤の方が風変わりな人、伊藤が世間に慣れていると言うべきでしょう。
――“佐賀の七賢人”の中でも…
江藤新平・大木喬任は、わりと長州藩士と関わります。会合を持った場所には久留米などの地名が見えます。現在は福岡県内ですね。
九州を出てすぐの山口県。長州藩士はピンチの時、福岡に駆け込む傾向も見られ、福岡の平野国臣、久留米の真木和泉など、勤王志士の名も知られます。
『青天を衝け』で放送中の年代(1864年頃)では、水戸天狗党の影に隠れていますが、当時は福岡出身の方々も、各地で壮絶な闘いを繰り広げていました。
――時には佐賀だけでなく、九州の話にも引き込みます。
尊王攘夷派との接点少なめの佐賀藩士も、九州者同士だと心安かった(?)のかもしれませんね。
少し話を戻します。幕末に横浜で起きたイギリス公使館襲撃事件(1862年)。この騒動には、伊藤博文も参加。その翌年には密航してイギリスに留学。
日曜放送の『青天を衝け』で一瞬出た「四国艦隊 下関砲撃事件」(1864年)。
――長州藩の使者として登場する2人。
井上馨〔演:福士誠治〕と伊藤博文〔演:山崎育三郎〕。身に付けた英語を使っての交渉でしたがイギリスは説得できず、下関は砲撃されます。
しかし、特筆すべきは「攘夷派から開国派への変わり身が早い…」ことだと思います。この柔軟性が、長州の大きな武器だったのでしょう。
――ここから本日、一番言いたかったことを言います!
今回は演じる対象の人物ではなく、役者さんへの今後の期待を語ります。まず江藤新平の活躍を“フィクション”でも見たいという気持ちを書いた記事から。
〔参照(中盤):
私は山崎育三郎さんを「佐賀の大河ドラマ」の主要キャストの有力候補と見ており、今回の発表を見て動揺しました。「…そう来たか」という感じです。
伊藤博文が「周旋の才あり」と言われたことを引き合いに「人と人とのつながりを大切に」演じたいと語る、山崎さん。これからの出演も楽しみなのですが…
――私は、すでに“次の展開”を見据えていたりします…
“ミュージカル界のプリンス”との異名を持つ、山崎育三郎さん。以前から私は、江藤新平の生涯が舞台の題材として“映える”と確信してます。
〔参照(中盤②):
まずは「大河ドラマ」で見たい、いずれミュージカルの名作に。「もし、この方が江藤を演じる機会があれば…」そんな展開も夢ではないと思うのです。
『青天を衝け』に「佐賀の大河ドラマ」への想いを重ねる私。純粋な「大河ドラマ」のファンとしては、『麒麟がくる』の方が集中できていたのかもしれません…
〔参照:
2021年06月04日
「新キャストを考える①」(“明治の父”の1人)
こんばんは。
5月27日に発表された、大河ドラマ『青天を衝け』の新キャスト。非常に個性的な3人の役者さんで、気になる人物が配役されています。
――さて、1人目の新キャスト。
江戸幕府・勘定奉行の小栗忠順(おぐり ただまさ)。「上野介(こうずけのすけ)」の名でも知られます。
演じるのはNHKでは『みんなで筋肉体操』でお馴染みの武田真治さん。
小栗さまは、1860(万延元)年。幕府の使節団としてアメリカに渡った方。海外で造船所など進んだ近代産業を目にして、世界一周のうえで帰国します。
――私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」“本編”では…
第14話「遣米使節」で、この1860年の使節団を題材にしました。
〔参照(後半):第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)〕
使節団に同行した小出千之助や川崎道民など佐賀藩士の視点で書きますので、幕府の“目付”である小栗さまの活躍は、まだ描けていなかったと思います。
ちなみに第16話「攘夷沸騰」では、外国奉行の立場で登場予定にしています。

――“開国”の当時から、問題になっていた…
日本と外国との金銀の交換比率の差で、国内から大量の金が流出しました。小栗はアメリカで“近代”に驚く一方で、通貨の外交交渉も行ったそうです。
アメリカへの出発時点、幕府の大老は井伊直弼。小栗忠順の優秀さを知って、使節団に抜擢を判断します。
“桜田門外の変”を描くとき、命を落とすことを悟った井伊さまが「世界を廻って来た者」を想う場面を表現しました。
〔参照(終盤):第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕
――この時、井伊が期待をした人物…
“近代化”に突き進む佐賀への期待を感じさせつつも、やはり直接的には「幕府側で近代化を進める小栗忠順」が念頭にあるだろう…という感覚で書きました。
実際、小栗は帰国してから凄い活躍を見せてます。
幕府の財政再建と紙幣発行、洋式軍制の整備、製鉄所や造船所の建設。“総合商社”(兵庫商社)も計画し、その実現は“三井”に引き継がれたようです。
ちなみに『青天を衝け』で井伊直弼を演じた岸谷五朗さんが、主役・小栗忠順を演じたドラマがあったとか…見たかった。

――そして、あの方も小栗さまを大絶賛。
「明治の近代化は、ほとんど小栗忠順の模倣に過ぎない」と。大隈重信は、そこまで評価したようです。
たしかに小栗が幕府で行った功績は、明治の新時代に引き継がれています。『青天を衝け』でも、渋沢栄一に大きい影響を与える役回りだとか。
――戊辰戦争の際、小栗忠順は新政府軍との対決を主張。
小栗には勝算がありました。敵の退路を完全に断ち、袋叩きにできる作戦が。しかし、幕府は戦闘を回避。小栗の意見は通りませんでした。
新政府軍の参謀たちは、小栗が立案していた作戦を知った時「この作戦を実行されたら、命が無かった…」と肝を冷やしたようです。
あまりの切れ者で恐れられたのか、小栗は罪状が不明瞭なまま処刑されます。
――先ほど、チラッと登場した大隈重信。
小栗忠順を絶賛する大隈。実は小栗の娘を、明治期に大隈家が保護します。これは大隈の妻・綾子が、小栗の親戚筋(いとこ)だったためだそうです。
最期まで幕府を裏切らず、忠誠を尽くして近代化に当たった小栗忠順。
「筋肉は裏切らない…」が決めゼリフの番組の主役・武田真治さんが、どんな演技を見せてくれるか楽しみです。
5月27日に発表された、大河ドラマ『青天を衝け』の新キャスト。非常に個性的な3人の役者さんで、気になる人物が配役されています。
――さて、1人目の新キャスト。
江戸幕府・勘定奉行の小栗忠順(おぐり ただまさ)。「上野介(こうずけのすけ)」の名でも知られます。
演じるのはNHKでは『みんなで筋肉体操』でお馴染みの武田真治さん。
小栗さまは、1860(万延元)年。幕府の使節団としてアメリカに渡った方。海外で造船所など進んだ近代産業を目にして、世界一周のうえで帰国します。
――私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」“本編”では…
第14話「遣米使節」で、この1860年の使節団を題材にしました。
〔参照(後半):
使節団に同行した小出千之助や川崎道民など佐賀藩士の視点で書きますので、幕府の“目付”である小栗さまの活躍は、まだ描けていなかったと思います。
ちなみに第16話「攘夷沸騰」では、外国奉行の立場で登場予定にしています。
――“開国”の当時から、問題になっていた…
日本と外国との金銀の交換比率の差で、国内から大量の金が流出しました。小栗はアメリカで“近代”に驚く一方で、通貨の外交交渉も行ったそうです。
アメリカへの出発時点、幕府の大老は井伊直弼。小栗忠順の優秀さを知って、使節団に抜擢を判断します。
“桜田門外の変”を描くとき、命を落とすことを悟った井伊さまが「世界を廻って来た者」を想う場面を表現しました。
〔参照(終盤):
――この時、井伊が期待をした人物…
“近代化”に突き進む佐賀への期待を感じさせつつも、やはり直接的には「幕府側で近代化を進める小栗忠順」が念頭にあるだろう…という感覚で書きました。
実際、小栗は帰国してから凄い活躍を見せてます。
幕府の財政再建と紙幣発行、洋式軍制の整備、製鉄所や造船所の建設。“総合商社”(兵庫商社)も計画し、その実現は“三井”に引き継がれたようです。
ちなみに『青天を衝け』で井伊直弼を演じた岸谷五朗さんが、主役・小栗忠順を演じたドラマがあったとか…見たかった。
――そして、あの方も小栗さまを大絶賛。
「明治の近代化は、ほとんど小栗忠順の模倣に過ぎない」と。大隈重信は、そこまで評価したようです。
たしかに小栗が幕府で行った功績は、明治の新時代に引き継がれています。『青天を衝け』でも、渋沢栄一に大きい影響を与える役回りだとか。
――戊辰戦争の際、小栗忠順は新政府軍との対決を主張。
小栗には勝算がありました。敵の退路を完全に断ち、袋叩きにできる作戦が。しかし、幕府は戦闘を回避。小栗の意見は通りませんでした。
新政府軍の参謀たちは、小栗が立案していた作戦を知った時「この作戦を実行されたら、命が無かった…」と肝を冷やしたようです。
あまりの切れ者で恐れられたのか、小栗は罪状が不明瞭なまま処刑されます。
――先ほど、チラッと登場した大隈重信。
小栗忠順を絶賛する大隈。実は小栗の娘を、明治期に大隈家が保護します。これは大隈の妻・綾子が、小栗の親戚筋(いとこ)だったためだそうです。
最期まで幕府を裏切らず、忠誠を尽くして近代化に当たった小栗忠順。
「筋肉は裏切らない…」が決めゼリフの番組の主役・武田真治さんが、どんな演技を見せてくれるか楽しみです。
2021年06月02日
「二つの感想」
こんばんは。
大河ドラマ『青天を衝け』。日曜の放送(第16回「恩人暗殺」)が凄かったので、感想を書いてみます。主な舞台は、とても危険だった1864年頃の京都でした。
ここで私は二つの立場を持つ者。普通の「大河ドラマ」の視聴者であると同時に、近いうちに「佐賀の“大河ドラマ”を見たい人」でもあります。
ちなみに主人公・渋沢栄一〔演:吉沢亮〕は現在の劇中では“篤太夫”の名で登場しますが、文章中では“栄一”で通します。また、配役のお名前は敬称略です。

※幕末の舞台:京都(三条大橋)
〇普通の「大河ドラマ」視聴者としての感想。
脚本の大森美香さん、朝の連続テレビ小説『あさが来た』での評判は聞いていました。やはり女性の描き方が違う…と感じる回でした。まずは、子を想う母の姿。
地元の岡部藩陣屋に呼び出された長兄・尾高惇忠〔演:田辺誠一〕の身を案じ、祈り続ける母・尾高やへ〔演:手塚理美〕。
取り調べの手は、まだ若い末弟・平九郎〔演:岡田健史〕にまで及び、母・やへと、姉(渋沢栄一の妻)・千代〔演:橋本愛〕の前で、役人に連行されていきます。
――“我が子”が、次々と連れ去られる母の苦しみ。
次兄・長七郎〔演:満島真之介〕も、人を斬った咎(とが)で牢に入ったまま。
一体、なぜこのような事に。部屋を見渡すと、子供たちが感化された水戸藩の“尊王攘夷”を示す書画の数々。
母は手を伸ばし、我が子の心を奪った「“尊攘”の思想」を「“水戸烈公”の姿絵」を手当たり次第に破り捨てます。
「水戸が、憎い…憎いよ。」
この言葉を発する、母・やへの目に、深い悲しみと“狂気”すら感じます。
――この場面には、圧倒されました。
おそらく脚本と役者。双方の力量なのでしょう。この“母の愛”の表現。志士たちを演じる役者を超える熱量まで感じました。
…ひとまず末弟・平九郎は“手鎖”をはめられるものの帰宅となります。
ここで、栄一の妹・渋沢てい〔演:藤野涼子〕が様子見に来る姿が描かれます。なかなか良い感じの“恋人未満”な雰囲気。
まぁ、凄まじい回でしたから、ホッと出来たのは、ここぐらいでした…

※幕末の舞台:京都(三条小橋・“池田屋”付近)
〇「佐賀の大河ドラマ」を見たい人としての感想。
ここからは、普通じゃない私の「大河ドラマ」の見方をお伝えします。
常々、私なりに「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の配役を考えています。ちなみに、何のコネクションもありませんので、ただの“空想”とお考えください。
第16回はそのタイトルが示すように、この話は渋沢栄一の恩人・平岡円四郎〔演:堤真一〕の悲劇を描きます。
――以前から、当ブログをご覧の方は…
私が“堤真一さん”に向けている視線に、お気づきではないでしょうか。
〔参照(後半③):「“青天”に呟く…」〕
しかし、私は劇中の「鋭い目の水戸藩の刺客」とはまったく違います。刃傷沙汰とはかなり遠めの佐賀藩士(?)なので。むしろ熱い期待が込められています。
皆様にも「佐賀の大河ドラマ」が実現した時の、配役のイメージを持っている方がいるかもしれません。少し感想から離れて、現時点の私の“空想”を語ります。
私が“大河”で見たい殿・鍋島直正公は、当然、“主役”クラス。演じるのに適した役者さんは限られます。『青天を衝け』で見た堤さんは、まさに主役の器でした。
――私が考える、佐賀の殿・直正公を演じてほしい方。
・明朗さと神経質の、二面性を表現できる
・槍でも振り回せるアクションへの適応力
・経営者や、管理職を演じて魅力的な人物
愛娘との手紙のやり取りで嬉々とする可愛らしい父親かと思えば、蒸気軍艦で海を駆けて“肥前の妖怪”と恐れられるわけですから、並大抵ではありません。
――そして、極めつけの希望が…
「“痔”(じ)でござってな。」
このセリフをカッコ良く決められること。堤真一さんならば可能だと思います。
幕末期。佐賀の殿様・鍋島直正公は何度も、幕閣から呼び出しを受けます。
しかし、ある時は長崎警備を、ある時は“健康上の理由”で動こうとはしません。
“幕末最強”との評価もある佐賀藩が動く時、“力の均衡”は崩れ去るのです。
――「この国を…、何より家来や領民たちを守りたい。」
佐賀の殿様が見ていたのは、日本の国内だけではありません。隙を見せれば、列強各国に介入される…これも幕末です。
先ほどのセリフ。“健康上の理由”で幕府の出頭要請を断った言葉だそうです。しかし、私は「何とか国内の騒乱を避けねば」という殿の深い愛を読むのです。
…純粋な『青天を衝け』ファンの方々、話が横道に逸れて申し訳ございません。私はいまの「大河ドラマ」を見つめても、“佐賀”への目線を忘れないのです。
――そして、ドラマ終盤で描かれる、平岡円四郎の最期。
平岡円四郎〔演:堤真一〕と、妻・やす〔演:木村佳乃〕との距離を隔てた別れ。
「おかしろくもねぇときは、掛け軸の小鳥にでも話しかけろ…ってな。」
渋沢栄一〔演:吉沢亮〕に託していた、こんな言葉が涙を誘います。
…非常に雑念が多くて頭の忙しい視聴ですが、今回も見応え充分でした!
大河ドラマ『青天を衝け』。日曜の放送(第16回「恩人暗殺」)が凄かったので、感想を書いてみます。主な舞台は、とても危険だった1864年頃の京都でした。
ここで私は二つの立場を持つ者。普通の「大河ドラマ」の視聴者であると同時に、近いうちに「佐賀の“大河ドラマ”を見たい人」でもあります。
ちなみに主人公・渋沢栄一〔演:吉沢亮〕は現在の劇中では“篤太夫”の名で登場しますが、文章中では“栄一”で通します。また、配役のお名前は敬称略です。
※幕末の舞台:京都(三条大橋)
〇普通の「大河ドラマ」視聴者としての感想。
脚本の大森美香さん、朝の連続テレビ小説『あさが来た』での評判は聞いていました。やはり女性の描き方が違う…と感じる回でした。まずは、子を想う母の姿。
地元の岡部藩陣屋に呼び出された長兄・尾高惇忠〔演:田辺誠一〕の身を案じ、祈り続ける母・尾高やへ〔演:手塚理美〕。
取り調べの手は、まだ若い末弟・平九郎〔演:岡田健史〕にまで及び、母・やへと、姉(渋沢栄一の妻)・千代〔演:橋本愛〕の前で、役人に連行されていきます。
――“我が子”が、次々と連れ去られる母の苦しみ。
次兄・長七郎〔演:満島真之介〕も、人を斬った咎(とが)で牢に入ったまま。
一体、なぜこのような事に。部屋を見渡すと、子供たちが感化された水戸藩の“尊王攘夷”を示す書画の数々。
母は手を伸ばし、我が子の心を奪った「“尊攘”の思想」を「“水戸烈公”の姿絵」を手当たり次第に破り捨てます。
「水戸が、憎い…憎いよ。」
この言葉を発する、母・やへの目に、深い悲しみと“狂気”すら感じます。
――この場面には、圧倒されました。
おそらく脚本と役者。双方の力量なのでしょう。この“母の愛”の表現。志士たちを演じる役者を超える熱量まで感じました。
…ひとまず末弟・平九郎は“手鎖”をはめられるものの帰宅となります。
ここで、栄一の妹・渋沢てい〔演:藤野涼子〕が様子見に来る姿が描かれます。なかなか良い感じの“恋人未満”な雰囲気。
まぁ、凄まじい回でしたから、ホッと出来たのは、ここぐらいでした…
※幕末の舞台:京都(三条小橋・“池田屋”付近)
〇「佐賀の大河ドラマ」を見たい人としての感想。
ここからは、普通じゃない私の「大河ドラマ」の見方をお伝えします。
常々、私なりに「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の配役を考えています。ちなみに、何のコネクションもありませんので、ただの“空想”とお考えください。
第16回はそのタイトルが示すように、この話は渋沢栄一の恩人・平岡円四郎〔演:堤真一〕の悲劇を描きます。
――以前から、当ブログをご覧の方は…
私が“堤真一さん”に向けている視線に、お気づきではないでしょうか。
〔参照(後半③):
しかし、私は劇中の「鋭い目の水戸藩の刺客」とはまったく違います。刃傷沙汰とはかなり遠めの佐賀藩士(?)なので。むしろ熱い期待が込められています。
皆様にも「佐賀の大河ドラマ」が実現した時の、配役のイメージを持っている方がいるかもしれません。少し感想から離れて、現時点の私の“空想”を語ります。
私が“大河”で見たい殿・鍋島直正公は、当然、“主役”クラス。演じるのに適した役者さんは限られます。『青天を衝け』で見た堤さんは、まさに主役の器でした。
――私が考える、佐賀の殿・直正公を演じてほしい方。
・明朗さと神経質の、二面性を表現できる
・槍でも振り回せるアクションへの適応力
・経営者や、管理職を演じて魅力的な人物
愛娘との手紙のやり取りで嬉々とする可愛らしい父親かと思えば、蒸気軍艦で海を駆けて“肥前の妖怪”と恐れられるわけですから、並大抵ではありません。
――そして、極めつけの希望が…
「“痔”(じ)でござってな。」
このセリフをカッコ良く決められること。堤真一さんならば可能だと思います。
幕末期。佐賀の殿様・鍋島直正公は何度も、幕閣から呼び出しを受けます。
しかし、ある時は長崎警備を、ある時は“健康上の理由”で動こうとはしません。
“幕末最強”との評価もある佐賀藩が動く時、“力の均衡”は崩れ去るのです。
――「この国を…、何より家来や領民たちを守りたい。」
佐賀の殿様が見ていたのは、日本の国内だけではありません。隙を見せれば、列強各国に介入される…これも幕末です。
先ほどのセリフ。“健康上の理由”で幕府の出頭要請を断った言葉だそうです。しかし、私は「何とか国内の騒乱を避けねば」という殿の深い愛を読むのです。
…純粋な『青天を衝け』ファンの方々、話が横道に逸れて申し訳ございません。私はいまの「大河ドラマ」を見つめても、“佐賀”への目線を忘れないのです。
――そして、ドラマ終盤で描かれる、平岡円四郎の最期。
平岡円四郎〔演:堤真一〕と、妻・やす〔演:木村佳乃〕との距離を隔てた別れ。
「おかしろくもねぇときは、掛け軸の小鳥にでも話しかけろ…ってな。」
渋沢栄一〔演:吉沢亮〕に託していた、こんな言葉が涙を誘います。
…非常に雑念が多くて頭の忙しい視聴ですが、今回も見応え充分でした!
2021年04月25日
「大河よ、共に」
こんばんは。
今年の大河ドラマ「青天を衝け」。毎回、徳川家康が登場することもあってか(?)、江戸幕府の描き方がなかなか好評のようです。
〔参照:「茶歌(ちゃか)ポン。」〕
――遅くなりましたが、青天版「桜田門外の変」を振り返ります。
幕政を仕切る大老が、白昼に江戸城の門前で暗殺される事件。映像の構成が予想外でした。
謹慎中の水戸藩・徳川斉昭が雪の庭で、家族と穏やかに語らう場面に始まり、一方、“水戸さま”を謹慎させた大老・井伊直弼は、駕籠(かご)で江戸城へ。
駕籠で移動中に読んでいる書物は、一流の文化人でもあった井伊直弼が、自ら創った新作狂言「鬼ケ宿」の“台本”です。
――その狂言のイメージも映像で流れます。
こうして水戸の庭での雪景色、大老・井伊直弼の登城、狂言「鬼ケ宿」の舞台。3つの映像が並行して展開します。
江戸城への短い道のり、井伊直弼の周囲に異変が起きます。乾いたピストルの発射音、井伊の持つ台本は血に染まりました。
――息を飲むような展開。さすがの映像構成。
「…これを文章で描くなら、どう書いたら良いんだろうか?」
レベルの問題はあれ、私の“書く側”の立場での感想です。
ちなみに、この場面を私が描くとこうなります。
〔参照:第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕

――“大河”の時代は進み、今日の放送では1863年…
今のところ、私が“本編”で描けているのは、この辺り(1860年の春頃)まで。
〔参照:第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕
「桜田門外の変」の後、井伊直弼と親しかった佐賀藩主・鍋島直正への襲撃を計画しているグループもあるとの情報が流れました。
幕閣には佐賀藩を政権に取り込み、難局を打開するという動きもあり、安全な立ち位置ではありません。佐賀藩士たちは急ぎ殿・直正への警護を固めます。
――「もしや、ここで“第1部”は完結しているのでは…?」
1808年に長崎で起きたフェートン号事件での大失態から、佐賀では異国に危機感を持つ人たちが頑張ってきました。
教育係(古賀穀堂)は佐賀を救う策を練り始め、幼い若君(鍋島直正)に期待。武雄領主(鍋島茂義)は、長崎に家来を派遣し、西洋砲術の導入を進めます。
佐賀藩士たちは、諸国を駆けます。殿の期待のもと必死で学び、行動してきた藩士たちの努力は、日本の近代化につながって行くのですが…
――「第1話から、50年ほどが経過」した、この時点。
「幕末の分水嶺」とも語られるほどの“大きな変化”の時期。それまでは幕府に協力的な“優等生”として、異国に睨みを利かせ、近代化を進めてきた佐賀藩。
ここで井伊直弼という強い幕府との接点を失って、状況は混沌としていきます。
こうして佐賀は“独自路線”を歩むこととなり、殿・鍋島直正は真意の読めない「肥前の妖怪」と語られるに至るようです。
※以下、本日のおまけ
今日の記事タイトルは、以前、紹介したアニメの主題歌が“ネタ元”です。
これが「大河よ共に泣いてくれ」というタイトルなのですね。意味深に感じられてゾクッとしました。もし、共感していただける方がいれば幸いです。
〔関連記事:清々しいほどの佐賀“推し”,「再起の剣」(後半)〕
今年の大河ドラマ「青天を衝け」。毎回、徳川家康が登場することもあってか(?)、江戸幕府の描き方がなかなか好評のようです。
〔参照:
――遅くなりましたが、青天版「桜田門外の変」を振り返ります。
幕政を仕切る大老が、白昼に江戸城の門前で暗殺される事件。映像の構成が予想外でした。
謹慎中の水戸藩・徳川斉昭が雪の庭で、家族と穏やかに語らう場面に始まり、一方、“水戸さま”を謹慎させた大老・井伊直弼は、駕籠(かご)で江戸城へ。
駕籠で移動中に読んでいる書物は、一流の文化人でもあった井伊直弼が、自ら創った新作狂言「鬼ケ宿」の“台本”です。
――その狂言のイメージも映像で流れます。
こうして水戸の庭での雪景色、大老・井伊直弼の登城、狂言「鬼ケ宿」の舞台。3つの映像が並行して展開します。
江戸城への短い道のり、井伊直弼の周囲に異変が起きます。乾いたピストルの発射音、井伊の持つ台本は血に染まりました。
――息を飲むような展開。さすがの映像構成。
「…これを文章で描くなら、どう書いたら良いんだろうか?」
レベルの問題はあれ、私の“書く側”の立場での感想です。
ちなみに、この場面を私が描くとこうなります。
〔参照:
――“大河”の時代は進み、今日の放送では1863年…
今のところ、私が“本編”で描けているのは、この辺り(1860年の春頃)まで。
〔参照:
「桜田門外の変」の後、井伊直弼と親しかった佐賀藩主・鍋島直正への襲撃を計画しているグループもあるとの情報が流れました。
幕閣には佐賀藩を政権に取り込み、難局を打開するという動きもあり、安全な立ち位置ではありません。佐賀藩士たちは急ぎ殿・直正への警護を固めます。
――「もしや、ここで“第1部”は完結しているのでは…?」
1808年に長崎で起きたフェートン号事件での大失態から、佐賀では異国に危機感を持つ人たちが頑張ってきました。
教育係(古賀穀堂)は佐賀を救う策を練り始め、幼い若君(鍋島直正)に期待。武雄領主(鍋島茂義)は、長崎に家来を派遣し、西洋砲術の導入を進めます。
佐賀藩士たちは、諸国を駆けます。殿の期待のもと必死で学び、行動してきた藩士たちの努力は、日本の近代化につながって行くのですが…
――「第1話から、50年ほどが経過」した、この時点。
「幕末の分水嶺」とも語られるほどの“大きな変化”の時期。それまでは幕府に協力的な“優等生”として、異国に睨みを利かせ、近代化を進めてきた佐賀藩。
ここで井伊直弼という強い幕府との接点を失って、状況は混沌としていきます。
こうして佐賀は“独自路線”を歩むこととなり、殿・鍋島直正は真意の読めない「肥前の妖怪」と語られるに至るようです。
※以下、本日のおまけ
今日の記事タイトルは、以前、紹介したアニメの主題歌が“ネタ元”です。
これが「大河よ共に泣いてくれ」というタイトルなのですね。意味深に感じられてゾクッとしました。もし、共感していただける方がいれば幸いです。
〔関連記事:
2021年04月06日
「茶歌(ちゃか)ポン。」
こんばんは。
2回続けて大河ドラマ『青天を衝け』の感想です。
冒頭は渋沢栄一の恋物語で展開しましたが、今回の注目は大老・井伊直弼。
楽し気に自分が見た“青天”の景色を語る、栄一。
キラキラした栄一を、優し気に見つめる、千代。
――盛り上がる若い2人の眼前。なぜか、タヌキ(?)も現れる。
「これは、何の前振りなんだ…!?」
テレビの前で、私は困惑します。
オープニングの後、「タヌキ親父」とも揶揄(やゆ)された、徳川家康が登場。
そこで、彦根藩主・井伊直弼の渾名(あだな)が披露されます。
――井伊直弼は「茶歌(ちゃか)ポン」と呼ばれた…と。
茶の湯、和歌に通じた文化人・井伊直弼。幕府の官僚からは、甘く見られます。
しかし、幕府官僚たちの思惑は外れ、井伊は大老への就任後、卓越した決断力を発揮します。禅の修行を積み、居合の達人でもあったのですね。

――“青天”で井伊直弼を、演じるのは岸谷五朗さん。
私が見てみたいのは、佐賀藩主・鍋島直正と意気投合する“強い”井伊直弼。
しかし、紹介から「茶歌(ちゃか)ポン」と愛らしい呼び名。まずは、第13代将軍・徳川家定の屈折した想いから、重責を担うことになる展開で描かれました。
将軍の手ずから和菓子をいただき、その食べっぷりで大老に任命された感じ。
――さて、岸谷版・井伊直弼の魅力を語ります。
周囲からの評価は低く、やや小心者という設定を強調して進みます。
〇通商条約調印…まさか勅許なしで調印するとは思わなかった!と驚きながらも、幕政の実務トップとして周囲からのお叱りは受け止める。
〇将軍継嗣問題…ひたすら「畏(おそ)れ入って」から、一橋慶喜(演:草彅剛)の様子を伺う。
慶喜が「私も次期将軍を一緒に支えよう!」と言われ、ホッと胸をなでおろす。あとで「良かった~」と、畳に寝ころぶ井伊直弼。
――「なんだ!?この妙に愛くるしい井伊大老は…」
“青天”の井伊は、将軍・徳川家定の想いを大事にする「愚直な忠義者」という要素が強いようです。
虚弱だったがゆえに、幕臣から相手にされない将軍の悲しみ。マジメな岸谷版・井伊直弼は、全てを受け止めます。
井伊は、世を去った将軍・家定の遺志を忠実に守り、次々と大名・官僚を処罰。穏やかだった「茶歌ポン」とは違う姿になっていきました。
――何だか「悲しい匂いがする…」と言いたくなります。
とくに尊王攘夷派を敵に回し、もはや「赤鬼」と忌み嫌われる「茶歌ポン」。
いつになく、“良い人”設定の井伊直弼。岸谷五朗さんの演技も期待以上です。来週は辛い展開になりそうですが、見届けたいと思います。
2回続けて大河ドラマ『青天を衝け』の感想です。
冒頭は渋沢栄一の恋物語で展開しましたが、今回の注目は大老・井伊直弼。
楽し気に自分が見た“青天”の景色を語る、栄一。
キラキラした栄一を、優し気に見つめる、千代。
――盛り上がる若い2人の眼前。なぜか、タヌキ(?)も現れる。
「これは、何の前振りなんだ…!?」
テレビの前で、私は困惑します。
オープニングの後、「タヌキ親父」とも揶揄(やゆ)された、徳川家康が登場。
そこで、彦根藩主・井伊直弼の渾名(あだな)が披露されます。
――井伊直弼は「茶歌(ちゃか)ポン」と呼ばれた…と。
茶の湯、和歌に通じた文化人・井伊直弼。幕府の官僚からは、甘く見られます。
しかし、幕府官僚たちの思惑は外れ、井伊は大老への就任後、卓越した決断力を発揮します。禅の修行を積み、居合の達人でもあったのですね。
――“青天”で井伊直弼を、演じるのは岸谷五朗さん。
私が見てみたいのは、佐賀藩主・鍋島直正と意気投合する“強い”井伊直弼。
しかし、紹介から「茶歌(ちゃか)ポン」と愛らしい呼び名。まずは、第13代将軍・徳川家定の屈折した想いから、重責を担うことになる展開で描かれました。
将軍の手ずから和菓子をいただき、その食べっぷりで大老に任命された感じ。
――さて、岸谷版・井伊直弼の魅力を語ります。
周囲からの評価は低く、やや小心者という設定を強調して進みます。
〇通商条約調印…まさか勅許なしで調印するとは思わなかった!と驚きながらも、幕政の実務トップとして周囲からのお叱りは受け止める。
〇将軍継嗣問題…ひたすら「畏(おそ)れ入って」から、一橋慶喜(演:草彅剛)の様子を伺う。
慶喜が「私も次期将軍を一緒に支えよう!」と言われ、ホッと胸をなでおろす。あとで「良かった~」と、畳に寝ころぶ井伊直弼。
――「なんだ!?この妙に愛くるしい井伊大老は…」
“青天”の井伊は、将軍・徳川家定の想いを大事にする「愚直な忠義者」という要素が強いようです。
虚弱だったがゆえに、幕臣から相手にされない将軍の悲しみ。マジメな岸谷版・井伊直弼は、全てを受け止めます。
井伊は、世を去った将軍・家定の遺志を忠実に守り、次々と大名・官僚を処罰。穏やかだった「茶歌ポン」とは違う姿になっていきました。
――何だか「悲しい匂いがする…」と言いたくなります。
とくに尊王攘夷派を敵に回し、もはや「赤鬼」と忌み嫌われる「茶歌ポン」。
いつになく、“良い人”設定の井伊直弼。岸谷五朗さんの演技も期待以上です。来週は辛い展開になりそうですが、見届けたいと思います。
タグ :大河ドラマ
2021年04月04日
「“青天”のヒロイン」
こんばんは。
久しぶりの「青天を衝け」の感想ですが、今回はドラマ要素に注目しました。あまり語って来なかった、主人公・渋沢栄一(演:吉沢亮)周辺の話から。
写真は掲載しませんので、大河ドラマの余韻とともに、ご覧ください…
――冒頭で、栄一と尾高千代(演:橋本愛)との物語が展開します。
演じる女優さんに関連して、2013年朝ドラ『あまちゃん』に話を引っ張ります。
岩手・三陸海岸で魅力を開花させ、東京に戻った主人公・アキ(演:能年玲奈)に対して、不運が重なり地元に残ったユイ(演:橋本愛)。
地元を早く出て、憧れの都会で才能を発揮したい…主人公の親友であり、内心ではライバルでもある、屈折した感情の役回り。
――2人の関係性は、まるで「太陽と月」。
物語の展開に沿ってクール…というより鋭い存在感を示し始めた、ユイちゃん。
東京に出たかった少女は、現地で大災害に直面。地元の人とともに乗り越えていく立場になっていきます。
準主役として強い印象を残した橋本愛さん。近年は大河ドラマでよく見かけます。2018年『西郷どん』、2019年『いだてん』と立て続けに出演していました。
――ついに『青天を衝け』では、大河ドラマのヒロインに。
栄一(吉沢亮)と渋沢喜作(演:高良健吾)の2人が、千代(橋本愛)をめぐって、剣術の試合で勝負します。
激しい竹刀での打ち合い。幼少期から密かにアイドルだった女子の面前。もう、その想いは隠すことなく、火花を散らすイケメン2人。
――そして、ここで“真の勝者”が現れます。
周囲も盛り上がる、熱戦の最中。渋沢喜作(高良健吾)の方と縁談が進んでいた“よし”(演:成海璃子)が登場。
…よし(成海璃子)が、突然に喜作の応援を始めたことで、場の空気が一変。
千代(橋本愛)も、内心を吐露して栄一(吉沢亮)に声援を送ります。
――これで“勝負あり”。
剣術の試合とは、まったく違う次元で決着は付きました。
こうして栄一と千代(吉沢亮と橋本愛)。喜作とよし(高良健吾と成海璃子)。目にも優しい、美男美女のカップルが2組誕生しました。
――めでたし、めでたし…
…しかし、今回は書くうちに予定外の内容になりました。
もともとは、井伊直弼(演:岸谷五朗)の描き方について語るつもりが、前置きで話がまとまってしまったので、また改めたいと思います。
久しぶりの「青天を衝け」の感想ですが、今回はドラマ要素に注目しました。あまり語って来なかった、主人公・渋沢栄一(演:吉沢亮)周辺の話から。
写真は掲載しませんので、大河ドラマの余韻とともに、ご覧ください…
――冒頭で、栄一と尾高千代(演:橋本愛)との物語が展開します。
演じる女優さんに関連して、2013年朝ドラ『あまちゃん』に話を引っ張ります。
岩手・三陸海岸で魅力を開花させ、東京に戻った主人公・アキ(演:能年玲奈)に対して、不運が重なり地元に残ったユイ(演:橋本愛)。
地元を早く出て、憧れの都会で才能を発揮したい…主人公の親友であり、内心ではライバルでもある、屈折した感情の役回り。
――2人の関係性は、まるで「太陽と月」。
物語の展開に沿ってクール…というより鋭い存在感を示し始めた、ユイちゃん。
東京に出たかった少女は、現地で大災害に直面。地元の人とともに乗り越えていく立場になっていきます。
準主役として強い印象を残した橋本愛さん。近年は大河ドラマでよく見かけます。2018年『西郷どん』、2019年『いだてん』と立て続けに出演していました。
――ついに『青天を衝け』では、大河ドラマのヒロインに。
栄一(吉沢亮)と渋沢喜作(演:高良健吾)の2人が、千代(橋本愛)をめぐって、剣術の試合で勝負します。
激しい竹刀での打ち合い。幼少期から密かにアイドルだった女子の面前。もう、その想いは隠すことなく、火花を散らすイケメン2人。
――そして、ここで“真の勝者”が現れます。
周囲も盛り上がる、熱戦の最中。渋沢喜作(高良健吾)の方と縁談が進んでいた“よし”(演:成海璃子)が登場。
…よし(成海璃子)が、突然に喜作の応援を始めたことで、場の空気が一変。
千代(橋本愛)も、内心を吐露して栄一(吉沢亮)に声援を送ります。
――これで“勝負あり”。
剣術の試合とは、まったく違う次元で決着は付きました。
こうして栄一と千代(吉沢亮と橋本愛)。喜作とよし(高良健吾と成海璃子)。目にも優しい、美男美女のカップルが2組誕生しました。
――めでたし、めでたし…
…しかし、今回は書くうちに予定外の内容になりました。
もともとは、井伊直弼(演:岸谷五朗)の描き方について語るつもりが、前置きで話がまとまってしまったので、また改めたいと思います。
タグ :大河ドラマ
2021年03月16日
「“青天”に騒めく…」
こんばんは。
毎週、大河ドラマ「青天を衝け」の冒頭に来る徳川家康にも慣れました。日曜に放送された第5回「栄一、揺れる」。心が騒(ざわ)めく要素が多かったです。
…なお当ブログでは、常に佐賀藩の動きをイメージしますので、記事内に「青天を衝け」には出て来ない場面が多数含まれます。
まだ、ご覧でない方は、ぜひ土曜の再放送か、録画視聴後にお読みいただくと、混乱しにくい…と思います。
――その1つ前、第4回の話から。
有能な幕府官僚として登場する、川路聖謨(演:平田満)が一言。
「それがしの“話術”で要求を躱(かわ)す」と長崎に向かう前に役目を語ります。
“本編”ほかで繰り返し紹介している、長崎へのロシアのプチャーチン来航です。この情報でアメリカのペリーは「ロシアに先を越される!」と焦ります。
年越しの時期。佐賀藩が守る長崎砲台。寒空の下でロシア船を見張る佐賀藩士たち。殿・鍋島直正も現場を訪れ、自ら、餅や酒を振る舞って労ったそうです。
〔参照(後半):第9話「和親条約」⑨〕

――佐賀藩の警備は充実。これで川路の“話術”も冴える。
川路聖謨は「プチャーチンとは、安心して話が出来た」と感想を持ったようです。
〔参照(中盤):第9話「和親条約」⑧〕
ロシアとの交渉は一旦終了し、川路たちは佐賀藩の長崎砲台を見学します。
〔参照(前半):第10話「蒸気機関」⑩(佐賀の産業革命)〕
江戸に戻った川路たちが、佐賀藩の働きを絶賛したこともあり、幕府からの“ご褒美”も出ました。国政とは距離を置いていても、佐賀の存在感は強まります。
――そして、第5回。私のイチ押しポイントは…
やはり藤田東湖(演:渡辺いっけい)でしょう。例えば、徳川斉昭(演:竹中直人)に詰め寄られる、老中・阿部正弘(演:大谷亮平)の苦労を描く場面。
〔参照:第9話「和親条約」③※中盤が似たような展開〕
阿部正弘は、外国との駆け引きに全神経を削り、憔悴の様子。最初に“黒船”と対峙した国政の実質的責任者。幕末で一番難しい立場だったかもしれません。

――この場面で、藤田東湖が有能さを発揮。
老中・阿部正弘の苦労を考慮し、主君・徳川斉昭の暴走を諫(いさ)める。
…ここで「理想どおりの藤田さまだ!」とテレビの前の私。
また佐賀藩に話を寄せると、これでこそ島義勇が学びに行く価値があります。
この藤田さまと、佐賀の枝吉神陽を“東西の二傑”と評した方もいるようです…とはいえ、枝吉神陽は島義勇と同い年のいとこ。憧れの対象にはなりづらい。
後に“札幌”を創った男・島義勇が「あの人のようになりたい!」と敬愛するのが、藤田東湖…という表現にしました。
〔参照(前半):第11話「蝦夷探検」③(“懐刀”の想い)〕
――そして“青天”第5回で、最大の事件…
後半、安政年間に群発した巨大地震が題材となりました。
〔参照:「“大災害”と微かな希望」〕
まず、安政の東海地震が描かれます。下田沖では、ロシアのプチャーチン提督が被災。少し前には大坂沖に出現し、京の“攘夷派”を大騒ぎさせたのですが…
津波に遭ったロシア船「ディアナ号」は、損傷により沈んでいきます。長崎でロシアと交渉した、川路聖謨が遭難の救護に当たる姿が印象的でした。
実際、地元・下田の人に助けてもらった、ロシア側の船医が地元の人を診たり…と人道的な風景があったと聞きます。

――続いて、安政の江戸地震の場面…
今回で、藤田東湖の最期が描かれることは予想していました。
ひたすら「東湖(とうこ)!東湖…」と号泣する、水戸さま・徳川斉昭。
こうして“懐刀”を失った“水戸烈公”。次第に水戸藩には暗雲が立ち込めます。
私は「藤田東湖は母を救った後、亡くなった」という説で書きました。佐賀で知らせを聞いた島義勇は落涙。“蝦夷地”探検の決意につながる…という展開に。
〔参照(後半):第11話「蝦夷探検」⑦(“拓北”の決意)〕
「青天を衝け」にあわせ、自分の記事も顧みました。期待した登場人物の描き方に納得です。今年も見応えある「大河ドラマ」。佐賀藩士の登場も待っています。
毎週、大河ドラマ「青天を衝け」の冒頭に来る徳川家康にも慣れました。日曜に放送された第5回「栄一、揺れる」。心が騒(ざわ)めく要素が多かったです。
…なお当ブログでは、常に佐賀藩の動きをイメージしますので、記事内に「青天を衝け」には出て来ない場面が多数含まれます。
まだ、ご覧でない方は、ぜひ土曜の再放送か、録画視聴後にお読みいただくと、混乱しにくい…と思います。
――その1つ前、第4回の話から。
有能な幕府官僚として登場する、川路聖謨(演:平田満)が一言。
「それがしの“話術”で要求を躱(かわ)す」と長崎に向かう前に役目を語ります。
“本編”ほかで繰り返し紹介している、長崎へのロシアのプチャーチン来航です。この情報でアメリカのペリーは「ロシアに先を越される!」と焦ります。
年越しの時期。佐賀藩が守る長崎砲台。寒空の下でロシア船を見張る佐賀藩士たち。殿・鍋島直正も現場を訪れ、自ら、餅や酒を振る舞って労ったそうです。
〔参照(後半):
――佐賀藩の警備は充実。これで川路の“話術”も冴える。
川路聖謨は「プチャーチンとは、安心して話が出来た」と感想を持ったようです。
〔参照(中盤):
ロシアとの交渉は一旦終了し、川路たちは佐賀藩の長崎砲台を見学します。
〔参照(前半):
江戸に戻った川路たちが、佐賀藩の働きを絶賛したこともあり、幕府からの“ご褒美”も出ました。国政とは距離を置いていても、佐賀の存在感は強まります。
――そして、第5回。私のイチ押しポイントは…
やはり藤田東湖(演:渡辺いっけい)でしょう。例えば、徳川斉昭(演:竹中直人)に詰め寄られる、老中・阿部正弘(演:大谷亮平)の苦労を描く場面。
〔参照:
阿部正弘は、外国との駆け引きに全神経を削り、憔悴の様子。最初に“黒船”と対峙した国政の実質的責任者。幕末で一番難しい立場だったかもしれません。

――この場面で、藤田東湖が有能さを発揮。
老中・阿部正弘の苦労を考慮し、主君・徳川斉昭の暴走を諫(いさ)める。
…ここで「理想どおりの藤田さまだ!」とテレビの前の私。
また佐賀藩に話を寄せると、これでこそ島義勇が学びに行く価値があります。
この藤田さまと、佐賀の枝吉神陽を“東西の二傑”と評した方もいるようです…とはいえ、枝吉神陽は島義勇と同い年のいとこ。憧れの対象にはなりづらい。
後に“札幌”を創った男・島義勇が「あの人のようになりたい!」と敬愛するのが、藤田東湖…という表現にしました。
〔参照(前半):
――そして“青天”第5回で、最大の事件…
後半、安政年間に群発した巨大地震が題材となりました。
〔参照:
まず、安政の東海地震が描かれます。下田沖では、ロシアのプチャーチン提督が被災。少し前には大坂沖に出現し、京の“攘夷派”を大騒ぎさせたのですが…
津波に遭ったロシア船「ディアナ号」は、損傷により沈んでいきます。長崎でロシアと交渉した、川路聖謨が遭難の救護に当たる姿が印象的でした。
実際、地元・下田の人に助けてもらった、ロシア側の船医が地元の人を診たり…と人道的な風景があったと聞きます。

――続いて、安政の江戸地震の場面…
今回で、藤田東湖の最期が描かれることは予想していました。
ひたすら「東湖(とうこ)!東湖…」と号泣する、水戸さま・徳川斉昭。
こうして“懐刀”を失った“水戸烈公”。次第に水戸藩には暗雲が立ち込めます。
私は「藤田東湖は母を救った後、亡くなった」という説で書きました。佐賀で知らせを聞いた島義勇は落涙。“蝦夷地”探検の決意につながる…という展開に。
〔参照(後半):
「青天を衝け」にあわせ、自分の記事も顧みました。期待した登場人物の描き方に納得です。今年も見応えある「大河ドラマ」。佐賀藩士の登場も待っています。
タグ :大河ドラマ
2021年03月01日
「“青天”に呟く…」
こんばんは。
昨日の日曜で、大河ドラマ「青天を衝け」は第3回でしたね。
私は「青天を衝け」を見ている間、ずっと気忙しいです。今日はその理由となる個人的なポイントを順に紹介します。
ちなみに私の話は、だいたい結論を佐賀藩に持っていきます。そのため実際の「ドラマの感想」以上に、「佐賀藩への想い」が書いてあるのでご注意ください。
――①時代背景が気になる。
・「アヘン戦争」(1840年~)が度々、引き合いに出される。
長崎を警備する佐賀藩にとっては「今、そこにある危機」でした。殿・鍋島直正は、幕府や福岡藩が動かずとも、佐賀藩単独でも長崎砲台を築いていきます。
〔参照(終盤):第8話「黒船来航」④〕
・「ペリー来航」(1853年~)を、どう描くかに興味がある。
“青天”のペリー。わりと他の欧米列強との順番争いを気にします。「偉大な兄に追いつきたい」気持ちも加われば、“本編”で描いたペリーに近づきそうです。
〔参照(後半):第8話「黒船来航」⑥〕

――②登場人物が気になる。
・水戸さまの“懐刀”として藤田東湖(演:渡辺いっけい)に存在感がある。
水戸藩の「尊王攘夷」の柱。思想家・藤田東湖。徳川斉昭を支える実務家で、これは「島義勇からも尊敬されるだろうな」…という説得力を感じます。
〔参照(前半):第11話「蝦夷探検」③(“懐刀”の想い)〕
・幕府エリート官僚の川路聖謨(演:平田満)も、序盤から登場する。
ペリーが一時退去した直後、長崎に現れたロシアのプチャーチンと折衝した人物。佐賀藩の「長崎砲台」に守られ、堂々と外交ができたと幕府に報告します。
〔参照(後半):第9話「和親条約」⑧〕
――③キャストが気になる。
・平岡円四郎(演:堤真一)が、何となく佐賀の殿様に見えてしまう。
…これは以前からの、私の勝手なイメージです。
二枚目と三枚目の顔を併せ持ち、表情も口調も変幻自在。
精悍な顔立ちですし、武芸にも励んだ殿が表現できるかも…
・尾高惇忠(演:田辺誠一)も、佐賀藩の“請役”さまに見えてしまう。
…同上で、当初からの個人的なイメージです。
妹・千代(演:橋本愛)が「女子だって人の道理を学びたい!」と訴えます。目下とされる人の想いを聞いて、自分の意見を正したりする感じが…補佐役っぽい。
――おそらく、私は「青天を衝け」だけではなく…
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を重ねて見ているようです。
…私が“本編”を描く時のキャストのイメージも、機会があれば語りたいと思います。こんな調子なので、私の「大河ドラマ視聴」はとても忙しいです。
――もし幕末期の佐賀藩で「大河ドラマ」が実現したら…
想像は膨らむところですが、例えば…
第3回の“紀行”でも、水戸の藩校「弘道館」が紹介されました。大河ドラマ化の暁(あかつき)には、佐賀の「弘道館」も全国で知られる機会が…
独特のポイントを呟(つぶや)きましたが、冒頭の「こんばんは、徳川家康です」が毎週気になるのは、私だけではないようです。
昨日の日曜で、大河ドラマ「青天を衝け」は第3回でしたね。
私は「青天を衝け」を見ている間、ずっと気忙しいです。今日はその理由となる個人的なポイントを順に紹介します。
ちなみに私の話は、だいたい結論を佐賀藩に持っていきます。そのため実際の「ドラマの感想」以上に、「佐賀藩への想い」が書いてあるのでご注意ください。
――①時代背景が気になる。
・「アヘン戦争」(1840年~)が度々、引き合いに出される。
長崎を警備する佐賀藩にとっては「今、そこにある危機」でした。殿・鍋島直正は、幕府や福岡藩が動かずとも、佐賀藩単独でも長崎砲台を築いていきます。
〔参照(終盤):
・「ペリー来航」(1853年~)を、どう描くかに興味がある。
“青天”のペリー。わりと他の欧米列強との順番争いを気にします。「偉大な兄に追いつきたい」気持ちも加われば、“本編”で描いたペリーに近づきそうです。
〔参照(後半):

――②登場人物が気になる。
・水戸さまの“懐刀”として藤田東湖(演:渡辺いっけい)に存在感がある。
水戸藩の「尊王攘夷」の柱。思想家・藤田東湖。徳川斉昭を支える実務家で、これは「島義勇からも尊敬されるだろうな」…という説得力を感じます。
〔参照(前半):
・幕府エリート官僚の川路聖謨(演:平田満)も、序盤から登場する。
ペリーが一時退去した直後、長崎に現れたロシアのプチャーチンと折衝した人物。佐賀藩の「長崎砲台」に守られ、堂々と外交ができたと幕府に報告します。
〔参照(後半):
――③キャストが気になる。
・平岡円四郎(演:堤真一)が、何となく佐賀の殿様に見えてしまう。
…これは以前からの、私の勝手なイメージです。
二枚目と三枚目の顔を併せ持ち、表情も口調も変幻自在。
精悍な顔立ちですし、武芸にも励んだ殿が表現できるかも…
・尾高惇忠(演:田辺誠一)も、佐賀藩の“請役”さまに見えてしまう。
…同上で、当初からの個人的なイメージです。
妹・千代(演:橋本愛)が「女子だって人の道理を学びたい!」と訴えます。目下とされる人の想いを聞いて、自分の意見を正したりする感じが…補佐役っぽい。
――おそらく、私は「青天を衝け」だけではなく…
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を重ねて見ているようです。
…私が“本編”を描く時のキャストのイメージも、機会があれば語りたいと思います。こんな調子なので、私の「大河ドラマ視聴」はとても忙しいです。
――もし幕末期の佐賀藩で「大河ドラマ」が実現したら…
想像は膨らむところですが、例えば…
第3回の“紀行”でも、水戸の藩校「弘道館」が紹介されました。大河ドラマ化の暁(あかつき)には、佐賀の「弘道館」も全国で知られる機会が…
独特のポイントを呟(つぶや)きましたが、冒頭の「こんばんは、徳川家康です」が毎週気になるのは、私だけではないようです。
タグ :大河ドラマ
2021年02月19日
「“青天”を追う…」
こんばんは。
「俺は己の力で立っている…青い天に拳を突き上げている!」
顔だけじゃなくて、声も良いですね。吉沢亮さん。
紹介番組で見たシーン。切立った岩場から、右拳を高く掲げて…このセリフ。
今年の大河ドラマ「青天を衝け」。14日(日)からスタートしていますが、明日、土曜の再放送に合わせて、遅ればせながらの感想です。
主人公は「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一。ちなみに幕末期の話から始まるため、大河ドラマを視聴している間ずっと…私は頭の中が忙しいです。

――まずは、その時代と人物を追います。
オープニング近く。成長した渋沢栄一(演:吉沢亮)が、徳川慶喜(演:草彅剛)と出会う場面。まず慶喜たちの馬を止めようとし、駆け抜けられても、走って追う。
1864年の文久年間。場所は京都の設定でした。
「今すでに、徳川の“お命”は尽きてございます!」と叫ぶ、渋沢が印象的でした。
…私が書く“本編”は、いま1859年前後なので、まだ描けていない時期。
知ってはいますが、5年後くらいには江戸幕府…かなり危ういですのですね。
――でも、第1話の主な時代設定は、渋沢栄一の幼少期。
先の場面から20年ほど遡り、1844年頃が中心だったかと思います。子役たちの演技で、養蚕が盛んな農村風景が瑞々しく描かれました。
…少し「青天を衝け」から離れます。
日本史的には、オランダ国王が幕府に開国勧告をしている時期。
「アヘン戦争の結果、見たでしょ。もう危ないから開国しましょうよ。」
…わりと面倒見の良いオランダからの“開国のススメ”。
ここでは幕府は動きませんでしたが、佐賀藩主・鍋島直正はこれを好機とみて、長崎でオランダの軍艦に乗り込んだりしています。
〔参照(終盤):第5話「藩校立志」③〕

――私のブログは、隙あらば佐賀藩の話に引き込みます。ご注意を。
話は「青天を衝け」に寄りますが、また「佐賀の大河ドラマ」のイメージと絡めてみます。“青天”第1話のキャストで、“本編”にも登場されている方を一部紹介。
〇幕府老中・阿部正弘(演:大谷亮平)。
私が“調整の達人”と考える方。押されているようでも、意外と思惑どおり。“やや太め”のイメージを持ちますが、大河ドラマでのスマートな印象に期待です。
〇水戸藩主・徳川斉昭(演:竹中直人)
とても過激な水戸烈公。「イメージどおりだ!」と世間の評判も上々のようです。砲術訓練の場面では、勇猛な水戸藩士たちに気持ちがザワザワします。
…“本編”でもこの2人のやり取りをイメージした話がありました。調整型の老中・阿部正弘と、過激な“水戸烈公”の会話で、佐賀藩がキーワードになります。
〔参照(中盤):第9話「和親条約」③〕
――そして、第1話の後半で護送されていた人物…
〇西洋砲術家・高島秋帆(演:玉木宏)
長崎の有力者・町役人だった高島秋帆ですが、この頃は囚われの身でした。
ちなみに、この直前期までは、佐賀藩の西洋砲術の先生だった方です。
私が描く“本編”では、高島秋帆が捕えられるまでを、こう表現してみました。
〔参照(終盤):第3話「西洋砲術」④-2〕
――「青天を衝け」の高島先生。
そのうちで良いですから、佐賀のことも想い出してください…
また機会があれば語りたいのですが、「青天を衝け」には、私が殿・鍋島直正や、請役・鍋島安房の第1候補にイメージする役者さんも出演されています。
「麒麟がくる」以上に、大河ドラマを追わねばならない1年になりそうです。
「俺は己の力で立っている…青い天に拳を突き上げている!」
顔だけじゃなくて、声も良いですね。吉沢亮さん。
紹介番組で見たシーン。切立った岩場から、右拳を高く掲げて…このセリフ。
今年の大河ドラマ「青天を衝け」。14日(日)からスタートしていますが、明日、土曜の再放送に合わせて、遅ればせながらの感想です。
主人公は「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一。ちなみに幕末期の話から始まるため、大河ドラマを視聴している間ずっと…私は頭の中が忙しいです。

――まずは、その時代と人物を追います。
オープニング近く。成長した渋沢栄一(演:吉沢亮)が、徳川慶喜(演:草彅剛)と出会う場面。まず慶喜たちの馬を止めようとし、駆け抜けられても、走って追う。
1864年の文久年間。場所は京都の設定でした。
「今すでに、徳川の“お命”は尽きてございます!」と叫ぶ、渋沢が印象的でした。
…私が書く“本編”は、いま1859年前後なので、まだ描けていない時期。
知ってはいますが、5年後くらいには江戸幕府…かなり危ういですのですね。
――でも、第1話の主な時代設定は、渋沢栄一の幼少期。
先の場面から20年ほど遡り、1844年頃が中心だったかと思います。子役たちの演技で、養蚕が盛んな農村風景が瑞々しく描かれました。
…少し「青天を衝け」から離れます。
日本史的には、オランダ国王が幕府に開国勧告をしている時期。
「アヘン戦争の結果、見たでしょ。もう危ないから開国しましょうよ。」
…わりと面倒見の良いオランダからの“開国のススメ”。
ここでは幕府は動きませんでしたが、佐賀藩主・鍋島直正はこれを好機とみて、長崎でオランダの軍艦に乗り込んだりしています。
〔参照(終盤):
――私のブログは、隙あらば佐賀藩の話に引き込みます。ご注意を。
話は「青天を衝け」に寄りますが、また「佐賀の大河ドラマ」のイメージと絡めてみます。“青天”第1話のキャストで、“本編”にも登場されている方を一部紹介。
〇幕府老中・阿部正弘(演:大谷亮平)。
私が“調整の達人”と考える方。押されているようでも、意外と思惑どおり。“やや太め”のイメージを持ちますが、大河ドラマでのスマートな印象に期待です。
〇水戸藩主・徳川斉昭(演:竹中直人)
とても過激な水戸烈公。「イメージどおりだ!」と世間の評判も上々のようです。砲術訓練の場面では、勇猛な水戸藩士たちに気持ちがザワザワします。
…“本編”でもこの2人のやり取りをイメージした話がありました。調整型の老中・阿部正弘と、過激な“水戸烈公”の会話で、佐賀藩がキーワードになります。
〔参照(中盤):
――そして、第1話の後半で護送されていた人物…
〇西洋砲術家・高島秋帆(演:玉木宏)
長崎の有力者・町役人だった高島秋帆ですが、この頃は囚われの身でした。
ちなみに、この直前期までは、佐賀藩の西洋砲術の先生だった方です。
私が描く“本編”では、高島秋帆が捕えられるまでを、こう表現してみました。
〔参照(終盤):
――「青天を衝け」の高島先生。
そのうちで良いですから、佐賀のことも想い出してください…
また機会があれば語りたいのですが、「青天を衝け」には、私が殿・鍋島直正や、請役・鍋島安房の第1候補にイメージする役者さんも出演されています。
「麒麟がくる」以上に、大河ドラマを追わねばならない1年になりそうです。
タグ :大河ドラマ