2022年01月22日
「佐賀の空を起点として振り返る。」
こんばんは。
遠方に住むため、私はニュースで状況を知りますが、佐賀でも新型コロナの感染者数が増えたり、地震での揺れがあったり…と心配事の多いところです。
最近、下を向きそうになるような話題も多いですが、『さがファンブログ』には、よく空の写真を載せておられる方々もいます。
「時に、空を見上げることも大事。」と教えられた私は、青天を仰ぎ見ることに。ただ、そのたび「ポキポキっ…」と音をたてる関節。加齢と疲労は感じます。
――さて、振り返りシリーズ第2回・中編です。
特に『佐賀空港』がキーワードというわけではなく、最近の“本編”では江戸(東京)との手紙のやり取りで展開する話が多いため、こういう表現にしました。
気持ちだけでも「佐賀の中心から空を見上げて、東京方面に向かう」ぐらいのイメージで語ります。
〔参照(直近の本編記事):第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)〕

――本シリーズは「制作裏話」でもあります。
私が「幕末期の佐賀の歴史」を顧みるようになって、まだ3年ほど。それゆえ、調べながら書いており、未知だった“史実”が次々わかってしまうことが。
書き手としては、「話を作り終えた後で、この展開になると辛い…」というのが、素直な感想です。
――“創作”を標榜するとはいえ、
「もし、佐賀の大河ドラマが実現すれば、こんな書き方もありうる!」という域を目指したい気持ちだけはあるので葛藤しながら、話の”着地点”を探ります。
実際の「大河ドラマ」では、史実を監修する先生が仕上がった原稿をチェックするのか、会議でシナリオの方向を決めてから書くのか…興味深いところです。
――ケース①「長崎街道の旅人」
佐賀城の南堀端をゆく、大木喬任(民平)と江藤新平。師匠・枝吉神陽宅の門前に見えるのは、会話している二人のさむらいの姿。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑧(福岡から来た“さぶらい”)〕
一人は佐賀藩士・古賀一平なので問題なし。しかし、うち一人は福岡脱藩の志士・平野国臣。ここが問題なのです。
ここで2年ちょっと前に佐賀市内、白山通りのアーケードの下で、撮影した写真をご覧ください。

――“長崎街道”の看板があります。
よく見ると江戸時代に「街道を行く旅人たちは、城内はもちろん武家地への立入りは原則禁止。街道以外の通行も制限」されたと説明が記載されています。
「こいは、いかんばいっ!」とばかりに、筋書きがマズい方向に行っている…と気付いた私。ここから軌道修正を試みます。
平野国臣は、隣県である福岡(藩)を代表する勤王の志士。私の書いた文章では“さがんもん”じゃない人が城下の奥深くに来ている展開になっています。
――“史実”と思われる情報から。
文久元年(1861年)秋、佐賀の義祭同盟のメンバーと福岡脱藩の平野国臣が出会って、意見交換をしたと幾つかの資料で見かけました。
行動力のある勤王の志士・平野国臣ですが、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』頃の時代(平安末期・鎌倉初期)のような装束を好んで着たと聞きます。
…その辺りからの発想で「福岡の“さぶらい”」という表現をしてみました。
地元・福岡に居る時ならともかく、佐賀に来た時まで“古風”な格好をしたかは不明です。問題は出入り禁止のはずの佐賀城下に“旅人”がいる状況。
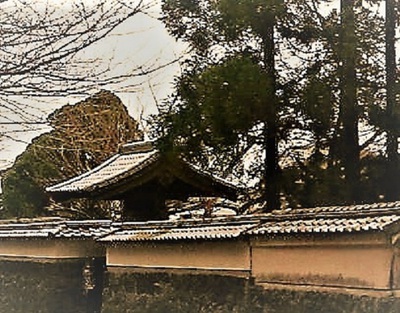
――江藤らの義祭同盟の仲間・古賀一平。
ひとしきり勤王の話に熱中した古賀ですが「ここに“お客人”が居ては危うい」と気づき、旅人・平野国臣を“長崎街道”沿いに戻して一件落着(?)。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕
大木と江藤、そして中野方蔵の三人を軸に描くことが多かったので、どうしても他の仲間が“常識人”としての役回りになりがちです。
古賀一平は、明治初期に東京(埼玉、神奈川)の一部にあった“品川県”を任された人物…ですが、古賀の担当地域が、そのまま“県”になったようです。
――ケース②「江藤新平の家族」
佐賀藩の下級役人として、のちの“働き者”の片鱗を見せる、江藤新平。
妻・千代子と結婚し、長男・熊太郎も誕生。武家屋敷街の一角に居を構える。そんな時期だったようです。
当時の江藤家に近い姿を想像し、穏やかな日々も描いてみました。但し「いずれ国に大事がある時には、立たねば」と気概を秘めた一家と表現しています。
〔参照(後半:第17話「佐賀脱藩」⑫(陽だまりの下で)〕
――この場面にも登場する、江藤新平の妻について。
私はある“創作物”での情報から、江藤のいとこだった千代子の年齢を設定し、筋書きを作成していました。
最近、ある資料を参照したところ当初の想定より、江藤千代子の年齢はかなり若かったようです。
しかし「溢れる才能には危ういところもある」のが江藤の人物像だとすれば、「奥様は年齢によらず“しっかり者”にならざるを得ないかな…」とも思います。ここは、とくに軌道修正せずに進めようと思います。

――江藤らに届く、親友・中野方蔵からの手紙。
佐賀の義祭同盟のメンバーは、大都会・江戸(東京)に出てから他藩の志士たちと活発に交流する中野の動きを知ります。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」③(江戸からの便り)〕
下級武士としては、江藤はおそらく順調に活躍している方です。佐賀藩からも「英語を学ばせたい」と期待されている印象。
暮らし向きも良くなっていますが「このままで良いのか…」との焦りは強くあったのではないかと想像します。
〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)〕
江藤新平の時代と前提は異なるものの、現代の若者にも「地元で暮らすか、都会に出るか」は大きい選択なのかもしれません。
――今後も思い切って“本編”を書きたいので、
今回はあえて、制作上の諸問題があることをご紹介しました。いまは、「誤りを恐れずに進む」つもりで書き続けたいと思います。
こうして「史実と創作の狭間で」もがき続けることで、きっと佐賀藩士に魅力的な人物が、数多くいたことが見えてくるはず。
…私は“佐賀の先輩たち”の、歴史ドラマにおける活躍の幅が広がることを切に願っています。
次回は「みやきから振り返る」企画の予定でしたが、一旦“本編”を再開します。みやき町のお話は「ここぞ」という時に繰り出すので、ご了承ください。
遠方に住むため、私はニュースで状況を知りますが、佐賀でも新型コロナの感染者数が増えたり、地震での揺れがあったり…と心配事の多いところです。
最近、下を向きそうになるような話題も多いですが、『さがファンブログ』には、よく空の写真を載せておられる方々もいます。
「時に、空を見上げることも大事。」と教えられた私は、青天を仰ぎ見ることに。ただ、そのたび「ポキポキっ…」と音をたてる関節。加齢と疲労は感じます。
――さて、振り返りシリーズ第2回・中編です。
特に『佐賀空港』がキーワードというわけではなく、最近の“本編”では江戸(東京)との手紙のやり取りで展開する話が多いため、こういう表現にしました。
気持ちだけでも「佐賀の中心から空を見上げて、東京方面に向かう」ぐらいのイメージで語ります。
〔参照(直近の本編記事):
――本シリーズは「制作裏話」でもあります。
私が「幕末期の佐賀の歴史」を顧みるようになって、まだ3年ほど。それゆえ、調べながら書いており、未知だった“史実”が次々わかってしまうことが。
書き手としては、「話を作り終えた後で、この展開になると辛い…」というのが、素直な感想です。
――“創作”を標榜するとはいえ、
「もし、佐賀の大河ドラマが実現すれば、こんな書き方もありうる!」という域を目指したい気持ちだけはあるので葛藤しながら、話の”着地点”を探ります。
実際の「大河ドラマ」では、史実を監修する先生が仕上がった原稿をチェックするのか、会議でシナリオの方向を決めてから書くのか…興味深いところです。
――ケース①「長崎街道の旅人」
佐賀城の南堀端をゆく、大木喬任(民平)と江藤新平。師匠・枝吉神陽宅の門前に見えるのは、会話している二人のさむらいの姿。
〔参照(中盤):
一人は佐賀藩士・古賀一平なので問題なし。しかし、うち一人は福岡脱藩の志士・平野国臣。ここが問題なのです。
ここで2年ちょっと前に佐賀市内、白山通りのアーケードの下で、撮影した写真をご覧ください。
――“長崎街道”の看板があります。
よく見ると江戸時代に「街道を行く旅人たちは、城内はもちろん武家地への立入りは原則禁止。街道以外の通行も制限」されたと説明が記載されています。
「こいは、いかんばいっ!」とばかりに、筋書きがマズい方向に行っている…と気付いた私。ここから軌道修正を試みます。
平野国臣は、隣県である福岡(藩)を代表する勤王の志士。私の書いた文章では“さがんもん”じゃない人が城下の奥深くに来ている展開になっています。
――“史実”と思われる情報から。
文久元年(1861年)秋、佐賀の義祭同盟のメンバーと福岡脱藩の平野国臣が出会って、意見交換をしたと幾つかの資料で見かけました。
行動力のある勤王の志士・平野国臣ですが、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』頃の時代(平安末期・鎌倉初期)のような装束を好んで着たと聞きます。
…その辺りからの発想で「福岡の“さぶらい”」という表現をしてみました。
地元・福岡に居る時ならともかく、佐賀に来た時まで“古風”な格好をしたかは不明です。問題は出入り禁止のはずの佐賀城下に“旅人”がいる状況。
――江藤らの義祭同盟の仲間・古賀一平。
ひとしきり勤王の話に熱中した古賀ですが「ここに“お客人”が居ては危うい」と気づき、旅人・平野国臣を“長崎街道”沿いに戻して一件落着(?)。
〔参照(中盤):
大木と江藤、そして中野方蔵の三人を軸に描くことが多かったので、どうしても他の仲間が“常識人”としての役回りになりがちです。
古賀一平は、明治初期に東京(埼玉、神奈川)の一部にあった“品川県”を任された人物…ですが、古賀の担当地域が、そのまま“県”になったようです。
――ケース②「江藤新平の家族」
佐賀藩の下級役人として、のちの“働き者”の片鱗を見せる、江藤新平。
妻・千代子と結婚し、長男・熊太郎も誕生。武家屋敷街の一角に居を構える。そんな時期だったようです。
当時の江藤家に近い姿を想像し、穏やかな日々も描いてみました。但し「いずれ国に大事がある時には、立たねば」と気概を秘めた一家と表現しています。
〔参照(後半:
――この場面にも登場する、江藤新平の妻について。
私はある“創作物”での情報から、江藤のいとこだった千代子の年齢を設定し、筋書きを作成していました。
最近、ある資料を参照したところ当初の想定より、江藤千代子の年齢はかなり若かったようです。
しかし「溢れる才能には危ういところもある」のが江藤の人物像だとすれば、「奥様は年齢によらず“しっかり者”にならざるを得ないかな…」とも思います。ここは、とくに軌道修正せずに進めようと思います。
――江藤らに届く、親友・中野方蔵からの手紙。
佐賀の義祭同盟のメンバーは、大都会・江戸(東京)に出てから他藩の志士たちと活発に交流する中野の動きを知ります。
〔参照(後半):
下級武士としては、江藤はおそらく順調に活躍している方です。佐賀藩からも「英語を学ばせたい」と期待されている印象。
暮らし向きも良くなっていますが「このままで良いのか…」との焦りは強くあったのではないかと想像します。
〔参照(後半):
江藤新平の時代と前提は異なるものの、現代の若者にも「地元で暮らすか、都会に出るか」は大きい選択なのかもしれません。
――今後も思い切って“本編”を書きたいので、
今回はあえて、制作上の諸問題があることをご紹介しました。いまは、「誤りを恐れずに進む」つもりで書き続けたいと思います。
こうして「史実と創作の狭間で」もがき続けることで、きっと佐賀藩士に魅力的な人物が、数多くいたことが見えてくるはず。
…私は“佐賀の先輩たち”の、歴史ドラマにおける活躍の幅が広がることを切に願っています。
次回は「みやきから振り返る」企画の予定でしたが、一旦“本編”を再開します。みやき町のお話は「ここぞ」という時に繰り出すので、ご了承ください。




