2024年05月14日
第20話「長崎方控」⑧(長く生きた者よ)
こんばんは。
前回は大殿・鍋島直正(閑叟)の幼少期の場面を綴りました。直正の14歳年上の少年として登場した鍋島茂義は、佐賀藩の重役となる立場の武雄領主。
この武雄領も含めた自治領主は、かなりの権限があったので、茂義は幕末の佐賀で“西洋化”を先導する役回りを果たしました。
その頼れる“兄貴分”が逝去したのが、文久二年十一月(旧暦)と聞きます。これは、鍋島直正が京都に出向いていた時期と重なるようです。
この一報を、寒い冬の京都にいたはずの直正がいつ聞いたかは、今のところ不知なのですが、御所に参内した前後では無いか…と考えています。

――文久二年(1862年)の晩秋。佐賀藩の武雄領。
ザッザッザッ…、武雄領の侍が“行進”をする様子で、揃った足音がする。
「ハルト!(止まれ)」
ザッ!動いていた侍たちが、一斉に停止した様子だ。
チャカ、チャカチャカ…その場で、待機した者たちが、長い銃を扱う音が鳴る。
指揮を執る者は、幾つかの号令を発した後、大きくうなずいて一声を発した。
「ヒュール!(撃て)」
――パン、パパン、パン…!乾いた音が響いた。
ザザッ…、チャッ…
ひとしきり発砲した侍たちが、退避の動きを取り、控えていた侍が立ち上がる。
控えの侍たちも、すぐさま、肩に据えた銃を、パパパン…と撃ち始めた。
その場を仕切っていた指揮官、鍋島茂昌(しげはる)は、幾つかの確認を完了すると、「よか!」を大声を上げて、その場を締めた。
ここで行っているのは、軍事訓練のようだ。服装は侍のままだが、装備する銃は最新式、号令はオランダの影響を受けたようだ。

――しばらく後、武雄領の屋敷。
武雄の隠居(前領主)・鍋島茂義は、ひどく体調を崩しているが、この日は小康を得て、のんびりと過ごす様子だ。
老臣が先ほど見た、訓練の風景を茂義に報告している。
「そうか。“銃砲”の鍛錬に励んでおるか。」
「茂昌さまも、ご立派に成られました。」
少々、感慨深そうな老臣だが、茂義は「う~む」と苦い顔をしている。
「はて…、いかがなされましたか。」
「あやつは、“銃砲”にしか興味を持ちよらん。」
――鍋島茂義が、早々に武雄領主を引退したので…
茂昌は幼少期から領主の肩書きを引き継ぐが、実権は茂義にあった。佐賀藩へ欧米列強の技術を取り込むべく、茂義は自由に動ける身分が欲しかった。
「西洋の文明は、もっと深きものよ。」
茂義の世界への興味は、軍事だけでは無かったが、子・茂昌が学ぼうとする範囲は限られている。
「もっと、学んでほしいものだがな。」
「…茂昌さまも、励んでおられますよ。」
現在の武雄領主・鍋島茂昌は、戦に使えそうな西洋の技術にしか、ほとんど関心を持たない。だが、それも努力のうちだと、老臣がかばっている。
「はっはっ…お主は昔から優しか男だったからのう。」
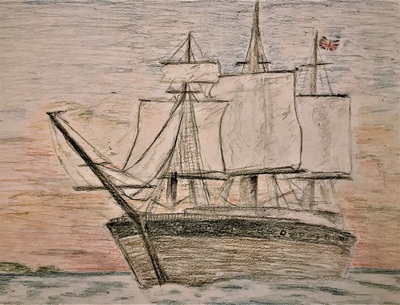
――かれこれ、六十余年の歳月を生きてきた。
幼き日に聞いた「英国の軍艦が長崎の港で暴れた」ことを。佐賀藩が幕府から咎められた、フェートン号事件の時、茂義はまだ子どもだった。
それから異国と戦うには、異国の力を知る必要があると思った。だが、調べれば調べるほどに“西洋”には惹かれていった。
実用的な理化学だけでなく、飲食物・嗜好品・絵画…何でも面白く感じた。
「そういえば、山口が、“小言”を申してきおった。」
「山口範蔵ですか?何ば言いよったのですか。」

武雄領から長崎に派遣し、英語も学ばせている、山口範蔵(尚芳)。先日に、何やら慌てて武雄に帰ってきた。
「異国に興味を持たなくなれば、儂(わし)は、儂でなくなるそうだ。」
「…なんと、無礼な。山口も随分なことを申しますな!」
老臣が怒ったが、茂義は「当たっておる」とばかりに、からからと笑った。
――この年、茂義は大好きな“西洋の文物”の注文を抑えていた。
茂義の“お買い物”が途切れていることが、山口を心配させたようだ。
「もはや、この世から去る者が、あまり買い物をしてもな。」
茂義が、そう語る目はどこか寂しそうだった。老臣には、かける言葉がない。
「儂は“長生き”をしたのだろうか。それだけ多くのことを為したか…」
「…しましたとも!武雄の働きあって、いまの佐賀の力はあるとです!」
老臣が若かった頃のように、声を張る。
「お主は、優しいからな…」
「いえ、たとえ、平山が見ておっても同じように申すはず。」
「おおっ、平山か。“平山山平”か。」
茂義が、少し愉快そうな顔をした。

――かつて、茂義が重用した“平山醇左衛門”という家来がいた。
長崎で西洋式の砲術を学んで、それを茂義に伝える仕事もしていた。平山の熱心な指導もあって、茂義は高島流砲術の免許皆伝を許された。
茂義も、平山が長崎から帰ってくるのを楽しみにするから、「平山、平山…」と言い過ぎて、“平山山平”と呼んでしまっていた事もある。
「いや、平山は…儂には言いたい事が山ほどあるに相違ない。」
「…そんな、平山も分かっておるはず。」
――かつて天保年間に、西洋の学問が厳しく取り締まられた時期がある。
幕府で権力を持っていた、鳥居耀蔵の執拗なまでの“蘭学”への敵意。オランダ渡りの蘭学が最も盛んだった、佐賀藩も目を付けられていた。
その時、平山醇左衛門は武雄領、そして佐賀藩が追及されないように、一人で“疑い”を背負い込み、切腹により命を落としたのだ。
ここで茂義は、後悔を口にした。
「儂は、蒸気船も作れておらん。まだまだ出来ることがあったはずじゃ。」
「…それは、佐賀の者がきっと成し遂げましょう。」
「そうやもしれぬな。」

――茂義は区切りを付けるように、ふーっと一息を付いた。
「これからも、“小言を申す者”は、大事にいたせ。」
「…はっ。」
短く応えながら、老臣は目に涙を浮かべていた。
「そろそろ儂は、平山から“小言”をもらってくるとするか。」
「…きっと、労(ねぎら)いの言葉もありましょう。」
「では、茂昌を頼んだぞ。山口範蔵にもよろしく伝えてくれ。」
幕末の黎明期より近代への扉を開いてきた、佐賀藩武雄領主・鍋島茂義は文久二年十一月二十七日に、この世を去ったと記される。
そして、茂義が購入した西洋の文物を書き留めた買い物帳『長崎方控』も、この年の記録で終わっている。
(続く)
◎参考記事〔本編〕
○鍋島茂義と家臣の場面(第2話)
・第2話「算盤大名」②-1
・第2話「算盤大名」②-2
○蘭学の弾圧(第3話)
・第3話「西洋砲術」④-1
○平山醇左衛門の最期(第3話)
・第3話「西洋砲術」④-2
・第3話「西洋砲術」⑤
○山口範蔵(尚芳)の心配(第20話)
・第20話「長崎方控」③(西洋風の“紳士”)
前回は大殿・鍋島直正(閑叟)の幼少期の場面を綴りました。直正の14歳年上の少年として登場した鍋島茂義は、佐賀藩の重役となる立場の武雄領主。
この武雄領も含めた自治領主は、かなりの権限があったので、茂義は幕末の佐賀で“西洋化”を先導する役回りを果たしました。
その頼れる“兄貴分”が逝去したのが、文久二年十一月(旧暦)と聞きます。これは、鍋島直正が京都に出向いていた時期と重なるようです。
この一報を、寒い冬の京都にいたはずの直正がいつ聞いたかは、今のところ不知なのですが、御所に参内した前後では無いか…と考えています。

――文久二年(1862年)の晩秋。佐賀藩の武雄領。
ザッザッザッ…、武雄領の侍が“行進”をする様子で、揃った足音がする。
「ハルト!(止まれ)」
ザッ!動いていた侍たちが、一斉に停止した様子だ。
チャカ、チャカチャカ…その場で、待機した者たちが、長い銃を扱う音が鳴る。
指揮を執る者は、幾つかの号令を発した後、大きくうなずいて一声を発した。
「ヒュール!(撃て)」
――パン、パパン、パン…!乾いた音が響いた。
ザザッ…、チャッ…
ひとしきり発砲した侍たちが、退避の動きを取り、控えていた侍が立ち上がる。
控えの侍たちも、すぐさま、肩に据えた銃を、パパパン…と撃ち始めた。
その場を仕切っていた指揮官、鍋島茂昌(しげはる)は、幾つかの確認を完了すると、「よか!」を大声を上げて、その場を締めた。
ここで行っているのは、軍事訓練のようだ。服装は侍のままだが、装備する銃は最新式、号令はオランダの影響を受けたようだ。

――しばらく後、武雄領の屋敷。
武雄の隠居(前領主)・鍋島茂義は、ひどく体調を崩しているが、この日は小康を得て、のんびりと過ごす様子だ。
老臣が先ほど見た、訓練の風景を茂義に報告している。
「そうか。“銃砲”の鍛錬に励んでおるか。」
「茂昌さまも、ご立派に成られました。」
少々、感慨深そうな老臣だが、茂義は「う~む」と苦い顔をしている。
「はて…、いかがなされましたか。」
「あやつは、“銃砲”にしか興味を持ちよらん。」
――鍋島茂義が、早々に武雄領主を引退したので…
茂昌は幼少期から領主の肩書きを引き継ぐが、実権は茂義にあった。佐賀藩へ欧米列強の技術を取り込むべく、茂義は自由に動ける身分が欲しかった。
「西洋の文明は、もっと深きものよ。」
茂義の世界への興味は、軍事だけでは無かったが、子・茂昌が学ぼうとする範囲は限られている。
「もっと、学んでほしいものだがな。」
「…茂昌さまも、励んでおられますよ。」
現在の武雄領主・鍋島茂昌は、戦に使えそうな西洋の技術にしか、ほとんど関心を持たない。だが、それも努力のうちだと、老臣がかばっている。
「はっはっ…お主は昔から優しか男だったからのう。」
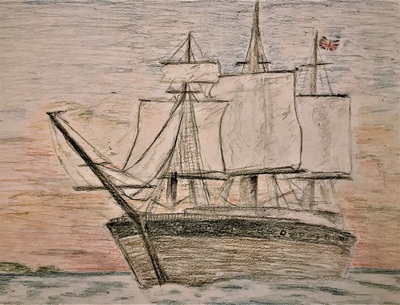
――かれこれ、六十余年の歳月を生きてきた。
幼き日に聞いた「英国の軍艦が長崎の港で暴れた」ことを。佐賀藩が幕府から咎められた、フェートン号事件の時、茂義はまだ子どもだった。
それから異国と戦うには、異国の力を知る必要があると思った。だが、調べれば調べるほどに“西洋”には惹かれていった。
実用的な理化学だけでなく、飲食物・嗜好品・絵画…何でも面白く感じた。
「そういえば、山口が、“小言”を申してきおった。」
「山口範蔵ですか?何ば言いよったのですか。」

武雄領から長崎に派遣し、英語も学ばせている、山口範蔵(尚芳)。先日に、何やら慌てて武雄に帰ってきた。
「異国に興味を持たなくなれば、儂(わし)は、儂でなくなるそうだ。」
「…なんと、無礼な。山口も随分なことを申しますな!」
老臣が怒ったが、茂義は「当たっておる」とばかりに、からからと笑った。
――この年、茂義は大好きな“西洋の文物”の注文を抑えていた。
茂義の“お買い物”が途切れていることが、山口を心配させたようだ。
「もはや、この世から去る者が、あまり買い物をしてもな。」
茂義が、そう語る目はどこか寂しそうだった。老臣には、かける言葉がない。
「儂は“長生き”をしたのだろうか。それだけ多くのことを為したか…」
「…しましたとも!武雄の働きあって、いまの佐賀の力はあるとです!」
老臣が若かった頃のように、声を張る。
「お主は、優しいからな…」
「いえ、たとえ、平山が見ておっても同じように申すはず。」
「おおっ、平山か。“平山山平”か。」
茂義が、少し愉快そうな顔をした。

――かつて、茂義が重用した“平山醇左衛門”という家来がいた。
長崎で西洋式の砲術を学んで、それを茂義に伝える仕事もしていた。平山の熱心な指導もあって、茂義は高島流砲術の免許皆伝を許された。
茂義も、平山が長崎から帰ってくるのを楽しみにするから、「平山、平山…」と言い過ぎて、“平山山平”と呼んでしまっていた事もある。
「いや、平山は…儂には言いたい事が山ほどあるに相違ない。」
「…そんな、平山も分かっておるはず。」
――かつて天保年間に、西洋の学問が厳しく取り締まられた時期がある。
幕府で権力を持っていた、鳥居耀蔵の執拗なまでの“蘭学”への敵意。オランダ渡りの蘭学が最も盛んだった、佐賀藩も目を付けられていた。
その時、平山醇左衛門は武雄領、そして佐賀藩が追及されないように、一人で“疑い”を背負い込み、切腹により命を落としたのだ。
ここで茂義は、後悔を口にした。
「儂は、蒸気船も作れておらん。まだまだ出来ることがあったはずじゃ。」
「…それは、佐賀の者がきっと成し遂げましょう。」
「そうやもしれぬな。」

――茂義は区切りを付けるように、ふーっと一息を付いた。
「これからも、“小言を申す者”は、大事にいたせ。」
「…はっ。」
短く応えながら、老臣は目に涙を浮かべていた。
「そろそろ儂は、平山から“小言”をもらってくるとするか。」
「…きっと、労(ねぎら)いの言葉もありましょう。」
「では、茂昌を頼んだぞ。山口範蔵にもよろしく伝えてくれ。」
幕末の黎明期より近代への扉を開いてきた、佐賀藩武雄領主・鍋島茂義は文久二年十一月二十七日に、この世を去ったと記される。
そして、茂義が購入した西洋の文物を書き留めた買い物帳『長崎方控』も、この年の記録で終わっている。
(続く)
◎参考記事〔本編〕
○鍋島茂義と家臣の場面(第2話)
・
・
○蘭学の弾圧(第3話)
・
○平山醇左衛門の最期(第3話)
・
・
○山口範蔵(尚芳)の心配(第20話)
・




