2022年02月05日
第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)
こんばんは。
前回の続きです。文久二年(1862年)の一月、江戸城門前で老中・安藤信正が襲撃された“坂下門外の変”の場面を描きました。
これは既に幕府に捕らえられていた佐賀藩士・中野方蔵の立場では、極めて都合の悪い展開だったはずです。
大木喬任・江藤新平らは、親友・中野方蔵を窮地から救おうと奔走することに。今回のお話は、江戸(東京)と佐賀の往復で展開します。
――老中襲撃事件の直後、江戸城内は騒然としていた。
「対馬守(安藤信正)さまは、ご無事なのだな!」
「手傷は負われておいでですが、お命には別状はござらぬ。」
「賊は、一人残らず、斬り捨て申した!」
「おのれ…不逞(ふてい)の浪士どもめ!」
“桜田門外の変”とは異なり、駕籠の中にいた老中・安藤信正には、襲撃者が放った銃弾が当たらなかった。
警備も厳重となっており、“坂下門外の変”では浪士たちの計画は失敗に終わったのである。
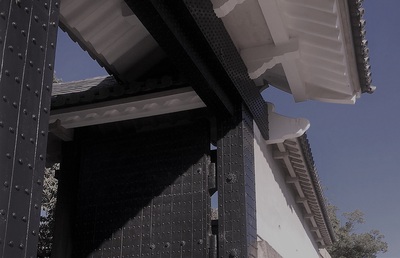
――この事件には、余波があった。
城内の書院にも幕閣たちが集まり、騒然としている。
「ご老中は、安藤さまは!いかがなさいましたか。」
「…小笠原どのか。ご無事ではあったのだがな。」
諸外国との難事にも対応した老中・安藤。唐津藩・小笠原長行ら、開国を進める幕府官僚の評判は悪くなかったが、負傷により療養、求心力が低下する。
「その場で打ち合わず、逃げ去るとは…。」
「武家の名折れよ…。」
どこからともなく、批判も湧いてくる。幕府内部にも、襲撃から身を守るべく退避した老中・安藤に、「そもそも“武士として”どうか」という声までが生じる。
老中を襲撃した浪士たちの狙いの一つ、幕府を揺さぶる効果は生じていた。
――冬の突き抜けた寒さが続く、江戸の牢獄。
「大木兄さん、江藤くん…それがし、少々調子づいていたのかもしれませぬ。」
弱々しく反省の言葉をつぶやく、中野方蔵。あるいは急ぎ過ぎていたのか、人付き合いを広げすぎたのかもしれない。
中野は、獄中からの手紙をしたためていた。
「…これも“身から出た錆”。恥じ入るばかりです。」
いつものように、佐賀の同志たちに熱気を伝える文面を書ける状況にはない。囚われの身では高らかに“国事”を語ることはできないのだ。
――佐賀。大木が右拳に握りしめているのは、中野からの手紙。
「…中野。」
「都合の悪か事に、安藤老中を襲った者たちは、大橋の塾の門弟らしい。」
江藤は淡々と語っているが、内心は大木と同じ想いだ。
「一時、中野が出入りした塾だな。」
その場に居合わせた坂井辰之允。以前の、中野からの手紙を思い起こす。
〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」④(上方からの“花嫁”)〕
ここで、江藤が一言を発する。
「獄につながれておるとはいえ、文(ふみ)が届くならば、途切れず続けよう。」

――江戸。次第に身体の弱っていく中野のもとに手紙が届いた。
差出人は、江藤だった。
「…どうした、中野。まるで、囚われの佳人(美人)のようではないか。」
「これもお主が軽率に人と関わったゆえ。お疑いが晴れるまで辛抱せよ。」
途中で役人が見る事を想定したか。堅物の江藤にしては、軽い文面である。
「中野は“八方美人”だったのか騒動に巻き込まれた」と見せたい意図か。
許される範囲で中野も筆を執った。親友二人には伝えておきたい事がある。
「江藤くん、大木兄さんにもお伝えください。この国に必要な学問の事です。」
――佐賀城内。大木は藩の重役に掛け合っていた。
「中野は藩校・弘道館でも規律を重んじた男。暴挙には関わりのなかです。」
「…騒動の首魁(しゅかい)・大橋の塾に出入りしたのだぞ。」
中野方蔵、藩校では“優等生”の振る舞いだった。佐賀藩の上層部にも受けが良いため、江戸に出られた経緯がある。
〔参照:第15話「江戸動乱」⑤(仮面の優等生)〕
――それが、いまや幕府から老中襲撃への関与を疑われている。
「まさか、中野があのような騒ぎに関わるとは…。」
佐賀藩保守派の筆頭格・原田小四郎をはじめ、重役たちに動揺も見られる。
「あやつは、学ぶ気持ちの強すぎ、人付き合いの良過ぎたとです。」
大木は、腹立ち気味に言い放った。
「中野は勉強熱心ゆえに、市中の私塾にも出入りした」という訴えだ。

――話は通らない。もどかしい思いのまま、その場から退出する大木。
「大木さん、いかがだったか。」
江藤が尋ねる。大木は無言で拳を握り、口惜しそうにしている。
「…まだだ。神陽先生も、副島さんもいる。諦(あきら)める道理は無い。」
大木は絞り出すように語った。
親友・中野を救う努力を打ち消すように、“坂下門外の変”が暗い影を落とす。大木や江藤が期待する面々に、幕府に気を遣う“保守派”の手が回っていた。
――再び、江戸。佐賀藩の屋敷でも訴えを続ける者がいた。
「あれは短慮に加わる者ではない。中野の釈放を掛け合っていただきたい。」
大木・江藤の先輩格である、副島種臣も上役への談判を繰り返している。
「副島よ、伝えねばならない事がある。」
「…先のお話を、お聞き届けくだされ。」
「佐賀のご隠居の傍に仕えよ。内密の役目ゆえ、他国との関わりも許さぬ。」
江戸で若手藩士の学問を指導する副島だが、佐賀に送還されることとなった。
前藩主・鍋島直正の側近に加えるためという名目も付き、自由に手紙を出す事も禁じられたのである。
(続く)
前回の続きです。文久二年(1862年)の一月、江戸城門前で老中・安藤信正が襲撃された“坂下門外の変”の場面を描きました。
これは既に幕府に捕らえられていた佐賀藩士・中野方蔵の立場では、極めて都合の悪い展開だったはずです。
大木喬任・江藤新平らは、親友・中野方蔵を窮地から救おうと奔走することに。今回のお話は、江戸(東京)と佐賀の往復で展開します。
――老中襲撃事件の直後、江戸城内は騒然としていた。
「対馬守(安藤信正)さまは、ご無事なのだな!」
「手傷は負われておいでですが、お命には別状はござらぬ。」
「賊は、一人残らず、斬り捨て申した!」
「おのれ…不逞(ふてい)の浪士どもめ!」
“桜田門外の変”とは異なり、駕籠の中にいた老中・安藤信正には、襲撃者が放った銃弾が当たらなかった。
警備も厳重となっており、“坂下門外の変”では浪士たちの計画は失敗に終わったのである。
――この事件には、余波があった。
城内の書院にも幕閣たちが集まり、騒然としている。
「ご老中は、安藤さまは!いかがなさいましたか。」
「…小笠原どのか。ご無事ではあったのだがな。」
諸外国との難事にも対応した老中・安藤。唐津藩・小笠原長行ら、開国を進める幕府官僚の評判は悪くなかったが、負傷により療養、求心力が低下する。
「その場で打ち合わず、逃げ去るとは…。」
「武家の名折れよ…。」
どこからともなく、批判も湧いてくる。幕府内部にも、襲撃から身を守るべく退避した老中・安藤に、「そもそも“武士として”どうか」という声までが生じる。
老中を襲撃した浪士たちの狙いの一つ、幕府を揺さぶる効果は生じていた。
――冬の突き抜けた寒さが続く、江戸の牢獄。
「大木兄さん、江藤くん…それがし、少々調子づいていたのかもしれませぬ。」
弱々しく反省の言葉をつぶやく、中野方蔵。あるいは急ぎ過ぎていたのか、人付き合いを広げすぎたのかもしれない。
中野は、獄中からの手紙をしたためていた。
「…これも“身から出た錆”。恥じ入るばかりです。」
いつものように、佐賀の同志たちに熱気を伝える文面を書ける状況にはない。囚われの身では高らかに“国事”を語ることはできないのだ。
――佐賀。大木が右拳に握りしめているのは、中野からの手紙。
「…中野。」
「都合の悪か事に、安藤老中を襲った者たちは、大橋の塾の門弟らしい。」
江藤は淡々と語っているが、内心は大木と同じ想いだ。
「一時、中野が出入りした塾だな。」
その場に居合わせた坂井辰之允。以前の、中野からの手紙を思い起こす。
〔参照(中盤):
ここで、江藤が一言を発する。
「獄につながれておるとはいえ、文(ふみ)が届くならば、途切れず続けよう。」
――江戸。次第に身体の弱っていく中野のもとに手紙が届いた。
差出人は、江藤だった。
「…どうした、中野。まるで、囚われの佳人(美人)のようではないか。」
「これもお主が軽率に人と関わったゆえ。お疑いが晴れるまで辛抱せよ。」
途中で役人が見る事を想定したか。堅物の江藤にしては、軽い文面である。
「中野は“八方美人”だったのか騒動に巻き込まれた」と見せたい意図か。
許される範囲で中野も筆を執った。親友二人には伝えておきたい事がある。
「江藤くん、大木兄さんにもお伝えください。この国に必要な学問の事です。」
――佐賀城内。大木は藩の重役に掛け合っていた。
「中野は藩校・弘道館でも規律を重んじた男。暴挙には関わりのなかです。」
「…騒動の首魁(しゅかい)・大橋の塾に出入りしたのだぞ。」
中野方蔵、藩校では“優等生”の振る舞いだった。佐賀藩の上層部にも受けが良いため、江戸に出られた経緯がある。
〔参照:
――それが、いまや幕府から老中襲撃への関与を疑われている。
「まさか、中野があのような騒ぎに関わるとは…。」
佐賀藩保守派の筆頭格・原田小四郎をはじめ、重役たちに動揺も見られる。
「あやつは、学ぶ気持ちの強すぎ、人付き合いの良過ぎたとです。」
大木は、腹立ち気味に言い放った。
「中野は勉強熱心ゆえに、市中の私塾にも出入りした」という訴えだ。
――話は通らない。もどかしい思いのまま、その場から退出する大木。
「大木さん、いかがだったか。」
江藤が尋ねる。大木は無言で拳を握り、口惜しそうにしている。
「…まだだ。神陽先生も、副島さんもいる。諦(あきら)める道理は無い。」
大木は絞り出すように語った。
親友・中野を救う努力を打ち消すように、“坂下門外の変”が暗い影を落とす。大木や江藤が期待する面々に、幕府に気を遣う“保守派”の手が回っていた。
――再び、江戸。佐賀藩の屋敷でも訴えを続ける者がいた。
「あれは短慮に加わる者ではない。中野の釈放を掛け合っていただきたい。」
大木・江藤の先輩格である、副島種臣も上役への談判を繰り返している。
「副島よ、伝えねばならない事がある。」
「…先のお話を、お聞き届けくだされ。」
「佐賀のご隠居の傍に仕えよ。内密の役目ゆえ、他国との関わりも許さぬ。」
江戸で若手藩士の学問を指導する副島だが、佐賀に送還されることとなった。
前藩主・鍋島直正の側近に加えるためという名目も付き、自由に手紙を出す事も禁じられたのである。
(続く)




