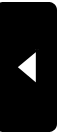2021年08月04日
第16話「攘夷沸騰」⑥(積年の胃痛にて…)
こんばんは。
“鉄腕”と称され実行力には評価のあった大老・井伊直弼。知識に優れた人材は居ても、統率力のあるリーダーを失ったことで幕府内では迷走が始まります。
…幕末の黎明期、技術開発や外交政策で幕府に協力し、目立って力を発揮した佐賀藩。次第に幕閣から距離を取るようになっていく時期です。
――江戸。“厳戒態勢”の佐賀藩邸。
今日も屋敷内では、警備の剣士たちが目を光らせている。
そして、その日も江戸城からの遣いは来る。
「鍋島肥前守は、まだ御城に参じないのか…?」
「あいにく“胃の腑(ふ)”に強い痛みあり、それも引かず…他にも…」
登城を催促する幕府からの使者。江戸詰めの側近が殿様の不調を伝える。
――その頃。殿・鍋島直正は、ある家来と会っていた。
「佐野よ…、ひとまず“観光丸”は任せたぞ。」
座ったまま、そう語る佐賀の殿様。何だか前かがみで姿勢が悪い。
「馴染みのある蒸気船にございます。お任せくださいませ。」
力強く返答する佐野常民(栄寿)。時おり述べるが、正式な名は“栄寿左衛門”。
いまの佐野は、医者時代の丸坊主ではない。しっかり髷(まげ)を結う侍の姿。
「…して、殿。お加減は、如何(いかが)なのでございますか?」
かつてオランダ医学を修練した佐野。ほぼ“患者”に見える殿様への問診だ。

――その殿様が、引きつった笑みを浮かべて応える。
「良からず。“胃の腑”のみならず、あちこちが痛む…」
「殿…笑い事ではございませぬ。養生をなさらねば!」
佐野が、急に医者の顔になって語気を強める。“消化器系”の不調の様子だ。
…1か月ほど前。突然の“凶事”により井伊大老と進めていた、天草(熊本)への佐賀藩の海軍基地の計画は消滅した。
外洋を守る海防政策について、幕府での理解者を失ったうえに、逆に幕閣たちからは「混乱の収拾に力を貸せ」と矢の催促である。
殿・直正の失望は大きかった。佐賀を雄藩へと導く中で積年の無理は重なり、以前から主に胃痛などの体調不良に陥っていた。
――側近・古川与一(松根)も、佐野の言葉を聞いていた。
「殿、佐野の申す通りでござる。一度、国元にお戻りになってご養生を。」
「いかにも。佐賀にお戻りになられませ。」
周りの側近たちも声を揃える。“幕府がすごく催促してくるし、混乱に巻き込まれては面倒だ…”という本音が見える者もいる。
「…そうか。そうやも知れぬな。」
殿・直正も、“では、佐賀に帰ってしまうか”という表情を見せた。長崎警護の重責を抱える佐賀藩には、殿様は江戸への滞在が短期で済む特例がある。
――屋敷内。剣士たちの引率役・中野数馬が、また声を張る。
「皆、よく聞け。殿はこれより国元にお帰りになる。」
…剣士たちが、神妙な面持ちで聞き入る。
「わかっていると思うが、ここからがお主らの働くべきところだ。」
「はっ!」
幾人かの声が重なる。すでに腕をまくって、気合十分の者までいるようだ。
一刻も早く、殿を江戸より退避させる。こんな時の佐賀藩の対応は迅速である。鍋島直正の影響力に期待していた、幕府の閣僚たちは唖然とした。
――こうして帰路の警護につく、佐賀の剣士たち。
今度は東海道を西へ。剣士たちとしては、来た道は走りだったが、戻りは襲撃を警戒しながら…というところが大きな違いだ。
京の都を西に過ぎ兵庫の港に至ると、すでに佐賀藩が蒸気船を待たせている。

「ここまで来れば、ひと安心でございますな。」
何より、殿の無事が一番。側近・古川は、柔和な笑みを浮かべた。
「お貢(姫)も我が身を案じておるかもしれぬ。文(ふみ)でも書くとするか。」
不穏となった江戸を離れたが、川越藩(埼玉)に嫁ぎ、佐賀藩邸の近隣にいる愛娘・貢姫とは遠くなってしまう。
ひとまずは、娘に無事を知らせる手紙を思い立つ、佐賀の殿様だった。
(続く)
“鉄腕”と称され実行力には評価のあった大老・井伊直弼。知識に優れた人材は居ても、統率力のあるリーダーを失ったことで幕府内では迷走が始まります。
…幕末の黎明期、技術開発や外交政策で幕府に協力し、目立って力を発揮した佐賀藩。次第に幕閣から距離を取るようになっていく時期です。
――江戸。“厳戒態勢”の佐賀藩邸。
今日も屋敷内では、警備の剣士たちが目を光らせている。
そして、その日も江戸城からの遣いは来る。
「鍋島肥前守は、まだ御城に参じないのか…?」
「あいにく“胃の腑(ふ)”に強い痛みあり、それも引かず…他にも…」
登城を催促する幕府からの使者。江戸詰めの側近が殿様の不調を伝える。
――その頃。殿・鍋島直正は、ある家来と会っていた。
「佐野よ…、ひとまず“観光丸”は任せたぞ。」
座ったまま、そう語る佐賀の殿様。何だか前かがみで姿勢が悪い。
「馴染みのある蒸気船にございます。お任せくださいませ。」
力強く返答する佐野常民(栄寿)。時おり述べるが、正式な名は“栄寿左衛門”。
いまの佐野は、医者時代の丸坊主ではない。しっかり髷(まげ)を結う侍の姿。
「…して、殿。お加減は、如何(いかが)なのでございますか?」
かつてオランダ医学を修練した佐野。ほぼ“患者”に見える殿様への問診だ。

――その殿様が、引きつった笑みを浮かべて応える。
「良からず。“胃の腑”のみならず、あちこちが痛む…」
「殿…笑い事ではございませぬ。養生をなさらねば!」
佐野が、急に医者の顔になって語気を強める。“消化器系”の不調の様子だ。
…1か月ほど前。突然の“凶事”により井伊大老と進めていた、天草(熊本)への佐賀藩の海軍基地の計画は消滅した。
外洋を守る海防政策について、幕府での理解者を失ったうえに、逆に幕閣たちからは「混乱の収拾に力を貸せ」と矢の催促である。
殿・直正の失望は大きかった。佐賀を雄藩へと導く中で積年の無理は重なり、以前から主に胃痛などの体調不良に陥っていた。
――側近・古川与一(松根)も、佐野の言葉を聞いていた。
「殿、佐野の申す通りでござる。一度、国元にお戻りになってご養生を。」
「いかにも。佐賀にお戻りになられませ。」
周りの側近たちも声を揃える。“幕府がすごく催促してくるし、混乱に巻き込まれては面倒だ…”という本音が見える者もいる。
「…そうか。そうやも知れぬな。」
殿・直正も、“では、佐賀に帰ってしまうか”という表情を見せた。長崎警護の重責を抱える佐賀藩には、殿様は江戸への滞在が短期で済む特例がある。
――屋敷内。剣士たちの引率役・中野数馬が、また声を張る。
「皆、よく聞け。殿はこれより国元にお帰りになる。」
…剣士たちが、神妙な面持ちで聞き入る。
「わかっていると思うが、ここからがお主らの働くべきところだ。」
「はっ!」
幾人かの声が重なる。すでに腕をまくって、気合十分の者までいるようだ。
一刻も早く、殿を江戸より退避させる。こんな時の佐賀藩の対応は迅速である。鍋島直正の影響力に期待していた、幕府の閣僚たちは唖然とした。
――こうして帰路の警護につく、佐賀の剣士たち。
今度は東海道を西へ。剣士たちとしては、来た道は走りだったが、戻りは襲撃を警戒しながら…というところが大きな違いだ。
京の都を西に過ぎ兵庫の港に至ると、すでに佐賀藩が蒸気船を待たせている。
「ここまで来れば、ひと安心でございますな。」
何より、殿の無事が一番。側近・古川は、柔和な笑みを浮かべた。
「お貢(姫)も我が身を案じておるかもしれぬ。文(ふみ)でも書くとするか。」
不穏となった江戸を離れたが、川越藩(埼玉)に嫁ぎ、佐賀藩邸の近隣にいる愛娘・貢姫とは遠くなってしまう。
ひとまずは、娘に無事を知らせる手紙を思い立つ、佐賀の殿様だった。
(続く)
2021年08月02日
第16話「攘夷沸騰」⑤(警護者たちの黄昏)
こんばんは。
オリンピックの編成で『青天を衝け』の放送は5週もお休みだとか。幕末の大河ドラマを見ると頭の中が忙しいので、逆に“本編”を進める好機かもしれません。
さて、「桜田門外の変」以降、さらに不穏な空気の強まる江戸の市中。当時は“開国”の影響で、日本に入った外国人を襲撃する事件も起きていました。
尊王攘夷派の過激な行動の“後始末”に追われる幕府。政治体制の弱体化につながっていきます。
次第に殺伐とした幕末の姿が現れますが、佐賀藩は“独自路線”を歩むことに。その理由の1つは、あまり芳しくない事情でした。
――江戸。佐賀藩邸。
「お召しにより、ただいま江戸に参上いたしました。」
藩政のエリート・中野数馬が佐賀から30余人の剣士たちを率いて姿を見せる。
…なお、先行して江戸に出た中野方蔵とは別人物だ。大木・江藤の親友である中野の方は、ごく一般的な佐賀藩士。
剣士の一団を率いる中野は、藩の重役を補佐する名家の者と説明しておく。
一行は、まさに昼夜を問わず駆け続けてきた様子だが、さすがに剣を得手とする者たち。旅の埃(ほこり)で身ぎれいとは程遠いが、息も乱れず、士気も高い。

――殿の護衛のために、集められた精鋭たち。
「これは中野どの。何とも頼もしいことだ。」
幼少期から殿・鍋島直正の傍にいる、側近・古川与一(松根)が出迎える。
「殿は何処(いずこ)に居られますか。」
中野数馬は、遡っては「戦国の世で佐賀藩祖・鍋島直茂公に仕え、西の要衝・伊万里の抑えを任された」という中野清明を先祖に持つエリートだ。
…由緒正しいうえに有能なので、当然のように出世している。
――古川は「まずは殿に、ご挨拶を」という、中野の気持ちを察する。
「中野どの…、これへ。」
公家との交際にも適する文化人・古川は、所作に品位があるのだ。
「はっ…。」
江戸まで駆けてきたので、土埃にまみれているが、名門の出自を持つ中野数馬にも品格がある。
「実のところ、殿はお加減がよろしくない…」
古川が告げたのは、殿・鍋島直正の不調についてである。
――小声で会話する、側近・古川とエリート・中野。
「では、ご挨拶の儀は差し控え、ただちに警固に入りまする。」
いま、為すべきことを察した中野数馬。そのまま藩邸の警備の任にあたる。
30人を数える剣士の一団に対して、中野は声を張った。
「皆、長旅ご苦労である。」
「はっ!」

――剣士たちの幾人かの声が揃う。
ただちに気持ちを転じて“警備隊長”として指揮に入る中野数馬。
「我々は手筈(てはず)通り、殿をお守りする!決して手抜かりをいたすな。」
「はっ!」
さらに大勢の声が揃った。こうして、佐賀藩の屋敷では、腕利きの剣士による厳重な警備が敷かれることになった。
――夕刻。廊下を通りががったのは、佐野常民(栄寿)。
江戸に到着した時は、予想より穏やかな屋敷内だったが、急に物々しくなった。
「俄(にわ)かに、慌ただしかね…」
さっそく日中の警戒を始める者、夜警に備えてか鍛錬の組太刀を始める者も…
「ヤッ!」「トォーツ!」
…こうして四六時中、藩邸の庭には気合に満ちた声が響くことになった。
「勇ましかね。“さがんもん”は、こうでなくては。」
佐野は常々「佐賀の侍は、頑張らねばならない」と考えている。一言つぶやくと、次の任務に取り掛かるのだった。
(続く)
オリンピックの編成で『青天を衝け』の放送は5週もお休みだとか。幕末の大河ドラマを見ると頭の中が忙しいので、逆に“本編”を進める好機かもしれません。
さて、「桜田門外の変」以降、さらに不穏な空気の強まる江戸の市中。当時は“開国”の影響で、日本に入った外国人を襲撃する事件も起きていました。
尊王攘夷派の過激な行動の“後始末”に追われる幕府。政治体制の弱体化につながっていきます。
次第に殺伐とした幕末の姿が現れますが、佐賀藩は“独自路線”を歩むことに。その理由の1つは、あまり芳しくない事情でした。
――江戸。佐賀藩邸。
「お召しにより、ただいま江戸に参上いたしました。」
藩政のエリート・中野数馬が佐賀から30余人の剣士たちを率いて姿を見せる。
…なお、先行して江戸に出た中野方蔵とは別人物だ。大木・江藤の親友である中野の方は、ごく一般的な佐賀藩士。
剣士の一団を率いる中野は、藩の重役を補佐する名家の者と説明しておく。
一行は、まさに昼夜を問わず駆け続けてきた様子だが、さすがに剣を得手とする者たち。旅の埃(ほこり)で身ぎれいとは程遠いが、息も乱れず、士気も高い。

――殿の護衛のために、集められた精鋭たち。
「これは中野どの。何とも頼もしいことだ。」
幼少期から殿・鍋島直正の傍にいる、側近・古川与一(松根)が出迎える。
「殿は何処(いずこ)に居られますか。」
中野数馬は、遡っては「戦国の世で佐賀藩祖・鍋島直茂公に仕え、西の要衝・伊万里の抑えを任された」という中野清明を先祖に持つエリートだ。
…由緒正しいうえに有能なので、当然のように出世している。
――古川は「まずは殿に、ご挨拶を」という、中野の気持ちを察する。
「中野どの…、これへ。」
公家との交際にも適する文化人・古川は、所作に品位があるのだ。
「はっ…。」
江戸まで駆けてきたので、土埃にまみれているが、名門の出自を持つ中野数馬にも品格がある。
「実のところ、殿はお加減がよろしくない…」
古川が告げたのは、殿・鍋島直正の不調についてである。
――小声で会話する、側近・古川とエリート・中野。
「では、ご挨拶の儀は差し控え、ただちに警固に入りまする。」
いま、為すべきことを察した中野数馬。そのまま藩邸の警備の任にあたる。
30人を数える剣士の一団に対して、中野は声を張った。
「皆、長旅ご苦労である。」
「はっ!」

――剣士たちの幾人かの声が揃う。
ただちに気持ちを転じて“警備隊長”として指揮に入る中野数馬。
「我々は手筈(てはず)通り、殿をお守りする!決して手抜かりをいたすな。」
「はっ!」
さらに大勢の声が揃った。こうして、佐賀藩の屋敷では、腕利きの剣士による厳重な警備が敷かれることになった。
――夕刻。廊下を通りががったのは、佐野常民(栄寿)。
江戸に到着した時は、予想より穏やかな屋敷内だったが、急に物々しくなった。
「俄(にわ)かに、慌ただしかね…」
さっそく日中の警戒を始める者、夜警に備えてか鍛錬の組太刀を始める者も…
「ヤッ!」「トォーツ!」
…こうして四六時中、藩邸の庭には気合に満ちた声が響くことになった。
「勇ましかね。“さがんもん”は、こうでなくては。」
佐野は常々「佐賀の侍は、頑張らねばならない」と考えている。一言つぶやくと、次の任務に取り掛かるのだった。
(続く)