2020年07月04日
「主に小城市民の方を対象にしたつぶやき」
こんばんは。
「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内の皆様につぶやくシリーズ。第4弾は、小城市に設定してみました。
さて、残る1つは“松前口”です。江戸時代、蝦夷地(北海道)のアイヌ民族との交易は、主に松前藩が仕切っていました。
そして、幕末期の佐賀と蝦夷地(北海道)との関わりは、“本編”でも書き始めています。のちに大都市・札幌を創る“団にょん”こと島義勇の冒険を描きました。
〔参考:第11話「蝦夷探検」⑩(“開拓神”の降臨)〕
――この内容ならば、“つぶやき”にしなくても“本編”で書けますね…
今日は“変化球”を投じます。まずは現代の佐賀へ。
佐賀玉屋さんです。
“北海道物産展”が、人気イベントであると聞いています。催事は百貨店ならではの“得意技”でしょう。

――私は佐賀に“帰藩”すると、地下の食料品売り場(玉ちか)によく立ち寄ります。
そのとき、“北海道のお菓子”が並ぶ一角を見て、思いました。
「北海道の名産の販売と“団にょん”の偉業のアピールを繋げないものか」と。
…残念ながら、現時点では島義勇の記念館は無いのです。
将来的に佐賀ではなく、札幌に記念館ができる可能性もありそうですが…
私は、いつも慌ただしく“帰藩”を終えます。そのときの“佐賀みやげ”の中には、なぜか“北海道キャラメル”が混ざることとなりました。
全国各地の名産の“目利き”は、百貨店のバイヤーさんの得意とするところと聞きます。
――いま地方の百貨店業界には厳しい状況が続いているようです。
時代を経て、消費行動(ショッピング)の選択肢は激増しました。
個人的には「わざわざ足を運んでしまう」百貨店が存在してほしいという想いがあります。

――ちなみに佐賀玉屋のルーツ、田中丸商店が創業したのは、現在の小城市・牛津の地。
JR長崎本線の牛津駅。
レンガの駅舎にかかる謎のスローガン(?)の看板。
「牛津・津でもち、駅でもつ、町の栄えは店でもつ」
…看板の言葉。気になってはいたのですが、とくに調べてはいませんでした。
そして、理由がわかりました。
――江戸から明治にかけて、商売の街として栄えた牛津。
「西の浪速…」との異名まであったようです。
“浪速”は、大阪(江戸時代は大坂)の古い呼び名ですね。
江戸期の大坂は“天下の台所”と呼ばれ、経済的な意味では、日本一の都市。
小城の街並みは、今でも“小京都”と呼ばれますが、牛津の活気は“大坂”に例えられたようです。
――1806年。初代・田中丸善蔵が、呉服商・田中丸商店(玉屋のルーツ)を立ち上げます。
ここから数えれば、すでに創業200年を超えている、玉屋さん。2018年が“明治維新150年”でしたから、堂々、江戸時代からの老舗です。
参考に“田中丸商店”が創業した頃の、佐賀藩の状況にも触れておきます。
・創業2年前の1804年にはロシアの提督レザノフが長崎に来航。
→このとき佐賀藩は千人体制で警備を敷きます。幕府がまともに交渉に応じなかったので、レザノフは蝦夷地近辺で暴れます。
・創業2年後の1808年にはイギリスのフェートン号が長崎に侵入。
→このとき佐賀藩は勝手に警備を減らしていて、幕府に厳しく処罰されます。“本編”では第1話を、ここに設定しています。
〔参考:第1話「長崎警護」④〕
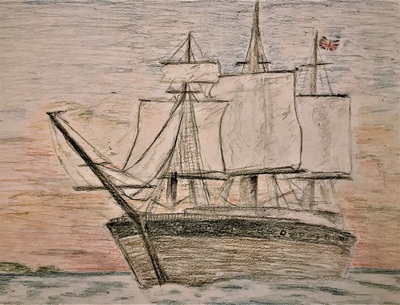
――激動の時代を駆け抜けたのは、武士だけではありません。
幕末、日本では盛んに海上輸送が行われていました。
「蝦夷探検」で、よく語られる“販路開拓”は、この海上ルートと深く関わります。
北前船と呼ばれた大型帆船による輸送は、全国の特産を各地に流通させました。
例えば、蝦夷地(北海道)の昆布が、富山で消費され、北の漁場でとれたニシンを遣った蕎麦(そば)が京都で名物になる…といった具合です。
日本海側から瀬戸内海を回って、大坂に至る“西廻り航路”は、のちに蝦夷地から大坂までを結ぶことになります。
当時、海上輸送は物流の主役でした。商人たちは、各地の港から港へ特産の売買をしていったのです。
――のちに佐野常民は、海外に陶磁器の販路を求めたり、見本市で産業を活性化したりします。
江藤新平は貿易部門のお仕事に就いていますし、大隈重信は長崎で「蝦夷地の昆布」の取引を行い、藩の収益に貢献したようです。
特産開発と販路開拓は、藩の財政を潤します。
そのため、意外と商売熱心な佐賀藩士たち…
――“商都”牛津。九州で“西の大坂”とも呼ばれた、長崎街道の宿場町。
大河ドラマ「麒麟がくる」では、熱田(愛知)の賑わいが描写されていました。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、活気あふれる商都・牛津を見てみたいものです。
…ちなみに第12話「海軍伝習」では、佐賀藩が48名もの大人数で、精鋭を“長崎海軍伝習所”に送り込みます。
普段から当ブログをお読みの方なら、「佐賀城下から長崎に向かった!」とか描写するたびに、長崎街道の牛津宿を通過していくイメージお持ちいただくと面白い…かもしれません。
「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内の皆様につぶやくシリーズ。第4弾は、小城市に設定してみました。
さて、残る1つは“松前口”です。江戸時代、蝦夷地(北海道)のアイヌ民族との交易は、主に松前藩が仕切っていました。
そして、幕末期の佐賀と蝦夷地(北海道)との関わりは、“本編”でも書き始めています。のちに大都市・札幌を創る“団にょん”こと島義勇の冒険を描きました。
〔参考:
――この内容ならば、“つぶやき”にしなくても“本編”で書けますね…
今日は“変化球”を投じます。まずは現代の佐賀へ。
佐賀玉屋さんです。
“北海道物産展”が、人気イベントであると聞いています。催事は百貨店ならではの“得意技”でしょう。
――私は佐賀に“帰藩”すると、地下の食料品売り場(玉ちか)によく立ち寄ります。
そのとき、“北海道のお菓子”が並ぶ一角を見て、思いました。
「北海道の名産の販売と“団にょん”の偉業のアピールを繋げないものか」と。
…残念ながら、現時点では島義勇の記念館は無いのです。
将来的に佐賀ではなく、札幌に記念館ができる可能性もありそうですが…
私は、いつも慌ただしく“帰藩”を終えます。そのときの“佐賀みやげ”の中には、なぜか“北海道キャラメル”が混ざることとなりました。
全国各地の名産の“目利き”は、百貨店のバイヤーさんの得意とするところと聞きます。
――いま地方の百貨店業界には厳しい状況が続いているようです。
時代を経て、消費行動(ショッピング)の選択肢は激増しました。
個人的には「わざわざ足を運んでしまう」百貨店が存在してほしいという想いがあります。
――ちなみに佐賀玉屋のルーツ、田中丸商店が創業したのは、現在の小城市・牛津の地。
JR長崎本線の牛津駅。
レンガの駅舎にかかる謎のスローガン(?)の看板。
「牛津・津でもち、駅でもつ、町の栄えは店でもつ」
…看板の言葉。気になってはいたのですが、とくに調べてはいませんでした。
そして、理由がわかりました。
――江戸から明治にかけて、商売の街として栄えた牛津。
「西の浪速…」との異名まであったようです。
“浪速”は、大阪(江戸時代は大坂)の古い呼び名ですね。
江戸期の大坂は“天下の台所”と呼ばれ、経済的な意味では、日本一の都市。
小城の街並みは、今でも“小京都”と呼ばれますが、牛津の活気は“大坂”に例えられたようです。
――1806年。初代・田中丸善蔵が、呉服商・田中丸商店(玉屋のルーツ)を立ち上げます。
ここから数えれば、すでに創業200年を超えている、玉屋さん。2018年が“明治維新150年”でしたから、堂々、江戸時代からの老舗です。
参考に“田中丸商店”が創業した頃の、佐賀藩の状況にも触れておきます。
・創業2年前の1804年にはロシアの提督レザノフが長崎に来航。
→このとき佐賀藩は千人体制で警備を敷きます。幕府がまともに交渉に応じなかったので、レザノフは蝦夷地近辺で暴れます。
・創業2年後の1808年にはイギリスのフェートン号が長崎に侵入。
→このとき佐賀藩は勝手に警備を減らしていて、幕府に厳しく処罰されます。“本編”では第1話を、ここに設定しています。
〔参考:
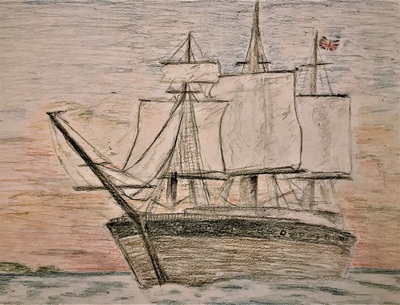
――激動の時代を駆け抜けたのは、武士だけではありません。
幕末、日本では盛んに海上輸送が行われていました。
「蝦夷探検」で、よく語られる“販路開拓”は、この海上ルートと深く関わります。
北前船と呼ばれた大型帆船による輸送は、全国の特産を各地に流通させました。
例えば、蝦夷地(北海道)の昆布が、富山で消費され、北の漁場でとれたニシンを遣った蕎麦(そば)が京都で名物になる…といった具合です。
日本海側から瀬戸内海を回って、大坂に至る“西廻り航路”は、のちに蝦夷地から大坂までを結ぶことになります。
当時、海上輸送は物流の主役でした。商人たちは、各地の港から港へ特産の売買をしていったのです。
――のちに佐野常民は、海外に陶磁器の販路を求めたり、見本市で産業を活性化したりします。
江藤新平は貿易部門のお仕事に就いていますし、大隈重信は長崎で「蝦夷地の昆布」の取引を行い、藩の収益に貢献したようです。
特産開発と販路開拓は、藩の財政を潤します。
そのため、意外と商売熱心な佐賀藩士たち…
――“商都”牛津。九州で“西の大坂”とも呼ばれた、長崎街道の宿場町。
大河ドラマ「麒麟がくる」では、熱田(愛知)の賑わいが描写されていました。
「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、活気あふれる商都・牛津を見てみたいものです。
…ちなみに第12話「海軍伝習」では、佐賀藩が48名もの大人数で、精鋭を“長崎海軍伝習所”に送り込みます。
普段から当ブログをお読みの方なら、「佐賀城下から長崎に向かった!」とか描写するたびに、長崎街道の牛津宿を通過していくイメージお持ちいただくと面白い…かもしれません。
Posted by SR at 21:57 | Comments(0) | 各地域の皆様へのつぶやき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。




